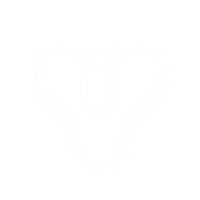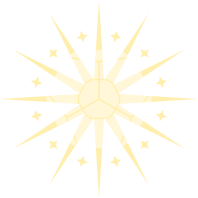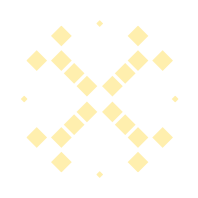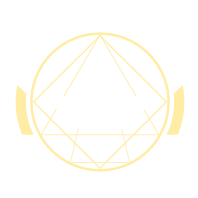▬
暁旦の喜び
明るい日々 
知ってのとおり、私はザヴァラとは旧知の仲だ。彼は私がその昔タワーに到着したとき、最初に挨拶した人々の1人だ——いや、「挨拶」というのは婉曲表現が過ぎるかもしれない。ある種の好意や真心があることを示す言葉だ。それにザヴァラに会ったことがあれば分かるかもしれないが… 彼は少々厳格な所がある。彼はカバル大戦以来、更に頑固になった。気の毒だと思う。だが、皆ある程度はそうなのだろうな。いずれにせよ、初めての出会いは後味の悪いものだった。認めたくないが、それ以降はできるだけザヴァラのことを避けていた——時には彼自身が避けられないようにしてきたが。
私がタワーでの最初の暁旦を祝ったのはそれから間もなくのことだった。皆気分が高揚していて、大事な人達が笑顔でお互いに杯を交わしているのを見るのはとても気分がいいものだった。忘れもしない、テスと私が飾り付けを終え、彼女が何かを取りに離れたときにザヴァラが私のほうへ向かってきたときのことだ。「しまった」と、私は思った。「こいつには会いたくなかった」ああ、だが結局彼はやってきた。だから私は微笑んで、いい暁旦をと言った——本当に良いことがあるよう願っていたからだ。最も悲しんでいるのは、厳格な者だというのはよくあることだ。
彼も私に祝いを述べた。それから——信じられないことに——微笑んだのだ! 私たちは手短に社交辞令を交わし、それから… どんな話の流れでそうなったのか覚えてないが、突然彼が言った。「ああ、面白い話を思い出した!」と。
面白い話だって! 最初は聞き間違えたのだと思った。タイタンバンガードはいつだって「そんなことを言っている場合じゃない」という空気をかもし出していたからだ。彼が話し始めるなり、彼の姿勢がとてもリラックスしていることに気づいた。まるで暁旦の精神がこの石のように冷たい男にまで届いたかのようだった。
彼の話した内容自体はほとんど覚えていない——ガーディアンとフォールン・キャプテンに関するものだったか? だが、彼は話の始めで詰まって、最初から言い直さなければならなかったことは覚えている。私が彼を勇気づけるために精一杯暖かい笑顔を向けると、彼は私が今まで聞いた中で最も長く、最もぎこちない冗談話をしてくれた。驚いたことに、私はその話を素晴らしいと思った。あれほど幸せな気分を味わったことがない。ザヴァラも心の底から楽しんでいたようで、彼と一緒になって手を叩いたり笑ったりした。ああいう閉ざされた心を開いてもらえること以上に、美しいことはないのはなかろうか。あの時、彼に敬服した。彼が閉じこもっていた境界線を自ら越えたことに対して。私もいつか自分の人生の中であれくらい勇敢になれたらと願ったのを覚えている。彼をシティのリーダー以上の存在として尊敬したのはそれが初めてだった。人としてのザヴァラに、本物の愛情を感じたのは初めてだった。ザヴァラ、我が友よ。
それ以来、彼は私にとって愛すべき人だ。
ギャラルドゥードル:
エーテルの茎とデリシャス・エクスプロージョンを混ぜ、暁旦のエッセンスを加えて焼く
伝統はあなたより大きい 
私が奥地にいる間に、フレームたちが新しいタワーで暁旦の準備をしていたとテスから聞いたとき、私抜きでどうやったのだろうと思った。そして自分に言い聞かせた。エヴァ、伝統はあなたよりも大きなものよ。代々受け継いできた人たちの心と精神に住み着いているんだ、って!
タワーに戻った今、今までで最高に素敵な暁旦を創り出す手伝いをしている。そして私は毎年必ず繰り返すであろう伝統を引き継ぐ。私はイコラに暁旦のクリスタルを作るよう頼む。彼女が実行してくれるまで、何度でも。
装飾について話し合うために約束を取り付けるけど、彼女がいつも緊急のバンガードの件で忙しくしていることは分かっている。だから彼女の小部屋に近づいたときに低い声が聞こえたら、いきなり入っていかずに少し覗いてみる。
イコラはブツブツ言っている——怒っているのかもしれない。「暁旦の装飾ですって! うわついてる場合じゃないのに…」
男の声が言う。「人々に必要なことです。“うわついたこと”ではありません。あなたにとって困難なのは分かります。ケイドを失って初めての——」
「オフィウクス。今すぐに黙りなさい」イコラが誰と話しているのかも、その名も分からなかったがイコラの声は厳しかった。「他の懸念がある。入り組んだ岸辺に関する最新の報告はどうなってるの? どう解釈すればいいのか分からない。それに、潜みし者が近くでトラブルが発生したと報告してきてる…」私は彼女の視線がメインの通路のほうに漂ったのに気づいた。一部だけ閉じた人気のない片隅に向かって。
「はい、イコラ。しかし——」
「それにオシリスから連絡がない。期待しているわけではないけど…」彼女は首を振った。
「なぜ彼にメッセージを送らないのです?」
「そうね。ただ時間がない…」彼女は言葉を止めた。「エヴァ・レバンテ!」
私はわざと大きな足音を立てて、暁旦のクリスタルのデザイン画をガサガサとさせながら入っていく(盗み聞きをしていたなんて思われたくないでしょう?)。彼女は腕を組んで私を見る。ゴーストが彼女の耳元を油断なくブーンをいう音を立てながらホバリングしている。
「暁旦おめでとう、イコラ・レイ!」私は始める。私の明るい笑顔と、ここから選ぶようにとデザイン画をどんどん並べていくのを見れば、「イエス」と言えば早く済むことを理解してくれるだろう。彼女は私たちの伝統を尊重してくれる。彼女は2回拒否したが、結局「分かった、エヴァ」と折れてくれた。彼女はクリスタルの重要性を信じてはいない。彼女は私の視線を避けたが、ゴーストの目が私に向かってまたたいたのを見た。
彼女が作ると約束してくれたデザインは絶妙だ。
作業を終えたらまた会うということで私たちは合意した。私は助手のマリアと一緒に用事をこなしている間にバザーで彼女と合流した。——ぎりぎりに済ませる仕事がたくさんある! 私たちが近づくと、イコラと彼女のオフィウクスは身を寄せ合っている。彼女は首を振り続けている。だがそれでも彼女は腕をあげ、きらめく巨大な暁旦のクリスタルがタワーの上空に出現する。まるで無数のダイヤモンドが空中に浮かんでいるかのようだ。
マリアが息を飲んだ。彼女はタワーのこんなにも高いところへ来たことも、暁旦のクリスタルを近くで見たこともない。はるか下のシティからだけだ。彼女は運んでいた荷物を全て落としてしまった。
ウォーロックバンガードがマリアの荷物を拾うのを手伝った。マリアが石のようにじっとしているのに気づくまで、荷物を1つ、また1つと積み上げていく。マリアはひざまずき、イコラと、空中から光を作り出した彼女の手を見ている。少女の傷のある顔は涙で濡れ、それは袖でぬぐっても止まることはない。マリアの家族はカバル大戦中にシティから脱出した。彼らは生き延び、再び家を持ったが、美しいものに恵まれることは多くはなかった。
マリアはイコラの腕に振れ、声を出さずにありがとうと伝える。彼女の頬は紅潮している。
私もイコラから荷物を受け取るためにひざまずいた(最近では幾分か苦労するようになった)——1つを除いて。黄金のリボンで結ばれ、包み紙には太陽に包まれた開いた目が浮き彫りにされている。私は頷き、それを彼女の手にしっかりと持たせる。イコラのゴーストが囁くのが聞こえた。「言ったとおりでしょう」そしてイコラが答える。「たしかに」
トラベラーのドーナッツ:
カバルの油と閃きの光を混ぜ、暁旦のエッセンスを加えて焼く
暁旦の前の夜明け 
かつてアマンダから、彼女の母親ノーラがここからはるか遠くの砂漠の民出身だと聞いたことがある。ノーラは小さな頃から旅をしていた。時には古い走り書きの地図と彼女のショットガンしか持っていないこともあった。彼女は多くを必要とはしなかったが、仲間は必要だった。ノーラはとある半分見捨てられた村でアマンダの父親と出会い、最後の安全な都市について話すと、彼は彼女に付いてきたのだという。最初は2人きりだった。道中で避難民の仲間ができ、一部の仲間を失った。
それから、2人の間に女の子が生まれた。最初は小さな赤ん坊、それから小さな子供を連れた旅路はとてもゆっくりとしたものだったに違いない。だが彼らは信じていた。希望を捨てなかった。彼らは前進した。
アマンダは、彼らが荒野で共に過ごしたある暁旦について話してくれた。彼らはアマンダより少し年上のルシアという子供を持つ他の家族と一緒に行動していた。彼らは好ましい旅の同行者だった。気付くと、一行は深い森の中にいた。風が唸り、嵐が迫る中、小枝が飛び… それ以上進めないことが分かった。
彼らはドロップシップの残骸を見つけ、翼と崩れた壁を立てかけ、大人たちと2人の小さな子供たち全員が錆びた船体の下の乾いた空間に身体を押し込んだ。
それからアマンダの母親が言った。「しばらくここにいるし、何か元気が出るようなことをしましょう」
大人たちを食べ物や飲み物、身体を覆う物を探すために送り出した。アマンダの父親が、編んでマットにできるような長い葉を持つ植物を持ち帰った。同行者は、水で満たしたフラスコと、トゲのあるフルーツと、キュウリに似た野菜を1ダースほど持ち帰った。彼らの荷物にあった干し魚と合わせると、結構なご馳走だった。
大人たちが働いている間、ルシアはフルーツの固い皮を巻いて小さな花を作っていたが、小さなアマンダは足をバタつかせて苛々していた。「あなたもちゃんと働いて。装飾を作りなさい」アマンダの母親が彼女を咎めた。彼女はアマンダにワイヤーやナットやボルトを与え、小さな電球でいっぱいの回路基盤を手渡した。
ルシアが飛び跳ねながらやってきた。彼女の手には古いバッテリーがあった。少女たちは一緒に小さな電球で花輪を作った。そしてルシアがアマンダにどのようにワイヤーをバッテリーに繋げて光らせるかを教えた。広大な暗い森の中に、小さな光が輝いた。
アマンダは、白く柔らかい果肉で酸っぱい味のするフルーツについて話してくれた。ハミングと、隠れ場所の金属の壁を叩いてリズムを取って、言葉のない歌を即興で歌ったことも。
彼女はそのフルーツが何なのかは知らない。もう存在していないかもしれない。もう1つの家族とははぐれてしまった。その後、アマンダの両親も… いなくなった。最後の安全な都市へと向かう他の多くの人たちと同じように。
だけど、アマンダ・ホリデイは今もイルミネーションを作る。余った半端ものを使い、工房を装飾する。暁旦が来ると、いつもそうする。
チョコレート船のクッキー:
カバルの油とヌルテイストを混ぜ、暁旦のエッセンスを加えて焼く
大事なのは気持ち 
タワーの住民の一部はかなり昔から住んでいる。ガーディアン、エクソ、古き鉄の王——彼らは何度も暁旦を見て来た。タワーがそれを現在のような祭日として祝い始める前でから、今のような光と希望のセレモニーで祝う者たちが存在した。時にはその記憶が混ざり合ってしまうこともある。だがその思いは… 思いは残る。
今年の暁旦は——先週? 先々週? 思い出すこともできない、ハハ! 卸売業者の1人が、私の荷物を間違えて銃器技師に配達したと告げる。だから、行き違いを解決するためにバンシー44に会いに行く。
エクソは荷物を受け取った覚えはなかった。だが私を見知っていて、彼の目がごくわずかに明るく輝いたことに気づく。「暁旦の話だろうな」彼はつぶやき、振り返ると後ろにある棚に真っ直ぐ向かう。彼は大きな箱を2個持って戻ってくる。
「これがそうか?」彼は尋ねる。
私たちは最初の1個を開けた。中にはとてもとても古いチョコレートの箱があった。様々な武器のクリーニングキット。「中枢のハンター」が一冊(私はこの小説を知っているけど、万人向けではない)。小さな箱に大事にしまい込まれた弾丸がついたペンダント。暁旦のグリーティングカードの山。
私は穏やかに首を振る。「これはあなたに贈られた暁旦のプレゼントよ、バンシー!」
銃器技師の目が2回ほどまたたく。それから、彼は箱を閉じる——チョコレートを捨てるべきだったかもしれないと心配になるが、来年でいいだろう——そして、彼はカウンターの上にあるもう1個つの箱を見る。カバーを上げる。
中は暁旦の贈り物でいっぱいだった。明るい色あいの紙で包まれ、キラキラしたリボンで結ばれている。いくつかは小さな箱に入っていたが、当然、いくつかは銃だった。それらは細心の注意を払ってラベリングされていた。
「これは今年あなたが友達に贈るプレゼントじゃないかと思うんだけど、違う?」ウィンクしながら尋ねる。
バンシーはラベルを裏返して読み、素っ気なく頷く。私はそのうちのいくつかに詳細な説明が付いているのを見る。エクソは肩をすくめる。
「何でも書いておくようにしている。時々… 覚えていられないから」彼は考えを振り払うように「そう」と言う。
「私の品は? 取りに来た箱よ」優しく告げる。
彼は一瞬頭を傾げ、そして最後には指を上げた。「ああ。どこだか分かった」
だが彼が箱を持ち去る前に、私はカバーを軽く叩いた。「ラベルを付けたほうがいいわ。“古い暁旦の贈り物”、“新しい暁旦の贈り物——送付用”って」彼は頷き、蓋に走り書きをした。
「暁旦のために友達を忘れないようにしているんだ」彼は私に荷物を手渡しながらきっちりと私に伝える。
「嬉しいわ。暁旦おめでとう、バンシー!」私は答え、彼の腕を握る。
どうか彼があのチョコレートを捨てるのを忘れませんように。
テレメトリータピオカ:
ベックス液と弾丸スプレーを混ぜ、暁旦のエッセンスを加えて焼く
選択が私たちを定義する 
時々、恐ろしい何かに直面したとき、自分が知っている強い人々のことを考え、彼らに力をもらう。スラヤ・ホーソーンはその1人だ。彼女のぶっきらぼうな態度には反感を覚えるかもしれないが、それは彼女がわざとやっていることだ。それに慣れれば、学ぶべきことがたくさんある。
彼女は小さい頃に家族を失い、デヴリムとマークが引き取った。正直に言えば、この2人を見て育ったことが彼女の強さの一因であると私は思う。彼らは彼女が自信を持って正しいと思うことをするように育てた… たとえそれで最終的にはシティを去らなくてはならなくなったとしても。
スラヤの話によると、ある日彼女が家に帰ると、マークとデヴリムが待ち受けていたかのようにキッチンテーブルの前に座っていたそうだ。彼らは彼女を座らせ、何か言いたいことがあるのではないかと尋ねた。
彼女は首を振った。「ううん」
マークはもう一度考えてみるように言ったが、彼女は沈黙していた。そこで彼は遂行者ヒデオが家に来たことを伝えた。彼女は、彼の様子を尋ねた。
「知っているんだろう」デヴリムは言った。「何があったか教えなさい」
「彼の顔が邪魔だったの」
マークは深く息をつくと、ヒデオはその日の朝に彼女が物資を盗んだと言ってたことを伝え、それについて何か言うことはないかと尋ねた。言うことはなかった。
盗みとファクションの指導者の鼻を折ることは、どちらもシティを追い出されかねないことだと彼が言うと、スラヤは黙っていられなかった。彼女はほとんど叫ぶように説明をした。ファクションは食べ物や物資を必要としている人たちのことを気にかけていない——生きていくだけでも大変でファクションに誓いを立てることができない人たちのことを。彼女は彼らを助けたかった。そのために、時々ニューモナーキーから物資を盗むことがあった。
デヴリムは尋ねた。「ヒデオのことは?」
彼女は目を反らしてうめくと、ヒデオに見つかったとき、悪意のある暴言を吐かれたことを説明した。彼女は無価値だ、取るに足らない、そんなようなことを言われたと。
デヴリムはヒデオが… 実際の言葉は繰り返さないでおくが、あえて言うなら「好ましくない人間」であることには同意した。だが、彼は大きな影響力を持っていた。そしてスラヤを罰するよう強く求めていた。それも厳しく。スラヤは、この時何かが確信に変わるのを感じた。それが、初めてシティを出たいと自覚した時だったそうだ。——彼女がヒデオを殴ったのも、そういった気持ちがあったからかもしれない。彼女は保護者たちにそう訴え、驚かれた。
彼らは少しの間黙っていた。それから、デヴリムが沈黙を破った。「じゃあ、荷造りしようか」
「いや」彼女は言った。「絶対にやめて」彼女は自分の決断で、自分を引き取り、育ててくれたこの人たちを傷つけたくはなかった。彼らは何も悪いことはしていない。
そして、彼らは彼女と言い争った。ずいぶん長い間、言い合いが続いたそうだ。ついに彼女は肩をすくめ「ついて来るつもりなら、逃げるから」と告げた。
彼女の主張がハッタリではないことが伝わったようだ。彼らは疲れた、心配そうな声で最後の反論を述べるに留まったからだ。スラヤは断固として譲らなかった。「私の選択で2人を苦しめられない」と主張する彼女を前に、彼らに何ができただろう?
スラヤはいつ発つべきかと尋ねた。マークは、計画を全て立てる間、ヒデオを1日か2日追い払うことができるだろうと言った。彼の声が再び厳しくなり、「せめて、すぐ様子を見に行けるくらいの距離にいてくれ。少なくともしばらくの間は。こればっかりは交渉の余地がない」
もちろん、彼には交渉材料など無かった。だがスラヤは同意した。彼女は正式に別れを告げて、遠くの世界へ向かうまで、1年以上シティのすぐ近くに滞在した。
私の心の中のスラヤ・ホーソーンは、結果に関わらず自分が正しいと思うことをすることを体現している。困窮する人々を助けることは正しいと確信していた。デヴリムとマークを危険にさらさないことは正しいと確信していた。そして近くに留まって安心させてやることが正しいと確信していた。こういう勇気は、常に称賛されるべきものだと私は思う。
エリクスニーバードシード:
エーテルの茎とパーソナルタッチを混ぜ、暁旦のエッセンスを加えて焼く
家族同然 
ああ、デヴリム。デヴリムに会って好きにならない人なんているかしら? 面倒見がよくて、困っている人がいれば必ず助けるような人だ。奥地に戻ってから何度も会った。みんなの様子を見たり、問題がないか確かめるために時々立ち寄ってくれた。何度かは一緒に座ってお茶すら飲んだ。本当に優しくて誠実な人よ。みんながああだったらいいのに。
戦いについて何度も話をして、私に武装するよう一生懸命説得してきた。「外の状況は知ってるだろう」って。あんな光景忘れる訳ないのに。
何度も何度も話し合ったわ。あえて戦わずに済む仕事をしてるんだと説明した。その方が私の実力を発揮できるし、そっちに集中するつもりだと。
一度、デヴリムが頑なに譲ろうとしなかったことがあった。「エヴァ!」デヴリムは、きっと彼自身が出すつもりだったよりも大きな声でついに叫んだ。その目は怒っていると言ってもいいぐらい血走っていて、私の目を見据えていた。「これは仮定の話じゃない。実際に自分の身を守らなければならなかっただろう。もう一度そうならないとなぜ言える。カバルは引き下がらない。しかも、脅威はカバルだけじゃない。それをわかっていながら身を守ろうとしないなんて… 無責任だ」
そう、私は自分の身を守った。そしてもう二度としたくないと思った。
「デヴリム」私は小声で、だけどしっかりとした口調で言った。「戦いにも銃にも暴力にも——もう関わりたくないの。もう十分よ。また巻き込まれたとしても——確かにありえることよ——それは仕方ないわ。私は治療に携わりたい。皆で立ち直る手助けをしたいの。必要なことでしょう?
哀れなデヴリムは、それでようやく説得をあきらめてくれた。その後も様子を見には来てくれたけれど。習慣を変えるのは難しいと言うものね。
ようやくタワーに戻ったとき、私を待ち受けていたのは何だと思う? ちょうど暁旦のお祭りが始まったところで、ポストマスターが荷物を届けてくれた。中には綺麗なピストル——凝った装飾で古風な色合いのピストル——と、手紙が入っていた。もちろんデヴリムからだった。
最初は腹が立った——あんなに話し合ったのに! そのまま銃を捨ててしまおうかと思った。でもそうはせずに、その手紙を読んだ。
「親愛なるエヴァ!
結局奥地を去ったと聞いたときは残念だったが、大事な友人と過ごせると知ってとても嬉しく思うよ。この気持ちと、暁旦の精神に従ってプレゼントを贈ろうと思う。うちで何世代も引き継がれて来たものだ。ケイ家の家宝だ——弾は撃てないから、捨てないでくれ。いい妥協案じゃないかと思ったんだ。受け取ってくれるといいが。
タワーでも元気で。
——デヴリム」
何度か読み返してから、その手紙を折り畳んでポケットに入れた。
それからもう一度その美しい家宝、友情と家族の象徴を見下ろし、いろいろあったけれど、何とか友情と家族と再会できたという事実に思いを馳せた。
紳士のショートブレッド:
エーテルの茎とパーフェクトテイストと暁旦のエッセンスを混ぜて焼く
嵐の海の暁旦 
暁旦の度に、顧客からたくさんのカードが届く。一番嬉しいのは、太陽系中の人々がどうやって祭日を祝っているのかが書かれているもの。中でも特に嬉しかったのは、一度だけ出会った顧客から来た手紙。土星の衛星の一つであるタイタンに住む、ストーンボーン・スロアン卿から届いたものだ。
「親愛なるエヴァ
暁旦おめでとう。
まず最初に、配達を受け取った、ありがとう。注文はすべて完璧な状態で届いたし、チキンの梱包も素晴らしかった(チキンについてはまた後で書こう)。司令部の外の柵をイルミネーションで飾ってみたのだけど、フォールンが光を使って射撃訓練をし始めてしまった。来年は、代わりに休憩室を飾ろうと思う。暁旦のランタンも風でいくつか吹き飛ばされた——メタンの海の天候は、穏やかだとはとても言えない。
タイタンで手助けしてくれているガーディアンたちから聞いたのだけど、シティ外の暁旦の話を聞くのが好きなのだな。私たちが故郷と呼ぶこの衛星での祝い方を紹介しよう。
今年は司令部で暁旦の夕べを過ごすために、乗組員には16時までに仕事を切り上げてもらって、私自身も1時間の休みを取った。
セイレーンの監視からは波や浮桟橋が綺麗に見えるから、休憩室のテーブルをくっつけて、水平線を見ながら皆で宴を楽しんだ。部屋が風に晒されていて(ずいぶん前にガラス窓が割れてしまったのだけど、修理は後回し)、デルとアリは服を着込まないといけなかったし、金属の塊でテーブルクロスの端を抑えないといけなかった。これくらいまだマシな方だが。
エヴァ、食事は絶品だった。あのチキンも美味しかった。みんなで一口ずつ食べられたよ。タンパク質のレーションを色々な形に切って、あのタフィーを十分に温めて齧ったときと言ったら、まるで天国だった。
暁旦のプレゼント交換もした。営舎に飾るために「心に響く言葉」の刺繍を作ってくれた人もいた(「私のビーコンはどこ?」っていう内輪ネタだ)。道具やヘビーウェポン弾や分厚い靴下——ここではそういった物を贈り合う。タワーの暁旦に慣れている人たちにとってはつまらない物かもしれないけど、私たちにとっては素敵なプレゼントだ。
その後で、暖を取るためか、祭りを楽しむためか手を取り合った。それまでは話したことがないような話をした。進んで自分の話をしたことなんて生まれて初めてだった! カバル大戦前の生活の話や出身地、将来の夢まで話したんだ。
この暴風の衛星で暮らすのは簡単なことじゃない——浮桟橋から振り落とされたら一巻の終わり。フォールンとハイヴと風に囲まれて、いつも生き残るだけで必死。でもあそこで座って話をしているときは、生きているという実感があった。
これを書いたのは、お礼を言いたかったからかもしれない、エヴァ。あなたは、どんな時でも忘れずに祭日を祝い、楽しむことの大切さを思い出させてくれた。心に響いたよ。
敬具
スロアン」
私は地球から離れたことがないけど、タイタンは… とても面白い場所のようだわ。この祭日のおかげでそんなに遠く離れた人たちが一つになれたなんて、頑張った甲斐があった気がする。
いつかまたスロアンに会えたら素敵。
アルカンドラジェ・クッキー:
キチンパウダーと弾丸スプレーを混ぜて、暁旦のエッセンスを加えてから焼く。
お祝いを祝福 
前にエクソダスのコロニー船の話を聞いたことはあった。詳しい情報はほとんど覚えていない——歴史の授業で聞かされて印象に残っている名前だっただけだ。実を言うと、最近になって複数のガーディアンたちから、ネッススで墜落したコロニー船を見つけたこと、そしてフェールセーフたちに起こった出来事を聞かされるまでは、そのことをすっかり忘れていた。
2つがもともと1つのAI、船のナビゲーション人工知能だったが、時間経過により分裂してしまったことは知っている。片方はいつも陽気で、もう片方はいつも陰気なようだ。そんな生き方はどちらにも良くない。生きていくにはバランスが必要なのだ。確かにコンピューターではあるが、それでもやはり心配だ。
つい最近あるガーディアンから、フェールセーフに暁旦のことを伝えた話を聞いた。彼はバウンティを届けた後、フェールセーフに祭りに参加するために地球に戻るのが楽しみだと伝えた。フェールセーフは彼を引き留めると、その意味を尋ねた——フェールセーフは暁旦を知らなかったのだ! ガーディアンは「地球の伝統的な催しをいくつか組み合わせた冬の祭りだ」というようなことを伝えた。
フェールセーフは——できるだけ彼が言ったままを再現する、なぜならフェールセーフの真似に自信があるらしかったからだ——フェールセーフの陽気なほうがこう言った、「私のデータベースによると、地球の冬は一方の半球が太陽から最も離れた時に発生します! なぜ寒さを祝うのでしょう?」すると陰気な方が続けて「私は寒さを感じることができませんが、とても大変そうです」と言った。
ガーディアンは「寒さというよりも、人々がお互いの関係を祝福するための祭りだ」と説明した。悪くない答えだ。というのも、私も以前からそう思っていたからだ。皆が1つの場所に集い、甘い物を食べ、友情を深め合う。
フェールセーフはさらにいくつか質問をした後、陽気なほうが「お互いを祝福するための祭りということは、私は参加できないということでしょうか? 私は独りぼっちです。酷すぎます!」と言った。すると陰気な方が言った、「フォールンを祝福するつもりはないよ」
私の知り合いのガーディアンはすぐにあることを思いついて言った。「ネッススを訪れるガーディアンが素晴らしい暁旦を迎えられるように祈るのはどうだろう! 皆と一緒に祝福するんだ! そうしてくれると我々もありがたい」
それを聞いてどちらも少しは元気が出たはずだ、彼がそう言ってくれたことに感謝している。どうやらフェールセーフは、小1時間も暁旦の挨拶の練習に費やしたようだ、今ごろかなり上達しているだろう。時間があったらフェールセーフのもとを訪れてみてほしい。シティから遥か遠くに離れた場所にいても、暁旦を楽しむことはできる。
——-
無限の森のケーキ:
ベックス液とインポッシブル・ヒートを混ぜてから暁旦のエッセンスを加えて焼く。
教訓的な物語 
「エヴァ・レバンテ!」イコラは私の手首を掴むと、私を引き寄せて囁いた。「エリス・モーンのことで話したいことがある」
ああ、あの日のことは絶対に忘れない。あの日、私はバンガードやタワーの他の商人たちと一緒に暁旦のことで盛り上がっていた。多くの人々がひっきりなしに、祭日に関することで私に話しかけてきた。それでも、ウォーロックバンガードが私に会いに来るとは思ってもいなかった——しかもよりにもよってエリス・モーンのことを聞きに来るなんて!
さすがの私も震えたかもしれない。
「飾り付けをしている時に、彼女と話しているのを見た…」
そういえば、ランタンを吊り下げようとしていた時に、エリスがアビスのことを延々と話していた、でもそのことをイコラには言いたくなかった。
彼女は続けた。「彼女が心配だ。かなり落ち込んでいる様子だった」
私はイコラを一瞬見た後、目を逸らした。自分の名誉のために言っておくが、決して嘲笑したわけではない。
「彼女はいつも以上に機嫌が悪くて、ガーディアンの間の技術者たちから苦情が出ている。エヴァ、彼女と話してくれないか? できれば… 彼女に手伝わせてやってほしい。人手は足りないだろう」
酷いアイデアだ、だがそう言うわけにもいかない。その代わりに私は、「彼女には友達——いや、友達ではないかもしれないけど——とにかく、話したい相手がいるんじゃないかしら、彼女と共通点がある人…」と提案した。話しながら、それに当てはまる人物を思い出そうとしていた。
イコラはその話に興味を示した。「彼女がよく話題に出す人物がいる——アシェル・ミルというジェンシム書記官だ。彼は… 素晴らしい学者でもある。連絡してみようか… あなたが彼を知っているなら話は別だが…」
「知らないわ!」と私ははっきりと言った。「とにかく上手く行くといいわね。皆に暁旦を楽しんでもらいたいもの。そろそろ失礼させてもらうわ。配達があるの」
その頃の私は腕を握りしめてお別れの挨拶をするほどイコラとは親しくなかった、だからうなずいてその場から立ち去った。
その日にまた彼女と偶然出会った時のあの顔は今でも忘れられない!「提案に従って、アシェルと話した」と彼女は言った。
「どうだった?」
「彼は最初、不満を漏らしていた。暁旦が来ていることに気付いていないようだった。だから私は事情を説明して… 何とかして、彼女にグリーティングカードを出すか、彼女に会ってくれないだろうかと言うと、彼はカードを書くことはできると答えた。それにプレゼントも用意してあると言った」
「あら! それは素敵ね!」
「そうだろうか」と彼女はため息をつき、私に1枚の羊皮紙を見せた。
それは4つ折りにされ、グリーティングカードにされていた。表は無地だったが、中には文字が書かれていた。「エリスへ。ウォーロックバンガードが、今開かれている祭のため君を元気づけたいと私のもとを訪れた。この予期せぬ機会を利用して、頼まれていたハイヴの異端の儀式に関する調査内容を贈る。君がなぜ依頼したかはともかくとして、だ。暁旦の祝福あれ!——アシェル・ミル」
「イコラ、最後の部分、彼にそう書くように言ったの?」
彼女は一瞬動きを止め「そうだ」と言った。
私は笑った。「なるほど、彼女に渡してあげて。ハイヴの研究資料は伝統的な暁旦のプレゼントとは呼べないけど、彼女が欲しがったものなのよ」
イコラはうんざりした様子で頭を振り、私たちはそこで別れた。
その日の遅く、私が最後の配達に向かおうとしていた時、イコラがまた私のもとを訪れた。
彼女はこう言った。「エリスに会ってきた。機嫌が良くなったかは分からないが、『そうそう、連絡を待っていたのよ。よかった』とも言っていた。アシュルへの暁旦のメッセージも書いていたよ」
イコラは書記官が使ったのと同じ羊皮紙を私に見せてくれた。それは折り直されていて、「アシェルへ。愚か者は囁きに屈服してしまう、あなたはそうならないように注意して。暁旦の祝福あれ!——エリス・モーン」と書かれていた。
私は肩を竦めた。
ウォーロックは咳払いをすると、「エリスからはアシェルへのプレゼントも預かった」と言った。
「何もないよりはマシよ」
「そうだな…」イコラは私を隅に呼ぶと、布に包まれた小さなでこぼことした小包を取り出した。彼女はそれを慎重にめくっていった。そして中身が現われた。その暁旦のプレゼントは緑色に輝いていた。
「これは彼に渡せない!」とイコラは囁いた。「私には…」と言うと、近くに誰もいないのを確認してから「…これを没収する権利がある、そうだろう?」と続けた。
「暁旦のエチケットを気にしてる場合じゃないわ」と私も囁き声で返した。
彼女はうなずくと、顔引き締めた。「この話はこれで終わりにしよう」
——-
レディオラリア・プリン:
ベックス液とエレクトリックフレーバーを混ぜてから暁旦のエッセンスを加えて焼く
暁旦の贈り物に思いを込めて 
私が忙しい原因は顧客だけではない。色々な人にアドバイスを求められる。「どっちのシェーダーがいいと思う?」や、「この紋章は私に合っているだろうか?」とか、「暁旦パーティーを開くべきだろうか?」「なぜあいつの暁旦パーティーに出席しなきゃならないんだ?」といった感じだ。ただ、こんな簡単な質問ばかりではない。
私はある日の静かな午後を利用して包装紙の陳列棚を整理していた。突然私を呼ぶ声が私の耳に響いてきて、思わず飛び上がってしまった!
その声は… 間違いなくあのタイタンだった——ザヴァラではない。誰かは言えない。エヴァ・レバンテはセンシティブな問題には関してはしっかりと言葉を選ぶのよ。
彼は見事な武器を持っていた、金属の部品が多い複雑な作りで、太い紐が両端を結んでいた。彼は私の視線に気づき「コンポジットボウだ」と説明した。「矢を放つ」私は困惑して眉を釣り上げた。
彼はその武器に、大きな赤いベルベットのリボンを付けていた。リボンの付きの弓だ。
彼の傾いたヘルメットと、その武器をしっかりと握っている様子を見れば、どこか普通とは違うことがすぐに分かった。
私はため息をついた。暁旦が始まるとたびたび目にする光景。恋をしている。説得に時間がかかりそうだ。
「暁旦おめでとう、トリト!」(これは彼の本名ではない、もちろん偽名だ)
「エヴァ・レバンテ。みんなに聞いたんだが… 特別な相手には、暁旦のプレゼントをあげる決まりなのだろう」小声で話そうとしていたが、その声は大きく響き渡った。
「みんなとは?」私は笑った。
彼は私を無視して言った。「この弓を用意したんだ。いいプレゼントだろうか?」
「それは相手次第ね。その人の趣味は? どんな人なの? 詳しく聞かせてくれる?」
「彼女は… 戦いが好きだ。堂々としていて、とても…」タイタンは一息ついた。「コンポジットボウよりもリカーブボウのほうがロマンチックだろうか?」(今回は小声で話すことに成功した)
「なるほど」と私は知ったかぶりをしてうなずいた。私が見ても違いは分からないだろう、ただ彼がどんな問題を抱えているのかは理解した。
「本のほうがいいだろうか?」と彼は尋ねた。
「どんな本かによるわね」
「イコラの『円陣にて』の改訂版は読んだことがある。面白かった」
「それは暁旦のプレゼントには相応しくないわ。純文学なんてどう?」
トリトは兜の角を軽く叩き考えた。「彼女の本を台無しにしてしまったことがある。代わりを贈るべきだろうか?」
「悲しい思い出には触れないほうがいいわ…」
彼は何も言わず、私は続けた。「あなたのお友達にはこの弓をプレゼントするのが正解なのかもしれない。彼女なら使ってくれると思う?」
「もちろんだ」
「それなら」と私は笑顔で言う。「あなたはもう答えを知ってる。あなたとお友達に暁旦の祝福あれ!」と続けた。
「君もだ、エヴァ。記憶に残る暁旦になるといいな」
タイタンは私に礼を言い、弓を手に取り、大股で立ち去った。
バニラブレイド:
カバルの油とシャープフレーバーを混ぜてから暁旦のエッセンスを加えて焼く。
偶然は起こりえない 
夕方遅くの忙しい時間になると、必ず悩み多き顧客が私の店に現われる気がする。今日は女性だった。美しくたくましいガーディアンで、黒髪を短く切り揃えており、それぞれのまぶたから頬にかけて白い縞模様が描かれていた——とても素敵だった! 片方の肩にかばんを引っ掛け、片腕に本の山と小包を抱えていた。その様子から、彼女が商品を購入してくれるだろうと見当が付いた。彼女は生意気そうに唇を歪めると、腰に手を当て、自分の順番が来るまで繰り返し指で机を叩いた。その様子から、彼女がハンターだと見当が付いた。
「暁旦おめでとう、ミス…」私は彼女に挨拶をした。
彼女は私の言葉を遮った。「仲間内でちょっとした暁旦パーティーを開きたいんだけど、力を貸してくれない? なんというか、その、パーティーセットみたいなものはないの?」彼女はそう言うと、イライラした様子で肩越しに後ろをジロリと見た。「実は… シティの暁旦をよく知っている人を驚かせたいのよ、でも今は火星にいるから…」
「なるほど! それなら、暁旦の基本は飾り付け、食事、それとプレゼントよ。まずはランタンから始めましょう」私は店に並んでいるカラフルな球体を指さした。「それとキャンドル」私はカウンターの下からティーキャンドルの箱を取り出すと、彼女の目の前にドサッと置いた。「次は飾りのリボンね」
「キャンドルとリボンだと火事になるかもしれない。キャンドルとランタンをもらうわ」
「銀色と黄色のランタンは色の相性がいいわ…」
彼女は店の展示をチラリと見て言った。「紫をお願い」
「紫と緑、それと銀のを入れておくわ。綺麗な組み合わせよ。暁旦は驚きと美しさが重要なのよ、だからランタンは1種類じゃダメ」私はキャンドルの上に蛇腹式のランタンを乗せた。
彼女は口を開こうとしてすぐに閉じた。私は一番大きな暁旦用の菓子の詰め合わせを取り出すと、それをカウンターの上に置いた。「暁旦は共感と寛容さを祝う祭日。この詰め合わせなら間違いないわ」私は一拍置いてから続けた。「あなたの大切な人も喜んでくれるはずよ」
彼女は唇をすぼめると、キャンドルとランタンの隣にリボンで飾られたスイーツセットを置いた。
私は微笑みながら、綺麗な衣装が並んだ棚の前で足をとめた。「最後は、贈り物よ。これが一番重要で——」
「いえ、プレゼントはもう用意してある」彼女は持ち物をカウンターの上に置くと、一番上のネックレスの箱を指さした。私は無意識のうちに分厚い本の束の背表紙にも目を通していた、中には非常に長いタイトルのものもあり、どの本にも「フアン図書館——参考図書——持ち出し厳禁」のラベルが張られていた。
ハンターは私が眉をひそめたことに気が付くと、乱暴に本を鞄の中に押し込んだ。「これを買ったんだけど、彼女は気に入ると思う?」
私には「彼女」が誰なのか分からなかった。それでも、彼女の見せてくれたネックレスに思わず目を奪われた。素晴らしい細工が施された小鳥のエンブレムが付いた細長いペンダントだった。
彼女はにやりと笑うと、「黄金時代のデザインよ、しかもこのペンダントには35ペタバイトのデータを保存できる!」と言った。
私は笑顔を返した。その後、本を入れるためのバッグと紫の包装紙の購入も勧めた。
「どうぞ! あなたの暁旦が詰まったバッグよ!」私はそう言うと、彼女からグリマーをもらい、彼女に商品を渡した。「あなたのお友達はきっとサプライズを喜んでくれるはずよ」
ハンターはうなずいてお礼を言うと、後ろを振り返って店の出口に向かった。
「アナスタシア!」
そこにいたのは他の誰でもない、ザヴァラ司令官だった。彼は、多くの買い物客が行き交う午後の大通りのど真ん中で両手を腰に当てて立っていた。
「ザヴァラ」とハンターは呟いた。彼女は肩を後ろに下げて、顎を突き出していた。まるで気性の荒い猛禽のようだ。
「暁旦おめでとう、アナ。まさかタワーにいるとは思わなかった」
「ちょっと用事があって…」
小包を抱えた人物が私に駆け寄ってきて話しかけてきたせいで、それ以外の言葉は聞き取れなかった。「さっき話しているのが聞こえたんだけど、さっきの人、火星に行くのか? これも送ってほしい」
私は小包の目録を読んだ。キャンドル、ランタン、菓子の詰め合わせ、包装紙、クローク… 注文者はカムリン・ドゥムジ。私は奇妙な感覚にとらわれた、こんな偶然があるだろうか…
「これはサプライズ用ね。発送は明日にするわ」と私は答えた。
視線を戻すと、ザヴァラとハンターが話し込んでいる姿が見えた。タイタンバンガードは半笑いで、女性のほうはにやにやとしていた。それを見た私は、暁旦の精霊が古い友人を巡り合わせてくれたのだと感じた。
そう思いながら、私は次の顧客に目を移した。
——-
ジャベリンムーンケーキ:
キチンパウダーとシャープフレーバーを混ぜてから暁旦のエッセンスを加えて焼く。
慣れ親しんだ顔 
会うなり神経を逆なでしてくるような人物に会ったことはあるだろうか? 彼らは一見すると人懐っこい——ただ、実に独特なフレンドリーさなのだ。若いころは様々な種類のフレンドリーさに気付けないが、ただ経験を積めば、それが理解できるようになる。本物の親切心から来ているものにはなかなかお目にかかれない。中には、平時限定のフレンドリーさや、何かがほしい時のフレンドリーさや、フレンドリーさをアピールするためのフレンドリーさもある。特に最後のフレンドリーさには必ず何かしら裏がある、そしてそういった人はそれを隠そうとする。
放浪者とやらも、最後のグループに含まれる。他人のことを悪くは言いたくない、だが彼はどうだろう? どうも信用できない。
彼があのゲートの先で何をやっているのかは知らないし、知りたくもない。彼とは何度か話したことがあるだけだ。彼はいつも忙しそうにしている。
自己紹介がてらに話した時は、すぐに会話が終わった。彼は私の質問に答える前にその場から立ち去ってしまった。暁旦の祭が始まる直前のことだった。私が飾り付けをしている時に、彼が私の店に来てこう尋ねた。「何かあるのか?」
「暁旦のことは知っているでしょ?」私はそう言った——失礼な言い方ではなく、フレンドリーに。あなたがつかみ所のない人物だとは知っているわよと伝える感じだ。
「ああ、もちろんだ」と彼は答えた。「もうそんな時期だったんだな。時間が過ぎるのは早いな? あっという間だ」彼は腰に手を当ててしばらく飾り付けを見ると、満足げにうなずいた。
「そうね」と私は言った。「ところで、聞きたかったことが——」
「実は」と言うと彼は続けた。「実際に暁旦を祝っている場所に来たのは初めてなんだ。いくつか教えてくれないか?」
私はそこまで年寄りではないが、無知な子供でもない。人生経験のあるエヴァは、嘘を聞けばすぐに分かる。とにかく私は少しだけ時間を割いてこの祭について話し、私たちの伝統とその意味を説明した。彼は興味深そうに何度もうなずいていた。私は話題を彼に戻すことにした。
「それで、放浪者、あなたはどこから——」
「それでは、そろそろ行くとしよう!」彼は私の質問が聞こえなかったふりをして、さらに付け加えた。「もうこれ以上、邪魔をするのは申し訳ない——残された時間がどれだけあるかなんて誰にも分からないからな」そう言って彼は立ち去ると、背中越しに「素敵な装飾だ! 色合いが素晴らしい!」と言い、街角に姿を消した。
他の人がこの奇妙な男の話をしていたのを聞いたことがある。多くの人が口を揃えて同じことを言う。少しミステリアスだが、とてもフレンドリーだと。その一方で、口に出したくないような話も聞いた。あまりに悲惨で、にわかには信じがたい内容だ、不確かな噂を広めるつもりもない。私は、彼の食生活が私たちと同じだと信じている。
とにかく、彼は少し変わっている。注意しておいたほうがいい。
——-
闇チョコレートのかけら:
宿りのバターとヌルテイストを混ぜてから暁旦のエッセンスを加えて焼く。
ありふれた話 
タワーに戻ってきて一番よかったことは、皆と再会できたことだ。向こうにいたときは友人たちに会いたくて仕方なかった、彼らのことを毎日のように考えていた。正しいことをやっていると分かってはいても、過去を懐かしまないでいることは難しい。
私はとにかく皆の近況が知りたくて仕方なかった、ただガーディアンたちはいつも忙しくあちこち飛び回っている。彼らから話を聞けるような機会はなかなかない。色々なことがあったようだが、得られる情報はほんの少しだ。
「スパイダー」という名前を何度も聞いたが、誰なのだろう? ただの犯罪者? 神? 友人? その全てに当てはまるような話をする者もいる。ガーディアンたちの心を掴むこのスパイダーとは何者なのだろうか?
彼がゴーストを食べるというのは本当なのだろうか? あのゴーストをだ! 何て酷い話だろう。どんなに忌々しいゴーストでもそれはあまりにも可哀想だ(そのとおり、私は今あるゴーストを思い浮かべている、ただ… それを誰かに話すつもりはない)。
集めた情報から判断すると、スパイダーはバロンの一団を率いていたようだ。それが正しければ、彼らの関係は… 緊張感のあるものだったはずだ。この入り組んだ岸辺で何を企んでいるのかは知らないが、彼はバロンを1人残らず始末したらしい。
ただその前に、スパイダーのバロンたちは宇宙のどこかにある警備の厳重な牢獄を襲撃した。彼らは… スパイダーの所有物を探していたようだ。それが何かは分からない。ゴーストかもしれないし、武器かもしれない。それにしても、彼はなぜそれを牢獄に探しに行かせたのだろう。牢獄に侵入したバロンだったが、囚人たちが彼らの前に立ちはだかった。その牢獄にはあのならず者のケイド6もいた、スパイダーとは関係ない任務でそこにいたと思われる。でも、どうやら彼らは同じ戦いに参加することになったようだ。皆が戦っている所に、今度はリーフ・クイーンの弟が現われたそうだ!
この話を最初に聞いた時、私はこう思った。「ああ、よかった! ようやく私たちに仲間ができた。アウォークンの王子なら何とかしてくれる」ただ、彼は… かなりの頑固者だと言われていた。それでも、いざという時には、頼りになる人物らしい。ただそれは彼の姉がいた頃の話だ。喪失感は人を変える。
ここから私が確信を持って真実だと言えるある情報に繋がる。ユルドレン・ソヴはケイド6を殺した。
理由は分からないが、心の痛みに負け、真実が見えなくなってしまったからかもしれない。とにかく、スパイダーのバロンたちは牢獄から立ち去ると、今度はリーフになだれ込んだ。恐らくスパイダーの探し物を見つけたが、スパイダーに渡さなかったのだろうと思う。それを知ったスパイダーはバロンたちを追跡するために部下を送り込んだ、バロンは1人残らず始末されたようだ。
その戦いの最中にユルドレンは誰かに殺された。恐らくケイドの復讐を果たしたかったのだろう、ただ誰もその復讐者の名前を教えてくれない。スパイダーに関する話を聞く限り、ユルドレンも彼が始末したのではないだろうか。
知り合いのガーディアンの多くは今もこの… 仲間を裏切るような存在に力を貸している。それが正しいことなのかは分からない。きっと私の知らない真実がまだ隠されているのだろう。
これは歴史の授業ではない。どう解釈するかはその人次第だ。全ての人がエヴァと話すために時間を割いてくれるとは思っていない。
——-
デッドゴーストのキャンディー:
ダークエーテルの茎と閃きの光を混ぜてから暁旦のエッセンスを加えて焼く。
私たちを1つにするもの 
アウォークンとは何なのだろう?
「どういう経緯で生まれてきたのか?」ということではない。その点についてはカバルやフォールンの生い立ちと同じぐらい興味がない。私に言わせれば、宇宙の意志がそうなることを望んだから、彼らはああなった。宇宙に質問しても意味がない。
最近、多くの人々が、ペトラ・ベンジや入り組んだ岸辺の話をしている。だがどうにも要領を得ない——ロープで結ばれた岩? そして… その間をジャンプする? リーフ生まれのアウォークンが、大地すら安定していない場所で育ったなら、他人を疑ってかかるのもうなずける話だ!
ただ、アウォークンは概して… 確かに彼らに関する私の知識は増えている、それでも今でも理解できないことがいくつもある。彼らは間違いなく人間やエクソと同じように、私たちの考える「人類」に属している。そのことは知っているし疑ってもいない、ただその根拠は?
彼らも… 私たちと同じような見た目をしているからだろうか? カバルも大ざっぱに言えば私たちに似ている、でも私たちは彼らを人類とは考えていない。
トラベラーとの関係が似ているからだろうか? 信じがたいことだが、フォールンもトラベラーと繋がりを持っているらしい。でも彼らは人類ではない。
「人類」とは、人間と共に歩むことを選んだ者だけを指すのだろうか? ただその理屈だと、リーフに残っているリーフ生まれのアウォークンは人類ではなくなる。私にはそうは思えない、でも…
ペトラは人生の大半をリーフで過ごしてきたはずだ。彼女はしばらくの間ここで使者として働いていたが、彼女はリーフこそが故郷だと考えていた。彼女は自分を人類だと思っているだろうか? ペトラの所に行って「あなたは人類の一員?」と質問すれば、彼女は恐らく「私はリーフのアウォークンだ」と答えるだろう。それでも諦めずに彼女に「それは分かっているけど、どっちの味方?」と質問すれば、彼女は「マラ・ソヴ女王の味方だ」と答えるはずだ。
人類とは選んでなるものなのだろうか? それとも最初から決まっているものなのだろうか? 称号として手に入れるものなのだろうか、生得権や遺産のようなものなのだろうか? その規定の1つに当てはまっているからアウォークンは人類なのだろうか、それとも——
アウォークンが人類の一員なのは、この全てに当てはまるからだろうか? 私に言わせれば、これで人類を定義するのは、クロークでハンターを定義するようなものだ、ただ総合的に考えれば——彼らは私たち似た体を持ち、私たちと同じようにトラベラーと繋がりがあり、その多くが幸せそうに地球で暮らしている… だからこそ彼らは人類なのかもしれない——私たちがそうであるように、全てが1つに結び付いている。
私たちはその結束があったからこそカバル大戦で勝つことができたのだ。この暗闇を退ける時にも結束は強力な武器になるだろう。とにかく忘れてはならないのは、この結束こそが私たちを強くするということだ。その時にはアウォークンも必ずそこにいるはずだ。
——-
イルフォーチュン・クッキー:
ダークエーテルの茎とインポッシブル・ヒートを混ぜてから暁旦のエッセンスを加えて焼く。
いずれ慣れる 
ある奇妙な人物がいる… あなたも知っているかもしれない。彼は私達が思うほど行ったり来たりはしない。どちらかというと、後ろを振り返ると、いたりいなかったりするような存在だ。それでも、彼の出現には一定の決まりがあり、予測することができる。彼は「シュール」と呼ばれている。妙な名前だが、私たちの理解を超越する人物たちの考えを尊重するのは大事だ。
私が初めてシュールを目にしたのは、タワーの屋台に1人でいた時のことだった。今は旧タワーと呼ばれている場所だ。着いたばかりだった。顔を上げると、どこからともなく現れた男の姿がそこにあった。彼は私に背を向けていたが、後ろからでも、彼が普通でないことは分かった。独特な雰囲気を醸し出していたのだ。彼が後ろを振り返った時、その顔の大部分が髪の毛で覆われていることに気づいた。、しかもそれが動いている。ゆっくりと、まるで意志を持っているかのように——風は吹いていないのに。
光が彼の顔を照らした時、私は悲鳴を上げてキャビネットの後ろにかがみ込んでしまった。私にはこの醜い存在が、私たちを襲いに来たとしか思えなかった、彼の仲間がどこかにいるはずだ、もう終わりだと覚悟を決めた。
やがて私は、自分以外の悲鳴が聞こえてこないことに気付いた。襲われているような音も聞こえてこない。影から覗いてみると、いつもどおりに商売をしている皆の姿が見えた。私以外、パニックになっている者がいないのだ! 多くの人が私のほうを見ていた——中には彼に話しかけている者もいた。
私はゆっくりと立ち上がると、何とかして自分の仕事に集中しようとした——ただ視線はほとんど固定されたままだった。しばらくしてテスが私のところに来た。私は彼女にあの奇妙な人物について尋ねた。
彼女は「あら、シュールじゃない!」と慌てる様子もなく言った。「彼は時々ここに来て、貴重な商品の販売を売っているのよ」暫く考えてから、さらに続けた。「確かにあの格好は改めるべきかもしれないけど、それ以外は無害よ」
「何者なの?」と私は聞いた。「あんな姿の人は見たことがない」
「シュールは… 確か木星人よ。彼らの故郷はリーフを越えた先にある。それ以外のことはよく知らないわ」
「彼らは… 味方なの?」
「攻撃をされていないことは間違いないわ。シュール自身が友好的かと言われると何とも言えないけど、敵ではないわ」
彼女と話して、かなり気持ちが楽になったものの、恐怖心は拭い去れなかった。それから何カ月もの間、私は彼を見るたびに飛び上がり、逃げようとする自分の本能と戦わなければならなかった。
それでも、私も彼の姿に次第に慣れていった。それどころか定期的に現われる彼のことを歓迎するようになっていた——彼が現れると全てが順調だと分かった。時間と共に恐怖心は完全に消えていた。
今に始まったことではないが、私は初めて出会ったものに対して恐怖心を抱いてしまう。私だけではないかもしれない。ただ、恐怖心を受け入れて理解することは、それ自体を克服するための大きな助けとなる。そうすることで、その新たなものに対して、最初に感じたほどの恐怖心を抱かなくなる。
——-
奇妙なクッキー:
宿りのバターとエレクトリックフレーバーを混ぜてから暁旦のエッセンスを加えて焼く。
噂 
例のオシリスというウォーロックの予言についてはあまり詳しくは知らない。でも、彼の理論によって、タワー、市民、そしてガーディアンには分断が生まれた。オシリスが急進的な研究を続けるためにこの地を離れた後も、思いもよらない場所でその分断は起こり続けた。
これに関する面白いジョークがあるの。
1人のオシリスの信奉者と、1人の懐疑論者がお互いを説得するために同じテーブルについた。そして彼らはそこで死んだ。
どこで耳にしたのかは聞かないで。でも、シティの住人がガーディアンを茶化すことなんてないって思っているのなら、あなたの注意力が足りてない証拠ね。
まあそれは置いておきましょう。
オシリスの信奉者の1人、修道士バンスの噂話を耳にしたの。まるで神話みたいな噂で、その中では彼がオシリスの発見した知識を利用して奇跡を起こすとか、ガーディアンを復活させてその潜在能力を最大限にまで引き出すとか。でもある時急にその噂話の内容が突然変わったの。バンスはオシリスとは全く面識のないただの狂信者で、水星の砂漠で来るはずのない何かを永遠に待ち続けているんだとか。
ガーディアンは行動力の塊だから、そういう消極的な姿勢が理解できないのかもしれない。
私は、自分たちの目の前にあるものや人々のことを信じるべきだと思ってる。これまでどんな伝説を生み出してきたかではなくて、今まさに何をやっているかが自身の内面を証明する。英雄の帰還を永遠に待ち続けながら、同じ本と手紙に繰り返し目を通して、自分ではコントロールできない未来に期待するようなことは… 私からすれば単なる時間の無駄に思える。
だから私は進んで行動を起こすようにしている。常に手を動かして、常に頭を働かせている。
とはいえ、憧れている存在に見捨てられるのは、間違いなく孤独で落胆も大きいはず。たとえそれが、自分の心の中で起こっただけのことだとしてもね。バンスのような男ならきっと1人でも夜通し見張り続ける。もしかしたら、彼は自分の噂話についても知っているのかもしれない。それでも彼は折れずに、ますます孤独になる。
ただ、私は彼に会ったことがない。どの噂が真実で、どの噂が馬鹿げた悪口なのか判断がつかない。私に言えるのは、暁旦は誰でも歓迎するということだけ。誰よりも孤独を感じている者ならなおさら。
大義のための戦い 
夢見る都市への入り口を見つけた時、多くのガーディアンがそのことを私に教えてくれた。美しい場所だという彼らの話には、高くそびえる崖や古の神聖な建物までもが登場して、まるでおとぎ話のようだった。ガーディアンからたくさんの話を聞きながら、現実とは思えないような内容に私は驚いた。
特に印象深かったのがナディアというアウォークン・ウォーロックで、他のガーディアンのように私のもとを訪れると、静かに、おどおどしながら、お茶がしたいと言ってきたの。
もちろん、お茶ならいつでも歓迎よ。
その日、ナディアは椅子に腰掛け、でもティーカップに手を伸ばそうとはしなかった。もし、私がキッチンで皆を元気づけた後でなければ、無理矢理にでも話を聞き出そうとしていたことでしょう。でも私はどうすべきかを知っていた。私は待った。しばらくすると、彼女は私を見上げた。
「まるで自分の一部を見つけた途端に、それをなくした気分」とナディアは優しく、悲しげに言った。「トラベラーの授けたものを守るのがガーディアンの仕事だということは分かってる。でも夢見る都市はまるで…」彼女の声が小さくなっていく。
「故郷?」と私は言った。
ナディアは目を伏せた。「そう。まるで故郷」そう言うと彼女は黙り込み、再び私を見た。「そう感じるのは間違ってる?」
「いいえ」と私は言った。「そんなことはない。故郷が1つとは限らない。私にもたくさんの故郷がある」
ナディアは頷くと、ぼんやりとした様子で、テーブルの上のティーカップを動かした。今度は彼女が話し始めるまでしばらく時間がかかった。やがて彼女は口を開いた。「まるで本当は自分のものじゃなかったものを失って悲しんでるみたい」
アウォークンの故郷に蔓延る呪いのことを完全に理解しているわけじゃない。でも、それが大きな誤解と危機によってもたらされたことは知っている。ユルドレン・ソヴと、聞いたこともないある生き物が、その出来事で中心的な役割を果たしたのだと。ただ、聞いた話によると、この事件には明確な敵は存在しなかったらしい。つまり責めるべき相手はいない。
そうなると尚のこと事実を受け入れるのが難しくなる。
ナディアが悲しんでいることは明らかだった。私は心から同情した。彼女は苦しみを感じながらも、立ち上がって自分の仕事に戻っていった。彼女は夢見る都市に毎週のように帰っていった。
私たちの存在価値は、単に成功を積み重ねたかどうかではなく、勝算のない状況でも全力で戦い続けられるかどうかによって決まる。それはガーディアンだけの話ではなく、全員に当てはまる。
皆が行動でそれを示してくれている。本当にありがたいことね。
好青年 
タワーの私のお気に入り場所の1つが、シティを見渡せる高台にある人目に付かない小さなベンチ。私はそこから、港に入ってくる船、鳥、そして雲を見る。忙しくなると、それがちょっとした気晴らしになって、外の世界のことを思い出させてくれる。ある日、このベンチに座っていると、とても背の高いタイタンが手を前で組みながら私に近づいてきた。
「失礼」と彼は言った。「ここに座っても構わないか?」
私は笑顔で横にずれて、「どうぞ」と促した。彼は座った。もう少し横にずれなければならないほど、彼の肩幅は広かった。
彼は鳥の餌を持っており、私は彼がそれを蒔くのを見ていた。するとハトがすぐに近づいてきた。実のところ、彼が座った途端にいつもよりたくさんのハトが集まってきていた。ふと、彼はどれぐらいの頻度でここに来ているのだろうと思った。今日まで顔を合わせなかったのが不思議なくらいだ。見かけたらすぐに気づいたはずだ。
ハトの鳴き声と遠くから聞こえるシティの喧噪が心を落ち着かせてくれた。この紳士はどうやら心地の良い静寂に理解があるらしい。私は目を閉じた。でも、少しすると、後ろから足音と囁き声が聞こえてきた。若い女性のタイタンで、ベンチに近づくと、強張った笑顔を浮かべながら、その紳士に話しかけた。「あなたにお会いできて光栄です。あなたはあらゆるタイタンにとって憧れの存在です」
彼は恐縮した様子で頷いた。「ありがとう」と彼は言い、その後に短い言葉を交わした。彼は彼女に名前を聞いた。どうやら彼女はイオのパトロール任務から帰ってきたばかりらしい。彼はこの太陽系の人々を守ることに尽力している彼女を賞賛した。そして彼女とその友人の一団はその場を後にした。
彼は再びハトに餌をやり始めた。しばらくたった後、私は冗談めかして彼に聞いた。「有名なのね?」
彼は私の方を見ると、ためらいがちに頷いた。「少しだけ」
「なるほどね」と私は笑いながら言った。少し間を置いてから、私は続けた。「私はエヴァ」
「私はセイント」
私はその答えに一瞬思考を巡らせてから聞き返した。「セイント14?」シティを守るためのシックスフロントの戦いでの彼の活躍は聞いたことがある、かなり昔の話だ。それに強力なフォールンを頭突きで倒したという素晴らしい逸話も残している。私はその話を聞くたびに、彼が丈夫なヘルメットを持っていることを願っていた。
「そうだ」と彼は言うと、また餌をまいた。「お会いできて光栄だ、エヴァ」
私たちはその後もしばらくの間ハトと雲を一緒に眺めていたが、私は仕事に戻る時間になったので、挨拶をしてその場を後にした。
先ほど言ったように、セイント14の伝説は聞いたことがあった。有名なガーディアンは多くの伝説により神格化されており、シティの住人にとってはかなり遠い存在でもある。でも伝説のセイント14にはそういう雰囲気は感じられなかった。
むしろ、感じの良い好青年に思えた。
忠告 
暁旦は慈悲と贈答の期間。贈り物を渡されるのは気持ちのいいもので、自分のよく知る人が選び抜いた心のこもったプレゼントならなおさらね。無償の愛と共にプレゼントを渡す場合は、他者との関係が重要になる。もう知っているでしょうけど、プレゼントを貰うほうにも贈るほうにも得るものがある。
予想外にプレゼントをたくさん貰った時は、その贈り主をよく見てみることね。彼らに何かを渡したことは? 贈答は記録に残るわけではないけれど、惜しみないほどの賞賛と共に、あなたの名前が刻まれた高価な金の贈り物を溢れんばかりに受け取った時は、一端落ち着いて、なぜそれが贈られたのかを考えるべきよ。
貰ったプレゼントであっても、時には疑う必要がある。贈り主が前に誰を好んでいたのかを考えてみるといい。なぜあなたなのだろう? なぜ今なのだろう? その疑問に対する満足な回答が得られない場合は、かなりの確率でその贈り主はしっかりとそれをあなたへの「貸し」として勘定していて、いずれは取り立てに来る。
全てのプレゼントがタダで貰えるわけではない。それをよく覚えておくことね。
話は以上よ、親愛なる友よ。今回は特にエピソードもない、ただの忠告ね。
流行のスタイル 
暁旦の準備を進めていた時、初めてエイダ1に会った。彼女は私の店を訪れると、私が他の客と話している間、邪魔をしないように距離を取っていた。私は視界の端に彼女を捉えていた。彼女は身じろぎひとつぜず、静かで… 少し緊張している様子だった。
もしかしたら私の勘違いだったかもしれない。
客との話が終わって、彼女に作業台のほうに来るように促した。彼女はそれに応じると、一瞬止まって私の生地に目を落として質問をした。「暁旦はガーディアンの祝日なのか?」
私は笑った。ゴシップ好きの常連客から聞いていたが、エイダにとってシティの伝統行事は初めてのことだった。
「暁旦は皆のためのものよ」と私は言った。「シティの住人だけじゃない。お祝いする気持ちを持ってるなら、誰でも参加できる」
彼女はしばらく何も言わず、考えを巡らせていた。彼女が人見知りなのか、静寂を苦にしない孤独を好むタイプなのかは判断がつかなかった。そのどちらであっても私は構わない。しばらくすると、話は終わったらしく、彼女はこちらに背中を向けた。でもすぐに足を止めてもう一度私を見た。
「その模様は見たことがある」と彼女が言った。「この祭りのための配色だ。もし興味があるなら、いくつかアイデアがあるのだけど」
私は驚き、すぐに彼女の考えを聞かせてもらった。彼女が色とデザインに関して抜群のセンスの持ち主であることがすぐに分かった。彼女は別に暁旦のシェーダー作成プロジェクトを牛耳るつもりはなく、もの静かで有能なコンサルタントとして振る舞った。その翌週まで、私たちは一緒に長い時間を過ごしながら、生地をより分け、色を比較し、組み合わせを考えた。彼女は相変わらずどこか他人行儀だったけど、どうも私に親しみを感じ始めたらしく、シティの歴史ある伝統行事の一員になるのも悪くないと感じているようだった。
私はエイダのことを詳しくは知らない。でも彼女は暗黒時代を生き抜いた。あれは悲惨な時代だった。ガーディアンも今とは全く違っていた。
厳しい時代を生き抜くと、様々なことに影響を及ぼす。その経験が人を良い方向に導くこともあれば、その逆もある。彼女はその経験を通して、自分に合った生き方を手に入れた。そしてゆっくりとではあるものの、自分の生活を、タワーやシティで暮らす人々の生活と融合させ始めた。それは勇気のいる決断だ。心から尊敬している。
必要な距離 
シティにとって何よりも重要なのは、ガーディアンとその保護の対象である人々が一緒に生活を送って、お互いの経験と伝統を共有することだと私は思う。
私たちの中で、ガーディアンが経験することを完全に理解できる人なんてほとんどいないだろう。幸福だけを求める愚か者ならきっとこう言うはず。「できることなら永遠に生きていたい」と。その命はトラベラーからの大いなる贈り物。でもそれには大きな責任が伴う。そしてシティのガーディアンはここで私たちと共に暮らすことで、その責任を引き受けてきた。
トラベラーの光を有することで、ガーディアンは常に危険な場所へと送り込まれる。確かに危険の捉え方はガーディアンと普通の人々で異なる。でも感情的な痛みはどうだろう? 日々の仕事をこなすために、どれだけ自分が恐怖とトラウマに鈍感になっているか考えたことはあるだろうか? イコラには考えすぎないように言われているけど、それは無理な話だ。
私はまだ、ガーディアンであるエリス・モーンを真に理解できてはいない。私は今実在するこの時間を大切にしたい。どうすれば今すぐ友人たちの生活を改善できるだろう? どうすれば彼らを元気づけて、一緒に会話を楽しんで、美味しい食事を用意できるだろう? かつてのエリスはその真逆のような存在だった。少なくとも私は頭の中で、彼女の… 悲観的な考えを批判してきた。
でもやがて私は、彼女が私とは全く違う視点から物事を見ていると考えるようになった。彼女がこれまで経験してきたことは私には想像できないようなことばかりだ。それは、世界の見え方がそもそも違っているということ。
つまり、ガーディアンとそれ以外の人々は、近くで生活を送り、互いの共通点を大切にすべきなのだ。ただ、考え方の違いが私たちを分断させる可能性があることも知っている。それは必要な距離で、自分の仕事をこなすために距離を保つべきだと考える人もいる。これは私たち全員が受け入れなければならない事実だ。
これまで説明してきたように、エリスは私たちの伝統行事に進んで協力し、特に死者の祭りでは重要な役割を果たしている。それでも一筋縄ではいかない! 初めて協力を頼んだ時、彼女はこう言った。「エヴァ、私の仕事は人類の存続に関わることだ。そんな… パーティーなんかに割く時間はない」
私はいつもように言った。「大きなことも小さなことも生きる上では重要なことよ。庭の土を耕している間に、鉢の花を枯らしていいわけじゃないでしょう?」
彼女はこういう話が嫌いだ。それでもいつも同意してくれる。
それに彼女にしても、本当は参加したいと思っているはずだ。彼女がマスクをかぶった無表情なガーディアンにレーズンの入った箱を渡した後、振り返って笑みを浮かべていたのを見たことがある。あのエリスが笑うなんて!
いつか彼女に暁旦のイベントを任せてみようと思う。これ以上ないほどの笑顔を見せてくれるはずだ。
暁旦の協力者 
タワーのフレームは、シティの住人のために伝統行事を開く上で大きな助けになっている。私も昔ほど若くはないし、祝典が終わった後はとてつもない量のお菓子が残されるので掃除が必要になる。
ある日、私は別館の近くにある古い階段で、リボンの箱を抱えながら助けを求めていた。階段の下にはきれいな床を掃いているフレームがいた。私はすぐにその姿に同情して、たちまちそれは苛立ちに変わった。もっと上手な使い方を考えるべきだ。
「私はここでメンテナンスを任されています」とフレームは言った。
「もう十分にメンテナンスされてるみたいね」と私は楽しげに言った。私はリボンの入った箱を渡した。「この部屋は十分きれいよ。広場の飾り付けの手伝ってちょうだい」
フレームは首を傾けて箱を見た。「私はここでメメメメメメ――」再び私を見た。そして掃除を再開した。でも今度はさっきよりも速い。「メンテ――ジジジ――この仕事は――素晴らしい彼には相応しくない――邪魔をしないでください、お話は、イイ以上に――」
私は辛抱強く待った。
「彼のジジジ――慈愛に満ちたそのドドド――堂々とした、堂々とした――メンテナンス」そして掃除をやめた。「私はここでメンテナンスを任されています」
私は咳払いをすると、箱を下ろし、フレームからほうきを奪った。それを壁に立てかけてから再び箱を持ち上げた。既に腰が痛かった。私は箱を渡すと階段を指差した。「一緒に来てちょうだい」
何度か説得しつつ、広場まで誘導することに成功した。そしてリボンを付けたい場所を指さした。
「私はここでメンテナンスを任されています」とそれは弱々しく言った。
私は大きな期待はせずに、とにかくその仕事をフレームに任せた。期限が迫っている状況で贅沢なことは言ってられない。思っていたとおり、私が戻ってくると、フレームとリボンの箱は姿を消していた。こうなったら自分でやるしかない、私は覚悟を決めた。今では、あのフレンドリーで、働き者のフレームたちと一緒に仕事をできることを本当に嬉しく思っている。

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ