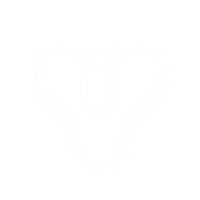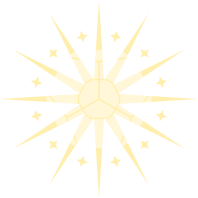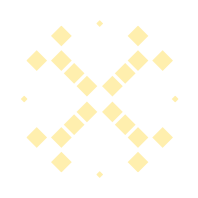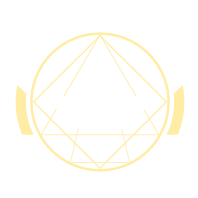「反応するだけでは駄目だ! 反撃を食らわせたいのであれば、相手の次の動きまで読む必要がある」――シャックス卿 
「私は恐れているのだろうか?」
シャックス卿は足を止めると、視線の高さを合わせるように、新兵に顔を近づけた。
「教えてくれ。私がそのヘルメットをかぶれば、私はお前のように戦えるのか?」
そのガーディアンは明らかに萎縮しながら首を振った。
「もちろんそうはならない。我々は敵の武器を利用する、だが奴らになるわけではない。なぜだか分かるか?」
その新兵は何も言わない。シャックスが彼女の肩に手を掛けた。
「なぜなら、武器が戦士を変えることはないからだ。武器がお前を怪物にしたとしたら、最初からお前は怪物だったということだ」
彼が他のガーディアンのほうに目を向けた。
「我々は恐怖に包囲されている。それがあらゆる方向から我々に圧力をかけてきているのだ。兄弟姉妹の心に恐れを抱いているなら、彼らと話し合うべきだ」
シャックスがその新兵を肘でつついた。彼女は恐る恐る手を上げると、一掴みのステイシス・クリスタルを召喚した。彼は認めるようにうなずいた。
「もし恐れているのが自分の心なら」と彼は静かに言った。「私に話せ」
イコラ・レイは今でもクルーシブルにおける連続勝利記録を保持している。その記録は誰にも破れそうにない。 
クルーシブルの新シーズン開幕の日、叫び声がタワーに鳴り響いた。
手に持っていたエングラムを落としそうになるマスター・ラフール。
ザヴァラ司令官がデスクから上方へと視線を移す。
カディ55-30は無秩序に積まれた荷物の山を慌てて支えた。
ハンガーから、よく肥えたハトの群れがいっせいに飛び立った。
「新型のグレネードだ!」
「お前の光は炎だ、ガーディアン。火を灯し、轟かせろ」――シャックス卿 
シャックス卿がクルーシブルの戦場に駆け込んだ。
「近くに寄れ、チャンピオンたちよ」と彼が叫んだ。「そう、両チームだ。全員におめでとうと言いたい」
ガーディアンたちは遮蔽物の後ろから用心深く覗き込んでから、シャックスの前に集合した。
「ハードライトから放たれた弾が跳ね返って遮蔽物の後ろに回り込んだ瞬間を今でも覚えている」と彼は話し始めた。「初めてマウンテントップを渡した時のことも覚えている。クルーシブルにギャラルホルンを初めて持ち込んだガーディアンのこともだ」
巨躯の男が懐かしむように首を振った。
「お前たちの力はすぐにありふれたものになってしまうだろう。だがその力をここで初めて披露したのは間違いなくお前たちだ。私にとってはな」
「そのクリスタルを見せてくれたことに感謝する」と彼はタイタンに言った。
「よくぞその杖を使って嵐を呼び出してくれた」と彼は言うと、ウォーロックに向かってうなずいた。
「そしてお前!」
彼は大股でハンターに歩み寄るとその背中を叩いた。ハンターは持っている武器がリロードされるほどの勢いで地面に膝を打ち付けた。
「鎌を投げつけてやったな!」と陽気にシャックスは言った。
彼はハンターに手を貸して立たせると、再び一団の前へと戻った。「その力があらゆる困難を乗り越えるための導きとなるだろう」そう言うと彼は敬礼をし、ガーディアンたちは頭を下げた。
シャックス卿が腰に手を当てながら、何も言わずに、誇らしげにその場に立ちつくしている。「何をしているんだ?」と彼が言った。「対戦を再開しろ!」ガーディアンたちが再び戦い始めた。
「捕まえられないものは倒せない。やってやれ」――シャックス卿 
意気消沈したウォーロックがクルーシブルから去って行った。彼の肩の上では1体のゴーストが浮かんでいる。
「彼は気付いていたようだ」とウォーロックははっきり言った。
「意味が分かりません」とゴーストが嘘をついた。
「シャックスのことだ。彼は見ていたんだ、私が――」そう言うと、ウォーロックは手のひらを広げ、指先を小刻みに動かした。
ゴーストが肩をすくめるような動きと共に、曖昧な警告音を発した。「そうかもしれません」
ウォーロックがうめいた。「そんなに酷かったか?」
ゴーストが同情するようにノイズを出した。「そうでもありません」
ウォーロックは無表情でゴーストを見つめている。
「分かりました、かなり酷かったです」とゴーストが認めた。「ボロボロでした」
「どのくらいボロボロだ?」
「まるで誰かに倒された石像みたいでした」とゴーストが言った。「あなたがあちらこちらに散らばって… 壊れていないのはそのブーツぐらいです」
ウォーロックがゆっくりと息を吐いた。「で、シャックスにも見られたと?」
「ええ、恐らく」
ウォーロックがフードの中で表情を固くする。「なぜそう思う?」
「なぜなら」とゴーストが言葉を選びながら言った。「彼があなたに向かって、いいブーツだなと言ったからです」
「倒した相手が憎いか? 本来なら感謝するべきだ! 何を改善すればいいのか、教えてくれたのだからな」――シャックス卿 
シャックス卿はシティを見下ろしながら話し始めた。
「シティの子供は昔からガーディアンの真似をして遊んでいた。ハンマーとシールドの名を大声で叫び、ドーンブレードになりきって枝を振り回す。私はシティを歩いている最中に、幾度となく子供たちの攻撃で倒される真似をしてきた。そうすることで子供たちはいつも喜んでくれた」
シャックスが手すりを握っていた手に力を込める。
「今、子供たちは遊びの最中に他の言葉を叫んでいる。子供たちは異なる力の名を呼んでいる。それに攻撃された子供は、その場で凍り付き、一切動けなくなる。子供たちの顔には笑顔が張り付いたままだ。そして一言も発しない」
彼は話を続けようと、無意識にシティのほうを示すが、何も言わずにそのまま腕を下ろす。彼がこちらに振り返った。
「お前も私も戦士だ。武器を構えれば、その重さを知ることができる。だが子供たちは…」
彼の声に覇気がなくなる。
「それが私を不安にさせる」

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ