ユーリカ
【死因】
【関連キャラ】ギュスターヴ(上司)、クロヴィス(同僚)、ヴィルヘルム(拷問)
3312年 「蝕」 
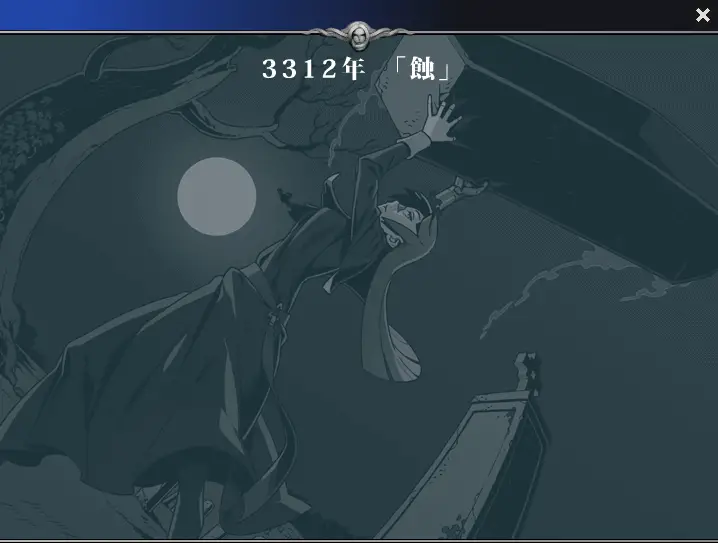
暗く湿った地下の部屋に、くぐもった呻き声が響いていた。
そこには男が鎖で繋がれており、全身に大小様々な傷を負っている。
「これでもまだ話す気はありませんか」
「だ……れが、お前たちに……」
ユーリカはそれを聞くと、掌ほどの長さがある細い針で男の肩を刺した。
何度かそれを繰り返していると、地下の部屋の扉が開いた。
「様子はどうだい?」
「よく訓練されています。こちらの提案に乗ることはないと判断してよろしいかと」
「愚かな男だ。素直に従えば、苦痛なく死ねたものを」
部屋に入ってきたクロヴィスは虫の息の男を見て、吐き捨てるように言った。
「ところで、この様な場所まで何をしに?」
「少々やってもらいたいことがあってね。本来なら貴女の手を煩わせるものではないが、貴女以外に任せられそうにない」
「そうですか。では、この男の処分はお任せします」
「わかった。仔細はあとで説明しよう」
ユーリカはミリガディアから西に12リーグほど離れた場所に来ていた。
そこはミリガディアやグランデレニア帝國の障壁の恩恵が届かないサベッジランドの一つであり、渦の影響が色濃い地域であった。
ユーリカはその地域にある古びた聖堂を訪ねていた。
「ミリガディアの僧侶様が、何故この様な所に?」
「こちらの聖堂に命の神にまつわる書物が祀られている聞き、巡礼に参りました」
「そうでしたか。でしたら、書物の閲覧が終わったら早々にお発ちになられるのがよろしいでしょう」
「どうしてまた。何か理由でもおありなのですか」
「この地域にはグールド病を患う者が多いのです。いかに命の神の加護がある僧侶様とはいえ、長く滞在すれば……」
グールド病は障壁の恩恵を受けられない荒野で発症する致死性の風土病である。有効な治療法や薬は無く、一度患ったが最後、死を待つしかないのが現状であった。
「まあ……。それはご苦労されていることでしょう」
「ここら一帯には病院もございません。僧侶様、どうかここの事は忘れて巡礼をお続けください」
ユーリカは聖堂の管理者とひとしきり会話を交わすと外へ出た。外では僧服を纏った数人の女性が待っていた。
「いかがでしたか?」
「この場所が良いでしょう。皆さん、準備を」
「承知しました」
女性達は一礼すると、足早に去っていった。
半月ほどして、ユーリカは再びあの聖堂を訪れていた。
「おお、僧侶様。どうなされましたか?」
「この地域の皆様を救う施設を作るため、そのご挨拶に参りました」
聖堂の管理者は目を見開いた。
「なんと。いや、ですが僧侶様。以前も申し上げました通りここは……」
「命の神はどの様な病に罹った者でも決して見捨てることはありません。私は命の神から陶冶を授かり、再びここへ舞い戻ったのでございます」
ユーリカは管理者の手をしっかりと握り、慈愛に満ちた言葉を伝えた。
諸々の手筈を整えると、それから半年ほど掛けて、ユーリカは聖堂から少し離れた場所に中規模の医療施設を作り上げた。
障壁が無いために集落としての体裁を成せないこの地域で、ユーリカの医療施設は盛大な歓迎を受けた。
小さな怪我から風邪、そしてグールド病に至るまで、この施設は様々な患者を受け入れていた。
普通であれば医者にさえも見捨てられてしまうグールド病の治療を施してもらえるということで、10リーグ離れた場所からわざわざ訪ねる患者もいるほどであった。
ユーリカは執務室で膨大な数の書類を見ていた。毎日のように運ばれてくる患者のカルテを見て仕分けを行う。 仕分けされるのは主にグールド病に罹患した人達の物で、それは他の患者の物とは別に、詳細がまとめられていた。
「ユーリカ様、97号の脳活動停止を確認しました。それと同室の108号の容態が急変、あと数日で脳活動も停止する見込みです」
「わかりました。101号と97号の搬送の準備をお願いします」
患者の容態を聞いても、ユーリカは眉一つ動かすことなく淡々と指示を出す。
「101号は見舞いに訪れるストームライダーが数人おりますが、いかがしますか?」
「グールド病由来の免疫低下で感染症に罹患したため隔離した、と伝えてください。搬送後は死亡し埋葬したことにすれば、彼らも手出しできないでしょう」
「承知しました」
現在のユーリカの任務は、グールド病の末期患者を見繕って組織の人体実験施設に収容することであった。
グールド病はその致死性と治療の手立てが全く無いことから、罹患した者はすべからく見捨てられる。患ったが最後、ただ死を待つだけなのだ。
組織はそれを利用し、実験材料としてグールド病患者を積極的に回収しているのだった。
それから暫く経ったある日の深夜、見舞いの客もいなくなって静まり返った医療施設の裏から、大型の馬車が出てきた。
「では、よろしくお願いします。グールド病の患者とはいえ、 大事な献体です」
「はい。全ては大善世界の実現のために」
「全ては偉大な首領、ギュスターヴ様の復活のために」
馬車がミリガディアの方角へと走っていくのを見送ると、ユーリカは医療施設の中へと入っていこうとした。
その時、馬車が去っていった方角とは別の方向から草を踏むような音が聞こえた。微かな音だったがユーリカの耳は確かにそれを捉えていた。
ユーリカが音のした方向に向かうとすると、何者かが逃げていくのが見えた。
「……警戒を強める必要がありそうですね」
次の日の昼、ユーリカ達が101号と呼称していた人物に面会を求めるストームライダーが現れた。
101号は感染症で隔離していると説明していたにも関わらず、三日と間を置かずに見舞いに訪れていた人物であった。
「お前ら!ジンをどこに連れて行った!」
このストームライダーは101号――ジン――と共に荒野で輸送業を営む男であり、友人であると名乗っていた。
「お静かに願います。あなたのご友人は感染症を併発し、それが原因で息を引き取られました」
ユーリカは責任者として、粛々とした態度でこのストームライダーに対応した。
「嘘を吐くな!俺はお前らが夜な夜な入院患者をどこかに運んでいる事を知ってるんだぞ!」
施設の受付で治療を待つ人達がざわついた。
「そのような事実はございません。いたずらに治療を受けている方々を不安に陥れるのはおやめください」
「じゃあジンと会わせろ!本当に死んでるって言うんなら、葬式くらいは!!」
「申し訳ございません。ジン様が患った感染症は非常に強い感染力を持っていたので、こちらで然るべき処置をして埋葬を行いました」
「ふざけるな!!」
ストームライダーは床に崩れ落ちてしまった。ユーリカはその男の傍に屈むと、体を支えるように起こした。
「この度の事、私達も大変心苦しく思っております。アルス、彼を墓地へ」
傍にいた看護担当の女性僧侶にストームライダーを任せると、ユーリカは受付付近で騒然としていた人々に謝罪に回るのだった。
夜も更けた頃、ユーリカは施設から少し離れたところにある墓地を訪れていた。
101号を埋葬したと偽った場所に、数人の影があるのが見えた。土が掘り返され、埋めておいた棺の蓋が開いている。
「やっぱりそうだ。ジンは死んだりしてない」
「疑って悪かったな」
「しかし、ジンはどこに連れて行かれたんだ?あの施設にはいなかったんだろ」
「ユーリカとかいう奴が知ってるに違いない」
「どうやって調べる?」
ユーリカは足音を立てずに男達の背後に迫った。墓穴に視線が集中していた男達はユーリカに気が付かない。
「がっ!!」
会話に必死だった男達の一人から鋭い呻き声が漏れた。残った二人には、男の腹部から血に塗れた女の腕が生えているのが見えた。
「なんだ!?」
「どうなってる!」
男の背後にユーリカが立っている。残りの二人は突然のことに対処できずにいた。
「遅い」
狼狽する男達にユーリカは告げると、腹部を貫いた腕を抜き、その男の体を無造作に投げ捨てた。
「貴様ぁ!」
施設で騒ぎを起こした男が漸く事態を把握し、ユーリカに向かって手榴弾を投げつけた。ユーリカはそれを片手で受け止めたが、間を置かずに爆発する。
「よし!」
男の勝利を確信した声が響く。
「待て、まだだ!ぐぁ!」
「この程度、問題はありません」
煙が風で流されるよりも前に、ユーリカの腕が手榴弾を投げ付けた男の胸を刺し貫いた。
ユーリカの腕と顔は手榴弾の爆発により焼け爛れていたが、骨や肉の代わりに金属質の何かが露出していた。
「そんな……!!お前、何者な!!」
最後に残った男が言葉を言い終わる前に、ユーリカは重たい棺を男の脳天に振り下ろしていた。
全てが沈黙した墓地に、ユーリカは夜詰めの女性僧侶を呼び出した。
「どうかなさいましたか?そのお姿は……」
「私のことに構う必要はありません。それより、ストームライダーが我々のことを探ろうとしていました」
「この死体がそれであると」
「ええ。献体の数も要求数は集まっていますし、そろそろ潮時かも知れません」
ユーリカは墓地に建てられた主のいない墓標を見回して淡々と言うと、ストームライダー達の死体の処理を任せてその場を立ち去った。
「―了―」
2993年 「恍惚」 
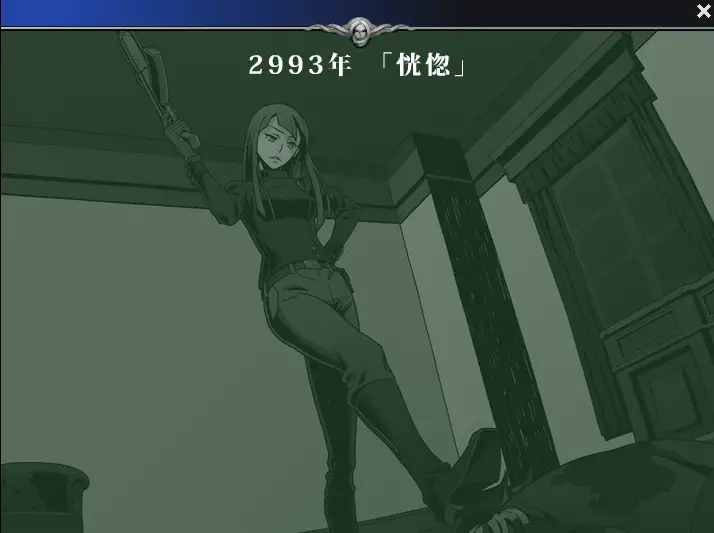
聖ダリウス大聖堂の裏手にある、掃除用具が納められた小屋。
ユーリカはそこで、仲間の諜報員から得た地下施設の情報に関して調査を行っていた。
小屋の内部を調査し、掃除用具が収められた棚の裏に隠し階段を発見する。
周囲に人の気配が無いことを確認し、ユーリカはその隠し階段を下りていく。
「これは……」
石造りで荘厳な聖ダリウス大聖堂とは様相を違え、コンクリートと金属で構成された無機質な地下に、ユーリカは衝撃を受けた。
更に詳しい調査を行いたいが、深入りすれば何者かに見つかる可能性が高まってしまう。
地下に何かしらの施設があるということが判明しただけでも、大きな収穫だった。
ユーリカはヨーラス大陸北方にある都市国家、マイオッカの軍人だ。
マイオッカは軍事政権によって統治されており、国家の安寧と領土の拡大を求めて、周辺国家の吸収を狙っていた。
吸収に有利な情報を求めるために謀報員を各地に送り込んでおり、ユーリカもその一員として活動している。
ユーリカは美貌の諜報員ノンナと共に、新興国ミリガディアに潜入していた。
ミリガディアはヨーラス大陸の南部で信仰されていた『命の神』を祀る教団が母体となった国だ。教団の理念に則って民を率いており、《渦》から逃れてきた人々を積極的に救っていた。
首都ルーベスに難民として保護されたユーリカ達は、教団の理念に感銘を受けたと装って入信に成功した。
二人は聖ダリウス大聖堂で入団の儀式を受け、表向きは信徒として真面目に教団の仕事をこなしていた。
ノンナはその美貌を利用し、高位の祭司に接触を図っていた。
ユーリカは真面目に教団の職務をこなすことで、出入り可能となる施設を着実に増やしていき、ノンナの入手した情報の裏付けを取るために行動した。
だが任務は失敗した。あまりにもノンナが祭司に探りを入れすぎ、間諜の疑義が掛けられたのだ。
投獄されたノンナを助け出し、二人は首都ルーベスから脱出を試みる。
「すまない、ユーリカ……」
「謝るのはあとだ」
ミリガディアの警官が二人を追うが、高度な潜入訓練を受けているユーリカとノンナの方が上手だった。
警官を巻き、首都ルーベスを守る障壁の外に向かう。
障壁の外ではユーリカの連絡を受けた自国の馬車と同胞が待っていた。追っ手の姿は無い。あとは馬車に乗り込んで出発しさえすれば助かる。
二人は馬車に近付いた。その刹那、連続した銃声が響く。同時に、前方にいたノンナが倒れた。
ユーリカは咄嗟に体をずらしたが、強い衝撃と熱さに体を焼かれた。
「馬鹿な……救援では……」
「逃げ帰る者には死を。将軍からの命令です」
同胞は無表情のままユーリカに小銃を向ける。
不意に周囲が明るく照らされる。ミリガディアの警官だった。
「ちっ……」
霞む視界が、馬車と共に走り去る同胞の姿を映していた。
ユーリカは自身から流れ出る血をどうすることもできず、意識を手放した。
ユーリカは目を覚ました。状況は不明だが、箱のようなものの中に寝かされていた。
顔の周辺だけがガラスで覆われていて天井を見ることができたが、この場所がコンクリートで囲まれた大聖堂の地下室に似ているくらいのことしかわからなかった。
もしここがミリガディアだとするなら、他国の諜報員である自分が何故生きているのか、それが不思議だった。
だが、それを問おうにも、いつまで経っても誰も訪れる気配は無かった。
どれ程の時間が経過したのだろう。何も摂食していないのに空腹感に襲われず、生理現象等に悩まされることも無かった。
明らかに異常なことではあったが、様々な感覚が消失している現状では、何をどうすることもできなかった。
誰とも会話せず、何もできない状況は、ユーリカに思考する時間を与えた。こんな風に自身の心と向き合って思考するのはいつ以来だろうか。
ユーリカは、己が自分の意志で何かをすることを放棄していたと思い至った。
今までは何も考えなくとも国が全てを与えてくれていた。寝床も、食事も、衣服も、そして生き方さえも。
それは、国のために奉仕する軍人を救出することなく平然と殺害する国に、何もかもを支配されていたということである。
そんな状況を当然と思っていた自分に愕然とする。
次いで、自分達を助けず、殺害しようとした将軍に憎悪が湧いた。
久方ぶりの感情の想起だったが、今の彼女にその憎悪を昇華させる手立ては無かった。
感覚さえ失われた身体では何もできない。仮に身体が動いたとしても、脆弱な一個人の身ではどうしようもない。
そのことを自覚し、身悶えしたい程に苦しんだが、どうすることもできなかった。
すっかり日課のようになってしまった思考時間中、話し声が近付いてきた。
「祖国に切り捨てられたとはいえ、彼女を抱えるのは危険すぎやしないかい?」
「そうかな?だからこそ、我々と共に進む価値があると思わんか?」
中年の男性が二人、ユーリカの箱の前で立ち止まった。どちらも見覚えがあった。大君の側近として仕える高位の祭司ギュスターヴと、この国の警察機関の長であるクロヴィスだった。
「……君の悪い癖だ、ギュスターヴ」
クロヴィスは溜息を吐いて肩を竦めると、ユーリカを一瞥する。そして、あとは好きにすればいいとばかりに一歩下がる。
「何故、私を生かした」
ユーリカはギュスターヴに問うた。音になっているかわからなかったが、自分の声は相手に届くらしい。
「お前の潜入能力は評価に値する。だから欲しいと思った。それだけに過ぎぬ」
「いつ裏切るかもわからぬ者が欲しいだと?馬鹿馬鹿しい」
「己の危険性を先に説くとは、実に好ましい。さて、そんなお前は何を望む? 何が欲しい?」
ギュスターヴは人好きのしそうな笑みを浮かべてユーリカに問う。
「……私に何をさせたい」
「吾が聞いているのだ。お前が真に望むものは何だ?」
その言葉は「己の欲望をさらけ出せ」と言っているかのようにも聞こえた。
「真に……?」
ユーリカはギュスターヴの言葉を反芻する。同時に憎悪と諦念が交差し、持て余していた感情に一つの道が示されたように感じた。
「いま暫く、吾の言葉の意味を考えるがよい」
ギュスターヴはそう言ってクロヴィスを無言で促し、背を向けた。
「ま、待て……」
その背をユーリカは呼び止めた。今ここで自分の意志を示さねばならないと思い至った。
だがそれは同時に、彼女の『今まで』を全て捨て去ることと同義であった。
「何ぞ?」
ギュスターヴは振り返る。その表情は、確信に満ちた笑みに溢れていた。
「力が必要だ。奴等に復讐するための……」
ユーリカの意志を受けたギュスターヴの口元が、深い笑みを湛えた。
数ヵ月後、ユーリカは祖国の大地を踏み締めていた。
目の前には自身を見捨てた将軍や軍人がいる諜報機関の建物がある。
勤務終了時間の直前、軍人達がほんの少し気を抜く時間に、ユーリカは奇襲を掛けた。
緊急時の脱出通路を警備する兵を拳銃で沈黙させると、そこから潜入する。よく熟知している建物だ、監視の位置やその交代時間まできっちりと把握している。
難なく将軍のいる執務室まで辿り着くと、即座にそこにいた将軍以外の軍人を撃ち殺した。
一瞬のことに対応できなかった者達は、すぐに物言わぬ肉塊となった。
こんなものに怯えていたのかと、ユーリカは嘆息する。あの時、延々と悩んでいた自分が馬鹿らしく思えた。
「ひぃ!や、やめろ!誰か!」
手足を撃ち抜かれて動けなくなった将軍は、瀕死の動物のようにのたうち回る。
軍人達のようにすぐには殺さなかった。絶望という感覚を一瞬でもいいから将軍に思い知らせたかった。
「無駄です、将軍」
「た、たす、助けて……」
「いいえ。将軍、これで終わりです」
ユーリカは怯える将軍を無表情で見つめながら、構えた小銃の引き金を引く。
腕に感じる僅かな衝撃と、軽い音がした。
「あが、ごぉ……」
脳漿と血を噴出し、将軍は動かなくなった。ユーリカは倒れた将軍に近付くと、何の躊躇いもなしにその頭を踏みつけた。
足に自身の体重を掛ける。頭蓋骨が砕ける音と、泥の中に足を思い切り踏み入れたような音が、執務室に響き渡る。
「貴方のような者でも、最後の音だけは素敵なのですね」
靴に付着した将軍だった何かを見つめ、ユーリカは淡々と、だがどこか恍惚とした風に呟いたのだった。
「―了―」
3376年 「復活」 

逆賊カレンベルクの手によって組織の首領ギュスターヴが倒されてから、長い年月が流れていた。
不幸中の幸いか、ギュスターヴの頭脳には致命的な損傷は無く、組織の技術によって完全な死を免れていた。
しかし身体に受けた傷はあまりにも深く、組織の総力を挙げて再生治療に尽力しているものの、再生には未だ活路を見出せずにいた。
ユーリカはグールド病患者を験体として収容する傍ら、かつての同志であったグラントの行方を調査していた。
「グランデレニア帝國の工業都市にて、対象者らしき姿が確認されました」
「当人であると確認でき次第、速やかに接触しなさい」
グランドはかつてギュスターヴの思想に共鳴し、ギュスターヴの手によって超人となった人物であった。しかしユーリカが組織に参画した直後に、彼なりの思惑があるとして組織を出奔していた。
グラントはギュスターヴと同じく、薄暮の時代にバイオニクス研究の権威として名を馳せていたテクノクラートである。その彼の協力を仰げば、ギュスターヴの治療も前進するであろうと考えてのことであった。
だが、グラントはその影を発見することはできても、一度として接触することは叶わなかった。
そうして、ギュスターヴの復活に目処が立たないまま長い時間が過ぎていき、組織のありようにも少々の変化が見えていた。
「ローゼンブルグの下層に設置していた孤児院ですが、最終的な処理が完了しました」
「孤児達は?」
「コンラッド祭司が抗争に利用していたようで、全員が重篤な薬物中毒に陥っています」
「……貴重な超人候補でしたが、仕方がありませんね。治療の目処が立たない者は、全て再生治療の実験に回しなさい」
組織の幹部であるコンラッドが、ローゼンブルグで進めていた超人化計画の遂行中に死亡。詳細な経緯は調査中だが、犯罪組織間の抗争に関与したことが原因であった。
古くからの幹部を失い、クロヴィスはその穴埋めのために奔走。ユーリカもローゼンブルグ内でのコンラッドの痕跡を消す作業に追われていた。
ローゼンブルグに関連する処理が終わってから間もなく、とある聖堂に滞在していたユーリカの耳に、併設の医療施設に一人の少年が収容されたとの報告が入った。
運ばれてきた少年は魔物に襲われて酷い怪我を負っており、一応の応急処置を施したものの、治療の甲斐なく死亡するであろうと思われていた。
身分を証明するものは何も無く、程なく死を迎えるであろう少年。
その少年の傷が収容時よりも回復しているとの緊急報告を受けたのは、身寄りのない少年の墓を用意せねばと手配を始めた時のことであった。
「誤診ではないのですね?」
「はい。私が彼を診たとき、彼は脊椎に致命傷を負っておりました。ですが……」
「隔離室にこの少年を運びなさい。実験を行います」
少年の身体の謎に、ユーリカは興味を抱いた。
隔離室に運び込まれて拘束された少年の腕を、ユーリカはナイフで深く切り付けた。
「ぐ……」
少年は呻き声を上げる。表情は苦痛に悶えていた。
だがそれも一時のことだ。少年の腕に付けられたナイフの傷はゆっくりと、だが常人では、いや、超人でさえも有り得ない早さで塞がっていく。
「なるほど。これは研究のし甲斐がありそうです」
ユーリカはすぐにルーベスの研究員に招集を掛けた。
この医療施設からルーベスまで、足の速い馬車を使っても一日は掛かる。少年が目を覚ます前に、ルーベスの研究所へ運び込む必要があった。
「この少年にD4265の薬剤を投与。目が覚める前に大聖堂研究所に移送します」
「承知しました」
この異常な再生能力を持つ少年こそがギュスターヴを救う鍵になると、ユーリカは確信していた。
「ここは……」
少年が目を覚ます。澱んだ昏い目がユーリカを見つめる。
だが、理由はわからないが、少年は少しの抵抗さえ見せようとしない。何が少年をそうさせるのかはわからないが、ユーリカ達にとっては好都合であった。
「それを知る必要はありません。あなたは今から、我らの首領を救うための礎となるのですから」
ユーリカのこの少年に対するもっぱらの関心は、その異様な再生能力のみにある。
「何を……」
「光栄に思いなさい。神を救うための贄となることを」
少年のいる部屋を出ると、ユーリカはそのままその足で研究者達の待機する部屋へと向かう。
「この生命体を徹底的に研究しなさい。生命活動の停止間際まで追い込むくらいが丁度よいでしょう」
「そこまでしてしまってよろしいので?」
研究者が怪訝な顔でユーリカを見る。この少年がどの超人ですら持ち得ていない再生能力を持つとはいえ、実験に耐えきれるかどうかを不安視しているようだった。
「この生命体は驚異的な回復力を持つ、人間ではない何かです。何をしようと問題はないでしょう」
「では、念のために頭部と心臓への実験は最小限に抑える、というのでは?」
「……そうですね。ギュスターヴ様を復活せしめるものが見つかる前に、万が一死んでしまっては意味がありません」
「畏まりました。最良の結果を提示してみせましょう」
「あなた方の研究に全てが掛かっています。肝に銘じておきなさい」
出自不明の少年の研究は、昼夜を問わずに続いた。
研究を続ければ続けるほどに、少年の身体が持つ特異性が明らかになっていく。
そして、少年の細胞には首領ギュスターヴを完全に復活させるに足る力があることが、確信に変わっていった。
研究者達の嬉々とした報告を、毎日のようにユーリカは聞き続けた。
「ユーリカ様、動物を使用した細胞再生の実験が成功しました」
「では、人体での検証を許可します。実験体五〇一号から五一 〇号までの十体を使用しなさい」
「はい」
幾度かの人体実験を経て、ついにギュスターヴの再生治療が開始された。
損傷が激しいために時間こそ掛かるものの、ギュスターヴの治療は確実に進んでいく。
目的を達し、ほぼ用済みとなった少年は、研究者達の体のいい実験玩具となっていた。
ギュスターヴが目を覚ましたとの報告を受けたのは、ギュスターヴが再生治療機器からベッドに移されて間もなくであった。
ユーリカとクロヴィスがギュスターヴのいる部屋へ赴くと、すでにギュスターヴは起き上がり、ベッドの上でいくつかの書類を読んでいるところであった。
「気分はどうだい?」
「うむ。何も問題ない。むしろ、若い肉体というものの健康ぶりに驚いているところだ」
「再生治療に使用した細胞による作用です」
「ほう、面白いものを作り上げたようだな。あとで研究資料を見たい」
「畏まりました。すぐに用意させます」
倒れる以前と何も変わらぬギュスターヴの様子に、ユーリカは安堵する。
クロヴィスもそれは同様であったようだ。ギュスターヴが倒れて以降ずっと引き締まっていた表情が、幾分か和らいで見えた。
それから一ヶ月は、ギュスターヴの身体検査などで慌しい時間が過ぎていった。
復活の知らせはギュスターヴ当人が『その時宜ではない』とし、再生治療に関わった研究者達と幹部のみが知るに留まっていた。
「謀反人の処分、ですか?」
「いくつかの聖堂で不穏な動きがある。そう報告があっただろう?」
「はい。ですが、ギュスターヴ様が直接手を下すまでもないかと思われますが」
長期にわたるギュスターヴの不在によって、力を持つ祭司が不穏な動きを見せ始めていた。
ユーリカ達は彼らを密かに監視下に置き、行動を起こし次第粛清に乗り出す計画であった。
「なに、彼の者らがどのような思惑で謀反を企んでいるか、直接尋ねるだけぞ」
「身体の慣らしも兼ねて、かい?」
「そうだ。この若い肉体がどれ程の力を行使できるのか、それを知りたくもあるのでな。丁度よい実験よ」
ギュスターヴは以前と変わらぬ深い笑みを浮かべた。
クロヴィスはその様子にやれやれといったように肩を竦めたが、表情は心底から嬉しそうだ。
ギュスターヴの容姿はだいぶ変わってしまったが、それ以外は何も変わっていない。
「わかりました。手配をいたします。まずは何処に潜入なさいますか?」
自らが信頼し続けた首領が本当に帰ってきたことを、ユーリカは実感する。
そして以前と同じく、ギュスターヴのためにあらゆる準備を粛々と進めるのだった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ