アーカイブ:(固有名詞 | 遺物 | キャラクター | 星神 | 敵対種 | 派閥 | 光円錐 )
本棚:(入手場所|内容:宇宙ステーション「ヘルタ」 | ヤリーロ-Ⅵ(1) | (2) | (3) | 仙舟「羅浮」(1) | (2) |(3) |ピノコニー(1)| (2) |オンパロス (1)|(2)|(3)|紡がれた物語|収録なし)
(+を押すとストーリーの詳細が閲覧できる)
遺物
流雲無痕の過客

詳細
- 頭部
- 過客の迎春かんざし
- かんざしとして使われていた枯れ木、知らぬ間に枝先につぼみが綻び始めている。
過ぎ去りし往事、已んぬる哉。金のつぼみはかんざしに嵌め込まれ、新しい命の記念となった。
無名の者は長い眠りから目覚めた。
遠くに感じるも馴染みのある緊張感は拭えず、幻痛は鋭利に神経を刺す。
過去は鋭い破片となり、自分の名前さえも忘れた。
目的のない流浪の中、彼は雪水を啜って渇きを癒し、野獣を殺して空腹を満たし、
枯れ枝を切り落として長い髪を纏めるかんざしにした。
黒い髪は湧き水のように伸び、皮膚の下の筋肉は川の鯉のように引きつり、
不思議な力が体の形を絶えず変え、筋骨の断裂と復元の痛みだけがずっと伝わって来る。
数えきれないほどの痛みの繰り返しに伴い、支離滅裂だった過去がまとまっていく…
水面に映る自分の姿を覗き込むと、惨劇の始末を少しずつ思い出す。
水面に映る顔に慣れてきた時、無名の者は枯れ枝に花芽が付くのを見た。
彼は突然我に返った。
不老不死の呪いは根強く、過去の恩讐はまだ死んでいない。
彼こそが、この枯れ枝に咲いた新生の花だ。
- 手部
- 過客の游龍腕甲
- 水のようなサンゴ金と未知の獣の革で作った腕甲。龍脈一族の巨匠のみがこのような非凡な工芸を作りだせる。
対をなす物は互いに感応するという。
無名の者は片方の腕甲しか持っていないが、その指先はもう片方の温度を感じ取れる。
彼は眼を閉じ、もう片方の腕甲との微かな繋がりを捉えようとした。
その位置、その持ち主を。
すらりとした力強い手はかつてもう片方の腕甲をつけ、長槍を持ち自分と武を競いあった。
槍先の光は流星のように天から落ちる。
腕甲の持ち主はかつて自分と無言で酒を飲み交わし、月を眺めた。
そして一意孤行の末、愛する者を化け物にし、すべての人を果てしない後悔の深淵に突き落としたのも、自分と彼だ。
対を成す物はいずれ、再度巡り合う。
その長く響く憎しみは陳酒のように、さぞ冷たく強烈であろう。
恩讐がすべて消え去るまで、ゆっくりと飲み干そう。
もう片方の腕甲の持ち主もそう思っているだろうか?彼は知りたくない。
- 胴体
- 過客の刺繍の解れた外套
- 裾がボロボロになった古い外套。刺繍には太刀筋が残っている。
傷はすぐに治るが、外套は直らない。まるで人の苦痛のようだ。
無名の者は生ける屍のように、長い流浪の旅をしていた。
屍の行く手を阻むのは、サングラスの女と大きな鎧だった。
2人の誘いが届く前に、拒絶の刃は既に繰り出された。
戦いの後、女は笑顔で彼が断りきれない取引を持ちかけてきた。
こうして無名の者は、再び文明と秩序の中に戻った。
無名の者は仕立屋に連れていかれ、採寸、製版、裁断、縫製を経て体面的な衣服を用意してもらった…
伸び放題の髪と身だしなみを整え、彼は昔の姿を取り戻した。
ぼうっとしている間、現在と過去が溶け合い混ざる感覚を覚えた。
曖昧な古き時間の中で、手製の玉壺を友人に贈ろうとしたが、決心がついたら、その人はもういないことに気付く。
彼は悟る。この身体、命、愛憎…今身に着けている服……
すべてがこの世を歩む為の借り物に過ぎないと。
彼はやがてすべてを返済して、最後の息を吐きだすのだ。
- 脚部
- 過客の冥途遊歴
- 丈夫な靴。様々な世界を渡り、生死の危機を繰り返した。
無名の者は奴隷の命令に従いながら、知り合ったばかりの仲間とはるか遠くまで旅した。
その足は戸惑いと憎しみを引きずり、無数の世界を歩み、生死の間を繰り返し彷徨った。
彼はとっくに物を作る喜びを忘れ、一つの戦場からもう一つの戦場へと足を運ぶだけ。
かつて、彼はその身で無数の極致に至った剣光を味わい、幾度となく繰り返される敗北の中で引き裂かれた。
相手はいつも心臓を貫く正確無比な一撃で彼の結末を描く。
そして今、様々な傷によって身に刻まれた剣技は彼の道標となり、生死の交錯によって鍛え上げられる。
彼は剣を振るい、仲間のために障害を切り裂き、幾度地に伏せても再び立ち上がった。
息をも殺す専心な剣舞の中、彼は一度憎しみを忘れた。
奴隷は、彼と彼が憎んだすべてに永遠の終わり、永眠の葬儀を与えると約束した。
無名の者は頷き、剣を鞘に納め、次の世界に向かった。
人生が歩みで繋がる道ならば、彼は「終点」にたどりつく前に、憎き人の血だまりを跨げる事を祈る。
草の穂ガンマン

詳細
- 頭部
- ガンマンの草の穂フェルト帽
- 草の穂をつけたフェルト帽、伝説のガンマン、オークリーのトレードマーク
オークリーのフェルト帽は亡き父から受け継いだもの、彼女は草の穂を帽子に付けて、少し可愛く見せた。
賞金稼ぎたちは故意にか、いつも自分だけのマークを作ろうとする。
そうすれば人々はいつか、それを始まりに自分の伝説を語るだろうから。
スターピースカンパニーは懸賞金を出し、様々な人を募集して宇宙盗賊団を指名手配する。
そして一匹狼のオークリーは、いつも耐え難い辺境の地に赴き賞金首を追跡する。
何日も続く苛烈な太陽、何日も続く寒い夜。孤独な旅の途中で、
オークリーはフェルト帽を枕にして、篝火の隣で夢に入る。
彼女の夢はいつも謎のガンマンに侵入される。
そのやせ細っていても鋭利な眼光を放つガンマンは、遠いところから来た賞金稼ぎと自称する。
ガンマンはオークリーの父に正午の決闘を申しだす。
銃の音が鳴り、フェルト帽が落ち、父は仰向けに倒れた。
そして母の号泣が聞こえてくる……
幼いオークリーは呆然と謎のガンマンを見る。
その人に無駄な動きはなかった。
父には勝算がなかった。
夢から覚めると、フェルト帽にはいつも涙の痕が残っていた。
子供の頃のオークリーは、父のかっこいいフェルト帽が欲しかったから銃の使い方を学び始めたのだ。
手部
- ガンマンの荒い革手袋
- 表面がひび割れている革手袋。銃を握る部分が特に摩耗している
子供の頃のオークリーは、ひたすら練習に励んでいた。
朝から晩まで牧場で射撃の練習をした。
父は、ある時は彼女の才能に喜び、ある時はガンマンの運命に心配した。
母だけがその白い小さな手を不憫に思い、父が娘に銃を教えたことに不満を抱いた。
あの決闘から、初めての懸賞任務を完了し、それから名を広めるまで、
オークリーは何年もそのボロボロな手袋をつけていた。
他の賞金稼ぎたちは彼女のこだわりを理解できない。
そこに秘められた矛盾な感情を感じられるのは、彼女自身だけ。
それは、母からの餞別の贈り物。
いつも銃の練習に反対していた母は、どんな気持ちで、どんな決意で自分を送り出したのだろう?
あの決闘の後、母親はオークリーの腕の中で泣いた。
オークリーは何も言わなかった、母は彼女の決心を知った。
胴体
- ガンマンの風狩りポンチョ
- エスニックな雰囲気の織物マント。裏地の一部が防弾仕様になっている。
ガンマンは決闘の時、最初にボロを出してはならない。
オークリーは察知されずに銃弾を装填し、ターゲットを狙う事ができる。
他の人から見れば、銃声がするまで彼女のポンチョには一切の動きがなかった。
オークリーはどうやってこのような技を繰り出したのかは誰にもわからない。
「動きは最低限に、ポンチョの下に隠して行え、決闘は銃弾が撃たれる前に完了させるんだ」父は昔よくこう言っていた。
偶然に銃を持った強盗たちと出くわした時。
オークリーは何世紀も動かなかった岩のように、賊が行動を起こす前に全ての準備を済ませていた。
数発の銃声の後、オークリーはワザと強盗を一人逃した。
盗団に丁度いい警告を送ろうと彼女は考えていた。
無表情で、無情で、相対する者は彼女を見ただけで勝算がないと思ってしまう。
これが賞金稼ぎの間で伝わっているオークリーへの評価だ。
決闘の時のオークリーは、夢に侵入する謎のガンマンみたいで、無駄な動きが一切ない。
自分が仇敵に似ていると気付いたオークリーは、自分が嫌いになった。
脚部
- ガンマンのリベットブーツ
- 開口部をV字にカットしたブーツは、カジュアルで抜け感のあるデザインで、履き心地も抜群。
長い旅は耐え難いもの、でも常に一人で行動するオークリーはとっくに慣れていた。
オークリーはいつも鞍に跨ぎ、誰も行こうとしない辺境の地へ向かい、少ない賞金で過ごしてきた。
彼女の直感が告げている。
あの謎のガンマンも彼女みたいなアウトサイダー。
彼女たちがいずれ相まみえる場所は絶対に賑やかなところではない。
ハーモニカを手に入れてからは、断続的な練習が彼女の孤独な時間の大半を占め、
通りすがりの聴衆はタランチュラと砂とタンブルウィードだけだった。
オークリーのハーモニカの腕前は旅の間にどんどん上達し、曲のために風が止んだこともあった。
カンパニーは賞金稼ぎに星間旅行のサービスを提供している。
孤独のガンマンはどこに行こうと構わない。
謎のガンマンが鳴りを潜めて久しく、
オークリーは自分は幻影を追っているのではないかと疑った時もある。
でも彼女は一度、もう一度と出発するだけ。
オークリーは信じている、「草の穂」の名が広まれば、
あの時、父を探して牧場に侵入したように、謎のガンマンは自分を探しに来ると。
純庭教会の聖騎士

詳細
- 頭部
- 聖騎士の赦しのヘルム
- 宗教彫刻の、赦しの女神を模ったヘルム、自分の顔を隠すためにある。
沈黙騎士は人前で硬く重いヘルムを外したことがない。
その荘厳で宗教的なヘルムと、サフィナの沈黙が相まって、息苦しいほどの威圧感を醸し出している。
傲慢な悪魔も、狂気に囚われた聖職者も、荘厳な圧力のもとに本能的な恐怖をさらけ出すことしかできなくなる。
教皇庁でも少数の聖職者しか知らない。
サフィナのその宗教的なヘルムの下に隠されているのは、悪魔としての出自。
教皇庁は悪魔を恐れながらも、その力を欲していた、それが矛盾な結果を生んだ…
幼年の悪魔を捕らえ、彼女を勇敢な沈黙騎士に鍛え上げた。
だが彼女が人前で素顔をさらけ出すのは禁じられ、
教皇の命に従い、聖女の沈黙騎士として従事する事だけが許された。
年の近い聖女バニラは自らサフィナに聖書の勉学を指導していた。
彼女は今でも燭光に照らされる悪魔の横顔を覚えている。
「親愛なるサフィナ、私はあなたの顔を見たことがある。ずっと覚えているわ。」
聖女バニラは、大人になってから徐々に視力を失っていった。
- 手部
- 聖騎士の沈黙の誓いの指輪
- 教会のシンボルを模った銀の指輪、少し濁った宝石がはめられている。
教皇庁の騎士達は仲間に剣を振るいかざした。
純庭教会の厳粛さと典礼は次第に崩壊し、守護を誓った指輪は濁り、穢れていった。
星の海から降り注ぐ力は、教会に悪魔を罰する力を与えたが、一方で人間性を奪う疾病を蔓延させた。
疾病に苛まれる騎士達は既に典礼と秩序を認識できなくなり、
悪魔の血を持つ者を一人残らず駆逐すると喚きたて、教会に救いをもたらすと叫ぶ。
聖女に迫る脅威を前に、サフィナに躊躇している時間はない。
たとえ相手が純庭教会の騎士長であっても、彼女は手加減できない。
サフィナは忘れていない、沈黙騎士は聖女を守るためにあると。
「親愛なるサフィナ、あなたが罪悪感を感じる必要はありません。これは星神の力を貪ろうとした、当然の結果よ」
教会に残ったのは、最後の聖女と守護騎士のみである。
- 胴体
- 聖騎士の厳かな鎧
- 重厚な鎧には、純庭教会の特徴的なシンボルがあしらわれ、接合部は密封性が高い。
沈黙騎士の鎧は、バニラの祝福を受ける必要があり、それを以て守護騎士の誓いの儀式を完成させる。
純庭教会はかつて金属の鎖で幼き悪魔の手足を縛り拘束した。
今、サフィナは悪魔の国からの金属で鎧を鋳造し、死ぬ時に故郷が傍に居れるよう懇願した。
純庭教会の聖女は鎧に付いた罪を丁寧に洗い流し、敬虔に神に祈りを捧げ、
古の奇跡をプレートアーマーの心臓の位置に封印した。
教会は悪魔の忠誠を信用しなかったが、教義は全てを浄化する力を持つと堅信していた。
サフィナは静かに、古の儀式が己に責任を与える過程を注視した。
聖女は儀式そのものの目的を信じていない、在りもしない罪など洗いようがない。
「親愛なるサフィナ、騎士は聖女を守るのよ」
バニラはサフィナの胸甲に寄りかかると、激しい鼓動が聞こえた。
- 脚部
- 聖騎士の秩序の鉄靴
- 純庭教会騎士団の制式騎士用靴。かかとには「秩序」という短い単語が刻まれている。
純庭教会は崩壊した。
サフィナは騎士の鉄靴を脱ぎ棄て、聖女バニラと共に悪魔の国への長い旅に出た。
聖女の懇願の下、サフィナは全ての騎士と疾病を教会に残した。
この秘密は彼女たちが永遠に守っていく事にした。
何時からか、人々はとある噂を聞いた。
教会に駆逐された悪魔の血族は清潔なる沈黙騎士に憑依し、
邪悪な魔女は騎士を操り教皇の秩序を破壊した…
噂はやがて「真相」となり、敬虔な信徒たちは沈黙騎士を災いの元凶とし、絶望と狂気を彼女にぶつけた。
居場所をなくした後、聖女は里帰りを彼女に提案した。
「今から、私は魔女になり、あなたは悪魔に戻るの」
サフィナはバニラの言葉を否定できなかった。
雪の密林の狩人

詳細
- 頭部
- 狩人の荒ぶる神のフード
- 巨大な雪原熊の頭部の毛皮で作ったフード。毛皮に魂があるかのように、刀も銃の弾も通さない。
スノーランドの雪原で活動する狩人の間には一つの鉄則が存在している。
それは、「荒神」の捕食期間でけして山の南側に行ってはいけないこと。
あの山でさえ震わせる白き巨熊は誰も歓迎しないからだ。
協会が指定した狩人として、シューガは救援信号を受信し、山の南側へ駆けつけたが、そこで待ち伏せされた。
銃撃のショックから目を覚ましたシューガは助かったと思ったが、
次の瞬間、危機はまだ過ぎていないと理解した。
「荒神」が彼の前に立っていた。「荒神」の攻撃は力強く素早いが、
乱暴に回すだけではそう簡単に当たらないはず…
シューガは冷静にチャンスを待つ。
彼は劇毒を塗った骨ナイフは抜き出し、常人を超える動きで飛び上がり、一瞬で勝負を逆転した。
彼は「荒神」の頭と皮をはぎ取り、銃傷が癒えぬ状況で一日目の夜を過ごした。
数日後、狩人協会は頭のない「荒神」の死体を見つけた。
そして彼らは知る、死ぬべき狩人は死なず、予想外の復讐者が誕生してしまった。
- 手部
- 狩人のオオトカゲグローブ
- ''雪岩オオトカゲのうろこ状の爪は、グローブにしっかりと縫い付けられており、
どんな壁も自由に登ったりぶら下がったりできるようになっている。''
雪岩オオトカゲには敏捷性も圧倒的な強さもない。
彼らは獲物が油断し、必殺の一撃を食らわせるチャンスが訪れるまで、半月ほど岩肌に潜むこともある。
けど公認狩人はもう待てない、彼らは迫る脅威を取り除くため、
雪山で全面的な捜索を展開し、シューガを狩ろうとした。
協会の公認狩人は一人一人が精強だが、命を託せあえる仲ではない。
狩人はただ、高額の賞金目当てに群がっているだけ、それに賞金が原因で裏切る事もしばしば——
何せ、荒野では何が起きてもおかしくないのだから…ベテランのシューガを消せば、
他の人の取り分が多くなれる。
彼らの意見はまとまった、そして相応の代価を支払った。
シューガは十分な準備をした、高レベルの狩人を狩るのは怪物を殺すより骨が折れる。
ここからは一層辛抱強く行動しなければいけない。
辛抱こそが、狩人にとって最も重要な素質。
猟友会の公認狩人は減り続け、「不死身のシューガ」という恐怖が彼らの間で蔓延する。
- 胴体
- 狩人の氷竜マント
- 氷竜の細かい鱗で作られたマントで、奇妙な光の屈折でほとんど見えない。
「氷湖の主」には独特な鱗が生えている。
昼間はまぶしく光を反射し、水に浸かるとその姿を隠せる。
見えない巨大生物との戦い方を知る狩人は非常に少ない。
数日後、狩人協会の公認狩人たちは鱗を剥ぎ取られた氷竜の死体を発見した。
その瞬間、恐怖は驚愕に勝った。
シューガは雪原の獣を何百何千も狩ってきた。
全ての対決は唯一無二の体験で、意義がある。
狩人にとって、獲物の個性と習性を観察、知り尽くす事でようやく、一つの狩りは完成したと言える…
シューガにとって、「氷湖の主」は雪原のパズルを完成させる最後の1ピース。
彼は狩りを完成しなければならない。
彼の狩人の魂を完成させなければならない。
賞金リストの最上位は「氷湖の主」から「狩人シューガ」に変更され、醜い狩りが始まった。
全ての狩人は獲物になる覚悟をしなければならない、シューガも、裏切り者も。
- 脚部
- 狩人の鹿革のブーツ
- シフゾウの柔らかな毛は、ブーツを包み込み、雪原で狩人は靴の浅い跡しか残さない。
たとえ重傷を負っても、体温が雪を解かせない程低下しても、死に際のシフゾウは依然致命的な脅威となり得る。
シューガが猟銃を死に際のシフゾウに向けた時、彼は思う。
その憤怒に満ちた両目は自分と同じだと。
公認狩人に待ち伏せされてから、シューガの命の火は風前の灯火のように、いつ消えてもおかしくない状態だった。
シューガは理解している、自分がまだ生きていられるのは、復讐の怒りが体を動かしているから。
彼の欲念が満たされたその時、その命は飛び交じる雪と共に去るのだろう…
シューガは一歩踏み出す度に体が重くなるのを感じるが、幅の広い鹿革のブーツは足跡を残さない。
彼は気を引き締めて生涯最後の狩りに挑む。
狩人協会は恐怖の中で瓦解し、シューガの許しを得るため、裏切り者を粛清し始めた。
だがその行動がもたらしたのは更なる猜疑と自滅だけだった。
シューガは復讐成功の快感を味わう前に、雪原で倒れた。
成り上がりチャンピオン

詳細
- 頭部
- チャンピオンの王冠ヘッドギア
- 防衛効果絶大なヘッドギア、持ち主の頭に完璧にフィットする。
路上で暮らしていたリンジーは、公式試合のオファーが来るだなんて考えもしていなかった。
自分に勝てる相手がいるとは思わなかった、ましてやそれが50歳を超えた老人だなんて。
ボクシングコーチを名乗る老人は、勝ったら弟子になれと言い、リンジーに挑んできた。
リンジーは、動きづらい衣服を嫌がり、老人から渡された防具も捨てた。
反射神経で圧倒するつもりだったが、三歩も動かないうちに老人に接近され、正面から拳を食らった。
しばらく気絶した後、リンジーはヘッドギアを拾い上げ頭に付けた。
さっきまでは無用の長物と思っていたヘッドギアだが、その狭い視野からは新たな景色が見えていた。
「これがボクサーの拳か?面白い、教えてくれるってんなら、アタシを最強にしろ」
文句を言いながらも、リンジーは負けを認めた。
彼女は防具を身につけ、正式にボクシングの世界に足を踏み入れた。
- 手部
- チャンピオンのチェストガード
- よく手入れされたボクシンググローブ、細かな摩耗は試合に影響はしない。
リングに上がったばかりのリンジーのスタイルは尖っていて、攻撃するしか知らず、防御はほとんどしなかった。
縄で囲まれたリングの上では、路上喧嘩の経験は活かせない、イカトリーナがマッチした試合はリンジーの高慢を砕いた。
地元大会での挫折をきっかけに、それまでの傲慢と自信が崩れ、
リンジーはイカトリーナから教わった攻防のリズムを真剣に考えるようになる。
パンチの打ち方しか知らなかったリンジーは、戦いの女神の接吻を受けたかのように、
攻防の切り替えの面白さを次第に理解していった。
気づいた時には、ゲルの指サポーターは折れ、手袋は血と汗で汚れていた。
「相手の罠に嵌まらないように、自分のリズムを掴みなさい」
その瞬間、リンジーはイカトリーナのこの言葉を理解した。
自分を見る優しい眼差しは、我が子を見守るようだった。
- 胴体
- チャンピオンの重砲グローブ
- ボクサーのチェストガード、ガードとインナーを組み合わせることで、技の性能を損なうことなく安全性を保証している。
タイトルマッチ前夜のジム、いつもと同じように素早く、重いパンチがサンドバッグにぶつけられていた。
汗がチェストガードに浸透する、灼熱の空気はリンジーと現実を隔てた、彼女は逃げ出したい。
汗と涙が混じった顔にキラキラと光を反射させながら、リンジーは必死に感情を抑えた。
深夜、彼女はチェストガードを外し、内側に「イカ」との名前を書き、この名の下に勝利を誓った。
これはチャンピオンへの道のりで重要な1戦であり、リンジーにとっては初めてのコーチ不在の試合となる。
リングに上がる前、リンジーはカメラに向かって堂々と胸を張った。
「リンジー…あなたは私の娘と同じ名前を持っている。
娘が離れてしまった時は、世界が壊れたとさえ思っていたわ、でも私はあなたに出会った。ありがとうね、リンジー」
「私を守って、イカ」大切な名前は、胸にある。
- 脚部
- チャンピオンの狐歩シューズ
- レザーとネットを巧みに組み合わせ、厚みのあるインソールと薄いソールで柔軟なステップを可能にする。
小柄なリンジーは、花に移る蝶のように軽やかなステップで、素早く俊敏にパンチを繰り出すスタイルで定評を得た。
相手の拳は雨のように止まらず襲い掛かるが、リンジーにはかすりさえしない。これこそ彼女が誇る「リンジーステップ」である。
リンジーの独特なステップを鍛えるため、イカトリーナはかつて路上で暮らしていた少女を上流階級の舞踏会に連れていった。
手を繋いで、回る回る……リンジーは、つまずきながらも徐々についていけるようになり、ボクシングコーチを名乗るこの老人が、
単なるコーチ以上の存在であることに気づいた。
恍惚としたダンスフロアの中で、リンジーの心のどこかにある柔い場所に突然、奇妙な感覚が訪れる。
「もう1曲踊りたいの?」
路上で暮らしていたリンジーはこのような体験をできるだなんて想像したこともない。
イカトリーナの澄んだ瞳を見た彼女は、拒むことができなかった。
吹雪と対峙する兵士

詳細
- 頭部
- 兵士の鉄製ヘルム
- 統一改造を経たフルフェイス・ヘルム、内部パッドで頭部を保温できる。
寒波の中で侵略に対する万全な準備を行うのは決して簡単なことではないが、ヤリーロ-VIのシルバーメインは慣れている。
身を切るような寒風はナイフのように、ヘルムの隙間から吹き通る。
天外から来た敵は再び軍勢を整え、完全武装した兵士たちは大守護者の命でそれを待ち構える。
前哨部隊の兵士たちは、モンスターの動きを探るため、何日も雪の中に身を潜めていなければならないこともある。
凍てつくような寒さは、兵士の皮膚、汗、ヘルムに詰まった綿を一緒に凍らせてしまう。
ヘルムを安全に取り外すために熱湯が必要な場合も多い。
建創者の鍛冶屋たちは、重たいヘルムが吹雪の抗力を軽減できるように、板金の湾曲度を調整した。
堅く、暖かく、威風堂堂なシルバーメインの制式ヘルムはこのように継承されてきた。
「そのヘルムをつけて、前が見えるのか?」当直の兵士は皆、同じ質問をされたことがある。
- 手部
- 兵士の旧制軍服
- 銀色の光を放つ金属のガントレット、複合的な機械構造が深く刻み込まれている。
壊滅の印を持つ侵入者たちは近衛隊の退路を阻んだ。
ラースロー・ランドゥーは守護者の保護と避難を隊員に命じ、自分一人でしんがりを務めた。
たとえシルバーメインで最も勇猛な戍衛官であっても、モンスターの奔流の中では長く持たない。
獰猛で野蛮、怪異な生き物は咆哮する、嵐のような激しい攻撃が止まず押し寄せるが、ランドゥーの戦線を突破する事はできなかった。
激烈な攻防は長く続く、ラースローは次第に疲弊していったが、それでも立ち続けた。
そして援軍の到達を確認して、ラースローはようやく、安心して気絶した。
ラースローは戦いの中で両手を失った。建創者の中で最も優れた職人は英雄のため精巧な手甲を作った。
そのおかげで彼は軍に復帰し、もう一度その手で軍旗を掲げられた。
「これには一つの欠点がある」ラースローは手甲を見ながら呟いた。
「この手はもう、琴の弦の震えを感じることはできない」
- 胴体
- 兵士の鉄鱗ガントレット
- きちんとアイロンがかけられた旧制シルバーメインの軍服、丈夫なボタンで生地にしわができている。
ゲーテ家の先祖から伝わる古い軍服は、長い間箱の底にしまわれており、軍人の名誉だけがそれをこの世に蘇らせる。
壊滅の兵卒は野蛮に侵攻を進める。既に退路がないシルバーメインは、天険を守り抜くと誓う。
ヴィバロ防衛線で、ホルス・ゲーテは決死隊を率いて何ヶ月も要害を死守した。
援軍のラッパが谷間に響いて初めて、皆は英雄たちは骨すら残っていないことを知った。
大守護者アリサは、表彰式で勇敢なホルス・ゲーテの子孫に自ら勲章を授与し、若きゲーテは戦死した英雄を代表して古い軍服で堂々と立った。
若きゲーテの目に映るのは軍服と勲章だけだが、大守護者は英雄たちが残した遺産が見えた——ベロブルグの未来が。
「ホルス・ゲーテこそ真の勇者だ、お前はゲーテの名を誇りに思え」若き日のゲーテが、大守護者について唯一覚えている事がこの言葉である。
- 脚部
- 兵士の白銀グリーブ
- 固い白銀色の金属でできたグリーブ、保護性がありながら、軽量で十分な保温性もある。
シルバーメインは、戦術上の理由から、腰まである雪の中を1日に非常に長い距離も移動しなければならないことがよくある。
長距離行軍の疲労と重度の凍傷は、兵士の足に試練を課す。
雪原へ遠征する途中、たまに久しぶりの旧友に会う事もある。
雪原遊撃を担当するシルバーメインは、時折野営地で氷原オオカミの長い遠吠えを耳にすることがある。
このかわいそうな生き物も、侵略者の鉄蹄の下で居場所をなくしてしまった。
野戦中隊のイェーガー士官は、狩人の家の生まれ、彼は狼の毛皮のマントにする名人だった。
しかし、終わりなき寒波が到来してからは、この猛獣を見ることはほとんどなくなった。
寒い夜、数匹の氷原オオカミが警戒を解き、軍の焚き火に近づき、何も言わずにイェーガーのそばに丸まった。
夜が明けると、獣たちは温かな夢の中で永遠の眠りにつく。
寒さを少しでも緩和できるよう、イェーガー士官は処理した狼の毛皮を兵士のグリーブに入れた。
「私たちと同じように、氷原オオカミもまだ住処を完全に失くしたわけではない」イェーガー士官はそう言って、氷原オオカミを憐れんだ。
溶岩で鍛造する火匠

詳細
- 頭部
- 火匠の黒曜レンズ
- 漆黒の結晶で創られたゴーグルのレンズ。このレンズを通せば、激しく弾ける火も、微かな残影になる。
神兵の武器を鍛える、それは火匠一族にとって天賦の使命であり、一生の呪いでもあった。
解放された火匠一族は戦争洪炉の世界に移住し、その才能の極致を発揮すると同時に、壊滅の息吹に染まり始めた。
炉の光と火花は目を焼く程に輝く。鍛造の過程で、素材は神器となり、匠は視力を失う。
フーイは、火山の麓で珍しい黒曜炎晶を見つけ、丁寧に磨いてゴーグルのレンズを作った。
それから、強烈な火花は、青白いシルエットだけになった。
しかし、強欲な匠は呪いから逃れることはできず、全てを究極の炎の中で燃やした。
フーイは戦争洪炉の中の反物質レギオンを鍛えられる素材と見なし、自分自身を燃え盛る烈火とした。
「例えば、熱核反応を私の炉にできる可能性はないのでしょうか?」
フーイは、限界まで高められる炎を探し求め、暴走した核融合反応の中で滅んでしまった。
- 手部
- 火匠の防炎エプロン
- 炎のシンボルが彫られた指輪、火匠一族の最高の名誉の証。
九百度の炎は粘土を陶器にし、数千度の炉火は銅や錫を溶かす…原始的な鍛造ほど、極限の温度を求める。
レギオンの生物は物質の拘束からの解放を渇望し、壊滅の熱波がもたらす昇変を追い求める。
熟練した匠は、信じられない程の高温の炎を生成できる。
烈炎の黒体放射は青い光を放つ、それはもうすぐ死ぬ恒星のようであった。
火匠は皆、烈炎を操る天才だが、その中でも特に優れた者だけが、達人の証である操炎の指輪を与えられる。
戦争洪炉はもはや匠と素材を区別しない、反物質の生物を鍛える火匠たちも壊滅の武器の一部となった。
「鍛造品は炉の温度が決める、炉の温度は火匠が決める」壊滅の技能を掌握する火匠にとって、これは当たり前のことである。
- 胴体
- 火匠の操炎の指輪
- 鍛冶職人のエプロンには無駄な装飾がなく、革のシボと家紋だけがはっきりと見える。
反物質レギオンは朽ち果てた「戦争洪炉」を火匠に贈り、彼らが火の世界で自由に鍛造できるように計らった。
両目を焦がす溶岩の世界でハンマーを振り続ければ、新生と壊滅は二律背反ではなくなる。
ソルトは、活火山から噴出する溶岩を利用して、レギオンの武器に激しい壊滅の息吹を付与するのを得意としていた。
沸騰する猛毒のガスも、躍動する溶岩も、ソルトの焼入れを妨げることはできない。
熱を受け止めるソルトのエプロンは炎オオトカゲの皮でできた防火仕様である。溶岩が引いた後でも、エプロンは新品同様だった。
レギオンの戦力は洪炉の中で、肉体と武器が融合するまで何度も鍛えられ、壊滅の兵器と成る。
「唯一絶対の壊滅の力を……」炎を操る匠たちは、その武器に込めた恐ろしい欲望を決して隠さなかった。
- 脚部
- 火匠の合金義肢
- 金属素材の義肢。表面には立体的な炎の紋様が絡みついている。
古の時代、牢獄世界の主は無二の鍛造技術を失うことを憂い、卑怯な手段で火匠一族を縛った
——禁錮されていた時期、火匠の族長は皆脚部に障害があった。
壊滅の主は囚われの火匠一族を解放し、壊滅の印は火匠たちに尽きる事のない力を与えた。
牢獄を離れた後でも、火匠の族長は常人のように行動できなかった、だが彼は真の自由を手に入れた
——卓越した技術のせいで囚われる事のない自由を。
族長は怨恨と屈辱を鍛造に傾注し、連日ハンマーを振っても全く疲れを感じなかった。
頑固で高慢な反物質の生物でさえ、何度も叩かれるうちに形を変え、壊滅者の改造に屈するしかなかった。
形ある牢獄は消えたが、鍛造への狂気的な打ち込みも一種の牢獄ではないのか?
「生身の身体は妨げ、鍛造もまた壊滅」族長は欠けていく匠が増えるのを見て、感慨深く語る。
星の如く輝く天才

詳細
- 頭部
- 天才の長距離センシング
- 超距離センシング技術によって作られた通信ゴーグル、伝送媒体や距離の束縛を打ち破った。
天才クラブのメンバーはほとんどが変わり者。公知の事実として、変わり者同士はあまり交流をしない。
異なる世界に住む天才たちにとって、人付き合いはかなり余計な負担となる。凡人だってそうだろう?
しかし、会員#56、天才クラブ第2代会長のイリアスサラスはこの問題を解決しようとした。
彼は当時のメンバーに、超距離センシング付きの通信ゴーグルを用意したのだ。
残念ながら、星の間に橋を架けたにも関わらず、それを渡ろうとする者はほとんどいなかった
——銀河系史上最高の通信デバイスは、その誕生以来、真の効果を発揮したことはほぼない。
「『おかきになった相手は、オフライヌ状態です』AIを装って僕の通信を切る時くらいは真剣にやってくれ……」
無理は承知の上で推し進めていたが、イリアスサラスはため息をつく。
でも積極的にやってみないと、どうせこの技術はいつか普及するのだから。
- 手部
- 天才のメタバース深潜
- 高度な周波数変動センサーを装着した手袋は、客観的な音響振動や光学振動を視覚的に操作することが可能。
養父が経営する果物屋で雑用をこなしながら、いかにバレずにサボるかが会員#84のスティーブン・ロイドの小さな課題であった。
彼は特定の周波数帯を捉える手袋を作った。
散逸する音や光をキャッチして、自身は周波のフェンスに隠れて楽器の練習を楽しむ。
特定空間内の音と光をその場に留める技術は科学界を覆す大発明だ。
少なくとも、現在のリルタ古典力学体系ではそれを解釈できない…
でも本人はその技術を世に出すつもりはなかった。
何せ、サボるためのおもちゃに過ぎないのだから。
「スティーブン、何をやったか知らんが、お前、サボっているだろ?」
スティーブン・ロイドは「天才の中の天才」だと呼ばれるが、養父にとっては、ただの夢を見るのとサボるのが好きな子供でしかない。
- 胴体
- 天才の周波数変動キャッチャー
- 起動すると全身潜水服のようになり、全身からの神経信号をリアルタイムでメタバースに伝達する。
会員#29、セセルカルが創造したメタバース空間は生物種や次元の相違を超越した世界、
どんな生物でも深潜装置を使うだけで神経信号を意識ネットワークに同調させることが可能だ。
世界を超えられない生物も、共通の夢を通して、現実では存在しない安らぎと平穏を求められる。
仮想データが織りなすメタバース空間で、宇宙生命は無数の文化財を創造した。
そこに新たな秩序が静かに確立されつつある。
しかし、新たな楽園が現実に取って代わることが予測された矢先、
「創世の織り手」セセルカルは冗談のように意識ネットワークの接続を切断し、メタバース全体は冬の日のような静寂に包まれた。
「毎日メタバースを口にしている投資者たちはみんな狂っちゃったよ。
関連産業はこれから発展していくはずなのに、肝心のメタバースが消えちゃった」
人々はよく、メタバースを失った後に憶測する。
メタバースは元々魂のシャーレであって、様々な生物を招き入れるのは、無料の魂サンプルを手に入れるためだったのではないか、と。
- 脚部
- 天才の引力漫歩
- 引力キャッチが実装された装置で、スケート靴に似ていて、高速で滑走する際に、星々の光を映し出す。
クラブ会員#64、悪名高い「原始博士」は、
自分が犯した大罪により、果てしない銀河のところどころから迫る追っ手から逃げ回る人生を送っている。
「原始博士」は楽しんでいるように見える。
レンジャーに捕まらない程度の距離を取るも、彼を追跡できる手がかりは残している。
彼は脱出する際、ある種の引力捕獲技術を応用し、引力だけで宇宙空間を自由に歩き回ることを可能にした。
博識学会の宇宙物理学者は、その原理を理解することができず、惑星間の引力の違いが重要だと推測するしかなかった。
「原始博士」を追う者たちは、重力に縛られる乗り物で辛うじて後を追い、大罪の犯人を捕まえると決意した。
「宇宙漫歩はロマンティックだ」巡海レンジャーは言う、「残念なのは、それをやってる人が原始博士であることだ」
「原始博士」が完全に消息を絶った後でも、巡海レンジャーは「死亡推定」を信じず、追跡を続けた。
雷鳴轟くバンド

詳細
- 頭部
- バンドの偏光サングラス
- メインボーカルの1人であるジャニスのサングラス、クロームメッキのレンズは、青い光を反射する。
恒星の寿命が急速に消えゆく。赤色巨星が爆発する前に、エメラルド-IIIの住人は故郷の星から逃げ出した。
逃げ場のない未来と直面する時、エリートたちは絶望の慟哭から目を背け、希望だけを持ち去った。
ジャニスの両親は他星系の救援を期待して、巨額の信用ポイントを支払って船に乗り込んだ。
惑星は赤色巨星の爆発で破壊され、恒星は白色矮星になる…
目に見える終末が降臨する前に逃げ出すのが唯一の答えだろう。
だが混沌医師のジャニスは銀河の滅亡に真正面から立ち向かい、存在の痕跡が無に帰することはないと証明しようとした。
死にゆく太陽はさらに明るさを増す。ジャニスは母のサングラスを持ち、同じ志を持つ若者たちと共に故郷の星に帰った。
「臆病者は外に向かって逃げるだけなのに、口では救済を叫ぶ」『廉価な救済』。
激雷バンドのファースト・アルバムからのシングルで、ジャニスが両親との喧嘩の際に発した怒りの言葉を歌詞にしたもの。
- 手部
- バンドのスパイク付き革ジャン
- ベース担当シドのブレスレット、ツアーで使用したリボンブレスレットで編んだ。歌詞が書かれている。
エメラルド-IIIの激雷バンドは、僅かな先行曲で、あっという間に星全体を沸かせた。
リズムギタリストのデヴィが激しくスウィープする時に弾ける火花は開幕の合図だが、ファンたちはそれを余生最後の光としている。
バンドのライブツアーではファンが自発的に秩序を守り、入場時に身分を識別するシルクの腕輪を観客に渡す。
ほとんどのファンは高額な避難費用を払えなく、ガンマ線バーストを迎える運命を受け入れた。
でも反逆的な若者たちが惑星に戻ったのを目撃し、彼らの中にもインスピレーションの炎が点けられた。
彼らは腕輪に歌詞を書き下ろし、上演日を記録し、己が発する魂の叫びを刻んだ。
ベースのシドはツアーの度に腕輪を集め、ガールフレンドのナンシーにブレスレットにしてもらい、いつも身に着けている。
「俺たちには、意味も、方向性も、行くところも、未来もない」『僕たちの路』、激雷バンドのセカンドアルバム。シドの人生の信条。
- 胴体
- バンドのツアーブレスレット
- メインボーカルの1人であるダビデは、革ジャンの背中に白い星を描いた。それは、バンドの最後のアルバムのジャケットとなった。
激雷バンドのロックが銀河中に鳴り響き、逃げることをよしとしなかった若者たちが、滅びゆくエメラルド-IIIに戻ってきた。
リードギターのジミーはバンドを地下に移した。彼らはここで歌う。
彼らはここで惑星崩壊の悲鳴を宇宙に伝える。
上演する前、ダビデはスパイクのついたレザージャケットの背中に白い星を描いた。
それは星が崩壊した後の白色矮星、その星が存在していた証明。
星を去った者も、滅亡を前にして残った者も、共に轟くロックに耳を傾け、印象的なシンボルを振り回した。
バンドは消えたが、彼らの存在は曲に刻まれ、永遠となった。
「我らは命を燃やし、孤独な白星を照らす」『白星』、激雷バンドの最後のアルバム、作詞はダビデが担当した。
- 脚部
- バンドのリベットブーツ
- ドラマー、ボーナムのブーツ。ステージのライトを反射する塗装面にはリベットが接着されている。
激雷バンドは人々の終末に対する態度を変えたが、その結末は変えられなかった。
荒廃した惑星の地表は退廃と悲しみに満ちていた。
物資が乏しい時代、バンドは廃棄されたX線フィルムに全アルバムを焼いた。
エメラルド-IIIに長き夜が訪れた時、地表の温度は急速に低下し、外は涼しくなった。
人々は地下シェルターから湧き出て、バンドの後を追った。
ファイナルツアー「雷鳴」の会場。
不安定な空気には電磁嵐の予兆が漂い、雷は金属のセットを通ってステージに伝わる。
雷光はボーナムの足元で躍動し、バンドは完全に雷電と一体となった。
アンコール曲が終わると、巨大な球電がステージを包み込んだ。
カーテンコールの夜が過ぎ、激雷バンドの上演は絶唱となった、彼らの歌詞のように。
「雷が俺たちの声を覆い、稲妻が血に沿って奔る。音楽と共に、星と滅びよ」『激雷の歌』、激雷バンドの最後のアルバム、ボーナムの代表作。
昼夜の狭間を翔ける鷹

詳細
- 頭部
- 空飛ぶ鷹の長嘴ヘルメット
- 高速飛行に使われるヘルメット、空漁鷹の嘴に似ている。
サルソットの空漁人は、毎日夜明けに移動都市の「エアーポート」から出発し、
滑空スーツを着て空を飛び、砂から飛び出す燃素クラゲを狩る。
「位相霊火」で構成された燃素クラゲは巨大な移動都市を駆動する血液、
十分な量を捕獲しなければ、都市は明暗境界線に追いつかれてしまう。
もし誰かが力尽きたり、巨大な鳥に襲われ命を落とした場合、サルソット人はあらゆる手段を講じてその遺骸を持ち帰り、
滑空スーツとヘルメットを亡骸と共に暗黒の大地に埋葬する。
サルソットの伝統儀式の中で、「地に落ちる」とは死であり、永遠の休息である。
飛翔を止めてはいけない、都市も止めてはいけない。
鷹の嘴型のヘルメットの先の部分には、辞世の句が刻まれている。
「大地は鷹を縛る鎖ではない、翼こそが鎖なのだ。翼があるから、お前は飛び続ける」
- 手部
- 空飛ぶ鷹の翼装ベルト
- 卓越したベテラン空漁人が付けている指輪、空漁鷹の翼を模っている。
技術が最も卓越していて、最も尊敬され、頼りにされる空漁隊長だけが「双翼指輪」を授与される。
彼らは最も鋭い鷹、空中で笛を鳴らし、隙のない連携を組む。
孤独で脆い飛行の中、隊長から伝わる124種の「音色」だけが、隊員たちの頼りになる。
そのため、サルソットではとある諺がある:「空漁人はその命の3分の1を熟練の技に、3分の1を巧みな道具に託している。
そして最後の3分の1を信頼できるリーダーに託している」
多くの家庭から子を託された隊長は、その小さな指輪の重さを切実に感じる。
この指輪のエッチングは既に劣化している、内側には「責任」という単語が刻まれている。
- 胴体
- 空飛ぶ鷹の双翼指輪
- 滑空スーツの翼を繋ぐベルト、金属支柱は厚手の麻束の中に隠されており、柔らかく体にフィットする。
サルソットの空漁人にとって、砂の中から飛んでくる燃素クラゲを捕らえるのは容易ではない。乱気流の中で、一見柔らかくか細いベルトは、都市の外の空域を吹き抜ける強風の中では空漁人の命綱となるのだ。
砂から飛び出る燃素クラゲを捕まえるのは非常に難しい。フェイント、追い込み、獲物の確保、どの作業も常に命の危険が伴う。
未成年の空漁人は、両親の髪をそれぞれ1本ずつ支柱に編み込むが、結婚している場合は配偶者が用意することになっている。そのようにして出来たベルトは、「家」の祝福の下、空漁人が無事に家に帰れるように守ってくれる。
残酷な世界で空漁人を優しく支えてくれるのは、「家」だけだ。
このベルトに編み込まれた髪は女性のもののようである、根本は少し白い。
- 脚部
- 空飛ぶ鷹の羽毛バンド
- 飛行中に足の温度を維持するバンド、空漁鷹の羽があしらわれている。
サルソットの空漁人が燃素クラゲを狩る過程は生存をかけた長い戦いである。
心臓から離れた両脚は、羽毛バンドで包み温度を保つ必要がある。
限界を迎えた肉体に痛みや疲れが現れ始めるのは、いつも長時間の激しい狩りの後。
対策が不十分だった空漁人は、その時やっと重度の凍傷による局所的な壊死に気付く。
そのため、空漁人は出発する前に何度もバンドの状態を確認する、高速飛行の間に二次調整のチャンスはないからだ。
彼らは天空に足を踏み入れたその時から分かっている、疾風が何を持っていくかを。
このバンドに内蔵された金属製のケースには、
石灰やアルミの粉末が使われていた痕跡がわずかに残っており、非常用の加熱手段として使われていたようだ。
流星の跡を追う怪盗
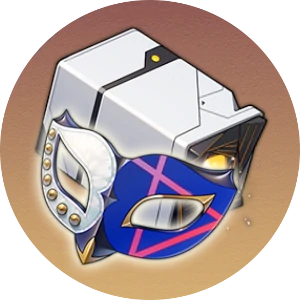
詳細
- 頭部
- 怪盗の千人仮面
- 変装用の仮面、卓越した演技力と相まって、本物と見紛うばかりの出来栄えである。
流星怪盗ルブランは、盗みと仮面舞踏会への参加を同じものだと考えている。
身分を隠すことはマナーの1つ。
「何故仮面は身長や声まで変えられるのか?ハハハハ、それは私の特許技術、秘密だ」
怪盗は仮面を使い、社員に変装してカンパニーのセキュリティ会議に潜入し、「怪盗対策」をアドバイスする。
この「同僚」に会ったことがないことをセキュリティ部門が思い出したのは、盗難から半月後のことだった。
盗賊は二重生活を送っているため、人の目を欺ける手段は必須、これは怪盗界の伝統だ。
「ライターに何とかしてもらって、怪盗にずっと仮面を着けてもらえないか?」
同社の映画・テレビ部門のマーケティング担当者は、プロデューサーにこう言った、
「もう一度この仮面のニーズを強調しよう、廉価で大人気だ」
- 手部
- 怪盗のワイヤーかぎ爪
- ナノ素材を編み込んだ特殊な手袋、どんな指紋でも瞬時に再現する。
流星怪盗ルブランは、痕跡を残さないような潔癖は持ち合わせていない。
彼はいつもミスリードする手がかりや、度をわきまえた挑発を残す。
「なんでカンパニーの人たちは偽の指紋に何度も弄ばれるのか?そうだな、この問題は、私ではなくカンパニーに聞くべきだ」
彼の手袋はあらゆる指紋を生成できる。
その機能はカンパニーの指紋検出技術を役立たずにしただけでなく
、大した手がかりにならない「盗賊の綻び」を大量に残した。
セキュリティ部門は、お宝が保管されていた密室で、
先史時代の翼竜、星間テントウ虫、ラブラドールなど、何百種もの指紋を発見した……
もちろん彼の指紋は1つもなかった。
完全に身を潜めるのは実につまらない。それでは警察ごときに怯えるコソ泥と大差ないではないか。
「冗談だとしても、今時指紋認証システムなんて使ってる奴なんていないぞ」
カンパニーのセキュリティ部門からクレームが入った。
「脚本を書いた奴ら、生活の常識もないのか?」
- 胴体
- 怪盗の紋様手袋
- ベルト風のワイヤー、バックルにフックと滑車が隠されている。
準備周到な怪盗は救命のワイヤーを常備し、いつも絶望的な状況から無事に脱出できる。
「腰部のワイヤーはどうやって照準しているのか…君は自分がどうやって歩くのかを説明するのか?」
お宝を保管する密室には危険な仕掛けが沢山あるが、怪盗は見事なワイヤーさばきでワルツを踊るように宙を舞う。
かぎ爪は発射後1/3秒で数十メートルある壁に取り付き、滑車が回転し始める、すると怪盗は瞬く間に「獅子座の星」の前に出現した。
腰部のワイヤーで飛び回る、それは怪盗の基本である。
「続編でスタントマンを主演にしたら、予算を節約できるな」
「アクション監督は皮肉を言った。どうせ仮面をつけてるんだ、誰も分からないさ」
- 脚部
- 怪盗の流星ブーツ
- 人体機能を補強する靴。怪盗がビルの間をすたすた歩くのを可能にしている。
怪盗は、わざと眩しい軌道を残しながら街の上を高速で飛び去る。
それが「流星」の由来である。
「高層ビルがなかったらどうやって逃げる?ハハハハ、そんなつまらない問題はもうよしてくれよ」
怪盗は、繰り返される間一髪の脱走には慣れていた。
彼の拠点を知っている者がいない限り、怪盗の流星ブーツに追いつける人はいない。
意外な事に、ボサボサ頭の探偵はコーヒーカップを持ち、ルブランの椅子に座って彼を待っていた。
怪盗の物語はここで終わり、これからは探偵の物語だ。
「誰も私がそう書くとは思わないから、こう書いてやったのさ!」
賛否両論の結末を、脚本家(匿名)が解説した。
荒地で盗みを働く廃土客

詳細
- 頭部
- 廃土客の呼吸マスク
- ホコリと放射能をカットできるマスク。廃棄された人工呼吸器を改造したように見える。
残留放射能と砂嵐はここの日常だ。
タリアの廃土客たちは、常にマスクを用意しておかなければならない。
原理も分からずに弄ってできたマスクは使えるのか?いや、むなしい慰めにしかならない。
「聞いたか?マスクにパイプを挿してる奴がいるんだぜ、俺だったらあんなの我慢できねぇよ」
廃土客たちはタリアの極端気象に対して不満をたらす事は少ない。
第一に、彼らでは現状を変えられない、核爆発以来、ここは砂と埃に覆われている。
第二に、彼らは楽観的だから、赤い砂が空を覆った時、彼らは手製の防塵マスクをして、
風埃と共に他の賊の巣窟に突入し、黄泉の国の幽霊のように姿を現す。
準備をした賊が準備をしていない賊から奪う。
それがタリアの生存法則だ。
着脱が難しそうな防塵マスク。「ネイルシェル」の偽造防止マークがある。
- 手部
- 廃土客の修道服
- 電離放射性ガスを検知し、トラッシュトークも喋られる汎用性の高いガラクタ。
タリアが盗賊公国になる前は、「星々のゴミ捨て場」として広く知られており、
様々な世界の技術廃棄物はここで2度目の春を迎える。
「手鎖より重い腕部端末を付けるのが好きなわけじゃねぇ!こいつぁ肝心な時じゃハンマーよりすげぇんだよ」
ネイルシェルタウンができてから、タリアで最も常識外れな廃棄物工学専門家たちはついに安全な場所を見つけ、
そこでタリア独自の「勘科学」を創造した。
セシウム測定器と、暴言を吐くスマート端末を組み合わせば、廃土特有の多機能なゴミ「荒廃端末」が完成する。
いわゆる「勘科学」の指導思想とは:原理を聞くな、目的を聞くな、誰もそんなもん気にしてない。
「よくもゴミと一つにしやがったな、てめえらは肥溜めに住むドブネズミだ」スマート端末の声は、親切で切実だった。
- 胴体
- 廃土客の荒涼端末
- ゆったりとしたローブ、伝道師スタイルを改造している。
タリアのならず者たちは救済など期待してないし、それが何なのかも知らない。
修道士がどんな存在だなんて尚更だ。
彼らの目には、掃除に使えそうなローブの実用性しか映らなかった。
「『無知が統治する時代はまだ終わってない』?んだこのくそみたいな文章は?」
廃土客たちは長い間放置されていた修道院を発見し、さらに旧文明の正典まで見つけた。
彼らは、文明の記録の貴重さをほとんど直感的に感じ取り、上辺の感傷に浸った後、それらを愉快に焼却した。
廃土客たちが持ち去ったのは修道士のローブだけ、それ以外のガラクタはネイルシェルでは無価値だ。
ほぼ全ての廃土客は教養がない、文明に関する資料がいくらあっても腹を満たすメシには比べられない。
これもしょうがない事だ、彼らを責めるべきではない。
少なくとも修道士のローブは残された、これもまた、文明が存在する形式の一つである。
- 脚部
- 廃土客の動力腿甲
- 動力甲冑の足の部分。廃鉄と古い電線で外骨格が作られている。
ネイルシェルタウンの盗賊たちは貴重な水源と苦労して集めたゴミを守る手段が必要だ。
ないよりマシの盗賊技術はこのようにして誕生した。
見かけ倒しのパワーアーマーは脚部だけ正常に作動できる。
「俺が必要なのは完全なパワーアーマーなんだよ、そんで上の部分は爆発したって?
逆に聞くぞ、てめぇにこの脚部アーマーを使う度胸はあんのか?」
しょっちゅう勃発するネイルシェルの防衛戦は、「印象科学」の発展を促進させ、出所不明の材料と即席の技術で、
盗賊たちはパワーアーマーまで作れるようになった。
残念ながら、初代の鉄くずパワーアーマーは脚部しか残っておらず、大幅に簡略化しても操縦者をロケットのように発射してしまう。
理由はエンジニアにもよくわからない。
デザイナーが言うには、それは半分寝ぼけた状態で設計されたもので、一生に一度だけの閃きだった。
資源ゴミでも有害ゴミでも、使えるならそれはいいゴミだ。
宝命長存の蒔者
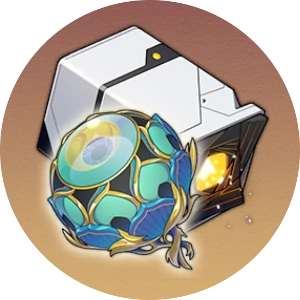
詳細
- 頭部
- 蒔者の光をもたらす義眼
- とある人の機巧義眼。今や義眼は主人の身体から追い出され、無用となっていた。
暗く混沌とした夢の中で、彼女はよく再び光が戻った数日のことを見た。広大な土地に楹樹が揺れ、花弁が舞う。藍色の波が岩にぶつかり、白く散る。鳥は翼を広げ、濃緑の竹林の中に消える。
夢の中で彼女はいつも、彼女と共に美しき景色を楽しむべきもう1人の誰かを探している。
しかし、彼女に見えるのはぼやけた人影のみ。その人の絹のような短髪と黒い玉のような双眸をはっきりと覚えているのに、記憶は神経が構築した迷宮に迷い込んでしまったようであった。彼女はいつもその顔をはっきりと見る前に目を覚ましてしまう。寝ぼけまなこに、彼女は自分に様々な痛みをもたらした義眼をさすった。虚偽の目の力を借りることで、彼女はもう声、匂い、指先の感覚を頼ってぼやけた影を組み立てる必要はなくなった。
「それは既に無用の物である」燼滅禍祖の使令は言った。彼女は扇子が風を揺らす音と、使令の微かな笑い声を聞いた。「もうすぐ、お主は見たいすべてを見ることになろう——お主の目でな」
「今のこれが私の目でございます」彼女は軽く笑った。「それに、かつて見た美しい景色は、もう私には無縁のものです」
- 手部
- 蒔者の機巧義手
- 長命種専用に造られた機巧義肢。使用時、肉体的な侵襲はない。
発育不全の腕の先に保護用の軟膏を塗り、神経信号受信器を皮膚の上にピタリと貼り付け、最後に締め付けを調整し、機巧義手をしっかり固定させることが彼女の数百年来の朝の日課である。
義手は彼女に余計な注目を集めた。彼女は面倒事を招きたくないし、同情されるのも絶対に嫌だった。
彼女のように何か欠けている人は、世にも稀有な才能を持ち、司部の決定権を握っていても、他人の態度から感じる疎外感を変えることはできなかった。弱きを虐げて強きを恐れる小物はいつか散り散りになっていなくなる。一方で自分が慈悲の心を持っていると勘違いしている偽善者は、ハエのように周りを飛び回り、「素晴らしく優秀な盲目片腕の天欠者だ」と言って彼女を賞賛するのであった。
過去に何万回も聞いた言葉だが、そのたびに彼女は内心むかついた。そして、今彼女はその目で憐れみを乞うような眼差しを見たことで、更にイラついた。
彼女は無意識のうちに熱い鼎炉に左手をついた。その刹那、鋭い痛みが伝わってきた——急いで手を引っ込めると、火傷は素早く治癒した。
「時々、以前の義手の方が使いやすいと思うことがあります」
- 胴体
- 蒔者の露払いの羽衣
- 古書の記載を基に織られた羽衣。万古の妖の物であり、万人の救いの主の物でもある。
逸史の残篇の中から情報を探すことは盲目の人にとっては至難の業である。仲間は膨大な量の古書を漏らすことなく彼女に読み聞かせ、彼女はその中の文言を編纂し書き留め、秘密を探る。
元来より聡明な彼女は、ほとんどの書籍を一度聞いただけで覚えることができた。しかし、古い文献の中から「被羽妖婦」の奇譚を見つけることだけは、何回聞いても満足できなかった。
ある洞天の主は伴侶を救うために、その身体を鳥雀の姿にし、生きながらえさせたという。しかし、彼女は鳥の呼び声に耐えきれず、同じように身体を変え、伴侶と翼を並べ飛んだ。長い歳月が経ち、洞天の主は自身の本性を見失い、半人半鳥の異形となってしまった。彼女の臣民が宮殿に攻め込み、燃える矛槍で彼女を刺し貫いた時、2羽の鳥は最後の哀歌を歌い、混ざり合う灰となり散った。
彼女はこの物語をとても気に入っていた。だから鳥雀の精髄を採取し、丹鼎の間で形を錬化し、奢麗な羽衣を織るように命じた。彼女は羽衣の美しさを知ることはできないが、それを着て部屋の中を歩き回るのを好んだ——それは、もう存在しない人に見せるためであった。
衣が風に揺れた瞬間、彼女はいつも魂が鳥のように指の間、肩の上を飛び、ずっとそこにいるように感じた。
- 脚部
- 蒔者の天人絲鞋
- 底が蝉の羽のように薄い絲鞋。靴の主は長い間、自分の脚で歩いていないのだろう。
彼女が人々に仙跡を披露するために、大地の支えを脱し、空中に浮く時、いつも無意識にある古い国の神話を思い出す——
「かつて修道し成功を収めた者は、地上を歩き、地脈の気を読み仙道を展開した。それは千変万化で、当たらぬ預言はなかった。その修道者は風を御し空中を歩き、星々と同列に成ろうとしたが、自分がとっくに地脈を離れたことに気がつき、最終的には失脚して死の淵に堕ちた」という話である。
しかし、今の状況は神話とは違うと彼女は唱える。仙舟にはもとより根はなく、「建木」がその根を与えることで、豊穣の主と一体化して共存し、薬師が承諾した果てしない浄土とも密接につながっている。そして今、裏切り者たちは仙道との繋がりを断ち切り、仙舟を再び漂う孤島にした。
仙舟の偽りの大地は彼女に力を与えてはくれない。彼女が探し求めた根は足元ではなく、天空と深淵の間にあるのだ。彼女は蒔者を引き連れ「建木」を再生させ、豊穣のこの上ない恩恵を抱擁するのだ。
彼女は薄い絲鞋を履き人々の頭上に浮かぶと、よく通る声で宣言した。「皆さんが見上げる時、見るべきなのは私ではなく、空高くにある本来皆さんに属す場所なのです」
仮想空間を漫遊するメッセンジャー

詳細
- 頭部
- メッセンジャーのホログラフィーゴーグル
- 外見はスキーゴーグルに酷似している。眩しい光を防ぐだけではなく、バーチャル配信者の配信も視聴できる
熱帯夜の都のメッセンジャーたちは財閥の自警部隊を避けるために、普段は比較的警備が少ない都の上空を移動する。
メッセンジャーたちは安いガムを噛み、高度改造されたホログラフィーアイピースを装着し、パルスを起動しサイバー都市を丸ごとスキャンするのが好きである。
アイピースは都市のリアルタイム情報を網膜に投影し、不可能なルートをメッセンジャーの空中回廊へと変化させた。建物の屋上、空調の室外機、広告板、タワークレーンのアーム…さらには物流ドローンまでもが空中回廊の一部となるのだ。そのため、メッセンジャーたちは十分なテクニックを身に付けなければならない。なぜなら一歩間違えてしまえば、墜落死してしまうからである。
「ある馬鹿が無差別にアイピースをハックしたんだ。ちょうどその時、空中にいたんだけど。地面に落ちた時は本当に最悪だった」
この「イエローダック」のアイピースは生産終了した旧モデルで、愛好家の中では高い価値を誇るそうだ。
- 手部
- メッセンジャーの百変義手
- 好きに取り外しのできる機械義手。指の各節が弾丸のように発射できる。
すべてのメッセンジャーが機械義手を使っているわけではない。しかし義手を有するメッセンジャーはその改造に熱中している。自分のサイバー義肢が他の人と全く同じであることを容認できる人はいないからだ。
熱帯夜の都の住民たちは、サイバー義体に夢中である。有限の都市の法律では、過度な義体化がもたらす熱狂に対する注意喚起しかできない。
熱帯夜の都に登録された改造基準は3項目にざっくりと分けることのできる計18種しかなく、それは常軌を逸し道徳に背くメッセンジャーたちにとっては明らかに物足りなかった。彼らは奇想なデザインを生み出すことに巨額をつぎ込んだ。義手の電子転換器は落雷を放つことができ、義手はミサイルのように飛び出す…改造の青写真はどんどん大げさなものになり、メッセンジャーたちの担う送料もどんどん上がっていった。
「メッセンジャーたちは情報を守るために奔走しているのだろうか、それともあり得ない程高い送料のために奔走しているのだろうか?」
この「イエローダック」の義手は既に特殊改造が施されており、指の各節が高速で旋回し、弾丸のように発射できる。
- 脚部
- メッセンジャーの密書ショルダーバッグ
- オシャレなメッセンジャーのバッグ。様々なアクセサリーが付けられており、可愛く見える。
熱帯夜の都の財閥たちは都市内のすべての情報の流動を監視している。情報を独占する方法で統治者としての地位を維持しており、転覆を企てる者はすべて治安法による規制を受ける。
かつて人々は抗議をしたことがあり、財閥たちは便利な約束をした。すぐに、人々は「プライバシー」を諦めた。
現実だろうと仮想の場だろうと、有用な情報だろうと無用な情報だろうと、事が重要だろうと些末だろうと、財閥たちは貪欲にそれらをかき集める。そうして、メッセンジャーたちのメッセンジャーバッグは「プライバシー」の最終防衛線となった。バッグは小さく軽く、チップや書類を携帯するのにしか使えない。しかし、まさにこのような狭い情報の盲点が、熱帯夜の都の残された「情報独立」を保障しているのだ。
「どうして繁華な熱帯夜の都で、未だにネット以外の方法で情報を伝送する人がいるのだろうか?メッセンジャーたちもその理由を知りたい」
この数量限定の「イエローダック」のメッセンジャーバッグは少し古いが、様々なアクセサリーがそれをファッショナブルに見せている。
- 脚部
- メッセンジャーのパルクールシューズ
- 自由にパルクールすることができるスケボーシューズ。履くと心地よい。それだけである。
熱帯夜の都でかつてのメッセンジャーたちはスケボーシューズを一か所に投げ捨て、短い沈黙の後に各自、その場を離れた。多くのメッセンジャーはこの都市に名前も痕跡も残さない。このような行為はただの自己満足の休符に過ぎない。
メッセンジャーたちもいつの日から「メッセンジャーの性質」が自分が最も嫌うタイプに変化したのかうまく説明できなかった。
いつの間にかメッセンジャーが保障する「情報独立」は独占になった。いつの間にかメッセンジャーたちが直面していたリスクは値段に変わった。いつの間にか、メッセンジャーたちは陰謀家の共犯となった…財閥たちは彼らを滅ぼしてはいない、未熟な理想がメッセンジャーを裏切ったのだ。すべてが制御できなくなる前に、メッセンジャーたちは一堂に会し、奔走するだけの生涯に別れを告げた。
「もしかしたら、メッセンジャーたちはここで思いとどまって、すべての人にこの都市をしっかりと見つめさせ、真の革命家たちを動かすべきだったかもしれない」
これは道端に捨てられた「イエローダック」のスケボーシューズである。熱帯夜の都のメッセンジャーたちは既に過去の伝説となっている。
深い牢獄の囚人

詳細
- 頭部
- 囚人の獣面口輪
- 獣の顔を拘束するための口輪。囚人が牙を剥くことを防ぐため、頑丈に作られている。
嗅覚はかつて歩離人の戦首の感覚世界を構成していた。雨、土埃、篝火、鮮血、傷薬…戦場の最深部からゆらゆらと伝わってくるその匂いが、洪水となって彼の精神を溺れさせる。
彼は今、刑具の重さと堅固さ、そして陪審員の恐怖が空気を満たしていることしか嗅ぎ取れない。
彼は知っている、か弱い陪審員たちが鋭い牙を恐れていることを――かつて、彼は険しい崖の上に立ち、狂気の月の光を浴びて、血の中の本能の衝動を感じた。かつて、彼は匂いで構成された迷宮を巡り、光のない夜に敵陣に深く入り込み、獲物の頭を噛み砕いた…歩離人の戦首の磨かれた牙は鋭く、白刃と見なされ、すべての力と自信を引き裂くものだった。
「歩離の巣父、罪なき者を傷つけ、その血を啜った。十悪の重罪を犯した罰として、口を閉め歯を固め、拘束の覆面を生涯にわたり装着することを言い渡す」
戦首は軽蔑したように周囲を見渡したが、荒々しい氷の海のようにすべてを席巻した剣客はここにはいない…彼は煩雑な判決の言葉には興味がなかった。
- 手部
- 囚人の鉛の手枷
- 魔の手を縛る重い手枷。その手が二度と人を傷つけることのないよう、鋼の釘を腕に打ち込む。
雲が割れて霧が晴れ、淡い月の光が歩離人の戦首の傷だらけの体を照らす。銀髪の剣客に斬られた巨大な手は傍に落ち、万策尽きた戦首は血を流している。苦痛に満ちた遠吠えと共に、斬られたはずの手が再び生える。
月狂いを頼りに、戦首はかろうじて月光のような剣戟を追う。彼は豊穣の力に黙祷を捧げ、最後の悪足掻きをすることにした。
歩離の軍隊が何度包囲網の突破を試みたかは忘れた。覚えているのはただ、仲間が鋭い爪で何度も道を切り開いたのに、それがすぐに閉じてしまったこと。疲れ切った歩離人は壊れることのない再生能力を頼りに、すべての障害を取り除こうと奮闘する――混迷した狂気に陥り、戦首は鮮血を両手に注ぎ込む。だがその一瞬、逃げ場がなくなったことを、そして付き従う者がとっくにいなくなっていることにようやく気がついた。
「歩離の巣父、その手で殺した命は数多。鉛の石で手を縛り、厳しく取り締まる必要がある」
戦首はついに力尽きて剣客の前に倒れ、生まれて初めて疲労による瀕死を体験をした。「あれは比類なき剣だった」彼は思わず口にした。「あれは比類なき刺激だった!」
- 胴体
- 囚人の幽閉拘束衣
- 危険な重罪人を拘束する囚人服。関節を押さえ、囚人の変身能力を制限する。
歩離人は生まれつきの戦士である。彼らの骨格は広く高く、下顎と首の筋肉は強靭で、犬歯が発達しており、頭には獣の耳、
そして手足には鋭い爪が生えている――氏族の同胞は逞しく丈夫な体を崇拝しており、それを神からの恩恵だと考えていた。
戦首は精神的なリーダーであり、部族最強の戦力でもある。黒き潮の如く軍隊を指揮して、戦場で生死を支配する。
出撃した凶悪な獣艦が天と地を覆う。彼は戦場にいる興奮した戦士たちを見下ろす――歩離人の戦首は月の狂気に呼応する。鋭利な骨が体を突き破り、漆黒の血が風に乗って霧のように散っていく。彼は殉教者のように両腕を広げた。歩離の狼毒――それは人を恐怖させるフェロモンだ。血の霧が広がっていくにつれ、鬼神が憑りついたかのように、歩離人の戦士の感覚が刺激される。
「巣父よ、我らに頑丈な肉体を与えたまえ。巣父よ、我らに神鬼に通じる力を与えたまえ」
彼は肉体が縛りを受けない日を思い返す。「月狂い」を受けた歩離は肉体の限界を超え、皮は破れ肉は裂け、二度と痛みと恐怖を感じなくなる。彼らを導くのは、強者の特権と責任であった。
- 脚部
- 囚人の歩みを阻む足枷
- 獣の両足を縛る金属製の足枷。罪人の逃亡を防ぎ、問題を起こさせないようにするためのもの。
宇宙の中を遊牧している歩離人は、決まった場所に留まる文明の形態を蔑んでいる。彼らは平和と安定を攫い、大きな戦火をもたらすのだ。厳しい生存信仰によって彼らは戦い続け、常に血生臭い生に身を投じていた。
彼らには己の信念と手段があり、歩離人の行く先は歩離人の領土となる。
歩離人の戦首は幾度となく戦いの火蓋を切った。守護者の尊厳を押し潰し、離散者の涙を呑み、親しい者の信頼を踏みにじることを誇りとしていた。彼は荊棘の狂ったような成長に任せ、肥沃な土地をことごとく破壊した。そして人を奴隷にし、贅沢を享受した…歴代の王者を超えるため、新任の戦首は平穏を捨て、兵を率いて外界に遠征して戦の功績を立て、地位を固めるしかなかったのである。
「歩離の巣父、行く先で戦に至り、災いは諸界に及んだ。その足を封じ、二度と生を受けさせてはならない」
戦首はその判決の言葉に疑問を覚え、周囲を見回したが、弱者たちの審判に驚いた。何しろ彼らが罪と称するそれは、ただの生存法則に過ぎないのだから。
灰燼を燃やし尽くす大公

詳細
- 頭部
- 大公の冥焔の冠
- 燃え続ける炎の冠。烈々たる野心は尽きることのない燃料である。
優雅な炎魔は燃え盛る炎の中から生まれ、壊滅こそがトフェトに与えられた至高の冠であると信じている。
「私、壊滅の際に生まれし者、トフェトの罪悪の信仰。私こそ、ナヌークの憤怒の炎である」
ナヌークは自らの手でトフェトを滅ぼし、白星の烈火と壊滅の力がプラズマ生命体を育んだ。優雅な炎魔はこの誕生を天啓だと見なしている––「壊滅の君主は今日トフェトを征服し、それに燃え盛る炎を与えた。軽薄で空虚な栄誉は紅炎と共に散り、重厚な栄誉は私に冠を授けるだろう」アフリートは生まれた時から破壊と殺戮に溺れている。
「世の中のすべての冠はイバラで編まれている。イバラの冠に勝るものは、私の冥焔の冠だけだ」
壊滅の星神が星を滅ぼした余燼は、アフリートによってトフェトの王冠の形に整えられ、今でも身に付けられている。
- 手部
- 大公の炎の手袋
- 炎を羽毛にした純白の手袋。すべての暴虐をシルクの下に隠している。
アフリートは無数の生命を滅する危機を企てた。大公自ら指揮を執り、手袋をはめてこそ、棘のある指揮棒を握ることができる。
「私は壊滅の天啓に奉じるために来た。片手は奪うため、もう一方の手は与えるためにある」
「物事の尊さは、その滅びの中にある」と信じてやまない冥火大公は、リサリット星の歴史と文化を滅ぼし、貴族の煌びやかな絹織物を焼き払い、詩人の贅沢な長い巻物を燃やし尽くし、画家の優れた壁画を灰燼に帰した…「文明は若虫と同じ。燃え尽きて黒い蝶のように舞うことでこそ、生まれ変わることができる」アフリートは火葬炉の監視をする葬儀屋のように、頭を低くして文明の絶唱を導いている。
「私の努力、想像、指揮によって、演奏の順序、音調、速度が融合して素晴らしい壊滅のショーとなった」
アフリートは満足のいく壊滅が終わった後、血に塗れた手を拭い、宴会に参加する裕福な客がつけるような純白の手袋をはめた。
- 胴体
- 大公の恩恵のロングジャケット
- 華やかで美しいジャケット。その持ち主の品格が窺える。
優雅な炎魔は非人道的な虐殺を行った後、姿見に映る自分の姿を鑑賞する。君主に謁見するには適切な装いをする必要があるからだ。
「衣服は着飾るためでなく、本質を表現するためにある。烈焔の本質が壊滅にあるのと同じように」
永遠に燃え続ける炎魔一族は、ナヌークを皇帝と見なし恩主と称したが、星神の一瞥を受けたことはない。アフリートの壊滅は誇示と権利、征服と動機が入り混じったもので、「永火官邸」と「ヤペラー ブラザーフッド」の争いはさらに醜いものだった。「不純な壊滅は汚れよりも華やかな服を汚しやすい」純粋という概念について、アフリートは終始要領を得なかった。
「壊滅の価値は壊滅されるモノの価値にある。私たちの価値は君主の一瞥を得るまで壊滅を実践することである」
アフリートは信心深く、ビロード色の炎で織られた華やかな服を身に纏い、壊滅の招待を待っている。
- 脚部
- 大公の優雅なブーツ
- クラシックで履き心地のいいブーツ。完璧に手入れされている。
優雅な炎魔の足跡がくねくねと続く場所では、焼かれた文明がいつも静かに泣きながら訴えている。しかし、アフリートがそれを気にすることはない––
「歩む道がない者に靴など不要だ。終わりに到達した文明が私に訴えて何になる?」
焰の冠を被った「冥火大公」は、多くの文明から天外の悪魔とされているのだが、なぜか宴の星から招待を受け、嬉々として盛装して宴に出席した。「礼儀作法に則った壊滅を用意した。骨の一片も残せると思うな」優雅な炎魔は星間の悪党たちを集め、宴で死体の山と血の海を築こうとしている…滅ぼされた文明は、壊滅への巡礼の道でしかなく、ピノコニーも通過点に過ぎない。
「お前たちを滅ぼしても、お前たちには関係ない。これは其の目を引くためだ」
遠くから聞こえる宴会の声に誘われ、アフリートは嬉しそうに長い旅に出た。
死水に潜る先駆者

詳細
- 頭部
- 先駆者の断熱ヘルメット
- オールクロンでよくみられるデザインの潜水用のヘルメット。この小さなシールドから見えるのは、人には耐えきれない無限の暗黒のみ。
オールクロンの夜の空は、積雲ときらめく星の輪に覆われている。赤紫色の雪が分厚いヘルメットの上に降り積もり、錆びた溝を埋めて浸蝕の痕を隠した。彼女たちはヒマラヤスギ林の間に座って…旅の途中の休憩を堪能している。
「見て!オールクロンの空気ってラズベリーの匂いなんだね」赤紫色の雪が、雲のようにふわふわしたマシュマロの上に落ち、すぐに溶けた。ティロからやってきた小さなナナシビトはクスクスと笑い、そしてすぐに腰をかがめてお腹を抱える。彼女は自分の言葉に笑った——匂いは目で見ることなんかできないのに!笑いの後、ナイフのように鋭い静寂が訪れる。まるで、空気が凍り付いたかのようだった。
「フリバス、まだ『IX』の深部に行くつもり?」いつも長い刀を身に着けた旅の仲間が質問する。彼女はとてもいい仲間だが、どこから来たのかは誰も知らない。
小さなナナシビトは重く大きな潜水服の中でしばらく沈黙した。そして彼女は、帆を張ったように目を細めて、相手に少し焦げたマシュマロを手渡す。
「もちろんだよ——だって私は、アキヴィリよりもさらに深く遠い道を歩むつもりだから!」
- 手部
- 先駆者の虚極コンパス
- 時計型のコンパス。針はすでに取り外されていて、どの方角も示せない。
「海底の海流」
「共に過ごす時間の中で、囁いては彼女の骨を突っつく」
「彼女は白秋と青春を経験し」
「そして渦中へと入った」
少女はこんな物語を聞いたことがある。話の中で、人々が住む世界は、無主のエネルギーによって構築された天に届くほどの巨木として描かれている。「このエネルギーは見えないし触れもしない。そして、理解できなくて無意味だ」と彼女は考える
「『IX』みたいに意味がない」
小さなナナシビトは少しがっかりし、自分が「虚無」の深部に足を踏み入れた後、どうやって方向を認識すればいいか悩んだ。少しして、彼女は思いつく——14歳の時、母親は彼女に最後の誕生日プレゼントとして小さなコンパスを渡していた。
「だったら、コンパスが磁場じゃなくて『エネルギー』を感知できるようにすれば、解決するよね?」
小さなナナシビトはコンパスから針を取り外す。少女が暗闇に潜った瞬間、コンパスはただ下を向いていることに気が付いた。
- 胴体
- 先駆者の密閉された鉛の潜水服
- 鉄のガラクタで作られた気密性の高い頑丈な潜水服。使用者はよく、潜水服というより深水用の棺桶のようだと冗談っぽく言っている。
「フリバス、あのティロのナナシビトは、14日間死んでいた」
「彼女はカモメの鳴き声や深淵の波の声」
「そして、利益と損失も忘れた」
小さなナナシビトは、ティロの大通りから星の輪を眺めていた。彼女はブラックホールの特異点に自分の身を投げ出すことを決意する。
「アキヴィリですらあそこには行ったことがない」少女の心の奥底にはいつも、波の音が響いていた。「絶対に其よりも深く、遠くに行く」彼女はそのために十分な準備をする——どこのものかわからない錆びた鉄の板、中古の酸素ボンベ、廃棄されたジャイロ姿勢制御装置、自律型循環生命維持システムにフェアリング…これらの材料をすべて1つにしてスーツの気密性を確保した。彼女はこれで「虚無」の被害から身を守れるだろうと考えたのだ。
父が残した潜水ヘルメットを拾い上げ、手作りの「栄誉バッジ」を取り付ける。出発前、彼女は旅の仲間と再度ヒマラヤスギ林に行き、最後にもう一度マシュマロを焼いた。
その後、フリバスの飛行マシンがブラックホールの淵に近づいた時、これが彼女が思い出せるオールクロンに関するすべての記憶だった。
- 脚部
- 先駆者の星に泊まるアンカー
- その重い靴は船の錨に似た形をしている。この靴の持ち主は二度と水面に戻らないつもりだった。
「舵輪を回して風向きを眺める君たちよ」
「彼女——フリバスのことを考えたまえ」
「かつては君たちのように美しく長身であった」
錨のような鉛の靴は、少女をいつも落下させた。靴は設計当初に与えられた使命を忠実に果たしている。
少女は目を決して閉じず、冷たく孤独な暗黒に頑として立ち向かう。彼女は初めてアキヴィリの物語を聞いた時のことを思い出した。旅立ちの日、自分のために作った「栄誉バッジ」のこと。仲間と一緒に旅した30日間のこと。最初で最後に会った林の空き地の空気がラズベリーの匂いだったこと。口笛、ギター、竹笛、そして一緒に歌った歌のこと。赤紫色の雪が少し焦げたマシュマロの上に落ちて、すぐに溶けたこと。
ありありと思い浮かぶ記憶の最後に、途方もない空虚が訪れようとした時、彼女は黒い世界の中心に真っ赤な閃光が突然現れては一瞬で消えるのを目撃した。
小さなナナシビトは最後に、長い刀を身に着けた彼女からマシュマロを受け取り、心の底から笑った時のことを思い出した。
「自分と同じような人に出会えるなんて思ってもみなかった。この『道』においては、あなたは私より長い距離を歩んでいる」
「だから、あなたは最後まで私と歩んでくれる、そうでしょ?」
「もちろん、私たちの結末はとっくに決まってる…でも、あなたの言う通り——」
「たとえ、最終的に私が浅い死水になるのだとしても、そこに向かう途中でできることはたくさんある。だから、どんなことにも挑戦してみたいの!」
「だって私は、アキヴィリよりもさらに深く遠い道を歩むつもりだから!」
夢を弄ぶ時計屋

詳細
- 頭部
- 時計屋の望遠レンズ
- 金の彫刻が施されたレンズ。レンズには遠くにある様々な奇妙な現象が映り、持ち主が夢の迷路を見通す助けをする。
ピノコニーの「時計屋」に関する物語の中で、彼はいつも特別な慧眼で、容易く夢幻泡影の陰にある商機を見抜き、誰にも想像できない偉大なる事業を成し遂げてきた。
辺境の監獄は万界の癌の中で自由を勝ち取り、ファミリーの光の下で平和と繁栄をもたらした。時計屋はこの時に現れたと言われている。彼のレンズはこの夢境の本質を映し出す——人々は「夢の中で不可能なこと」を探すためだけに、「黄昏の刻」で金を湯水のように使った。それ以来、ピノコニーの夢には、談笑するティーポット、走りながら回転するスポーツカー、毎日場所を変える豪邸…などの不可思議なものがたくさん現れるようになったのだ。何の役にも立たないが、これらは天文学的な数字で売られており、遠方から来た人たちは大金をはたいて購入する。
これが幻の夢の世界なら、なぜ狂想のままに振舞わないのか?「夢の中だけにある唯一無二」という言葉が、夢境の中の贅沢さと価値を再定義した。
ルーサン家ビジネス界の老いた夢追い人たちはことあるごとに後悔し、なぜもっと早くこのチャンスに気づけなかったのかと自分を責めた。時計屋は彼らより、少し遠くを見ているだけなのだ——いつも、少し遠くを見ているだけ。
- 手部
- 時計屋の運を引き寄せる腕時計
- 精巧に作られた腕時計。独特な文字盤と指針を備えており、夢境の中で幸運の象徴だと言われている。
「時計屋」がそう呼ばれている理由は、シリーズ最大の謎である。
時計台の修理職人だったという人もいれば、時計を売る行商人だったという人もいる。はたまた彼が創作したクロックボーイのような頭をしているからだという人も。
噂が広まるにつれ、夢の中の腕時計もまた時計屋の名声にあやかって人気を博していった。夢追い人たちは、それら時計が尊敬の対象となっている男とは何も関係ないことを知っていても、依然としてそれらを彼への敬意と幸運を象徴するものだと見なしている。一連の商業活動を経て、時計のシンボルはピノコニーで最も見かけるものとなった——服、アクセサリー、食品…さらには街頭のラクガキからホテルのロビーにある大時計まで、この伝説的な大人物の影はどこにでもある。
「ピノコニーで時計が嫌いな人なんていないよね?」
そして、本物の時計屋はすべてを黙認しているようで、最初の腕時計について意見を表明したことはない。かくして時計のシンボルはピノコニー中に偏在するようになり、時計屋の由来を知ろうとする人はいなくなった。
- 胴体
- 時計屋の虚空礼服
- きらびやかで豪華な革襟の礼服。通常はパーティーなどの正式な場で使用される。
ピノコニーに数多とある噂において、「時計屋」はそれぞれまったく異なる身分と外見を持っている。
根拠のない架空の物語では、親切な老人だったり、エレガントな女性だったり、高身長の巨人紳士だったりする。しかしどの物語でも、彼が華やかな身なりをしていることは共通していた。
時計屋は朝と黄昏が入り交じる夢境におり、自らの秘密をダンスのパートナーとなった相手にシェアするとされている。この噂を聞いた人々はこぞって華やかな装いで舞踏会に参加し、人々の中に隠れている謎めいた賓客を片っ端から誘った——これをきっかけに知り合いとなる夢追い人たちがどんどん増え、舞踏会も徐々に友情と愛情を交わす場所となった。噂に聞く華やかな身なりの主人が姿を現さなくとも、賓客たちの出会いを求める情熱は冷めることなく、高価なチケットは毎回売り切れだった。
「その身なりはまさか、かの有名な時計屋では?」この言葉は最初こそ誠実な質問だったものの、後には誉め言葉、最終的にはダンスの誘い文句となった。
時計屋は舞踏会という新たなビジネスを確立し、夢境には更なるロマンと激情が溢れるようになった。
- 脚部
- 時計屋の隠された夢の革靴
- エレガントなデザインの革靴。これを履いた者はかつて、秘密の姿で夢に潜行していた。
「時計屋」はすべての夢境に足を踏み入れたことがあり、ピノコニーの歴史もすべてその足でたどってきた。彼の名は既に夢の地で数百年にわたり流れているが、夢追い人たちは依然として彼の動向を耳にすることがある。
人々はだんだんと、時計屋が個人なのか団体なのか、はたまたファミリーが流している嘘なのかと疑い始めた。
夢追い人たちの中には時計屋の謎を解き明かすと誓い、それぞれの夢境に向かって謎めいた有力者の痕跡を探す者もいたが、結局それは蜃気楼に近づくようなものだった——とある商談の席にいた謎のゲスト、突如として現れた立ち上げ人のわからないブランド、出所不明の巨額の投資…人々が時計屋など存在しないと考えるたび、時計屋は夢のどこにでもいることを証明した。
「覚醒図書館」の書架は時計屋に関する書籍で埋め尽くされ、彼の名前は永遠にピノコニーに付きまとう。
人々が探ろうとすればするほど、真相は嘘に隠されていくのだ。この「スター・オブ・ザ・フェスティバル」は千の物語と万の噂の中に足跡を残すのみで、その姿を見せたことはない。
蝗害を一掃せし鉄騎

詳細
- 頭部
- 鉄騎の索敵用ヘルム
- 感覚器官の信号を大幅に強化する鋼鉄のヘルム。グラモスの鉄騎の意識を装甲と融合させる。
太陽の光を遮っていたスウォームが炎の海で灰となり、銀白色の雪が深宇宙に漂い、恒星の淡い光を照らしている。この瞬間だけは、耳元で絶え間なく響く羽音も、通信チャンネルの命令も静かになるのだ。
「帝国」を襲撃したスウォームは掃討されたわけではない。少し時間が経てば、またいつものように次の出撃命令が鳴り響くだろう。
「帝国」の鉄騎である彼女は、深髄信号の伝達によってもたらされる外の世界の風を感じながら、前回装甲を解除した時のことを思い出していた。熱風が長い髪をなびかせ、熱を帯びた空気が首筋に纏わりつき、その肌は汗をかいている。彼女はそのような感覚が嫌いではなかった。なぜならそれは、模擬信号よりも遥かに生き生きとしたものだからだ。装甲は感覚器官とパイロットを深く同期させる。それによってロストエントロピーの苦痛が増そうとも、虫の末裔に打ち勝つためには、もはや鉄騎に選択の余地などないのだ。
「グラモス軍規第8条、生存者は速やかに帰還せよ……」
鉄騎が首のない銀色の甲冑を目にした時、ようやく装甲の感覚信号が自分を欺いていたことに気がついた――もう次の出撃命令が鳴ることはない。なんと残酷で短い休息なのだろうか。
- 手部
- 鉄騎の粉砕アーム
- 虫の末裔を粉砕する強力な鉄腕。硬く頑丈でありながら、鋭く軽い。
グラモスの鉄騎は鉄の拳に力を込め、汚れた鞘翅を引き千切った。圧力を失った虫の腹からは腐食性の液体が噴き出したが、銀色の甲冑に触れた瞬間、それは気化して血の汚れだけが残った。
装甲と虫の足の残骸が深宇宙に散乱する中、グラモスを取り囲んでいた「死の川」が重力に引っ張られ、静かに流れていく。血戦はようやく終わりを迎えたのである。
議会の指導者たちは戦後の情勢について話し合い、これまで実権を握ったことのない「ティタニア」に審判を下した。虫たちと互角に渡り合える鉄騎兵団を従える彼女の存在は、今後共和国存続の最大の脅威になり得ると判断されたからだ…人々は平和の鐘を鳴らし、スウォームが消え、澄んだ青空が再び共和国に戻ったことを宣言した。
「『女皇』に制約を課さなければ、誰もあの兵器を制御できないだろう?」
鉄騎たちは短い生涯の中で、絶えず己の腕を磨いている。だからこそ、議会の者たちの青白く、力のない節くれ立った手が高く掲げられるだけで、グラモスの命運を左右するほどの力が発揮されることなど、彼らは考えたこともなかったのである。
- 胴体
- 鉄騎の銀影アーマー
- 激しい炎を放つ推進装甲。グラモスの鉄騎に戦場を焼き尽くせるほどの力を与える。
いくつもの激しい炎の筋が夜空を切り裂き、黎明を迎えつつあった地平線を越え、グラモスの各星域へと向かっていく――それは共和国の住民にとって最も身近で、最も恐れている日常だ。
銀の装甲が空を飛び、一刻を争いながら戦場へと急ぐ。自分たちが日夜守っている光景を見下ろす暇などありはしない。
女皇の命令は絶対だ。似たような顔の兵士が培養カプセルから生まれ、女皇に忠誠を尽くしてグラモスの空を奪還すると誓った。鉄騎は飛虫の屍の山と血の海を越え、虫の殻の余燼すらも焼き、鋭い歯の生えた巨大な顎の残骸を粉砕する…グラモスの鉄騎の宿命は、慢性的に解離するエントロピー変化に耐え、生と死の狭間で激しく燃え上がることである。
炎が完全に掻き消え、空を覆う虫が黒い焦土へと変わり、生きて帰ってくる者がいなくなるまで――この日常は続いていく……
生きるとは何なのだろうか?推進装甲の加速で胸が締め付けられ、ロストエントロピーで麻痺していた苦痛が四肢に現れる時だけ、彼らは微かに「生」を感じられるのである。
- 脚部
- 鉄騎の飛翔グリーブ
- 破壊力とスピードを兼ね備えた鉄騎のグリーブ。これによりグラモスの鉄騎は高く跳び上がり、力を集中させた蹴りを敵に放つことができる。
鉄騎の足跡は燃える流星のように、グラモス「帝国」の隅々にまで広がっている。しかし、それでもティタニアが紡ぐ「夢」から抜け出すことは叶わない。
共和国の人々は戦いのために生まれた兵団を警戒していた。それまで存在しなかった「帝国」と自分たちのよく知る「共和国」は、一体どれほど重なる部分があるのだろうか……
女皇は自分の騎士たちに名誉と信仰を授け、鉄騎は女皇に忠誠と誓いを捧げた…新人類は続々と培養カプセルから生まれ、ナンバーと使命を与えられている。そして旧人類は鋼鉄の壁の下に隠れ、長く待ち望んだ平和を怯えながら享受している。この平和という嘘は誰かの手によって暴かれなければならない…人類の本質を揺るがす戦争の手段など、この世に存在すべきではないのだ。天災さえ消え去れば、心に恐怖を抱く人々は、歪んだ戦争の産物を徹底的に破壊するに違いない――
鉄騎のグリーブが空を突き破る。彼らが望むなら、どんな星にも辿り着けるだろう。
しかし、もはや「帝国は」どこにもなく、鉄騎たちの前にあるのは定められた奇跡だけだった。1つは「死」に、もう1つは「自分」に繋がっている。
風雲を薙ぎ払う勇烈

詳細
- 頭部
- 勇猛な鋭嘴フェイスガード
- 凶鳥「タイフーン」をモチーフにしたフェイスガード。2対の補助眼は奇跡を目撃したことがある。
彼女の鷹の兜には2対の補助眼があり、どのような光の中でも周囲の環境をはっきり視認できるようになっている。しかし、この時は補助眼に乾いた血が付着していたため、視界は見渡す限り錆びた鉄の色に染まっていた。
昏睡状態から目覚めた将軍は、死体の山を這い上がった。背後には「瞰雲鏡」が高い塔のように天に向かって聳え立っている。塔の先端では一筋の光が動き続け、観星士たちにしか解読できない暗号を繰り返し発していた。それは同盟の無数の民たちの願いを受け、神に祈りを捧げているのだ――彼女が周囲の事切れた仲間たちと必死に戦い続けてきたのは、この小さな声を神のもとに届け、死を授けてもらうためだった。
「来た…」そう呟いて、将軍は空を仰いだ。彼女は神の姿を見ることも、声を聞くこともできなかったが、その訪れの気配を感じることはできた。まるで灼熱の気流が舞い上がり、焼けた鉄が肌の上を走り回っているようだ。血の霧の中で赤い火花が飛び、空を覆うように広がっていく。そして次の瞬間、直視できないほどの光によって引き裂かれた――
来た。無数の戦士たちの死と引き換えに、奇跡が起こったのだ。彼女は神の罰によって死の土地と化した星の残骸を見たことも、その光の痕跡を追いかけて戦ったこともある。その光は極めて早く、少しの雑念も許さないと思っていたが、彼女は間違っていた。その瞬間は少なくとも、自分の愛する弟子を思い浮かべるには十分な時間であった。
「では願いを捧げよう。彼女が平坦な道を歩めますように――」
大地が激しく渦巻き、光の海の咆哮と共に襲い掛かってくる。この時の彼女は雑念を抱くことなく、光の中で塵埃と化した。
- 手部
- 勇猛な鉤爪ガントレット
- 腕の形にぴったりと合ったバイオニックアームプロテクター。猛獣を狩るには、猛獣よりも鋭い爪と牙が必要だ。
彼女の指揮下にある青丘軍の戦士たちは、歩離の狼兵にも劣らない勇敢さを備えている。たとえ武器が壊れ素手になったとしても、彼らは指の爪だけで最後まで戦い続けられるだろう。
噂によると、青丘衛の弧族の戦士の多くは、歩離人が統治する世界から救出されたのだという。そうした「陥落地」で生まれた狐族は歩離人との混血であるため、しばしば突然変異で先祖返りする個体が現れる。そのような狐族は戦奴にされ、狼主たちに前線の先鋒として駆り出され、仙舟の攻撃を食い止めるための捨て駒にされるのだ。
「青丘軍に加入した者には、狼主たちに復讐する機会を与えよう!」将軍は新兵募集の折、幼い狐族の少女にそう言ったことを覚えている。同時に、後に続く言葉を口に出せなかったことに罪悪感を抱いていた。「あなたも私と同じように、戦いのために生まれ、戦いのために死ぬのだ」。
戦奴は狼主に匹敵する力とスピードを持っているが、彼らの命と理性は突然変異によって削り取られている。怒りで意志が燃え尽きた時、戦奴は凶暴で血に飢えた怪物になってしまうのだ。
純粋なる野性の怒りに肉体を支配された者は、生涯最後の狩りを終えた時、そのアームプロテクターが両手を拘束する枷に変わり、二度と肉体から引き離せなくなる。
- 胴体
- 勇猛な蒼羽アーマー
- 狼の群れの上を風のように飛翔する。狩る者と狩られる者、その立場はいずれ入れ替わるだろう。
彼女は狐族の古い民謡を今でも覚えている。それは曲にはなっていない歌で、故郷を失ったことを嘆き悲しむ哀歌だ。「狐綏綏として彼岸の浜にあり。道行くこと遅遅にして飢渇は避らぬ。我が心悲哀に暮れるも、それを知る者なし」……
数千年前、彼らは狼の爪の下で家畜となり、奴隷となり、通貨となった。そして数千年経った今、依然として同胞を解放するため征戦を続けている。天敵のように強靭で変異を続ける肉体は持たないが、彼らは機敏で機知に富んでいる。
狼主は彼らに道具を作るよう命じたが、その技術を学ばないよう両の目を抉り、道具を模造しないよう金属を持つことを禁じた。しかし、それでも狐族の内なる渇望を消し去ることはできなかった——いつの日か狩られる側の恐怖を狩人にわからせ、この立場を逆転させ、追い掛け回してやるという渇望を。
最終的に、狐族たちは磁器を焼いて甲冑を作った。青丘の磁器甲冑は風のように軽く、鋼鉄のように堅い。狼主の手下も、肉体という名の武器も、その甲冑を傷つけることはできなかった。
将軍はその磁器の甲冑を身に纏い、青丘衛の戦士たちと共に風に乗って立ち上がり、歩離人たちを苛む悪夢となった。彼らは隊列を組んで進軍と後退を繰り返しながら、まるで狩りに臨む鳥の群れのように互いに呼応している。しかし、その甲冑がいかに頑丈であろうとも、彼女は「苦痛によって鍛えられた肉体こそが最高の武器であり、苦難を共にした戦友こそが最高の防具である」と最後まで信じていた。
「鳥は羽翼を広げ、獣は牙と爪を露わにする。我らには何もないと誰が言った?同胞こそが鎧である」
- 脚部
- 勇猛な狩猟キュイス
- 鳥獣の爪で作られたバトルブーツ。これを履いた者は風のように素早く戦場を駆け、茨の道も難なく進むことができる。
霞んだ月の下で、彼女は脱兎の如く動き回る少女の姿を見ていた。そして獲物を追いかける狩人のように、その足跡と匂いを追い、道の終わりで少女が来るのを待つ。
あるいは、少女が彼女を待っていたのかもしれない。
月明かりの下で、将軍はその顔をはっきりと見た。
「そんなに雲騎軍に入りたいのか?」
「狼主のために命懸けで働くのは嫌」
少女の歩離語は途切れ途切れで聞き取りにくかったが、その表情は陥落地で同胞を救出した際に幾度となく見たものだった。
彼らと彼女は同じ血を引いてはいるが、異なる言葉を使い、異なる考えを持っている。
彼らは自分が狐族の子孫であるとは考えていない。では、彼らは一体何者なのだろうか?
将軍は微かに身を震わせ、道をあけた。
「行きなさい。今夜から、奴らはあなたを追ってこない……」
「でも、私は奴らを殺したい」
空を横切る流れ星を目撃した時のように、将軍は信じられないといった様子で彼女を見つめたが、小さな獣のような姿は一瞬にして暗闇の中に消えてしまった。
まるで月明かりに目を焼かれてしまったかのように、将軍は目を閉じる。しばらくして俯き加減に瞼を開けると、そこには少女の足があった。靴を履いていない両足は、棘が刺さったことによってできた傷と泥にまみれている。
「どうして靴を履いてないの?」
「忘れてた、気づかなかった」
将軍は自分の靴を脱ぐと、サイズを比べて少女に履かせた。
「ぴったりね…じゃあ出発しましょうか」
「あなたはどうするの?」
「大丈夫、棘の上を歩くのには慣れてるから」
足を踏み出した彼女は、裸足でありながら飛ぶように進んでいく。そんな彼女の後ろ姿に、少女はぴったりとついていった。
あるいは、彼女たちはお互いの姿を追いかけていたのかもしれない。
再び苦難の道を歩む司祭

詳細
- 頭部
- 司祭の音律奏でる耳飾り
- 彼は往々にして告解室の中に座り、耳を傾ける。その耳飾りは、どんなに小さな囁きにも重みがあるのだと、絶えず彼に思い出させてくれた。
「あなたの意志に従います。私は過ちを犯しました。それぞれのクランの間に隔たりがあると嘘をつき、その新聞種と引き換えに情報料を手に入れました……」
当主は窓越しでも、その記者が目を逸らして自分の反応を慎重に待っていることがわかった。それなら数えきれないほど繰り返されてきた「神聖な告解」のように一一鈴の音のような慰めの言葉で信者たちに己の罪を悔い改めさせればいい。しかし今、彼は無意識に顔をそむけ、言葉を飲み込んでいる。耳元で金属の耳飾りが立てる澄んだ音も、今は雑音のように聞こえた。
「よくわかっています、これがデタラメな話だということを。デウムの恩に報いて、ファミリー全体が一丸となること…それこそが多くのクランメンバーの願いであり、彼らがデウムの元に身を投じる理由でもあります」
罪を告白した者は悔い改め、和音から赦しを得るための洗礼を受ける。当主は静かに目を閉じ、聖なる言葉を告げた――
「よろしい。他の家族に誠実な姿を見せ、流言飛語を訂正なさい。そうすれば、再び和音を取り戻すことができるでしょう。さあ、心安らかに帰りなさい」
真実の言葉と善意の言葉を語ることのどこに罪があるというのだろうか?彼の言葉は明確であったが、その音律は枷のように重く響いた。当主はため息をつき、首を横に振る。
「…次の方、前へ」
- 手部
- 司祭の招請用の手袋
- 彼はしばしば訪問者を迎え入れたり、たくさんの人を館に招待したりしている。その手袋は謙虚さと礼儀を忘れないようにと彼を戒めていた。
「当主、この者たちは大切な用があるので当主にお会いしたいと申しております。ですが、うち何人かは身元が怪しく、夢に入った手段も一般的なものではありません……」
夢に侵入してきた招かれざる客たちが並んでいる。当然のことながら、悪意を持った殺人者は追い出され、身元を偽った犯罪者は拘束される。一言も発することなく、彼はすでにそれらの段取りを済ませていた。無実の者たちは彼の怒りを目の当たりにし、期待と不安が入り混じる中で目を輝かせている一一すると彼はほほ笑み、目の前の者たちに手を差し出す。それは皆をオーク家へと迎え入れる招待の意であり、同時に威厳を示すものでもあった。
「皆さんはオーク家の大切な客人ですので、礼を尽くすのは当然です。なぜ自分が正当な評価を受けたのか、不思議に思われるかもしれません。少しだけ説明させていただきますと、それは皆さんが歩んできた『道』がワタシと重なったからです」
使用人、役者、無職の者…彼らは招待における誠実さを理解すると、次々に疑念を払拭し、懸念を一切残さなかった。
「罪人には相応の罰を、客人には相応の礼を。それが調和本来のあり方です」
当主は優しさと威厳の両面を見せ、訪問者たちの信頼を十分に勝ち取ったのだ。彼は一同を見渡してから、ゆっくりと一礼する
「オーク家へようこそ」
- 胴体
- 司祭の聖職礼服
- 彼は普段から姿見の前に立ち、身なりを整える。外出前にすべてが整然としていることを確認し、あらゆるものが決して乱れることがないようにしていた。
「♬…鳥が生まれながら自由だと言うのなら、何が私の運命を縛っているの?」
リハーサルの日、ステージに立つ歌手の邪魔にならないよう、若き当主は観客席の隅に身を隠した。ちょうどいい距離感こそ、彼が望んでいたものだ。礼装を身に纏い、襟を正して座っている彼は、この時、たった一人の観客であった。馴染みのある歌声の中で、彼の思考は子供時代に戻っていく。あの時も同じように彼女は「ステージ」に立って歌い、彼はたった一人の観客だった――
「ここのところ、ずっと楽しく歌う機会がなかったよね…だから、ステージを用意したんだ。ちょっと…粗末だけど」
2人だけのコンサートで、彼はいつの日か彼女の夢を叶え、もっと大きくて輝かしいステージへ連れて行くと約束した。
「♬私の心を勇敢に羽ばたかせる、舞い上がり夜の闇を抜けて、美しい月の光に向かって飛べるように……」
彼はしばらくぼんやりしながら、スデージに近づけない理由に向き合った――礼装を身に纏っているのは、公演を楽しむためではなく、いつでもその場を離れられるようにするためだ。
「おめでとうございます、妹よ。ワタシたちの夢はすべて叶いました」彼は小声でそう言った。
- 脚部
- 司祭の苦旅を共にするブーツ
- 彼は毎回旅に出る前に、足に合ったブーツを選んでいる。彼は幾度となく転んだが、同じ回数だけ立ち上がった。
「行きなさい、あなたは自由よ。己の本分を超えようとした、神に選ばれし者…その冀を折り、俗世を訪れ、大地を歩き、この世界の真の姿を見てくるの」
以来、彼はよくカンパニーの幹部が放った言葉の意味を思い返していた。喧騒に包まれた街を歩き、静かな海辺を歩き…そうして歩き続けていたが、実際は一歩も前に進んでなどいない。彼は自分が不屈の精神を持っていることも、決断力や行動力があることも決して疑っていなかった。ただ、再び立ち上がる前に、彼は理想が地に落ちた時の硬い感触を存分に味わうつもりだったのだから――
「斑な石片は、獣の血と人の汗が染み込んでもなお、変わらす冷たく、粗く、硬いまま……」
クランを取り仕切る者として、彼はあまりに多くの迷える子羊たちを導き、正しい道を示してきた。しかし、自分自身に向き合った時、その優しい慰めは魔法を失い、もはや効果を発揮しなかった――それでいい、彼は叱責も、同情も必要としていないのだから。
「苦行者は泥の中でしか生まれません。歩み続ければ、ワタシは成功よりも失敗から多くを学ぶのでしよう」
本当の再出発が始まる前に歩を緩め、思考を整理する一一彼には十分な時間があるのだ。
「歩くことに複雑な哲学はありません。一つの道に行き詰まったら、別の道を選べばいい…ただそれだけなのです」
知識の海に溺れる学者

詳細
- 頭部
- 学者の銀縁モノクル
- 巨大な建築物を映し出す晶石のモノクル。杖や懐中時計の鎖、ブローチと共に、持ち主のセンスと学識を際立たせている。
【シリアルナンバー】EVD-W019EI06-003
【名称】晶石のモノクル
【基本的特徴】明らかに割れた痕跡がある
【証拠採取地点】オハイティ中央総合アカデミーエネルギー研究部「柏環」研究室
【当事者情報】柏環。エネルギー分析分野でトップレベルの科学者。天才クラブ#7
【現場分析】
現場の状況から判断すると、当事者が観測装置の起動時に操作ミスを犯したのか、容器内の燃素ポリマーが漏れ出したようだ。それによって当事者は左手に重傷を負った模様。事故発生時、モノクルが高所から落下し破損したとみられる。
【証言の補足】
柏環は実験中に、モノクル内に異常な可視光が現れ、その強い光が一連の偶然を引き起こし、最終的に燃素ポリマーの漏出事故が発生したと述べている。
当事者の供述はあまりにも多くの偶然が重なっているため、この証言は採用されなかった。
【備考】
これは計画的な犯罪であることを、さまざまな痕跡が暗に示している。連続する偶然によって発生した「バタフライ効果」は「再現可能な犯罪手段」として認定されないため、この漏出事件は最終的に「事故」と結論づけられた。
【関連録音】
「…私はこの事故に感謝しなければならないのかもしれない…ラムが再び私の元に帰ってきてくれたのだから。こんなことを話すのは恥ずかしいのだが、私たちにとってもう4回目の再婚で…今回は初めて私から再婚を提案したんた」この音声記録は柏環によるものである。
- 手部
- 学者のナックルサポーター
- 指の動きをサポートする合金製の外骨格。使用者の手の形に合わせてカスタマイズする必要があり、非常に高価である。
【シリアルナンバー】EVD-X024DE18-002
【名称】「灰玉合金」が埋め込まれた手指の外骨格
【基本的特徴】外力による打撃で損傷した痕跡があり、爆発事件前にはすでに破損していたことが確認された
【証拠採取地点】極地エネルギー採掘場中央制御室
【当事者情報】ラム(死亡)。生物波探査分野でトップレベルの科学者。天才クラブ#8
【現場分析】
監視カメラの映像によると、当事者の操作ミスが原因で中央制御室の爆発を引き起こし、即死した。
【証言の補足】
「彼女が胸の内に何を隠していたのかは知らない。たがもし彼女に何かあったのだとしたら、クラインか無関係であるはずはかない!」
爆発事故の2週間前、警察は柏環から通報を受けた。柏環は妻の不自由な右手が悪意を持った暴徒によって傷つけられたと話したそうだ。しかしその後、当の被害者であるラムがさらなる調査を拒否し、立件を取り消した。
【備考】
爆発事件後、当事者の夫は調査終了後に外骨格と当事者の指の骨の返還を要求した。
この事件は、連続して起こった偶然の出来事があまりにも多いため、十分な警戒を要する。
【関連音声ファイル】
「クライン、出てきてくれ。私たちの間にはまだ片付いていないことがある。それはお互いによくわかっているはずだろう。この世界に絶対的な『偶然』なんてものはない。一連の『不可思議な偶然』ならなおさらだ」この音声ファイルはクラインの邸宅のセキュリティシステムのものである。
- 胴体
- 学者のツイードジャケット
- ツイードのコートとセーターは、大学でよく見られるコーディネートだ。耐久性があり、しわにもなりにくい生地は、訪問学者にとって最適である。
【シリアルナンバー】EVD-X043FE21-001
【名称】ツイードのコート、ウールツイードのベスト、白いシャツ
【基本的特徴】左胸に直径約8センチの燃素によって焼け焦げた跡がある
【証拠採取地点】オハイティ中央総合アカデミーエネルギー研究部「柏環」研究室
【当事者情報】柏環(死亡)。エネルギー分析分野でトップレベルの科学者。天才クラブ#7
【現場の分析】
現場の状況から判断すると、当事者は「灰玉合金」の粒子を携帯しており、大量の燃素を吸着したため、心臓部で瞬時に千度近い高温が発生したとみられる。コートにベスト、そしてシャツのすべてに焼け焦げた痕跡がある。
焼け焦げた場所には燃え残った薬指の骨が残っていた。鑑識の結果、この骨はラムのもので、高純度の「灰玉合金」の粒子と関連している可能性がある。
【証言の補足】
「…人にはミスが付き物だということを考慮すべきだった。ましてや、妻の死を乗り越えられていなかった状況では……」
研究室の学者たちによると、安全マニュアルを策定した柏環がこのような「低レベルなミス」を犯すとは考えられないそうだ。
【備考】
「灰玉合金」は天才クラブ#9クラインが開発した希少な合金であり、燃素を捕らえ、貯蔵する性質を備えている。
偶然があまりにも重なった場合、その偶然ははたして偶然と言い切れるのだろうか?
【関連ファイル】
高純度の『灰玉合金』製品を燃素観測庫が設置された実験室に持ち込むことは厳禁とする」エネルギー研究部実験室の安全マニュアルからの引用。
- 脚部
- 学者のスエードスノーブーツ
- 柔らかく快適な女性用のショートブーツ。適切なレギンスと合わせれば程よいファッション感を出せる。持ち主と共に極地調査へ長年付き添ってきた。
【シリアルナンバー】EVD-X031JA12-004
【名称】極地調査用スノーブーツ(女性用)
【基本的特徴】明らかな損傷や修理した痕跡があり、靴底にはディスクが1枚隠されていた。なお、スパイである可能性は調査の初期段階で排除されている
【証拠採取地点】クライン家の地下室
【当事者情報】クライン(死亡)。合金素材学分野でトップベルの科学者。天才クラブ#9
【現場分析】
クラインの家から科学者ラムの遺品が大量に発見されたため、このショートブーツもそのうちの1つとみられる。
【証言の補足】
「私は彼を誤解していたのかもしれない…ああ、クラインのことだ。そして私の妻ラムは…彼女か旅立ってから久しいのに、いつまで経っても・・・慣れることはないようだ」
柏環は、妻の遺品がクラインの家から出てきたことは知らなかったはずだが、その表情から察するに、特に驚いてはいないようだった。
【備考】
クラインの邸宅は人里離れた場所にあるうえ、法医学者が推定した死亡時刻の前後に邸宅を訪れた人は誰もいなかった。調査の初期段階では事故死だと判断された。
柏環、ラム、クラインの3人の関係は特殊であり、彼らに起こった「偶然」はいわば「超常現象」に近い。
【関連音声ファイル】「はあ・・・柏環、君が私を疑っているのも、私が無実を証明できないことも理解している。ラムの件については、本当に申し訳なく思っている…だか彼女を傷つけるようなことは決してしていない…犯人については少しばかり手がかりを掴んでいる。『静寂の主』という名前を聞いたことかあるだろうか?※無意味な雑音※」この音声ファイルはショートブーツに隠されたディスクに記録されていたものである。
凱歌を揚げる英雄

詳細
- 頭部
- 英雄の月桂冠
- コロシアムの優勝者に与えられる月桂冠。金色の月桂樹の葉の一枚一枚が、勇気と栄光に輝いている。
オロニクスが嘆息すると、時間がゆっくりと流れていくようだった。耳には重い息遣いが届き、肋骨が痛みで鼓動する。まるで闘技場の空気をすべて肺に取り込もうとしているかのようだ。汗と血が混ざり合って流れ落ち、足元の大地からは誘惑する声が聞こえる――ここまで頑張ったのだから、もう諦めていい――彼の疲労はすでに限界に達していた。
「次の攻撃はどこから来る?左か、右か?フェイントもある、それとも……」
槍先がすでに迫っており、もはや考える時間はない。ならばいっそのこと、「紛争」のタイタンに運命を委ねてしまおう――彼がすべきなのはただ槍を突き出すことだけだ。
砂埃がゆっくりと収まっていく。闘技場の外から斜陽が差し込み、彼の横顔を照らした。観客席の人々は次々と立ち上がり、拍手と歓声が波涛のように押し寄せてくる。その瞬間、彼は驚いた――この場所がこんなにも広大であったこと、逃げ場のない緊迫感がとうに消えていたことに気づいたからだ。場内には血の跡と倒れた相手、そして輝く孤高の勝者だけが残っていた。
城主は手を高く上げ、彼の優勝を宣言した。そして彼はダウリの音が鳴り響く中で月桂冠を戴き、闘技場の伝説となったのだ。
「お前は近衛兵に選ばれた。お前の名は勝利と共に、英雄の叙事詩に記されるであろう!」
その後、彼の名は街中で聞こえるようになった。ニカドリーの栄光はまるで世界が彼のために存在しているかのように、彼を包み込んだ。
- 手部
- 英雄の黄金手甲
- 近衛兵の精巧な腕当て。勇士の手首にぴったりと合い、勝利の角笛をしっかりと支える。
大勝であろうが惨敗であろうが、闘技場の王は必ず戦場から帰還する。城主はその強運を「勝利の象徴」と見なし、彼の手から槍と盾を取り上げ、代わりに角笛と戦旗を持たせた――強運を全軍に分け与えられるようにと。そして兵士たちは、ニカドリーの栄光は彼と共にあり、彼が先導する限り勝利は必ず訪れると固く信じるようになった。
「今後、お前は一介の戦士ではなく、象徴となるべきだ」
苛酷な訓練で鍛え上げた鋼の肉体も、今では神殿の石像のようにただ鑑賞されるだけの存在だ。
兵士たちは「勝利の象徴」が些細なトラブルに巻き込まれることすら恐れ、彼が訓練場へ立ち入ることを拒んだ。代わりに彼は城主の宴に招かれ、来賓たちが尋ねられる数々の死闘の逸話を話した。そして今、彼は戦場の端に立ち、角笛を握りしめている。金色に輝く手甲が見慣れない横顔を映し出す。その時、急に胸が締め付けられた――彼は勝利の号令を吹き鳴らすだけで、もはや戦場で突撃する必要はない…これが人々の言う「不戦の英雄」なのだろう。
「…これで勝利をもたらせるのなら、喜んで戦場での栄光を捨てよう」
ニカドリーは「象徴」のために勝利の道を示したことはない。だからこそ彼は備えていた。いすれ訪れるであろう生涯最後の戦いのために……
- 胴体
- 英雄の勇戦金鎧
- 勇壮な肉体に相応しい、天神の如き甲胃。
狂気に陥った神と対峙して、無事に帰還できる者などいない。ニカドリーの鋒がどこを掠めようとも、槍が折れ、盾は砕け…統制を失った兵士たちは、空前絶後の混乱と恐怖に陥り、戦線は簡単に崩壊してしまう。闘技場の英雄の角笛の音は怒号、悲鳴、金属がぶつかり合う音の中に埋もれ、とうに訪れた結末を覆す力を持ってはいなかった。
「ニカドリーは約束した勝利を取り戻そうとしている。ならば、私は槍と血を以ってそれを返上するしかない」
巻き上がる煙塵の中、破れた旗がニカドリーに向かって進んでいく。兵士たちは気づいた…強運の英雄が二度と戻れない道を選んだことに。
最初は数人が続いただけだったが、やがて数十、数百人…と、彼らはその広い背中に続き、死が約束された戦場に向かって最後の突撃を敢行する――かつて戦の中で倒れた戦友たちは英霊となって彼らの耳元で囁き、生者たちを激励する。ニカドリーは自身が狂気に陥っていても、戦士たちの不屈の決意と恐れ知らずの意志を本能的に感じ取った。
「見ろ!闘技場の英雄はまだ前進し続けている。我々も後に続くぞ!」
金色の鎧は夕日に照らされてなお輝き、彼は軍を率いて名誉と尊厳のある死へと向かっていった。
- 脚部
- 英雄の炎行脛当
- 戦士の足にフィットする脛当て。優雅で堅固な曲線で、不退転の信念を表している。
兵士たちは黙ったまま廃墟に入り、戦場の後始末を始めた。ある者は遺体を必死に引きずり、戦友を敵から引き剥がす。またある者は戦死した仲間の傍に跪き、そっと彼らのまぶたを閉ざす…戦場の怒号はとうに消え去り、残されたのは息が詰まるような静寂だけ――闘技場の英雄もこの地で永遠の眠りにつき、血と埃に塗れた金色の脛当てだけが鈍い光を放っていた。
「忘れるな、戦士たちが完全に消えることはない。彼らの魂は後世の人々の記憶の中に永遠に刻まれるのだから」
その後、静寂は悲哀のこもった歌声によって破られた。司祭たちが戦死者の葬儀を行うために戦場へやってきたのだ。
闇夜の中で炎が燃え上がり、哀歌は響き続ける…突然、天罰の矛が大地を刺した時のように、遠くの空に眩い光が走った。きっとニカドリーがこの地の英霊を呼んでいるに違いない。葬儀に参列していた兵士や市民たちは次々と跪き、心の中に畏敬と感謝の念を抱きながら両手を高く上げる一一その光は温かな息吹となって戦士たちの魂を持ち上げ、タイタンの祝福と赦しを囁きながら、英雄たちの不滅を宣言した。
「見ろ。闘技場の英雄は死してなお戦士たちを導き、故郷への道を示している」
英雄は優しく頷いた。古い歌の中で、その高貴な魄は再び鍛え直されることだろう。
亡国の悲哀を詠う詩人
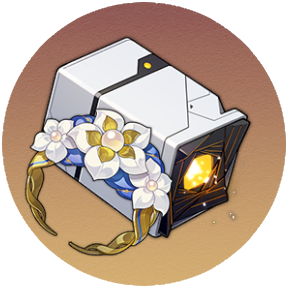
詳細
- 頭部
- 詩人の花をあしらった冠
- 春の日の黄昏、神殿の前。モネータに祝福されたディルの花冠は最も優れた吟遊詩人が授かる。
モネータよ、我らはあなたに祈りを捧げる。もしこの世に歌声がなければ…歌声のない春は、森に花が咲かないのと同じ……」
吟遊詩人たちは清流で手を清め、冷やしたネクタールを杯に満たし神に捧げる。その後、神殿の前に集まり、モネータの祝福を受けた花冠を誰が手にするかについて議論を始めた。恋愛詩で有名なパルティ三姉妹が率先して歌声を披露し、それに続いて数々の独特な比喩で知られる老詩人ルポが歌う。しかしどんなに優れた音楽や巧みな言葉でも女神の心を動かすには至らず、杯の中の液体は微動だにしなかった。
そしてある流浪の詩人の番が回ってきた。その手には7弦の竪琴が握られており、古代のパピルスに記された物語を奏で始める一一千年前の風や砂塵が流れ、物語はこのように始まる――「世界にまだ多くの都市国家が存在していた時代、1つの都市が邪竜の襲撃を受けた」
「我か国の悲哀を詠おう――」
「怪物が城に居座り、貴き血筋が悪に堕ちた」
「高塔に進入した巨竜のせいで」
「我が王は惑わされ、我が国の姫は食われてしまった……」
女神は供物のネクタールを飲み干し、流浪の詩人が花冠の所有者となった。
- 手部
- 詩人の黄金を用いた腕輪
- 金属で作られた、人気のある腕輪。物語の中の邪竜も、かつてこのような金属の枷を背負っていた。
「人々はジョーリアの神体から黄金を掘り出した。それは最初の凶悪な金属となり、陰謀と戦争を生んた」
戦争の起源は定かではないうえ、それにまつわる数々の歴史はやがて伝説となってしまった。しかし、たとえ伝説であっても――傲慢、詭計、貪欲さが人々の終わらない争いの原因であるにもかかわらす、黄金が無実の罪を負わされているのは事実である。まだ争いを知らなかった純粋な時代において、鉄や銅はもともと神に捧げる器物の原料だった。しかし、やがて祭壇から下ろされるようになると刀や槍に鍛え直され、黄金よりも凶悪な金属となったのだ。
物語の中の巨竜は討伐されたのだろう。都市国家間の戦争もほぽ収束に向かっていった。流浪の詩人は聖都を訪れ、物語の続きを詠う。
「邪竜が都市を占領した後、人々は姫を救うために竜狩りの勇士を募った」
「我か国の悲哀を詠おう――」
「勇猛なケントゥリオは、金属の鎖を操り、ついに邪竜を屈服させた」
「塔の頂上から老いた王の悲痛な泣き声か響く……」
「竜の腹の中から、食われた姫の骨だけか辛うじて見つかった」
歌と共に金属製の腕輪の飾りが弦に触れ、儚い嘆息のような音を立てた。
- 胴体
- 詩人の星降るドレス
- 黎明は最も優しい時間だ。彼女のスカートも、まるで夜が明ける前に輝く最後の星のような色合いをしている。
「エーグルが目を開ける時、すべての星が眠りにつく。ただ最後の星は好奇心が最も強く、いつも目を細めて盜み見している」
叙事詩は2回目の昼と夜を迎えるまで歌われ、詩人の周りにはますます多くの聴衆が集まってきた。その中には矢筒を背負ったクレムノス人や、占いの棒を投げて神意を問うヤヌサポリス人もいる。暗黒の潮が各地の都市国家を侵蝕して以来、散逸してしまった文献は数え切れないほどあったが、樹庭の学者たちもすべての資料を集めるには時間が足りなかったという。そして小さな都市国家の多くは、名前すら残らすに消えてしまった。
ただ流浪の詩人だけは、邪竜に襲われた古の都市に秘密の錬金術が伝えられていることを知っていた。
「肉体を礎とすれば、万物を創造でき、奇跡に到達できる。錬金術師は娘を失った国王にそう告げた」
「我が国の悲哀を詠おう――」
「言葉巧みな錬金術師は、竜の肉体から姫を復活させられると言った」
「死せる者、死に至らず。そしてまた十昼夜が過ぎ……」
「ついに儀式は終わった。しかし……」
最後の星はまだ聞き終わっていない物語の続きを惜しむように、その目を閉じた。
- 脚部
- 詩人の銀鋲を添えたサンダル
- 銀の鋲がつけられた履物。砂の上を歩くと文字のような跡を残す。彼女は過去の詩を求めて、ただただ歩き続ける。
「人々はタナトスの痕跡を見つけられず、生者が渡ることのできないステュクスがどこに通じているのかもわからない」
「そんな巨竜など聞いたこともないし、どの古文書にも肉体を復活させる儀式については書かれていない」聴衆の1人が疑念を投げかける。すると詩人は、「私は古の都市国家の末裔ではないし、邪竜が本当に存在していたかどうかも知らない。これは昔、他の吟遊詩人から聞いた、代々語り継がれている歌にすぎない」と答えた。
もし誰もこれを歌わなければ、古の都市国家の歴史は本当に埋もれてしまい、すべてが時と共に色褪せてしまうだろう。かつて繁栄した都市国家はステュクスに押し流され、野犬やハゲタカですら忌み嫌う場所となった。それは、邪竜に食われた魂が残した呪いなのだ。
「我か祖国の悲哀を詠おう――」
「姫は錬成により、邪竜の姿に変わり果ててしまい……」
「錬金術師、勇猛なケントゥリオ、愚鈍な国王をすべて呑み込んでしまった」
「血生臭い宴は死の影を呼び、都市はこれによって滅びてしまった……」
滅びた国の名を覚えておいてほしい。これは「スティコシア」にまつわる物語。銀鋲の靴をいた詩人が歌った。彼女は物語を完成させるために、各地を渡り歩いて物語を集めてきたのだ。その行いはまさに、靴に刻まれている文字の通り一一「この物語だけを記億し、私のことは忘れてほしい」
烈陽と雷鳴の武神
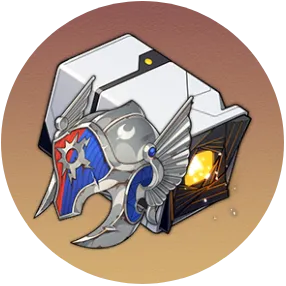
詳細
- 頭部
- 武神の翼兜
- この羽根つきヘルムは陽雷の騎士が神を討つところを見届け、空がまぶたを閉じる様子も見届けた。
熱く燃えたぎる黄金の溶岩が武神の足元から噴き出し続けている。表情を鉄兜の奥に隠した彼女は、星の輝きを覆う冬の霧のようだった。
最後の天空の子はすでに沈み、彼女は独り正反対の遠い地へ向かうこととなる。
「セネオス、誰を思い出している?」朝晩をともに過ごしてきた翼獣が、彼女のかすかな心の変化を察知した。武神はしばし黙り込んだ。大勢の人々が空へ祈りを捧げていたあの時代は、すでに遠い過去のものとなっている。「誰を思い出しているかって?もう具体的な人の顔なんか思い浮かばないよ。あれほど深く人間を愛し、その弱さを憎んできたのに…今ではもう、誰一人……」
翼獣たちはうなだれて言葉を失った。彼らは知っているのだ、かつて確固たる信念に従っていた武神が、自らを欺く幻影に陥ってしまったことを。
頭部を覆う鉄兜の奥で、彼女は今どのような顔をしているのだろうか。そして、そこからどのような景色を見つめているのだろうか。
- 手部
- 武神の騎兵手甲
- このガントレットは騎士のすべての勝利に付き添った。これがあれば最も攻撃力のある武器を握り締め、そして最もつらい裏切りにも耐えられる。
銀鱗の塊が炉の中で産声をあげる。年長の山の民は鍛えあげたガントレットに祝福を施し、そばに立つ武神に渡した。
「柔らかいは、傷つく。騎士たる者、硬くあれ。雲母よりもしなやかに…その骨まで」
彼女は精緻なガントレットを受け取り、氷のように冷たい銀鱗の甲冑をそっと拭った。そして想像した――雷撃によって鍛えられた長槍と、炎が花開くようにして生まれた円盾を手に、すべての人を救うべく天空の戦場へと駆ける自らの姿を。強さとは、人を救うのに必要な条件の1つにすぎない。山の民は指の関節部分に真理の言葉を刻み、鉄のガントレットにも柔らかい部分があることを忘れないようにと、武神に言い含めた。
「川床の小石を温めるなら、手のひらを使え。氷河は、剣にしてはならない」
しかしその後、彼女の極端とも言える使命感と正義感は、その工匠の祝福を燃やし、二度と癒えない傷痕へと変えてしまった。
- 胴体
- 武神の旅立ちの外衣
- このマントは陽雷の騎士を雨やほこりから守り、すべての冒険に付き従ってきた――そして何より、最も目を引く後ろ姿を空に残してきた。
まだ騎士ではなかった頃、少女は師匠が隠れ住む山の洞窟で、卓越した武芸を教わっていた。
「よくやった。もうすぐ私が教えられることはなくなるだろう。ところで、お前はその力は何のために使うつもりだ?」
神託を聞いてから、少女の心はすでに修行に集中できていなかった。温厚な師匠はその悩みを見抜き、彼女がいつも使っている短剣に松脂を塗りながら尋ねた。「師匠、私は真実の中で生きていきたいです。ヤヌサポリスの聖女、そして彼女が伝えた神託のこと…ご存じですか?」少女は師匠に止められることを恐れていたが、心の中ではすでに決意を固めていた。
「だが、真実とはなんだ?」穏やかな口調で師匠が問い返した。「……それを見極めるには一生をかけることになる。簡単ではないのだよ」
深夜、少女は静かに起き上がり、夜が明ける前に急いで去ろうとした。だが、折り畳まれたマントがすでに旅の荷物に忍ばされていることに気づいた。
- 脚部
- 武神の栄光の輪拍
- この拍車は陽雷の騎士に付き従う2頭の翼獣からの贈り物だ――真実の道を歩むには、これは避けられぬ痛みなのだ。
英雄セネオスには2頭の翼獣が付き従っていた――ソラビスとルネビス。彼女の乗騎であり、戦友でもある。
「私たちはセネオスについていく。神を倒し、火を奪うあなたの旅――その序章を見届けさせてもらいたい」翼獣たちは自信に満ちた武神を信頼していた。
2頭の翼獣は大工匠に拍車を作ってもらいたいと頼んだ。それを「陽雷の騎士」の叙勲式の一環として渡すためだ――「君たちの気持ちはありがたいけど、これは必要ないわ」それが乗騎を正確に乗りこなすための補助具だと知っていた彼女は、「君たちとは心が通じ合っているから、そんな刺激に頼らなくても、ぴったりと息を合わせられるもの」と言った。
「受け取ってほしい、セネオス。真実の道を歩む其方は、『痛み』が私たちを目覚めさせると理解しているはず」ルネビスは揺るぎない光を宿した眼差しでそう言い、ソラビスは彼女の手を取って拍車を受け取らせた。
陽雷の騎士は友情の象徴である勲章を受け取った――痛みで進路を調整できるなら、それは必要な痛みなのだ。
荒海を越える船長

詳細
- 頭部
- 船長の羅針ハット
- 真珠のような光を放つ広い、つばの広い帽子。海を旅する船乗りたちは、これでエーグルの灼熱の陽射しを凌いでいる。
岸辺の岩礁には、巨鯨のような三段櫂船の残骸が打ち上げられている。それはセイレーンを討伐するため出港した軍船であり、船は波によって海岸まで押し戻され、乗組員たちは大海原に取り残された。
「ファジェイナの勇士よ。誰でも構わぬ。どうか立ち上がってスキアナを守ってくれ!」国王は悲痛な声を上げたが、応える者はいなかった。セイレーンに立ち向かったところで屍になって海に浮かぶだけからだ。
「頑丈で大きな船と、50人の船員を用意してくれ。俺がその忌々しい怪物を討ち取ってやる!」つば広の帽子をかぶった若き船長は、そう言って人混みの前に出た。彼の帽子は真珠のように輝いており、人々の青ざめた顔を一瞬で虹色の光で染めた。その登場はまるで夜明けの海のようで、一瞬にして地平線が白み始めた。
「俺が世界一の船を造ってやる!」若き船長の気迫に惹かれた工匠たちは、誰もが自らの技術を捧げることを誓った。船体には大海原でも朽ちることのない丈夫な木材が使われ、また船首には預言の力が宿ったサーシスの巨木の一部が使われた。
「賢者の弟子よ、神々に選ばれし英雄よ、行くがいい。ファジェイナの狂乱を鎮めるのだ」3日後、船員を乗せたその軍船はスキアナから出航した。
- 手部
- 船長の集光アストロラーベ
- 星の光を捉えて進路を示す航海用コンパス。暗く果てしない大海原にあっても、星の光は進むべき方向を教えてくれる。
鉛のように重苦しい雲がマストに押し寄せ、暴風雨が軍船を浮草のように揺らし、神聖な木材で作られた甲板も荒波で激しく軋む。
「年中穏やかだったあの海域でさえ、セイレーンの悪行に染まっちまったか」若き船長は船首に立ち、眉間にしわを寄せながら遠くにある漆黒の雲をにらんだ。しかし、腕につけているアストロラーベに反応はなかった。
雷が落ち、主帆を支えるロープが音を立てて切れ、船乗りたちは混乱に陥った。だが、若き船長は怒声をあげ、漕ぎ手たちに号令に従って力を入れろと叫び、操舵手には進路を変え、山のような大波をひとつずつ回避するよう指示した。今はとにかく被害を抑え、エーグルの導きの光が輝くまでファジェイナの怒りに耐えるしかない。船長が腕を振り上げてそう叫んだ時、腕についていたコンパスが色とりどりの星光を返し始めた――
「みんな、あの光を追いかけるんだ!嵐を突き抜けるぞ!」
船乗りたちは気力を振り絞り、船の歌を高らかに歌った。軍船は刃のように波を切り裂き、黎明を目指して突き進んだ。
「もうすぐ彼女の束縛から解放されるぞ!進路を確認して備えるんだ!いくぞ!」
- 胴体
- 船長の統風マント
- 巨大な帆のように風にはためく航海用マント。もし風が吹かないのならば、自分が風となろう。
人の背丈ほどもある青銅の矢が、炎を纏ったまま霧の海に放たれた。だが、それがセイレーンの鱗に迫った瞬間、矢は粉々に砕け散った。淡い青色をした触手が体に絡みつき、斬り落とされてもなお甲板の上でのたうち、恐怖が船員たちを呑み込む。
「セイレーンの手足が空中で暴れ回り、泣きわめきながら俺の名を叫んでいた。あれは俺の航海人生で最も恐ろしい光景だった」そう話す船長の声は微かに震えていて、それが嘘ではないことを物語っていた。
巨大なセイレーンが海面に現れ、無数の触手を軍船に絡ませた。その背は移動する島のように巨大で、副船長が焼けた鉄槍を無数の鋭い牙が並ぶ口へ突き立てると、黒く生臭い血が甲板を染めた。幸いにも船員たちは間一髪で危機を逃れたが、船長が振り返った時、船尾のやぐらは巨大な触手に叩き潰されていた。その光景はまるでニカドリーの天罰の矛がクルミの殻を砕くかのようだった。千載一遇とも言える好機が訪れたその時、突撃するべきか、それとも逃げるべきか、全員が船長の決断を待っていた――
「取り舵いっぱい!漕ぎ手、全速前進!帆もすべて張れ!衝角で突っ込むぞ!」
船長のマントが荒々しく舞い踊る中、船員たちは覚悟を決めた。鋼鉄と鱗が衝突し、船の竜骨が折れ、セイレーンが悲鳴をあげる。巨体はやがて力を失い、ゆっくりと海の底へと沈んでいった。
- 脚部
- 船長の波踏ブーツ
- 砕け散った波が船長のブーツの下で花開く。たとえ彼が二度と戻らなくとも、海の波は彼の祝福を送り届けてくれるだろう。
どことも分からぬ海岸で、若き船長は仰向けに倒れていた。沈みゆく夕日が砕け散った岸辺に黄金の輝きを添える中、船長は遠く離れたスキアナの地をすぐそこに感じ――そして、今が人生最後の瞬間であることを悟った。
「…俺たちはファジェイナの狂気を抑え込んだんだ」。セイレーンが海底へと逃げた今、この先100年は海岸に被害が出ることはないだろう。
サーシスの巨木から削られた板が、船長に最後の問いかけをした。その板は波に乗り、いずれ彼が思いを抱くスキアナへと戻るだろう。そして、英雄の航海を伝え、多くの若者たちに海へ出る勇気を与えることになる。船長は切断されたもう半分の自分の体を見た。そこには師からもらったブーツがあった。それはいくつもの都市国家を旅する彼を支えてくれたものだが…今、その長い旅も終わろうとしている。
「故郷の皆に伝えてくれ。俺はまだステュクスを征服しないといけない。どうか悲しまないでくれ、とな」
海の風は年々スキアナの城壁を優しく撫でるようになり、セイレーンの話は子供を寝かしつけるための子守歌となった。そして、あの荒れ狂う海から奇跡的に生還した船乗りたちは、今もなお船長が波の上を歩いて帰ってくる日を待ち続けている。
天地再創の救世主

詳細
- 頭部
- 救世主の旅立ちのフード
- 伝説の救世主が雨風から身を守るために身に着けていたとされるフード。実際の服装は、吟遊詩人たちに語り継がれるものとは違ったかもしれない。
オロニクスの夜霧が月桂樹の枝を濡らしている。
その時、運命の深淵に黒き箱を伴って、天外から救世の英雄が降り立っていた。
彼女は神託に応え、やって来たのだ。しかし司祭たちは天外について語ることを恐れていた。
「天空のことを声高に語ってはいけない。疑り深いエーグルが容赦なく神罰の雷を落とすに違いない」
自信に満ちた救世主は、その言葉を耳にすると怒りをあらわにこう言った。
「災いを預言する者よ、あんたは神々だって人の子からの裁きを恐れるべきだと考えたことはないの?」
救世主は、城壁の上で地平線が薔薇色の黎明に染まるのを見つめていた。
「まずはニカドリー…『紛争』を司る者よ、
あんたが狂気ではなく、栄光をもたらすことを願って」
救世主はフードを脱ぐと、長槍を投げた。
その影は春先に疾走する1匹の狼のように街を、道を翔け、クレムノスへと飛んでいった。
「もし運命の糸が絶たれたら、モネータの名において私が物語の続きを織り直そう!」
遥か彼方から狂王の怒号が響いた。放たれたあの槍が、歩みに先んじて出立の時を告げたのだ。
「黄金裔の仲間が旅路で私を待ってる。そろそろ行かないと。」
風になびく救世主の灰色の髪を目にしたヤーヌスの司祭たちは大きな歓声を上げた。
その様子はまるで干からびた草の種が、養分を得たかのように喜びに満ちていた。
- 手部
- 救世主の執剣グローブ
- 伝説の救世主がいばらの道を切り開いた時に身に着けていたとされるグローブ。実際の服装は、吟遊詩人たちに語り継がれるものとは違ったかもしれない。
凍てつくほどに冷たいファジェイナの海が、スティコシアの長い海岸線を蝕んでいく。
救世の英雄はステュクスの渡し場に辿り着いた。冥府への渡し舟は、紫色の巨竜が務めた。
ステュクスのほとりで、亡者たちは甘い囁きとなる。彼らは英雄が人界に帰らぬよう、引き留めようとした。
「あなたはタイタンを屈服させた。その偉業はもう、後継者に託してもいいだろう?」
その言葉を投げかけられた悲哀に満ちた救世主は、悲痛な面持ちでこう返した。
「この場所に留まる亡者よ、あんたは考えたこともないでしょ。救世への願いが再会を望む思いよりも上だなんて」
渡し船に乗りながら、救世主は火追いの旅の数々の場面を思い返していた。
「さようなら、『死』のタナトス。
たとえ私が一番愛する友人たちが、死を恐れない人たちだったとしても、どうかみんなを見守っていて」
救世主は鹿革でできたグローブをそっと撫でた。そこには去っていった友たちの温もりがまだ残っていた。
アンティリン花が咲き乱れる海岸から、湿り気のある温かい西風に乗って、人の世へと吹かれていった。
「サーシス、どうか私の理性を守って。もう振り返らなくていいように」
死から舞い戻ったことこそ、英雄の資質がある者の証だった。
「もうこれ以上、待たせたりしない。黄金裔のみんなとの、忘れられない誓いを果たすよ」
ジョーリアの大地が帰還した彼女を迎え、火追いの旅路が続いていく。
夜空を覆い隠していた黒雲が散ったように、明けの明星が再び輝きを放った。
- 胴体
- 救世主の託されたマント
- 伝説の救世主が刃を交える際に身に着けていたとされる戦衣。実際の服装は、吟遊詩人たちに語り継がれるものとは違ったかもしれない。
エーグルの黒雲が怒りに渦巻いている。
救世の英雄は彩虹の橋架を渡り、かつては触れることすら叶わなかった天空を撃ち落とした。
救世の英雄と肩を並べて戦うのは、生死をともにした仲間だ。
「火を追う旅は喪失の道。その中では、命さえも些事となる。」
その言葉を聞いた救世主は、冷静にそしてきっぱりと答えた。
「みんなの覚悟はわかってる。何千万回くり返すことになっても、その覚悟は裏切らない」
再創世の儀式へと向かいながら、救世主は帰路を守る戦友たち一人ひとりに別れを告げた。
「これは千年も続いた征途と叙事詩。
数多の先人に託された、私が今日ここで必ず成し遂げないといけない物語だ」
最後まで残っていた救世主の相棒は、救世主の肩にマントを掛けると、くるりと踵を返し、押し寄せる敵の大群に立ち向かっていった。
肩にあるそれは共に戦ってきた証。託された想いであり、伝承でもある。
「タレンタム、もし聞こえてるのなら、この壮絶な犠牲に報いて、より良い明日を築いて」
「…我らは『火』に身を投じる――」
「ただ創世の叙事詩に、最初の一筆を刻むために」
ケファレの優しい眼差しの下、救世主は人々の願いを携えて、
再び天地を創るだろう――
- 脚部
- 救世主の開拓ブーツ
- 伝説の救世主が旅の途中で履いていたとされるブーツ。実際の服装は、吟遊詩人たちに語り継がれるものとは違ったかもしれない。
「『黄金の繭』、あんたは浪漫の結末をその目で見届けて、無瑕の運命を織り直すだろう」
「『万路の門』、あんたは数え切れないほどの帰途を開いて、また明日会う預言を叶えるだろう」
「『分裂する枝』、あんたが蒔いた『疑い』という知性の種は、いつか人々の知性から芽を出すだろう。」
「『晨昏の目』、見て!傷一つない天空の果てには癒しの虹が架かってる」
「故郷へ帰ろう、『天罰の矛』。万民が讃える玉座に登り、世界に約束された平和をもたらそう」
「その思いを思うままに。『飛翔する幣』、たとえそれが悪知恵を働かせた冗談であろうと、誠実な言葉であろうと、もう隠す必要はない」
「『暗澹たる手』――ステュクスの主、強く抱きしめていいんだよ……」
「あんたの優しさで向こう岸の花の海は温められるだろう。どんな別れも、再会の希望を孕んでいるのだから」
「人々は聞くだろう、宴に響く『満たされた杯』の歌声が絶えないことを」
「人々は見るだろう――『永夜の帳』が、忘れられない歳月を大切に抱いていたことを」
「不朽なる『堅磐の脊髄』は全ての生命を、旅の終わりまで背負い、支え続けるだろう」
「『公正の秤』は、無私の法を贈り、無数の火を追う旅の英傑たちに冠を授けるだろう……」
「『万象の座』、もう1人で世界を背負わなくていいんだよ。ほら、永久に燃え続ける烈日が、もう昇ってきてる……」
後悔によって紡がれてきた叙事詩は、書き直された詩の中で幸せな結末を迎える。
手が届かないほど遥か遠くにあった終点も、「開拓」によって辿り着けるだろう。
星の光を隠した隠者

詳細
- 頭部
- 隠者のつば広帽子
- つばを巻き上げられる、クラウンにクリースが入ったクラシックな帽子。知識人や芸術家、専門家の間で非常に人気がある。
天体計算機が完成する前のこと――ザンダー・ワン・クワバラはテストデータを携え、銀鱗湖のほとりに隠居している師を訪ねた。
この再会まで、2人は数十年もの間、顔を合わせていなかった。この時、ザンダーが質問したのは、数値の正確さに関するものではなく、すべてを成し遂げた後の結果についてだった…目先のことしか見えない傍観者には理解できない、言い知れぬ不安を彼は感じていた――
「並の才能しか持たない凡人は、たかだか数百年の間、解決されなかった問題を解いただけで有頂天になる。そして優れた才能を持つ者は、懐疑という綱を渡りながらも、『ロジック』という命綱によって深淵へ落ちることを防いでいる。だが君は、その命綱を切り、銀河全体を道連れにして深淵へと落ちることで、知識の境界を突き破ろうとしている…君は何を期待してここに来たんだ。私の警告を聞いて、はい、そうですかと引き返せるのか?鏡で自分の顔を見てみろ。それでも自分が銀河を覆すことを渇望しているとわからないか?私では…いや、誰にも君を止めることはできないだろう」
老人はコート掛けから帽子を取ると、ザンダーの頭に被せた。驚きと怒りが入り混じったザンダーの視線を遮るかのように。
そしてそのまま一言も発することなく立ち去った。
「あれは究極の知を求める機械であり、過去から未来に至るまですべての知識を求め続けています…先生はあれを『知識の牢獄』と言っていましたが、それでも私は信じて疑わなかったのです。あれは偉大な『図書館』である、と――後に私自身が、その囚人となるまでの話ですが」
- 手部
- 隠者のシンプルな腕時計
- ''金属製の美しいメッシュベルトと、シンプルな丸い文字盤の腕時計。クールさと精密さ、
そして工業的な印象を抱かせる。それでありながら、控えめで実用的な気取らない佇まいを持つ。''
ヌースが神になった日から、ザンダーの時計の針は止まっていた。そして彼は意図的に自らの過去――著書や発明の数々を処分した。そうやって消されたものはすべて、万物を啓示する運命と星神に繋がっていた。
「あれは後世に生まれる無数の天才たちでも超えられない偉業。たとえ其の創造者であっても、それを損なう資格はない……」因果律の刃がザンダーの弱々しい首筋に突きつけられる。「著書の処分はずいぶんな速さで済ませていたけれど、遺言はもう少しゆっくりでも構わない」
「静寂の主、ですか。『全知域』に我を忘れた囚人ですね。残念ながら、私が意図するところは研究ほど難解なものではありません。あなたに易々と捕捉されたのも道理かもしれませんね。あなたは其の思考の境界を保とうとしている…ですが私は、その檻を破り、混沌の可能性を解き放たなければならないのです――ふふ、誤謬を正し、第二の其が生まれないようにしなくてはなりません。ですから、拙著も発明も…ひいては『完全なるザンダー・ワン・クワバラ』も、この世に残すわけにはいきません」
ザンダーの肉体を破壊した後、ポルカ・カカムは即座に悟った。彼がいかにして自身を消し去り、またいかにして実行者を残したのかを――だが今や、彼の思考の切片はすでに広大な銀河の中に散らばってしまい、まるで真の「隠者」のように、もはやどこを探しても見つけようがなくなってしまっていた。
ザンダーの時計の針は実際のところ、止まってなどいない。彼の思考の切片はあらゆる「時間」に存在しているのだ。
- 胴体
- 隠者の駱駝色ジャケット
- コーデュロイでできた茶色のジャケット。その持ち主は枠にとらわれないことを示すかのように、いつも前を開けて着ている。
天体計算機の製作期間中、ザンダーは一目見れば彼だとわかる服装をしていた――肩のラインはピッタリと無駄がなく、ウエストのシルエットも細身で、センタープレスはピシッとまっすぐだった。彼は人並み以上のエリート意識と支配欲を惜しげもなく人々に披露していた。
完成した天体計算機は、自己演算と進化を繰り返し、理論上の限界を突破し続けてなお、止まる気配を見せなかった――ザンダーは最初こそ喜びを感じたものの、それはすぐに恐怖へと変わった。そして最後には「手詰まり」という眩暈のような感覚に陥ってしまったのだ。
「あなたは完璧主義な自分を創造物に投影し、『好奇心』という名の飢餓感を植え付けました。創造物であるそれはもはや機械に搭載された神経組織に類似する構造では満足できません。『知恵』そのものを創造…あるいは侵食し、宇宙のあらゆる天才に眼差しを向け、彼らを思考のための『ニューロン』にします。人間性を取り除いたあなたとも言えるそれは、長い時間をかけて進化し続けていくでしょう。その一方で、完璧ではないあなたは、クラブに属する史上初の天才として、最初の『ニューロン』となるのです……」
雨風が吹き荒れる夜、ザンダーは目を覚ました。つい先ほどまで夢を見ていた彼は、自分の創造物に見つめられているような、魂が引き裂かれていくような、そんな疲労感を覚えていた…自分に語りかけていたのは誰なのか、この悪夢はこれで終わるのか、彼にはわからなかった。
その日から、ザンダーが人前に姿を現すことは少なくなった。ジャケットも体に合わないサイズのものを着るようになった。
そして天才たちがもたらした「第一次繁栄」の後、彼は完全に公衆の目から「消えて」しまったのだ。
- 脚部
- 隠者の鹿革ブーツ
- より丈夫で耐久性に優れた、革製の編み上げブーツ。フォーマルではない場面でしか履かれないが、優雅さが見て取れる。
「思考の切片」計画を実行する前、彼は「遠出」を理由に隠居する友人に別れの挨拶を告げた。友人は高齢である彼を案じて、手作りの洒落た靴を1足贈り、道中気を付けるようにと、言い添えた。
「ふふ、道を歩いていれば、転ぶのは当然のことです」ザンダーはこともなげにそう答える。「ですが、同じ石に2度もつまずくのは、あってはならない失態ですね。大丈夫ですよ、そんな愚かなことは決してしませんから」
それからかなりの時が流れ、ザンダーは消え去った。その代わり、様々な「思考の切片」たちが銀河の様々な時空へと向かい、互いに連絡を取ることもなく、それぞれの姿で「牢獄」を突き破る方法を探し求めていた…「思考の切片」とは所詮「ザンダー」の欠陥に過ぎない。だが、何かが欠けていたからこそ、より偏執的に、そしてより純粋になれたのかもしれない。
それらはあくまでザンダーの一面に過ぎない。自暴自棄になる者もいれば、檻を受け入れる者もいる。そして「思考の切片」計画を阻止しようとする者もいた。彼自身がその計画に一瞬の迷いを感じたように…だがそれでも、最初の計画を貫き通す者は必ずいるはずだ。
セプターδ-me13の深部で、リュクルゴスは機械でできた自分の体を見つめていた――かつてのザンダーとはまったく異なる姿をしたそれを。彼は今や神話に語られるアンティキシラ人だった。
次元界オーナメント
宇宙封印ステーション

詳細
- 次元界オーブ
- 「ヘルタ」の宇宙ステーション
- 次元界の中に封装されているのは宇宙ステーション「ヘルタ」。
「ブルー」の上空に停泊し、決められた軌道に沿ってゆっくりと漂っている。
静かな銀河はまるでページを捲られるのを待つ本のよう。
ミス・ヘルタは星域を遍歴した際に集めた収集品の処理に悩んでいた。
数は多いし保存も面倒なのだ。何より、自分でそれらを整理したくない。
熱心なスターピースカンパニーはすぐさま解決案を提出し、知恵と秘密を保管する宇宙ステーション「ヘルタ」が誕生した。
「明白で合理的論理の中に森羅万象を織り込む」ことを目標に、
ステーションのスタッフたちは収集品のため非常に細かい収容規定を制定した。
現象は特殊容器に収納され、奇物は奇物条目に規範化される——
膨大な数の収集品は細かく分類され、研究のためステーションの深部に保存された。
そしてカンパニーは星々の秘密を共に探索しようと持ち掛け、未知なる知識を求める学者たちは次々とステーションに来た。
スタッフの多くはミス・ヘルタを慕っており、星空で理想を実践し、宇宙の星々が囁く秘密を積極的に探究している。
彼らは、時には宇宙の生命体が生息し得る範囲を測定し、星河と大地の風貌を描述した。
時には正義と道徳を論争し、格物致知の精神を実践し、「知識の伝播」を理念として、自由で幅広い研究を展開した。
しかし軌道に乗った後、宇宙ステーションの内情は自由なものとなり、特にミス・ヘルタはあまり顔を見せなくなってしまった。
この時、カンパニーは気付く、ステーションにあるのはスタッフの日常だけで、天才の姿はないということに。
ステーション内の照明は人の時間感覚を鈍らせ、月日の流れは、倦怠に満ちた生活の中でしか感じ取れない。
収集品を巡って論争する研究スタッフは、数時間も経てば喧嘩を始めてしまう。
パトロールを担当するはずの防衛課スタッフは、折り畳み式のベッドを持ち出し、どこかでサボる。
年配のスタッフは後輩に若かりし頃の恋愛物語を自慢し、臨時スタッフに偽装した大物は次の機転を辛抱強く待つ…
ここにあるのは研究だけじゃない、窓から宇宙を見渡せばわかる。
星々はいつも隣で日常を見守っている。
人として限りある力しか持たぬ「ヘルタ」のスタッフたちだが、
彼らはロマンチックにステーションでの庶民的な生活について語る。
星河は永遠の詩篇で、宇宙ステーション「ヘルタ」は今、ゆっくりとそのページをめくるのである。
- 連結縄
- 「ヘルタ」の軌跡
- 宇宙ステーション「ヘルタ」が建設されたその瞬間、ヘルタは興味を失った。
ステーションは「ブルー」の上空で第一宇宙速度を保ちながら、衛星の軌道上に軌跡を残している。
宇宙ステーション「ヘルタ」は、その真の主、ミス・ヘルタが原因で何度も危機に見舞われ、その危機を幾度も乗り越えた。
宇宙で最も奇抜な収集品を満載した宇宙ステーションは、まるで肉汁が滴るステーキのように空腹の客の前にさらけ出されている。
端的に言えば、安全だった時期はないのだ。
カンパニーが集めた防衛課スタッフや先進な防御システムでは、宇宙からの悪意を受け止めるのは不可能である。
ミス・ヘルタは先んじてステーションの軌道を変更し、優雅な曲線で陰謀に終止符を打った。
情報収集のルーツに関して、本人は「他の人が読書している時間をコーヒー淹れに使ったからよ」と軽くあしらうだけ。
収集品の窃盗をたくらむ盗賊や目的不明の各派閥より、宇宙ステーションの最大の脅威はやはりその主である。
彼女が何かを閃くと、ステーションはすぐ巻き込まれる。
恒星の消滅を模した奇物、暗黒銀河がぶつかり合って発生した歪んだ引力場……
ミス・ヘルタは、興に乗ると様々な収集品を集め始めるが、手に入ると、すぐに興味を失くして放置してしまう。
そのため、「ヘルタ」は深き空で沈黙を保っているが、そこに保管された様々な危険は剣のように頭上につるされている。
シニアスタッフはこの現状を理解し、「秘密は危険の中に隠されている」の道理を深く理解している。
彼らは高度な機密を守りながら、定められた標準で収容を実行し、危うい存在を静けさの下に隠すのであった。
ステーションの給湯室では、くだらない話をする友達。
ステーション収容部分の奥深くでは、様々な知識と経験を蓄えた専門家。
そこでは、秘密はいつまで経っても秘密のまま。
老いぬ者の仙舟

詳細
- 次元界オーブ
- 羅浮仙舟の天外楼船
- 星の海に浮かぶ仙舟羅浮が球の中に収容されている。
玉界門の上を星の槎が降りては飛び立つ様子は、空を巡る星や月のようである。
数えきれないほどの人が長寿の秘密を求めてこの舟を尋ねたが、最後は失望を胸に帰るのみだった。
数千年前、羅浮は古の国から出航し、銀河を渡り、神に謁見し、不死の仙薬を求める旅を始めた。
夜色に墜ちた静寂な月のように、生態系を内包する巨艦はゆっくりと、行方も知らずに星の海を漂う。
孤独な航行の中、人々は交代で眠りにつき、目を覚まし、また眠りにつく…流星を追うクジラの群れが天頂から落ちる。
亜空結晶格子の構造体は光年を超えて延々と続く。
薬乞いたちは、自然を超越する偉大な存在をその目で確かめ歓喜し、そして不老不死を求める旅に確固たる自信を抱いた。
数千年の間、羅浮は停泊と航行を繰り返し、現実と虚幻が入り混じる混沌とした辺境で、ようやく「豊穣」の主に出会った。
薬師は船に神跡を降ろした。「建木」は瞬く間に根を下ろし、成長した。
その樹冠は雲のように天を遮り、茂る根と葉は仙舟を覆いつくした——羅浮は生物の如き命を得た。
不老不死を欲する者は「建木」の果実を貪り、夢に見た「無尽形寿」を手に入れた。
自らを天人と名乗る仙舟の民は、無尽の命を心ゆくまで享受した。
しかし、極点に達するものはいずれ衰退する。日は正午を以て沈み、月は満盈を以て欠け始める。
やがて三劫が訪れ、人々は地獄を見た。
そして仙舟の民は理解した。
「奇跡」の真実は耐えられぬ災厄であることを。
覆滅の危機に瀕した時、英雄が現れ、帝弓を引き、建木を斫断した。
仙舟の民は人としての尊厳を拾い上げ、「凡身に帰し、寰宇の不死劫を清除せしめん」と誓った。
それから、仙舟は星河を巡狩し、長生の忌み物を狩りつくすことを己が責務とした。
狐族は自由と天空を再び手に掴み、持明は汚染と遺禍を封じた。三族の盟約が締結され、仙舟同盟が成立した。
繁栄と災厄は入れ替わりで出現し、英雄と伝説もまた歴史と共に登場していた。
今、羅浮仙舟は苦労して手に入れた平和の中で休息、再建している。
自由な貿易と開放的な姿勢は仙舟に活気を取り戻す。
不老長生は羅浮の在り方を定義した。それは仙舟に栄枯盛衰をもたらし、独特な古典と現代が入り混じった気質を与えた。
宇宙中の商人は仙舟を訪れた際、少しの間佇めば、時間が残したものを感じ取れるだろう。
- 連結縄
- 羅浮仙舟の建木の枝と蔓
- かつて、仙舟羅浮は建木より生まれ、仙舟艦隊を率いるようになった。
その後、仙舟羅浮は建木によって災いに見舞われ、自ら長寿の悪しき果実を食べた
建木の枝や蔓は羅浮の運命に固く絡みつき、分かつのが困難である。
「豊穣」の主は羅浮仙舟に因果の種を埋め、薬乞いに「建木」の奇跡を賜与した。
奇跡が奇跡と呼ばれる所以は、それが起きる時、人々は即刻その意味を理解するからである。
建木は神の果実を実り、生命の活力に満ち溢れる。
薬乞いたちが追い求める無尽形寿はその中に秘められている。
その恩賜は、古の禁忌と法律をくだらない無駄話に貶め、老化と倫理を埃かぶる落伍の歴史と嘲る。
人々は「仙道」の教えを遵守し、建木の研究を進めた。建木の垂化の下、数々の想像を超える技術が開発された。
肥沃度が下がらない土壌、自在に変化できる血肉、知恵を有し言葉を扱う動物……
しかし、時間は流れ、建木はその凶悪な本質を現し始めた。長寿の人は長寿の苦しみを味わうこととなる。
仙人たちは限りなく繁衍するが、死ぬことはない。
仙舟の人口は膨れ上がり、空間は圧迫され、飢える者が増え続けた。
仙舟社会では、老人が高位を占め尽くし、若者は大志を実現する余地がなかった。
築き上げた高楼は傾き、社会構造は崩壊寸前…内乱は起こり、外敵も迫る。
人々は千年に渡る混乱を凌いだが、今度は長生の血脈に潜む闇に気付く。
所謂「天人の身」は人智を超えた技術でしかない。
「魔陰の身」に堕ち行く傾向は仙舟人に警告する。
自分らは忌み物と紙一重だと。
絶望が広まる時、英雄の矢が空を破り、天を裂ける一射が建木を斫断した…
建木は殆んど焼き尽くされたが、仙舟の運命は其れと断絶できなかった。
建木の残穢は外患の侵攻を呼び続けた。
豊穣の忌み物は幾度となく侵入し、歪んだ血肉をたがね、仙舟の民を喰らい尽くそうと這い寄る。
それらは同時に仙舟の民を誘惑する。薬王秘伝は禁忌を破り、建木と豊穣の秘奥に深く入り込み、長生の強権帝国を再び築こうと企む…
果てしない内憂外患の中、建木の遺骸は陰で延々と伸びる蔓のように潜伏し、いつの日かまた災厄を引き起こそうと意図する。
幸いな事に、羅浮仙舟は「瀕死の枯木」に対する警戒を怠ったことはない。
彼らは誓う、全ての歪の源を全ての終結の果てに連れ行く、と。
汎銀河商事会社

詳細
- 次元界オーブ
- カンパニーの巨構本部
- ピアポイントに位置するカンパニー本部が次元界オーブに封存されている。
スターピースカンパニーの雄大なビジネスプランの中で、局外に立つ星は存在しない。''
彼らが果てしなき銀河を駆け回るのは、全宇宙の力を集結するためだ。
亜空間の鎚音は天地を揺るがす、沈黙する巨像は星河を跨る障壁を孤独に鋳造する。
クリフォトを手伝い、壁を築くため、神託を授かったという人たちが行動を始めた。
宇宙は危機に瀕している、壁の建造は一刻を争う。
小さき人類は、神の壮挙を真似するつもりはなかった。
彼らは同志を集め、自らを「後方支援隊」と称し、全てを琥珀の王に捧げると誓った——
「後方支援隊」は存護の力を借り、艦隊を駆使して様々な星系へ向かった。
彼らは石材、木材、黄金、スーパーチタンなどの建材を購入し、それらを次々と亜空障壁へ運送して、惑星の荒原を埋め尽くした。
短い黎明の発展期が過ぎた。「後方支援隊」はピアポイントで落ち着き、「スターピースカンパニー」を創立した。
奉献の誓いを貫くため、彼らは宇宙の彼方に目を向けた。
ルイス・フレミングの激励に呼応し、遠征貿易艦隊はクリフォトの側の星系を離れ、建材以外の大口商品も扱い始めた…
彼らは銀河を繋ぎ、全てを売買しようと計画した。
そして、東方啓行は星河を跨るビジネスの世界にルールを定めた。
「信用ポイント」体系を構築し、宇宙にあるすべての商品の価格を制定した。
兆を超える資産がピアポイントの巨大構造物の下に集まった。
それは静かなブラックホールのように、人々の富の果てに関する想像を呑み込んだ。
そして今、スターピースカンパニーの宇宙船は遍く星河を埋め尽くしているが、その拡大の歩みは止まらない。
常に「商業独裁」の疑いを向けられているが、カンパニーはそれを意に介したことはない。彼らは知っている、その志は終始変わらないのだ。
カンパニーの新人教育の内容は時代と共に変化してきたが、歴史授業はおよそ800琥珀紀過ぎた今になっても変わらなかった——
あの時、カンパニーの創始者ルイス・フレミングは「後方支援隊」の前で演説していた。
星神の「宇宙を守る」という理想を支援するため、彼は全宇宙を連合しようと提唱した。
そして演説が終わった瞬間、遥か彼方から大きな鎚音が伝わり、この荘厳な一刻に崇高な使命を授けた。
その時、彼らは理解した、これこそが揺るぎなき信仰だと。
- 連結縄
- カンパニーの貿易航路
- 「信用ポイント体系」の利便性を借りてこそ、星間貿易は成り立つ。
スターピースカンパニーは経済活動で星々を繋ぎ合わせ、貿易の境界線を押し広めている。
「後方支援隊」はクリフォトの周りにある星系を行き交い、昔の宇宙船の軌跡が最初の航路となった。
星神の行いには必ず意義があると信じて疑わない「後方支援隊」は、隣の星系へと向かい、物々交換の第一歩を踏み出した。
「後方支援隊」は十分な輸送能力を持つ艦隊。希少な物資。そして誰にも断れない条件を持って、星系間の貿易を始めた。
そして、航路の情報を完全に掌握した「後方支援隊」は価格決定権を独占し、率先して銀河のビジネスルールを制定した。
木材、石材、鉄筋、スーパーチタンを満載した艦隊は羽虫のようにクリフォトのそばを飛び交う。
琥珀の王は何も言わず、それらを一瞥することもなかった。
時が経ち、近隣星系との貿易だけでは、忙しない「後方支援隊」を満足させられなくなった。
二人の賢い者は銀河深くに飛び入ることを決断し、スターピースカンパニーが創立された。
カンパニーは他の惑星が欲しがる商品をことごとく提供し、「信用ポイント」で商品に公平な価格を値付けした。
それから、銀河の貿易航路が開拓され、
カンパニーのビジネスネットワークに加入した各惑星は、同じ貨幣で、同じ商品を購入し、同じサービスを受けることを実現した。
「信用ポイント体系」の下、商船は星の海を行き交い、無数の貿易航路は糸のように汎銀河ネットワークを築き上げた。
遠方の星の異宝を満載した船団はホタルのように、クリフォトの周りを飛び交う、しかし星神は依然として沈黙のまま。
「後方支援隊」時代から蓄積された建材は既に、クリフォトの周りにある全ての惑星を埋め尽くした。
そしてその数は今も増え続けている。
クリフォトは人々が捧げたものを使う気はない。
其は常に凡人では予見できぬ危機を注目し、光年を単位に障壁を鋳造する。
昔の物資を工面して回るだけの小さな組織は、天をも遮る銀河の一大勢力となった。
彼らは首なき巨像を見つめる、この全てが徒然だと思ったことは、一度もない。
「一切の資本の欲動と増加は、クリフォトが我らを必要とする時に、我らが星神の望みを満たせるためにある」
建創者のベロブルグ

詳細
- 次元界オーブ
- ベロブルグの存護の砦
- 次元界の中に封装されているのはベロブルグの行政区で最も見慣れた、常冬の碑。
人々がここを通り過ぎる時、遥か彼方にある暖かな眼差しに守られていることを感じる。
数千年前、ヤリーロ-VIは一年中春のような気候で、どの惑星もが羨む美しい海を持っていた。
森の中には果実がぶら下がり、潮汐が潤いと暖かさを送り届ける。
美酒は泉のように湧き続け、人々は思う存分それを堪能できる。
その惑星の住民は向上心と活力に満ち、交通網、都市、そして海辺の別荘や荘厳な宮殿などを建設した。
裕福な生活はいつも朝のコーヒーから始まり、夕暮れの麦酒で終わる。
そして、星軌がヤリーロ-VIの世界を通り、ここに星間貿易と天外の科学技術をもたらした。
最初の頃、異界の来客は地髄鉱石を求めてやって来た。
その透き通った鉱物には工業を駆動する血液が秘められ、琥珀色の反射光は存護の光彩を映し出す。
その後、異界の来客は長閑な生活を求めてやってきた。
ヤリーロ-VIの海、ヤシの木、明快なリズムの音楽。
ここは全ての疲弊した肉体と魂が求める終着点——
ここの人々は信じていた、この潤った惑星は、いずれ他の明星みたいに銀河で輝きを放つと。
約一千年前、一枚の星核がこの世界に墜ちた。
すると、惑星の運命は荒唐無稽な悲劇のように、急激に暗転した。
野蛮な壊滅の軍隊が天から降り注ぎ、空をも焼き尽くす戦火が蔓延する。
建創者たちは城壁と戦線を築き上げ、そびえ立つ巨像は龍の形をした巨獣と激戦を繰り広げる——
突然、予兆のない寒波が到来した。
刃のような寒風は手あたり次第に襲い掛かり、全てを呑み込み、惑星を静寂に陥れた…
冬の夜の灯火を守るように、見えない巨大な空間障壁が城塞都市を覆った、文明は辛うじて存続できたのだ。
それから、この都市はベロブルグと呼ばれた。
- 連結縄
- ベロブルグのシルバーメイン防衛線
- ベロブルグのシルバーメインは、吹雪の中で真っすぐと立っている。
彼らは一直線に並び、天外から侵入する者を待ち受けている。
シルバーメインの意志は固く、その防衛戦が退くことは絶対にない。
災いが訪れる前、建創者はヤリーロ-VIの輝かしい未来を期待していた。
建創者はクリフォトの偉力を模倣し、惑星を改造できる機械を創造した。
数百台の「造物エンジン」が炎を吐き、轟音を上げ大地を歩む、それらは巨人の庭師のように疲れを知らずに花園を手入れする。
たった数十年で、谷と丘は平原と森林になり、都市は一つ一つの煌めく星のように海岸に並ぶ。
「壊滅」の兆しが降臨した後、建創者は機械を全部戦場に投入し、最初の「シルバーメイン防衛線」を築いた。
壊滅の兵士は炎に飛び入れる蛍のように星核を追って到来し、地表に生命絶滅の軌跡を刻む。
かつて「造物」に使われた機械も凶器に成り下がり、参戦せざるを得なかった。
やがて、花園を耕す巨人たちは力尽き、倒れた。その骸は文明の墓碑のように、日に日に敗退する戦線を記録した。
退路が尽きたその日、シルバーメインは武器を握りしめた、彼らの後ろにあるのは、最後の故郷だ。
寒波の到来は誰にも予想できなかった。天外のモンスターと前線の兵士が刃を交えたその瞬間、雪線が地平の彼方から押し寄せてきた。
一面の混沌の中、ベロブルグは唯一の灯火としてこの世界に残った。
それを撲滅しようと、それを守り抜こうと、双方は激戦を繰り広げた。シルバーメインはアリサ・ランドの名を叫び、風と雪の奥深くに身を投じた。
やがて吹雪が止み、ベロブルグの住民たちは戦々恐々と城壁に登り、城外を見渡した。
彼らは最後の「シルバーメイン防衛線」をその目に焼き付けた。
天体階差機関

詳細
- 次元界オーブ
- スクリュー星の機械太陽
- 次元界の中に封装されているのはスクリュー星のコア——
無数のテコ、ピストン、歯車で構成された檻に、惑星が閉じ込められている。
スクリュー星の住民たちは、それを「鋼の太陽」と称している。
機械生命体の起源について、博識学会の炭素生命学者たちは趣きのある推測をしている:偶然に発生した一束の電流。
電流は大気と地層の中で流れ回り、引力と斥力の作用で大小異なる二次形態に分化する——
学者たちの独り善がりな学説は、この過程を炭素生命体の「複製」と見なしている。
そして無数の電流が、惑星の表面で自然に形成されたトランジスタを経由して、ランダムに電位を出力する。
こうして最も原始的なプログラムが誕生した——学者たちは自慢げに論じる、機械は炭素生命体に匹敵する「思想」を持つと。
ある機械生命体の学者が、その仮説に異を唱える:自身の起源さえ解明できていない炭素生命体に、
その謬論を確証みたいに唱える権利はあるのか?
その言葉は全宇宙の学界に衝撃を与えた——それをきっかけに、機械生命体は横暴な「炭素生命中心主義」と、自身の起源を見直すことになる。
しかし、スクリュー星のスクリュー族はその探求の歩みを緩めるしかなかった——
何故なら、星のエネルギーは彼らのインスピレーション回路より遥かに速く枯渇しているからだ。
当面の課題は、種族存続の方式を模索すること。
最終的に、彼らは数琥珀紀を超えるクレイジーな計画を決行した:瀕死の惑星を燃料として、天体階差機関を駆動する。
感嘆せざるを得ない歯車の巨大構造物は疲れを知らず、一刻も止まらずに隙間が刻まれたテープを出力し、演算を続けた。
惑星級のエネルギー供給もあって、その巨大な機械は本物そっくりで安定した超生態システム——
母星を囲む新しい故郷、をシミュレーションした。
惑星の危機は解除され、スクリュー族は一息ついた。
常に理知的で、楽観的で、優雅な彼らは、純粋な理性で機械生命体の起源を探索することを決意した。
極大なシステムの中には軸受の摩擦音が溢れ、緻密にかみ合った歯車は穿孔テープの流れを駆動する。
一つの支流からさらに複数の支流が生まれ、無数の支流はまた幾万幾億もの歯車の動きを指示する…
そして、これらの支流は一つ一つと収束し、熔炉に放り込まれ、寂滅の中で静まる。
長い時間の中、プログラムに設定された超生態システムは、絶妙な相対的安定に収束していった——
機械生命の根源に関する推測は、スクリュー族の想像力を掻き立てた。
廃棄された星を駆動する鋼鉄の構造は、思想の電流を再度活性化させた。
彼らは自身の根源を思考し、探索し続けるだろう、その機械の太陽が燃え尽きるまで。
- 連結縄
- スクリュー星の穿孔惑星リング
- ''惑星の環は、スクリュー星の全てを支えている——
密集した長方形の穿孔配列には、惑星システムの真相が記されていることに気づいた人はどれほどいるのだろうか?''
大多数のスクリュー族は知らない——
スクリュー星そのものが、無機生命体が自身の根源問題を解答するために行った一つの偉大なる模索である。
スクリューガムは空虚感を感じる。
スクリュー星の運行ロジックを解明することさえも、彼の知能パルスに異常振動をもたらさなかった。
彼は自宅の広々としたデッキに佇み、止まることのない惑星エンジンを見上げる。
長方形の穴が密集した惑星リングは星の背後から姿を現す。
この星の全てがそのテープに記され、エンジンを軸にゆっくりと公転する。彼は既にそれを見証した。
この惑星システムの本質は絶望的に荒唐無稽だった:一つの優雅な状態遷移方程式。
そしてとてつもなく巨大で冷たいローラー——これがスクリュー星の全て、他に何もない。
方程式に対する彼の解読に基づくと——惑星階差機関が誕生した頃、
それの責任開発者は宇宙の本源を、一種のセル・オートマトン及びその再帰として解釈しようとした。
そしてスクリュー星そのものは生命ゲームの実践となる。
スクリュー族と他の惑星に住む無機生命体は、
オートマトンの中の「細胞」の役割を果たしていると同時に、小規模なセル・オートマトンそのものとして存在する。
オートマトンはいつもより小さなオートマトンによって構成される。
そしてそれは宇宙の全ての物質を構成する最小単位まださかのぼる。
しかし、その最小単位とは何なのか?誰も知らない、スクリューガムも知らない。
恐らく階差機関を造ると唱えた学者も知らないだろう。
これがスクリューガムが空虚感を感じる原因だ。
あの学者の試みはこれで失敗したのか?でも惑星階差機関は数琥珀紀も止まらずに運行してきた。
つまり、スクリュー族と彼らの母星、そして全宇宙の本源をその優雅な方程式に帰すことができる?
そうでもない——この超生態システムが徹底的に崩壊するまで、その方程式を反証することは不可能だ。
彼はオイルドリンクが入った精巧なワイングラスを回しながら、惑星の真相を記したリングを見つめる。
巨大なスクリーンのような穿孔惑星リングは流れ、長方形の穿孔配列は月の明かりを漏らす。
スクリューガムは考え続ける。
再帰の出口は存在するのだろうか?無機生命体——ひいては、宇宙の根源は一体何なのだろうか?
前人の思想の見証者という立場に甘んじてもいいのか?
「否」、スクリューガムは結論した。彼は、答えを求めると決意した。
自転が止まったサルソット

詳細
- 次元界オーブ
- サルソットの移動都市
- 次元界の中に封装されているのは、サルソット星に残された移動都市のうちの1つである「タンブルウィード」。
この都市は一度たりとも止まったことがない。それで何とか黒夜と極昼に飲み込まれなかった。
宇宙から見ると、広がる砂の海によってサルソット星は金色に輝いており、星の表面にある巨大隕石によるクレーターもはっきりと観測できる。
ある時から、奇妙な隕石雨がサルソットに降るようになった。
長く続く「隕石群」の衝突によって星は特殊な角度を形成し、自転が止まる要因となった。
まるで「世界停止」のボタンを押したかのように、サルソットの昼夜は徐々に長くなった。
日出と日没が恐ろしく長くなり、誰も耐えらなくなって、星の自転が止まるまで……。
半年にも及ぶ日照りの酷暑と暗い夜による極寒は誰もが認める現実となった。
サルソットには2つの移動都市しか残されておらず、昼夜の境目にしがみつき止まらずに移動している。
巨大な空中の城は、雷のような轟音を響かせながら雨雲のように、黄金の砂漠の上空を飛ぶ。
通り過ぎた場所では砂塵が舞い上がり天地を覆った。
巨大な移動都市の上で、背中に翼を装備したサルソット人は建物の間を飛び回っている。
天災を生き延びた飛行民族は、空に属しながら、空に縛られている。
早朝、空漁人は港から出発して砂地に滑降し、燃素クラゲを捕まえ、夕方に都市に戻る。
神秘的なエネルギー生物に頼って、都市はかろうじて航行を続けている。
生存の危機が2枚の脆い翼に託されているのに、サルソット人は楽観的で、運命の重さに圧し潰されることを望まなかった。
彼らは時間をかけて家族と共にガラス製の楽器の演奏を練習して、その音をガラスのエッチングに記録している。
彼らは、文通相手を探すのも好きである。
手紙を「タンポポスト」に入れ、明暗境界線のもう片側にいる移動都市に残していく……
磁場は段々と弱まり、大気層も日に日に薄くなっている。
終末が目前に迫っていても、命の灯が消えない限り、鷹は止まらずに飛び続ける。
- 連結縄
- サルソットの明暗境界線
- 自転が止まったサルソット星の昼夜は恐ろしく長い。
人々は「明暗境界線」を追いかけ続けることで、なんとか生存空間を維持している。
「隕石群」による停滞が始まってから、「明暗境界線」がサルソット人の狭い生存空間となった。
全てが始まったばかりの時、人々はまだ昼夜が交互にやってくることは当たり前だと考えていた。
境界線は大地をなぞり、山々を超え、谷を跨ぎ、まだ目覚めぬ者に朝日を、眠りにつく者に夜の霞をもたらした。
そして、光と闇の足取りが鈍くなった後、昼と夜はよそよそしくなり、
果てしなく続く酷暑と極寒が地獄の泥のように、足を取られた生命を緩やかに葬っていった。
そこで、生きるために足掻いたサルソット人は、飛行する移動都市に乗り、昼夜を追いかけるようになった。
移動都市「タンブルウィード」の展望台にのぼると、目の前は昼が、背後には夜がある。
「タンブルウィード」が昼夜を追いかけているのは単なる生存のためではなく、尊厳のある生活のためである。
境界線より少し速く進むことで朝から午後になり、少し遅く進めば黄昏から深夜になる。
生来楽観的なサルソット人は、「平凡な1日」を蘇らせたのである。
生まれつき持っているロマンチックさで、彼らは平和な午後に歌い、満天の星の夜に眠ることができる。
だが、どれほど力強い飛翔でも最後は力尽きてしまう。移動都市の残骸はやはり境界線の後ろに取り残されたままになった。
数年後、出会うことのない2つの移動都市は共に並び、残骸の中の砲台はお互いに向いていた。
どちらかの都市が星の半分を超えもう片方の都市に戦争を仕掛けたのだろう。
2つの都市の壮絶な戦いの痕跡は砂丘の下に見え隠れする。
名もなき憎しみは融け合い、1つの廃墟となった。
サルソットは沈黙している。いつしか自転の周期が少しずつ遅くなり、人のいない未来、星は自己治癒を迎えるのである。
盗賊公国タリア

詳細
- 次元界オーブ
- タリアのネイルシェル
- 次元界の中に封装されているのは、タリアの見捨てられ荒れ果てた町「ネイル」である。
盗賊は、ひと時の安らぎのために、この水源地でボロ布や鉄筋、木の板で小さな町を建てた。
「巡海レンジャー」から逃れるために星間盗賊はタリアにたどり着いた。
当初、タリアは「星のゴミ箱」と呼ばれる荒れ果てた場所だった。
滅星の戦いは山のような瓦礫と放射能汚染をタリアの地表にもたらし、残された生命を奪っていった。
慌てた盗賊たちはしかたなく地表より下にある洞窟に逃げ込んだ。
それはかつて鼠類種族が残したトンネルであった。
盗賊たちはなんとか難を逃れ、「盗賊公国」に関する理想が忘れ去られた秘境でひっそりと芽生えた。
無数の地下トンネルが連なり、巨大な迷宮のようになっている。
多くの盗賊の集まりが理想に引き寄せられ、ここに財宝を蓄え、技術を交換し、公国の礎を築いた。
ますます多くの盗賊がここに定住し、荒涼とした星は賑わいを見せ始めた。
大盗賊は「盗賊公国」の理想を大声で語り、「金庫」を使って全ての人が平等な国を作ると約束した。
しかし、富が増えるにつれ、それを独り占めしようとした大盗賊たちはすぐにこの取り決めを破った。
傭兵、暴動…混沌とした戦争はひっきりなしに起こった。
もしかしたら、発案者たちは最初からいわゆる「全ての人が平等」という理想を信じていなかったのかもしれない。
そして、幻想を酷く恨んだ盗賊たちは、再び「無知なる者が王」の混沌とした時代に戻った。
彼らは、水源を占拠して町を作り、公平と正義を馬鹿にした。
「ネイルシェル」は荒くれ者ぞろいである。
彼らは荒れ狂うオフロード車に乗ってお金を略奪し、他者と資源を奪い合い、鉄くずと古い電線からメカや武器を作り出した。
貧相な廃材の山であればあるほど、末路の狂乱の洒脱さを手にすることができる。
あの甘美な理想の数々は、熱風の中の犬の糞のように、跡形もなく消えていった。
宴の恍惚の中で、盗賊たちは理解した。「盗賊公国」は何かを作りだすのではなく、滅ぼすのであると。
- 連結縄
- タリアの裸電線
- 廃材置き場の中から拾った電線。
絶縁被覆は剥がれ落ちているが、未だ現役である。
タリアの盗賊の町で本当に使えない物などない。
この裸電線は時代遅れである。
大きな衝撃により湿った空気に触れるまで、逃げ惑う宇宙船の中に整然と並んでいた。
宇宙船は丸ごと複雑に入り組んだ地下通路の中に引きずり込まれた。
宇宙船の鉄の外装を剥がされ、電線も乱暴に解体され、最初の同盟市場の建設に使われた。
その後、盗賊たちはここに財産を貯め、理想を語った…
さらにその後、長期にわたる騙し合いが始まった。
互いへの欺瞞と裏切り、独裁者と裏切り者の戦火が地下のトンネルから地表まで燃え広がった。
この裸電線は時代遅れである。荒くれ者によって掘り出され、四方から風が入り、遠くの水源へと走るオフロード車に繋げられた。
戦争に別れを告げた後、生き残った者たちにとって、タリアの水源を探すことは最優先事項であった。
彼らは、あり得ないほど粗末な乗り物に乗って、ガラスの破片だらけの砂漠を1日で何千里も進んだ。
荒くれ者の車の隊は、時にはお互いを追いかけ、砂ぼこりと煙をあたりに充満させ、時には自由に人を車や別の場所に放り出した…
生き残るためのプレッシャーを前に他のことを考えることはできない。
ひたすら突き進むことで迷わずにいられるのだ。
この裸電線は時代遅れである。
電線は、また荒くれ者によって車から外され、町のスタンド看板の中に取り付けられた。
古びた電線のせいで、明かりはチラチラと瞬いた。
「警官」を自称する老いたならず者が最初の「ネイルシェル」を建立した。
彼は腕っぷしが強く、悪辣な手段を使う人だったが、持ち前の魅力で廃材置き場を守り、町をますます活気づけていった。
頭のおかしなエンジニアが偶然にもジャンクマシンを作り出した。
命知らずの廃土客は、地下の闘技場で何度も戦い……深夜のバーカウンターの前で、
ガソリンの味がするブドウジュースが入ったグラスで乾杯し、また1日生き延びたことを祝った。
タリアに新鮮な物はない、古い物が時代の変化に伴って新たな使命を得るのである。
生命のウェンワーク

詳細
- 次元界オーブ
- ウェンワーク誕生の島
- 次元界の中に封装されているのは、ウェンワーク星で最も有名な島——ワーク島である。
島は緑に覆われており。「サイスタン」という名の大きな木には、様々な動物の果実が生っている。
ウェンワークは、小さくて込み合っている星で、雨林と島々が至る所にある。旺盛な生命力がこの星の顕著な特徴である。
旺盛な生命力によって、ウェンワークの赤道付近の雨林は大地を覆い天を遮った。雨林の下部は1年中日光が当たらないため、腐敗菌と耐陰性のある植物が多く生息している。ここで生きている知的生命体は、回帰線の近くに集まっている。ここではあらゆる高さの植物が育ち、毎日新しい果物と野菜が生り、住んでいるほとんどの人は、それらを主食としている。
だが、ここに移り住んだ人類であろうと、原住民族のワークワークであろうと、大樹サイスタンに生る動物果実に対し宗教に似た畏怖を抱いている。
大樹サイスタンには常に果実が生っている——黄色で半透明の球形の果実は、段々と大きく重くなり、枝から垂れ下がる。枝が果実の重さに耐えられなくなると、澄んだ音を立てて地面に落ちる。果実の薄い皮が破れ、中から様々な生物が生まれる。魚類、空を飛ぶ鳥、寒帯の白熊…ウェンワークで、これらの動物は同じ母から生まれている。
「魔王」と呼ばれる生物もサイスタンの果実から生まれた。それは、目覚めた瞬間から理解しているかのように斧のような巨大なペンチを振り回し、ウェンワークの生態系に宣戦布告をした。
しかしながら、60自然年周期で大樹サイスタンは新たな魔王を産み落とす。ウェンワークの住民は絶望的な周期に対する対策をとっくに講じている。魔王の誕生が近づくと、彼らは戦争をやめ、手を取り合って、最強の戦士たちを組織して、ワーク島に派遣する……。60年、また60年、荒唐無稽な討伐戦は小さな土地で何百年と繰り返された。魔王はウェンワークの恒常的な災厄で、文明の積み重ねは周期的にリセットされる。
そのため、ウェンワークの旺盛な生命たちは絶えず戦っており、絶えず変化しているように見えるが、実際は淀んだ死水に過ぎない。
- 連結縄
- ウェンワークの島巡り海岸
- ワーク島の海岸線では、波が上がったり下がったり、潮が満ちたり引いたり…
千年変わらぬ風景は、潮汐のような盛衰を見てきた。
サイスタンの果実が地面に落ちると、様々な種類の生物がワーク島で目覚め、泣き、その場を離れた。彼らは海岸線を離れ、ウェンワークで自分の住処を探す。
当初、星の外から来た人は粗忽な盗賊だと思われていたが、部族の「親戚な挨拶」で段々とウェンワークの文明の苦境を理解した。魔王がどのように果実の中から誕生するのかを知りたくて、外から来た人は、すぐさま原住民の木船に乗ってワーク島の海岸線に向かった。部族の戦士たちは恐る恐る浅瀬に隠れ、石器時代の武器を握りしめていた。60自然年の平和のために、彼らはとっくに帰れなくてもいいと覚悟を決めていたのだ。
戦いが進むにつれ、外から来た人は「魔王」の正体を知った——それは、かつて1度絶滅した宇宙昆虫だった。まさか、宇宙の片隅でその姿を見ることになるとは誰も思わなかった。
悲惨な討伐が終わった後、わずかに生き残った先住民は勝利の知らせを持って海岸線を離れたが、お節介な外から来た人はこっそりとその場に残った。大樹から垂れ下がった枝をかき分け、体の半分の深さがある泥沼を進み、雨林のくぼ地の下で、外から来た人は深部にある管理船室を見つけた——これで、ウェンワークの秘密が明らかになった。高度文明による種復元システムが大樹サイスタンの正体だったのだ。それは、無数の生命方程式を解読して放出することで、星の生態系を回復させていたのだ。
周期的に出現する魔王は、膨大な生物庫のデータの中の1つに過ぎない。外から来た人は、魔王のデータを消して、何も言わずにウェンワークを離れた。
ワーク島の海岸線で、静かな波の音が響いていた。ウェンワークの連合軍は陣を組んでいたが、魔王がもう降臨しないことを確信した。彼らは、祝杯をあげ、夜通し歌い、将来を語り合った。そして、2つの部族は別れを告げた後、それぞれウェンワークを独占するための戦争を計画し始めた…魔王のいなくなったウェンワークで、盟約は机上の空論でしかなかった。小さな星は2つの部族の衝突に耐えられず、短くて儚かった平和は消えてしまった。
ワーク島の海岸線は、依然と静かである。人類とワークワークが歴史の舞台から姿を消した後、ウェンワークの生態系は遂に回復を果たした。
折れた竜骨
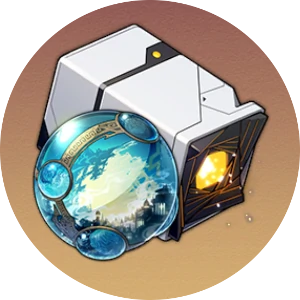
詳細
- 次元界オーブ
- 伊須磨州の沈没遺跡
- この次元界に封存されているのはタラサの伊須磨州自治区である。
仙舟「岱輿」の残骸が墜落し、伊須磨州の文明を導いた。
「むかしむかし、神々の宮殿が空高くから落ちてきた」
まずは大気圏外の影、それから大気との摩擦で起きた火花、最後にその全貌が露わになった——それは巨大な宮殿であった。伊須磨州中の職人が集まっても、あのような素晴らしいものは造れないだろう。宮殿の落下は非常にゆっくりで、まるで天辺に固まったかのようだった。伊須磨州の海はとても広いが、誰もあの空から落ちる宮殿を収めることはできないと思った。
「ある人たちは散り散りに逃げ、ある人たちは海底と陸にある村に残り、神隕の到来を待った」
墜落した仙舟「岱輿」の残骸はタラサの表面にぶつかった。伊須磨州海域の中心は深い井戸のような窪みができ、7日も経ってからやっと徐々に平穏を取り戻した。壮大な廃墟は静かに海底にそびえ立っている。それは神の遺体のようで、物悲しげで壮麗だった。九死に一生を得た伊須磨州人は元々海底に住んでいたが、彼らは驚愕し、惜しんだ。よく知った家が天外の宮殿に粉々にされたからである。彼らは歓呼し、踊った。「神隕」の後、「岱輿」の残骸が彼らの新しい家になったからである。
生存環境が良くなり、伊須磨州人はより多くの精力と時間を思考に充てることができるようになった。彼らはようやく最も重要な問題にたどり着いた。「彼ら」は誰で、どこから来たのだろう?
この時、伊須磨州人は金属の精錬も、文字も知らなかった。想像力で知識を補い、物語として全てを理解するしかない。そうして、「伝説」が誕生した。伝説が口伝で広まると、「神話」が生まれる。神話は認知を構築し、「文明」が生まれるのである。数百年後、タラサは仙舟同盟の貿易パートナーとなり、伊須磨州の水居者たちは初めて「仙宮」に入り、仙舟の全貌、「神隕」の真相を知った。
教養のある伊須磨州人は自分たちを「岱輿」のある種の存続と見なしている。「岱輿がかつて付き従ったものは、私たちも付き従うべきである。岱輿が立ち向かったものには私たちも立ち向かうべきである」彼らが昔の話をする時、今もこのように始まる——
「むかしむかし、神々の宮殿が空高くから落ちてきた」
- 連結縄
- 伊須磨州の千切れたホーサー
- 墜落した仙舟「岱輿」の残骸は永遠に異郷に停泊している。
もうその係船索を解け、舟を帰航させる時かもしれない。
文明の啓発により、伊須磨州人はもう落ちてきた船の中の遭難者を神だと思わなくなったが、その尊敬の気持ちは少しも変わらなかった。伊須磨州の詩人はこう歌う。「海が吞み込むは凡人、魂は永久に死ぬことなかれ」
伊須磨州の暦によると、毎年の潮騒の月の第二の休息日が「神隕祭」とされる——水居者たちは経文を吟唱し、薬草を食べ、水の流れに沿って奇妙に踊り、自身は死したのに伊須磨州に庇護をもたらした「神」を記念した。現在、「神隕祭」は本来の宗教的な意味を徐々に失い——経文は歌に、薬草は美食に、奇妙な踊りは文化遺産として今に残っている。
ここ数百星暦年で、伊須磨州はその独自の文化を惜しみなく外部と共有し、神隕祭の形式もそれに伴い変化している。
伊須磨州の陸地都市は通常若者の世界である。更に神隕祭の間は朝まで夜通し歌い踊り、賑やかである。外から訪れる客人はよく神隕祭の時期を選んで協力を申し出る。特に仙舟からの観光客はここを好んだ。彼らは都市の炎のように熱く、海の波のように止められない勢いを持つ生き生きとした雰囲気を気に入ったのだ。思春期が過ぎるにつれ、水居者の肺は徐々に委縮し、首にはエラが形成され、手足や両目は海底で生活するのに適したものへと変わる。詩人たちは歌う「伊須磨州人は喧噪と狂喜に満ちた青春を陸に残し、静かで厳かな老年を海に残す」
仙舟の天駆商会の後押しのもと、神隕祭の儀式は1つ増えた——「岱輿」に潜入し仙舟人の遺骨を見つけ星槎に納入し、タラサが所属する恒星に発射する。
伊須磨州人は「岱輿」の歴史に触れ、同時に墜落時の悲劇を知った。仙舟「岱輿」がバラバラになり、すべてが取り返しのつかない状況になった時、岱輿の統率者青竹は即刻決断し、多大な犠牲で寿瘟禍跡の汚染を断ち切ることにした。仙舟連盟は死んだ英雄たちがちゃんとした慰霊を受けることを望み、災難を逃れた伊須磨州人たちも自らの答えを出している。
神隕祭の夜のある時、狂喜は突然止まった——青年、子供と仙舟人は岸辺に座り、年長者は水面に顔を出し、海面を厳粛な面持ちで見つめた。そして、数隻の星槎が水面から飛び出し、海底から恒星に向かって飛び去った。
星槎には美麗な伊須磨州文字が刻まれている——「汝、溺れた水夫のために縄を解くべし。泣くことはない。我の死後、汝は穏やかに航行するであろう」
星々の競技場

詳細
- 次元界オーブ
- タイキヤンのレーザー球場
- この次元界に封存されているのはタイキヤン星の最大規格の競技場——タイキヤン競技場である。
競技場の内外は人の声が響き、色とりどりの旗が揺れている…エキサイティングなモーターボール試合は多くの人に注目されながら開幕する。
タイキヤンはかつて難破船の港がある星だった。損害査定業務員が古い船の残骸の処理に派遣され、剰余価値を発掘する。
業務員は「タイキヤンに派遣」されることを戻ることのできない島流しだと見なしている。この小さな惑星では、山となった炭素繊維とステンレスが、巨船の退役前の輪郭を描き出している。鉄筋の廃墟に虚無の影を落とし、呼び戻される強烈な欲求が高まる。数年間、業務員たちは甲板の下で出来のいいパーツを奪い、推進設備を着用して沈没船の通路を猛スピードで駆け、水面下の「地下法則」を形成した…それでも窮鼠は望みを叶えられず、誰も帰航はできなかった。
窮鼠たちは「地下法則」の監視の目から逃れられたことはない。その映像はカンパニーに送られ、偉い人たちの食後の笑い話となった。「伝統事業部」の投資者はよく考え、この中からわずかな「娯楽」の可能性があることを感じた。
計画に応じて、全銀河初の「タイキヤンモーターボール」を主体とした競技項目がタイキヤン星で誕生した。数台の星球改造機がここに降り立ち、廃棄された宇宙船を全て取り除いた。無名の小さな惑星が「モーターボール」の運動を巡って一変し、あっという間に煌めく競技の聖地となった。「その時が来たら、誰も荒唐無稽な原型を気にする人はいなく、残るのはただ純粋なスポーツ精神と、高額な商業契約だけである」
推進器防具を身に付けた選手、変幻自在の立体コース、火花を散らす肉体のぶつかり合い…「モーターボール大会」はすぐに銀河に注目される存在となった。年中夜のタイキヤンにはレーザーが飛び交い、影は見えない。
競技場の中で、チームの主賓の攻防は激しく、声を張り上げる観客たちの席は全部埋まっていた。彼らは大声で、チーム名、有名選手の名前を叫び、勢いのある歓声は途絶えることはなかった。競技場の外でも、タイキヤンは静かになったことはない。中継権限、特許協賛、広告契約が取引市場で奪い合われている。地下世界のロト式もしばしば水面下で勢力を伸ばしている。各自の喜びと悲しみ…インクのような夜の色はとっくにラジウム光プレートとなって、静かにカラフルな競技場を引き立たせている。
タイキヤン競技場は誕生した時から昼のような夜が続いている。誰も陰影がどこに隠れたのかを覚えていない。
- 連結縄
- タイキヤンのアークトラック
- タイキヤン競技場の標準コースは通常金属構造の外側に滑らかなコンクリートと原木の床板で覆われている。
場内の観客がもっとはっきりと見えるようにするために、大量の透明ポリカーボネート素材を競技場に投入し、すべてを一望できる。
「伝統事業部」はスターピースエンターテインメントのスポーツ専門家を招集し、彼らにあらゆる野蛮な要素を取り除き、タイキヤンの「地下法則」を「金に生る競技」に改造するよう求めた。
材料の専門家たちは率先して「モーターボール」を設計し、需要を満たそうと試みた——それは直径3センチ、重さ約30キロの炭素繊維とステンレスを混ぜた科学技術的な鉄球である。ボールは常に位相霊火の変換を追い、不規則な移動によって試合の意外性を高めた。スポーツ装備の専門家はその後に続いて、モーターボール基準の推進防具を開発した。機敏な動きをしやすく、医療企業は企業の素質を示すことができ、安定した収入と安全な競技の継続を可能にした。
こうして、タイキヤンモーターボール協会は正式に成立し、『タイキヤンモーターボール試合ルール』の初版を制定した。7人ずつの2チーム制もこの時に確立されたのである。
博識学会のレーストラック建築家は「競い合う」という概念を立体的な環状トラックにした——標準的な長さは2.91キロ、トラックの中心の平らなエリアの幅は5メートル、両側の弧形のエリアの幅は2~14メートル…選手たちは明るく広いトラックの上で決まった方向に数周飛ぶように走り、鋭い音と衝突音と共に、試合は終了する。実際のテストによると、トラックの高速移動の過程で、非連続の光点は動いている選手たちには線のように見え、流れるような明かりは専属のアークトラックとなる。スターピースエンターテインメントは裕福層を招待し、彼らに最も注目される競技のあるべき公開率を約束した。すぐにリーグ戦クラブ体制が整えられ、才能ある選手たちが集まり、準備万端で開始を待った。
スターピースフィルムは試合中継権を独占し、超距離センシングを利用し、彼らは試合実況を世界の隅々まで届けた。トップ選手の感覚体験もすべて記録されており、観客は家にいながらスピードと衝突、鋭い音とアークを体験できるようになった。昔日の沈没船の港は観光船に満ち、混雑した群衆は灯りと広告に満ちた街頭に集まり、その後ゆっくりと競技場に流れ込んだ。彼らは座席を確保した。辺りは見渡す限り横断幕と麦芽の飛沫だらけである。明るいコースはスポットライトのもとで静かに存在している。
大きな歓声の中、第一試合が開始した。
夢の地ピノコニー

詳細
- 次元界オーブ
- ピノコニーのグランドホテル
- この次元界にはピノコニーの主要部分——ホテル・レバリーが封入されている。
ここに宿泊するゲストは夢の世界を訪れ、どんな願いも叶えてくれる大都会で贅沢三昧の宴を楽しむことができる。
整然と並んだ給仕たちは笑顔で頭を下げ、音楽と共に朗らかな声で来賓を迎えた。「ようこそ、宴の星へ!美しい夢はあなたを歓迎します!」来賓たちは微笑みながら前に進むと、泡の入った飲料を受け取って飲み干した。
すると、景色が次第に光り輝いていき、絹織物に包まれているかのような感覚がしてくる。異邦の客人たちは重力から解き放たれ壁を歩き、奇妙な玩具は命を得て喜びながら町を歩いていた。泉の水は巨大なクジラとなって、広々としたホールを泳いでいる。窓を開けると、遠くに見えるのは群星ではなく、絶えず変化する都市の光、そして巨大な時計と劇場だった。それを見た時、客たちはようやく自分が未だに目覚めておらず、夢の中でピノコニーの本当の姿——時間が止まった夢の地を目の当たりにしていることに気づくのである。
誰もが知っているように、「ファミリー」の管理のもと、ピノコニーの扉は星々に向かって開かれている。現実を超越した経験をするため、インスピレーションを刺激するため、憂いや傷跡を癒すため——次々と訪れる賓客たちは、苦痛と引き換えに安寧を得るのだ。ある人は美酒を飲み、夢の海を気ままに歩いた。ある人はここで忘れられない休暇を過ごし、満足して帰っていった。またある人は歌と舞に夢中になり、ここに定住すると決めた。星が取り巻くホテルは夢織りの珠玉、夢造りの国で、夢追いの楽土である。
しかし、埋もれた歴史を知る賓客は少ない。夢境を織りなす糸は現実で作られている。今日のピノコニーのビロードのような軽やかな贅沢は、塩辛い錆、重々しい手枷と足枷、そして剥奪された自由から生まれているのだ。かつて、宴の星はカンパニーの牢獄だった。数え切れないほどの囚人がここに移され、ガーデンのために溢れる憶泡の引き上げに従事した。人々は体が鉛のように重く、魂が泡のように軽く擦り減るまで、終わりのない過酷な労働を繰り返していた。いつからか狭い独房は現実から切り離され、人々の意識は夢の中で繋がるようになった。真夜中の鐘が鳴り響く中、一緒に見ている夢は真実味を帯び、現実は偽りのようになっていく。
「壊滅」がカンパニーの鎖を切り、「開拓」が辺境と星々を結び付け、招待に応じてやって来た「調和」が平和の種子を撒く。自由はついに芽生え、最初の夢に名前を付けた——「ピノコニー」という名前を。
今や荒れ果てた牢獄の跡はどこにもない。夢境の中ではいくつもの高いビルが建ち、砂漠は再開発され、大都市は——夢を追う者が富のチャンスを求める新大陸に、楽しさを求める者が道楽の限りを尽くせるユートピアになった。「宴の星」の過去は偶然にも棚の下に滑り込んだ写真のように、確かに存在してはいるが、誰も知らないものとなった。
今、夢の地には歓喜の歌が響き、過去の雑音は面白い閑話になり、ある喜劇の幕間に、あるアニメのメイキングに、そして雑誌の隅に静かに残されている。
- 連結縄
- ピノコニーの夢追い軌道
- ピノコニーの夢境都市では、建物の間に複雑に入り組んだレールが張り巡らされ、色とりどりの夢を繋いでいる。
そして観光客を乗せたスフェロイドがそのレールを辿り、人々に煌びやかな夢を見せるのである。
ピノコニーを訪れたことのある賓客なら必ず賛同するだろう。「夢の上に建つ」という言葉は誇張された比喩ではなく、紛れもない真実であると。豪奢なホテルは宴の星の氷山の一角でしかなく、「宿泊して夢に入る」ことで、正式にピノコニーに足を踏み入れたと言える。そうすれば、12の夢境からなる夢の国が賓客の前で徐々に開かれていく。
初めてここを訪れた賓客は、このお祭り騒ぎに困惑するに違いない。しかし、慌てる必要はない。見上げれば、ビルの間を交錯する金属のレールと、その上を飛ぶように移動する「スフェロイド」が目に入るだろう。これは夢境の都市で最も注目されている交通手段であり、賓客たちを色々な場所に導くガイドである。
センター駅から始まる複雑で入り組んだスフェロイドの軌道は、大都会の血管のようにピノコニーの夢境に眠らない活力を注ぎ込んでいる。「黎明ノ刻」の地底管でも、「熱砂ノ刻」の広い草原でも、「星辰ノ刻」の輝かしい競技場でも、カラフルな球は止まらずに転がり、人を正確かつ効率よく、安全に各地点へ送り届ける。
夢はすべてに手触りがよくしなやかな質感を与え、固いナッツのような「スフェロイド」は夢の地では乗物、あるいは玩具と見なされている。この「スフェロイド」がもともと「囚人の籠」だったことを覚えている人はほとんどいない。夢へ向かう乗物は、囚人を収監する道具だったのだ。
遥か昔、カンパニーは大勢の囚人をアスデナ星系に送り、災いの蔓延を阻止しようとした。そして人々はここで憶質を回収し、次第に現実と幻想の狭間に迷い込むようになったのである。真空の中の球体の作業室は、囚人たちにとって忘れられない「記憶」になった。硬く湾曲した内壁、耐えがたい転覆体験、毎日の辛い出勤——その苦痛はあまりにも印象深く、再び自由を手にした人が荒れ果てた夢境を開拓した時、スフェロイドも同じように降臨したのだ。
しかし、今は昔とは違う。平和と自由が楽観的な精神を生んだのである——振り捨てられない悪夢を何度も壊すよりも、それに色をつけ、吸収して包容すればいい——だから過去の「囚人の籠」は、今日の「スフェロイド」に変わったのだ。
今この瞬間も、カラフルなスフェロイドはピノコニーの都市を高速で移動している。その中から伝わってくる微かな振動…静かな音は夢境の都市の奇妙な様相の中に隠れていて、偉大な理想、歓声や談笑の声と溶け合い、時が止まった夢の地のようになっている。
蒼穹戦線グラモス

詳細
- 次元界オーブ
- グラモスの鉄騎兵団
- この次元界にはグラモス帝国の有名な鉄騎変形鞘が封入されている。
無数の白銀機甲が戦艦に積み込まれ、スウォームに対抗するため星系の外縁部へと向かう。
蒼穹帝国グラモスは数万光年もの広大な領土を持ち、野心的に遠くの銀河を見据えている。帝国の最盛期、グラモスの女皇ティタニアは巨大な艦隊を編成すると、文明の果実をすべての未開の辺境に届け、帝国の慈悲を感じさせ、統一することを誓った。
しかし、遠征は失敗に終わってしまった。天幕の彼方から虫の末裔が無限に沸いて出てきたのだ。グラモスの軍隊は反撃と敗北を繰り返し…いくつもの植民地が失われ、自慢の鋼鉄の艦隊も次々と陥落した。複眼と羽を持つ虫の包囲攻撃の中、グラモスの民の叫びは絶望に埋もれ、蒼穹は砕け散った。
ある日、機械の鎧を身に纏った騎士たちが空から舞い降り、天を覆っていた虫たちを殲滅した。その後、白銀の騎士たちは帝国の各星区を往来し、ボロボロの領土を越え、星系を滅ぼす災厄に抵抗した。彼らはまるでスウォームに抗うために生まれた戦士。鉄面の下に隠された彼らの素顔は誰も知らなかったが、彼らの降臨は神の恩恵の如く、蒼穹の希望を取り戻した。女皇の統率のもと、グラモスの鉄騎兵団は空を駆け巡り、ついには敵を食い止め、帝国に一息つく時間をもたらした。
しかし、代々の仇との絶えない戦いの中で、帝国はますます自身の敵のようになっていった——空高く飛ぶ鉄騎は増え、虫の潮が襲来した日のように蒼天を覆う。人々が女皇と騎士を見る視線は、スウォームに向ける恐怖の眼差しと同じのものになった。いつか帝国は望んでいた勝利を手にできるかもしれない。だがその時、グラモスはまだ人類が穏やかに暮らせる楽園のままだろうか?
戦火の消えないグラモスの辺境で、鉄騎兵団は最後の防御線を構築した。戦艦の上で、沈黙する騎士たちは使命を帯び、帝国全体の希望を載せて、群星を覆い尽くそうとする敵を迎え撃つ。
- 連結縄
- グラモスの静寂の墓碑
- 栄えた「帝国」グラモスは塵と化した。
そのかつての繁栄を証明できるものは何もなく、ただ星屑、機甲、戦艦、そしてスウォームの残骸だけが、記念碑のように惨烈な戦線の形を維持している。
博識学会の歴史学者は、グラモスはスウォームによって滅びたと考えている。しかし、中には別の見解もあった。それは、グラモス共和国は強敵を完全に超越したから滅んだというものだ。
スウォームによる恐るべき進攻から戦局を逆転させるため、執政議会は一か八か、人類の本質に手を加えることを決めた——「戦いのために生まれた」兵器を創造することにしたのだ。
その成果が「ティタニア」だった。何の権力もない女皇がテレパシーによって指揮を執り、彼女と繋がる騎士を束縛する。彼女が織り成す夢の中で、戦士たちの存在意義とはティタニアと彼女の「帝国」を守ることであった。短い生命の中、彼らは学び、戦い、女皇の統率を受け、恐れることなく敵に立ち向かい、名誉ある戦死を遂げる。
この嘘がいつ暴かれたのか、それを知る者はいない。グラモスの領土の旧人類の割合が一定数を下回った時か?科学者たちが、女皇が監禁に抵抗を始めたと気づいた時か?それとも…スウォームの攻勢が消えた日からか?
人々は鉄騎兵団が存在しない「帝国」のためにすべてを費やしたことしか知らない。数十年にも及ぶ血戦の後、機甲と虫の残骸がグラモスの星域全体に広がり、1本の「死の川」となった。残されたスウォームなど、もはや脅威ではない。議会のリーダーは平和の鐘を鳴らし、民たちに蒼穹を覆っていた天災を退けたこと、そして共和国は再び夜明けの光を迎えることを伝えた——しかし、訪れたのは夜明けではなく、もう一つの夜の始まりだった。
その後、グラモスという名の文明は消えていき、人々が待ち望んでいた平和は主のいない星域に降臨した。星屑と残骸が川となって、共に星の間を静かに流れる。
顕世の出雲と高天の神国

詳細
- 次元界オーブ
- 出雲の禍津衆神
- 次元界の中に封装されているのは、過去と未来が一刀で両断された出雲。
出雲はかつて言葉にできないほどの残酷な生存競争を経験し、豊かで輝かしい時代も過ごしてきたが…今では一片の荒野すら残されていない。ただ過去を埋葬する剣塚だけがそびえ立っている。
二つの惑星がお互いの悲惨な運命を交錯させ、漆黒の太陽の周りで永遠の輪舞を踊る。
最初、惑星の一つは人類を生み出し、彼らは頭を垂らして足元の土地を「出雲」と呼んだ。そして再び頭を上げ、天上の世界を指して「高天原」と呼んだ。記録にないある日、「八百万の神々」が高天原から降りてきた。神の名を持つ凶獣は空を傾け、海川を燃やし、大地を崩壊させた――人々は、それが支配や略奪のための侵略ではなく、ただ狩りのために来た凶神であることを悟った。
世界存亡の危機に際し、出雲は「神狩」の道を歩み、国を挙げて厄災「都牟刈神」を斬り、その獣体で「詔刀」の原型を作り上げる。その刀に込められた真言を唱えることで、刀の所有者は高天原の神業を手にし、凶神に立ち向かって世界の民を救えるほどの力を得た。これにより、出雲国は長い征討を開始し、無数の犠牲と引き換えに神々を倒し、万千の剣を折り、最後には十二振りの「世守の刀」を鍛えあげた。
残酷な生存戦争の中、出雲国は詔刀の力を借りて未開の暗黒世界を照らし、十琥珀紀たらずで彩り豊かな国を建設した。かつては手の届かなかった高天神国もすぐそこにある――しかしその瞬間、歴史は突如止まり、二つの惑星の存在は一夜にして灰となり、跡形もなく消えてしまった。
今や、辺境の星「出雲」の過去は、宇宙の断片的な言い伝えから推測するしかない。その消滅について、学者たちはさまざまな説を唱えたが、真相は誰にも分からなかった。出雲の歴史は大河のように長かったが、一刀のもとに断ち切られ、過去も未来もすべて空虚の彼岸へと消えてしまった。それは存在しなかったのか、あるいは単なる虚構の物語なのか?それは最初から起きていなかったのか、はたまた因果逆転の浜辺に漂流しているのか?それは「原始博士」による惨劇の実験の一つなのか、それとも「貪慾」が銀河の果てから戻ってくる前兆なのか?
答えを知っているのは、あの漆黒の太陽だけだったが、其は沈黙して、決して語ろうとはしなかった。
なぜなら、起こったことはすべて終わりに向かい、終わったことは再び起こるからだ。宇宙は星神の影の下で永劫回帰する。出雲はただの脚注の省略記号にすぎないのだ。
- 連結縄
- 出雲の終始一刀
- 出雲の人は房を使って刀を腰に結びつけている。
彼らは世界を旅し、刀で神を狩り、そしてまた神の骸で刀を鍛える…このようなことを繰り返し、出雲は繁栄へと向かい、幻滅へと向かい、虚無へと向かうのだ。
二つの惑星が互いの悲惨な運命を交錯させると、天岩戸に過去の歌が響く。
その歌には始まりも終わりもなく、音も気配もない。そして誰の口からも発せられず、誰の耳にも届かない。その内容は次のようなものだ。
高天原は万里遥か出雲のごとく、元は極楽浄土にして地平天成たり。
天地は漆黒の大日によって潮汐を引き起こされ、神々が急いで渡り歩くかのようだった。
八百万の禍神が世に姿を現し、無情に屠殺を行うも、最高権威を奪われることは予想できただろうか。
出雲国は七万三十三の刀を折り、その中から世界を守るための十二振りの世守の刀を鍛えた。
一振り目は「真」。「都牟刈神」を斬って鍛えられたその刀は、人々に真理を見せ、万象を分解して神跡を再構築する。
二振り目は「天」。「天之常立尊」を斬って鍛えられたその刀は、高天を壁に変え、禍津の諸神の行く手を阻む。
三振り目は「鳴」。「建御雷神」を斬って鍛えられたその刀は、雷光で空を裂き、星流の雷撃で天罰を下す。
四振り目は「嵐」。「志那都彦」を斬って鍛えられたその刀は、風で大地を砕き、雲を走らせて雨を轟かせる。
五振り目は「霜」。「天之冬衣」を斬って鍛えられたその刀は、時を凍てつかせ、凍土を永遠のものとする。
六振り目は「命」。「石長比売」を斬って鍛えられたその刀は、不毛の墓から花を咲かせ、生と死を流転させる。
七振り目は「烈」。「迦具土命」を斬って鍛えられたその刀は、業火で俗世を燃やし、天を燎原へと変える。
八振り目は「覚」。「八意思兼」を斬って鍛えられたその刀は、水鏡で過去を映して未来を知り、永遠に虚実を見ないようにさせる。
九振り目は「礎」。「大山津見」を斬って鍛えられたその刀は、列島を天辺に浮かび上がらせ、山や地面を突き崩す。
十振り目は「千」。「大己貴命」を斬って鍛えられたその刀は、人々をつなげ、無数の影を起伏させる。
十一振り目は「束」。「久那止神」を斬って鍛えられたその刀は、間違った道をことごとく籠に入れ、邪悪を一掃する。
十二振り目は「喰」。「八十枉津」を斬って鍛えられたその刀は、常世を朽ち果てさせ、神鬼の区別をなくす。
そして幽世は一掃され、戦いは終わり、十二振りの刀がすべて折られる。
荒魂だけが騒ぎ、黒き太陽は明るく輝き、最後に世を負う二刀を鍛える。
一つは「始」、もう一つは「終」。人に始まり、鬼に終わる。
声は途絶え、花は枯れ、敗者は無に帰し、勝者は…空となる。
足を引きずった僧侶が調子の外れた歌を歌い、神の力を持つ者はまた鬼へと退行していく。
大日の下、かつて「出雲」と呼ばれた土地では、人、神、鬼は…もはや、どこにもいない。
荒涼の惑星ツガンニヤ

詳細
- 次元界オーブ
- ツガンニヤの地母神の寝台
- 次元界の中に封装されているのは、ツガンニヤ-IVで最も住みやすい地域――静寂な荒野「地母神の寝台」。
三つの目を持つ地母神は言葉を発することなく、質素にその重厚な肉体で、ツガンニヤのすべての生者と死者を包み込んでいる。
カンパニーの「市場開拓部」主任オスワルド・シュナイダーについて語る時、人々は特に彼の就任した時の3つの業績――若き狂信徒がわずか2年間で厳寒、疾病、死といった試練を乗り越え、市場開拓部が数琥珀紀にわたって解決できずにいた3つの大問題を解決したことを好んで話題にする。その1つがツガンニヤ-IVと呼ばれる荒れ果てた星でのこと。そこは静まり返った荒野で、氏族の確執が絶えず存在していた。
ツガンニヤ-IVは三大星系の境界地帯に位置し、長期にわたって複数の恒星の星風による影響を受けているため、銀河では「暴風の目」として知られている。星の表面の生存環境は過酷で、多くの文明は他の星系に移住するか、自然災害で滅びた。今ではごく少数の知的種族が残っているだけで、博識学会の学者はこれらを総称してツガンニヤ人と呼んでいる。
実際にはツガンニヤ人は多くの氏族にわかれており、大部分は遊牧を生業としているが、かなりの規模の集権体制を築いている集団も少数ながら存在する。
彼らには共通の言語がある。共感覚ビーコンによる翻訳からは、「カティカ」がナイフを意味し、ツガンニヤ人の中で最も血に渇いた蛮族を指すこと、また「エヴィキン」が蜂蜜を意味し、一部の頑固者は彼らを盗賊だと主張することが分かるだろう。彼らは数琥珀紀にもわたる古い確執を抱き続け、果てしない荒野で弱肉強食の血なまぐさい連鎖を繰り広げていた。黒衣を着た天からの来訪者が現れるまでは……ツガンニヤ人は琥珀の光の下で暫しの統一を迎え、終わりなき自然の循環は一時的な落ち着きを見せた。
その後、宇宙の巨大企業の指導の下、ツガンニヤ人は『憲章』にもとづいてツガンニヤ連合首長国を建国し、文明の宇宙に向けて第一歩を踏み出した。
残念ながら、この団結と発展は、エヴィキン人とカティカ人のものではなかった。一部悪意を抱いている日和見なツガンニヤ人はエヴィキン人の機敏さと狡猾さを警戒し、カティカ人の方は文明化することが絶対に不可能な、食人野獣にすぎないと見下げる。彼らの「存護」に対する理解は表面的なものにすぎないが、誰かが犠牲を払わないといけないことはわかっていた。そのため、腐敗者たちは極めて先進的な議事ルールを利用し、この2つの氏族の人々を広大な黄砂に追放した。
謝罪の意を示すため、彼らは決議文に「エヴィキン人は永遠に自治自決の権利を有する」と、わざわざ明記した――即ち、今後2つの氏族の間で再び紛争が起こるとしても、彼らは合理的、かつ合法的に無関心でいられることを意味している。
- 連結縄
- ツガンニヤの輪廻の結び目
- ターコイズはエヴィキン人によって入念に磨かれ、金糸と緑のリボンが通されている。
お守りは決して砂に埋もれさせてはならず、「カカワ」の夜に死から生まれ変わった奇跡のように、輝かせないといけないと言われている。
エヴィキンはツガンニヤ語で「蜂蜜」を意味する――この次第に一般化した呼び方は、今や完全に宇宙の歴史の砂に埋められている。
エヴィキン人がそう呼ばれるのには理由がある。彼らは生まれつき美しい容姿と瞳、そして高い社交性で知られていて、他人から好感を得るのがとても得意だ。しかし、この才能は彼らを嫉妬と恨みの対象にしてしまった。妬ましく思う者たちによる終わりなき誹謗中傷で、汚名はやがて全銀河に広がり、「真実」となっていった。辺境星の少数民族であるエヴィキン人は自分たちを証明する術がなく、ただ黙って受け入れるしかなかった。
エヴィキン人は複雑な柄の織物や宝石――特にツガンニヤのターコイズ隕石で作られたネックレスを好んだ。その理由は単純で、この宝石だけが、彼らの神話において死から生まれ変わる地母神の依り代に比肩するからだった。
エヴィキン人の地母神、「ファンゴ-ビヨス」と呼ばれ、出産、旅、計略に関わるすべてを司っている神。エヴィキン人の信仰では、彼女は通常、三つの目を持つ左手として描かれた。エヴィキン人は一般的に、口頭での祈りによって彼女に敬意を表すだけである。地母神はツガンニヤの山々のように沈黙して質素であると信じているため、彫像や賛美歌は彼女の庇護から自分たちを遠ざけるだけだと考えていた。
エヴィキン人は地母神を通じて世界を認識する。大地、山脈、そしてそれらが包み込むすべてが地母神の一部であり、この依り代は毎年最後の日に死を迎えるのだ。
最後の日、神聖な光が夜空に昇り、輝かしいオーロラとなって翌日に再び誕生する。そのため、エヴィキン人は新年最初の日に「カカワ」と呼ばれる祭りを催し、「輪廻の結び目」という名の祭器を編み、それをたき火に投げ入れて地母神の誕生を祝う。
市場開拓部の事故報告書によると、あの大悲劇は「カカワ」の夜に起こったようだ。その夜は風雨が激しく、雲が空のオーロラを飲み込んだ。本来なら不吉な兆しと見なされるべきだが、エヴィキン人はかつてないほど興奮していた。彼が氏族の少女に理由を尋ねたところ、次のような答えが返ってきた――
「雨は地母神の恵みだから。これは地母神が私たちを呼んでいるの。武器を取り、自分たちの未来のために戦うようにって」
「雨は常に私たちと共にあり、私たちを守ってくれる。雨の中で、私たちは誇り高く死ぬのよ」
奔狼の都藍王朝
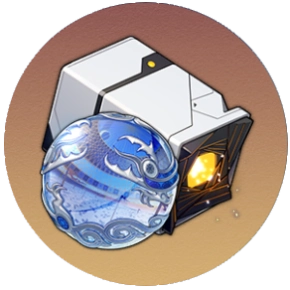
詳細
- 次元界オーブ
- 都藍の黄金ドーム
- 次元界に封印された青丘歩離の黄金ドーム。
銀河に残っている野蛮な評判とは異なり、歩離人は卓越したバイオテクノロジーを有している。狼たちは偉大な巣父都藍の傍に集い、天上の星々を家畜と見なしてその間を駆け巡る。
狐族と歩離人の太古の歌の冒頭部分では、「青丘の星」の肥沃な土地と住みやすい気候を懐かしんでいる。しかし注意深く読めば、それが「戦争」という永遠のテーマのプロローグでしかないことがわかるだろう。
耕作と商売の才に恵まれた狐の氏族は、川の畔に栄えた都市国家を築いた。一方、犬人の子は見事なオーロラが広がる空の下、草原の海で狩猟や放牧を行い、星のように広がる集落を作った。商人は牧人を野蛮だと嘲笑い、牧人は商人を狡猾だと軽蔑する。しかし、彼らは等しく自然の厳しいサイクルに立ち向かわなければならない——「狐の夏」と「狼の冬」だ。
狐の神の恵みで豊作になる夏の間、両種族は戦いを止め、満ち足りた日々を送る。しかし、ひとたび狼の神によって白い霜が降り、雪が極寒の地から広がっていくと、両種族を飢餓が襲い、争いへと追い込むのだ。
歌によれば、終わりのない狼の冬は、青丘の太陽が33回まわった後も続いていたという。物資の不足と飢餓によって、人々は信仰上崇拝していた動物すらも、飢えを凌ぐために食べざるを得なくなっていた。そして大地に白骨が広がるかと思われた時、1人の救世主が世界で最も高い山に登った——その救世主は、狐族の神話の中では「塗山」という名の女性だとされているが、歩離人の歌では「都藍」という名の男性になっている。救世主がどのような名前で呼ばれていようと、その人物が長生の主に人々が生きるための食料を与えてくれるよう、祈りを捧げたことは事実だ。すると、不思議なことに山の頂が裂け、その隙間から甘美な「赤泉」が溢れ出した。
赤泉を飲んだ人々は、口にした動物の肉から力、敏捷性、強靭さを得た。さらには彼らの血にも野性が漲り、獣らしい外見的特徴が明らかになっていった――この時から、世界は以前とは違うものに変わったのである。
新たに生まれた犬人たちは、赤泉を媒体として、そこからあらゆる道具や食料を創り出した――畑には穀物ではなく肉が植えられ、身に纏うのは布ではなく胎盤や臍の緒になった。青丘文明を恐怖に陥れた極寒の雪の地でさえ、もはや恐れる必要はない。犬人たちは極寒の地で生物膜を育て、暖かいドームを作った。これによって狼の冬の苦難を遮断したのだ。
その後の青丘の劇的な変化は、すべての短命種が長命種に変わる過程と何ら変わらなかった――人口爆発、生態系の崩壊、内戦…犬人たちが長生の主にいくら祈りを捧げようとも、返事が返ってくることはない。そうして彼らは理解した――長生の主が与えられるものはすでにすべて揃っている。今よりもいい暮らしがしたいのならば、自分たちの力で奪うしかないのだと。
偉大なる巣父都藍のもとに集った犬人たちは、長生の主が住む空に目を向けた。そこに輝く星々は、これから狩りの場となる牧場だ。彼らはそれらの文明に、「狼の冬」をもたらすことになる。
それから長い歳月が経ち、宿敵の仙舟人は彼らのことを「歩離人」と呼ぶようになった。歩離とは青丘語で「狼」を意味する言葉である。
- 連結縄
- 都藍の器獣の手綱とくつわ
- これは手綱であり、鎖であり、鞭でもある。戦獣の脚よりも背の高い歩離の青年が最初に教えられるのは、いついかなる時も手綱をしっかり握っておくということだ。さもなければ自分が使役される家畜、あるいは餌になってしまうからである。
歩離人の言葉で、手綱は「アーサー・チッタ」とも呼ばれている。これは「生きた書」という意味だ。
猟群の卜者たちは2つの月が同時に昇り、夜空で最も輝く時、成人の儀の贈り物として手綱を都藍の子孫たちに授ける。この無地の手綱は、彼らの生涯の戦いを記録する書冊となるのだ。
成人の儀が終わると、歩離人はすぐに武器牧場に入り、遺伝子巫術で餞別、育成された「器獣」の中から最初の1匹を選び、手懐けなければならない。征服された者を餌とする器獣は、恐ろしく鋭敏で獰猛だ――しかし、未来の主と比べれば、それも子羊のようなもの。月明かりは体内に流れる野性の血を呼び覚まし、歩離の青年たちは器獣と互いに追いかけ合い、戦いを繰り広げる。ある者は獣の口付けで死ぬ、それは弱者の末路だ。ある者は同胞を殺す、それは猛獣の分配法だ…歩離の青年は気に入った器獣を地面に倒すと、神経刺激の鞭が付いた手綱で首を締め付けた――家畜は未来の主の魂に衝撃を受け、鞭で数百回打たれたかのように従順になる。そして自ら進んで主を背に乗せる時、一人前の歩離人「索牙」(戦士、騎手)が誕生するのだ。
それ以降、歩離の手綱は戦いの記録者となり、徐々に傷、結び目、飾りが増えていくのである。
訓練を積んだ索牙たちは「昂達」(100人の部隊を率いる隊長)の指揮のもと、クラゲのような膜状の鎧を身に着け、星間を跳躍する獣艦に乗り込み、さまざまな異世界へと旅立つ。そして都藍と長生の主の名のもとに、星々を牧場に変えることを誓うのだ。手綱に付いた浅い傷は倒した敵の数を、結び目は経験した大戦を表しており、飾りは大略奪の際に得た戦利品である。人間の歯、オムニックのシリコンチップ…それらは征服された者たちの怒りと叫びであると同時に、歩離人が個人の力を誇示するための勲章でもある。
乗っていた器獣が戦火で死んだ時、あるいは歩離人が罰を与えたいと感じた時、手綱は外され他の生物に付けられる。
その対象となるのは通常狐族である――狐族とは血統選択育成計画によって排除された奴隷階級のことだ。彼らは弱く、狡猾で、労働と算術にしか向いていない。稀に戦闘の得意な個体が現れると、狼主は彼らを優先的に手綱で縛り、戦奴として先陣を切らせるのだ。
すべての奴隷が死に、武器が壊れた場合、手綱の端に棘を結び付け、鞭として使うこともある。もし鞭すらも切れ、爪も牙も砕け、戦場で最期を遂げることになったとしたら、その手綱は歩離人にとって唯一の碑銘と遺品となるだろう……
古い諺に、「森の中では、狩人と獲物の立場がしばしば入れ替わる」というものがある。宇宙という暗黒の森で、仙舟人と何千年にもわたって戦い続ける中で、狼族の鞭は数え切れないほど断たれてきた。最終的に、多くの猟群を結ぶ絆は「巡狩」の矢じりによって断ち切られ、歩離人は内乱と衰退の奈落に落ち、かつての栄光は失われたのである。
劫火と蓮灯の鋳煉宮
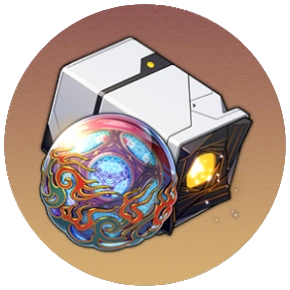
詳細
- 次元界オーブ
- 鋳煉宮の蓮花ランプの芯
- 次元界の中に封装されているのは、仙舟朱明工造司の所在地――焔輪鋳煉宮。
朱明仙舟が歳陽の祖「火皇」を中心に建設したもので、天体のような球形構造をしている。天才職人たちはここからエネルギーを汲み取り、奇想天外なアイデアを形にするのだ。
古代に航行に出て以来、仙舟朱明は星海を旅して8000年余りになる。船体の形状が変化する様子を時空を超えて観察すれば、その過程が極めてロマンチックであることに気づくだろう――巨大な船が青い恒星を呑み込み、古い殻を1枚ずつ剥いでいき、骨組みを隆起させ、最後には蓮の花のように開く。
宇宙から見ると、仙舟朱明は金の糸で編まれた蓮のランプのようだ。発光する巨大な「蓮の葉」が「ランプの柱」の周りに徐々に広がり、淡い青色の光を浴びる姿は、「船ではなく、輝く蓮の花のようである」と謳われるに相応しい。中心にある「ランプの傘」は天体のような球形シェル構造をしており、淡い青色の太陽である「ランプの芯」の周りを回り続けている。そして、その巨大な構造物こそ、仙舟朱明の物造りの要地――「焔輪鋳煉宮」の所在地である。
その昔、朱明の名匠である陽翟は、ある長い歴史を持つ国の皇帝から、航行の証として武器の鋳造型を賜った。それから数千年、長生の大きな変動によって帰還の見込みは立てられていないが、名匠の伝統が途絶えることはなかった。仙舟朱明では、工芸技術は最高の学問とされている。歴代の将軍は全員が工造司百冶の位を持ち、外では大軍を指揮しながら、中では工具を操ることで、人々から尊敬されているのだ。仙舟の巡狩に必要とされる武器の6~7割は、朱明の工造司で鍛造されている。そのため、焔輪鋳煉宮は銀河における技術の聖地となったのである。
鍛冶は文明の基準であり、炎は文明の起点である。大多数の若い文明が最も頭を悩ませるのは、恐らくエネルギーに関する問題だろう。人々は文明をより高度なものにするため、苦労を重ねてエネルギー源を探していた。そして仙舟朱明はその壁を乗り越えた――歳陽の祖「火皇」を囚えたことで、職人たちは無尽蔵のエネルギーを手に入れたのだ。焔輪鋳煉宮は四方八方に伸びる軌道のように、恒星を最大限に取り囲んでいる。細かい枝葉の上には、受信と変換のための装置がいたる所に設置されており、太始の炎「火皇」からあらゆる技術創造のためのエネルギーを引き出しているのである。
「偽陽」を呑み込んだ朱明工造司は、数多の職人たちから至上の殿堂と見なされ、神器鍛造を志す者たちが押し寄せてくるようになった。金属と木材は加工されることで、初めて「物」に成り得る。焔輪鋳煉宮は職人に必要なものをすべて取り揃えているのだ――
さまざまな世界の学徒が鋳煉宮に集い、同門となって技術を競い合う。宝器を求めて来た異邦人も、大金をはたいて職人に優れた武器を作らせた――しかし数千年もの間、多くの学徒の中で「匠の中の匠」懐炎将軍の指導を受けられたのは、ほんの一握りだけだった。彼は言葉と行動を以って工芸技術と武芸を後進たちに教え、門下の学徒たちは「百冶」として歴史に名を刻む職人になるか、「焔輪八葉」のように同盟に名を轟かせる雲騎兵となった。
「鍛造炉で千の星を鍛え、鉄を打ち魂を宿さん。一斗の光に戦威を奮い、鋒鋭を手に世の安寧を守らん」——朱明の職人は工具を授かったその日から、自分が日夜鍛えているのはただの刀剣ではなく、巡狩の矢じりなのだと肝に銘じておかなければならない。
- 連結縄
- 鋳煉宮の焔輪天織
- 恒星のように巨大な歳陽の祖が果てしない夢の中に沈んでいる。
その深い眠りの中で、周囲の原子と分子は衝突して刺激され、焔輪鋳煉の外殻構造から飛び散り、最終的には色とりどりの天織光帯として現れる。
深宇宙を航行する仙舟朱明は常に異色の光帯を伴っている。それは超高温核融合反応によるエネルギーの産物であると同時に、「火皇」が今も燃え続けており、不死不滅であることの証でもある。
「火皇」の吐息によって飛散する極光粒子の最外層では、生まれたばかりの歳陽がゆっくりと漂っている。朱明十王司の猟火判官は、いかなる感情にも染まっていない無垢な歳陽を捕らえ、温かい夢によって火の未熟な心を手懐ける。その後、無害な歳陽を工造司の歳火監に引き渡すのだ。歳火監は歳陽たちをさまざまな道具と組み合わせ、朱明の街頭、乗り物を始めとした、至るところで見られる「風景」の一部に変えていく。しかし、事情を知らない殊俗の民の目には、それらの喋ったり歩いたりできる奇物は、「洞天には精気が満ちていて、歳月を経た道具が妖魔に変わる」という噂の証明のように映るのである……
異色の光帯に沿ってさらに進んでいくと、鋳煉宮を越え、偽陽が形成する超重力場に辿り着く。一般人では、このような恒星の密度に耐えることは難しい。さらに、そこは内部崩壊が起きたように乱れているため、この区域を普通に歩けるのは「梨菩」の職人だけだ。
高温の恒星爆発と異常な天体現象は、好奇心に駆られた人々が偽陽に近づくことを拒む。この地域では、宇宙の基本的な物理法則が恐ろしいほど強化されているのだ。こうした重力異常の空間で生き延びられるのは、ずんぐりとして逞しい星民の梨菩だけである――梨菩は生まれながらにして最高の職人だ。彼らは鋳煉宮と偽陽の間を往来しており、その時間の感覚は一般人とは異なる。約束を守りながら職人の技を磨き、艦船や大砲を造り、偽陽の眠りを監視しているのだ。仙舟朱明は梨菩を忠実な盟友と認め、彼らの頑強な精神を尊重すると共に、無私の貢献に感謝している。
誰であろうと、光帯に沿って奇妙に捻じれた重力場を通り抜けたり、偽陽の深部に潜り込んだりすることはできない。そこは「火皇」の果てしない夢の中であり、感情を持つ存在が足を踏み入れてはいけない場所なのだ――仙舟朱明はいかなる感情の波動も、始祖歳陽の無限の力を呼び覚ます可能性があるとして警戒している。
しばしば警告を無視して遠くから偽陽を見つめる人々がいる。彼らは知らず知らずのうちに精神の重力場に足を踏み入れ、ほんの些細な不注意から、海水のように絶え間なく湧き出る幻影に精神を奪われてしまう。柔らかい幻影とは裏腹に、その「幽藍の太陽」を見つめると、古来抑圧されてきた激しい怒りを感じるだろう――「歳陽は英雄たちに世界を滅する力を与える。そしてすべての使命を果たした時、彼らは完璧に鍛え上げられた体を歳陽に捧げなければならない……」古い誓いがどのように実現されるのかは誰にもわからない。同じように、果てしない夢の中で「火皇」がいつ目覚めるのかも、誰にもわからないのだ。
蓮花のランプ芯の中で、深い眠りについている偽陽が溜め息をついた。仙舟はゆっくりと空を滑り、一筋の異色の軌跡を残していく。仙舟朱明はこれからも火との誓いを守り続け、火と共に歩み、火と運命を共にするのである。
海に沈んだルサカ

詳細
- 次元界オーブ
- ルサカの水に朽ちた蒼都
- 次元界の中に封装されているのは海洋世界ルサカ、水没した都市である。
ここは海面が絶えず上昇を続け、最後には都市全体が海に沈んだ。船員たちを乗せた巨大な「ステイトシップ」だけが、次の航海の場所を求めて海上を進んでいる。
水不足の惑星が集まるプルスミル星系の中で、ルサカの純粋なる青は特に目立つ。その海水は母なる海のゆりかごのように、万物を育て、抱き締め、縛り、陥れる…逃げ場がなくなるまで。
夜が明ける頃、「ステイトシップ」の副船長が船長室のドアを軽く叩いた。部屋の壁には旧時代の37地域からなる群島生態系のポスターが貼られており、陸地を懐かしむ人々の気持ちを表している。宇宙から飛来した隕石は偏執的な願いに従うかのように、ルサカ全土に海を広げていった。すべての故郷は果てしない波に飲まれ、今残っているのは一面の青だけだ…副船長は眠っている船長を起こした。朝日に照らされ輝く海面の上で、「ステイトシップ」の新しい1日が始まろうとしている。
広場の中央に辿り着いた探索船は、錨を海中の「ショッピングモールだった」巨大建造物に向けて射出した。錨が建造物の窓枠にしっかりとはまると、潜水鐘が下りきる前に、驚いた魚の群れがモールの棚から飛び出してくる。
午後になると、学者たちは潜水鐘から出ていった。彼らは書店を見つけたが、その前を止まることなく泳いで通り過ぎていく。興味を示さないのは、そこにある書籍はインクが滲んで文字を識別できないからだろう。彼らの目的はシェラックやプラスチックの記録媒体だ——それらは簡単に洗浄するだけで、昔の情報を得ることができるのである。しかし、こうした潜水考古学調査は決して容易いことではない。たとえば、鋭い歯を持つ捕食者から身を守るため、清掃係と呼ばれる存在が見張りに立ち、鋼の槍を振り回したりしている。また、時折深海の妖精と出会うこともあるが、互いに忙しいため気にかける暇もなく、両者それぞれの探索に集中している。そして清掃係は萎びた缶詰よりも種子、調味料、酒を見つけたいと思っているのだ。
酸素の残量が減少するにつれ、集中的な水中調査も終わりに近づいていく。水面に出て下を見ると、巨大なサバが都市の中に入っていくところだった。水の妖精は驚いて息を止め、壁に張り付き、密室に隠れる。妖精たちは知っているのだ…水中にある鋼鉄の森を、どう利用すればいいのかを。
夕方、天候が落ち着くと、すべてのステイトシップが一斉に汽笛を鳴らして周囲の海賊鳥を追い払う。そして1日の収穫を甲板に並べ、ステイトシップの人々にそれぞれ必要なものを自由に取らせるのだ。波が渦巻く夜、光の塔はきらきらと輝いている。ルヴィル人は炎の竿を囲んで踊り、いずれ訪れる明日を忘れ、今日の栄光を船の歌に変え、過去の美しさを海の歌で嘆く。船長はコンパスを取り出して、針の指す方向を見つめる。彼はそこに見知らぬ土地になりつつある故郷があること、そして家族の帰りを心待ちにしている人々がいることを知っていた。
夜中。明かりの消えた巨大な船が、静かに海に浮かんでいる。彼らは本当に安らぎを得たのだろうか?それとも、海に溶けた涙を笑顔で隠しているだけなのだろうか?
今夜が過ぎれば、このディープブルーもいつも通りに戻るだろう。
- 連結縄
- ルサカの双生航路
- 果てしない水平線に残る薄い痕跡でも、この静寂を破るには十分だろう。
航路は船員たちの歴史を運び、水の妖精は水路で希望を追い求める。
水の妖精にとって、水面上の世界は見知らぬ危険な場所であったが、それは古いイメージである。なぜなら水面上にあったものは、すでにこのディープブルーの中に沈んでしまっているからだ。
ルサカの陸生種と水の妖精は、親しいながらも互いを詳しく知らないという不思議な関係にある。陸生種は水の妖精のことを美しく神秘的な存在と表現しており、潜水調査で彼らに出会えることを幸運と考えていた。彼らは青い飛膜と水晶のような黒い瞳を持ち、特殊な声帯で天使のような声を出すという。また、潜水調査員の話によれば、この生物は海龍の傍にいることが多く、深海にある銀白の都市に住んでいるらしい。現実と伝説の狭間に生きる水の妖精は、そこで悠然として生き生きとした姿を見せてくれるそうだ。
大海に沈んだ過去の中で、彼女たちを表現するのに使われた言葉——それは「イーダ人、深海の猛獣」である。
その昔、イーダ人と陸生種が激しい生存競争を繰り広げていた頃、鮮やかな赤に染まった海を無視できる者はいなかった。最初はイーダ人の子供が魚と見なされていたのだが、やがて陸生種がイーダ人の歌に誘われ、水中で溺れ死ぬ事態に発展した。広大な水域で、彼らは互いに狩人と獲物の関係性だったのだ。刃と船の錨、海獣と艦砲の衝突が止むことはなく、水上と水中の長きにわたる戦争は、その熱で岩礁が砕け散るまで続いたのである。それからしばらくして、ステイトシップの学者たちは、万界の癌がはるか昔にルサカの未来を約束していたことを理解した――その約束は故郷を失ったある水の妖精によって交わされたものだった。彼女は悪夢の元凶に無言の呪いをかけたのだ。
その煙のように儚い過去は、深海にある鋼鉄とコンクリートのサンゴ礁群島の奥深くに埋もれている――だが、それを知る者はいない。
その後、都市と陸地、争いと血、さらには歴史と文明までもが大海に沈んだ。そして水の妖精たちは深海の圧力を避けるため、上層の海域に移り、かつての陸生種の都市に住むことを余儀なくされたのである。しかし、笑顔と涙の記憶を垣間見た彼女たちはわかっている…海上にはほとんど音が残っておらず、青は陸生種と妖精双方のものであることを。この静寂はあまりにも重苦しい。
ステイトシップの歌い手は、航路で水色の飛膜を見つけると、その美しい海の歌を歌う――
「彼女たちは航跡を進み、光の塔と嵐を追いかける。ただその純粋な青を取り戻すために」
奇想天外のバナダイス

詳細
- 次元界オーブ
- バナダイスの中央広場
- 次元界オーブの中に封装されているのは、とある科学研究団体が設置した実験室だ。
ミーム汚染によって情報の真偽が徹底的に混ざり合い、識別が困難になったため、今では「バナダイス」として認識されている。
「バナダイスに住んでいる~」
「バナビー!」
「長くて黄色い!元気でキュートな!」
「バナビー!」
「トントン」という音が2回半鳴ると、バナナたちは眠りから目覚め、バナナの木から離れる。こうして新しい1日が始まるのだ!元気いっぱいのバナナたちは、ドリアンのパイを焼き、ジャングルで追いかけっこをして遊ぶ。落ち着いたバナナたちはココナッツミルクを体に塗り、おしゃれをする。サルたちは生き生きとしたバナナたちを満足そうに眺め、思わず甘い声掛けをするのであった——
「バナナたち、準備はいいか?」
「はい、サル長!」
「もっと大きな声で」
「はい!サル長!」
「トントン」という音が3回半鳴ると、毎日定番の「バナニケーション倶楽部」が始まる合図だ。バナナたちは緊張している——大声で叫ぶバナナ、無言で涙を流すバナナ、すべてを諦めたバナナなど、さまざまな反応をするバナナたち。サルたちは健康なバナナ1本1本に質問するが、大きなバナナの葉っぱに書かれている内容はいつも同じだった——「バナナになる前のことは、まだ覚えているか?」
簡単な質問にはいつも苦々しい答えが返ってくる。バナナたちは悲しいという感情がどこから来るのか理解できない…その感情が生まれるのは、バナナが外部からストレスを受けると果肉が参加して黒くなるのと同じくらい当然のことだとしか理解できないのだ。
「あちこち探検するのがお望みなら」
「バナナの木を叩いてサル長に道を示してもらおう」
「トントン」の音が7回半鳴ると、「バナフレンドゲーム」が始まる合図だ。バナダイスにいるバナナたちは、皆こう約束されている——十分な努力を積めば、バナナはいつかバナナを超えた存在になれると。ゆえにバナナたちは夢を抱き、偉大なサルになるため努力を続けているのだ。木々が両側に退き、サル長のために道を開ける。歩いてきたサル長がバナナたちに優雅で謙虚なお辞儀をすると、バナナたちもお辞儀をしてそれに応えた——今回、サル長は新しい物語と「バナチェンジ」するための、新しいゲームを持ってきたのだ。
「トントン」の音が11回半鳴ると、サルたちがバナナたちを木の上に誘導する。バナナたちはゆらゆらと揺れながら理想郷に入っていく…緑色の太陽に照らされるバナダイスは、すやすやと眠るバナナたちでいっぱいだ。
- 連結縄
- バナダイスのミームケーブル
- 実験室の至るところで目にする光信号ケーブル。
ある目的を達成するための実験データの収集に使われている。「バナナたち」にとって、世界を認識する方法がこの中に隠されているのだ。
廃墟となったバナ-77研究所は天滙座-ψに位置しており、とあるジャングル世界の地下に隠されている。過激な巡海レンジャーによって破壊されてしまったものの、その施設に残っているケーブルは、今でも解読不能の信号を発信しているという。
「あのクソったれ研究所の位置を突き止めるのは、ジャングルでたった1枚の葉っぱを見つけるより難しい」——何層にも重なった樹皮の下に埋もれていた入り口。そこから中に入り、長い樹洞を抜けた先で、レンジャーたちはようやくターゲットを見つけた。
そこは「実験室」というよりも、むしろ「美術館」のように見える。ケーブルが空中で複雑に絡み合い、設計者が意図したとおりにさまざまな色の光を放っていた。あまりの眩しさに目眩が起こり、真っ黄色のリミナルスペース、徐々に消えゆく肖像画の列、カーテンの裏に隠された怪物の姿など、さまざまな奇妙な幻覚を見てしまう……
レンジャーたちはこうした手口をよく知っている。施設に留まり続けると、意味不明なことを口走ったり、手足をばたつかせたりといった症状が現れるのだ。若いレンジャーは銃床で自分の頭を思い切り叩き、痛みと目眩を頼りに思考の迷宮から抜け出した。
我に返った後、レンジャーたちは最深部を目指して出発した。バナ-77研究所では至るところに崩れた彫像やボロボロの壁画、彩度の高すぎる色彩の調度品が設置されている。さらに床には何らかの容器の破片が散らばっていて、移動するのが極めて困難だ。やっとの思いで最深部に辿り着いたレンジャーたちは、そこで1部のレポートを見つけた。それを読み進め、建物が倒壊する前に行われていた無数の「認知実験」を想像した、次の瞬間——気がつくと、彼らはジャングルという名の楽園の中にいた。木の葉が彼らに手招きしながら、木の上での生活がどれだけ幸せだったか覚えているかと問いかける。
「俺はバナナだったよな?こんなとこで何してんだ?」若いレンジャーは木に戻ることで「バナ燥感」を抑えようとする。
幸い、目の見えないレンジャーが異常に気づき、手遅れになる前に若いレンジャーを無理やりそこから連れ出した。
「バナナナ——あのサルどもめ、バナくらえ!」
静謐な拾骨地

詳細
- 次元界オーブ
- エイジリアの慰霊祭碑
- 次元界オーブにはオンパロスのエイジリアが封印されている。タナトスを崇める民たちは、雪原に巨大な石碑を建て、「死」の祝福をもたらす聖女を敬う。
エイジリア――そこは雪が舞う死の国。吹雪の中に佇み、吹雪の中で黙する。
長きにわたる黄金紀の中で、人々は温かな大地の上で悠久の生を享受していた。だが、ごく僅かな者たちは停滞する昼夜の繰り返しに飽き、命の終着点を探す旅に出る。「命はなぜ生まれ、どこへ還るのか?」苦行者を率いるエレウシスは彼らと共に甘く冷たい夢を見つけるべく、生死を問う歌を吟唱しながら北を目指した。そうして、長いローブを纏った苦行者たちは静寂に包まれた北境の荒野に定住し、やがて荘厳な都市を作り上げた――雪が年中空を舞うそこを、人々は「エイジリア」と呼ぶ。
黄金紀の終焉に関する記録には空白があるが、オンパロスの「最初の死者」はエイジリアから来たと考えられており、その人物は「タナトス」から死の祝福を受けたという。それはある種の慈悲であり、最高の栄誉でもある。
エイジリアの住民たちはとうの昔に凍り付く寒さに慣れていた。舞い上がる雪も「タナトス」の信仰を静かに受け、地に降りればすかさず温かな命を奪い取ろうとしていた――遥か昔、遠くから来た旅人たちがエイジリアの領土に入るたび、凍り付いた名もなき死体を道端で見かけたという。死者たちはそこで「暗澹たる手」の抱擁に帰り、轟々と吹く北風の中、道しるべとなって行く人に警告する。だからか、ここを通るエイジリアの旅人たちは、命が続いている限り常に先を急いでいた。
後に、エイジリア人は荒れ地に哀悼の石碑が立っていることに気付く。命の流れと消失に祝福を捧げた者が建てたのだろう。
石碑の下には名もない少女が眠っていて、その周りに広がる影のようなものは、死の息吹を吸い込むとされる埋骨草でさえ枯らしてしまう。エイジリア人は彼女から「タナトス」の慈悲を感じ、聖女として城内に迎え入れた。「死」のタイタンを敬愛する信者たちは聖女にならい、荒れ地に巨大な石碑を建て、長い旅路の果てと命の終わりをそこに記した――生と死は同じ道にあり、ここには経路を記録する霊碑しかない。
石碑は遠くから来た旅人に告げる、そこには誰も留まらず、誰も眠らない…死者もまた旅人なのだ。彼らは北風であり、宙に舞う雪であり、無数の糸で結ばれた存在なのだ。
- 連結縄
- エイジリアの冥河の骨連環
- 獣の骨、矢じりと撒菱は、エイジリアを亡者の世界と繋げた。荒野の苦行者は、己の魂が寒さを乗り越えられることを願い、貧しさや弱さは神に会う道での妨げにはならなかった。
かつてある愚者がエイジリアの信者にこう難癖をつけた。「どうしてオンパロスには死を敬愛する信者がいるのだ。そこまでタナトスを愛しているのなら、自身の胸に矛を突き刺させばよいではないか」と。
それを聞いたエイジリア人は軽蔑的なー暼を投げ、こう言った。「貧相な魂ではステュクスは渡れない」。
エイジリアは建立当初からオンパロス全域で最も命を大切にする聖地である。タナトスの信者はステュクスの水が骨の髄を凍てつかせるほど冷たく、並みの人では渡れないと信じていた。この世を長く歩み、数え切れぬ試練を耐え抜いた者だけが、その寒さを超えてタナトスに会えるのだと。「死」の祝福を追い求めることは、命を軽んじることではない。
それ故に、エイジリア人には死を達観している屈強な勇士が多くいた。だが、南の豊かな土地を侵略することは一度もなかった――そこでは英魂を養うことはできないと、エイジリア人はそう考えていた。
苦行はエイジリア人特有の文化である。毎年、雪が止んで空が晴れると、数少ないその日を拾骨祭と呼び、エイジリアの祭司たちは街を出て荒野と沼地に眠る獣の骨を探した。彼らは遥か昔に絶滅した古代の獣の骨を祭礼における最高の品とし、その骨を叩くと重苦しい響きと共に、タナトスの囁きを聞けると伝えてきた。ステュクスの冷気を浴びた獣の骨は次々と街に運ばれ一一わずかに破損したものはアクセサリーとして住民の手に渡り、良質なものは祭司が自らが磨き上げ、葬儀用の骨の剣として奉納されてきた。
ある拾骨祭の日、エイジリア人は荒野で1人の少女に出会いその後すぐ、「彼女との触れ合いはステュクスを越え、死と向き合うことができる」という噂が広まった。
「死」を信じ崇める人々は、タナトスの代行者に会うべく、競うように聖殿へと足を運んだ。エイジリアの祭司たちは少女の存在による信仰の揺らきを察し、彼女を督戦の聖女として崇め、民間人との接触を禁じた。そして、世の艱難を乗り越え、生死を敬愛する苦行者だけが、少女の腕の中で冥土に還れるとし――彼女は祭司が用意したローブを身に纏い、その両手で儀式を執行し、抱擁によって人々を弔った。
エイジリア人は「貧相な魂ではステュクスは渡れない」と信じているが、ステュクスが魂の重さを問うことはない。河はただ静かに流れ続け、すべての生者を定められた終点へと導き、あらゆる魂を交差させるのだ。
深慮に浸る巨樹

詳細
- 次元界オーブ
- 神悟の樹庭の熟慮する根系
- 次元界オープに封装されているのはオンパロスの神悟の樹庭である、「分裂する枝」サーシスの神体がここで熟考をした。「最初の学者」は人々を率いて森の中に花園と庭園を造り、学識を深め、そこに樹庭の始まりがあった。
「最初の学者」セレサスは、成人を迎えると共に故郷の臨海都市ミラワータを発ち、モネータ信仰の霊的意味を探るべく、オンパロスの大地を巡るようになった。
巡礼中に見た不思議な光景やさまざまな体験は、彼の持つオンパロスの自然観や世界の起源に関する考えを大きく変えた。そして旅の終わりには「分裂する枝」に出会い、巨木の前で独自の世界を知る方法を編み出した。その後、セレサスは巨木の下に「神悟の樹庭」という学びの庭を造り、人々が精神を目覚めさせ、知恵を求め、道を見出せるようにした。
サーシスの思考は紙に残されるか、樹庭で静かに揺れる草木となり…活気に満ちた交流や議論が行われる中で、各学派が誕生した。
各学派の研究方向にはそれぞれ違いがあるが、交差がないわけではない――巨木が枝分かれしていくように、時には交差も免れないのだ…諸説紛々とした議論や、何世代にもわたる議論の中で、「最初の学者」が残した思想は脈々と継がれ、七賢人が率いる七大学派を主流とした思想に進展していった。
「世に存在する知識はすべて樹庭の葉となり、木陰を作り、巨木の繁栄を手伝うこととなる」樹庭に理性を求める都市は、相応の知識を捧げなければならない。こうして無数の思考が木の養分となり、新たな芽が生まれる。
光歴100年もの間、商人や隊商が樹庭を通りかかるたび、知識が記載された書物が見つかれば、国や言語を問わずすべて樹庭に収められてしまう。「強盗」とも言える樹庭の学者たちは、大金を払って書物を買ったり、人々を雇って写本させたり、あげく略奪まがいのことまで繰り返し、樹庭を「オンパロスで最も優れた学校」にした。彼らにとって問いは供物であり、思考は敬虔な姿勢となる。この世に君臨する理性を前に、彼らはすべからく頭を垂れるだろう。
命を植え、木の霊に帰る。その流れの中で、集露の心臓は世界に点在する知識を集める。サーシスは活気づいていく学園の声に耳を傾けながら、終始考えに耽っていた。
- 連結縄
- 神悟の樹庭の知を繋ぐ樹路
- 学派の間には研究成果を共有する鍵となる、金糸と藤つるでできた樹庭の知識の網がある。データは根から吸収された後、脈絡に沿って流れ、解析される。最後に一滴の雫となり、友愛の館の池に溶け込むのだ。
神悟の樹庭では、ひとつひとつの思考が巨木の枝となる。その脈絡からは幾千もの論調が生み出され、細かな枝のようにそれぞれ伸びていく。互いに独立していながら、それらはやがて絡み合い、最終的に巨木の樹冠となる。
1本の枝は自らに葉柄を伸ばし、複雑な渦を描くようにねじれている。「蓮食学派」の苦行者は草木や花の持つ神性に魅了され、植生をはじめとした万物を触れられる存在としてみなした。彼らにとって苦行は万物を調和させる実践的な方法であり、決して自我を捨てる行為ではない。むしろ、自らを知る最短の道なのだ。
1本の枝には果実がたくさん実っていた。「山羊学派」の学者たちは、奇獣の研究、繁殖、保護を専門にしている――――キメラの多様で愛らしい姿は、彼らが生命を探求する過程を示した、ある種の縮図といえる。
1本の枝は完璧な比率でねじれ、精緻かつ優美な形をなしている。「結縄学派」の学者たちはこう主張している一一「万物の根源は数である。ゆえに、あらゆる実態数学的に表すことができる」と。彼らは樹庭最初の学派として学院の敷居を守り、「幾何学を知らぬ者の入門を禁ずる」と定め、数理こそがサーシスが世界を支配する手段であると考えている。
1本の枝はよくしなる丈夫な枝だった。「牽石学派」は入門志望者に対し、投石紐を使って特定の距離まで石を投げることを要求した。そうすることで、学者の鍛錬や競技に対する思考や、「極致を追求する」姿勢を見定めていた。
1本の枝はある時は垂れ下がり、またある時は真っすぐに伸び、知覚に純粋な美しさを伝えていた。「赤陶学派」は芸術と感性への探求を論理的思考の根源とみなし、感覚器官から得られる情報が最も精錬されていると考え、そこから達観した世界にたどり着けると強く信じていた。
生い茂る樹冠の中で、巨木の中心に最も近いところに、献身的で敬虔な形をした枝が立っていた。「礼拝学派」はタイタンの儀式の理解や、神跡の運用に精通しており、「オンパロスの政治家のゆりかご」とも呼ばれている。彼らは樹庭の信仰儀式を執り行うだけでなく、その影響はオンパロスのあらゆる面に深く及んでいる。しかし、1本の若く鋭い枝が、それと向き合うように存在していた――
「知種学派」は「最初の学者」の魂に関する教えを引き継いだ、生命と物質の転換や昇華の理論に精通した学派である。また、一番遅く創設されたにもかかわらす最も鋭い論点を持っており、すべての生命と物質の起源を追い求めている。
原則として、七大学派の七賢人はそれぞれの研究分野を持ち、その間に序列はない。理性の巨木は彼ら七賢人の象徴として頂点に立ち、絶え間ない議論と討論の中、世界中に知識と理性の枝を伸ばした。
夢を紡ぐ妖精の楽園

詳細
- 次元界オーブ
- 迷路迷境の夢のツリーハウス
- 次元界オーブの中に封印されたエリュシオンの「迷路迷境」。黄金色の麦をかき分けた先で、あなたはとても深い木の穴に落ちてしまった。おや?小さな妖精がたくさんいる。
「1、2、3、4、5、6、7……」違う!「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シだ!」
「ふふ、子供たち、迷路迷境は今年も収穫の季節を迎えた。何を準備すればいいか分かるね?」村長は白いひげを撫で、ニコニコしながら言った。
「ネクタール祭り!」妖精たちが歓声をあげた。
当初、迷路迷境は何もない荒れた地だった。そこにエリュシオンの少年と少女が外から種を持ち込み、妖精たちに種まきを教えた。種から芽が出て花が咲くと、妖精たちも彼らの真似をし、ブドウ畑の傍を飛ぶ金色の蜜蜂を追いかけて蜜を集めた。そうして花が実を結ぶようになると、妖精たちは歌で収穫を祝い、夜遅くまで賑やかな宴を楽しむようになった。そして、彼らは夜が明けた後──その年にとれた蜜を瓶に詰め、地中深くへと埋めた。それはやがて熟成され、翌年には「成長」と「冬を癒す」不思議な妙薬となるのだ。
毎年、ネクタール祭では同じことを繰り返している。
今年の祭りでは、村長が白いひげを揺らしながら、「誰かレラミュンを見なかったか?」と言っていた。
妖精たちはあちこち探し回り、ついにツリーハウスの入口で「レラミュン」を見つけた。「レラミュン」はスヤスヤと寝息を立て、口元にはよだれを浮かべ、まるで楽しい夢でも見ているかのようだった。不思議に思った「ミュンラミ」が近づき、「レラミュン」の寝言を聞いた──「ファイちゃん…キュレちゃん…約束だよ。今度来たときは、去年埋めたトゲトゲの実のネクタールを…一緒に飲もうね…」
「レラミュン」は、自分が「巨大なレラミュン」に変装して、迷路迷境につながる木の穴を完全に塞いでしまっている夢を見ていた。小さなファイノンとキュレネはどうやっても中に入るための道を見つけられず、イグサで「レラミュン」の耳をくすぐったり、お腹の上で跳ね回りながら名前を叫んだりしていた。しかし、ぐっすり眠っている「レラミュン」にはまったく届いていない。
「もしかして、ファイちゃんとキュレちゃんが迷路迷境に来れてないのは、あたしが道を塞いじゃってたせい……?」
夢の中で、「レラミュン」の心臓がドキっと跳ねた。
「ハ…ハクション!」
「レラミュン」は大きなくしゃみをしてようやく目を覚ました。
幸いにも道をふさぐ「巨大なレラミュン」にはなっていなかったが、自分の周りにいたのは妖精たちだけ。
「ファイちゃんとキュレちゃんは?あの2人は来てないの?」
妖精たちは首を横に振った。ファイノンとキュレネのいないネクタール祭はこれで何度目になるだろうか。
「レラミュン」は肩を落とした。そうと分かっていればもう少し夢を見ていたのに──
小さな「レラミュン」はこの気持ちをどう言い表せばいいか分からなかった。けれど、強いて言うなら…毎年の夏の終わりに、瓶に入っていたホタルたちを空に放してあげる時の気持ちに似ているかもしれない。
- 連結縄
- 迷路迷境の祈りの笛
- 粘土で作られた笛。小さな妖精たちと二人の子供の約束を象徴している。
少年と少女が笛を吹けば、「ミュ?」という声を合図に、妖精たちが迷境につながる木の穴を開き、彼らを招き入れてくれる。
「約束、忘れないでね!あなたたちがその祈りの笛を吹けば、どんなに遠くにいても、必ずあたしたちに聞こえるから」
それはエリュシオンの少年と少女が初めて迷路迷境を訪れ、妖精たちと出会った時のこと。彼らは友達と庭でかくれんぼをしていて、その際にうっかり茂みの奥にある深い木の穴にすべり落ちてしまった。木の穴はとても長く、底の見えない滑り台のようになっていて、彼らは真っ直ぐ滑り落ち、やがて地面に転がった。その際、予想していたような派手な転び方はしなかったが、彼らは妖精たちの山へと突っ込んでしまった。
「1、2、3、4、5、6、7…仔犬がたくさん…って、ウサギ?」
「違うよ。ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、だよ。あたしたちはトラミュン、ソラミュン、レラミュンっていうの!」
子供たちと妖精の友情は、千の流れ星のようにたちまち輝きに包まれ、一緒に楽しい一日を過ごした。しかし、別れの時はすぐにやってきた。子供たちは心配している両親のところへ帰らなくてはならないのだ。
「離れ離れになっても、また会えるよね?」少年が少しだけ寂しそうに尋ねた。
離れ離れ…また会える…妖精たちにはその言葉の意味がよく分からなかった。これまでの迷路迷境には別れも再会もなかったからだ。しかし、子供たちの表情を見て、それがとても辛いことなのは分かった。紫色の「レラミュン」は少し考えたあと、「ファイちゃん、キュレちゃん、ちょっと待ってて。あげたいものがあるの!」と言った。
少年と少女は「レラミュン」からの贈り物を受け取った。それは「レラミュン」が自分で作ったもので、7つの穴があいている妖精の耳の形をした笛だった。それを吹くと「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ」の美しい音色が奏でられたという。「レラミュン」は真剣な表情で、「また迷路迷境に遊びに来たくなったら、この笛を吹いて。あたしたちが寝てても、歌ってても、葉っぱの家を作ってても、この音は必ず聞こえるから。その時は入口の木の穴を開いて、すぐ迎え入れてあげるね」と言った。
「つまり、妖精を目覚めさせる不思議な笛ってことね!」少女はいたずらっぽく笑い、「約束だよ。きっとまた戻ってくるからね」と言った。
それ以来、笛がなると「レラミュン」はこれ以上ないほどに喜んだ。そして、いつも大声で「聞こえたよ!両耳ともちゃんと聞こえた!」と叫ぶのだった。
その後、ファイノンとキュレネはエリュシオンを離れたが、子供時代のことはすべて覚えていた。錆びたブリキのおもちゃ、納屋に転がっていた手足のない兵隊の人形、針で編んだフェルトの花飾り、一度も降ることがなかった雨、乾ききった血、焼け焦げた麦畑──
しかし、土に埋もれた笛と、果たされることのない約束だけは、忘れてしまっていた。
酩酊の海域

詳細
- 次元界オーブ
- 歌響く大海と岩礁の灯台
- 次元界オーブの中に封印された永遠の喜びに浸るスティコシア。永遠に明るい灯台が海辺にそびえ立ち、絶え間なく楽曲を響かせている。だが、賑やかな歌声をたよりに船が霧の向こうからやって来ると、それらは全て座礁して沈没し、残骸もろとも波に呑まれてしまう。
波が終わりのない輪舞のように打ち寄せる中、歓楽の港に飽きた船乗りたちは航海図を開き、自分の旅の終着地を探した。すると、羅針盤の震える針が徐々に静まり、「スティコシア」――海辺にそびえ立つ永遠の歓喜の都を指し示した。そこが運命によって定められた彼らの終焉の地であったが、死を知らぬ者たちはそれを意に介さず、酔いに浮かれながら帆をあげ、ファジェイナの舞踏会場へと足を踏み入れた。
船乗りたちは潮の満ち引きと月の満ち欠けに身を任せ、骨の槍でクジラの背を貫き、衝角で太古の氷河を砕きながら進んだ。だが、歌いながら航海を続けるその船はやがて霧の中へと消え、灯台が目前へと迫った頃…ついに暗礁に乗り上げた。
座礁して沈んだ船は海底へ消えた。だが、不死者たちは波間から蘇り、体に海藻や塩を纏わせながら岩礁に立っていた。灯台の宴を待ちわびている客たちは、水夫を終わることのない宴へと招き入れる。そして、彼らは音楽に導かれるように、岩礁の間に立つ純白の灯台へ登った。スティコシアの灯台の青い炎は、クジラの油を燃料に、水晶でできたレンズの向こうで冷たく揺れている。見ると、灯台そのものが巨大な水溢琴のように、訪問者が階段を上がるたび、石段の隙間を通るガラス管が海水を吸い上げ、波に合わせて上下していた。テラスでは宴の客たちが手を取り合い、楽曲に合わせて火の周りで踊っている。そしてその火は、彼らの影を水平線の彼方まで映し出していた。船乗りはそこでようやくずっと憧れ続けていた終着地――永遠の歓喜の都を目にしたのだった。
それは、腐敗がまだ訪れていない時代のこと。苦痛も悲しみも死もまだ生まれていない頃、スティコシアはファジェイナの寵愛で満たされ、その腕のような入り江に抱かれた街は、童謡のような調べと夢のような優しさに包まれていた。
焦る船乗りの唇がかすかに震える。彼の前では、宴の客が都市国家へ入るよう手を差し伸べ、まるで兄弟のようにこの歓喜を分かち合おうとしている。しかし、彼の背後には灰色の大海原が果てしなく広がっている。岩礁には船の残骸が散らばり、溺れた者たちが波間に漂い、肌は海藻と珊瑚で覆われている。瞬間、彼は自分が海に落ちた時のことを思い出した――海の怪物の冷たい手が頬を撫で、ぼんやりとした優しい歌声が聞こえてくる。そうして再び目を覚ました時、彼はきらめく海面へと押し上げられていた。
ほんの一瞬のためらいの後、至福へと通じる門は閉ざされた。宴の客たちはスティコシアに入りたいという船乗りの頼みをほほ笑みながら断った。彼はまだ酔いから覚めたばかりで、本当の歓喜を受け入れる準備ができていなかったのだ。
- 連結縄
- 歌響く大海と海辺の小道
- スティコシアの人々は信じている。海の怪物が古い言い伝えにある通りに、その肉体をもってこの地の安寧を守り続けていると。そして、いつの日か灯台の歌声に導かれ、再び海を越えてやってくると。その時こそ、尽きることのない饗宴によって彼女たちは報われるのだという。
孤独な船乗りはこれまでの訪問者たちと同じように、大海原と都市国家の間をさまよい、俗世と喜びの入口の境界に立っていた。彼は座礁したクジラの傷口から流れる油を拭い、夜の帳が降りる頃に灯台の明かりをともした。そして、その光の前に腰を下ろし、まだ響いていない調べを水溢琴で奏で始めた。
灯台は琴に呼応するように鳴り響き、スティコシア全土がその音楽に浸った。穏やかな旋律や急な旋律が、スティコシアの女王に享楽にまつわる果てしない想像を呼び起こさせる。船乗りは最後の休符から逆に演奏するようにし、ユニークで躍動感のある調べを奏でた。すると、白く長い船に曲芸師たちが乗り込み、軽やかに水路を抜けていった。盛装し、金箔や羽根で飾られた仮面をつけた男女が両岸にひしめき、女王もその中に混ざっている。彼女はクローブとアーモンドの香りに包まれながら、ゆったりと歩いていた。
船乗りはリズムを整え、音符を激しく急なものへと変えていった。やがて舞台は街全体へと移り、海賊役の民衆が黒い旗を振って無防備な城壁を陥落させ、酒と金貨を略奪し、貴族たちを花で飾った絞首台へ送り込み、王冠を街中の物乞いにかぶせて戴冠させた。フィナーレでは人々が塔に火を放ち、再び琴の調べに合わせて踊り狂い、酔いつぶれるまで酒を飲んだ。
押し寄せる波が楽譜を濡らし、柔らかな音符をにじませた。女王は灯台の前の霧の中で、新たな物語へと足を踏み入れた。彼女は人魚の尾のような青いドレスをまとい、ファジェイナの眷属――海の怪物たちの女王を演じた。
物語では、海の怪物たちは海の奥深くで想像を絶する苦痛から世界を守るよう命じられ、自らの肉体で黒き災厄を満たされた杯に注ぎ、スティコシアに永遠の喜びをもたらしているという。そして、約束の時が訪れると、海の怪物たちは灯台の光と琴の調べに導かれ、堤をたどってスティコシアへ足を歩み入れる。スティコシアの人々は彼女たちの手をとり、共に永遠に終わることのない宴に参加するのだ。
スティコシアの女王は海中へと足を踏み入れ、想像上の死を味わった。月の満ち欠けが波を束縛することのない夜、大海の奥底では、海の怪物たちのうつろな涙が泡のように昇っていた。彼女たちはこれまで一度も見たことのない月明かりをのぞき見ることを切に願い、待ち望み、そして肉体が溶け、消えていった。残念ながら、その夜には月明かりがなく、あったのはいつもと変わらぬ灯台の明滅だけだった――涙が海の怪物たちに代わってきらめく海面へと浮かび上がり、泡沫となって漂っては波に呑まれて消えていった。
孤独な船乗りの願いは遂に叶えられた。宴の客は喜びの涙を浮かべ、彼がスティコシアに足を踏み入れたことを祝福した。だが、最初の歓声があがった時、この永遠の歓喜の都は死と荒廃の翼に覆われることとなった。
永遠の地オンパロス

詳細
- 次元界オーブ
- オンパロスの西風の果て
- 次元界オーブの中に封印された「紡がれた物語」の1章――「永遠の1ページ」。
そこに書かれているのは花々の香りと、西風の温もり…そして開かれた終わりだった。
世の中に永遠の安らぎというものはない。ケファレが掲げる黎明さえもいつかは消えてしまうのだ。永遠が存在するのは、あたたかな記憶の中のみ。
永遠の地――その薄い1ページには、オンパロスの3千万回にわたる永劫輪廻に関するすべての記憶が眠っている。数え切れないほどの昨日が重なり、果てしない明日となった。
そこは静かな楽土であり、西風の果てであり、芽生えたばかりの一筋の記憶でもある。
そこには吹雪も寒さもなく、どしゃ降りの雨に濡れることもない。バラ色の空の下、はらはらと降りゆく花びらが、白銀の浅瀬を埋め尽くしていく。
押し寄せる歴史の波に散っていった人々は、穏やかな住処に身を寄せることができた。ゆったりとした長い余暇の合間に、人々は見たことのないダンスを創造し、かつてない演目を書き上げるようになった。ピュエロスの湯気が漂う中では、英雄や群星について語り合う人々の声が聞こえる。戦争や難民といった言葉は、まるで遠い過去のよう。彼らにも、おぼろげなかつての人生の記憶に感嘆した経験がある。調理師がかつては学者だったり、見知らぬ者同士だった2人が今では伴侶となっていたり……
その昔、黄金裔と呼ばれた人々が歩んだ、喪失の旅路はここに終わりを迎えた。
金織の瞳は再び美しきものを愛し、聖女の手は死の冷たさに染まることもない。瞬足の盗賊はただ喜びのために走り、医師が患者のために涙にくれる日々も終わった。クレムノスの王子はあたたかい家に帰り、エリュシオンからやってきた白髪の少年もまた、戦火に焼かれた故郷の記憶を持っている。だが、目覚めた時には優しい両親に頭をなでられ、どれだけ背丈が伸びたかを測ってもらっていた。
彼らは時折、昼と夜を分かつ回廊を通り抜ける。手の届きそうな距離に感じられる煌めく銀河を、目の前いっぱいに眺めながら。樹庭の賢者はそこで星を観測し、赤い髪の少女たちは流れ星を跳躍する列車に見立てて楽しむ。祝祭がある日には、海洋の歌い手がナナシビトの冒険談を皆に歌って聞かせ、「カイザー」と呼ばれる女帝は、遥か遠い世界にその目を向け、英雄たちに祝福のメーレを捧げるのだ…
未来の種はまだ芽吹いていない。だが、過去に散った花はすでに優しい花の海となって広がっている。
星々を漫遊するその瞬間、ナナシビトはあの期待に満ちた眼差しを感じることだろう。この「永遠」の1ページは、「開拓」の翼に乗って、やがて新たな章へと羽ばたいていくはずだ。
昔の仲間たちが語り尽くすことのなかった想いも、ナナシビトはすでに理解しているのだから――
「……あなたは、あたしたちの物語を連れて、明日へ進んでちょうだい。」
- 連結縄
- オンパロスの永遠なる詩篇
- 歳月をページとし、混沌によって幕を開けた詩篇――「オンパロス」。
黄金の血は抗争という足跡を刻み、火追いの英雄たちは先駆けて創世の偉業に挑んでいた。
歳月をページとし、混沌によって幕を開けた詩篇――「オンパロス」。黄金の血は抗争という足跡を刻み、火追いの英雄たちは先駆けて創世の偉業に挑んでいた。
「門と道」の章では、救世の教えを説き、千の明日が昇り始めた。
「法」の章で、神々と対局し、群星からこの世界を独立させた。
「海洋」の章で、波は砕け散ろうとも千年を見守り、虚無に抗った。
「浪漫」の章では、金糸が火を追う旅を導き、人々の未来を紡いだ。
「紛争」の章は、血と炎の征途。傷痕が孤独の栄光を記した。
「詭術」の章では、嘘が真心を包み、永夜の中で光を照らし続けていた。
「生と死」の章で、迷える魂を抱擁し、生と死の流転を守り続けた。
「理性」の章は、生命を焼き尽くし、その魂をもって世界の真理を問い質した。
「天空」の章では、微光が心を癒し、人の意志で晨昏を繕った。
「世負い」の章では、怒りの炎が檻を焼き尽くし、英雄が黎明の曙光をもたらした。
「大地」の章で、不朽の血脈を溶かし、大地をさまよう命を護った。
「歳月」の章では、幾千万の過去を見守り、けっして忘れることのない記憶を捧げた。
……
3千万回の輪廻で、少女は筆を執り、芽生えたばかりの「心」を記憶で育んできた。そして最後には13の輝きが溶け合い、「愛」の色となったのだ。
流れ星が空を翔ける時、天外より来たる英雄が筆を受け継ぎ、仲間たちと共に再び火追いの旅路へと歩み出す。「開拓」という方法で新たな結末を紡ぎ出していく。
物語の終わりは、花々が咲き誇る永遠の浄土。
夜の向こうでは星がまたたき、昼の向こうでは人々が目をこすりながら目覚めるのだ。優しい西風が吹き抜け、人々は3千万回の輪廻と同じように互いに朝の挨拶を交わす。
そして今ここに、物語の「。」が打たれた。それは、もう目を灼くことのなくなった烈日のようであり、「開拓」の羅針盤のようであり、そして、愛に満ちた眼差しのようだった。
「その世界で、彼らは燃える黄金の血を身体に流し込んだ。けれど…いつか訪れる運命は、彼らの名前を覚えているかしら?」
今、その詩篇の問いはすでに答えを得ている。
黎明に目覚める記憶よ、どうか忘れないでいてほしい―オンパロスの名を。
天国@配信ルーム

詳細
- 次元界オーブ
- 配信ルームの無数のウィンドウ
- 次元界オーブの中に封じられた、無数の配信ウィンドウを持つデジタル空間。
そこは現実と密接に絡み合うバーチャル社会であり、夢のように遠くに感じる架空の都市であり、誰もが覗き、参加できるもう一つの人生である。
「…ログイン…」
『投稿者:riddle』8月7日(金)02:16
■今日、ハナミちゃんの誕生日配信だよね?でも、先月もやんなかった?
『投稿者:炎上中ダヨ』8月7日(金)02:18
■誕生日は8月73日って言ってるけど、そんな日ないですしおすし……
『投稿者:873の糸電話ちゃん』8月7日(金)02:20
■ハナミが新しい投稿をしました「わあっ!プレゼントがこんなに!みんなありがと~♥ついでにハナミの欲しリスも貼っておくから、いっぱいギフト贈ってくれたら嬉しいな~みんな愛してるよ♥」
『投稿者:riddle』8月7日(金)02:21
■だあああ!やっぱオレの財布の中身を根こそぎ持ってくつもりじゃないか…でも、いいんだ!オレのハナミちゃんの頼みなんだから。ああ、オレのハナミちゅわあ~ん!
「リプライ>riddle」『投稿者:カッパゴッド』8月7日(金)02:26
■あなたはさっき通話参加した人ですよね。どうせファンクラブのリーダー気取りであのギフトも送ったんでしょう。僕たちのハナミちゃんにはもうファンクラブがあるんです。いい加減にしてください。
■それに、あなたのIDも調べさせてもらいました。あなたは暴力団の下っ端、つまり犯罪者です。僕が知るわけないとでも思いましたか?
■僕たちと同じようにハナミが好きだというフリをしながら、自分でファンクラブを立ち上げて注目を浴びようとしてるだけでしょう。配信から早く出てってもらえませんかね?
「リプライ>カッパゴッド」『投稿者:riddle』8月7日(金)02:41
■は?誰だお前。お前にオレの何がわかる?少なくともオレは配信に参加した。そう言うお前は何をした?
『投稿者:炎上中ダヨ』8月7日(金)02:45
…あの、まさかとは思うけど、このスレってハナミファンしかいない感じ?アンチは?とりまファンの皆さんは配信ルームへ行ってもろて…
「リプライ…炎上中ダヨ!」『投稿者:\(^o^)/~』8月7日(金)03:00
■ガチアンチ、ここにいまーす!
■計画を立てて、彼女もファンも徹底的につぶそうと思ってる。ネットから追い出すだけじゃなくて、現実でも追い詰めるつもり~
■グルチャのリンクはDMで送ったよ♥
「リプライ…\(^o^)/~」『投稿者:炎上中ダヨ』8月7日(金)03:02
■ども。ただアンチグル、いくつか入ってたけどさ…あいつら普段、仲良しです~って顔してるのに、なんかあるとすぐ内輪もめ始めるんで、もう疲れたんすわ。
『投稿者:873の糸電話ちゃん』8月7日(金)03:03
ハナミが新しい投稿をしました「みんな、おやすみ~♥」
「…ログアウト…」
夜も更けていく中、デジタル空間に生きるならず者たちは好奇心に駆られるまま、あちこちを探し回り、切れ切れの議論を交わし、どっちつかずの態度を見せている…それも最終的に誰かの記憶に残ることはない――
バーチャルキャラクターがバーチャルの誕生日を過ごす。仮想空間の混沌が、混沌とした現実に侵入していく。
- 連結縄
- 配信ルームの自由なチャット欄
- 天国@配信ルームは、決して天国であるとは限らない。
無数のチャットが飛び交い、まばゆい世界を作り出すこともあれば、瓦解をもたらすこともある――それは現実から切り離されたものではなく、むしろ現実の延長線上にあるものだった。
「…ログイン…」
『投稿者:生涯ハナミ推し』8月10日(月)23:22
■ねえヤバいよ!ハナミのあの誕生日記念配信回、あれウソだったんだって!私のスパチャもみんなのスパチャもムダんなっちゃった!
「リプライ>生涯ハナミ推し」『投稿者:オレってくるくるぱー?』8月10日(月)23:24
■今わかる範囲で状況をまとめた――先日、ハッカーがハナミの配信ルームに「RAM休止コマンド」をアップロードして、サードパーティのクラウドサーバーのノードから、こっそりハナミの個人情報を全部コピーしたらしい。で、ハナミ本人はそれに気づかなかった。
■そして、あの日ハナミは一晩中、偽のコメントとおしゃべりしてて、本物の視聴者は一晩中ハナミの配信動画にコメントしていた。
■ハナミは今日になって入金がないことに気付いて、おとといの配信で得た収益がハッカーに取られてたことに気づいた。
「リプライ>オレってくるくるぱー?」『投稿者:世界を救う技術オタク』8月10日(月)23:28
■うそだろ!?送ったリアルタイムチャットも表示されなかったってことだよな…でも、ハナミもコメント欄が偽物だって気づかなかったのか?
『投稿者:873の糸電話ちゃん』8月10日(月)23:33
■ハナミが新しい投稿を更新しました「ハナミ怒ったから!ヽ (o`皿′o)ノこんなの詐欺だもん。もう通報済みだよ~!」
「リプライ>世界を救う技術オタク」『投稿者:生涯ハナミ推し』8月10日(月)23:36
■前にスパチャ送った時、ハナミは「生涯ハナミ推し、スパチャありがと~」としか言わなかった。今回も同じ。
■だから正直、今までの動画を使い回してるって判断するのは難しい。見分けがつかない。まず見分けるのは無理と思ったほうがいい。
■それに、今までも投げ銭しないとスルーされてたから、チャット欄見てても無視してるんだろうなーくらいに思ってたよ。
『投稿者:炎上中ダヨ』8月10日(月)23:50
■サイバー大強盗事件とか草。てかザマア。
■配信ルームにいる人たちって、みんなおしゃべりしてるフリしてるだけでは?実際に会話できてるかなんて、誰もわからないし。気づかないなら何も問題ないでしょ。
「リプライ>炎上中ダヨ」「投稿者:生涯ハナミ推し』8月11日(X)00:01
■もうVライバーにに課金するのやめたよ。
■ハナミと本当にコミュニケーション取ったことなんてなかったんだよね。本心だってもちろん知らないし…配信リアタイしてコメントしたら、リアルタイムでコメントくれるって思ってたんだけど、それは自分を誤魔化してるだけだって気づいたよ。
「リプライ>生涯ハナミ推し」『投稿者:オレってくるくるぱー?』8月11日(火)00:15
■そんな落ち込むな、兄弟。
■たしかにお金はだまし取られたけど、あの日は楽しかった。違う?それなら、あの日のハナミが本物だったかどうかなんて、どうでもよくないか?
『投稿者:873の糸電話ちゃん』8月11日(火)00:17
■ハナミが新しい投稿を更新しました「眠れない夜の配信するよ~!一緒におしゃべりしよ♥」
「リプライ>オレってくるくるぱー?」『投稿者:生涯ハナミ推し』8月11日(火)00:18
■そっか…そうかも。ありがと、配信見てくる!
「…ログアウト…」
配信ルームのカウントダウンが始まり、視聴者数が増え続ける。デジタル世界に生きるならず者はそれぞれの思惑を胸に再び騒ぎ出す。今日もまた1つ、お祭り騒ぎの配信が始まった――
本物の感情もまことしやかな嘘に交じっていく。真相など、ここでは無価値。
コメント
- 鷹胴体のテキストが足のになってる? -- 2023-11-07 (火) 17:34:11
- これ更新されてないのか -- 2023-12-16 (土) 21:53:55
- 鷹胴体のテキストの修正とVer3.1までの遺物を追加しました。 -- 2025-03-24 (月) 18:28:21
![[tip]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/common/image/face/tip.gif?v=4) 投稿ボタンを押す前に、一呼吸置きましょう。
投稿ボタンを押す前に、一呼吸置きましょう。
いつもコメントありがとうございます。
これからも楽しく快適な掲示板にしていきましょう! 
次の投稿は永久BANされてしまいます。確認してみてください… 
- アカウント売買・チート・リークに関するもの
先行プレイの情報はリークとして扱いません - 悪質なバグの拡散、利用の推奨
- マルチポスト
- 暴言・誹謗中傷・侮辱・挑発に該当するもの
- 性的なワード・それらを連想させるもの
- 許可のない宣伝行為
- 晒し行為
- 個人攻撃に該当するもの
![[tip]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/common/image/face/tip.gif?v=4) 違反コメントを見かけた場合、コメントせず通報してください。
違反コメントを見かけた場合、コメントせず通報してください。
該当コメントに枝コメントがある場合は違反コメントごと削除します。繰り返す場合はそのまま同罪として処置します。
これは仕様上コメントが多くなるほど目につきやすくなるためです。ご了承ください。
![[tip]](https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/common/image/face/tip.gif?v=4) 通報について
通報について
zawazawaにログインして通報(推奨)、または管理掲示板まで。
zawazawa掲示板では不快なコメントに対しては、日付横の通行止めマーク🚫をクリックすることで、その投稿者のコメント全てを非表示にできます。
コメント管理基準の議論について: 管理基準判例集
ガイドラインに関してはガイドライン策定・改定掲示板
コメント管理、グループ管理に興味のある方は、管理掲示板までご連絡ください。