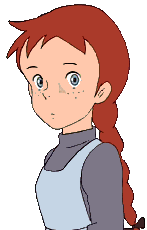10."Anne Takes a Fall"
春になった。次に夏が来た。それでも、アンの完璧に幸せな気分はずっとつづいていた。もちろんちょっとした間違いはあった。豚の餌用のバケツのかわりに編み糸かごにミルクを注いでしまったりだとか、本を読みながら丸太橋を渡ろうとして、足を滑らして川に落っこちてしまったりだとか。けれどそんなことくらい、ほんとうに悪いことのうちにはいらなかった。ケーキを作るとき食用油の代わりに水薬を入れてしまったことでさえ、アンに言わせれば深刻な問題とは言えなかった。そして八月の半ばのある日、ダイアナがあるパーティーを催した。
「よりぬきの人を集めた小さなパーティーよ」と、アンはマリラの問いにこたえた。「なんと、あたしたちのクラスの女の子だけ」
そのとおり、粒選りの人間が集まった、誰もが楽しめるすてきなパーティーだった。その日バーリー家の庭にいた人間にとっては、あんまりにも楽しすぎて、この世に悪や不運というものがあることさえ、信じられなくなるほどだった。もっとも、それもお茶がすむまでのあいだに限って言えばだったが。それまでやっていた遊びにそろそろ飽きて、新しい、別の、もっとわくわくするようなゲームをはじめようとしていたとき、それは起きた。
そのときマリラは果樹園でりんごの木から実をもいでいた。するとダイアナの父親のバリー氏が、アンを背中に乗せて丸木橋を渡ってくるのをみつけた。アンの頭はバリー氏の肩にもたれかかり、ぐったりとしていた。少女たちが列をなして彼の後をついてきていた。
「バリーさん、いったいこの子がどうしたんです?」真っ青になり、恐怖でふるえた声で、マリラは問いかけた。
その声を聞くと、アンは頭をちょっともちあげて、自分自身でこたえた。
「ねえマリラ、あきれるね、なんて言わないでね。ジョーシー・パイが、屋根の梁の上を歩けるか、ってあたしに挑戦してきたの。はしょっていえば、それであたし落っこちたのよ。くるぶしが痛くって歩けないの。でもねマリラ、まずい落ち方だったら首の骨を折るかもしれなかったのよ。物事は常に明るい面をみるようにしなくちゃいけないわ」
「ああ、あんたをパーティーに出してやるとなったときから、こんなことぐらいの予感はあった気がするよ」大いにほっとしながら、マリラはため息をついた。「こっちへ運んでくれますかね。バリーさん、この子をソファに寝かせてやってくださいね」
マシュウが医者を呼んできた。アンのくるぶしの骨は折れていた。
その夜マリラは東の切妻の部屋にやってきた。部屋の持ち主の少女は真っ白な顔色をして、ベッドのなかから弱々しい小さな声で養母を出迎えた。
「ねえ、あたしのこと、すごくかわいそうに思ってるでしょ」
「自分ががぜんぶ悪いんじゃないか」と、窓を閉め、ランプに火を灯しながら、マリラはこたえた。
「それだからかわいそうに思ってほしいのよ」と、アン。「ほんとにぜんぶ自分の落ち度だと思うと、たまらない気になるの。誰かのせいにできたらずいぶん楽でしょうけどね。でもあたしどうすべきだったのかしら。マリラ、もしあなたが――それもジョーシー・パイからよ――屋根の上を歩けるか、って挑発されたらどうするの?」
「あたしはずっと地面の上にいて、おっちょこちょいが屋根の上を歩くのをながめてるだろうね」
アンはため息をついた。
「マリラは侮辱に耐える勇気のある人ですもんね。でもあたしはそうじゃないの。ジョーシー・パイにずっとからかわれつづけるなんて、とても我慢ならないと思ったのよ。もし何も行動しなかったら、一生涯このことで馬鹿にされるに決まってるんだもの。ああマリラ、あたしはもうずいぶん痛めつけられて、罰を受けてるわけだし、これ以上叱らないでほしいの。六週間か七週間はどこへも学校へも行けないのよ。その間ギ、ギル――クラスのみんなは勉強を先に進めちゃうでしょうね。ああ、あたしはかわいそうな子だ! でもマリラ、あなたがこれ以上叱らないっていうなら、あたし今度こそ勇敢に侮辱に耐えてみせるわ。ね、だからね」
「誰も叱りやしないよ」と、マリラは言った。アンの口上を聞いているうちに、苦笑するほかない気分になってしまったのだ。「はいはい、あんたは運が悪かっただけさ。落ち度があったわけじゃない。さて夕食を持ってきてやったんだけど、食欲はあるかね」
「あたしこんなに想像力があって幸せだったな」と、アンはつぶやいた。「もし、骨を折ってどこにもいけなくて、そんな子どもが想像力のひとかけさえ持ち合わせなかったらいったいどうすればいいのかしら。マリラはどう思う?」
それからの七週間、案の定アンは自らの想像力に感謝することしきりだった。とはいえ彼女は頻繁にp見舞い客をむかえていて、学校の女の子たちがあらわれては花や、本を持ってきてくれた。そしてアヴォンリーの子どもたちの間でうわさの出来事を毎日のように運んでくるのだ。
「誰もがよくしてくれるし、とても親切なの」と、アンは幸せそうに息をついて、ベッドから降りた。足を引きずってはいたけれど、しばらくぶりに一人で歩けるようになった最初の日だった。「もちろん寝たきりになるのはゆかいなことじゃないわ。けど、良い面だってあるのよね。自分にどれたけたくさんの友達がいるか、知りたいときには良いかもってこと。ダイアナは毎日来てくれてずっとはげましてくれたのよ。
でもやっぱり、学校に通えなかったのは非常な残念ごとだわ。というのも、あたしが休んでる間に新しい先生がいらしたそうなの。ミュリエル・ステイシー先生よ。ねえなんてロマンチックなお名前かしら? 女の子はみんな、最高にすてきな先生だって思ってる。ダイアナの定期報告によると、驚くほど豪奢な金髪の巻き毛をお持ちで、同じ色の、とてもすてきな瞳なんですって。着物もとってもおしゃれで、その袖はアヴォンリーではだれもみたことがないほど大きくふくらんだパフスリーブだそうよ」
「確かなことがひとつあるようだね」と、マリラはぼやいた。「屋根から落っこちたところで、アン、あんたの舌は傷ひとつ負わなかったんだね」
アン、落っこちる
Last-modified: 2010-07-19 (月) 12:10:40