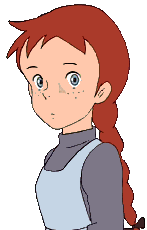7."Diana Is Invited to Tea"
十月になった。十月はグリーン・ゲイブルズの四季の中でももっとも美しい季節のひとつ。カエデの葉が鮮やかな赤に変わり、農場は美しく着飾ってお化粧をした貴婦人のようになる。アンは彼女をとりまく色とりどりの世界に魅了された。紅葉した木の枝を折り取り、自分の部屋を飾り付けるほどだった。
ある朝、マリラがやってきて、互助会の寄り合いで少し離れた町まで出かけるので、昼間は留守にするとアンに告げた。「暗くなるまで帰ってこれない。マシュウの夕食の用意はあんたにまかせたよ。そのかわり、午後のお茶にはダイアナを招待するといい」
「ああ、マリラ」アンは飛び上がってよろこんだ。「それってあたしがいま一番やりたかったことよ。まるで大人の女性になったみたい。すっごくいかしてるわ。ねえあの一番上等の、かわいらしいティーセットを使ってもいいかしら?」
「だめ。とんでもないこという子だね。いつも使ってる茶色のやつでじゅうぶんだよ。けれどそうだね、チェリーのジャムのふたを開けていいし、この前のケーキとクッキーの残りも食べてよしとしよう」
「すばらしいお茶会になるわ。ダイアナを招いたら、居間に通していいかしら? 居間のテーブルにお皿を並べたいの」
「それもだめ。あんたとあんたのお客様は、台所を使うことになってるんです。でも台所には以前用意したいちご水が残ってるから、あんたたちが好きなら飲んじまってかまわないよ」
アンは大興奮してダイアナの家まで飛んでいき、お茶会の約束をとりつけた。その後マリラが馬車に乗って出かけてしまうと、すぐにダイアナが彼女の持っているうちで二番目に上物のドレスを着て、まるで貴婦人のような上品な所作でグリーン・ゲイブルズのドアをたたいたのだった。アンもまた二番目に良いドレスに身を包み、ドアをゆっくりと開けた。二人の少女はあたかも長い間会っていなかったかのように、感動的に手を握りあった。
二人は午後のほとんどを屋外ですごした。果樹園のりんごを食べながら、ものすごい、できるかぎりの勢いでおたがいにしゃべりあった。とくにダイアナにはたくさん話すことがあった。アンが学校に来なくなってから、彼女の隣の席には今はガーティー・パイが座っていて、それがたまらなくいやなこと。みんなさみしがっていて、アンに戻ってきてもらいたいと思っていること。そしてギルバート・ブライスは――
とダイアナが話しかけたが、アンはギルバート・ブライスのことなど名前を聞くことすら嫌だったので、さっと立ち上がろ、家に入っていちご水を飲もうとダイアナをうながした。
台所に戻り、マリラに聞いたところをアンはよく探したが、いちご水は見つからなかった。捜索範囲を広げると、やっと棚の一番上にあるのが見つかった。お盆にコップを用意して、テーブルの上に並べた。
「さて準備ができました。ではダイアナ、召し上がってね」アンはおしとやかにすすめた。「りんごをたくさん食べたから、わたしはいまのところほしくないの」
きれいで魅惑的な赤色をしたジュースをコップに注ぐと、ダイアナはなめるようにして少しだけ味をたしかめた。「あらこれすごくおいしいわ。ちょっとおそろしいくらい、ひどくおいしいわ。木いちごのジュースがこんなにおいしいなんて知らなかったわ」
「好きなだけ飲んでいいのよ。あたしはちょっと失礼して、暖炉に火をおこしてくるわね。家のきりもりをしている者はいろいろ気を配らないといけないのよ。そうでしょ?」
アンが戻ってくると、ダイアナはすでに二杯目のグラスをからにしていた。
「あらあら、よっぽどおいしいのねえ! もう一杯いかが?」
ダイアナはまたグラスいっぱいにジュースを注ぎ、「こんなおいしいものはじめてよ、ほんとうよ」と言った。
「マリラはアヴォンリーのなかでもそうとうな料理上手ですからね」アンはこっくりうなずいた。「マリラはあたしにも、その料理の腕前をしこもうとするんだけど、でもとてもむずかしいの。料理の手順には想像力をはたらかせる余地がないんだもの。なにもかも決まりにしたがわなければならないのよ。一番最近にケーキを作ったときなんか、小麦粉をいれるのを忘れちゃった。そのときね、ダイアナ、あたしとあんた二人のすてきな物語を考えていたのよ。おかげでケーキは完全に失敗。ケーキ作りに小麦粉を忘れるなんて、なんというかもう、問題外よね。マリラはかんかんに怒ったけど、もっともだと思うなあ。あれダイアナ、どうかしちゃった?」
ダイアナは突然立ち上がり、そのまままた座りなおした。頭をかかえるようにして身をかがめていた。
「あたし――あたし、病気になっちゃったみたい」小さな、かすれてくぐもった声で、ダイアナは言った。「家に帰らなくちゃ」
「いやよ、またお茶会が終わってないじゃないの。家に帰るなんて、夢でもそんなこと言っちゃいやよ」アンは叫んだ。「ちょっと待ってて、すぐお茶をもってくるからね」
「家に帰らなくちゃ」ダイアナは繰り返した。「ひどいの。くらくらするの」
アンは悲しみのあまり目に涙をためつつも、ダイアナの帽子をとってやり、いっしょに歩いてバリー家の柵のところまでダイアナを送った。グリーン・ゲイブルズへの帰り道ではしくしく泣いてしまった。木いちごのジュースの残りをもとのところに戻すと、すっかり力をおとして、マシュウのためにお茶のしたくをした。
翌日は日曜日で、朝から晩まで雨がざあざあ降っていた。アンは家から一歩も出ずひきこもってすごした。月曜日の午後にマリラがアンをお隣りのリンド夫人のお宅までおつかいにやると、行ったが早いか、まもなくアンは飛ぶような勢いで小道を走って帰ってきた。頬を涙の粒がつたい落ちていた。
「いったいぜんたいどうしたってんだい?」マリラはたいへんにおどろき、いぶかしげにたずねた。
アンは泣くばかりで返事もしなかった。
「アン・シャーリー、質問にこたえなさい。あたしは答えられないことは聞いてないつもりだよ。気を落ち着けてここにおすわり。ねえ、どうして泣いているんだか教えておくれ」
おとなしく座りこむと、アンは話しだした。「リンドの小母さんから聞いたの。ダイアナのお母さんが、ひどく怒ってるんだって。あたしが、土曜日にダイアナにお酒を飲ませて、酔っ払わせてみっともないありさまにしたからだって。あたしのようなとんでもなく悪い子は二度とダイアナと遊ばせない、って言っているそうよ。ああ、あたしはいま、深い深い絶望にとらわれているのよ。ああ、マリラ」
マリラは驚きのあまり目をまんまるにして、「ダイアナが酔っ払っただって?」とやっとこさ声を出した。「アン、あんたとバリー夫人と、気がおかしくなったのはどっちなんだい? あんたダイアナに何を飲ませたの?」
「いちご水のほかにはなんにもよ」かみつくような声でアンはこたえた。「いちご水で酔っ払うなんて思ってもみなかったもの。たとえダイアナみたいに大きなグラスで三杯も飲んだって。どうなるかなんて知りっこないわ」
「いちご水で酔っぱらう、だって? まったく聞いてあきれるね!」とマリラは言い放つと、足音を高くしてずかずか台所へ向かった。棚の上の以前にたしかめたのと同じところに、彼女の手作りのぶどう酒のびんがあった。マリラは葡萄酒作りでもアヴォンリー有数の名人として有名なのだ。そしていちご水はアンに話した戸棚ではなく、地下室にしまっていたことをマリラは思い出した。
ぶどう酒のびんを片手に抱え、マリラは居間へとってかえした。口元にはおさえきれない微笑がうかんでいた。
「アン、あんたはたしかにやっかいごとをひきおこす天才だね。あんたはダイアナに葡萄酒を飲ませちまったのさ。それにしても、ちがいがわからないもんかね?」
「あたし、一口も飲まなかったんだもの」と、アン。「ジュースだとばかり思ってたし、一生懸命おもてなしするつもりだったのよ。ぶどう酒を飲んだせいで、ダイアナは酔っ払って病気のようになっちゃって、家に帰ったっていうの? あの日のダイアナはまるで死んだように酔っ払ってたって、バリーの小母さんは言ったらしいわ。あたしが最初からそのつもりだったんだろうって」
「馬鹿をお言いでないよ。あんた、夜にでもひとっぱしり出かけて、何があったかほんとのことを話してやるといい」
「あたしが、バリーの小母さんに? いやよ、顔を見る勇気もないわ。ああマリラあなたが行ってくれると、とてもうれしいんだけど」
「そうだね。あたしが行くのが良いだろうね」と、マリラはうけおった。それがもっとも賢いやり方だと思ったのだ。「だからね、アン、もう泣くのはおよし。すべてうまい具合にいくからね」
が、バリー家から戻ったとき、マリラの心はまったく反対方向に変わっていた。アンはマリラが戻ってくるのを窓から見張っており、ドアに飛びつくようにして出迎えた。
「ああマリラ、何も言わなくても、あなたの顔を見ただけでわかるわ。悪いお話を聞かされるのね」悲しそうにアンは言った。「バリーの小母さんはあたしを許さなかったんでしょう」
「ふん! まったくもってね!」と、マリラは憤慨した様子だった。「まったくもって石頭の、気難し屋の奥さんだよ。あんな女は見たことないね。今まで会ったなかでいちばんの難物さ。ぜんぶ手違いで、あんたが悪いんじゃないって教えてやったのに、あたしの言うことをひとつも信じないんですからね」と言い放つと、ドアのところにアンを取り残したまま、マリラはさっさと台所に引っ込んでしまった。
けっきょくアンは自分自身でオーチャード・スロープのドアにすがりつき、許しをこうことになった。けれどアンを出迎えたのは、バリー夫人の親愛さのかけらもない、冷え切った表情ばかり。「何かご用かしら?」とすましてたずねる声には怒りが込められていた。
「ああ小母さん、どうか許してください。こんなことになるなんて、土曜日のあたしにはわかっちゃいなかったんです。想像してほしいの。ねえどうしてあたしにそんなことができましょうか? もし小母さんがかわいそうなみなしごで、奇跡のような幸運で親切な人の家に引き取ってもらえたとします。そして世界でたったひとりの大切な大切な友達に出会うの。その友達を酔っ払わせちまおうなんて、どうして考えるでしょう? あたしはあれをいちご水だとばかり思ってたんです。信じてください! ダイアナとまたいっしょに遊ばせてほしいの!」
このスピーチはバリー夫人の心をやわらげることになんの効果もあげず、かえって怒りをかきたてるだけに終わった。夫人はアンが自分をからかっているのだと考えたのだ。冷たく残酷に、夫人は言いわたした。「ダイアナの交際相手として、あなたはまったくふさわしくない女の子だと思うわ。お帰りはあちらですよ」
深い絶望に身を切り刻まれながら、アンはグリーン・ゲイブルズへと引きあげた。
「最後の希望もついえてしまったわ」と、アンはマリラに心中を語った。「祈るよりほかにすることないように思う。けど、それも望み薄ね。だって神様だってあの小母さんみたいな石頭の女を、うまくあつかえるとは思えないもの」
「そういうことを言うものじゃありません」マリラがきつくたしなめた。
けれどその夜、やすむ前にマリラは東側の切妻の部屋にやってきて、泣きながら眠ってしまったアンの顔を見つめていた。いつもは固く引き締められているマリラの表情が、ふとやわらかくなった。
「かわいそうな子」と彼女はつぶやいて、アンの頬にかかんでキスをした。
ダイアナをお茶に招く
Last-modified: 2010-07-19 (月) 08:49:12