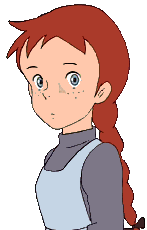13."Marilla Makes Up Her Mind"
次の朝目覚めると、窓の外で桜の花が満開に咲いているのがアンの目に飛び込んできた。アンははね起き、ベッドから飛び降りると、窓を全開にして六月の朝の空気を胸いっぱいに吸い込んだ。よろこびに満ちあふれた瞳がきらきらと輝いた。
ああ、なんてすてきなところなんだろう? ほんとうはここにはもういられないんだけど、とアンは考えた。まあかりにいられるとして想像してみよう。想像のしがいのあるところだし。アンはこれまでひどく殺風景な景色ばかりをみてきた子どもだった。けれどグリーン・ゲイブルズの窓から見える農場の木や野原はたいへんに美しく、心をふるわせるものだった。アンがいままで想像の中で夢見てきた景色と、そっくり同じだった。
さて、昨日の夜話したように、今日はスペンサー夫人に会って、間違いを問いたださなければならない、とマリラはアンとマシュウに告げた。そしてアンを連れて馬車で出かけた。グリーン・ゲイブルズ門の下をくぐるとき、アンは心を決めた。
「あたしこのドライブをせいぜいいっしょうけんめい楽しむことにするわ」と宣言したのだった。
「なんでもそうだけど、楽しもうとかたく決心すればきっと楽しくなれるのよ。いままでずっとそうだったもの。つまり、この馬車に乗っているあいだは、孤児院に戻ることなんか考えないでおこうと思うの。
ああ小母さん、野生の薔薇が咲いてるわ。見ました? 最高にきれいだったわ。薔薇がおしゃべりできたらきっとすてきでしょうね。それにピンクって世界で一番魅力的な色だとあたしは思うんです。でもあたしの髪はこんな赤毛だから、ピンク色の洋服を着れないの。赤い髪にピンクの服なんて、想像しただけでなんともまずい気持ちになるわ。ねえ小母さん、こどものころ赤毛だった女の子が、大人になったら色が変わって別の色になることってあるでしょうか?」
「そんな話聞いたことないね」と、マリラ。「それに、よしんばあるにしたってあんたの身には起こりそうにないね」
「ああまた希望がひとつ、消えてしまった」アンはため息をついた。「あたしの人生ってほーんと"うずもれた希望の墓場"よね。これ、いつか本で読んだ文句なんです。何かにがっかりするたびに、こう言って自分を慰めているの」
「そんなのが慰めになるとはとても思えないけど」
「だって響きがきれいだし、幻想的な印象のある言葉だわ。アヴォンリーって村の名前もそうだけど、アヴォンリー、アヴォンリー、アヴォンリー。まるで音楽みたいな名前だと思います。ええとスペンサー夫人のお宅まで、あとどれくらいですか?」
「五マイルくらいかね。しかしあんたよほどしゃべりたいみたいだから、身の上話でもはじめたらどうかね。自分のことを、はじめからなんでもかんでもあたしに教えてくれるといい。どこで生まれて、いまいくつなの?」
「この前の3月で11歳になったの」と、アンはこたえはじめた。
「生まれはノヴァ・スコシア州のボリングブロークです。両親はどっちも高校の教師だったの。二人とも若くて、あまりお金を持っていなかったそうです。あたしが三歳のとき母さんが熱病で死んじゃって、父さんもあとを追うようにして、その四日後に同じ熱病で死んでしまいました。
孤児になったあたしをトーマス夫人がひきとってくれました。彼女はあたしのことを、いままで見たなかで一番醜い赤ん坊だ、って言ってたそうです。8歳のときまでわたしはそこにいて、4人のこどもの面倒をみていたわ。でも、トーマスの旦那さんが死んじゃって、夫人がこどもをつれて実家にもどることになると、わたしはついていかれなかった。
その次にはハモンド夫人のところで、8人のこどものお世話をしました。おそろしいことに、ハモンド夫人は三回も双子を生んだのです。二年間そこにいました。つまり、一家がアメリカに引っ越しちゃうまでのあいだね。
それから引き取り手のあらわれなかったあたしは、孤児院に行くしかしようがなかった。孤児院でだって、今は満員だからといってあたしを受け入れたくなかったみたいだけど、でも彼らには義務がありますからね。それでわたしはスペンサー夫人がやってくるまでの四ヶ月間、そこにいたってわけです。おしまい」
アンは大きなため息とともに、身の上話を終わらせた。想像の世界とは違って、この現実世界では誰も彼女をほしがってなどくれない。だから身の上話なんてするのは、たまらなくいやなものだった。
「学校には行っていたの?」と、マリラは質問した。
「いいえ。いつも、学校に行くには遠すぎるところだったし。ああ孤児院のときはのぞいてね。あたし本を読むのがとても得意なんです。いままで読んだすてきな詩をいくつも胸にしまっていて、暗唱できるのよ」
「あんたを引き取ったそのご夫人がただけどね、トーマス夫人とハモンド夫人。彼女たちは、あんたによくしてくれたかい?」
「ああ」アンの顔色がさっと赤くなった。「そうね、二人ともそう思っていたのにちがいはないのよ。よくしてくれようって二人が思っていたのを、あたし知ってるわ。でもみんなそれぞれ心配事をかかえているものですからね。だから、よくしてくれようと思っていたことは実際にそうしたのと同じようなことなのよ」
マリラはそれ以上聞こうとはしなかった。目を馬車の前に向けると、唇をひきしめ、真面目な表情になった。心のうちに、このかわいそうなこどもに対する、あわれみの気持ちが育ちつつあったのだ。この子をうちにおいてやることはできるだろうか? 思っても見なかったことに、マリラは検討を始めていた。
「この子はすこしおしゃべりがすぎる」と、マリラは考えた。「それについてはしつけが必要だろう。けれど下品で荒っぽい言葉はつかわないし、ものごしがしとやかだ。その点については周りの人々も立派だったんだろうね」
その後はスペンサー夫人の黄色い大きな家に着くまで、二人は黙ったままだった。夫人の家はホワイト・サンドの海沿いにあった。ドアをあけてマリラがすがたを見せると、夫人の人のよさそうな顔に驚きと歓迎の表情がいっしょに浮かんだ。
「あら、ようこそマリラ。今日いらっしゃるなんて思ってもみなかったけど。こんにちはアン、うまくやってるかしら?」
「あまり長居はしませんよ。スペンサーさん、どうも間違いが起きているようだから、どこでどうかけちがったのかたしかめに来たんですよ。あたしたち、マシュウとあたしは、孤児院から男の子を連れてきてほしいってたのんだはずなんだけど」
「まあ、何を言うのよ!」スペンサー夫人は驚き、それから申し訳なさそうに付け加えた。「わたしはあなたたちが女の子をほしがってるって聞いたんですよ。ひどい間違いだったのね。ごめんなさい、けどわたしも、あなたたちのご希望に沿うようにとできるだけ運動したんですからね。さあお入りになって。この問題についてはよくよく話し合わなければ」
お客を居間に招き入れると、スペンサー夫人は「さて、しゅびよくものごとを正したいところね。マリラ、ええと、ミス・カスバート。あなたはそこのひじかけ椅子に座ってちょうだい。アン、あなたはあそこの長椅子がいいわ」とそれぞれの席を割り振った。腰を下ろすやいなや、
「ねえこれはあたしたちの失敗だったね」と、マリラが口を開いた。「口伝えなんかにしないで、ちゃんと自分たちであんたのところに話を持ってくるべきだったんですよ。とくにこんな大切な用件のときはなおさらそうです。けどもう間違いは起きてしまったんだから、何かうまい方策を考えなければね。この子をもとの養護施設に帰すことはできますかね?」
「そうね、できると思うわ」と、スペンサー夫人は考え考え話しだした。「けど、そうする必要はないと思うの。昨日ブレウェット夫人が、家の手伝いをする女の子をよこしてくれないかってわたしにたのんできたんですよ。彼女の家はたいへんな大家族ですからね。アンはぴったりだと思うわ」
マリラはアンを見やった。彼女の顔は悲しみに曇り、馬車の上で薔薇について話していた時のような輝きのいっさいが消えてしまったようだった。マリラは自分の心臓がやわらかくなったように感じた。それから自分の見ている女の子によって、どくんと動かされたように感じた――アンはまるで、一度逃れたと思った罠に再度かかってしまった、小さな動物のようだった。彼女が助けを求めていることをマリラは理解した。そしてマリラは、ブレウェット夫人をけして好いてはいなかった。
「納得いきませんね」マリラはゆっくりとそう言った。「あたしはこの子を手元におかないことにした、なんて、一言も言ってないですよ。じっさい、マシュウはこの子といっしょに暮らしたがってるんです。スペンサーさん、ここに来たのはね、間違いがどこで起きたのか、はっきりさせたかっただけなんですよ。さてそろそろおいとまして、兄さんと相談したほうがいいようだ。もちろんこの子は連れて帰りますよ。今日のところはね」
この言葉を聞くとアンは立ち上がり、部屋のまんなかを横切ってマリラに飛びついた。「ああカスバートさん、ほんとうにそう言ったの? わたしをグリーンゲイブルズにおいてくれるかもしれないって、ほんとうにそう言ったの?」息もつけない様子で、ささやくような小さな声でアンはつづけた。「ほんとうに? あたしの想像のなかの出来事じゃないのよね?」
「その想像とやらをどうにか始末したほうがいいね」すこし怒ったような口調でマリラは言った。
「あんたはあたしの言ったことをちゃんと聞いたんだから、二度とは言いませんよ。それにまだ決めちまったわけじゃないんだ」
「あたし精一杯がんばります。あなたの言葉のとおりになれるよう、あなたの言うことはなんでも聞くし、してほしいことはなんでもするわ」
二人がグリーン・ゲイブルズに戻ったのは、その日の夕方になってからだった。
気が気でならなかったマシュウは、家の中では待っておれず、農場から母屋へ続く小道の途中で待っていた。マリラがアンを連れて帰ってきたのを見て、とてもほっとしたようだった。「わかりやすいこと」とマリラは思った。けれどアンがそばにいるうちは、マリラはなかなか口を開こうとせず、今日のことをすっかりマシュウに話したのは兄妹二人きりになってからだった。農場の納屋の影に隠れるようにして、マリラは少しずつアンの身の上や、ブレウェット夫人が女の子をほしがっていたことなどを話しだした。
「たとえ犬一匹だって、あんな女に、わしの可愛がっているものはくれてやるもんか」と、マシュウは常にない様子で怒ったように口にした。
「あたしもそう思います」と、マリラ。
「それに兄さんがあの子と暮らしたがってるのはわかっていたからね。ねえ、マシュウ・カスバート。あたしに限って言えばですけどね。アンをここにおいてやってもいいと思ってるんですよ」
マシュウの顔がよろこびに輝いた。「お前がそう思ってくれればいいって思ってたよ。あの子といっしょにいるととても楽しいだろう。わしらにとってめったにない喜びだ」
「ええ楽しいのはけっこうですけどね。あたしはちゃんとしつけをするつもりですからね。こまごましたことを何でもこなせるよう、役に立つよう仕込んでやります。兄さんはあまり口を出してくれますまいね。もしあたしがしつけに失敗したらそのときになって出てくればいいんであって、それまでは出番はありませんよ」
「そうするといいよ。お前の思うとおりにするといいよ。だけどまあ甘やかさない程度にやさしくしてやっておくれ。わしがみるところ、あの子はお前になつきさえすれば、ちゃんと言うことを聞く性質の子だと思うね」
次の日の朝、自分だけがよく知っている理由により、マリラはアンに何も伝えず、次々と用事を言いつけてこきつかった。アンが手伝いをどのようにこなすか観察していた。それでお昼になるころにはいちおうの評価がさだまった。アンは物事を手早く、上手にすませることができるし、仕事に喜びを見出し、自分からやることを探すこともできた。けれどときどき夢を見ているような顔つきになって、大事な仕事の途中でも手を休めてしまうことがあった。そんなときはたいてい想像の世界に落ち込んでしまっていて、やるべきことをすっかり忘れてしまうのだった。
もちろんアンのほうは自分の身の上における最重要の問題を忘れてしまったわけではなかった。午後になると、もう矢も盾もたまらず、「ああ、カスバートさん、お願いよ」とマリラにすがりついた。すっかり恐怖におののいている様子だった。
「やっぱりわたし、孤児院に送り返されちゃうんでしょうか。もしくは、昨日のあの錐のようなご婦人のところに行かされちゃうの? あなたから言い出してくれるまで我慢しようとがんばったけど、もうだめです。これ以上、こんな気持ちに耐えられません」
「アン、あんたはまだ皿ふきを洗い終わってないだろう。お湯で洗うよう、あたしは言いつけたつもりだけどね」と、つとめて冷たい物言いで、マリラは言った。「ものをたずねる前に自分の仕事を終わらせなさい」
アンはマリラにくるりと背を向けると、言われたとおりに皿ふきを洗い、また戻ってきた。
「できるだけ行儀よく、あなたの言いつけをきかなきゃって思ってたけど」マリラをじっと見つめる目にはうたがいの気持ちがこもっていた。さて、これ以上ひきのばすのもそろそろ無理みたいだね、とマリラは思った。
「あたしたちはあんたをここにおくことに決めたよ。もしあんたがいい子でいて、このことを感謝してくれるならね。
ちょっと、どうしたんだい」
「わたし、泣いてるの」アンは泣いていた。
「でも、どうして涙が出るのかわからないの。こんなにうれしいのに、こんなにしあわせなのに」
「まあ、おすわり。おちつくといいよ」と、マリラは自分でも椅子に腰掛けながら、アンをなだめた。
「あんたは泣くのも笑うのもかんたんすぎて、あたしはちょっと心配だよ。あんたはここに住んで、秋になったら学校に行くんですよ」
「ねえマリラ伯母さんって呼んでいい?」と、アンはたずねた。
「だめ。みんなと同じく、ただの"マリラ"と呼びなさい」
「でも、ほんとうの叔母さんみたいに思うんだもの」
「あたしは思わない」と、マリラ。
「ほんとうにははそうじゃないことでも、そうだったらいいな、って想像することあるでしょう?」
「ないね」
「もう!」アンは長いため息をついた。「もう、ミス・カスバート、じゃなかった、マリラ。想像することがひとつもないなんて、そんなのひどくつまらないわ」
「あたしは想像上の出来事なんて信じませんからね」と、マリラ。「そしてアン、あたしが何か物事をいいつけたら、あんたは聞き分けよく、いちどでそのとおりにしなけりゃいけないんだ。おわかり?」
マリラの決心
Last-modified: 2010-07-19 (月) 08:47:43