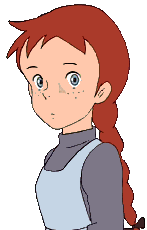6."Anne Shows a Temper"
アヴォンリーの学校の新学期が始まるころには、アンとダイアナはすっかり仲良しになっていた。何をするのもいっしょだった。アヴォンリーの学校へは森を抜けていく道を通る。アンはこの道を歩くのが大好きだったし、ダイアナといっしょに学校に行くのを、ほんとうにすばらしく思っていた。アンは学校では優等生で、入ってすぐにクラスで一番の成績になった。「あたし学校って大好きよ」と、ダイアナにもマリラにも、マシュウにも話した。日に日に強く思うようになっていた。
ある日、いつものように二人がいっしょに学校へ向かっていると、「今日はギルバート・ブライスが学校にくると思う」と突然ダイアナが言い出した。
「夏の間ずっとニュー・ブランズウィックのいとこのところに行っていて、土曜の夜に帰ってきたの。とってもハンサムだけどいたずら好きで、女の子をひどくからかってはよろこぶのよ」付け加えるように言ったが、まるでダイアナ自身がからかわれるのをよろこんでいるようだった。「頭が良くて常にクラスのトップだったわ。彼が来たからには、あんたが一番でいるのも今までほどかんたんじゃないでしょうね」
「望むところよ」すぐさまアンは言葉をかえした。打てば響くような応答だった。「そもそも、小さな子たちにまじって一番でいたってさしてすごくもないじゃない。でもね、わたしは昨日もつづりのクラスで一番だったのよ。ジョーシー・パイがずるをしてたのに、それをおさえてね」
「パイ家の子はみんなそう。しょうがないのよ。あ、それより、あれがギルバートよ。ねえハンサムでしょう?」
ギルバートは背が高く、茶色の巻き毛に茶色の瞳の少年で、口元にはいたずらそうな、人を馬鹿にしたような微笑がうかんでいた。ギルバートはこちらを振り向くと、アンに向かってウインクし、そのまま通り過ぎて学校に入っていった。
「そうね、たしかにハンサムね」と、アンは認めた。「でもお行儀は良くないわね。はじめて会う女の子にウインクするなんて、良い作法とはいえないわ」
その日の昼休みになるまで、ギルバートはあの手この手でアンの注目を集めようとしたが、アンは彼を避け続けた。けれど正午になってアンが窓の外に目をやり、想像の世界に心を羽ばたかせていたときだった。ギルバートがそばによってきて、手を伸ばし、アンの三つ編みのはしっこをつまみあげた。
「にんじん、にんじん!」彼はささやき声で、しかしはっきりと聞こえるように言った。
アンははじめてギルバートに向き直り、正面から見つめた。怒りのあまり瞳は涙で濡れており、きらきら光っているのが火花のように見えた。それからぴょんと飛んで立ち上がった。「なんて言ったの。信じられない、あんたなんて大嫌い! なんて言ったの!」それからパリーン! と音がして――アンはまっすぐ、自分の石盤をギルバートの頭に振り下ろし、まっぷたつに割ってしまった。
教室のみんなは「ひゃあ!」とさけび、怖いもの見たさに色めきたった。ダイアナは息が止まりそうなくらい驚いた。担任の教師である、フィリップス先生がつかつかやってきて、アンの肩に重々しく手を置いた。
「アン・シャーリー、いったいどうしたことかね? 説明しなさい」と、怒りをこらえるような調子で先生はたずねた。
アンはなにも答えなかった。学校のみんなに"にんじん"呼ばわりされたことを知られるなんて、耐えがたいことだった。
ギルバートが進み出て、「フィリップスス先生、僕が悪かったんです。僕が彼女をからかったんです」とはっきりと言った。しかしフィリップス先生は彼には注意を払わなかった。
「こんな短気な生徒がわたしのクラスにいるとはとても残念です。アン、昼休みが終わるまで、黒板の前に立っているんだ。さあ行きなさい」
怒りのあまり真っ青になった顔で、アンはその言葉にしたがった。むちで打たれたほうがまだましなくらいだった。その上、フィリップス先生は黒板に、アンの頭の上を指すようにしてチョークで書き加えた。「アン・シャーリーは自分の短気をなおさなくてはならない」そして教室じゅうに響きわたるような大声でそれを読み上げた。
アンは言われたとおり、昼休みじゅうそこに立っていた。泣かなかったし、うつむいて下を向くこともしなかった。怒りのこもった目で教室を見回し、ダイアナの気の毒そうな顔や、ジョーシー・パイの意地の悪そうなにやにや笑いを見つめた。ギルバート・ブライスは? アンは彼のほうをちらりとも見なかったから、どうしているかわからなかった。ギルバートなんか見るのも汚らわしい。二度と口をきかないだろう!
授業が終わると、アンは赤毛をことさら高く持ち上げてずかずか教室を出て行った。ギルバートがドアのところで待ち構えていて、「ほんとうにごめんよ。ちょっとからかっただけのつもりだったんだ。ねえ許しておくれよ」と小さな声であやまった。
が、アンは一瞥もくれず、さっさとその場を通り過ぎた。謝罪の言葉のひとかけらも聞いてはいないようだった。「あたしは生涯にわたってけっしてギルバート・ブライスを許さないわ」いつものようにいっしょに家に帰りながら、アンはダイアナに宣言した。「彼はこれ以上なくひどく、あたしの心を傷つけたのよ。それにフィリップスス先生はあたしの名前に"e"の文字を付け忘れたわ。それで決めたの。明日から学校に行かないわ。これからずっとね」
ダイアナは息をのんで、まるで彼女が何を言ったのかわからないというふうに、アンを見つめた。
「あんた、ずっと家いるつもり? マリラがそんなこと許すと思う?」
「そうねそれは問題だわ。でもマリラも最終的には許すほかないのよ」と、アン。「あたしはあいつがいるかぎり、絶対に、けっして、なにがなんでも、学校には行かないんだから」
「いやよアン、学校には楽しいこともたくさんあるでしょう。それをぜんぶ失うことになるのよ。ねえ考えなおして、帰ってきてよ」ダイアナは今にも泣き出しそうだった。
家に帰り着いてから、アンはマリラとマシュウに今日の事件のすべてを話てきかした。「馬鹿馬鹿しい。寝言をいってないで、明日からもいつもと同じようにちゃんと学校に行くんですよ」マリラがきつく言いわたした。
けれどアンの心はかたく決まっていた。「あたしは学校に行かない。勉強なら家でだってできるわ。うまくやってみせます。でも、けっして、学校には行かない!」
「聞くかぎりだと、フィリップス先生はあまり良い先生だとは言えないようだ」と、マシュウが助け舟を出した。
けっきょくのところ、二人はアンが学校に行かず、家にいることをみとめた。アンは家で自分の勉強をすすめながら、わりあての仕事をこなし、夕方からはダイアナと遊んだ。ときどき道や教会でギルバート・ブライスと行き会うと、冷たい怒りとともにきまって彼を無視した。ギルバートはあれこれ彼女に働きかけようとするが、アンはすでに一生かけてギルバートを憎みつづけると決めてしまっているのだった。