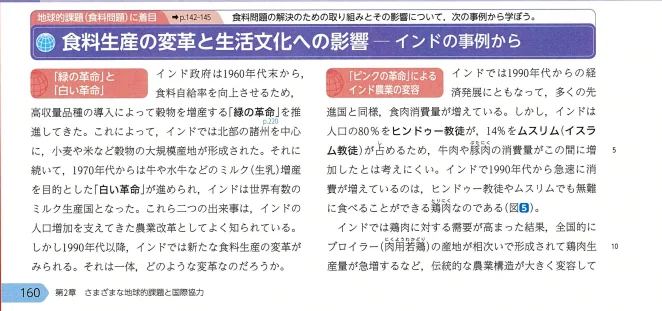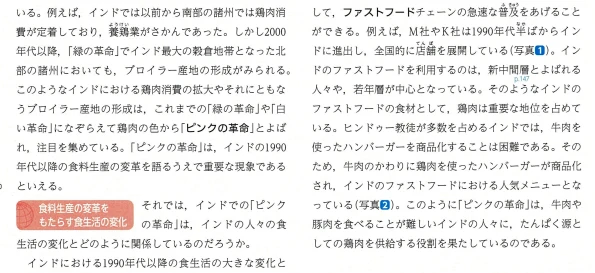第12表 パンジャーブ州農村部における経営規模別農家数 ・経営耕地面積構成比の推移
1961~1971年にかけて減少が大きい→最下層・最上層
1961~1971年にかけて増加が大きい→1~2haや3~6ha層
理由は土地改革にともなう地主の小作地引上げと土地保有の上限設定にあった。
1971~1991年にかけて下層部は増加。それ以上の経営規模をもつ農家群の構成比は減少もしくは停滞傾向。
1971年以降、2ヘクタール未満層の構成比が上昇した理由のひとつは、これらの農家群においても農業所得が増加し、存続可能性が高まったため。パンジャブ州ではこれ以外にも零細化を招く社会的要因が存在する。 第1は男子均分相続制と高い人口増加率とが結びついて、土地がたえず細分化の圧力にさらされていること。第2はカースト上の身分と土地所有とが密接に結合しており、土地の喪失がただちにカースト上の地位喪失につながるため、農民の土地の執着がきわめて強いうえ、カースト上の理由からジャート農家が農業雇用労働に従事することを極端に忌避するため。離農がきわめて生じにくいことである。 もちろん相続した土地の経営を親戚等にゆだねて、自らは都市部で職を得るといったことも頻繁におこなわれていると考えられるので、土地所有の細分化からス トレートに経営の零細化が進行するわけではないが、相続のたびに地片が細分化されることは、大規模農家への土地の集中を遅れさせ、零細農家の残存を長引かせることにつながる。
増加しつつある小規模農家がどのような存在形態にあるのかを探る→第13表(1974年における農家の家計状況)。
農家総消費支出額に占める農業所得の比率は1ヘクタール未満層で43%、1-2ヘクタール層で66%に過ぎない。これらの農家群は農業収入のみで生計を推持できないので、農外所得によって所得を補充する必要がある。 農外所得の内容をみると、経営耕地面積 2ヘクタール未満の2つの農家群においてもっとも重要な農外所得源は年金と送金であり、世帯員の一部による出稼ぎが家計維持のうえで重要な地位を占めている。 つぎに比重が高いのは農外雇用労働で、村の市場や都市部での、主として雑業的な雇用労働も欠くことの出来ない収入源となっている。しかし、こうした農外所得を加えてもこれら小規模農家群の家計は赤字である。
第14表→農村世帯がどのような職業によって所得の過半を得ているのかを経営耕地面積別に示したもの。
農業労働世帯と農家世帯とが明確に異なる社会集団を構成している点。
ら農業自営世帯比率は若干上昇すると思われるが、この点を考慮しても農業自営の後退は明瞭である。 前節で検討したように、1- 2ヘクタール層の農家群も 「緑の革命」技術の導入と過重労働にもとづく労働集約的経営によって農
業所得を向上させたが、耕地面積が狭隆なため、そこにはおのずと限界があった。そのうえ商品経済の浸透にともなって家計費が上昇したために、1- 2ヘクタール層の農家群は農外収入の依存を深めざるをえず、農家としての実体
を失いつつある。
第12表にみられるとおり、経営耕地面積2ヘクタール未満の農家群は1991年において農家総数の約半数を占めている。「緑の革命」 によって農業所得が増加したにもかかわらず、パンジャーブ州では農業のみでは生活できない農家が少なくとも全体の半分を占めていることになる。1970年代以降進行している2ヘクタール未満層の増加は、小商品生産者としての農民経営の増加ではなく、むしろ農家としての実体を失いつつある農家群の増加である。 バッラが1970年代半ばに家計調査を行って以降、米の「緑の革命」が急速に進展したにもかかわらず、当時彼らが指摘した、経営耕地面積2ヘクタール未満の農家群における困窮状態は解消していない。むしろこれらの農家群では農家としての存立が一層困難になっている。