「京都の微熱」に向けて
27日夕方より、次回の京都の街歩きに備えて、鷲田清一先生の著書『京都の平熱――哲学者の都市案内』(講談社、2007年)をテクストに、簡単な勉強会というか話し合いを行った。この本は、いわゆる学術書というジャンルには属さず、ゆえに、ある一貫した形式のもとに内容をまとめるのは容易ではない。というのも、著者の個人誌、記憶、専門領域に、京都の歴史が交錯し、また、京都の景観・風景がバスの進行経路にしたがって記述されるという本書の構成は、その内容を豊かに、また多層的にしているからだ。実際に、人名、場所名、料理名など、本書に登場する固有名詞の多さには圧倒され、そのどれもが、魅力的に語られている。それが、いわゆる、ふつうの観光案内とは異なる類のものであることは、言うまでもない。にもかかわらずーーつまり、個人的な経験や体験、記憶や固有名詞の多さにもかかわらず――、本書の記述が一貫していると感じられるとするならば、それはなぜなのだろうか。
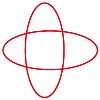
その秘密は、本書の最初と最後にはっきりと表明してある。それを簡単にまとめるならば、都市を都市たらしめている条件、しばしば「聖―性」や「学―遊」といった図式で表現される、宗教、神社、場末、恋愛、性愛、勉学など、つまり、文化への執拗なこだわりと言えるかもしれない。いわゆる「観光地」に関する記述がそれほど多くなく、というかほとんどなく、逆に、「食」や「衣」に多くの記述が割いてあるのもその例証であろう。ゆえに、本書は、「京都」という個別の都市を語りつつも、普遍的な都市文化をも語ってしまっているのだ。
勉強会参加者の本書の読み――つまり、どの場所に魅かれたか?どこに行きたいと思ったか?――は、当然のことながらさまざまであった。写真や建築に魅かれる、食に魅かれる、新撰組の系譜に魅かれる・・・などである。さしあたって私は、縁切り神社には行かないと、と思ったのである・・・。