概要 
| 作品名 | 作者 | 発表日 | 保管日 |
| Petit-haruhi | 86-14氏 | 08/04/04 | 08/04/10 |
作品 
ネコって奴が飼い主のところに自分が捕まえたネズミや小鳥などの獲物を自慢げに見せびらかしに持ってくる、なんてのを聞いたことがある方も多いだろう。
なんでもあれは、狩猟能力に欠ける我々人間のことを哀れんで、『俺様がお前の餌を捕ってきてやったニャン』と、いう風に、俺たちのことを養っている感覚なのだ、という説もあるが、正直それもどうかと思う。
まあそんなことはどうでもいい。
今の俺が抱えている問題は、晩飯後に自室に戻り、ベッドに転がって、以前に長門から借りた本を読みかけたものの、つい居眠りしてしまい、胸部に圧迫感を感じて慌てて目を覚ましたところ、目の前に展開されている状況をどう判断したものかということなのだ。
「って、シャミセン! 何だそりゃ?」
「ちょっと、そこのひと! いますぐあたしのこと、たすけなさいよ!」

今の後者のセリフは俺のモノでもなければシャミセンのでもない。っていうかシャミセンは鳴き声一つ発していない。
何故ならシャミセンは、その口に獲物を咥えており、その口に咥えられたモノ――ウチの学校の制服によく似た――セーラー服とスカート姿のどう見てもぬいぐるみ人形のそいつがジタバタ暴れながら発したセリフだったのだ。
「……ハルヒ?」
その人形みたいな奴の顔はハルヒにソックリだった。セーラーの襟をシャミセンに吊り下げられて、宙ぶらりんで半泣き状態である。
「えっ? なんであんた、あたしのなまえしってるのよ」
どうやらこいつはやはり『ハルヒ』らしいが、俺のことを知らないみたいでもある。
しかし、本当にハルヒによく似ている。言うならば『ぷちハルヒ』ってところであろうかね。
しかし、ハルヒの傍にいたせいで、散々いろいろなことに巻き込まれていたためだろうか、今目の前で起こっている非現実的な光景を、俺はさほど驚かずに受け止めてしまっているのであった。全く、慣れというものは恐ろしいものだね、本当に。
俺はシャミセンの口から『ぷちハルヒ』を開放してやる。
「にゃあ~」
シャミセンは、もう用はないとばかりに俺の部屋から出て行ってしまった。晴れて自由の身となった『ぷちハルヒ』は俺の腕の中にわたわたと飛び込んできた。
俺が抱きとめてやると、『ぷちハルヒ』は俺の方をじっと見上げるように眺め、
「あんた、ずうたいはでかいけど、キョンににてるわね。あんたはいまから『でかキョン』よ」
似てるも何も、俺は本人だろう?
と、そこでふと俺は気紛れに、携帯電話を手にするとハルヒにコールしたのだった。呼び出し音が三回なったところで、
『キョン? ちょ、ちょっと、何であんたから今頃電話が来るわけ?』
と、ハルヒの怪訝そうな声がした。
まあ、俺から電話なんてのも確かに珍しいことかも知れん。しかしハルヒの奴、気のせいか妙に慌ててないか?
「ああすまん。いや、その、特に用事はないんだが――なんとなくハルヒの声が聞きたくなってな」
『はあっ? んな、なに突然わけのわかんないこと言い出すのよ、あんたは! このバカキョン! ふざけてるんだったら承知しないんだからね』
電話越しでもハルヒの大声は健在だ。間違いない、電話の向こう側にいるのは、いつもの俺のハルヒだ。でもそれだと、手元のこいつは一体?
『キョン? どうしたの、何かあったの?』
っと、考え事しててついハルヒを放ったらかしにしてしまったな。
「悪い悪い。んじゃ、また明日学校でな」
『んもう……じゃあねっ!』
通話終了後、改めて手元の『ぷちハルヒ』に目を遣る。『ぷちハルヒ』はシャミセンから開放されて気が緩んだのか、俺の膝の上ですーすーと寝息を立てていた。
その寝顔を見て、何とも説明しがたい奇妙な感情が胸に宿るのを感じてしまう俺だった。
「んー…………『キョン』…………」
寝言か。だが、こいつの言う『キョン』は、どうやら俺以外の存在らしい。
さて、どういうことなのか、一通り説明してもらう事にするか――まあ、こいつが目を覚ましてからで構わないけどな。
俺は眠っている『ぷちハルヒ』の髪をそっと撫でた。人形でも夢を見るとして、こいつは今どんな夢を見ているんだろうかね?
Petit-haruhi II 
結局『ぷちハルヒ』が目を覚ましたのは、日付も変わろうかという頃合だった。いや、正確には、居眠りしてしまっていた俺が『ぷちハルヒ』に叩き起こされたのが、と言うべきだろうか。
「ちょっと『でかキョン』! なにいねむりしてんのよ? さっさとおきて、あたしをはなしなさいよ」
胸元をポカポカと殴りつける感触で目を覚ます俺。ちっこいクセに結構威力があるな、こいつのパンチは。
「何だ、起きたのか?」
「それはあたしのセリフよ、このまぬけづら! いいからはやく、てをどけなさい」
そういえば俺はこいつを腕に抱いたままの格好で寝転がっていたのだった。
だが、俺が腕を放してやっても『ぷちハルヒ』は何故か俺の胸元にしがみ付いたままだった。
「なによ、あんたのうでがおもたかったからよ。べつに、あんたにくっついてるのがいやだってんじゃないわ」
そう言って頬を染めると顔を逸らしてしまう『ぷちハルヒ』だった。何だろう、反応的には一応元祖ハルヒに似ているんだろうか?
その後、床に就こうとする俺の枕元で、『ぷちハルヒ』は散々妨害をしてくれたのであった。
「ちょっと、なんでねちゃうのよ? 『でかキョン』もあたしの『キョン』をさがすの、てつだってくれてもいいじゃない」
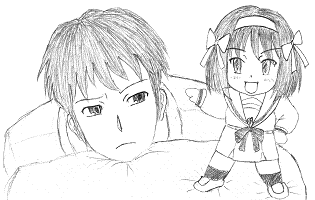
すまん、時間も時間だし、もうちょっと静かにしてくれないか。親とか妹とかに見つかったら面倒だ。
「ふんだ。――わかったわよ」
それで、お前の『キョン』ってのは、やっぱりお前と同類の、ぬいぐるみの人形なのか?
「あたしとどうるい、っていいかたはなんかきにくわないけど、まあたぶん、そんなところね」
枕の上に立った『ぷちハルヒ』のその動作が一々本物ソックリなために、俺はつい噴出しそうになる。
「ちょっと、なによ『でかキョン』? あたし、なにかへんなこといった?」
別に。ところでお前とその『キョン』はどこにいたんだ?
「わかんない。ただ、まわりにはあんたのいう『ぬいぐるみ』ってのがいっぱいいっしょにいたんだけどね」
で、その『キョン』が姿を消しちまったってことか?
「うん。――ほんとは、あたしがさきにみんなといっしょにいたところからつれだされちゃったのよね。でも、つまんないから、すきをみてにげちゃったの、あたし」
んで、元に帰ったら、『キョン』がいなくなってたと。
「ちがうわ。あたしは、もとのばしょにはかえれなかった……ずっとさがしたけど、けっきょくみつかんない」
先程の勢いはどこへやら、『ぷちハルヒ』は俯いて悲しそうに語り続けた。
「もうなんかげつもさがしたのよ。でも……ねえ『キョン』、あんたどこにいっちゃったのよ? あんたがいないと、あたし……」
とうとう『ぷちハルヒ』は泣き出してしまった。それを見ていた俺の胸に複雑な想いが生まれる。
もし俺がいなくなったら、ハルヒは俺のために泣いたりするのだろうか?
って、何を考えてやがる、俺。血迷ったか?
「ねえ『でかキョン』?」
は、はい。なんでしょうか?
「おねがいがあるんだけど、きいてくれる?」
まあ、俺にできることならなんでもな。
「あたし、もうエネルギーがなくなっちゃいそうなの。――なんだかもう、たおれちゃいそう」
おいおい、お腹でも空いたのか? 何か食べるか?
「あんたたちみたいなにんげんじゃないから、なにもたべたりしないわ、あたしたちは。……『でかキョン』、あんたのエネルギー、あたしにわけてちょうだい」
そういって『ぷちハルヒ』は、顔を赤らめると、目を閉じて口元を窄めるように突き出してきた。
「お、おい。……まさか、その――――キスしろ、ってことなのか?」
俺の言葉に『ぷちハルヒ』は答えず、そのまま縦に首を振って肯定の意を示した。
意を決した俺は、目を瞑って自分の唇を、『ぷちハルヒ』の唇に触れさせた。
不思議な感覚が俺を襲った。まるでそれは、逆に俺の方が『ぷちハルヒ』からエネルギーを注入されているような、温かな感覚――。
「ありがと、『でかキョン』。これであたしも、あといちねんはたたかえるわ」
何かよく解らんエネルギーの補給方法だが、そんなことを気にするよりも、他に気掛かりなことはいくらでもあるのだ。
「ふわぁ~、あんしんしたら、何だかねむくなっちゃったわ、あたし。おやすみ、『でかキョン』」
そう言って『ぷちハルヒ』は俺の首元に潜り込んで、スヤスヤと寝てしまったのだった。
やれやれ、とことんマイペースな奴だな、お前は。本当に、ハルヒにソックリだぜ。
そんな俺も実は睡魔に襲われており、かなり限界だ。目蓋が急速に重くなるのを感じて、俺の意識はゆっくりと消えていったのだった――。
Petit-haruhi III 
翌朝、珍しいことに目覚まし時計の設定時刻よりも早く目を覚ました俺は、起き上がると同時に襟元から垂れ下がる感触を知覚して、ああ、やはり昨日の晩のアレは夢じゃなかったんだな、とか暢気に考えていた。
このままでは顔を洗いにも行けないので、俺は襟にしがみ付いている『ぷちハルヒ』を離れさせると、ついでに頬を突いて起こしてやった。
「う~ん――ここは、どこ?」
寝惚けている様子の『ぷちハルヒ』は、頭を振って自分の意識をハッキリさせようとしていた。
「もう目は覚めたか?」
「はっ!」
突然何かに気付いたのか、『ぷちハルヒ』は俺から距離をとるように後退りして、その顔を赤くした。
「あ、あんたまさか、あたしがねてるあいだに、いやらしいことしてないでしょうね? このエロ『でかキョン』!」
してねーよ。
「ほんと? まあいいわ――――そんなことよりも、ほら…………ん!」
俺の掌に飛び乗った『ぷちハルヒ』は、昨日の再現よろしく、目を瞑って唇をこちらに差し出していた。
「何の真似だ?」
「きまってるじゃない! おはようのキッス。…………ほら、はやくしなさいよ」
朝っぱらからぬいぐるみ相手にバカなことをやらかしている俺はすっかり油断していたのだが、唯一幸運だったのは、シャミセンの奴が部屋のドアの前で寝ていてくれたことだった。
「あれれ~、シャミー、なんでこんなとこでねてるの~?」
まずい、妹だ。
「ちょ、ちょっとなにすんのよ?」
いいからお前は黙ってろ、と、俺は『ぷちハルヒ』をパジャマのお腹部分に潜り込ませる。
直後、シャミセンを頭に乗っけた妹が部屋に侵入してきた。
「ああっ、キョンくんがもう起きてる~。――ねえ、ハルにゃんはどこ?」
ハ、ハルヒって?
「さっき、ハルにゃんの声が聞こえたような気がしたんだけど。まあいっかー。てへっ♪」
そう言ってシャミセンを振り回しながら妹は俺の部屋から出て行った。
「おい、もういいぞ」
俺はパジャマの中から『ぷちハルヒ』を取り出してやる。『ぷちハルヒ』は息苦しかったのだろうか、しばらく顔を真っ赤にして呆けていた。大丈夫か、お前?
「んな、なんでもないわよっ!」
そうか、ならいいんだが。
適当に顔を洗ってきたものの、なんとなくまだ眠気は頭の中から抜け切っていない。
「ちょ、ちょっとなにしてんのよあんた!」
何って、着替えするのが何か問題でもあるのか?
「うるさいバカ!」
「?」
真っ赤な顔をして布団に潜り込んでしまう『ぷちハルヒ』。変な奴だな。
「……もう、きがえおわった?」
「ああ。じゃあ、俺もう学校に行くからな」
「そう…………ん~」
何だそりゃ?
「いってきます、のキス。ほら、はやく!」
おいおい。
「――――なあ、その、どうしてもしなきゃ、ならんのか?」
「なにいってんの? あたりまえでしょ。さあ、ちゃっちゃとしなさいよ『でかキョン』!」
「えっと…………パスするわけにはいかないのか?」
「ダメ!」
はあっ、やれやれ。
そんな感じで、ここ数日の俺は、学校ではハルヒを、帰宅してからは『ぷちハルヒ』を相手にする、という妙に疲れる生活を送ることになってしまっていたのだった。
まあ、ここ数ヶ月ぐらいハルヒが――ちょっとぐらい言い争ったりすることはあったものの――概ね大人しくしていたのが多少なりとも救いだったな。
しかし、そもそも当のハルヒはどうなってるんだ? 古泉にさり気なく訊いてみても、特に閉鎖空間とかを発生させているわけでもないらしい。
朝比奈さんがおもちゃにされている場面に出くわすことも減っていたし、裏で長門がなにやら始末を付けている様子でも無さそうだ。
もっとも俺が『ぷちハルヒ』のことを誰にも打ち明けていないように、長門も何かあっても俺に黙っているだけなのかも知れんが。
何にせよ、当面の問題は『ぷちハルヒ』の方だからな、余計な気苦労は無いに越したことはない。
で、『ぷちハルヒ』はというと、俺が学校にいる間は、シャミセンの背中に乗ってこの近辺を探索しているらしい。
最初が最初だっただけに、『ぷちハルヒ』はシャミセンを苦手にしているのかとも思っていたのだが、どうやらいいコンビになったらしい。っていうか、大変だな、シャミセン。お気の毒に。
「にゃあ~」
俺の考えは甘かった。シャミセンに同情なんてしてる場合ではなかったのだ。
とある日の晩、窓からシャミセンと戻ってきた『ぷちハルヒ』は、俺にお帰りのキスをせがんだ。ここまではいつも通りだった。
「ただいま、『でかキョン』――ん~!」
自然に唇を交える俺と『ぷちハルヒ』。全く、慣れってのは恐ろしいものだ。
「ねえ『でかキョン』。あしたはがっこうってとこにつれていきなさい!」
はいよ、って、おい! 藪から棒に何てことを言い出すんだこいつは。
「なにそのいやそうなかおは? もんくはいっさいみとめないんだから」
いや、待て待て。いくらなんでも問題あり過ぎだろ。ハルヒにソックリな人形を持っていって、それが勝手に喋って動き回るなんてのは。
「だいじょうぶ、たいていのにんげんはあたしのことみえてないし、こえもきこえないみたいよ。あたしをまともににんしきできたの、あんたがはじめてだったんだから」
でも、妹だって声は聞こえてたみたいだぞ。
「こころのきれいなじゅんすいなこにはわかっちゃうのかも。でも、あんたのこころがきれいでじゅんすいかっていわれるとかなりぎもんよね」
大きなお世話だ。
しかし、それなら最大の懸念は――ハルヒだ。
言動は置いておくとして、あいつの信念はどこまでも真っ直ぐであり、純粋な心を持っているというのは俺も認めざるを得ないからな。
何としてもハルヒに見つかることは避けなければならない。俺は怪訝そうな『ぷちハルヒ』を尻目に、宇宙人未来人超能力者の三名に電話をしたのだった。
翌朝、相当早い時間に何とか目を覚まし、俺は肩に『ぷちハルヒ』を乗せたて自転車を駆っていた。ああ、いい加減茶番めいた朝のやりとりなんてのは散々ウンザリだろうから割愛させてもらった。
途中『ぷちハルヒ』が落っこちそうになる都度髪の毛を引っ張られては痛い思いをした俺は、文句あり気な『ぷちハルヒ』に有無を言わせず、制服の胸元に押し込むことにした。
最初は抵抗したものの、いざそうやってみれば何故か大人しくなってしまった『ぷちハルヒ』である。なんというか、こいつの反応は俺には全く読めないね。
教室に到着後、自席に鞄を置き、俺は一目散に屋上を目指した。この時間はさすがにまだ人が少ないものの、リスクは最小限に留めるべきという判断だ。
予想通り三人は既に勢揃いしていた。呼び出し本人が最後ってのもアレだが、いつものパターンを考えるとこれも順当なところといえるのかも知れん。
「……」
「どうも、早くからお疲れ様です。でも、あなたが我々をこのような場所に呼び出し、というのも、何か珍しい気もしますね」
「お、おはようございますキョンくん。あ、あのぅ、何かあったんですか?」
「おはようございます。……えーと、俺の口から説明しても上手く理解してもらえるとは思えなかったんで――まずはこれを見てくれませんか」
俺はシャツのボタンを外して、胸にしがみ付いていた『ぷちハルヒ』を三人の前に取り出した。
「?」
「おや、これはこれは」
「うわあ、これ、涼宮さんですか? 何だか小っちゃくってとっても可愛いですねぇ」
「ちょっと『でかキョン』! いきなりなにすんのよ? って……ここは? ――あんたたち、だれ?」
「!」
「ほほう」
「ふえっ? こ、このお人形さん、今、しゃべって――う、動いてますぅ!」
「……へえ~、あなた、なかなかかわいいわね。きにいったわ!」
そう叫ぶが早いか、『ぷちハルヒ』は朝比奈さんの胸元に飛びついて弄り始めた。ちびっこくても、やってることは本家と同じセクハラだ。
「ほへぇ~!」
「ちょっと『でかキョン』。あたしにこんなかわいいこをかくしてたなんてズルいわよ! しょうかいしなさい」
俺が溜息混じりに長門や古泉の方に目を遣ると、両者共に察してくれたのか、
「長門有希」
「古泉一樹です。どうかお見知り置きを」
と『ぷちハルヒ』に自己紹介してくれたのだ。
「ふーん、あなたがゆきで、あなたはこいずみくんね。――――ねえあなた、なまえは?」
「ふひぃ~ん! あ、朝比奈みくる、ですぅ」
「そう、みくるちゃんっていうの? よろしくね、みくるちゃん」
『ぷちハルヒ』は朝比奈さんの首筋に取り付くと、耳を甘噛みし出したのだった。
「あふぅ、く――くすぐった、や、やめてくださーい」
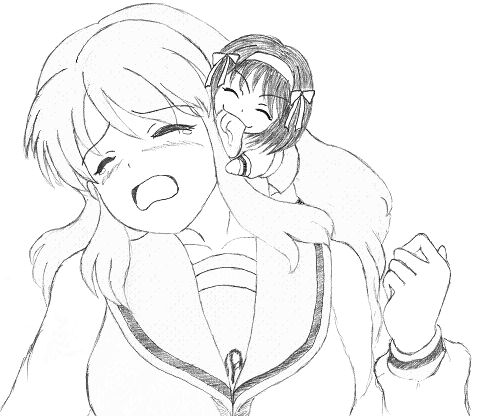
いろいろと朝比奈さんも限界のようなので、俺は『ぷちハルヒ』の首根っこを掴んで何とか離れさせた。
「へひゅ~……」
「ちょっとちょっと、じゃましないでよ『でかキョン』! ――ははーん、あんた、ひょっとしてあたしのことがうらやましいんでしょ?」
「そ、そんなことは断じてないぞ!」
俺はムキになって否定したのだったが、却って苦しかったかも知れんな。やれやれ。
Petit-haruhi IV 
俺が『ぷちハルヒ』から目を逸らしたその先には、まるで真夜中の湖水のように静かな長門の瞳があった。
「……みせて」
俺は言われるまま長門に『ぷちハルヒ』の身を手渡す。長門はどこに隠し持っていたのか、さり気なく取り出した眼鏡を掛けると、しばらくの間『ぷちハルヒ』とにらめっこ状態だったのだ。
「へえ、ゆきってメガネっこだったのね。うんうん、あたしにもわかるわ。あなたみたいなおとなしいタイプのこには、きっとねっきょうてきなマニアがいっぱいいるはずなんだからね。いい、ストーカーとか、へんなやつにはちゅういしなさいよ」
「了解した。用心する」
長門は『ぷちハルヒ』に素直にそう答えると、更に今度は古泉に大して『ぷちハルヒ』を手渡したのだった。
「あなたがこいずみくんね。ふーん、なかなかいけてるんじゃない?」
「これはこれは、お褒めに与りまことに恐縮です、可愛らしいお姫様」
「まあ、あたしがかわいいってのはとうぜんのことだからね。でも、あたりまえのことをちゃんとくちにできるのはえらいわよ」
『ぷちハルヒ』と古泉のやりとりを聞いているだけでいい加減にしやがれとか思ってしまうのは俺だけではあるまい。というわけでしばらく放置しておこう。
「なあ、長門」
「なに?」
「お前には『ぷちハルヒ』のことで――何か解ったことがあるんじゃないのか?」
「…………」
長門は黙って俺の目を見つめていたのだが、俺にはそれが僅かながらの躊躇いのように感じられたのだった。
「なんだ、その――俺には話せないようなことなのか?」
「そうではない。我々情報統合思念体も『彼女』に対する該当データを全く持っていない」
なんだって?
「『彼女』自体が我々の物質世界と矛盾する存在。初めてのケース。このまま観測を続けることに意味があるかどうかすら不明」
長門は口調を変えることなく淡々と言葉を続ける。その内容に関しては俺はサッパリ解らんのだが、一つ解ることは、あの長門が今まで見たこともないぐらいの焦りを見せている、ということだった。
「我々の物質世界と矛盾するというのは、例えば『反物質』のようなもので構成されているということなのでしょうか?」
いつの間にか古泉が俺の脇から話に割り込んできた。って、相変わらず顔が近い! ところで『ぷちハルヒ』は……朝比奈さんの頭に乗っかって、髪の毛を弄ってはしゃいでいるみたいだ。まあ、あの調子ならまだ大丈夫か。
「『反物質』とも異なる。そもそも『反物質』なら、大気に触れただけで対消滅を起こしてしまうはず。それに、『反物質』自体は我々の世界の物理学で説明可能なレベルの存在」
「では、『彼女』は異次元世界の存在、と考えても構わないのでしょうか?」
「寧ろ可能性という点では異次元世界や平行世界などといった概念を超える存在」
あー、その、全然話に着いて行けないのは、俺がバカなせいなのか?
「ああ、申し訳ありません。僕の方でも解ったことを、少しだけ説明させてください」
どーでもいいけど、俺が聞いて意味がある話なんだろうな、それは?
「勿論――『彼女』と涼宮さんとの関係について、ですので」
おい――やっぱり、ハルヒと関係があるのか?
「結論から言えば、ノーです。……最近の涼宮さんの動向から、僕は一つの仮説を組み立てていました。涼宮さんが閉鎖空間を発生させるためのパワーから、何らかの存在が生じたのではないか、ということをです」
そういえば、古泉によるとハルヒはここしばらくは閉鎖空間を発生させていない、ということだったな。
「ですが、先程しばらく観察させていただいたところ、『彼女』からは涼宮さん由来のエネルギーらしきものを全く感じ取ることはありませんでした。外見もその言動も、瓜二つといっても良いにも拘らず、ですが」
つまり、ハルヒの閉鎖空間の問題と、この『ぷちハルヒ』とは全然関係ないってことか?
「その通りです。もっとも、ハッキリしたのはそのことだけで、後は長門さんと同じく、全く何も解りません」
と、大袈裟に手を広げて微笑んだのだったが、その古泉からはいつもの余裕らしきものが俺にはあまり感じ取れなかったのだ。
とにかく、事態は思っていたよりも深刻らしかった。こんなことならもっと早く相談していた方が良かったか、と後悔しても後の祭りである。
そうこうしている間に、そろそろ他の生徒たちも登校し始める時間が来てしまったようだ。
とりあえず俺は――――朝比奈さんの髪にぶら下がってご満悦の『ぷちハルヒ』を回収しようと一歩足を踏み出した。
「待って」
長門に呼び止められ、回れ右する俺。
「どうした、長門?」
「このまま『彼女』と涼宮ハルヒを接触させるのはリスクが大きすぎると判断した。ただ、わたしが『彼女』に直接情報操作を施すことも相応の危険を伴う事になる」
そう言って長門は俺の手を取ると、
「代わりに、あなたの身体を用いて有効と思われる対策を採らせてもらう」
と、俺の小指を口に含んだ。
「お、おい、長門?」
「……完了した」
咬まれた痕が急速に塞がるのが解る。やれやれ、またナノマシンか。
「ってことは、俺が『ぷちハルヒ』の身を離さない限り、ハルヒにはバレないようにしてくれた、ってことなんだよな?」
「そう」
いつもすまんな、長門。
俺は再度踵を返すと、半泣き状態の朝比奈さんを救出すべく、暴れる『ぷちハルヒ』を、
「こらあ、『でかキョン』! いきなりなにすんの――むぎゅっ」
と、無理矢理シャツの胸元に押し込んで、屋上を後にすることにしたのだった。
その日の休み時間、俺は『ぷちハルヒ』に命じられるまま、校内のあちこちを案内させられるハメになったのだった。
問題はハルヒなのだが、いつものようにどこかをほっつき歩いているみたいであったものの、不思議と俺たちに遭遇することはなかった。
放課後、掃除当番の俺を放置して、ハルヒはさっさと部室に向かってしまった。まあその方が好都合といえるのかも知れん。
すべきことを終わらせ、俺は鞄を取りに教室に戻った。かなり遅くなってしまったためか、もう誰も教室内には残っていなかった。
と、俺の胸元から『ぷちハルヒ』が勝手に飛び出してきた。おいおい、今でこそ誰もいないから構わんけど、あんまり無茶すんな。
「うるさいわね。ああもう、『でかキョン』のにおいがしみついちゃったらどうすんのよ? ――――あれ?」
『ぷちハルヒ』はしきりに辺りの匂いを嗅ぐような仕草をしていた。って、そんなに俺の体臭って気になるものなのか? と、『ぷちハルヒ』は突然周囲をキョロキョロと見回すと叫びだした。
「『キョン』! 『キョン』? でてきなさいよ」
いや、出てくるも何も、俺はここに――、
「あんたのことじゃないわよ『でかキョン』。いま、このちかくで『キョン』のけはいがしたの――ここよ!」
『ぷちハルヒ』は俺の座席の後ろに――ハルヒの机の上に――仁王立ちしてそう宣言したのだった。
って、お前の探してる奴が、ハルヒの席に?
「ちょっと『でかキョン』、こっちにあんまりちかよんないでよ。あんたのそばにいたらなんだかわけわかんなくなっちゃうの」
どういう意味だよそれは、と声に出掛かったところで、俺はハッと気付いた。
まさか、長門が俺に施した対策ってのが、『ぷちハルヒ』の感覚にまで影響していたってことなのか?
なるほど、確かに授業中散々こんな近距離にいたはずなのに、『ぷちハルヒ』は全く気付かなかったではないか。
俺が少し距離をとって様子を見ていると、『ぷちハルヒ』は窓から外を見たり、椅子に乗って机の中を覗いたり、床に下りて席の後ろの掃除用具入れをガンガンぶっ叩いたりしていたのだが、その表情はハルヒがよく俺に見せていた真剣な顔そのものであったのだ。
「ダメね。『キョン』のこんせきはみつかんないわ。でも、たしかにこのへんから『キョン』をかんじたの。もしかしてここにいたひととなにかかんけいがあるのかも」
思案するような『ぷちハルヒ』を見て、俺は嫌な予感がした。おそらくこの次にこいつが言い出しそうなことは決まっているのだ。
「ねえ『でかキョン』。いますぐあたしをここにすわってたひとにあわせなさい!」
……やっぱりな。
「なによそのかおは。なにかもんだいでもあるわけ?」
問題なら大ありなんだがな。『ぷちハルヒ』とハルヒが対面、なんてことになったらどんな騒ぎになるものやら、俺は想像するのも恐ろしい。
「ちょっと『でかキョン』? あんた、あたしのめいれいがきけないってわけ?」
「こればっかりは勘弁してくれ」
「どうしてもダメ?」
「どうしても、だ」
「――――そう」
『ぷちハルヒ』は元気なさそうに俯いてしまった。
「なによ、バカ『でかキョン』。やっと――やっと『キョン』のてがかりがみつかったかもっておもったのに、そんなにいじわるすること……ないじゃないのよ」
いや、意地悪とか、そんなつもりは更々ないんだが、
「ねえ『でかキョン』。あんた――あたしのこと――キライなの?」
潤んだ瞳で俺を見上げる『ぷちハルヒ』。ううっ、卑怯だぞ、その上目遣いは!
「どうなの? ハッキリこたえなさいよ」
「……チクショウ、解ったよ。ハルヒに会わせてやる。それだけでお前は満足なんだな」
「えっ、ほんとにいいの?」
「ただし、絶対に動いたり喋ったりしないでくれ。あくまでも離れたところから見るだけだ」
「うん、ありがと『でかキョン』! やっぱりあたし、あんたのことがダイスキよ!」
嬉しそうに飛びついてくる『ぷちハルヒ』を捕まえて胸元に押し込んだ俺は、仕方なく部室に向かうことにしたのだった。
部室前の廊下で、俺は『ぷちハルヒ』を取り出すと、『文芸部』と書かれたプレート――勿論その上から『SOS団』との貼紙がされてはいるのだが――の上に腰掛けさせたのだった。
さて、準備はこれで終わったが、問題はハルヒをどうやってここに引っ張り出すか――、
「ちょっとキョン、あんた今までなにしてたのよ?」
突然ドアが開き、ハルヒの登場だ。俺は心臓が口から飛び出さんばかりに驚いた。
「い、いやーその、掃除当番が長引いてしまってな。あははは」
「もう下校時刻じゃないの! なによ…………せっかくずっと待ってたのに。ふんだ、あんたなんかもう知らないわ!」
お、おい。何そんなに怒ってるんだ?
「あたし――――もう帰る」
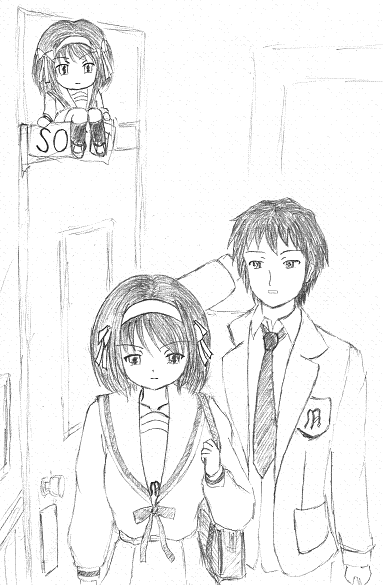
ハルヒはそういってさっさと俺に背を向けて歩き去っていったのだった。気のせいか、俺にはその背中が妙に寂しそうに見えたのだ。そういえば今日は『ぷちハルヒ』に気を取られていたせいで、ハルヒと全然話してなかったっけ。
呆然とハルヒを見送っていた俺の頭の上に『ぷちハルヒ』が着地した。
「う~ん、よくわかんないんだけど、やっぱり『あのこ』と『キョン』はなにかかんけいがありそうなのよね」
すまんな、あまり長いこと引き止められなくって。
「べつにいいわよ。それより『でかキョン』、あたしと『あのこ』ってそんなににてるの?」
ああ、瓜二つといってもいいくらいだと思うぞ。
「へえ。じゃあ『でかキョン』もあたしにするみたいに、『あのこ』といつもキスしてるってこと?」
お、おい! そんなわけないだろ。
「おやおや。では、あなたはその『彼女』といつもそのようなことをされている、ということですか?」
「…………」
いつの間にか廊下に古泉と長門が立っていた。って、まさか今の会話内容を聞かれちまったってことなのかよ。
「そう」
おーい、誰かロープを俺に貸してくれないか。今すぐ吊ってくるから。
と、いつの間にか『ぷちハルヒ』は俺から離れて、目を閉じて何かに耳を澄ませているようだった。どうかしたのか?
「ん……べつに、なんでもないわ」
やがて、ドアが開いて中から着替えを済ませた朝比奈さんが現れたのだった。
「お待たせしましたー。って、あれ、キョンくん、いらっしゃってたんですか?」
朝比奈さんの声を聞いて俺は、そういえば今日は朝比奈さんのお茶をとうとう飲み損ねてしまったなあ、とかマヌケなことを考えていたのだった。
いや、俺がマヌケだからというのは抜きにしても、ちょっと危機感が足りなかったのかも知れんが、その辺はできればご容赦願いたいものだ。
その時点で遥か上空から俺たちのことを監視している存在がいた、なんてことは、あの長門でさえも全く気付いていないことだったのだからな。
その日の晩、何故か『ぷちハルヒ』は言葉少なで、なにやら迷っているようにも俺には思えた。
俺が何か話し掛けても上の空である。おーい、もう寝ちまうぞ。
「うん」
オヤスミのキスを要求してもこない。明らかに変だ。俺は寝た振りをしながらコッソリと様子を窺っていた。
しばらくすると『ぷちハルヒ』はやがて何か決心したかのような表情で立ち上がり、何やらシャミセンにちょっかいを出し始めた。
俺に似たのかグータラな三毛猫は起きる素振りを見せることはなく、諦めたのか『ぷちハルヒ』は一人で――俺に何も告げることもなく――窓から外に出て行ってしまった。
やれやれ、本当に世話が焼けるな。
俺は――何故か自分でも解らんけど――さっさと制服に着替え、家族に気付かれないように自転車を持ち出し、いつもの通学路を急いだ。
果たして、しばらく進んだところでトボトボと歩いている『ぷちハルヒ』の姿が目に入った。
「おい! こんな夜中にどこに行くつもりだ?」
「えっ……『でかキョン』? なんであんたが?」
「学校か?」
「まあ――ちょっときになることがあって」
「乗ってくか?」
「……ありがと」
その後は俺も『ぷちハルヒ』もずっと黙ったままだった。自転車を漕ぎながら俺は、もう『ぷちハルヒ』といられるのはこれが最後なのかもしれない、という予感めいた考えに囚われてしまっていたのだった。
Petit-haruhi V 
真夜中の学校に到着した俺たちを出迎えてくれたのは、見覚えのある三つの人影だった。
「やあ、どうも」
「こ、こんばんわ――キョンくん」
「……」
おいおい、どうしてみんながこんな時間に勢揃いしてるんだ?
「ふふふ。あなたが『彼女』とここに来ている――しかもこんな時間に――というのでは、理由にはなりませんか?」
相変わらずのニヤケ顔だが、古泉のその声はどこか真剣みを帯びていた。俺は残りの二人に目を遣る。
朝比奈さんはちょっと困ったような表情ながらも、胸の前で握り締められた両手の拳からは、何とも必死な様子が伝わってくる。
長門はただひたすら真っ直ぐに、俺に対して視線を注いでいた。何の言葉も要らなかった。その瞳の色を見ただけで、俺にはこいつが俺の身を案じていることが解ったのだから。
長門、朝比奈さん、そして古泉――みんな、すまないな。
「……さて、お前はどこに行きたいんだ?」
俺の言葉を境に『ぷちハルヒ』は胸元から飛び降りると、
「こっちよ、みんな」
と、小さな歩幅でパタパタと駆けて行く。
俺の予想に反して『ぷちハルヒ』の目的地は、五組の教室でも文芸部室でもなく――本館の屋上だったのである。
踊り場を埋め尽くしている障害物をものともせず、『ぷちハルヒ』はドアを抉じ開け、屋上に飛び出していった。
『キョン様!』
『ハルヒ? 何故あなたがこのような場に』
俺たちが屋上に辿り着いたとき、そこには『ぷちハルヒ』の姿はなく、代わりに一組の男女の姿のみがあった。
女性の容姿はハルヒそのものといってもよいぐらいだった。そして、男性の方は――、
「えっ? 俺?」
『……成程、君がハルヒのことを匿っていてくれたのだね。言葉などでは言い表せぬほどに感謝している』
『キョン様……それではあなたは一体?』
『奇遇な事もあるものだ。私はハルヒ――君ソックリな人物の元に今まで保護されていたのだよ。つい先刻までね』
えーと、ちょっと待てよ。
どうやら『ぷちハルヒ』が捜していた『キョン』ってのがこの男性なわけで、しかもその『キョン』は今まで『ぷちハルヒ』にソックリな女性の元に匿われていた、ということは、
「やっぱりあんたは今までハルヒのところにいたのか?」
『君の言っている人物が「涼宮ハルヒ」という女性のことなら、まさにその通りだ。出来ることなら……『彼女』にも直に御礼の言葉を伝えたかったのだが』
『キョン様……』
「ええっ、あ、あのっ、これってどういうことなんですか? お人形さん、どこ行っちゃったんですか? それに涼宮さんと……あれっ? なんでキョンくんが二人もいるんですか?」
「どうやら涼宮さんにソックリのあのお方が、あの人形の真の姿、ということのようですね」
何だか解らんが、どうもそうらしいな。でも何で俺とハルヒの姿なんだ?
「気をつけて」
さっきからずっと沈黙していた長門が、こいつにしてはハッキリとした声量で告げた。って、何に気をつけろって?
「迂闊……わたしたちがこの場に来た時点で、既に囲まれていた」
長門の言葉が終わるか終わらぬかの内に、足元を摩訶不思議な紋様のパターンが覆い尽くした。
「なに?」
「ふえぇ! な、なんなんですか、これ~?」
「ほほう、この気配は――異空間――それも今まで僕が体感したこともない種類のものですね」
足元の紋様はコンクリートに染み込むように薄れていき、やがてコンクリート、いや建物自体がまるでブラックライトのような目に見えない光を放ったかのように思われた。
ほぼ同時に、腹の底に響くような地響きにも似た低音が辺りを埋め尽くす。それは北高一帯の空気が一瞬にして凝縮したかのような強烈な歪みをもたらしたようであった。
いつの間にか空の色が暗いモノトーンに染められている。俺はつい、あの閉鎖空間のことを否応にも思い出させられてしまう。
『これは――まさか結界? しまった!』
『もう一人の俺』が悲鳴じみた声を上げた。
直後、屋上の中央辺りに黒い靄のような人影が浮かび上がった。何だこいつらは? ハッキリしないその姿を見ようと目を凝らそうとしても、痛みのような感覚が両目を襲ってまともに正視できない。
『ふむ、「王」を追い詰めたつもりが、まさか「妃」まで網に掛かるとはな』
その黒い靄の中心付近から、なんというか、まるでゼリー状の汚物を頭上からぶちまけられたように不快で粘着質な響きが、耳を突き刺すような声量で発せられたのだった。
『やはり――「謀」――貴様らか』
『もう一人の俺』に『謀』と呼ばれたそいつらは正確なところは解らないものの、ざっと十人ぐらいはいそうだった。
もっとも顔はおろか輪郭さえハッキリしないので、ひょっとしたら分身術のようなものでも使ってるのかもな、とか、この期に及んで俺はマヌケなことを頭に思い浮かべていた。
『最早、貴様らに未来は無いのだ。――「王」に「妃」よ――我らが糧となれ。その身に宿りし事象の根源と共に、我々と同化するのだ!』
叫び声と共に、空気が凍りついた、いや、目の前の空間がまるでガラスか何かのように粉々に砕け散った。
その中から、まるで真っ黒な人魂、とでも言ったらよいのだろうか、不気味な塊が飛散し、俺たちの頭上に降り注ぐ。
「うおっ!」
不意に襟首が引っ張られる。どうやら俺は長門に掴まれた状態で、床面から数メートルの高さまで上昇させられていた。
目の前では『もう一人の俺』が『元ぷちハルヒ』を抱いて、隣では紅球に包まれた古泉が朝比奈さんの腰を担ぐようにしてジャンプしていたのだった。
「わひゃ~!」
「おっと、失礼。しかしどうやら、この場では僕の能力も開放されてしまうようですね」
「あの存在を中心に………………半径一キロメートルの球状の特殊空間が形成されて……………いる」
って、おい、長門。どうしたんだ?
「メインシステムが予期せぬエラーで損傷。…………現在、第二及び第三リソースを用いて対処中。…………メインの復旧と、あなたの……保全だけで処理能力の…………限界」
不意に長門の力が抜けたのを感じる。と同時に、俺たちの身体は重力に捕らえられてしまう。
「うおおぉぉ!」
床面に激突する寸前、何とか受身の態勢で、俺は長門を抱えて背中から転がる事に成功した。すぐ目の前に着地する古泉たち。
「お二人とも、ご無事ですか?」
「ああ、俺は大したことない。でも、長門が」
長門は俺の腕の中で目を閉じたまま、肩で息をしていた。
「ふえっ、な、長門さん!」
古泉から降ろされた朝比奈さんも俺たちの元に駆け寄る。
「まずいですね。長門さんをしてもこのような状況に追い込まれてしまうなんて。……あるいは、敵方も長門さんのことを最大の脅威と捉えているのかもしれません。だからこそ、第一に長門さんに攻撃を加えたものとも考えられます」
どっちにしろ、情勢は変わらない気もするんだがな。
「いけない……来る!」
長門が目を閉じたまま叫ぶと、右手を前に突き出した。
またしても空間が罅割れて、その中から――何も出てこない?
いや、飛び散った空間の破片そのものが、鋭利な槍状の散弾となって、俺たちに襲い掛かる。
間一髪、長門が張り巡らしたバリアがその攻撃を食い止める。無数の槍がバリアに接触しては粉々に砕け、周囲の大気に溶けるかのように消えていく。
朝比奈さんは両手を耳に当て、長門に覆いかぶさるように蹲っている。もう悲鳴すら出している余裕も無いのだろうか。
「……だめ」
長門の呟きと同時に、バリアが明滅を始めた。どうやらもう限界のようだ。
とっさに俺は長門と朝比奈さんを庇おうと身を乗り出す。
飛来する槍が俺の背中に到達するまさにその直前――辺りは一瞬だけ真っ白な光で包み込まれた。
「? お前……」
『やっぱり「でかキョン」にはあたしが付いててあげないとダメみたいね。――キョン様、そちらはお願いします』
俺たちの前で『元ぷちハルヒ』は右手を前方に掲げて仁王立ちしていた。
『了解した。……そこの君、頼みがあるのだが、構わないかな?』
「はい、僕でよろしければ、協力させていただきます」
敵に対峙する古泉と『もう一人の俺』。
『ふん、たかが「駒」如きが加わったところで、形勢を覆せるとでも思っているのか?』
『せいぜい油断して後で泣きを見るがよい――「謀」よ――いざ、参る!』
宙を舞う二人を、今度は床面のコンクリート片が迎撃ミサイルのように襲う。
『もう一人の俺』が、剣のような武器でそれらを薙ぎ払う。その様子はまるでカメラを円周上に配置した特殊な撮影法のスローモーションのように思われるほど鮮やかなものであった。
一瞬にして粉砕される大量のコンクリートの欠片。その後ろから古泉が、
「ふ~~ん――――もっふ!」
と、作り出した紅球を立て続けに敵に打ち込む。
古泉の攻撃が敵の姿を覆い隠す。もうもうと巻き上がる白煙。
『やったか?』
「いえ、どうやら敵本体には直撃、とまではいかなかった様子です」
古泉の言った通り、白煙の中から敵がその姿を平然と現した。
『ほう、中々楽しませてくれるではないか。だがこの程度で我々を仕留められると思っているのなら、そのような甘い考えはさっさと捨て去る方が貴様らのためだ』
まるで物語とか、映画とかにありがちな悪役のセリフそのまんまではないか。チクショウ! あの野郎、余裕ぶっこきやがって。
『ならばその余裕』
「僕たちが打ち砕いて差し上げましょう」
いつの間にか息もピッタリ合った『もう一人の俺』と古泉は、再度敵の攻撃を掻い潜り、攻撃に転じた。
「いけませんね。やはりどうしても、床の破片が防御壁の役割を果たして、攻撃が本体まで届いていません」
『だが、奴の周りはもう穴だらけだ。その内防御壁すらも構成できなくなるはず』
『果たして貴様らの思惑通りにいくかな?』
その後、幾度となく二人が攻撃を繰り返しても、何故か古泉の紅球は敵の防御壁に阻まれてしまう。
よくみると、攻撃が着弾する寸前に、敵の足元の床面が復元している。このままではいつまでたっても埒が明かない。
戦局は膠着状態といってもよかった。となると、消耗戦ではどうもこちら側の分が悪そうだ。
焦りの色を隠せない古泉と『もう一人の俺』。その隙を突くかのように、敵がその攻撃方法を変化させた。
「おい、古泉! 後ろだ」
先程まで一時停止していた空間破裂攻撃が、古泉の背面で炸裂した。
「くっ、不覚……」
辛うじて古泉は自分の身体を赤いバリアで包み込んだものの、破片の直撃を受けてバランスを崩し、落下していく。
そこを狙い澄ましたように、コンクリートミサイルが四方から襲い来る。
「古泉~!」
俺の叫びも空しく、敵弾は古泉のいた地点に殺到して炸裂した。
『ふん、成程な。「駒」を捨ててまでの一太刀とは、貴様にしては上出来だ』
敵がガックリと膝を落とすような姿勢になった。
次の瞬間、俺たちの眼前に、『もう一人の俺』が古泉を両手で抱えた状態で着地した。
まさか、古泉を犠牲にして、こいつは攻撃を?
「いいえ、それは違います。僕が攻撃の要と見せかけて……囮になることで敵に何とか隙を作る……それが当初からの、作戦でした」
古泉はそういうのが精一杯といった様子で、そのまま力なく目を閉じた。お、おい? 大丈夫か?
『心配ない。気を失っているだけだ。――――彼の勇敢な行動に私は応えたかった。だが、結果的に私は仕留め損なってしまった。……面目ない』
そのまま『もう一人の俺』は力を失ったかのように崩れ落ちる。その背中には、空間が裂けたときにできた破片が深々と突き刺さっていた。
『キョン様! ……しっかりなさってください』
慌てて駆け寄る『元ぷちハルヒ』。
『ハルヒ……すまない。――またしても、君を…………独りぼっちにしてしまうことになるな』
『ダメよ、キョン様。もう喋らないで! 今すぐに傷の手当を』
『残念だが、私はもう助からない。ハルヒ――どうか君だけでも、生き残って欲し……』
『キョン様? ……そんな、いやぁぁぁぁ!』
『元ぷちハルヒ』の腕の中で『もう一人の俺』は眩い光の粒子となり――その跡には一体の人形のみが残されたのだった。
その、俺によく似たぬいぐるみ人形を『元ぷちハルヒ』はしっかりと抱きしめて嗚咽していた。
『せっかく、せっかくまた逢えたのに――キョン様ぁ!』
辺りに絶叫がこだまする。
直後、『元ぷちハルヒ』の身体はオーラのような白い光に包まれていった。その姿はまるで光のハルヒであった。
『許せない……あたしはあいつを、絶対に許さないんだからっ!』
『光ハルヒ』は、『もう一人の俺』が残した剣を手に、一歩一歩敵の元へ近付いていった。
『ぬう、先程の一撃は想定していたよりも利いたぞ。だが――「妃」よ――お主の腕で、我々にもう一太刀浴びせることが出来るかな』
『出来るかどうかじゃないわ。やらなくちゃいけないのよ!』
どこかで聞いたような熱血なその言い草は、いつかのハルヒのセリフそのものだった。
『いくわよ!』
剣を一閃する『光ハルヒ』。敵の攻撃はその一動作で全て無効化されてしまう。
『おのれ!』
敵はコンクリート床を掘り起こして『光ハルヒ』の攻撃を回避すると、その背後に躍り出る。
『くっ、ちょこまか逃げ回るなんて卑怯だわ! 正々堂々と勝負しなさいよ!』
あきらかに『光ハルヒ』がイライラしている。敵の狙いは『光ハルヒ』を焦らして、その隙を突こうとしているに違いない。
クソっ、俺には何もできないのか? 何か勝つためのチャンスを見つけられないのだろうか?
そのとき、俺の下で伏せていた朝比奈さんが訊いてきた。
「キョンくん、あの――さっきから変な音がしてるの、聞こえませんか?」
はあ? 音――ですか?
「ええ、なんだか、周期的に……七秒ぐらいかな、ガラスを引っ掻いたみたいな音がして――あっ、今もです」
直後、『光ハルヒ』の背後から敵が攻撃を仕掛ける。間一髪避ける『光ハルヒ』。って、まさか?
どうやら、朝比奈さんは敵の攻撃の予備動作音を知覚できるらしい。
あとは、どこに敵が出るかさえ解れば――、
「……システムを復旧完了」
突然長門が目を開けて起き上がる。おい、長門! お前本当に大丈夫なのか?
「もう平気。……現時点より攻性情報の展開が可能。敵が攻撃行動に転換する際に生じる時空震を検知して、それを封じる。……タイミングの同期を」
「えっ、あ、はいぃ!」
長門はそう告げると、朝比奈さんの額に手を当てる。朝比奈さんは目を閉じて、意識を耳に集中しているみたいだ。
「――今です」
朝比奈さんの合図で長門が例の早口言葉コマンドを発令する。直後、床面に一瞬にして氷が張るようにコンクリート面が復元される――『光ハルヒ』の正面を除いて。
「来るぞ『ハルヒ』! お前の目の前だ!」
『とりゃぁ、必殺! あたしの怒りを食らいなさーい!』
床を破って現れた敵の脳天から、『光ハルヒ』の剣がまともに振り下ろされる。
『うぐぁ! ば、バカな?』
『キョン様の仇、思い知りなさい!』
だが、終わったわけではなかった。敵の身体はまるで触手状に分散し、『光ハルヒ』の全身に絡みついた。
『このままでは済まさん! 貴様も道連れにしてやる!』
『うるさい! あんたなんか、あたしの前から消えてなくなっちゃいなさいよ!』
『光ハルヒ』の身体は更に発光を増す。
「いけない。伏せて!」
「『ハルヒ』ーっ!」
長門は叫ぶ俺の襟を掴んで押し倒すと光の網状のバリアを俺たちの周囲に発生させた。
直後。
目の前が真っ白になって、俺は何も見えなくなってしまった。
しばらくして、俺が視界を何とかとりもどしたところ、俺のほぼ目の前から校舎の殆どが消滅していた。背後で何かが倒れる音がして振り返ると、長門の華奢な身体が仰向けに転がっていた。
「おい、長門? しっかりしてくれ」
「大丈夫。一時的な高負荷状態のため、リブートを行っただけ」
ゆっくりとした動作で上半身を起こすと、長門は平然と告げた。
「直ちに校内の環境を復旧させる。終了予定は四分十六秒後」
長門の予告どおり、俺の眼前でビデオの逆再生が行われるかのごとく、瓦礫が盛り上がって建物の体裁をとっていく。しばらくして、校舎は何事も無かったかのように、以前の姿を取り戻していた。所々走っていた罅割れまで元通りだ。
「ん?」
そのとき、上空から降ってくるモノを俺は目にした。
しばらくしてコンクリートの上に着地したそれは――二体のぬいぐるみ人形だった。
一体は俺ソックリの人形、そしてもう片方は……、
「――うーん」
「おい、『ぷちハルヒ』! 大丈夫か?」
俺の言葉に『ぷちハルヒ』は身を起こそうとして、再び転んでしまった。
「あいたたた。あーあ、あたしとしたことが――ちょっと、ドジっちゃったかしら」

俺は慌てて駆け寄ると、すっかりボロボロになってしまった『ぷちハルヒ』を抱き寄せた。
「まあでも、あんたがぶじみたいで……ほんと、よかったわ、『でかキョン』」
無理に平気そうに喋る『ぷちハルヒ』だったが、その声はか細くて力のないものだった。
「ねえ、あたしの『キョン』はどこ?」
そのとき、いつの間にか起き上がっていた古泉が、黙って脇から俺ソックリの人形を差し出した。
「もう、すっかりよごれちゃって。ほんとにしょうがないんだから、『キョン』は」
お前だって酷い格好だぞ。
「うるさいわね! ……でも、ありがと、『でかキョン』。――あんたのおかげで、あたしは『キョン』のかたきをうてたわ」
俺には掛ける言葉がなかった。もっと早く敵の弱点に気付いていれば。『キョン』を助けることができたのかも……。
「あんたがきにすることじゃないわ。……あたしと『キョン』はもう……いつでもいっしょなんだから」
『ぷちハルヒ』と『キョン』は淡い光に包まれていく。朝比奈さんの啜り泣く声が聞こえて、俺は自分の頬に伝う温かなものを意識したのだった。
「なにないてんのよ……このまぬけづら……じゃあね、『でかキョン』。――あんたも『あのこ』をだいじに――しなさいよ」
そういい残して、二体の人形は光のシャボン玉が弾けるようにその姿を大気に溶かしてしまったのだった。
俺はその場にへたり込んで、しばらく呆けていた。
全身の力が抜けてしまって、身動き一つ取れそうになかった。自分では何もできなかったっていうのにな。――情けない。
ふと気が付くと、古泉の奴が、俺に背中合わせで凭れ掛かってきていた。
「あまりお気を落とさないで下さい。僕たちは――あなたはご自分にできること全てに手を尽くしたはずですから」
たしかに、お前とか長門は頑張ったろうさ。それに朝比奈さんが敵の攻撃の規則性に気付いたから、あいつを倒すことができたんだもんな。それに引き換え俺は、ただ傍観していることしかできなかったんだ。
「それは違う」
俺の目の前に正座した長門は、力強い口調でハッキリと告げた。
「あなたがいなければ、『彼女』と『彼』は再会することはなかった」
「ぐすっ、そ、そうですよ。――ひっく、あの、『ちっちゃい涼宮さん』だって、……えぐっ、キョンくんに――お礼、言ってたじゃ、ないですかぁ? ううっ……」
先程から涙でボロボロの朝比奈さんも、何故か自分のことを棚に上げて、俺を必死で励ましてくれようとしていた。
みんなの気遣いに、止まっていたはずの涙が溢れ出し、俺の視界は再びぼやけてグシャグシャになってしまった。
風の音のみが聞こえる静かな真夜中の校舎の屋上。
月明かりが優しく照らし出していたのは、俺たち四人の影のみであった。
「……起きて」
長門の声に目を覚ます。俺の目の前には見覚えのない天井が。ここは?
「保健室。あの場であなたたち三名が睡眠を採るのは健康上よくないと判断した」
と、ベッドから跳ね起きる俺。隣のベッドには古泉が寝息を立てていた。対面の方には――カーテンで見えないが――朝比奈さんが寝ているのかもしれない。
って、まさか、長門の奴、俺たち三人を抱えて屋上から保健室まで連れてきたってことなのか?
「先に教室に向かって。あなたの鞄は既に座席に配置してある」
「なあ、長門」
「なに?」
「ありがとうな」
誰にも見つからぬよう保健室を抜け出し、俺は五組に向かった。
既に鍵は解錠されていたが、結局俺は誰にも会わなかった。
無人の教室で、俺は自席に着くと、机に突っ伏して目を閉じた。
もう、『ぷちハルヒ』に逢うこともないのか。何処から現れて、何処に行っちまったのか最後まで解らずじまいだったな。
しかし、あいつは本当にハルヒにソックリだったな。妙に自信家なところも、怒りっぽいところも、すぐ拗ねるところも、そして――笑顔が最高に眩しいところもな。
だが、しみじみとそんな物思いに耽っていたのが間違いだったのだ。他の生徒が登校し始めても、俺は姿勢を全く変えずに、うだうだと思索していたのだったが、
「うわっ!」
バーン! と、背中を勢いよく引っ叩かれ、弾みで俺は思わず起立してしまう。
「おっはよう、キョン! ……なによ、あんた――朝っぱらから居眠りしてたわけ? おデコに机の跡、付いてるわよ」
「――ハルヒ」
「ん? どしたの、キョン?」
そういえばここ最近は『ぷちハルヒ』にさっきみたいな調子で叩き起こされたりもしていたし、『ぷちハルヒ』がいなくなってしまったせいでハルヒまでがこの世から姿を消してしまったんじゃないかって錯覚に囚われてもいたのかもしれない。
あろうことか、俺は反射的にハルヒの身体を抱き寄せると、互いの唇を触れ合わせた――早い話、キスしてしまったのだ。
「んな、ちょ、ちょっとなにすんのよ、このエロキョン!」
『でかキョン』と呼ばれなかったことで、俺は初めて自分のしでかしてしまったことの重大さに気付かされた。
既にクラス内には大半の生徒が集まっていた。俺が見た限りでは谷口や国木田の姿もあった。なんてこった。
ハルヒはまるで甲殻類を茹でたときのような色の変化をその顔面上に展開していた。
「どーいうつもりなの? あんた、なに朝っぱらから発情しちゃってるわけ?」
「いや、違う!」
「なにが違うのよ?」
「これは『オハヨウ』のキスだ。つまりただの挨拶だ」
あまりに気が動転していたせいか、更に墓穴を掘ってしまった。
いかん、このままではハルヒに「ふざけんな」とか怒鳴られて、張り手を食らうに間違いない、って――ハルヒ?
「……何であんたが知ってんのよ? あたしと『ぷちキョン』だけの秘密」
はあっ? まさかお前、俺ソックリの人形相手に、
「それ以上言うな、このバカキョン!」
ハルヒは実力行使とばかりに、俺の口を塞いだのだった――自らの唇でもってな。
その日以来、俺とハルヒの間に、朝の日課が目出度く一つ追加されたのだった。やれやれ。
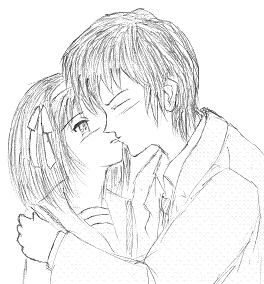
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ