カレンベルク
【死因】
【関連キャラ】ビアギッテ(恋人)、コンラッド(交戦)、ギュスターヴ(交戦)、シャーロット
3257年 「箱」 
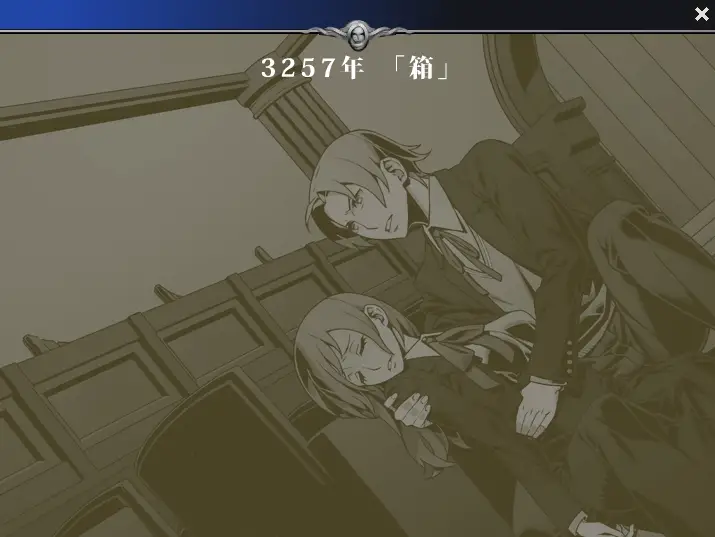
薄暗い講堂のスポットライトが当てられた壇上に、一人の少年が佇んでいる。
「これより、本年の監督生からの挨拶があります」
壇上の上手から司会者によるアナウンスが入った後、少年は壇上に設置されたマイクに向かって声を出した。
「本年の監督生、カレンベルクです。よろしくお願い致します」
深く一礼すると、カレンベルクは講堂全体を見回しながら定型の挨拶を行う。
そして最後に、監督生としての行動目標について語った。
「僕達は世界を背負って立つ者として、正しい方向に世界を導く義務があります。僕は本年、その模範となるべく努力する事を誓います」
挨拶は盛大な拍手をもって終了した。
その後、特別講師の講演会などが入り、恙無く式典は終わりを告げた。
――大善世界の実現――
この教育理念を持つルピナス・スクールは、ローゼンブルグの山岳地帯に広大な敷地を持つ、全寮制の学園だ。
この学園で生活をするのは七歳から十八歳の男女数百人。
グランデレニア帝國各地から生徒が入学し、その全員の両親が、学園に対して大なり小なり寄付を行っている。
カレンベルクの両親はいくつもの医療施設を経営する経営者であり、ローゼンブルグでも指折りの資産家であった。
当然、カレンベルクもその恩恵を受けており、学内での地位も高い。
幼い頃よりこの学び者で学ぶカレンベルクにとって、自分と自分に続く卒業生達こそが、世界を変える重要な人材であると認識している。
そしてそれを牽引するのが自分の役目であるとし、学園で生活する生徒達の模範となるべく振舞っている。監督性に選ばれたことも必然であるといえた。
「お疲れ様です、素晴らしい挨拶でした。何かお飲みになりますか」
「いや、大丈夫だ。ありがとうビアギッテ」
講堂での式典が終わり、舞台袖で休憩していたカレンベルクに一人の少女が近付いてきた。
カレンベルクの恋人であるビアギッテだった。華やかな容姿であるが、よく気が付く性格と清楚な雰囲気により、派手な印象は受けない。
二人の付き合いは幼少の頃まで遡ることができる。両者の家庭に行き来があり、その過程で親交を深めていったのだった。二人は学園内でも多くの耳目を集める、理想の恋人同士として知られていた。
「カレンベルク様、お父様からの贈り物をお届けに上がりました」
ある日、寄宿舎の使用人が綺麗にラッピングを施された大きな箱を手にして、カレンベルクの部屋を訪れた。
「ありがとう、中に運んでくれ」
「かしこまりました」
使用人はカレンベルクに恭しく一礼すると、大きな箱をそっとカーペットの上に置いた。
使用人が立ち去るのを確認し、カレンベルクはラッピングされた箱を手に取った。
かなりの大きさがあったが、持った瞬間の重さは見た目程はないようだった。
ラッピングされた箱の上部に一枚のメッセージカードを見つける。
メッセージカードには、カレンベルクの父親の筆跡で、丁寧に一文が添えられていた。
『最愛なる我が息子へ お前が生を受けた日と更なる力に感謝と祝福を。 父より』
「更なる力……?どういうことだろう」
意図が読み取れない一文に首を傾げつつも、カレンベルクはシルクの赤いリボンを解き、包装を丁寧に剥がしていく。
包装を解いて箱を開けると、中から緩衝材に包まれた本体が姿を現した。これでもかというほどの梱包に、カレンベルクは苦笑した。
「やっと完成したんだな……」
箱の中から出てきたものは、渋い茶色のニスでコーティングされた艶の少ないボディを持つ、一本のバイオリンだった。
手にした感触は、現在使用しているバイオリンよりも少し重厚である。
バイオリンの道を志た頃より懇意にしているバイオリン職人が、特別に誂えたものだ。
今年の誕生部祝いに最高のバイオリンを送りたいと願った父親からのプレゼントであった。カレンベルクも自分に合うバイオリンを作るべく、学業の合間を縫って足繁く工房に通っていた。
そうやって完成した、世界に二つとない逸品。それがこのバイオリンだった。
「カレンベルク様?どうかなさったの?」
寄宿舎の音楽堂にビアギッテを呼び出したカレンベルクは、父親から送られてきたバイオリンをビアギッテに見せた。
「急に呼び出してすまない。父からのプレゼントが届いてね。一番にこれの音色を君に聞かせたくて。迷惑だったかい?」
「とんでもないですわ。でも、最初にこのバイオリンの演奏を聞くのが私で、いいのかしら?」
「君だからこそだよ。さあ、そこに掛けて」
ビアギッテを音楽堂に備え付けられた椅子に促すと、カレンベルクはバイオリンを肩に当て、弓を構えた。
まるでこのバイオリンが最初から自分のものであったかのように、カレンベルクには感じられた。
そう、このバイオリンは今まで愛用していたものよりも遥かによく馴染んだのだ。
事前に職人による調整があったようで、自身での調整にはさほど時間は掛からなかった。
チューニングを行い、軽く弦を弾いて音色の感触を確かめてから、比較的難しくないエチュードを奏でる。軟らかく、かつ力強い音色が音楽堂に響いた。
ちらりとビアギッテを見やると、その音色にうっとりと聞き入っているように見えた。
それに気を良くしたカレンベルクは、エチュードを弾き終えて本格的な演奏に移る。旧時代に作曲された名曲で、上流階級だけでなく、一般大衆にも馴染む深い曲だ。
何度となく弾いているので、盛り上がりの強弱や多少のアレンジなども織り交ぜて、様々な奏法で演奏する。
だが、曲が最も盛り上がりを見せる終盤に差し掛かった頃、ビアギッテの顔色がだんだんと悪くなっていくことに気が付いた。
「ビアギッテ?どうした!」
「だ、大丈夫、です……どうぞお続けになって……」
ビアギッテは苦しそうに胸元を押さえていた。
只事ではない様子に、演奏を中断してビアギッテに駆け寄る。
「う……ぐ、ううう……!!」
ビアギッテの顔色は青ざめ、唇はチアノーゼを起こしているかのように紫色になっていた。
カレンベルクは彼女を横たえ、脱いだ自分のジャケットを彼女の頭の下に敷いた。そして彼女の手を握った。
「すぐに人を読んでくる。少しだけ待っていて」
握っていた手を話して外へ向かおうとすると、突然音楽堂の扉が音を立てて開いた。
同時に、ゆったりとした拍手のリズムが聞こえてくる。
「お父様!?」
「おめでとう!素晴らしい力だ。さすがだな、カレンベルク。我が息子よ」
驚愕するカレンベルクに、父親は大仰な手振りで嬉しそうに笑いながらそう言い放った。
楽屋に通じる扉には、いつの間にか黒服の男達が現れて扉を塞いでいる。
「ビアギッテが倒れたんです。早く医務室に――」
「何も心配することないぞ。それはお前の力がみせた結果であり、証なのだから」
「そんなことを言っている場合ではないでしょう!早く医者に見せないと!」
人が一人、しかも懇意にしている家の一人娘が倒れているというのに、無闇に芝居がかった父親のその調子に、カレンベルクは苛立ちを抑えきれない。
「そんなことはどうでもいいのだ、カレンベルク。お前は今、この瞬間、超人として覚醒したのだ!」
このままでは埒が明かない。そう感じ取ったカレンベルクは、ビアギッテを抱きかかえて音楽堂から出て行こうとする。
「ハッピーバースディ!カレンベルク。お前を我が組織の一員として歓迎しよう」
「何を、何を仰っているんですか、お父様!ビアギッテが苦しんでいるんです!お願いです、そこを退いてください!」
音楽堂を出て行こうとするが、黒服の男達がカレンベルクの行く手を阻む。
「おめでとうございます、カレンベルク様」
「我々はこの日を待ち望んでいたのです、カレンベルク様」
「素晴らしいことなのでうよ、カレンベルク様」
「これで組織の未来も安泰ですな」
「ビアギッテ様もいずれは覚醒なさいますよ、カレンベルク様」
「何も心配することはないのです、ただ祝いましょう」
口々に祝いの言葉を発する黒服達。それぞれが皆、形容しがたい陶酔したような笑みを浮かべていた。
「―了―」
3257年 「超越する者」 

父を何とか説得して、ようやく倒れたビアギッテを医務室に運ばせることができた。
音楽堂に残ったカレンベルクは、なおも嬉しそうな表情の父に怒りの目を向ける。
「どういうことか説明してください。ビアギッテが苦しんでいるのに、何がそんなに嬉しいのですか!?」
「そう憤るな。順番に説明しよう」
父はそう言うと、大仰な手振りで語り始めた。
――薄暮の時代、人間の進化の停滞を嘆いた偉大な人物がいたこと。
――その人物は、人類を新たなステージへと昇華させるために行動を起こしたこと。
――その結果が、超越した力を得た者達だということ。
――このルピナス・スクールは、超越した力を持った者を生み出すために作られた施設であるということ。
――そして、カレンベルクはその力を最大限に発揮することができる、新しい超人の第一号だということ。
「僕が、人間じゃない……」
俄には信じがたい話ではあったが、現にビアギッテはバイオリンの音色一つで傷つき、倒れた。それこそが、カレンベルクに与えられた力の証明となっていた。
「否、超人だ。カレンベルク、お前には人を超越した新たな人類として、皆を導く役目があるのだ」
「お父様はビアギッテや他人を傷つける力が人々を導くと、本気でお考えなのですか?」
悲痛な声で父に尋ねる。
「力こそが善き世界を作るために必要なものなのだ。我々には障害が多い。それを叩き潰す圧倒的な力が必要なのだ」
「僕にはわかりません」
「すぐに理解しろとは言わん。今日は疲れたろう、もう休め」
父はそれだけ言うと、黒服を連れて音楽堂を去った。
残されたカレンベルクはしばし呆然とした後、重たい足取りで音楽堂を立ち去った。
翌日、カレンベルクはビアギッテのいる病院を訪れた。スクールに併設されており、手術設備などが一通り整った病院である。
スクールが山岳地帯にあるために、ローゼンブルグの病院への搬送時間が懸念されたために作られたとカレンベルクは聞いていた。
ビアギッテの意識ははっきりとしていたが、まだ青い顔をしてベッドに横たわっていた。
「ビアギッテ、すまない」
「謝ることはないですわ……」
「どこか痛いとか、苦しいとかはないかい?」
「大丈夫です」
「よかった……」
カレンベルクは何度も病院に通い、ビアギッテを見舞った。
日々元気を取り戻していくビアギッテを見て、カレンベルクは安堵した。
カレンベルクは自分が手に入れたという力について考え始めていた。音楽堂で一人、カレンベルクはザジを手に演奏を試みる。
「……だめだ」
だが、ビアギッテを苦しめた場面がありありと思い出されてしまい、どうしても弾く事ができずにいた。音楽堂の椅子に座り、カレンベルクは気を落ち着かせることにした。
父の言葉がカレンベルクの心に重く圧し掛かっていた。超越する者とは何なのか、自分はいつ人間でなくなってしまったのか。
あれ以来、父とは会話をしていなかった。
自分にどういった力があって、何ができるのか。ザジと銘打たれた新たなバイオリンを手に考え続けていた。
「カレンベルク様?」
不意に音楽堂の扉が開いて、ビアギッテがゆっくりとした足取りで入ってきた。
私服姿のところを見ると、退院してきたばかりと見える。
「ビアギッテ!?身体はもういいのかい?」
「はい、お医者様からもう大丈夫だろうと」
「そうか……」
「どうかしましたか?」
「……部屋に戻ってくれないか。それに、もう僕とは会わないほうがいいだろう」
ビアギッテが倒れてから言うか言わまいか、ずっと悩んでいたことを口にした。
今までずっと最愛の人として想ってきた相手にそれを告げるのは、カレンベルク自身も辛かった。
だが彼女を傷つけるよりはいい。自分にそう言い聞かせて、決別をすることを決めていた。
「なぜ?まさか、あの時のことを気にしていらっしゃるの?」
「ああ。僕がバイオリンを弾いて、また君があんなことになったら……」
「あの時は素晴らしい音色にちょっと圧倒されてしまっただけです」
「違う!僕はもう、人間じゃない。化け物なんかに近づくんじゃない!」
あの時のことを、まるで軽い事故のように言ってのけるビアギッテ。いっそ恐怖の目で見られた方が、どれほど気が楽か。
最愛の人から拒絶され、自身の存在を否定されれば、自分が人ならざる者であるという現実をいやでも直視できるのに。
カレンベルクは、それでも共にあろうとする彼女に苛立ちを覚えた。
「大丈夫ですわ。どんな姿でも、どんな人でも、貴方は貴方ですもの」
一瞬怯んだ様子を見せたビアギッテだったが、少しの間を置いて微笑んだ。
そうして、カレンベルクの頭を優しく撫でた。
「……ビアギッテ、すまない」
「なぜ謝るのですか?貴方は悪いことなど、何もしていませんわ」
カレンベルクは俯き、ビアギッテにされるがままになった。
優しい彼女を怪物になどしてはならない。彼女を連れてどこか遠くへ逃げなければ。
カレンベルクは新たな覚悟を固めたのだった。
カレンベルクはスクールがある山岳地帯とローゼンブルグ周辺の地図を密かに入手した
次にバイオリン工房に出向くという名目で扮装用の襤褸着を調達し、当座凌ぎで隠れるための寂れた宿も探し、少しずつ脱出に関する手筈を整え始めた。
残る問題はビアギッテの説得だった。彼女はまだ自分が置かれている世界が危ういものであるとは微塵も思ってもいない。
それでも、彼女が領けばすぐにでもスクールから脱出できるよう、準備を進めていった。
準備が完全に整ったとき、カレンベルクはビアギッテを自室に呼び寄せた。
「こんな時間にどうされました?」
寄宿舎の消灯時間はとうに過ぎていたが、監督生としての優遇か、教師らに何も咎められることなくビアギッテを呼ぶことができた。
とは言え、見回りの教師が巡回に来るまでにはビアギッテを説得しなければならなかった。
「ビアギッテ、今から言うことをよく聞いて欲しい。驚くかもしれない、怖いかもしれない、それでも僕を信じて欲しい」
カレンベルクは真剣な態度でビアギッテにスクールの実体を告げた。
自分は何かしらの処置を施されて化け物のようになってしまったこと、自分の父親がスクールを作った人物と共に恐ろしいことを計画していること。
「そんな。私も怪物になってしまうの……?」
ビアギッテは話を聞き終えると、青い顔をして震えた。
「そんなことは僕がさせない。だからビアギッテ、一緒にここから逃げ出そう」
「カレンベルク様……」
ビアギッテはカレンベルクの目を見つめて領いた。
二人は用意した襤褸服を纏うと、窓から縄梯子を降ろして寄宿舎から脱出した。カレンベルクは頭に叩き込んでおいた獣道を、ビアギッテの手を引きながら早足で進んでいく。
獣道を進めばローゼンブルグの第十階層隔壁と第九階層隔壁の間に流れる堀に通じる川に出る。そこから川を下れば、ローゼンブルグの中流層が暮らす第十階層へ抜けられる。
ルピナス・スクールはローゼンブルグの支配層が管轄している。中流層の第十階層に入り込んでしまえば、隔離された階層が仇となって、支配層でも追うには時間が掛かると予測がついた。
しかしそれは一種の賭けでもあった。支配層は強大な権力を持っている。階層の壁など容易く破る可能性も大きかった。
「ビアギッテ、大丈夫かい?」
「えぇ、なんとか……」
カレンベルクはビアギッテの様子を気に掛けながら獣道を進んだ。漸く、山岳から流れる大きな川が見える谷に辿り着いた。その場所に着いた途端、ビアギッテの足が止まった。
「どうしたんだい?もうすぐ隔壁に出る、そうしたら脱出もすぐ……」
言葉は空を切る音で中断される。カレンベルクの腹に鋭利な何かが突き刺さっていた。
「いけませんわ、カレンベルク様」
いつもの優しげな表情のまま、ビアギッテはカレンベルクの腹から血塗れた指先を引き抜いた。
綺麗に整えられていた爪が、刃物のように鋭く伸びていた。
「ビア……ギッテ?……まさ、か」
「ええ、そうです。私も貴方と同じになりたくて。お父様にお願いしましたの」
恍惚の表情で自身の爪を見るビアギッテに、カレンベルクの目から自然と涙がこぼれた。
間に合わなかった。ビアギッテは既に自分と同じものになってしまっていた。その悔しさは腹の傷の痛みさえも凌駕していた。
「だから、逃げる必要なんて無いんです。善き世界のために、私たちはこれからもずっと一緒ですわ」
ゆっくりとカレンベルクの涙を爪で拭う。
「スクールで傷を治してもらいましょう。そうすればきっと、貴方のお父様の言うこともおわかりになりますわ」
「だめ、だ……」
ここで連れ戻されては、自分もビアギッテと同じようになるという確信があった。
そうなればもう二度と彼女を救うことはできない。カレンベルクは最後の力を振り絞って、川へと飛び込んだ。
急流に流されるうちに、出血と身体の冷えが原因か、意識が遠くなっていった。
「―了―」
3258年 「ザジ」 
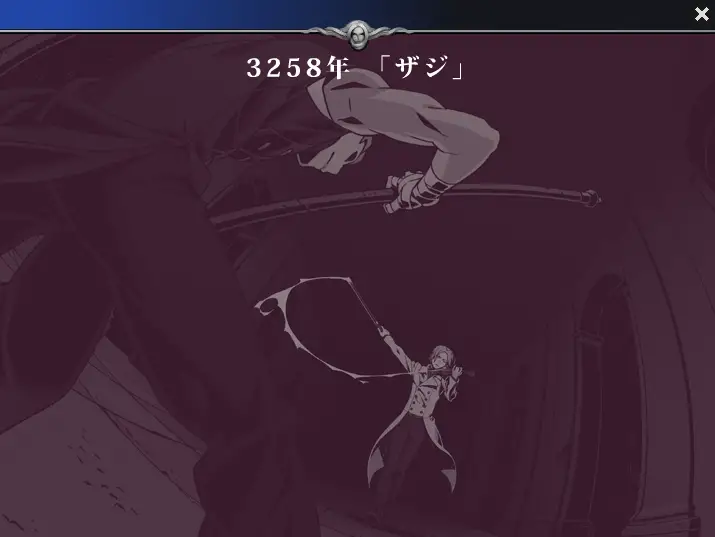
薄汚れた天井。意識を取り戻したカレンベルクの視界に入ったのはそれだった。
すぐ横で何かを片付ける音がする。その方向を見やると、無精髭を生やした中年男性が医療機器を片付けていた。
「……ここ、は」
「気が付いたか、カレンベルク」
男性は衝撃的な言葉を口にした。何故自分の名を知っているのか。カレンベルクは衝撃に目を見開き、同時に身構えた。
「組織の関係者か……」
「警戒するなとは言えんが、私が組織の関係者なら、君の意識が戻る前に組織に引き渡している」
男性はロンゴと名乗った。以前はルピナス・スクールの併設病院で研究者を務めていたという。
そして、カレンベルクに超人となるための種を植え付けたのは自分だと、簡潔に語った。
「そんな、いつの間に……」
「十歳の頃。と言われれば、心当たりがあるだろう?」
そう言われ、カレンベルクは十歳の頃を思い出した。ちょうどその頃、病を患ってルピナス・スクールの病院に数週間入院したことがあった。
その時から自分の体は人間でなくなっていたのかと思うと、カレンベルク身震いした。
「貴方は、何故……」
「何故君を助けたのか?それとも、何故組織を抜けたのか?どちらだ?」
「……両方です」
ロンゴは静かに息を吐き出すと、カレンベルクの疑問に答えた。
――苛酷な実験を繰り返す内に組織の活動に疑問を持ち、実験体の死体を自身の自殺死体に偽装して組織を出奔したこと。
――サベッジランドに辿り着いた自分は組織で得た技術を利用して医療業を営むことで、組織で犯した罪を償おうと決意したこと。
――そしてつい先日、瀕死のカレンベルクが自分のところに運び込まれてきたこと。
――怪我をしている患者を救わない理由は無いこと。
それらを粛々と語った。
「それで、お前はこれからどうする?」
今度はカレンベルクの番だ。ロンゴの視線はそう告げていた。
「ビアギッテを助けたい。それだけです」
迷いは無かった。自分が生き存えた理由はこれだけだと、カレンベルクは思っていた。
傷の癒えたカレンベルクは、自らの力を正しく扱えるように特訓を開始した。
ビアギッテを取り戻そうとする以上、組織からの攻撃は避けれれない。
「お前は音の力を操る能力を持っているのだろう。バイオリンの音によって恋人が苦しんだというのは、それが原因だ」
力の正体を知るためにいくつかの心当たりをロンゴに告げると、彼はそう返した。ロンゴは愛する人を助けるために組織に反逆しようというカレンベルクの覚悟を気に入り、あれこれと助言するようになっていた。
カレンベルクは新たなバイオリンを入手して超人の力を操る訓練を進めていったが、何かが違う。
やはりザジでなければ駄目だ。そう断案したカレンベルクは、忌まわしきルピナス・スクールの寄宿舎へ忍び込む決意をした。
自分の超人の力はビアギッテを苦しめてしまった力だ。だが、それよりも組織に対抗してビアギッテを取り戻す力を得たい、その願望が勝った。
脱出した時のルートを遡る形で、カレンベルクは寄宿舎へ向かう。
建物の周囲を見回る警備員をやり過ごして侵入すると、まずは自室へと向かった。
自室だった場所は、すでに荷物が処分された後であった。だが、ザジの回収は容易だった。
ビアギッテを害してしまった時に、クローゼットの底に穴を開けてザジを封印していたのが幸いした。
次にビアギッテの部屋へ向かったが、そこにビアギッテの姿は無かった。
それどころか、自分の生活していた部屋と同じように荷物が処分されている。ビアギッテは何処へ行ったのか。
カレンベルクは寄宿舎の寮長室に忍び込んだ。寮長であればビアギッテの行方を知っている可能性がある。寮長は寝室で寝入っていたが、不審者の侵入を察知したのか、目を覚ます。
そして、寮長はカレンベルクの顔を見ると、その表情を恐怖に歪ませた。
「き、貴様、何故ここに!?」
助けを呼ぼうとする寮長をザジの音色で拘束する。碌にメンテナンスをしていないにも関わらず、ザジはカレンベルクの力に完璧に応えた。
「ビアギッテを何処へ隠した?」
「……し、知らん」
怯えた声で話す寮長だが、この寄宿舎の全権を任されている彼が寮生の所在を知らぬ筈がない。
寮長が嘘を吐いていると考えたカレンベルクは、ザジの弦を一つ弾く。低い音色が寮長の耳に届くと、寮長は苦悶の呻き声を上げた。
「お、ああ……」
「さあ、ビアギッテは何処だ?」
再び寮長に問う。ザジの音が寮長の脳を支配していた。
「み、リ……ガディア……」
「ミリガディアの?」
「首都近く……スラム……今は、使われていない、聖堂……」
「そうか」
聞きたい事を聞き終えたカレンベルクは、再びザジの弦を弾く。
寮長は苦悶の表情を浮かべたまま悶死した。外見ではわからないが、彼の脳細胞はバイオリンの音によって破壊し尽くされているだろう。
何処からともなく響くバイオリンの音色。
作曲者の悲しみを旋律とした曲が、聖堂に響き渡る。
「ぐ、ぎゃ……あ、あ……たす、た……」
「な、何だ、これは、あぐ……!?ぎぇ、があああああああ!」
次いで、バイオリンの音を掻き消すように悲鳴が響き渡る。真夜中の聖堂は阿鼻叫喚に包まれた。
僧侶達の絶叫が収まると、カレンベルクはバイオリンを携えたまま聖堂の奥へと進んだ。
累々と横たわる僧侶達の中、聖堂の奥にいる二つの影だけは、何事もなかったかのように立っている。
片方は女性で、もう片方は男性だった。女性の方は僧侶のフードを目深に被っており、表情は窺い知れない。
「我らの組織を背負って立つ若者が、このようなことでは困る」
「コンラッド祭司……。ビアギッテを返していただきます」
「私の教育は失敗だったようだな。神の名の下に、私が直々に裁きを下してやろう」
カレンベルクとコンラッドは対峙する。相手を射殺さんとする両者の視線がぶつかり合う。
「僕はビアギッテさえ解放してくれれば、貴方がたには何もしません」
「そうか。ならば行け、ビアギッテ」
フードを被った女性が、コンラッドの言葉に促されるようにカレンベルクに駆け寄った。
「ビアギッテ……?」
カレンベルクは駆け寄ってくる女性を見て一歩後退る。
その直後、ビアギッテと呼ばれた女性が蟷螂の鎌のように変化した腕を振り翳して、カレンベルクに襲い掛かる。
突然の攻撃に見えたが、カレンベルクは冷静にバイオリンの弦を一度弾いた。すると、彼女の体は金縛りにあったかのように動かなくなる。
バイオリンの音が女性の行動を支配していた。
「な、に……!?」
女性の顔が驚愕と恐怖に彩られた。
「僕を嵌めましたね、コンラッド司祭」
カレンベルクは女性の先に居るコンラッドを見据えていた。
「ああ。だが、それがどうしたというのだ?」
フードを被った女性がビアギッテでないことは、ひと目見たその瞬間に把握していた。確かによく似ていたが、長い年月を共に過ごした人を見間違うほど、カレンベルクは鈍感ではない。
カレンベルクはバイオリンの弦を弾き続ける。そのリズムに合わせるように女性の体が動き、ついにはその腕の鎌をコンラッドに向ける。
「行け」
言葉と共に、カレンベルクは一層強くバイオリンの弦を弾いた。
それを合図に、女性がコンラッドに向かって鎌を振り上げる。
「……失敗か」
「た、助けて……コンラッドさ――」
何かが潰れるような音が響き渡る。コンラッドの手には棍が握られており、その先端は血と脳漿で濡れていた。
「祭司……貴方という人は……」
カレンベルクの目には絶望ともつかない色が宿っていた。
まさか、助けを求める者を一撃で殺害してしまうとは予想しなかった。カレンベルクの知るコンラッドは、別け隔てのない無償の愛を生徒達に与える僧侶であった。
「我らの神に仇なす者を排除したのみ。我々は我々を脅かす者の存在を許さぬ」
コンラッドは棍を構えると、常人では見切れぬ速さでカレンベルクの距離を詰める。間合いに入ったその瞬間、カレンベルクの脳天に向かって棍が振り下ろされた。
しかし、カレンベルクはその一撃を左に大きく避けることで回避した。
「ぐ……」
ザジの音により、コンラッドの動きが一瞬だけ止まる。
しかし、超人としての力かそれとも精神力の賜物か、コンラッドはザジの音色から無理矢理抜け出した。
「甘い!」
棍の追撃がカレンベルクを襲う。先程よりも鈍い速度ではあったが、今度はカレンベルクの脇腹を捉える。
呪縛が振り解かれたことに対する動揺が、カレンベルクに隙を作っていた。
カレンベルクは息と共に悲鳴とも呻きともつかない声を吐き出すと、床に叩き付けられた。
不意の一撃をもらってしまったが、カレンベルクは動揺を隠して体勢を立て直す。
コンラッドが強いであろうことは想定済みであった。カレンベルクはコンラッドの更なる追撃を回避し、距離を取りながらザジの弦を何度も強く弾く。
曲を奏でる暇は無い。とにかくコンラッドにザジの音を何度も聞かせ続けなければと、必死に弦を弾く。
「小癪な真似を……」
コンラッドの攻撃を何度も回避していく内に、聖堂の最奥へと追い詰められた。
「神の名の下に滅せよ、カレンベルク!!」
コンラッドの棍が迫る。カレンベルクはその攻撃を躱すことなく、再びザジの弦を弾く。
今度こそ、コンラッドの動きが完全に止まった。
「な……」
コンラッドの口や鼻から血が流れ出た。
同じ超人であったため時間は掛かったが、コンラッドの体細胞をザジの音色で振動させ、内部からの崩壊を狙っていたのだ。ついに耐え切れなくなったコンラッドは、穴という穴から血を流しながら床へと倒れ付した。
聞くべき事があったため、脳細胞には攻撃をしていない。だが、このまま放置しておけばじきに失血死を迎えるだろう。
「コンラッド祭司、ビアギッテは何処にいるのです?」
カレンベルクはザジの弦を弾き、コンラッドの精神に問う。
「ビアギッテ、は……聖……ダリウス大聖堂に……いる……」
コンラッドは息も絶え絶えながら、ビアギッテがいるらしい場所を口にする。
ザジの音色から逃げおおせるだけの精神力も体力も、彼にはもう無かった。
「お前は……せめて、私の……手で……」
その言葉を最後に動かなくなったコンラッドを一瞥すると、カレンベルクは聖堂を後にした。
そして一縷の希望を胸に、ミリガディアの首都にある聖ダリウス大聖堂へと向かうのだった。
「―了―」
3259年 「幼子」 
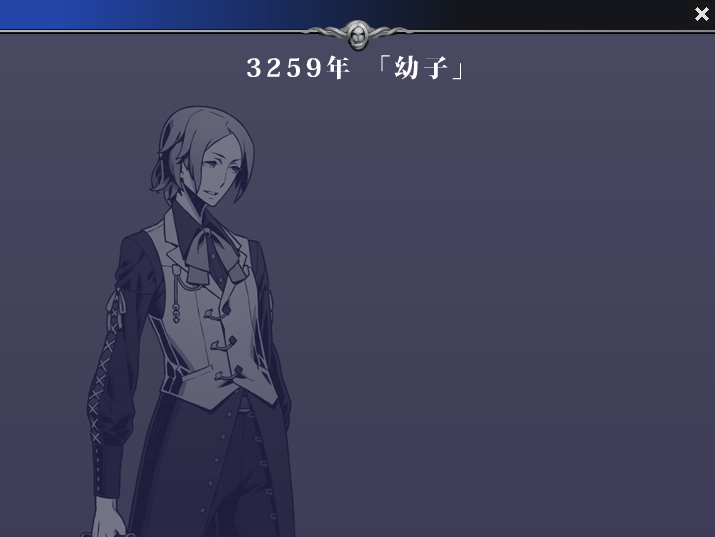
スラムの廃聖堂を出たその時、カレンベルクは急に酷い頭痛と動悸に襲われた。
「う……ぐうぁ……」
堪らずに膝を突くが、このままここで倒れてしまえば組織に見つかってしまうかもしれない。カレンベルクは苦しみながらも廃聖堂の物陰に隠れ、そのまま朝がくるのをじっと待った。
夜明けと共に空が白んできた頃、ようやく頭痛と動悸が治まった。
体はまだ重いままだったが、カレンベルクは引き摺るようにして何とかロンゴの元へと戻った。
ビアギッテの居場所はわかった。だが、敵の本拠地でこのような事態が起きればどうなるか、敗北にしかならない。
「能力の使い過ぎだな。コンラッドに打ち勝つために無理をしたんだろう」
ロンゴに頭痛と動悸のことを話すと、すぐにそんな返答が戻ってきた。
「お前の力は強大だ。だがそれ故に、使い方を誤れば今回のような不調に見舞われることになる」
「力をコントロールするための訓練が必要、ということですね」
「その通りだ。大事な人を助け出すためには、まずはお前自身が能力を完璧に使いこなさねばならん」
ロンゴの助言に従って、カレンベルクは更なる訓練を重ねた。訓練や能力の調整には二年程の時間を要したが、確実にビアギッテを救い出すためであれば焦りも無かった。
能力を完璧にコントロールできると実感してきた頃、ビアギッテがミリガディアの西端にある聖堂に『大君直属の祭司』として遣わされているという情報を入手した。
カレンベルクはビアギッテを取り戻す契機であるとみなし、急いでその聖堂へと向かった。
結果から言えば、既にビアギッテは聖堂から去った後であった。
さらに、この聖堂には組織の超人化実験施設が存在していたため、組織の構成員から手荒い歓迎を受けてしまった。
組織の構成員をあらかた片付けたカレンベルクは、ビアギッテの洗脳を解く手掛かりがないか、施設を調査することにした。手掛かりは無さそうだと諦めかけた頃、どこかから子供の泣き声が聞こえてきた。
声のする方へと足を運ぶと、子供部屋もかくやと言わんばかりの小さな部屋に、泣きじゃくる一人の幼子を発見した。
「どうしたものか……」
カレンベルクは思案した。
このままここに放置してしまえば、死んでしまうか、運よく生き残ったとしても、超人実験の犠牲者となるだけだろう。
それならば自分がこの子を保護し、ロンゴと共に生育に適切な場所を探すのがいい。一人でもいいから、自分と同じように力に翻弄される子供は減らしたい。
カレンベルクはそう考え、何もわからずに泣き続ける幼子を保護した。
「この子の生育に相応しい施設を探してくれませんか」
カレンベルクが連れてきた幼子にロンゴは驚いたが、カレンベルクから話を聞くとすぐに頷いた。
「ならば、マイオッカに私の個人的な知り合いが運営している養護院がある。そこなら組織の手も伸びてはこないだろう」
幼子の保護先はすぐに決まった。
しかし、一つだけ問題が起きた。幼子がカレンベルクに懐いてしまい、傍を離れるのを嫌がってしまったのだ。
「これは……。困ったな」
「もう少し自我がはっきりすれば諭すこともできるだろうが、この成長具合ではどうしようもない。ひとまず、マイオッカまではお前が連れて行くしかなさそうだ」
「そうですね。この子は僕が助けた子です。責任を持ってマイオッカまで連れて行きます」
「では、向こうの司祭に連絡を入れておく。道中は交易をやっているストームライダーに案内してもらうといい」
そうして、名もない幼子はシャーロットと名付けられ、カレンベルクによってマイオッカ共和国にある養護院へ預けられることになった。
「君がここに来る数日前、ロンゴから君宛の手紙が届いた。君が到着したら至急渡して欲しいとのことだ」
「至急、ですか。ありがとうございます」
シャーロットを連れて到着した養護院には、ロンゴからの手紙が届いていた。手紙を受け取ったカレンベルクは、すぐにその内容を確認する。
手紙にはビアギッテの目撃情報が書かれていた。カレンベルクがシャーロットと共に旅立った後、聖ダリウス大聖堂で行われた式典にビアギッテが祭司として参加していたとのことだった。
「シャーロットをよろしくお願いします」
「ああ。彼女のことは我々に任せてくれ」
「何かあったら、すぐにご連絡を」
手紙を読み終えたカレンベルクは、シャーロットとの別れもそこそこに、すぐに首都ルーベスに向けて旅立った。
ミリガディア王国の首都ルーベス。その中央通りとされる通りの先に、目的地である聖ダリウス大聖堂が見える。
中央通りは真夜中にも関わらず人の往来が多かった。こんな夜更けに大聖堂へ向かう者など、不審者以外の何者でもない。だが、往来する人々はカレンベルクのことを見向きもしない。
妨害も警戒するような視線も寄越さないルーベスの人々を一瞥しつつ、カレンベルクは聖ダリウス大聖堂への道を急いだ。
聖ダリウス大聖堂は組織の本拠地なだけあって、異形や超人による猛攻が相次いだ。だが、繊細な能力のコントロールを可能にしたカレンベルクに適う者はいない。
妨害してくる敵を次々とザジの音で屠り、ビアギッテを探した。だが、彼女の影すらどこにも見あたらなかった。
カレンベルクは大聖堂の大深部、玉座の間へと到着した。
そこには、カレンベルクを待ち構えるように、杖を手にした一人の老人が佇んでいた。
この老人には見覚えがあった。ルピナス・スクールの創設者であるとされる老人で、スクールに飾られていた肖像画で幾度も目にしていた。
そしてこの老人こそが、かつて父が語った『偉大な人物』その人であり、醜悪な組織の首領、ギュスターヴであった。
「ビアギッテを何処に隠した!」
「隠してなどはおらぬよ。あの娘には組織のシンボルとして尽くしてもらっている。それだけだ」
「ふざけるな!それが彼女の意志だとでもいうのか!」
カレンベルクは怒りのままにザジの弦を弾く。しかし老人はザジから発せられる音波を杖の一振りで掻き消した。
ザジの音と杖から発せられる術がぶつかり続ける。
相手が老体ならば接近戦が有利であろうと、カレンベルクはとにかくギュスターヴへ近付こうとする。
カレンベルクの考えを見抜いているギュスターヴは、距離を取ろうとする。
互いに優位な位置を確保すべく、音波と術の応酬の合間に匠に位置取りを変えていく。
若者と老人では基礎体力にそもそも大きな開きがある。少しずつギュスターヴが圧され始めた。
「貴様を殺す前にもう一度聞く、ビアギッテを何処へ隠した!」
「若造が、ほざくなよ。あの娘が欲しくば自らの力で探し出すがよい」
「この……!」
答える気など欠片もないギュスターヴに、ついにザジが発する音波が届く。
音波をまともに受けたギュスターヴは倒れ伏した。
それを見たカレンベルクは、ギュスターヴが完全に動かなくなったのを確認しようと近付く。
老体の脈を測ろうとしたその瞬間、カレンベルクの目の前に光り輝く不思議な文様が出現した。
「しまっ――」
油断したつもりはなかった。だが、ギュスターヴの巧妙な罠にはまってしまった。
文様から放たれた光と熱が、うねりとなってカレンベルクに襲い掛かる。
(防ぎきれない!)
諦念から目を瞑ってしまうカレンベルク。
その時、突如カレンベルクの身体が光に包まれ、宙を舞った。
「何だ!?」
術を回避されるとは思っていなかったのか、ギュスターヴは明らかに動揺を見せた。
カレンベルクも何が起こったのかわからずに困惑したが、ギュスターヴよりも早く我に返ると、そのままギュスターヴに向かってザジの楽曲をぶつける。
動揺した隙を突かれたギュスターヴは、カレンベルクが奏でる復讐の楽曲をまともに浴びてしまう。
「こ、こんな……こと、が……」
カレンベルクの力を全身に受けてしまったギュスターヴは、今度こそ絶命した。呼吸も止まり、もはや二度と動き出さないことが明白であった。
カレンベルクを包んでいた柔らかな光は徐々に弱まり、間もなく消え失せた。
光が消える間際、誰かの囁き声が耳に届いた気がした。だが、カレンベルクはその声を聞き取ることはできなかった。
「……まだ終わってはいない」
動かなくなったギュスターヴから視線を外すと、カレンベルクは玉座の間から立ち去った。
能力のぶつかり合いによって体力は殆ど残っていなかったが、そんなことに構ってなどいられなかった。
広大な地下施設の一部屋一部屋をカレンベルクは調べて回った。
ビアギッテがこの場にいないとしても、行方を知る何かしらの手掛かりを掴めればそれでいいと考えた。
結局、ビアギッテに関する情報は何も得られなかった。
だが、諦める訳にはいかない。首領が滅したことで、超人組織の有り様も変化するだろう。
その混乱に乗じてビアギッテを探し出し、取り戻す。
カレンベルクは決意を新たに、崩壊した組織の本拠地から立ち去るのだった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ