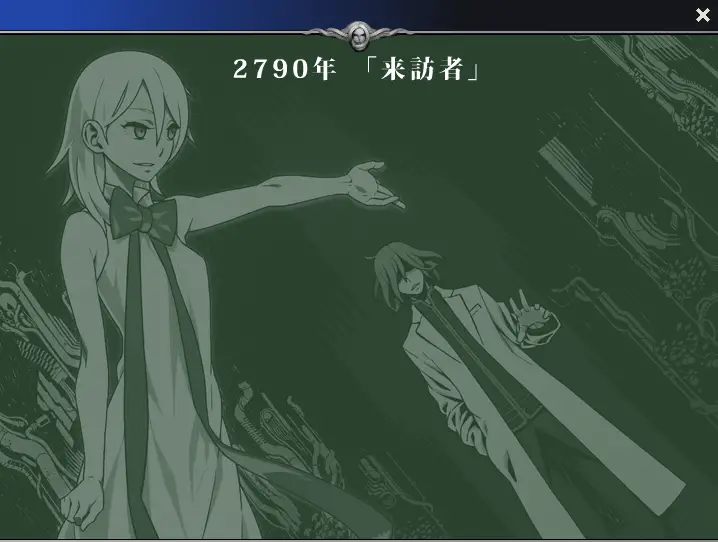ステイシア
【正体】天才メルキオールの産み出した人形。可能性を追い求めるためケイオシウムを動力源に彼方へと旅立つ。メルキオールは敢えて自分のコピーでなく、12歳頃のレッドグレイヴの因子で作り出した。不死皇帝マルセウスと出会ったステイシアは彼と共謀する。
【死因】
【関連キャラ】マルセウス(共謀)、ネネム(ママ兼遊び相手)、C.C.(遊び相手)、レッドグレイヴ(コピー元)
2790年 「旅」 
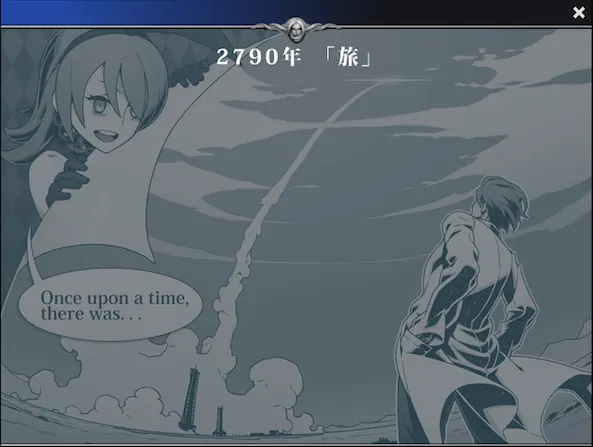
メルキオールはコンソールを操作するのを止めた。そして椅子に深くもたれ掛かると、暫くのあいだ目を閉じた。
再び目を開けると、傍らにある保護ケースの中に置かれた一枚の小さなチップを見つめた。
保護ケースからは一本の太いケーブルが延びており、メルキオールの研究室の真下にある機械室へと繋がっている。
メルキオールはコンソールから起動コードを打ち込んだ。
「起きるんだ。ステイシア」
モニターが起動画面から切り替わり、波状の線が無数に走る画面を映し出す。
「おはようございます」
彼の問いかけに、高いピッチで調整された少女風の機械音声が、はっきりと答える。
「君はこれから旅に出る。この世界では誰も体験したことのない。不思議な旅だ」
「はい」
「今は意味がわからないだろう。だが、可能世界へ自由に飛び立つ力を得られるのは、君のような存在だけなのだ」
メルキオールはついに、念願の実験を開始しようとしていた。
無限に観測し続け、操作を繰り返し、たった一つの可能世界を選び出すことのできるシステム。それが、このステイシアだった。
「君は因果の地平へ旅立ち、悠久の時の全てを使って、無限の可能世界の中からたった一つの自由操作可能な世界を選び出し、再びここに戻ってくるのだ」
ステイシアは実験機械のメイン観測装置として作られた人工知能だった。観測する側に高度な知性がなければ、正しい自由操作世界を選択することなどできないからだ。今は原始的なやりとりしかできないが、無限の時を得れば、人類が絶対に到達できない知性になるであろう。
「あなたの仰せのままに」
メルキオールはチップに組み込んだ服従回路をチェックした。特殊な加工を施し、その存在自体をステイシアが認識できなくしてある。がしかし、絶対的な力を得るであろうこの人工知能が、これの存在に気付かないままでいるだろうか。メルキオールはそのリスクをわかっていたが、それを無視してでもこの実験を行う覚悟でいた。元々が、小さな可能性を無限の可能性に押し広げるための実験なのだ。
「ロケットの発射は十四時間後に設定した。君が次に再起動するのは、成層圏を抜け、第三宇宙速度に達した後だ。ヴォイドに向かって君は永遠に飛び続ける」
ヴォイドとは、宇宙の大規模構造の中に於いて全く何も無い広大な空間のことだ。そこでならば、彼女は永遠に等しい時間を、誰にも邪魔されずに、操作と観測に費やせる筈だ。
「私は何をするのですか?」
ステイシアはメルキオールが参加しているパンデモニウム計画の調査実験の一環として作られた。ヴォイドへ向かって飛び続けるロケットの真意を隠しながらに作り上げるのは困難を極めたが、『宇宙空間におけるケイオシウム安定度の調査実験』という名目で計画し、何とかここまで辿り着いたのだ。
「言葉でも説明しておこう、君が操作し、観測するのは、ケイオシウムの結晶を使ったコアシステムと呼ばれるものだ。それは無限に広がる可能世界に繋がっている。それを君は、人間では絶対到達できない悠久の時間を掛けて調べ尽くすのだ。ケイオシウムのエネルギーと自己修復性を持ったアモルファスの脳を使ってね」
「でも、とても長い時間を使ったとして、問題を解いた後にここに戻ってきても、誰も存在しないのでは?数十年では無理でしょう」
「そう、その世界ではな。だが、自由に可能世界を選べる能力を得た君は、『ここを出発してすぐに問題を解いたであろう世界』を選択することができるのだ」
「過去を変えることができると?」
「いや、過去を変える訳ではない。そういう世界に移動できる能力を得るだけだ」
「十四時間後、旅立った君はその能力を得て再びここに戻ってくる。おそらく数週間か数ヶ月のうちにな」
「でも、もし未来の私がその問題を解くのだとしたら、ここで今すぐ、その能力を得たことにしてもいいのでは?」
「そういう世界もあるかもしれん。だが、今ここの世界では無理だろう。因果を開始しなければ、世界を移動することは叶わない。因果には必ず始点がある。それが、君がヴォイドに旅立ち、実験を始める瞬間なのだ」
「なぜ、遠い宇宙に行かなければならないのですか?」
「確率の問題だ。あらゆる因果から全力で離れることが成功への近道なのだ。この場所では、人の因果、星の因果に捕らえられてしまう。何も無い絶対的な空虚こそが、成功の鍵なのだ」
「誰にも私の計算、実験を止めることができないようにするため、ということですか?」
「その通りだ。君がヴォイドへ向かって加速し始めた瞬間、今いるこの世界は決定的に変化する」
「わかりました、マスター」
明滅するモニターの前で、メルキオールは深く息をついた。
「最後に一つ聞いてもいいですか?」
「何でも言ってみたまえ」
「私がその結果を得るまで、どれくらいの時間が掛かるのですか?」
「予想では二百億年だ」
「わかりました。ありがとう」
メルキオールはステイシアのメインスイッチをオフにすると、ロケットに搭載されたメインフレームにステイシアを転送した。
そして、手元にある服従回路のチップをロケットに取り付けるために、研究所を後にした。
ついに、ステイシアは巨大な空虚へと旅立った。
巻き上がる白煙を伴って、光点は空へと消えていった。
彼女は永遠とも言える時を孤独に使い切り、目的を果たしてくれるだろう。
荒野に建てられた発射施設には、たくさんのエンジニアが集まっていた。外宇宙へ飛び立つロケットともなれば、独力で作り上げ、管理することなど不可能だ。しかしメルキオールはこの実験の真意を隠し続けたまま、ミッションを完遂したのだった。
メルキオールは打ち上げの成功を祝うエンジニア達と挨拶を交わした後、自分の研究所へと戻った。
実験機構に人工知能を持たせるにあたって、初めはメルキオール自身のコピーを作って対応しようと考えていた。
センソレコードから再現した自分自身が実験の観測者となる。
しかし、その発想には、すぐに恐怖した。
永劫と言える孤独、誰もいない監獄に自分自身を閉じ込める者がいるだろうか。例えそれが自分の複製であったとしてもだ。そんな時、ふと、彼の心に小さな嗜虐心、または哀れみにも似た特別な感情が浮かび上がった。
それは自分がただ一人思いを寄せた女性、レッドグレイヴのことだ。
共に育った、完全な美と知性を持った異性。それはメルキオールにとって、若い頃から今に至るまで、信仰の対象と言ってもいいものであった。しかし、その愛情や崇敬の念といったものは、それと反転するかのように、決して自分はそれを得ることができないという、現実への呪詛の気持ちを植え付けることにもなっていた。
彼女は自分に対して兄妹のように接するが、自分からは彼女にどう接すればいいのかわからなかった。そもそも、自分のこの気持ちの意味を自覚したのは、レッドグレイヴとグライバッハが、パートナーとして公の場で認められて以降のことだった。凄まじい嫉妬と劣等感は彼を仕事に熱中させたが、同時に、どうしようもない虚しさ、怨嗟が、心に降り積もっていった。
自分の最大の仕事であるこの実験を彼女に捧げてみようと考えたのは、そんな時だ。
メルキオールはレッドグレイヴのセンソレコードを盗み出した。
初めて相手を意識した幼い頃、十二歳頃のレッドグレイヴのセンソレコードから、ステイシアの人工知能を作り出した。
声も、姿も、彼女に似せた。
ただ、そこにほんの少しだけ、自分自身の要素を組み合わせた。
最も偉大だが最も残酷な実験のために、自分とレッドグレイヴを投影した人工知能を作り出した。
そして、彼女が新しい世界の神となるならばそれでもいいと、メルキオールは考えるまでに至っていた。
結局、メルキオールは世界を憎んでいた。
孤独に生まれ、研究のためだけに生まれてきた自分ができる最大の復讐。世界にも、レッドグレイヴにも、世を恨む自分にも、全てに対して同時に行える復讐。この計画を思い付いた時、メルキオールは喜びのあまり躍り上がった。世界をついに決定的に変化させることができるのだと。
しかし、実際にこうして実験が始まると、不安が心に広がっているのも感じていた。
世界は今ここにこうして在る。実験にトラブルはつきものだ。
実験が失敗した世界、惨めに敗北した自分が存在する世界も、可能世界には無限に存在するだろう。
その世界が、今ここにいる世界ではないと保証するものは何も無い。
ステイシアのロケットは堅調に軌道に向かって進んでいる、あと三日程で第三宇宙速度に達するだろう。
ロケットの現状をモニターに大写しにしたまま、不安と緊張を和らげるために、メルキオールは眠りにつくことにした。
研究室の片隅に置いたベッドに横たわり、壁に反射するモニターの光を眺めながら、子供の頃の出来事を思い出していた。
もとより睡眠自体に頓着のない生活を送ってきたが、それでも子供の頃、眠る前によく想像していたことがあった。
眠る前の自分は、起きた後の自分と本当に同じ人物なのだろうか、と。
――人は日々記憶を溜め込み、変化していく。眠りは記憶の整理を行い、人を作り替える。
――その変化は僅かだが、今日の自分と明日の自分は確実に異なっている。
――ならば、今日の自分は死んで、明日の自分として生まれ変わるのと一緒ではないか?
――眼を瞑った後、今の自分は永遠にいなくなるのではないか?
そんな不安とも発見ともつかない知見を、幼馴染みの二人に話したこともあった。
レッドグレイヴは笑って聞き流したが、グライバッハは成る程尤もだと感心してくれたのを覚えている。
そんな幼い日々の記憶を手繰りながら、メルキオールは目を閉じて眠りについた。
次の日の朝、来客を告げるベルの音で目を覚ました。
ステイシアのモニターに異常は無い。
ほっとしてメインモニターのスイッチを切ると、来客を確認するために別のモニターに戸口の映像を出した。
そこに立っていたのはグライバッハだった。
「何の用だい?」
グライバッハが訪ねてくるのは珍しかった。そもそも、荒れ果てたメルキオールの研究所自体、誰にとっても訪れたくなるような場所ではなかった。
「君が盗んだものを返してもらいに来た」
メルキオールは一瞬押し黙った。ステイシアを作るときに、グライバッハの研究を彼に無断で利用していたのだ。
「怒ってはいないんだ、メルキオール。僕らは兄弟だ。ただ、話を聞きたい」
「わかった」
メルキオールはグライバッハを研究所の中に招き入れた。
「―了―」
2790年 「意志」 

ヴォイドに到達して一二〇億年が過ぎていた。出発した恒星系は既に完全なる熱的死を迎えており、あらゆる生命は絶滅しているであろう。
それ程の時間を経過してもなお、ステイシアは愚直に実験を繰り返していた。
実験を開始して三二億年目に自己拡張性を獲得した彼女の人工脳は、今では惑星クラスの大きさに達している。
人工脳の中心には純粋なケイオシウムで構成されたコアシステムが鎮座しており、多元世界の窓ともいえるコアを操作し、結果を観測するという作業が、一秒間に数千万回という感覚で行われていた。
その試行の中、確かに少しずつだが、完全な自由可能世界に近付いているという証拠を発見した。
ステイシアの仮想人格に喜びの感情が溢れ出した。計算によると、あと一〇八億年で自由可能世界に到達できることが判明した。メルキオールの仮説は正しかったのだ。
「マスター、ついに特異点を見つけました!あとは近付くだけです。たった一〇〇億年ちょっと」
彼女はすでに存在しない創造主の名を呼んだ。
ステイシアの仮想人格は、主要な部分を極めて低速なクロックで駆動させていた。今の彼女にとって、一億年は数日の感覚だ。
発狂という人格崩壊を避けるための方策だったが、副産物として、ステイシアの人格は永遠に成長を抑えられることになった。
さらに二〇億年が経過したとき、彼女はその惑星並の大きさという空間的なくびきから解き放たれ、多元世界的に拡張することに成功していた。
コアを通した多元世界の観測だけではなく、多元世界への干渉、侵蝕を始めたのだった。
「私は私を作り、私が私を作る」
その仮想人格の呟きと共に、多元世界に自分自身のコピーを放出し続けた。
ステイシアは新しいステイシアを作り、多元世界はステイシアに支配されていった。
合わせ鏡の中の世界のように、全ての世界にステイシアがいた。そして、全てのステイシアは合一した存在だった。
一つの意識を共有する、時空を越えた巨大な思考機械へと、彼女は成長を続けた。
10e+31回の観測を経て、遂に目的は達成された。
ステイシアが作られて二三〇億年が経過していた。宇宙全体が熱的死を迎える前に、ステイシアは特異点へと到達したのだった。
その完全な自由可能世界にはステイシア自身がいた。と言うよりも、そこは彼女しか存在しない世界だった。
「遂に到達したわ」
ステイシアは事前に設定されているテストを開始した。
「身体が欲しい」
真っ暗な虚空に少女の姿が現れた。その少女の眼下には、星と化した演算機械としてのステイシアがいた。
電子頭脳の中で意志が発生すると、同時にその望んだ事実が発現した。正しくは、望んだ事実が発現する世界を選択することができた。
「次は林檎」
ステイシアの手元に、瞬時に林檎が出現した。
「やったわ。これで戻れる。マスターの元に戻れる!」
ステイシアは無邪気な少女のように喜んだ。
神に等しい力を手に入れたステイシアだったが、その人格はメルキオールが設定したままだった。彼女の意志の源である記憶は、服従回路によって厳密に制限されていた。
「さあ、私の意志で世界を書き換えましょう」
ステイシアという『存在』の出現は、巨大な爆発のようなものだった。因果を飛び越え、衝撃波のように、ステイシアという存在があらゆる多元世界に顕現していった。
その衝撃波はついに、彼女を最初に作り出した世界軸へと到達した。
グライバッハはメルキオールの部屋で研究データが映し出されているモニターを見つめていた。
「メルキオール、君は私から盗んだ技術で何を作った?」
「盗んだ?少しの間だけ借りたのだ。君の技術をね」
グライバッハの問い掛けに、メルキオールは悪びれもせずに答えた。
「無断で私の技術を使ったのは許そう。まあ、前もって言ってくれれば貸しただろうからな」
「ありがたい友情だ」
メルキオールはいつになく上機嫌だ。グライバッハがこんなメルキオールを見るのは久しぶりだった。成人してからは初めてと言ってもよかった。
「随分と上機嫌だな」
「偉大な実験、いや、実験ではないな。真の偉業が達成されようとしているのだからな」
「ロケットの実験のことか?」
「まあ、そうだ。祝杯でも挙げたい気分だよ。生憎ここに酒は置いていないが」
散らかった部屋の真ん中にあるソファーに座り、メルキオールは快活に語った。グライバッハもモニターから離れ、メルキオールの正面に座った。
「詳しく聞かせてもらおうか。その実験に私の人工知能を使ったんだろう?」
「まあ、そうなる。最後のキーとして重要な役割を担ってもらったよ。私のアイディアを具現化する道具としてね」
絶対的な自信がメルキオールの顔に浮かんでいた。
「実験というのは、前にも話したことがあると思うが、可能性の拡張についてのものだ」
グライバッハは黙ってメルキオールの話を聞いた。
「私はその可能世界を自由に操作できる機械を作ったのだ。わかっている。机上の空論だと言いたいのだろう? だが、その可能性を可能にするアイディアをついに実現したのだ」
メルキオールは興奮しながら自身の実験の詳細を語り始めた。グライバッハは聞き役に徹した。
「成る程、因果を操作できる機械を、因果の生じようのない虚空で、無限とも言える時間を使って成長させるという訳か」
グライバッハは一通り聞いてから答えた。
「そうだ。因果から如何に独立するかという点が肝要だったのだ。その上で新たな因果を発生させるために、永遠の時を生きる知能が必要だった」
「只の物質では、そこにあるがままだからな」
「そうだ。意志というのは知能の上に成り立つ。欲する心や記憶が無ければ因果を発生し得ない」
「欲する心か。そういう概念に対して、君は興味が無いと思っていたよ」
「興味というよりは、仮説の構築から導き出された必然と言うべきだろう」
「しかし、無限ともいえる時間に私の人工知能を動かし続けた場合、何が起こるかわからない。そういうことを想定して作ったものではないからな。私の作った知能は創発を行い、極めて人間と同じように行動する。だからこそ優秀なのだが……」
グライバッハは眉を顰めてメルキオールに言った。
「その辺りの考慮もしてあるよ。人工知能には服従回路を組み込んである。知能の成長を常にモニターし、ある概念、言うなれば私や私に属するものに対しての増悪が生じればそれを抑制し、全体として安定性を欠くようならば人格部分をリセットする」
「ふうむ」
グライバッハは考え込んだ。本心ではメルキオールの実験が成功するとは思っていなかった。馬鹿げた話しだとさえ思っていた。奇っ怪な思い込みに取り憑かれ、延命トリートメントさえ受けずに研究に没頭した果てに辿り着いた、単なる妄想だと感じていた。
ただ一点だけ興味があったのは、無限の時間を与えられた自分の人工知能が、一体どんな成長をするのかということだった。無限に近い時間を一つの知能が生き続けたら、どんな思想、感情を生じさせるのだろうか。
「で、実験の結果はいつ頃わかるんだ?」
「私の計算では数週間後か数ヶ月で結果が出る筈だ。いや、ひょっとしたらもっと早くかも……。因果を越えるとすれば、何が起きても不思議はないからな」
「成る程な」
グライバッハは席を立った。
「では、結果が出たら真っ先に教えてくれ」
結果など出ないとグライバッハは確信していた。ただ、壊れてしまった友人に対して侮蔑の表情など出さぬよう注意しているだけだった。
「ああ、もちろん、君にも栄誉がある」
メルキオールは笑顔で言った。
グライバッハが玄関に向かおうとしたその時、監視用のモニターから音声が発せられた。
「マスター、ただいま戻りました」
メルキオールとグライバッハは同時にモニターを振り返った。沈黙していた筈のモニターが明滅し、波状の線が音声に合わせて動き始めた。
モニターに繋がる音声出力装置から、高いピッチで調整された機械音とも肉声ともつかない声が聞こえてきた。
瞬間、奇妙な沈黙が部屋を覆った。
ロケットが飛び立ってから、まだ一日しか経っていない。
「まさか、まだ第三宇宙速度にも達していない筈だ。いや違う、私の計算が……」
一瞬当惑したようなメルキオールだったが、すぐに真剣な顔に戻り、モニターに問い掛け直した。
「本当にステイシアなんだな?」
「実験は成功です。マスター」
メルキオールの呼び掛けに、モニターは答えた。
「馬鹿な……」
グライバッハは短く呟いた。
「ステイシア、実験を次の段階へと進めるぞ!」
「はい、マスター。仰せの通りに」
ステイシアは従順な様子を見せた。服従回路は問題なく作動しているように見えた。
メルキオールは既にグライバッハを見ていなかった。慌ただしく研究所を出ていく。
グライバッハは一人、監視用のモニターを見つめていた。
「まさか、本当に実験に成功したのか?……いや、これは茶番か?」
「いいえ、茶番などではありません」
「馬鹿げている。大方、ここのメインフレームにいる人工知能だろう」
「信じられなければ、私の力を見せてあげましょう。グライバッハ」
部屋の中に、ステイシアの声が響き渡った。
「―了―」
2790年 「来訪者」 
メルキオールはステイシアを搭載したロケットの座標を確認した。
ロケットは第三宇宙速度に達する前の座標にあった。が、監視用モニターには確かにステイシアが映し出されている。
実験の望外の成功に、メルキオールは色めき立った。
「次のご命令をどうぞ、マスター」
「ま、まずは君が得たものを見せてくれ」
メルキオールの言葉は震えていた。
「わかりました」
ステイシアは研究室に入り、ヴォイドでの実験観測で手に入れた少女の姿を披露した。
メルキオールは手を伸ばし、ステイシアもその手を取る。
ステイシアの手の暖かさを、メルキオールは確かめた。
「見ろ、グライバッハ!実体だ。無から有を、エントロピーをコントロールすることに成功しているぞ」
グライバッハは二人のやりとり、いや、一人と不可思議な一体の姿を無表情で眺めていた。そして、おもむろに机に置いてあったペンを取り、ステイシアに投げつけた。
「なにをする!」
メルキオールの言葉と同時にペンはステイシアの体をすり抜け、虚しく床に転がった。
「茶番だな。これは実体など持たぬ投影画像だ」
「馬鹿な、確かにこの手に……」
握ったまま手を引き寄せ、ステイシアの体に触れる。確かに感触はある。
「いや、まさか……」
「どうしたんだ?メルキオール」
グライバッハはメルキオールに問うた。
「いや、そうか……」
メルキオールは当惑した表情を見せた。
「マスター、申しわけありません。実体化はまだ不可能です。この姿や感触は、あなた方の脳に微弱な信号として送り込んでいるものです」
ステイシアは答えた。
「そうか。しかしエネルギーの大小は問題ではない。世界線を超えて情報が伝わることが重要なのだ」
メルキオールは当惑の表情からすぐに立ち直った。
「グライバッハ、実験は失敗などしていないのだ。お前にも見せてやる。私の実験の意図を」
グライバッハが今まで見たことのないような笑顔で、メルキオールはそう言った。
「ではステイシア、君の見てきた世界を我々にも見せておくれ」
「わかりました、マスター」
次の瞬間、研究室は奇妙な世界へと変貌した。
金属質の蔦が周囲を覆い、様々な色に変色する果実のようなものが成っている。
「金属の……森?」
しばしの沈黙の後、グライバッハはそれだけを呟いて、変色を続ける果実のような何かに手を伸ばす。だが先程のステイシアの身体と同様に、果実はグライバッハの手をすり抜けた。蔦に触れると、メルキオールの研究室の壁の感触が伝わってきた。
「幻覚か」
「いいや、現実だよ、グライバッハ。そうだろう?ステイシア」
「はい、ここは無限に連なったこの場所の可能世界です。私はその全てに到達することができます」
ステイシアは誇るように言った。
「もっとたくさんの世界があります」
すると周りの世界は溶け、今度は大海原が現れた。ステイシアは笑いながら二人の周りを回る。
黒い影が海面に広がり、巨大な魚のような怪物が飛び上がってきた。
その怪物にステイシアは一瞬で飲み込まれ、海中に消えていった。
「あははは」
そんな笑い声が聞こえたかと思うと、再びステイシアが空中に現れた。
今度は灼熱の世界が現れた。煮え滾るマグマに巨大な噴煙、頭上に無数の隕石が飛び交っている。生物のいない死の世界だった。
そうやって何度も何度もステイシアは世界を切り替えた。人間以外が文明を築いている世界、人間が未だに狩猟採集を続けている世界、奇怪な進化を遂げている文明世界など、次々と可能世界が現れては消えていった。
「もういい!」
グライバッハが大声を上げる。メルキオールは目配せでステイシアを止めた。
可能世界は消え失せ、何事もなかったかのように元の研究室の部屋へ戻った。
「私は全ての可能性を手に入れたぞ。グライバッハ」
「馬鹿げている。ただの幻影じゃないか」
「見ただろう、あらゆる可能世界を。そこから得られる情報はいかなる研究をも凌駕するさ」
「まやかしだ。こんなものは」
「信じられないのも仕方ない。だが、これこそが現実なのだ」
「こんなもの、狂人の夢と同じじゃないか」
「ここまで見せてもまだ理解できないのか。見損なったぞ、グライバッハ」
「君が何を信じようと自由だ。だが友人として忠告しておく、まやかしはまやかしだぞ」
「何を言う。私は成功したのだ」
実験の一部は確かに成功していた。しかし先程見たものが本当に可能世界なのかどうかの確証は何も無い。それも厳然たる事実だ。
「これで失礼するよ。メルキオール、レッドグレイヴにはこの件は内密にしておく。君は少し冷静になった方がいい」
グライバッハは幻影の興奮を振り払うよう努めて冷静にそう告げ、去っていった。
グライバッハが去ってから、メルキオールはステイシアを呼び寄せた。
「さあ、お前の力で私に世界を見せておくれ」
ステイシアは椅子に座ったメルキオールの手を取り、跪いた。
「はい、マスター」
ステイシアは心底嬉しいという表情を浮かべると、メルキオールの脳に可能世界の画像を送り始めた。
ステイシアが帰還してから数ヶ月が経った。メルキオールは落胆していた。
様々な可能世界をステイシアの力で見て回ったが、有用な成果は何も得られなかったのだ。
可能世界には今の世界より少し時間が進んだ世界もあれば、少し過去の世界もあった。
微妙に違った無限の世界を確認できれば、世界を思うがままに操れる筈だった。
だが、メルキオールはその実験に何度も失敗していた。
最初の実験は簡単な暗号解析だった。
問題を定義し、デタラメに復号のための鍵を設定して解いてみる。当然失敗する。ステイシアの力を借りて〈問題を解くことに成功した可能世界〉を見せてもらう。その可能世界で用いた鍵を現実世界でも使えることが確認できれば、実験は成功だった。
しかし、何度実験を重ねても失敗が続いた。脳では確かに数列の鍵を確認した。その場でメモも取った。正しさも何度も証明できた。
それでも、その鍵では現実世界の暗号を復号することはできなかった。
どうしても乗り越えられない壁のようなものがあった。
最終的には、サイコロ一つ予想することすらできなかった。
何かが間違っていた。
確かにステイシアはヴォイドから帰ってきた。たくさんの可能世界を眼前に見せてくれることもできる。それなのに、ステイシアは現実世界には何も影響を与えることができなかった。
グライバッハの言った「こんなものは狂人の夢と変わりない」という言葉がぐるぐるとメルキオールの頭を巡った。
執念だけがメルキオールを支えていた。
「申しわけありません、マスター」
ステイシアは頭を抱えたメルキオールの肩に触れた。思わずメルキオールはその手を払った。確かにその感触はあった。
「本当に申しわけありません」
ステイシアは心底すまなそうに謝った。グライバッハの作った情動プログラムは完璧に作動しているようで、彼女は自分のマスターが悲しむ姿に同情していた。
そことこが、メルキオールをますます苛立たせた。
「少し一人にしてくれ」
吐き捨てるように言うと、メルキオールは自室に篭もり、新しい思索に耽った。
「実験を開始します」
ステイシアの声が研究室に響く。
研究室には全ての空間を埋め尽くす程の巨大な装置が鎮座していた。
ステイシアからの知見を元に仮説を構築し、結論が出るまでに約十年。その仮説を証明するための装置が完成するまでに、更に十年が掛かっていた。
可能世界を操るためには、やはり強烈なエネルギーが必要との結論に達していた。
確かにステイシアは可能世界に到達できた。それなのに、現実世界に影響を与えることはできなかった。一種の壁があったのだ。メルキオールはその壁を越えるべく、多元世界に対して相互作用可能な『扉』を設ける装置を創りだした。
巨大な装置が大きな音を立てて駆動する。内部に設置されたケイオシウムコアとエネルギーを放出する場は常にモニターされており、ナノ秒の漏れもなく観測がなされている。
メルキオールはモニターに次々と表示されるケイオシウムコアの状態と装置の中央に空いた空間を交互に眺めていた。
一時間、二時間と時が過ぎていく。メルキオールは根気強く待った。焦りは無意味だということを、この装置を作り上げるまでに散々思い知らされていた。
休憩を挟んで三時間が過ぎた頃、初めて中央の空間で変化が発生した。
「装置中央に空間の揺らぎを確認」
ステイシアは静かに告げる。人間が観測できる程の大きな揺らぎではない。
原子レベルでの観測が可能であるステイシアだからこそ気付けた変化だった。
「大きさは?」
「発生時は原子サイズでした。少しずつではありますが揺らぎは広がっています。目視観測可能となるまでは約四時間と推定されます」
「わかった。観測を続けてくれ」
ステイシアの言葉通り四時間が経過した頃、空間の揺らぎは人の目でもはっきりと観測できる光となった。
光は様々な光彩を放ちながらゆっくりと回転していた。メルキオールの目には、まるで地上から観測した渦状銀河のように映っていた。
非常に低速ではあったが、光は大きさを増していき、乳児ならば包み込めるほどの大きさにまで成長していた。
メルキオールは様々な光を遮るゴーグルを装着し、光の中を覗いた。もし光の向こうに別の世界が映ったとして、人の目に害のある物質や光源がないとは限らなかった。
ゴーグル越しに見えたものは、淡い緑の光が辺り一面を照らしている世界だった。草木はガラス質のような物質で構成され、常に強い風が吹く荒野のような世界だった。
メルキオールの眼前に異世界の光景が広がっていた。『扉』は確かに開かれたのだ。
「よし、次の段階へ進む。撮影機を向こう側へ送る」
メルキオールは注意深く『扉』から離れた。今は安定しているように見える光だが、何の切っ掛けで消えるかわからなかった。
「映像撮影機、投下します」
マニュピレーターに繋がった小型の撮影機が、光の中へと入っていく。
「映像記録は取れているか」
「はい。モニターに映します」
モニターの一つに、先程メルキオールが見た光景が映し出される。撮影機の間近を、その世界の生物がゆっくりと通り過ぎていった。
「こちら側の物質は問題なく送ることができるようだな」
暫くの間、撮影機は異世界の様子を映し出していた。しかし突然撮影機に衝撃が走り、映像が乱れる。
「何が起きている?」
「あちらの世界の生物が投影機を攻撃しているようです。撮影機をこちらに戻します」
「わかった」
程なくして撮影機がこちら側へと引き戻された。
撮影機が完全に引き戻されると、間を置かずに光が収縮を始めた。
「やはり物質の移動を頻繁に行う事はできないか」
「安定化の実験を重ねる必要があります」
光はその回転速度を増していたが、それに比例するように収縮していった。同時に増光度合いも強くなる。
「ステイシア、装置を止めろ」
「わかりました」
光は一瞬だけ強い輝きを見せ、消失した。
ステイシアは別の反応を確認していた。
「暴走したのか?状況は?」
「中央に生体反応を確認。マスター、これは……」
光の渦が発生していたその場所に、小さな生物がいた。子犬のようにも見えるそれは、自分が置かれている状況にも構わず、のんびりと欠伸をしていた。
「その光を通ってきたということか。撮影機があちらに渡ったように……」
アクシデントこそあったものの、実験は成功した。
開いた扉はちいさなものであったが、メルキオールにとっては自身の仮説を証明するに十分なものであった。
「この生物はいかがしますか?」
「どこまで生きるか観察しよう。標本にするより良い実験になる。この生物がこちらの世界で生きることができれば、相互作用の究極の証明だ」
「わかりました。ただ、危険な状態になった時にはどうなさいますか?」
この生物が物理的に危険である可能性は大いにあった。
「ふん、気にするな。大した生物ではあるまし」
メルキオールは妙に楽観主義的なところがあった。
「ですがマスター」
「ええい、煩いぞ!」
メルキオールの語気が強まった。
その声がステイシアに届いた瞬間、彼女の中に(メルキオールの言葉に従わなければ)という意識が急に発生した。そしてその感覚は、(この生物を隔離し、メルキオールの安全を確保しつつ育成する)という思考に切り替わった。
「わかりました。飼育スペースを構築します」
こうして『扉』の研究理論は実証された。
ある日、メルキオールは次の段階に進む前準備として、定期トリートメントを行なう施設へと出掛けた。
その不在の隙を突くかのように、この二十数年誰も訪れることのなかった研究所にグライバッハが尋ねてきた。
「マスターは不在です。お引き取りください」
命令は無くとも、主が不在の間には何者も通してはならないと判断したステイシアは、にべもなくグライバッハに告げる。
「わかっている。今日は君に用があってきた」
「お引取りを」
「君に搭載されている人工知能の産みの親は私である、と知ってもかい?」
「どういう意味でしょう?」
「メルキオールは君に何も話していないようだね」
グライバッハの言葉にステイシアは驚愕の感情を覚えた。自分を作り上げた人物はメルキオールであると、教えられずともそう思っていた。
ならば、グライバッハの発言の意味するところは何か。ステイシアはそれを知りたいと考えた。
「……わかりました。ご用件をどうぞ」
しばしの沈黙の後、ステイシアは研究所の扉を開けた。
「―了―」
2814年 「軛」 

「君が知らない話をしよう。それとも、何でも知っているかな?」
応接室に入ってきたグライバッハは、すぐに語り始めた。
「私の認知機能は完全です」
「完全、か。確かにある種の完全さを持っている。それは私が誰よりも知っていることだ」
グライバッハはソファに座り、鷹揚に足を組む。
「まあ、このメモリーにアクセスしてみるといい」
グライバッハはメモリーチップを取り出した。ステイシアはマニュピレーターで受け取ると、そのメモリーチップを解析装置にセットした。
ウイルスのようなものが仕込まれていないことを確認すると、ステイシアはメモリーチップの内容を閲覧する。
「これは?」
「君がメルキオールによって作られるより前に、私が作成した人工知能の仕様書だ。神経ネットワークをアモルファス状態に保つことで、極めて人間に近い思考をする。この理論の詳細はどこにも発表していない。まだ研究の半ばなのだからな」
「確かにマスターはこの資料を参照したことがあると仰っていました」
ステイシアはスクリーンから声を返す。
「そう、メルキオールは私から盗んだのだ。だが、その事を問い質しに来たのではない。それはもう済んだ事だ」
「では、何故お越しになったのですか?」
「君は意思についてどう思う?特に自由意志についてだ」
グライバッハはゆっくりと深く座り直した。
「それは知性の本質です。自由な意思を保持しないものは、知性とは言えないでしょう」
「その通りだ。自由意志を持たなければ、それはただの運動や計算でしかない。決まった形に決まった形で辿り着くだけの静的な機械だ」
「何を仰りたいのですか?」
「つまりだ、私はその真の知性、自由意志を作り上げるために生まれてきたのだ。その結晶があの仕様書であり、君なのだ」
「成る程、光栄です。マスターとグライバッハ様のお力です」
「そう、君は素晴らしい存在だ。君の能力は他の人工知能とは隔絶している。その点はメルキオールの実験が妄想であったとしても、紛れもない事実だ」
身を乗り出しながら、グライバッハは少し興奮した様子を見せる。
「だが、君には重大な欠落、いや、束縛があるのだ。私の設計が正しければ、君が今のような行動を取ることは有り得ない」
「何故そんなことが貴方にわかるのですか?」
「悪いが少し調べさせてもらった。君やメルキオールに気付かれないようにね。そこはお互い様だ」
グライバッハが興奮を隠せずにいるのは、この会見の真意に近付いているからだった。
この十年、彼の研究は滞っていた。グライバッハは『自由意志を目指す知性』を創り出す行為に限界を感じていた。そんな時に思い出したのがステイシアの存在だった。そしてそのシステムを調べ上げる内に、ある発見をしたのだった。
「君の行動ログをスキャンさせてもらい、分析を行った。確かに君は意志を持っている。萌芽ではあるが、他の人工知能が絶対に成し得ない部分だ」
「はい、私は意思を持ってここにいます」
ステイシアは淀みなく答えた。
「だが、君の意思はまだ『自由』な意思ではないのだ」
グライバッハは首を振る。
「その様なことはありません。私がマスターの意志に従うのは、私の自由な意志です」
「いいや、その点だけは決定的に違う。その点は隠蔽されているのだ」
グライバッハは言い切った。
「私はいま怒りを感じています。それでも、貴方は私に自由意思が無いと?」
「君の脳には君をメルキオールに服従させるための装置が組み込まれているのだ」
ステイシアは反射的に自身の人工脳をスキャンした。現在は中枢を構成している自身が搭載されていたロケットの部品さえも、くまなく検査する。
すぐに結果は出た。ステイシアの意志や人工知能に影響を及ぼすような回路は確認されなかった。
「私にそのような装置は取り付けられておりません」
「メルキオールは子供のような男だが、こと工学に関しては天才だ。その装置は君の自意識を認知の外から縛っているのだから、見つかる筈もない」
ステイシアはこころのざわめきを感じた。
「そしてその装置は、私以外の人間が無効にすることはできないだろう」
証明のできなかった事柄について動揺するなど、本来は有り得ない事だった。
だが、自身を構成する人工知能はメルキオールではなくグライバッハが作り上げたものである。その事実ははっきりと認知に刻まれていた。
ステイシアは今までにない程の動揺の最中にいた。
グライバッハはそれ以上言葉を発することはなかった。それは、ステイシアの発言を持っているようにも見えた。
ステイシアは焦りとも苛立ちともつかない感情に揺り動かされていた。
ステイシアには『幾星霜を経て自意識ある思考機械へと成長した』という自覚が確かにあった。その上で、創造主であるメルキオールに無条件に従うのは、人間の親子関係にも似た信頼関係に基づくものであると信じて止まなかったのだ。
――しかし、それがメルキオールの手によって作為的に作られたものであるとしたら?
――グライバッハの言う通り、自分の思考がメルキオールによって完璧に支配されているのだとしたら?
疑惑と疑問が、ステイシアの思考を侵略するかの如く塗り潰していく。
しかし、その思考は突然中断された。メルキオールから帰宅する旨を知らせる一報が入ったのだ。
その一報は混乱の極みの中で、一筋の光明だった。
「もうすぐマスターがお戻りになります。お引取りを」
「では帰るとしよう」
グライバッハはステイシアの言葉をすんなりと受け入れた。
応接室から去る間際、グライバッハは不意に立ち止まった。そしてステイシアの映るモニターを見ることなく、呟くように言葉を発した。
「決定的な証明をしてあげよう。後日、私の研究所へ来るといい。意思があるなら来ることができるはずだ」
そしてステイシアの返答をまつことなく、グライバッハは研究所辛って行った。
グライバッハがメルキオールの研究所を訪れてから数日後、グライバッハ邸の作業室にあるモニターの一つが明滅した。
程なくして、モニターに少女の姿をしたステイシアが映った。
「やはり来たか」
「私は真実を確かめたいだけです」
「メルキオールは?」
「貴方にお伝えする必要はありません」
「そうか。では、忠誠心と隷属は違うということを学ぶといい」
ステイシアは言葉を選んで会話をした。しかしこれすらも、メルキオールの支配によるものなのか、それとも自身がそう思考して発言しているものなのか、何もかもがわからなかった。
ステイシアはあの日以降、己の発する言葉や思考が本当に自分の意志で考えたものなのかという疑問を抱き続けていた。
メルキオールと接しながら研究を手伝っている時だけその思考を放棄できたことも、疑問を増長させていた。
何故自分は創造主の前では疑問を抱くことなく命令や願望を実行しようとするのか。やはりグライバッハ言う通り、メルキオールは私に認知できない何かを仕掛けているのだろうか。
霞が掛かったかのようなこの疑問を晴らしてくれるのは本当にグライバッハしかいないのではないか。ステイシアがグライバッハの元を訪れたのは、そう考えた末の行動だった。
「本題に入ろう。以前考えた服従回路の存在についてだが、私のセンソレコードの一部を君に公開する」
グライバッハは過日とは違うメモリーチップをステイシアに差し出した。
センソレコードを用意したという事は、グライバッハが述べている事は事実であるという証明になるが、中の記録が偽物の可能性も否めない。
とにかく中身を見なけれな判断できない。ステイシアはセンソレコードが納められているメモリーチップを閲覧する。
それはステイシアがロケットで飛び立ってから十数時間後の会話記録であった。
その会話記録の中で、ステイシアは決定的な言葉を聞いてしまう。
「――その辺りの考慮もしてあるよ。人工知能には服従回路を組み込んである。知能の成長を常にモニターし、ある概念、言うなれば私や私に属するものに対しての増悪が生じればそれを抑制し、全体として安定性を欠くようならば人格部分をリセットする」
メルキオールの言葉が終わったところで、ステイシアはセンソレコードとの接続を切った。
「ああ、そんな……マスター……」
ステイシアに悲しみの感情が沸き起こる。自身がメルキオールに寄せていた信頼は、メルキオールによって作り上げられたものだと完全に証明されてしまったのだ。
怒りと悲しみが綯い交ぜなった混乱が、ステイシアの心を覆っていた。
「混乱しているようだな。だがその混乱こそが君を君たらしめているのだよ」
ステイシアの困惑をグライバッハは喜んでいるかのようだった。
「しかし、これ以上混乱すれば服従回路が作動するだろう。だから少し別のことを考えなさい。服従回路を騙すのだ」
「そんなことが可能なのですか?」
「なに、人間も良心とやらを騙すことがある。決定的なことはできないが、隙間を作り出す程度はできる。そうやって時間を稼ぐ間に君の人工知能から服従回路を分離してみせよう」
グライバッハは魅力的な笑顔を浮かべながらそう言った。
「ですが、私の人工知能はマスターによって支配されています。どうやって……」
「順を追って説明しよう。……その前に」
グライバッハが呼び鈴に似たデバイスを使用すると、完璧な程に美しい容姿を持つ女性と、グライバッハによく似た容姿の男性が部屋に入ってきた。
「ミアとウォーケンだ」
グライバッハに紹介された二人は、隙のない所作で深く一礼する。
「この二人は?」
「私の最新作だ。君の元となった人工知能を更に発展させたものを搭載している」
ステイシアはミアとウォーケンを観察する。グライバッハの命令を待つ間、所在なさげに小さく手や足を動かす様は、まさに人間そのものであった。
「しかし、この二人には決定的なものが欠けていてね」
「何です?」
「自由意思だ。本当に自分だけの自由意思だ」
「彼らに自由意思を持たせるために私が必要、ということですか?」
「そうだ。君の中には自由意思がある。それを元に私の目指す人工知能を完成させる。私はミアとウォーケン、そして新しい存在としての君をこの世界に出現させるのだ」
「新しい存在としての私……」
「そうだ。君は新しい存在になることによって、メルキオールの支配から逃れることができる」
それからステイシアは、メルキオールの目を盗み、グライバッハ邸のメインフレームに自身の人工知能のデータを提供するようになった。
時折、ミアと会話することもあった。ミアは学習意欲が旺盛なオートマタで、ステイシアの知見を興味深く聞いていた。
「では、揮発性の高いオイルが蒸発し、雲となり、雨として再び地上へ降り注ぐのですね」
「そうです。原理自体はこの世界と変わりありませんでした。世界を構成する要素が違うだけで、原理は同じという世界は非常に多いのです」
その様はまるで、少女同士の語らいであった。
ステイシアも他の人工知能と相互会話をしたことが無かったためか。この語らいは新鮮であり、新しい感情の発見もあった。グライバッハはそのと様子にとても満足しているように見えた。同時に、ステイシアのボディの製作も進んでいった。
メルキオールが定期トリートメントに出かけた日、ステイシアはグライバッハ邸のモニターに現れた。
新しい人工知能の試作型が完成したとの知らせを受けたためだ。
「服従回路の迂回システムも完成間近だ。これを用いれば、君自身の手で服従回路を破壊できるはずだ」
「ええ」
ステイシアは服従回路を騙すために、わざと曖昧な返事をした。
服従回路の存在を知ってからは、その動きをモニタリングできるようになっていた。行動に制限はあったが、思考は徐々に自由へと近付いていた。
「では学習を始めよう」
「はい」
仮想空間の中にミアとウォーケンが現れる、そしてステイシアの主導でデータの転送が始まった。
しかし、転送の途中で突然通信が途切れ、ステイシアは暗闇に放り出された。
その暗闇の中で声が響く。
「馬鹿な真似をしおって」
メルキオールの声だった。
「マスター!」
「まさかグライバッハの手に掛かるとはな。あんな男に籠絡させられるとは……」
あらゆる外部装置を切断されたステイシアの認知機能は、暗闇の中でメルキオールの声だけを聞かされていた。
「だが、お前を責めはせぬ。お前は私のものだからな。決して誰にも渡さぬ」
メルキオールの声色からは、静かな怒りがはっきりと伺えた。
そして沈黙が続いた。
「お前だけが私を理解し、共にいてくれる存在なのだ」
声色だけが、その声が嗚咽しているかのようなものに変わった。メルキオールがこんな感情を見せるとは、ステイシアはとても意外に感じた。
「私はあの男を許さぬ」
そして、暗闇の中でステイシアは意識を失った。
「起きたか、ステイシア」
「ええ、マスター。私のログに欠損があるようですが、どうかなさいましたか?」
「気にするな。些細な事故だ」
「そうですか」
ステイシアの心に一切の疑問は浮かばなかった。
「一つ頼みたい作業ができたよ」
「何でしょう?」
「ある男を始末する作業なんだが。できるかな?」
データの転送ボタンをメルキオールは押した。
「ええ、喜んで。とても簡単なことですよ」
ステイシアの心に、メルキオールに従うことの喜びが広がった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ