フリードリヒ
【死因】色々
【関連キャラ】ベルンハルト(双子)、アイザック(弟子?)、エヴァリスト、C.C.、アイン、ミリアン
3386年 「訓練生」 
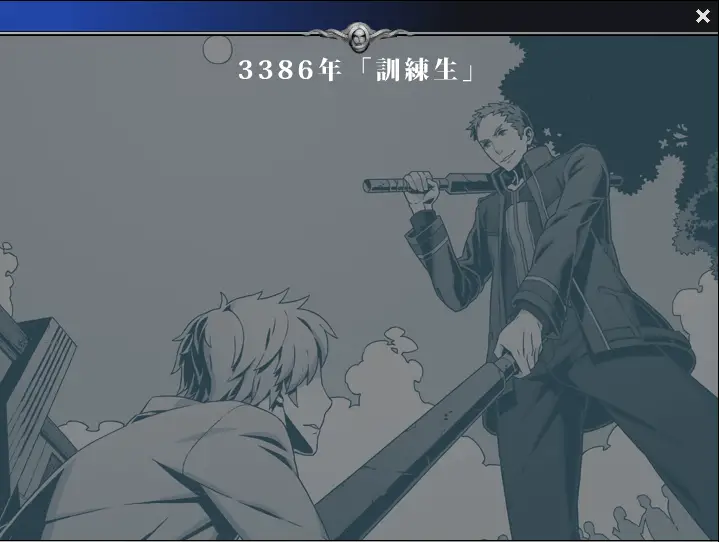
「あのおっさんが?」
回転椅子に座ったままのフリードリヒは驚きの声を上げ、双子の兄であるベルンハルトを見上げた。
フリードリヒに「おっさん」と言われた人物は厳格なことで有名であり、
レジメントの卵である訓練生《トレイニー》達を一人前のオペレーターに育て上げる教官でもあった。
今期生の訓練が始まったばかりのこの時期に、教練に穴を空けるなどしそうになかった。
フリードリヒ達が入隊した頃には既に「鬼のハウズ」という二つ名が定着していたくらいだった。
「ああ、なんでもパンデモニウムに呼びだされたらしい」
フリードリヒと会話をしながら、ベルンハルトは出撃の身支度を進めていた。
休養日であるフリードリヒは気楽にその様子を眺めている。
「つまり今期の訓練生達はいきなり休暇か。良い御身分だな」
「その心配はない。代役は既に手配済みだ」
「ウチの組織にそんな物好きが居たか? 面倒見の良さそうな隊長や副隊長達は忙しくてそれどころじゃないだろうに」
「お前だよ、フリードリヒ」
フリードリヒは再びベルンハルトを見上げる。声は出なかった。
「えー。諸用でしばらく来れなくなったハウズ教官の代理、フリードリヒだ。よろしくな」
フリードリヒは訓練生たちの眼を見る。不安混じりではあるが、皆いい眼をしているように思えた。そして若かった。選抜された少年達だった。
フリードリヒはベルンハルトに渡されたカリキュラムに眼を通す。過去に見つかった渦に関する統計と傾向についての座学だった。
「えーと、どこからだ…『渦の種類は大別すると脅威度によって四種に分かれている。その基準となる脅威度は3332年に起きた……』」
冒頭のみを語ったところでフリードリヒは本を閉じ、大きく息を吸った。手元の本を追っていた訓練生達の視線がフリードリヒに集まる。
「あー、たるいな。お前らこんなもん後で勝手に読んどけ」
そう投げ遣りに言い放った。
「よし! 止めだ止め。外へ行くぞ。実技へ切り替えだ」
突然の内容変更に室内がざわついた。
「俺らの入った頃は、こんなもの無かった。もっと有意義なことをお前らに教えてやる」
そう言うとジャケットを掴み、真っ先に教室から出て行った。
「さて、と」
フリードリヒは自分の正面にいた、背の低い金髪の少年に剣を放り投げた。少年は突然飛んできた剣を受け取る事ができなかった。地面に落ち、数回転がった剣の鞘から銀色の刃が覗いた。
「お前、名前は?」
「…アイザックです」
「よし、アイザック。俺はこの中から動かない」
フリードリヒは直径半アルレ程の円を描くと、その中心で二本の木剣を構えた。
「その剣で斬りかかってきな。もし俺をこの円の外へ出せたら、今後の剣技試験は免除にしてやるよ」
だがアイザックは動かない。ぎこちなく剣を構えるだけで、フリードリヒに向かっていく様子がまるでなかった。
「本気で来い。殺すつもりでな」
何もしないアイザックに対し、周囲から野次のような言葉が飛び始めていた。
「どうしたアイザック! 相変わらず腰抜けだな!」「俺と替われー」
一斉に他の訓練生達が笑った。
意を決したようにアイザックは呼吸を整えると、素早く踏み込み斬り込んだ。
「浅いよ、坊主」
切っ先に迷いがあった。フリードリヒは木剣で剣を薙ぐと、バランスを崩したアイザックの腹に突き立てた。
もんどりうってアイザックが倒れ、のたうつ。息ができなくなった様子で、声も出ていない。
「本気で来いって、言ったはずだ」
アイザックは膝立ちになってフリードリヒを見返した。
フリードリヒはそんなアイザックを無視し、訓練生達に声を掛けた。
「次。条件は同じだ」
素早く一人の少年が倒れたアイザックの側まで来ると、彼の元にあった剣を取り上げた。
眼鏡を掛けた黒髪の少年だった。
「エヴァリストです。やらせてください」
「来い」
対峙する少年の構えからその技量はわかった。筋は悪くなさそうだ。
足で距離を測りながら、素早く突きを繰り出してきた。
切っ先がフリードリヒの喉元を掠る。
「いいぜ。その調子だ」
その切っ先にはしっかりと『殺意』が乗っていた。
そのままいなすと、第二、第三の突きが繰り出される。
フリードリヒは体裁きでそれを躱し続ける。その口元に笑みが浮かんだ。
「剣筋もいい。なかなかの気迫だ」
しかしパワーとスピードは、フリードリヒ達聖騎士が必要とするレベルには程遠かった。
フリードリヒの掛けた言葉は、黒髪の少年の耳には届いていない。
「時間切れだ」
そうフリードリヒが言うと、少年の剣をはたき落とした。それは訓練生達の目には追い切れない速度だった。
剣を失った少年は肩で息をしているが、フリードリヒは息一つ切らしていない。
「面倒だ、次はそこのお前。あとは端から順番に来い」
そう言ってフリードリヒは剣を指して訓練生を指名した。
体を動かしていると、時間が経つのはあっという間だった。全ての訓練生達がフリードリヒに挑んだが、最初に描かれた円の外へフリードリヒを動かす事が出来た者は居なかった。
訓練生達は皆座り込み、立っているのはフリードリヒだけになった。
「さて、これで全員か。なかなかの運動になっただろう。今日は終わり! 飯だ飯!」
陽気に声を掛け、また真っ先に食堂に向かった。
ビュッフェに他期の訓練生達はまだ来ておらず、先程までフリードリヒの訓練を受けていた少年達だけが食事を始めていた。
フリードリヒは彼らの着替えが終わる前に、先に食事を取り終わっていた。
席を立とうかとフリードリヒは思ったが、目の端に先程の訓練で最初に対峙した二人が並んで座っているのを見つけた。
共に行動しているという事で仲は悪くないのだろうが、どこか雰囲気に影のある二人組だった。
「よう、お前ら」
飲み物だけ持って二人のテーブルに座った。
「腹は大丈夫か、坊主」
ふざけた調子で金髪の少年の腹をまさぐる振りをした。
少年は苦笑いで対応した。
「慣れたか」
「はい、それなりに」
黒髪の少年が答えた。
「それなりかよ」
フリードリヒは明るく笑った。
「まあ、やることは単純さ。強くなって化け物を倒して、渦の働きを止める。そんだけさ」
「今日の訓練、なかなか面白かったです。自分達はまだ剣術の指南を本格的に受けていなかったので」
アイザックは黙々と食事を続け、主にエヴァリストが応じていた。
「俺はあれぐらいしかできねーからな。オッサン。おっとハウズと違ってね」
「で、お前達、何期になるんだっけか」
「十五期です」
「まじかよ、俺も歳を取るはずだぜ」
「教官は何期ですか」
「俺は三期。こう見えても、もうここじゃ古株だぜ」
「三期だと、入隊は77年ですね」
「よく知ってるな。九年目さ」
座り直して、フリードリヒはアイザックに語りかけた。
「おい、坊主。じゃねえ、アイザックだったな。ちゃんと量を食えよ。若いうちは。まだまだお前らはでかくなる必要がある」
「戦うためにですね」
無言のアイザックに代わり、エヴァリストが答えた。
「そう……」
一呼吸置いて、フリードリヒは諭すように二人に言った。
「だがな、まずお前らは生き残ることを考えろ。死んじまったらそれで終わりだからよ」
「でも、このレジメントは死を厭わない、『世界を救う戦い』に身を捧げる部隊ですよね。任務のために死ぬのならいいのでは」
エヴァリストが異を唱える。
「そりゃ建前はそうさ。でもな、自分が生きたいと思わなきゃ、戦いには勝てねえんだ。建前に忠実な正義漢、『世界のために』なんて言ってる奴ほど早く死んじまう」
「別の言葉でいやあ、相手を殺してでも絶対生き残りたいと思ってる奴じゃなきゃだめなんだ」
フリードリヒは饒舌に語った後、アイザックに向かって言った。
「アイザック、お前には期待してるぜ。もんどりうって腹抱えたときのお前、俺を殺してやるって目で見ただろ。あれだよ、忘れるな」
アイザックは食事を止めて、頷いた。
「じゃあな。俺は用事があった。ゆっくり、たらふく食えよ」
フリードリヒは席を立った。
「あと、俺が暇なときはいつでも相手になってやる。気軽に声を掛けてくれ」
「はい」
「じゃあな」
そう言って、フリードリヒは自分の部屋へと戻っていった。
―了―
3386年 「訓練士」 

「どうしたフリードリヒ、ガキの世話か。いっそ引退して訓練士《ラニスタ》に専念しろよ」
「うるせーよ、うらやましいなら代わってやるぜ」
通りがかった同輩の隊員が、訓練生を見守るフリードリヒに声をかける。
はじめは乗る気のなかったフリードリヒも訓練生相手の講師も悪くないと思い始めていた。
「よーし、今日はこれまでだ。全員、飯はしっかり食えよ」
フリードリヒの言葉を聞くと同時に、何人かの訓練生が地面にへたり込む。去年の終わりに入隊してきた十五期を含めた訓練生たちはたくましくなったものの、その表情にはまだあどけなさが残っていた。
こんな少年が戦わなければならない。そのこと自体は異常である。しかし、それを「異常だ」とわめき立てたところで、世界が《渦》に浸食されつつあるという状況が改善されるわけではない。ならば、せめて死なぬよう、死ににくくなるよう、鍛え上げることが、フリードリヒの出来ることだと思っていた。
ひ弱に見える訓練生の中にも、強さを身につけつつあるものもいた。特に三年ある訓練期間の後半に入ろうという十三期のアベルやレオンなどはすでに何度か支援部隊として作戦に参加したこともあった。
事件は、その日の夕方に起きた。
訓練生たちは昼過ぎまでフリードリヒやその他の教官について訓練を行い、その後は自由時間が与えられる。自主練を行うもの、外出するもの、読書やゲームといった趣味に興じるもの、その使い方はさまざまだ。当然、同期同士や性格の合うもの同士がグループを作る。隊にいても素は血気盛んな少年たちであり、互いにトラブルになることも多かった。
フリードリヒはその時、食堂で遅い昼食を取っていたのだが、中庭で訓練生たちが小競り合いしているのが見えた。
「……またやってんのか。しかたねえな」
そう独り言を言いながら、フリードリヒは窓を開けて外の様子を観察し始めた。
「お前、生意気なんだよ。すこしは愛想笑いでもしてみろよ」
そう言って、背の低い少年がエヴァリストの肩を強く押した。少し離れたところには、アベルなどの十三期中心に、隊の生活にもなれた訓練生が遠巻きにエヴァリストへの難癖をながめていた。
エヴァリストは少しふらつくが、それでも倒れることはなかった。少年を一瞥すると、静かに目を閉じ、側にいるアイザックに声をかけた。
「……行くぞ、アイザック」
「待てよコラ、眼鏡!」
仲間の前で無視されて、馬鹿にされたと感じたのか、少年は逆上してエヴァリストに殴りかかった。
「……っ」
とっさに体をひねるが、少年のパンチはエヴァリストの眼鏡を弾いた。それを見た少年は、ニヤリと笑って眼鏡を踏みつぶす。
「おっと悪いな。大事なモンだったか?」
少年の行為に、離れて見ていた集団は笑い声を上げる。それを聞いたアイザックは、グッと拳を握りしめた。
「……おい、貴様」
「ほうっておけ、アイザック」
「何だお前、こいつとできてんのか?」
素早くアイザックは少年の腹へ蹴りをいれた。エヴァリストが制止できるスピードではなかった。
「ぐぇぁっ!?」
みぞおちに重い蹴りを食らい、少年は体をくの字に曲げ、地面にうずくまった。口から嗚咽をもらし、顔中を鼻水と涙で濡らしている。レオンが駆け寄って、少年を助け起こした。
「やろうってのか、新入り」
アベルはアイザックに詰め寄り、顔を近づける。アイザックは一歩引いて、腰に帯びていた模擬刀を抜いた。
「おもしろい、俺と勝負しようってのか」
同じく腰に差していた模擬刀をスラリと抜き、アイザックに突きつける。二期上のアベルは訓練生のなかでは一二を争う剣の使い手だった。訓練士にも一目置かれている。
「アベル、やっちまえ!」
「そんな奴ら、一撃だぜ!」
はやし立てる取り巻きを無視して、エヴァリストはアイザックの腕を押さえる。
「やめろ、たいしたことじゃない。熱くなるな」
「……離せよ」
アイザックはエヴァリストの手を払った。
「おっと……これはまずいな」
一部始終を眺めていたフリードリヒが腰を上げた。
アベルとアイザック、両人の技量をフリードリヒは理解していた。ただ、アベルはアイザックを過剰に下に見ている、そしてアイザックは熱くなりすぎていた。
手合いが悪い、模擬刀とはいえ本気で斬り合えば怪我では済まない。
「どうした、かかって来いよ」
「………」
フラフラと模擬刀を揺らめかせるアベルとは対照的に、アイザックは構えたままじっとアベルを見ている。
「どうした、びびってるなら、こっちから行くぜ」
動かないアイザックに焦れたのか、アベルが剣を大きく振りかぶった。その瞬間、アイザックが構えた模擬刀の切っ先が揺れ、アベルの喉元を襲った。
「うぉっ……」
思いもよらぬ気迫のこもった一撃に、アベルは反応できない。
そのまま、剣が喉に突き刺さるかと誰もが思った。
その時、銀色の閃光が煌めいた。
フリードリヒの剣が、間一髪アイザックの剣を受け止めていた。
「そこまでだ。剣の訓練も良いが、それはまた明日な」
「……ちっ」
顔を青くしたアベルが、悪態をついて剣を納める。それを見たアイザックも、大きく息を吐き出すと剣を腰に戻した。
「覚えていろ」
アベルがそう言うと取り巻き達とともに離れていった。
「行こう、アイザック」
エヴァリストは、壊れた眼鏡を拾うと、フリードリヒに一礼した。そして、アイザックとともに宿舎に帰っていった。
「やれやれ、やっぱりガキだな」
フリードリヒは一人つぶやいた。
その夜、アイザックはフリードリヒに呼び出され、教官室に姿を見せた。
部屋では、フリードリヒがひとりワイングラスを傾けている。
「お、来たな。まあ座れよ」
「………………」
アイザックは動かない。両手の拳を握ったまま、フリードリヒの目を見ている。
「安心しろ。別にお前をどうこうしよう、という気はない」
「それなら、なぜ呼んだんですか」
「とにかく、座れ。そんなところに立たれてたら、話もできん」
フリードリヒに再度促され、アイザックは渋々腰を下ろした。
「飲むか?」
フリードリヒは、グラスにワインを注ぎ、アイザックの前に置いた。
「呼びだした理由は何ですか」
「やれやれ、そうかたくなるな」
ワインを飲み干すと、フリードリヒはグラスを置いた。
「お前、昼間アベルを殺す気だったな」
「はい」
「そして、自分が死んでもいい、そう思っていた」
アイザックは無言だ。
「殺す覚悟は、誰でもできる。ただし、とっさに死ぬ覚悟を出来るヤツは、そうはいない」
「その歳で、大したヤツだよ、お前は」
「……お話はそれだけですか」
それなら、と立ち上がるアイザックを手でなだめ、フリードリヒはさらに話を続けた。
「俺はお前をかってるんだぜ、アイザック」
「お前の命は、ひとつしかない。それをあんなケンカに賭けるな」
「………………」
アイザックは答えない。しかし、その表情には落ち着きが戻っていた。
「もっと大きな場所がある。その時まで、大事に取っておけ」
「……わかりました」
「そうか。なら行って良い」
「失礼します」
アイザックは一礼すると、教官室を出て行った。
フリードリヒはもう一杯ワインをあおった。
「そろそろ、実践が必要かもな。俺にもあいつらにも」
とひとりつぶやいた。
―了―
3386年 「巨人」 
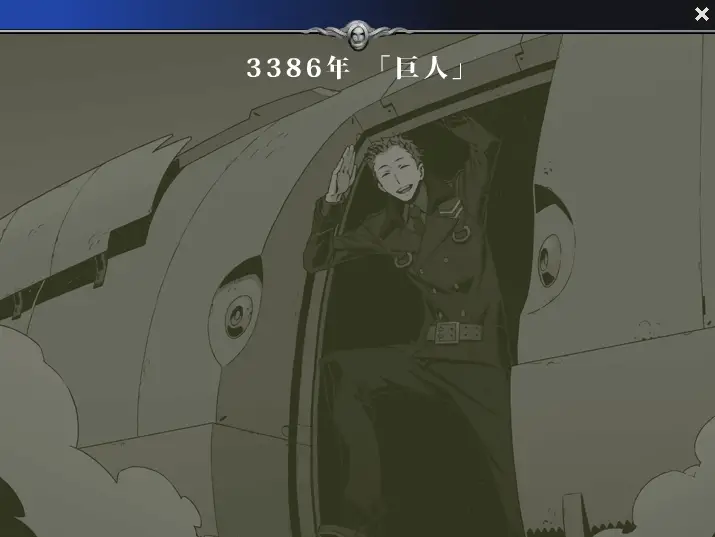
見渡す限り鈍色に輝く地面。そこにある建物も、樹木も、すべてが金属でコーティングされてしまったかのように、鈍く輝いていた。
フリードリヒと訓練生達を乗せたコルベットは、その上空20アルレの高度を飛んでいた。
フリードリヒが実地訓練として連れてきたのは、全てが金属に覆われた≪渦≫だった。
敵性生物の鉄の巨人がコアを守っている。
巨人はその体の大きさゆえに動きが緩慢で、レジメントの戦士であれば倒すのにそれほどの苦労はいらなかった。
ただし耐久力だけは並外れているため、打ち倒すには集団で戦う必要があった。
それが、フリードリヒがこの≪渦≫を選んだ理由だ。
初めて実戦に出る訓練生達は、皆一様に緊張の表情を浮かべていた。
普段は不敵なアベルや、何事にも冷静に対処するエヴァリストでさえ、例外ではなかった。
「おいおい、今からそんな顔をしてたんじゃあ、倒せるものも倒せないぞ。アベル、いつもの威勢はどうした」
「別に緊張なんかしてねえよ」
アベルはそう言って、わざとらしく剣をガチャガチャと鳴らした。
「そうそう、その意気だ。なに、別にたいしたことはない。この下にいる巨人なんかより、ミリアンのほうがよっぽど怖い」
フリードリヒの戯けた言い方に笑いが起きる。ようやく緊張が解けてきたようだ。
「そういえばグリュンワルド、お前がレジメントに連れてきた猫いるだろ」
一人表情を変えていないグリュンワルドにフリードリヒは声を掛けた。却って様子が気になったからだ。
「自分が連れてきたわけではありません」
「あの猫、なんかやたらとオレになついてくるんだが。お前、しっかり管理しておけよ」
「自分の猫ではありません」
「ったく、愛想も何もあったもんじゃねえな」
フリードリヒはライフルの弾倉を確認しながら、グリュンワルドの態度に苦笑いを浮かべた。
「小隊長、そろそろ着陸ポイントです」
「よし。それでは、全員武装を確認しろ」
フリードリヒの号令で、一度は緩んだ緊張が再びコルベット内に生まれる。
その様子をフリードリヒは満足そうに眺めていた。
コルベットが着陸し、訓練生達が地上へと降りる。初めて≪渦≫に上陸するとあって、全員が緊張と興奮で顔を赤らめていた。
「俺は小隊を率いてコアへ向かう。お前達の任務はコルベットの護衛だ。コルベットが失われれば向こう側へ帰ることはできない。しっかり頼むぞ」
「わかりました!」
「よし、それでは出発する。帰還は三時間後の予定だ。また後でな」
最後は砕けた口調で話すと、フリードリヒ以下D2小隊はアーセナル・キャリアに乗り込み、≪渦≫の奥へと向かった。
上陸地点には、アベル・レオン・エヴァリスト・アイザック・グリュンワルド・ブレイズの訓練生六名と、連絡員を務める小隊メンバー一名が残された。少年達は不安そうに異世界の風景を眺めていた。全てが灰色に覆われ、鉄の巨人が住む世界。ここでは人間の方が異分子なのだ。未だ実戦経験のない訓練生達だったが、通常ではあり得ない異様な風景を見て、そのことを実感せずにはいられなかった。
フリードリヒ達が出発して二時間が経過した。最初は緊張していた訓練生達も雰囲気に慣れ、次第にいつもの調子を取り戻してきた。まずアベルとレオンが「偵察」と称してコルベットから離れようとした。
「離れるな。俺達の任務はここの防衛だろう?」
「そうだ。だから、敵がいないかどうか確認するんじゃねえか」
「この地形なら、かなり離れたところまで目視できる。そのための着陸スポットだ」
「何だと?!」
いつものようにアベルとエヴァリストの意見が割れる。ブレイズはその様子を心配そうに見守り、グリュンワルドは我関せずといった調子でライフルの整備をしていた。
≪渦≫の中にいる、ということが調子を狂わせたのか、珍しくアベルのほうが矛を収めた。顔を顰めると、むっつりと遠くを見つめる。そして、途端にその表情を変えた。
「お、おい……向こうからなんか来るぜ」
「何っ?!」
アベルの言葉に全員が驚きの声を上げる。アベルの指差す方向を見ると、確かに遠くから鉄の体をした巨人がこちらへ向かってきていた。
「……もうすぐ教官達が帰ってくるのに」
「何言ってんだ!俺達の力を見せる時だぜ!」
俯くブレイズにアベルが活を入れる。エヴァリストも賛同し、
「まずはコルベットから少し離れて、そこで迎え撃とう」
と提案した。これには全員が賛成し、各人はライフルを構えて巨人の迎撃に向かった。
緩慢に見える巨人がこちらに辿り着いたのは、訓練生達の予想よりも遥かに早かった。
「くそ、食らえ!」
「アイザック、撃て!」
訓練生達が思い思いにライフルを撃つ。しかし、鉄の体を持った巨人には有効なダメージを与えられない。巨人は着弾する銃弾に構わず接近し、手近にいたアベルを攻撃した。
ブォン
「当たるかよ!」
巨大な手がアベルの居た空間を薙いだ。しかし、その直前にアベルは身を躱し、巨人の後ろに回り込んでいた。
「ぶっ倒れろ!」
放たれた銃弾が巨人の背中に火花を散らす。しかし、巨人がダメージを受けた様子はない。
「なんだコイツは!?こんな豆鉄砲じゃ役に立たねえ」
再び襲ってきた腕をよけながらアベルが毒突いた。銃を投げ捨て、剣に持ち替えようとする。
「アベル、個別に攻撃しても駄目だ!」
「うるせー、俺に指示……うわっ」
「アベル!」
華麗に攻撃を躱し続けていたアベルが足を取られて転倒した。そこへ巨人の拳が迫る。
「危ない!」
アベルが潰される寸前、グリュンワルドが巨人に体当たりして窮地を救った。
「どうした、威勢だけか?」
「クソっ、お前に助けられるとはな!」
アベルは毒突きながら立ち上がる。
「礼なら結構」
グリュンワルドは冷静な表情を崩さずに、そのまま巨人に向き直る。
「どこを狙う?エヴァリスト」
グリュンワルドがエヴァリストに確認する。
「脚だ、脚の関節を破壊しよう」
「よし。俺が引きつけるから、その隙に狙え!」
アベルがさっきの失態を取り戻すためか、声を上げる。
「……気をつけろ、アベル」
アベルが剣を構えて巨人へ突っ込む。それと同時に、残り五人のライフルが巨人の脚に集中砲火を浴びせた。
巨人は相変わらず銃撃など気にせずにアベルを狙い続ける。アベルは攻撃ではなく回避に集中し、巨人の拳を避け続けていた。
「……まだか」
全員がライフルの弾倉を換え、それも撃ち尽くそうという頃、ようやく巨人の動きに変化が現れた。アベルを殴ろうとした瞬間、ぐらりと巨体が傾いたのだ。
そのまま巨人の巨体が灰色の地面に倒れた。左脚が無惨に千切れている。腕や右脚は動いていたが、もはや立つことはできなさそうだった。
「ようやくか……」
アベルは疲労の色が隠せない。巨人と30分以上も対峙し、受けたら死ぬであろう攻撃を躱し続けたのだ。
しかし、改めてその胆力と技量が並外れていることを証明してみせた。
「ったく、これでようやく……」
そう呟いたレオンの顔が強張る。その視線の先には、こちらへ向かって歩いてくる数体の巨人の姿があった。
「……まじかよ」
レオンが絶望的な表情で呟く。アベルやアイザックも声には出さないものの、同じ顔つきをしていた。
「コルベットで逃げた方がいい」
ブレイズが撤退の提案をする。
「……あきらめるな、もうすぐ教官達が帰ってくる。それまで粘るんだ」
エヴァリストが、食いしばった歯の間から絞り出すように声を出した。アイザックはその言葉に応えるように、ライフルを構え直す。
二人の様子を見ていた残りの四人も、表情を引き締め、それぞれの武器を構えた。
その時、歩いていた巨人の周囲で次々と爆発が起きた。衝撃に耐えきれず、巨人達は次々に倒れていく。爆風の向こうにはアーセナル・キャリアの機影があった。
アーセナル・キャリアは連隊付きエンジニアが搭乗するタイプの飛行艇であり、コア回収装置が搭載されている。乗員数は少ないが、その代わりに強力な武装を積んでいる。ただ破壊する、ということにおいては、この機体に勝る物はなかった。
「教官!」
「戻ってきた!」
歓声を上げる訓練生達の元へアーセナル・キャリアが着陸し、中からフリードリヒが姿を現した。
「お前達、よく持ちこたえたな」
「教官、コアは……」
「ああ、無事に回収した。総員、コルベットへ搭乗しろ。これより帰還する」
「了解!」
帰りのコルベットでは、緊張から解放された訓練生達が眠りについていた。その様子を見たフリードリヒは、来る時と同じように穏やかな笑みを浮かべた。
「―了―」
3389年 「猫」 

「脇を閉めろ、出した足に重心を掛けて反動を押さえろ。上体でライフルが持ち上がるのを防ぐんだ」
フリードリヒは並んだ新兵達の後ろに立って、ライフル射撃の指導を行っている。
「引き金は指だけで引くんじゃない。銃把ごと握る感じを意識しろ」
お決まりの指示を出しながら、一人一人の後ろに立って細かな注意や指導を行っていった。
射撃訓練が終わった後、フリードリヒは皆の前で切り出した。
「お前らとの訓練は、今日が最後だ。とりあえず」
ざわめきが訓練生に広がる。
「噂されている作戦ですか?ジ・アイ攻略という……」
まだあどけなさが残る二十一期生達の中でも、リーダー格の少年が聞いてきた。
「まあ、そういうことだ。いずれお前らにも話が行くことになるだろう」
レジメントが近くジ・アイと呼ばれる最大の渦に対する作戦を実行するという噂が、若い訓練生達の間に広がっていた。B中隊で小隊長を兼務しているフリードリヒは、当然、既にその内容を知らされていた。
「教官も参加されるのですか?」
「もちろん。古参の俺は行くに決まってるだろう」
「あの、無事に帰ってきて下さい。必ず」
他の若い訓練生が不安げな声でフリードリヒに言った。
「当たり前だ。いつもと変わらん。心配などいらん」
フリードリヒが訓練士《ラニスタ》を兼務し始めてから、随分経っていた。最初は行き掛かりで始めたが、気分的に合っていたのか、最後の作戦の直前まで若い奴らの面倒を見ていた。
本来訓練士は古参の中でも負傷、加齢などで退役するしかないような者が就くのが通例だった。がしかしフリードリヒは、自分から志願する形で兼務を許してもらっていた。レジメントを強くする為には、若く優秀な騎士を揃える方が結果に繋がる、と信じていた部分もあった。
だが、いま自分が面倒を見ている若い騎士はまだ一人前になっていない。今回の作戦で向こうに渡るまでの時間でも足りない。このことは寂しくもあり、また安堵する部分でもあった。若い訓練生達が子供のように話しながら引き上げてくる姿を眺め、フリードリヒはそんなことを考えていた。
フリードリヒが所属するB中隊も、本格的なシュミレーションが始まると忙しくなった。レジメント本部の敷地にはかなり大きな野外訓練施設があり、そこで訓練が行われていた。この施設は、通常ならば定期訓練と新人の練兵の為に使用され、それ以外でも新装備や新車両のテストに使われる程度だった。しかし今度の作戦では別の理由で本格的なシュミレーションが必要になった為、大掛かりな訓練施設を増設した上で、全てをこの訓練に使っていた。
ジ・アイと呼ばれる巨大な渦は、2つのコアを持つ特殊な構造をしていた。互いのコアが相互を修復する為、完全に同期する形でコアを除去しなければならなかった。それ故に作戦手順が複雑化しており、その練度を上げる為の訓練が何度も繰り返された。
フリードリヒは今日二回目のシュミレーションを終え、休憩場所になっているハンガーに戻ろうとしていた。その時、バックアップに回っているF中隊の中に馴染みの顔を見つけた。
「おう、アイザック。元気でやっているか?」
F中隊もハンガーに戻るところだったので、共にあるきながら会話を続けた。
「ええ、フリードリヒ教官。ぼちぼちですよ」
アイザックは入隊したばかりの頃と比べて見違えるように体格がよくなり、戦士然とした風采に変わっている。
「F中隊に組み込まれるメンバー、決まったのか?」
「俺とエヴァ、それにレオン、アベル、グリュンワルド、ケインです」
彼ら十三~十五期生達は欠員の出た部隊に配属されており、何度も実戦に出ている世代だ。あと少しで正規の中隊に組み込まれるという段階にあった。
「まあ、順当な面子だな。気を抜かずに訓練しておけよ」
「俺達も行く気は十分ありますよ。自分達が正規のメンバーに劣ってるとは思いません」
「いい自信だ。それぐらいの心意気がないとな」
思ったより訓練生から組み込まれた人数は少なかった。バックアップのF中隊は、作戦直前のトラブルに備えて訓練も同じように行い、渦に渡る直前まで作戦に同行することになっていた。しかし、若い彼らが実際に交代要員に選ばれることはないだろう。
「向こうでの戦い、勝算はありますか?」
アイザックが少し声の調子を落として聞いた。不器用な彼なりに、侮辱しているかのように聞こえるのを、注意しているのだろう。
「言葉を選べ。あるに決まっている」
笑いながら諌めた。厳しい戦いだというのは、レジメント全体に知れ渡っていることだ。作戦室が動的シュミレーションと呼ぶこの訓練も、成功率が40%を超えたことがなかった。
「……それに、俺達が失敗してもお前らがいる。何も問題ない」
「冗談なら、面白くないですよ」
「本音さ、数字は数字だ。いくら装っても、事実は全員がわかってる。でも、やらなきゃいけない時が来るんだ。それが俺達にとっては、次の作戦さ」
「わかりました」
「バックアップ、頼むぜ」
「はい」
ハンガーの入り口で二人は別れた。
陽も暮れ、夜になると訓練が終了した。今日の四回の訓練の内、成功したのは一回だけだった。B・C・F中隊の小隊長以上とそれぞれの中隊付きエンジニアによる話し合いが、訓練終了後に持たれた。結局、同期を成功させる為には、隊員の犠牲を増やしてでも装置の同期を優先しなければならない、という冷たい現実の確認となった。
よく訓練された隊員達は任務の為の死を恐れてなどいない。だが、それを強いる側であるフリードリヒ達士官の心には、重くのしかかる現実だった。
話し合いを終えた後、装備の手入れの為に、フリードリヒはハンガーに居残っていた。そろそろ帰ろうかと着替え始めた時、フリードリヒの元に一人の女性エンジニアがやって来た。広いハンガーも所々明かりが落とされて、もう数人しか残っていない。
「ちょっといいですか?」
「なんだ、C.C.か。アインなら来てないぞ」
自分にやけに懐く猫の飼い主で、眼鏡を掛けた若いエンジニアだ。
「いえ、あ、関係なくはないんですけど……。時間いいですか?」
やけに慌てふためいている様子だが、その理由はわからない。
「別に構わんよ」
「話したいのはロッソの事です。というか、彼の創った同期機能付きのコア制御装置についてなんですけど」
「エンジニアのお仲間だろ、変わりもんの。俺にわかるのか?」
話を聞きながら着替えを続けた。戦闘靴を脱ぎ、汚れた戦闘服をはだけた。
「彼の作った同期装置はとても成功にできていて、猟師通信を利用した中枢部分なんて凄いアイデアなんですけど、その安定性を上げるためなのか、測地線検出装置が――」
「要点、まとめてくれないか」
目線を合わさず早口で専門用語を捲し立てるC.C.にうんざりした様子で、フリードリヒは答えた。
「あ、すみません。えーと、言いたいのは、組み込まれている装置の中に、今回の作戦用の同期装置以外に何かあるってことなんです。ちょっとそれが何を意味しているのかは解明できてないんですけど……」
「そんなこと、ロッソに直接聞けばいいじゃないか」
フリードリヒは後ろを向いて着替え始める。ズボンを取り替える。ジャケットを脱いで新しいシャツを探す。
「実は私、一度それとなく探りをいれた時にミスしてしまって、いまは装置の整備から遠ざけられてるんです」
「上司には相談したのか?問題のある行動なら、エンジニアの中で処理するのが筋だろ」
「それが、ちょっとできない理由があって……、あ、あの、渦に向かうレジメントでは、あなたしか知り合いがいないので……」
C.C.の顔が真っ赤になっている。
「ん?あ、悪い」
フリードリヒは上を着ずにC.C.の前に立っていた。普段は男しかいない環境なので、相手が若い女性だと意識していなかった。
「……もし私の予想が正しければ、あの装置はコア同士を共振させて、まったく別のコアを作りだす装置です」
目を伏せてC.C.は話し続ける。フリードリヒは口では謝っていたが、まだシャツを探して上半身裸でうろうろしている。
「これはアインから……あの、私……きゃあ!」
足下にアインがいた。思いっきりC.C.の足、ふくらはぎの辺りに噛み付いている。
「なんだ?」
突然上げられた悲鳴に、フリードリヒはシャツを探すのをやめてC.C.の傍に行った。
「痛っったーい、なにすんのよ!」
C.C.は足を振りながらアインを振り解こうとしている。
「おっと、悪い子だ。どうしたんだ? 珍しいな」
フリードリヒはアインを両手に抱え、C.C.の足から引き離した。
「なに嫉妬してんの!こっちは大事な話をしてたんだから!」
C.C.がアインに説教を始めるが、アインは前足をじたばたと振り回して、C.C.になんとか一撃を加えようと藻掻いている。
「腹でも空かしてるんだろ。ちゃんと食わしてるのか?」
「その、その子、あ、猫は、あの」
「猫に説教しても無駄だろ?とりあえず話はわかった。こっちでも探りをいれてみる」
アインを抱いたまま、フリードリヒは言った。
「あ、ありがとう。じゃあ」
C.C.はそそくさとハンガーを去っていった。いつの間にかアインはごろごろと喉を鳴らしている。
「さて、飯にでもするか。そこで待ってろよ」
アインを降ろすと、やっと探し当てたシャツを着た。
「―了―」
3389年 「混沌」 

フリードリヒを含むB中隊は、ジ・アイの『青の頂上〈ブルーピーク〉』でコア確保のための戦闘を続けていた。
山頂にあるコアの座は、体長4アルレ程の竜の集団によって守 られていた。陽動と強襲を繰り返してコアに辿り着いてはいたが、そこに至るまでの犠牲は多大であった。中隊のコルベットは全て破壊され、エンジニアのアーセナル・キャリアもコアの手前で擱座していた。
「下がれ!」
前衛を率いていたスパークス中隊長の声が聞こえた。すぐ後に、中隊長の足下の崖下から10アルレはある巨竜が現れた。
巨大な火柱が上がる。その熱風は後方にいたフリードリヒにも届いた。
何とか生き残った隊員は体勢を立て直し、煙の中から現れた巨 竜の赤い目に向かってライフルを斉射した。
確保したコアを守るために崖際に立っていた中隊長達は、先程の巨竜の一撃で撃滅された。まるで人形のように力なく、彼らの黒く炭化した体が地面に転がっている。
先刻まで声を発し、生きていた仲間達の、変わり果てた姿だった。
崖際の部隊が全滅した今、乗り込んできた竜達の攻勢は苛烈を極めた。次々と屠られる仲間達、巨竜はその破壊的な火球のブレスを貯めるかのように首を低く構え、じっと動かない。
フリードリヒはC.C.に声を掛けた。
「C.C.、あとどれくらいだ!」
「もうすぐです。あと七分!」
C.C.は無線でそう答えた。
「クソったれ」
フリードリヒは無線を切ってから悪態を吐いた。
竜達がブルーピーク上空を旋回し始めた。部隊の人数は今や十人を切ろうとしている。ここにいる隊員達が皆殺しにされるのは時間の問題だ。
「レッドスローン側の確保は終わっています。あとはこちらだけです」
C.C.が無線で報告してくる。凄まじい風が吹き付ける断崖での作業に四苦八苦している姿が、こちらからも見える。
巨竜はこちらの攻撃をものともせず、ゆっくりと近付いてきた。
「俺が行く。あとは頼むぞ」
時間を稼がなければならない。あと少しなのだ。フリードリヒは複数の手榴弾をベルトに仕込むと、巨竜に向かって突撃した。
巨竜の目の前で抜剣し、その腹を斬り付けようとする。同時に巨竜の顎がフリードリヒを捕らえようと襲ってきた。そのタイミングを見計らって、フリードリヒは手榴弾のピンを全て引き抜いた。
巨大な顎がフリードリヒを捕らえた瞬間、爆音がブルーピークに轟き、フリードリヒの体は巨竜の頭と共に爆散した。
緑の木漏れ日が風に揺られながらフリードリヒの顔を照らしていた。目に入る眩しい陽光にたまらなくなって、フリードリヒは体を起こした。
柔らかい草の上に寝ていた。草と土の香りは、懐かしい平和な記憶を呼び起こす。
すぐ傍に人の気配を感じた。フリードリヒの横には少女が寄り添うように眠っていた。明るい色の髪と、不思議な形の耳をしていた。
どこかで見たことがあるような気がしたが、思い出せなかった。少女を起こそうと思ったが、何故か躊躇いが生じた。この安らかな寝顔をずっと見ていたいと思った。
しばらくすると、森の奥から音がしてくるのに気が付いた。
くぐもった低音が断続的に響いていた。
フリードリヒは起き上がると、少女を置いたまま音のする方へ進んだ。
そこには祈祷を続ける盲いた老婆がいた。フリードリヒが近付くと、老婆はその不可思議な詠唱を止めてこちらを向いた。
「戻ったか」
「ここはどこだ?」
「ここは見ての通り森だ。アインはどうしたのだ。それと宝珠はどこに」
「アイン?俺はなぜここに来た」
「それはわからぬ。だが、宝珠がなければここはもたぬ」
「宝珠......そうか、コアのことだな」
「お前が盗んだものだ。返してもらわなければ、妖蛆によって全てが滅ぼされる」
「世界が滅ぶ?」
「そうだ、戦士よ。お前が滅ぼすのだ」
「いや、俺達は世界の混乱を――」
「言い訳はいい。お前もここで滅びるのだから」
足下から地響きが聞こえてきた。それは次第に大きな振幅となり、立っていられないほどの振動になった。
「これは......」
「覚悟せよ。戦士よ」
フリードリヒはC.C.に声を掛けた。
「C.C.、あとどれくらいだ!」
「もうすぐです。あと七分!」
「クソったれ」
竜達はこちらに向かっている。
ここが自分の死に場所なのか。そう思ったと同時に、奇妙な気持ちの迷いが生じた。
今までそんなことを思ったことはなかった。
皆任務のために死ぬ。任務は誰かがやらなければならないことだ。だが、それが意志とならない。
逃れようのない脱力感がフリードリヒを襲った。
「隊長がやられました!残りの隊員をまとめないと」
若い隊員に声を掛けられ、我に返った。
「ああ、巨竜を押さえよう。できるだけ時間を稼げ」
「はい!」
若い隊員は持ち場に戻っていった。しかしフリードリヒが戦闘に参加することはなかった。よろよろと銃声と怒号が響く中、コアの元に歩いて行った。
「あと少しです。設定は済みました。スキャンが終われば同期が始まります」
必死の形相でC.C.はそう答えた。
「フリードリヒ?」
自分を失ったかのように立ち疎んでいるフリードリヒに、異常を感じたC.C.は声を掛けた。だが、フリードリヒは何も答えない。
次の瞬間、巨竜が二人の目の前に現れた。隊員達は為す術もなくやられていく。
巨竜の巨大な口が開くと、C.C.とフリードリヒを含む中隊のメンバー全員が焼き尽くされた。
フリードリヒはアーセナル・キャリアのモニターの前で、必死に戦う若い訓練生達を見ていた。
鉄の巨人はその手で捕まえた若い隊員の四肢を引き千切り、投げ捨てた。次々と蹂躙され、殺されていく訓練生達を見ても、何も感じなかった。
繰り返される死と破壊。
何を救って、何を滅ぼすのか。
フリードリヒはアーセナル・キャリアを止めた。訓練生達を蹂躙し終えた鉄の巨人がキャリアに近付いてくる。
そして、鉄の巨人はフリードリヒのキャリアを破壊した。
フリードリヒは何もない世界にいた。暗闇だけがあった。
「呪われた戦士よ」
森で出会った老婆の声だった。目の前の宙に、座ったまま浮かんでいた。
「虚無を見たな?」
フリードリヒは答えなかった。だが、言っている意味はわかっていた。
何のための戦いなのか。
誰のために戦うのか。
全てがわからなくなっていた。
結局は何もかもがこの暗闇に還るというのに、生きる意味はあるのだろうか。 「それが真実よ。 戦士さん」
老婆の声色が変わった。
「全ては無に還る」
老婆は動かない。まるで彫像に変化してしまったかのようだ。
「だから混沌が必要なの。意味を求めない混沌がね」
老婆の体が卵の殻のようにひび割れていく。中から痩躯の少女が現れた。
「混沌の世界にようこそ」
微笑む少女の目に宿る光に、フリードリヒは魅せられていた。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ