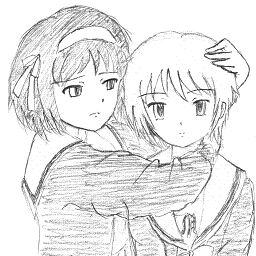概要 
| 作品名 | 作者 | 発表日 | 保管日 |
| ハルニフルユキ | 80-222氏 | 08/02/13 | 08/02/13 |
作品 
「あ~あ……雪、すっかり溶けちゃったわね」
涼宮ハルヒは憂鬱そうな呟きと共に、深い溜息を漏らした。
放課後の文芸部室。
今この空間には、彼女の他にはわたしがいるのみ。
朝比奈みくるも古泉一樹もまだ今日は姿を見せていない。そして、おそらく彼女の退屈の原因は『彼』が来ていないこと。
いつものように読書を続ける私のことを、涼宮ハルヒは暫くの間、じっと観察していたようだ。観察対象から観察される、というのもある意味、興味深い事象ではないだろうか。
とても静かだった。といっても、全ての音が消失してしまったというわけではない。聴覚レベル的には、わたしが本のページを捲る音も、涼宮ハルヒの心音・呼吸音も認識可能である。
しかし、ある種、非常に稀なことなのかもしれない。彼女がわたしと二人きりでこの場に存在する、ということ。そして、彼女がこれほどまでに沈黙を続けている、ということも。
しかし、その沈黙も長くは続かなかった。
多分、なにかを逡巡しているような素振りを見せていた涼宮ハルヒが、意を決したように、わたしに話しかけてきたのだった。
「ねえ、有希」
「……なに?」
「ちょっと教えて欲しいことがあるんだけど、いいかしら?」
「回答可能な範囲であれば」
「ええ、それで構わないわ」
「そう」
「えっと、それから、今これからここで話すことは、あたしと有希の二人だけの秘密にしてもらってもいい?みんなには――特に、キョンには絶対教えちゃダメよ」
「なぜ?」
「実は、これから訊くことは、キョンに口止めされてたことなの。……うん、あたし自身、キョンとの約束を破ったのに、それでいて有希には秘密にして、なんてのはムシが良過ぎるってのも承知してるわ。でも――」
彼女は一瞬目を逸らして俯いたが、すぐにわたしに向き直り、
「どうしても、あたしは自分で確認したかったの。――ねえ、有希――あなた、転校しちゃうかもしれない、って……ほんとなの?」
彼女の質問はわたしにとっても予想外だった。
回答するなら一言だ。『いいえ』。そう答えればいいだけのこと。現時点で、わたしがこの学校から転校するなどという可能性はゼロである。
だが、わたしはすぐそう答えるのを躊躇した。そもそも彼女がなぜ、このような疑問を抱いたのかをまず明らかにした方がいい、そのようにわたしは判断した。
「それは『彼』が言っていたこと?」
「ええ、そうよ」
「そのことを『彼』が話したのはいつ?」
「え~と、確か、この前の冬合宿だったかしら。あたしたち、スキーしてる途中に吹雪に遭って――って、アレ?あのときの変な館って、幻覚だったんじゃ……」
涼宮ハルヒは自分自身の記憶に混乱させられている様子だった。
「と、とにかく、合宿の間のこと、ってのには間違い無いんだけど、その時キョンが、有希のことで『遠くの親族のもとに行く可能性がある』って言ってたんだから」
「……『彼』はわたしがそう言ったと?」
「うん。キョンが入院してたときに、有希――あんた一人でお見舞いに行ったりしたの?あたしもずっといたはずだけど気付かなかったわ。まあ、とにかくそのお見舞いのときに聞いた、って言ってたわ」
それを聞いてようやく今までの話の内容に整合性を見出すことができた。
おそらく『彼』は、わたしの暴走による世界から帰還したとき――『わたしの処分が検討されている』――とわたしが伝えたことを、彼女に対して当たり障りなく教えようとして、そのような作り話をしたのであろう。
転校、というのは、以前わたしが情報操作で『朝倉涼子は転校した』ことにしてしまったのを参考にでもしてくれたのだろうか。
とにかくここは、『彼』に話を合わせておくべきだろう、と判断する。
「そのような話を、確かに『彼』に対してしたことは事実」
「そう――やっぱり」
涼宮ハルヒの表情が僅かながら曇る。心拍数の増加を確認。動揺……しているのだろうか。
「でも、先方の事情もあり、その話自体は既に解消済み」
「じゃあ、有希は転校したりしないってこと?」
「そう」
「……よかった」
涼宮ハルヒは安堵したかに見えたが、すぐに咎めるような口調で捲くし立てる。
「でも、なんでキョンに教えてあたしには話してくれなかったの?これでもあたしはSOS団の団長なのよ。責任者よ、責任者」
少しの間をおいて、彼女は改まった感じて訊いてきた。
「――――ねえ、有希。もしかしてあなた、あたしのこと、信用してないとか、そんなわけ、ないわよね?」
射抜くような視線にもかかわらず、彼女の声はなぜか不安げだった。
「あなたのことは信頼している。我々のリーダーとしても、一人の人間としても。……あなたに伝えなかったのには理由がある」
「えっ?」
「……あなたに、心配は掛けたくなかった。あなたの不安そうな顔を見たくなかったから……今のような表情を」
「!」
涼宮ハルヒは、両手で口元を覆うと、わたしの視線から外れるように後ろに回りこんでしまった。
「な、なによ。有希までそんなこと言うなんて。遠慮しなくてもいいじゃないの。キョンにも言ったけど、団員の心配をするのは団長の務めなんだって――」
あとは声にならなかったようだ。
涼宮ハルヒは、突然わたしの背中から抱きついてきた。
「………………」
どう反応して良いか解らない。
せめてもの救いは、彼女が泣いているわけではなかったことだ。
彼女は声を震わせながら囁く。
「ごめん――有希。でも……あたしだって不安になったりすることもあるわよ。いつか急に、有希があたしたちの前から急にいなくなっちゃうんじゃないかって――まるで、春になると溶けてなくなってしまう、積もってた雪みたいに」
「…………大丈夫」
「――――えっ?」
「……『鳥だって空から落ちることもあるし、時には四月にだって雪が降ることもある』……」
「有希――何のこと?」
「……今読んでいる本に書かれていた一文。特に意味はない」
「有希……」
「大丈夫。わたしは急に消えたりしない。あなたと……『彼』が、みんながいる限り、絶対にいなくなりなどしない」
何の根拠があるわけでもない。でも、涼宮ハルヒを安心させるための方便などではない。
私自身が、今のわたしの言葉にすがりたかったのだ。
任務とか、そういったものは関係ない。
今のこの環境を、SOS団という『仲間』の存在を失いたくないと思っているのはわたしの方も同じだ。
「だから、お願いがある」
「……なに、有希?」
「あなたも、わたしたちと共にありたいと思っているのならば…………その想いを大切に持っていて欲しい……いつまでも」
わたしの言葉に、彼女はようやく落ち着きを取り戻した。
「ありがとう――有希。そうよね、団長のこのあたしが、みんなのことを信じないことには始まらないわ」
そう言って涼宮ハルヒはわたしの体を開放すると、腕組みして室内をうろつきだした。
「でも『四月にだって雪は降る』か……。そうね、この前も秋なのに桜が咲いちゃったりもしたし、ひょっとしたら入学式のころに大雪になったりするかもね」
彼女がそう願えば、それは実現してしまうだろう。環境情報の改竄がこの惑星に与える影響については、『彼』には既に話していたのだが、さて、どうしたものだろうか?
だが、心配は要らないのかもしれない。
他の団員がこの部室に集合すれば――『彼』が現れたならば――涼宮ハルヒの興味はまた別のことに移るに違いないのだ。
かといって、それが新たに我々、特に『彼』の悩み事となる可能性は低くはないのだが。
しばらくして、二人だけの空間は終わりを告げることとなった。
「す、すみませ~ん。すっかり遅くなっちゃいました~」
「あっ、みくるちゃん!もう、来るのが遅いじゃないの」
「ふ、ふえっ……ご、ごめんなさい~」
「まあ、別に怒ってるわけじゃないわ。…………そうだ、有希、みくるちゃん、今度のバレンタインデーのことなんだけど、あたしにいいアイディアがあるんだけど、ちょっと協力してもらってもいい?」
「は、はい」
「……了解した」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ