概要 
| 作品名 | 作者 | 発表日 | 保管日 |
| 北高 Under Ground | 87-376氏 | 08/04/20 | 08/04/21 |
作品 
そのとき、俺が最初に感じたのは「またか」という想いだった。
多分真夜中だろう。つい先程部屋の目覚まし時計を確認した時の時刻が午前一時にまだなっていなかった覚えがある。
そこからしばらく布団に潜ってうとうとしていたはずが、いつの間にか俺の身体は北高のグラウンドのど真ん中に転がされていたのだった。
起き上がって『制服』に付いた土を払う。
またしてもご丁寧に着替え済みってわけだ。もしも可能ならば平日は毎朝こんな感じで無意識に登校させてもらうってのも楽でいいかも知れんな。まあ、問題は全然別のところにあるんだが。
さて、その問題とは――ハルヒだ。
おそらくあいつも校内のどこかにいるに違いない。だが、一体何処に行っちまったんだ?
星明り一つない漆黒に近いグレーの空を見上げて俺は一呼吸入れた。とりあえず、今の俺の置かれている状況をできる限り把握しておいた方がいいだろう。
無人の校舎に侵入するのも手馴れたものだった。全く自慢にもならんけどな。
職員室でガメた鍵を手に、俺は真っ先に旧館部室棟三階の一角――文芸部室を目指した。
部屋に入るなり、俺は団長席のパソコンの電源を入れる。果たしてディスプレイにはOSの起動画面がいつものように表示されることはなく、黒画面の端に白いカーソルが小さくブリンクしていた。
どれくらいの時間が過ぎたのだろうか、俺が少々不安になりかかったまさにその瞬間、天からの蜘蛛の糸のごときメッセージが表示されたのだった。
YUKI.N> 待った?
『いや、大丈夫だ』
こういった場合は、素直に『待った』ということを伝えない方がいいということらしい。まあそんなことは今考えるべきことではないのだが。
YUKI.N> 今からわたしが伝える通りに行動して欲しい。もうあまり時間的猶予も残されていない。
『何だって? とにかく、ハルヒはどうなってるんだ?』
YUKI.N> 涼宮ハルヒは本館屋上にいる。まだ覚醒状態ではない。速やかに彼女を連れてその場から離れて。
『屋上か。って、ここから逃げろってことなのか?』
YUKI.N> そう。具体的には学校の敷地から三キロメートル以上距離をとる必要がある。あなたたち二人の生命にかかわる問題。急いで。
『三キロ? なあ、長門。そもそも俺たちは学校外に出られるのか?』
YUKI.N> あなたたちのいる空間の規模はその程度ではない。それに、その空間は涼宮ハルヒの意思によって構成されたものではない。古泉一樹も私と同じ結論に達している模様。
『古泉が? てことは、古泉自身はこの空間には侵入できない――ってことなんだな』
YUKI.N> そう。
まあ、もしできるのなら。既に俺の目の前にあの紅球があらわれていてもおかしくないだろう。
『でも、ハルヒのせいじゃないってのなら、この閉鎖空間は誰が作ったんだ?』
YUKI.N> 情報統合思念体でもその者の存在を確認することはまだできていない。ただ、彼らは我々のように観察するだけでなく、涼宮ハルヒ本体に直接干渉することを選択した、としか判断できない。
何処の誰か解らんが、全く余計なことをしてくれたもんだ。
YUKI.N> 彼らは涼宮ハルヒの能力を利用してその空間を構築していると推測可能。よって脱出に際し彼らからの妨害が予測される。くれぐれも気をつけて。
『ああ、解った』
YUKI.N> こちらから直接支援はできないが、事態の収拾に可能な限り尽力する。
僅かの間が空いた後、
YUKI.N> あなたはあなたにできることを
と表示された時点で、画面は再度ブラックアウトし、しばらくしてパソコンが普段通りの起動シーケンスに入ったのが確認できた。
やれやれ。
そうとなればこの場に長居は無用だ。俺は長門に言われた通り、本館の屋上――ハルヒの元へと向かったのだった。
「な、何だこりゃ?」
屋上に辿り着いた俺を待っていたのは、コンクリートの上に横たわっているハルヒの姿と、その真上の空中で不気味に浮遊している、虹色に煌くダチョウの卵とでもいうべき珍妙な物体だった。
この奇妙なオブジェクトが何なのかは解らないが、一つだけ言えることは、こいつのせいでハルヒと俺がとんでもない目にあったに違いない、ということだ。
俺はハルヒの元に駆け寄る。
「おい、ハルヒ……ハルヒ?」
ダメだ、全く起きる気配がない。
仕方なく俺はハルヒの身体を――いわゆる『お姫様抱っこ』状態で――抱えると、さっさと回れ右で階段の方に向かったのだった。
そのとき、背後で例の物体が何やら怪しげな光を放ったらしいのだが、そんなことを一々気に掛けている余裕なんて、俺には全くなかったのだ。
ハルヒの履いている靴を見て、俺は律儀に上履に履き替えていたことを悔やんだ。この空間が閉鎖空間の類なら、別に土足で校内を歩き回ったところで咎める者など誰も居やしないのだからな。
下駄箱で自分の靴に履き替えようとハルヒの身体を一旦下ろしたところで、
「――う~ん」
どうやら眠り姫がようやくお目覚めのご様子だ。
「あれっ? ここは一体……」
「ハルヒ――やっと起きたか」
「って、ちょっとキョン! 何でこんなところにあたしとあんたがいるわけ? ――ま、まさか」
ハルヒは両手で自分の肩を抱くように身を硬くすると、
「あんたまた、あたしにおかしなことするんじゃないでしょうね?」
おいおい、『おかしなこと』って一体何のことだ? 四百字以内で説明してみろ。しかも『また』ってのは何だ?
「う、うるさい! どうでもいいでしょ、そんなの」
と、そのとき付近で何者かが動く音がした。
「静かにしてくれ。話は後だ」
俺はハルヒの腕を掴んで、校舎外に出ようとした。
「な、ちょっとキョン、離しなさいよ」
「だから話は後だって。文句だろうが愚痴だろうがいくらでも聞いてやるから」
何か咬み合っていない気もするが、そのまま俺は強引に駆け出す。ハルヒは不満そうというよりは怪訝な表情だった。
ふとバカバカしいことを考えてしまう。普段とは立場が全く逆ではないか。いつだってハルヒは俺の手を引っ張り回した挙句に、散々とんでもない目に俺を巻き込んできたんだからな。
だが、俺は溜息を吐くヒマも与えられなかったようだ。背後からのガラスの砕けるけたたましい音と共に、そいつらは突然現れた。
「キョン! なによこれ?」
いや、俺に訊かれても困るんだが。
そいつらは――『骨』だった。と言っても人骨ではない。俺の知る限りでは図鑑の中か、博物館にしか存在しないはずの――恐竜の化石標本そのまんまの姿をしたのが何体も、まるで生きているかのように蠢いている。
確かアレは『コエロフィシス』とかいう種類の骨格だ。時代的には三畳紀だったか、相当古い種族だったと思う。軽量な身体による機敏な動作の持ち主、そして――肉食恐竜の一種でもあった。
などということを解説している余裕なんて全くない。俺は骸骨恐竜に見惚れるハルヒを必死で引っ張りながら校門の方に急いだ。
「ねえキョン、あたしたち、学校の外に出られるの?」
どうやらハルヒも以前のことを思い出したのか俺に訊いてきた。あの時は学校全体を取り囲んでいた見えない壁のようなものが俺たちの脱出を阻んでいたからな。
俺たちはスピードを落とさずに校門を駆け抜ける。見えないバリアは――なかった! そのままいつもの帰り道を走り続けるものの、後方から例の骨格標本共が追いかけてくるのだ。全く気が抜けない。
しかし全くの予想外だった。長門の言っていた『妨害』ってのは俺も気を配っていたつもりだ。だが、どうしてまたそれが『ホネホネ・ロック』なんだ?
と、そこで俺は唐突に昨日の部室でのことを思い出したのだった。
………
……
…
「みんな~、今度の土曜日は恐竜の化石発掘ツアーに行くわよ!」
壊れんばかりにドアを蹴っ飛ばして現れたハルヒの第一声がそれだった。
部室内にいた俺以外の三人――宇宙人未来人超能力者――の誰もが沈黙したままであった。って、やっぱり俺が訊かないといけないのかよ。やれやれ。
「おいハルヒ。何処に行くんだって?」
ハルヒは虫けらでも見るような目で俺を睨み付けると、
「何度も言わせないでよバカキョン! あたしたちSOS団は恐竜の化石発掘ツアーに出発するの。発見した恐竜には『スズミヤザウルス』って名前が付けられるんだからね」
と宣言した。いや、そういうのは発掘してから考えてくれ。
「ってまさか、いきなりユタ州の砂漠の中にでも俺たちを連れて行こうってことなのか?」
「もっちろん違うわ。前に宝探ししたときのあの山よ。ああ、安心して。鶴屋さんにはもう許可を取ってあるから。そうよね、みくるちゃん」
「は、はいぃ?」
何のことだか全く理解していらっしゃる様子のない朝比奈さんのメイド服姿が、まるで臆病な小動物のようにビクリと震える。
いつの間にか朝比奈さんの背後に回りこんでいたハルヒは、その可愛らしい先輩に突然抱きつくと頬擦りしながら、
「みくるちゃんにはまたお弁当をお願いしてもいいかしら? ……そうだ、また三人で一緒に作りましょうよ。ねえ有希、あなたも手伝ってくれる?」
と適当な思い付きを撒き散らしている。
長門は一瞬顔を上げて、
「……了解した」
と返答したのみで、そのまま元の読書ポーズに戻ってしまったのだった。
正面に目を遣ると、一手詰め問題集と共に将棋盤の上で駒を不器用に並べていた古泉が、
「おや、どうやらあなたはご不満のようですね。何か問題でも?」
と小声で訊いてきた。
「以前の宝探しじゃないが、恐竜の化石なんて見つかるはずがないからな」
「ほほう、どうしてそう言い切れるのでしょうか?」
「古泉、お前『御影石』って知ってるか?」
「ええ、確かこのすぐ近くで取れる石材のことですね。それが?」
「その御影石ってのは『花崗岩』のことだ。『花崗岩』ってのは代表的な火成岩の一種で、この辺の山も大体は花崗岩からなっている。時代的には中生代――恐竜時代のころのもので、化石が含まれる堆積岩はそれよりも表層の新しい時代のものばかりだ」
「つまり、この近辺で採取されるはずの化石は時代的にずれているので、恐竜の化石が見つかることはありえない、と仰るわけですか」
「まあ、そんなところだ」
うろ覚えなので細かいところは突っ込まれても困るんだがな。
「でも……少々意外ですね。何故そんなにお詳しいのでしょうか?」
「決まってるさ。俺もガキの頃は恐竜博士とかいうのに憧れたクチだったからな」
古泉は何か言いたそうに笑みを浮かべた。気色悪いから止してくれ。
「ふふっ、申し訳ありません。でもまあ、いいではないですか。桜の時期はもう過ぎてしまいましたが、新緑を愛でつつピクニックというのもなかなか乙なものですよ」
「余計な肉体労働さえなかったら俺もそう思うがな」
しかし化石発掘とはな。ハルヒのことだから、その辺の校庭とかお構いなしに掘り返しそうな気もしないでもないんだが、そうならなかっただけでもマシってことなのか?
「そうですね。確かこの近辺には新幹線のトンネルが地下を通っているはずですが……」
まかり間違えてそんなところまで穿り返さないとも限らないのが涼宮ハルヒという存在なのだ。ひょっとしたら今回のツアーのために、鶴屋さんの私有地の山丸ごと、どこかの堆積岩の地層にそっくり入れ替えてしまいかねんからな。
「我々としては何事もなくただのハイキングで終わって欲しいところなのですけどね」
苦笑する古泉を尻目に、俺は先程から朝比奈さんにじゃれ付いているハルヒに目を向けた。
いや、大した意味はないぞ。あまりセクハラの度合いが過ぎるようなら、そろそろ止めに入った方がいいかもしれないと思ったまでのことだからな。
…
……
………
この空間はハルヒが作ったモノではない、と長門は言っていた。古泉もそれに同調していたみたいだ。
まあ、きっと古泉なら『おそらく彼らは涼宮さんの潜在意識に眠っていた「恐竜の化石」というものを具現化したのでしょう』だとか、また妙なこじつけの解説してくれたことだろう――この場にいてくれたならの話だが。
坂道を駆け下りながら俺は長門の言葉を思い起こしていた。
『学校の敷地から三キロメートル以上距離をとる必要がある』
三キロね。いつも市内探索で集合している北口駅辺りならそのぐらいの距離は余裕でありそうだが、果たして徒歩でそこまで辿り着くことが出来るかどうか……。
「ねえキョン! ちょっとあれ、見なさいよ」
ハルヒの声に前方を見る。
橋の向こうの県道を下った辺りに、デカい図体の恐竜の骨が二体――背中の特徴的な板状の鰭は『ステゴサウルス』のものだ。
そいつの尻尾の先のスパイク状の棘からの間合いを取るように立ちはだかるのは――肉食恐竜の『アロサウルス』だ! こちらには気付いていないようだが、そのまま脇を通り抜けさせてもらえるとも思えない。
迷っている時間はなかった。背後からは先程の『コエロフィシス』の群れが追いかけてくるのだ。
「くそっ! ハルヒ、こっちだ」
「ええっ、なによキョン? そもそもさっきからなんであたしたち走ってるの?」
「食い殺されてもいいのか?」
「本気で言ってるわけ?」
「えらく本気だ」
俺は橋を駆け抜けるとそのまま県道を上るコースを取った。しかし困ったことになったぞ。このままではどんどん山に向かう一方ではないか。しかも、こっち方面の道はあまり詳しくない。おまけに辺りは真っ暗だ。
でもまあ、県道だからそのうち下りに分岐する道があったはずだ、などといった俺の考えは甘過ぎた。前方からは別の種類の小型肉食恐竜――『ドロマエオサウルス』らしき骨格――の一群が押し寄せてきたのだ。
俺は引き返そうとしたものの、後方からはさっきの奴らが迫ってきているはずだ。
辺りを見回すと、脇の小高い丘の方に向かう道が見えた。確かここは公園だか植物園だったはずだ。
「キョン、あっちに逃げましょう」
珍しくもハルヒの言う通りに俺は従った。
敷地内に入ってすぐ俺は右に曲がる道を選んだ。
「ねえキョン、なんでこっちの道なわけ?」
「確か県道脇のガソリンスタンドの向こう辺りに、公園から下りてくる道があった――と思う」
「ってちょっと! そんなうろ覚えで大丈夫なの?」
「なんなら引き返すか?」
「そんなわけいかな――ねえキョン」
突然ハルヒが立ち止まる。どうしたんだ、急に?
「……戻りましょう」
ハルヒは呆然と前方を見ていた。それを見て振り返った俺もギョッとした。
その先には今まででもっとも巨大な影――『ティラノサウルス・レックス』の禍々しい全身骨格が待ち構えていたのだった。
とっさに俺はハルヒを引き寄せると、道を外れて林の中に飛び込んだ。まともに追いかけてこられたら時速五十キロのスピードのはずなので振り切れるはずもないのだが、何故か『Tレックス』の骨格は一歩一歩足元を踏み固めるかのように進んでいる。
暗闇の中をわけも解らず突き進む俺とハルヒ。その前方の斜面に一際暗い部分がポッカリと口を開けていた。
「見て、キョン! あれって洞穴なんじゃないの?」
ハルヒに言われるまでもなく、俺はその空洞に飛び込むことにしたのだった。
さすがに『Tレックス』はそのデカい図体が邪魔になって奥まで入ってこられない。
だが執念深いのか、先程からずっと入り口でガチガチと鋭い牙の咬み合わされる音が鳴り響いている。このままではいつまで経っても脱出不可能だ。
「さて、どうしたもんかね?」
俺は独り言を言ったつもりだったが、ハルヒはそうは受け取らなかったらしい。
「ねえキョン、このままじっとしててもしょうがないじゃない。せっかくだから奥の方に行ってみない?」
あのなあ、こんな真っ暗闇の中で、洞窟探検のつもりか? 明かりもないのに無茶もいいとこだろ。
「あら、明かりならあるじゃない。あんたもケータイぐらい持ってないの?」
ハルヒはそう言ってスカートのポケットから自分の携帯電話を取り出すと、フォトライトを点灯させたのだった。
白色LEDの頼りない明かりの下、俺は仕方なくハルヒの後ろについて行った。
途中で人一人通れるかどうかという狭い箇所があり、俺たちはしばらく四つん這いになって進むハメになった。その、目の前のハルヒの尻に向かって、俺は話し掛ける。
「なあハルヒ。お前、何だかこの状況を楽しんでないか?」
「なに言ってるのキョン! そんなの――当たり前じゃないの」
表情こそ見えないが、声だけでハッキリ解る。今のハルヒの瞳は銀河系全ての星々を集めたよりも眩しくキラキラしているに違いないのだ。
やがて少し広い空間に辿り着いた俺たちは、ようやく二足歩行に復帰することができた。
「ところで、キョン…………あたし、ちょっとだけ、あんたのこと見直したわ」
「へっ?」
マヌケ声で答える俺をよそに、ハルヒは滔々と語り続けた。
「さっきのあいつらから逃げてる時、キョンは必死だったでしょ」
まあ、必死だったかどうかと言われれば、確かに必死だったんだろうな。
「キョンったら、ずっとあたしの手首掴んで離さないだもん。さっき見たら、ちょっと痕が付いてたわ」
いや、それは――なんというか、その、スマン。
「謝んなくてもいいわよ。それに……なんだかあたしも、ちょっぴり――嬉しかったんだから」
「おいハルヒ、それって――」
「えっ、そ、そのっ――別に何でもないって――きゃっ!」
突然俺の目の前からハルヒの姿が消え失せた。
「ハルヒ!」
思わず飛び出しかかった自分の足を何とか踏み留め、俺は自分のポケットから携帯電話を出してフォトライトを点灯させた。
足元には縦穴が大口を開けていた。底の方にハルヒのものらしいライトの明かりが微かに見える。
「おーい、ハルヒ。大丈夫か」
――返事がない。
「ハルヒ? 返事をしてくれ」
――やはり返事は戻ってこない。
まさか、頭でも打って、意識を失ってしまったのだろうか?
いや、意識を失うだけならともかく、大怪我とかしてたら、どうすればいいんだ? 救急車を呼ぶどころか、この空間は俺とハルヒの二人きりなのだ。
焦る気持ちを何とか堪え、俺はもう一度必死に考える。
俺までもこの縦穴に降りて大丈夫なのだろうか? しかし、このままハルヒを放っておくわけにはいかない。でも……、
そのとき、不意に長門が紡いだ最後のメッセージが俺の頭に浮かんだ。
『あなたはあなたにできることを』
そうだ、ここで考え込んでいても始まらない。
意を決した俺は、携帯電話を落とさぬようにポケットに仕舞うと、深い縦穴に向かって自分の身体を躍らせたのだった。
俺の予想に反して、縦穴の底は平坦であった。携帯電話の照明を頼りに進むと、地面に転がっていたそれのすぐ傍で、ハルヒは膝を抱えて蹲っていた。地面からハルヒの携帯電話を拾い上げると、俺は跪いてからハルヒの肩に手を掛けた。
「ハルヒ、お前大丈夫なのか?」
「!? キョン!」
ハルヒは突然俺にしがみ付いてきた。
「お、おい……」
ハルヒは黙ったまま俺の胸元でブルブルと震えていた。その様子を見て初めて、俺は先程のハルヒの態度の裏にあるものを悟ったのだった。
確かにこいつは今までの状況を楽しんでいたのかもしれない。でも――それ以上に不安がっていたに違いないのだ。しかも突然真っ暗な空間に放り出されて、俺と逸れて独りきりになってしまったんだ。パニックを起こしても不思議じゃないだろう。
でもハルヒは、じっと俺が来るまで待っていてくれたんだ。返事をしなかったのも、不安そうな声を出すことで、俺に心配を掛けるのを嫌ったのかもしれない。
「ハルヒ――その、俺が悪かった」
俺の言葉にハルヒはようやく反応を見せた。
「だから……なんで……キョンが――あたしに謝るわけ?」
途切れ途切れの口調から、俺はハルヒが必死で泣きそうになるのを堪えているみたいに思えてならなかったのだった。
「いや――なんとなくな」
「なんとなくで――謝んないでちょうだい」
「その、スマン」
「ほら……また謝ってる!」
顔を上げたハルヒをLEDで照らすと、俺の思っていたのとは異なり、そこにはいつになく穏やかな表情があった。俺はポケットからハンカチを取り出すと、少し泥で汚れていたその頬を拭ってやった。
「立てるか?」
「うん……でも、落っこちた時にちょっと足首を捻っちゃったみたい」
「そうか……」
「ねえキョン――ゴメンね」
「ハルヒこそ、何で謝るんだ?」
「だって、あたしが落っこちたせいでキョンまで降りてきちゃったじゃないの。このまま二度と――地上に戻れないかもしれないでしょ。あたしのせいで……あんたまでも」
俺は改めて辺りを見渡す。そういえば地面が妙に平らだったというのも不自然だ。よくよく観察してみれば、床面も壁面も人の手が入っているらしいことがハッキリ解る。ということは……。
俺はハルヒを背負うと、僅かな空気の動きを頼りに歩き始めた。
「行くぞ、ハルヒ。俺たちは地上に戻るんだ」
俺の予想通り、しばらく進むと『扉』が目の前に現れた。しかも半分開きかかっている――つまり鍵も掛けられていない。
さび付いた扉をゆっくりと抉じ開け、俺たちはその先の空間に足を踏み入れた。
「キョン、ここは?」
「――――見ての通り、鉄道のトンネルだ」
足元に伸びているのは千四百三十五ミリ幅のレールが二組。俺自身も忘れかけていた。きのう古泉が言っていたではないか。『確かこの近辺には新幹線のトンネルが地下を通っているはず』だと。
このトンネルを東に進めば地上に出られるはずだ。まあ、間違って西に進んでしまったとしても結果は同じ――トンネルを出てすぐのあの駅に辿り着くだけのことだ。もっともそれはそれで相当な距離を歩くことになりそうだが。
「なあ、ハルヒ」
「えっ――なによ、キョン?」
「東はどっちか、お前解るか?」
「――なんでそんなこと、あたしに訊くわけ?」
「もし俺が決めた方向が間違ってたら、お前文句言うだろ?」
「バカ……そんなこと、言わないわよ」
「へっ?」
「だって、あたしは――キョンのこと、信じてるんだもん」
「……そ、そうか」
慌てて俺が一歩踏み出そうとすると、
「ちょ、ちょっとキョン、待ちなさい! やっぱりあっちが東だと思うわ」
「おい! さっきお前、俺のこと――」
「なによ、そもそもキョンの方からあたしに訊いてきたんじゃないのよ」
「全く……じゃあ、本当にこっちでいいんだな?」
「うん――なんとなくだけど」
「なんとなくで――決めないでくれないか」
「うるさい、バカキョン!」
俺はハルヒの示した方向に歩き始めた。確かこのトンネルは全長が十六キロメートル以上はあるんだっけ。北高の辺りがトンネルの中間点とは思えないし、間違いだったら正解の方の数倍は歩かされるハメになりそうだな。
でもそうだな、どの道このまま進むことができれば、長門の言っていた『三キロメートル』は何とかクリアできそうな気がする。
「ねえキョン」
「何だ、一体?」
「……ありがと」
今度は何のつもりだ? と俺が怪訝に思っていると、ハルヒは俺の肩越しに廻した腕の力を少し強めてきた。おいハルヒ、お前、俺の首でも絞めるつもりか?
「バカ……」
ハルヒの勘は正しかった。
一時間も歩かない内に、出口の明かりが見えてきた。つまりこちらが東側の出口らしい。
「って、おい! 明かりだと?」
ということは、俺たちは無事に閉鎖空間から脱出できたってことなのか? そういえばいつの間にか、トンネル内の蛍光灯も点灯されている。
慌てて携帯電話の時計表示を確認する。まずい、そろそろ新幹線の始発列車の通過時刻が来てしまう。『無事に』などと判断するのはまだ早過ぎたのか?
と、トンネルの出口辺りに見覚えのある人影が――長門か!
「急いで」
長門に言われるまま駆け出す俺。ハルヒは結構前から俺の背中で寝息を立てていた。
「掴まって」
長門はそう言って俺の正面から抱きついてきた。背中にはハルヒ、前には長門、俺はサンドイッチ状態。などとバカなことを言っている場合ではない!
「うおっ!」
次の瞬間、俺たち三人の身体は空中高く跳ね上がっていた。滞空時間がやけに長く感じられる。
しばらくして俺たちはトンネルの真上にあった公園らしきところに軟着陸した。
「キョンく~~ん!」
我らがスィートエンジェル、朝比奈さんの悲鳴じみた呼び声が聞こえる。
「よかった……無事で……涼宮さんも――えぅぅ! ほんとに――よかったですぅ~……ぐすん」
朝比奈さんは顔をグシャグシャにしたまま、ハルヒと長門ごと、俺に体当たりするように横から抱きついてきた。
「どうもお疲れ様でした。閉鎖空間の方は先程、長門さんの協力でなんとか消滅させることができました。あのまま放っておいたら、地球を丸ごと包んでしまうぐらいの大きさにまでなっていたかもしれません」
待て古泉、お前は抱きつかなくていいからな。って、そんなに大規模な閉鎖空間だったのか?
古泉はどこか寂しそうな表情で続けた。
「ええ。でも一番の功労者はあなたですよ」
はあっ? 俺は何もした覚えはないぞ。
「敵本体があの空間を維持し続けるためには、涼宮ハルヒの身体からエネルギーを吸収し続ける必要があった。その有効射程距離は三キロメートル」
それで北高の敷地から離れろ、ってことだったのか。
「そう」
やれやれ。ところで長門、それに朝比奈さんも、一体いつまでこうしてくっ付いてるんですか?
「……もうしばらく」
「ふえぇ……ひっく――」
「ぐー、すぴ~」
三人の女神に抱きつかれ状態のまま俺は深く嘆息した。
「――なあ、古泉」
「何でしょうか?」
意味ありげな視線で答える古泉。何だその目は?
「いえ、単純なことです。正直、僕はあなたのことをこれほど羨ましいと思ったことはありません」
そうかい。まあそんなことはどうでもいい。お前って、事後処理とかは得意だったりするか?
「はて? どういうことでしょうか」
「なに、単純なことだ。手首に痣がついてたり足首を捻挫した人物に、今までの出来事は全部夢でした、って納得させるためには、果たしてどういった言い訳を駆使すればいいのかってことなんでな」
「なるほど、それは難問ですね」
真剣なんだかそうでないのかイマイチ解らん古泉の表情から目を逸らすと、俺はいっそ何もかもハルヒにバラしてしまったらどんなに楽だろうな、とか出来もしないことを考えながら、すっかり明るくなった空を見上げたのだった。
ちなみに、SOS団のみんなで例の鶴屋山に出かけたのは更にその翌週の土曜日のことだった。
さすがに恐竜の化石は懲り懲りだったのだろうか、ハルヒが発掘云々はどーでもいい、とか言い出したため、何のことはない、ただのハイキングに成り果てていたのだったが……。
「ねえキョン。今のはどうだった?」
「ん~、結構いいんじゃないか」
「ちょっとキョン、さっきからそればっかりじゃないのよ。もっと真面目に答えなさい!」
「いや、だから旨いって言ってるじゃないか」
「ほんと?」
「本当だって」
「ふーん。まあいいわ……じゃあ、次はこれよ。はい、あ~ん」
「……うん。ハルヒ、やっぱり俺、好きだな」
「へっ? ちょ、ちょっとなに言い出すのよ」
「何って、お前がさっき訊いたんじゃないか、『卵焼きは甘い方が好きなんでしょ?』って」
「もう! 紛らわしいのよ、あんたは。さてと――ほら、今度はこっち。……あ~ん」
「あ、あのぅ、なんだか涼宮さん、あの日以来、キョンくんに対してものすごく積極的になってる気がするんですけど――」
「確かにそうですね。長門さん、あの時お二人の間に、何かおかしなことはありませんでしたか?」
「……おかしなこととは、具体的にはどのようなことか? 四百字以内での説明を求める」
イラスト 
恒例ラクガキさん。誤魔化しのために滅茶苦茶縮小したけど
結局誤魔化しきれてないんですね、わかりますwww
まあ挿絵的なものってことでご勘弁
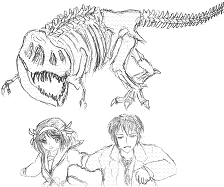
上記だけではあんまりなのでもう一個ラクガキ

 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ