概要 
| 作品名 | 作者 | 発表日 | 保管日 |
| 小さな来訪者 | 83-388氏 | 08/03/08 | 08/03/09 |
作品 
今まで色々とわけの解らん事件に巻き込まれてきたSOS団、っていうか、主に俺なのだが、何か事件の前には決まって予兆のようなものがあるということは、なんとなくではあるが俺にも解ってきた。
まあ、これほどまでに散々経験値を積めば、否応なしに学習するってところだろうけどな。
まず一目瞭然なのは、ハルヒが満面の笑みを浮かべた状態で、勢い良く部室のドアを開けて現れたときだな。その次の瞬間のあいつの口から飛び出した言葉のせいで、何度悲惨な目にあったことやら。
それ以外にもいくつか前触れらしきものはあるが、みなさんも思い当たることと言えばこれに尽きるだろう。
即ち、文芸部室への意外な来客、というものだ。
というわけで、今回のお話はとある珍客にまつわるものなのだが、よくよく考えれば事件、とまでは言えない程のささやかな出来事に過ぎなかったのかも知れない。
だが、その来訪者は、俺たちの胸の中に、何か確かなものを残していったのであった。
ある日の放課後のこと。
ハルヒと俺と朝比奈さんと、ついでに古泉、の四人は、パイプ椅子に腰掛けて読書を続ける長門の周りを取り囲んで、静かに見守り続けていた。
いや、これだけでは説明が足りんな。俺たちが見守っていたのは、長門の腕に抱えられた、小さくて茶色の毛むくじゃらなフワフワのモコモコな存在だったのだ。
黙っていられなくなったのか、最初に声を発したのは朝比奈さんだった。
「あっ、今ほんの少しだけ、動きましたよ」
「ちょっと、みくるちゃん。ぬいぐるみじゃないんだし、いくらなんでも動いたりぐらいするわよ」
っていうか、さっきハルヒは『まるでぬいぐるみみたい』って言ってなかったっけ。
「なによ、キョン。『みたい』って付けてるんだから、ぬいぐるみじゃないのは当たり前じゃないの。いちいち屁理屈をこねないでよね」
「まあまあ、みなさん、お静かに。あまり騒がしくすると、『彼』が目を覚ましてしまいますよ」
古泉の一言で沈黙する俺たち。
「…………」
長門は終始無言のままで、片方の手に持ったハードカバーのページを器用に繰りながら、もう一方の腕でその可愛らしい存在――柴犬っぽい幼犬をずっと抱き続けていたのだった。
話は数時間さかのぼって、昼休みのこと。
パソコンで調べ物でもしようと部室のドアを開けた俺を待っていたのは、仔犬をしっかりと抱えて突っ立っていた長門だったのだ。
「な、長門。――それ、どうしたんだ?」
「拾った」
「そ、そうか、拾ったのか。……いつ、何処でだ?」
「今朝、通学の途中」
「って、朝からずっとそいつと一緒にいたのか?」
「そう」
よく騒ぎにならなかったものだな。まさか一限目からここでサボってたとかじゃないよな。
「教室では視覚、聴覚、その他問題と思われる要素から全て遮蔽。誰にも気付かれることはない。食事をさせる必要があったため、一時的にこの場に移動」
そこに偶然俺が来ちまったってことか。なるほどな。
「偶然ではない。あなたが来ることは予測済み」
なんだ――――まさか、俺の昼飯を当てにしてたってことか。
「厳密には飲み物」
って言われても紙パックの牛乳しか持ってきてないぞ。
「構わない」
そう言って長門は仔犬を抱えたまま俺の方をじっと見つめてきた。仔犬も長門に合わせたかのように俺のことを見ている。
なんだろう、同じ光を放つこの四つの瞳を前にして、抵抗可能な人間が存在するであろうか、いやいない(反語)。
「解った解った。謹んで進呈させていただきますとも」
「……感謝する」
長門は俺の牛乳を受け取ると、何処から取り出したのか金属性の容器に注ぎ、朝比奈さん御用達のコンロで温め始めた。
その間、代わりに仔犬を抱き上げる俺。なんか、力の入れ加減とか解らんので怖々ではあるのだが。
直火に掛けた容器を平気な顔で手にした長門は、暫く手元の白い液体を眺めていたが、
「……適温」
と言って俺の方に差し出してきた。
釣られて俺も仔犬の顔を容器に近付ける。火傷の心配は――――まあ、長門のことだから心配あるまい。
仔犬は暫く鼻をヒクヒク鳴らしていたが、やがて小さな舌を繰り出して器用に生温い牛乳を飲み始めた。
「なあ、長門。お前、こいつを飼うつもりか?」
「諸般の要因を考慮すると、自宅での継続的な飼育は困難。ただし……引き取り手が決まるまでは面倒を見たい」
そう言い切った長門の表情は、普段は滅多に見られないハッキリとした意思が感じられた。
まあ、そういうことなら俺もできる限り協力しなけりゃな。
再び時間は放課後。
各メンバーと仔犬の初対面の様子なのだが、
「あ、あのぅ、長門さん。その、お犬さん、どうしたんですか?」
「おやおや、これは可愛らしいお客さんですね」
「ちょっとちょっと有希!なにそれ?可愛いじゃないの。あたしにも触らせてよ」
おっかなビックリの朝比奈さん、相変わらずのスマイル古泉、興味津々のハルヒ、と三者三様の反応であった。
「おい、ハルヒ。今は眠ってるみたいだから、ちょっかいを出すのは止めとけ」
「なによ。キョンのクセに偉そうね」
そう文句を垂れるハルヒだったが、さすがにいつものような無茶はする気配がない。少しはこいつも丸くなったのか?なんて思わない方が正解なんだろうけど。
そんなこんなで、先に述べたように、長門を囲んで大人しく仔犬観賞していた俺たちだったのだが、
「あっ、お犬さん、目を覚ましましたよ」
「ねえ、有希。あたしにも抱かせてちょうだい」
「…………」
長門は無言でハルヒに仔犬を手渡す。って、おいハルヒ、その抱き方、なんか危なっかしくないか?
「大丈夫、平気だってば。――あはっ、なんだかふかふかで気持ちいいわね、この子」
ハルヒの腕の中で仔犬は大人しくしている。そうだな、大人しくしてた方が身のためだぞ。
しかし、仔犬を抱きかかえて満足そうに微笑むハルヒを見て、俺は何とも説明し難い妙な気持ちになったのだった。
十分仔犬の感触を堪能したらしいハルヒは、
「ほら、みくるちゃん。あなたも抱いてみなさいよ」
「へっ、わ、わたしですか?」
と、戸惑う朝比奈さんに何の躊躇も無く手渡す。すると、そのとき今まで静かにしていた仔犬が初めて予想外の反応をした。
「ひゃっ、ふひゃぁぁ~~!く、くすぐったいですよぅ」
ペロペロと朝比奈さんの顔中を舐めている。悲鳴を上げた朝比奈さんの口の中にまで鼻を突っ込む勢いだ。うむ、羨ましいヤツめ。
「ふ、ふぇっ、も、もごっ!や、やめてぇ、い、いやはぁ……キョ、キョンく~ん、助けてくださ~~い」
慌てて俺は朝比奈さんから仔犬を引き離す。って、今度は俺の顔にむしゃぶりついてくるではないか!
「うぉ!ちょ、ちょっと待て。ぶはっ!おい、コラ!――ええい、止めんか――すまん、古泉」
無理矢理に古泉に受け取らせる俺なのだった。緊急避難だ。この際致し方あるまい。
「おっとっと、よしよし。お願いですから大人しくしていてくださいよ。でないと――――少々困ったことになるかもしれませんね。うふふふっ」
って古泉、なに笑ったまま恐ろしげなセリフを言うんだお前は。
しかしまあ、再び古泉の腕の中で言われた通りに大人しくなる仔犬様であった。顔中涎まみれの朝比奈さんと俺は顔を見合わせてつい溜息を吐く。
こいつ、人によって反応変えてないか?怒られそうにない相手にだけ悪戯するなんて、大した野郎だぜ、全く。
ところで、ハルヒはどうかしたんだろうか?大きく口を開けて俺と朝比奈さんの方を見ていた。と思いきや、
「こ、古泉くん。ちょっと、もう一度あたしに貸して」
そう言って、半ば強制的に古泉から仔犬を受け取ると、ハルヒは顔を近付けて頬擦りを始めた。しかし、ハルヒの腕の中では大人しくしているヤツなのだった。
「あれっ、ちょっとあんた?もうペロペロはしないの?」
何だ、ハルヒ。お前、そいつに顔を舐めてもらいたかったのか?
「う、うるさいわね。そんなのキョンに関係ないでしょ――きゃぁっ」
ハルヒが俺に対して叫ぶと同時に、仔犬がハルヒの口元を一舐めした。おいおい、そんなに叫ぶ程のことか?
「もう…………キョンのバカっ!」
何で俺なんだよ。それに、ハルヒ――どうしてお前そんなに顔が赤いんだ?
「し、知らないったら!」
しかし、いつまでもこいつを『仔犬』とばかりも言ってられないよな。
「そうねえ。ところでキョン、この子って眉毛っぽいのが結構特徴的じゃない」
「…………涼子」
ん、長門?何か言ったか?
「なにも」
「しかし、涼宮さんの言う通り、興味深い眉毛ですね。なんというか、公家のような高貴な感じでもありますよ」
「そうだ、決めたわよ。この子の名前はたった今から『まろ』よ!」
なんだそれは。画像も貼らずにスレ建てとな、っていかんな、俺。悪いインターネットに毒されない!
「そういえば、わたしの知り合いの方が飼っていたお犬さんが『マロンちゃん』ってお名前でしたけど、なんだか可愛い名前ですよねぇ。えへへっ」
そう言って微笑む朝比奈さんに癒される俺なのだったが、何故そういう話がここで出てくるのかは全く解らない。まあ、気にするな。
結局、その日は長門が『まろ』を連れて帰ることになったのだが、何故かハルヒまでが長門のマンションまで行くことにいつの間にか決定していたのだった。泊めてもらうつもりかよ。
「そうよ。ねえ、有希。いいでしょ?」
「いい」
やれやれ。しかしハルヒめ、よっぽど『まろ』のことが気に入ったらしいな。
果たして翌日、再び『まろ』を学校まで連れて来たハルヒと長門なのである。
って、ハルヒよ。平然と『まろ』を教室に連れて入る長門を見ても、お前は何も不思議に思わないのか、お前は。
まあ、なんにせよ、ここ数日イライラしている様子だったハルヒの機嫌が上方修正されていることには違いない。これもきっと『まろ』のおかげなのかも知れん。
だが、いつまでも中途半端な飼い方はできないわけだし、俺たちは阪中を始め、多方面に『まろ』の里親の募集をして回ったのだった。
ところで、と言うか案の定と言うべきか、今日のハルヒは一日中上の空状態であった。ホームルーム終了後、待ちきれないとばかりに教室を飛び出して部室に駆け出して行くハルヒ。おーい、あんまり慌てて転ぶなよ。
「なにしてんのよ、キョン。あんたもさっさと来なさ~い」
へいへい。
ちなみに、本日の昼休みにも俺の牛乳が『まろ』に与えられることになったのは言うまでもない。
まあ、それを見越して、今日は余分に買ってきてたしな。っていうか、昨日飲み物なしで食ったサンドイッチはパサパサで喉につかえそうになったっけ。結構厳しかったな。
部室では『まろ』を抱えてご機嫌なハルヒがお待ちかねであった。
どうでもいいけど、あんまり弄り回さない方がいいんじゃないか。まだ仔犬なんだし、疲れてしまうぞ。
「大丈夫、大丈夫。ねぇ、『まろ』ちゃま~。よちよち、お腹空いてないでちゅか~?」
何だその幼児語は。と、ご覧の通りハルヒはすっかり壊れてしまったようである。やれやれ。
「はは~ん。なによキョン。あんたも『まろ』ちゃまを抱っこしたいんでしょ?ダメよ。次は有希の番なんだからね。ホラ、有希!」
「…………」
長門も待ちきれないといった様子で『まろ』を抱き寄せる。『まろ』は長門の腕の中が一番安心するのか、すぐに寝てしまった。
「はあ~、『まろ』ちゃまは寝顔も可愛いでちゅね~。…………まあ、どっかの誰かさんも、寝顔だけは可愛いんだけど」
その『何処かの誰かさん』ってのは一体誰なんだろうね。
「う、うるさいわね。あんたは一々ツッコミ入れなくっていいの」
その後、目を覚ました『まろ』は、朝比奈さんに温めてもらったミルクを飲み干すと、昨日の再現VTRよろしく朝比奈さんの顔を舐めまわしたりとか、俺の腕の中で粗相したりとか、そんな按配であった。
放課後、またも長門宅に押しかけるらしいハルヒは、一度自宅に戻るとか言って、先に帰ってしまった。
『まろ』を抱えた長門を先頭に、俺と朝比奈さんと古泉はいつもの坂道を下っていた。
「おい古泉、どうかしたのか?」
ふと俺はいつものスマイルを半減させたかのような古泉に声を掛けていた。
「いえ――――少々、涼宮さんのことが心配でしたので」
心配?あんな御機嫌なハルヒの何を心配するって言うんだ?
「まさにそこですよ。僕が懸念しているのは」
はあ?サッパリ意味が解らん。
と、朝比奈さんも、おずおずと話に加わった。
「あ、あの、キョンくん。『まろ』ちゃんは、そのうち、誰かのところにもらわれていくんですよね」
まあ、そのためにも俺たちは色々と八方に声を掛けたりしてきましたからね。
「涼宮さん、すっかり情が移ってるみたいで――別れが辛くなっちゃわないか――わたしも心配です」
なるほど、そこで俺も腑に落ちた。
朝比奈さんはまるで自分自身のことのようにハルヒを心配していた。それは多分、朝比奈さん自身が、いつか自分の時代に戻らなければならなくなったときに、辛い思いをすることを解っていて、それを覚悟しているようにも俺には見えたのだった。
そして翌日。
朝比奈さん経由で鶴屋さんの知り合いに『まろ』の引き取り先が見つかったとの連絡がもたらされた。
昨日の帰り道の会話のこともあり、ちょっと気にはなっていたのだが、急な話にもかかわらず、ハルヒは率先して『まろ』受け入れのための準備を手際よく進め、
「それでは、『まろ』ちゃんのこと、どうかよろしくお願いします」
と、先方にも簡単な挨拶のみして、あっさりと『まろ』を託してしまったのだった。別れを惜しむような湿っぽいムードなんて欠片ほども見られなかったのは意外だった。
ハルヒのその態度のため、却って俺は妙に不安になってしまったのだ。
更にその翌日。
傍目には、すっかりいつも通りに戻ったハルヒであった。いつも通り、というのは、適度に退屈そうであり、適度に笑顔を見せ、度を越して我侭な、という例のパターンだ。
でも、俺はそんなハルヒを見ても、昨日以来の胸のわだかまりを解消させることはできなかった。
放課後、部室のパソコンでしばらくネットサーフィンをしていたらしいハルヒだったが、突然立ち上がったかと思うと、
「みんな、ごめん。あたし、今日用事があったの、うっかり忘れてたわ。悪いけど先に帰るわね。ああ、みんなは適当に解散していいから」
と、自分の鞄を手に、普段よりも随分と控えめなドアの開閉とともに出て行ってしまった。
「はあ~っ」
暫しの沈黙の後、つい、深い嘆息を漏らしてしまった俺を見て、古泉が尋ねてくる。
「さて――――どうしますか?」
どうもこうも、今日はもう解散ってことなんだろ。帰るしかないんじゃないか。
「僕が訊いているのはあなたのことですよ」
ちっ、図星か。
「さてな……ちょっと寄り道して帰ることにでもなりそうだな」
俺の声に朝比奈さんも
「キョンくん…………涼宮さんのこと、お願いしますね」
と、縋るような目で声を掛けてくる。ええ、言われなくても解ってるつもりですよ。
「…………本館の屋上」
長門よ、それは今ハルヒがいる場所のことか?
「そう」
やれやれ、いつもすまないな。
ドアを出る寸前で、俺は再度長門の方に振り向き、
「なあ、長門。――――お前も、『まろ』がいなくなって残念だとか、ちょっと寂しいとか、思ってたりするのか?」
と訊いてみた。
長門は、いつかのような『まろ』と同じような瞳をして答えた。
「『彼』が引き取られることは当初から想定済み。『彼』にとってもそれは現時点で最適と思われる措置。そのことに関しては、わたし個人としても特に残念だという感慨はない。…………でも」
でも?
「おそらく涼宮ハルヒが今感じている複雑な心理状態と同じものがわたしの中にも発生していることは否定しない。…………ただ、これが寂しいという感情なのかどうかは判別不可能」
そうか、解ったよ、長門。――ちなみに、今のその感情ってのは、俺にも朝比奈さんにも、ついでに古泉にだってあるはずなんだぜ。
「そう」
なんとはなくだが、俺は長門が頷いてくれたように思えたので、あらためてハルヒの元へと向かうことにした。
屋上ってのは本当は立ち入り禁止なのだが、すっかり俺たちSOS団員はこの場所の常連と化してしまったな。
果たして、ハルヒは手すりにもたれて、遠くの空を眺めているようだった。
「…………キョン、なの?」
こちらのことも振り返らずにハルヒはそう呟いた。まるで後ろにも目がついているみたいじゃないか。
「ああ。――――ハルヒ、お前用事があって帰ったんじゃなかったのか?」
「あたしはここに用事があったの」
どんな用事だよ、それは。
「あんたこそ、なにしに来たのよ?」
まあ、なんとなく、ってのはダメか?
「――別にいいけど」
一応ここにいてもいい許可を得たことになるんだろうか。だが、そんなハルヒに対して、俺が何と声を掛けたものか逡巡していると、ハルヒはそのままの姿勢で俺に語りかけてきた。
「ねえキョン。…………あんたがあたしに言いたいことってのは、なんとなくだけど解る気がするわ」
一瞬ドキリとした俺のことなど構わずに、ハルヒは言葉を続けた。
「実は一昨日、有希のところでちょっとね。喧嘩って程でもない、っていうか、有希とは喧嘩になんてそもそもなりっこないんだけど、『まろ』のこと話しているうちにあたしが勝手にアツくなっちゃって」
ハルヒは多分無意識だと思うが、髪を払うとあちら向きのまま腕組みをした。
「有希は貰い手が決まることをもう知ってたみたいだったわ。まあともかく、表面上はいつも通り冷静そのものだったけど、内心は寂しがってるんじゃないかって思って、あたしは有希にずっと飼ってみるように説得してたの…………でも」
結局、長門は受け入れなかったわけだ。
「……うん。それに――――途中で気が付いたの。本当に寂しいって思ってるのは、実はあたし自身だったんだ――――ってことにね」
「ハルヒ…………」
「滑稽だわ。人のことを心配してるつもりで、ほんとは自分がそうなんだってことを認められなくって――なんかすっごいバカみたいじゃない、あたしって」
ハルヒは自嘲気味に笑うと、ポツリと呟く。
「こんなことじゃこの先どうなっちゃうのかしらね。例えば、SOS団のみんなと離れ離れになったりしたら、あたしはちゃんとやっていけ――」
多分魔が差したんだと思う。
気が付くと俺は、ハルヒを背中側からすっぽりと抱きしめていたのだった。何故かは解らんが、そうしないとハルヒが、また俺の前から姿を消してしまうような、そんな錯覚に囚われてしまっていたのかも知れない。
「ちょ、ちょっと、キョン?」
「縁起でもないこと、言わないでくれ」
「えっ?」
「第一、ハルヒ。お前常々言ってるじゃないか。SOS団は全員集合でなきゃダメだって。団長のお前がそんなこと言っててどうするんだ?」
「キョン…………あんた――まさか、泣いてるの?」
「そんなわけねーだろ」
「だって……」
ハルヒは俺の腕の中でぐるっと百八十度身体の向きを反転すると、不意に顔を近付けて、俺の頬をペロッと舐めた。
「……涙って、やっぱりしょっぱいわね」
違う。それは涙じゃなくって――――そう、汗だ。
「なによ、心の汗とでも言いたいわけ?」
「大体、何でいきなり俺を舐めるんだ?『まろ』の真似でもしてるつもりか?」
「キョンの方こそ、ずっと『まろ』を抱っこしてたせいか、癖になっちゃったみたいじゃないのよ」
そういわれて初めて、俺は自分のしていることに気付いた。慌てて腕を解いてハルヒを開放する俺。ハルヒも真っ赤な顔をして俯いてしまっている。しまった、怒らせちまったのか?
「…………バカキョン」
「す、すまん。俺は、その――――」
「ねえ……あんた、あたしのこと、慰めようとしてくれたのよね」
「へっ?」
「――――ありがと、キョン。あんたの言う通り、あたしたちSOS団はみんな一緒でなきゃね……これからもずっと」
ハルヒはそう言って、俺の胸に顔を埋めるようにもたれ掛ってきた。それにつられるように、俺もハルヒの背中に両腕を回していたのだった。
やれやれ、『まろ』のせいで、俺にも変な癖が付いちまったのかも知れんな。
やがて下校時刻となり、俺とハルヒは連れ立って校舎を後にした。
って、なんで校門前にお前ら三人が勢ぞろいしてるんだ?
「おや、決まっているではないですか。『SOS団は全員集合でなきゃダメ』――そうですね、涼宮さん」
「えっ、ええ。その通りよ、古泉くん」
まさか、みんなで俺とハルヒのことを覗いてたりしないよな?
「ひえぇっ、な、長門さん、なんですかぁ?」
悲鳴の方を見ると、長門が朝比奈さんの身体を背後から羽交い絞めにしていた。
って、長門よ、お前も抱き癖が付いたってわけでもないだろうに。
「抱き癖とは、正確には赤ん坊が抱かれていないとむずがる状態のことを言う。なお、親子のスキンシップ面から考慮すれば、抱き癖が付くのは寧ろ望ましいこと」
って、解説しながらも朝比奈さんを抱っこ状態である。
しかも、なんというか、さっきうっかり俺がハルヒにしていたのと寸分違わぬ体勢ではないか。
さすがだな、長門。もう笑うしかないぜ。あははは。
「しかしなあ、ハルヒ。『まろ』のこと見ててふと思ったんだが、お前に子供が産まれたら、なんていうかもの凄く甘やかしてしまいそうな気がしてならないんだけどな」
「なによキョン。それはあたしが甘やかすってこと、それともあんたがそうするってことなの?どっちなのかハッキリしなさいよ!」
「無論、お前のことだ。ハルヒのあの可愛がりっぷりを見てると、過保護になりすぎやしないか俺は心配でたまらん」
「ふんだ。確かにあたしは我が子を思い切り可愛がるつもりではあるけど、ちゃんと厳しくするべきところではそうするんだもん。そもそも、キョンみたいに頼りないお父さんじゃ、なにかと不安なのはあたしの方だわ」
甲斐性なしで悪かったな、こんちくしょうめ。
「ところでハルヒ。お前将来は、その、犬を飼ってみるとか、そういうつもりはあるのか?」
「まあ、それもいいんじゃない。そうそう、『まろ』みたいに可愛い柴犬なんてどうかしら。一匹だけだと寂しがるといけないから、最低でも三匹。どうせなら五匹ぐらいは飼いたいところよね。ああ、もちろんキョンにもちゃんと世話を手伝ってもらうんだからね」
ハイハイ、相変わらず無茶な要求ばかりしてくれるぜ、本当にな。しかしそうなると、将来的には少なくともちゃんとペット許可の物件に住めるようにならないといけないな。
まあ、適度に頑張ってくれよ、俺。
「ふえぇっ、誰も指摘しませんけど、涼宮さんもキョンくんも、あまりにも自然にお二人自身の将来設計をちゃっかり済ませてるんですぅ」
「ふ~む。でもまあ、このパターンも、僕たちからすればもう慣れっこですからね」
「…………なお、最近はペットも虫歯を発症するので、糖分にはご注意を」
イラスト 
前半が長門成分多すぎなのでちょっとバランス的にどーかなとか反省点タプーリ orz
なんか犬が犬に見えないラクガキ
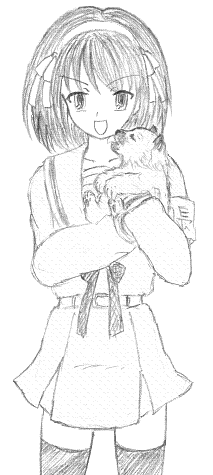
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ