概要 
| 作品名 | 作者 | 発表日 | 保管日 |
| 日常 | 75-564氏 | 08/01/06 | 08/01/06 |
作品 
『一寸の虫にも五分の魂』という言葉がある。体長三センチばかりの虫ですら、その半分にもなる魂を持っており、いくら小さかったり弱いものでも侮るべからず、という意味であることは今更解説の必要もあるまい。
だが、あのSOS団の団長にとっては、雑用係という者が、虫どころかミジンコ程にすらも気遣いの対象となることは無い。
本日もクソ寒い中ジュースを買いに外の自販機までパシらされたりとか、人使いの荒さも毎度のことである。
「遅い!なにやってたのよ、キョン。三十秒以内に買ってこなきゃダメじゃないの」
どう考えてもそれは物理的に無理なんだがな。光速のランニング・バックでもそうは行かんだろう。しかし冷えるな。っていうか寒気がするぞ。風邪引いて熱が出るとか、そんなパターンはゴメンだぜ。
「バカは風邪引かないっていうし、気のせいよ。大体、キョン。病は気からって言葉もあるんだから、あんた気合が足りないのよ」
そんなオリンピック代表の女子レスリング選手に檄を飛ばすその父親みたいなこと言われてもな。精神論だけで何とでもなるなら、金銀銅のメダルは日本人が独占だ。おまけにパールのプレゼントまでついてくるぞ、きっと。
と、俺が愚痴をこぼしたところでハルヒの耳にそれが届いているかどうかも怪しい。
何を企んでるのかは解らんが、今のこいつの奴の瞳に宿る光は通常の三倍モード。せめてもの救いはすこぶる上機嫌なことぐらいかな。やれやれだ。
ハルヒの満面の笑顔とは対照的に、その日の俺は、カレーを食っていてうっかり丁子とか月桂樹の葉を思いっきり噛んでしまったときのような苦々しい顔のまま授業を受けていたのだった。
放課後、体調のことを考えるなら、SOS団の活動なんぞサボって、とっとと帰宅して寝てた方がいいというのは、重々承知之介なんだが、今こうして俺がいつもの如く旧館に向かう渡り廊下を歩んでいるのは一体どういうことなんだろうね。
まあ、ハルヒの奴が眼を三角にして閻魔大王のごとく怒り出すのが怖いから、という理由よりは、朝比奈さん印の香り豊かなお茶目当て、といった方が正解に近いだろう。
いつだったかの、玉露の茎のお茶、なんて名前だったっけ、針ガネ、じゃないけど何かそんな感じの、あれは絶品だったね。是非もう一度ご馳走になりたいものだと思う。俺なんぞにはさぞかし勿体無いシロモノなのだろうけどな。
ドアをノックして、我等が絶対無敵最終兵器メイド天使様の『はぁい』という清らかな声を確認した俺は、
「ちわーっす」
と、挨拶して部室に足を踏み入れる。
非日常的な日常空間。そこには、既に宇宙人未来人超能力者と我等が団長様が、いつものように怠惰な時間を過ごしているのであった。って、俺も人のことは言えないよな。
「あ、キョンくん。おつかれさまです。今、お茶用意しますから、ちょっとだけ待っててくださいね」
編み物をしていたらしいメイド服の朝比奈さんは、自分の作業を中断してまで、俺のために急いでお茶を用意してくれる模様だ。
いつもいつも申し訳ありませんね。俺なんかのためにそこまで慌てる必要なんて無いんですよ、と一声掛けるべきなのかも知れんが、俺は黙って朝比奈さんのことを眺めていた。
この可愛らしい先輩が小動物チックにちょこまかと動き回る仕草は、見ているだけで癒される。アロマテラピーやリフレクソロジーなんかよりもヒーリング効果抜群だと勝手に俺は思い込んでいる。
おおっと、いかんな。顔面の筋肉が緩んだせいか、鼻水が出そうになってしまった。すすり上げる音が室内にみっともなく響く。
「おや、本日はあまり体調が優れない様子ですが、大丈夫ですか?」
将棋盤を広げて、一人で初級詰将棋問題集とでも格闘していたのであろう古泉が、いつもの調子で俺にニッコリ微笑む。
「風邪でも引いたかもな。ちょっと熱っぽい気もするし」
まあ、何にせよ、お前なんぞに心配してもらったところで大して嬉しくもなんともないんだけどな。
「ふふふ。では、今日あたりは、僕にも勝機あり、ということなのでしょうかね」
と言って、持っていた歩を三枚盤面に転がすと、駒を初期状態に並べ直し始めた。ってまさか、今のは駄洒落のつもりだったのだろうか、古泉よ?
それを合図に、長門が一旦本を閉じ、奥の席から俺の隣のパイプ椅子に移動してくる。
ああ、この銀河を統括する情報統合思念体謹製の対有機生命体コンタクト用ヒューマノイド・インターフェースが何でまた俺と古泉の暇つぶしゲームなんぞに関心を示しているのかというと、それは最近の長門の読書傾向に端を発するのであった。
数日前から長門が読んでいた本は将棋の定跡書だとか観戦記とか、はたまた江戸時代に作られた長編詰将棋集の類のものだった。そのことを知った俺は長門にこう訊いてみたのだ。
「長門、お前がその手の本読んでるなんてな。将棋に興味でも持ったのか?」
「……」
毎度の如く、無言で僅かに首を縦方向に動かす。肯定の意味だ。
「ルールは知ってるのか?駒の動かし方とかそういうのは」
「……一応は把握している」
「へえ、なんなら俺と指してみるか?」
「それよりも、対局者の心理的動向に興味がある。できれば……あなたが対局しているところを観戦してみたい」
というようなやり取りがあって、ここのところ、俺と古泉が将棋盤をはさんで対局しているのを脇で観戦、というか人間観察している長門、という構図が数日続いているのだった。
ただ、今にして思えば、もし対局していたならば、初めて将棋を指したはずの長門にボッコボコにされて、俺の虫ケラ程のプライド(推定一.五センチ)が木っ端微塵になっていたであろうことは明らかだ。
きっとそれは長門なりの俺に対する思いやりみたいなものだったんだろうな、と思った。全く、奥ゆかし過ぎるぞ、長門。ハルヒの奴にも是非見習って欲しいところだ。
で、そのハルヒはというと、そんな俺たちの様子が気になったりでもしたのだろうか、度々俺の方を見ていることがあった。で、俺がハルヒの方を見た途端、何事も無かったかのようにパソコン画面に集中している振りをするのだ。
見たいなら長門がしてるようにもっと近くに寄ってくればいいだろうが。
「ふん。プロ棋士のタイトル戦とかの対局ならともかく、あんたのヘボ将棋なんて、見るだけ時間の無駄よ」
と、想像通りの反応だ。でもって、やっぱりチラチラとこちらを覗き見ているのは変わらない。
なあハルヒよ。お前も意地を張らずにもう少し素直になってみたらどうだ。きっと世の中の違う面が色々見られると思うぜ。
なんてことを俺は口に出して言ったりはしない。それ以前に、俺自身が素直じゃないってことを自覚しているからな、うむ。
朝比奈さんのお茶で喉を潤し、一呼吸入れた俺は古泉に宣言する。
「いつも通り、お前の先手で構わんぞ。それじゃあ一つ、よろしくお願いします、っと」
「了解です。お手柔らかにお願いしますよ」
一礼を交わす俺と古泉。将棋は礼に始まり礼に終わるっていうらしいし、一応そういうのはきちんとしておくのが俺の流儀だ。
ちなみに、例によって俺と古泉の棋力にはそこそこ開きがある。といっても、俺の方の腕前も将棋同好会の連中には歯が立たないであろうレベルなので高が知れてはいるのだが。
というわけで、本来なら駒を何枚か落としてハンデを付けるべきなのだろうが、駒落ちのことはよく解らないし、なんとなく平手のまま指し続けている俺たちだったりする。
初手から十数手進み、先手古泉は四間飛車、後手の俺は居飛車、という、オーソドックスな振り飛車対居飛車の対抗型に落ち着いた。
(第一図) 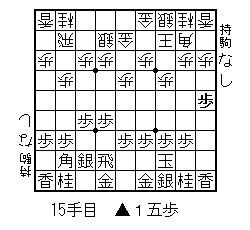
現局面は古泉の奴が悠長に端歩を伸ばしたところだ。誘いの隙、とかそういうことではなく、こいつは俺が逆の振り飛車側をもって指していたときの手順を辿っているに過ぎないのだ。
対する俺も、そのとき古泉がうろ覚えで指していたであろう急戦策を採ることに決めた。別に意地だとかそういうのでは全く無くて、むしろお手本を示してやっているような気分だ。
(第二図) 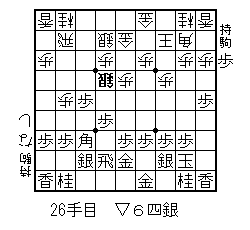
速攻に適した陣形を構築した俺は、古泉側の弱点とも言える角の頭を目標に攻撃を開始する。
先に一歩を突き捨ててから銀を繰り出す。『開戦は歩の突き捨てから』という格言もあったっけ。振り飛車側の銀が低い位置にいる場合は、先に銀を出たのでは歩で追い返されてしまうのだ。
「おや、これは以前に本で読んだことのある定跡形ですね。確かあの名前は――と。さて、僕の方はどう対処するのが最善なのでしょうね」
そんなこと、対局者の俺に訊かれてもな。
と言いつつも、古泉の記憶力は俺なんかよりよっぽどいいんだろう。定跡名は忘れていても手順は覚えていたらしい。
柔よく剛を制すの言葉通り、居飛車の攻めを呼び込んでからの、カウンター狙いの大捌きは、振り飛車側としての基本的なセオリー通りの手筋といえる。
(第三図) 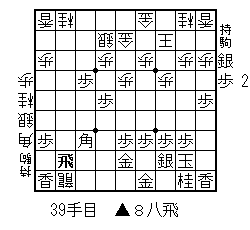
飛車交換確定の局面だ。こうして派手に双方の駒を交換し合った場合は、自陣が穴熊などならともかく、居飛車急戦側というのは玉の囲いが薄い、つまり俺の方が不利というのが定説だ。
だが、悲しいことにというべきか、これからが古泉の真骨頂なのだ。中盤から終盤にかけて失速、というのが毎回のパターンときたもんだ。適当に手心を加えていたのに、いつの間にやら逆転、という毎度の俺の勝利の方程式は、今回も既定事項のようである。
(第四図) 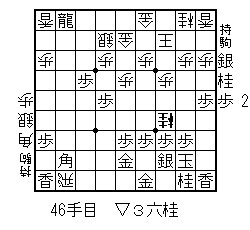
数手後、俺は古泉の角筋を止めるために打った桂馬を、わざと取られてしまう地点に跳ね出す。
「おっと、王手ですね。まあタダみたいですし、ありがたく頂いておきましょうか」
何の疑いも無く桂馬を手にする古泉。かといって残念ながら取らずに逃げるわけにもいかなかったりする。まあ、もう手遅れなわけだ。
(第五図) 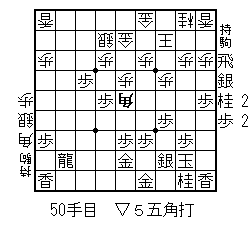
というわけで、さらに数手後の局面。王手龍取りが炸裂なのだった。
「へえ……。キョン、あんたにしてはやるじゃないの」
いつの間にか身を乗り出して盤面に見入っていたらしいハルヒは、俺に目が合った途端、バツが悪そうに一睨みすると、またパソコンディスプレイの陰にコソコソと隠れてしまった。黄色いリボンがピョコピョコと揺れているのが伺える。
それをみて、一瞬だが、こいつも可愛いところあるじゃないか、とか俺がうっかり思ってしまったりしたのは内緒の話にしておいてくれたまえ。俺とキミとの約束だぜ。
「これは一本取られてしまいましたね。ただし、飛車なら先程あなたの方も手放していらっしゃるので、都合、角一枚の損で済んでいるだけまだマシなのでしょう」
厳密に言うなら角桂交換ってところだな。まあ、これでも冷静に局面を分析すれば、互角ってところだと思う。今回は気持ちいい手も指せたし、負けてやってもいいかもな、とか余裕を見せる俺なのであった。
だが、そんな俺の情けをも裏切るのが古泉クオリティである。せっかくの攻め駒を妙に重ね打ちしたせいで、かえって動きが取れなくなってやがる。ハッキリ解るのは、とにかくこいつは『攻め』も『受け』も下手っぴだということ位だな。
ところで全然関係ない話で恐縮だが、某8○1ちゃん的腐女子判定に『攻め』の反対は『受け』というのがあったが、将棋関連でもその言い回しは多用されているので、出来れば無用な誤解は無しにして頂きたい。そこのところ、一つよろしく。
(第六図) 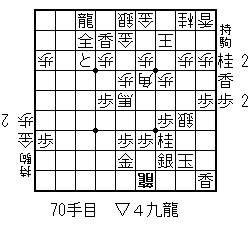
というわけで、俺が現ナマではなく駒の金の方を毟り取って古泉陣の美濃囲いを崩壊させた時点で、大勢は決していた。
長考する古泉。あのな、今更考えてる位ならここまで敗勢になる以前に策を講じろよ。挽回の利く局面はいくらでもあったと思うぞ。
「ふむ……、龍を取ると詰まされてしまいますし、ここは我慢の一手でしょうか」
と桂馬を自玉の真下に打つ。いや、だからそれ、全然受けになってないんだってば。
それから、俺は古泉玉を追いまわして、十五手かけて詰まし上げた。
(第七図) 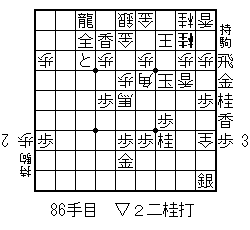
俺の持ち駒も歩が二枚残るだけの、ピッタリの手順だ。
ちなみに、これは後で長門から指摘を受けたときの話なのだが、
「もっと短い詰手順が存在した。金を打たずに先に馬を切って桂を取れば五手で詰み」
とのことだ。なるほど、全然気付かなかったね。俺もまだまだだな。谷川流光速の寄せ、のようにはいかないものだ。
あ、ところでこの『谷川流』というのは我が県出身の十七世永世名人の流儀を意味するのであって、やはり我が県出身の某ライトノベル作家の筆名とは全然関係ない。
「どうも、参りました。また僕の負けですね。完敗です」
古泉の投了に俺も一礼で応える。そういえば俺は通算何勝ぐらいしたんだろうな。とりあえず無敗神話は継続中だ。
「いやはや、あなたの指し手は大変参考になりますよ。――そうだ思い出しました。『山田定跡』というのでしたね、確か。この戦形も中々に奥が深いものですね」
その『山田定跡』という名称には俺も聞き覚えがあるのだが、その名の元となった山田さんとやらってどんな人なんだろうな。
俺の疑問に対し、有希ペディア、もとい、長門が
「山田道美九段。第十期棋聖戦にてタイトルを獲得。対振り飛車に関する急戦定跡を体系化した。また、現代のプロ棋界における研究会の礎となる人物。昭和四十五年六月十八日、現役A級在位のまま、突発性血小板減少性紫斑病にて逝去。享年三十六歳」
と詳細に至るまで解説してくれた。
そのとき、俺は朝比奈さんが青ざめた表情で、両手を組んで震えているのに気付いた。
「あ、あの……長門さん。そのお方の、ご病名って――」
「特発性血小板減少性紫斑病。自己の抗体により脾臓や肝臓などで血小板が破壊され、結果的に全血液中の血小板減少を招く疾患。詳しい原因は不明。症状の重さによっては頭蓋内部での出血の可能性あり。早急に治療が必要」
「やっぱり――そう……なんですね」
長門の舌を噛みそうな位のややこしい言葉だらけの説明に、朝比奈さんは力なく俯いてしまった。あの、どうかしましたか、朝比奈さん?
「い、いいえ、ごめんなさい、キョンくん。ただ、あたしの知ってる人も、同じ病名だったから、それを思い出しちゃって、わたし……」
ええ?ひょっとして、その方はまさか――
「あ、違いますよ、うん。その人は今でも元気です。わたしも、直接面識があったり、とかじゃないんですけど」
そういって、朝比奈さんは、いつもと少し違う声のトーンで、静かに俺に語り始めた。
「その人は、あ、女性の方なんですけど、中学生のときにその病気にかかったんそうなんです」
いつの間にか、その場にいた全員が、朝比奈さんの話に集中していた。
「さいわい一命は取りとめたものの、退院の見込みもなかったりとか、高校の進学もムリそうで、お薬も、ステロイド剤っていうんですか、すごくきつくて、そのせいで顔とか身体がパンパンに腫れちゃったんだそうです」
「薬の副作用ですか。僕も聞いたことがあります。若い女性の方にはさぞかし嫌なことだろうと察せられますね」
「ムーン・フェイス。ステロイド剤の副作用により、体重増加と共に、顔が満月のように丸く膨らむ症状。投薬減量と共に症状は治まる。ステロイド剤投薬における、高確率で発症する副作用例として知られている」
ステロイド、とかいうのは俺も聞いたことがあるな。何かあまりいい話じゃなかった気がするんだが。そんな薬に頼らざるを得ないぐらいの病気ということか。
「彼女、心身ともに、とってもつらかったと思います。退院してからも、容姿のことでからかわれたりとか。――でも、ほとんどの友達は体を気遣いながらも、以前と同じように接してくれたんだそうです」
それを聞いて、俺はどことなく救われた気分になった。
「その人は、もうお薬も抜けて、今もお仕事を通じて、たくさんの人に夢や勇気を与え続けてくれています。わたしにも。――彼女のおかげで今のわたしがある、今ここに、こうしていられるんだって、わたし、ずっとずっと感謝してるんですよ」
と涙目になりながらも、女神のように優しげな微笑を浮かべる朝比奈さんだった。
いやはや、朝比奈さんにここまで敬愛されているなんて、さぞかし素敵な女性なんだろうね、きっと。流石は、と言うか、モノが違うって言うべきだろうか。
少々しんみりとした空気の中、夕日の赤が辺りを染める。気付けばもう下校時刻も近い。
朝比奈さんの話が終わった後、俺たちはそれとなく帰宅の準備に入っていた。古泉と共に廊下に出た俺は、そういえばハルヒの奴がずっとだんまりだったな、とか思い返していたのだった。
その後、帰り道の下り坂を、何故かハルヒと二人で肩を並べて歩いている俺なのだった。ちなみに朝比奈さんは鶴屋さんと待ち合わせとのこと、古泉は野暮用だとか、長門は――いつの間にか姿を消していたな。
ふと、いつに無く真面目そうな声で隣のハルヒが話しかけてきた。深刻そうな様子は、昼間の上機嫌もどこへ行ってしまったのやらといった感じだ。
「ねえ、キョン。――あんた、もしも自分があと一日しか生きられないってことが解ったら、どうするのかしら?」
いきなり縁起でもないこと訊いてくるなよな。……さて、それは急に『今から二十四時間後』って宣告されるわけか。心の準備とかそういうのも全く無理だし、大いに取り乱すことだろうよ。
「そうよね。でも……ありえない話じゃないわ。急にみくるちゃんとかが言ってたような病気になっちゃうかもしれないし、そうでなくても、交通事故だとか、足滑らせて階段から落っこちたりとか――」
そう言われて初めて理解した。こいつは十二月の――俺が入院していた(ということになっている)あの三日間のことを思い出したのだろう。
「あたし自身のことなら、健康に気を配ったりとか、危ないところには近寄らないようにだとか、努力で何とかできるところもあるじゃない。……でも」
一つ大きく深呼吸するようなハルヒ。
「あたしじゃなくて、――有希やみくるちゃんや古泉くん、それに……キョン、あんたも――あたしに自分の身体のこと隠してたりとか、あたしの見てないところで事故に遭ったりするかも知れないじゃないの!」
そう叫んで、足を止めるハルヒ。つられて俺も足に急ブレーキだ。
「時々考えるの。あたしはSOS団を作って、こうしてみんなと一緒に楽しくやってきてるけど、それもいつか終わってしまうんじゃないか、いつかはまた――独りぼっちになっちゃうんじゃないだろうか、って」
そう言ったきり、唇を噛んで俯いてしまうハルヒだった。
しばしの沈黙。
やれやれ、こいつ自分の言葉に自分自身で怯えてやがるな。
このまま放っておく訳にはいかないな。ハルヒの奴がどんどん物事を悪い方に悪い方に考えてしまえば、それがいつ現実のものともなりかねないのだ。
もしも、『キョンの奴が風邪をこじらせて倒れちゃったら』とか思い込まれたら、俺は最低でも肺炎とかでぶっ倒れる羽目に遭わされるに違いない。そいつは御免被りたいね。
俺は、右手をハルヒの頭の上にそっと置き、こちらを向くように顔を起こさせた。
「え、キョン?」
「なあ、ハルヒ。お前に頼みたいことがあるんだが、ちょっと聞いてくれないか?」
「う――な、なによ?」
「もし、お前が朝比奈さんや長門や古泉、ついでに――俺と――これからもずっと一緒に居たいと思うなら」
「――思うなら?」
「簡単なことだ。――そのまま、ずっとそう思い続けててくれ」
「――はあ?意味わかんないわよ。なによそれ。そんなのあんたに言われるまでのことじゃ……ないんだから」
突然、我に返ったハルヒは俺の手を振りほどき、頬を赤くして目を逸らしてしまった。
「やれやれ、それじゃついでにもう一ついいか?」
「何なのよ、もう。キョンのクセにいちいち注文が多いわね」
そっぽを向いたまま文句を言うハルヒ。
「昼間も言ったと思うが、俺はちょっと風邪気味でな。お前の持論からすれば、気合とやらが足りないんだろうな。だから、いつかみたいに、少し……分けてもらっていいか?ハルヒのエネルギーを、その、視線に込めて」
コンピ研との一戦の時のアレを思い出した俺がそう告げると、ハルヒは一瞬背筋をピクリとさせた。
「い、今はダメ……ダメよ。――そ、そうね、明日よ明日。その時になってもまだあんたが調子悪いんだったら、ちょっとは考えてあげないこともないわよ」
そう言って俺を放置したままハルヒの奴は一人駆けて行ってしまった。
何なんだろうな、全く。まあ、さっきよりは元気になったんだろうかね。しかしあいつ、さっきから顔が赤かったけど、ひょっとして俺が風邪をうつしてしまったんだろうか?明日はちゃんと出てこられるんだろうな。
ハルヒの遠ざかる背中を見送りながら、俺は明日も、それから先もずっと、宇宙人未来人超能力者にトンデモパワーの持ち主と一緒に、ささやかな日常を過ごせたらいいな、なんてことを肩を竦めて考えていたのだった。
そうさ、非日常の中のささやかな日常ってのが、今の俺の何物にも替え難い宝物なんだからな。
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ