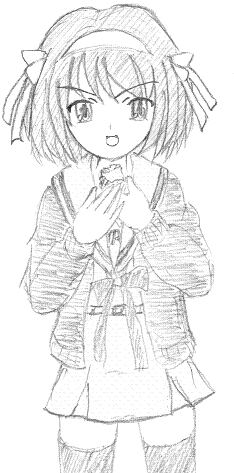概要 
| 作品名 | 作者 | 発表日 | 保管日 |
| Sweet Sweet Hamming | 81-29氏 | 08/02/20 | 08/02/21 |
ド○えもんの『メロディーガス』ネタのつもりが全然わけの解らんのに化けたので
全体的にまとまり無いっつーか意味不明なのは勘弁してください orz
作品 
何だ、この空気は?
ある日の放課後、文芸部室にしてSOS団のアジトである旧館三階の一室のドアを開けた俺は、思わず声に出掛かった冒頭の一言をやっとのことで飲み込んだ。
以前に古泉が、この部室はとっくに異空間化している、と言っていたはずだが、今の俺は正に異空間の真っ只中にいるような心境だ。
ただ、それがまたハルヒの仕業か、と言われると、ちょいとばかり微妙なところではある。
確かにここ最近のあいつは妙に機嫌が良かったし、何か不満を溜め込んだ挙句に暴発させるような気配も無ければ、俺たちの想像の斜め上を衛星軌道上程の高度で突っ切るような奇天烈なイベントを企てている様子にも見えなかった。
ただ、その、妙に上機嫌だ、というのが今のこの雰囲気の一因でもあるわけで……、というか、ハルヒが一因、ということはその原因要素がまだ他にも存在するわけなのだが――。
「ふん♪ふん♪ふふふふっ♪ふっ♪ふふんふん♪ふん♪ふん♪ふふふふっ♪ふっ♪ふふんふん♪」
麗しの美の女神にして、癒しの上級天使である我らが朝比奈さんは、例によってメイド姿で温度計を片手にヤカンとにらめっこなのだが、
「ちゃ~ん♪ちゃ~ん♪ちゃ~ん♪ちゃ~ん♪ぱやっ♪ぱやっ♪ぱやっ♪ぱぱぱぱっぱっ♪~~」
いつもと違うのは、朝比奈さんがご覧の通り鼻歌を口ずさんでいることなのだ。気のせいか、『それにしても、このメイドさん、ノリノリである』なんてナレーションがどこからともなく聞こえてくるんじゃないかって思えてしまう。
しかし、よりにもよって、この歌とはねえ。確か朝比奈さんはハルヒに無理矢理歌わされたこの曲がトラウマになっていたような気がしたのだが、今ではもう平気なのだろうか?ちょっと意外である。
更に意外、というか、普段通りでないのは長門であった。
まず、読書をしていない。何の気紛れかは俺には解りようもないのだが、ノートパソコンに向かって、軽快にタイピングのリズムを奏でている。それだけならまだなんてことは無いと思えるのだが、
「……ち~ち~ん、ぶいぶい♪……」
なんと、あの長門まで鼻歌である。普段のこいつを知るものならきっと信じられないことであろう。っていうか、この俺が一番信じられん。
しかし、何か聞いたことのあるメロディだな、とか考えていた俺だったが、ノートパソコン越しの長門を見てふと思い出した。確か、コンピ研のあのゲームのBGMじゃないか、これ。
なるほど、長門はきっとコンピ研がらみの作業を何か頼まれたとか、そういう類のことなんだろうな。これで謎は一つ解けたぜ。
とは言え、依然として最大の謎は残っているのだ。みなさんご存知の通り、ハルヒである。
鼻歌とも歌詞とも判断が付かない歌声らしきものを口ずさみながら、パソコンの操作をしたり、手元に開いたノートらしきものに書き込んだり、と作業に熱中している様は、まるで何かに取り憑かれたかのようですらある。
しかも、ときたま何かに頷くように頭を振るとか、口元に拳を当てて小さく笑ったりとか、一体何だこれは?
「うふふ」
そうそう、そんな感じの笑い方、って古泉!
「おや、どうかしましたか」
どうもこうもない、今のお前の一撃で俺の周りに展開されていたフルーティな靄は消し飛んじまったじゃないか。どうしてくれる。
「それは申し訳ありませんでした。お詫びに僕も何か歌でも……」
断固遠慮する。
「そうですか。それはではしかたありませんね」
何そんなにしょげてやがる。まあ、それは置いておいて、古泉。三人とも妙な按配だが、一体何かあったのか?
「さて、それは僕にも解りかねますが……」
そう言って古泉は両手を広げたいつものポーズで微笑んだ。
まあいいか。何にせよ、宇宙人未来人超能力者の誰もが心配している様子も無いし、険悪とかそういうのとは真逆な雰囲気だからな。奇妙なことが起こったら起こったで、そのときになってから考えるしかないわけだし。
俺は朝比奈さんに淹れていただいたお茶を一口啜ると、暫くの間ぼんやりとハルヒの様子を見ていた。
しかし、何だろう、この感じは?気のせいか、目蓋がだんだん重くなってくる。さっきまでは全然眠くなかったのに、これじゃあまるで子守唄…………。
どのくらい時間が経ったのだろうか。
気が付くと、外はもう真っ暗だった。
「キョン…………起きた?」
目の前に、ハルヒがいる。
「みんなならとっくに帰っちゃったわよ。あんた中々起きないし、仕方ないからあたしが残っててあげたの。――もう、みっともないわね、涎垂らしちゃって…………ほら」
ハルヒはそういったかと思うと、素早く自分のハンカチを取り出して、俺の口元を拭った。
「ほんと、キョンたら、まるで子供みたいね。さっき寝てるときの顔も、なんかちょっと可愛かったかも……」
ガキで悪かったな。しかし、参ったな、こんなに遅くなっちまうなんて。
「こら、キョン。グズグズしてないで、とっとと帰りましょう」
何だ、急に慌てて。おい、ハルヒ。ちょっと待ってくれ。
「うるさい!いいから早く来なさいよ!」
解ったから、そう急かすな。
帰り道、遅くまで付き合せてしまったお詫びに、俺はハルヒに何か食い物でも奢るハメになってしまった。やれやれ。
コンビニかどこかで適当にお茶を濁そうと思っていたのだが、丁度目の前に石焼き芋の屋台が通りかかったのが俺の不運だった。
「へえ、焼き芋ねえ。いいわ、キョン。今日のところはこれで勘弁してあげるから」
そう言ってハルヒは屋台のオヤジさんに一番大きいのを選んでもらっていた。何か、全然勘弁されてない気がするのは何故だろうな。
と、すっかり懐事情の寒くなった俺の目の前に、熱々の芋が半分差し出された。
「――ほら、キョンの分、あげる」
なんだよ。お前は半分で良かったのか?だったら、別に俺は食わなくてもいいから、もっと小さいのを選べば済んだだろうに。
「いいの。だって…………あたし一人で食べても、なんかつまんないじゃないのよ」
そう言ってハルヒは、自分の半分を、少しずつ齧り取るように食べていた。いつもみたいに大口で一気食い、なんてのはさすがに火傷しそうで無理なのだろう。なんか、少しばかり微笑ましい光景だ。
「なによ、あんた。こっちをジロジロ見てニタニタするの、止しなさい」
はいはい。俺は頷いて自分のを一口――熱っ!確かにこれを丸呑みは止めた方が無難だな。
「ねえ、キョン。そういえば、さっきの屋台にも『十三里』って書いてあったわね」
ああ、『九里四里美味い』って語呂合わせだかなんか知らないけど、昔からそう言われるみたいだな。
「何か納得がいかないわ。あたし……栗よりも焼き芋の方が断然美味しいって思ってるから、何で当たり前のこと言ってんの、とか疑問に思っちゃうわけなのよ」
そうか?栗は芋より高級、ってイメージが俺にはあるんだがな。
「大体、食べるの面倒くさいじゃないの。そもそも棘だらけのイガの中に、あんなに硬い皮があるなんて、なに様のつもりよ?」
そういえば、ハルヒは似たような理由でカニも好きじゃないって言ってたな。でも、それは結構勿体無くないか?
「別に。そんなにイライラしてまで無理に食べることないじゃない」
解った解った。じゃあ、今度、俺が栗でもカニでも剥いてやるから、それならお前も嫌じゃないだろ?
「えっ?…………あ、うん。――――お願い」
やれやれ。しかし、そんな面倒くさがってちゃ、将来自分の子供に食べさせるときにどうするつもりだ?
「いいの。あたしはそーいうのは全部キョンに任せるから」
おい待て。まさかハルヒ。お前ついでに自分の分まで俺に剥かせようって魂胆じゃないだろうな?
「当たり前じゃないの!――なによ、キョン。あんた、さっきから全然食べてないじゃない。いらないんなら、あたしが貰うわよ」
そう言うとハルヒは俺の手から芋を奪い、平然とパクつき始めるのだった。
やれやれ、そんなに沢山食べて、身体からほとばしるガスに悩まされても俺は責任取れんからな。
「バカキョン!……あんたって、ほんとにデリカシー無いんだから、もう」
夕闇の中、冷たい風は容赦なく吹き荒んでいたのだが、俺は不思議と寒さは感じずに、真っ赤な顔で膨れているハルヒを見て歩き続けていたのだった。――――自分でも気付かない内に、鼻歌を口ずさみながら。
「ふえぇ、涼宮さんとキョンくんのお二人とも、古泉くんの誘導もないのに熱々なんです!(><;)」
「全くですね。まるで将来のお二方の会話そのものが聞こえてきたのかと思ってしまいました」
「……『妬芋』、あなたも食べる?」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ