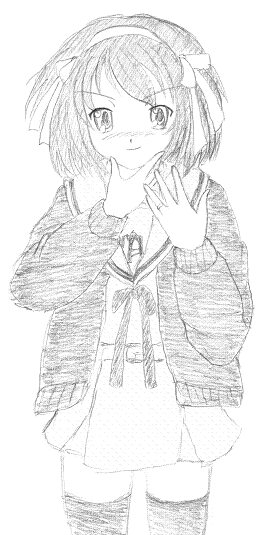概要 
| 作品名 | 作者 | 発表日 | 保管日 |
| Ring Sparkling | 82-12氏 | 08/02/26 | 08/02/26 |
作品 
暑いのと寒いのでは、どちらがが平気か?などという質問には、俺はこう答えることにしている。『寒いときは厚着すればなんとか耐えられるけど、暑いのは裸になってもそれ以上脱ぎようがない、よって寒い方が平気だ』とね。
ただし、この時期、着膨れしているのと、妙に乾燥した空気のせいで、少々厄介な問題に悩まされている方も多いのではないかと思う。
今回は、まあ、そういったトラブルにまつわる話なのだ。
ここ数日、理由はよく解らんのだが、ハルヒの機嫌が良好だったのはこの前も少しだけ話した通りだ。
昨日もちょっとした買い物で部室に戻るのが遅くなったにもかかわらず、ハルヒは朝比奈さんや長門と仲良さそうに身を寄せ合って楽しそうにしていた。――そういえば古泉は三人に遠慮するように廊下で待機していたが、何故そうしていたのかは俺には解らん。
「あっ、キョンくん。昨日はありがとうございました」
我らが上級天使のメイド姿朝比奈さんが、昨日の買い物の件だろうか、ぺこり、と可愛らしくお辞儀をしてくださったので、俺の表情も自然と緩む。
「いえいえ、あんなことでよければ、何でも俺に頼んでくださいよ」
「そんな、悪いですよ~。……あれっ、そういえば、わたしまだカセットボンベの代金をキョンくんに立て替えてもらったままですよね。今すぐ返しますから」
そういって朝比奈さんは自分の財布を取り出そうとしたのだが、
「ちょっと、みくるちゃん。あなたが自腹を切ることなんてないわよ」
ここぞとばかりに、ハルヒが話に割り込んできた。また、ややこしいことにならなければ良いのだが。
「えっ、でも、涼宮さん……こういうのは、ちゃんとしておいた方が、いいんじゃないでしょうか?」
「ええ、あなたの言う通りだわ。ここはちゃんと、部費から出しましょうよ。みくるちゃんがその格好でお茶を淹れてくれるのは、誰が何と言おうと、立派にSOS団の活動の一つといっても過言ではないわ!」
色々と突っ込みどころの多いセリフだな。
まあ、よくよく考えてみれば『未来人がコスプレ姿でお茶を給仕してくれる』なんてのは十分不思議なことではあるのだろう。慣れというものは恐ろしいものだ。
それに、文芸部唯一の部員である長門が、部費の使途に関してハルヒに異を唱えるはずも無い。
そもそも、ここで俺が余計なことをハルヒに言って、結果的に代金を受け取れなくなる、なんて可能性もある。ていうか、俺にちゃんと代金を支払おうとしていること自体が奇跡的なのかも知れん。
というわけで、ハルヒに促されて、長門は鞄の中からごそごそと封筒らしきものを取り出すと、朝比奈さんに手渡した。って、長門、お前いつも部費を持ち歩いてるのか?まあ、ある意味それが一番安全なんだろうが。
「――あれれ?小銭が全然ありませんけど――あの、長門さん、細かいのって、ないんですか?」
「ない」
即答する長門。朝比奈さんは困ったような表情だ。
「ああ、それなら、俺の手元に昨日のお釣りがそっくりそのまま残ってますから。朝比奈さん、千円札一枚ぐらいはありますよね?」
「あっ、ええ、ありますよ」
俺はポケットから昨日店で受け取ったままの小銭を取り出すと、朝比奈さんの小さな手に乗せた――その瞬間。
バチッ!
「うおぁっ!」
「ふえっ!」
俺の指と、朝比奈さんの手の間で何かが弾けた。油断していたせいか、マジでビビったぜ。
「おや、静電気ですか。確かにこの時期は空気も乾燥しているし、衣服も帯電しやすいものを着用することが多いでしょうから、何かと大変ですね」
あえて触れなかったが、さっきからずっといた古泉にようやく解説役が巡ってきたのだった。しかし、他人事みたいな言い方しやがって、全く。
「そうですね、個人差というものもあるようです。幸い、今のところ僕は帯電体質ではないようで一安心、といったところです」
両手を広げて余裕のスマイル古泉だ。
「ふ、ふえぇ~」
すっかり涙目で怯えた様子の朝比奈さんを気遣うように、ハルヒが声を掛ける。
「ちょっと、みくるちゃん、大丈夫?」
「ぐすっ、なんだか、キョンくんから、ビビビってきて…………ビックリしちゃいましたぁ」
朝比奈さんがべそをかきながら答えたそのとき、ハルヒの目の色がハッキリと変わるのが俺には見て取れた。何故だかしらんが、嫌な予感がする。
「ねえ、キョン。あんた、電気ウナギかピ○チューの生まれ変わりなんじゃないの?それとも、あたしたちには内緒にしてたけど、実は改造人間でした、なんてことはないかしら?スト□ンガーっ、とか」
すまん、仮○ライダーなら他の職人に振ってくれ。ていうか、相当古いネタだと、年齢がバレるぞ。
「ちょっと、あんた。試しにあたしにもやってみなさいよ、その電撃を!」
まるでポ○モン扱いである。やれやれ。
「いいから早く!ほら、キョン。百万ボルト攻撃よ!」
ハルヒの差し出す手に、俺は指先を伸ばす。
「――なによ、全然ビビビってこないじゃないの!」
そりゃそうだ、さっきので俺の身体からは、溜まってた静電気が放電してしまったろうからな。
ハルヒは、自分の鞄から下敷きを取り出して、俺の髪に擦り付けたりとか、まるで小学生並みにふざけていたりしたのだが、何故か、いくら俺がハルヒに触れても、もう放電現象は発生しなかったのだった。
「つまんないわね。キョンって、ほんとに役立たずなんだから、もう!」
気付けば、ここ数日の上機嫌も終了となった様子のハルヒである。って、ひょっとして、俺のせいなのか?
結局、その日は早々に活動終了。
帰り道、色々と宥めてみたものの、その日ハルヒはついに笑顔を取り戻すことはなかった。
翌日のこと。
朝から俺は静電気の猛攻に悩まされることとなった。髪の毛は逆立つわ、触れるもの全てがスパークするわ、散々である。
まさか、ハルヒの仕業なのか?――いや、いくらなんでもな。
だが、教室に着いた俺を待っていたのは、やはりどこと無く髪が逆立っているようなハルヒであった。
「ねえ、キョン。面白いわよ、これ。なんだか、触るものがみんな、ビリビリくるの。一体どうしちゃったんだろう?」
そう言ってハルヒは俺に手を差し伸べてきた。って勘弁してくれ、俺は今朝から――、
「……あらっ?」
拍子抜けしたようなハルヒ。それもそのはず、ハルヒが俺に触れても、何も起こらなかったのだ。
「おかしいわね?――――っと、やっぱりよね。その辺のものならちゃんとビリビリくるのに」
辺りのものに手を伸ばしては、電撃を確認している様子のハルヒ。って、放電しきってしまう気配がない。どういうことなんだ、これは?体内で発電でもしているかのようではないか。
まるでラ○ちゃんだな、おい。まあ、中の人の苗字がが平野ってのは共通点かも知れんが、それがどうした、って言われても俺は正直困る。
そして俺は、自分のの身にも同じようなことが起こっていることを思い知らされたのだ。触れるもの全てから受ける電気ショック。これは一体何の拷問なのだろう?
しかも、よりによって、触れても平気な唯一の存在がハルヒだなんて。
当初は面白がっていた様子のハルヒも、そのうち飽きたのだろうか、不快指数MAXといった表情でこう言った。
「もう、何でキョンだけはビリビリってしないのよ?うんざりするわ!」
俺としては触れるもの全て感電するなんて方がよっぽどうんざりなんだがな。
誰か、何とかしてくれ。
「ちょっと、キョン。何とかしなさいよ、これ」
その日の放課後、全員集合の部室内で、ハルヒがパソコンの前で喚いている。って、まさか、お前、その身体で触っちまったのか?
「さっきからスイッチ入れても、ウンともスンとも言わないのよ。どういうこと?」
どうもこうもない。ハルヒが触ったせいで壊れちまったんだろう。
「うそ、何で?――――あっ!」
ハルヒもどうやら、コンピュータなどの精密電子機器が静電気に弱いことに思い至ったらしい。
「ゴメン…………あたし」
すっかりしょげてしまったハルヒは、自分の鞄を手に、呆然と見守る俺たちを背に帰ってしまった。
携帯電話の着信音。――古泉のか。
「……申し訳ありません。例のアレが発生してしまったようですので、僕はもう行かなければなりません。あとのことはよろしくお願いします」
そう言い置いて、古泉も部室を退去した。
「ごめんなさい、キョンくん。……きっと、わたしのせいで、また涼宮さんは……」
そんな、朝比奈さんが悪いわけ、ないじゃないですか。
「でも――わたしがキョンくんと感電しなければ、涼宮さんもこんなこと、思い付かなかったでしょうし」
だから、ただの自然現象ですってば。気にすることなんて全然ありませんって。
しかし困ったな。というか、そもそもハルヒと俺の身に何が起こってるんだ、長門?
「涼宮ハルヒは自分自身とあなたの電位を周囲の環境から常にシフトさせ続けている。あなたと彼女が触れても何も起こらないのは、電位が同じため」
よく解らんが、なんとなく厄介事だとは想像できる。って、今朝から今までのことを省みれば、それも当然か。
「今からあなたの身体に対策を施す。……あなたの手を」
長門に言われるまま俺は手を出そうとして、ふと思った。
「なあ、俺が今、長門に触ってもやっぱり放電現象は起きるのか?」
「問題ない。すでにわたしの電位をあなたに合わせている。……指、出して」
指、って人差し指でいいのか、って訊ねる間もなく、長門は俺の手を取ると、俺の人差し指を自分の口で銜えた。
「!」
朝比奈さんが真っ赤な顔で俺と長門の方を見ている。そうだな、朝比奈さんも長門からこれを、『ナノマシンの注入』とやらをされたことがあったっけ。
「…………もう大丈夫」
結構な時間の沈黙の後、俺の指は解放された。試しに、その辺のものに触れてみるが、不快なスパークを感じることはもう無かった。
「残念ながら、わたしから涼宮ハルヒに対しては、有効な対処を施すことができない。……全ては、あなた次第」
やれやれ、またこのパターンかよ。
今となっちゃ、もうどーにでもなれって心境だな。気休めでもなんでもいいから、ちょっとはマシな知らせとかはないのか?
「パソコンは故障していない。……セーフティを解除」
長門の言葉と共に、団長席のパソコンが起動を始めた。なるほど、こうなることを見越して、予め対策しておいてくれたわけだな、長門。
確認するまでも無さそうだが、俺はパソコンが正常に動作しているらしいことを一通り調べ、ついでにネットで検索して、静電気対策グッズなどを調べたりしたのだった。
仕方がない、今日は帰りに、ちょっと遠回りしてみるか。
翌朝。
教室では、ハルヒが頬杖を突いて窓の外を見ていた。
「おい、ハルヒ」
「……なに?」
俺はハルヒの目の前に、昨日買ってきたばかりのブツを放り出した。
「やるよ」
「へっ?……ちょっと、キョン、何なのよ、これは?」
「『静電気防止リング』って奴だ。まあ、数百円程度の安物だし、効果あるかどうかはわからんけど、気休めぐらいにはなるだろ」
本当はもう少しまともなブレスレットみたいなのを買いたかったんだが、なにせ先立つものがな――ハルヒには口が裂けても言えんが。
「キョン…………ありがと」
やけに神妙、というか、普通に礼を述べたハルヒである。いつもこのぐらい素直なら、何も言うことはないんだがな。
早速開封して、説明書を眺めながら、
「へえ――指に嵌めるだけでいいわけね」
と言って、何故かそのリングを左の薬指に嵌めた。
「なあ、ハルヒ。そういうのって、物によく触る右手の人差し指とかに着けるもんじゃないのか?」
「いいの!どこに着けたって構わないじゃない。あたしの勝手よ!」
ハルヒはそう言いながらも、先程までの不景気な表情はすっかり霧散してしまったようだ。俺もひとまず安心というところかな。
数百円のリングの効果かどうかは果たして解らないが、それ以来俺とハルヒは静電気に悩まされることもなくなった。
だが、クラスのみんなの視線が妙な按配に変化したような気もするのだが、なあ、谷口。お前、何か理由を知らないか?
「うるせー!!オメェらなんか、さっさと電撃入籍でもして幸せになっちまえ」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ