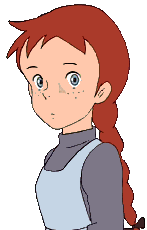16."A Queen's Girl"
それからの三週間、グリーン・ゲイブルズの日々は忙しく過ぎていった。アンの入学の準備でてんてこまいだった。マリラとマシュウはアンに必要なすべてのものを用意してやろうとしていた。アンはそんな二人にとても感謝していた。ある夜、マリラが腕いっぱいに優しげな色合いのペールグリーンの布地をかかえて、アンの部屋へあがってきた。
「この布地であんたのドレスを作るよ。きれいで、軽い印象のやつをね。――あんたはもうたくさんいいドレスを持ってるから、いらないかとも思ったけどね。でもまあ、たとえば夜になって町に出かけるとするだろう。するとパーティーかなんかに誘われるだろうね。あんたはどこでもひっぱりだこさ。そのときに、こういう改まったものが欲しいんじゃないかと思ってね。ジェーンもルビーもジェシー・パイも、"イブニングドレス"なんての持ってるってあんた言っただろう。あたしはね、あんたが彼女たちにおくれをとるべきだなんて、ちっとも思わないんだからね」
「マリラ、これすごく可愛いわ」と、アン。「ほんとうにありがとう。こんなによくしてくれて、なんだか悪いみたい――ねえ毎日どんどん、ここを離れるのが辛くなるのよ」
ドレスが縫いあがった日の夜、アンは嬉々としてそれを着て、台所にマシュウとマリラを座らせて自作の詩の朗読を聞かせた。マリラは朗読を聴きながら、目の前の若くて愛らしい女性を見つめた。アンは輝いているようだ、生命かなにか、そんなものでまぶしいくらいだ、と思った。マリラは思い出した。グリーン・ゲイブルズにやってきた日、この子はひどくおびえていて、瞳は涙ぐんでいた。傷つけられた小さなかよわい心がみえるようだった。思い出が、彼女の目から涙をあふれださせた。
「なんてこと。あたしの詩がマリラを泣かせちゃうなんて」と、アンは言うと、椅子の上からマリラにかがみこみ、頬にキスをした。「ふむ、でもこれって大勝利よね」
「詩で泣いたんじゃないよ」と、マリラは弁解した。「昔のことを思い出したんだ。あんたが昔、とても小さな女の子だったんだって、考えずにはいられなかったんだよ。あたしはあんたがずっと子供のままでいてくれたらいいって思ったんだ。心底願ったんだよ。でもあんたは大きくなって、遠くへ行っちまう――こんなドレスが似合うくらいに、背が伸びたんだね――まるで最初から、あんたがいなかったみたいになるんじゃないかと思うと、怖くなって、さみしさで胸がいっぱいになったんだ」
「マリラ」アンはマリラのしわのできた顔を両手でかかえて、目の奥をのぞきこむようにじっと見つめた。「あたしは何も変わってないわ。ほんとうのあたし自身はちっとも変わらず、ずっと同じままなのよ。背が高くなっても、心の中は、いつでもあなたの小さなアンのままなの。あなたとマシュウと、すてきなグリーンゲイブルズをずっと、毎日、以前にもまして愛しつづける、あなたのアンなのよ」
マリラは少女に腕を回し、抱きしめた。小さなアンは腕の中にあり、心をやさしく癒してくれた。それでマリラは、この子を絶対に手放したくない、なんて思ってしまった。マシュウは目に涙をたたえて二人を見ていた。椅子から腰を上げると、外に出て、雲ひとつない夏の星明りの下、農場をつっきって門のところまで歩いていった。
「あの子はほんとうにまっすぐに育ってくれた。わしはそう思うんだ」と、空に向かって話しかけた。「あの子は頭が良く、機転がきいて、とても可愛いし、愛嬌があって、そしてもっとも大事なことに、みんなから愛されてる。あの子は神様からの贈り物だった。ああ、こんなに幸運な間違いは聞いたことがない、スペンサー夫人が――これが幸運だって? わしには信じられない。間違いでも、幸運でもない。これは運命だったんだ。神様が、わしらがあの子を必要としてると知って、それであの子をよこしてくださったんだって、わしは確かに信じてるんだ」
クイーン学院のアン
Last-modified: 2010-07-19 (月) 12:19:09