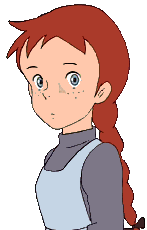19."The Bend in the Road"
それから数日経ったある日の午後、マリラは農場で訪問者をむかえた。アンが観察しているのも知らず、長い時間ずっと話をしていた。ゆっくりと彼女が帰ってくると、アンは質問をあびせた。
「あのお客さんどなた? どんな用事だったの?」
窓の近くの椅子に腰を下ろすと、マリラはアンを見据えた。急に両目から涙が流れはじめた。震える声でつっかえながら話しはじめた。
「この農場を買う相談だよ。いくらで売るのかあたしに聞いたんだよ」
「グリーンゲイブルズを買う? いくらで、ですって!」アンは飛び上がって驚いた。自分の耳が信じられなかった。「もちろんあなたはそんなことしないわよね。ここを売っちゃったりしないわよね?」
「もちろんそうしたくはないよ。でもわからない。それ以外に方法がないんだ――いろいろ考えてみたんだよ。それこそここを売る以外の全部のやり方について検討したんだ。ああもし、あたしの目がちゃんとしていてくれたら、なんだってできたろう。ずっとここにいて、自分のことはなんでもやりくりできたさ。新しく作男を雇ったりしてね。
でもそうはできない。お医者様は、あたしの目が、ゆくゆくは失明するだろうと言った。そうなったら何もできなくなっちまう。今までのようにはなにひとつね。あたしはここを出たくない。ここを売って、他の場所で、他の景色を見ながら暮らすなんて、一度だって考えたことなかった。ここはあたしの家なんだ。ほかのどこでもなくね。でも、仕方ないんだ――時間が経つにつれ、あらゆる物事が、どんどんひどくなっていく。
あんたが奨学金をとってくれて良かったって思うよ。アン、これからはお休みの間も、ここには帰ってこれなくなっちまう。ほんとうにすまない。でもあんたはもう大人で、自分の面倒は自分で見れるからね」
マリラは疲れたように言い終わると、両手で顔を覆い、さめざめと泣きはじめた。
「グリーン・ゲイブルズを売る必要なんてないのよ」とアンは言った。
「売らずにすめばどんなにいいだろうってあたしも思うよ。でもアン、考えてもみておくれ。目の見えないあたしが、ここでひとりきりで住めると思うのかい?」
「ひとりきりで住むことなんてないの。あたしが一緒なんだもの。あたしレドモンド大学に行かないって決めたの」
「大学に行かないだって!」マリラは驚いて、顔から手を離し、アンを見つめた。
「あら聞こえなかった?」と、アン。「そうよ、大学には行かないの。奨学金を受け取るのもやめるわ。あなたが眼医者さんから帰ってきた日の夜、そう決めたの――あなたが困っているのに、あたしがあなたをおいてどこかへ行っちゃうなんて、ほんとに思ってたの? マリラ、全部あたしにまかせてほしいの。
驚いた顔してるわね。これでもいろいろ考えたのよ。まあ、聞いてちょうだい。
まず、来年になったら、バーリーさんが畑を借りたいって言ってるわ。貸してしまえば世話なしだし、それだけじゃなくて、あたしは教師になるの。アヴォンリーの学校のね――カーモディの学校に願書を出しに行ったとき、ギルバート・ブライスがしてくれたことを聞いたわ。彼はあたしのために、アヴォンリーでの教師の口をあきらめて、ゆずってくれたのよ。あなたとあたしが一緒に暮らせるようにってね。
あれ、これでぜんぶ話しちゃったわ。ねえあたしはここで、あなたに本を読んであげるのよ。これからもずっと元気づけてあげるの。一緒にいたら、ほんとうに、すごく幸せになれると思わない? あなたと、あたしで」
アンがそう言うのを、マリラは夢を見ているような気持ちで聞いていた。
「そりゃあ、あんたがここにいてくれたらどんなにいいだろう。だけどあんたに自分の目標をあきらめさせることはできない。そんなおそろしいこと、神様だって許しはしないよ」
「グリーン・ゲイブルズを失うことより悪いことなんてないわ――それ以上にあたしを傷つけることなんて、この世にひとつもないのよ。この懐かしい、おだやかな土地を、ずっとこのままにしておきたいの。あたしたちそうしなきゃならないのよ。もう決心してるの。マリラ、あたしは大学には行かない。ここで教師になるの。
心配は御無用よ。あたしにとってここで暮らすのが一番いいことだと思うし、それにこの美しい土地は、あたしが注ぐ愛情よりはるかに大きなものを返してくれると思う。クイーン学院を卒業したとき、あたしの未来には一本のまっすぐな道だけがあるように感じた。でも、今それは曲がりくねっているように思うの。曲がり角の先には、きっと今まで見たことのない何かが待っているんだと思う。あたしはそれをまだ知らない。でもこうすることが一番いいって信じてるから」
オーチャード・スロープに向いた窓から光がピカピカ入ってきた。「ダイアナが光でサインを送ってるのよ。こっちに来いですって」アンは笑った。「ちょっと失礼して、行ってくるわね。まったく何の用事なんだか」
アンは丘を駆け下りていった。マリラからは、すぐに影に隠れて見えなくなった。すごく空気が新鮮で、森に入ると、枝の隙間から家の光がチカチカまたたくように見えた。向こうには海があるのもわかる。それらすべての美しいことが、アンの心をぞくぞくっとさせるのだった。
「懐かしくて美しい世界」心の中で、アンはそう言った。「愛してる。あたしあなたとともに生きていけるのを、ほんとうにうれしく思う」
丘を半分ほど下ったところに、背の高い若者が立っており、口笛を吹いているのを彼女は見つけた。ギルバート・ブライスの家の門の前だった。ギルバートはアンに気づくと、口笛をやめ、礼儀正しく帽子をとった。たぶん、そのまま何も言わず行ってしまおうとしたんだと思う。アンが足を止めて、彼に手を伸ばしてさえいなければ。
「ギルバート」彼女は話しかけた。頬が真っ赤になっていた。「お礼を言いたいの。アヴォンリーの仕事をゆずってくれて、ありがとう。ほんとうに助かったわ」
ギルバートはアンの手をとり、しっかりと握りしめた。
「たいしたことじゃないよ。少しでも君の力になりたいって、ずっと考えてたんだ。僕のほうはホワイト・サンドでも教えられるしね。――ねえ、アン、もう一度聞くよ。僕を友達にしてくれるかい? 僕が昔にしでかしたこと、許してくれるかな?」
アンはおかしくて、笑い出してしまった。
「あたしもうとっくあなたを許してたの。あの、バーリーの池の日にね。でも、そのときは自分でわからなかったの。あたしはとっても自分勝手で、自分のことしか見えていない女の子だったんだもの。ずっとあなたに謝りたいと思ってた。ごめんなさい、ギルバート」
「僕たち親友になれんだね」ギルバートは言った。ほんとうに幸せそうだったに。「僕たちまるで生まれたときから仲良しだったんだって、そんな気がするよ。ねえアン、これからはお互いに助け合って、力を合わせていこう。できるだけどんな場面でもね。
ねえ、君はこれからも、自分の勉強をつづけるつもりだろう? もちろん僕もそうだ。おいで、君を送っていくよ」
アンが台所の勝手口から帰ってくるのを、マリラはいぶかしげに見つめた。
「あんたはダイアナのところに出かけたと思ってたけどね。そこの小道のところまで、誰かと一緒だったようじゃないか。どちらさんだい?」
「ギルバート・ブライスよ」アンは答えると、さっと顔が赤くなった。「丘の途中で会ったの」
「ふうん。あんたとギルバートがそんなに仲良しだったなんて、今まで知らなかったよ。門のところで突っ立ったまま三十分も話し込んでたみたいじゃないか」とマリラはひやかすように微笑んだ。
「ずっと友達だったんじゃないわ。あたしたち――あたしたち、ずっと敵同士だったのよ。でもこれからは良い友達になったほうがいいって、ふたりでそう決めたの。
でも、さ、三十分も? ほんとうに? ちょっとしか話してないつもりだったけど――けど、あたしたち五年間も無駄にしてきたんだもの。それくらいは大目に見てほしいもんだわ、マリラ」
その夜、アンは彼女の部屋の窓に腰かけて、長いこと深い感謝の気持ちを感じていた。風がやさしく吹いて桜の木の枝を揺らした。雲ひとつないきれいな夜で、島のどこからでも星がキラキラまたたくのが見えた。
クイーン学院から帰ってきたときにアンの前に見えていた、地平線の向こうまで続くようなまっすぐな道は、ずいぶん短くなったように思った――けれど、たとえ道がせまく短くとも、静かな幸福の花がその道に沿って咲いているのだと、彼女は知っていた。
「"神は天にいまし、すべて世は事もなし"」アンはそっと、口の中でつぶやいた。
神は天にいまし すべて世は事もなし
Last-modified: 2010-07-19 (月) 12:22:32
(了)