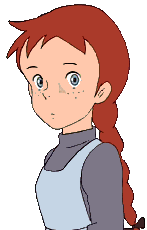17."The Glory and the Dream"
そんな調子で、その年の冬はあっという間にやってきた。クイーン学院で過ごす初めての冬。そしてまたあっという間に過ぎ去っていった。ほとんど春が来てから、冬なんて季節があったんだと気づいたくらいだった。部屋で勉強をしたり学校で授業を受けたりで、あまりにもいっしょうけんめいに忙しくしすぎてしまった、とアンは後に述懐した。アン自身の感想は別として、彼女がクイーン学院ですごした年月は、はたから見れば誰もがそう考えるくらいの完璧な勝利の年月だった。卒業年には英語の試験で最高得点をたたき出し、レドモンド大学にすすむための四年間の奨学金を勝ち取っていた。
「マシュウとマリラもよろこぶにちがいないわ! すぐ、手紙を書かなくちゃ」と、アンはひとりごちると、引き出しから便箋を取り出した。
「ええと、人生の望みを高く持つことは喜びであると思います」と、彼女は書きはじめた。「もちろんあたしの人生の望みがこれですべて達成されたとは、あたしは思わないのです――すごくいいことでしょう? ひとつの夢を終わらせても、またすぐ次の、さらに高みで輝いている夢が見つかります。それは人生を有意義で、おもしろいものにしてくれるのだと思います」
卒業式で、マシュウとマリラはずっとひとりの生徒だけをみつめていた――背が高く、ペールグリーンのドレスに身を包んで、バラ色のほっぺたをした、星明りのように輝く大きな瞳をもった女の子を。彼女は壇上で最高の答辞を読んだ。そして奨学金を得た優秀な生徒であると発表されたのだった。
「あの子を手元に置くことにしてほんとうに良かった。お前がそう言ってくれたんだ。そうだろう、マリラ」アンが答辞を読み終えるのを見届けると、マシュウはマリラにそうささやいた。
「ええそうです。けど兄さん、あたしはそう思うのは今が初めてってわけじゃないんですよ」と、マリラはこたえた。
その夜、アンはマシュウとマリラといっしょにアヴォンリーに戻った。四月以来一度も帰っていなかったのだ。アンはもう一日も待てないくらい、早く帰りたがっていた。
りんごの花が咲いていた。世界が新しく、若々しく生まれ変わる季節だった。ダイアナがグリーン・ゲイブルズへの道を歩いてくるのを見つけると、アンは幸せの長い吐息をこれまで以上に長く長く吐き出した。
「ああダイアナ、あたし帰ってきてよかったわ」
「あんたなんだかすごく立派になったみたいよ。大学に行くために奨学金をとったんですって? 教師にはならないの?」
「そうよ。九月になったらレドモンド大学に行くの。で、これからはじまる生涯最高の三ヶ月の夏休みに向けて、準備の真っ最中ってわけなのよ」
「ジェーンとルビーは先生になるんだってね」と、ダイアナ。「それと、ギルバート・ブライスもそうするみたい。そうしなくちゃいけないって言うべきかしらね。大学に行きたかったんだけど、お父さんがどうしても許さなかったんだそうよ。今じゃギルは、アヴォンリーの学校の先生になることに自分自身の道を見つけようとしているみたい」
思いもよらないことで、アンは衝撃を受けた。ちっとも知らなかった。アンは当然、ギルバートもいっしょに大学に行くものだと思っていた。どうしたらいいんだろう? 大学で友達もおらず、周りが敵ばっかりになってしまったら?
次の日の朝、朝食を食べていると、マシュウが具合が悪そうにしているのに気づいた。アンはしばらく黙っていて、
「マリラ」と、彼が仕事に出かけてしまうのをみてから、マリラに尋ねた。「マシュウ、あんまり良くないの?」
「ああそうだね」と、少し困ったようにマリラは話した。「この春からちょっとよくないね。だけどマシュウはちっとも不平を言わないし、自分の体のことを気にかけもしない。あたしはほんとうに心配なんだ。ちょっとは休んで、少しでも体にいいことをしたらいいのに。きっとあんたが家にいてくれるから、心臓のことを忘れたつもりになってるんだよ。あんたはいつでもマシュウを元気づけるからね」
「マリラ、あなたもよさそうにはみえないわ。なんだか疲れてるみたい。仕事がきついんじゃない? ずっと我慢してるんじゃないかって心配なの。あなたも休むべきなのよ。せめてあたしが家にいるうちはね、仕事はぜんぶわたしにまかせてちょうだい」
マリラは彼女のかわいい少女に向かって、にっこりと笑いかけた。
「仕事がきついわけじゃないよ。近頃頭痛がひどくなってね――目が原因なんだ。眼鏡をかけてもちっともよく見えやしない。六月の終わりに、有名な目医者さんがこの島に来るそうだから、あたしはきっとかかりに行くよ。でないと落ち着いて本が読めないし、縫い物もできないんだ。ずいぶん悪くなっちまったもんだ」
夕方になると、アンはマシュウを手伝いに行った。いっしょに牛を追い、小屋に入れた。夕陽に照らされて森は黄金色に輝き、暖かい光が西の丘の上をつたって夜へ滴り落ちようとしていた。マシュウはゆっくりと、こころもちうなだれた姿勢で、前かがみになって歩いていた。
「仕事のしすぎよ」と、アンは声をかけた。「どうしてそんなに働くの? そんなにしなくてもやっていけるじゃない。休んで、楽をしようとは思わないの?」
「単にわしが年をとっちまってるってことさ。アン、気にすることはないよ」
「もしあたしが男の子だったら」と、アンはつぶやいた。「あなたがもともと欲しがってた、男の子だったら、いま、あなたを助けられるのに」
「わしは一ダースの男の子の手助けよりお前ひとりのほうがいいよ」と、マシュウはこたえて、アンの手を軽く叩いた。「よく聞いておくれ。一ダースの少年より――わしはお前のほうがいい。大学への奨学金を勝ち取ったのは、男の子だったかね。そうじゃないだろう? それはわしの――わしの可愛い娘だ。わしはそれをとても誇りにしているんだよ」
そういって照れくさそうに笑いかけると、マシュウは家に帰っていった。アンはその夜、自分の部屋に戻ると、このことを頭の中でじゅうぶんためつすがめつしてみた。窓を開け放ったまま、長いこと座っていた。昔のことを思い出して、考えて、それから未来の夢を思い描いていた。
アンはいつも、このすてきで穏やかな夜のことを思い出す。悲しみが彼女の人生に触れる前の、最後の夜だった。誰の人生でも二度とはない運命の冷たい手が伸びてこようとしていた。