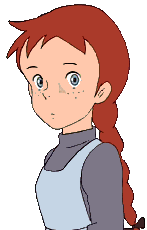14."The Queen's Class Is Organized"
マリラは編み物の手を休め、椅子の背もたれによりかかって背を伸ばした。目が疲れていて、次に町に行ったときに新しい眼鏡を買わなければいけないと思った。が、彼女は徐々に失明に近づいているようで、眼鏡もそれほど手助けにはならないとも感じていた。周りはほとんど暗闇で、十一月の夕暮れがグリーン・ゲイブルズに落ちかかっていた。明かりといえば台所のストーブのなかで、踊るように燃えている赤い炎ばかり。
アンは床の敷物の上で丸くなり、じっと火に目を据えてその輝きを見つめていた。火には歓喜にちかい喜びがあるわ、と彼女は詩的に考えた。アンは本を読んでいたのだけれど、いつのまにか本は床にほうりだされていた。夢を見ているような瞳で、唇には笑みがうかんでいた。柔らかい火の明かりに照らされるアンを、マリラは愛情のこもった目で見つめた。マリラがどれだけアンを愛しているか、アンはちっとも知らないのだった。
「アン」と、マリラは声をかけた。「今日の午後、ステイシー先生がここをたずねてきたんだ。あんたとダイアナが外で遊んでる間にね」
アンは唐突に、夢の世界から引き戻されたようだった。
「ステイシー先生が? ああ、じゃあ、ここにいればよかった。すごく残念だわ。マリラ、なんでそのとき呼んでくれなかったの? あたしたち、向こうの森にいただけだったのに。ええとそれで、先生はなにしにいらっしゃったの?」
「それをあんたに話したいんだよ。ねえアン、ステイシー先生は優秀な子を集めて、ひとつのクラスを作って特別の勉強をさせたいんだそうだ。クイーン学院の入学試験に向けた勉強だよ。学校が終わった後、そのまま校舎に居残ってさらに一時間の特別授業をやる。で、あたしとマシュウに、あんたをそのクラスに入れてもいいか、って聞きに来たのさ。アン、あんた自身はどう思うね? あの先生に教わって、クイーン学院に行きたいかい?」
「ああ、マリラ、それこそあたしがずっと夢見ていたことなのよ。そういえば、六ヶ月前にルビーとジェーンが受験勉強について話していたっけ。あたしね、学校の先生になりたいって思っているの。心から思っているのよ。でもクイーン学院に入るのって、とてもお金がかかるんでしょ」
「あんたが心配する必要はないね。マシュウとあたしは、あんたがずいぶん成長したって、この前も二人で話したよ。アン、あたしたちはできるかぎりの良い教育をあんたに施してやろうって、そう決めたのさ。女の子が自分の人生を生きるためには、必要かどうかに関わりなく、自分でお金を稼がなくちゃならない。あんたがもし、もしだよ、このグリーンゲイブルズの家でずっと暮らしたいと考えていたとしよう。あたしやマシュウと同じにね。でも、このあてにならない世界で、何が起きるかなんて誰にもわからないんだからね。何が起きてもいいように、準備は万端にしとくもんだ。やれることはやっておくべきなんだよ。だからあんたはただ、特別クラスに入りたい、って言えばいい。もちろんあんたが望めばだけどね」
「ああマリラ、ほんとうにありがとう」アンは両腕をマリラにまわして抱きしめた。そして養母の顔をじっと見つめた。「あなたとマシュウにはいくら感謝してもし足りないわ。あたし、死ぬ気で勉強する。どんなことがあっても全力を尽くすから」
「あんたはうまくやると思うよ。いままでそうだったもの。ステイシー先生はあんたのことを"特別な輝きをもっている"と言ってたよ。でもね、あんまり急いじゃいけない。極端に勉強して本ばかり読みすぎると、おかしな人間になっちまうからね。まだ一年半も先の話だ。よくよく基礎を固めておくがいいんだよ」
「でも、いままで以上に勉強が大好きになったって、かまわないわけでしょ?」と、アンは幸せそうに言った。「人生の目標ができたんだもの。あたし、ステイシー先生みたいな教師になりたい。あたし先生って、すごく大事で高尚な仕事だと思うのよ」
そして特別クラス――クイーン組が編成された。学校に通うすべての生徒から選び出された七名によるエリートクラスだ。ギルバート・ブライスとジョーシー・パイがそこに入るだろうことは、アンもわかっていたけれど、ダイアナ・バーリーがいなかったことには少なからずショックを受けた。ダイアナの両親は、彼女を大学へ送る気はなかったのだ。
クイーン組ができて最初の放課後、学校に残って特別授業を受けていたアンは、教室の窓から、ダイアナがゆっくりとひとりで歩いて家に帰っているところを見つけた。その日は席に座っていてもそのことばかりが気にかかって、他のことが何もできなかった。本を目の前にかかえて、泣いているのを隠した。ギルバート・ブライスやジョーシー・パイに泣き顔を見られるなんてまっぴらごめんだった。
「ダイアナがひとりで帰っているのをみたとき、ほんとうに胸が張り裂けそうになったのよ」家に帰ると、アンは悲しそうに話し始めた。「ダイアナといっしょに勉強できたらどんなにすばらしいだろう。でも、何事にも完全はありえないこの世の中で、完全は望めないのでしょうね。
それにクイーン組がこれからすごく面白くなるだろうってことは、あたしも認めるのよ。ジェーンとルビーはあたしと同じく、先生になるために勉強してるの。ルビーは教師になったとしてもきっと二年間しかやらないわ、って言ってるけど。すぐ結婚するつもりなんだって。ジェーンは反対に、人生のすべてを教育にささげて、結婚なんて絶対にしない、って。先生になったらお給料をもらえるけど、結婚したって旦那さんからはお給料をもらえないのよ、だって」
「そうかい。ギルバート・ブライスは何になりたいんだい?」と、マリラがたずねた。
「さあ? あたしはギルバートの将来の夢なんか興味がないし、知らないの――そりゃ何かひとつ、あるんでしょうけど」と、アンは冷たく言った。
もちろんまた、ギルバートとアンの競争ははじまっていたのだった。いまのところ一進一退で、どちらが優勢ともわからなかったが、ひとつだけ間違いなく言えることは、ギルバートはアンがそう思っているのと同じくらい、完璧な優等生であろうと決心したということだった。
ギルバートはアンを除く他の女の子とたちと良くおしゃべりし、冗談を言い、本の貸し合いっこをしていた。勉強のことや将来のことについて悩みを話し合ったり、ときどきはその女の子たちのひとりといっしょに帰ったりもした。アン・シャーリーははっきりと無視されていた。そしてアンは無視されると、どうにも気分がよくないのに気づいた。ギルバートに何されようとぜんぜん気にしないのに、と彼女は自分自身に言い聞かせていたけれど、心の奥底で、自分の女の子の気持ちはずいぶん傷つき、彼の行動を気にかけないではいられないのだと、ちゃんとわかっていた。
アンは自分の心に深く問いかけてみた――これまでのことを思い出して、整理して、感情の出所をくまなく探った。バーリーの池での機会がもう一度あったら、自分はなんと答えるだろう、と考えた――それで何もかもがいっぺんにすっきりしたようになった。つまり、アンはもうギルバートを許してしまっていたのだ。でも、もう遅いということもわかっていた。
かくのごとき問題をかかえながら、この年の勉強漬けの冬は過ぎていった。アンにとっても日々は瞬く間に過ぎていった。まるで金色のビーズをネックレスにつけてるみたいな一年だった。彼女は幸福だった。熱心で、とても興味をもっていた――授業を受け、学び、知識を自分のものにすることについて。それから夢をかなえる栄誉と、本を読む喜びについて。
そして新しい春が来たということは、クイーン組はその期間を終えたということだった。先生も、生徒も、安心して息をついた。目の前にあるのはうれしい、薔薇色の休暇だった。
その夜アンは家に戻ると、いままで使っていたすべての科目の教科書をすべて、古い箱につめこんで、片付けてしまった。
「この休み中は学校の本なんて開くどころか、表紙だって目にしたくないわ」と、マリラに話すのだった。「クイーン組の間、自分でできるぎりぎりまでずっとぶっ通しで勉強してたんだもの。代わりにお休みの間はめいっぱい楽しむことに本気を出すわ。もしかするとあたしの少女時代の最後の夏になるかもしれないんですものね。
もし今年と同じくらい来年もあたしの身長が伸びるなら、そのときは長いスカートをはかないといけなくなるでしょう。長いスカートをはかないといけないってことは、それにふさわしい威厳をもって中身をみたさなきゃならないのよ。そのときには、あたしは妖精を信じるような子どもではいられないわ。だからそのためにも――今年の夏いっぱいは、心の底から妖精さんを信じる子どもでいるわ!」
宣言どおり、アンはその夏をめいっぱい楽しんだ。いわく「あたしの人生における黄金の夏」で、朝から晩までまったくの自由にしており、ずっと屋外で遊んでいた。アンの関心のすべては、太陽の下を歩き、ボートをこぎ、友達と遊ぶことに向けられた。すべては完全に輝いていた。ただひとつ、マシュウの健康状態をのぞいては。
「以前から心臓は良くなかったけどね、このごろはひとしお発作が多くなった」と、マリラはアンにうちあけた。「お医者様はあんまりつらい仕事をさせちゃいけないって言ってる。あたしからも、仕事をするより生きて息をするほうが大事なんだって教えてやれ、なんて物言いさ。でもあんたが気にすることはないんだよ。アン、あんたはあたしたちにとって、とても助けになってるんだ。あたしはいつでもあんたを信用してる。ほんとうさ。何も心配しちゃいないね」
九月になった。一時期は心配したものだったが、このころにはマシュウはずいぶんよくなったように見えた。アンは目を輝かせて新学年の準備をはじめた。
「あたし勉強するの好きよ」と、本と新しい洋服を並べて、アンはマリラに言った。「頭を使って考えて、答えを出すことこそ、人の成長に必要だと思うのよ。だからあたしはいつでもそうしてる。ほんとうは何が正しいのかってたくさん考えるの。とても忙しいわ。
だから成長することって、たいへんなことだと思う。マリラ、あなたや、マシュウや、ステイシー先生みたいなすばらしい人たちが周りにいて、あたしほんとうに良かった。
ねえこの夏であたし二インチも背が伸びたのよ。新しい洋服、すそを長めにつくってくれてありがとう。この暗いグリーンの色がすてきよ。それにこのひだ飾り、すごく可愛いわ。こんなのつけてくれたのはじめてね。もちろん、こんな可愛いドレスがほんとうは必要じゃないんだって、知ってるわよ。そう言いたいんでしょう? でも、このひだ飾りはすごくおしゃれで、この秋の流行よ。ジョーシー・パイの服にはひとつ残らずついてるわ。
あたし自分が今までもらったもののために、たくさん勉強をするだろうって、自分でちゃんと知ってるの。このすてきなひだ飾りはあたしの心をたいへんに安らかな気持ちにしてくれた。心のずっと奥の方からそうなったように感じたのよ。大事にするわ」
「それだけの値打ちはあるものだよ」と、マリラは簡単に、しかし厳粛に認めた。
休暇が終わった。ステイシー先生はアヴォンリーに帰ってくると、以前以上の仕事への情熱をたちまちとりもどした。とくにクイーン組については、この学年の終わりまでに入学試験の準備を終わらせておかなくてはならないのだ。
もしも不合格になってしまったら? その冬、アンの頭からその心配事が離れた瞬間はなかった。起きてる時間のほとんどはそのことで頭がいっぱいだった。夜の眠りの中でも、みじめな気持ちで合格発表をみている夢を見た。トップ合格の場所にはギルバート・ブライスの名前が大きく書かれている。アン・シャーリーの名前はというと、目を凝らしてくまなく探してみても、どこにもない。
けれどそれも、冬の楽しさに比べれば笑い話のひとつだった。季節はとてもすばやく、忙しく過ぎ去っていった。また新しい世界が、アンの好奇心たっぷりの、貪欲で熱心な瞳に映りはじめたのだった。ステイシー先生はクラスを統一し、見事に導いた。生徒ひとりひとりに考え、探索し、自分自身を発見することを教えた。勉強を別にしても、此の冬、アンの住む世界はずいぶんと広がった。パーティー、コンサート、スケート、それにその他のすてきな遊び。
アンがどんどん成長していくのをマリラは驚きの目で見つめていた。ある日、彼女とアンが並んで立つと、いつの間にかアンはマリラの身長を追いこしていた。あの小さな子どもはもういなくなってしまったのだ、とマリラは考えた。彼女に愛することを教えてくれた子ども。目の前にいるのは背の高い、凛々しい目をした十五歳の少女だった。考え深げな眉に、こころもち頭を持ち上げて、前を向いているのが、彼女の内心の誇りをうかがわせた。もちろんマリラは、以前の子どものアンを愛していたのと同じくらい、少女のアンも好きになった。
その他にも、アンは以前と比べて変わってしまったところがあった。背が伸びたなどの体にまつわることよりもそれは深刻な変化だった――彼女は以前よりずうっと静かになってしまったのだ。
「あんたは以前の半分くらいしかおしゃべりしなくなったね。それに大げさな言葉づかいも、半分くらいになったみたいだ。さて、あんたに何があったんだろうね?」ある日、マリラは少女にたずねてみた。
アンは少し表情を変え、それからちょっと笑って、読んでいた本を置き、うっとりするように窓の外を見た。そして、
「知らないわ――あたし、そんなにしゃべりたくなくなったのかも」と、答えた。「楽しいことや、可愛いもののことなんか考えるのは今でもとても好き。だけどそれを口にしないで、心の中でずっところがしてるのも好きになったの。あたしにとって宝物みたいな時間よ。それにいろいろ勉強したり、やってみたり、考えたりするので忙しくて、おしゃべり使う時間がなくなっちゃったのもあるわ。
それからええと、大げさな言葉をあまり使わなくなったのは、ステイシー先生を見習ったの。先生はとても短い言葉でずっと強い効果を出すし、ぴったりと性質を言い表すの。"できるだけ簡潔に書くように"って指導して、先生はあたしたちに自分自身についてのエッセイを書かせたわ。はじめのうちはものすごく難しかった。あたしは大げさで、格好の良い言葉ばかりに慣れていたし――頭の中でも、そんな言葉ばかり使って考えていたんだし。でもいまじゃあ簡潔な言葉で表現するのにも慣れたし、そのほうがうまいこといくのもわかったのよ」
「そうかい。あと二ヶ月で入学試験だけど」と、マリラ。「どうだい、合格できそうかね?」
「わかんない。ときどき何もかもうまくいったらって楽天的に想像するんだけど――次には同じくらい不安な想像が襲ってきて、怖くなっちゃうの」と、アンは認めた。「たくさん勉強してきたけど、やっぱり、人それぞれどうしても弱点はあるのよ。あたしにとっては幾何学がそう。ステイシー先生は六月に入学試験と同じくらいの難しさの模擬試験を行うそうよ。それで、まあ、一応の判断はできるでしょうね。でも、そのう――あたしときどき、夜中に飛び起きるのよ。不合格になった夢があんまりにも怖くて」
「そんなに怖がることないじゃないか。なんならもう一年アヴォンリーの学校に行って、また次に受けなおしたらいい」
「ああ、ありがとう。でもきっとあたしそんなの耐えられないわ。もし不合格になったら、絶望で心臓が破けちゃうと思う。とくにギ、ギル――他のみんなが合格してたりしたら」と言うと、アンは窓の外の、緑色の春の世界から目を離し、また本を読み始めた。
そう、また春がやってきたのだ。六月の模擬試験の結果は良くなかった。本試験で合格するためには、この春に彼女がやろうとしていた様々な楽しみを、すべてあきらめないといけなかった。
クイーン組の呼びかけ
Last-modified: 2010-07-19 (月) 12:17:52