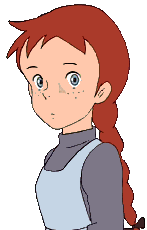18."The reaper Whose Name Is Death"
「マシュウ――どうしたんだい? 具合が悪いのかい?」
マリラが震える声で呼びかけた。アンは外から戻ってきたところで、手には摘んできた花をいっぱいに持っていた。マシュウは扉の横に立って、折りたたまれた新聞を読んでいた。とたんに彼の顔が奇妙な形に歪み、すぐに白く、次いで黒くなっていくのを二人は見た。手に持った花を落っことすと、アンは台所を飛び越えてマシュウに飛びついた。マリラもほとんど同時に手を伸ばした。でも、二人ともほんの少し遅かった――マシュウは床に崩れ落ちた。
「大変だ! 気が遠くなってるよ!」マリラが叫んだ。「アン、マーチンを呼んできておくれ――早く、早く!」
雇われ人のマーチンがすぐに医者を呼びに行った。途中でオーチャード・スロープに寄り、バリー夫妻と、たまたま来あわせていたをリンド夫人を送ってよこした。
彼らがグリーンゲイブルズに着くと、アンとマリラが床の上のマシュウに覆いかぶさっておろおろしていた。リンド夫人はやさしく彼女らを押しのけ、マシュウの心臓に耳を当てた。顔を上げると、誰もが心配そうな表情で注目していた。リンド夫人の目から涙がこぼれおちた。
「おお、もう、わたしたちには、もう――彼のためにできることはないんです」
「小母さん、できることはないって――マシュウは」アンはそれ以上言うことはできなかった。口に出すことが躊躇われる言葉だと思った。病人のように青ざめていた。
「わたしにはわかるんです。わたしのようにこうした経験をたくさんしてきたものには――アン、彼の顔をご覧なさい」
言われた通り、アンはマシュウの顔を見た。とても静かな表情になっていて、ぴくりとも動かなかった。そこには神の手の跡があらわれていた。
知らせはすぐにアヴォンリーじゅうに広まった。一日かけて友人や隣人がグリーン・ゲイブルズに集まり、また去っていった。内気で恥ずかしがり屋で、物静かだったマシュウ・カスバートが、はじめて町の注目の的となった一日だった。
夜がやさしく、グリーン・ゲイブルズを包み込んだ。年月を経た古い家は静かな安息に包まれていた。マシュウ・カスバートは棺に入れられ、居間に横たえられていた。まるで眠っているかのようなおだやかな微笑をうかべていた。気持ちの良い夢を見ているようだった。遺体の周りには花がいっぱいに飾られていた。アンがそれを摘んで、彼のところまでもってきたのだ。それがアンにとって、マシュウにしてあげられる最後のことだった。表情をなくし、乾いたように燃えるふたつの瞳が、アンの真っ白い顔の真ん中で動いていた。
部屋でひとりきりになると、はやく涙があふれてくればいいのに、とアンは思った。マシュウのために泣けないなんて、恐ろしいことだと思った。一番大好きで、愛していた人だった。彼ほどアンにやさしくしてくれた人はいなかった。マシュウと一緒に夕陽の中を歩いてから、一日しか経っていなかった。けれどマシュウは今、暗い部屋の中で、おそろしいおだやかな表情をみせながら横たわっているのだ。
だが、涙は出てこなかった。窓を開けて、外の真っ暗闇に向かってひざまづいて祈っている時でさえも。顔を上げると星々が丘に寄り添っているようだった――涙が邪魔をしないので、それがくっきり見えた。その日眠りにつくまで、その光景は彼女を責めつづけた。おそろしく、鈍く、確実にやってくる痛みのようだった。
夜が明ける前にアンは一度目を覚ました。まだ夜のうちだと思った。とたんに今日の記憶が津波のように彼女を襲い、痛めつけた。遺体のマシュウの浮かべている微笑が、前の日に彼が彼女に向けてくれた、あの照れたような、はにかんだような笑いと重なった。声が聞こえるようだった――「わしの可愛い娘だよ、わしはとても誇りに思ってるんだよ」。
そのとき、アンの目からはじめて涙があふれだして――胸が張り裂けんばかりに彼女は泣き出した。マリラはそれを聞きつけてやってくると、ベッドのなかの彼女へやさしく語りかけた。
「可愛い子――泣くのはおよし。あんたが泣いても、マシュウは戻ってこないさ。悲しむべきことじゃないんだ。神様がみんな良いようにしてくれたんですからね」
「これからどうすればいいの? 彼なしであたしたちどうすればいいの?」
「ああアン、お互い助け合って、頑張って生きていくんだよ。ねえあたしはあんたがここに来る前、どうやって生きていたのかわからない――アン、マシュウがあんたを愛していたのと同じくらい、あたしもあんたを好きなんだ。わかってほしい。こんなときでもないと、素直な気持ちを言うなんて、あたしには難しいんだ――あんたを愛してる。血を分けた肉親と同じように、あんたはずっと、あたしに安らぎを与えてくれたし、あんた自身があたしの生きる喜びだったんだ。あんたがグリーンゲイブルズに来てからずっとそうなんだよ」
それから二日経った。マシュウ・カスバートは彼が愛し、育てた森の中へ運ばれて行った。アヴォンリーの町は落ち着きをとりもどし、普通の生活へ戻っていった。グリーンゲイブルズでもそれは同じで、いつもの毎日がはじまったようだった。もっとも、一番大事な、一番身近にいた家族をなくした痛みは、ずっと消えることはなかった。
死と呼ばれる刈入れ人
Last-modified: 2010-07-19 (月) 12:21:07