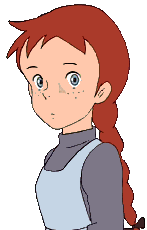13."An Unfortunate Lily Maid"
あまりの興奮状態が二ヶ月も続いたため、コンサートの後、アンたちは普段どおりの生活に戻るのにずいぶん苦労したものだった。アンはなかでも特別にそうで、なかなか熱気が冷めやらず、数週間も経った後にようやく目をぱちくりさせ、しらふで物事が見えてきたような調子だった。そしてこう感想を述べた。コンサートの前の喜びに満ちた日々をなつかしく思うが、ただちにもう一度戻りたいかっていうと、そうは思ってないのよ。最初に聞かされたのはダイアナだった。
「あたしは前向きな人間なの。人生に同じ時は二度と来ない、というじゃない。残念ながら、コンサートがあると、いつもの当たり前の生活が犠牲になっちゃうのね。いまならわかる。それがマリラがぶつくさ言って、賛成しなかった理由だったんだわ」
ともあれアヴォンリーの学校は少しずつ熱気からさめて、いつもどおりの日常に戻っていった。コンサートの後も学校はステイシー先生の小さな王国で、すべてが彼女の意思にしたがって運営されていた。数ヶ月がいつのまにか過ぎていき、ふと気づくと、やるべきことはスラスラとはこんでいた。アンたちはテニスンのアーサー王についての物語詩を学んだ。そこではまるで実際の人物みたいに、登場人物がいきいきと動き回っているのだった。
夏になった。ある日の放課後、アンと何人かの女の子がバーリーの池の周りで"ごっこ遊び"をしていた。エレーンは白百合のお姫様で、亡骸となって小舟に乗せられ、川をくだっていくのだ、とアンはみんなに向かって物語上の事実を思い起こさせた。
「もちろんエレーンはあんたがやるのよね、アン」と、ダイアナ。「ボートの底に横たわって流れていくなんて、おそろしくてあたしできないもの」
「エレーンが赤毛だなんて書いてなかったでしょ」と、アン。エレーンを演じたくないわけではなかったが、彼女の芸術的良心が抵抗するのだった。「おっかながってるわけじゃないわ。でもルビーのほうがエレーンにふさわしいと思う。だって、ルビーの髪の毛ったらすごく綺麗な金髪のロングヘアーじゃない――エレーンは"彼女の輝かんばかりの髪が滴り落ちる"なのよ。知ってるでしょ?」
オーチャード・スロープから下ったところにある池のまわりで、ルビーとジェーンはこの午後をずっとアンとダイアナといっしょにすごしていた。この日だけではなく、この年の夏のほとんどの遊び時間を、彼女たちはここで費やしていたのだった。橋を渡ればすばらしいマスがいたし、バリー氏所有の底の平らなボートをうかべて遊ぶこともできた。
ボートはいまのところきちんと繋ぎ止められていて、ロープをほどいて池面に押し出したとしても、流れていく場所はだいたいわかっていた。たぶん橋の下をくぐって、向こう側の土手に着くだろう。エレーンの場面を演じるにあたって、他に問題になりそうなところはなかった。
アンはなかなか承知しなかったが、最終的にはアンがエレーンをやることに決まった。「ルビー、あんたがアーサー王で、ジェーンがグィネヴィアね。ダイアナはランスロットよ。ダイアナ、ボートの底にショールをしいてもらえる? あんたのお母さんの古いやつ、もってきたでしょ」
ショールを広げ終わると、アンはいそいそとボートに乗り込んだ。底に横たわって、目を閉じ、手をたたんで胸の前に置く。
「やだ、ほんとに死んでるみたい」と、ルビー・ギリスがおそるおそる小さな声で言った。「ちょっと怖くなっちゃった」
「落ち着いてよ」と、アン。「じゃあ、ジェーン、スタートよ」
ジェーン・アンドリュースが金色の布をアンにかけてやり、大きな青いアイリスの花をアンの組み合わせた手の上にたむけた。「準備完了よ」と、ジェーン。「あとは、動かない眉の上にキスして、"わたしたちの近しい妹よ、永遠にさようなら"と言って、ボートを押してやればいいわ」
少女たちがボートを押し出すと、ボートは一度、池面に突き出ていた岩に衝突したものの、すぐにするすると水の上をすべっていった。
ゆっくり浮かんで流れていた少しの間、アンはロマンチックなシチュエーションを心ゆくまで楽しんでいた。だがその後に起きたことはちっともロマンチックじゃないことだった――ボートの底から水がもれはじめ、たちまち内部に水が溢れ出した。向こう岸に着くはるか前にボートは沈んでしまうだろう。オールで漕いだら? もちろん、オールは出発前においてきてしまっていた!
アンは小さな叫び声をあげた。だが誰も聞くものはいなかった。恐ろしさに唇が白くなった。が、ひとつだけ助かる方法があることに気づいた――ひとつだけ。アンは神様に祈った。「ああ神様、どうかこの舟が橋の脚のところに流れ着きますように」。何度も何度も繰り返し祈った。祈りの答えは正しくあらわれた。すぐにボートは橋脚にどんと突き当たり、アンは乾いた木でできたそれによじ登った。
ボートはそのまま流れていき、ずぶずぶと沈んでしまうと、すでに下手の土手で待ち構えていた少女たちからはアンもいっしょに沈んでしまったように見えた。あわてて彼女たちは助けを求めに走り去った。橋のほうを見ていればアンがそこにしがみついているのが見えたはずだったが。
取り残されたのはほんの少しの時間だったが、不幸な白百合姫としては、それが一時間にも思えた。どうして誰も助けに来てくれないの? みんなどこに行っちゃったの? もしかするとこの場所って、いままで誰も来たことないところなんじゃないかしら!
そのとき、アンがほんとうにこれ以上ちょっともしがみついていられないと思った瞬間だった、ギルバート・ブライスがボートを漕いで橋の下にやってきた。
「アン・シャーリー! いったいぜんたい何だってそんなところにいるの?」
アンが答えるのを待たず、ギルバートはボートを橋の脚に寄せ、アンに手を伸ばした。――アンはギルバートの手をとり、しがみついていた木から離れて彼のボートに乗り込んだ。体は濡れていたし、まったく気に食わなかった。何なのよ、これ! 助かってよかったって思わなきゃいけないの?
「何があったんだい?」ギルバートがたずねた。
「エレーンの演劇をしてたの」アンは説明した。あまり彼のほうを見ないようにしていた。「ボートの底から水が漏れ出して、みんなは助けを求めにどこかへ行っちゃったってわけ。向こう岸まで、あたしを運んでくれる気はある?」
ギルバートが舟を漕ぎ、向こう岸に着けると、アンはぴょんと跳んで地面に降り立った。
「すごく感謝してるわ。どうもありがとう」アンは無表情に言うと、背を向けてすぐに去ろうとした。けれどギルバートもそのときボートから降り立っていて、後ろを向いたアンの腕を手でつかまえた。
「アン」と、ギルバートが声をかけた。とても早口だった。「聞いてほしいんだ。僕たち、良い友達になれるわけないって、今でも思ってる? あのとき君の髪の毛をからかったこと、とても後悔してる。君を怒らせるつもりじゃなかったんだよ。冗談のつもりだったんだ。それに、もうずっと昔のことじゃないか。いまじゃあ僕は君の髪の毛、とても可愛いと思ってるんだ――正直な気持ちだよ。ねえ、僕たち友達になろうよ」
アンは立ち止まり、振り返った。ギルバートの茶色の目には恥ずかしい気持ちと、懸命な気持ちが半分ずつ浮かんでいるように見えた。それは彼女にとってとても好ましく思えた。心臓が小さく早く鼓動を打ちはじめた。が、そのとき、二年前の情景がアンの心にとつぜんよみがえり、まるで昨日のことのようにはっきりと思い出された。あたしはまだ怒っている、とアンは感じた。あたしの受けた侮辱は決して時間では癒される性質のものではないのだ。アンはギルバート・ブライスが大嫌いだ! 絶対に許さないだろう! 「いやよ」と、アンは冷たく言い放った。「ギルバート・ブライス、あなたとは決して友達にならないわ。さあ、あたしはもうここにいたくないの!」
「よくわかったよ」頬を怒りの色に染めて、ギルバートはボートに飛び乗った。「友達になりたいなんて、二度と言ってやらないからな。アン・シャーリー、君のことなんかもう考えない!」
ものすごい速さで舟を漕ぎ、ギルバートはあっという間に向こうへ行ってしまった。アンはカエデの木の下の急な小道を駆け上がった。きっと顔を上げていたが、心の中は後悔の気持ちでいっぱいだった。ギルバートに違った答えを返せば良かった、という疑念が心の中に生まれてきて、あわてて打ち消した。もちろん、彼はアンの心をひどく傷つけたのだ。でも、――それでも。
その場に座り込み、思い切り泣いてしまえばきっとせいせいするだろう、とアンは考えた。その日グリーン・ゲイブルズに戻り、マシュウとマリラといっしょになると、やっと彼女の心は安らいだ。
不運な白百合姫
Last-modified: 2010-07-19 (月) 12:12:37