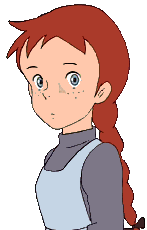12. "Matthew Insists on Puffed Sleeves"
十二月の夜は冷え込み、空も地上も灰色になる。マシュウは外から帰ってくると台所に座り込み、重たいブーツを脱ぎにかかった。彼は気づいていなかったが、アンとクラスメイトの女の子たちが居間でコンサートのための練習をしていた。ちょうど練習が終わり、少女たちは台所を遠って玄関へ向かった。楽しそうに笑いあい、小鳥のようにひまなくおしゃべりをしていた。コートを着込み、帽子をかぶって、コンサートのことを話している間、マシュウのほうをちっとも見なかった。アンは女の子たちの中でも一番いきいきとしており、よく口を動かし、誰よりも瞳を輝かしていたが――マシュウは突然気がついた。アンと友達との間にははっきりした違いがある。アンの着物は、他の子たちの着物とぜんぜん似通っていない!
マリラは常にアンに飾り気の無い、暗い色合いの、同じような簡単な柄の着物ばかりを作って着せていた。マシュウのような人間には当然のことながら、彼は着物の流行に詳しいとは言い難かったが、それでもアンの着物の袖が他の女の子たちの袖とまったく違うのは一目見てわかった。アンの周りの子たちは赤や青、ピンクや白の可愛らしい着物を着ていて――それで、マシュウはどうしてマリラがアンに地味な着物ばかりを着せるのか、不思議に思った。
もちろん、マリラはそのことについて、他の誰よりもよく知っていた。そこにはマリラなりの考えがあるのだろう。マリラだけがよくご存知の、とマシュウは思った。しかし彼らのこどもに、ダイアナがいつも着ているような、すてきで可愛らしい服を一着あつらえてやることに、ひとつの害もありそうにないのもまたもっともだった。マシュウはアンにクリスマスプレゼントを贈ることを決意した。
思い立ったがすぐ、次の日の夜にはマシュウは町までドレスを買いにでかけた。しかし女の子のドレスを買うことはマシュウにとって想像を超えた大難関だった。何件も店を回り、幾度かの成功とは言えない挑戦を経て、最後には彼は隣のリンド夫人にドレスを作ってもらうことにした。リンド夫人はわけ知り顔でたのもしく引き受けてくれた。さあ、あとはアンを驚かせるばかり。
クリスマスの朝、窓の外は美しく真っ白な世界となった。その年の十二月は例年より寒さが和らぎ、雪の無いクリスマスになるのではないかと思われていたが、明けてみれば前の晩にじゅうぶんな量の雪がやさしくしずかに降り積もっていたのだった。喜びに満ちた瞳でアンは窓から顔を突き出した。木々の枝に雪が乗っかってまるで白い羽根に覆われているように見えたし、空気はとても新鮮で、神々しい感じさえした。申し分のないすばらしい朝だった。アンは歌いながら階段を駆け下りていった。
「メリー・クリスマス、マリラ! メリー・クリスマス、マシュウ! とんでもなくすてきなクリスマスね。雪が降ってくれてよかったわ。雪のないクリスマスなんて、なんだかほんとうじゃないみたいだもんね。ねえそう思うでしょ? マシュウ――これ、あたしに? ああ、マシュウ!」
包んであった紙をあけて、マシュウはドレスを広げてみせた。そしてアンに渡して、よく確かめさせた。
物音ひとつたてず、アンは手の中のドレスをじっとみつめた。部屋中がしーんとしていた。なんて可愛らしい服だろう――愛らしくてやわらかそうな茶色のシルクでできており、首のところにレースの飾りがついている。スカートも流行最先端だ。そして袖――それは最上の栄光につつまれていた! 長い肘のカフスの上に二つの美しいパフスリーブがついており、弓のようにふくらんで、茶色の絹のリボンで仕切られていた。
「クリスマスの贈り物だよ。そのう、そうさな、ああ――アン、気に入ってくれるかね?」
はにかみながらマシュウは言ったとき、アンの目にはすでに涙があふれだし、いっぱいになってしまっていた。
「気に入るに決まってるわ。ああ、マシュウ!」アンはドレスを皺にしないよう、一旦椅子の背にかけると、気持ちを押えきれないように両手を胸の前でがっちりと組み合わせた。「最高に、文句のつけようがないくらいほんとうにきれい。これ以上すてきなものなんかあたしには考えられない。このそでを見て! ああ幸せすぎて夢を見ているみたい」
「じゃあそろそろ朝食を片付けましょうかね」マリラがわりこんだ。
「言っておく義務があるだろうね。あたしはあんたにそんなドレスは必要ないと思っています――だけど、マシュウがあんたにあげたんだからね。大事にしなければならないよ。その袖には特別な布地がたくさん使ってあるようだよ」
「ええもちろんよ。でもあたしどうやって朝食を食べたものかわからないの」夢見るような声でアンはこたえた。「この特別の瞬間にくらべたら、朝食なんて平凡すぎるわ。食事よりドレスを眺めてるほうがいいの。ああパフスリーブがまだ流行っていて良かった。一度も着ないうちに流行りがすたれてしまったら、一生涯あきらめきれないところだったわ。ねえあたしこんなに満たされたこと今までなかった。わかるでしょ? あたしがこのドレスにふさわしいような、模範的な女の子じゃないのを残念に思うわ。あたし今まで以上に、特別の努力をはじめるわ」
朝食が終わったころにダイアナがやってきた。華やかで小さなくて、真っ赤なドレスに身を包んでいた。アンはとんでいって腹心の友を出迎えた。
「メリー・クリスマス、ダイアナ! すばらしいクリスマスね。ねえあんたに見せたいものがあるの。とってもすてきなのよ。マシュウがドレスをプレゼントしてくれたの。たまらなく美しい、大きくふくらんだ袖がついてるのよ。あんなにすばらしいもの、このあたしにして想像したこともないほどよ」
「実はあたしも、あんたにあげたいものあるのよ!」と、ダイアナは言うと、「どうぞ」と贈り物の箱を差しだした。箱を開けると最高に可愛らしい皮ごしらえの靴がはいっていた。つま先はビーズ玉でかざられ、サテンのリボンときらきら輝く留め金がついている。
「ああ……」と、アンは感極まった声を出した。「すごすぎて声も出ないわ。あたし夢を見てるにちがいないわ。ドレスも靴も、あつらえたようにコンサートにぴったり」
その夜、アヴォンリーの学校に通う生徒たちは誰もが興奮し、熱を上げていた。町の広場はきらびやかに飾り付けられ、最後の準備も終わっていた。
コンサートは夕方から開演し、そして、結論から言うと、大成功をおさめた。町中の人間が広場につめよせた――すべての演者たちが個々人の持てる力を出し切り、出来る限りのすばらしい出し物を見せた。なかでももっとも輝いたものといえば、アン・シャーリーをおいて他にいなかった。アンはその夜、ひときわ輝いたスターだった。。
「ああほんとうにすばらしい夜だったわね。驚異的な夜だったわね」すべてが終わったあと、ダイアナと家路につきながらアンは感想を述べた。空には星がきらきら輝いていた。空気が澄んでいて、いつもよりも星の数が多く見えるように思った。。
「なにもかもが一番いい想像以上にうまくいったわ」と、ダイアナ。「あたしたちきっと十ドルも稼いだにちがいないわよ。新聞に載るわよ」
「明日の朝新聞を読んだら、自分の名前が目に飛び込んでくるのね。考えただけでぞくぞくっとしちゃう。ねえダイアナ、あんたのソロパート、ひとつの狂いもなかったわ。言葉通りに完璧な出来だった。あたしあんたのような友達がいて、心の底から誇りに思うわ。大好きな腹心の友よ、そは名誉なり」
「あんたの朗読こそ満場の大喝采だったじゃない。なかでも悲劇詩のほうはそりゃあすばらしかったわ」
「あたしあの詩を読む前は、小鼠のようにおどおどしてたのよ。名前を呼ばれてもわからなかったくらいで、どうやってステージに上がったかも憶えてないのよ。やっとこさ人前に出たら、百万もの視線に射ぬかれたような気持ちだったわ。もし何も起きなければ一言だって口にできなかったでしょうね。
あたしその時、この袖のことを考えたの。この格好良いパフスリーブのことよ。そしたら泉の水のように勇気がわいてきたの。読み終わって椅子に座る頃には、あのお年を召したスローン夫人が涙を拭いているのがステージの上から見えたわ。あたしの朗読が彼女の胸に届いたんだって思った。誰かの心に触れる朗読が出来たんだって思ったの。それであたし、すごく感動して、泣きそうになっちゃった。
ねえコンサートに参加するのって、なによりロマンチックなことね。そうじゃない? ああ実際いつまでも、生涯にわたって心に残る経験だわ」
「男の子たちもすてきだったわね」と、ダイアナがさらりと、アンの注意をうながした。「ギルバート・ブライスが、やっぱり一番ハンサムだったわ。ねえアンあたしね、あんたのギルバートにたいするやりかたって、決して良くないと思うの。ほんとうにひどいと思うわ。待って、話を聞いて。あたしたちの劇の妖精のシーンの後、あんたがステージから引き上げた後よ。あんたの頭から飾り付けの薔薇が一本落ちてたのよ。ギルバートがそれを見つけたの。彼はそれを拾って、自分のポケットに挿したわ。ほんとうよ! ねえあんたロマンチックなこと好きだから、この話よろこぶって思ったのよ」
「そいつが何しようがあたしはなんにも感じないの」と、アンはすまして言った。「あいつのことを考えるなんて無駄なことはけっしてしないのよ」
その夜、マリラとマシュウもコンサートに出掛け、アンの晴れ舞台を見物していた。老兄妹がコンサートなどというものに行くのは、実に二十年ぶりのことだった。アンが寝てしまったあと、二人は台所の火のそばに腰掛けて、しばらく話をした。
「アンは他の誰よりもうまくやっていた」とマシュウが言った。声には誇らしい得意げな調子があった。
「ああ、あの子はよくやったよ」と、マリラも認めた。「言いたかないがあの子にはなんというか、華があると思うんです。それに今夜はとてもきれいにみえた。あたしでさえあの子を自慢に思ったくらいだよ。もちろん本人にそんなこと言う気はありませんけどね」
「わしはアンが自慢だし、あの子が寝る前にきちんとそう伝えたよ」と、マシュウ。「わしらがあの子にしてやれることが何なのか考えにゃならんだろうな。今だけじゃなくて、将来についてもだ。わしはあの子がやがてアヴォンリーの学校では満足できないくらい、多くのものを必要とするようになると思う」
「そんなことを考える時期に来たのかね。次の三月で、やっと十三歳になるばかりだってのに。ああ、あたしだって、今夜あの子の姿を見て、すごく成長したのに気づいたんだ。あたしは何かに打ちのめされた気持ちになりましたよ。あの子は驚くべき早さでいろんなことを覚えていくし、ねえ兄さん、あたしたちがあの子にしてやれるもっともいいことと言えば、クイーン学院に入れてやることじゃないかと思ってるんですよ。でも、まだ早いね。あと二年経たなけりゃ、わざわざ言う必要もないことだ」
「そうさな。が、真面目に考えていくこととしよう。決して無駄にゃならんからな」マシュウが言った。「何事についても真剣に検討せにゃならん。いつだってそれが一番大事だし、良い方法なんだ」
マシュウ、パフスリーブにこだわる
Last-modified: 2010-07-19 (月) 12:12:02