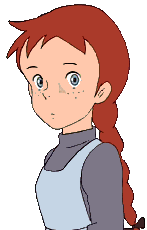15 "The Pass List Is out"
六月が終わり、アンのアヴォンリーでの最後の学年も終わった。ステイシー先生の授業を受けられるのも今日が最後だった。学校がひけた後、アンとダイアナはいつものように歩いて帰る途中で、悲しい気持ちにおそわれた。ほんとうにとても悲しい気持ちだった。ダイアナは丘の上で足を止め、振り返って校舎をみつめた。
「なんだかすべてが終わってしまったみたいな気分だわ。あんたもそうじゃない?」と、アンに言う。
「ダイアナはあたしの半分くらいしかそう感じてないと思う」と、アン。泣いていたせいで目は真っ赤になっていた。「だってあんたは冬になったらまたここに戻ってくるんじゃない。でもあたしは永遠にこの親愛なる、古ぼけた学校から離れてしまうのよ――運よく試験に受かったらだけど」
「あたしたちすごく楽しい時間を過ごしたものね。ほんとうにね。ねえあたしはおびえているのよ、その時間がもう終わっちゃったんだって、もう戻ってこないのだと思って」
大きな涙のつぶがふたつダイアナの瞳からこぼれおちて、鼻の頭までつたった。
「あんたが泣くの、あたしに止められたらいいんだけど」と、アンは言った。
「ステイシー先生が言ってたわ。"楽しくないときでも、まるで楽しいみたいな顔をしてなさい"って。でもダイアナ、あたしなんだかんだ言って来年もここに戻ってくるような気がするのよ。だってきっと合格しないもの」
「ほんと、あたしもいっしょに行けたらいいのに。ずいぶんがんばって、運動したんだけど」と、ダイアナ。「ねえ向こうに着いたら手紙を書いてね。きっとよ」
「もちろん。木曜の夜には、最初の日にあったことなにもかも書いて送るわ」と、アンは約束した。
次の月曜日アンは町を出た。水曜日にはダイアナは最初の手紙を受け取っていた。
限りない親愛をこめて ダイアナへ
今は火曜日の夜で、あたしはクイーン学院の図書館でこの手紙を書いています。昨日の夜はひとりぼっちでさみしくて、とても怖かった。あんたがそばにいてくれたらいいのにって、何度思ったか知れないわ。昨日は最初の試験があったの。心臓がどきどきしちゃって、音が隣の部屋にまで響いてるんじゃないかって思った。男の人が入ってきて、英語の試験用紙を全員に配ったの。緊張して手が冷たくなって、紙をめくるとき、頭の中がぐらぐらする感じだったわ。あたしの人生の中でも一、二を争うくらい緊張した瞬間だったわ――ダイアナ、あたしそのとき、ちょうど四年前に戻ったみたいだった。あたしはマリラにこう聞いたのよ、あたしをグリーン・ゲイブルズおいていただけますか、って。――で、そのことを思い出したら、全部の心配事が頭から抜け出て、すっかり落ち着いちゃった。試験といっても、たかだか紙に書いてあることだけの話です。このくらいのことあたし簡単にこなせるんだって思ったの。以前の経験と比べたらね。
その日のテストが終わると、あたしたちは街にくりだして、アイスクリームを食べました。ほんとあんたが恋しかったわ。
ああダイアナ、幾何学のテストさえ終わってくれたらね! でもステイシー先生ならこう言うでしょう。あなたが幾何学で落ちるかどうかに関わりなく、太陽はまた昇るのよ。曇か晴れかはそのときになってみないとわからないことです、なんて。もちろんそれはそうだけど、でもちっとも元気づけられないわね。ええい、もし落っこちても、つまるところ先へ進まないよりはましだ、って思うことにしよう!
あなたの献身的な友達アン
アンが帰って来たのは金曜の夜だった。疲れてはいたけれど、むしろ帰ってきたよろこびのほうが強かった。ダイアナはアンの帰宅をグリーン・ゲイブルズで待ち構えていて、まるで一年も引き裂かれていたかのように腹心の友を出迎えた。
「おかえりなさい、いとしい人。あなたにもう一度会えるのは望外の喜びです。ねえアン、あんたが去ってしまってから、まるでひとつの時代が過ぎたように感じていたわよ。あんたはこの年月をどのように過ごし、何を手に入れたのかしら?」
「ダイアナ、この台詞をご存知かしら? <bold>ああ、まだあたしには帰れる所があるんだ……こんなに嬉しいことはない。</bold>あのね、グリーン・ゲイブルズは世界で一番優しくて、すてきで、環境が良くて、愛にあふれた幸せなところよ」と、アンは言った。「試験に受かったかどうかはわからないけど、でもへたに最下位なんかで通るようだったら、落ちちゃったほうがましだと思ってるわ」。つまりアンがなにを言いたいかというと――それはダイアナも、じゅうぶん気づいていたことだが――もし、彼女がギルバート・ブライスより劣る成績で合格するようなら、それは完璧な成功とはいえないし、きっと苦い気持ちになるに違いないということだった。
アンはこれまでギルバートと道で十二回も行きあったが、二人ともお互いを見ようとしなかったので、十二回も無視して通りすぎていた。そして毎回、すれちがいざま、アンは頭をちょっと高くもちあげてみたりするのだったが、心の中ではいつもギルバートと仲直りすることを考えていた。つまり彼がまた彼女に友達になりたいと言ってくれればいい、と考えているのだった。でもそうならなければ、お互いの関係はこれまでどおり。アンはアヴォンリーの全住民が、誰が一番試験で良い点数をとったのか、興味津々であることを知っていた。アンはどうしても勝ちたいと思っていた。
けれどそんな意地のほかにも、アンにはもうひとつの勝ちたい理由が――より崇高な理由もあった。良い成績で合格するのはマシュウとマリラのために望んだことだった――とりわけ、マシュウのために。彼はいつも、アンが「この島のすべてものに元気をあたえてくれる」と信じていた。マシュウの目はやさしい茶色の目で、アンは彼に彼女の達成したことを、そして誇りに満ちているであろう自分自身の将来の喜びを、見せてやりたいと強く望んでいた。それは彼女自身にとっても、この上なく甘いごほうびになるはずだった。
三週間経った。まだ合格発表は出ておらず、アンはそろそろ待つことに耐えられなくなりそうだった。そしてある夕方ニュースがやってきた。アンはグリーン・ゲイブルズの出窓に腰かけて、美しい夏の夕暮れを見ながら陶然としていた。ダイアナが飛ぶように丘の上を駆けてくるのがみえた。手には新聞紙を持っていた。
「アン、あなた受かったわ」と、彼女は叫んだ。「合格したの。それも、一番の成績でよ――あなたとギルバートが、同点一位だったわ――あなたたち二人が! でもつづりの都合であなたの名前のほうが上にあるわよ。おめでとう! あたし、なによりも誇らしいわ!」
アンはじっと新聞をみつめた。そう、たしかに、彼女は受かっていた――二百人の合格者のなかでも、彼女の名前が一番上に書かれているのだ! これまでの人生のすべてが報われたのだ、とアンは思った。
「ああびっくりよ」と、アン。「ああダイアナあたし百個も言いたいことあるわ。でも、何を言っていいか言葉がみつからない。ちょっとだけ落ち着かせてほしいの。あのねダイアナ、あたしすぐマシュウを探しに行かなきゃいけないと思う」
少女たちは息もつかずに走りまわり、納屋で仕事をしていたマシュウを見つけた。運のいいことにマリラもいっしょにそこにいた。
「マシュウ!」と、すばらしい興奮を隠さず、アンは告げた。「受かったわ。あたしクイーン学院に合格したの。それであたし一番だったのよ。一番のうちのひとりだったのよ」
「わしはいつも言ってただろう」マシュウは喜びに満ちた目で、じっくり新聞を読んだ。「お前はなんでもうまくやれる子なんだって」
「あたしからも言わせてもらうよ。アン、ほんとうによくやったね」マリラは誇りではちきれそうにみえた。