アイザック
【正体】元聖騎士。渦により故郷を失い、幼馴染みのエヴァリストが覇道を進むのを補佐する。
【死因】不明(塔の崩落)
【関連キャラ】エヴァリスト(盟友)、フリードリヒ(上官)、ベルンハルト、マックス、マルセウス
3396年 「ドッグ・イート・ドッグ」 

アイザックは座った男の頭を撃ち抜いた。
後頭部へ抜けた弾は血潮をはじけさせ、その血は赤い霧となって部屋を漂った。
アイザックの銃を抜く挙動は、男と向かい合っていたエヴァリストも気付けないほど素早かった。机を挟んで対面して座っていた男は、シドール将軍からだと言っていた。
夜も遅かったが急な話だと言い、軍属であることは確かだったので、話を聞くために部屋に招き入れた。
「こいつ、やる気だった」アイザックは呟きながら男を椅子から降ろした。
身体に巻きつけられた爆薬を、上着をはだけさせて見つけ出した。部屋ごと吹き飛ばすに十分な量だった。
アイザックは男から爆薬を引きはがすと雷管を抜き、無造作に机の脇に置いた。
「いつ気付いた?」
椅子に座ったままのエヴァリストが聞く。死体と爆薬の前だが、落ちついた口調だった。
「匂いさ。その合成爆薬の匂いは独特だからな」
エヴァリストは座に浅く座り直し、机に置かれた爆薬を手にとって眺めた。
アイザックはこの暗殺者の懐中を探っている。
将官の多く住むこの地域で爆弾騒ぎとなれば、暗殺者側にもかなりのリスクがある。
「物騒な話だ」
「まったくだ。心当たりは?」
「さあな」
軽い冗談でも言っているかのような調子で答えた。エヴァリストはアイザックと二人だけの時は、普段の態度よりもずっとくだけていた。
「ありすぎて困るってのも考えモノだ」
男を物色しながらアイザックも言った。
いずれこうなることは、アイザックには前からわかっていた。
帝國内での闘争はエスカレートしていた。その一端を担っているのが自分達だからだ。
今の帝國内部は、軍閥であるシドール将軍を中心とした拡大派と、帝國軍政治局のカンドゥン長官と有力政治家達で作られる統制派に分裂していた。
際限なく戦火を拡大させる将軍の拡大派に対し、ルビオナとの和睦も含め、国内の安定を第一に考えるという統制派の二派の対立だった。しかし、表向きの対立軸はそうであっても、統制派の大部分は「薄暮の時代」に権力を持っていた政治家達であり、戦時が続くことによって拡大した軍閥側との、純粋な権力闘争に過ぎなかった。
そんな対立軸の中、エヴァリストはシドール将軍一派の若い将校として台頭していた。狂的に拡大の情熱に取り憑かれた老将軍、それを陰で支える若く冷徹なエヴァリスト、というのは、拡大派の両輪として機能していた。
その両輪の邪魔になるものを影で排除してきたのがアイザックだった。
まず統制派の政治家の内、幾人かが突然失踪した。あらゆる手を使って証拠を残さずに始末したのだった。この事実に統制派は恐怖し、萎縮した。
閉じた世界に長く暮らしていた政治家達は、ここに至って初めて、拡大と闘争の時代が来ていることを知った。エヴァリスト達は常に相手が行動を起こす前に痛撃を加え続けた。それは外敵に対しても、政敵達にあっても同じだった。
アイザックはこの汚れた仕事に対して何も感じていなかった。
エヴァリストとアイザックの二人は、闘争の世界のただ中にいることを自ら望んでいた。
特にアイザックはその場のスリルを徹底的に楽しんでいた。軍閥同士の戦いも戦場で敵国の兵と戦うのも、どちらも「闘争」という点でアイザックには等しかった。
今や帝國でシドール将軍を筆頭とする拡大派は権勢を誇っていた。しかし、統制派も黙ってやられる訳にはいかないだろう、と感じていたのだった。
次の日、アイザックはエヴァリストを国境まで送り、彼を部隊に引き渡した後に館に戻った。殺した男の始末をつける必要があったからだ。警察機構の長は敵対する相手なので、信用する訳にはいかなかった。
下手な情報を渡すのは得策ではなかった。面倒な作業ではあるが、別に気にはならなかった。
館に戻りコートを置いたとき、爆発音と閃光に包まれた。
アイザックは自分を「切り替え」た。光と煙がゆっくりと自分の周りに生じた。
その空間の中、煙の向こうを観察しながら素早く正対して、アイザックは銃を抜いた。
煙の向こうから重武装の憲兵四人が次々と部屋の中に入ってくる。
アイザックは一度銃を下ろし、時間を通常の感覚に戻した。
サブマシンガンを構えたままの憲兵の後ろから、政治局の制服を着た男が出てきた。政治局員は皇帝への忠誠を守るという名目で、帝國軍内で大きな権力を持っていた。
「ロスバルド大尉、ご同行願いたい」
無表情に男は言った。さも当然といった様子だった。
「行く理由が無いね」
「バスルームの死体と爆薬の件です、大尉。同行いただかなければなりません。査問を受けてもらいます。反逆罪の疑いがあります」
アイザックは昨日の出来事が相手のシナリオの一部だと、すぐに理解した。
「拒否したら?」
「これは政治局の決定です。抵抗すれば、即それは皇帝陛下への反逆とみなされます」
「反逆か……。面白い」
アイザックは奇妙な笑みを浮かべて言った
「?」
意外な言葉に、無表情だった局員の顔にも一瞬困惑の表情が浮かんだ。
アイザックは世界を切り替えた。世界が一瞬暗くなったように感じたが、すぐに戻る。通常の兵には見えない世界へ突入した。
一瞬で間合いを詰め、政治局員の傍らに立ち、腕を掴んで捻りあげる。そしてその腕を力任せに引き抜いた。
生きたまま引き裂かれた政治局員は、まるで人形のように力なく宙を舞った。その身体は武装した憲兵隊に叩きつけられた。
憲兵達の視界には、一瞬で身体を引き裂かれた政治局員しか写らなかった。予期せぬ出来事に彼らの知覚は凍っていた。速度と力は圧倒的だった。白刃が狭い空間に舞うと、また血飛沫が舞った。
サブマシンガンを持った憲兵達の腕が次々と落ちる。まるで昆虫の四肢をもいで遊ぶ子供のように、わざと即死せぬように憲兵達を血祭りに上げていった。そしてその顔には、やはり笑みが浮かんでいた。
数分後、アイザックは血溜まりの中に立っていた。
血溜まりに沈む男達はすべて息絶えていた。無残な殺され方だった。
アイザックはバスルームに向かった。そして昨日の死体が収められたバスタブに腰掛け、丁寧にブーツの血を拭った。
そしてゆっくりと息を吸い、天を眺めた。
夜が来た。帝都に爆音が響いた。
エヴァリストの館は燃え、夜の帝都の天蓋を赤く照らした。公館の多い帝都中心部における爆発騒動を発端とした混乱は、夜半まで続いた。
しかし、翌日の新聞の見出しにはならなかった。なぜなら、カンドゥン長官が謎の死を遂げたことを告げるニュースが入ったからだった。
「─了─」
3397年 秋 「庭園」 
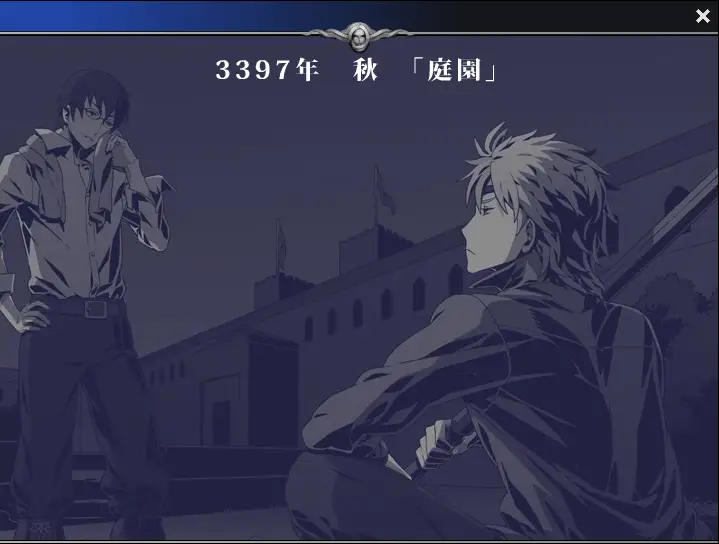
晩餐会以降、エヴァリストとアリステリアは、しばしば会うようになっていた。
人気のない夕方の回廊を二人は歩く。
アリステリアがやや先を歩き、少し後ろをゆっくりとエヴァリストが追う。
二人で過ごす時間は僅かだったが、それでもその関係は次第に深まっていた。
「先の話、考えてもらえた?」
皇妃は振り向いてエヴァリストに話しかけた。
「はい、私でよろしければ」
ためらいなく、エヴァリストは答えた。
「それはよかった」
優しく微笑む姿は傍目には美しく高貴な女性としか写らない。
しかし、エヴァリストは皇妃の大きな瞳の奥に暗い愁いを感じることがあった。
「私にはあなたが必要です」
巨大な帝国の深部に位置する彼女のすべてを信用している訳ではなかった。
それでも、今は彼女と進むべきだと考えていた。
利は自分にあると信じていた。
「光栄です」
皇妃と若い騎士の影は重なった。回廊には夕陽の光が満ちていた。
「アホらしくなるぜ、間抜けすぎる。 オレに覗きの趣味はねえぞ」
皇妃との逢瀬を終えたエヴァリストは、アイザックと帝都内のある一室で落ち合った。
「悪かった」
逢瀬の場を見張らせていたことに愚痴をこぼすアイザックをエヴァリストはなだめた。
「しかし信用できねえな」
エヴァリストと皇妃の関係が深まっていくこと、皇妃の計画にこちらが乗ることについて
アイザックははっきりと疑義を口にした。
「すべてを信じている訳じゃない。 十分状況はコントロールできる」
アイザックはエヴァリストの言葉を無視する。
「オレはお前と皇妃の周りを何度も探ったが、カストードどもの影も見えない。おかしな話だと思わないか?」
皇族の護衛官たるカストードは帝國では絶対的な戦闘力を持った集団だった。
直に戦ったことはないがアイザックでさえその力は認めている。
自分たちの動きが彼らにまったく通じてないとは考えられない。
「見透かされてるみたいだぜ……。 何もかも」
「何をだ?過去か、野心か?ここまで来て何を恐れる」
「そこだぜ。エヴァリスト、お前にしては入れあげすぎじゃねえか?」
「皇妃にか?計画にか?」
エヴァリストの語気に力がこもっていた。
「どっちでもいいさ」
アイザックは捨て鉢に言い放ち、部屋を出た。
もとより戦功・能力ともに十二分に持ち合わせているエヴァリストが
皇妃の後ろ盾も得た事で、その影響力は日に日に増していた。
「エヴァリスト・ヴァルツを准尉に任命します」
皇妃の手により新しい階級章がエヴァリストの軍服に付けられ、会場は拍手の音で埋まる。
グランデレニア帝國の若き英雄は、表向きは総督府での活躍が認められて将軍として列せられることになっていた。
しかし、皇妃の後ろ盾なくしてこの地位につくことなど不可能なことは、列席者の殆どが理解していた。
その列席者の中に、常にエヴァリストの影のように寄り添っていたアイザックの姿はなかった。
「精が出るな」
夜の庭園で鍛錬中のアイザックを見つけ、エヴァリストが話し掛ける。
かつて一つしか差の無かった階級は、今や大きな差が付いていた。
「閣下、わざわざご足労いただかなくても、呼ばれれば伺いますよ」
慇懃な態度を無視してエヴァリストは話し掛けた。
「言いたいことがあるなら、ここで話せ」
「特にないね。 言葉で言ったって無駄だろ」
エヴァリストは傍に並べてある木剣を握った。
「なかなか机仕事には慣れない。 久しぶりに腕試しをさせてもらう」
エヴァリストが剣先を向けると、黙ってアイザックも剣を構えた。
夜の庭園に空を切る剣の音、ぶつかり合う剣の音が響きだす。
剣戟はしばらく続いたが、明らかにエヴァリストが押され始めていた。
二人の間合いが離れたとき、肩で息をしているエヴァリストに向かってアイザックは話しかけた。
「随分となまっちまったみてえだな」
「いいや、まだだ」
振りかぶって力を込め、エヴァリストが打ち込む。次の一撃には特殊な力が込めてあった。
その技をよく知るアイザックだったが、意外な一撃に守勢に出てしまった。
「雷撃」と呼ばれる一撃は、受け止めた者の神経に作用する。
握った木剣から手に衝撃が走り、剣を取り落としてしまう。
「きたねーぞ!技を使うなんて」
眼前に剣先を向けてエヴァリストは言った。
「油断する方が悪いな」
二人の暗黙の了解で昔の技を使うことは殆ど無かった。どこに眼があるか分からないからだ。
「過去からは逃れられない。私は昔の事を忘れた訳じゃない」
エヴァリストは剣を放り投げ、膝を突いたアイザックに手を差し伸べた。
アイザックは差し伸べられた手を取らずに自ら立ち上がる。
「オレだって忘れるものか」
叫ぶように言い放つ。
無言で見つめ合った二人だが、アイザックはかぶりを振った後、苛々をぶつけるように剣を地面に突き刺した。
「じゃあな、エヴァ」
そう一言残して、アイザックは去っていった。
「-了-」
3385年 「丘の上」 

丘の上を駆ける少年が二人。
「待ってよ、エヴァ。城壁の外は危ないから行っちゃダメだって言われてるんだよ」
「平気さ!少しの間なんだから」
「だけど……」
「もういいじゃん。今はさ」
不機嫌な体を装うエヴァリスト。アイザックはばつが悪そうに頷く。
「わかったよ、エヴァ」
二人の関係は、領主の息子とそれに仕える使用人の息子。二人でいるときは友達としても付き合ってはいるが、もし怪我でもさせたらいけないと思い、気が気でなかった。
しかし、そんなことを気にするそぶりを見せること自体が、エヴァリストにとって気にくわないことだった。
丘を登り切ると、少年達の住む屋敷も含め町全体が見渡せる位置に辿り着く。
その中でも一際巨大な建物が彼等の住む場所だ。
「んー。やっぱりここからの眺めは最高だなぁ」
エヴァリストは大きく伸びをした後、草の上へ大の字になって空を見上げる。アイザックもそれに倣う。
やや退屈ながらも平和な時間。アイザックはそれが嫌いではなかった。
互いに何も喋らず、空と街を気ままに眺めながらゆっくりと流れる時間。
しかし、その時間は轟音と共に崩された。大地が揺れ、丘に散在する木々も大きく左右に揺れ続けているのが目に入る。まるで強風にあおられているかのようだった。
街の様子を確認しようとするも、あまりの揺れに立ち上がる事すら難しい。
アイザックとエヴァリストは座り込み、揺れが収まるのを待つ。
「何だ?」
「わ、わかんないよ」
揺れが収まり、ようやく街に目を向けるも、土煙に覆われて状況がわからない。
じっと目を凝らして土煙の中からうっすらと見えたもの。
それはアイザックとエヴァリストが見慣れた街並みではなく、瓦礫の山と化した家々の姿だった。
「父さん!母さん!」
矢も盾もたまらず街へ向かって走り出すエヴァリスト。
あまりの事に頭の中が真っ白になっていたアイザックも慌てて後を追う。
街の状況は丘の上から見えた異常に惨憺たるものだった。
多くの家屋が倒壊し、かろうじて残っている建物も明らかに危険な状態だった。
痛みを訴える声、助けを求める声が瓦礫の中から聞こえてくる。
様々な声に聞こえぬ振りをし、アイザックとエヴァリストは立ち止まる事無く走り続けた。
屋敷の周りには、衝撃による被害を免れた思われる人達が集まり始めていた。
人だかりを掻き分け、やっとの思いで辿り着いた先に瓦礫の山は無かった。
しかし、アイザックとエヴァリストの暮らしていた屋敷も無かった。
「そんな…」
予想だにしていなかった光景が現れ、アイザックは膝をつく。
諦め切れないエヴァリストは、群集に両親の所在を聞いて回る。
皆黙って首を横に振るだけで、誰もエヴァリストの聞きたい答えを言う者はいなかった。
屋敷のあった場所にできていたものは黒く昏い何か。それは少しずつ大きくなっているようにも見えた。
黒く昏い何かへ引き寄せているように、辺りに集まる人の数は増え続けている。
「渦だ……」
誰かが気付いた時には遅すぎた。渦の中から見たことのない生き物が次々と現れ始める。
緑色や青色の肌をした二足歩行の生き物。背丈こそアイザックやエヴァリスら子供達と大差がないが、瞳のない大きな目と尖った耳、手には原始的な武器…斧や鉈を持っていた。
ヒト型は成していても明らかに人間ではなく、この世界には存在しえない生き物に違いなかった。
人間達の姿を認めると、てくてくてくとゆっくり近付いてくる。その様子には不思議と愛らしさが感じられ、目が離せず、その場を逃れようとする者はいなかった。
人だかりの前まで辿り着き立ち止まると、口元をつり上げ最前列に居る人間を見上げる。
それを友好的な態度と判断してしまった群衆の一人が歩み出て、視線の高さを合わせるためにしゃがみ込んだ。
子供をあやすように笑みを浮かべ、手を差し伸べる。
しかし、その人物が次に出したのは挨拶や歓迎の言葉ではなく、臓物と大量の血液だった。
地面に半身が転がり、残った体も静かに倒れる。小人が持つ武器は赤く染まっていた。
それを間近で見た者の上げた悲鳴で群集は目を覚まし、渦と小人から少しでも離れようとした。しかしパニックを起こして不可解な行動をとるものも多く、思うように移動できない。
一部の大人達は瓦礫から取り出した鉄棒や角材を手にとって小人へ攻撃を試みたが、その素早さと力は常人が対抗しうる域ではなく、悲鳴と血の量が増える結果にしかならなかった。
「アイザック!何ボケっとしてるんだ。逃げよう!」
混乱の中、呆然と佇むアイザックの肩を揺すって移動を促すエヴァリスト。
人混みに揉まれながらも比較的損傷の少ない家屋を見つけ、そこに身を隠した。
「大丈夫。レジメントがきっとすぐ助けに来てくれるよ」
小声でアイザックを励ますエヴァリスト。連隊とだけ呼ばれる、渦と戦う英雄達。ニュースや本の中でしか知らない存在だが、今はそれにすがるしかなかった。
いつしか辺りから悲鳴と怒号が消え、瓦礫を踏みならす音だけが響くようになっていた。
とうとう足音が身を隠している家屋の前で止まる。もう逃げ場は無い。目を閉じ、その時が来ない事を祈り続けた。
ドサッという音と共に生温い液体がアイザックの体を包む。
(エヴァ!)
次は自分の番だと恐怖に怯え、より体を強張らせる。
「大丈夫か、坊主」
恐る恐る目を開くと、そこにあるのは小人の死骸。隣にいるエヴァリストは無事だった。
体の震えが止まらず喋ることもままならない。首を縦に振り、自身の無事を助けてくれた男へ伝える。
「家族は?」
今度は横に。
「ここに留まっていては危険だ。ついて来い」
「は、はい」
ようやく出せた声はとても弱々しいものになっていた。
助けてくれた男達の乗る浮遊艇から、変わり果てた故郷フォレストヒルを一望する。
眼下に広がる光景は信じがたいものだった。ほんの少し前、丘の上から見ていた綺麗な街並みはどこにもない。
屋敷がない。学校がない。公園がない。パン屋もない。時計屋もない。花屋もない。鍛冶屋もない。
ただ、異界へと繋がる闇が渦巻いている。
もうあの場所に戻ることはできない。帰る場所はない。
アイザックとエヴァリストは事の重大さを改めて思い知らされた。
「ミリアン、この子達はどうしますか」
浮遊艇の中で眠りについてしまったアイザックとエヴァリストを指しながら、部下が隊長に判断を仰ぐ。
「このままじゃ避難キャンプ行きだな。他に身寄りがあればいいが」
身寄りのない子供が避難キャンプで生きていくのは厳しかった。
「まあ、慣れればレジメントに来るのも悪くはない。たしか、お前もそうだったよな。ベルンハルト」
レジメントには故郷が渦に飲み込まれてしまったが故に参加したメンバーも少なくない。
声を掛けられた戦士は剣を肩にかけ瞑目していた。二人を助けた男だった。
「もしそうでも、選ぶのはこの子らさ」
そう言ってまた、ベルンハルトは瞑目した。
―了―
3398年 「決別」 
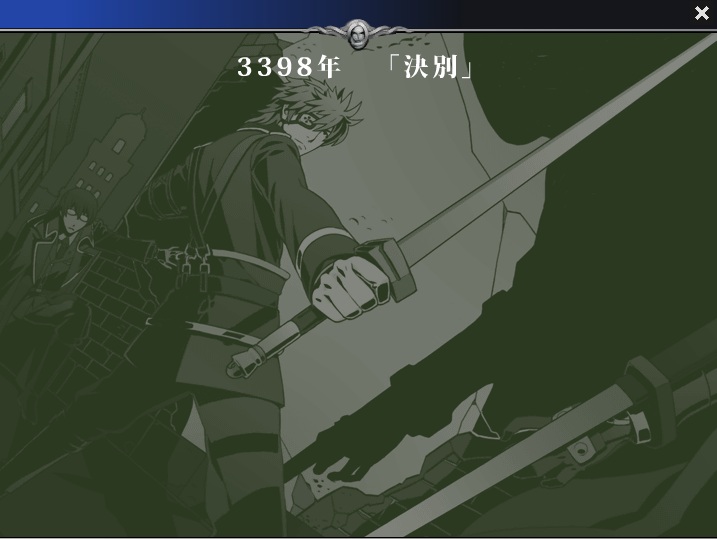
構えていたライフルを降ろし、アイザックはエヴァリストと刺客の間に素早く割って入った。
遠巻きに自分の連れた兵士達がいる。アイザックは微動だにしない仮面の男の瞳を見つめた。
その瞳に動揺を感じている様子は無い。アイザックはこの男の次の一手が読めなかった。
自身の状況をかなぐり捨ててでも目的を達するのではないか、と直感していた。
緊迫した一瞬の後、仮面の男は身を離すと闇の中に走り去っていった。
追撃しようとする兵士を手で押しとどめる。
兵士達に直接理由を言うことがなかったが、小さく、呟くように吐き捨てた。
「無駄死にすることはない」
エヴァリストが刺客に襲われて数日。現在は一命を取り留め、帝國最大の病院にいた。
もはや帝國内でも大きな力を持ったエヴァリストの元には、日夜大勢の見舞客が訪れ、医師が一部の見舞客を断るほどだった。
そのような状況の中、アイザックはエヴァリストの護衛のために次の間に詰めていた。
「本当に大丈夫なのですか?エヴァリスト」
「問題ありません。すこし大げさに報道されているだけです。たいした怪我ではありません」
「そう、よかった。もしあなたに何かあったら私は……」
扉の影に立つアイザックの耳に、エヴァリストとアリステリアの会話が漏れ聞こえてきた。
太陽なとうの昔に姿を消し、外では虫が秋の訪れを告げていた。
見舞客の姿は既に無く、現在は皇妃アリステリアがひとりエヴァリストの元を訪れていた。
皇妃がお忍びであれ、わざわざ臣下を見舞うなどというのは前代未聞だったが、
それは二人の関係がすでに帝国の深奥でも認められていることを表していた。
二人の会話が続く中、アイザックはアリステリアの護衛の人数、配置を窓と廊下から確認していた。
お忍びのため大げさではないが、かなりの人数が配置されていた。
やがて、アリステリアが名残惜しそうに部屋を去ると、エヴァリストが大きな溜息をついた。
その溜息を合図に、アイザックは部屋に入る。
「……ようやく姫のお帰りか。偉くなると、怪我をする事もできねえな」
アイザックの皮肉に、エヴァリストは苦笑を浮かべた。
「すまんな、警護のためにわざわざ詰めてもらって。だが、ここならもう大丈夫だろう。元の仕事に戻ってくれ」
「本気で言ってんのか?」
アイザックはエヴァリストのベッド脇に座った。
「どういう意味だ」
「お前は、インクジターどのが俺達を見逃すとでも思っているのか?」
「あの時は油断したが、もう新しい警護計画を立てさせた、二度目はない」
「そんなものは無駄だ。知ってるだろう、相手は俺達と同じ力を持ってる。本気を出せば何だってやれる」
「私達がやってきたように?」
「そうだ」
「買いかぶりすぎだな。所詮は一人の騎士にすぎんよ。あらかじめ分かっていれば防げる。あいつらのチャンスは一度だけだった」
「お前、誰がインクジターをここに呼んだか、見当はついているのか?」
「エンジニアの手は長い。それに私は目立ちすぎた。ただ、リスクは勘案済みだ」
「オレは帝国の人間がお前をはめたと思ってるぜ」
「いや、それはない。状況は掌握している」
「ずいぶんな自信だが、お前はオレがいなきゃ死んでたんだぜ」
少しアイザックは声を荒げて言った。
「感謝は忘れていないさ。何をイライラしている?」
アイザックはしばし沈黙した。そして、眼を逸らして絞り出すように言った。
「そろそろ潮時じゃないのか」
「何が潮時なんだ?」
眼鏡の奥の眼を細めて、エヴァリストは聞き返した。
「ここにいるのが、だ」
アイザックの言葉は、いつになく真剣な調子だった。
「傷を治すまではこの部屋にいてもいい。だが治ったら、ここを出よう。オレ達だけなら、どこへだっていける、なんだってできる」
「今だって何でもできるさ。何を恐れている」
エヴァリストは冗談を聞き流すように、軽く肩をすくめてみせた。
「オレは恐れちゃいない。何度も死んだも同然の目に遭ってきた」
アイザックは声量を抑えず、畳み掛けるように語る。
「だが、このまま二人がばらばらにいたら、必ず仕留められちまう。今の俺達は狩る側じゃない、狩られる側だ。不利すぎる」
だがエヴァリストは、アイザックの言葉に耳を傾けなかった。
「らしくないな、アイザック。もう少しで私達は全てを得られるんだ。落ち着け」
「全てを得られる?得てどうする、何が変わるんだ。オレが欲しいのは権力でも富でもない……」
立ち上がったアイザックにエヴァリストは諭すように言う。
「お前の気持ちは分かった。いつも面倒を掛けているのは私の方だ。すまないと思ってる」
そしてアイザックを見つめ、はっきりと答えた。
「だが、これは私の人生だ。私の賭だ。今、降りるわけにはいかない」
「もし納得がいかないのなら、ここで終わりだ」
アイザックはエヴァリストの言葉を聞いて、少し俯いた。
そして絞り出すように答えた。
「そうか、わかった……ここで終わりにしよう」
呟くようにアイザックは言った。
沈黙が部屋を包んだ。
「……残念だ。今まで世話になったな」
黙っていたエヴァリストは、握手の手を差し伸べながら切り出した。
アイザックはポケットに手を突っ込んだままで、握手には応じない。
「エヴァ、お前はいつも冷静に、そうやってうまくやってきた」
アイザックの声は少し震えている。
「これからもうまくやっていけよ」
「じゃあな」
アイザックは視線を合わさず、病室から出て行った。
アイザックが出て行った後も、その扉をエヴァリストは暫く見つめていた。
そして、眼鏡を外すとゆっくりと目を閉じ、電灯を消して眠りについた。
アイザックは護衛の敬礼を無視して、早足で病院から飛び出した。
ふと振り返って、窓から漏れる明かりを見つめた。
その明かりの元は、先程までいたエヴァリストの病室だ。
まだ逡巡する自分に腹が立った。
エヴァリストに怒ってはいなかった。
自分の弱さに腹が立っていた。
あいつは変わっていない。
変わったのは自分の方だと言い聞かせた。
窓を見つめていると、護衛が声を掛けてきた。
「どうかしましたか?」
「……なんでもない、ちょっとした思い違いのようだ」
護衛にそう言って向き直ると、アイザックは二度と振り向かず、黙々と歩いていった。
-了-
3398年 「仮面」 
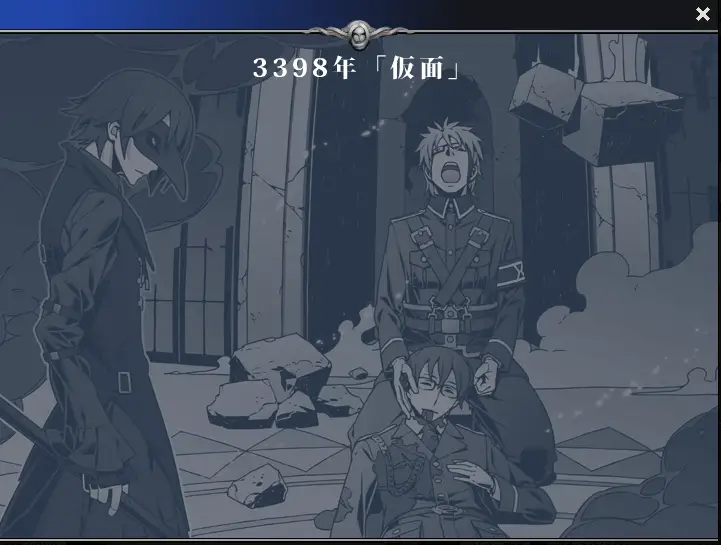
「こんなところか」
荷物を纏め終わったアイザックは呟いた。必要最低限な物だけを荷物にしたので、部屋の様子に変わりは無い。軍用のダッフルバッグ一つを担いで玄関を出た。
エヴァリストとの別離の後、暫くは軍務を続けていた。
除隊の手続きを踏んで国を出ることも考えたが、この国に戻ることも無いと思い直し、黙って抜け出すことにした。
そして休暇の申請が通ったこの日、帝國を出ることにした。
「大尉、お疲れ様です。こんな遅くにお出掛けですか?」
宿舎のMPから声を掛けられる。
「やっと取れた休暇でな。オレはせっかちなんだ」
適当に言葉を返し、宿舎を出た。
尉官の軍服のままなら帝國内を自由に動ける。街を出てから軍服を脱げばいい。 夜の街を一人で歩きながら、馴染みの酒場に寄って最後の酒を呷ることにした。ひなびた酒場で、軍関係者が現れることも少ない場所だ。
「親父、ここをやって何年になるんだっけか?」
七十は過ぎているであろう老主人に、アイザックは聞いた。
「四○年さ。この通りのボロだ。もう潮時かもしれんな」
「酒場を始める前は何を?」
「色々さ。 街を潰されてから色んなところを回ったよ。人夫もやったし、アンタと同じ兵隊だってやったよ」
「そっか……酒場をやるのは楽しいか?」
「別に。まあ、他人にこき使われるよりはマシってだけだ。何にせよ、働いて金を稼ぐってのは面倒なもんさ」
話し好きでない偏屈な主人だったが、アイザックはここが気に入っていた。
「でも、ここまで続けられたんだろ?」
「そうだな。とりあえず生きてはこれたよ。巡り合わせだね」
「巡り合わせか……ありがとう、世話になったよ」
金を置いてアイザックは立ち上がった。
「ああ、またな」
主人は金を受け取ると、素っ気なくそう言った。
店を出たアイザックは、あまり酔えていないことを自覚していた。
街道を将校らしき人物の乗った馬車が通り過ぎていった。一瞬 エヴァリストかと思い目で追ったが、無関係の人物だった。
自分の行動に苦笑しながら、街を出るために駅に向かった。
ファイドゥの外郭に辿り着くためには、列車を使うのが一番早い方法だった。夜中を過ぎた駅舎に人影は無かった。最も早い列車は明け方に来る。それまで二時間は過ごさなければならない。
ベンチにダッフルバッグを置き、枕代わりにして横になった。
これから何をすべきかを考えていた。自分にできることは戦うことだけだった。若い頃にレジメントに入り、それから帝國で軍人として生きてきた。身体を鍛え、与えられた任務を決められた通りに遂行してきた。
目的があり、整えられた世界をアイザックは気に入っていた。 自身は品行方正なタイプではなかったが、それでも、軍務や任務をこなすことには充実があった。戦いの緊張も心地よかった。
「目的の無い戦い、か」
目的は全てエヴァリストが決めていた。幼い頃から一緒で、それに何の不満も無かった。ただ隣にいて、同じ目標を見て進み続けることが、今までの人生だった。
一人になった今、初めて己を振り返っていた。 ホームに貨物列車が入ってくる。大きな音を上げて通り過ぎて行く。
静寂が戻った。誰もいない駅舎にはアイザック一人だけだった。まるで、世界にただ一人取り残されたような気持ちになった。
アイザックは眼を瞑った。列車が来るまで眠ろうとしたが、眠れなかった。そして、エヴァリストとの過去を思い出していた。初めて会った時の事、レジメントでの日々、帝劇での戦いの日々。
自分を形作った過去の日々を、出来るだけ詳細に思い出そうと していた。
暫く意識を過去に戻していたアイザックの耳に、微かな足音が響いた。目を開け、身体を起こす。
ホームに人影は無い。
「誰だ?」
誰何の声に反応して、赤黒いコートを着た男が柱の影から現れた。その顔は仮面に隠されている。アイザックは反射的に銃に手を掛けた。
「インクジターか?」
「いや、我々は違う」
こちらに進んできた男は確かにインクジターではなかった。しかし、その姿にアイザックは心当たりがあった。
「皇帝のカストードだな……」
自分の逐電が嗅ぎ付けられたのか。いや違う。一介の兵の動きに皇帝付きのカストードが出向く筈は無い。そうアイザックは 思い直した。
「そう、皇帝の代理人たるカストード。我々には名前も個人も存在しない」
「オレなんかに何の用だ?穏やかな話じゃなさそうだが」
「お前とエヴァリスト、共にどこからやって来て、どんな力を持っているのかは調べさせてもらった」
「そうか。なら、オレがお前を殺してでもやることはやる人間だってわかってるな?」
アイザックは立ち上がった。
「そう熱り立つ必要は無い。 我々は話をしに来たのだ」
「別に話なんか無いぜ。オレは帝國から出るんだ」
面倒になったことはわかっていたが、ここでこんな奴に構いたくはなかった。だが逆に、いっそこのカストードと切り結び、 大々的な逃走劇をファイドゥで繰り広げるのも悪くない。そんな自暴自棄な気分にも乗り掛かっていた
「貴様らレジメントの生き残り、昔の名前で呼ぶなら「聖騎士」の力は惜しい。復活する皇帝のためには、是非ともその力が必要なのだ」
「皇帝の復活か。悪いが、もう興味は無いね」
「だろうな。 だが、エヴァリストの命には興味がある筈だ」
「……もう、あいつとは関係ない」
「ならば明日の夜、奴が死ぬとしても全く興味は無いというわけだな」
「どういうことだ?」
「インクジターはエヴァリストの行動を押さえた。 明日、襲撃を実行するだろう」
「オレにそれを伝えてどうしたい? エヴァを守りたいのか、皇帝は」
「ふふふ、皇帝は誰かを守ったりはせぬ。博く者を見定めているのだ」
「意味がわからないぜ」
「これは取引だ。インクジターは私の下に来ている、そしてお前達も私の下に来ることになる」
「オレはお前らと取引などしない」
「かもしれん。だが、お前は我々に傅くことになる」
「くだらねえ」
アイザックは銃を抜きざまにカストードを撃った。何の回避も、防御もせずに、カストードは胸を貫かれて倒れた。
「ふん、とんだ買い被りだったな。木偶以下だ」
倒れたカストードの傍まで寄って死体を蹴った。
「もう、どうなったって構やしねえ……」
そう呟いて、アイザックはファイドゥの街に戻った。
次の日、エヴァリストの行動を追ったアイザックは皇妃の住む尖塔の前にいた。誰かを追跡するのには慣れていた。
襲われるとしたらここだと勘付いていた。カストードを殺した事が騒ぎになっていないのは不審だったが、今はエヴァリストを守ることが先決だと思っていた。
エヴァリストが中に入って三○分程経っていた。
塔は巨大だったが入り口は少ない。ここで見張りを続ける選択肢もあったが、既にインクジター達が塔に入り込んでいる可能性もある。意を決して中に入ることにした。
その時、巨大な爆発音と共に塔の中層部分で爆発が起きた。
建物の瓦礫が通りに降り注ぐ。すぐに通りは大騒ぎになった。警備隊の怒号や飛散した破片に当たった者の叫び声が響く。
「エヴァリスト准将の警護の者だ。入るぞ!」
「危険です、まだ爆発が――」
アイザックは身分を告げ、警備の兵を押し退けて中に入った。
塔のロビー部分に人は殆どいなかった。塔は二十階程の階層になっている。爆発したのは十二階層目だったのを外から確認している。エレベーターは当然止まっていた。
最上階にある皇妃の居室を目指して、アイザックはロビーの左端にある階段を駆け上った。
十二階の爆発したフロアを過ぎたが、幸いにも煙は階段に来ていなかった。扉が無事だったのだろう。しかし、階段が無事でも火の回りは確認できない。
十八階に辿り着くと、そこで階段は終わっていた。警備の関係上か、この階段は皇妃の居室に続いていないようだった。中央のフロアに出て別の経路を通らなければならない。アイザックは扉を開け、皇妃の住むフロアに入った。
フロアには煙が充満していた。エレベーターシャフトから煙が回ったようだ。袖を口元に当て、身体を低くして進む。
すっと、アイザックの前を赤い姿の男が通り過ぎるのが見えた。一瞬体が固まるが、相手が誰なのかはわかっていた。路地でエヴァリストを襲撃した仮面の男だ。奴の足下には警備兵達が転がっていた。幸い、まだこちらには気付いていないようだ。
銃を抜き、構えた。
ゆっくりと仮面の男の後を追った。
奴はまだ警備兵を探しているようだった。フロアを掃除するかのように、ゆっくりと見て回っている。
仮面の男は扉を開け、警備室の一つに入ろうとしていた。アイザックは仮面の男が扉に手を掛けたところを見計らって激しく銃を撃ち込んだ。仮面の男は全ての弾を背中の急所で受けたが、何事もなかったかのように振り向いた。
「ちっ、化け物め」
アイザックは銃を仕舞い、剣に手を掛けた。それと同時に、仮面の男も両手の仕込み剣を出した。剣に持ち替えたアイザックは、煙を避けるために別の部屋に飛び込んだ。
仮面の男の出方を部屋の中で窺った。急がなければならないが、奴と正面で斬り合うのは面倒な事だと知っていた。
(一撃だ。一撃で仕留めるんだ)
耳を澄まし、相手の動きに全神経を集中した。
奴がゆっくりとこちらに近付いてくる。部屋の壁の向こうで止まったのがわかる。
次の瞬間、激痛がアイザックを襲った
壁から仮面の男の剣が飛び出し、アイザックの肩を斬り付けていた。
「くっ!」
思わず声を上げて壁から距離を取る。自分の迂閣さに悪態をつく間もなく、仮面の男が部屋に躍り込んできた。
インクジターの赤いマントをなびかせて、低い姿勢のまま斬り掛かってくる。その特異な剣の軌道をアイザックはすんでの所で避け、仮面の男の頭に剣を振り下ろした。確かな手応えがあった。
「遅いぜ!」
しかし、その明らかな致死性の一撃を喰らっても仮面の男は立っていた。マスクが外れて床に落ちる。緑色の液体が頭蓋から溢れ、その髪と顔を濡らしていた。 「お前は!?」
アイザックはその顔に驚きを隠せなかった。だが次の瞬間、仮面の男の身体から発せられる光に危機感を感じたアイザックは、部屋の外へ飛び出した。
仮面の男の爆発に押し出されるように、外の壁べとアイザックは叩き付けられた。
「クソッ……」
悪態をつきながら、アイザックはふらふらと立ち上がった。
「悪い冗談が続くぜ……」
アイザックは中央の階段を上がって、エヴァリストがいる筈のアリステリアの居室に向かった。
アイザックは既に事切れたエヴァリストの隣に噂っていた。彼は泣いていた。子供のように声を上げていた。
階下で何度も爆発音がしていた。そして、この部屋にも煙が回ってきていた。
それでも、アイザックは俯いたままエヴァリストの傍から動こうとはしなかった。
「どんな気分だ?」
聞き覚えのある声に顔を上げる。そこには昨晩会ったカストー ドが立っていた。
「化け物め……何の用だ」
「昨晩の話、考えてもらえたかな?」
「うるせえ!!」
剣を持ち上げ、カストードに投げつける。カストードは避けもせずに剣に貫かれ、絶命した。
しかし、もう一人のカストードが別の場所から現れ、アイザックにこう言った。
「ここもすぐに火が回る。お前もここで死ぬだろう」
「だからなんだ?亡霊め。 何度だって殺してやるぞ!」
アイザックは子供のように泣きながら大声を上げた。
「アイザックよ、死を乗り越えることができるとしたら、お前は何を賭けることができる?」
カストードの言葉が終わると同時に、火の回った塔は大きな音を立てて崩れ始めた。
「-了-」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ