ディノ
3384年 「任務と違和感」 
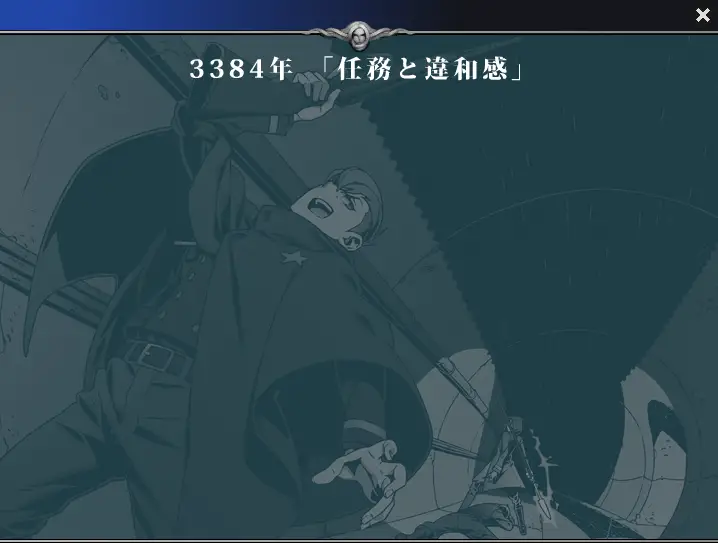
連隊施設地下の下水道には霧が漂っていて、陰気な感じだった。
水が流れる音に混じって、施設の方向から足音が聞こえてくる。
それと同時くらいに、エンジニア謹製の時計に似た機械が小さなランプを明滅させる。イデリハからの合図だ。ってことは、そろそろこっちに来る。
その合図を見た俺様は、殺傷能力の低いテイザーライフルを構えた。当たると弱電流を流す電撃弾が込められている。
足音が大きくなった。テイザーライフルを構えると、安全装置を解除して狭い整備用通路に出る。
イデリハのいる地点からここへは完全な一本道で、そして俺様の10アルレ先には外に出るための梯子がある。
そっから先は施設の外。連隊司令部の管理が及ばない場所だ。
めんどくせー手続きやら許可やらをすっ飛ばして外へ出るには、この手段を使うのが唯一だ。
連隊側の出入り口は司令部が管理してるけど、こいつは下水道だ。あちこちに雨水や溶けた雪なんかを排出するための穴が開けられてる。訓練所の広場にも人が落っこちそうなでっかい穴があって、そこからここへ入るフトドキモノがたまーにいたりする。
連隊施設の外に繋がる場所はこの先にしかない。だから、ここを通ろうとする奴はこの狭っ苦しい整備用通路に必ず入ってくる。
間近に迫る足音。そして濃くなっていく霧。
「はい、そこまで。こっから先は通っちゃダメなんだぜ」
足音が止まる。俺様の声にビックリしたのか、地面を擦るような音さえ聞こえない。
「動くなよ、動いたら撃たないといけねーんだから」
テイザーライフルの銃口を足音の方向に向けたまま移動する。再び足音が聞こえ、俺様に近付いてきた。警告が無視されたのなら仕方がない。テイザーライフルを撃つ。霧で視界が悪いから照準は適当だ。
とりあえず、イデリハに当たらないことだけは祈っといた。
銃声にも怯まずに足音がどんどん近付いてくる。そう思ったのも束の間、足音が俺様の背後に移動した。振り向くと、体格のいい男の影が走っていくのが見える。
「イデリハ!」
「わかっちょる」
俺様の言葉に応えるように霧が晴れた。同時にイデリハが男の眼前に飛び出す。
「なん!?」
呆気に取られた男は、イデリハの電磁槍に一突きされておとなしくなった。
イデリハの使う槍も特別製。殺傷能力は無いけれど、槍頭から電流を相手に流して動けなくするシロモノだ。
電撃で動けなくなった男を縛り上げ、額にこれまたエンジニア謹製の聖騎士の力を抑えるシールを貼り付ける。
「ふー、終わった終わった」
「放……なせ!」
電撃を浴びてなお、男は藻掻いた。それなりにダメージを受けた筈だけど、さすがは歴戦の戦士。気絶まではしなかったようだ。
「ダメダメ。ここでお前を放したら、俺様が怒られちゃう」
「くそっ……くそっ!」
憤慨してるこの男の名前はアスカム。B中隊所属で、短い距離を瞬間移動する能力を持っている。さっき俺様をすり抜けたのがそれだな。《渦》のコア回収ポイントが要塞化されている時とかに絶大な力を発揮していた、と資料に書いてあったっけ。
だけど力に溺れて、休暇の度に都市に出向いちゃー、この力で犯罪を重ねていたらしい。
急に羽振りが良くなりゃ、そりゃ誰でも不審に思うわけだ。
で、速攻で司令部にバレて謹慎させられたらしいんだけど、謹慎が解けたとたん、今度はこうやって下水道を通ってちょくちょく抜け出してたとかなんとか。
こうなったらどうしようもないってことで、俺様達にアスカムの捕獲命令が下ったってわけ。
らしいらしいばっかりなのは、俺様とイデリハは捕獲命令が出るに至る話を直接聞いたわけじゃないから。あくまで資料として知ってるってだけ。
「さ、行くぞ」
アスカムはイデリハに立たされると、おとなしく来た道を歩き出した。
電撃で痺れている上に聖騎士の力も使えないとなれば、そりゃおとなしくするしかないわな。俺様でもそうする。
下水道の連隊施設側の出入り口を入ったその先に、一つの小部屋がある。
中は会議室くらいの大きさで、簡単な執務用の机と椅子が備え付けられている。
この部屋は連隊の中でも俺様とイデリハ、他はミルグラム副長くらいしか知らない部屋だ。
「ミルグラム副長、アスカムを捕らえました」
「そうか、わかった」
中にいたミルグラム副長にイデリハが報告する。
縛り上げていた縄越しに、アスカムがびくっとなって固まった感覚が伝わってきた。ミルグラム副長が出てきたことで、自分がこれから何をされるのか自覚したんだろう。
ミルグラム副長がどこかへ通信を始める。通信が終わってすぐに、赤くて動きにくそうな服を着た男達が入ってきた。
連隊の主な出資者である導都パンデモニウムからの使者だとか。こういった犯罪を繰り返す戦士から聖騎士の力を除去するために、パンデモニウムへ連れて行くことになってる。
「では、宜しくお願いします」
赤服の男達は無言で俺様からアスカムを縛っていた縄を受け取る。
「ミルグラム副長!もうこんなことはしませんから!」
「その言葉は謹慎中に何度も聞いた」
「い、嫌だ……。助けてくれ、頼む!なあ、お前らからも何か言ってくれ!!」
俺様とイデリハは顔を見合わせると、すっかり怯えた様子のアスカムに視線を移して肩を竦めた。
「そりゃ無理な相談だな」
「ディノに同意じゃ」
冷たいようだけど、司令部から何度も何度も忠告を受けて、謹慎までさせられたのに、それでも一向に改善しなかったこいつの自業自得だ。今さら助けてくれなんてムシが良すぎるってもんだぜ。少なくとも俺様はそう思った。イデリハも似たような反応をしてたから、多分同じ考えだろう。
赤服の男達は騒ぐアスカムをよそに、無言で奴を引っ張って部屋を出て行った。
アスカムの「許してくれ!」とか「嫌だ!」とか言う声も、すぐに聞こえなくなった。
「お前達、ご苦労だった。今日はもう戻って構わない」
そう口にすると、ミルグラム副長は重い溜め息を吐いた。こんなミルグラム副長を見るのは何度目だろうなぁ。
世界を救わんと集まった仲間が聖騎士の力に目覚め、その力に溺れてどうしようもないところまで落ちてしまったのを見るのは、かなり辛いんじゃないかと思う。
特にミルグラム副長はスターリング連隊長の副官的な立場の人、つまり連隊ができた頃からいる人だし、連隊への思いは誰よりもあるだろう。
俺様とイデリハは顰めっ面のミルグラム副長を残して、住居として宛がわれている部屋へ戻った。
それから暫くして、また犯罪を重ねる戦士を捕獲して例の小部屋に連行すると、そこにはミルグラム副長の他にD中隊のミリアン中隊長がいた。
「あれ?どうしたんスか、ミリアン中隊長」
「スターリング大佐に代わり、ミルグラムが一時的に連隊長代理となって連隊を率いることになった」
スターリング大佐がいなくなって数ヶ月、とうとうこの時が来た。おそらくこのままミルグラムが連隊長の座を引き継ぐのだろう。そうなれば、この任務の指揮を執るような暇は無くなる。別の責任者が来るのは当然といえば当然だった。
「よってお前達、今後は俺の指揮の下で任務を行ってもらう」
「任務の内容に変更は?」
「特に変わりはない。今までと同じようにしてくれ」
「わかりました。ミリアン中隊長、宜しくお願いします」
「宜しくお願いします」
俺様とイデリハは同時くらいにミリアン中隊長に頭を下げた。
ミリアン中隊長に指揮が替わっても、俺様達のすることに変化はなかった。
だけど数ヶ月が経った頃から、赤服の男達が次第に姿を見せなくなっていた。替わりに、テクノクラートのラームとかいうお偉いさんとその部下が姿を見せるようになった。
そして今度はそのラームの部下らしい奴らが、捕まえた戦士を何処かへと連れていった。
「なぁ、ミリアン中隊長。こいつを何処に連れて行くんだ?」
「オイ……いや、俺も気になっています。ミリアン中隊長」
ふと思い立ち、俺様はミリアン中隊長に尋ねた。イデリハも同様らしい。
「……パンデモニウムにある施設だ。そこで特殊な更正プログラムを受けることになっている」
ミリアン中隊長はぶっきらぼうにそう答えた。
「そんなこと可能なのか?前に捕まえた奴らは誰も帰ってきてないぜ」
赤服の連中に連れて行かれた戦士達は、皆帰ってこなかった。
聖騎士の力を奪われて何処かへ放逐されたと聞いている。
「君達が知るほどのことではないよ。パンデモニウムの方針転換はよくあることだ」
ミリアン中隊長が何か言おうとする前に、ラームが答えた。ラームの言ってることは尤ものような気がしたが、違和感がないわけではなかった。
「ラーム技官の言うとおりだ。お前達が気にするほどのことではない」
二人の言葉はやんわりとしてたけど、変に強制力がある言葉だった。任務を黙って遂行しろ、そう言われている気がした。
「そうスか。それならいいんです」
「妙なことを聞いて申し訳なか……ありませんでした」
「納得してくれたのなら、それで問題はないよ」
「さあ、お前達も疲れただろう。今日はもう戻っていい」
ラームとミリアン中隊長に促され、俺様達は居住区へと戻った。
「なあ、イデリハ」
居住区へ戻って一息つくと、俺様は思ったことをイデリハに聞いてみることにした。
「なんじゃ」
「俺様達、この任務についてどれくらい経った?」
「二……いや、三年じゃ」
「結構長いことやってたのに、急に変えられるもんなのかな?」
「わからん。けんど、オイ達は従うしかなか」
「……ま、行く当てがあるわけでもないしな」
連隊を出たところで、俺様とイデリハは路頭に迷うのが目に見えていた。
イデリハは故郷の村を《渦》によって失っていたし、俺様のいたところは革命が終わったばかりでゴタゴタの真っ只中らしく、とてもじゃないけど帰れるような状況じゃない。
何より、ミルグラム副長にはE中隊があんなことになっちまった時に救われた恩があった。
今の状況はマシなんだ。
俺様はミリアン中隊長やラームが匂わせる違和感を頭の隅に追いやると、次の任務に備えて武器の整備を始めることにした。
「―了―」
3381年 「全滅」 
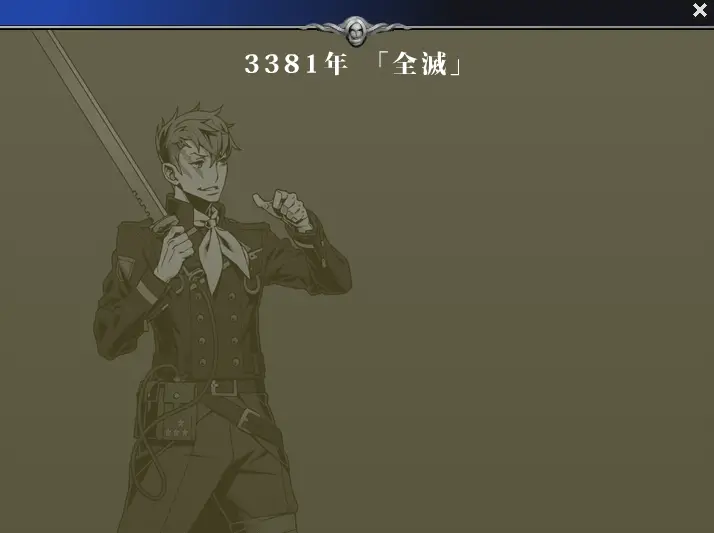
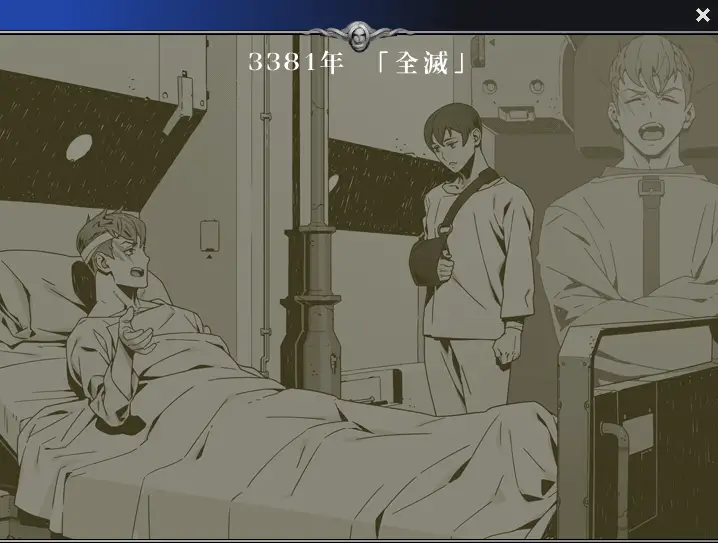
ジ・アイから命からがら逃げ帰った俺様は、帰ってきた早々、施設にある医療棟にぶち込まれた。
さしもの俺様もジ・アイでの戦闘でかなりの傷を負い、結節点《ノード》を出た辺りからの記憶も無い。
医療棟にぶち込まれてから一日かそこらで目は覚ましたけれど、結構な重傷だった所為なのか、暫く頭がぼーっとしてた。
周囲も妙に慌しく、マキシマスの情報なんかも入ってこなかった。
目を覚ましてから一週間くらいして、D中隊のミリアン中隊長が治療中のイデリハを伴って俺様に会いに来た。
「マキシマスは助からんかった」
故郷の言葉を出さないようにと普段から無口気味なのに、それに輪を掛けて無口になっていそうなイデリハがやっと一言、それだけを言葉にした。
「そっか……」
俺様とリーズがあいつを発見した時には、既に瀕死の状態だった。
コルベットにあった応急手当用の装備じゃ完全な止血もままならなかった。一度は意識を取り戻したけど、その時はもう呼吸すら怪しくて。
わかってたんだけどなー……。でも、少しだけは意識があったから、もしかしてって希望があったんだけどなー……。
改めてあいつの死を突き付けられて、俺様も俯くしかなかった。
「E中隊は全滅という形で処理されることになった」
イデリハに代わり、ミリアン中隊長が連隊で起きていることを 説明し始めた。
ジ・アイから『生きて』帰還できたのは俺様たった一人。ローレンスを連れて戻ると吠えたリーズは、結局帰ってこなかったそうだ。
「E中隊の全滅により、連隊の組織全般も再編される。お前達も治療が終了次第、どこかの部隊に配属してもらうことになるだろう」
前の作戦で重傷を負ったE4小隊の連中も、復帰にはまだ時間が掛かるらしい。
「そう、ですか」
E中隊は実力者や所謂『聖騎士の力』を発現させた連中を集めた、ジ・アイ攻略作戦のために用意された特別な部隊だった。
それだけに連隊全体からの期待も大きかったし、難しい計算はわからないけど、作戦成功率も高かったとかなんとか。
確かにジ・アイで竜を倒し、コアの確保までは完了していた。それは俺様がこの目で見てる。そこまでは確かに成功していた。ただ、それ以降に起きたことが想定外だった。
コアが回収できないという異常事態、竜の復活と反撃。アーセナルキャリアの破壊。それも全部この目で見た。
「それから、エンジニアがジ・アイ内部のことをお前から直接聞きたいそうだ。当然、カウンセリング結果に問題が無ければだが」
ミリアン中隊長の表情は消えている。まあ、俺様の立場に立ったときのことを考えてくれてるんだろう。
俺様も今は何となく大丈夫そうだけど、いざ喋る段階で駄目になる可能性はゼロじゃない。
それにだ、俺様がエンジニアに話す内容は、おそらく連隊の歴史の中でも最も凄惨な失敗の報告だ。
「あー……。多分、大丈夫。です」
「無理はするなよ」
それから俺様の病室に、カウンセリングを担当するユーインっていうエンジニアが来た。カウンセリング担当っていうくせに、他のエンジニアと同じく無感動な感じの奴だけど。
カウンセリングが始まって一週間くらいした頃、ユーインがもう一人エンジニアを連れて来た。
そのエンジニアを、俺様は見たことがあった。
「アンタ確か、モニタリング調査の……」
「そうだ。今は作戦技官として作戦室に配属されている」
「ふーん」
去年だか一昨年だかに急遽E中隊に配属された、能力調査技官のヒネクって奴だ。
俺様とはあんまり関わりが無かったけど、運悪くこいつの調査中に『聖騎士の力』が発現したイデリハとローレンスはしつこく付き纏わられてた。それに、作戦中でも構わずデータとやらを取りたがったので、とにかく邪魔だった印象がある。
ジ・アイ攻略作戦の直前に行った部隊再編の時から姿を見せなくなったんで、てっきりパンデモニウムに帰ったと思ってたけど、何だまだいたのかって感想しかない。
「では、ジ・アイでお前が見たものを聞かせてもらう」
「はいはい」
「お前の証言はコルベット内に残されていた記録と照合され、正式な調査報告として作戦室に送られる。何が起きたか、できるだけ正確に話すように」
「話す過程で嘔吐感や頭痛など、身体に不具合が起きたらすぐに報告するように」
どっかに表情を置き忘れてきたようなエンジニア二人に囲まれ、俺様はジ・アイ攻略作戦の開始からコルベット内部で気絶するまでに起きた出来事を話した。
「コアの確保までは順調に見えた。けど、いつもなら余裕で回収が終わるくらいの時間が経っても、コアが回収できなかった」
「回収班はその時何を? 回収班の会話などは聞いていたか?」
「わかんねえ。コアを取り返そうとする竜人を退けるので手一杯だったから」
話してる最中は頭の中に靄が掛かったみたいになってて、時々映像のようなものが再生されてる感覚だった。
「これで全てのようだな」
特に気分が悪くなったりすることもなく、俺様はジ・アイ内部でのことを話し終えた。
「もう何もないぜ」
「この件について聞き取りを行うことは今回で終わりだ。暫く脳を休めるように。また、何か心身に不調を感じた場合はすぐに知らせろ」
ユーインは最後にそう言って、ヒネクと共に病室を出て行った。
「お前達は今日から一時的に研究棟の所属となる」
それから更に暫くの時間が過ぎて、俺様はイデリハ、ミック、バシリオの生き残った元E4小隊の面々と一緒に、再配属を待つばかりとなっていた。
だけど、治療が終わって晴れて復帰となった時、やって来たエンジニアが妙なことを口にした。
「はあ? 何言ってんだ?」
「俺達はエンジニアじゃない。何かの間違いでは?」
「お前達には後進の能力開発のため、研究棟で能力解析に協力してもらうこととなった」
「俺達は戦うために連隊に入ったんだ。研究だか何だかに協力する筋合いはねえぞ!」
血気盛んなバシリオがエンジニアに食って掛かる。
「話は最後まで聞け」
「何があるってんだよ」
「今回の措置は傷病者の復帰訓練プログラムを兼ねている。主任務は復帰訓練だ。その傍らで我々の研究に協力してもらう」
復帰訓練という言葉には、納得するしかなかった。俺様達は治療を終えたばかりの病み上がりだ。そんな連中が連隊の訓練や作戦にすぐ復帰できるかと言われれば、まあ無いわな。
医療棟をやっと出られた俺様達は、そんな事情で研究棟に一時配属となった。
だが、一ヶ月、二ヶ月と能力開発への協力と復帰訓練を重ねていくが、段々とエンジニアは俺様達に、協力というのも怪しい、実験みたいなことを強要し始めた。
「いい加減、俺達を部隊へ復帰させろ!」
バシリオがエンジニアに怒声を浴びせた。
復帰訓練のプログラムは、もう何も問題なくこなせる。若い連中を相手にする能力開発のための模擬戦も、以前と変わらずに戦える。調子は取り戻していた。
だけど、一向に部隊への復帰命令が下らない。もう俺様達も我慢の限界だった。訳のわからない薬の投与や、意味不明の体力測定なんかをやるのは復帰訓練でも何でもない。
「エンジニアじゃ話にならない。ヘルムホルツ中隊長やミリアン中隊長へ取次ぎをお願いします」
比較的冷静なミックがエンジニアに告げる。
「それはできない。お前達を施設から出すことは許可されていない」
「話が違う! どうなってるんだ!」
「お前達は聖騎士の力を完全に扱えるのだ。そんな貴重なサンプルを施設から出すことはできない」
奴らの主張はもうワケがわからなかった。エンジニア共は俺様達を実験動物か何かとして扱っているような口ぶりだ。
「ふざけんな! 俺様達は人間だ、サンプルだのなんだの、冗談じゃねえぞ!」
「オイ達は渦と戦うために連隊に入った。こげんことをするためじゃなか!」
「これだから地上の者は野蛮だというのだ。貴様らが死なぬよう尽力しているというのに、わざわざ死地に赴こうとするとはな。沈静ガスを噴射しろ。この者らを拘束する」
訓練室に煙が吹き上がった。抵抗する間もなく、意識が遠のいていった。
気が付くと、俺様は医療棟の病室にいた頃と同じようにベッドに寝かされていた。しかもご丁寧に拘束衣を着せられて。
エンジニアは俺様達を施設の外へ出す気は微塵も無いらしい。
イデリハもミックもバシリオの姿もない。でも、皆同じようにどっかに閉じ込められてるんだろうなと思った。
どれ位そうしていたのか。俺様は拘束されたまま寝て起きるを繰り返していた。トイレは何かよくわかんねー装置が全部処理した。食事を取ることはできず、点滴で栄養補充されるだけだ。
生かさず殺さずってのはこういうことを言うんだろうなって、ぼんやりと思った。
時間の感覚も曖昧になってきた頃、突然俺様は拘束衣を脱がされ、部屋から出された。
部屋の外にはミルグラム副長とイデリハ、ミック、バシリオがいた。
「ディノ!」
「お前ら、無事だったか!」
「これで全員だな。すまない、私が不甲斐ないせいで、お前達をこのような目に遭わせてしまって」
ミルグラム副長が頭を下げた。
「副長が謝ることないッスよ! 俺様をあそこから出してくれただけで感謝ですって!」
「そうです、副長」
「これでやっと連隊に復帰できます!」
「……いや、それはそうもいかないのだ」
「もう俺達は解放されましたよね?!」
「……解放は条件付きなのだ」
「じゃあ、俺様達はまた、エンジニアの変な実験に付き合わされるってことですか!?」
「いや、決してそれはない。お前達は私の直下に入ってもらい、聖騎士の能力を悪用する隊員の捕縛任務に当たってもらう」
「実験体にされるよりはマシですが、そんな奴らがいるのですか?」
ミックの言葉も尤もだ。そんな奴らがいたなんて、今まで聞いたことがない。
「今後も引き続き隊員は増強される。となれば、そういった悪意ある者が少なからず出ることは見越しておかねばならん」
「もしかして、俺達を施設から出さずに、という条件を満たすために?」
副長は無言だった。 他にも何か事情があるように見えたけど、それを言うことはなかった。
「私ができるのはここまでだった、本当にすまない」
ミルグラム副長は沈痛な面持ちのまま、俺様達に頭を下げ続ける。
副長は頭を下げたまま話を続ける。
――連隊の再編により、エンジニアがより強い権力を振り翳すようになったこと。
――『聖騎士の力』が解析中であるとされている今の状況では、俺様達を拘束から解放することはできても、施設の外に出すことはできないということ。
――もし、施設の外へ出ようとしたりした場合、エンジニアによって再び拘束されてしまうであろうということ。
――何年掛かるかはわからないが、必ず状況を改善し、外へ出られるようにする。
といったことが語られた。
「わかりました、副長」
「ミック……。すまない」
「何年か我慢すればいいなら、あんな風に拘束されないなら、俺はそれで構いません」
「オイ……いや、俺も同じです」
「だから副長、頭を上げてくださいよ!」
「みんな。すまない。本当に……」
俺様達は、頭を下げ続けるミルグラム副長を励ますことしかできなかった。
「―了―」
3376年 「荒野の民」 
| 画像なし |
《渦》の通り道を避けるように、俺様は馬を走らせていた。
目的地はインペローダ王国の遥か南にある施設だ。
その施設には『連隊』と呼ばれている軍団が入っており、その連隊の一員になるべく、俺様は生活していた場所を離れて向かっている。
俺様は生まれたときから今まで、ずっと荒野の只中で生きてきた。
そんな荒野で生きる連中はストームライダーと呼ばれている。基本的に定住地を持っていなくて、馬車やテントが自分の家って感じの民族なのさ。
ウチは親父、お袋、俺様、妹。そんな四人で一つの馬車とテントで生活してる。他の連中も似たような感じで、生活は基本的に家族単位だ。
世界各地に発生している《渦》から出てくる魔物や生き物と何とか折り合いを付け、荒野を巡って生活する俺様達。
どうしてストームライダーがそんな生活をするのかは知らない。ストームライダーにとっては、それが当たり前のことだからだ。
大人になると家族から離れて一人で旅をする奴もいた。兄貴なんかもその口で、旅先で出会った気の合う連中と一緒に旅団を作ったって話を耳にしてる。
気に入った街や村に定住する奴もいるんだけど、そういう奴は稀だ。《渦》から出てくる異形の生物を利用して生きてきたってのが足を引っ張るのかね。
そんな状況を理解しているから、ストームライダーは子供達に代々の教えを受け継がせる。
「荒野で生きて荒野で死ぬ。それがストームライダーだ。俺達は荒野の民、それを努々忘れるな」
親父も爺さんから。爺さんも爺さんの親父から。そうやって言い聞かせられてきた。
そんなストームライダーの俺様が連隊の一員となるべく施設に向かっているのには、それなりの理由があった。
異形の生物を狩って毛皮や頭部を売り、時にはミリガディアなんかの国から隊商の護衛依頼を受けて報酬を貰う。
そういう生き方が必然なせいで、ストームライダーの子供は結構早い段階から大人と一緒に生きるための仕事をするようになる。
俺様も十歳になるかならないか位の頃には、大人に混じって異形の生物を狩るようになり、家計の一部を担っていた。
「痛ってえ!」
中型の鹿に似た異形の生物を狩ろうとして、顔に深めの傷を負った。
「んのヤロウ!」
怒りに任せて猟銃を放つと、運よく異形の心臓部分を撃ち抜いた。異形はその一撃で崩れ落ちる。
「ふう」
鹿のような異形を運搬機に乗せる。頭部を傷付けなかったので、お袋に頼んで立派な剥製にしてもらおう。
剥製は好事家っていう不思議な連中に高い値で売れるし、これで妹にいい服を買ってやれる筈だ。
「まーた怪我したのか」
「ブレンダちゃんを笑顔で送り出したいんだったら、あんまり無理すんなよ」
一緒に狩りに来ていたオッサン達が呆れたように言う。この言葉を何度聞いたことやら。
「わかってるよ」
年が明けたら、妹のブレンダは俺様より十歳ほど年上のストームライダーのところへ嫁いで いく。
姉貴のときと同じように、嫁ぐときには少しでもいい嫁入り道具を渡したい。俺様と親父はそう考えて、狩りや仕事に精を出していた。
それがいけなかったのだろうか。
数ヶ月前、親父はニヴェルという小さな都市国家から依頼された大型の魔物の討伐隊に参加したんだけど、その際に大きな怪我を負ってしまった。
親父の治療に付き添わなきゃいけないってんで、ウチの家族は親父が入院している治療院がある町で暫く生活をすることになった。
親父達が相手取ったのはとんでもない強さの魔物だったそうで、数十人で組まれた討伐隊で生き残ったのは、親父と腕っこきの数人だけだったとか。
生き残りの中で一番の軽傷が親父だったらしいが、それでも未だに怪我が治りきっていない。だとすると、他に生き残った腕っこきはもっと酷いことになっているんだろう。
「……ニヴェルの討伐隊には悪いけど、アンタがちゃんと帰ってきてくれてよかったよ」
「ははっ。心配かけたな」
「大掛かりな仕事の度にこれじゃあ、アタシの心臓がもたないよ。まったく」
俺様が知っている限りでもそうだけど、よくよく話を聞くと、親父は若い頃からずっとこんな感じで、窮地に追い遣られることばかりだったみたいだ。
稼ぎ頭が動けなくなったことで、俺様はより一層働かなければならなかった。
普段の生活維持とブレンダの嫁入り支度に加え、親父の治療費までが加わった。正直、結構金が掛かる。
いつもみたいに中型の異形を狩ってるだけじゃ、到底間に合わない。
かといって俺様が駄目になったらウチの家族はオシマイになってしまうから、あまり無茶もできない。でも、俺様が多く稼がなければ意味がない……。
状況を打破するいい解決方法が見つからず、俺様は悩んでいた。
そんな折、定期的に開かれているストームライダーの集会へ親父の代理で出席したとき、一つの道筋が見えた。
集会で各々が情報を出して会話をしている最中に、一人の爺さんが手を叩いてみんなを注目させた。
「あー、少し時間をくれ。ブルベイカーから連絡が来たんだが、何人かを連隊に寄越して欲しいということだ」
ブルベイカーというのは、《渦》の活動を読むことに長けた中年のオッサンだ。
ストームライダーの間では有名なオッサンで、今は連隊という《渦》を討伐するための軍団に入隊して働いている。
爺さんの話を聞き終わったみんなの中から、どよめきのようなものが湧いた。
「そういえば、ベイルのとこの倅が……」
「最初に行った連中は、ブルベイカー以外みんな死んだって……」
「死にに行くようなもんだぜ」
漏れ聞こえてくる言葉から、連隊という場所は相当に苛酷な場所だということがわかった。
「まあ聞け。もちろん、報酬は危険に見合った額が出るそうだ。家族持ちの奴なら、入隊後すぐに報酬が支払われる。その後も定期的に――」
その報酬金額を聞いた俺様は、飛び上るような感覚に囚われた。
爺さんが口にした報酬の額は、親父の治療費とブレンダの嫁入り支度、それに家族全員の当面の生活、それら全てを賄ってもお釣りが出るくらいの金額だった。
「お、俺様行きます! 連隊、行きます!!」
爺さんの話を遮るように大声を出す。周囲のストームライダーが驚いたようにこっちを見た。
「おいおい、若造。お前みたいなヒヨッコに連隊の隊員なんて務まるわけないだろ」
「大体お前、そんなに大きくもない異形を手にするので精一杯じゃねえか」
俺様を知るオッサン達から野次が飛ぶ。だけど、そんなことは気にしてられない。
「静かに。お前さん、覚悟はあるんだな?」
爺さんが周囲を窘めて俺を真っ直ぐ見つめた。
「ある!」
俺様は爺さんの言葉に即答する。これで親父の怪我が治るまで、お袋やブレンダに苦労させずにすむ。
だったら、俺様は何だってできる。そんな気がした。
集会の後、爺さんはすぐに連隊の施設がある場所を教えてくれた。入隊には諸々の検査があるらしく、施設に行ったとしてもすぐに入隊が決まる訳でもないらしいけど。
俺様に家族がいることについても、爺さんからブルベイカーに連絡をつけて証明してもらうことになり、入隊が決まれば報酬の半分以上が家族に渡るよう手配してもらえた。
「ディノ、この中には我が家に代々伝わる守護の石の欠片が入っている。大事にするんだぞ」
連隊へ向かう前夜、親父が首下げ紐の付いた皮袋を俺様に寄越した。
皮袋の中には緑色をした宝石のような結晶が入っていて、これが守護の石というものらしい。
「お前が無事に連隊でやっていけるように、祈っている」
「頑張ってくるぜ!」
「……ディノ、死ぬなよ」
「俺様は親父の子だぜ? そう簡単に死んだりしないっての」
「そうか。うん、そうだな!」
そして翌朝、俺様はお袋とブレンダに見送られて旅立った。
「兄さん、気をつけて」
「ブルベイカーさんに迷惑かけるんじゃないよ」
「わーかってるって。じゃ、行ってくるぜ!」
遠目からでもわかるほど、でっかい施設が見えてきた。
治療院のある町から数日の旅を経た俺様を出迎えたのは、巨大な鉄の建造物と、これまたでかい頑丈そうな扉だった。
「はー、でっけえなー」
扉の前には、俺様と同じ入隊志願者が何人か集まっている。
みんな《渦》と戦う覚悟を決めた連中ばっかりだ。
早ければ今日中にでも、俺様はあの扉の向こうで隊員として徴用され、《渦》と戦うことになるんだろう。
これからどんな事が起きるのだろう。恐怖と期待が入り混じったような思いを抱きながら、俺様は志願者の列に並んだ。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ