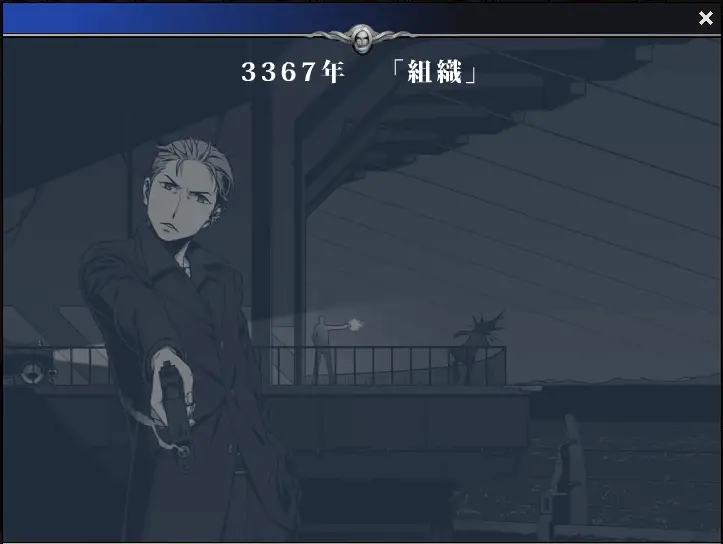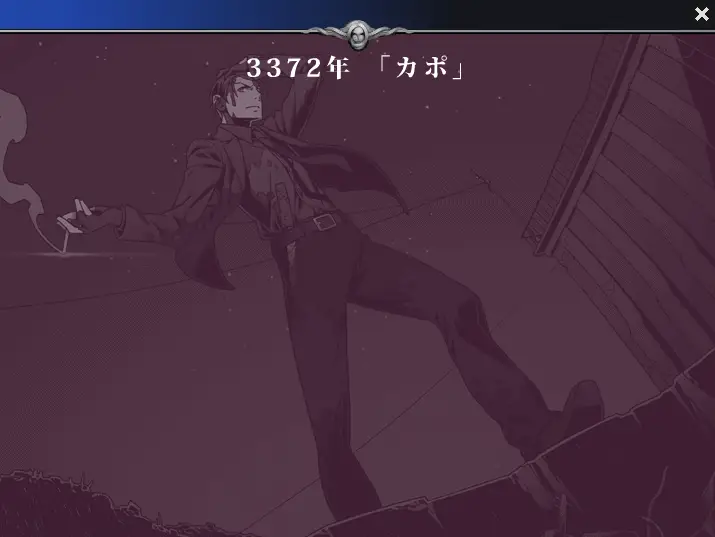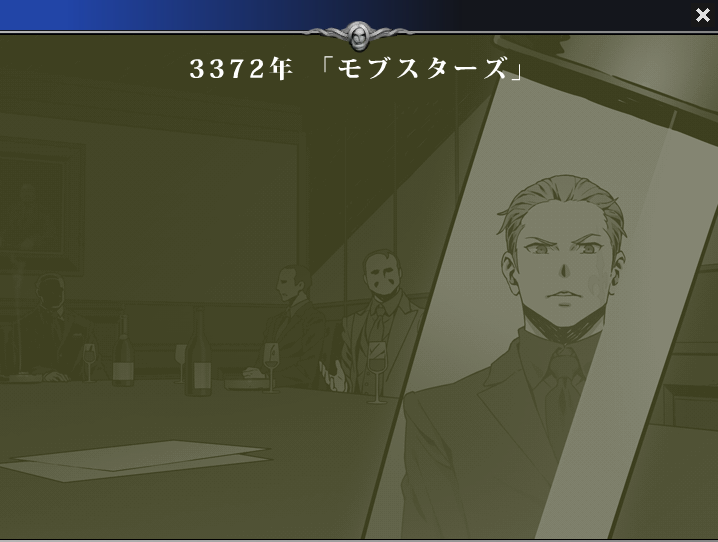コッブ
【死因】
【関連キャラ】
3367年 「組織」 
ローゼンブルグ第七管区の外れにある人気の少なくなった夜の街角を、ゆっくりと車が走っていた。この時代、自動車が市井を走っているのは、帝國の中でも特異なこの都市ぐらいだった。
この街には混乱の早い時期にウォードが建設され、広大な領地が渦から隔離されていた。多くの黄金時代の遺産が残され、退潮し続ける薄暮の時代を乗り越えてなお、この街は例外的に文明世界が保たれていた。この街が魔都と呼ばれる所以である。
車が駐まり、二人のスーツ姿の若い男が降りた。通りを歩く恰幅のいい男に近付いていく。
「エリスン、約束のものだ。礼はいらねえぜ」
若い男の一人がエリスンに封筒を渡した。エリスンの短く刈り揃えられた髪と前に突き出た腹には、独特の威圧感があった。エリスンは受け取った封筒の厚さを確かめると、背広の内ポケットにそれを仕舞った。
「おい、新入り。お前いくつだ」
「関係あんのかよ」
「やめとけ、コッブ」
隣のもう一人の若い男が制止した。コッブと呼ばれた男は相手を睨み付ける。
「分別をわきまえねぇガキを寄越すようじゃ、お前らの組織も落ち目だな」
「何だと?」
「頼むよ、今日はやめとこうぜ。用事はすんだんだ」
苛立ちを隠さない態度のままチッと舌打ちして、コッブは地面に唾を吐いた。
二人の若い男、コッブとリーは車に戻った。二人は先月、プライムワンと呼ばれる組織の『ソルジャー』になったばかりだった。幹部に命令され、賄賂をエリスン警部に渡しに来たのだった。
「余計な真似はすんなよ。やっと組織の一員になれたんだ」
車の助手席からリーは諭すように言った。
「うるせえ。俺は警官に舐められるためにソルジャーになった訳じゃねえ」
コッブは逆上していた。こうなるとやばい事になるのは、付き合いの長いリーにはよくわかっていた。
「やることだけやってよ、金を稼ごうぜ。俺達はやっと組織の一員になれたんだ」
リートは同じ養護院を出た幼馴染だった。共にやっと街のチンピラから卒業できた、コッブはそう感じていた。
コッブは年代物の車を発信させた。ローゼンブルグの高階層でしか見られないもので、組織のステータスでもある。
車はスピードを上げ、Uターンした。
「何するつもりだ!?」
「見てりゃわかるぜ」
エリスン警部がヘッドライトに照らされる。鈍い音と共に弾け飛んだ。
コッブは車を降り、道路脇に蹲ったエリスン警部の横に立った。エリスンは頭から血を流しているが、意識はあるようだ。
「おい、言葉には気をつけろよ」
「……クソ餓鬼が、タダじゃおかねえぞ」
「やってみろよ、デブ!ここで殺したっていいんだ」
コッブは硬い革靴の爪先を、倒れているエリスンの腹に蹴り入れた。そして、リーが止めるまで存分に痛め付けた。
「お前は警部にへこへこしてもらいたかったんだろ。やっと組織の一員になれてよ」
カーマインはデスクの上のタバコを手に取り、火を点けた。
コッブは無言のまま立っていた。
「その期待を裏切られたから、頭にきてヤツを轢いた」
「そんなつもりはありませんよ。カーマイン」
「口答えなんか聞いちゃいねえぞ、コッブ。いいか、俺達は力が全てだ。だからこそ、力を見せる時はよく考えろ」
「はい……」
「若いから仕方ねえって言う奴もいる。だが、若い内に覚えておけ。この世界で生き残って強くなるには頭が必要だ。クソ度胸よりもな」
コッブは黙って聞いていた。
「切れるのも必要だ。もちろん、やらなきゃいけない時にやらない奴は役立たずだ。俺達は暴力と恐怖を金に変えてるんだからな。だが、やる時は道理と損得の両方を考えろ」
「わかりました」
「ヤツの治療費はお前が出せ。あれはまだ使える」
「それと、二度とつまらねえ真似はするな。お前は組織の人間なんだ」
コッブは頷き。出口へ向かった。カーマインも立ち、コッブを見送った。
「俺を怒らせるな」
カーマインは胸に人差し指を突き立ててそう言った。そして、言い終わった後にニヤッと笑った。
「わかってます」
コッブはそう答えて事務所を出た。
酒場の裏ではリーが待っていた。
「どうだった?」
「別に。治療費は出せってよ」
「それだけか?」
「ああ」
「ったく、びびったぜ。カーマインが怒ってたら、俺もアブねえ」
リーの言葉尻にコッブは苛立ちを覚えたが、カーマインの言葉を思い出し、黙っていた。
エリスン警部はコッブのことを喋らなかった。ただの轢き逃げで、自分を轢いた車については記憶が無いと言い張った。組織との関係が少しでも疑われるのを恐れたのだ。
それから街でコッブと会っても、エリスン警部は目を合わすことすらしなくなった。
コッブが所属するプライムワンは長く続く組織だが、最近は他の組織との抗争の中で力を落としつつあった。
カーマインら幹部――カポと呼ばれる――は、闘争の過程で疲弊していた。
「アイラーをタレ込んだのは誰だ?」
狭い事務所に集まった幹部を前に、ボスの質問が飛んだ。
「ファイヴの一人、パントリアーノと揉めたのはしってますが、奴らがタレ込んだにしてはタイミングが――」
アイラーは愛人宅で捕まった。隠してあった銃と現金も即座に押収された。そんな情報を知っているのは内部の人間だった。
「鼠がいるってことだ。誰の差し金かは別にしてな」
「カーマイン、お前が抱えてる警官から情報が聞けるか?」
ボスはカーマインにそう言った。
「やってみます」
カーマインはコッブを呼びつけた。コッブは組織に入って二年が経っており、それなりのシマを任せてもらっていた。与えられた仕事を忠実にこなしてきたコッブを、カーマインは高く買っていた。
「エリスンから鼠の情報を聞き出せ」
「わかりました」
コッブはエリスンの自宅前に車で乗り付け、呼び出した。
「困るぜ、こんなとこに来てもらっちゃよ」
部屋着のまま呼び出されたエリスンは、車に乗り込むなり愚痴った。
「お前がこまろうが困るまいが知ったことじゃねぇ。仕事だ。アイラーが捕まったのは知ってるな」
「ああ」
「誰かのタレ込みだ。誰がやったか知ってるか?」
「知らねえな。そういうのは大体匿名だ」
「匿名だろうが何だろうが、誰かがタレ込んだんだ。そいつが一体誰なのか知りてえんだ」
「無理だって。管轄外の情報は――」
「おい!」
コッブはエリスンの襟元を掴んだ。
「わかってねえな。組織はお前に情報を期待して金を渡してるんだ。いざというとき役に立たねえんじゃ、こっちにも考えがあるぞ」
「ま、待ってくれ」
初対面のトラブルから、エリスンはコッブの狂気を恐れていた。
「今度は入院するぐらいじゃ済まねえかえらな。家族がいるんだろ?」
玄関横のガレージ前には、子供用の自転車が二台置かれている。
「勘弁してくれ……必ずやる。調べるから」
エリスンの怯えは本物だった。三日後、連絡があった。
「で、誰なのかわかったか」
「ああ、特別捜査官のダチに金を握らせた。電話を掛けてきた場所がわかった。先月一日の十六時三十分、レキシントン・モーテル前の公衆電話からだ」
「それだけじゃねえだろうな、てめえ!」
「待ってくれ、まだ情報がある。こいつはその時の録音記録だ」
エリスンはコッブに小さな再生機を渡した。
警察との遣り取りをコッブはイヤホンで確認した。タレ込んだ男の声を聞き終わったコッブは、引き千切るような勢いでイヤホンを外した。
「くそっ!」
ばんばんと両手でハンドルを何度も叩いた。
「クソッ、クソッ、クソッ!!」
突然激高したコッブにエリスンは身を庇うように手を上げた。
ドアに手を掛けて飛び出す準備までしている。
「な、何かまずかったか?」
「うるせえ、失せろ!もういい」
コッブはフロントガラスを見つめたまま目も合わさずに言った。エリスンはこそこそとコッブを刺激しないよう、静かに車から降りた。
コッブは車を飛ばした。あるアパートの前に駐まり、中に入っていった。
コッブはドンドンと扉を叩く。出てきたのはリーだった。窪んだ眼窩に汚れたガウンが、リーの日々の生活を表している。
「どうした、こんな遅く」
「付き合え。話がある」
「明日じゃだめか? 今日は疲れてるんだ」
「だめだ、すぐに来い」
コッブは真剣な眼差しでリーに言い切った。リーも事の次第を飲み込んだ。
「わかった、着替えさせてくれ」
組織に入ってから、リーとコッブの差は広がる一方だった。
コッブと同じ事をするにも、どこかリーは事勿れ主義なところがあった。そのため、金の取り立てや売春婦の管理といった日々の仕事にしくじることが多かった。後から入った連中にも馬鹿にされ、それに本人が気付くようになってからは、麻薬と借金に塗れた生活を送る羽目になっていた。
「先月の一日、お前はどこにいた?」
二人は車の中にいた。最初に言葉を発したのはコッブだった。
「覚えてねえなあ」
「ごまかすなよ。俺は証拠を掴んでる」
「何の話だ?回りくどい真似はやめろよ」
「警察にタレ込んだな」
リーは黙った。
「正直に言え。まだ俺しか知らない話だ、悪いようにはしない」
コッブは諭すように言った。
「……ああ、そうだよ。ただ、こんな事になるとは思わなったんだ。電話すれば借金をチャラにしてくれるって」
リーは顔を両手で覆った。
「借金?誰の借金だ」
「俺のさ。俺は上がりがイマイチだろ。だからバーで会った気の良い奴から金を借りてたんだ。あいつらがパントリアーノの連中だなんて知らなかったんだ」
「金に困ったんなら、何で俺のところに言いに来なかった?」
「言えるかよ。恥ずかしかったんだ、お前と会うのが。俺は情けねえからさ」
一年くらい前から、コッブはリーと会う回数が減っていた。自分が会おうとしてもリーが何かと理由をつけて避けていた。
コッブは黙ってそれを受け入れていた。
「こんなことになるなんて思ってなかったんだ。本当に……」
コッブはリーの弱さに気付いていた。それでも、男として、友人であったからこそ、リーの行動に意見も文句も言わなかった。前と変わらず接していた。
「すまねえ、コッブ。本当にすまねえ。でもよう、俺は役立たずだから幹部の送り迎えくらいしかできねえし、いつも金はねえしよ……。ああ、こんなことになるなんて」
リーは泣いているようだった。
コッブは黙っていた。
「なあ、俺を殺すのか?」
リーガ下を向いたまま呟くように言った。
「悪いようにはしない、って言ったぜ」
「ああ、ありがとう、コッブ。お前はいい奴だ。本当に」
リーはパッと顔を明るくしてコッブの方を向いた。
「外縁まで送ろう。下の階層へ抜ける場所を知ってる」
ローゼンブルグは大陸に残った数少ない階層都市だ。薔薇の都市の名の通り、中心から花弁のように地区が重なり合っている。それぞれの階層は隔離されているため、階層を出てしまえば誰も追っては来ない。加えて、階層は下がれば下がるほど文化レベルが退潮する。わざわざ降りる者など、通常はいない。
「ああ、そうだな。すまねえ。本当に。クソみたいな場所らしいが、死ぬよりましだもんな」
コッブは車を出した。リーはほっとしたのか、饒舌になった。
「なあ、最初に乗った車、覚えてるか?マイヤーのを盗んだ時さ」
十代の前半、二人で知り合いのいけ好かない金持ちの家から車を盗み出した思い出を語り出した。
「ああ、覚えてるさ」
「笑ったよな。最高だった。犬と一緒にあのおっさん、俺達を追い掛けてよ。雨上がりだったか石畳ですっ転んでさ――」
コッブは黙って聞いていた。
「昔はよかったよ。何しても自由だった。昔に戻りてえなあ」
街のチンピラから抜け出して組織に入ろうと誘ったのはコッブだった。コッブはただのチンピラとして底辺で生きていくのは御免だった。リーもそう思っているものだと信じていた。
「ああ、下の階層ってどんなとこなんだろうな。車もねえって話だ。どうやって生きてるんだ」
「少し休め」
「ああ、そうだな……」
コッブの車は外縁に着いた。夜明け間近の外縁――アウターリーム――には人影など無かった。埃が部屋の隅に溜まるように、隔壁の前はゴミで溢れていた。
「着いたぜ」
コッブは眠っていたリーを起こした。
リーは車から降りた。隔壁の縁にはスロープで上がれるようになっている。せり上がった隔壁の向こうは断崖となっていて、普通は誰も通ることなどできない。深い谷の奥には暗闇しか広がっていない。
「ここからじゃ何も見えねえな。どこから降りれるんだ?」
リーは隔壁の手摺りに手を掛けて下を眺めた。空はほんのりと明かりを帯びていたが、断崖の奥底は真っ暗闇のままだった。
「向こうに梯子が隠してある」
リーは指された方向を、上半身を揺らすように探した。
「どこだ?」
コッブは懐から銃を出して、リーの頭を後ろから撃った。頭蓋の中身をぶち撒けて、リーは絶命した。
リーの死体はガラクタだらけの場所に横たわった。まるで見捨てられた人形のように。
「悪いようにはしない、か」
コッブはそう呟くと車に戻った。そして、タバコを出して一服してから、ゆっくりと車を発進させた。
「―了―」
3372年 「カポ」 
「まだ来ねえのか?」
コッブは苛ついていた。ブツの取引場所に指定されたゴミ集積所の悪臭にうんざりしていた。車の脇には護衛役として二人の若い奴らを立たせている。
「少し遅れているようです」
運転席の男はそう答えた。
組織は流行の薬の取引に目を付けていた。そしてついに大口の配給元と仕事をすることとなり、その最初の取引にコッブを責任者として選んでいた。
車の音とヘッドライトの明かりがこちらに近付いてくる。その車から四、五人の男が降りてきた。ライトの逆光でどんな姿かはわからない。
カシャ、という特徴的な音がゴミ集積所に響いた。銃のボルト操作の音だ。コッブは咄嗟に声を出す。
「出せ!罠だ!」
しかし次の瞬間、敵の銃弾が霰のような音を立てながら車に降り注いだ。コッブは身を伏せる。
銃弾は車内を駆け巡り、運転手は血達磨になった。脇に立っていた二人の子分は反撃する前に蜂の巣にされた。コッブは破片が降り注ぐ中で反対側のドアを開け、這うように車の外に出た。車自体を盾にしながら、胸のホルスターから銃を抜いた。
誰も動く者がいなくなると、敵は撃つのを止めた。ゆっくりと歩きながらこちらに近付いてくる。コッブは車体の下から相手の動きを見ていた。敵の数は五人。車に近付いてくるのをじっと待った。十分に引き付けた後、コッブは車体の下から相手の足を撃ち抜いた。三発で二人の足が撃ち抜かれ、その場に倒れ込んだ。残り三人の内の一人が一気に距離を詰めてくる。コッブは素早く立ち上がってその男の頭を撃ち抜いた。あとの二人は脇のガラクタが積まれている場所に走って身を隠した。
コッブも車から離れ、敵が隠れたガラクタ置き場の反対にある小屋の影に身を潜めた。
できればこれで相手が引き下がってくれることをコッブは祈っていた。放っておけば失血死するであろう仲間が二人いる。そいつらを連れて逃げてくれればいい。金だってくれてやる。今回だけは。
コッブは小屋の脇にしゃがんだ状態で敵の様子を窺っていた。
沈黙が続く。
ふと脇腹に鈍痛が走る。どうやら弾が掠ったらしい。シャツが血で濡れて嫌な感触がある。
早く終わってくれと、コッブは願っていた。我ながら情けない気分だったが、こんなところで死ぬのだけは御免だった。この腐ったゴミ集積所で誰にも知られずに朽ちる自分の死体。そんなイメージが浮かぶ。
車の扉が閉まる音がした。隠れていた男達が乗り込んだのだ。エンジンが吹かされ、砂利を踏むタイヤの音が響く。
一瞬ほっとしたコッブだったが、すぐにその安心は誤りだと気付いた。車はスピードを上げてコッブの隠れていた小屋に突進してきた。立ち上がったコッブだったが、小屋ごと跳ね飛ばされた。そして小屋の反対側のごみ溜めに落ちた。
汚水と生活ゴミの混じった最悪の場所に頭から浸かっていた。辛うじて意識はあったが、銃が手元から無くなっていた。車から降りた男が自分の生死を確かめるために下りてくる。よほど俺を殺したいらしい。大きく動く訳にはいかなかった。コッブは何か武器になるものはないか探した。偶然、錆びた奇妙な形のナイフがあった。真っ赤に錆びたそれは何かを切ることができるとは思えなかったが、何も無いよりはましだった。
敵の一人が車の隣でライトをかざし、もう一人がその指示に従って自分を探している。まだ自分は見つかっていない。
絶対にあいつらを殺してやる。
そんな闘志が急激にコッブの中に湧いてきた。ゴミの匂いと錆びたナイフが、自分の中の根源的な怒りに火を点けたようだった。
男と光がゆっくりと自分の方に近付いてくる。心臓の鼓動が早くなる。早くこいつを殺したい。殺さなければという思いで頭が熱くなった。
そしてその熱さが頂点に達した時、獣のようにコッブは敵に飛び掛かった。
一瞬で相手の胸元に飛び込み、腹に錆びたナイフを突き立てた。そして一気に腹を引き裂く。ライトを持った最後の敵が銃を撃ってくる。コッブは腹を引き裂いた男を背負うようにして盾にした。男の血と内蔵が湯気を立て、コッブの頭に降り注いだ。
最後の敵は銃を撃ち尽くすと車に乗り、去って行った。
コッブは盾にした男を下ろすと、ゴミ溜めから這い上がった。立ち上がると汚水に濡れた血みどろの頭を掻き上げ、乱れた髪を後ろに撫でつけた。片手にはまだ錆びたナイフがあった。
錆びたナイフをベルトに挟むと、胸ポケットからタバコを出した。幸いケースに入ったタバコは無事だった。そして火を点けると、自分の車に向かった。
車の傍に二つの敵の死体があった。一人は頭を撃たれた男。もう一人は脚を撃たれて失血死した男。
そしてもう一人、脛を撃たれた男が這いずりながら逃げようと藻掻いていた。
コッブはその男の真後ろに立った。コッブに気づいた男は、肩にかけた短機関銃をおぼつかない手つきで構えようとする。
コッブは男に乗りかかるようにして短機関銃を取り上げた。そして斜め後ろから首に手を回して締め上がる。
「パーティは始まったばかりだぜ。落ち着いて一服しろよ」
そう言って左手に持ったタバコを男の眼球に押し当てた。瞼から煙が上がり、男は甲高い叫び声をあげる。
「ぎゃあぎゃと喚くんしゃねえ」
首を締め上げていた腕を離すと、今度は男の顔を殴った。地面に叩きつけられた男は小さく呻いた。
「さあ、誰の差し金か聞かせてもらおうか」
「……何も知らねえ。俺はしがねえ下っ端さ。頼む、殺さないでくれ」
コッブはベルトに差していた錆びたナイフを抜いた。
「上手く喋るなら、腕の一本、いや、指の一本ぐらいは残してやってもいいぜ」
そう言うと男の片耳を掴み、千切るように錆びたナイフで切り取った。
「大変だったな。もう大丈夫なのか?」
カーマインは立ち上がり、抱擁でコッブを迎えた。場所は組織が管理している酒場の事務所だ。
「ああ、腹の破片を出してもらっただけで。当たり所が良かったらしい」
襲撃から五日しか経っていなかったが、顔に貼られた絆創膏ぐらいしか痕は残っていない。
「男前が増したな」
コッブの頬をカーマインは軽く叩いた。二人は席に着く。
「誰が手引きをしたのか、わかったのか?」
「金で雇われた下層からの不法移民のチンピラで、バックは追えませんでした」
「そうか」
「ですが、いま不法移民を扱ってるのはキアーラの所だけです。あたりをつければ何か手掛かりを掴めるかもしれません」
「しっかりと方を付けろ。組織の威厳に関わる。お前も、もうここらへんじゃ顔役なんだ」
コッブが組織に入って七年。若い連中の中では一番の稼ぎ頭で、幹部になるのも間近だと噂される男になっていた。今回の取引も相談役から直々の指名があって行われたものだった。
「わかってます」
コッブは席を立った。
「そうだ。明日なんですが、新しい取引について相談したいので、夜ここへ迎えを出します。平気ですか?」
「ああ、問題無い」
そう約束を取り付けて、コッブは事務所を出た。
「貴方に見せたいものがあるんです。ちょっと大きな取引で、保証が必要なもので」
コッブは車中でそう語って、カーマインを倉庫に連れてきた。コンシリエーレ――相談役――のクレメンザともう一人のカポ、マリオが立っていた。そして倉庫の奥には、黒い布が掛けられた何かが置いてあった。
「どうした?マリオ、クレメンザ」
「俺から説明しますよ。カーマイン」
コッブは黒い布の隣に立っていた部下に、顎で指図をする。
布が取り払われると、そこには両足を脚から、右腕を肘から切られた包帯だらけの男が椅子に縛り付けられていた。
「実はコイツが口を割りましてね。それでちょっと貴方に話を聞こうという流れになりまして。相談役と」
「カーマイン、コッブから話しを聞いた。厄介な事だぞ、コレは」
「何を言ってるんだ?」
カーマインは憮然とした表情で言った。
「アンタが例のアップスターズと組んで俺を嵌めた、ってコイツは言ってるんですよ」
アップスターズはプライムワンと因縁のある振興組織だった。新型ドラッグを捌き、ファイヴと呼ばれる古参の組織を切り崩しに掛かっていた。
部下が包帯の男の猿轡を外して軽く小突くと、包帯の男はくぐもった声で喋り始めた。
「……俺はリーダーの口から……プライムワンのカーマインからコッブを始末する許可を得た……って聞いた」
「本当か?嘘だったら殺すぞ」
コッブは大声で聞く。
「本当だ!本当なんだ!これだけだ……俺が知っているのは……」
部下は猿轡を戻した。
「金か?兄弟」
呆れた調子でマリオが言った。見届人としてクレメンザが呼び出していた。
「馬鹿な!何で俺が尤も信頼している部下のコッブを嵌めなきゃいけねえんだ。道理が通らねえだろ?」
カーマインは威厳を保とうとしたが、焦りは明らかだった。
「俺が幹部になれば割を食うのはあんただろ、カーマイン。独立してシマを分けてもらう相手はアンタなんだから」
コッブは怒りを抑えた調子で言った。
「馬鹿を言うな!そんなことで組織を裏切る真似などするか」
カーマインの額には汗が浮かんでいる。
「アップスターズに恩を売っておけば、いざという時に助かるって訳だ。あいつらは随分と羽振りがいいらしいな」
マリオが言う。
「他の組織でも金で転んだのがいると聞いてるが、まさか俺達の組織から出るとはな」
クレメンザはマリオに言った。
「クレメンザ、頼む、俺はこんな馬鹿なことはしない。わかってるだろ」
懇願するような調子でカーマインは言った。
「裏切りは死んでしか償えん。知っている筈だ」
クレメンザは諭すように言った。
「や、やめろ!!」
カーマインの首筋をコッブは真っ直ぐに引き裂いた。思わず顔を庇おうとして出した手の指が一緒に切られ、床に落ちた。
カーマインは跪き、溢れる血を指の無くなった手で抑えた。ゴボゴボと声にならない声を発している。
「方は付けさせてもらいましたよ」
そう耳元で呟くと、コッブはカーマインから離れた。
続いてマリオが銃を抜き、カーマインの頭を吹き飛ばした。兄弟分への情けだった。
「みっともねえ真似しやがって……」
そう言って、マリオは憮然とした表情で倉庫から去っていた。
コッブは部下にカーマインの死体を始末するよう指示した。部下達はカーマインの死体を引き摺って倉庫を出て行った。
倉庫にはコッブとクレメンザ、縛られ拷問された襲撃者が残された。
「よくやった。カポの座は俺から推薦しよう。来週の会合で、お前は正式な幹部だ」
クレメンザは言った。
「ありがとうございます」
「カーマインが裏切るとは意外だった。昔気質のいい男だったんだがな」
「カーマインはいい男でしたよ。俺もそう思います」
「どういう意味だ?」
クレメンザは訝しんだ様子で聞き返した。
「実はコイツが話した内容には、もう一つ別のものがありましてね」
顎で襲撃者を指す。
「どんな話だ?」
「コイツが聞いたという裏切り者なんですが、普段は『相談役』って呼ばれてるそうです」
コッブは話しながらタバコを出して吸い始めた。
「何だと……」
クレメンザは動揺を隠さなかった。
「俺の取引を知っていたのは、依頼してきたあんたと上役のカーマインの二人だけだ」
「何でお前を俺が始末しなきゃならない」
「さあ、金でしょうかね。アップスターズは俺を殺したがってる。奴らと前線で派手にやり合ってるのは俺ですからね」
吸ったタバコの煙をゆっくり吐いた。クレメンザは黙っている。
「俺を売ることができるのはアンタだ。そのアンタを金で抱き込めて――」
「……証拠は無い」
「要りますかね?俺がアンタをここでやるのに」
クレメンザは固まった。
「それに、アンタがこの件に無関係ならカーマインを庇った筈だ。拷問されたチンピラの自白一つで功績のあるカポを始末する、普通そうはいかない」
「何が望みだ」
「俺がカポになった後は、俺のいいように動いて欲しい。そうすれば命の保証はしましょう」
「……よかろう」
クレメンザは従った。
「それと、アップスターズの連中と話がしたい。殺し合い以外にもやり方がある筈だ」
「わかった。取り次ごう」
クレメンザは逃げるように倉庫を後にした。
コッブは縛られた襲撃者の後ろに立った。もう倉庫には二人以外誰もいない。
「さて、約束通りに喋ってくれたようだから、お前は殺さない」
ナイフで身体と椅子を結びつけている縄を切った。そして乱暴に男を蹴り倒した。両足を失った襲撃者はもぞもぞと床で藻掻いた。
「だが、助けたりはしねえ。俺を的にかけたヤツを助ける訳がねえだろ?」
床にのたうつ男を思い切り蹴った。
そして倉庫に襲撃者を置き去りにして、コッブは去った。
「―了―」
3372年 「名誉」 
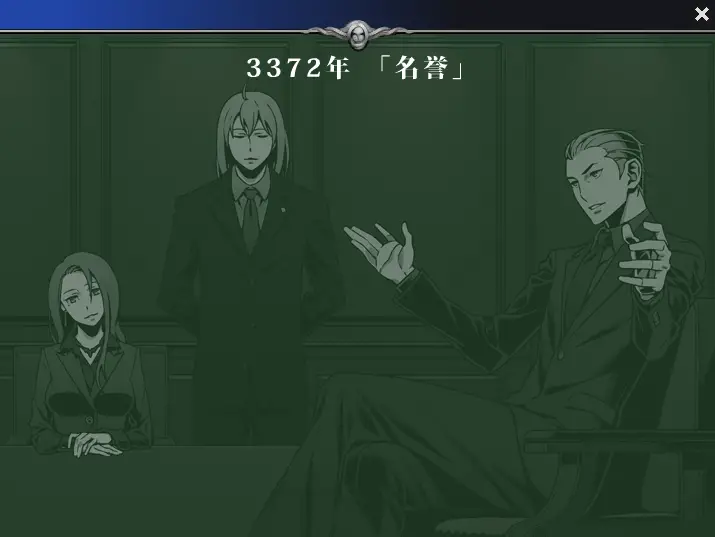
コッブはアップスターズが会談の場所に指定してきたホテルへと向かっていた。
「噂は本当ですかね。あいつらのボス」
「さあな」
ドライバー兼ボディガードのヘイリーが、後部座席のコッブに声を掛けた。
「でも、マジならすげえ話だ。絶世の美女だとか」
「馬鹿野郎、よく考えてみろ。伝説とやらがホントならシワだらけのババアだろ。でなきゃ魔女か化物だ」
「いや、でも昔の姿のままだって噂なんで」
運転席のヘイリーは頭の回転は少し鈍いが、こと暴力に関しては躊躇のない男だ。コッブはその点を信頼していた。ただ、あまりにも馬鹿話が好きで下らないことをよく喋る。
今日は例のブツの件でアップスターズとの会談が行われる。さすがのコッブも、今日はこの男のムダ話を利きたい気分ではなかった。
「お前は魔女とやりてえのか?」
「へへ……一度くらいなら、その」
「呆れた野郎だ。もう口を閉じて運転だけしてろ」
思ったままを口に出す正直なところも気に入っているのだが、今は無視することにした。
この階層で最もクラスの高い、インペリアルホテルの表玄関に着いた。
「お前はロビーで待ってろ」
「すげえホテルだ。ここなら何も起こしようがねえ」
「いいか、わかってるな」
「ええ、もしものときは……。わかってますよ」
ビビっても仕方がない。この家業にはつきものだ。それにヘイリーもクソ度胸だけはある男だから大丈夫だろう。
ヘイリーをロビーに置いて、指定された部屋にコッブは向かった。
部屋は16階にあった。自分以外誰も乗っていないエレベーターが昇っていく。
アップスターズ――成り上がり者――と呼ばれる組織は、元々プライムワンと関わりが深いと言われていた。何より、その創設者とされるボスは元々プライムワンの一介の上布だったという話だ。しかし、そんなものは噂に過ぎないという説もあった。それに組織の年寄りに話を聞いても、なぜかこの件についてははぐらかされることが多かった。
自分はアップスターズのボスがどんな人物であろうと気にしていなかったが、この組織の上部について秘密が多いことは確かだ。
エレベーターが16階に着き、エレベーターフロアにいたボディガードに部屋まで案内される。フロア全てが貸し切られているようだった。
「どうぞ、ボスがお待ちです」
ボディガードはそう言ってドアを開けた。
「ボディチェックはいいのか?」
「俺達のボスにその必要はありません」
「そうかい。大した自信だ」
コッブは部屋へと入った。向こうから長身の男が現れた。見栄えのいい男で、モブスターには見えない。
「ようこそ、こちらでお待ち下さい」
スイートの会議室へ案内される。少し待つと女が現れた。
「はじめまして。私はビアギッテ」
美しい女だ。噂通りの。だがこの女が本当のボスかはわからない。組織によっては表向きだけのボスを立てることもある。
「どうも、コッブだ」
「手短に済ませましょう。例のモノを取り扱いたいとか」
アップスターズと繋がっている相談役を通して、自分のシマで新型のクスリを捌く件について話し合いを持ちたいと伝えていた。
「無駄な争いをするより、互いに儲かる方がいいと思ってね」
「それはそうね。私達も争うのは好きではないわ」
顔色一つ変えることなく冷淡に言い切るこの女をこの場で斬りつけたらどうなるか、一瞬想像してみた。
「なら話は早い。俺達にもブツを流してくれ」
この女をこの場でぶっ殺しても得は無い。わかっている。
「互いのシマをこれ以上荒らさない。ブツの卸価格はそっちが決めてくれていい」
まずはブツを扱うことが先決だ。ブツの出処がわかれば、その後は別のやり方もある筈と踏んでいた。
「ずいぶんと好条件ね」
「ブツを持ってるのはあんたらだからな」
ここは相手に見くびらせておこうとコッブは思っていた。面子を潰されれば、それはそれで抗争の立派な理由になる。
「こちらの手数料は無しでいいわ。私達が取引している相手を紹介するから、そちらと直接やりとりして。ただし、互いのシマを荒らさないという点は守りましょう」
「それであんたらがいいのなら」
気味の悪い申し出だったが、とりあえずは受けておこう。
「決まりね。じゃあ、あとはこのクーンに任せるので、彼と話し合って。よろしく、クーン」
アップスターズの女ボスは席を立った。
「これからはうまくやっていきましょう」
「ああ。これからはな」
そう言うと微笑みながら握手を交わし、女ボスは去っていった。
「商品の取扱方法を説明しましょう」
クーンとブツの受取方法の詳細を詰めて、会談は終わった。
「どうでした?」
ロビーで待っていたヘイリーが自分のところに来ると、第一声そう言った。
「一応、取引の目途はつけた」
「で、ボスはどんなやつでした?」
「噂通りだったぜ」
「マジですか!?魔女でした?」
「見ただけでわかるよ。それに興味もねえ」
「すげえな……。ほんとにいたんだ」
「あまり口外するなよ。アホだと思われるぞ」
言っても無駄だろうが、釘は刺しておいた。
「ええ、もちろん。秘密の会談ですからね」
ブツの取引はスムーズに進んだ。指定の場所に現れた男に金を渡すと、きちんとブツが手に入った。
ブツの入っていたバックを調べてみると、どうやら宗教団体が製造を行っているようだった。その宗教団体も探ってみたが、確かにアップスターズの影は無い。
あいつらに旨味のない奇妙な取引だったが、とりあえず暫くは様子を見ることにした。
半年も経つと取引も順調に拡大していき、儲けも大きなものになった。プライムワンの他の組へもブツを卸すようになって、組織内でもコッブの存在感は見る見る大きくなっていった。
そうして一年が経った頃、上納金の額も幹部の中でトップクラスになり、ボスのコッブに対する扱いも変わっていった。ただ、若すぎるコッブが幹部の中で大きな権力を持つことは、他の古参幹部の大きな反発を受けることにも繋がった。
「ブツの独占はおかしい。組織には規律が必要だ」
ある幹部が定例の会合でブツのやり取りについて異議を出してきた。
「だが、この取引を始めるときにリスクを取ったのはコッブだからな」
相談役のクレメンザが助け舟を出す。
「そうはいっても、今は奴のシマだけで捌いている訳じゃない。なのに、どの幹部もコッブから買い入れてるのは現状だ」
他の古参幹部もこの言葉に同調する。ここの思案のしどころだった。
確かに大きく儲ける事ができたが、そのスピードが思ったより早く、味方を作る前に反発を買うことになってしまった。
「まあ、暴利を貪ってるわけじゃありません。あくまで手間賃程度のものです」
「なら、ブツの元締めを俺達が扱っても問題ねえんじゃねえのか?」
幹部の語気が荒くなった。
「まあ落ち着け。少し時間が必要だろう。持ち帰って考えろ、コッブ」
ボスが取り成した。
「わかりました」
「ワシはブツの扱い自体をやめた方がいいと思っている」
最古参で、自分のシマでブツを扱っていない幹部がそう言った。同意するように頷く幹部も数人いる。
「子供や若い母親にも売ってるって話じゃないか。そんなことを続ければ街自体が成り立たないし、サツ共との折り合いも無くなる」
「本当か?コッブ」
「売ってるつもりはありません」
「しらばっくれるな、若造が!金ばかり目が眩みおって」
「ブツの取引は続けてもいいが、売人共の管理はきちんとしろ」
ボスは面目を保つためにコッブに言った。
「わかりました」
「まあ、次の会合までに考えておけ」
定例の会合は終わった。
コッブは面倒事をクリアする方法を思案していた。ブツの取引を分けるのは避けられない状況だ。だが、このまま他の幹部にみすみす利益をやるのは馬鹿らしい。せめてブツの反対派を潰して自分のシマを拡げるくらいしないと旨味のない話だ。やり方は考えないといけない。
そんな考えを巡らしているうち時、事件が起こった。郊外地区の支部が壊滅させられたのだ。
荒事には慣れていたが、状況が謎だった。
支部は『ヴィジランテ』と呼ばれる謎の男一人によって壊滅させられたのだった。
「―了―」
3372年 「モブスターズ」 
コッブの目の前に二名のソルジャーが並んでいた。彼らを見つめるコッブの顔は険しい。話の内容がまるで出鱈目に思えたからだ。
「失敗は失敗だ。それでも汚名返上のチャンスは与えられる。だがな、嘘や裏切りは絶対に許されねえ」
コッブは言い切った。
「嘘はついてません。アニキ、あの……マジで鉄の怪人が襲ってきやがってんです」
「俺も確かに見ました」
二名のソルジャーは腫れた顔をコッブに向けてそう答えた。
「ふん。大方クスリをやってたんだろう」
側近のヘイリーが横槍を入れた。
「いえ、その時はシラフでした」
「じゃあ、何でおめおめと逃げ帰ってんだよ!」
襲われた酒場の事務所はブツの一時保管場所として使っていた。こいつらの言う『鉄の怪人』とやらがやって来て大騒ぎになった。当然、ブツは警察に押さえられてしまった。こんな騒ぎの中では、捕まった連中や押収されたブツを取り返すのはかなり難しい。
「奴は銃も効かねえし、力も化物みてえで……」
「おい、まだクスリが抜けてねえのかテメェは!」
ヘイリーは片方のソルジャーを首元から捩じ上げた。
「もういい」
片手を上げてコッブはヘイリーを制した。
小さな支部の一つが潰された形になったが、問題はそこではなかった。
他の幹部から突き上げられることが容易に予想された。あいつらはこれを理由に、オレからブツの権益を奪おうとするだろう。
「やられっぱなしってのは、絶対に有り得ねえぞ!」
コッブは指を突き付けて怒鳴った。
「やった奴を必ず探し出せ。怪人だが怪物だが知らねえが、背後で糸を引いてる奴が必ずいる」
ヘイリーは頷き、しょぼくれたソルジャー達を小突くと部屋から出て行った。
シマが襲われたのは初めてではなかったが、今回気に食わないのは、正義漢とやらに一方的にやられたと報道されたことだった。
この世界は裏切りと暴力の繰り返しだ。コッブは今回の件についても、自分を妬むプライムワン内の幹部を真っ先に疑っていた。
どす黒い感情が次から次へと湧き出してくる。
コッブは酒を呷ると、引き出しからナイフを取り出した。ゴミ捨て場で拾ったものだが、あの一件以来いつも持ち歩いていた。
錆びていたブレードを綺麗に研ぎ直し、それらしいシースも新調した。見た目は悪くない、実用品としても気に入っていた。エッジを見つめていると不思議と怒りが収まり、頭が冴えるような気がした。
裏切りも暴力も躊躇はしない。コッブは自分自身をそう律してきた。
ボスは稼ぎ頭であるオレを信じちゃいない。組織は誰もが己の地位を守ろうとしている。これは互いの資産を食い合うゲームだ。強いものに味方し、自分の利益を広げる。
ボスは権威という資産を持ったプレイヤーに過ぎない。オレの資産は金とドラッグだ。周りの幹部は古参としての信用、それと弱者故の連帯感といったところだ。
この窮地を必ず好機に繋げなければならない。コッブはそう思った。
毎週のように例の怪人が世間を騒がすようになった。『マフィアを倒す英雄ヴィジランテ』、『弱者を守る戦士ヴィジランテ』。見出しの内容はともかく、起きた事実はその通りだ。他の幹部達を調べさせていたが、今のところ繋がりは見つかっていない。
何度か怪人を追うチャンスはあったが、今のところ全てが徒労に終わっていた。
そして、他の組織でも商売を邪魔される例が出始めた。
定例の会合でボスは苦々しく言った。
「例のヴィジランテとやら、裏は取れたのか?」
幹部達からは何の声も上がらなかった。
「いずれこっちの網に掛かります。必ず仕留めてみせますよ」
コッブは静かに言った。
「他のファイヴだけじゃなく、アップスターズのシマでも被害が出てるらしいな」
他の幹部が言った。
「だからって、あんなのにでかい顔されるようじゃ、俺達の商売は終わるぞ」
ボスは言った。
「わかってます」
コッブは請け負った。
「頼んだぞ」
今回の会合で、ドラッグの取引方法を変える件は棚上げとなった。
あの怪人が暴れている限り、警察の抱き込みには限界がある。加えてヴィジランテとやらは強力だった。銃やナイフが効いたという証言は一つも無い。
古参のレン中はタイミングが悪いと見て、ドラッグから距離を置くようだった。他の幹部が及び腰なのは有利だが、最も被害を被っているのはコッブ自身だった。
ヘイリーが電話を繋いできた。
クーンというアップスターズ幹部からの連絡だった。
「どうした?」
「例の事件について話し合いたいと」
「わかった」
ここに来てコッブは、ヴィジランテはアップスターズの仕業ではないかと思い始めていた。クーンや女ボスの雰囲気は我々とどこか違っている。
「アップスターズの幹部と会ってくる」
「へい、オレも付いていきますよ」
「いや、一人で平気だ」
「本当ですか?奴らの動きには注意しないと」
「罠なら罠で、オレに少し考えがある」
コッブは机からナイフを出して背中に仕舞うと、ジャケットを羽織った。
「例の件、そっちもやられているようだな?」
コッブはホテルの一室で歓待を受けていた。
「ええ、こちらの被害もかなりなものになっています」
クーンが酒を片手に正面に座った。
「商品の売上にも相当被害が出ていますし、警察との関係もギクシャクしていますよ」
「ヴィジランテは警察関係なのか?」
「いえ、そうではないでしょう。しかし動機を考えると、多くの人がそう思うのも無理はありません」
クーンは続ける。
「ローゼンブルグの警察はどこも犯罪組織と上手くやってきた。その信頼関係にヒビを入れるのも、奴の目的の一つでしょう」
「鎧を着たバケモノ、いや人型機械らしいが、そんなものが何故俺達を襲う?」
コッブは酒を飲み干した。
「何故でしょうね。ただ、ビアギッテ様は目星が付いているそうです」
クーンの言葉にはどこにも緊張感がない。奇妙な男だった。
「誰だ? 教えろ、他のファイヴが絡んでんのか?」
どの組織もやられてはいるが、それが目眩ましの可能性もある。
「焦らないでください。他のファイヴとの関係は不明です。まあ、物事は見た目通りにはいかないものです」
「まどろっこしいな。何故オレを呼んだんだ?」
「暫くの間奴を、ヴィジランテを泳がせてほしいのです」
「何だって?」
「我々アップスターズが信用しているファイヴのメンバーは貴方だけです。ですから、我々のビジョンに強力して欲しいのです」
「オレがあんたらを信用してるって言ったことがあったか?」
「貴方は商品をきちんと購入してくれているし、我々のシマを攻撃したことも無い」
「商売だからな。それに約束は約束だ」
クーンの奇妙な話ぶりはこちらを引き込むような感覚がある。だが、別にオレはこいつらと仲良しこよしになる気は無い。オレの目標はあくまで組織の中で地位を得ることだ。
「何かをしてくれ、という話ではありません」
「オレもプライムワンの幹部だ。それに武闘派のオレがやられっぱなして訳にはいかない。何よりメンツがある」
「確かにその通り。ですが、本当にヴィジランテが『無敵』だとしたら?」
一瞬言葉に詰まった。確かにこの数ヶ月、手下や他の組織がやられるのを見てきたが、誰一人奴を傷付けたり怯ませたりできたという話はなかった。
「だとしたら、何か手があるのか?」
「方法はあります。ただし正体、いや、操っている背後の人間を探しだす必要があるのです」
「それができれば世話がねえがな」
「必ず見つけ出しますよ」
「ふん。で、オレは奴と戦わないだけでいいのか?」
「ええ。そしてもう一つ、貴方は誰にもやられてはいけない」
「クーンはコッブのグラスに酒をつぎ直す。
「ドジは踏まねえさ」
「慎重に振る舞ってください。奴はこのまま攻勢を強める筈です。貴方の組織は一度完全に地下へと潜るべきです」
「屈辱だな」
コッブは自嘲的に言って、その酒を呷った。
「ですが、他に道はありません」
コッブはグラスを見つめながら間を置いた。
「……奴の正体がわかったら、オレにも知らせてくれるんだろうな?」
コッブはクーンの言葉に少し乗せられているのを自覚した。だが、奴の言っていることは間違いではない気がしていた。
「勿論。手柄は貴方にお渡しします」
「気前のいいこったな」
「協力は価値を産みます」
クーンは冷静にそう言い切った。
それから半年程を掛けながら、コッブは組織内での立ち振る舞いを消極的なものにしていった。
その間もヴィジランテは組織を叩き続けていた。かなりのソルジャーがやられ、何人かは幹部も捕まっていた。一部の組は壊滅状態にまで追い込まれていた。それでもコッブは幹部会で出る強硬策をなだめ、むしろファイヴだけでなくアップスターズの連中も含めて、一丸となって対抗策を練るべきだと主張した。
「ふん、アップスターズが同席する場に、残りのファイヴが出てくるものか」
古参幹部はコッブの意見を否定した。
「いえ、セルピエンテやフェロス、キアラの連中とは話をつけてあります」
「セルピエンテだ?あいつらはアップスターズに最も食われたところじゃねえか」
「跡取りのリカルドは方針転換したいようでしてね。相談は済ませてあります」
「あとはパントリアーノだけか」
別の幹部が口を開く。
「あそことウチは長いあいだの因縁がある」
「キアラのボスに頼むしかなかろう。あそこは繋がりが強い」
どうやら幹部連中も気弱になったようだ。この話に乗ってきた。
「なら、コッブを中心にファイヴとプライムワンの会合を設ける形でやってみますか。ボス」
うまく相談役がとりなした。
「そうだな。今回は若い奴らに任せてみよう」
ここのところボスは随分と歳を取ったように思えた。この魔都を支配し続けた暗黒街の帝王も、今の惨状には酷く気落ちしているようだった。
コッブ自身も今の状態を受け入れる気などさらさら無い。しかし、ファイヴ全体が大きく力を落としている。警察も近頃じゃ賄賂を受け取らない。すっかりヴィジランテ側に付いてしまったようだ。
だが、ヴィジランテさえ取り除けば、一気にシマを広げられるチャンスでもあった。
コブは必ずボスを追い落としてプライムワンの、いや、暗黒街の頂点に立ってやると思っていた。
そして、ついにクーンから連絡が来た。
「13地区にある養護院に、イヴリンという少女がいます」
「そいつが奴の身内か?」
「そうです、あとは貴方にお任せします」
「次に奴が出てきた時、そいつを使えばいいんだな」
「やり方は任せます。あなたの手口は買っていますから」
奇妙な褒め方だったが、気分は悪くはなかった。何より、ついにあのヴィジランテを葬ることができるのだから。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ