クーン
【死因】
【関連キャラ】ビアギッテ(契約)
「願い」 

――『美』とは、誰もが心の中で欲するものだが、その価値は様々だ。
彼女も私の所有する美しいコレクションの一つ。彼女が持っていた自身の『美』を私に捧げてくれている。
あぁ、別に私が何をした訳ではないのだよ。これは彼女が望んだことだ。そう、他ならない彼女自身がね。
窓辺に集う小鳥の鳴き声を目覚ましにして、私は起き上がった。
窓を開けると、風に運ばれてきた春の草木のいいにおいが鼻をくすぐる。
「おはよう、小鳥さん。いま朝ごはんを持ってくるからね」
窓の近くにある木に留まっている小鳥さんに声を掛けると、食事を用意する。
パンくずを窓の桟に撒くと、小鳥さんが食べに寄ってくる。そのかわいらしい様子を見ながら、おいしい朝食をいただくのが、 私の日課。
朝食が終わったら、朝の仕事の時間。
お店と自宅の掃除が終わって店を開ける頃には、気の早いお客さんが何人か待っていた。
「おはようございます!でき上がってますよ!」
お客さんに朝の挨拶をすると、ドレスやニット、シャツなどを一つ一つ取り出してお客さんに見せる。
「あら、綺麗に直してくれたのね。ありがとうソニアちゃん」
「いえいえ。もし気に入らないところがあったらすぐに直しますので」
私は破れた服の修繕や、古くなった服を仕立て直す仕事をしている。直した服や仕立て直した服を見て喜ぶお客さんの顔を見るのは、とても嬉しい。
直した服の返却と、新しく来た修繕する服を受け取る。それが途切れると同時に、朝の仕事は終わる。
朝の仕事が終わったら、街に出掛けて買い物をする。
必要なものを購入したら、ちょっと変わったお店でお昼ご飯を食べたり、アンティークの雑貨を見たり。午後の仕事を始めるまでは自由な時間。
今日はアンティークのお店で素敵な手鏡を見つけたの。
「やあソニアちゃん。それねー、結構前からあるんだけど、なかなか買い手がつかなくてね。今なら安くしておくよ」
「本当?それじゃあ、これください!」
手鏡を買って自宅兼仕事場に戻る。いい買い物をしたときは足取りが軽い。
午後の仕事は修繕の仕事。お客さんの大切な服を丁寧に直していく。日が落ちるのはあっという間。そうしたら今日の仕事はもうお終い。
あとは夜ご飯を食べて、自分の時間。アンティークの手鏡の置き場所を考えてあげなくっちゃ。でも、どうやっても手鏡がちょうどよく収まる場所がないの。
「うーん、素敵なアクセサリーボックスでもあればいいのに......」
手鏡に映る自分に向かって思わずつぶやいちゃった。とりあえず手鏡は大事に包装しなおして、鏡台の引き出しにしまうことにしたの。
次の日、お店に行くと見知らぬ人が尋ねてきた。
「服を直してもらいたいんですが」
「はい、ではちょっと拝見させていただきますね」
取り出した服をざっと眺める。綺麗に洗ってあるけど、ずいぶんと長い間着ていてボロボロになってしまった作業用の服。ちょうどズボンの股座の部分に大きな穴が開いていた。
「そうですね、直せないことはないと思います。全面の修繕になるので、お代は――」
料金表を見ていると、お客さんが何か言いづらそうに小箱を差し出した。
「ごめんなさい 明日にでも直さないと仕事ができないんですが、修繕用のお金を盗まれてしまって。 今、私が出せるものがこれしかなくて......」
小箱は手鏡を収めるのにちょうどよさそうなアクセサリーボックスだった。ちょっと日焼けしている木の色が、とても良い風味を出していた。
どうしよう、普段はこういう物での修繕は受け付けていないけど、すごく困ってるみたいだし。
「わかりました!明日までに直しておきますね!」
ちょっと考えてから私はこう言った。困ってる人を見捨てておけないしね。
「さあ、すぐに直してあげるからね」
私はボロボロの服に向かって話し掛けた。ちょっと変かなって思うけど、くせでついつい言葉に出ちゃう。
服の修繕に手間取って、結局夜中まで作業してしまった。そのおかげでなんとか間に合いそう。でも、ちょっと疲れたかも。手鏡をお代の小箱にしまう前に私の顔を映してみたら、疲れた顔が映ってた。
「もう、クマができてる。やだなあもう......あーあ、明日はお客さん少ないといいな」
またしても手鏡の自分につぶやいてしまった。くせになったら嫌だなぁ。
次の日は雨だった。朝のお客さんは作業着や期日の服を取りに来た人達だけで、少し休むことができた。
雨が降ってると外に出たくなくなるのは、みんな同じような心理なのかもしれない。
「ふふ、手鏡さん、ありがとう」
その日の夜、私は手鏡にお礼を言った。この手鏡を買ってから良いこと続きなんだし、これくらいはね。
そうやってお礼を言った瞬間、手鏡が光り輝いて、鏡の中から 長い髪の男の人が現れたの。あまりの眩しさにぼーっと見とれちゃった。
「あなたは?」
「私の名はクーン。私の主よ、貴女の願いを叶えよう」
「願い.........? もしかして」
私は『明日のお客さんが少なければいいな』と手鏡に向かってつぶやいたことを思い出した。
「そうだ。主が望むどのような願いでも叶えよう。宝石でも、 金でも、恋人でも、好きなことを願うといい」
私は戸惑った。いざ何でも叶う、なんて言われてしまうと結構困る。
「えっと、えっと......そうだ、新しいハサミが欲しいなー、なんて」
ちょうど、裁ちバサミが壊れていた事を思い出し、ためしに言ってみた。
すると、私の手元に真新しいハサミが現れた。この間お金がな くてあきらめた、有名工房のハサミだった。
「すごい!ありがとうクーン!」
次の日、変な話を耳にした。
「えっ、湖が?」
「昨日は雨だったのに、干上がるだなんて......」
お店の前を通る人の会話が耳に入った。何だろう、急に湖が干上がっちゃうことなんてあるのかな?
不思議に思いながらも仕事をする。新しいハサミはすごく使い心地が良かった。
それから、私はどんな些細な願いごともクーンに頼むようになった。
評判のお菓子屋さんのケーキや、明日起きて欲しいこと、色々な願いを、思いつくままに叶えていった。
私の生活は私の思うように動くようになった。欲しいものも、食べたいものも、着るものですらクーンに頼った。
「ねえクーン、私、幸せすぎておかしくなっちゃいそう」
「それは良いことだ」
ある日、ちょっと調子が悪くなったハサミを有名工房に持っていくと、店主がはっとしたような顔をした。
「このハサミはどうしたんだね?」
「え?友人にいただいたものですけれど」
「そんな馬鹿な......」
「どういうことですか?」
「お嬢さん、ちょっと良いかね?」
店主に促されるまま付いていくと、別室に通された。しばらく待っていると、やって来たのは警官だった。
「知っている事を詳しく話してもらおう」
「このハサミは領主様がお買い求めになられた品でね。引渡しの日に盗まれてしまったものなんだ」
「わ、私、何も......」
「ちょっと調べさせてもらうよ」
「領主様はお怒りでね。なんとしても犯人を見つけなければ、私の商売も危ういんだよ」
店主の言葉を呆然となりながら聞いていると、私のカバンは警官に取り上げられてしまった。警官は私の持ち物を見ると、これもそうだ、あれもそうだと、メモと照らし合わせている。
「これらは全て盗品だ。どこで手に入れたか教えてもらおう」
「し、知らない!クーン!助けて!」
「その願い、叶えよう」
服のポケットに入れていた手鏡からクーンが現れ、あっけにとられた警官の隙をついて、私を連れて外に出る。
後ろから警官達が追い掛けてきた。
お店に辿り着くと、私はあわてて鍵を閉めて自室に閉じこもった。
どうしてこんなことが起きたのかわからなかった。今日持ち歩いていたものは、服もカバンも全部、クーンにお願いしたものだった。
「なんで、どうして......」
「何かを手に入れるには、何かを犠牲にせねばならない」
「じゃあ、あの作業着の人からお金を盗んだのって......」
「私だ」
「街の近くの湖が干上がったのも?」
「それも私だ」
「そんな、私、人を不幸にしてまで欲しいものなんてない!」
「だが、主は願った」
クーンが突き放すように言うのと同時に、扉を強く叩く音と警官の怒声が聞こえてきた。
どうしたらいいか私にはわからなかった。私は、私は......
「新しいハサミもおいしいケーキも、手鏡も何もいらない!お願いだから私を前の生活に戻して!戻してよ!」
全てを無かったことにしたかった。力の限り私はクーンに向かってわめいた。 「その願い、叶えよう」
お店と自宅の掃除が終わって店を開ける頃には、気の早いお客さんが何人か待っていた。
「おはようございます!でき上がってますよ!」
お客さんに朝の挨拶をすると、ドレスやニット、シャツなどを一つ一つ取り出してお客さんに見せる。
「あら、綺麗に直してくれたのね。ありがとうソニアちゃん」
「いえいえ。もし気に入らないところがあったらすぐに直しますので」
私は破れた服の修繕や、古くなった服を仕立て直す仕事をしている。直した服や仕立て直した服を見て喜ぶお客さんの顔を見るのは、とても嬉しい。
それだけなのに、なんだか最近、身体が重い気がするの。
手鏡の中でソニアは眠っていた。若々しかったその容貌は老婆のように枯れ、痩せ衰えていた。クーンはその手鏡を手に取ると、うっとりとした表情で眺めてい いた。
どのような願いでも相応の代償が必要なのだ。彼女はそれを理解していない愚か者だった。
最後の願いの代償は彼女自身の人生。彼女はこの先、その命が尽きるまで私の腕の中でかつての夢を見る。
彼女は美しく輝いていた過去を望んだ。私はそれを彼女の命で叶え続けることにした。
『美』こそ我が糧。我が全て。慎ましくも輝かしい彼女の『美』は、命尽きるまで私のものとなったのだ。
「―了―」
「太陽の華」 
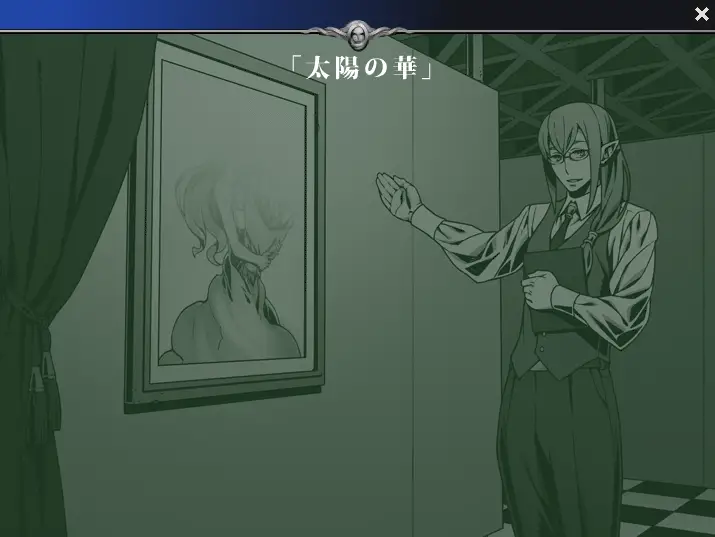
――もし、そこの貴方。さる若い天才画家が死の瀬戸際まで描き続けたと言われる、最終にして最高の傑作美女画、『太陽の華』をご存知かね?
花を抱えて微笑む美女が描かれた何の変哲もない絵画だが、その価値およそ一億。まあ、微笑と不思議な逸話に狂わされた、金の亡者どもが値を吊り上げた結果だがね。
知りたがりの貴方には特別に教えて進ぜよう。この絵画の生誕と美の秘密を。――
「こんなもん、うちでは買い取れん!」
「そこをなんとか!これが売れなきゃ露頭に迷っちまう!」
大判のキャンバスを抱え、俺は画廊の店主に食い下がった。
「うちの店は信用第一なんでな。紹介状も無いお前の貧相な絵なんか、扱えやしないんだよ。とっとと出て行け!」
店主に慈悲は無く、やって来た警備員によって俺は店の外につまみ出された。人通りの多い店先にいきなり放り出された小汚い俺。道行く人の視線がとても痛い。
絵描きはパトロンが付いてナンボ。そんなことは俺だって重々承知だ。それでも、いま抱えているこの絵が売れなきゃ、今日の飯もお預けだ。
そう思うと同時に盛大に腹が鳴り、ここ何日かを水と塩だけで凌いでいたのを思い出す。
少し歩いた軒先の隅っこで、浮浪者のように丸まって溜め息を吐いた。もう日は暮れかけていた。住んでいる部屋はまだ遠い。
「ちょっとあなた。私の店の前で寝ないでくださる?」
綺麗な声が頭の上から降ってきた。人の迷惑になるつもりはなかった。だから、すぐに立ち退こうと思った。
「うぇ?あ、ごめんなさい。すぐにどきますか……ら……」
突然目の前が真っ暗になって、体の感覚が無くなった。
「やだ、大変!誰か!お医者様を!」
慌てる綺麗な声だけが、俺の耳に届いていた。
朝日の光で俺は目を覚ました。ぐわんぐわんと揺れる頭で周囲を見回すと、豪華な調度品に囲まれた、随分と派手な部屋にいるようだ。
寝ているベッドも掛けてある毛布も、この派手な部屋に相応しい極上品だ。調子が悪いのに任せて、このまま二度寝を決め込みたいところだった。
「おはよう、気分はいかが?」
そんな俺の堕落した欲望は、気絶する前に聞こえたあの綺麗な声の登場で完全に吹っ飛んだ。
「あ、ハイ……」
「よかった。お医者様がおっしゃるには栄養失調だろうって。あとでスープを運ばせるわね」
美女の言葉が右から左に抜けていく。だって、いやね、もうね、すごいの。文句の付けようがない、完璧な美女。
すっと通った鼻筋に均整の取れた小さな鼻。夕暮れと夜の狭間のような青紫の瞳は大きな存在感を放ってる。やや先端がカールしている髪はシルクのように艶っつや。ちょっとぽってりとした唇に引かれた赤いルージュが、猥らにならないぎりぎりのラインで絶妙に色っぽい。
だから俺、思わず言っちまった。
「お、俺の絵のモデルになってください!」
美女は目を瞬いた。瞬く度に青紫の瞳が、星が零れてくるんじゃないかってくらい煌めいている。
「え、ええと、その。つまりあなた、画家ですの?」
「そうです!俺、人物画が得意なんです。貴女のような素敵な方、もう二度と出会えないかもしれない!」
我ながら言ってることが滅茶苦茶だ。しかも助けてもらったお礼も忘れて、美女に目が眩んで懇願なんかしちゃって。
「……ふぅん。いいわよ。でも、描くならとびっきり綺麗に描いてちょうだい」
しばらく考えるような素振りを見せた美女は、日の出のような華やかな笑みを浮かべて頷いてくれた。
美女の名前はクーラといった。女性ながらアンティークや雑貨を扱う商社を経営する人で、俺が倒れた軒先は彼女が経営する小売店の一つだった。
俺は世話になった次の日からクーラの屋敷に通い、彼女をデッサンした。そうしたデッサンを元に彼女の絵を描いていく。
ある日、彼女をアトリエに呼び寄せた。完成した彼女の絵を本人に見てもらうためだ。嬉しいことに評価は上々。この絵は屋敷に飾ってくれるらしい。
「あら、この風景画とっても素敵ね。こっちの静物画は応接室に合いそう。お代は出すから、これも持って帰っていいかしら?」
絵を包む間、他の作品を見ていたクーラがいくつかの絵を引っ張り出してきた。
「そりゃあ構いませんが、でもそれ、画廊に持ってっても売れなかった失敗作ですよ?」
「よっぽど節穴だったのね、そいつ。まあいいわ。私に任せなさいな」
クーラは怪しげな笑みを見せると、気に入ったという物も含め、俺のアトリエに置いてある全ての絵を持っていってしまった。
けれども、何度画廊に足を運んでも一度たりとも買い取られなかった俺の絵だ。売れずに落胆するクーラの顔が思い浮かび、何だか凄く悪いことをしているような気分になった。
数日して、クーラが大きな鞄に札束を詰めてアトリエにやって来た。聞けば、屋敷に置けなかった絵をクーラが経営する画廊に置いたところ、かなりの高額で売れたらしい。
「これがあなたの価値よ、バスコ」
一生お目に掛かることなんて無いと思っていた札束の量にポカーンとしていると、クーラは微笑んだ。
俺はクーラをモデルにデッサンを取りまくった。
クーラは俺の才能を高く買ってくれていた。その期待に少しでも応えたくて、俺は絵を描きまくった。何枚も何枚もクーラを描き続けた。
そうやっているうちに、少しずつ俺のアトリエに絵の依頼を持ち込む客が増えてきた。描けば描くだけ絵は売れた。
「はあ? まだ完成してないって?もう半年も待ってるんだぞ!」
「すみませんねぇ。どうにもピンとこなくて」
俺は絵が売れていくにつれて、少しずつ少しずつ、絵を描かなくなっていった。加えて社会に迎合できない性格だ。依頼の反故の仕方も、こんな風にあり得ない程に適当だった。
それでも俺の絵は高値で売れた。だからスランプとか、いまいち創作意欲が湧かないとか、そんな適当なことを言えば大体の客は引き下がった。
「さーて、遊びにいこ。今日はどこに行こうかなー」
俺はこの数年、クーラの依頼以外では殆ど筆を取らなかった。起きて、遊びに行って、たまにクーラの絵を描いて、寝る。そんな自堕落な生活を続けていた。
金に縁がなかった奴が突然大金を手にしたんだ。そりゃあ、仕事なんかしないで遊ぶよね、って話。
でも、クーラを裏切ることだけはしなかった。俺の才能を認めてくれた初めての人だったし、何より俺はクーラに惚れていた。
一度身についた贅沢な暮らしからは、どうにもこうにも抜け出せなかった。金が無くなった俺は、筆を取らずに金を借りることで贅沢を維持していた。
とうとう連日のように借金取りがやって来るようになった。あんまりにも煩くて、どうしようもなくなって、俺はクーラに泣きついた。
「ごめんなさい、それはあなたの責任なの。私にはどうしようもないわ」
「そんな……」
「だって私が借金を返したら、あなた、またどこかで新しい借金をするでしょう?」
「え、あ……」
クーラの言うことは尤もだった。俺は自分に任された仕事を放棄して遊んでいる。ここでクーラが問題を解決してしまえば、それは俺のためにはならない。
彼女は俺が抱える大きな問題点を見抜いていた。
「私はあなたの絵、大好きよ。だからまた描けばいいのよ。描いて描いてまた描くの。そうすれば借金なんてすぐに返せるわ」
俺の女神は微笑んでいた。そうだった。遊ぶことに熱中しすぎて、俺は当たり前の事を忘れていた。
俺は筆を取った。アトリエに篭ってキャンバスに向かい続けた。描き掛けの絵をいくつか仕上げるとそれで借金を返し、新作にも取り掛かった。
デッサンはたくさんあった。その中でも特に気に入っている、クーラが白い花を抱えて微笑んでいるデッサンから新作を創ることにした。
題名はもう決まっている。クーラの太陽が昇るときのようなあの輝く笑顔、俺の最高の女神。そう、題名は『太陽の華』だ。
『太陽の華』は完成間近のところまで来ていた。俺は慎重に瞳に色を入れていた。夕暮れと夜の狭間のような青紫の瞳。
瞳の色と唇に乗せるルージュの色。この二つをしくじれば、絵の中のクーラはクーラでなくなってしまう。最後まで油断がならない作業だ。
瞳に色を入れきったところで、アトリエの扉を乱暴に叩く音に気が付いた。
筆を置くと。俺は外に繋がる扉を開けた。
「どちらさ――」
ズドン、と腹に鈍い衝撃。見下ろすと、浮浪者のような姿の男が血走った目を光らせて俺を見ていた。
「貴方、は」
この浮浪者のような男には見覚えがああた。いつだったか、嫁さんの人物画の依頼をしてきた金持ちだ。
「お、おおお、お前、お前が、お前がちゃんと絵を描いていれば!!!」
男はそれだけを叫ぶと、どこかへと走り去った。俺の服は真っ赤に染まっている。その赤が何の色かを理解した瞬間、熱さと激痛が走り、頭から血の気が引いていくような感覚に襲われた。
ああ、そうか。これが俺の責任なんだな。仕事を放棄し、約束を反故にし続けた結果だ。俺が依頼を反故にしたことで何人もの人が信頼を失い、ああやって落ちぶれていったんだろうな。
何となくそんな気がした。
俺は痛みを振り切ってクーラの絵に向かう。まだこの絵は完成していない。何としても完成させなければ。今までどれだけ遊び呆けていても、クーラの依頼だけは守ってきた。だから。
いつも迷うクーラのルージュ。彼女に似合う最高の色を考え続けたくて、いつもそこだけ色が付けられない。
早く、色を。俺は手近にあった赤を小指に付け、クーラに口づけをするように色を乗せた。そして絵の全体がよく見えるように、椅子にもたれ掛かった。
絵の中のクーラは俺に向けて微笑んでいた。唇に指した……赤がとても……とてもよく……映えている。
やっぱり、クーラ……に……は真っ赤な……ルー……ジュが……よく……に……あ…………。
「その後、『太陽の華』は、この作品のモデルとなった女性によって持ち出され、世に出ることとなりました。しかし、この絵の所有者となった者はみな不幸な目に合ったと言われております。」
時は経ち、天逝した天才画家バスコの最後の作品『太陽の華』は、名も無き小さな画廊にあった。
「不幸の原因は、この美女の唇に差されている赤だと言われております。この艷やかな赤色が災いすらも魅了し、呼び寄せるのだと」
小さな画廊の店主が身なりの良い男に、バスコを『太陽の華』に纏わる話をしている。
「ほう。話を聞いていると、この唇の赤色はバスコの血であるかもしれないということかね?」
「そういった噂も囁かれておりますが、この絵が描かれたのはもう百年以上も昔でございます」
「その噂が本当だとしたら恐ろしい話だが、だとしても、この絵にあるのは美しさだけだ。恐ろしさなど微塵も感じないね」
「まあ、不幸な亡くなり方をされた芸術家の作品には、何らかの物語がまとわりつくものでございます」
身なりの良い男は、豪快に笑った。
「よし、この絵を買うとしよう。曰くありげな物語のある絵画か、実に面白い」
「ありがとうございます」
店主は恭しく頭を下げると、店員に指示を出して『太陽の華』の梱包に取り掛かる。
「中々にいい店だ。また利用させてもらうよ。ところで君、名前は何だったかね?」
「申し遅れました。私、クーンと申します」
名も無き小さな画廊の店主は、夕暮れの夜と狭間のような青紫色の瞳を輝かせてそう言った。
――彼は、自らが死の淵に立ってもなお、完成された美を追い求めた。
その執念こそが、『私』の美をこの絵の中で永遠のものとし、後世に語り継がれる傑作を生み出した。
例えそれが、この絵を持つ者に災厄をもたらす呪いだったとしても。――
「―了―」
「なくしもの」 
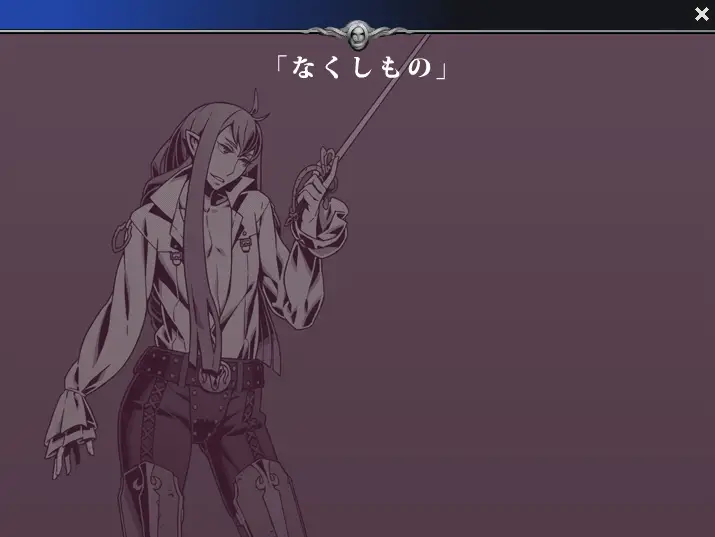
――ある者は言った。失うことで初めて、得られる幸せがあると。
――ある者は反論する。失ってよいものなど、一つとして存在しないと。
――どちらも真実であり、どちらも誤りである。
――何故なら、どれが最善かなど、その者にしかわからないのだから。
私は『なくしもの』を探している。
大事な大事なものだったけれど、いつの間にかなくなっていた。
いつ落としたのか、何処でなくしたのか、何も覚えていないけれど。
私にとっては、とてもとても大切なものだった。
休日によく訪れていた喫茶店を訪ねた。
「探しもの?見掛けないねえ」
「そうですか。ご迷惑をおかけしました」
喫茶店を出て、私は盛大に溜息を吐いた。
これでもう十件目。お気に入りのレストランや、時々立ち寄る本屋、いつも通りかかる公園。
他にもいっぱい探したけれど、なくしものは見つからない。
気が付けば、陽が暮れようとしている。今日はもう諦めよう。明日は何処を探そうか。前に行った展望台へ足を延ばしてみようか。
そんなことを考えながら歩いていたら、視線の先に『失せ物探します』の看板が見えた。
胡散臭いと思ったものの、あそこまで大書されていると、そういうものを探すのが得意なのかを思ってしまう。
「こういうのって、お金をいっぱい取られるんだろうなあ……」
いくら探してもずっと見つからないような『なくしもの』だ。専門家に頼んだら、一体どれだけ掛かるのか……。
「何かお困りか、お探しものですかな?」
看板を見て気落ちしていると、中から店主らしき人物が現れた。
長い髪に紫色の目をした気だるげな美形。とても探しものが得意そうには見えない風体の男の人だ。
「あっ、うえ。あの、その……」
「一度お話を伺いましょう。その上で、私めで探せそうなものかどうか判断して差し上げますよ」
「あの、でも、お金……」
「心配はご無用。相談だけなら無料です」
無料。その言葉に釣られてしまった私は、この店主に促されて店内へと入った。
店主に名刺を渡された。この方のお名前はクーンさんというようだ。
隅々まで掃除が行き届いた応接室に通される。
促されるように革張りのソファに座ると、すぐに良い香りのする紅茶が出てきた。
「では、お話を伺いましょう」
クーンさんに促されるままに、私は『なくしもの』を探していることを話す。
「その『なくしもの』は、どのような形をしているのですか?」
「え、えっと……。あれ?」
『なくしもの』の形を話そうとするが、何故か形を思い出すことができない。
「貴女、自分でも形がわからないものを探そうとしているのですか?」
そう言われてやっと気が付いた。私、何を探していたんだろう……?
「で、でも! 大事なものなんです! どうしてか思い出せないけど……、でも凄く大事な……」
大事な『何』なのか。言葉が出てこない。どうして? 何で?
「わかりました。では、催眠療法を行ってみませんか? なくしてしまったショックで、思い出せなくなっているのかもしれません」
クーンさんのゆっくりとした声が耳に入る。彼の声を聞いているうちに、私は眠たくなった。
「はい、終了です」
パン。という手をたたく音がして、私は目を覚ました。
ん? この場合は我に返ったって言うのが正しいのかな? こういうことは初めてなので、よくわからない。
「貴女の『なくしもの』が何なのか、わかりました」
「本当ですか!?」
「ええ。紅茶のおかわりを飲みながら、レコーダーに録音された声をお聞きください」
カップに新しい紅茶が注がれる。紅茶を口につけるのとほぼ同時に、レコーダーが再生された。
『貴女がなくした、大事なものとはなんですか?』
『私には、結婚を約束した恋人がいたの』
レコーダーから耳慣れない私の声がした。
『でも、結婚直前に浮気されちゃった』
録音されている私の声は、次々と私の知らない私の記憶を語る。
『だから忘れるの。彼との思い出は全部、忘れることにしたの』
そこで、さっき聞こえたクーンさんの手を叩く音と、催眠終了の言葉が流れた。
「さてお客様、いかがなさいますか?」
「え、どうしたらいいの……」
レコーダーの私が行った言葉は俄には信じられない。でも私の頭は、なくしものはその『思い出』であるということを完全に納得している。
「ではこうしませんか。後日、またここにお越しください。引き続き催眠療法で過去の思い出を探ってみましょう。それで納得できたら、その時にお代をいただくということで」
「私が嘘を吐いて、タダで思い出そうとするとは思わないの?」
「一度に思い出せるものは多くありません。催眠療法は脳への負担が大きいのです」
そういうことなら、このまま漠然と『なくしもの』を探し続けるよりはいいだろう。
私はクーンさんの言葉に従うことにした。
一週間後、私は再びクーンさんのお店を訪れた。
前回と同じように、応接室で催眠療法を行ってもらう。
『最初のデートは、私のお気に入りの喫茶店で待ち合わせをしたの』
『障壁の外には出て行けないから、公園でのんびりしたり、流行のお店でご飯を食べたり。楽しかったなぁ』
レコーダーの声と共に、彼との思い出が蘇る。『なくしもの』を見つけたという感覚は確かだった。
『彼はすっごくシャイでね。手を繋いだのも五回くらいデートしてからやっとだったの。とっても嬉しかったなぁ』
『初めてキスをしたのは彼の部屋だったわ。親御さんが一緒にいるでしょ。もうドキドキしっぱなし!』
むず痒いような、恥ずかしいような。私と彼との思い出がどんどんと思い出されていく。
と同時に、思い出の中の彼との別れも、近付いていた。
「今日の録音を聞くのは危険です」
ある日、クーンさんが沈痛な面持ちでそう告げてきた。
その言葉でなんとなくわかってしまった。今日のレコーダーの記録は、彼との別れの思い出なのだろう。
「大丈夫です。もう彼と分かれて一年以上経っていますから。ちゃんと整理も終わっています」
そう。私はここで、彼との出来事を思い出しながら、それを『過去の美しい思い出』として昇華しつつあった。
「思い出が貴女にとってショッキングだった場合、再び思い出を失ってしまう可能性が考えられます」
「大丈夫です。確かにショックな出来事だったかもしれないけれど、それはもう過去のことです」
「……わかりました。それでは再生しますよ。本当によろしいのですね?」
私は静かに頷いた。
それを見届けたクーンさんは、レコーダーの再生ボタンを押した。
『展望台でもデートの後からだったかしら。少しずつ彼がそっけなくなったの。ぜんぜん会ってくれなくなって、親御さんに聞いたけど、それでもわからなくって』
『最初は仕事が忙しいんだろうなて思ってた。それで心配になって、彼が働いている商店まで行ったのね』
『そしたら、彼が知らない女の人と仲良く商店から出てくるのを見てしまったの』
そう。彼は働き先で、そのお店のオーナーの娘さんと、いつの間にか良い仲になっていた。
そのことを私は知ってしまった。当然、家族と彼の親御さんに相談した。
お店のオーナーさん一家を交えた話し合いの席も何度か持たれた。お嬢さんには、彼には私という交際相手がいることを知ってもらった。
それでも、お嬢さんの態度は一途なまま変わらなかった。そして、彼もお嬢さんを選んでしまった。
彼の親御さんも、オーナー一家がお金持ちだと知ってからは、少しずつ態度が変わっていった。息子を一般家庭の小娘と結婚させるより、資産家のお嬢さんと結婚してもらった方が、いい暮らしができると思ったのでしょうね。
私はその時のことを思い出して涙を流していた。あの時は一滴だって出なかったのに。
『悲しかった。悔しかった。でも、資産家のお嬢さん相手じゃ仕方ないっで皆が言うの』
『彼の親御さんは何度も誠心誠意謝ってくれた。お店のオーナーさんからは多額の謝罪金っていうのも積まれたわ。でも、私の心はこれっぽっちも晴れなかった。誰一人として、彼と浮気相手のお嬢さんを怒ってくれなかったのよ』
『両親も多額の謝罪金に目が眩んで、もう今回の件は忘れようって言ってきた。私が持っている怒りとか悲しみとかに、真剣に向き合ってくれなかった』
私だけが、自分のことしか考えない我侭娘のように思われた。浮気をされたのは私なのに、私と一緒に怒ってくれる人は誰もいなかった。
「私に味方をしてくれる人はいなかった」
ぽつりと言葉が漏れた。自分でも怖いほど低く、冷たい声だった。
『だからね、お嬢さんの振りをして、彼をあの展望台に呼び出したの』
悲しみに暮れていた私の声が、同じように低く、冷たいトーンに変わった。
『あの展望台は切り立った崖の上にあるけど、景色が素晴らしい場所なの。それに、彼が私にプロポーズしてくれた場所だったんだ』
思い出してはいけない。頭の中で警鐘が鳴る。だけど私は知りたかった。
あの展望台で私が何をしたのかを。
『あそこはね、一箇所だけ腐っていて危険な柵があるの。いつもは近付けないようになっているけど、細工をして近付けるようにしておいたの』
『いつもは立ち入れない場所が気になったのかしらね。彼は何も警戒することなく、その柵に近付いていったわ』
『彼が柵の前に立った時、私は通行人の振りをして彼に体当りしたの』
『そうすると、彼が腐った柵に寄り掛かるでしょう? その衝撃で柵が崩れ落ちたのね』
『突然だったから、きっと何もできなかったのでしょう。彼は柵と一緒に崖の下に落ちていったわ』
「そう。そうよ。私は彼を殺したの」
気が付いたら、私は泣きながらもはっきりと「彼を殺した」と口にしていた。
『私が不幸になったんだから、彼も不幸になればいいって』
私の声に応えるように、レコーダーは言葉を紡ぐ。
「だって不公平でしょ? 私は浮気されたのよ? それなのに私が不幸になって、彼が幸せになるなんて」
『私がいると知って、それでも奪い取ったあの女も、彼を失って苦しめばいいんだ! ねえ、そうでしょう? そうに決まってるわ!』
私の声とレコーダーの声が重なった。
「ギャハハハハハハハハハハ!!」
『ギャハハハハハハハハハハ!!』
――失ったものを得た女は、それを得たがために狂気に囚われてしまった。
――彼女は『美しい思い出』と引き換えに、それ以外の全てを失った。
――だが、星空のような煌くえがおで思い出を語るその姿は、何ものにも代え難い程美しい。
――彼女は全てと引き換えに『恋する美』を体言する存在となったのだ。その姿こそ、私の求める糧である。
薄暗い室内に、女性の朗らかな声が響いている。
「彼がね、凄く素敵な展望台に連れていってくれたの」
「そしたらね。満点の星空の下で、『僕が君をずっと幸せにするから、結婚してください』って言ってくれたの! 素敵でしょ?」
「だから私も、彼を幸せにしてあげたいって、心の底からそう思ったんだ」
女性は虚ろな目で、自らの手で殺してしまった男との美しい思い出を、虚空へと語り続けていた。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ