アスラ
【死因】捕食
【関連キャラ】リュカ(上司)、エイダ、フロレンス(殺害)、スプラート(交戦)、タイレル、マルセウス、ベリンダ
3386年 「掟」 
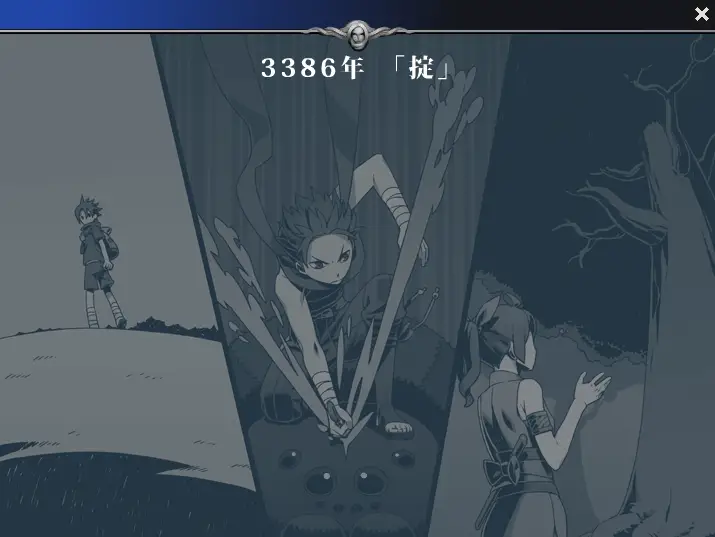
ルビオナ連合王国の東、バラク王国の外れにその集落はあった。
そこは文明の中心地からは遠く離れていたが、渦の惨禍から逃れることはできなかった。だがこの地に住む者達――ハイデンの民と呼ばれていた――は独特の適応を行った。文明世界が城塞に閉じこもる形で命脈を保ったのに対して、この地では自然の力と自民族の心身の強化によってそれに対応した。峻烈な精神をもってこの過酷な時代に適応したのだった。常に定住せず、谷や森を巡り、常に警戒を怠らず、老若問わずに苛烈な修養を行うことによって、その民族は漆黒の時代を生き抜いてきた。
いつしか彼らは、伝説的な民族として語られるようになった。
そのハイデンの集落にアスラというなの青年がいた。若くして『術』の天才と言われた男だった。どんな危険も恐れず、その目は毒を持つと恐れられた。彼は特に体術に飛び抜けて優れ、大人の術士でも彼に適う者は数える程しかいなかった。
そのアスラが十六になったばかりの頃、彼は『成人の儀』に参加することを決めた。
『成人の儀』とはハイデンに古くからある伝統であり、その年に成人する者は村の外から渦の獣の首を持ってこなければならない、という通過儀礼だった。この試練は厳格であり、この試練に失敗すれば命は無く、例え帰ってきたとしても、獣の首が無ければ二度と村に入ることを許されず、時には射殺される事もあるというものだった。
ただ、その峻烈さ故、なかなか若人達が参加しないのが問題となっていた。
「十八人か。今年は随分と多いな」
成人の儀を取り仕切る最長老が呟いた。それに答えるのは実質的な指導者で、頭と呼ばれるマルガだ。顔一面に疵のある、精悍で威厳をもった壮年の戦士だ。
「アスラが参加を決めた所為かと。あの男が参加するならばと、他の者達も腹を決めたようで」
「成る程な、若者らしい打算という訳か」
「奴の腕ならば、獣の一匹や二匹、殺して持って帰ることなど造作もないでしょう。しかし、それを当てにするのは感心できぬ話」
「確かにそうじゃ。されど、生き残ることこそが強さの証。打算もまた悪いことではない」
長老は長く伸びた顎髭を撫でながらマルガにそう答えた。
「アスラ、本当に成人の儀に出るの?」
武具を整えるアスラに、カマナという幼馴染の少女が声を掛けた。
アスラは幼い頃に両親をなくし、一人で暮らしていた。移動式の天幕には仕切りなど無く、入り口がすぐ居間であり寝室だった。そして、アスラの天幕は集落の標準と比べても質素で小さかった。
「ああ」
顔もあげずにアスラは答えた。
「なんか、みんな今年参加するみたいなんだ。メイガもスナジも参加するんだって。知ってた?あと、キドウも行くみたい」
皆、同世代の若者達だ。だがアスラとの付き合いは殆ど無かった。黙々と己が術を鍛える彼に、友人と呼べる人間は一人もいなかった。両親を失った後に自分の面倒をみてくれたカマナの家族ぐらいしか、村の者と普段関わることをしなかった。
「知らないな。興味が無いから」
アスラは武具の手入れを続けてきた。小さなクナイと呼ばれる短刀を研いでいる。
「あたしも参加しようかな。だって、みんなで行った方が成功しやすいじゃない。あのキドウでさえ行くんだもの。あたしだってさ」
キドウというのは足萎えの青年だ。とても成人の儀を達成できるとは思われていない男だ。
「やめておけ。お前はまだその強さにない」
「そう?あたしだって結構やるのよ、こう見えても」
からからと笑いながら少女は気安く答える。カマナは、アスラはただ不器用なだけで、感情を表に出さないだけだと理解していた。だから今までずっと、努めて明るく彼に接してきた。
「忠告したぞ」
「おお怖い。アスラ、あたしも成人の儀に出るからね。決めた」
そう言ってアスラの天幕からカマナは出ていった。結局、アスラは一度も顔を上げることはなかった。
成人の儀が行われる日、参加する若者達とそれを見送る親族が村の入り口の前に集まった。随分な人数になっている。十八人の参加者の中には女も五人いた。恋人同士で参加している者が殆どだ。女に成人の儀の義務は無かったが、成人できていなければ村での地位は低いままだ。男の場合は二十歳を過ぎるまでに成人の儀を達成できなければ、集落から追放となった。
「お前達が持って帰る『獣』の首はなんでもよい。ただし、一人に一つだ。これはお前達が真にハイデンの強き民として相応しいのかを試す試練だ。自分の全力を用いて事に当たるのがよい。わかったな」
頭の言葉に「はい」と若者達が答える。
ぞろぞろと若者達は村を出て行った。若者達を見送る親族の中には涙を浮かべている者もいる。そこにカマナの両親もいた。
「カマナ、必ず帰ってくるんだぞ」
「心配しないで、アスラもいるんだから」
笑いながらカマナは両親にそう言った。
若者達が村を出て二晩が経った。初めはちょっとした旅行気分だった彼らの心にも、少しずつ不安が広がり始めていた。リーダー格のメイガと呼ばれる体格のいい男が、皆を集めて話しを始めた。
「明日には獣の出没する境界に近付くことになる。皆で協力し合って試練を達成するんだ」
「でも、どこに行けば獣を見つけられるんだ?手頃な獣がどこにいるかなんて知らねえぞ」
「それは皆で協力して……」
メイガの話に反発の声が上がる。
焚き火の周りに集まった若者達は、不安と興奮から好き勝手な意見を述べ始める。
「ねえ、アスラ!ここら辺まで来たことある?どっちに行けば獣がいるの?」
何も発言しないアスラに、カマナから話を振った。その一言が発せられると、一斉に皆がアスラを探した。しかしアスラは見当たらない。皆、近付き難いが村一番の使い手であるアスラに期待していた。奇妙な静寂が辺りを包む。
「東だ。このまま東に行けば、何度か獣を見かけた場所に着く」
アスラの声だけが響いた。おそらく気配を消して木の上で休んでいるのだろう。
彼は成人の儀など関係なく、何度も獣と戦っていた。本来、成人前の子供が村の外に出ることは許されていない。ただ、卓越した術の使い手であるアスラは、特別に咎められることもなく村と外を行き来していた。
「だってさ。東に行ってみない?」
カマナが提案する。
「どんな獣に遭ったんだ?十角獣?それとも火吐鳥?」
他の者からも質問の声が上がる。どちらもよく知られた獣だ。中型で、油断しなければ大した脅威ではない。
「どちらもいた。ただ、気を付けた方がいい」
アスラの姿はまだ見えない。声だけが低く響く。
「よし、ならば決まった。明日、東に向かうぞ。なるべく早く出よう。危険な場所で夜を迎えるのは避けたいからな」
騒然とした一夜の集まりは、こうして終わった。
次の日、若者達は東へ進んだ。アスラの姿は見えない。少し集団から離れて進んでいるようだ。
しばらくすると、キドウが集団から遅れ始めた。ここまでは何とか集団に付いてきていたが、そろそろ無理が出てきたようだった。
「キドウ、諦めて帰ったらどうだ?お前には無理だ」
森に笑い声が響いた。
「泣いて謝れば、きっと長老様も許してくれるぞ」
また笑い声が湧く。キドウは笑い声を無視して、不自由な足を引き摺って付いていく。「俺は諦めない」と、誰にも聞こえないくらいの声で呟きながら。
しばらくすると、前方の森の茂みが大きく揺れた。誰かが叫んだ。
「十角だ!」
子牛くらいの大きさで、十の角を持つ四足獣がこちらに顔を見せた。
「そら、追い立てろ」
集団が色めき立った。こんなに早く適当な獲物が見つかったのは幸運だった。
「俺が一番乗りだ」
興奮した様子の若い男が十角を折って走り出す。次々と争うように四、五人が隊列から離れて、回り込もうと森に散った。
すると森の中から悲鳴が上がった。集団に戦慄が走る。
「まさか、十角なんかにやられたのか?」
彼らも、アスラ程ではなくとも術は心得ていた。それぞれ自分専用の武具を持った、若くとも鍛えられた戦士であった。
「まさか」
残った者達がしばらく動けないでいると、血生臭い匂いが周りに立ち込めはじめた。
「くそ、何が起きたんだ!?」
回り込んだ集団を助けようと、二人がまた森に消えた。
「なに?どうしたのみんな!ねえ、返事して!!」
残った集団は女のほうが多い。不安で震えている者もいる。
「ねえ、アスラ、どこ?助けて!」
カマナが叫んだ。
「俺はここにいる」
アスラの声がする。
「十角を追っていったみんなから、返事がないの」
カマナの声は泣き声に近い。
「忠告したはずだ。気を付けろと」
アスラの声に感情は籠もっていなかった。
「冗談はやめて出てきて!向こうに何がいるの?お願い、私達と一緒にいてよ」
返事は無い。
何かが森を高速に走る音が静寂を破った。残った集団の前の森が、勝手に開けたかのように木々を倒していった。
その向こうに巨大な『獣』がいた。それは漆黒の巨大な蜘蛛だった。何もかもを切り裂く鋭い脚とその色から『黒曜蜘蛛』と呼ばれている獣だった。蜘蛛は何体もいた。待ち伏せしていたのだ。集団は蜘蛛に囲まれていた。
狼狽した一部の者を除き、若者達は剣を構えて蜘蛛と対峙した。
しかし次の瞬間、一斉に蜘蛛の脚に切り裂かれる。蜘蛛のたった一振りで、三人の首が宙を舞った。
「アスラ!!」
カマナの悲痛な声が響く。だがその声を上げたまま、彼女は蜘蛛の餌食となった。振り下ろされた爪は肩から胸に至るまで彼女を引き裂いた。遠ざかる意識の中でアスラの声が聞こえる。
「俺は言った。やめておけとな」
冷徹な言葉が、蜘蛛達が餌食を屠る音に混じって森の中に響いた。
陰惨な宴が終わった後の森に、再び静寂が広がった。気配を消していたアスラが地上に降り立つ。
「弱いからこうなる」
一人呟いた。だがその時、何かの気配を背後に感じた。そににいたのはキドウだった。その手には十角の首がある。
「うまくやったようだな」
「アスラ、こいつらを見殺しにしたのか?」
「いいや、弱いから勝手に死んだだけだ」
「そうだな、弱いから死んだんだな」
キドウの顔に笑みが浮かぶ。
「先に行く」
アスラは足元に置いた黒曜蜘蛛の首を抱えて去っていった。若者達を襲った蜘蛛は全てアスラの手に掛かり、首を失っていた。
アスラの帰還に村は騒然となった。成人の儀に参加した若者の親達が、アスラの元に集まっている。
「本当に、本当に皆やられたの?」
「黒曜蜘蛛の待ち伏せに遭った。俺が追い付いた時には、皆死んでいた」
「なぜなの、アスラ。あなたが付いていながら!」
カマナの両親がアスラを責める。
「悲しむな。弱い者は生まれてこなかったのと同じ。それがこの村の掟じゃ」
長老が間に入って両親を諌めた。残酷な掟を長老は繰り返し述べる。その場にいた親達は泣き伏せった。
「よくやったな、アスラ」
アスラが幼い時に母親は病に犯され、徐々に痩せ細っていった。父親はもっと前に獣に殺され、その思い出はアスラの記憶に無かった。母親はたった一人で彼を育てていた。しかし病はひどくなるばかりで、伏せっている日々が続いた。
十年前、六歳の時、村の移動の日が近付いてきた。村は三年に一度移動をする。その時、付いていけない者は置いて行かれるのだ。
これはこの部族が生き残るために行ってきた手段だった。一族から弱者を廃する意味もあった。母親は悲しむ素振りも見せずに、アスラの手を握って何度も言った。「しかたない」と。今は母親の顔も思い出せなくなっているが、その細く白い指先の感触は、今でもはっきりと覚えている。
とうとう出発の日が訪れ、母親との別れの時がきた。しかし、アスラは全く涙を流さなかった。母親は最後の別れ際に言った。「強く、強く生きなさいと」と。
天幕も無く、雨晒しの地面に粗末な藁を敷いた上に母親は寝ていた。他の家族と共に村から離れる時、アスラは何度も振り向いた。母親は半身を起こして、ずっとこちらに手を振っていた。
それが最後の姿だった。
『成人の儀』の事件があった後、しばらくの間はアスラに感情的な敵意を向ける者達がいた。ただ、そんなアスラを庇ったのが、同じ成人の儀に参加してアスラ以外にただ一人帰還したキドウだった。
「アスラは皆を必死に助けようとしていた。声高にそれを説明しないのは、彼の誠実さだ」と言い、「足萎えの自分が帰ってきたのが、その証拠だ」と皆に説明した。その内に、仲間を見殺しにしたのではないか、という疑義は忘れ去られた。
そうして『成人の儀』から三年も経つと、アスラは副頭目候補に挙げられる程になっていた。
感情を表に出さない、冷厳な性格で知られていたが、このハイデンの社会では強さこそが全ての尺度の中心であった。
「では、一族の新たな副頭目にアスラを任命する」
アスラはついに、頭から副頭目の証である鉢巻を受け取った。証を身に着けて長老と頭、他の副頭目の前に出たアスラの瞳には、より一層冷たい光が宿っていた。
「―了―」
3396年 「誓い」 
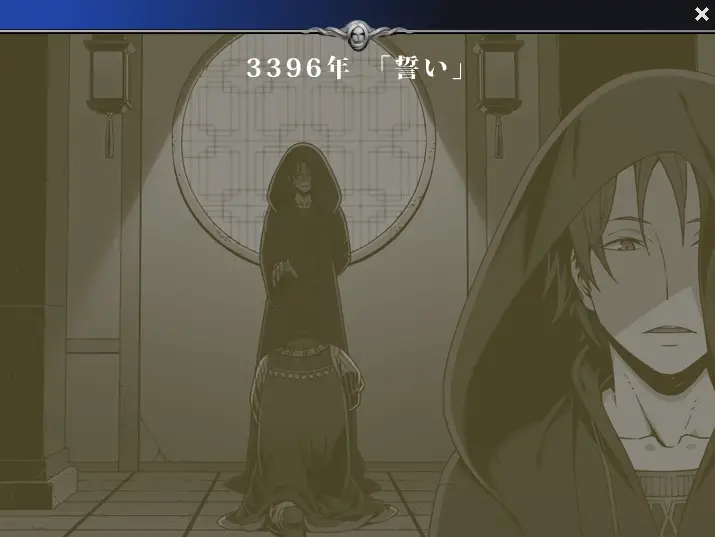
「報告は以上です。やはり、新女王の後見人争いは微妙な雲行きのようです」
「ご苦労だったな、アスラ。よく働いてくれた」
リュカは瞑想の途中であった。そこへ密偵として王都に派遣されていたアスラが帰還し、連合王国の国政の背後関係について報告に来たのだ。リュカは目を閉じたままアスラの報告を聞き終えた。
「リュカ様、次のご命令を」
「うむ。その前に、お前の意見を聞きたい」
リュカはゆっくりと目を開けた。その姿は、荒野を旅していた時と変わらぬ、東方の民族衣装そのままだ。
「リュカ様が立つのも一つの手かと。このまま後見人争いが長引けば、いずれ安定を求めてリュカ様の統率力と軍事力が必要だと考える者が出てくるでしょう。内々ですが、一部の者からは言質も取れています」
アスラは顔を伏せたまま言った。
「ふはは。それは出過ぎだな、アスラ。儂は今、女王を支えることしか考えておらぬ。確かに一時は自ら先頭に立とうと思った。戦争というのは何より決断の速度が重要だからな。軍を率いる者がなるべく大きな権力を持った方がいい」
「はい」
「しかし、それは常道よ。若き日の、いや、過去の戦いではそれでよかったかもしれん。だが此度の戦いは、常道では乗りきれぬと感じておるのだ」
先王の急死により、ルビオナ連合王国は混乱の最中にあった。そして、新女王即位の直後に起こったトレイド永久要塞の陥落をはじめ、ルビオナの劣勢は明白なものとなっていた。
「しかし、このままでは帝國の攻勢に対して、無力なまま敗退を続けることになるでしょう」
「そうだな。しかし、我々が対峙しているのは何だ?」
「グランデレニア帝國です。大陸で最大の勢力を誇る強国です」
「そうだ。しかし今や帝國は只の強国ではない。トレイドでの怪異、知っているな」
「歩く死者のことですか?」
「そう、恐るべき怪異だ。それに永久皇帝の復活の報もある」
リュカは瞑想を終え、アスラの前に立った。アスラは顔を上げていない。
「世界は新しい時代に達したのだ。渦を乗り越えたこれからは、次々とこの様なことが起こるであろう。死者が蘇り、不死を名乗る王が世界を手に入れようとしているのだからな。奴らは世界の摂理を変えてくる。過去を捨てねばならぬ。上手くいった過去に拘泥していては、未来を失うことになる。今を正しく見つめ、新しい世界に合わせるのだ」
「御意のままに」
「アスラ、お前にも新しい知見が必要だ。体術だけでは勝てぬ。強くあり続けるためには、前に進む必要がある」
「はい」
「お前には帝國に行ってもらいたい。特に帝都ファイドゥだ。彼の国へ行き、肌で彼らの世界を感じるのだ。私が東方で力を得たように、お前は西方で知識を得てくるがいい」
「わかりました」
「アスラよ、魂の思うままに行動してみろ。儂の命令ではなくな」
アスラは頷き、その場を辞した。
アスラはリュカと出会い、古き盟約に従って、リュカと共に王国の中枢で働くこととなった。彼の手となり足となり尽くしてきたが、違和感が無いわけではなかった。それはあの貧しい村での過酷な生活と、洗練され文明化されている中央国家の文化との間にある違和感でもあった。
故郷では常に死が身近にあり、明日をどう生きるか意識していた。己が力をどう生かすのかを、日々の鍛練を通して見つめ直していた。
それが、巨大な国家の中、制度化された文明国家の中では極端に薄まっている。死を間近に意識できたのは、戦場ぐらいなものであった。
力にしてもそうだ。リュカの属する政治の世界は生死を賭けた力の世界ではあるが、その世界には、アスラのように無言で相手を屠る技術では乗り越えられぬ、別種の力学が存在していた。
昨日の敵を今日の味方とし、昨日の友を今日切り捨て、目標を遂げ、力を行使する。それが、文明化された政治の世界だった。
アスラはこの世界に適応していた。何年もリュカと共に過ごし、文明化された世界での所作も学んだ。
と同時に、あの村で命懸けで磨いた技もまた、鈍らぬように鍛錬を重ねていた。
そして、同じように盟約に従ってリュカの下に来た部族の仲間とともに、できる限り戦場に出向いてその力を振るった。
遊撃隊としてリュカの軍勢に組み込まれたハイデンの民は、目覚ましい戦果を上げた。対帝國戦においても、敵兵を退ける活躍をした。
しかしそんな日々の中でも、アスラは焦燥を感じていた。
リュカの腹心としてそれなりの地位に就いてはいるが、所詮異民族の雇われ者という扱いから脱することはなかった。リュカはハイデンの民に敬意を払っていたが、他のメルツバウの貴族や中央の民らは、ハイデンの民に対する差別心を顕わにする者が多くいた。
それ自体については、アスラは恥辱を感じてはいなかった。彼らなど、アスラが本気で掛かれば数秒で絶命する虫のような存在なのだ。蚊の羽音は不快だが、恥辱を感じる性質のものではない。
ただ、己がここに居続ける意味や目的を失いかけていた。
曲がりなりにも連合王国第二の政治力を持つ大公の側近として多額の報酬も得ていたし、存分に技を使う機会も得ていた。
リュカとは盟約を超えて、互いの利益を一致させていた筈だった。
にも関わらず、違和感、焦燥感をリュカに見抜かれていたのだった。それが、先の帝國への密偵としての仕事だったのだ。
「どうしたアスラ。リュカ様の話は何だったんだ?」
アスラに声を掛けたのはキドウだった。不自由な足は奇妙に歪んでいる。成人の儀から月日が経ち、彼は彼なりに己の障碍を克服していた。その独特の足さばきから繰り出される体術は、今では接近戦で抜群の強さを誇るようになっていた。
「一度王国を離れ、帝國に向かうように言われた」
リュカの真意は測りかねていたが、与えられた任務は果たそうと決めていた。
「ふむ、面白そうだな。ここの生活にも少々飽きた頃合いだしな」
キドウとは奇妙な関係だった。成人の儀以降、キドウはアスラを常に立て、真っ先にその指示に従う忠信を見せていた。アスラはそれを受け入れ、頭の切れるキドウを重用するようになった。
ただ、互いに多くは語らなかった。二人の関係は、言葉ではなく行動でのみ示されるものだった。それでも、彼ら二人は互いに通底する一種の価値観を共有していた。
「帝國か、あそこでなら色々と力が試せそうだ」
「かもしれんな」
アスラは言葉少なく同意した。
まずアスラは、キドウを筆頭に少数の部下を伴って帝國に向かった。美術商を装い、密輸を請負う無法者として、帝國の闇社会に名を売ることにした。
「密偵という大きな嘘を密輸業者という小さな嘘で覆い隠す。帝國政府の権力中枢と闇社会との間には、必ず接点があるはずだ」
キドウの言葉にアスラは頷いた。
キドウは東方の変わった特産品を集めさせた。交易が活発になったといっても、帝國の大都市にこのようなものはまだ珍しかった。
そして、まずローゼンブルグの犯罪組織に伝手をつけた。帝國の悪徳を一手に引き受けているあの都市から足掛かりを得るのが得策、というのがキドウの考えだった。
間もなく、アスラの集団はローゼンブルグで名を上げた。キドウを頭目に仕立て上げてその交渉力を生かし、都市の中でも生きる戦闘力を使って他のグループを出し抜いた。ある時など、取引相手の敵対グループを数日で葬ってみせたこともあった。
「奇妙な連中だな。なぜ帝國に来た?」
ファイヴと名乗るローゼンブルグの巨大組織の幹部に聞かれたことがあった。
「流れですな。渦が無くなり、我々の世界も広がったんでね」
そのキドウの言葉には東方の訛りを戯画化したような響きがあった。キドウは何事にも器用な男だった。
「余所者にやるシマはここには無い。だが、お前らの働きは買ってやる。上手くやれば稼がせてやる」
「ありがたい話ですな。上手くやらせてもらいますよ」
キドウは余裕のある調子で相手に合わせた。
「カシラ、この暮らしも中々面白いと思うよ」
キドウがアスラにそう言った。傍目には、豪華な民族衣装を纏ったキドウに対してシンプルなフードを被っただけのアスラが、使用人のように見えた。
「所詮、小さな世界だ」
アスラは穏やかな調子で答えた。
「しかし、この社会は力さえあれば何でもできる。このまま行けば、ルビオナにいた時よりも稼げそうだ」
「贅沢がしたいのか?」
「経験しないより、してみたいというのが性分なんでね」
「成る程。だが、目的とは違うな」
「目的と言っても、帝國へ行ってこいとしか言われてないんだろう?」
キドウはどこか密輸業者の頭目を演じ続けている調子だった。
「そうだ。だがルビオナには戻る。近いうちにな」
短い沈黙が二人の間に流れた。
「なあ、じゃあ俺と仲間だけでも、ここに残してくれないか」
キドウの目は輝いていた。しかし、アスラは感情を表に出していない。
「い、いや、これは裏切りでもなんでもない、これはカシラのためにもなる話だ」
キドウは慌てて言葉を継いだ。
「聞かせてもらおう」
「若い奴らだけでいいから、里からここに人を送り込ませよう。俺達の力があれば、この辺りの闇社会の連中なんざ、あっという間に仕切れる」
「仕切ってどうする?」
「いずれルビオナは帝國に滅ぼされる。その時、ここで財を成しておけば皆が助かる」
「皆?」
アスラの眼光が鋭くなった。
「あ、ああ。カシラだってわかってる筈だ。リュカ様の力だけではどうにもならぬことを。要塞での戦い、俺はこの目で直接見た」
キドウはトレイド要塞の戦いに参加していた。
「あれじゃあ勝ち目はない。力の差は歴然だ」
「頭のいいお前らしい考えだな。だが、盟約はどうする?」
「あれは体のいい建前のようなものだろう。カシラもそう考えていると思っていた。俺達は力に見合った富や暮らしを手に入れるべきだって」
「力に見合う富か……」
「カシラ、頼む。俺はあんたにずっとついてきた。あんたの力を信じてきた」
キドウは懇願する調子でアスラに言った。
「ここからは別の道を、いや、俺の道を行かせてくれ」
「いいだろう。但し、ここで誓いを立ててもらう」
「ああ、カシラの頼みならば何でも。今までだってそうやってきたんだ」
少し間を開けて、アスラが口を開いた。
「俺が死ねと言ったら即座に死んでみせろ。一切の理由を聞かずにな」
アスラの冷たい眼光がキドウを捉えていた。
キドウはこの問いに否とは言えなかった。もし断れば、何の躊躇いもなくアスラはキドウの首を切り落とすだろう。
今ではキドウ自身も腕に自信がある。だがそれ故に、天才と呼ばれたアスラに逆らうのは無駄だということを、よくわかっていた。
「カシラの誓い、守らせてもらいます」
目を閉じ、キドウは跪いた。
「―了―」
3397年 「捕縛」 
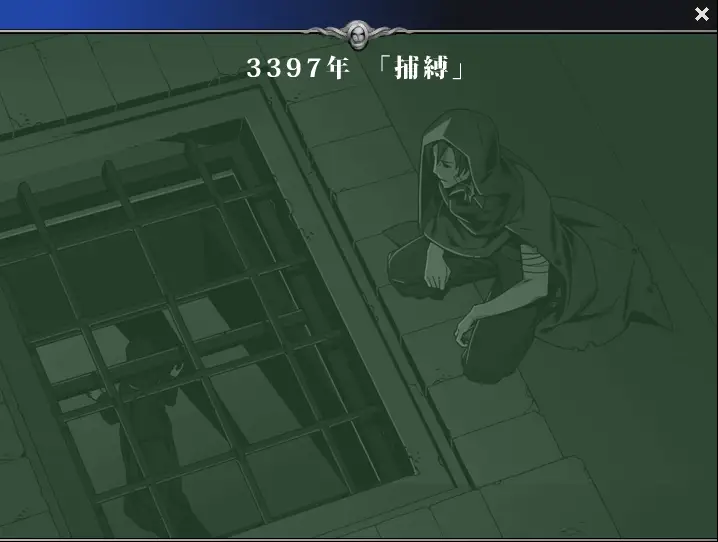
アスラは密輸業者として、キドウと共に帝都へ商談に赴いていた。ファイヴの伝手により、下位ではあるが帝國議会の政治家に近付くことができた。これはローゼンブルグの闇社会で一定の実績と信頼を得たキドウの手腕によるところが大きい。
誓いの後、キドウは多くを語らなくなった。アスラも黙ってその行動を見届けていた。
ただ、逐一キドウの動きは監視し続けていた。
帝都では毎日のように地方制圧の報、戦意高揚の宣伝が繰り返されていた。前線の苛烈さと程遠いそれは、却って銃後の豊かさを強調しているように感じられた。この帝國において、戦争とは産業であった。
この街では国家が作り出すこうした途方もない力を肌で感じ、また考えることができた。
そして政治家との接触で、グランデレニア帝國にもルビオナと同じように派閥が存在し、戦争の恒久的な続行を阻む派閥があることを知った。
「政治家も、戦争中は安泰とはいかんのです。今日日は暗殺なんて物騒なことも起きる。そうなると色々と入り用でね」
キドウの差し出した賄賂を受け取りながら、政治家はそうぼやいて見せた。交易権の便宜を図ってもらうために会った小人だったが、表には出てこない、帝國の枢要で起きている情報を入手できた。
どこの世界にも、どんな場所にも争いはあるということだ。この事実を持って一度ルビオナに戻る必要がある。アスラはそう判断した。
「カシラ、向こうにはいつ戻るので?」
拠点に戻り、人気のない場所で一人瞑想をしていると、部下の一人であるミカギがやって来た。
「聞いてどうする」
アスラは目を開けることなくミカギに答えた。
「お願いがあります。今回の帰還に私も同道させてください」
「何故?」
アスラは疑問を口にした。
ミカギは単独で行動するアスラよりも、密輸業者の頭目候補としてキドウと共にいることが多い人物だった。
「お恥ずかしい話ですが、西の風土が私には合わないのです。鍛錬が足りぬと言われればそれまでです。ですが……」
「好きにするといい」
「ありがとうございます!」
それから数日後、ミカギを伴ったアスラは出国手続きを行うために国境検問所にいた。
アスラ達は、美術商の仕事で東方に品物を買い付けに行くという体で、許可証の交付を受けていた。先にミカギが出国許可証を出し、何事もなく通過するのを見届けてアスラが続く。アスラが出国許可証を見せると、職員が許可証を手に取って立ち上がった。
「少々お待ち下さい」
職員は、出ていってからいくらも経たない内に戻ってきた。
「申し訳ございません。許可証に記載漏れがあるようなので、簡単な書類をお書きください」
アスラは検問の列から離れ、別室へと案内された。傍には警備兵が同行している。
政治家からの手引きで入手した正式な許可証の筈だが、様子がおかしい。それでもアスラは一切の動揺を見せずにいた。
通せれた別室には、すでに帝國兵が待ち受けていた。
「お前をスパイ容疑で逮捕する」
すぐに両脇を固められるように捕縛された。自殺を防ぐために猿轡を噛まされる。アスラはそれらを抵抗せずに受け入れた。乱暴な身体検査を受けた上で護送車に放り込まれ、車が動き出した。
アスラは誰もいない護送車に、瞑目したまま座っていた。
暫くすると目を開き、狭い車内でゆっくり左手の関節を外し、手錠から抜き取った。そして猿轡はそのままに立ち上がると、運転性に向かって身体をぶつけて警備兵達の注意を惹いた。覗き窓から警備兵がこちらを確認する。するとアスラはその覗き窓二頭を激しくぶつけた。何度もぶつけ続けると、額から血が噴き出す。
「くそ、自殺か!狂ってやがるな」
窓に飛び散る鮮血に自殺を疑った警備兵が、そう呟いて車を止めさせた。
上官らしき男が片方の兵士にそう命令する。部下の兵は銃を担ぎ直して護送車に乗り込み、アスラの横に立った。その瞬間、アスラは跳ね起きるように立ち上がり、兵士の喉元を外しておいた手錠の切っ先で力任せに掻き切った。血を吹き出しながら絶命する兵士を盾にしながら、外にいる上官にぶつかっていく。状況に恐慌している上官を当て身で倒し、その銃を奪った。
猿轡を外して手錠を捨てると、すぐに運転席に向かい、銃を突きつけてドライバーに車から下りるよう命令した。
運転手に死んだ警備兵二人の始末を手伝わせると、今度は服を脱ぐように命令した。脱ぎ終わった服を受け取ると、アスラは運転手をすぐに撃ち殺した。
額の血を拭い、簡単な止血をし、運転手の服に着替えると、護送車を発進させた。
窮地を脱出したアスラは、身を隠しながら二日でローゼンブルグの拠点へ辿り着いた。事の次第については予想できていた。それでも、当然の決着を付ける必要があった。
拠点ではキドウが誰かと話をしている声が聞こえた。相手の声は聞いたことがないものだった。
「なんてことです!逃がすなんて!ヤツは……」
「いずれ見つけ出す。ただ、間諜などというのは、ヤツだけではないのでな」
「いいや、あの男は厄介な男でして……てっきりあなた方が対処してくれるのだと……」
キドウはあくまでも密輸業者を演じているようだった。
「対処はした。だがその方法までお前に指図は受けぬ」
「ヤツはその……」
アスラは静かにキドウが喋るのを聞いていたが、少し経つと、拠点の中へと入っていった。
何事もなかったかのように拠点の廊下を歩いていると、ミカギに出会う。
「ア、アスラ!?どうし……」
アスラは何も言わずにミカギから武器を奪い、ミカギの首を取る。
「なにか言うことはあるか?」
アスラは静かな声で問うた。
「頭目……キドウが、このままルビオナに付いていても死ぬだけだって……だから……」
観念したのか、ミカギはキドウに言われたということを喋った。
「脅されて……だから……助けてくだ……」
アスラはミカギの首をそのまま締め上げ、へし折った。
ミカギの武器を持ったまま、アスラはキドウのいる部屋の扉を開け放った。
途中、キドウに付いて残った部下達を全て一撃の元に葬り去った。おそらく、己が死んだことにも気付いていないだろう。
「アスラ……」
冷たく一瞥すると、キドウはゆっくりと立ち上がりながら震える言葉を発した。
「さすがカシラだ。本当に素早い……」
キドウの喉元がごくりと動く。
「この間合でまだ生きてられるってことは、俺の話を聞いてくれるのか?」
アスラは黙っていた。
「俺はこの国に来て『自由』ってものの意味を知った。だが、カシラはそれを絶対に許さないこともわかっていた」
喋りながらキドウは、腰の剣にゆっくりと手を回す。
「けれど、自由を選ばずに死ぬ訳にはいかなかったんだ!掟だの盟約だのに縛られない、自由になる道を選んだんだ!!」
キドウは長柄のナイフを腰から引き抜いた。
「だが、貴様は負けた。弱いからだ。心も技も。ここで死ぬがいい」
アスラは口を開いた。
「……ああ、カシラに従うよ」
キドウはナイフを自分の首に当てると、勢いよく引き抜いた。そして血を吹き出しながら膝を突いて倒れると、絶命した。
「成る程、興味深い」
突然、背後から声がした。キドウと会話をしていた人物の声だった。
振り返ると、赤と黒の衣装を纏い、仮面を付けた者がそこにいた。
その声は、男か女かの判別はできそうにない。
アスラは持っていたナイフを仮面の人物の首元目掛けて投げ付けた。
仮面の人物はその飛んでくるナイフを空中で握ってみせた。尋常の人間ではあり得ない技だ。
「色々と調べていたが、想像以上のようだ」
アスラの中で、この得体の知れぬ者に対する警戒心がもたげた。
「逃げ道はない」
仮面の奥から、こちらの心を詠むかのように言った。
「もう少し手合わせを願おうか、我々と」
「―了―」
3398年 「狂乱」 
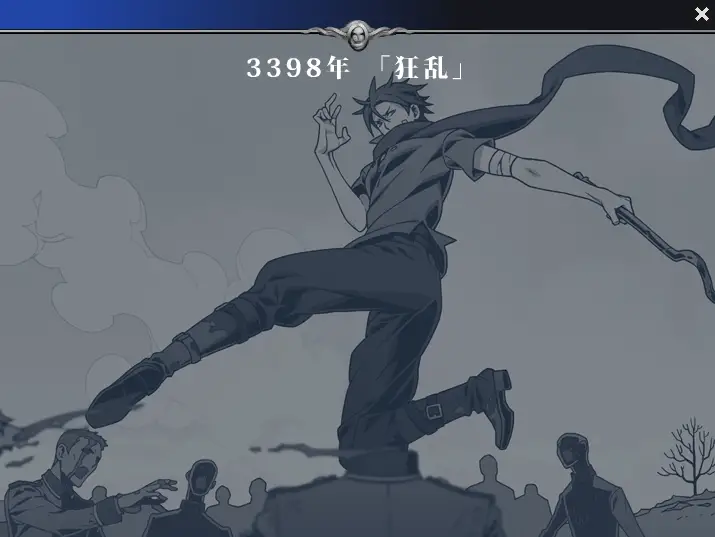
「もう少し手合わせを願おうか、我々と」
そう言い放たれたと同時に、背後からもう一人、仮面の者が現れた。
存在すら気取らせずに現れたことに、アスラは警戒心をより一層強めた。
「キドウと言ったか。あれはとても賢い男だった。我々の目的の真意を見抜く、本物の目を持っておった」
仮面の者の言葉に答えることなく、アスラは戦闘態勢に入る。
背後にいた仮面の者が機械鉾を取り出して振りかぶる。狭い室内で振り回されたそれは、調度品を壊しながらアスラに迫る。アスラは背後と目の前の仮面の者に向けて再びナイフを投げる。相手がナイフを叩き落とす僅かの時間を利用して煙玉に火を点け、地面に転がす。
一瞬にして室内は白い煙に包まれた。
だが、仮面の者は煙の中でもアスラの動きを読んでいるような行動を見せた。機械鉾が正確にアスラのいる場所に振り下ろされる。
煙が少し薄まってきた頃、仮面の者の眼前にアスラがゆらりと姿を現した。
二人の仮面の者は迷うことなくアスラに向かって機械鉾を突き出す。アスラの身体が二本の機械鉾に貫かれたように見えた。また少しだけ煙が薄くなる。
アスラはキドウの死体に己が纏っていたローブを被せ、囮に仕立て上げていた。
キドウの死体を身代わりにして稼いだ隙に、アスラは声を発していた仮面の者の背後に回り込み、そのまま首を掻き切る。
首を切り裂いた手応えは確かにあった。
しかし、仮面の者は首から血を噴き出しながらもアスラの腕を掴み取った。凄まじい力でアスラの腕を捻る。
繊細そうに見える細い手からは想像もつかないほどの握力に、アスラは初めて喫驚する。
アスラが次の行動に移ろうとした瞬間、背後に強い衝撃が走った。
幾度も続く強い衝撃に、ついにアスラは昏倒した。
暫くの監禁が続いた後、アスラは薄暗い部屋に連行された。
部屋の明かりが灯ると、周囲には複数の仮面の者がアスラを囲むように立っていた。
「さて、なかなか面白い鼠のようだ」
目の前の仮面の者がアスラを見下ろすようにしていた。
傍には白い軍服を纏う女が、寄り添うように立っていた。
その女はトレイド永久要塞で負傷し、長らく戦線から退いていた帝國の女将軍であることがすぐにわかった。
言葉を発するのは目の前の仮面の者だけで、女将軍も含めた他の仮面の者達は一言も発せずに、アスラをじっと見つめていた。沈黙が部屋を包み込む。
「我々もこの程度で貴様が屈服するとは、露程も思っておらぬ」
仮面の者は機械鉾を振り上げると、抵抗する術のないアスラに打ち付ける。
それでも、アスラは悲鳴や呻き声の一つも上げない。
「やはりな。結構な精神力だ」
わかり切っていたかのように、仮面の者はアスラを見やる。
「ならば、これはどうかな?」
合図と共に周囲の鎧戸が音を立てて動く。アスラの眼下には高速で移動する地表が見えた。
帝國が擁するする巨大戦艦ガレオン。その一室にアスラはいた。
地上では大勢のグランデレニア帝國兵とルビオナ連合王国ではないどこかの国の兵士達が激しい戦闘を繰り広げていた。
数人の仮面の者がアスラの拘束を解いて抱え上げ、その光景を見せつけるように窓に押しやる。
「見るがよい。これが我々の力の一端だ」
緩やかな振動が部屋を包む。ガレオンが着陸した。
「さあ、死を振りまくのです」
仮面の者に寄り添う白い女将軍が、ここで初めて声を出した。女将軍の合図と共にガレオンのハッチが開き、死者が屍の兵となって解き放たれた。
死者が放たれて少しの内に、生きる者を死者へと変えた。どこかの国の兵も帝國の兵も、死者へと変わった兵に対抗する手段を持ってはいない。
「この恐怖、貴様にも身をもって知ってもらおう」
一人喋っていた仮面の者は外の様子を見ると満足げに頷き、女将軍を連れて何処かへ去っていった。
彼らが去ってから程なくして、アスラの目の前に死者が現れた。
アスラを押さえていた仮面の者達は、アスラから離れると抵抗することなく死者に殺され、そのまま屍の兵の一部と化した。アスラは何も持たぬ状態で死者達と対峙しなければならなくなった。
「これは全ての生けるものが行き着く先にあるものだ」
どこからか仮面の者の声が響く。
「だが、それも我々が目指すものから見れば、通過点に過ぎぬ」
その声と同時に、部屋から外部に通じるハッチが開いた。アスラは死者を避けるために、素早く外へ出る。
ガレオンの外では、死者が生きている者に襲い掛かる光景が繰り広げられていた。
死者は敵味方を区別することなく生きている者を襲う。その様はもはや戦争ではなく、只の蹂躙であった。
ガレオンが着陸したのは戦闘の中心地であったため、何処を見ても屍の兵が跋扈していた。
戦闘で死んだ兵士の死体がそこかしこに転がっている。今はまだ物言わぬ肉の置物だが、いつ自分に襲いかかる屍の兵と化すかは予想が付かない。
アスラはまずはこの戦場から離れ、メルツバウに帰還することを第一と定めた。
近くに見える森の中に分け入って屍の兵をやり過ごし、メルツバウへの帰還の道を探ることにした。
最初の内は上手くいっていた。屍の兵の足取りは鈍重であり、振り切ること自体は容易であったのだ。
だが、森の中にも複数の屍の兵が潜んでいた。そして屍の兵は匂いに酷く敏感だった。アスラが何処へ隠れてやり過ごそうとしても、確実にアスラの潜む場所を探し当てた。
その都度、アスラは反撃した。森を利用したトラップや、太く頑丈な木の枝と石を組み合わせた即席の武器で応戦する。時には屍の兵が取り落とした壊れかけの兵器をも利用した。
どれ程の時間、屍の兵達と戦っただろうか。少なくとも一度なりと夜を迎え、朝焼けをその目で見ていた。
アスラは体力が消耗し始めてきたことに危機感を覚えた。
ついにアスラは屍の兵に取り囲まれた。
アスラが爆弾に手をかけたその時、不意に屍の兵達の動きが止まる。同時に、凄まじいエンジン音が周囲に響き渡った。エンジン音はそのまま西の方に向かって消えていく。ガレオンが飛び去ったことはアスラにも理解できた。
ガレオンが視界から消えた後、残ったのは動かなくなった屍の兵と、満身創痍のアスラだけだった。
アスラは身震いした。
『これは全ての生けるものが行き着く先にあるものだ』
仮面の者の声がアスラの脳裏を支配する。
「ふ、ふふふ……ふ……」
アスラの口から笑いが漏れる。目の前にある破滅に、アスラは言いようのない感情を抱いていた。
それが愉悦なのか、それとも恐怖なのか、アスラ自身にもわからない。
「はは、はははは。ひは、ははははは、げあははははは!!」
一度溢れた感情は留まるところを知らなかった。
――帝國も、連合も、他の国も関係ない。ただ死のみが在る世界――
アスラは死の力の行き着く先を見てみたいと強く願ってしまった。
死に支配された戦場で、誰の耳に届くこともない狂った笑い声が、ただ響き渡っていた。
「―了―」
3399年 「固執」 
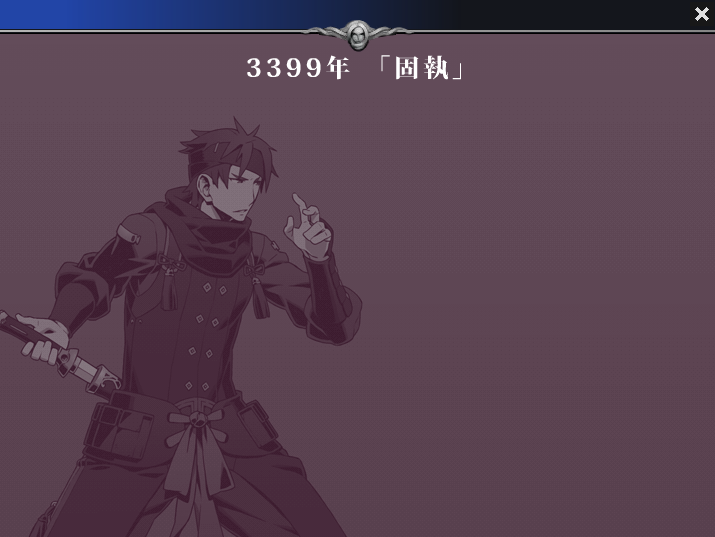
誰もいない広々とした謁見の間、その玉座にグランデレニアの不死皇帝が座っていた。
「……来たか」
不死皇帝は音も無く眼前に現れたアスラを一瞥すると、うすら笑いを浮かべた。
アスラは無言で不死皇帝に視線を向ける。
「我々はこれより、交易都市プロヴィデンスにガレオンを投入する」
感情が読み取れない不死皇帝の声が響く。
「貴様が為すべきことは何か、わかっておるな?」
アスラは不死皇帝の言葉に、静かに頷いた。
不死皇帝の間者となった後も、アスラはリュカの下で使命を全うしていた。
忠義、忠誠、古の盟約、連合国、帝國、何もかも、アスラにとっては全てがどうでもいいものになっていた。
今のアスラにある欲念はただ一つ。ベリンダという強大な力が世界を覆い尽くすのを見届けることだった。
弱い者から死んでいき、最後に強い力だけが残る世界。その世界を見届けるために必要なのであれば何も厭わない。ある時は不死皇帝にルビオナの動向を告げ、またある時は帝國の動向をリュカに報告もする。
そうしてリュカも不死皇帝も欺き続け、ついにベリンダを手中に収める好機が巡ってきた。
プロヴィデンスの広場に着陸しているガレオンの管制室で見つけたのは、白いフレームと複数のコードを露出させた、人間の形を成した何かであった。
これが機械人形であることは、かつての経験からすぐにわかった。
「……これが死を操る女の正体か」
ベリンダが機械であったことには驚いた。だが、あれだけ強大な力だ。むしろ人間よりも機械の方が力を御し易いのかもしれない。
死者の力がどの様な仕掛けによるものなのかは不明だ。が、もはや理に意味など無い。世界を覆い尽くさんとする巨大な力が目の前に存在している。その事実のみが重要だった。
そのような思いを巡らせていたところ、管制室の外から声が聞こえてきた。
アスラは物陰に隠れ、気配を消して様子を伺う。
やって来たのはタイレル、サルガドという二人の男だった。タイレルの方はベリンダの製造者であることが、会話から窺い知れた。
二人が会話を交わしていた途中、突如ベリンダから光る何かが立ち上がった。
その事態に対応するためか、タイレルがベリンダに近付く、二人が離れた時機を窺い、アスラはタイレルを捕獲するべく襲い掛かった。
襲撃は奏功した。サルガドという男は殺し損ねたが、タイレルの拿捕には成功した。
宙を飛ぶ不思議な球体から攻撃されたものの、それさえ破壊してしまえば、あとは簡単であった。
捕らえられたタイレルの腹部に、手始めとして拳を一発叩き込む。
タイレルからくぐもった呻き声は漏れ出る。
アスラはそれに構うことなく尋問を開始した。
「吐け。ベリンダという女を御する方法は何だ」
「ああなった以上、ベリンダを制御する方法はありません。例え彼女を制御できたとして、あなたは何をするつもりなのですか?」
「あの力を手に入れる。それだけだ」
「彼女は死そのものと化しました……。常人に扱いきれるものではない」
「そうような事は聞いていない。吐け、どうすればあの力を手に入れられる」
「無駄です。既に彼女は僕の手から離れてしまった。それを再び制御することは……」
「強情なやつだ、死にたいか」
幾度とない暴力と尋問。だが、タイレルは同じ言葉を繰り返すだけだった。
そうする内にタイレルは気絶した。強い痛みに耐え切れなかったようだ。
殺してしまっては元も子もない。アスラは一旦タイレルを解放すると、ベリンダに近付いた。
アスラがベリンダに触れようとすると、彼女を覆っていた光が移動し、管制室の壁と天井を覆った。
この光こそが死者を操るための鍵なのだろう。アスラは直感的に理解した。
そして、死を制御できるのはこのベリンダという機械だけであり、ガレオンとベリンダ、両方が揃って初めて、兵器として機能できるのであろうと考えた。
ならば、ベリンダをこの場から動かすことは得策ではない。
アスラは思案した。ベリンダをここから動かせないのであれば、やはりタイレルから全てを聞き出す必要がある。そう結論付け、意識を戻し始めたタイレルを再び尋問しようとした。
その時、獣に化ける少年スプラートと女の連合兵が管制室に入ってきた。
アスラは咄嗟に体を隠す。
タイレルと二言三言の会話を交わした女兵士が、タイレルを連れ帰ろうとする。いまタイレルを奪われる訳にはいかない。
「その男から離れろ」
女兵士に声を掛けてタイレルを引き剥がそうとする。沈黙が管制室を包む。
その沈黙はタイレルの言葉によって破られた。計画を変更し、女兵士とスプラートを葬ろうとしたが、スプラートの苛烈な抵抗によりタイレルは連れ去られてしまった。
「餓鬼が……くそ……」
アスラは失血で動きが鈍くなったスプラートを引き剥がし、床に叩きつけた。そしてそのまま、管制室を覚束ない足取りで逸出した。
スプラートに負わされた傷の手当が必要だ。その上、女兵士とタイレルを逃したことで、いつ連合兵がガレオンにやって来るかわからない。幸いにガレオンの周辺は市街地だ。身を潜められる場所はいくらでもあった。
アスラは連合兵の目を掻い潜り、一軒の民家に身を潜めた。
簡素ではあるが傷の手当を終えると、タイレルを奪回すべく、連合国の兵站に忍び込んだ。そこで、リュカとタイレルがガレオンの爆破計画を進めているという情報を耳にした。
ガレオンがベリンダ諸共に爆破されてしまうと、死者の軍勢の増加が止まってしまう可能性は高い。それは阻止する必要がある。
アスラは再びガレオンに侵入して罠を張り巡らした。暫くすると、情報の通り、十数人の白兵戦装備を装着した兵士がガレオンに侵入してきた。
今回の相手はルビオナの精鋭だったということもあり、すんなりと事を進めることはできなかった。その上、死者の軍勢にも妨げられたせいで、エイダ達を取り逃がしてしまった。
ここに至り、アスラはガレオンの爆破を止めることは不可能だと悟った。足早にガレオンから脱出する。
ベリンダを失うことになるが、次の手を打つためには生き延びることが絶対条件だ。そう考えた末の行動だった。
アスラは市街地を走り抜ける。背後で大きな爆発音が聞こえ、爆風がアスラの全身を撫でた。しかしそれらを一切気にすることなく、アスラは風に乗るように走った。
突然、物陰から一体の死者が飛びつくように襲い掛かってきた。
応戦しようとしたアスラだったが、先刻の戦闘でルビオナの精鋭を相手取ったことによって傷口が開いており、対処に一瞬の遅れが生じてしまった。
死者は長い髪を振り乱し、アスラのふくらはぎに歯を立て、その肉を食い千切らんとしていた。
「ふ、ひ、ひはは……!」
死者と揉み合いながらも、アスラは堪え切れない愉悦を露にして笑った。
ガレオンが吹き飛ばされてなお、死者の軍勢はその勢いを失っていない。己が見たいと願う世界は、未だ可能性を失っていないのだ。
アスラは歓喜に打ち震えながら、死者の攻撃に応戦した。
一人の死者が襲ってきたのを皮切りに、何処に潜んでいたのか、何体もの死者達が一斉にアスラに群がってきた。
「く……」
アスラはひたすら応戦し続けた。だが、笑い声を上げる余裕は無くなっている。
凄まじい形相で食らいつく死者を振り払い、次々に襲いくる死者達の頭部に手持ちの武器を叩き付けた。しかし、頭部を潰されたにも関わらず、死者は再び蠢き、アスラに襲い掛かってくる。
ついにアスラはバランスを崩し、死者の群れの中に倒れ込んだ。
死者達はその隙を逃すことなく、アスラに食いついた。
全身を激痛が走る。喰われていく感覚がアスラを襲った。
(しかたない)
不意に、母親の声が聞こえた気がした。
(弱いから死ぬんだ。いや、弱い者は死ななきゃならない)
成人したときの自分の声が聞こえた気がした。
――違う! それでは何のためにここまで!!――
獣じみた呻きが自らの喉から発せられる。ここで終わる訳にはいかない。
何としても、何が何でも生き延びねば。世界の行き着く先をこの目で見なければ。
その意志だけで、アスラはがむしゃらに反撃した。
死者の群れを薙ぎ払い、生き延びようと必死に藻掻く。
「あ、ぐ、ぐう、お、で……ば……ご、んな……」
しかし、死者の軍勢はそれを許さない。
アスラという人間の意志は、自分が喰われ逝く音と死者の群れの咆哮、それらの音に埋め尽くされていった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ