アーチボルト
【死因】
【関連キャラ】
3382年 「絆」 

弾丸が世界を切り裂きながら一点に向かって飛行していた。
鉛の弾はウィル・パランタインの首に掛けられた縄を千切る。
響き渡る銃声によって、群衆は散り散りにアーチボルトから離れていく。
アーチボルトの銃は馬上から間髪を入れず、捕縛していた処刑人達を容赦なく打ち抜いた。
反逆者として処罰される直前だったパランタインをアーチボルトは抱え上げ、馬に乗せる。
「ドジを踏んだらしいな。生きてるか?」
パランタインに声をかける。
「アーチボルト、お前か……なぜ来た?」
捕らえられていた間にパランタインは衰弱していたが、アーチボルトの背のしっかりとつかまった。
「その話は後だ、飛ばすぞ」
周囲の混乱の中、アーチボルトは馬を駆けた。手慣れた捌きで機械馬を操り、人と障害物を避け進む。
姿勢を立て直した守備隊が馬を捕らえようと次々に飛び出してくる。
この街の守備隊は「荒野」を渡る術を持っていないことをアーチボルトは知っていた。
アーチボルトの機械馬の駆動音が大きく唸る。散発的に続く守備隊からの銃撃を避けながら、緩急をつけた動きで門への道を駆けぬけた。
外へと続く門の前には門衛が陣取っている。そこへ速度を落とさずにアーチボルトは進む。構えた銃からは精緻な軌跡を描いて弾が飛翔し、兵たちを仕留めた。
門扉を打ち破り外に飛び出し、アーチボルトとパランタインを乗せた機械馬は荒野を進む。散発的な銃声が響くが、すぐにその音は聞こえなくなった。
追ってくる者はいなかった。
荒野には夜が迫っていた。西に沈む太陽を見ながら、アーチボルトはパランタイン達、反乱軍の拠点となっているキャンプに向かった。
パランタイン自身は「荒野」に暮らすストームライダーではなかった。
しかし荒野の民たるストームライダー達を彼の決起軍の中心に据えていた。パランタインはストームライダー達に紛れ、都市間を移動しながら革命のための準備を進めていた。
今では多くの城塞都市の守備隊にパランタイン派の部隊も増えてきたところだった。
しかし、その過程でパランタインは王国軍に捕らえられてしまった。彼が指導者だということは気付かれなかったが、怪しい者を全て厳しく処断している国軍によって、反乱軍の一味として処刑されるところだった。
アーチボルトはあらためて追っ手のいないことを確かめると速度を落とした。パランタインの様子がおかしい事に気付いたのだった。声をかけても唸るばかりだった。
日は暮れていた。荒野で一晩を過ごすのは危険なことだとわかりきっていたが、このままの状態で連れて行くのは難しいと判断し、馬からパランタインを降ろした。
「ウィル。聞こえるか?」
意識を失ったパランタインに話しかける。
パランタインは目を覚ますが、その視線は宙を彷徨っていた。
「アーチボルトか?ここは?」
「街の外だ。もう追っ手はいない」
「なぜ来た?」
「来たかったからさ」
「ごまかすな、シェイラか?」
「まあな」
アーチボルトはパランタインに水を飲ませた。ひどく熱がある。
「どこか傷はあるか?痛むところは?」
「すこしばかり休めば問題ない……。疲れただけさ」
「隠し事はしないでもいいぜ、オレはすぐ原隊に戻らないといけない」
アーチボルトはパランタインの表情に異変を感じていた。
「……胸さ。荒野の空気はオレにあわなかったらしい」
胸に手を当ててパランタインは答えた。グールド病が進行していた。「渦」の影響下にある荒野で発生する致死性の風土病だ。
真っ先に肺がやられ、その後は全身の硬直が進んでいく。パランタインはアーチボルトと同じ二十代後半だったが、やつれていてずいぶんと年かさに見えた。
「ここでしばらく休もう。眠ってくれ」
「……ああ、助かる」
パランタインは目を閉じた。
アーチボルトは立ち上がり、馬から荷を降ろした。
荒野の「獣」に見つからぬよう慎重に場所を選んではいたが、いつでも出発できるように馬と荷を配置した。
地平線の彼方には「渦」の光が夜の雲に反射していた。
パランタインとアーチボルトとは十年以上前からの友人だった。インペローダの一都市、ハイデンの州兵をやっていたころに知り合った。
アーチボルトは「荒野」に生まれたが、早くから故郷を離れて都市間を放浪していた。そんなときに気まぐれで雇われ兵として州軍に属していたとき、二人は出会った。
インペローダは王族の腐敗が進み、各都市では動乱の気配が漂っていた。治安の維持にあたる彼等州兵の仕事とは、市民に銃を向けることだった。
そんな仕事に嫌気が差したパランタインとアーチボルトは、一部の州兵とともに反乱軍として市民の蜂起に加わった。
若い二人の感情に任せた行動は苦い失敗に終わった。多くの市民が殺され、自分たちも惨めな敗北に終わった。パランタインはアーチボルトとともに荒野に落ち延びた。
二人はアーチボルトの生まれたストームライダーの一族に匿われた。ここでパランタインは革命家としての人生を始めた。
ストームライダーと共に都市間を巡り、王国内で抵抗する市民達を連携させ、指導を行った。
長い時間は掛かったが次第に彼の革命は現実味を帯び始めていた。何度も失敗を繰り返していたが、確実にその存在を大きくしていた。
しかし、その傍にアーチボルトはいなかった。
「…もう、オレがいなくとも革命は成就する 無理に助けに来なくともよかったんだ」
焚火の前で古い記憶を辿っていたアーチボルトへ、目を覚ましたパランタインが声を掛けた。
「らしくない話だな、『不屈の闘士』パランタインにしては」
「もうすぐ人生の願いが叶おうとしている。いまこのまま眠ったあと、目覚めなくとも後悔はない」
「本当か?シェイラはどうなる。お前は一人じゃないんだぜ」
苦い記憶の底にあるその名をアーチボルトは口に出した。
「もう長くないことはお互いわかってるんだ。自分なりに準備はしてきた」
「革命も、家族も出来るところまでやった。こうなったのは運命さ」
パランタインの顔は穏やかだった。
「オレはそんな風には思えないぜ。まだ出来る、まだ……」
アーチボルトは親友死病に冒されているという事実を受け入れられなかった。
「まだ…出来るか」
パランタインは目を逸らして空を見た。そして目を閉じてまた眠りについた。
日が昇り、朝になるとアーチボルトは荷を纏めた。
パランタインの症状は一晩でずいぶんと落ち着いていた。
野営地に向かって二人は出発した。
昼を過ぎた頃に拠点が地平線の向こうに現れた。近付いていくにつれ、その異変がはっきりとわかった。
野営地は完全に破壊されていた。
人影は見えなかった。
アーチボルトは馬の速度を上げた。
「―了―」
3382年 「祝杯」 

アーチボルト達が野営地のあった場所に辿り着いても、やはり人影は見当たらなかった。
「誰か、誰か居ないか!」
瓦礫をかき分けながら、呼びかけを行っても反応が返ってくる事はなかった。反乱軍の遺体も王国軍の遺体も見つからない。
野営地は破壊しつくされているものの、両軍の戦闘が起こった気配はないようだった。
攻撃を受ける前に上手く逃げおおせたのだろうか。
「ウィル」
「……こういう時に集まる場所はいくつか決めてある。そこへ連れて行ってくれ」
アーチボルトの問いを察したパランタインは弱々しい口調で場所を告げた。
「わかった。近場からまわっていこう」
馬にも疲れが見えるが留まる事などできない。もし、反乱軍に追撃されているようであればすこしでもはやく追いつかなければならない。幸いパランタインの病状は安定しているようだった。
走る馬の上でアーチボルトはパランタインに話しかけた。
「なぁウィル。そのグールド病、治せるかもしれないと言ったらどうする」
パランタインは答える。
「どういうことだ?」
「少しでも可能性があれば、賭けてみるのは悪くないと思うんだがな」
地上の医療技術では治るあてがなくとも、空に浮かぶパンデモニウムで生きるエンジニア達の医療技術なら治せるかもしれない。アーチボルトはそう考えていた。
レジメントへつれていくことが出来れば医療チームにパランタインを見てもらうことも出来る。
「……もういいんだ。王国も悪あがきはしているようだが、革命は時間の問題さ」
「医者につてがあるんだ。エンジニアのだ。あいつらだったら……」
外から連れてきた一般人をエンジニア達が治療してくれるかはわからない。ただ、やってみる価値はある。
「悪いなアーチ。俺は疲れてるんだ……」
パランタインはアーチボルトの提案を力なく拒否した。アーチボルトは説得するのを止め黙って馬を走らせ続けた。
アーチボルトは違和感に気付いた。
囲まれている。
先を急ぐ余り「獣」への注意を怠ってしまっていたのだ。
ずっしりとした体躯にラッパのような耳、そして短いながらも鋭いツノ。渦の向こうからやってきた獣に違いなかった。
それも相当に気が立っているように見える。
身一つなら如何様にも動けたかもしれないが、パランタインを乗せていては派手な立ち回りをするわけにはいかない。
「しっかり捕まっていてくれよ」
ゆっくりと周囲を回りながら徐々に距離を詰めてくる獣達。アーチボルトも手綱を握りつつ銃を構え、その時に備える。
二十数アルレあたりまで迫ったところで、一体で突進してきた。その巨大な体躯に似合わぬ瞬発力と速度で地面が揺れる。
それに合せるかのように銃声が一発。片手撃ちとは思えぬ速度と正確さで獣を撃ちぬく。
撃ちぬいたかに見えたが、銃弾は異界の獣の表皮を貫く事はできなかった。
衝撃でよろめいたものの、速度はほぼ変わらず突進は続いている。
アーチボルトは動揺する事なく、瞬時に目標を獣そのものではなく足元にある影に狙いを変え、一発。
何も無い地面を着弾したはずの銃弾が獣の動きを止め、その場に倒れこむ。
獣達が状況を理解できず混乱している間に、馬に鞭を打ち突進してきた獣の脇をぬけ、囲いを抜けた。
アーチボルト達は馬を降り、木の柵で囲まれた小さな街を眺めた。
「ここでいいのか?」
「ああ、反乱軍とそれに賛同する者たちで作った街なんだ」
訝しげにこちらを見ていた門番に近寄るとパランタインが親しげに話しかける。
「パランタインだ。すまないが門をあけてくれ」
険しい顔をしていた門番達はすぐに目の前にいる人物が誰か理解したようで、一気に明るい顔に変化した。
「…はいっ!」
街に入るやいなや住民や兵士達がパランタインに駆け寄り口々に歓声を上げる。
「パランタイン!」「パランタインが帰ってきたぞ!」「不屈の闘士のご帰還だ」
「おかえりなさい!」「よくぞご無事で!」「パランタイン様!」
街の成り立ちもあるのか、聞き及んでいた以上の人気ぶりにアーチボルトは少々あっけに取られる。
パランタインは笑顔でそれらに応じている。病の辛さなどおくびにも出すようすがない。
自身が居なくても革命は成ると言っていたが、やはりこの男は革命に必要なのだろう。
歓声をあげる人達をよくみるとアーチボルトが見た覚えのある顔も混ざっている。
「あの野営地に居た連中は、どうやらここに避難できていたようだな」
「ああ、本当によかった」
人垣が途切れてきたところで、一人の女性が目に入る。それはアーチボルトのよく知っている人物でもあった。
「シェイラ」
「ウィル!」
名を呼び合うとシェイラがパランタインのもとへ駆け寄り、力強く抱きしめあう。
「よかった。本当によかった。貴方が王国軍に囚われたと聞いた時には……」
「泣くな、シェイラ」
「身体のほうは、どう?」
「正直、今回は疲れたよ。発作の感覚が短くなってる。長くはなさそうだ」
「大丈夫。ここですこし休みましょう。きっと良くなるわ」
抱擁のあと、見つめ合う二人には強い信頼がみてとれた。そして、シェイラはアーチボルトに振り向いて言った。
「ありがとう、アーチボルト。貴方が私の無理な願いを聞いてくれなければ……」
シェイラは手紙でパランタインの危機を知らせてきてくれた。
彼女に対面するのも久しぶりだった。
「なに、ちょうど顔を見たくなってきたところだったんだ。気にすることはないさ」
「本当にありがとう。これで家族が一緒になれた」
うつむいた彼女の腹部のかすかなふくらみにアーチボルトは気付いた。
「あたらしい家族か?」
パランタインが言う
「子供か!」
「そう。新しい命、貴方の子よ」
シェイラはパランタインに、明るい笑顔で答えた。パランタインの顔に生気がもどったようにアーチボルトは感じた。
再びパランタインはシェイラを強く抱きしめた。
「いいのか。こんな夜にシェイラのそばに居てやらなくて」
夜の古ぼけた酒場でアーチボルトはやってきたパランタインに言った。
「シェイラはもう寝たよ。あれで疲れていたんだろう」
「治療の話、もう一度考えてみろよ」
「そうだな……」
パランタインは逡巡していた。普段は決断力の塊のような男が、こんな風にあんるのはめずらしかった。
「シェイラと子供は残していけないだろ」
「ああ。そうだな。アーチ、頼んでいいか」
「もちろん。何の問題もない」
「すまんな」
「今晩は祝杯だ。お前の新しい子供のために」
アーチボルトとパランタインの二人はグラスを掲げた。
パランタインはエンジニアの所有する浮遊艇前で最後の説明を受けていた。
「以上が大雑把な説明となる。ワシらとしてもグールド病治療は研究途上、何が起こるかは分からんぞ。それでもいいんじゃな」
「かまいません、ラーム。自分にはまだみたい未来がある。これに賭けてみたい」
パランタインとラームが浮遊艇に乗り込む。パランタインの足取りはとても軽いものに見えた。
「何から何まですまない、アーチボルト。感謝してもしきれない」
「気にするな。しっかり治してこい。皆が待ってるんだ」
「―了―」
3383年 「揺籃」 

パランタインが治療に向かってから数ヶ月が経っていた。
首都レイブンズデールに迫った革命軍は王国軍の頑強な抵抗に会い、前線では数ヶ月の膠着状態が続いていた。
元々寄せ集め集団である革命軍の士気は長く続く戦闘でずいぶんと落ちており、このままでは総崩れも有り得ると噂され始めていた。
そこにもたらされたのが指導者パランタイン帰還の報せだった。
革命軍を創り上げてきた指導力に変わりはなく、程なくして革命軍の状況は士気を含めて好転の兆しを見せ始めた。
パランタイン帰還の報せを受け、久し振りに革命軍の野営地を訪れたアーチボルトは目を疑った。
病を治して帰還した筈のパランタインはやつれ果て、とても健康体には見えなかった。
「ウィル、もっと休んでおいた方がいい。他の要因で死んでしまっては元も子もない」
「治らない筈の病を治したんだ。すぐに元通りという訳にはいかんさ」
話しながら胸ポケットから錠剤を取り出し、水で流し込む。
「大事な仕上げの時だ。引き下がる訳にはいかない」
充分な休養を促したアーチボルトの言葉に耳を傾ける様子はなく、そのぎらついた瞳の見る先を覗い知ることはできなかった。
病を治して帰還してきたというパランタインの姿は明らかに異常をきたしていたが、革命軍はパランタインに頼ることを止められるほど余裕のある状態ではなかった。
特にパランタインが直接指揮をする部隊は連戦連勝の負け知らずで、寡兵で挑まざるを得なかった時でさえ、それは揺るがなかった。
革命軍や王国軍の中で一つの噂が立ち始めた。パランタインはグールド病を克服する事で勝利を引き寄せる特殊な力に目覚めたのだ、と。
そんな噂がアーチボルトの耳にも入り始めた頃、シェイラに呼び出された。
「ウィルを助けて」
傍目には万事順調に事が進んでいると思われている中、アーチボルトはシェイラにそう懇願された。
「アーチも気付いているでしょう。あの変わり様は普通じゃないわ。外見だけじゃない、上手く言えないけど内面まで変わってきてしまっている気がするの」
語っているシェイラの瞳が潤み、今にも涙が溢れ出しそうだった。
「もう以前の彼には二度と会えないんじゃないかって……」
アーチボルトは以前警告したとき、簡単に引き下がってしまった事を後悔した。
自分ができる限りウィルに付き添い、無理をしそうになったときは必ず止める、そう伝えてシェイラを戻した。
「探しものはこれか?」
懐から取り出した小瓶をパランタインに示す。小瓶の中には錠剤が詰まっていた。
「この薬、本当に治療の為に必要なのか?」
「当たり前だ。コレがなければ俺は前に進むことは出来ん」
パランタインが小瓶の薬に執着していることは分かっていた。
内容はエンジニアから渡されているとしか分からない。
「もう一度治療に専念すべきじゃないのか」
「いや、それは出来ない。シェイラと子供と離れるのはもうごめんだ」
パランタインは頭を振った。
「アーチボルト、お前には教えてやる。俺は変わった。良い方にな。家族と治療によってな」
「変わったのは分かってる。だが、シェイラはお前を心配している」
「シェイラ……彼女は最高の贈り物を俺にしてくれた。家族さ。俺はこの世界を家族のため未来のために作り変える必要がある」
そう語る表情は、以前から知っているパランタインのものとは全く違っていた。
「俺には未来が見える、そしてその未来を自由に選択できる。自由にだ」
パランタインは毟り取るように取り返した小瓶を自身の懐に入れると、よろよろと去っていった。
革命は成功した。頑迷に抵抗を続けていた一部の王侯貴族はもう居ない。
体制は変わった。パランタインは自らを護国卿と名乗り、終戦間近の活躍も相まって民衆からの支持は絶大なものになっていた。
近しい者から見たパランタインは、少しばかり様子が違った。
日に日に情緒不安定具合が増しており、特に家族に対しては異常とも言える拘りを見せていた。
我が子が入れられた揺籠に近づいた若い兵士を、激昂して撃ち殺した事さえあった。
しかし、そんなパランタインだったが政策に関する選択には誤りが無かった。
まるで結果を知っているかのように。あらかじめ必要となる各地に物資を配置し、天候を読み、王侯派のテロさえも事前に防ぎ、人心を掌握した。
アーチボルトはパランタインの居室にむかった。中が騒がしい。危険を察知したアーチボルトは扉を蹴り上げて乗り込む。
「アーチ、この子を助けて」
ひどく顔に傷をおったシェイラが子供を渡す。
「どうしたんだ、ウィルがやったのか?」
「もう彼は戻らない、だから最後に、私、この子だけでも守ろうと……」
「どこだ、薬を隠したって分かるぞ。……俺の息子だけは渡さんぞ!」
叫び声を上げながらパランタインが現れた。その目は正気を失っていた。
「アーチボルトか…お前がシェイラに何か言ったのか?」
「薬はエンジニア共から貰える。子供の世話だって誰にやらせてもいい、だが息子だけは…」
パランタインは銃を構え、撃った。
とっさにアーチボルトは抱いていた子供を庇う。
しかし予想していた衝撃は来なかった。隣でゆっくりとシェイラが倒れていく。
「シェイラ!」
「行ってアーチ、その子を守って……」
「黙れ!」
二度銃声が鳴り、シェイラに当たる。
「ウィル、貴様!」
「子供を帰せ。お前にはもう関係のないことだ。この国の未来も、息子もすべて俺のものだ」
アーチボルトが銃を抜こうとすると、銃声を聞きつけた衛兵たちが居室に殺到した。
「アーチを……その男を捕らえろ!裏切り者だ!妻を殺しただけでなく俺の息子まで奪うつもりだ!」
パランタインに命じられた革命軍の兵士達は状況を理解しきらぬままアーチボルトに斬りかかる。
振り上げられた剣に銃弾を浴びせ、追撃の意思を挫く。アーチボルトに彼らと争うつもりはない。
パランタインの絶叫にも近い怒号が響き渡るが、兵士たちがアーチボルトを追ってくる様子はなかった。
革命軍の凱歌が今だ響く首都レイブンズデールをアーチボルトは赤ん坊を隠すように抱え、駆け抜けていく。
頭の中では変わり果てた親友の絶叫が反響していた。
シェイラとした会話を思い出していた。産後間もない、パランタインも治療中だった時の事だ。
その頃はパランタインにもシェイラにも明るい前途が見えていた筈だった。
「出産おめでとう、シェイラ。ウィルの奴はまだ戻ってきてないが、その子の名前は決めたのか?」
「実は既に彼と決めてあるの。ジェッドよ。いい名前でしょう」
「―了―」
3383年 「幼子」 

レイブンデールを立って五日、アーチボルトは目的の場所に到着した。
貧民達のキャラバンに紛れて街を出、小さな街で機械馬を買い、ここまで飛ばしてきた。
ジェッドの世話は心許ないものだったが、幸い健康そうだ。
「誰かいるか」
声を掛けながら背の高い頑丈な木製の扉を叩く。夜が明けたばかりのこの時間、冷たい湿った空気が辺りを漂っている。
しばらくすると扉が開いた。
「なんですか、こんな時間に」
「アーチボルトだ。ここの出の者だ。預けたい子供がいる」
アーチボルトが叩いた扉は孤児院だった。渦の惨禍で家族を失った子供達を養う施設はたくさんあった。
この孤児院は自分が少年期を過ごした場所だった。
「お入りなさい」
老いた院長が向かえてくれた。
「コリー先生、お久しぶりです」
帽子を脱いでアーチボルトは挨拶をした。
「アーチね。本当にひさしぶり。滅多に顔などみせないのに、どうしたの?」
「このこを預かって欲しい」
抱いたジェッドを見せた。
「まあ、こんな小さな子を。あなたの子なの?」
コリーと呼ばれた院長は眼鏡をかけ直した後、ジェッドを受け取った。
「死んだ友人の子供です。詳しい事情はあとで話します。とにかく、ここに置いてやって欲しい」
「そんなに急ぐことなの?」
「直ぐに立ちたい。俺がここにいたことを誰にも知られたくないので」
「わかりました。あなたの事です、信用しましょう」
アーチボルトは孤児院を去った。自分が育った懐かしい場所だった。
内庭も、毎日通った廊下も、何も変わっていなかった。
しかしそんな感傷よりも、パランタインの手がどこに伸びているかわからない。
革命後の混乱で、大規模な捜索隊は送り込まないだろうが、それでも、自分の足取りがばれるようなことがあっては困る。
陽動や欺瞞が必要だと考えていた。
ジェッドをくるんでいた毛布を取り出し、中に適当な衣類を詰め込んで、遠目には子供を抱えている風を装った。
レジメントに戻ってから半年は、気が気でない日々を過ごしていた。
孤児院に預けたジェッドが無事かどうかを調べるわけにはいかなかった。レジメントとしての仕事もある。
自分が監視されているとは思っていないが、念には念を入れる必要があった。
院長達を信じるしかなかった。
レジメントでの活動の合間を縫って孤児院に行くことができたのは、七ヶ月後だった。
「おいジェッド、ひさしぶりだな。覚えているか」
ふらふらだが、やっと立ち上がれるようになったジェッドをアーチボルトは抱え上げた。
「覚えてるわけないか」
ジェッドは手を振ってアーチボルトを叩く。
「はは、元気な坊主だ」
「悪いわね、ずいぶんと」
孤児院を訪ねたアーチボルトは、院長室でジェッドと面会していた。
「なに。レジメントにいる限り、金の使い道はないから」
院長はアーチボルトが寄付した金貨を数え、帳簿につけている。
「他の子供達にも会っていってくれるといいのに」
「いや、子供は正直苦手でね」
一人の少女が院長室に入ってくる。
「ジェッドいる?ごはんの時間なんだけど」
「ここにいるわ、パメラ。ちょうどいい、連れていってあげて」
パメラと呼ばれた少女は十歳くらいだったが、慣れた手つきでジェッドを抱え上げた。
「ほらジェッド、ごはんだよ」
優しくジェッドに語り掛けた。
「いつもジェッドを世話してくれているパメラよ。パメラ、こちらはアーチボルトよ」
「ありがとう、パメラ。ジェッドによくしてくれてるんだね」
「うん。かわいい弟みたいなものよ。アーチボルトさんはジェッドのお父さんなの?」
「違うんだ。でも、大切な子なんだ」
「そう。私、弟ができたみたいでうれしいの」
「よかった、これからもよろしく頼むな」
「うん」
そう言って、パメラはジェッドを連れて行った。
「それで、里親の件なんだけれど」
「できれば、ジェッドはここで育ててもらいたい」
「そうはいかないわ。子供にとって一番良いのは、いつも一緒にいてくれる家族がいることよ。お金だけじゃ解決できないものよ」
「俺はここの生活は悪くないと思ってたが」
「そうだったの、気づかなかったわ。その割には、十四歳でここを飛び出していったわよね」
「若かったのさ、何もわかっちゃいない子供だった」
「じぇあ、里親の話はまた別の時にしましょう。時が来たらきちんとあなたに説明するわ」
「身勝手な話ですまない」
「いいの。あなたの事情はわかっているわ」
しばらく孤児院を眺めていた。
幼児だけを集めた部屋では、六人の子供を年長の少女達三人が面倒を見ている。ジェッドはあのパメラという少女に笑顔をみせている。
これからのことを考えると不安が無くはなかったが、とりあえずジェッドが健康でいられればいいと思った。
アーチボルトは孤児院を後にして、レジメントに戻ろうと馬に跨った。
すると、この街で見掛けない服装をした一団が城門の前に集まっている事に気が付いた。
六人程の、インペローダから放たれたパランタインの私兵だった。
つけられていたのか、どこかに間諜がいたのか。どうであれ、このままでは子供達を危険にさらすことになる。
どうしたらいいのか、アーチボルトは考えを巡らせた。
その時、ドンという音は街中に響いた。アーチボルトの後ろに煙が立ち上がっている。
「クソっ」
アーチボルトは踵を返して孤児院に戻った。城門の前にいた連中は、自分を待ち伏せしていただけだったのだ。
すでに別部隊が孤児院を襲撃していた。
「なんてことをしやがる」
パランタインの私兵どもは、孤児院の周りに火を放っていた。
捜索など面倒な事はせずに、あぶり出そうとしているのだ。
アーチボルトは首謀者らしき男を探す。指示を出している男の足元には、血溜まりと死体があった。
服装からコリー院長だとわかった。アーチボルトは激昂した。
しかし、子供達を救うことを優先しなければならない。
孤児院は古い構造で入り組んでいる。煙が回ってしまえば、小さな子供達は外に出られないまま死んでしまうだろう。
アーチボルトは馬で孤児院に飛び込むことを決めた。
しかし孤児院の塀を直接超えることはできないため、門の前にいる私兵どもと撃ち合いになった。
敵は八人程度だが、倒すだけでも時間が掛かる。その間にも火の手は強くなっていた。
リーダーらしき男をアーチボルトが仕留めて相手の手勢が半分になった頃、街の守備隊が集まってきた。
私兵達は守備隊が集まってきたことを知ると、逃げ出し始めた。
やっと突入できる道ができたが、すでに孤児院は強い炎に包まれていた。
一か八か飛び込もうとするが、消化を始めている守備隊の連中に止められた。
「無駄死にしたいのか。それより消化を手伝え」
燃え盛る孤児院の壁が熱で崩れ、黒い煙が立ち上がった。
その中から一人の少女がよろよろと出てくる。パメラだった。
アーチボルトは駆け寄って、パメラを抱きしめる。
「ごめんなさい、ジェッドを……私、途中まで彼……」
「いいんだ。よく助かった」
パメラはアーチボルトの腕の中で気を失った。
全てが終わった後、生きていたのは、ジェッドによくしてくれていたパメラだけだった。
他の子供達も院長も、その他の職員も、みな犠牲となった。
小さなジェッドは遺体すら見つからなかった。
犠牲者の追悼式の前に、アーチボルトはレジメントに戻るために街を去らなければいけなくなった。
旅立つアーチボルトにパメラが話し掛けた。
「私、ジェッドに助けられた気がするの。煙を吸って気を失った時、彼が光に包まれた大きな人になって、私のそばにいてくれたの。そして、目を覚ましたら壁がくずれて、そとに出られたの。きっとジェッドは……」
「あの子は君に感謝していると思う。やさしくしてくれたから」
「ジェッドは、とってもいい子だった……」
すすり泣くパメラを、アーチボルトは抱きしめた。
この街は、淡い郷愁の場所から苦い記憶を伴う場所となった。
自分を育ててくれた院長の顔、見送るパメラの姿、小さなジェッドの手の感触。
それらの全ては自分が背負わなければならない借りだと、アーチボルトは感じていた。
「―了―」
3395年 「対峙」 
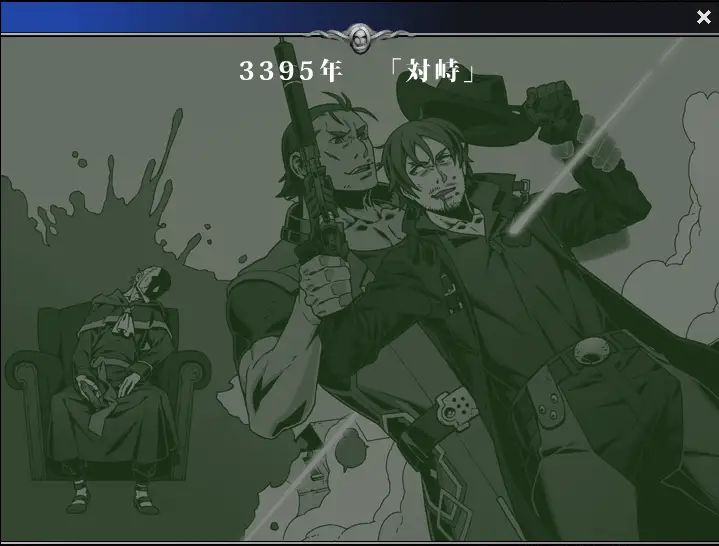
ミリアンとアーチボルトは向かい合っていた。
人気のない街角の静けさと二人の間の強張った空気が、奇妙な調和をもたらしていた。
「ロッソと女は死んだ。今ならお前の言い訳を聞いてやってもいいぜ」
アーチボルトは構えた銃を下ろさずにそう言った。
「言い訳か……そんなもので俺を許すのか?」
隻腕のミリアンが持つ巨大な戦斧も揺らいでない。
「さあな。若い奴らの命と引き替えた訳だからな。だがな、情けぐらいは掛けてやってもいいだろう」
アーチボルトは表情を隠すように帽子の鍔を下げている。
「退いてくれないか、アーチボルト。レジメントを売り渡してまでここに来たんだ。お前さえ――」
「聞きたいのはそんな泣き言じゃないぜ。お前と違って、俺には守るべき仁義がある」
アーチボルトはパランタインとの別れを思い出していた。
「貴様との取引など、どうでもいいのだ……」
アーチボルトは目の前に座ったパランタインの変わり果てた姿を見つめていた。
エンジニアから送られてきた薬をレオンを利用してまで強奪した後、パランタインに直接交渉に持ちかけた。一か八かの賭けだったが、彼は乗ってきた。パランタインは一国の元首だ。それが、脅迫者でならず者の自分と二人きり出会うという取引に応じたのは、意外であった。
二人の会談には古いホテルの一室が使われていた。
「強がりはよせ。この薬がなきゃ、お前は力を発揮できない」
インペローダの護国卿として君臨している男は、老いさらばえていた。やせ細り、髪は殆ど抜け落ち、幽鬼のような姿だった。
「そんな薬、もう必要ない……。俺はお前に会いたかったのさ」
パランタインは呟くようにそう言った。濁った眼の色と固まった表情からは、意志を読み取るのが難しかった。
「オレもケリをつけるために会いに来た」
「エンジニア共に何を言われた?復讐の為だけに来たのではあるまい?」
沈んだ表情のパランタインは低い声で言った。
「ジェッドが生きている、と。それにお前が隠している、ともな」
アーチボルトはラームから聞いたことをそのまま語った。嘘は必要ないと思ったのだ。
「俺が息子のことを喋れば、息子はエンジニア共に殺される」
抑揚のない調子で呟くように言った。
「オレがどっちを信じると思う?」
「好きにすればいい。だが、お前は真実を知りたいんだろう?」
アーチボルトは答えなかった。
「何が真実かはお前が判断すればいい。だがな、何故エンジニアが回りくどい真似をして、お前を使ってまで俺と交渉したがるのか、それをよく考えてみろ」
「話は聞いてもいい。だが、最後に決めるのはオレだ」
「この身体を見ろ。俺の力など、もう残ってはいない」
パランタインは顔を上げて、己の変わり果てた姿をアーチボルトに向けた。
「俺は無駄な時間を生きた。それが分かった。妻も息子も、俺が……」
「遅ずぎる。そんな懺悔を今さら!」
「分かっている、受け入れてくれとは言わん。だが息子は違う。その子は誰かが導かなければならない……」
「どういう意味だ?」
「アーチ、ジェッドをエンジニア共から守ってやってくれ。あの子はミリガディアのスラムにいる。頼む」
深々と頭を下げたパランタインは、顔を上げると同時に手元に隠していた銃を抜き出し、自分の口に入れて躊躇いなく引き金を引いた。脳幹を突き抜けた銃弾が背後の壁に真っ赤な血飛沫を吹き付けた。
「……これがお前の答えか」
そう呟いた。
アーチボルトは銃を下げた。
「どうしても理由を知りたい。何故お前らはジェッドを追う?エンジニア共の意図は何だ?」
ミリアンは無言だ。
「たくさんの死を見てきた。昔、何故自分が死ぬのかを知らずに死んでいった」
アーチボルトは帽子の鍔を上げ、手の先をアベルの死骸に向けて言った。
「エンジニアの連中にも派閥がある。その中でも、奴らはケイオシウムの真の力を開放しようとしている」
ミリアンも力を抜き、訥々と語った。
「真の力?」
「現実を書き換える力だ。その力があれば、人は無限の可能性の中から理想の状態を取り出すことができるようになる」
「馬鹿げた話だ」
「ああ。だが現実にケイオシウムの渦は多重世界のあり得ない可能性を結びつけ、理不尽な混乱で地上を汚染した」
ミリアンは戦斧を地面に突き立てた。
「その能力、エンジニアの連中が言う『超航海士――スーパーノート――』の力を、その子だけが獲得できた」
「都合のいい話だ。そんなものに俺達は……」
「あの子は部品として――」
「ミリアン、それ以上語る必要など無いわ」
アーチボルトは声のした方に顔を向けた。
殺気を感じ取り、飛び退く。
「情けを掛け合うなんて、みっともない男どもね」
ちかちかと明滅を繰り返しているが、女が立っている。
「人間じゃないお前には、わからん事だろうな」
「わからなくて結構」
奇妙な光を反射しながら巨大な怪物が虚空から現れ、アーチボルトに向かっていく。
距離を取るためにアーチボルトはジャンプした。
「逃がさないで、ミリアン!」
女の言葉に対するミリアンの反応は無かった。
「でかい図体をしているくせに怖気づくとはね。あとはあの鼠一匹だけなのよ」
距離を取ったアーチボルトは、目の端に倒れたジェッドが動くのを捉えた。
《ジェッド、まだ起きるな。面倒が起きる》
マルグリッドはミリアンの傍に来た。映像の一部が欠けているせいで、現実感を損なっている。
「ミリアン、ここまで来たのだから、最後まで契約を果たしなさい。あなたの望みはすぐそこよ」
「ああ、わかっている」
ミリアンは地面に突き立てていた戦斧を抜き、アーチボルトが飛び退いた方向へ身体を向けた。
「奴は俺が始末する」
アーチボルトはジェッドを視界に捉えながら、ミリアンと女との位置を計った。
ミリアンが跳躍してくる。
「くっ、早いな」
重たい一撃がアーチボルトを襲う。避ける事ができない。
「終わりにするぞ」
「望むところだ」
アーチボルトは痺れた腕を庇いながら身を翻すと、置き土産のように手榴弾を軽く投げた。雷管に細工がしてあり、通常より早く爆発する。危険だが、自分自身のスピードを信じているからこその技だった。
空中で四散する榴弾にミリアンは吹き飛ばされた。自身はミリアンの陰になるように身体を捻っていた。
「むう」
血を流しながらも、ミリアンは片膝を地面に突いただけだ。アーチボルトは銃を抜き、一気に前段を叩き込む。殆どの弾は戦斧に遮られたが、何発かがミリアンの太腿に傷を付けた。
「さすがだな、アーチボルト」
「いまさらだ」
「だが、俺も全てを擲ってここに立っているのだ。ただでは終わらんぞ」
ミリアンは隻腕を振るって戦斧をアーチボルトに投げつけた。
「そんなもの!」
アーチボルトが身を翻すと、そこにもミリアンがいた。
「陽動か!」
アーチボルトはナイフを握ってミリアンの斬ろうとする。
しかし、それは空を切った。
マルグリッドの投射映像だった。マルグリッドの能力はアベルとの戦闘で支障を来しているであろうという思い込み、油断があった。
「くっ」
崩れた体勢を立て直そうとするアーチボルトだったが、強い力で身体を捕らえられた。ミリアンが背後から組み伏せている。
「素早いお前には、こうでもしないとな」
「いいコンビネーションだったわね」
マルグリッドのドローンが目の前に現れた。
「やっと殺せる」
マルグリッドの声がそう語ると、ドローンから一条の細い光が放たれた。
その光はアーチボルトとミリアンの胸をまとめて貫いた。
「これで終わりか……ミリアン、お前、これでよかったのか」
アーチボルトはミリアンのちからが抜けていくのを感じた。アーチボルトは前に、ミリアンは後ろにバランスを崩した。
「終わりなどない……俺達は…………」
ミリアンはそう言うと、どうと後ろに倒れた。
アーチボルトは胸を押さえながら辛うじて立っていた。
「いいざまね。でも、長く生きるだけが幸せじゃないわ。そう、仲間と一緒に死ねるのも一つの幸せよ」
ドローンから投射されたマルグリッドの映像は、不敵な笑みを浮かべている。
「さて、あの子の力を……」
その時、一瞬強い光が辺りを照らした。
「これは!?」
アーチボルトは光の方向を見ようとしたが、眩しくて見ることができなかった。
薄れていく意識の中で、その強い光を瞼の裏に感じるだけだった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ