イデリハ
3379年 「能力」 
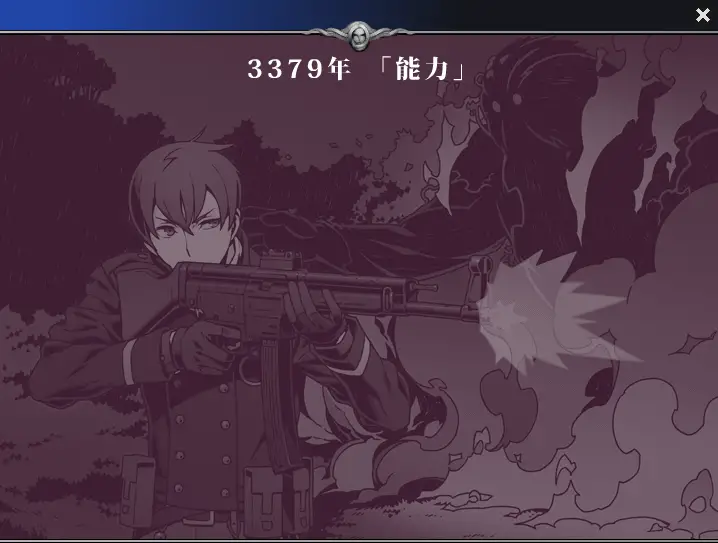
イデリハ達E4小隊は、コアを抱えて遁走する敵性生物を追い詰めていた。
「逃がすかよ!」
セリノのセプターが敵性生物に届くまさにその瞬間だった。周囲の植物が敵性生物とコアを守るように覆い被さってきた。
セプターはそのまま植物に飲み込まれ、セリノはそれに引き摺られる。
「セリノ!」
イデリハが咄嗟にセリノの制服の襟首を掴んで引っ張る。間一髪、セプターが植物に飲み込まれただけで済んだ。
「大丈夫か?」
「あ、ああ……」
暗い赤紫色をした植物は、さながら皮膚を剥かれて筋肉が露出した生物のようだ。イデリハは生理的嫌悪を覚える。
「まずい、撤退しろ!」
コアと敵性生物を取り込んだ植物は、更に周囲の岩や植物を取り込んで巨大化していく。ライフルとセプターがだけでは到底歯が立ちそうにないのは、E4小隊の誰もが感じていた。
敵性生物にコアを奪取されて森の中へ逃走された時点までは、この様なことが起こると予測できた人物は誰一人としていなかった。
「E1小隊はまだか!」
「通信、繋がりません!」
「くそっ!」
植物は意志を持つかのようにE4小隊を襲う。ある者は絡め取られて地面に叩きつけられ、またある者はそのまま植物に取り込まれた。
イデリハはセリノの援護を受けつつ、何とかセプターを振るいながら植物の猛攻を凌いでいたが、それも限界が迫っていた。
イデリハの眼前に殺意を持った植物の塊が勢いよく振り下ろされる。
その瞬間、植物が火炎によって焼き払われる光景が目に入った。
「イデリハ、セリノ、大丈夫か!?」
声と同時に、リーズがイデリハを庇うように立ち塞がる。
「E1小隊が来たぞ!」
「支援攻撃を開始する!E4小隊、下がれ!」
E1小隊長グレンの命令直下、アーセナルキャリアから放たれたミサイルが植物に着弾する。
ミサイル攻撃の効果があったのか、巨大化した植物が形を崩し始める。
「リーズ、今だ!他の者はリーズを支援しろ!」
リーズの操る炎は植物に対して最大の効果を発揮した。イデリハ達の援護もあり、リーズの炎は一瞬にして燃え広がる。
「敵性生物が見えたぞ!」
「イデリハ、撃て!」
「了解!」
敵性生物をイデリハのライフル弾が貫く。敵性生物の死と共に巨大な植物の塊も炎に包まれ、その形を完全に崩していく。
「消火剤、散布します」
程なくしてアーセナルキャリアから消火剤が散布され、灰になった植物と敵性生物の死骸が残った
リーズがケイオシウム汚染の影響によって炎を操る能力を発現してから、E中隊の渦攻略作戦の成功率は上昇の一途を辿っていた。もちろん、リーズの目覚ましい活躍に触発されたE中隊全体の士気高揚とそれによる錬度の上昇など、様々な要因を加味されてのことではあったが。
しかしそれは、レジメントのあり方にも少しずつ影響を及ぼしていた。
エンジニアはリーズのような特殊な力を発現することを他の隊員にも求めるようになり、モニタリング参加者に対して様々な検査や実験協力を要請するようになった。
「おい、ディノ。モニタリング室に来いとエンジニアからのお呼び出しだ」
「うげ。今週はもうモニタリングは無かったんじゃないのかよ……」
リーズに呼び止められたディノは、露骨にいやな顔をする。
モニタリング参加者は以前にも増して急に呼び出されるようになり、彼らは研究棟にいる時間が大幅に増えつつあった。
「二人とも大変じゃの」
「こればっかりは仕方がないさ。逆らったところで、どうなるものでもないしな」
リーズは肩を竦める。彼は炎を操る能力を手に入れて以降、特に割り切った態度でモニタリングに参加するようになっていた。
「夜間訓練までには戻れると思う。皆に伝えておいてくれ」
「じゃあまた後でなー」
「ああ、また後で……」
リーズとディノは連れ立って、研究棟へと足早に向かっていく。
一人残されたイデリハは黙々と模造セプターを振り、課された訓練をこなしていった。
そうする内に、二人一組での模擬戦の時間となった。
各所で思い思いに個人訓練していたE中隊の面々が広場の中央に集まる。
「リーズとディノはどうした?」
「モニタリングの方で何かあったらしい。詳しい話は知らない。夜間訓練までには戻ると言っていたが」
「またか。大変だな、あいつらも」
隊員達はやや心配そうに研究棟の方を眺める。
モニタリングに参加する隊員達は皆一様に、それが終わった後に酷い疲労感を訴えていた。イデリハはリーズもディノと友好的な関係がある分、モニタリングに関する愚痴めいたものを聞く機会も多い。
「モニタリングから帰ってくると、リーズもディノもげっそりしちょ……てる」
「訓練をサボれていいなとは思うけど、あのリーズがそんなに疲れて帰ってくるんじゃなあ……」
「ま、あとで労ってやろうぜ。それより早く模擬戦を始めないと」
誰かの一言を切っ掛けに、それもそうだと模擬戦が開始される。
イデリハは模造セプターを構え、ローレンスと対峙した。
模擬戦の最中、その様子を熱心に眺めている男がいた。男の傍には記録機械らしき球体が浮かんでいるのが見える。
視線を感じるのか、どうにも男の存在が気にかかったイデリハは訓練の合間に様子を見やる。
「どうした?イデリハ」
その様子に気付いたローレンスが、不審そうに手を止めた。
「あ、いや。あんな人、うちの中隊におったか?」
イデリハは小声でローレンスに言いながら、男の方を指差した。
男を目の端で捉えたローレンスは、思い当たる節がないか少し考える。
「知らん顔だな。エンジニアみたいだが、あんな奴いたか?」
「わからん」
じっと訓練を眺めている男を不審に思ったローレンスは、ちょうど訓練を見回りに来たベルキンに尋ねる。
「ベルキン中隊長、ちょっといいですか?」
「どうした?」
「あの、向こうでこっちを見ている彼は一体……」
「ん?ああ、ヒネク技官のことか。あの人は今度からE中隊付きになるエンジニアだ」
「ついこの間代わったばかりなのにですか?」
「いやいや、交代ではなく追加要因だな」
ベルキンはローレンスの物言いに、苦笑気味に答えた。
「というと?」
「モニタリングに参加している隊員以外にも優れた能力を持つ人物がいないかを調査するんだそうだ。他の中隊にも同様の調査技官が付くことになっている」
「はあ、そういうことですか。でも、いま以上に人数を持っていかれたら、作戦に支障が出ませんか?」
「その辺は上手く調整するさ。それにまだ誰がどうという話でもないしな。ほら、理解したら訓練に戻った戻った」
「あ、はい。呼び止めてすみませんでした」
「すみませんでした」
ローレンスとイデリハは、早足で施設へ向かうベルキンに一礼する。
顔を上げた二人は、ヒネクと呼ばれた技官のいた場所を見やった。彼の姿は既に無く、ヒネクと共にいた球体だけがそこにあった。
イデリハはその球体が気になって仕方がなかった。
じっと球体を見ていると、球体が回転したように見えた。レンズらしき部分がイデリハの方を向いた。
「……なんだ?」
その瞬間、球体と『目が合った』ような感覚にイデリハは襲われていた。
「―了―」
3380年 「霧」 
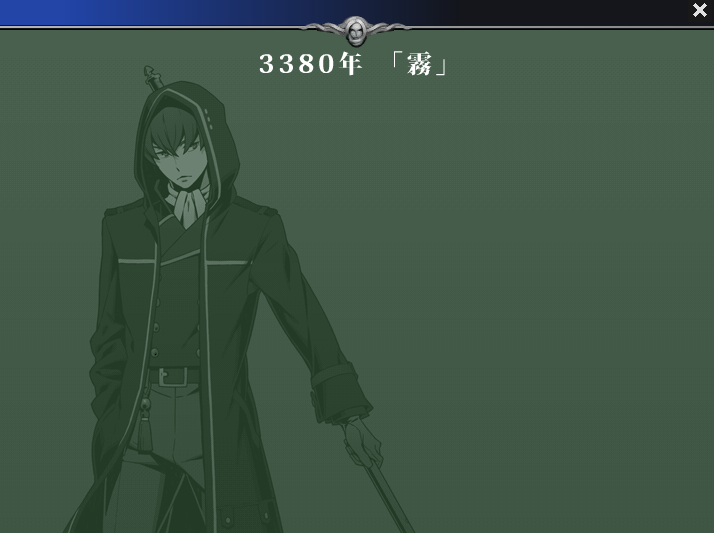
コアが存在する中心部に向かうにつれて霧が濃くなると、コア回収部隊からの報告が度々入ってくる。
イデリハの所属するE4小隊及びB2小隊は、迫り来る敵性生物からコルベットを防衛すべく奮闘していた。
中心地ほどではないにせよ、コルベット周辺も霧に覆われて視界が悪く、周囲の様子に注意を配って警戒しなければ、容易に敵性生物の攻撃を受けてしまう。
敵性生物は蟷螂のような姿をしており、加えて、全身がゲル状の粘液で覆われていた。しかもこの霧に順応しているようで、こちらの動きを正確に把握しているようであった。
回収部隊からの通信音、エンジニアや小隊長が支持を出す声。そういった様々な音が飛び交う中、イデリハはアサルトライフルで牽制射撃を行っていた。
残弾数に注意しながら、にじり寄る敵性生物をコルベットに近付けさせないよう奮闘する。アサルトライフルの貫通力が、ゲルに覆われた敵性生物の外殻を何とか貫通できたのは幸いであった。
戦闘が激しくなるにつれ、イデリハは自分が奇妙な感覚に襲われつつあるのを感じ取っていた。
周囲の霧が自分に寄り集まり、行動を阻害している。そんな感覚だった。
「なん……だ?」
しかし、激しさを増す戦闘に対応するのに精一杯で、そんな感覚を気になどしていられない。
まとわりつく霧を振り払うように、イデリハはライフルを掃射し続けた。
「おい、この馬鹿野郎!アーセナルキャリアに戻れ!」
「データを取らねばならん。そういう訳にはいかない」
背後からB2小隊のフリードリヒの怒声が聞こえる。
怒声の激しさに只事ではないと感じたイデリハは、急いで声の方へ駆け付ける。
そこでは、E中隊付きの調査技官ヒネクがアーセナルキャリアから降り、戦闘中の隊員の様子を録画していた。
「あいつ……!」
イデリハはヒネクの姿を見て、呆れと怒りが入り混じった声を絞り出した。
ヒネクは職務に忠実過ぎるところがあり、『調査、観察』と言い張って、戦闘中だろうが訓練中だろうがお構いなしに、危険なところへ飛び込んでくる。
イデリハを含めたE中隊の面々から見れば、はっきり言って邪魔で面倒な存在以外の何物でもなかった。
幾度かベルキンに申し立てをしたこともあったが、管轄が違うとの理由で、ヒネクの行動が咎められることはなかった。
「何をしちょる、ここは戦場じゃ!アーセナルキャリアに戻らんか!」
国の言葉が出ることも構わず、イデリハはヒネクを叱責する。
危険意識の足りないエンジニアをお守りすることほど面倒なことは無い。放っておいて勝手に死なれたとしても、それは戦闘中の事故という処理がされるだけで、自分が咎めを受けることはない。
だが、何もせずに見殺しにするというのも気分が悪い。
「誰に向かって命令している。私は調査技官だ。お前達のデータを取るのが私の仕事だ」
ヒネクはイデリハの叱責を意に介すことなく、高圧的に言い放った。
放っておいてくれと言わんばかりの物言いだったが、エンジニアの護衛も任務の内だ。はいそうですかともいかない。
「そんなに死にてえのか?ここは戦場だ!いいから戻るんだ!」
フリードリヒがヒネクの腕を掴み、アーセナルキャリアへと引っ張っていく。
「離せ!」
「ええ加減にせんか!おんしの面倒を見切れるほど、オイ達も暇じゃなか!!」
宙に浮いていた記録用のドローンを鷲掴んでアーセナルキャリアに放り込む。
「何をする!」
ドローンを追ったヒネクがアーセナルキャリアに上半身を突っ込んだところを、イデリハは臀部を押して内部に無理矢理押し込んだ。
何とか厄介者の処理を終えてフリードリヒの方へ視線を移すと、背後から今まさにフリードリヒを襲おうとする敵性生物が目に入った。
フリードリヒと敵性生物の距離は1アルレもない。霧で視界が悪かったのと、ヒネクとの揉め事に気を取られて敵性生物が近づく音に気付けなかったのだ。
「フリードリヒ、後ろだ!」
イデリハの叫び声にフリードリヒは背後を振り返る。だがもう遅い。敵性生物の鎌のような腕が振り下ろされた。
「え……?」
「危なか!」
仲間を守ろうというイデリハの意志であろうか。
イデリハは、一度リーズに聞いた『力を使うときはどうするのか』という話をそのままなぞるように、意識を霧に集中させた。すると、自身に集まる霧がフリードリヒに寄り集まり、水流となって彼の体を包み込んだ。
そしてその水流は、今にもフリードリヒの脳天を叩き潰さんと振り下ろされた敵性生物の腕を弾き返したのだ。
敵性生物はフリードリヒに向かって振り下ろした勢いを跳ね返され、大きく仰け反った。
「あ、助かっ……」
死を覚悟したフリードリヒが、自身が未だ生きていることに呆けたように呟いた。
「呆けるな!斬れ!」
攻撃が弾かれたことに戸惑う敵性生物を追撃すべく、イデリハはフリードリヒに鋭く指示を投げかけた。
「……!お、応っ!」
フリードリヒの二つの剣戟が敵性生物に迫る。
攻守反転。敵性生物は攻撃を受け止めようと構えた腕ごと、フリードリヒの繰り出す刃によって為す術もなく斬り刻まれた。
どうにか敵性生物の襲撃からコルベットを守りきり、コア回収に向かっていたリーズ達も帰還した。
死傷者を含めた隊員達を乗せ、コルベットは連隊施設へと戻る。
そのコルベットの中でイデリハはフリードリヒを救った『聖騎士の力』について、ぼんやりと考えていた。
自分には取り立てて何か得手がある訳でもない。リーズやディノとは違って自分は平凡な人間だ。そんな自分がこんな力を持っていいのだろうか。
あまり明るくはない思考がイデリハを支配した。
霧が支配する《渦》の攻略が完了してから三日後の朝、イデリハはエンジニアの研究棟を訪れていた。
戦闘中に『聖騎士の力』を発現したことで、検査が行われるということであった。
体のあちこちに電極が貼り付けられ、検疫施設でも見たことがないような大掛かりな装置で徹底的に調べられる。
検査が二時間、三時間と続くにつれ、早く自分達の生活棟に戻りたいと思い始めた。
「あの……、まだ掛かりそう、ですか?」
指示は全てモニターに表示される文字で行われているため、イデリハの声だけが室内に響く。
エンジニア自体が元々抑制的で感情に乏しいとはいえ、この検査室にいるエンジニアはひたすら無言でイデリハの検査を行っている。
その様はまるで、大小に関わらずイデリハには一切の知識を与えない、といった感じであった。
リーズやディノは今まで何度もこんな検査とも実験とも付かないようなことをされていたのか、そう思うと酷い寒気に襲われた。
こんな恐ろしいことが繰り返されるような『聖騎士の力』なんて、どうして得てしまったのか。
イデリハを陰鬱な気分が襲った。
ようやっと研究棟を出た頃には、すでに夕食の時間となっていた。
検査の合間に食べた固形の栄養剤では食事を採った気に到底なれず、何はともあれ食事にありつくために食堂へ向かった。
「イデリハ!」
食堂に向かう通路を歩いていると、横の通路から走ってくるフリードリヒに呼び止められた。
「どうした?」
「前回の作戦、助けてくれてありがとな」
フリードリヒはそれを言うためだけに、走ってイデリハの所でやって来たようだ。
「……なんだ、そんなことか。オイ……俺もあんなに上手くいくとは思わなかったよ」
結果的には上手くいったが、『聖騎士の力』が発動したのは偶発的な出来事だ。次に似たような状況、事態に陥った際に、再び上手くいくとは限らない。
「俺はアンタに命を救われたんだぜ。そんなこと、とか言わないでくれよ」
自分の力によって助かった者がいる。それは事実なのだ。それは否定していいものではないのだ。
「……そう、だな。すまん」
「よし、じゃあ今日のメシは俺の奢りだ!ちょっとした礼だから、遠慮なんて野暮なことはするなよ?」
満面の笑みを浮かべるフリードリヒにつられてイデリハも笑う。
「いい……のか?俺、結構食うぞ」
「まーかせとけって!」
帰還するコルベットの機中から今までずっと、面倒な力を得てしまったと思っていた。
だが、死と隣り合わせの連隊で、共に戦う仲間を守ることができた。それは誇っていいことだろう。
『聖騎士の力』を確実に扱えるようになれば、こうやって仲間を守りながら戦うこともできる。
ふと、イデリハの脳裏にそんな考えが過った。
「―了―」
3387年 「視線」 
| 画像なし |
薄暗い地下通路を、男は息を潜めて注意深く進んでいた。
男は、他者が持たざる力を持っていた。
だがその力は、連隊と呼ばれる閉鎖空間ではごくありふれたものだった。
だから、男は力を持っている者が存在しない外の世界を求めた。
男は力を使って鬱屈を晴らすかのように、外の世界で暴虐を尽くした。
しかし、それも長くは続かない。
その力は、人に向けて振るうにはあまりにも強大で異端だった。
男の行為は瞬く間に露見し、懲罰を受けた。
男は大人しくなったふりをした。
権力に従順になり、内省したふりを見せて、更なる懲罰から逃れた。
そうすれば、再び外の世界へ出られる機会も巡ってくるだろう。
外での行いは、男にとって麻薬のようなものだった。
簡単に手に入る欲望に取り憑かれた男は、外の世界へ出る機会を窺うだけの存在となった。
死地へと赴く度に、男は外への渇望を強くしていくばかりであった。
異界へ向かい、帰還するだけの実力がありながら、男は弱者へと力を振るう快楽に溺れていた。
男は知っていた。通常の出入り口の他に、物資の搬入に利用されている地下通路があることを。
この狭い世界。いつ死ぬかもわからない日常。それらにうんざりしていた男は、連隊からの逃亡を決意した。
真夜中の静かな地下通路を男は慎重に進む。油断はしていない。いざとなれば力を使えばいい。そうすれば逃げ果たせるだろう。
そう考えながら、周囲を注意深く窺って進み続ける。
もうすぐ、もうすぐ出口だ。
男の手が出口へ繋がる扉に掛かる。
その瞬間だった。
ひやりとした金属の感触が男のうなじに当たる。
少しの間を置いて、男の全身から脂汗が吹き出て来た。
「そこまでじゃ」
聞こえてきたのは、独特な訛りが混じった男の声。
あぁ、捕まってしまった。
そんな思考が頭をよぎるのを感じながら、男は意識を落とした。
違反者の捕縛任務に関する責任者がミルグラムからミリアンに代替わりして数年。
連隊は更なる人員の増強を行い、隊員数は年々増えていった。『聖騎士の力』の解析も進み、能力を扱うことが出来る者も、以前とは比べ物にならないほど増えた。
と同時に、力を悪用する者も増える一方であった。
違反者が増えるに従い、任務に就いているイデリハら元E中隊の面々だけでは対処が厳しくなっていく。
そこでラームからの提案により、何らかの理由によって《渦》攻略作戦へ参加できなくなった隊員を捕縛任務の人員として宛がうことになった。
今では元からいたイデリハ達四名の他、十数人が捕縛任務に就いている。
人員の増加によって任務の内容にも変化があった。
その一つが、違反者が脱出に使う可能性の高い通路の哨戒任務だ。
特に注意を要するのは、下水道と物資搬入用の地下通路。
この二つは強化された警備用ドローンが常に見回り、それ以外にも一定時間毎に捕縛任務に就いている人員が哨戒を行っている。
イデリハは、その要注意通路の哨戒中に、脱走しようとする男と遭遇したのだった。
「懲罰房から出たばっかりだってのに、よくやるな……」
イデリハとバシリオは深く溜息を吐いた。
違反者を拘留施設に収監した後にデータを確認すると、この男はつい数日前に懲罰房から出たばかりである内容が記載されていた。
『聖騎士の力』を《渦》の内部以外で振るって懲罰房へ入れられた者は、要注意人物として捕縛部隊にデータが回される。
今回は懲罰房から出されてすぐの行動だったため、イデリハが見つけなければそのまま逃亡していた可能性もあった。
「十五期の中でもエース級じゃったというに、勿体なか」
違反者は二年ほど前に入隊した若い隊員で、南東の地域からやって来ていた。
正規のオペレーターになって程なく『聖騎士の力』を得たらしい。同期の中ではそこそこに突出した才能をもっていたようだ。
だがそれが災いしたのか、次第に力に驕るようになり、周囲への態度が高圧的になっていったらしい。
懲罰房へ入れられたのも、外出の際に出くわした揉め事で『聖騎士の力』を一般人に振るった結果だとか。
連隊が把握しているのは懲罰房行きになった一件だけだが、聴取を行ったところ、過激な行動を自慢げに話していたのを、何人かの同期が聞いたことがあるらしい。
「しかし、増えたのう」
イデリハは再び溜息を吐いた。ここ数ヵ月で捕縛した違反者は三名。数年前は半年に一人ほどのペースであったことを考えると、その増加傾向は顕著である。
「聖騎士の力を呼び起こす訓練法が確立してから、余計にな」
「いいことなのか悪いことなのか、わからんなぁ……」
「まったくだ」
この数年で『聖騎士』となった者は、二期や三期と呼ばれる時期の隊員と比べると遥かに多い。
力を持たない者を数えた方が早いくらいであった。
違反者を捕縛し続けて数年が経ったが、力に溺れる者は増えるばかり。
しかし、力を得てみるまでは、そのような事態に陥るかどうかは誰にもわからない。
「ま、仕方がない。そういう奴ってのは往々にして出るもんだ。誰かが止めてやらないと」
「そう、じゃな……」
始めは嫌々とやっていたこの任務だが、元E中隊の面々は時間の経過と共に、妙な使命感を覚えているのだった。
翌日の昼頃、ラームが捕縛隊の待機部屋に姿を見せた。通常であればミリアンと共にやって来る筈だが、ミリアンの姿は見えず、代わりに見知らぬ女性エンジニアを連れて来ていた。
「ミリアン中隊長はどうしたんですか?」
「ああ、彼なら作戦会議が長引いているようでね」
「それと、その女性は?」
「彼女は聖騎士の力を研究しているエンジニアだよ。違反者に装着する抑制シールの開発者でもある」
「シールの使用状況が知りたくて、ラームに無理を言ったのよ。お邪魔するわね」
そう言って女性エンジニアは微笑んだ。
ラームと同様にこの女性エンジニアも表情を表に出すタイプのように見えた。
類は友を呼ぶという言葉があるが、ラームの周囲には抑制的ではないエンジニアが集まりやすい傾向があるのかもしれない。
イデリハはそんな風に考えたが、決して口には出さなかった。
捕縛されていた違反者は、ラームの連れてきた男達に連れられて出てきた。
「勿体ないわね。でも、いい研究ができそう」
女性エンジニアは小さく呟いた。
このエンジニアは抑制シールの使用状況を見に来ただけではなかったのか。
「マルグリット」
ラームが女性エンジニアの名前を呼ぶ。その口調は窘めるようなものだった。
「ああ、ごめんなさい。こうやって直接見るのは初めてだから、つい、ね」
「さ、用事は終わった。行こうか、マルグリット」
ラームは少し慌てているようだった。マルグリットの言葉を極力聞かせたくないようにも見えた。
追い立てられるように部屋を出て行こうとするマルグリットだったが、ふとイデリハに視線を向けて微笑んだ。
「貴方、ここに飽きたらラームの所へいらっしゃらない?悪いようにはしないわ」
「マルグリット、やめるんだ。すまないな、イデリハ君」
「あ、い、いえ……」
マルグリットの表情は笑っているが、その視線は鋭い。だが、彼女の目の奥には光が宿っていないように見えた。
イデリハは、以前ドローンが自分を見ていた時の気分を思い出す。
その不気味さを拭いきれぬうちに、ラームとマルグリットと呼ばれたエンジニアは去っていった。
「ミリアン中隊長。ラームというエンジニアは一体何者なんですか?」
ラームと女性エンジニアの動向に不審なものを感じていたイデリハは、その日の夕方に捕縛隊の待機部屋を訪れたミリアンに尋ねた。
しかし、ミリアンはイデリハの質問には答えず、首を横に振った。
「彼らには深入りしないほうがいい」
「ミリアン中隊長、ですが……」
「これ以上食い下がるようなら、お前も違反者となるぞ」
ミリアンは鋭い視線をイデリハに向けた。
「な!?」
「できれば俺もそんなことはしたくない。前任のミルグラム副長からも、お前達が理不尽な目に合わないようにして欲しいと頼まれている。ここはわかってくれ」
「わ、かり、ました……」
ミリアンの言う通り、これ以上深入りすると何が起きるのかわからないのだろう。
それに、スターリングを追って連隊を辞したミルグラム副長が最後まで自分達を気に掛けていたと言われると、副長の意志を無碍にすることもできなかった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ