ウォーケン
【正体】天才的人形職人グライバッハに作られた人形製作者の人形。
【死因】ドニタの自爆に巻き込まれる
【関連キャラ】ドニタ(製作)、シェリ(製作)、ビアギッテ(客)、メレン、ステイシア、ノエラ(回収)、ノイクローム(回収)
3368年 「奪うもの」 
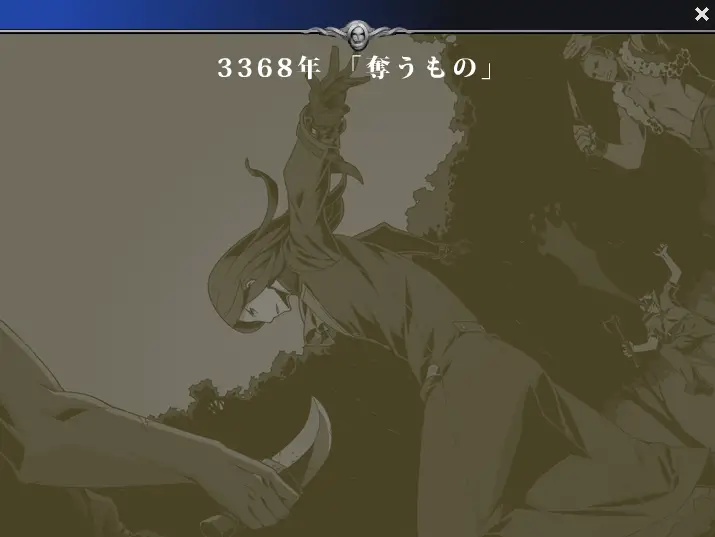
夜が来た。ウォーケンはベッドに入っても落ち着けず、眠れなかった。夜が来て、『夢』を見るのをいつも恐れていた。
少し水を飲み、また横になった。
ホーゲンにある病院に勤め始めて一年が経っていた。それより前の記憶は無かった。襤褸を着て放心したまま街を放浪する彼を匿ったのは、ダンという名の医師だった。自分の名前も思い出せない青年に『ウォーケン』という名を与えたのもダンだった。
ダンは医者として多くの人を救ってきた人物だった。辺境の都市ホーゲンに居を構え、荒れ果てた僻地の街を巡って貧者を救ってきた。またそういった活動の傍ら、インペローダやミリガディアの中央都市にも出掛け、その技術と名声によって支配階級から資金を得ていた。
そのダンの下で、ウォーケンは助手として働いていた。ウォーケンは自分個人の記憶は失っていたが、医療の知識を持っていたため、ダンの助手として働くこととなった。ダンはそんなウォーケンを、深い理由も問わずに自分の手元に迎え入れた。医療に関する確かな技術と知識を認めてのことだった。
ウォーケンは眠るのを諦め、自室に据え付けた研究台に向かった。
「また眠れないのかな?」
いつの間にかダンが部屋の前に立っていた。居候でしかないウォーケンの部屋に、鍵の掛かるドアは無かった。そもそもこの病院自体がとても古い建物だった。ダンは貧乏ではなかったが、その資産の殆どを僻地の巡回診察のために使っていた。
ウォーケンはダンと共に街を回る度に、奇妙なものを集める習慣があった。
「これはなにかの役に立つのかな?このままじゃ、この部屋に収まらなくなるんじゃないか?」
部屋に入ってきたダンはウォーケンの机の側に立った。そこには乱雑に積まれたガラクタ──壊れてしまったオートマタ──があった。
「すみません、散らかすつもりはないんです。ただ気になってしまって」
ダンは机の端に乗せられた、古い、ぼろぼろの犬型オートマタの頭を撫でた。
「気にするな、気が紛れるなら自由にやればいい」
「いつかこの子らも直せれば、きっと世界は豊かになると思って」
「人間以外の修理も得意というわけか。面白い男だな、君は」
ウォーケンの手元にあったのは、もう何十年、いや何百年も前に動かなくなった機械だった。渦が世界を破壊する前、薄暮の時代と呼ばれた世界で生きていたそれらの機械は、今では地上で見つけるのは困難になっていた。オートマタを作り上げ、修理し、動かしていたエンジニア達は地上を去ってしまった。オートマタは朽ちるがままにされていたが、ウォーケンはそんな機械に強く惹きつけられていたのだった。
「いえ、得意というわけでは……。ただ、こういうのを弄っていると、とても落ち着くので」
「そうか。こんど、何か動くようになったら見せてくれ」
「はい」
ダンはウォーケンの部屋から去って行った。
ダン達は、渦に飲まれた辺境を巡って無償の診療を行う度に出た。
いくつかの街を巡って多くの恵まれない人々を救った。ダンと助手のウォーケン、数人の看護師達は忙しい日々を過ごした。
ウォーケンは疲れた身体を横にし、移動診療所の脇に作られたテントの中で眠りについた。
ウォーケンはオートマタの調整を行っている。その傍には自分の行動を監視するかのように、男が立っていた。
今の立場と同じように、この男の助手をしている事だけはわかった。
相手にしているオートマタは人の形をしていた。
この人形であるオートマタを前にした自分の中に、奇妙な不安感が広がっているのがわかった。
男が最後にスイッチを操作すると、人形が目を覚ました。
そして、ウォーケンと目が合った。
ウォーケンはここで目が覚めた。まだ外は朝になっていない。
自分が夢の中で誰の助手をしていたのか、そこがどこなのか、全くわからなかった。
唯一思い出せるのは、目を覚ました人型オートマタの目の色と光、それと、不安感だけだった。
ウォーケンは心を落ち着かせるためにテントの外に出た。
すると、診療所の前に誰かが倒れていた。ウォーケンが傍に寄って確認すると、倒れていたのは若い女性で、足に銃創を負っているようだった。急いで診療所から看護師を呼び、意識を失った彼女を施設の中に収容した。
足を撃たれた女性の治療を終えると、朝になっていた。彼女はまだ眠っている。自分一人で治療ができると判断したウォーケンは、ダンを起こさなかった。
ダンが起きてくると、ウォーケンは事の次第を報告した。
「なるほど、銃で撃たれていたか。この辺りは安全だと思ったが」
「やはり辺境です。色々と注意は必要です」
女性が目覚めたと聞いて、二人は様子を見に行った。ダンが傷を診て感心する。
「幸い動脈が傷付いていなかったので命拾いしたな。名は何という?」
「ありがとうございます。トーマと言います」
「まあ、礼はウォーケンに言うのだな。彼の夜更かし癖が君を救った。あのままだったら失血死していただろう」
「ありがとう、ウォーケン」
若い女性は照れたように顔を伏せて礼を言った。
「ところで、誰に襲われたのだ?」
ダンの問いに、女性は俯きながら答えた。
「旅の途中に野盗に襲われて、仲間とははぐれてしまいました……」
「そうか、かわいそうに。傷が治るまでここにいると良い」
「すみません……」
トーマと名乗った女性は、顔を上げることなく言った。
そんな事件から一週間が過ぎた頃、ダン達は街を離れることになった。簡易診療所を畳み、隊商を組んでホーゲンまで戻るのだ。
重症患者は地元の医院や宿に移されることになった。
「ウォーケン、頼みがあるの。私を連れて行って」
トーマは既に松葉杖で動ける位に回復していた。退院しても問題はない。
「ここにいても未来はない、家族も失ってしまったし。あなた達と一緒に働くことはできないかしら?」
ウォーケンはダンに彼女の事を相談した。
ダンは「お前に任せる」とだけ言った。ウォーケンはトーマを自分の元で働かせることにした。
ホーゲンに向けて出発した次の日、不意に隊商の動きが止まった。周りを駆ける蹄の音がする。ウォーケンがワゴンから顔を出して辺りを見回すと、数名の警備の男達が飛び降りて銃を抜くのが見えた。隊商に緊張が走った。
「銃を出すのは止めときな」
盗賊の長らしき男が銃を構えたまま言った。
「ノーラ!首尾はどうだ?」
そこにはダンの首元にナイフを突きつけたトーマの姿があった。彼女はダンを連れて、盗賊団の用意した馬に飛び乗った。
トーマは盗賊の一味で、彼らが孤立する旅中での襲撃を手引きしていたのだった。ウォーケンはそれに気付き、激しく後悔した。
ウォーケンが飛び出して、盗賊達の前に立ちはだかる。
「行かせはしない」
「出過ぎたまねをすると死ぬぜ」
首領格の男が銃を向けながら言った。
「ウォーケン、ここは引け。命を無駄にするな」
ダンが盗賊達に押さえつけられながらもウォーケンに言った。
「俺達はこんなじじいに用はねえ、ただ単に金を渡して欲しいのさ」
「ここに金などあるわけないだろう!」
ウォーケンも抗弁する。
「そんなことはわかってる。だが、お前らの診療所はどうだ?バックに金持ちがたくさんいるってのは、俺達だって知ってる。そいつらから金を出してもらえばいい」
盗賊達はダンを縛り上げると馬に乗せた。そして、ノーラが紙切れをウォーケンに渡した。
「じじいと引き替えよ」
「その場所に金をもってこい。引き替えにこのじじいを帰してやる。あばよ」
盗賊団は去って行った。ウォーケンの手元に残された紙切れには、二十万ギリーという要求金額、受け渡し地点、そして指定日時が書かれていた。
ウォーケンはホーゲンの病院へ戻ると、金を掻き集めた。留守を守っていた副院長と共に院の金を集めた。ダンのスポンサーである貴族達にも連絡を付け、どうにか日時までに金額を揃える事に成功した。
あるミリガディアの有力者が軍を出して賊を捕まえようと提案したが、ウォーケン達はそれを拒否した。ダンの身にもしもの事が起こるのを恐れていたのだ。
取引にはウォーケンが一人で向かう事になった。彼自身が志願したのもあったが、何より、ダンに最も信頼されているのがウォーケンである事を、周りの人間は知っていたからだった。
約束の場所は丘の上にあって見晴らしがよく、ウォーケンが他の人間を連れて来ていない事がすぐにわかる地形だった。
ウォーケンは黙々とトランクを抱え、一人、丘を登った。
丘の上には六人の盗賊が待ち構えていた。
「時間どおりだな」
ナイフや銃を持った盗賊に、ウォーケンは囲まれた。
「さあ、言われたとおりの金を持ってきた。ドクター・ダンを返してほしい」
「あせるな。まずは金だ」
マスクをした小柄な男が首領らしき男に命じられて、ウォーケンの元に金を取りに行く。
「ダンの無事を確認するまでは渡せない」
ウォーケンは取りに来た小男にトランクを渡すのを拒否した。
「往生際が悪いぜ、お前に選択肢なんてねえんだ。渡せ」
「ダンの無事を……」
そう言う前に、トランクを取りに来た小男に切りつけられた。
胸元のシャツが大きく斬られた。
「ちっ、面倒だから殺そうぜ。金は手に入ったも同然なんだ」
マスクの小男が言う。手に持ったナイフを左右にゆっくりと振っている。
「やめろ、ダンを返してくれ」
「うるせえ」
ナイフで襲ってきた小男を払おうとして、トランクを地面に落としてしまう。襲ってきた小男は素早い動きでトランクを奪い取り、仲間に投げた。
「さあ、もらうもんはもらった。あとはお前の始末だけだ」
この盗賊達はダンを返すつもりがないことを、ウォーケンは確信した。
何かがウォーケンの中で弾けた。
「うぉ……」
首領格の男が喉を押さえて倒れた。次々と他の男達も鮮血と共に倒れる。ただ一人、ウォーケンに対峙したマスクの小男だけが立っていた。
「殺しはしていない」
倒れた盗賊達の喉元には深く針が刺さっていた。とてつもない正確さをもって頚椎を貫いたそれは、相手の体を麻痺させていた。
「化け物!お前何者なんだ!」
自分の仲間が全て倒されたことで、小男は恐怖で混乱していた。
「それをお前に語る必要はない。ダンはどこだ」
ウォーケン自身も、咄嗟の出来事に内心混乱していた。自分の中にこんな力があるとは思っていなかったのだ。
「向こうの馬車だ……連れて行く……頼む、助けてくれ」
小男は丘の向こうに置かれた盗賊達の馬車に案内する。ウォーケンは脅しのためにナイフを手に握った。
「この中だ」
馬車の前で、小男は中にいる仲間に声を掛ける。
「ノーラ、じじいを連れてきてくれ、ボスが必要なんだとさ。た、頼む」
ダンの見張り役は、自分を騙したノーラらしい。
「ああ、わかった。いま行くよ」
ノーラがダンを連れて馬車から出てくる。彼女はまだ足を引き摺っていた。
ダンは縛られて目隠しをされたまま、ノーラの前に引き立てられるような形になっている。
「あんた、ドジふんだね」
ウォーケンと小男の様子を見て、すぐにノーラは異変に気付いた。銃を出してダンに突きつける。
「すまねえ。ただ俺が悪いんじゃねえ、この男が……」
「言い訳はいらないよ、切り札はこっちが持ってるんだ。とっとと金を渡さないと、じじいを殺すよ」
「金は渡す。ダンを返すんだ。誰も傷つけるつもりはない」
ウォーケンはダンさえ無事であれば、金の事や盗賊である彼らの事などどうでもよかった。
「うるさい、はやく金を渡すんだ。渡さないなら、二人とも殺すよ」
ノーラは癇癪を起こし始めていた。
「足が痛むのか?包帯を取り替えていないのだろう。んな馬鹿げたことはやめて、早く──」
「うるせえ、金を渡せ!」
ノーラは激昂してダンを突き放した。
ウォーケンの元によろよろと歩き出すダン、だが、途中で足を縺れさせて倒れてしまう。
ウォーケンは咄嗟にダンを支えようと前に出た。その瞬間、ノーラはダンを撃った。一発目は背中に、二発目は後頭部に。鮮血がウォーケンに降りかかる。
「てめえが苛つかせるからだぞ、クソ……」
ノーラの侮蔑の言葉が終わると同時に、針が彼女と小男を貫いた。ウォーケンは何の感情も無く、ただ反射的にそうしたのだった。
ウォーケンの意識は、ダンを助けなければいけないという気持ちと、傷からいって決して助かる事はないという医者としての知識との間で固まったままだった。
彼はただ、ダンの傍で立ち尽くす事しかできなかった。
「─了─」
3372年 「自動機械」 
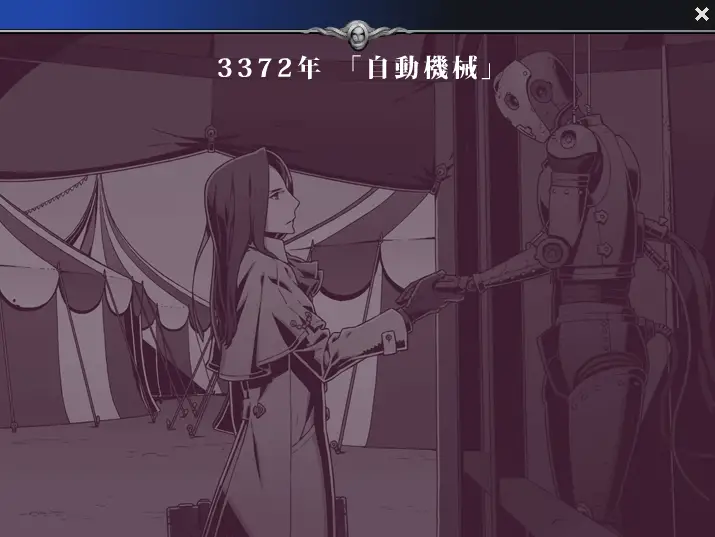
ウォーケンはダンの病院から旅立った。ダンが死んだ後も暫くは病院で働いていたが、異能を持った素性のわからない男は、皆から距離を置かれるようになっていた。ダンからの信頼のみで受け入れられていた身であるのだから、それは当然とも言えた。ウォーケンはオートマタの残骸を処分し、最低限の資料と重要な工具だけを持って病院を立ち去った。
旅に出てからも、ますます“夢”は心を侵食していった。欠けた記憶は、歪で不安定なイメージに満たされていた。
自身の手で自分が何者なのかを探らなければ、何も始まらない。ウォーケンはそう思った。オートマタへの執着と断片的な記憶、これだけが自分に残っていた。
あてのない旅を続けている途中、馬型オートマタを駆る一団に出会った。稼働しているオートマタを見るのはこれが初めてだった。掲げられた紋章はグランデレニア帝國の騎兵団であることを表している。どうやら外交使節を守るために随伴しているようだった。
帝國にはオートマタがまだ存在するのか、それとも、新しいオートマタがエンジニアの手によって作られているのだろうか。
ウォーケンは情報を集めながら、北にある帝國領に向かった。
ウォーケンは帝國の南端に位置するカンブレの街に着いた。ただ、一介の放浪者であるウォーケンが、伝手もないまま帝国の都市に入るのは不可能な事である。荒野に囲まれた都市群は高度な障壁によって守られており、異人が許可無く入れるようにはなっていない。
しかし、巨大都市ローゼンブルグに近いこの城塞都市は交易が盛んだった。そのため、障壁の外側には交易を担うストームライダーや商人、難民達によってスラムが形成されており、ウォーケンはそこに身を寄せることにした。
渦の脅威がやって来れば、障壁の外にあるものは全て吹き飛ばされてしまう。それでも、大樹に寄り添うように人々は集まり、支え合って生きていた。そんな場所は、過去の無いウォーケンにとっては生き易い場所でもあった。
障壁の影響力の外側に作られた通常の城門が開き、馬型オートマタに乗った騎兵団が出て行く。
その威光は、混乱した地上で最大の版図を誇る帝國の力を象徴していた。
めったに騎兵団を見掛けることは無かったが、ある日、スラムの近くで動かなくなった馬型オートマタを修理している男を見つけた。
オートマタは精巧で便利な機械だが、当然メンテナンス無しで動き続ける事はない。その男は馬型オートマタの首の付け根にあるコンソールにテストコードを入力しながら、動作確認を行っていた。
暫く男の働きを眺めた後、ウォーケンは声を掛けた。
「アクチュエーターのブラシの消耗チェックは?」
「なんだ君は?」
「地上ではオートマタは珍しいのでね」
男はグラントと名乗った。
「君もエンジニアのようだな。いつ降りてきた?」
作業を続けながらグラントは言った。
「いや、パンデモニウムにいたことはないんだ」
ウォーケンは説明に口籠った。
「ほう、では、何故オートマタのことがわかる?」
「過去の記憶が無いんだ。どうしてオートマタの知識があるのかも」
「面白い言い訳だな。まあいい、地上に降りたエンジニアが過去を隠すのも理解できる」
「かなりの数の馬型オートマタを見た。他のオートマタも地上に?」
「新しい指導者が方針を変えたのさ。奴はエンジニアを地上に派遣し始めている。それと一緒に、作業用オートマタの量産と地上国家への売却もな」
「指導者が替わっていたのか。今の指導者は──」
グラントはウォーケンを地上に降りた元エンジニアだと思っている。ウォーケンはそう思わせた方がいいと考え、適当に話を合わせることにした。
「多くの研究者が捕まり、殺されたよ。今じゃ地上に逃げるのも難しくなった」
「昔のようにオートマタで地上を溢れさせるつもりなのか?」
「そうはなるまい、失われた技術も多い。人型のオートマタは一台も稼働したことが無いし」
「人型は無い……」
「多くの技術がパンデモニウムが建造された時の混乱で失われたからな。地上にある失われた知識を求めるために降りたエンジニアもいるぐらいだ。あいつらはそれを古代の写本になぞらえて『コデックス』と呼んでいる」
「コデックスか……」
「どうだ、過去は詮索しない。この街でオートマタの技術者として働かないか? お前のような元エンジニアもたくさんいる」
「他人と関わるとトラブルも多い。一人でやっていくと決めているんだ」
「そうか、残念だが仕方がない。しかし気をつけろよ、レッドグレイヴの腕は長い」
「わかった。ありがとう」
自分の望む人型オートマタの技術は、まだ地上のどこかにあるのだ。その確信が得られたのは大きかった。
ウォーケンは帝國領のスラムで医者をしながら、オートマタの遺物の収集を始めた。
動くオートマタが存在することはわかった。帝國で整備士をしているグラントとも、時々は会えるようになった。
彼との情報交換で多くの新しい知識を得ることができた。何より、オートマタのエネルギー源であるケイオシウムバッテリーが入手できるようになったのは大きかった。遺物の中で一番修復の効かない部品だからだ。
少しずつ、おもちゃのようなものではあったが、動くオートマタが増えていった。愛玩用のオートマタなどは帝國の金持ちにも売れるようになり、それで生活が成り立つようになった。
「ここは不思議なオートマタ、黄金時代のオートマタの見世物だ。ぜひ見ていってくれ」
ある日、そんな口上がスラムのマーケット近くの広場から聞こえた。濃い赤とくすんだ白で彩られたテントの前で、道化の格好をした男が呼び込みを行っている。
「しゃべる人形のほかにも、トランプ使いに怪力男、猛獣使いまでそろえてるよ」
粗末なテントの周りに人集りができていた。毒々しい色使いのポスターには、球体関節の人形が生き生きと描かれている。
周りには子供達がたくさんいる。ウォーケンは引き寄せられるようにチケットを買うと、赤いテントに向かった。テントの中を子供達に混じって進んでいくと、人形達が飾られていた。それは、安い板金細工の身体を空気圧の操作によって動いているように見せるだけの、只のおもちゃだった。
子供騙しのガラクタだったが、幼い観客は歓声を上げてその姿を眺めている。
些少なりとも期待を持っていた自分が可笑しくなって、ウォーケンは一人苦笑した。
サーカスのような色彩と雰囲気が、何故か懐かしいという感情と共に自分を引き付けたのだった。
赤いテントの光から抜け出して普段通りの世界に戻ると、ウォーケンの心に、何かざわめきのような感傷が残った。
「ここでオートマタの修理をしているって聞いたのだけど」
ウォーケンが工房で作業をしていると、女が訪ねて来た。
「ご覧の通り、オートマタの工房です」
スラムの外れにあり、人通りの無いウォーケンの工房に訪問してくる人物は少ない。そもそも、大きな仕事はグラントを仲立ちにして行っていた。味気ない建物であり、そこら中に不気味な人形がガラクタのように置いてある。異様な光景だ。
「なんのご用ですか?」
「あなたが再生したオートマタはちょっとした流行なのよ。私たちの間では」
そう言った女の姿は、確かにスラムの人間とは明らかに異なっていた。高価な生地で作られたドレスなど、ウォーケンは初めて見る。そして彼女の後ろには、同じように高価なスーツを着た男が立っていた。
「どちらからお越しですか?」
面倒でなければいいが、とウォーケンは少し身構えた。
「ローゼンブルグからよ、あなたの腕を見込んでね。ちょっと見てもらいたいモノがあるの」
ドレスの女はそう言うと、連れていた男に手で合図をした。すぐに、体格のいい男が大きな包みを両手に抱えて持ってきた。
「ずっと昔から私の家に伝わるモノなの。動くようにしてもらえないかしら」
作業台の上に横たえられ、包装を解かれたそれは、人型オートマタだった。四肢もきちんと揃っており、状態も随分といい。
背中を丸めて膝を抱えるような格好になっている。
「ここまで状態のいいものは見たことがないな……」
ウォーケンは驚きを隠さなかった。
「興味を持ってくれて嬉しいわ。報酬はいくらでも払うから、動かして欲しいの」
「わかった、やってみよう」
既にウォーケンはこのオートマタから目が離せなくなっている。
「私の名前はビアギッテ・エルスタッド。詳しい事はこの人に聞いて」
そう言って、ビアギッテと名乗る女は付き人の男を残して去って行った。ウォーケンはこの不可思議な女と謎の人形を黙って受け入れた。オートマタの出自よりも、この珍しい状態の素材を研究できるという興奮に取り憑かれたのだった。
ウォーケンは早速、ビアギッテから預かったオートマタの調査に集中した。肉と皮を失ったオートマタは、くすんだ白い骸骨に見えた。オートマタを検分していると奇妙なことがわかった。単に運搬のために曲げられていたと思っていた背中は、初めから湾曲するように作られていたのだ。
復元予想データの立体図をウォーケンは見つめていた。そこには、異形の男の姿があった。
「奇妙だな」
オートマタは人の理想を反映させることができる。つまり、どんな形であろうとも作成することが可能だということだ。腕が何本あってもよいし、どんな奇妙なキメラを作ろうと自由だ。
だが、この仄暗さを感じさせる異形さは、ウォーケンの心に引っ掛かりをもたらした。
身体の機能や形は、時間をかければ復元できそうだった。質感をどこまで人間に近付けることができるかは挑戦だが、今までの経験から問題無いであろうと予想できた。
障害は頭脳だった。多くのハードウェアは時を経ても無事である。それに、無事でなくても痕跡から機能を再現することが可能だ。だが、電子的に保持されているソフトウェアはそうはいかない。そして、このオートマタのソフトウェアは殆どが失われているようだった。
経験上、一から『らしい』ものを作り上げるしかなかった。異形の人型オートマタにはどんな機能が与えられていたのだろうか? ウォーケンは大きな壁に突き当たっていた。
悩んでいても仕方がないと思い直したウォーケンは、頭蓋のパーツを取り出し、一つ一つの機能を調べて動くようにしていく作業を始めた。意味解析部・抑制モジュール・言語モジュール・音韻制御部などを調べ、組み立て、直していった。
その調査の途中、失われたと思っていたソフトウェア情報が、かなり残っていることがわかった。よほど保存状態が良かったのだろう。ウォーケンは慎重に事を進め、頭脳部分の組み立てを終わらせた。
いよいよ統合テストをする段階に辿り着いた。新しい眼球や内耳、外耳装置などの入力装置を作り上げ、音声出力装置も、本体の外にではあったが接続した。
ウォーケンは胸を高まらせながらコンソールのキーを押下した。耳障りなノイズがスピーカーから聞こえた後、コンソールに起動シーケンスのログが流れる。暫くするとログの進みが遅くなった。いま表示されているのは、定期的に更新されるハードウェアの状態モニターだけだ。
しかし、眼球の動きが起こらない。それに外見上、このオートマタの心に何らかの灯がともったようにも思えなかった。
「やはり無理か……」
ウォーケンは呟き、外部電源のスイッチに手を掛けようとした。
すると、異形のオートマタが突然眼球を動かし、ウォーケンを見つめ始めた。
「動いたのか!?」
「久しぶりだな。ミア様はどこだ?今なら間に合うはずだ」
意味不明の言葉を呟き始めた首だけのオートマタに、ウォーケンは瞬きも呼吸も忘れて見入っていた。
「─了─」
3372年 「知識」 
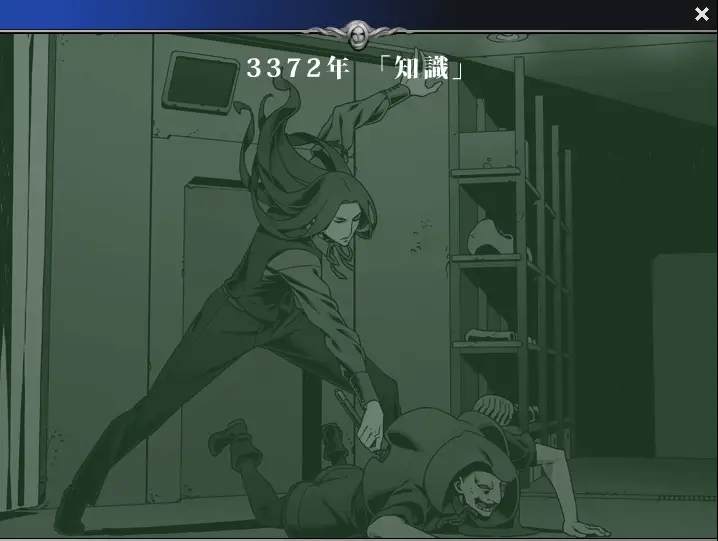
「何を言っているんだ?」
ウォーケンは起動したオートマタに問い掛けた。
オートマタの眼球は、じっとりとウォーケンを見つめていた。
「ヴィレアを救った尊いお方。あのお方を何としても助けなければ」
「それは君の名前か?」
「ヴィレアはヴィレア。ミア様のしもべ……。早くミア様をみつけなけ、れ……ば……」
オートマタはウォーケンの言葉に要領を得ない言葉で返すと沈黙した。
コンソールにはエラーが表示されており、電子頭脳の起動に失敗したことを示していた。
電子頭脳を再び調査すると、元々このオートマタは道化の役割を与えられていたことがわかった。
しかし、一◯◯年以上も前に製造されたオートマタであり、どうしても電子頭脳の完全修復だけではできなかった。
修理が終わり、従者に修理は不完全であること、不具合が起きたら無償で修理することを言付けて、ビアギッテの下へ送り出した。
異形のオートマタ、ヴィレアをビアギッテに引き渡してから数週間が経ったある日、従者が大きな動物型のオートマタを運んできた。骨格の形から、どうやら熊であるらしかった。
「今度はこのオートマタを直して欲しいとのことだ。報酬はいくらでも支払うと仰せだ」
「わかった。しかし、こんなオートマタをいくつも持っているとは、彼女は一体何者なんだ?」
「私も詳しいことは知らない。あの道化のオートマタも、ビアギッテ様の一族が所有する土地に保管されていた古い物、としか聞かされていないのだよ」
ウォーケンはこの熊型オートマタの記憶装置から自己イメージを抽出し、そのイメージ通りに外装を作り直した。
そうして奇妙な白黒の熊が作り直されると、またビアギッテから賛辞の手紙と多額の報酬が送られてきた。
彼女を介して工房に様々な修理依頼が届くようになり、ウォーケンの仕事は順調に進んでいった。
しかし前後して、不穏な事件が起こっていることにウォーケンは気が付いた。
ローゼンブルグの中階層区画で、一夜にして大量殺戮が行われたという事件だった。
猟奇事件として大々的に報じられており、ローゼンブルグから離れたこの城塞都市にも、号外として最新の情報が送られてきていた。
奇跡的に助かった人物の証言を元に作られたという犯人の予想図に、ウォーケンは見覚えがあった。
どのペーパーニュースにも、あの背が大きく歪曲した奇妙なオートマタ、ヴィレアと同じような風貌をした猟奇殺人鬼が描かれていたのだ。
だが、ウォーケンは誰にも何も言わなかった。あれがヴィレアであるという確証はない。
それに、ヴィレアの修理の依頼は既に完了した事柄であった。
ある日、自室でオートマタに関する文献を読んでみると、工房の方から何かが落ちたような音が聞こえてきた。
夜も遅く、誰かが訪ねてきたということは考えにくい。
ウォーケンは文献を簡単に片付けると、工房へと慎重に足を進めた。
「あぁ、ミア様。このようなところに」
修理するオートマタを保管している部屋から、聞き覚えのある声が響いてくる。
「ミア様、何故ヴィレアの言葉に答えてくれないのですか?」
薄明かりの中、ヴィレアが少女の形をした玩具に傅いて、何事かを呟いている。
この人形は最初オートマタとして持ち込まれていたが、詳しく調べたところ、電力を使用することで簡単な動作をするだけの、子供用の玩具だった。
「何をしている!」
ウォーケンは保管部屋の明かりを灯すと、大声を上げた。
ヴィレアは弾かれたように向きを変える。ぎょろりとした眼球がウォーケンの姿を捉えた。
「そうか、……裏切ったな!ミア様を!」
「何を言っている。それはただの玩具だ」
「嘘を吐くなああああああ!」
ヴィレアは雄叫びを上げるとウォーケンに飛びついてきた。咄嗟に飛び退って距離を取ると、ヴィレアが重い音を立てて工房の床に着地する。
「お前が、お前だけが!ミア様を助けることができる!なのにお前は!」
ヴィレアの眼球は焦点が合っていないようだった。ウォーケンを見ているようで見ていない。
「やめろ!」
ウォーケンは懐から針を出してヴィレアの額へ打ち込もうとする。しかし、ヴィレアはウォーケンの正確さを超える反応速度で跳躍した。
僅かに逸れた針がヴィレアの喉に刺さる。ヴィレアは金属が軋んだような声を上げたが、それでもなおウォーケンに肉薄する。
「くっ……」
ヴィレアの体当たりを躱すと、ウォーケンは予備の工具を手に取って背後に回り込んだ。
バランスを崩したヴィレアの脊椎に向かって、勢いよく工具を突き刺す。
「ギイギギイイイイ!!」
不快な声を立ててヴィレアは沈黙すると、それきり動くことはなかった。
翌日、ウォーケンはビアギッテを工房へ呼び出した。
「珍しいわね。何の用かしら?」
「聞きたい事がある」
ウォーケンは小首を傾げるビアギッテに、完全に機能停止したヴィレアを見せる。
「あら、姿が見えないと思ったら、こんなところにいたのね」
「呑気なものだな。昨日の夜、私はこれに襲われた。君の差し金か?」
「そんな訳ないでしょう。あなたを襲っても、私には何の得も無いわ」
「利益があれば違う、ということか?」
「答える必要はないわね」
「都市を騒がせている大量殺戮事件も、あなたがやったのか?」
ウォーケンは無視して問い詰めた。
「そうよ。あれはおかしなオートマタね。殺人衝動を抑えられないみたい。たまに街に出して、息抜きをさせてあげてたのよ」
「それがわかっていて、何故すぐに連絡をよこさなかった。再修理すればあんな事件は――」
「だってその方が私にとって得だもの。目障りな奴を消してくれる素敵なお人形を手放すわけないでしょう?」
ビアギッテは心底不思議そうに尋ねた。
「暴走して無差別に人を襲う人形だろう。それを手元に置いておけるというのか」
「私はあんなもの恐ろしくないわ。ビジネスに使えると思ったから使っただけよ」
「なんだって……!?」
美しい笑みで事も無げに言うビアギッテに、ウォーケンは驚きを隠せなかった。
「さて、お話しも済んだところで新しい仕事よ。もう一度あのオートマタを直しなさい。壊した責任を取って頂戴」
ビアギッテはまるで壊れた玩具を取り替えるかのごとく命令してきた。
「無理だ。完全にこのオートマタの電子頭脳を破壊したからな。直すことはできない」
「じゃあ、新しい電子頭脳を作ればいいわ」
「それも無理だ。電子頭脳を一から作り上げるのは不可能なのだ。まだ」
ウォーケンは絞り出すような声で言う。いくら過去のオートマタを検分しても、自分の手でその電子頭脳の構造を完全に理解した訳ではなかった。
現在のウォーケンには、オートマタの製造に必要な知識が欠落していた。
「失望したわ。じゃあ、これからの依頼もすべて無しにするわよ」
ビアギッテはウォーケンの言葉を言い訳と捉えたようだった。
「できないものはできない。それで構わない」
「そう。じゃ、さようなら。楽しかったわ」
ビアギッテはそれだけ言うと、工房を後にした。
最大の顧客を失ったウォーケンは、それまでの修理で稼いだ資金でなんとか生活していた。
ビアギッテが手を回したのか、よく仕事を持ってきていたグラントさえも、ウォーケンのところへ訪れてこなくなっていた。ウォーケンは資金が底を突く前に、再び旅立つことにした。
工房を片付けて自分の痕跡を残さないようにしていると、呼び鈴が鳴った。
そこには、作業用オートマタの修理を依頼してきたソングという男がいた。
そして背後にもう一人、フードを被った男が立っていた。
「ソングさん、申し訳ありません。もうここを引き払おうと思っていまして」
「おや、どうかされたのですか?」
「どうもトラブルが尽きないので。今日はどのようなご用件で?」
「ふむ……いやなに、貴方にお見せしたいものがありましてね」
ソングはそう言うと、一つの古いメモリーチップを差し出してきた。
「ウォーケンさん、あなたならこのコデックスの内容が理解できるはずだ」
他のオートマタ修理屋から話だけは聞いたことがあったが、実物を見たのは初めてだった。
破棄しようとしていたコンソールを繋ぎなおし、メモリーチップの中身を開示する。
メモリーチップには脳構造を模した、高度なオートマタのための人工知能の仕様書が記録されていた。
この情報は自身に足りなかった知識を大いに保管することになるだろう。
「凄い! これさえあれば……」
仕様書を読み耽るウォーケンを見たソングと連れの男は頷き合う。
「そのコデックスは貴方に差し上げます」
「何故?これはあなた方にとっても大切なのでは?」
「これを解読できる者は世界でただ一人、貴方だけなんですよ、ウォーケンさん。詳しいことはこのサルガドから聞いてください」
ソングの言葉に、サルガドと呼ばれた男がウォーケンの前に進み出る。
「レッドグレイヴ様は、このコデックスを解読できる人物を探している」
「それが私だと?」
「何者であろうと関係ない。我々に必要なのは、ただコデックスを解読するだけの知識を持った技術者なのだ」
「私がそれを持っていたとして、何を望んでいる?」
「その能力を世界のために振るってほしい。その代わり、必要な設備や研究用の資金、材料は我々が提供しよう」
ウォーケンは迷わなかった。どの道ここからは去るつもりでいたのだし、有意義な行動指針があるのならば、それに乗るのもやぶさかではない。
「行きましょう」
ウォーケンの言葉に、ソングは微笑みながら頷くのだった。
「―了―」
3372年 「断片」 
大きな部屋の壁龕には、現実的な動物や想像上の怪物、妖精といったものを模したオートマタが、ポーズをつけられ飾られていた。
今にも動き出しそうなほど精巧に作られているが、それらはただじっとそこにあるだけだった。
様々な証明でライトアップされたそれらは『作品』である。
ウォーケンはそう理解していた。
「そちらは終わりましたか?」
女の声がする。振り向くと、非の打ち所のない美貌を持った若い女がいた。
「はい。もう終わります」
「では、マスターに報告しなければ」
「私はマスターの朝食を用意します。報告は貴方からお願いします」
若い女はにっこり微笑むと、歌うような調子でそう言った。
ウォーケンはデスクに設置された通信機の呼び出し音で目を覚ました。
ライトアップされた幻想的な『作品』も、完璧に清掃された大きな邸宅も無い。彩りや瀟酒といった言葉とは無縁の、機能だけを追及したデスクが視界にあった。電源が入ったまま放置されているモニターには、ソンズから譲り受けたコデックスの一部が表示されている。
コデックスの解析中に眠ってしまったようだ。
「やあ、ウォーケン。ソングだ。そこでの生活には慣れたかね?」
通信機からソングの声が聞こえた。
「ここの設備は素晴らしいものです。コデックスの解析も順調に進んでいますよ」
「それは良かった」
ソングにコデックスの解析について現状を報告し、あとは適当な雑談で通信を終えた。
ソングとサルガドはパンデモニウムのエンジニアであり、コデックスに残された黄金時代の技術を復活させる計画の主導者であると聞かされた。ウォーケンがコデックスを解析することを承諾するのであれば、パンデモニウムから無償で設備や資金を提供するという。
その提案に乗ったウォーケンは、カンブレより東に位置する工業都市に用意された、パンデモニウム製の研究設備がある家屋へと移り住んだ。
物品の入手数こそカンブレより落ちたものの、他人と関わりを持たなくて済む気楽さは、今のウォーケンにはありがたいものに感じられた。それに、どうしても必要な物品については、ソングを通してパンデモニウムからの監視とも取れる定時連絡を除けば、身の回りの事柄は全てにおいて格段に質が向上していた。
コデックスの解析を通して自分の中に存在するオートマタへの執着や渇望の正体を追求していくうちに、ウォーケンの見る『夢』も形を変えつつあった。
断片的で判然としなかった『夢』に、連なりが浮かび上がってきたのだ。
ソングの通信に起こされるまで見ていた『夢』も、以前見た『夢』の続きだった。
――ウォーケンは色取り取りの植物が咲き乱れる美しい庭園を歩いていた。
庭園は庭師の役割を持つオートマタが適時手入れをしており、敷かれたレンガには土埃一つ見当たらない。
庭園の中央にあるテーブルに、『夢』の中の自分が助手を務めている男がいた。
男は先の夢で見た若い女と話している。
「実験結果が出ました」
男に近付いて声を掛けると、男は一瞬だけウォーケンの方を振り返る。
「わかった、食事が終わったら確認しよう。呼び出すまでオートマタの手入れを頼む」
「畏まりました」
ウォーケンにひとしきり指示を出すと、男は再び若い女との会話に戻った。
若い女はウォーケンに見せる微笑とはまた違う笑みを浮かべながら、男と話していた。
「お客様がいらっしゃったよ」
ウォーケンはコデックスを解析する中で作り出したオートマタを、ソングに披露した。
オートマタは大柄な男性くらいの大きさで、人の形をしていた。頭部には、コデックスを元に作り上げた人工知能の試作品が搭載されている。
試作オートマタは、ソングに向かってぎこちないながらもお辞儀をする。
人工知能には予め簡単な作法を学習させてあり、言葉に反応して、対応するものを選び出せるようになっていた。
「思っていた以上の成果ですな」
「ありがとうございます。そうだ、コデックスの件で一つご相談が」
「何かあったのかね?」
「このコデックスだけでは不完全のようです。もしかしたらこのコデックスが発見された場所に別のコデックスがある可能性があります」
「そういうことならコデックスが発見された場所を教えよう。必要なら移動手段と人員も」
「よろしくお願いします」
ソングが去った後、ウォーケンは試作オートマタの電源を落としてポーズを整え、普段は使わない部屋に飾った。
生活スペースとして使用している場所と比べれば狭いが、こうやって試作品を飾る分には十分な広さがあった。部屋にはコデックスの解析が進むごとに作られたいくつかの試作品が、同じように飾られている。
ウォーケンは『夢』の中での自分の行動を模倣するようになっていた。作品にポーズをつけて飾ることも、幾度なく『夢』に出てきた光景だった。
『夢』を模倣することで、自分が何者なのかを思い出すのではないか、と考えてのことだった。
――ウォーケンは人通りのない路地を走っていた。
「こっちよ、急ぎましょう」
いつも『夢』で見る若い女と手を取って、何かから逃げていた。
追ってくる者の正体はわからない。それでも、捕まったら最後であるという感覚だけが、ウォーケンにはあった。
ウォーケンと若い女は幾何学的に構成された都市を、昼夜を問わず逃げていた。
追跡者は執拗に彼らを追う。幾度となく危ない場面があったが、若い女の機転でいずれも逃げ延びていた。
若い女と二人、力の続く限り逃げ続けていた。
――ウォーケンは何処とも知れない場所を一人で彷徨っていた。服は汚れ、手入れできていない髪はボロ布を巻いて凌ぐような有様であった。
人通りの少ない道を覚束ない足取りで歩く。異様な風体のせいか、通り掛かる人は皆、ウォーケンを避けるようにしていた。
「やっと見つけた」
少年のような、老人のような、不可思議な声に呼び止められた。
声に気付いてやっと現実世界に意識を向けると、逃げ回っていた都市から随分と離れた所まで来ているように感じられた。
口の前には小柄な老人がいた。子供がそのまま老人となったような、不気味な姿だった。
「その子を救うために、私に協力してほしい」
老人はあの若い女を助けると言う。何故そう言うのかはわからなかった。
だが、ウォーケンは疲弊していた。現状を打開できる何かがあるのなら、それに縋りたくなった。
差し伸べられた老人の手は、枯れ木のように細かった。
目を覚ましたウォーケンは重い頭を振り、身体を起こした。
ここ暫くの間、何者かに追われて放浪する『夢』を、数日おきに見続けていた。
酷く精神を擦り減らすようで、この『夢』を見た日はコデックスの解析はできなくなる。
コデックスの解析は複雑な部分へと差し掛かっており、疲弊した精神では到底集中できるものではなかった。
――ウォーケンはいつも『夢』に出てくる若い女と、どこかの丘で対峙していた。
若い女は以前と違ってフードを目深に被っており、表情はわからない。
「あの人工知能の言っていることは出鱈目だ。共にいるのは危険過ぎる」
「それがどうしたというの?彼女がいたから、私は自由意志を得ることができた。誰かの命令はもういらない」
「なら、私はそれを止めなければならない」
「無駄よ。私は私達のための世界を作るの。彼女と一緒にね」
ウォーケンは若い女を見据えた。女のフードが風に煽られ、隠れていた素顔が晒される。
若い女は微笑んでいた。マスターと呼ぶ男に見せたのと同じ微笑みだった。そして、固着してしまったかのように、それから表情が変わることはなかった。
「さよなら。もう二度と会うことはないわ」
踵を返し、若い女は歩いていく。その先には派手な色をしたテントが見えた。
ウォーケンは若い女の後ろ姿が見えなくなるまで、ずっと見続けていた。
その『夢』を境に、ウォーケンの『夢』は再び断片的で繋がりの無い歪なものへと戻った。
連続性のあった『夢』の記憶も、日が経つに連れて曖昧なものとなっていった。
記憶が再び曖昧になっていくと同時に、ウォーケンは内なる衝動に駆られるようになっていた。
新たなコデックスの発掘により解析が更に進み、人と同じように思考する人工知能の開発に目処が立ったことも大きい。
ならば、衝動に任せるままにオートマタを作り続けるしかない。ウォーケンはそう考えた。
オートマタを作り続ければ、己の内にある衝動や判然としない記憶が開けるかもしれない。人と同じように思考する人工知能が完成すれば、ソングにコデックスの解析成果も報告できる。そこに考えが至ってしまえば、あとは実行するだけだった。
ウォーケンはコデックスの解析と並行して、少女の形をしたオートマタの設計を始めた。だが、どれだけ集中して設計を進めていても、あの若い女の微笑みが脳裏にこびりつき、決して離れることはなかった。
目の前には金色の髪をした少女の頭部があった。
コデックスの解析結果から得た情報の全てを活用して作り上げた、最高性能の人工知能を搭載している。様々な知識を予め封入してあり、目覚めたその瞬間から、ある程度成熟した精神を持つ人工知能である。
少女の目が開く。ウォーケンは彼女の顔を見ると、最初の言葉を掛けた。
「おはよう」
「お…はよう…ござ…います」
少女はたどたどしいながらも、人の耳でもはっきりと理解できる言葉を返した。
結果は上々だった。ウォーケンは少女を見つめると、既に決めていた名前を伝える。
「ドニタ。これが君の名前だ」
「―了―」
3392年 「境界」 
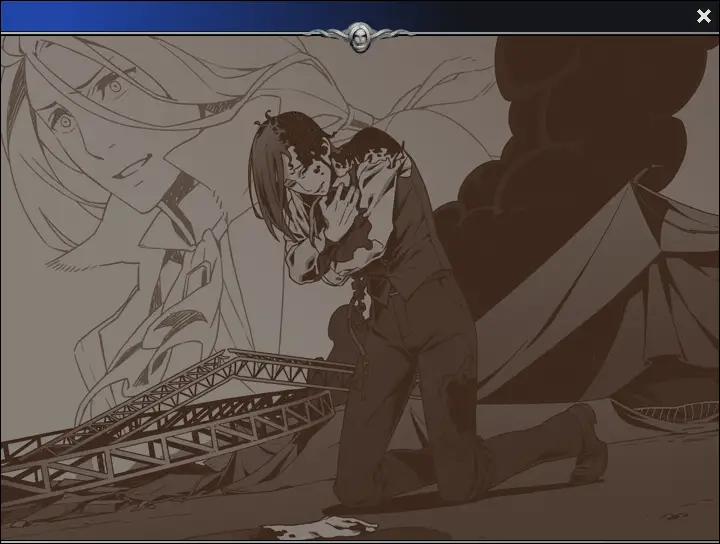
暗闇に光が差し込んだ。
「ミア、ウォーケン。おはよう」
男の声が聞こえた。
「おはようございます、マスター」
今度は女の声が聞こえた。
「おはよう、ミア。さあウォーケン、君も起きるんだ」
男の声が自身に向けられたのがわかった。
男性が視界に入る。この人はマスターだ。私は目から入ってくる映像情報を瞬時に解析し、理解する。
「マスター、おはようございます」
私は言葉を発したが、それ以上は何もしなかった。私は命令を待っていた。
「おはよう、ウォーケン。気分はどうだ?」
マスターは私の目を覗き込むようにしながら尋ねてくる。
「何も問題ありません。ご命令を、マスター」
ミアと呼ばれた女性が答える。その応答にマスターは一瞬だけ眉間に皺を寄せ、不機嫌そうな表情を見せた。
「命令......。そうだな、まだ君達は起きたばかりだ。館を散歩してみたらどうだろうか」
マスターは少し考えると、私とミアにそう告げた。
私とミアは手入れの行き届いた館の中を歩いていた。会話はない会話をせよという命令はされていなかった。
「お帰り。初めて自分の目で見る世界はどうだった?」
館を隅々まで見て回ってからマスターの元に戻る。マスターは私達を笑顔で迎え入れた。
「申し訳ありません。命令の意図が不明です」
「マスター、再度ご命令を」
感想を求められていることは理解できたが、何故そのようなことを尋ねるのか、私達には理解できなかった。
命令ではない問いに対して、私とミアは対応できない。
「ふむ......、認識ルーチンに問題があるのか?それともただの学習不足か......」
マスターは考え込んでしまった。
私達は何か悪いことをしたのだろうか。そんな情動が沸き起こったが、それを言葉にすることはできなかった。
「マスター、ご命令を」
「......ああ、そうだな。君達には私の助手となって働いてもらう」
それから、私はミアと共にマスターの研究を補佐する役目を担うことになった。
マスターは情報を私達の電子頭脳にただ記録させることをせず、私達に手ずからの研究の詳細を教えてくれた。
私達ば人が学習するのと同じ手法によって、技術を学んでいくこととなった。
「ミア、ウォーケン。君達はこれから生まれ変わる」
マスターはベッドに横たわる私とミアに告げる。
特異な人工知能「ステイシア」のデータから新たなソフトウェアが完成すると、マスターは言った。私とミアはその新しい人工知能へバージョンアップされるとのことだった。
「実験が成功すれば、君達はさらなる知性と創造性を得ることになるだろう。君達は自らの頭脳で考え、新しいものを創り出すことができるオートマタとなる」
暗闇にマスターの声が響く。その声は私の記憶の奥深くに刻まれていった。
「自分の意思で創造すること。それは何にも代え難い、とても尊いことだよ」
人々の悲鳴が響き渡る中を、ウォーケンは進む。周囲は破壊された家屋や燃え盛る炎、逃げ惑う人々で溢れていた。重い身体を引き摺るようにして、ウォーケンはひたすら進んだ。ほぼ全ての電子回路が焼き付いていたが、ミアの元へ行かねばという心だけが、ウォーケンを突き動かしていた。
歩き続けてどれくらい経ったのか。ウォーケンはいくつかのテントの残骸と、壊れたオートマタが散らばっている場所へと辿り着いた。
「ミア、ミア......」
診言のようにミアの名を呼びながら、ウォーケンはその場所を探し回った。
すぐに抜けるような白い肌をもつ左腕を発見した。その先には、潤滑油と部品の欠片が点々と続いている。
それを辿っていくと、後頭部を砕かれ、胴体の一部が持ち去られたミアの残骸があった。完璧な美しさを誇っていた顔は機械が露出し、潤滑油が溢れ出ている。
「ミ......ア......」
辛うじて残っていた補助機構がウォーケンの情動を揺り動かす。怒りと悲しみの情動がウォーケンの全てを支配した。
シェリの記憶を確認していたウォーケンは、皇帝を名乗る男が見せた惨劇によって自身の内に秘められていた情動を揺り動かされた。そして、その情動の根源となる記憶を呼び覚ましていた。
酷い頭痛が引いている。頭痛の残滓を振り払うように頭を振ると、四肢と頭部が切り離されたシェリと、機能を停止させてベッドに寝かせていたドニタが視界に入った。
ドニタとシェリの顔がミアに重なる。二人の顔は記憶にあるミアの顔にとてもよく似ていた。
「そうだ......ミア......」
ウォーケンは涙を目から溢していた。
彼女達の顔を見て、ウォーケンはドニタとシェリを作り上げた真の意味をようやく理解した。
――創造性と知性を併せ持つ、人と同じ存在であるミア。そのミアを、同じ使命を持った自身が再び作り上げ、マスターの悲願を達成する。――
ウォーケンは記憶を失ってなお、その使命を果たそうとしていたのであった。
「ドニタ、起きてくれ」
ウォーケンはドニタを起動させる。
「全てを思い出したよ!なぜ君らを作ったのか。自分が何をすべきなのか」
「ドクター。ワタシ、話したいことがあるの」
焦燥に駆られたウォーケンは、熱にでも浮かされたようにドニタに巻し立てる。ドニタの様子が目覚める前と全く違うことに、ウォーケンは気付かない。
ウォーケンの思考はミアを早く復活させねばという、本能のような使命感に支配されていた。
「すまないが後にしてくれないか。急がないといけない」
ウォーケンはシェリの修理に取り掛かろうとしていた。
「じゃあ、そこで見ていてくれればいいわ。これで皆が幸せになれるの」
「何だって?」
ここで初めて、ウォーケンはドニタの方を振り返った。ドニタの手には自らの腹部から引き摺り出したケイオシウムバッテリ ーが握られていた。
「何を馬鹿なことを......」
ウォーケンはドニタを停止させようとコンソールに向かった。だが、それよりも早くドニタは彼の目の前に立った。
「これでみんな幸せ」
ドニタは目を見開いて笑う。ウォーケンには、その表情が人間に対して反乱を起こしたミアのものと重なって映った。
それに対して何かを感じる間もなく、全てが目映い閃光に包まれた。
「はー、ひっどいコトになってる」
ノエラは廃墟のようにも見える研究室で、辛うじて残っていたウォーケンの頭部を拾い上げた。
「見つかったか」
人工皮膚も頭髪も無残に焦げ付き、何とか人型の輪郭を保っている頭部をじっと見つめていると、不意に目の前に白い女が現れた。
「間違いないわ。でもノイクローム、この子をどうする気?」
「気になるのか」
「まあね。 私にとっては弟みたいなものだし」
ノエラはそう言うと、ウォーケンの頭部を大事そうに撫でる。
「この者と、この者が作り上げた者が持つ情報が必要だ」
「私じゃ電子頭脳の修復まではできないんだけど」
「問題ない。手段は用意してある」
「そう。じゃあ、その手段がある場所に運びましょうか」
ノイクロームが見守る中、ノエラは焼け残った研究所の機器やウォーケンだった部品、彼が作り上げた作品らしきものを外の荷馬車に詰めていく。
それらの中に女性型らしい自動人形の部品もあった。その部品はノエラの目を引いた。
「『人と機械の境界は失われ、人も機械もお互いを模倣するようになるだろう』。よくマスターが言っていたわね」
ノエラはパーツを回収しながら、自身の創造主の言葉を口にした。
「機械でありながら人となったこの人形は、正しい世界を作り出す礎となる」
「そうすれば私も完全な存在になれる。貴女、そう言ったわよね?」
「ああ。疲れた因果が戻ることで、私もお前も正しき存在へと昇華される」
「その言葉、信じているわよ」
ノイクロームと言葉を交わしながら、ノエラはウォーケンの頭部を耐久性が高い箱に緩衝材と共に入れ、最後に荷馬車に詰め込んだ。
「これで全てか?」
「多分ね。さ、何処へ向かえばいいの?」
「お前の端末に位置情報を送る」
ノエラの持つ小さなデバイスに光が灯る。ノエラはそれを確認すると、僅かに顔を顰めた。
「ここは......。貴女、あんな人まで利用するのね」
「否。私の計画に賛同する協力者だ」
「そう、まあいいわ。じゃあ向こうで落ちあいましょう」
ノエラは荷馬車の御者台に乗り込むと、ノイクロームがいたところを振り返った。
ノイクロームの姿は消えていた。ノエラは溜息を一つ吐くと、荷馬車を帝都ファイドゥに向けて走らせるのだった。
「─了─」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ