エヴァリスト
【正体】元聖騎士にして成り上がり者の若手将校
【死因】刺殺
【関連キャラ】アイザック(盟友)、アリステリア(愛人)、ベルンハルト(師匠)、マックス、ブレイズ(殺害者)
3395年 冬 「泥濘」 
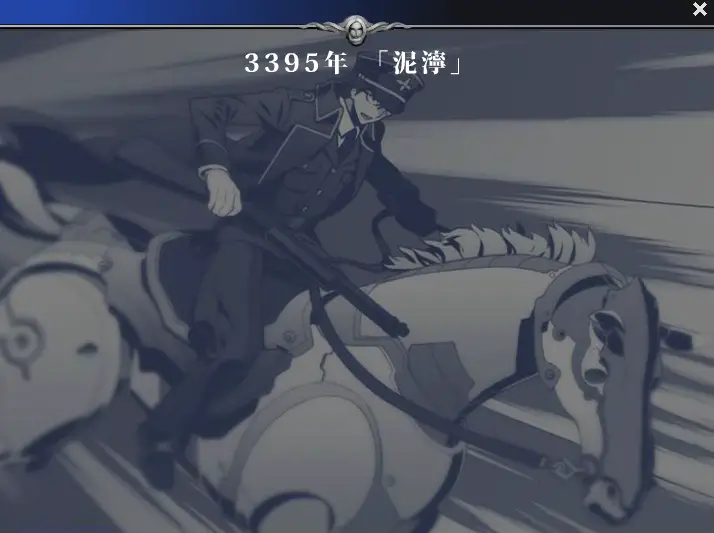
午後を過ぎて冷たい雪が降り始めていた。
激しい砲撃を受けた地上は泥濘と化し、エヴァリストの足下を汚していた。
帝國の東方、バーンサイドとの国境沿いにある橋を挟んで、膠着状態が続いていた。
土塁の傍まで来てアイザックは囁いた。
汚れた戦闘服は戦いの激しさを物語っていた。
「はめられたな」
ただし、その顔には笑みが浮かんでいる。
エヴァリストをからかっているかのような口調だった。
「知っていたさ。だから来た。何かを得たかったら犠牲は必要だ」
「……犠牲か。お前の部下たちは可哀想だな」
「お前だって私の部下だ」
「オレは好きなんでね、戦争が。楽しませてもらってる」
「これからもっと楽しくなるかもしれんぞ。見てみろ」
土塁の向こうをアイザックは乗り出して覗いた。
「わかるか?」
対岸の堤防側で、兵が慌ただしく行き来している様子が見える。
その装備は、今まで戦っていたバーンサイド軍のものとは明らかに異なっていた。
「援軍か?」
「インペローダの兵だ。戦獣をつれている」
エヴァリストはシドール将軍からの指令をアイザックにも伝えようと決心した。
「――帝都ファイドゥ――」
「私は不安なのだ」
酒杯を置いて、将軍は語る。
「我が軍には役人の様な軍人が多すぎる」
麾下の師団で頭角を現したエヴァリストを、シドール将軍は特別に目をかけていた。
「私は君をかっている。ヴァルツ大尉」
深い皺に囲まれた鋭い眼孔は、この小柄な将軍の威光の中心だった。
「特に軍人としてというより、戦士としての君をな」
将軍はグランデレニアの帝國軍にあって特別な人物だった。
曙光の時代が始まり、地上の多くの混沌から開放された時に、
真っ先に軍を増強して帝國の版図を広げることを主張したのが彼だった。
多くの戦果を上げ、帝國の威信を大いに高めた。
ただ、そのあまりに大きな成功がかえって帝國内での立場を危うくしていた。
ルビオナ王国との西部戦線では一進一退の状況が続き、軍内での政治力に陰りが出てきていた。
「生まれはどこかね。領内の生まれではないと聞いているが」
今までの会食は他の士官を交えて戦況や要望などを語り合う定型の場だったが、
今日呼ばれたのはエヴァリストのみだった。
「フォレストヒルです。今はもう存在しません。子供の頃に「渦」に飲まれました」
エヴァリストは正直に話した。将軍は真意のわからない内には、
駆け引きをする必要を感じなかったからだ。
「難民として帝國で育ち、17の時に軍に志願しました」
「軍に志願した動機は?」
「自分の力を試すためです。何処までやれるのか知りたかったからです」
将軍はエヴァリストの目をじっと見つめていた。
「なるほど。自身の出自や環境はどう感じている?」
「自分を憐れむ気持ちはありません。感情は所詮行動に付随するものです。
前進しているならば、拘泥する必要を感じません」
「面白い物言いだ。しかし前線指揮官としては頼もしい」
将軍は笑って酒杯をあおいだ。
「将軍、今日私をお呼びなった理由は何でしょうか?」
エヴァリストは直裁に切り出した。
「焦るな大尉。聞いてくれ」
「人生に目的はない。どこの街に生まれようが、どんな家系に生まれようが、結局は死ぬ」
「しかし戦争は違う。何処で始まろうとも、必ず勝利という目的がある。そこを私は気に入っているのだ」
将軍は立ち上がり、壁に飾られた地図に向かう。
「戦線は日々拡大している。西にも東にも南にもな。そしてすべての戦場で我々は勝利する」
振り返った将軍の目には、独特の光が宿っていた。
この歪んだ意気こそが小柄な男を将軍にしているのだと、
エヴァリストは感じた。
「そのためには新しい力が必要なのだ」
「ひとつ頼みを聞いてもらいたい。君のような男でないとできない、特別な仕事だ」
「――マイオッカ国境――」
朝が来た。夜明けと共に、対岸からゆっくりと戦獣三体が姿を現した。
背の高さは3アルレ<4.5メートル>ぐらいだが、
横にもそれぐらいの幅があり、肉塊の迫力はここからでも伝わってくる。
背にはインペローダの獣騎兵が乗っていた。突き出た口には拘束具が取り付けてあり、
拘束具から延びた手綱を獣騎兵が握っている。
昨日のうちに戦獣のタイプはわかっていた。
昔は「トーベア」と呼ばれていたタイプだ。
歩くときは四本足で進むが、捕食時には立ち上がって前足を器用に使う。
赤く甲羅のように厚い皮膚と、協力な治癒能力を持っている。
確かに戦争にも役立つタイプだ。
巨獣は障壁器を後ろに引きながら、ゆっくりと橋に向かう。
と同時に背後からバーンサイドの工兵達が現れ、橋を渡り始めた。巨獣が引く障壁器の力で銃弾や砲撃の心配が無い。
工兵達はこちらが橋に仕掛けた地雷や障害物を取り除き始めた。
バーンサイドやインペローダにはテクノロジーを管理する「エンジニア」達との繋がりが弱く、
こちらが使う自動機械や高性能な野砲などは持っていなかったが、
防衛の為にどの都市にもあった障壁器の技術は残っているようだった。
騎士隊はすでに集まっていた。
従卒が機械馬<オートホース>の傍に立ち、エヴァリストを待っていた。
馬へ乗り、彼から騎兵銃<カービン>を受け取った後、薬室を確認してから鞍へと差した。
従卒は自分の馬に乗り、他の隊員全てが騎乗した。
エヴァリストは剣を抜き、隊員に向かって叫ぶ。
「我が帝國軍の本隊は現時ルビオナと交戦中である。
今、このマイオッカにその後陣を突こうとバーンサイド軍が侵攻してきた。これは暴挙である。
しかもその背後には邪悪な獣をつれたインペローダがいることがわかった。
ここで引き下がることはできない!」
「西方で戦う同胞のために!故国で待つ家族を守るために!インペローダの意気をここで葬る!」
「邪悪な獣を恐れるな、敗北の恥辱を恐れよ!」
隊員は声を上げ、顔をあげた。
みな一様に緊張をしているが、その顔は戦いへの意欲を現していた。
「ゆくぞ!」
副長のアイザックが隊列を整えさせる。
エヴァリストの横にアイザックは立った。
「さて、楽しませてもらおうか。生きているうちにな」
いつもの調子なアイザックの後ろには従卒がいた。
だが、その顔は緊張のあまり蒼白になっていた。
「無駄口だな、中尉。彼を見習え」
急に声を掛けられた従卒は、驚いた顔でアイザックを見る。
「怒られたよ。大尉は怖いね」
陣地から勢いをつけて騎士隊が飛び出した。
自分達の工兵が置いた障害物を、踊るように機械馬が避けていく。
工学師<エンジニア>が作る自動機械<オートマタ>の精巧な動きは、
滑るように馬と騎兵を進めていた。
障害物に取り付いていたバーンサイドの工兵達は、持ち場を飛び退くように離れ、
元の対岸に向かって走る。
しかしすぐに機械馬に追いつかれ、振り出した剣と馬体に押し潰され、ぼろ切れのように地面に転がった。
バーンサイドの獣騎兵達は、突撃してくる騎兵に対抗しようと必死に手綱を引き、拘束具を解こうとしていた。
カービンを構えて馬を止め、獣の上に乗る獣騎兵を狙う。
まだ50アルレ<75メートル>以上はあるかという距離だったが、揺れる標的をしっかりと捕らえ始めた。
ゆっくりと時間が進むのが感じられた。はっきりとエヴァリストは「端」に立ったことがわかった。
力を使うときだ。眼の中で、照星の向こうに霞む獣騎兵達の「未来」が見えた。
揺れる銃口と未来の映像がシンクロしていた。
獣騎兵の倒れる絵をしっかりと捉えた時、引き金を引いた。
まるで一度時間が巻き戻ったかのように、起き上がった兵がまた倒れた。
獣騎兵は獣の鞍からぶら下がるようにして息絶えた。
縦列になった獣に乗る残りの獣騎兵二人も、同じようにして倒していく。
「大尉、お見事です」
恐れていた巨獣が力を奪われるのを見て、興奮した様子で従卒が声を掛けてきた。
立ち止まった自分と共に残っていたのだ。
「いいから前に進め。橋を渡りきってからが勝負だぞ」
従卒と共に一気に先陣に追いつく。巨獣の脇をすり抜けていく。
拍子抜けするほどに「トーベア」は動かなかった。
力なくぶら下がった獣騎兵の死体を一瞥すると、障壁器のある後方に向かう。
「これじゃただの荷馬ですね」
従卒が高揚した口調で叫ぶ。
障壁器の周りでは、先陣の部隊が足止めされていた。
障壁器は戦の要のため、どんな場合でも防衛兵がついている。機銃掃射で馬を近づけないようにしている。
「どうした」
「うまく配置されてやがる。抜けれねえ」
アイザックが答える。
「時間が無い、二人で行くぞ」
アイザックはうなずく。
「私とアイザックに付いてこい。必ず機銃は仕留める」
左右から同時に飛び出せば、必ずどちらかは辿り着ける。
ここで時間を取られれば対岸の本隊を仕留められず、犬死にとなる。
「行くぞ!」
声を掛け、同時に飛び出した。
機銃は一瞬の迷いの後にこちらに銃口を向けた。エヴァリストは機械馬を走らせながら体を伏せ、銃撃を待った。
数発ならば機械馬は持ち堪えられるし、体幹に弾を受けなければ死にはしない。
銃撃音が響くと同時に激しい衝撃を受けた。
機械馬がコントロールを失い、障壁器の手前で前のめりに倒れた。
放り出され、地面に叩きつけられる。
痛みは感じたが、後続に踏み潰されぬよう必死に顔をあげた。
うまく後続はエヴァリストを避けていく。
防衛兵の機銃はアイザックが仕留めたようだった。
「大丈夫ですか!」
従卒が傍に来た。
「馬を替えましょう」
「いや、後ろに乗せてくれ」
幸い骨は折れていないようだった。
失ったカービンを借り、機械馬の後ろに乗った。
障壁器を確保し、橋の三分の二を過ぎたところで、橋向こうから後続の装甲猟兵達が押し出てくるのが見えた。
訓練された装甲猟兵は騎兵にとって危険な存在だった。
馬による蹂躙も、士気を保った装甲猟兵相手だと分が悪い。
エヴァリストは馬上から装甲猟兵の中隊長マークを背負った者を狙った。
トリガーを引き絞る。シアが落ち、撃針が雷管を叩く。
ガス圧によって加速された徹甲弾が空を進んでいく。
全ての感覚が繋がっていた。
トリガーを引くことで弾が射出される道理と同じように、弾は確実に装甲猟兵のスリット状の眼孔に吸い込まれて行った。
前のめりに倒れていく中隊長。まだ敵は何が起こったのかに気付いていない。
次弾を先頭の兵へと合わせようとしたとき、先を行くアイザックが視界に飛び込んできた。
馬を下りたアイザックは、体捌きによって眼前の敵を倒して行く。装甲猟兵のスピードでは全く追いつけない。
敵の混乱は明らかだった。
前線に追いついたエヴァリストも馬を下り、アイザックと共に剣を振るう。ここでアイザックと共に装甲猟兵を引きつけ、他の隊員を先に行かせる。
後方にいた敵の部隊は、騎兵達が届くと潰走を始めた。
自分達の兵力の支えであった巨獣と装甲猟兵の敗北を見て、恐怖したのだ。
アイザックはとどめの一撃を装甲猟兵の首へ叩き込んだ。
傍らで戦況を確認しつつ戦っていたエヴァリストは、勝利を確信した。
損耗は激しかったが、得たいモノを得られた。
何も無い自分達が何かを得るためには、戦うしかない。
エヴァリストの決意は血に塗れた戦場の中でも変わらなかった。
「―了―」
3397年 夏 「晩餐会」 

宮殿で定期的に開かれる晩餐会には、貴族や政治家、高級官僚といった帝國の支配階級が集まっていた。
そしてこの日は、戦争で功績を上げた軍人達も招待されていた。エヴァリストとアイザックもその中にいた。実質、拡大派による晩餐会であり、統制派の有力者は殆ど参加していなかった。
「ムダに豪勢じゃねえか。こっちは戦争中だぞ」
アイザックは文句を言いながらも、出されている食事をがつがつと食べていた。
「ロスバルド大尉、そういう事は思っても口に出すものではない」
「へいへい。……っとこれはシドール将軍閣下、失礼しました」
振り返ると、将軍がグラスを片手に立っていた。
「折角の晩餐会だ。もっと楽しんではどうだね」
「十分楽しんでますよ。メシはなかなかだ。でも、こんなとこより戦場の方がよっぽど楽しめますがね」
「それはそれで頼もしい限りだ。ところでヴァルツ少佐はどこに」
アイザックはフォークを持った手で、エヴァリストのいる方向を示す。
「ほう。さすがだな」
エヴァリストは年頃の娘達とダンスを踊っていた。軍人らしからぬ足捌きで周囲を盛り上げている。
いずれも有力者達の娘であるのだろう。
帝國軍拡大派の若き英雄というだけでなく、あれだけ整った顔立ちだ。人気が出ない筈がない。
「ヴァルツ様、次は私とお願いします」「いえ、わたくしと」「いいえ、私と!」
踊りが一段落したところでエヴァリストへ近付こうとするが、黄色い声の嵐で入り込む余地が無い。
シドール将軍が大きな咳払いをし、女性達とエヴァリストに語り掛ける。
「すまないが、お嬢様方。少しの間少佐を借りるが構わないかね」
「だめです!」
てんでバラバラだった声が一つにまとまり、明確な拒否を示す。
エヴァリストが助け舟を出す。
「申し訳ありません、皆さん。後程必ず戻ってまいりますので」
優しくエヴァリストは微笑みかけた。
「はい!」「お待ちしております」
「やれやれ、彼女達の前では私の地位は何の役にも立たないようだな」
「ご婦人方は流行り物がお好きなのでしょう」
「ある方に会っていただく」
シドール将軍とエヴァリストはホールを出て、宮殿へと進んでいった。
別室に通されたエヴァリストの目の前には、壮麗な椅子に座った若く美しい女性がいた。
しかしその佇まいは、他の貴族とは明らかに異なっていた。
そこには皇妃アリステリアがいた。肖像画等でしか見た事のない、帝國を象徴する人物だ。
エヴァリストはその場で膝を突き、黙礼した。
帝國において皇妃は際立って特別な存在だった。不死皇帝の后として、その言葉を臣民に伝えることのできる人物なのだ。
絶対的な権力があるとすれば、この皇妃の存在に他ならない。
アリステリアは椅子から立ち、エヴァリストの前に立った。
「皇妃陛下、エヴァリスト・ヴァルツ少佐をお連れしました」
皇妃が腕を出すと、エヴァリストは面を上げ、手に口づけをした後、立ち上がった。
「お会いできて光栄です。皇妃陛下」
「あなたの活躍は聞いています。すばらしい働きでしたね」
「ありがとうございます、陛下。しかし私だけの力ではありません。部隊皆の力です」
アリステリアは肖像画よりずっと幼く見えた。しかし、その瞳の光は不思議な冷たさ、落ち着きがあった。
将軍はそっと場を辞すると、部屋には二人だけになった。
「何故ここにいらっしゃるのです?」
通常、皇族の警護にあたるカストードらの気配は無かった。
「帝國の宮殿に皇妃がいて不都合が?」
ゆっくりとエヴァリストの傍に立ち、皇妃は腕を組んだ。
「緊張を解きなさい。誰もここにはいません」
エヴァリストの心を読むかのように、皇妃は答えた。
エヴァリストを皇妃アリステリアに引き合わせたシドール将軍は、二人から離れ、気の赴くままに会場を歩く。
多くの人達はシドール将軍の姿を認めると、、向こうから話し掛け、遜ってくる。自らの権勢を再確認できシドール将軍ひどく機嫌がよかった。
そんな中、拡大派ではないにも関わらず晩餐会に来場していた人物が、シドール将軍へ話し掛ける。
「シドールよ。あの男、ヴァルツは危険だ」
拡大派にも統制派にも属していない、ベアード将軍だった。
「彼奴の眼は、使われるだけの軍人の眼ではないぞ」
「だからこそ使っている。奴は若い連中の象徴だ。功績に見合った報酬を与えておけば士気も上がる。それに奴とて私の後ろ盾が無ければ何もできぬ」
「昔はな。今後もそうだとは限らん」
「小心者のお前らしい意見だな、ベアード。私は使える駒は全て使う。そして、駒に使わるつもりはない」
「そのうえ皇妃陛下にまで引き合わせるとは、何を考えている」
「皇妃陛下たっての要望だ。真意は私の知るところではない」
「しらを切るか。まぁいい、精々自らの策に溺れることがないよう気をつける事だ」
「カンドゥン長官を失って以降の統制派は虫の息、拡大派の勢いは増すばかりだ。これで何を恐れろと言うのだ」
晩餐会が終わりに差し掛かり、来場者の一部が帰り始めた。
今日も素晴らしい日だった。もはや帝國内に敵対勢力などいないに等しい。あとは「いつ」決着をつけるかの問題だけだろう。
シドール将軍の気持ちは昂ぶっていた。
晩餐会で摂取したアルコールも手伝い、夢心地で統制派への処遇を考えていた。
徹底的に潰すか、ガス抜き目的に生かさず殺さずにしてしまうか。不利な戦線へ送り込むのもいい。
迎えの馬車に乗り込んだシドール将軍は、従者が普段と違う事に気づくことはなく、また、背後に本来の従者の遺体があることにも気付けなかった。
事実、統制派は追い詰められていた。故にシドール将軍殺害という乾坤一擲の策に出ざるを得なかった。
そして、それは成功した。馬車の扉が閉まり、しばらくすると特殊なガスが馬車内に充満しはじめた。
異常に気付き飛び出そうとするが、馬車の扉も窓も開かない。間もなくシドール将軍は意識を失った。
馬車はそこかへと去っていった。
その一部始終をアイザックは物陰から確認していた。しかし、将軍を助けようとはしなかった。
エヴァリストからそう命じられていたからだった。
すでに自分達にとって将軍の利用価値は無かった。統制派の最後の反撃の贄にすると決めていたのだ。
統制派の計画には気付いていたが、何もしなかった。
ひたすら領土拡大、戦線拡大に邁進するシドール将軍は、拡大派においても邪魔な存在になっていたのだ。
既に拡大派の主要人物には根回しを終えており、エヴァリストが実質的なトップになることが確定していた。
皇妃と別れたエヴァリストはホールへと戻った。すでに殆どの客は去っていた。エヴァリストは奇妙な緊張を解くため、バルコニーで夜風に当たっていた。
傍にアイザックがやってきた。
「どうした。ずいぶんと長くかかったな」
「あとで話す」
「さっき、シドールに客が来てたぜ」
シドール将軍が始末されたという符丁だった。いよいよ、自分達の力が試されるときが来た。そうエヴァリストは確信していた。
「―了―」
3389年 「脱出」 

「アイザック……」
地面に突き刺さった木剣を引き抜き、元あった位置へ戻す。二本並んだ木剣を眺めながら、エヴァリストは昔を思い出していた。
レジメントがその総力を挙げて向かった最初にして最後の戦い。最大の渦《プロフォンド》たる眼『ジ・アイ』の処置。
その甲斐あって、ついに眼『ジ・アイ』はその姿を消そうとしていた。
ところが、中心部へ向かったレジメント達は一向に戻ってこない。
「遅い。何をやってんだ。このままじゃまずい事になるぜ」
苛立ちを隠そうともしないアイザック。
「そう焦るな」
それでも眼下にある眼『ジ・アイ』が消えようとしている事は、作戦は成功したという事だ。
エヴァリストは仲間達の帰還を疑ってなどいなかった。
経験の浅さ故、突入メンバーにこそならなかったものの、中心から外れた場所とて危険である事に違いなかった。
中心部に向かったメンバーをやや外側で待ち、撤退経路の確保を行う。それがエヴァリスト達若手の役目だった。
「くそったれ、隊長達はまだか!」
渦《プロフォンド》の消滅が近付き、活発になった異形達を迎撃しながら仲間を待っていたが、限界は近付いていた。
「このままでは俺達も消滅に巻き込まれかねない」
「退こう!」
後ろ髪を引かれる思いで離脱しようとした時、ついさっきまで駆動音を鳴らしていた浮遊艇がまるで動かなくなっていた。
「そっちの浮遊艇はどうだ」
「駄目だ、動きゃしねぇ」
それも自分達だけではなく、他の隊でも同様の事が起こっているようだ。
「エヴァ!」
エヴァリストの死角より迫っていた異形の攻撃を、アイザックが防ぐ。
初撃は防ぐ事ができたが、次を受け流しきる事ができなかった。
呻き声と共に右目を押さえるアイザック。
「アイザック!」
「大したことはない、かすり傷だ」
アイザックは上着を脱ぎ、裾を破ると右目に当てた。布はすぐさま赤黒く染まる。気休め程度にしかなっていない。
レジメント達が「足」を失った事を察知した異形達は、数と勢いを増して彼等を追い詰めだした。
「乗れ!」
聞き覚えはあるが、ここでは聞こえない筈の声。
その声の先にいたのは、作戦の現場に現れる事はない、上級工学師『テクノクラート』のラームだった。
「どうしてここに!」
エヴァリストの疑問を遮り、老人は早口で捲し立てる。
「すまないが今は話をしている時間が惜しい。今の我々に用意できるのはこれが精一杯でな」
上級工学師の乗ってきた浮遊艇に飛び移る。
「後はお主らの足で逃げ切ってくれ。わしは一人でも多く回収しなくてはならぬ」
渦の外縁部に二人を降ろすと、再び中心部へ向かい飛んで行く。
去り際にラームは言った。
「とにかくレジメントには戻るな、姿を隠せ」
意図を問い質す間もなく、エヴァリスト達は取り残された。
眼『ジ・アイ』から少しでも遠くへ。気持ちは焦るが、アイザックの足取りが重い。
「ぐあああ……!」
異形より受けた傷が、普通と同じである筈がなかった。
いつもなら医療班の治療で事無きを得るのだろうが、今回はそうもいかない。
アイザックが呻き声を上げ続ける。
右目から流れる液体は赤黒いものだけでなく、黄色い液体も混じるようになっていた。
このまま傷を放っておく訳にはいかない。
「街に着くまでの辛抱だ。一刻も早く医者に見せよう」
「医者か。医者ね……。ここまで悪化したら、パンデモニウムに行かない限り、どうしようもないんじゃないか?ならばいっそ……」
アイザックは右目を覆っていた布を外す。
「中途半端に期待するのがいけねぇ。そうは思わないか、エヴァ」
エヴァリストの目に映ったアイザックの右眼周辺は既に本来の色を失い、眼を背けたくなるようなものへと変貌していた。
アイザックの右手が右目へ伸びていき、眼球に触れ、掴む。
断末魔に近い叫び声を上げながらも、手が止まる事はない。
アイザックの眼球だったものが地面に投げ捨てられていた。
「これで少しは痛みから解放されるといいがな」
そう言うと、アイザックはつい先程まで自分の顔に埋まっていたものを踏み潰した。
二人は辺境を彷徨い続けた。食料を確保し、導師ラームの言う通り、人目に付かぬように過ごした。
時が経つにつれ、少しずつ状況が理解できるようになった。辺境の街にもニュースは届いていた。ついに渦が全て消滅したこと、そして自分達レジメントが全滅したことも。レジメントは世界を命懸けで救った英雄達ということになっていた。隊員達は全て最後の戦いで死んだ、と。
エヴァリストは、自分達は見捨てられたのだとはっきり悟った。どんな工作が裏にあったにせよ、自分達は疎まれ、見捨てられたのだと。
不思議と怒りは感じられなかった。皆、死ぬ覚悟はできていた。生きて名誉や財産を得ようとは誰も思っていなかった。
しかし、今の世界が自分達を必要としないのならば、その世界を変えてやる。そう強い意欲が沸いてきた。誰の死も無駄にはしない。自分達が生き残ったことには必ず意味がある筈だから。
森の端、地平線に城郭が見えた。
「明日には、ようやく街へ着けそうだ」
エヴァリスト達は、グランデレニア帝國の末端に辿り着いていた。
「これからどうする」
アイザックが聞く。
「もう帰る場所は無い」
「ああ、そうだな」
「この街じゃ新兵を募集してる。経歴不問でな」
帝國は戦争の準備を始めていた。渦の無くなった今、城塞都市に籠っている謂れは無い。拡大のための戦力を帝國は準備し始めていた。
「傷の具合はどうだ」
「待っていても目玉が生えてくるわけじゃないしな」
「来てくれるか?」
「勿論。お供いたしますよ」
ややあって、笑い合う。久しぶりの笑顔だった。
故郷を失った時、レジメントを失った時、常にアイザックはエヴァリストの傍らにいた。
残酷な世界に自分達を認めさせるために、二人だけで戦ってきた。
だが、世界が自分達を認めようとしている時、二人の間には距離ができていた。
それでも歩みを止める事などできない。今立ち止まれば、また全てを失ってしまうのだから。
「―了―」
3398年 「偶像」 

敵の多さは十分自覚していた。内地にいても油断はしないようにしていた。
公的な地位と皇妃の後ろ盾で傍からは盤石に見える権勢は、その実、危ういものでもあった。
そのことを忘れていたつもりはなかった。
ある人物の密会との帰路、人気の少ない街角を進むエヴァリストの馬車が不意に動きを止めた。
しばらく間があいた後にも御者からなんの合図もないことを訝しんだ護衛が馬車を降りると、乾いた射撃音とともに崩れ落ちた。
襲撃が明らかになっても、エヴァリストに動揺はなかった。
むしろ護衛がいなくなり人気がなくなったことが「力」を存分に使える。そう考えていた。
護衛への着弾と銃声の僅かなずれから、襲撃者との距離と方角を見定める。
襲撃者が何人いるかわからない状態で馬車から降りるのは得策でないと考え、しばらく様子をうかがう。
外の反応はない。手の込んだ警告か、または次の手を考えているのか。
どちらにせよ、今の状況を打開するしかない。
撃たれた護衛が出た反対のドアを開け、馬車を降りる。視界に動きはない。
銃を抜き向かいの建物まで走りぬける。
建物へ渡るまでの刹那、衝撃がエヴァリストを襲う。
腕に銃弾があたりバランスを崩しながら物陰に飛び込んだ。
手練れがいる。そして脅しでなく、相手は確実に自分をしとめようとしていることをエヴァリストは悟った。
エヴァリストは自分の油断に、自嘲的な笑みを浮かべた。
しかし、時間はない。こちらの姿を確認した相手は今度は距離を詰めてくる。退路を見つけ出さねばならない。
飛び込んだ物陰は雑然とした路地へと繋がっている。腕の銃創を押さえながらその路地を走った。
エヴァリストは赤く染まった傷口を抑え、夜の帝都を走っていた。他に人影はない。
路地に入り、壁に背を預け、耳を澄ます。追手の気配はまだない無い。
軍服と白地の手袋は赤く染まっていた。
一呼吸置き、路地から空を眺める。いつもの変わらない夜空だった。
視線を落とすと眼前の壁には自身が描かれたポスターがあった。
『全ては帝國の為に』
勇ましく描かれたエヴァリストの姿がその紙の中にはあった。
帝國貴族や政治家の家計でないにも関わらず、現在の地位まで上り詰めたエヴァリストは一部の若者達にとっては羨望の的でもあった。
そこを広報部に見出されたのだった。民衆の間にも厭戦気分が漂い始めた頃の起用だった。
「……ふっ」
傷の痛みを堪え、姿を見せない敵の気配を探っている現在の姿は、ポスターに描かれた姿とは対照的な惨めなものだった。その落差に思わず苦笑してしまう。
これからどうするべきか、エヴァリストは思考する。
密会の帰路だった為、部下や仲間が異常に気付くには時間がかかる。
こちらから呼べる状態でもない。このまま身を潜めて夜が明けるまで待つべきだろうか。
否。そのような幸運を期待するのは戦いでは無意味だ。
自らの力で打開する。それがエヴァリストの導き出した答えだった。
統制派か、敵国か。あるいは把握している思っていた拡大派か。
どの勢力かはわからないが、今夜のような機会を逃すはずはない。
追手の気配はまだなかった。息を整え終えるとまた再び走り出す。
しばらく進むと、数少ない街灯の下に立つ男の姿が現れた。その動きに気配はない。
特徴的な赤い外套は闇夜でもよく目立った。襲撃者は統制派でも、拡大派でも、戦争中の敵国でもなかった。
仮面を付けた協定査問官《インクジター》だった。
「エンジニアの走狗か……」
インクジターの来襲が意味することをレジメントの生き残りであるエヴァリストは理解した。
「……ずいぶんと来るのが遅かったな」
腕の痛みは、ずいぶんと増していた。止血も十分おこなえていなかった。
「……」
仮面の男は返事のかわりに武器を構えた。
「悪いが過去の亡霊にとらわれている暇はない」
エヴァリストはそう言うと、男に銃弾をたたき込む。
しかし、相手はすべて両手の仕込み剣ではたき落とす。常人の技ではない。
一気に間合いを詰めた仮面の男はエヴァリストの首に向かって剣を振りかざした。
エヴァリストはその太刀筋をすんでの所でかわし、銃を捨て、剣に持ち替える。
男の剣は一撃一撃が速く、重い。金属と金属のぶつかり音が夜の町に響く。
かろうじて防げてはいるが、攻勢に出る切っ掛けは掴めない。
その間にも先に受けた傷口からの出血量は着実に増えていった。
苦戦はエヴァリストが負傷しているせいだけではなかった。
エヴァリストはこの地上でレジメントと同等に戦えるのは同じレジメントしかいないというのをはっきり思い出していた。
突如、仮面の男の攻勢が止んだ。仮面の奥で大きく呼吸音をする音がする。明らかに雰囲気が変わっていた。
何が起こったかエヴァリストは、次の攻撃で理解することになった。
先程までとは段違いに一撃が重くなっていた。
何度も太刀を受け、腕のしびれが極限まで達したために、エヴァリストは距離を取った。
「お前の太刀筋、レジメントで学んだ物だな。 なぜ、奴らの走狗になった」
仮面の男は答えない。心理的な挑発など聞こえていないかのように再び間合いを詰めてくる。
エヴァリストはこの短い時間でこの男の、太刀筋のバターンを分析していた。
一件、奇矯な太刀筋だったが、組み立てに規則性があった。
間合いをつめてきた次の一撃、その攻撃はエヴァリストの予想通りのものだった。
エヴァリストの剣が間合いを詰めてきた男の仮面をはっきり捕らえた。
かつて『茨』と恐れられたエヴァリストの必殺の一太刀だった。
男は一撃を受けてがくりと膝をついた。
「終わりだ、過去へと戻れ」
エヴァリストがとどめの一撃を振るうため剣を振り上げた時、腹部に衝撃が走った。
剣を振り上げたまま、エヴァリストは自分にささった剣を見つめた。仮面の男が腕から放った剣だった。
「くっ」
一気に力を失ってエヴァリストは倒れた。しかし意識は保っていた。
「まだ、まだだ……」
立ち上がろうと、地面をかきむしるようにエヴァリストはもがく。
寝転がったまま、落とした剣を手に取り、構えようとする。その剣を仮面の男は手ごと踏みつける。
ここで死ぬわけにはいかなかった。
今、この過去の亡霊に取り殺されれば、自分はなにもこの世界に残せずに死ぬことになる。
なぜ、ここまで自分は生き残ってきたのか、それがすべて無になってしまう。
押さえられた手を傷ついた腕で必死にどけようとする。
どんな無様であっても、自分は死ねない。その思いがエヴァリストを足掻かせた。
「くそっ、まだだ……」
地面にエヴァリストの血が広がっていった。足掻けば足掻くほど、そのスピードは増していった。
仮面の男の表情は分からない。
この男の最後の瞬間を目に焼き付けようとしているのか、とどめを逡巡しているかのように思えた。
そのとき、大きな銃声がとどろいた。仮面の男がエヴァリストの側から飛び退く。
「よう」
エヴァリストは朦朧とする意識のなかで声の主に気付く。
その不躾な声、聞き間違えるはずもない。アイザックだった。構えたライフルは仮面の男を捕らえている。
「まだやるかい」
アイザックが合図をすると背後からエヴァリストを信望する兵士達が現れる。
間もなく夜が明けようとしていた。
仮面の男はしばし逡巡すると、武器を下ろしアイザック達とは反対の方角へ去って行った。
「よろしいのですか?」
兵士の一人が当然の疑問を口にする。
「今はそっちが先だ。早く医療班を」
倒れているエヴァリストを示した。
「はっ!」
アイザックは傷ついたエヴァリストの横に座り、止血のための布を腹に当て、その頭に手を添えた。
「死ぬなエヴァ、これで終わる訳にはいかねえんだろ」
「―了―」
3398年 「決着」 

皇妃の居城である尖塔からは、巨大な街並みが一望できた。この塔は帝國の首都ファイドゥで最も高い。
もう夜半が過ぎていたが、街は小さな宝石を散りばめたかの様に輝いていた。
エヴァリストが襲撃されてから三ヶ月余が経っていた。エヴァリストはすでに公務に復帰していたが、復帰早々多忙な日々を過ごしており、こうして皇妃と二人きりになれたのは、襲撃後初めてだった。
「もう入りましょう。夜風が随分と冷たい」
バルコニーの手摺りにもたれて夜景を眺める皇妃アリステリアの横顔には、いつもと変わらない美しさが宿っている。
「もう少し見ていたいのです」
アリステリアは夜景から目を逸らさずに答えた。
二人に夜風が当たる。
アリステリアの肩にコートを掛けたエヴァリストは、そのまま彼女の金色の髪を撫でながら、優しく口づけをした。
「陸下、貴女ですね?情報を渡したのは」
襲撃の日、エヴァリストの動向を知っている人物はごく僅かだった。そして、あの日はアリステリアがセッティングした、旧統制派要人との密会の日であった。
アリステリアは何も答えない。
「貴女は私に助けを求めていた筈。それとも、全て私を落とし入れるための行動ですか?」
エヴァリストの口調は詰問するというものではなかった。ただ、囁くようにその言葉を口にした。
「選択肢など、私には初めから無かったのです。生まれ落ちてから、そして死ぬまで」
アリステリアは俯いた。その目には涙が湛えられていた。
「私ならその範から逃してあげられると申し上げた。それは奢った気持ちからではありません」
エヴァリストの声色は、それでも落ち着いている。
「もう遅いのです……」
アリステリアがそう言い淀んだ瞬間、衝撃と爆音が響き渡り、 尖塔全体が大きく揺れた。眼下を望むと赤い光が照り返している。
「ここは危険です。さあ、こちらへ」
エヴァリストはアリステリアを抱えて部屋の中へ戻ろうとした。しかし、アリステリアはその手を払った。
「陛下、私の誠心に変わりはありません。ご事情は後で伺います」
「もうよいのです……もう終わりです」
アリステリアは目を閉じて頭を振った。
「皇妃が正しい。終わりだ、エヴァリスト」
突然の声に振り返ると、一人の男がバルコニーの入り口に立っていた。紅衣を纏った協定審問官――インクジター――、ブレイズがそこにいた。
エヴァリストはアリステリアを庇うように立ち位置を変え、剣を抜いた。彼は特別に皇宮内での帯剣が許されている。
「貴様が塔に火を放ったのか?」
「それはどうでもいい話だ。それよりも、お前は皇妃を守れるのかな?」
ブレイズの視線はアリステリアに向けられている。エヴァリストも視界にアリステリアを捉えようと横を向く。
そこには、バルコニーの欄干に立っているアリステリアがいた。
「陛下、おやめください!」
エヴァリストはブレイズの動きを牽制しながらも、アリステリアを引き留めようと片腕を伸ばした。
「さようなら、エヴァリスト」
アリステリアはそう言うと、欄干から身を投げた。
エヴァリストは落ちかけるアリステリアを掴むこともできたが、そうはしなかった。エヴァリストに向けられたブレイズの殺気が弱まっていなかったからだ。
少しの間が空いた後、鈍く湿った衝撃音がバルコニーに届い た。
「ほう、やはり皇妃を見捨てたか」
世界を救うためにレジメントで共に戦った聖騎士。しかし時が経ち、二人の立場は全く違うものになっていた。
インクジターがレジメントの生き残りを始末して回っている事は、エヴァリストの耳にも入っていた。
「貴様がそうさせたのだろう」
「それはどうかな。それはお前の都合のいい解釈だ。私は何もせずに、お前が皇妃を助けるのを眺めていたかもしれない。決めたのはお前だ」
「何が言いたい?」
エヴァリストの言葉には、珍しく怒気が籠もった響きがあった。
「お前は無慈悲な男だ、エヴァリスト。お前には心が無い。そして、それを自分でもよくわかっている」
「だから何だ。誰かが私の代わりに生きてくれるのか?」
「打算に生きるお前らしい死が待っているぞ」
ブレイズは不敵な構えを崩していない。
「惰弱な貴様に、私が負けるとでも?」
エヴァリストはそう言うと、ブレイズに鋭い一撃を加えた。ブレイズは冷静にその一撃を難いで間合いを取る。二人とも部屋の中に入った。
表情にこそ出さなかったが、エヴァリストはブレイズの挑発に痛憤を持っていた。普段なら決して機先を制するような戦いはしない。
「なぜアリステリアが死ぬ必要があった。これは私と貴様らとの問題だろう」
室内で剣載の音が何度も響く。
「用済みだからだ。皇帝は自ら目覚めることを決めた。私は今、皇帝の命でここにいる」
ブレイズは軽やかにエヴァリストの剣を受け流す。
「エンジニアの次は皇帝か。小物らしい振る舞いだ」
再び、飛び退くようにして二人は間合いを取った。皇妃の住む豪奢な居室では戦うスペースに事欠かない。互いに己に有利な立ち位置を確保するように移動していく。
「不死皇帝やパンデモニウムにとって、お前など瑣事に過ぎんのだ」
エヴァリストはブレイズの傲岸な挑発に載る形になっている。
「その項事に苦戦する貴様は何だ?」
二の撃、三の撃と、エヴァリストの剣がブレイズを襲う。が、ブレイズはそれら全てを受け流す。
「ふっ、それは思い上がりだ。お前は弱くなった。そして、私は強くなった」
ブレイズが特殊な構えから一撃を放ち、その剣先がエヴァリストの肩口を捉えた。痺れがエヴァリストの身体を襲う。堪らず膝を折ってしまう。
「お前はテロリストによって皇妃と共に殺されたことになる。そして失意の国民は、復活した不死皇帝を熱狂の内に迎えるだろう。なかなかの筋書きだ」
ブレイズはそう語りながら、再び攻撃の構えを見せる。
「そんな茶番、認めるものか」
エヴァリストは膝を折ったままだ。
「お前にとっては、過ぎた役どころだと思え」
近付いてきたブレイズに対し、エヴァリストは立ち上がると同時に迎撃を加えた。『茨』と称された剣技だ。
「そんな技に、私が掛かると思うか!」
ブレイズの姿が幻のように消え失せ、エヴァリストの反撃は空を切った。
『茨』の終わり際にブレイズの突きが襲ってきた。エヴァリストは右胸を射貫かれる。ブレイズが剣を引き抜くと、エヴァリストはどうと倒れた。
仰向けに倒れたエヴァリストに止めを刺すために、ブレイズがゆっくりと近付いてくる。
「これも情けだ。楽にしてやる」
そう言うブレイズだったが、彼の喉元にも血が滲んでいた。避けた筈の『茨』はブレイズの首を捉えかけていた。ブレイズは血を拭い、深い傷ではないことを確かめる。
エヴァリストの肺が血で満たされていく。大きく胸が動く。落ちた剣を探すように手を動かしている。
ブレイズは剣を逆手に持ち、止めの一撃を加えようと振りかぶった。
その時、熱風と共にドアが開き、二発の銃弾がブレイズを襲った。ブレイズは素早く飛び退いて銃弾を躱す。
ドアから現れたのはアイザックだった。
扉の向こうは既に煙が回っている。下から登る火の手は、すぐそこにまで来ているようだ。
アイザックは間髪入れずに、飛び退いたブレイズに両手の拳銃から連射を加えた。
ブレイズは素早い剣裁きで弾丸をはたき落とす。だが、避けきれなかった数発がブレイズの身体を捉えた。しかし鎧の防御もあり、致命傷にはなっていない。
「これは面倒が省けた。忠犬のお出ましか」
「ブレイズ、少し見ないうちに偉くなったみたいだな。格好だけは立派なもんだ」
アイザックは弾切れになった拳銃を投げ捨て、剣を抜いた。その姿は火災の中を潜り抜けてきたせいか、酷く汚れている。よく見ると所々出血もしている。
「マックスを振り切るとはな」
「あんな仮面野郎、相手にならねえよ」
「にしては、随分と手傷を負っているようだが?」
ブレイズは一気に間合いを詰めた。この状況での長期戦に利は無い。それにアイザックは見たところ相当疲労している。身体を一回転させて薙ぐように剣を回し、アイザックの横腹に鋭い一撃を見舞う。
アイザックはその太刀を受けたが、受けきれなかった剣先が腹にめり込んだ。
「相変わらず威勢だけのようだな」
「……ふん、効いちゃいねえよ」
アイザックは足下を一瞬ふらつかせたが、その剣の気魂に変わりは無かった。ブレイズは間合いを再び取った。
「しぶとい男だ」
「いちいちうるせえぞ……」
アイザックの息は上がっており、すぐに反撃するまでの力は無い。やはりマックスとの戦いで力を尽くしているのだと、ブレイズは判断した。
ブレイズは剣を下段に構え、じりじりと間合いを計る。今度はアイザックの焦りが手に取るようにわかった。この男は瀕死のエヴァリストを助けたいのだ。
アイザックが裂帛の気合いと共に剣を振り上げ、ブレイズに斬り掛かった。ブレイズはその切っ先を際どいところですと、すぐさまアイザックと体を入れ替えるように移動し、体当たりのような形でアイザックを突き飛ばす。
アイザックがバランスを崩して床に転がった。ブレイズは躍り掛かるようにしてアイザックに止めの一撃を食らわせようとする。
が、身体を反転させたアイザックがブレイズの臍下を蹴り上げた。その重心を捉えた衝撃によってブレイズの身体は宙に舞った。
ブレイズが体勢を立て直そうと身体を捻って着地したその瞬刻、アイザックの剣がブレイズの首を捉えた。ブレイズはその剣を受け流そうとするが、アイザックの気聴の籠もった一撃に圧倒されてしまう。
アイザックの剣はブレイズの頸椎に刺さるように止まった。致命傷である。
血飛沫がブレイズの動脈から飛び散り、辺りに赤い霧が立ちこめる。
アイザックは剣を落としてふらふらと動くブレイズを見た。ブレイズは飛び散る血を押さえようと手を当てているが、吹き出す血は床へ流れ落ちるだけだった。
ブレイズは何かを口に出そうとする様子を見せたが、そのまま目を閉じ、自分の血溜まりの上に崩れ落ちた。
アイザックはその血溜まりの上で足を滑らせつつも、急いでエヴァリストの傍に走った。
エヴァリストもまた、自らの血に溺れていた。
辛うじて息はあるが、口元からも、胸の傷からも血が流れ続けていた。 アイザックはエヴァリストの手を両手で強く握った。
「必ず助ける。心配するな」
「……もういい」
血で溢れた口で、必死に呟くように発された言葉だった。
「馬鹿言うな、こんなのたいしたことじゃねえよ!またやり直せばいいんだ!」
エヴァリストはゆっくりと、少しだけ首を左右に振った。
「らしくないぜ、エヴァ……」
エヴァリストの閉じた目から涙が落ちるのが見えた。アイザックが初めて見るエヴァリストの涙だった。幼い頃からずっと共に過ごしてきたが、彼の涙を見たことは一度も無かった。
どんな時でも冷徹で、そして落ち着いて周りを導く。それが、アイザックの知るエヴァリストという男だった。
「やめろよ……」
アイザックは狼狽していた。もうエヴァリストが助からないことも、エヴァリストの中に覚悟があることもわかっていた。
しかし、わかってはいても、納得できるようなことではなかった。
エヴァリストはもう一度目を開け、アイザックに握られた手を自分の胸に引き付けるように力を込めた。
そして、少し口元を微笑ませたかと思うと、そのまま絶え果てた。
「―了―」
【EP1】3389年 「覚悟」 
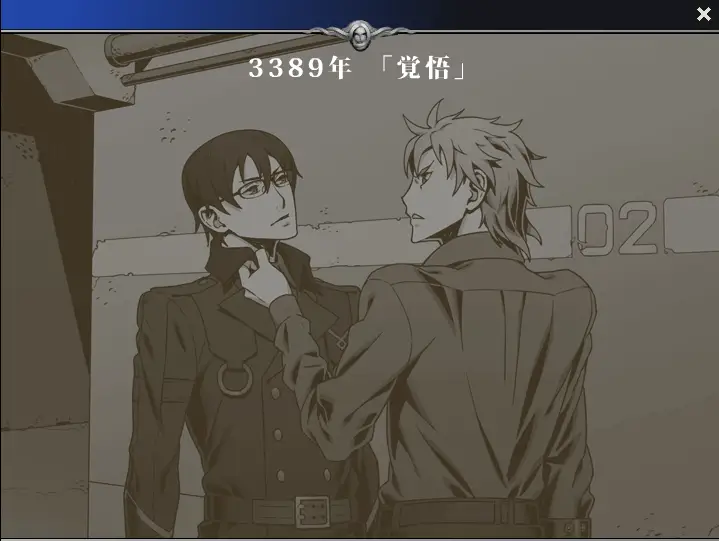
いくつもの死体を見た。脳髄に穴を穿たれた者、四肢を切り刻まれた者、あるいは全身を酸で溶かされた者......。そして、また今日も。
最早何の感慨も湧いてこない。いつしか彼はその光景に慣れ始めていた。
だが、まだ何も終わっていない。エヴァリストは死者達を冷たく見つめながら、そう思っていた。
《渦》の中ではありとあらゆることが起こり得る。既成概念など通用しない。
レジメントに入隊して三年、エヴァリストはそのことを自身の体と頭に徹底的に叩き込んだ。
常に冷静な判断を下せるように。常に思考をクリアに保つために。
エヴァリストは立ち込める硝煙の匂いの中に腐敗臭を感じた。
次の瞬間、背後から足を掴まれる。敵の触手だ。足が滑る。だがエヴァリストは慌てない。
触手の根元には、腐った蠅と蛸が混ざり合ったような化け物 が、大きな口を開けていた。
「なるほど、腐臭の原因はお前か」
そう口ずさむが早いか、周囲の時間が引き延ばされた。そうエヴァリストは体感するが、ケイオシウムの影響により発現した、レジメントの戦士特有の力だった。
その引き延ばされた時間の中、彼は落ち着いて敵を見つめる。
すると、化け物の胸元に鼓動する突起物が確認できた。エヴァリストはホルスターから銃を抜き、その一点に向けて精密な射撃を行う。弾丸の射出と同時に周囲の時間が元に戻っていくのを感じる。
化け物は苦しそうな咆哮をあげながら倒れ込んだ。触手の力が抜けていく。
化け物が絶命したのを確認すると、遠くから自分を呼ぶ声が聞こえた。
「おい、エヴァ!大丈夫か!?」
声のする方へ目を向けると、アイザックがこちらに向かって来る。
「ああ、何の問題もない」
「くそ、かなりの数がやられちまったみたいだな」
「……そのようだな」
見回すと、二人の周囲には多くの死体が転がっていた。先刻まで同じレジメントの隊員だった者達だった。
ここ数ヶ月、渦の数と規模は以前より増大していた。それに伴ってレジメントの戦力が疲弊していることは、誰の目にも明らかだった。レジメント上層部がいよいよ眼 《ジ・アイ》への 侵攻を考えているという噂もあながち間違いではないのかもしれない、エヴァリストはそう考えていた。
「だけどまあ、あらかたの敵は片付いたか」
「ああ、あとは隊長達がコアを持ち帰るのを待つだけだ」
不意にエヴァリストは何かの違和を感じた。腐臭が消えていない。
「アイザック!危ない!」
エヴァリストはアイザックを押しのけた。慣れ、油断、過信――その原因を何と呼ぼうが構わないが、明らかなのはそれが己のミスだということだった。先程の化け物はまだ生きていた。その触手がアイザックへ伸びようとしていたのだ。
「さっきのは擬死という訳……か」
エヴァリストはアイザックを庇う形で、また化け物の触手に捕らえられてしまう。
「エヴァ!」
アイザックがエヴァリストを救い出そうと試みるが、別の触手によって吹き飛ばされてしまう。
エヴァリストは銃口を化け物へと向ける。だが化け物はそれを見越していた。銃を持つ腕に触手が伸びる。同じ過ちは二度と繰り返さないらしい。
「ちっ!」
さらに首にも触手が伸びてくる。化け物はこのままエヴァリストの首を締め上げるつもりのようだった。エヴァリストはこの状況下での最善策を探す。聖騎士の力は連続して使えない。だが、辛うじて左腕の自由は利く。そしてその手の先にあったのは……。
――俺達は何かを得るために生きているんじゃない。終わらせるためにいるんだ――
エヴァリストの脳裏に、いつか耳にした声が去来する。
そう、覚悟ならある。終わらせる覚悟ならいくらでも。
そもそも二年前のあの日、故郷が渦に飲み込まれたあの日、自分は既に死んでいる。何の間違いか生き延びてしまった命など、いつでも、いくらでも捨てられる。エヴァリストの『覚悟』とはそういったものだった。
エヴァリストの手の先には手榴弾があった。
(せめて、お前を道連れにしてやる)
エヴァリストは手榴弾を握りしめる。
「エヴァ!待て!!」
遠くでアイザックの叫ぶ声がする。
これもまた見飽きた光景だなと、エヴァリストは思った。戦場でのありふれた光景だと。
死など別に恐れるものではない。それはどこにでもあるものだ。
エヴァリストは手榴弾のピンを抜こうとした。
その時、地響きのような大きな音がしたかと思うと
触手の化け物が緑色の血を撒き散らしながら真っ二つに裂けた。
「すまん、遅くなった」
エヴァリストの視線の先には、巨大な剣を持ったベルンハルトが立っていた。
「コアは奪取した。もうここに用はない。帰還するぞ」
また生き存えた。
基地に帰還後、エヴァリストは先の《渦》での作戦を反芻していた。
あの危機は自らのミスが届いたことだった。そして、目の前には死があった。その筈だった。
だが、まだ死んでいない。まだ終わっていない。何も......。
と、そこでエヴァリストは急に吐き気に襲われた。洗面所へと駆け込み、殆ど空っぽの腹から胃液を吐き出した。ひとしきり嘔吐し終えて鏡を見ると、そこには見慣れた自分の顔があるだけだった。
「顔色が悪いな」
洗面所を出ると、そこにはベルンハルトが立っていた。
「……隊長」
「今回の作戦ではかなりの死傷者を出してしまった」
「はい」
「アイザックから聞いたお前も危なかったみたいだな」
「あれは……敵の死を疑わなかった自分の判断ミスです」
「お前がミスを犯すとは珍しい」
「以後、気をつけます」
「……」
ベルンハルトはエヴァリストを見つめながら、何か言いたげな顔をしている。
「……何か?」
「お前はまだ若い」
「それは……」
「ああ。俺がかつて先輩から言われた言葉だ」
「ええ。そのお話は以前に聞かせていただきました」
「その言葉を今度は俺が使わせてもらう。エヴァリスト、お前はまだ若い。死に急ぐな」
「何を仰っているのか……」
「わからないか?そんなことはない筈だ」
「……」
二人の間に一瞬の沈黙が拡がった。エヴァリストがその沈黙を破る。
「……隊長は以前、覚悟はあるかと私に問いました。終わらせる覚悟はあるか、と」
「……」
「覚悟ならあります。戦いを終わらせる覚悟が。生き延びることなど望んでいません」
エヴァリストの脳裏には故郷を飲み込んだ《渦》の姿が浮かんでいた。あの《渦》をこの世界から消滅させる。そのことが、そのことだけが、エヴァリストにとって、いや、レジメントに所属する人間にとって全ての筈だ。
「それなのに、今度は若さを理由に死ぬなと仰る。矛盾していませんか?」
「矛盾か。そうだな。確かにお前にはそう思えるのかもしれない。だが、この戦いが世界の全てでないことも確かだ」
「え……?」
「いつかこの戦いは終わる。いや終わらせる。エヴァリスト、お前は《渦》が消えたときにどう生きる?」
「……」
ベルンハルトの問いに答える言葉をエヴァリストは持っていなかった。
「俺が言えるのはここまでだ。どうやらお客さんが来たようだな」
ベルンハルトの視線を手繰ると、松葉杖を突いたアイザックがこちらに向かってきていた。
「アイザック……。足は大丈夫か」
エヴァリストが声を掛けるが、アイザックはそれに応えようとしない。その代わりとでもいうようにエヴァリストの胸倉を掴む。
「アイザック、何を!」
意表を突かれたエヴァリストに、アイザックは怒りの声を上げる。
「エヴァ、てめえ。簡単に死のうとしてんじゃねえぞ!」
「!」
「死んでった奴等はもっと足掻いてただろうが!それにあそこには俺もいた!そんなに易々と自分の命を捨ててどうすんだ!腑抜けてんじゃねえよ!!」
いつの間にか、アイザックの目には涙が溜まっていた。
「……アイザック」
「いいか、今はまだお前の死ぬ時じゃねえ」
ああ、そうだった。三年前の故郷が消えたあの日、エヴァリストの横にはアイザックがいた。あそこには死のみが存在していた訳ではなかった。だとするなら、生きることに拘泥するのも悪くないのかもしれない。少なくともこの戦いの、《渦》の終わりを見届けるまでは。
「悪かった。アイザック、お前の言う通りだ」
そう答えるエヴァリストの目をアイザックは見つめている。
「......わかればいいんだよ」
そう言って、アイザックはエヴァリストを掴んでいた腕の力を緩めた。
「しかし、その怪我でよくそんな啖呵が切れるもんだな」
エヴァリストは小さな笑みを浮かべる。
「うるせえ!」
振り返ると、ベルンハルトはもういなかった。
――《渦》が消えたとき、エヴァリスト、お前はどう生きる?――
その問い掛けだけが、静かにエヴァリストの頭に響いていた。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ