ギュスターヴ
【死因】
【関連キャラ】クロヴィス(親友兼部下)、ユーリカ(部下)、ヴィルヘルム、メリー、カレンベルク(交戦)、コンラッド
3379年 「再動」 
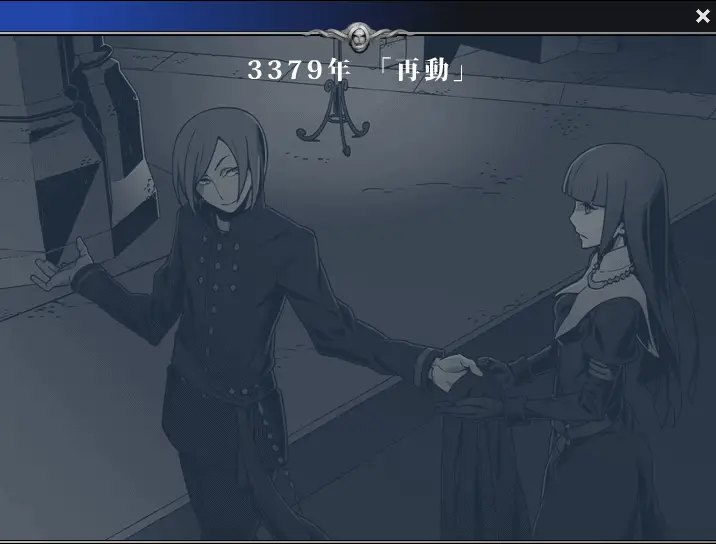
ミリガディアの南西にある小さな町トララ。渦の影響もあり、交易などが途絶えがちになっているこの町に訪れるものは少ない。
日が落ちる少し前、そんな町の聖堂に、小さな馬車がやって来た。
ストームライダーの商人以外は訪れる者が殆ど無いトララでは異例の事態であり、聖堂には町の人々が様子を見に集まっていた。
馬車の到着と共に祭司が聖堂から出てきて、馬車から降り立った人物を出迎えた。
「長旅ご苦労だった。町の皆にも紹介しよう。さ、挨拶しなさい」
「ルーベスより陶冶にやって参りましたシーギスです。トララの皆様、暫くの間宜しくお願い致します」
シーギスと名乗った青年が一礼する。一見十代にも見える彼は僧服を身に纏っており、聖堂の関係者であることが伺える。
陶冶《とうや》とは『命の神』に仕える僧侶に課される課題であり、これを達成することで命の神の御許へ行き、善き世界を作る礎となることができると言われている。
「疲れたろう、シーギス。すぐに部屋に案内しよう。職務の説明は明日の朝にするとしよう」
「ご好意に甘えさせていただきます」
祭司に促されて、シーギスは聖堂へと入っていった。
土着神を信仰する宗教が母体となって建国された国家であるミリガディア王国では、規模の大小に関わらず、必ず一つの集落に一つ国営聖堂が置かれていた。
それぞれの集落の聖堂は、現在の君主である大君《オーバーロード》バステタに任命された祭司が管理していた。
トララの聖堂は王国内に数ある聖堂の中でも殊のほか小さく、祭司のモルガンと僧侶一人がいれば十分に運営が可能であった。しかし少し前に前任の僧侶が生まれた街の祭司となるべく高位陶冶に入ったため、代わりとしてシーギスがトララへと遺わされたのであった。
夜が明けた。シーギスはモルガンの執務室に赴いていた。モルガンは既に祭司服に着替え、朝の礼拝の準備を行っていた。
礼拝の準備を手伝いながら、朝の礼拝に聖堂の扉を開ける時間や掃除の手順など、細かなことの説明を受けた。
「おおそうだ、朝の礼拝が終わり次第、町に買い出しに出掛けてほしい」
「買い出しですか?」
「この町の人々はちょっとばかり人見知りの気があるのだよ。ここで僧侶をする以上は、君にも早く町に溶け込んでもらわねばならん」
要は買い出しという名の挨拶回りといったところなのだろう。
「お心遣い感謝致します。早く皆様に認めていただけるよう、精進します」
朝の礼拝が終わり、簡単に聖堂の掃除を済ませた後、シーギスは町へと出掛けた。モルガンに渡された町の地図と買い出し用品が書かれた紙を持ち、散策がてらに町の中を巡っていた。
「こんな時期に僧侶様?」
「ほら、テッド様が陶冶の旅に出なすったから」
町の人々はシーギスを見ると、ひそひそと会話を始めた。首都から遠く離れたトララは、例え聖職者であっても他所からの人間の流入を嫌っているようだった。
シーギスにも会話の内容は届いていたが、聞こえないふりをすることにした。
「でも、いくらなんでも若すぎじゃ」
「都会の人ってだけで怖いわ」
「所詮は都会の僧侶様じゃ。ここでのお勤めはそう長くならんじゃろう」
新しい世界の情勢が届きにくい場所である。自分達の生活が物や人の流入によって変化することに怯えているのであろう。
ましてや国教のお膝元である首都ルーベスから来た僧侶である。警戒するのも止むを得ない部分があった。
シーギスは買い出しから戻ると、昼食後に聖堂前の掃除を始めた。そして聖堂に訪れる人、行き交う町の人に、丁寧に挨拶を繰り返した。
「これからお出掛けですか? 寒いですから、どうか気をつけて」
「あ、あらそう。ありがとうね」
顔を逸らして足早に通り抜けようとする人に対しても常ににこやかに対応するシーギスの姿は、少しずつ町の人々の警戒を解いていった。
「シーギスさまー、あそんでー!」
「あと少しでお掃除が終わりますから、少し待って下さいね。今日は何をしましょうか?」
シーギスは聖堂に訪れる子供達にも優しかった。祭司に相談事に来た家族の子供を外で遊ばせ、親が十二分に相談できるよう手配したことが始まりだった。
町の周囲に現れる魔物を倒すために若い男達が出払っているため、シーギスは町の子供達にとって身近なお兄さん役となっていた。
「テッド様もとてもいい方だったけど、シーギス様も若いのに素晴らしい僧侶様だわ」
「祭司様の代わりもよくお勤めになられていらっしゃる。ありがてぇこった」
一年もしないうちに、シーギスの評判は当初とは真逆のものになっていた。
職務にも慣れ、町の人々からの信頼も獲得しつつあったある時、その日の勤めを終えたシーギスは祭司に呼び出されていた。
「祭司様、お話とは何でしょうか?」
執務室はランプの明かりで薄暗く照らされていた。
「ああ、来たか。まぁそう身構えるな、ここに座って楽にしなさい」
シーギスは言われるがままに指定された椅子に腰掛けた。対面にはモルガンが座した。
「君は本当によくやってくれている」
「いえ、力不足の私を支えてくださる祭司様や町の方々のお陰です」
「謙遜するな。こう見えても私には人を見る目がある。そこで、君にはもっと高度な陶冶を積んでもらおうと思ってな」
「高度な陶冶、ですか?」
シーギスは鸚鵡返しに疑問を述べた。モルガンは祭司としてシーギスの陶冶を見守る義務がある。だが、シーギスに課されている陶冶はまだ完遂の目処が立っているものではない。
「君は命の神の真の姿を知っているかね?」
「神に形はない。教義にはそうございますが……」
「教義に書かれていることが全てではない。あれは超常的な力を手に入れたある者が作り上げたに過ぎぬ。我々はその者のことを首領と呼んでおるがな」
そう言うと、モルガンは何も使わずに一冊の本を手元に呼び寄せた。ふわりと浮く本は勝手にページを捲り、命の神の肖像が描かれているページを開くと、一瞬で燃え上がった。
「凄い!どうやったらこんな力を?」
「上位の組織から手に入れた力だ。命の神に仕える祭司であれば、皆これと同じ力を秘めている」
「そんなことができるのですか?私のような者でも、素晴らしい力が……」
「無論だ。君が力を手に入れたら、私の片腕になってもらおうと思っている」
「祭司様の片腕に……、祭司様は善き世界のために何をされるおつもりですか?」
「シーギス、君はまだまだ青いな。ともあれ、まずは目障りな首領の息の根を止めることが最初だ。死に掛けているとはいえ、あれが君臨している以上、我々の望みが叶うことはない」
「神に背けと仰るのですか?」
「首領はもはや物言わぬ飾りだ。私が手に入れた力は首領すら凌駕している。奴が何百年と眠りについている間にも、私は研鑽を重ねている」
「……それで、祭司様が偉大な首領となられた後はどうなさるつもりで?」
モルガンはシーギスに煽てられるまま、饒舌に話を続けた。
「私が首領になった暁には、この力の全てを使って地上の王となるのよ。手始めに目障りなグランデレニア帝國を潰して、あの広大な土地を手に入れるのさ。そして帝國の軍事力をもって地上を平定し、理想の世を作り上げる」
モルガンは気分が高揚したのか、立ち上がってシーギスの周りを歩き始めた。
「地上の財宝も全て私のものだ。財がなければ何もできんからな。どうだね、私と共に来れば財も権力も分け与えてやろう」
モルガンはシーギスに問うた。有無を言わせない迫力と、常人から見れば魅力的な褒美を提示していた。
「ふ、ふふ……ははははははは!」
しばしの沈黙を破ったのは、シーギスの笑い声だった。
「何だね!何がそんなにおかしいのかね」
「王だ財だと、何とも矮小な望みよな。世俗の欲ごときで神となろうとは、随分と滑稽な話だ」
シーギスの表情には人のよさそうな好青年の面影はなかった。
「私を愚弄する気か!」
「愚弄などしていない。ただ哀れだと思うただけよ」
モルガンはシーギスに向けて先程の燃え上がる本を放った。シーギスはそれを避けもせず、指先一つで受け止めてみせた。
シーギスの指先に羽を象った紋章が浮かぶ。
「お、お前……!」
「隠匿したとはいえ、吾の気配にすら気付かぬとは。モルガンよ、相当に耄碌したようだな」
「ば、莫迦な、お前はもはや死を待つだけのミイラではなかったのか!!」
モルガンの顔は青を通りこして白くなっており、完全に血の気が引いていた。
シーギスはその様子を見て更に笑うと、紋章が浮かんだ指をモルガンに突きつけた。
「謀反なぞ考えずに吾がお前に呉れてやったもので満ちたりておれば、今までどおり栄華を堪能できたであろうに」
モルガンの身体が宙に浮かぶと、音を立てて捻られ、圧縮されていく。
「や……め……」
「吾は謀反人を許す程の大きな器は持ち合わせておらぬ」
シーギスは一言、絶望の色に染まるモルガンに言い放った。同時にモルガンの身体は捻れた紙屑のように潰れた。
モルガンだったものはそのまま青白い炎に包まれ、跡形もなく消え去った。
夜が明ける。シーギスはモルガンが留守であることと、自身も首都の招集に赴かなければならなくなったことを告げ、トララの町を去った。
もとより留守がちだったモルガンのことを気に留める住民はおらず、揉め事なく町を去ることができた。
「ご帰還、お待ちしておりました。ギュスターヴ様」
首都ルーベス。国の中心である聖ダリウス大聖堂の最深部で、シーギス、いや、ギュスターヴは側近のユーリカとクロヴィスに迎えられた。
「中々に面白いものを見る事ができた。この姿も悪くないな」
「それはようございました」
「あの化け物はどうした?」
「捨て置きました。再生能力が確認できない値に落ち込んでいるため、もはや助かる道理はございません」
抑揚なく答えるユーリカの言葉にやや気に掛かるものを感じたが、ギュスターヴはそれを気のせいと断じた。
「……まあよい。これで謀反人は全て始末した。クロヴィス、配下を集めよ。吾の復活を知らしめるぞ」
「御意。偉大なる首領の仰せのままに」
ギュスターヴの姿が揺らめく。一瞬の間を置いた後、ギュスターヴは眼光鋭い老人の姿となっていた。
「―了―」
2769年 「始動」 

薄暮の時代、世界の改善を使命とするエンジニア達は、遺伝子操作を加えた人間を作り出した。
そして、その中でも特に秀でた三人にレッドグレイヴ、グライバッハ、メルキオールの名を与え、世界の改善と革新を託した。
ギュスターヴは、この三人の中に選ばれなかった数百人の内の一人だ。
彼を含めた数百人の子供達は、レッドグレイヴ達に勝るとも劣らない優れた能力を持っていた。ただ、彼等が持っていた能力はその時の技術者達が求めた能力、世界の頂点に立って人々を導くための能力ではなかった。それだけの話だった。
「お前達の命は世界を改善し、更なる発展を目指すためのみにある。努々忘れるな」
物心ついた頃から『親』に該当する存在に言われた言葉は、到底幼子に聞かせるようなものではなかった。だが、その言葉は刷り込みのようにギュスターヴ達の思考を支配していった。
十数年後、親の言葉に押されるように、遺伝子操作を加えられた子供達は世界を改善する使命のために研究を続けていた。
子供達は各分野で目覚しい活躍をし、世界は少しずつ改善されていった。
ギュスターヴは半年に一度の定例発表のために、統治局へ赴いていた。
この定例発表に集まるのは、ギュスターヴと同じ時に生み出された者達だけだ。この定例発表は、遺伝子操作を加えられた人間にとって非常に重要な意味があった。
ここで発表された研究が統治局に実用性を認められると、実用化に向けた研究を始めることができる。膨大な予算が組まれ、最適な環境と優秀な人員を取り揃えて更なる研究を進めることが可能となるのだ。
「やあ、ギュスターヴ。変わりはなさそうだな」
先に会場に着いていたテクノクラートから声を掛けられた。
「やあ、グラント、ゲイル。二人とも変わりなさそうだな」
「トリートメントを受けたばかりだからね。元気にも見えるさ」
グラント、ゲイルの二人とは、研究分野が近いためか、よく情報交換を行っている。やり取りの全ては電子メールや音声通信で行っているので、実際に会うのはそれこそ前回の定例発表以来だ。
「自明だったな。それよりも、前回提供した情報は無駄になっていないだろうな?」
ギュスターヴはグラントに向き直る。
「お陰様で、何とか発表に間に合ったよ」
「二人とも、続きは会場の中でやろう。早くしないと、話すどころじゃなくなってしまうよ」
提供した情報について話し込みそうになったところを、ゲイルに促される。
三人は会場に入り、隣り合った席に座った。
ギュスターヴはそこで、遺伝子治療の成功率を更に高める画期的な研究を発表した。
グラントもスムーズに発表を終えて席へと戻ってきた。入れ替わりにゲイルが席を立つ。
いくつかの発表の後、ゲイルの研究発表が始まった。
ゲイルは人の神経細胞を通る電気信号を変換し、電子ネットワークと相互に繋ぐ研究を発表した。これの実用化が決まれば、人類は更に豊かな生活を送ることができる。
極めて革新的な研究内容であった。
出席者全員の発表が終わった後、順に統治局の審査が下された。
ギュスターヴとグラントの研究は実用化までは認められなかったものの、研究の更なる発展のための予算が組まれることが決定した。
成果としては上々だ。
「あとはゲイルだけか」
「今回の発表は凄かったな。実用化が決定すれば、人類は更に発展する」
「僕も君達に負けていられないからね。少し冒険をしてみたのさ」
確かに、ここ数年のゲイルの評価は芳しくなかった。
それについて相談を受けたギュスターヴは、ゲイルの性質が慎重なために思い切った研究ができていないことが原因であると指摘していた。その指摘を受けて行動を起こした結果が今回の研究であるとしたら、その時の助言は良い方向に働いたということだろう。
それを思うと、ギュスターヴは嬉しくなった。
そして、ゲイルの研究についての審査結果が告げられる。
「ゲイル技官の研究について、時期尚早という結論が出た」
先程までと打って変わって、重い沈黙が三人を襲う。反対に、周囲は困惑したようにざわついていた。
ギュスターヴがこの研究を革新的であると判断したように、他の者も同じような思いだったのだろう。
「静粛に。この研究は確かに革新的ではあるが、それを一般市民が安全に扱えるようになるためには、今しばらくの時間が必要との判断である
統治局の言葉を代弁するエンジニアは言葉を続けた。
「この研究は、現在の文明レベルが数段上がった後に再評価を受けることになるだろう。為に、再評価の期限は不明」
会場は更にざわついた。だが、エンジニアはそのざわつきを気にも留めない。
「よって、ゲイル技官の発表は無効。三ヶ月後に別の研究の発表を命じる、以上だ」
全ての審査が終わった後、三人は足早に会場を後にした。誰も互いの顔を見ようとはしなかった。
ギュスターヴが声を掛けるべきか逡巡していたところ、ゲイルが二人の前に進み出て振り返った。
「はは。仕方がないよ。統治局の御眼鏡に適わなかった、ただそれだけさ」
努めて明るく振舞おうとするゲイルの声色は、どう聞いても精彩を欠いていた。
「さあ、帰ろう。二人とも次の研究課題が待っているんだろう?」
ゲイルは僅かに微笑むと、ギュスターヴとグラントの背を軽く押すのだった。
定例発表が終わってから数日のことだった。
ギュスターヴの研究所兼自宅に、一通の音声付き電子メールが届いた。
差出人はゲイルだった。
定例発表の件もあり、薄ら寒い嫌な感覚があった。
気のせいであることを願いながら、ギュスターヴはすぐにメールを開く。自動的に音声が再生された。
『私は、私という存在の意義を見出すことに疲れた。この電子メールを君達が見る頃には、既に私は自死しているだろう』
メッセージはまさに遺言だった。淡々と語られるメッセージ に、先日会った時のような柔らかい口調は無い。
言葉の内容から、この電子メールはギュスターヴの他にも何人かに送られているように受け取れた。
『私は、私が思っていたより弱い人間だったようだ。もう私には研究を続ける気概は無い』
音声に重なるように、ギュスターヴの通信機がけたたましく着信を告げた。
「おい、ギュスターヴ! ゲイルから――」
通信機越しに、グラントの焦った声が聞こえてくる。
「いま聞いている……」
青ざめるギュスターヴ。グラントにもメールが届いているということは、この電子メールはあの定例発表でゲイルを気遣った者全員に送られている可能性が高い。
『このような弱い私に手を差し伸べてくれたことに、唯々感謝するしかない。ありがとう』
ゲイルの抑揚のない声が耳に吸い込まれていく。
『だが、君達は私とは違う。私のようには決してならないでくれ。それが私の最後の願いだ』
音声はここで終わった。どこか悟ったかのように、最後まで淡々としていた。
ゲイルの死は、ギュスターヴ達が電子メールを受け取った数日後に周知された。
葬儀はひっそりと行われた。バックアップ用のクローンがあったが、センソレコードを移すことはせず、クローンも全て処分することになった。
このまま記憶を引き継がずに死なせて欲しいという、故人の意向だった。
葬儀に訪れた者はひどく少なかった。遺言を送られたギュスターヴとグラント、そしてゲイルが所属していた研究所のエンジニアが三人程。ギュスターヴやグラント以外の同期達は、ゲイルの死をどうでもいいものと判断したようだ。
葬儀が終わってすぐ、ゲイルが行っていた研究を引き継ぐテクノクラートが発表された。統治局と連名で提出された声明文には、統治局と共に人類の発展を目指すといった旨の文章が綴られている。
それは、統治局がゲイルの死を末梢的に扱っていることの証拠のように思えた。
「私は、統治局が何を考え、何をもって世界を改善しようとしているのか、わからなくなったよ」
「奇遇だな。私も同じようなことを考えていた」
ゲイルの墓前で呟いたギュスターヴの言葉に、グラントは静かに領いた。
「統治局の行うことは、本当に世界の改善に繋がるのか?」
ギュスターヴは疑問を呈する。
「わからない。だが、ゲイルはこんな風に自死するために生まれてきた訳ではない筈だ」
確かに、ゲイルは大きな評価を受けたテクノクラートではなかった。だが、誰よりも熱心に世界の改善を進めようと努力していた。
「ああ、その通りだ。だが、どれほど革新的な技術を発明しても、統治局の意向に沿わなければ排除されてしまう。こんな世界は間違っている」
「お前、何をする気だ?」
ゲイルの墓から立ち去ろうとするギュスターヴを、グラントは怪訝な目で見やった。
「黄金時代の研究資料を探す。我々を生み出すに至った技術者達の思惑を知り、本当の意味での世界の改善とは何かを見出す」
ギュスターヴの強い言葉に、グラントは眉を顰めた。
「私達全員の出生に砂を掛ける行為になりかねんぞ」
「このままレッドグレイヴや統治局の傀儡として生きる気は、もう私には無い。統治局の支配から脱する方法を探し出すんだ……」
「ギュスターヴ……。いや、何も言うまい。君を止められる言葉を、今の私は持っていないよ」
それきり黙ってしまったグラントを一瞥すると、ギュスターヴは今度こそゲイルの墓前から立ち去るのだった。
「―了―」
2839年 「国家」 
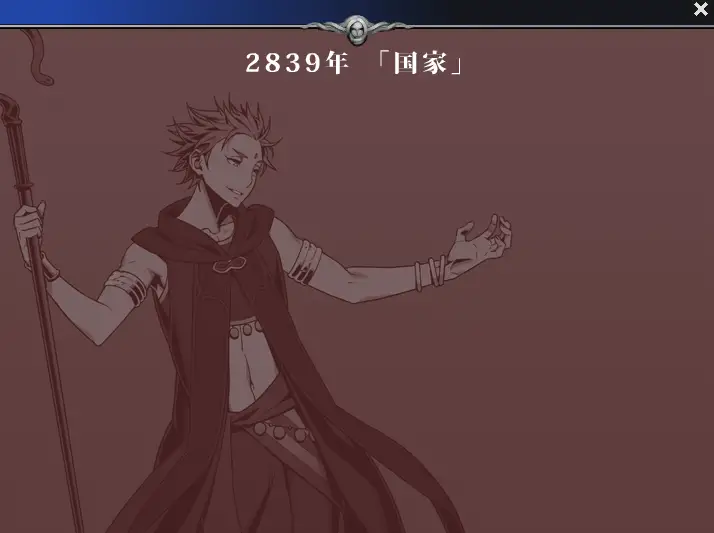
二八三七年、ローゼンブルグ第十二階層スバース地区で起きたオートマタの反乱。
それを境に、世界は混迷の只中へ突き落とされた。
あらゆる災害や疫病をコントロールしてきた筈の統治局は、この状況を収拾できずにいた。
もはや日常と化したオートマタ暴動のニュースを聞きながら、 ギュスターヴは盛大に溜息を吐いた。
「やはりこうなったか」
「君の予測が正しかったことが証明されたね。過去に君の論文を妄想と打ち棄てた統治局の面々は、どんな顔をしているやら」
ギュスターヴの秘書官を務めているクロヴィスが、苦笑交じりに答えた。
クロヴィスは優秀な国家保安局員であったが、統治局が行っていた市民コントロールの真実を知ってからは、ギュスターヴの同志となっていた。
同志となってから既に数十年が経っているが、ギュスターヴの専属秘書官という立場から特別に定期トリートメントを受けることができたため、未だ三十代中ごろといった容姿を保っている。
「そんなこと、統治局はとうに忘れているだろう。一度無意味と判断すれば、それは存在しなかったものと看做すのが奴らだよ」
オートマタの反乱が起きる以前に、ギュスターヴは一本の論文を発表していた。
ギュスターヴはゲイルの死後、黄金時代の技術者達が残した研究資料を解析して現在の世界の状況と照らし合わせていった。
そして照合を進める内に、ある一つの恐ろしい予測を導き出したのである。
――レッドグレイヴによる、完全にコントロールされた治世。
――グライバッハによって作り出される、人に付き従うオートマタ。
――メルキオールが確立した、ケイオシウムエネルギーの活用。
確かにこれらは人類に繁栄をもたらした。だが、それは同時に人類が思考を放棄することに繋がり、最終的には停滞、ないし衰退を迎えてしまうのではないか。
そういう予測を導き出したのである。
予測を決定的な確信に変えたのは、グライバッハが二八一四年、自死の数ヶ月前に発表した論文だった。
その論文には、人間と同じく思考能力を有し、自発的に創造することが可能なオートマタに関する研究内容が書かれていた。
この論文を読んだギュスターヴは、人類の衰退に関する危機感を加速させた。
レッドグレイヴによって真に思考することを委棄した人類が、自らの意志で考えて動くようになったオートマタに反旗を翻されたと仮定した場合、的確な対処はほぼ不可能であろう。
であれば、このままグライバッハの論文と研究を使用して自意識のあるオートマタを製造するのは危険ではないか。
ギュスターヴが発表した論文はこれらの仮説について論じていた。だが、この論文は統治局によって危険な妄言であると断言され、以降、ギュスターヴは異端者であると見なされたのであった。
「こうなってしまうと、他国から戦争を仕掛けられている状況と変わらんな」
モニターの向こうでは、人間とオートマタが激しく争っている様子が映されている。
「オートマタが人間に等しい、とでも言いたげだね」
「自ら考えることが可能であれば、もはやそれは一つの生物と言っても過言ではない。相違点など、身体を構成するものが有機物か無機物かというだけだ」
「特に自動人形は人を模して姿形が作られているからね。であれば、ある意味人間と何ら変わりはない。むしろ頑強な機械である分、人より優れている部分もあるか……」
「こうなってしまった以上、それは人類にとって脅威でしかないな」
暴動の様子を映していたモニターの電源を落とすと、ギュスターヴは立ち上がる。
「さて、我々は我々が為すべきことをしよう」
ギュスターヴは自らが発表した論文が間違っているとは考えていなかった。
自らの考えを統治局が無視するのであれば、自らの手によって来るべき時に備え、万全の準備をしておくことが大事だと考えていた。
新たな拠点を南方の片田舎であるルーベス地区へと定め、広い土地を一つ買い取って、そこに最新設備を惜しまず投入した研究施設を作り上げた。
邸宅兼研究所の完成後、すぐにギュスターヴは今の邸宅を完全に解体し、慣れ親しんだ中央から旅立った。
そうしてルーベスに生活や主要研究の拠点を移してから数日後、同期のグラントが突如来訪した。
ゲイルの死後、グラントとは定例会で会った際に多少の会話を交わすものの、以前ほどは連絡を取り合っていなかった。
疎遠となっていた同期の来訪に少々驚くも、元は親交の深かった者である。ギュスターヴは快くグラントを招き入れた。
「ギュスターヴ、折り入って相談がある」
グラントは神妙な面持ちでギュスターヴと相対した。
「例の論文を改めて読ませてもらった。今の状況は君の予測に合致していると言わざるを得ない。統治局はもう限界だ」
そう言いながらグラントはギュスターヴに頭を垂れると、すぐに顔を上げる。
「私も統治局とは違う視点で、君と共に世界の改善を模索したい」
グラントはギュスターヴの目を見る。グラントの真摯な眼差しに嘘偽りはない。ギュスターヴはそう考えた。
「ああ、もちろん構わない。むしろ、同志は多ければ多いほどいい」
「ありがとう……」
新たな同志を迎え入れ、ギュスターヴは少しずつ統治局からの脱却を目指していった。
しかし、ギュスターヴ達の予測を大きく覆す事態が起きてしまった。
メルキオールの開発したオートマタ鎮圧兵器が、ケイオシウムコアを暴走させたのである。
統治局の発表によれば、抵抗するオートマタによって鎮圧兵器が攻撃されたことによって引き起こされたものであるという。
更に、統治局は空中都市『パンデモニウム』に限られた人類を移住させ、《渦》の影響が及ばない空中へ逃避する計画を発動させた。
「世界の改善を謳う統治者が、自ら世界を捨てるとはな……」
統治局から届いた通達を見て、ギュスターヴは何度目かもわからない大きな溜息を吐いた。
通達された文面では『人類という種を残すため』ということであったが、結局は地上に残された大多数の人間を見捨てるということに他ならない。
「どうする?」
「決まっている。私は地上に残り、統治局とは違った方法で世界を改善してみせるまでだ」
「聞くまでもなかったな。私も同意見だ」
統治局の目がほぼ届かなくなった地上で、ギュスターヴは水面下で進めていた計画の大々的な開始を決定した。
しかし計画を実行するためには、何よりも自らの思想と研究を体現できる時間が必要であった。
遺伝子改良とトリートメント技術により、ギュスターヴは常人を遥かに超える若さと寿命を持ち得ている。バックアップとしてクローンも用意してあった。
だが、これらは不慮の死が極めて稀であった時代でのみ機能するものだ。安全という言葉が無意味になってしまったこの地上では、何が起きてもおかしくはない。
そういった不慮の事態を避けるため、ヒトの身体を根本的に改造、改良し、寿命に怯えることのないものを作り出す必要があった。
「グラント、君の力を借りたい」
「君のやろうとしていることは、人間を人間でなくする研究だ。それでもいいのか?」
「だからこそだ。この身では何もかもが足りない。人間であることで世界を改善できないのなら、私は人間でなくならねばならない」
ギュスターヴとグラントは、遺伝子と身体を改造する研究に着手した。
まずはテロメアの長さや細胞の老化を検査し、寿命を予測して数値化する技術を作り上げた。
次に寿命の短いマウスを実験体として、その寿命を十年単位で延ばすことに成功した。
その後も幾度かの動物実験を経て、ギュスターヴは自らを最初の改造体とすることとした。
寿命を司る細胞に手を加え、トリートメント技術を改良し、理論上は大幅に寿命を伸ばすことに成功した。だが五十年、百年と時間が経過することによって顕在化するかもしれない問題までは、仮定と予測に基づく他なかった。
改造体の作成に成功した後も実験を重ねたギュスターヴは、同様の処置をグラントやクロヴィスにも施した。
何とか時間の問題に光明が見えたが、それでも問題は山積していた。
障壁によって守られてこそいるが、《渦》が留まるところを知らぬ厄災であることに変わりはない。
ギュスターヴ達の頭脳をもってしても、得られた結論は「根本的解決を図るには何百年もの時間を必要とする」というものでしかなかった。
「……酷い有様だな」
淡い色彩で渦巻くものが、大きなモニターの画面を覆い尽くしている。
障壁の外の様子を観察するために飛ばした無人調査機から送られてきた映像だった。
ルーベスは障壁により安全が保たれてはいたが、その障壁の有効範囲は一つの都市を覆う程度の大きさしかない。
計画を推進していくには、人員も、土地も、何もかもが足りない。
土地の拡大に関しては資産の投入で解決できるが、拡大した土地を《渦》の脅威から守る術がない。工業都市インペローダから障壁生産技術を買い取ってはいるが、工業施設の乏しいルーベスだけで障壁を量産するには限界があった。
どうすべきか悩みながら、ギュスターヴは新しく製造された障壁の使い道を相談するために、ルーベス地区管理局を訪れた。
ルーベス地区管理局の局長に、障壁の生産を進めつつ、更に多くの人々を《渦》の脅威から逃すにはどうしたらいいかと訪ねてみた。地域を治めるための知識に明るい局長ならば、何か打開策に繋がるアイディアを持っているのではないかと考えたのだ。
この局長は黄金時代以前から存在する土着の宗教を代々信仰しているという一風変わった人物であったが、この地区に自費で障壁を導入したギュスターヴに対しても、強い信仰を捧げている。
「この地区を国家として樹立させませんか?」
「国、とな?」
「はい。以前、他地区の局長との通信を行った際、北方のローデ地区が独自の国家運営を行っているという話を聞きまして」
局長はギュスターヴが一つ領いたのを見て、話を続ける。
「この地区も国家として名乗りを上げ、周辺地区に合併を呼び掛けるのです。それによって連携できる地区が増えれば産業の補完に繋がるでしょうし、《渦》による難民の救済も多少は容易となります」
「なるほどな。私は国を治める知識には疎い。この地区を国家として樹立させた後も、君が引き続き治めてくれると助かる」
「わかりました。不肖な身ではありますが、懸命に努めさせていただきます」
「そんなに畏まらないでほしい。私達は同志なのだ」
「ありがとうございます、ギュスターヴ様。やはり貴方こそが世界を救うお方なのです」
局長が信仰する命の神に仕えた従者の名前から、国号を「ミリガディア」と定めた。
かくして、ここに『ミリガディア国』が樹立されたのであった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ