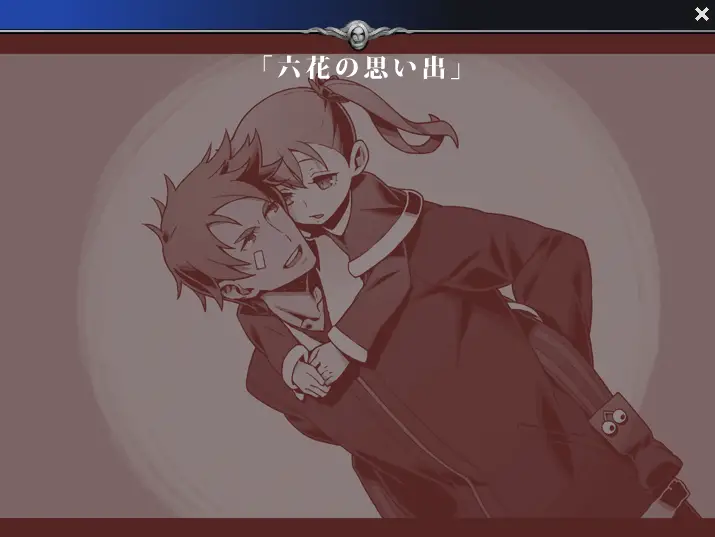| 「六花の思い出」 |
「なあ、本当にこのまま真っ直ぐで大丈夫なのか?」
ルディアは背中におぶさっている導き手に尋ねた。
彼女達の目の前には見渡す限りの雪原が広がっている。霞掛かった視線の先でさえも、同じような景色が続いている。
導き手の歩むままに進んでいたところ、この豪雪地帯に出くわしてしまった。
それでも歩みを止めない導き手に従っている内に雪深くなっていき、とうとう導き手が雪に埋まってしまう事態に陥ったため、今はルディアが背負っている。
ルディアの問いに導き手が答えることはない。
「……やっぱり黙ったままか。どうしたもんかね」
白い溜息を吐き出しながら、延々と続く雪原をひたすら歩く。
「導き手さんから何かありまして?このまま進んで遭難なんてことになったら、酒落ではすみませんわよ」
ルディアの前方で、ステッキで描いたスコップで雪を掻き分けていたメリーが振り返る。
「いや、さっぱりだ」
「仕方ありませんわね。何か反応があったら教えて下さいまし」
「ああ、わかった」
ザクザクと雪を踏む音、背中に背負った子供の人形。
そういえば昔、こんな風に人に背負ってもらったなとルディアは思ったーー。
両親の『おしごと』の都合で訪れたレジメントの施設。いつも 以上に長引く『おしごと』の話に退屈となったルディアは、こっそりと部屋を抜け出して施設の中を歩いてみることにした。
最初こそ探検気分、わくわく気分だったが、どこまで歩いても変わらない通路を歩いていく内に、その思いは恐怖へと変わっていった。
半べそをかきながら通路をうろうろしていたところを、トレー ニング帰りらしいレジメントの騎士達に見つけられた。
「お嬢ちゃん、どこから来たんだい?」
ルディアの存在に最初に気付いた茶髪の男が、屈んでルディアの目線を合わせ、存外に優しい声で問い掛けてきた。
「え、っと……うええ……」
道に迷った。その一言を言えばす済んだ筈なのに、恐怖に固まったルディアの日からは泣きべそをかく寸前の、言葉にならない声しか出てこなかった。
「わからないか。どうしたものか……」
困り顔で自分を見ている男の人。周囲にいる大人達も同様に困った顔をして、お互いの顔を見合っていた。
「中隊長に問い合わせてみるか。何か知っているかもしれない」
誰かがそう言いながら、どこかに連絡をしていた。周囲が騒がしくなる。
どうなっちゃうんだろうと思っていると、先程話し掛けてきた茶髪の男に背負われた。
「お嬢ちゃんのお父さんとお母さんが見つかったってさ。連れて行ってやるよ」
「ちゃんと送り届けてやるんだぞ、リーズ」
「わかってるよ。さ、行くぞ」
男達に茶々を入れられながら、リーズと呼ばれた男の人に背負われて、どこかに向かっていく。
「ちょっと寒いけど、我慢してくれよ」
リーズが扉を開けると、雪が積もった広場に出た。微かに雪が降っており、それが広場に積もっていくのが見えた。
「どうして寒いのにお外にでたの?」
「ここを突っ切っれば、すぐに元いた部屋に着くんだ。お父さんたちも心配してるだろうし、早いほうがいいだろう?」
「……心配、してるのかな?」
「そりゃそうだ。こんな小さい子がいなくなったんだからな」
「いつもおしごとばっかりで、わたしがいなくなっても気にしないよ」
「いいや。子供を心配しない親はいないと思うぞ」
「そうなのかな?わかんないや……」
短い会話を交わしていると、程なくして最初にいた部屋に戻ることができた。
『おしごと』ばかりでめったに取り乱したり声を荒げたことのない両親だったが、この時ばかりはかなり怒られた。
リーズという男性が言ったことは確かに正しかった。だけど、それ以降は迷子になるような出来事も、怒られる程の悪さをすることもないまま、両親とは死別してしまった。
そういえば、あの時のお兄さん。――リーズのことだ――とは、 その後もどこかで会っている。一体どこだったかは思い出せないが、何かしらの言葉を交わしたのは記憶に新しい。
妙なことに、お兄さんの容姿は自分が迷子になった時と殆ど変わっていなかったような……。
モザイクが掛かったように果てしなく怪しい記憶に混乱していると、ルディアは突然頭頂部に痛みを感じた。
「いぎっ!いた!痛いって!ちょ、こら、髪を引っ張るな!」
進路を変えたいらしい導き手が、ルディアのポニーテールを見た目に似つかわしくない力で引っ張りながら、右斜めの方向を見つめていた。
「あら、駄目ですよ、導き手さん。お姉さんが痛がっていますわ。こちらのほうに進めばよろしいのですね?」
ルディアの声に気付いたメリーが、導き手の手にそっと触る。
導き手は自分の意思が通ったのがわかったようで、髪を引っ張る手を緩めた。
メリーは導き手の向く方角にスコップを向けて、再び雪を掻き分けながら道を作る。もう髪を引っ張ってこないということは、この方向でいいのだろう。
「みたいだな。さあ、先に進もうか」
何を考えたところで、思い出せないものはどうにもならない。
ぼんやりとした違和感を頭の隅に追い遣って、メリーの後を付いていく。進路を変えても先の見えない雪原が続く。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ