クレーニヒ
【正体】マルグリッドの忘れ形見。自らの出自を知らぬまま出世した父イオースィフの保護下で何不自由なく育つが、悪夢が続いた後に幻獣に取り憑かれる。暴走する幻獣の力は父を殺害し、やがては制御不能に陥る。
【死因】力の暴走による射殺処分。
【関連キャラ】マルグリッド(母親)
3394年 秋 「夢幻」 
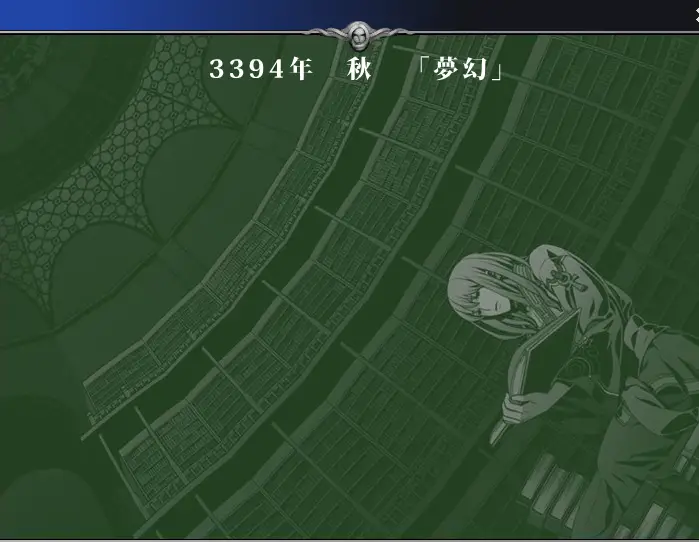
静寂が支配する空間に、ページを繰る音だけが響いていた。
かすかに歌う妖精の音声にもにたそれはしかし、わずかな焦りと苛立ちの感情を内包していた。
「これも違う。わからない……どれもあの"夢"とは違う……」
肩にまでかかる栗色の髪を揺らして、クレーニヒは誰にともなく呟いた。
手にした本を周囲に積まれた本の山の上に載せ、別の山から新たな本を手に取る。
再びぱらりぱらりと不規則な音だけが図書館にこだまする。
本来、工学師《エンジニア》の中でも上級職と言われる上級工学師《テクノクラート》しか立ち入ることのできない専門区画。
その一画に設置されたこの図書館には、自動機械《オートマタ》関連の技術書だけでなく、黄金時代と呼ばれた旧時代の遺物すら管理されていた。ある意味において、導都パンデモニウムの知の源と言ってもいい。
ひざの上でページをめくっていた本をさきほどと同じ山の上に載せ、クレーニヒは再び新たな本を手にする。
「精神病関連の書籍か」
あまり気は進まなかったが、何かのヒントが得られるかもしれないと、さきほど書棚から抜き出してきた本だった。
自らの身に起きていることを調べる者が、精神を病んでいたという結論に辿り着いたとしたら、それはまるで喜劇のようじゃないか。自嘲気味に口の端をゆがめる。
いっそ喜劇ならばどれほどよかったか。
目を凝らせばいつでも見ることのできる幻像。
この世のものとは思えない様々な生物や自然、空や大地。世界の在り様。
それは物心ついたときからクレーニヒのすぐ身近にあった。
最初は"夢"だった。
いや、"夢"だと思っていたと言うべきか。
ベッドに入って目を閉じると、いつもその世界はクレーニヒの眼前に現れた。
うねりをともなって押し寄せる白と黒。
その謎の液体――液体かどうかすらも怪しいが――の波は、なにかを打ち寄せては消え、引き寄せては現れた。
目を凝らすとそれは人だった。動かない人の身体が、光る海の中を漂っていた。
水平線に目をやると、巨大な背びれを持った生物が黒白の海面から姿を現した。
海中にその全容を隠したまま、生物はこちらに近づいてくる……。
そこでクレーニヒは目を覚ました。
冷たい汗が額を濡らし、幾筋かの髪の毛が不快感とともにわだかまっていた。
早鐘を打つ心臓が血流の勢いを増している。
"夢"と呼ばれるものはみなこういうものだと思っていた。
しかし成長するにつれて、人の言う"夢"と自分の"夢"に違和感を感じるようになった。
最初はわずかな差異でしかなかったその違和感は、次第に大きくなり、十代も半ばになった今では、もはや確信と言えた。
自分の見る"夢"は、人の見る"夢"などではありえない。
クレーニヒの体験する"夢"では、見える風景は常に異なっていた。
必ず違うものとは言えないにしても、少なくとも同じ"夢"を見たことはなかった。
その"夢"に共通するのは、それらが実在するはずのない光景だということだ。
この世のものとは思えない景色、生態系からかけ離れた生き物たち。
ありえない色と音とにおいと味のする世界。
そしてなによりもイヤだったのは、その世界にはクレーニヒ自身がいないことだった。"夢"は必ず傍観者としての主体性のない視点で映し出される。
手を触れることさえできそうな現実感がありながら、観察者としての自分は触れるべき手を持たない。
生物のにおいや空気の味さえわかり、ときには感触さえもが知覚できるにも関わらず、その風景に干渉することができなかった。
まるでクレーニヒ自身が世界に溶け込んでしまったかのようだった。
目を閉じれば押し寄せてくる"夢"。いつしか、クレーニヒは夜を畏れるようになっていた。
だが、その"夢"は、夜だけに留まってはいなかった。
次第にクレーニヒの日常をも侵食し始めていったのだ。
ふと部屋の暗がりに見える虹色の大地。目を瞑った拍子に広がる仄昏い海面。
建物の壁に、風になびく紫色の奇妙な植物の草原が映し出されることさえあった。
それらの幻覚じみた光景は、最初こそ無視することで消し去ることができた。
だが、その出現頻度は増大していき、クレーニヒ自身が自我を意識して集中せねば、いつまでも在り続けるようになっていった。
仕事で家を空けがちな父親の書斎で、上級工学師《テクノクラート》のパスキーを見つけたのはそんなときだった。
上級工学師《テクノクラート》しか入れない図書館には、旧時代や薄暮の時代《トワイライト・エイジ》における科学技術や医学、歴史、そして禁忌とされる知識が埋蔵されているという話を聞いたことがあった。
「あの図書館へ行けば、この幻覚の正体がつかめるかもしれない」
わずかな望みを抱き、クレーニヒは上級工学師《テクノクラート》専門区画へと忍び込むことにした。
上級工学師《テクノクラート》の専用区画とはいえ、図書館は研究施設のある場所とはかけ離れた位置にあった。
おかげでそのセキュリティは甘く、ほかの区画のように警備用に自動機械《オートマタ》が動き回っているようなこともなかった。そもそも本で知識を得ようとする上級工学師《テクノクラート》が少ないのか、図書館の内部にも人の気配はない。
長い間使われておらず、うっすらと埃が堆積している場所すらあった。
どれくらい時間が経っただろう。
難解な文章が羅列された専門書からふと目を上げると、唐突に、クレーニヒは奇妙な感覚に襲われた。
"夢"を見るときに似ているが、それとは少し違う。
意識ははっきりしているし、なにより、あの"夢"の世界は見えない。
何かに導かれるように視線を動かすと、金属で作られた書棚らしきものに目が留まった。
その書棚にはスライド式の扉がついており、ほかのものとは明らかに違っている。
読みかけの本を足元に落とし、クレーニヒはその書棚に近づいていった。
「開かない?ロックされているのか」
力を込めても微動だにしない扉に阻まれ、その中を見ることはできなかった。
――開けてみたい。
無意識にそう思った途端、さきほどから続いていた奇妙な感覚が身体の奥から一気にあふれ出してきた。
その奔流に血液が沸騰したような錯覚すら覚える。いや、それは錯覚なのだろうか。
痛み、嫌悪感、吐き気、快感……あらゆる感覚が一体になり、クレーニヒの身体を駆け巡った。
「……っ!?」
ぐらぐらと世界が揺れ、一瞬あの"夢"の中にいるかのような恐怖が背筋を這い昇る。
しかしクレーニヒが意識を保てたのは、皮肉にもその恐怖のおかげでもあった。
必死に意識を集中し、自分のいる場所をイメージする。
「ここにいる!……ボクはここにいるんだ!」
倒れそうになる身体を書棚に預けて荒く呼吸を繰り返す。
感覚の奔流は始まったときと同様、唐突に消失していた。
「なんだったんだ、今のは」
傾いた身体を起こそうと書棚にかけていた手に力を入れると、音も立てずに書棚のスライド扉が開いた。
おかしい。さっき触れたときは確実にロックされていたはずだった。
しかもこの扉は電子ロックではなく、前時代的な鍵による施錠式だったはずだ。
だが、そんな疑問よりも書棚の中身のほうが興味を引いた。
「研究資料……?」
どうやら古い実験のレポートのようだった。
ケースに収められたそれを手に取り、中を見ようとしたクレーニヒの視界に、あるはずのないもの――いや、いるはずのないモノが映った。
それが、クレーニヒと幻獣との最初の邂逅だった。
「―了―」
3394年 「劇場にて」 
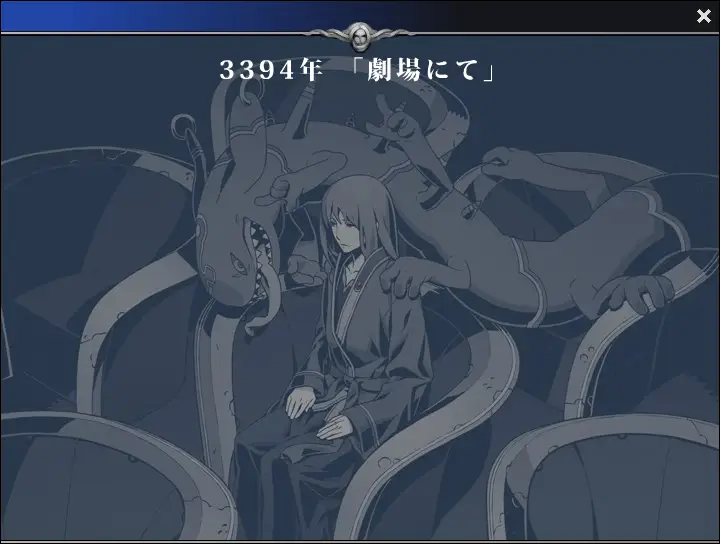
「くそっ!」
クレーニヒは部屋のゴミ箱を力任せに蹴り飛ばした。
ゴミ箱は中のものを派手にぶちまけながら、ガランガランと盛大な音を立てて転がる。
今までの自分ではとても考えられない行動だった。
少しは怒りが収まるかと思ったのだが、効果はなかった。それどころか、床に散乱した破れた包装紙がクレーニヒの苛立ちを余計に増加させた。昨夜久々に帰宅した父親が土産として持ってきた本を包んでいたものだ。
自分の心と世界の変調に付いていけなくなっていた。何もかもがクレーニヒの心にさざ波を立てた。
微かな動作音と共にどこからともなく現れた掃除用自動機械が、散らかったゴミを片付けてゆく。クレーニヒの不始末を黙々と片付けるの姿に、また衝動が抑えられなくなった。今度は反対側の壁にゴミ箱を蹴り飛ばす。再び中のゴミが放り出されるが、自動機械は文句も言わずに掃除を再開する。
その様子を見届けぬまま、クレーニヒは部屋を飛び出した。
「導師イオースィフ、出発の準備ができました」
士官が折り目正しく敬礼しながら言った。
大きな荷物を持った細身の紳士がそれに応じる。髪に白いものが僅かに混じってはいるが、それほどの年齢ではない。着込んだコートの裾が強風にバタバタとはためいていた。
導都パンデモニウムが地上からどれだけの高度を維持しているかは判らないが、いかに優秀な障壁器といえども風を防ぐことはできない。いや、優秀だからこそ風を防がないと言うべきか。パンデモニウム外縁部のフライトデッキは、特に外気の影響を受けやすい位置にあった。
「しかしパンデモニウムに戻ったばかりなのに、もうローゼンブルグへ再招集とは大変ですね」
「ああ、建造中のガレオンの不具合でな。まったく手のかかる機械だよ」
「しかしあの浮遊戦艦が完成すれば、下の紛争もずいぶん様子が変わるんでしょうね」
「もちろん激変するだろうね。これで下界の騒ぎもコントロールしやすくなるだろう」
飛行艇に乗り込み出発最終チェックをしている士官と会話を続けた。
「やはり下の世界は面倒ですか?」
「面倒とは思わないが、仕事なのでね。まあ環境はこことは違う。住んで心地の良いものではないよ」
「私は下の世界で暮らしたことが無いのですよ。憧れます」
「埃っぽく、汚い世界だよ。私はここのほうがいい」
士官が操縦室との無線で会話を始めると、窓を見ながらイオースィフは、息子のクレーニヒとの昨夜の会話を思い出していた。奇妙な幻覚に悩まされていると打ち明けてきたのは昨晩のことだった。母親のこともあり不安だったが、医師の元へ行ってみるように薦めたところで、ローゼンブルグからの緊急連絡が届き、結局話はうやむやのままになってしまった。朝も顔を合わせずに出てきてしまったのだ。もう少し詳しく話を聞けばよかったのだろうが、と思い返していた。
士官は無線での会話を終わらせて、イオースィフに声を掛けた。
「出発準備が整いました。出ます。ベルトをお願いします」
「あ、ああ……」
イオースィフはベルトを締めた後、振動し始めた翼を窓から眺めた。
「昔世話になった精神科医を知っているから、ここを訪ねてみてはどうだろう」
そう言って、イオースィフは一枚の名刺を差し出した。
違うんだ父さん、そういうものじゃなくて、と反論しようとした途端、クレーニヒの声を遮るように父親の端末が緊急連絡を告げた。そこからはクレーニヒの話を聞くどころではなかった。途中だった食事も放り出して書斎に行ったきり、父はクレーニヒの前に顔を出すことはなかった。
朝、テーブルの上には「仕事ですぐに下に戻ることになった。あとで連絡を入れる」とだけ書かれたメモが置かれており、父の姿は既になかった。
自分の父親への僅かな期待はここで打ち壊された。
クレーニヒを悩ませ続けている幻覚。その事に関して上級工学師である父に相談すれば何か解決の方法が掴めるのではないか。タイミングよく長期の仕事から帰宅した父親に、思い切って相談を持ちかけたのが昨夜のことだ。
ここ数年、父親とはまともに会話をした記憶がなかった。一緒にいるだけでも緊張し、何を喋っていいのかわからなくなる。
クレーニヒは部屋を飛び出し、あてもなく街を彷徨っていた。
父親の言う精神科の医師を訪ねてみようか。そんな考えもちらりと頭をかすめるが、軽く頭を振ってすぐに否定する。
ふと足を止めると、すぐ目の前には劇場があった。
悪夢や幻覚に悩まされると、クレーニヒはこの劇場に足を運んだ。映画や芝居自体にはあまり興味がなかったが、虚構の上に成り立っている物語を見ていると、どこか安らぎのようなものが感じられた。
幻覚に取り込まれ、現実が消えてしまいそうな恐怖。そんなものを体験したあとでは、元々存在しない筈の物語の世界の方が、よほど強固なものとして感じられたのだ。今では劇場という空間は、クレーニヒにとって現実回帰への一つの道標になっていた。
意識するまでもなく、彼は劇場へと足を踏み入れていた。
劇場内に客はクレーニヒ一人きりだった。
時間的に芝居は行われていなかったため、映画が上映されているホールに入り、適当な座席に腰を落ち付ける。
上映されている映画のタイトルすら見ていなかったクレーニヒは、ぼんやりとスクリーンを眺めていた。
不意に気配を感じた――。
急激に感覚という感覚が曖昧になり、世界から現実感が失われる。
「逃れられないのか……」
クレーニヒにとって、この劇場は唯一安らげる場所だった。
安らげる場所の筈だった。
スクリーンの世界が歪み、現実が曖昧になる。
どこが現実でどこが幻覚か。
どれが虚構でどれが真実なのか。
物事の輪郭線は失われ、すべての色が滲み始める。
そして、そいつが姿を現した。
そいつをクレーニヒは幻獣と呼んでいた。
あの日、上級工学師の図書館で初めて出会った異形の化け物。そいつはのっぺりとした顔の中心部に生気のない三対の目を有し、ゾロリと牙の生え揃った巨大な口を歪めるように動かしていた。
両生類に近いシルエットだが、どの生物とも異なる姿。まさしくこの世ならざる獣、幻獣と呼ぶに相応しい姿だった。
幻獣はあれからも度々クレーニヒの前に姿を現した。
しかし、その外見に反して、そいつはクレーニヒに襲い掛かってくるようなことはなく、ただじっと彼を凝視するだけだった。
「どうしたら消えてくれる?」
幻獣の方を見ようともせず、曖昧な世界の中で、それでもクレーニヒはスクリーンを、虚構の世界を見つめ続けた。その場所こそが憧れ続けた理想郷なのだとでも言うように。
「消えてくれだって?いて欲しいと言ったのはオマエだろう?」
クレーニヒは戦慄した
幻獣が意志を持ち、あまつさえ会話が成立するなどとは思っていなかったのだ。
「誰にも相手にされない。必要とされてない。だからいてくれって思ったんだろう」
「違う!なんの話をしているんだ!」
反射的に叫んでしまう。だが、
「そう苛つくなよ」
幻獣は禍々しい三対の目を一斉に細める。どうやら嗤ったようだった。
現実は歪んだままだった。虚構はこの世に染み出し続けていた。虚と実が混ざり合う世界で、幻獣は思いもよらない提案をクレーニヒに持ちかけた。
「どうだ?この世界をオマエの望む世界に創り変えてみないか?」
「―了―」
3394年 「嗤い」 

目の前に死体があった。しかし。それにはあるべき筈の首がなかった。
何かに引き千切られたかのような首の断面と、むせ返るような血の臭いに、吐き気がこみ上げる。クレーニヒは思わず目をそらしていた。
「これでオマエの望む世界に一歩近づいただろう?」
部屋の隅、薄暗がりからそんな声が聞こえた。
いや、それは果たして本当に“聞こえた”のだろうか。クレーニヒは未だにその獣が幻覚なのか妄想なのか、それとも実在するものなのか判断が付かずにいた。
――だからこそ“幻獣”と呼ぶのだが。
「なんだよこれは!?ボクが人殺しと望んでるって事なのか?ふざけないでくれ!ボクはそんなこと望んじゃいない!」
『そうだな。無差別な人殺しは望んでいないようだ。……今はな』
「じゃあこれはどういうことさ!こんな死体をどこから持ってきた?お前は自分が人を殺めたいだけなんじゃないのか!?」
クレーニヒの言葉に幻獣が三対の目を歪める。初めて出会った時と同じ表情だった。おそらく嗤っているのだ。
『こんな死体?よく見てみろクレーニヒ。コイツは“オマエが望む死体”だ』
そう言われて、クレーニヒは改めてその死体を見下ろした。コートを着た男の死体だった。
そこで彼の思考が一時停止した。
……このコートは?
途端に嫌な予感が襲ってきた。「まさか」という思いと、「そういうことなのか」という納得が入り混じって、クレーニヒの脳を混乱させる。再び吐き気がこみ上げてきた。
身元が分かるようなものはないかと、クレーニヒは仰向けに転がされた死体のコートの内ポケットを恐る恐る探ってみた。
見つかったのは上級工学師《テクノクラート》としての身分証だった。記されていたその名前は、クレーニヒが想像した通りのものだった。
『オマエが“いなくなればいい”と思っていた人間を、そのとおりにしてやっただけさ。もちろん、感謝してくれても構わないよ』
「そんな……」
崩れ落ちたクレーニヒは、死体の前に跪く。
「死んでほしいなんて……思ってなかったよ!ボクは!!」
イオースィフ――父の遺体を前に、クレーニヒの叫びが虚しく響いた。
『いいや、オマエは望んでいたのさ。自分をひとりにする父親など、この世からいなくなればいいとな……。心の奥底に閉じ込められていたその望みを、オレが引き出してやったにすぎないのさ』
クレーニヒは答えない。幻獣の言葉だけが頭の中に浮かんでは消える。
『オレはオマエの望みを叶える。そして世界はオマエの望むとおりになる。オマエの望む世界こそが、オレの望む世界でもあるのだからな……』
父親の遺体を前に、クレーニヒは一滴の涙も出てこない自分自身を、滑稽だ、と思っていた。
旅は順調だった。いや、順調に進む筈だったと言うべきか。
導都パンデモニウムを飛び立った飛行挺は、雲間を抜けて降下していた。気圧にも天候にも異常は見当たらない。
「ローゼンブルグまでは一時間くらいです」
パイロットと交信を終えた士官が声を掛けてきた。
「……ん、ああ」
窓の外を眺めていて一瞬反応が遅れたイオースィフだったが、それを気にも留めずに彼は再び空へと目を向けた。
「この辺りの飛行区域は安全なのかね」
話を聞いていなかったことを気にしたのか、士官が話好きだと感じたからか、珍しくイオースィフから話し掛けていた。
「今はとても安全ですよ。少し昔はあちこちにまだ渦があって、こんな風に飛ぶのも命懸けでしたが……」
士官はどこか懐かしむかのように、しみじみと答えた。
渦は全て排除され、漆黒の時代と呼ばれた時は終わりを告げていた。
「この世の混乱は、全てケイオシウムが原因という訳だな」
「たしかに。しかしケイオシウムがなければ、この飛行艇も飛ぶことができません。すべてに良い面と悪い面があるということでしょう」
「悪い面か。しかし、地上は渦のせいで暗黒時代を過ごすことになった」
「その時代も聖騎士達の働きでついに終わりました。これは人類と科学技術の勝利です。結局は我々が勝ったと言えませんか?」
「……勝利か。たしかにそうだ」
士官の思考に半ば感心と呆れが合わさったような感情をイオースィフは抱いた。
「パイロットが呼んでいます。失礼します」
インカムで会話しながら、士官は席を立った。
研究と開発の日々に勝利はない、ただ前進があるのみだ。自分達の創り出したものがどんな結果になろうとも、そこに前進があればいいのだ。テクノクラートたるイオースィフはそんな思考で生きてきた男だった。自分の研究、仕事の前進のみに人生を捧げてきた。そしてそこに疑問も迷いもなかった。
不意にイオースィフの視界が暗くなった。何事かと思考を切り替える前に声が響いた。
『やはりオマエの頭の中には、アイツへの思いは何も無いんだな』
突如、至近に出現した歪な三対の目。灰色をした闇がわだかまり、形を出そうとしていた。イオースィフが何か声を上げる前に、闇から生まれた巨大な顎(あぎと)が彼の視界を埋め尽くし、そして奪った。
『さて、忠実なる僕(しもべ)としては、“ご主人様”に働きの証を持ち帰らないとな……』
この場にその声を聞ける者はもういない。
士官が席に戻ると、イオースィフのいた座席は一面が赤に染まっていた。シートから天井までが、血臭を漂わせる鮮血で彩られていた。
シートの上には何かを言いたげに口を開いたイオースィフの首だけが、忘れ物のように置き去りにされていた――。
「―了―」
3394年 「因果」 

父が死んだ。
協会≪アカデミー≫からの知らせには、ローゼンブルグへ向かう飛行艇ごと行方不明になったと記されていた。
が、そうではないことをクレーニヒは知っていた。
父がいなくなることを、ボクが、望んでいた?
クレーニヒに自覚は無かった。
しかし父がいなくなって、心の中で重荷に感じていたような何かが無くなった様な、そんな開放感があるのもまた事実だった。
あれ以来、幻獣は口を開こうとしなかった。
普段はどこにも見えないのだが、ふと姿を探そうと視線を動かせば、その先にはクレーニヒをじっとみつめる幻獣が必ずいた。
まるで忠実で有能な執事であるかのように。
父親がいなくなってもクレーニヒの生活は変わらなかった。
家の中では自動機械≪オートマタ≫が殆どのことをやってくれる。
遙か昔の黄金時代とは比べられないのかもしれないが、それでも、ほぼ無尽蔵に生み出されるエネルギーによって、
市民の生活は一定水準が保証されていた。
全ては工学師≪エンジニア≫達の導都パンデモニウムが何世代にも渡って秘匿し続けてきた技術のおかげだ。
ただ一点、クレーニヒ自身の幻覚症状がますます激しくなってきたことは問題だった。
何となく目を開いているだけの時でさえ、まるで異世界がそこにあるかのような幻が迫ってきた。
一時は本気で目を潰そうとすら思い悩んだが、幸運にもその蛮勇が発揮される前に対処法を見つけることができた。
クレーニヒ自身が何かに集中していれば、幻覚を見る頻度が下がることに気がついたのだ。
色々と試した結果、最も有効だと思えたのは本だった。
文字を追い、文章を読み、頭の中でその内容を考えていれば、幻を見ることは少ない。
それ以来、クレーニヒはいつも何らかの本を持ち歩くようになった。
いつものように、クレーニヒが読み終えた本を本棚に戻そうとすると、ある書類ケースが見に留まった。
それは幻獣と初めて出会った図書館で見つけたものだった。
あの時は無我夢中だったため、そのま ま持って帰ってきてしまったのだ。
「そういえば、何かの研究レポートだったな」
改めて手に取ると、表紙には「異端研究報告書 No.983」とかかれ、「機密」の赤文字が踊っていた。
「…倫理規定違反…ケイオシウム管理法違反…特定研究禁止事項違反」
次のページには研究の停止にいたる理由が列挙されており、ページの最後に「3378年抹消」と書かれていた。
だが、それが逆にクレーニヒの好奇心を刺激した。
「ケイオシウムと人間との親和性について……?」
読み進めていくと、異端研究の主題がそう記されていた。
――ケイオシウム。
膨大なエネルギーを生み出す一方で、暴走することによって多くの命 を奪う危険性がある諸刃の剣。
公的な記録は既に失われているものの、渦≪プロフォンド≫をもたらし、全世界を荒廃させたのもまた、ケイオシウムが原因であると言われていた。
導都パンデモニウムが保持する技術の中でも、かなり重要なものであることに間違いはない。
そもそもパンデモニウムが半永久的に浮遊していられるのも、ケイオシウムの生み出す無限のエネルギーのおかげだった。
この報告書は抹消された異端研究の概要と成果についての記録であり、パンデモニウムの統治機構内で機密として扱われたものらしかった。
資料としてかなりの量、実際の研究で使われたデータと知見が添付されている。
「ケイオシウムの持つ確率と因果律の変動係数……なんだこれ、なんて読むんだろ……が、現在を表す……また読めない……に影響を及ぼすことにより……?」
研究の前提理論からしてクレーニヒにはさっぱりわからなかったが、
どうやらケイオシウムを上手く使えば、過去や未来すら変えられる可能性があるらしい。
もし本当ならすごいことだとは思うが、この十年でそんな成果が上がったという話題を耳にしたことがない。
それに、この研究自体が中止されているものだ。
「つまりケイオシウムを使って人間の過去や未来に影響を与えようとしたのか?」
難しい理論は読み飛ばし、パラパラとページをめくっていくと、最後に付記されたあるリストが目についた。
主研究者と被検体が列挙されていた。
主研究者のところには、母の名と「抹消」の文字。
そしてリストの最後には、まるでそれが些細なことであるかのように、小さく記載された被検体の名があった。
「被検体名、クレー……ニヒ……?」
音もなくクレーニヒを見つめる幻獣の目が、微かに嗤っていた。
幼い頃に、母親について聞いてみたことがある。
「お前の母さんは、心の病気にかかって亡くなってしまったんだ」
普段あまり感情を表に出さない父が、ひどく辛そうな顔をしていたのを覚えている。
それ以来、クレーニヒは母親のことを尋ねることはしなかった。
母が精神を病んだのは事実らしい。
そしてその心の病にかかるまでは、父と同様に上級工学師≪テクノクラート≫として様々な功績を上げていたという噂を聞いたことがある。
クレーニヒはその母の、最後の研究報告書を手にしていた。
自分の子をケイオシウムの実験に使い、統治機構から異端者として排除されたのだった。
「父さんがあんな態度をするのも頷けるってもんだよな……ははっ」
可笑しかった。本当に滑稽だった。
「ああ、そうか……最初から……狂わされていたんだ……」
ようやく得心がいった。
クレーニヒはそんな表情で顔を上げた。
いつの間に外に出たのだろう。
始まったばかりの曙光の時代、≪ドーンライト・エイジ≫において、導都パンデモニウムは唯一とも言っていい平和な街だった。
今はもう失われつつある技術を使って築かれた浮遊都市。
工学師≪エンジニア≫達の楽園。
ケイオシウムによってもたらされる無限のエネルギーは、人々の生活を豊かに彩っていた。
幸福を絵に描いたような桃源郷。
その光はクレーニヒには眩しすぎた。
突如、6アルレ(9メートル)ほど先を歩いていた女性が甲高い悲鳴を上げて倒れた。
首筋から、まるで冗談のように血飛沫を上げてゆっくりと崩れ落ちる。
刹那の時間を置かずに、近くを歩いていた家族連れの首が消え、先の女性と同様に、血潮を噴き出して折り重なるように倒れ伏した。
道路の中央では馬車を引いていた機械馬が別の馬車に全力で突っ込んだ。
どちらの馬車も、御者台にいた男性が頭から地面に叩きつけられ、すぐに動かなくなった。
本来なら機械馬同士のセーフティが働くため、絶対にありえないはずの事故だった。
街灯は明滅を繰り返し、あちこちから悲鳴と叫び声が上がっていた。
立ち尽くすクレー ニヒの目の前に は、先程の平和な街の面影は一片たりとも残されていなかった。
声が聞こえたのと同時に、目の前に幻獣が現れていた。
――オマエの望みを叶える。
幻獣はそう言った。
「まさか、これはお前がやったのか……」
『違うな。オマエが望んだのさ』
どこかで火の手が上がっていた。
「嘘だ!ボクはこんなこと望んじゃいない!こんな、こんな… …」
『羨ましかっただろう?妬ましかっただろう?無くなればいいと思っただろう』
「思ってない!思ってない!思ってない!」
まるで駄々をこねる子供のようにクレーニヒは首を振る。
耳を塞いでも、幻獣の声が容赦なく彼の頭に届いた。
『オマエが望めばこそ、オレは力を振るうことができる。さあ願え。次はどんな殺戮と破壊を繰り広げようか?』
「やめろ!」
クレーニヒは幻獣の目から逃れるように走り出した。
道路に飛び出したその目前に馬車が迫っていた。
「!?」
御者台の男が慌てて機械馬を静止させようとするが間に合わない。
クレーニヒは思わず目を閉じ、衝撃に身体を竦めた。
ズシャッ。
そんな音が響いた。
クレーニヒは跳ね飛ばされていなかった。
恐る恐る目を開けると、確かに馬車は静止していた。
しかし、クレーニヒに衝突するはずだった機械馬は、まるでクレーニヒのいる空間自体に切り裂かれたかのように、正面から真っ二つに分断されていた。
「いやあああ!」
歩道の女性が悲鳴を上げた。
彼女はクレーニヒの目の前に停止している馬車の御者台を指差していた。
そこには機械馬と同様、真っ二つに切り裂かれた男性の身体があった。
『さあ望みを思い描け。オレはオマエの望みを叶える力を与えよう』
その身体を鮮血に染めて、灰色の幻獣がクレーニヒに言った。
「―了―」
3394年 「煉獄」 
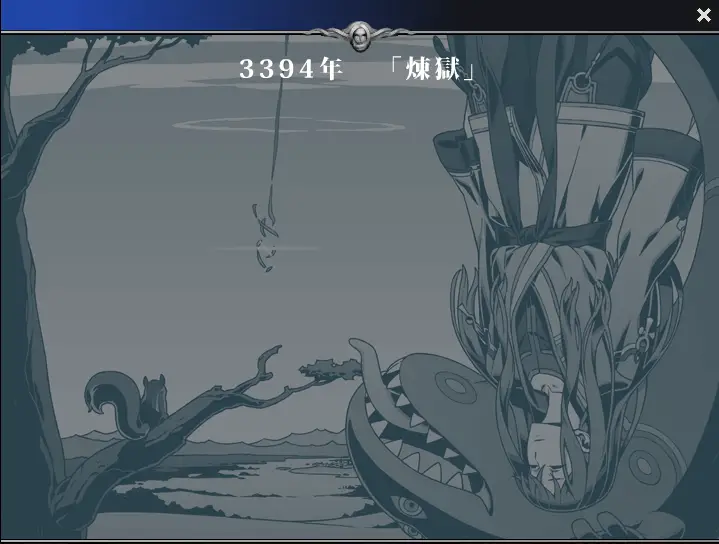
また悲鳴が遠くから聴こえる。燃え盛る炎の中でクレーニヒは呆然と立ち尽くしていた。
近くで何かが爆発し、吹き上がった炎がクレーニヒの頬を掠める。長い栗色の髪の先端がじっ、と焦げた。定まらぬ視線のままクレーニヒは歩き出した。が、数歩もいかないうちに何かに躓いてよろける。ふと見ると、それは子供の死体だった。生命の抜けたその子供の顔は恐怖に歪み、半ば焼け焦げた頬には乾ききった涙の跡が残っていた。
空虚な目で「それ」を見つめていたクレーニヒは。突如、苛立ちと共に焼け焦げた地面を殴りつけた。
「あああああああッ!」
言葉にならないその叫び声を聞く生者はいない。
まさに地獄だった。
考えまいとすればする程、クレーニヒの心の奥底に昏い炎が灯り、自らの感情を闇色に染め上げていった。
こんな破壊をボクは望んでいたのか――。
こんな虐殺をボクは望んでいたのか――。
問いかける声に応えるものがあった。
『そうとも。これはオマエの望んだ世界だ』
灰色の薄闇が炎の中に顕現する。三対の目がクレーニヒを捉えていた。
「おい、きみ!無事か!?」
少し離れた場所から声が聞こえた。クレーニヒが声のした方を見ると、炎の向こうに数人の人影があるのがわかった。防火服に身を包んだその服装からすると、おそらく救助隊員か何かだろう。
「すぐそっちに行くから、じっとしているんだぞ。大丈夫だからな!」
炎を避けながら救助隊員が近づいてくる。その様子を幻獣がまじろぎもせず見つめていた。
「だめだ!来ちゃだめ!戻ってください!」
ハッとなってクレーニヒが声を掛けるが、
「大丈夫だ、安心しろ。必ず助けるから諦めるんじゃないぞ!」
「違うんです!お願いだから戻って!」
1アレルまで近付いた隊員がクレーニヒに手を伸ばした。
「さあ、もう大丈夫だ。こっちに!」
「来ないでって言ってるのに……」
クレーニヒは真下を向いて、力なく呟いた。
「ボクのことは……放っておいてください」
瞬刻、クレーニヒに伸ばされた隊員の腕が宙を舞い、飛び散った血が炎に焼かれてじゅうと焦げる。
そこに灰色の幻獣が立ち塞がっていた。
「ぎゃああああああっ!」
腕を失って倒れこんだ仲間を支えながら、別の隊員が「ば、化け物だ……」と呟いたのが聞こえた。
「に、逃げろ!」
別の隊員が叫び声を上げながらその場を逃げ出そうとする。
が、その声は途中で途切れた。叫ぶべき頭部が幻獣の鋭い爪によって切断されていた。
「だから言ったのに……。近寄らないで、って」
炎の中、クレーニヒの昏い眼差しが不思議な光を放っていた。
咽ぶような血臭の中、クレーニヒは重い足を引き摺って歩いていた。周囲に人影は無い。正確に言えば、生きている者はいない 。
血に塗れたこんな自分を見てほしくない。そう思っただけで、幻獣は“目撃者”を片端から物言わぬ死体に変えていった。
クレーニヒを助けようとした救助隊員の内、生き残った誰かが通報したのだろう。いつの間にか治安維持のために配置された部隊がじりじりと彼を包囲していた。「敵」の威嚇射撃を躱しながら、クレーニヒは狭い通路を通り抜けていく。
追い込まれているのはわかっていた。だが、正面から戦って治安部隊を壊滅させる程の力が幻獣にあるのだろうか。仮にあったとして、その後どうすればいい。
「ははは、パンデモニウムを相手に戦争を始めればいいのか!?」
考えがまとまらない。思考が定まらない。足元がふらつく。
ふと、手をついた壁がぐにゃりと歪んだ。生暖かく、固めのゼリーのような質感の壁は、この世のものではなかった。
そこだけが、現実の中に幻覚として存在していた。
壁だった筈の空間に発生した幻の中から手を引き抜くと、どろりとした液体が纏わり付いていた。その不快な液体からは酷い臭いがした。
ふと見渡せば、周囲の空間に様々な幻覚の世界が見えていた。いや、それは果たして幻覚と呼べるのだろうか。
クレーニヒは、試しに別の幻覚に触れてみることにした。
見たことない草を千切ってみる。
空中に浮く奇怪な岩に爪を立ててみる。
幻の中に吹く風に手を当ててみる。
『そうとも。オマエが今まで幻だと思っていた全ては、実在しているのだ。ただし、オマエ達の世界とは時間や空間を超越したところにあるものだがな』
不意に幻獣の声が聞こえた。
『ふふ、どこを見ている。オレは“コッチ”だ』
空中に浮かんだ幻の世界。いつか見た白黒の海の中から、幻獣がじっとこちらを見ていた。
『もうわかっただろう。オマエの幻覚が何なのか。オマエにどんな力があるのか』
「全てはケイオシウムの……あの実験のせいなのか?」
『さあな。オレはきっかけは知らない。だが、オレはその力を持つオマエに呼ばれたからやって来たのさ。オマエの願いを叶えるために、な』
その時、路地の先に治安部隊の姿がちらりと掠めた。
「っ!」
反射的に脇道に飛び込んだクレーニヒだったが、目の前には銃を構えた隊員が待ち伏せしていた。
「あっ……!?」
――撃たれる!
そう思った瞬間、クレーニヒの意識が弾けた。
即座に手をかざし、目の前の空間に“幻覚を出現させていた”。
放たれた銃弾はその“幻覚”に吸い込まれ、瞬時に塵と化した。
「なんだ?何が起こった!?」
事態を把握できない隊員が狼狽した隙に、クレーニヒは別の幻覚から「何か」を呼び出していた。
ゲル状に見えるその物体は、隊員の体に張り付くと、じゅうじゅうと嫌な音を立てながら精気を喰らってゆくまるで枯れ枝のように変わり果てた隊員の姿は、もはや人間の搾り滓でしかなかった。
「い、今のは……」
急激な脱力感と共に、クレーニヒの中に現実が戻ってきた。血液はマグマのように熱く、肺はその熱を冷まそうとするかの如く空気を欲している。
『ふふふ。やればできるじゃないか。それが異界の力……いや、オマエの力だ』
クレーニヒは愕然と自分の手を見つめた。嫌な臭いのする液体は跡形もなく消えていた。「敵」を死に追いやったゲル状の謎の物体も同様だった。
しかし、枯れ枝のような人の死体は、紛れもなく眼前に残っていた。
「ボクが……ボクが殺したのか」
昏い色の瞳から、涙が一筋流れた。
はぁっはぁっはぁっ――。
息が上がっていた。
心臓が壊れそうなほどに痛い。耳の後ろがどくどくと脈打っている。
背後からは武装した治安部隊が物音も立てずに迫ってきていた。姿こそ見えはしないが、クレーニヒにはその気配が手に取るようにわかった。
頭の中にざわざわとした違和感がこびり付いている。「敵の臭い」が漂ってきているのだ。
「これも異界の力なのか?」
空間を異世界へ繋ぐ――これはまるで渦だ。
世界を混乱させたあの災厄、クレーニヒも知識としてその概要を理解していた。
クレーニヒは自分自身の中からその渦が生じ、世界にあの混乱を再びまき散らすのではないかと想像した。
『その望みを叶えるには、少し時間が掛かりそうだな』
「ち、違う!望んでなんかいない!」
『おや?違うのか。残念な話だ』
幻獣はニヤリと厭らしい嗤いを浮かべた。
『おっと、声を上げたせいでヤツラが動き始めたぞ』
その事はクレーニヒにも既にわかっていた。それでも、目的地はすぐそこに迫っている。
厳重に施錠された出入り口を幻獣の力で破壊し、クレーニヒが入り込んだのは、飛行艇のフライトデッキだった。
高高度に浮かぶパンデモニウムと外界との接点。そしてパンデモニウムの外縁部に最も近い場所。
『……!?』
クレーニヒの思考を読み取った幻獣が、僅かな戸惑いを見せた。
幻獣の戸惑いに気付きながらも、クレーニヒはそれを無視してデッキの先端部まで歩を進めた。轟々と唸る風が、華奢なその体身を吹き飛ばそうとする。
「ボクが死んだら、お前は消えるのかい?」
吹き荒ぶ風の中、クレーニヒは幻獣を顧みた。煽られる長髪を片手で押さえつけ、幻獣の歪な瞳を瞳をじっと見据えていた。
『……どうだろうな。叶えるべき望みがなくなれば、オレは消えるしかないのかもしれない』
「今までなんでもお見通しって感じだったのに、自分自身のことはわからないんだ」
『……』
幻獣の表情からは何も読み取れなかった。或いは本当に戸惑っているのかもしれない。
その時、遠くでパン、と乾いた音が響いた。音と同時にクレーニヒは異界と空間を繋ぎ、飛来してきた銃弾を葬り去った。
遠距離射撃用の長銃を構えていた特殊部隊の隊員には、クレーニヒの姿が蜃気楼のように掻き消え、刹那の後、再び同じ場所に現れたように見えた。しかし次の瞬間、身を起こして確認しようとした隊員が見た光景は、眼前に迫る幻獣の顎だった。
クレーニヒに銃弾を防ぐつもりはなかった。反射のように体が勝手に反応していたのだ。
「……もう時間がない」
これ以上、自分自身を押さえ込む自信が無かった。
心の奥底にある力への渇望が理性を上回った瞬間、クレーニヒの世界は変わってしまうだろう。もうこちら側には戻って来られない。
ならば、今しかないのだ。
『それがオマエの真の望みなら、オレは止めはしない』
一歩。クレーニヒが踏み出した。
「ああ、さよならだ」
一歩。そこは生まれて初めて歩く、パンデモニウムの外の世界。
大きく勢いをつけてクレーニヒは飛翔した。
両腕を翼のように広げ、全身で冷たい風を感じる。大気に翻弄されるように体がぐるぐると回転する。
パンデモニウムのフライトデッキから、クレーニヒを追っていた人々が見下ろしていた。もう彼らの表情も気配も読み取れない。
と、たった今決別したその世界から、灰色の闇が迫ってくるのが見えた。
なんで、来た――声は一瞬で遙か上級に置き去りになり、相手にまで届かない。
『オマエの望みを叶えよう』
クレーニヒの隣に並んだ幻獣から、そんな声が響いた。
ボクは助けてほしいなんて思ってない。それは本心だった。それともこの獣は、自身が消えるのが惜しくなったのだろうか。
瞬間、幻獣が苦笑したように見えた。それは果たしてクレーニヒの気のせいだったのか。
頭の中に幻獣の声が響いた。
『オマエはこう思っただろう』
――やっぱり、ひとりは寂しい――と。
青い、どこまでも蒼い世界をひとりと一匹が泳いでゆく。
そこは彼らの最後の理想郷だった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ