グリュンワルド
【正体】父王に疎まれ続けた黒太子。レジメントとして渦との戦いに身を投じ、帝國の侵略戦争においては諸国連合の将として戦うも女将軍ベリンダとの戦いで重体となる。王家存続を願う母の願いで再生されるが結果「人」ではなくなり、ロンズブラウを滅亡させる。
【死因】
【関連キャラ】ベリンダ(因縁)、ヴィルヘルム(部下)、アイン(輸送)
3392年 「孤影」 

「―ロンズブラウ王国市内―」
冷たい石畳の上で女は息絶えていた。女は肩口から胸の中央まで深く切り裂かれている。血は石畳を流れ、路肩まで流れていっている。
傍らに立つ男は女の顔を見つめていた。女の青白い顔の口元に溢れていた血は、薄明かりの中でもとても鮮やかに光っている。
しばらく男はそこに立っていた。
黒い外套とフードに隠れた顔にどんな表情が浮かんでいるのかはわからない。
街の時間はそのまま過ぎていった。月明かりは無い。
やがて、黒衣の男は幽鬼のようにその場から消えた。
「―ブローンハイド城―」
「それで?」
王子の言葉は空気を凍らせた。玉座に腰掛けたグリュンワルドの表情には、何の感情も浮かんでいなかった。
「洛内での出来事で、臣民はとても不安になっております。何卒これ以上……」
代々忠臣として王家に仕えてきたガイウス卿が言葉に詰まる。
前代未聞の出来事と言ってよかった。
現在ロンズブラウ王国では、病床にある老王の代わりにこの若き王子グリュンワルドが国を治めていた。
その主権者たる王子に家臣が、洛内での殺人をやめてほしい、と懇願しているのである。
元々王国にはグリュンワルドの他に二人の王位継承者たる兄がいたが、二人とも早世していた。
グリュンワルドは王の勘気を受けて放逐されていたのだが、数年前に帰還していたのであった。
その放逐の理由も、彼の奇怪な行いと性格にあった。
幼い頃から動物の死骸を集めて土に埋め、骨を取り出し、部屋に飾っていた。死刑にされた囚人の遺体を欲しがった。
そんな王子を呪われた子だと乳母達は噂しあい、誰も彼を世話したがらなかった。兄や王にその行動を咎められても、一切奇怪な行動は改まらなかった。
そして彼が十六の時、城の地下室から彼が殺めたと思われる屍体が数十と発見され、王国から放逐されたのだった。
「このことは、王にも必ず上奏させていただきます」
ガイウスは絞り出すように王子に言った。ガイウスは諦めていた。この王子は放逐されたときと全く変わっていないのだと。
放逐されるとき、王は何度もグリュンワルドに問うた。なぜ殺したのか、どうしてこんな真似をするのかと。
その時も一切答えようとしなかった。その様子に王は絶望し、彼を放逐したのだった。
「よろしいですかな?」
緊迫した状況で間に入ったのは、宮廷に学者として長く仕えてきたローフェンという男だった。
齢は八十を超え、痩せさらばえた老人だったが、その眼光には西方に名を馳せた工学師だった頃の面影を残していた。
「われわれ家臣団は不安なのです。あまり無体な真似は謹んで下さいと申しておるのです」
先々代の王から仕えた老人は、他の家臣とは違う物言いが許されていた。
「グランデレニアが兵を挙げたとの噂はここまで届いております。戦乱の時は近いと、国を跨いで様々な権謀が巡っているのです」
「今は変化の時です。世界は混沌の軛から解放され、各国は再び地上を再分割しようと軍備を進めています。その戦乱は必ずこの王国を巻き込むでしょう」
ローフェンは一息おいて、家臣達を見回しながら言った。
「国を思う彼らの気持ちもご理解ください」
老家臣の言葉を聞いても変わらぬ王子の様子を見かねたガイウス卿や他の家臣達は、憮然とした表情を隠さないまま玉座の前から辞した。
最後に残ったローフェンは、呟きともつかぬ言葉を発した
「善と悪、明るい日の下では明解でよろしいな」
「―暗路―」
グリュンワルドは城を抜け出し、夜半過ぎに城下の街へと出た。
彼にしかわからない抜け道がこの城にはたくさんあった。彼はこの古い城のことを誰よりも知っていた。幼い頃の孤独な彼にとって、古城の隠し通路や地下牢は何より落ち着く場所だったのだ。
夜の湿った空気が肺に入ると、グリュンワルドはあの欲望が疼くのを感じた。一瞬瞑目して欲望の舌触りを試した後、外套のフードを被った。
酒場と売春宿が集まる通りまで来ると、路地の影で壁に寄り掛かりながら通りを見つめていた。時折酔った売春婦とその連れが彼の前を通り過ぎる。しかし、誰も彼に気が付かなかった。グリュンワルドは静かに時を待っていた。酒場から出てきた女が通りを離れ、反対側の路地へと入っていくのが見えた。グリュンワルドもゆっくりと彼女を追うように路地に入った。人気のあった通りから、街灯もまばらな道へと女は進んでいった。
通りを進む女に黒い影が近付いていく。女はまだ気付いていない。影が女の後ろに付こうとしたその刹那、影と影がぶつかった。剣が地面に落ちる。
女は悲鳴をあげて逃げていった。立っているのは剣を抜いたグリュンワルド。女を襲おうとしていた男は、二の太刀を防ぐように距離を取った。男の背格好は黒き王子とよく似ていた。
「探したぞ」
男は相手が王子であると気付いたようだった。身構えた男は上着のボタンに指をかけようとしている。体つきや構えから、男が手練れだということがわかる。
「抜く前に思い浮かべろ」
グリュンワルドが機先を制するかのように言葉を発した。
「お前は何を望む?」
男は王子の奇妙な問いを無視して上着を跳ね上げ、銃を抜く。
一閃、男の首は綺麗に打ち落とされた。男の身体が銃を持ったまま倒れる。鮮血が地面を濡らす。一瞬、グリュンワルドの顔に笑みが浮かぶ。
夜の街の静寂がまた広がった。グリュンワルドは男の首を上着で包み、立ち上がった。
「―地下室―」
扉からは光が漏れていた。グリュンワルドは勢いよくその扉を開ける。そこには奇妙な機械に囲まれて座るローフェンの姿があった。老賢者は覗き込んでいた巨大な拡大鏡から顔を上げた。
「殿下、これは急な訪問ですな」
「こいつから聞きたい事がある」
グリュンワルドは奇妙な装置や古い革張りの本が散らかる机の上に、無造作に首を置いた。
「これは懐かしい。またあれをやるのですかな」
ローフェンの目に不気味な生気が宿った。
「これはお前の実験台じゃない。こいつは城下で起きている殺人の犯人だ」
「ほう、成る程。あれはあなたがやっていたのではなかったのだと。これは意外でしたな」
老人はゆっくり立ち上がった。
「くだらん冗談はよせ。首が腐るぞ」
「言われなくともわかっております。さて、あれはどこへしまったかな……」
ローフェンは堆く積まれた本と奇妙な機械が並ぶ部屋を掻き分けながら、奥へと去った。
グリュンワルドは、物置と化している長椅子からガラクタをはたき落として座った。
そして、事の顛末にどう始末をつけようか沈思した。
「―了―」
3392年 「死地」 

地下室。ロンズブラウ王国城下を騒がせた連続殺人犯の首は、複数の糸のようなものによって奇妙な機械に繋がれている。その機械はつい先日まで稼働していたようだ。その昔、エンジニア達の技術で製造されたという、他者の記憶を覗ける機械。頭部だけあれば死者に対しても使用可能な代物であったが、こんな代物を隠し持っているのは、地上ではローフェンぐらいなものであろう。
「役に立たぬ機械だ。本当に動いているのか?」
「機械に問題はありません。私と同じで見た目は古ぼけているが、動きはすばらしい」
王子は老人の軽口には反応だった。
「まあ、本人の知らぬものは引き出しようがありませんな。黒幕も馬鹿ではないということでしょう」
首と返り血を浴びた男と老人、異様な光景であるにも関わらず、二人はどこか楽しげな雰囲気すら漂わせている。
「服と金を渡し、無差別殺人を依頼する。奇妙な話だ」
「趣味で人を殺すのを楽しむ者もいます。それに比べれば奇妙ではありますまい」
ローフェンの冗談はまたも無視された。
「しかし、この服は殿下のものと見紛わんばかり」
首を包むのに使用していた犯人の上着を広げ、まじまじと見つめる。血によって汚れているが、注目すべき点はそこではない。
「同じだ。私のものとな」
家臣や臣民の評価はどうであれ、一国の王子が着る衣類だ。そう簡単に手に入るようなものではない。もちろん値も張る。
「この依頼主、意外と身近な所にいるのかもしれませんな。差し当たって心当たりはございますか?」
「さて、多すぎてわからんな」
グリュンワルドは肩を竦めて答えた。
翌日、城内を移動中のガイウスをはじめとした家臣団を見つけたグリュンワルドは、彼らを呼び止めると、首を包んだ上着ごとその足下へ放り投げた。
腐りかけの首が姿を現すと共に、悪臭が辺りに広がる。
「ひっ」
家臣の一人が思わず声をあげ、他の者も眼前の光景と悪臭に顔を顰める。
「件の犯人は始末しておいた。もう城下であの様な事は起こるまい。臣民にも伝えておくといい」
「わざわざ殿下ご自身が探し出したのですか?これは……」
ガイウス卿の表情は一瞬こわばり、言葉に詰まった。
「何か言うことはないのか?」
「誠に申し訳ございません。殿下を疑っておりました。何か処罰をお望みであれば、何であれ受け入れます」
ガイウスは王子を見つめ、淡々と言い放った。
他の家臣達の表情にはグリュンワルドを敵視するような鋭いものはなかった。自分にこの凶事が降りかかるのではないかと怯えているようだった。
「いや、何も無い。代わりにその首をお前にやる。飾っておけ」
王子は呆然とする家臣団を置いて、その場を去った。
「家臣達はなんと申しておりましたか?」
地下室に入るや否や、ローフェンが話し掛けてくる。
「なにも」
「まあ、彼等は自分達が正しいことをしていると思っているのですからな。誰の差し金であれ、あなたが目障りで仕方ない」
「私がいなくなれば、それでいいわけだ」
「まあ、そういうことですな」
「こんなくだらん茶番が続くなら、国に戻らぬほうがよかったか」
「そうとも言えません」
「あなたに相応しい仕事、いや、王族の勤めがそろそろやってきます」
幾日かが過ぎた後、王国にルビオナからの特使がやってきた。ルビオナへの援軍要請だった。
家臣団は集まり、王子の前で会議をしている。
「グランデレニアが動き出したという事か」
「ええ。ついにルビオナ方面へも乗り出すという情報を掴んだようです」
「ルビオナが落ちれば我が国も無事ではすまないでしょう。彼の国とは古くからの同盟国でもあります」
「我が国も既に準備はできています。一週間もあれば、一定規模の派兵準備は整いましょう」
「まずは先遣隊を……」
グリュンワルドは王座に座り、家臣団の行っている会議の様子を静かに眺めていた。
「先遣隊には私も加わろう」
王子は呟くように会議で言葉を発した。
「国王陛下が現在のような状態で殿下が戦地に赴かれるなど、滅相もございません」
周りの臣下が諌めようとするが、ローフェンが割って入る。
「殿下は若いながらも自ら国難に立ち向かおうというのです。ここは殿下を送り出しましょう」
家臣団は押し黙った。
「ガイウス。留守は頼んだぞ」
提案に無言を通していたガイウス卿へ王子は声を掛け、王座を立った。
「御意のとおり」
慇懃にガイウスは言葉を返した。
兵の招集には五日を要した。王国中より招集された兵達が隊列を組んで並ぶ。遠征軍としては建国以来の規模である。
「グランデレニア帝國はルビオナ連合王国に侵攻を開始し、世界に不要な混乱を撒き散らしている!」
「古くからの友邦たる国を放っておくことはできぬ。我らロンズブラウ王国、ルビオナ連合王国と共に帝國を打ち倒そうぞ!」
「帝國に死を!」「帝國に死を!」「帝國に死を!」
声を張り上げる兵団長に対し、兵達が雄叫びをもって答える。グリュンワルドはずっと瞑目していた。
出兵式を眺めながらローフェンは呟いた。
「殿下の力、皆に見せつけましょうぞ」
「―了―」
3393年 「戦場と血」 
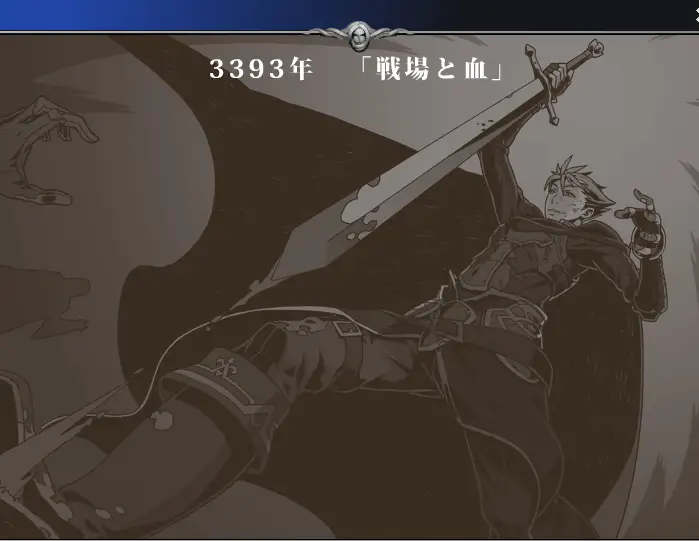
グリュンワルドが最後の帝國兵に対して剣を振り上げる。
「降伏させてくれ!捕虜になる!死、死にたくな……」
両手を上げて命乞いをする帝國兵の言葉は、最後まで発せられる事なく途切れた。
再び剣を振り、血を飛ばすと鞘に収める。その日は完勝と言っていい程の勝利だった。
数においては劣る状況ながらも、ロンズブラウ王国軍は善戦を続け、グランデレニア帝國の侵攻を阻んでいた。
ルビオナ国境に陣を置いてから数カ月、グリュンワルド達は個々の戦闘では勝利を納めていた。しかし、地力に勝り領土拡大の意志を抑える事のない帝國軍は、講和を持ち出す気配を見せていない。ロンズブラウ・ルビオナ軍にはいまだ帝國を打ち負かす程の軍事力が無い為、その戦力はゆっくりと、だが確実に摩耗していった。
「お待ちください。本日も前線へ向かわれるのですか」
参謀長が必死な形相でグリュンワルドを諌める。
「……」
黙々と武器の手入れを続けるグリュンワルド。
戦地に赴いてから幾度となく繰り返されたやりとりだった。
「どうかご自愛ください。勝利を続けているとはいえ、帝國の力は侮れません。貴方様はロンズブラウの総大将、奥でどっしりと構えていただければよいのです。第一、御身に万が一のことがあっては、国王陛下に顔向けができませぬ」
何度も同じ進言を受けたが、グリュンワルドの考えが変わる事はなかった。
「私の剣は血を欲している。血だ……、それもたくさんのな」
刀身に傷がないかを確認しながら不気味に呟く黒い王子に、参謀長は怖気を震った。
「本国からの兵員・物資の補充は十分か?」
突然の話題の切り替えに参謀長は驚いたが、その意図を知ると、また恐怖した。
「……いえ、あまりうまくはいっておりません」
当初こそ要望通りに送られていた兵員・物資の補充は、戦争が長期化するに従い、何かと理由をつけられて遅延や減少する事が常態化していた。その事が、細事を報告される事のない立場にあるグリュンワルドに気付かれていたのだった。
「標的にされやすい私が前に出れば、兵の消耗も減るというものだ」
幾度となく前線に立ち、戦功をあげてきた事実がそこにあった。
「ですが」
「それとも、報告を怠っていた罪で首を跳ねられたいと?」
「……くれぐれも無茶はなさらぬよう」
参謀長は観念したという表情で白旗をあげた。
「考えておこう」
グリュンワルドは頷くと、馬のいる場所へ向かって歩き出した。
『ロンズブラウ日報』
「グランデレニア帝國軍恐るるに足らず!」
「常勝無敗王国軍!」
「健闘!ルビオナ軍!」
城下で発行された新聞を眺める臣民達は、口々に王子の活躍を語っていた。
「今日もずいぶんと威勢のいい事が書いてあるな」
「なんでも、敵兵の半分は王子が一人でやってるらしいぜ」
「おいおい。いくらなんでも、そりゃ盛りすぎだろう」
「まぁ、相当に活躍してる事は確からしい」
「しかし、兄王子二人が亡くなり、あの薄気味悪い黒太子様が戻ってくると知った時はどうなる事かと思ったが」
「神様の思し召しってのは、あるもんだな」
「この調子なら王国も安泰だ」
「戦勝祝いに税金でも下がってくれりゃいいんだがね」
「ははっ、違いねぇ」
新聞を肴に思い思いの事を語る臣民達。戦地は遠く、また戦勝報告が続いているという事もあり、城下の雰囲気は明るいものだった。
それに反して、家臣団の表情は一様に暗いものだった。
一人が紙の束を取り出し、机の上に広げる。
「これを見ろ」
「おかげで臣民達に黒太子と恐れられていた殿下の評判は、今やこのとおり」
ロンズブラウ日報を始めとした王国の新聞記事。王国軍の勝利と王子を称えるものばかりだった。
家臣団は一様に苦々しい表情を浮かべている。
「これでは何のために兵員・物資の補充を何かと理由を付けて最小限に抑えているのか、わからんではないか」
「敗北の責任を殿下に取らせ、実権を奪う計画がこの有様だ」
「もしこのまま凱旋でもされては、我々の立場、いや命が危うい」
「話が違いますぞ。どうなさるおつもりか、ガイウス卿!」
一同が家臣団の中でも最も地位のあるガイウスを見つめる。国政からの王子排除は彼が言い出した事でもあった。
「恐らく、殿下は自身の立場を理解しておいでです。いずれは我等の思うようになるでしょう」
自軍以外に立つ者のいなくなった戦場で、倒れた敵兵を砕く剣の鈍い音だけが響く。
「殿下」
胸を刺し、腹を刺し、手を切り、脚を切り、あるいは頭蓋を叩き割る。
倒れた敵兵を切り刻み続けるグリュンワルドの姿があった。
「殿下!」
息のある者に止めを刺すという理由だけではなかった。
グリュンワルドは、人体が砕ける「音」が好きだったのだ。
剣先から伝わる衝撃も、飛び散る肉片も心地良かった。
生から死への不可逆な変化、それを自由にしている感覚こそ、彼の望むものだった。心が真に開放される瞬間だった。
兵団長の再三の呼び掛けで、やっと鈍い音は止んだ。
「もうここに戦う相手はおりません。陣地まで退きましょう」
「……わかった」
我に返り、兵団長の用意した馬に乗る。
総大将として赴きながら誰よりも前に出て、誰よりも戦功をあげていたにも関わらず、グリュンワルドの心はより一層飢餓感を強めていた。王子は己の昏い欲求にすっかり飲み込まれていた。
「―了―」
3394年 「死の軍勢」 
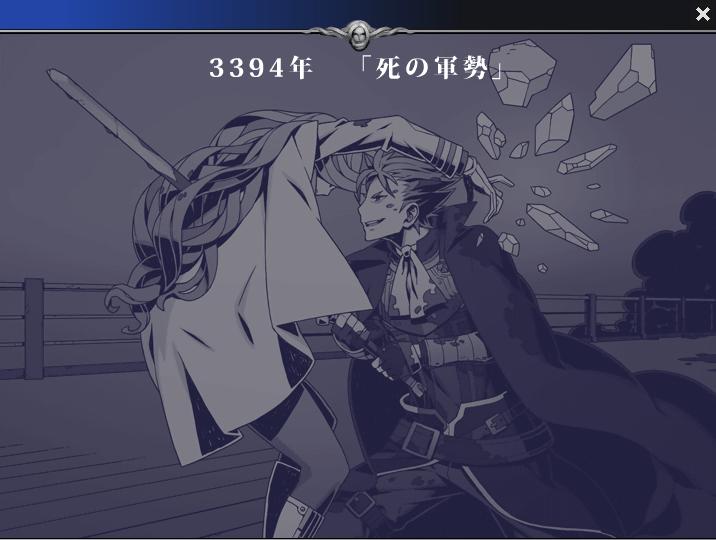
夜明け前。黒いベールを一枚ずつ剥ぐように空が白んでいく。普段ならば、鳥や虫が目を覚まし、やがて昇る朝日を歓迎する歌を奏でる時間帯だ。しかし今はその代わりに、金属と金属が擦れ合う音と大勢の人間が立てるざわめきが支配していた。
援軍としてロンズブラウ軍を率いているグリュンワルドはひとり陣から外れ、黙々と剣を磨いていた。
トレイド永久要塞。それがグリュンワルド達がいる砦の名前だ。古くからルビオナ王国において難攻不落と謳われてきた砦だ。今日に至るまで幾度も帝國軍に苦汁を嘗めさせてきた。今回も同様に自分達が勝利する。それはこの場に居並ぶ将兵の誰もが確信していたことだろう。払暁の光に照らされる兵士達の顔には余裕があり、中には笑い声を上げている者さえいた。しかし、その笑い声は空からの轟音によって掻き消された。
──ズゥゥン
空に浮かんだ巨大な戦艦・ガレオンから轟音が響き、一瞬の後、王国軍の陣に爆発が起きた。砲撃の直撃を受けた兵士達は人形のように吹き飛び、残った者も恐怖に陣を乱した。
そこに決死の突撃を行う帝国兵が襲い掛かる。怯んだ王国兵は瞬く間にその数を減らしていった。
帝國の新兵器の圧倒的なその姿は、様々な小国家の連合体である王国兵の意思と統率を挫くのに十分だった。
「殿下、このままでは我が軍にも甚大な被害が」
グリュンワルドの元に部隊長が駆け寄ってくる。直接の砲火に曝されていないロンズブラウ軍は統制を保っていたが、兵士達の間には恐怖と動揺が走っていた。
「全軍に後退を支持しろ。あの化け物から離れて機を伺う」
「りょ、了解しました!」
部隊長が顔を強張らせて走っていくのを見送った後、グリュンワルドは前方に展開する部隊を眺めた。混乱する部隊の中に統率の取れた動きで展開する部隊があった。そこにはルビオナ装甲猟兵の戦旗がはためいている。女王直下で名を馳せるオーロール隊の姿も見えた。
トレイド永久要塞がルビオナ王国を守る『盾』ならば、装甲猟兵は敵を打ち破る『矛』。その火力は他の部隊を遥かに凌駕する。いかな巨大戦艦といえども無傷という訳にはいかないだろう。それがグリュンワルドの考えだった。
──ドゥゥン。
──ドォォォンンン。
装甲猟兵による砲撃が始まり、巨大戦艦に火柱が上がる。戦艦も砲撃を装甲猟兵に集中させているが、その巨体故の動きの遅さが徒となって攻撃を当てる事ができない。装甲猟兵達は持ち前の機動力を生かして、巨大戦艦に果敢に挑んでいった。
やがて、ガレオンは黒煙を噴いて高度を落とし始めた。
「墜ちる!」
「やったぞ!」
それまで絶望に打ち拉がれていた王国軍から歓喜の叫び声が上がる。それとは対照的に帝國軍の士気は下がり、戦況は逆転した。
「今だ! 突撃せよ!」
その機を逃さず、グリュンワルドは自らが先頭に立ってガリオンが墜ちてくる場所へと突進した。眼前の帝國兵を斬り殺し、刺し殺す。敵の血がグリュンワルドのマントを赤く染め、その切っ先は人間の骨を砕いた代償として僅かに欠けた。
――ズゥゥゥゥン。
やがてガレオンは地響きを立てて地面へと着陸した。甲板の上には王国兵と帝國兵が入り乱れ、一瞬ごとにその命を散らしていた。
その戦いの中心に一人の異形の女性の姿があった。その手には指揮杖がある。返り血に塗れた凄惨な姿で、うっすらと笑みを浮かべている。グリュンワルドはその姿に僅かな共感を覚えた。
「女、貴様が指揮官か」
グリュンワルドが問いかけると、女将軍は美しく微笑んだまま首を傾げた。
「あなたは誰?」
「グリュンワルド・ロンズブラウ」
「そう……あなたがあの」
女将軍の表情は変わらない。夥しい数の死体の中で美しく微笑んでいた。だが、それはグリュンワルドも同じであった。
「その命、もらい受ける」
そう呟くと、身を屈めて突進する。一瞬にして女将軍の眼前に迫り、振りかぶった剣を鋭く振り下ろした。
ギィン!
女将軍が咄嗟に氷の盾を生み出してその身を庇う。しかしグリュンワルドの切っ先は、僅かながらも女将軍を傷つけていた。
「はっ!」
突然現れた人外の技にも、グリュンワルドは怯まない。
そのまま人間とは思えぬスピードで剣を振るう。振り下ろす度に女将軍の身を守る氷を削り、ジリジリと詰め寄っていった。
「くぅっ!?」
やがて女将軍はグリュンワルドの猛攻を支えきれなくなり、体勢を崩して舳先へとはじき飛ばされた。
「もう逃げ場はない……死ね」
相手に立ち直る隙を与えずに再び突進した。グリュンワルドの体が霞み、次の瞬間には女将軍の目前に出現した。そしてそのまま、グリュンワルドの繰り出した刃は女将軍の体を貫いた。
「ぐっ……」
白き女将軍は信じられないといった表情でグリュンワルドの剣を見る。そして、「……私は、まだ」と呟いた。
「まだ息があるか」
グリュンワルドは無造作に剣を引き抜く。その感触はいつもと違い、固く無機質なものだった。
「貴様……」
人ではないな、という言葉がグリュンワルドの脳裏に浮かんだ。しかし、だからどうだと言うのだろう。グリュンワルドが殺めてきたのは人間だけではない。獣、自動人形、≪渦≫の化け物。そして、今では自分自身も『人』ではない。
「いや、言うまい。死ねば皆同じだ」
そう言うグリュンワルドの顔には笑みが浮かんでいた。
ビチャリ。
剣を振り上げたグリュンワルドの背後で不快な音がした。何かが粘り気のある水に落ちたような音。本能的に危険を感じて、グリュンワルドは振り返る。
「……っ」
そこには首が切れて片腕が無い死体がいた。それに、脚を失って体に大きな穴を開けた死体も。もはや活動を止めた筈の肉体が、ユラユラと立ち上がってグリュンワルドへと向かってきていた。死の感触に耽溺してきたグリュンワルドであっても、それは脅威の光景であった。
「貴様、何をした。女」
蠢く死体から目を離さずにグリュンワルドは声を上げる。背後から女将軍の鈴を鳴らすような声が響いた。
「……死を、あなたも私に死を見せてくれるんでしょう?」
「何を……」
「さあ、死者達。お前達の手で、さらなる死を生み出しなさい!」
グリュンワルドが剣を構えるのと同時に、女将軍は叫び声を上げた。その声を聞いた眼前の死体が一斉にグリュンワルドに群がる。
「くっ……」
グリュンワルドの振るった剣が一体の死体を吹き飛ばす。死体の動きは遅く、個体で見ればその戦闘力は低い。しかし、恐怖も痛みも知らぬ膨大な数の死体に囲まれては、剣を振るう事もままならない。
剣を振るった右手が死体の腹にめり込む。その右手にいくつもの口が噛み付き、肉を食い千切られる。それを払おうとした左手に死体の骨が刺さって血飛沫を上げる。その血を啜ろうとさらに死体が群がる。
グリュンワルドの肉体は、死体で押し潰されていった。
「………………」
死が迫っていた。
全身の肉を食い千切られる苦痛の中でグリュンワルドは考える。自らが生み出し、楽しんできた「死」によって、今度は自らが死ぬ。
死は平等に降りかかる。
それが今だ。
目を閉じたグリュンワルドの口に自らの血が流れ込む。口の中に鉄臭い血の味が広がった。その瞬間、ボロボロだった体に一瞬だけ力が戻った。生への執着が、他者を踏みにじる愉悦への渇望が突如沸いてきた。
先程まで諦めかけていた脳に活力が漲る。体中から肉が削がれ、片腕は半ば千切れている。しかし、まだ動くことは出来る。
グリュンワルドは力を溜めて体を反転させ、自分の肉体へ群がる死体達を振り解いた。
「死者どもよ、ただの肉塊へ戻れ」
そしてどうにか握られていた剣を振ると、凄まじい剣圧で死者どもを吹き飛ばした。
グリュンワルドは笑っていた。
しかし、精神の高揚とは逆に体は無残な姿を晒していた。剣を持たぬ右腕は肘先が無くなり、片足の大腿部からは白い骨が見えている。
死者との間合いを取ったグリュンワルドだったが、すでに立つことも容易でなくなっていた。装甲猟兵の砲撃が激しさを増し、その衝撃で足下が揺らいだ。グリュンワルドはふらふらと甲板の端まで来ていた。
死者の軍勢が再びグリュンワルドの元に集まり始めていた。聞こえなくなった耳のどこかで、あの女将軍の嬌笑が聞こえたような気がした。
笑みを浮かべたグリュンワルドが残った左腕で剣を構えようとしたとき、死者の軍勢とグリュンワルドの間に砲弾が着弾した。
衝撃で意識が薄れつつ、グリュンワルドは甲板から落ちていった。その四肢の力は抜け、奇妙な形のまま地面に打ち付けられた。
「―了―」
3394年 「虫」 
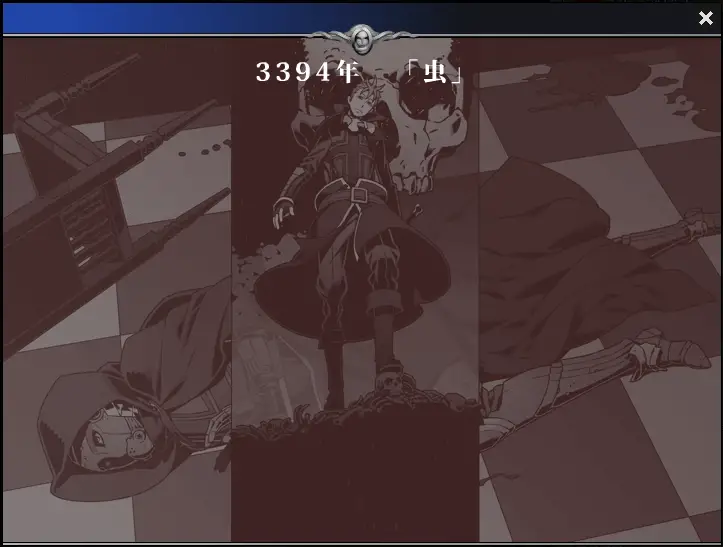
薄暗い居城の中にいるということは、ぼやけた視界でもわかった。薬臭い己の体臭に混じって感じる空気の匂いは、故郷のものだ。
目を覚ましてから長い間、グリュンワルドはその片方しかない瞳で天井を見つめていた。懐かしい天井だった。ただ、こんなに長い間見つめ続けたことは無かった。
混濁する意識は、子供時代へと戻っていった。
彼の記憶の中では、暗く湿っていて孤独な世界だったが、心落ちつく世界だった。他人から気味悪がられ、避けられていたが、何も思い煩うことは無かった。
そこはただ、好きなものに囲まれた、自分だけの世界だった。
グリュンワルドは急に声を上げたくなった。
だが、包帯に巻かれた下顎に感覚は無く、今、自分の口が開いているかどうかもわからなかった。 奇妙にくぐもった、何かが泡立つような音だけが部屋に響いた。
部屋には誰もいない。何の反応も無い。
そして、今度は急な眠気を感じ、目を瞑って眠りについた。
夜中の突然のノックにローフェンは驚いた。ローフェンの地下の研究室を訪れる者などいない。ある一人を除いては。
扉を開けた彼の前に、王妃マルラがいた。
歳を取ってはいたが、未だにその高貴で近寄り難い美しさを保っていた。
「相談があって参りました」
「なんでしょうか、マルラ様」
ローフェンは丁寧に挨拶をした。
「王と王子の為にやっていただきたいことがあります」
マルラは雑然とした地下室を一瞥すると、そう言った。
「詳しい話を聞かせていただきましょうか」
ローフェンはぼろぼろの椅子を出し、テーブルにマルラを招いた。
「こんな場所にあなたが来られるとは。この城の地下にあなたが訪れることなど、決して無いと思っていましたよ」
「忌々しい思い出、と言いたいのですか」
「まあ、そんなところですな」
ローフェンはパイプを取り出した。もう滅多なことでは吸わなくなっていたが、苦手な人物を相手にするときには、つい欲しくなってしまうのだった。
「今度の宮廷会議が三日後にあります。あなたも出席なさるでしょう?」
マルラは話題を切り出した。
「ええ、もちろん」
「王権の今後について、何かしらの話し合いが行われるのでしょう」
既に王の意識は無い。王子が帰還する直前に重篤な事態に陥っていた。そして、グリュンワルドも帰還したが、誰もその姿を見ていない。
「まあ、現状を鑑みれば、そうならざるを得ませんな」
ローフェンは煙を吐きながら、一緒にそう言った。
「王子の様子は既に宮廷内で話題になっています。それと、王の病状は聞いていますか?」
「いいえ、まだ」
「一月も保たないでしょう」
「そうでしたか......。陛下は長く立派な人生を送られた」
ローフェンは目を瞑って背もたれへ身を沈めた。ローフェンと王は、若い頃からよく見知った仲であった。
先代の兄王は、即位後僅か一年で亡くなった。彼が王位に就いてからは、長く相談役として彼を支えていた。
政策や王子達についても、随分と二人で話し合った。ただ、グリュンワルドの追放を決めてからは、彼との距離ができていた。
「ガイウス卿は王権の委譲の話を持ち出すでしょう。グリュンワルドが生きているにも関わらず」
「彼ならそう言い出すでしょうな」
「混乱した国の状況を治めるには、王位に空白があってはならぬと、諸公に訴える気です」
「なるほど」
「だから、グリュンワルドが健在であると示して欲しいのです」
「どのようにして?」
「あなたの技術で彼を立たせ、声を出せるようにしてあげて欲しいのです」
「王妃、あなたは勘違いをなさっておられるようだ。私は義肢職人でも医者でもありませんよ」
「いいえ、やっていただかなくてはなりません」
「いっそ廃王し、諸公に譲られればよろしい。穏便だ」
とは言っても、穏便に事が済まされるとは、当のローフェンも思っていなかった。諸公の誰が王になろうとも不満は出る。そして、その不満は陰謀や内乱を生じさせ、この国を混乱に陥れるであろう。
もちろんローフェンは、そうなればこの国から出て行こうと決めていた。
「今はそんな時期ではありません。もしそうなれば、グリュンワルドも殺されてしまうでしょう」
「今になって母の情ですか?」
「いいえ、王族としての威厳を守りたいのです」
「でしょうな。殿下の放逐の時に、あなたは何も文句を言わなかった」
少々きつい言い方だったが、ローフェンは遠慮などしなかっ た。
「王も王子も、まだ生きています。馬鹿げた話し合いなど、まださせません」
マルラは毅然としたまま、ローフェンの皮肉を無視した。
「殿下を晒し者にするのですか?」
「いいえ。ただ、グリュンワルドが生きているということを、 威厳をもって示せればいいのです。あなたはグリュンワルドを理解し、友人であったのでしょう?」
ローフェンは彼女の強い決意を理解した。それは彼女の、王妃としての、譲れない意志なのだ。
「殿下はどう思っておいでかは存じ上げません。ただ、私が殿下を導こうとしたのは事実だ」
「彼の威厳を守ると思って下されば、それでよいのです」
「威厳ですか......わかりました、やってみましょう。ただし、あなたの望み通りになるかは保証できかねます」
マルラの決意に絆される形になった。
「頼みます、ローフェン」
マルラは地下室から出ていった。彼女の香水の匂いだけが、不釣り合いに地下室に漂っていた。
ローフェンはすぐに地下室にグリュンワルドを運び込み、施術を始めた。
グリュンワルドの身体の損傷は甚大だった。両手両足を失い、右目と下顎も失っていた。気高さを讃えていたその若い肉体は、無残に、そして徹底的に打ち壊されていた。
ローフェンはグリュンワルドの頭に奇妙な機械を取り付け、簡単な意思疎通ができるようにした。脳へのダメージも相当なものであろうと、ローフェンはみていた。
「声は聞こえていますか?殿下」
くぐもった唸り声と共に、ローフェンの見ていたコンソールに色とイメージが浮かんだ。
「なるほど。痛ましいお姿ですが、これも一つの運命です」
ローフェンは、これから彼に施す施術について説明した
「わかっていただけましたか?」
奇妙な光がコンソールに浮かんだ。それを見たローフェンは、 一瞬、当惑の表情を浮かべた。
「......それがあなたのお望みですか。 いいでしょう。私の最後の奉公とさせていただきます」
ローフェンは冷静だった。
「仰せのままに」
そう呟くと、ローフェンは眼鏡を掛け直し、作業を始めた。
昼夜を問わぬ二日間で、ローフェンはグリュンワルドの施術を終えた。
控えの間に、家臣達が謁見のために集まっていた。そこで彼らは宮廷会議に王子が出席すると聞き、一様に驚きを隠さなかった。
家臣達が議事堂に入ったときには、既に王子が席に着いていた。
王子はフードを目深に被り、片目だけを出した奇妙なマスクを着けていた。両手は彫金で装飾された王族の甲冑を纏っている。
一瞬設しむ一同だったが、その瞳の色は確かにグリュンワルドのものだった。
諸公は王子の前で感嘆や賛美の声を上げた。ただ、一様に、その不気味な王子の姿に警戒していた。
全員が席に着き、奇妙な沈黙の時間が流れた。
ガイウスが堪らず言葉を切り出す。
「殿下が無事のご帰還をなさったこと、その無事なお姿に臣民も必ずや歓喜のうちに......」
切り出したガイウスの言葉を、グリュンワルドはその鉄の腕で不器用に制止した。
そして、机に置いた紙をガイウスに向かって指し示した。
ガイウスはその紙を取り、読み上げた。
「私は死地から帰ってきた。そこで得たものを皆と分かち合いたい。是非とも、その味を諸公らに味わってもらおうと思う」
ガイウスは詰まりながら、そして意図を計りながら、辿々しく 読み上げた。
ガイウスが読み終えると同時に、グリュンワルドは両腕に仕込んだ散弾を、左右に並んだ諸公に一度ずつ撃ち放った。爆音と硝煙、真っ赤な血煙が部屋を満たした。グリュンワルドの真横にいたガイウスに弾は当たらなかったが、粉々になった家臣 肉片が彼の顔一面に飛び散った。
「狂いましたか!殿下!」
ガイウスがそう叫んだ時、グリュンワルドは機械で作られた声で笑っていた。ただそれは、何かが地獄で着られているような、奇妙なぶくぶくという鈍く低い響きでしかなかった。
そして、怯えて立ち尽くすガイウスの頭を、腕に仕込まれた刃で顎から頭頂に貫いた。
左右に並んでいた家臣の中で生き残った四人が、這々の体でグ リュンワルドから逃げようとする。それを逃さんとするグリュンワルドが椅子から立ち上がった。が、膝から下の義足が上手く機能せず、そのまま床に崩れ落ちた。しかし、そのままグリュンワルドは膝と手で這うように彼らを追った。
そして、義手の刃を杖のように使って立ち上がり、逃げる四人の背中を切り裂いた。
血の海となった議事堂で、奇妙にねじ曲がった四肢を揺らしな がら、グリュンワルドは笑っていた。まるで子供が悪ふざけを成功させたときのように身体を震わせ、のたうち続けていた。
グリュンワルドは衛兵によって捕らえられた。そして義手義足を取り外され、元の居室に幽閉された。
今回の凶事はまだ城外には知らせていなかったが、既にローフェンは城からいなくなっていた。とてつもない混乱がこの国を襲うだろうということは、マルラにもわかっていた。
「なぜ、あんなことを」
グリュンワルドは血の薄く滲んだ白い包帯に包まれて、囲いのあるベッドに寝かされている。
グリュンワルドの反応は無く、眠っているように思えた。
「なぜ.......王も私も、なぜこんな目に遭わねばならぬのです」
マルラは泣いていた。
「王家の尊厳も、輝かしい歴史も、全てあなたが台無しにしてしまった」
呟きが部屋に低く響いた。
「私や王が悪かったのですか?あなたの望みは何だったのです?」
ふと目をグリュンワルドに向けると、彼の目は開いていた。そしてその目は、マルラには笑っているように思えた。いや、はっきりと笑っていた。
マルラは胸元から鋭く細い短剣を取り出し、グリュンワルドの胸を突いた。
虫のようにのたうつグリュンワルドに、何度も何度もその短剣を振り下ろした。赤い斑点が包帯に巻かれた身体に次々と浮かび、花が開くように広がっていった。
王妃の顔も、手も、何もかもが真っ赤に染まっていた。
グリュンワルドの血はベッドに満ちると、床へと一滴、落ちていった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ