コンラッド
【死因】
【関連キャラ】
3243年 「神秘」 
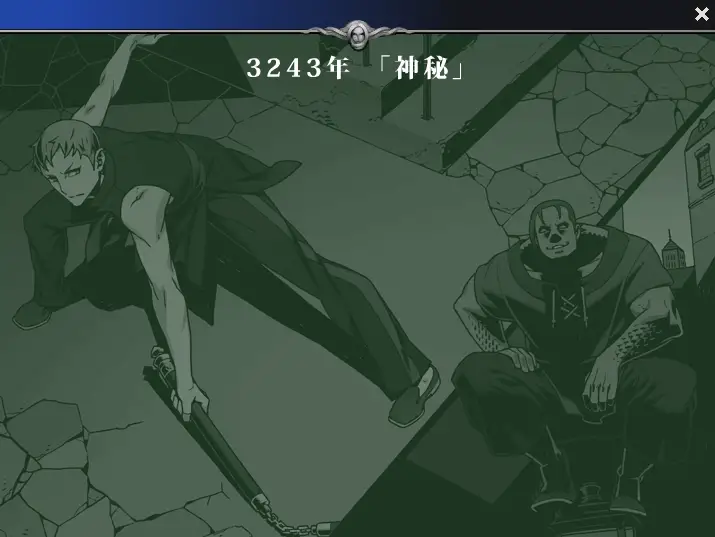
有機化合物と塩基の混合液に満たされた楕円形の箱の中に、コンラッドは納められていた。
外には何人かの人の気配があり、始終何か会話を交わし、時には怒鳴るような声さえも聞こえてきた。
中から外の様子はわからない。そもそも、目を開けていられないほどにコンラッドは傷つき、衰弱していた。
手足の感覚はなく、身体が上を向いているのが下を向いているのかさえもわからない。
覚束ない感覚の仲、コンラッドは昔の夢を見た。
「ぐぞ……」
顔の下半分を赤黒く染めた筋肉質の大男が、壁にもたれるようにして呻いていた。
「ぬるい」
コンラッドはその男を一瞥すると、一言吐き捨てて薄暗い路地を後にした。
スラムで生活していたコンラッドにとって、暴力沙汰は日常茶飯事であった。
自身の詳しい出自は知らなかった。物心ついて時から、養父と共に棍術を主体とした武道と酒に明け暮れていた。
「オレはよぉー、首都じゃ勇名な武道家だったんだよぉー。おらぁ、酒だ、もっと酒もってこいよぉー」
「いい加減にしろ、もう酒はないぜ」
「アァン?ケチつけんだったらオレに一回でも勝ってからいえよぉー」
酒に酔った戯言と思ったことも一度や二度ではないが、養父の強さは確かなものであった。事実、養父が亡くなるまでコンラッドは彼から勝利を奪うことはできなかった。
「おめーにオレの技術全部教えてやっからよぉー、首都の連中を見返してやってくれよぉー」
これもまた養父の口癖だった。どうしてスラム暮らしの転落人生を歩んだのかはわからなかったが、その言葉には悔しさや憎しみが募っていた。
だが、コンラッドが養父の言葉に従うことはなかった。彼にとって養父の技術は、スラムで生きていくためのものに過ぎなかった。
力には力で対抗した。そうする内に、コンラッドは誰も彼も叩きのめす凶器と化していった。何かが憎かった訳ではない。生きるためにはそうする他なかった。
「もし、そこの若者よ」
路地を出てすぐ、嗄れた声に呼び止められた。声のする方を睨み付けると、声に違わぬ小さな老人が立っていた。
「あん?」
「道をお尋ねしたいのですが、アキムという者がやっている薬屋の場所はご存知ですかな?」
「アキム……、ジジイ、あの男の知り合いか?」
「えぇ、そんなところです」
老人はにこやかに答えたが、コンラッドは眉を顰めた。つい二日前、コンラッドは薬屋のアキムと揉め事を起こしたばかりであったからだ。
「悪いなジジイ。俺はアキムの野郎に一杯食わさないと済まなくてね。少々痛い目を見てもらおうか」
この老人がアキムの客であるならば、少々痛め付けてアキムの商売を邪魔をしてやろうと。そんな程度に考えた。
「おやおや、血気盛んな若者だ」
老人はコンラッドの態度に鷹揚に笑った。ただ笑っているだけなのに、コンラッドは見下されたように感じた。
「調子に乗るな、くたばり損ないが!」
ただ一撃、棍棒で殴りつけるだけ。それだけでこの老人は事もなく倒れる。そのイメージを思い描きながら、コンラッドは腕を降った。
その時の老人の目はコンラッドを見据えており、またコンラッドの目も老人を捉えていた。
「ぐ……」
「どうかしましたか?得物が届いていないようですが」
武器が老人に届かない。まるで全身が見えない鎖に拘束されたように、どうやっても動かすことができなかった。
「少々、心の鍛錬が足りないようですね」
老人は事も無げに言うと、コンラッドに近付いて腕を取り、軽々と背後へと投げ飛ばした。
地面に叩きつけられて呆然としていたコンラッドだったが、暫くして身体の自由を取り戻した。立ち上がったときには、既に老人は立ち去った後であった。
「な……にが……」
何もできずに敗北することは、養父以外では初めてであった。金縛りのようなものから解放されると、その足ですぐにアキムの店へと向かった。
不可思議な現象を目の当たりにしたコンラッドは、その力の秘密を知りたくなった。となれば、唯一の手掛かりは老人の知り合いらしいアキムから聞き出すしかない。
揉め事を起こしたばかりで癪ではあるが、それよりも老人への好奇心が勝った。
薄汚れた店内には、何に使うのかわからない草や調合された薬による嫌な臭いが立ち込めており、コンラッドは顔を顰めた。
「相変わらず酷い匂いだ」
「何の用だ、罵倒するだけなら帰ってくれ!」
「さっきお前のところに身なりのいい小さなジジイが来ただろう。アレは誰だ?」
「あぁ?人に物を聞く態度じゃねえな。情報が欲しけりゃ、よこすもんよこしな」
アキムは下碑た笑いを浮かべながら手を差し出す仕草をした。コンラッドは舌打ちすると、アキムの顔面に持っていた金を投げ付けた。
アキムから老人についての話を聞き出した翌日、首都ルーベスへと赴いた。
普段の格好では目立つため、以前誰かから奪い取ったそれなりに上等な服を着込み、そも首都の人間であるかのように歩いて目的地を目指した。
アキムから聞き出せたのは二点だけだった。老人はウェルザーという名であること。そして、首都ルーベスにある大聖堂で祭司職に就いているということであった。
ミリガディアはこの世界に《渦》が発生して少し経った頃に、ヨーラス大陸南部に伝わる『命の神』を信奉する宗教が母体となってできた国である。
スラムに暮らす者や渦から逃れてきた難民は例外としても、国民は基本的に皆『命の神』を祀っている。
ウェルザーという老人が祭司を勤める大聖堂も、この宗教施設の一つであった。
大聖堂の中に入ると、祭祀用の服を身に纏ったあの老人が、赤子を抱えた女に何やら説いているところだった。
「ありがとうございます!ありがとうございます!」
「神は行動するもに必ず加護を授けます。あなた自身が救われる道を選択したからこそその結果なのです」
ウェルザーらしき老人は、穏やかな笑みで親子を見送った。
「おや、あなたは昨日の。何かお悩みごとでもあるのですか?」
親子がコンラッドの横を通り過ぎたのを見計らい、備え付けの椅子に腰掛けようとしていたコンラッドをウェルザーが呼び止めた。
遠目からどのような人物か観察するつもりだったコンラッドは小さく溜息を吐くと、ウェルザーに近付き、率直に疑問をぶつけることにした。
「昨日アンタが使った妙な力はなんだ?」
「おやおや、何かと思えば。わたしは何もしておりませんよ」
コンラッドの失礼な態度にも、にこやかな笑みを崩さずにウェルザーは答えた。その余裕そうな態度に、コンラッドは苛立ちを募らせる。
「そんなはずはない。あの時、オレは金縛りにあったように動かなかった。あんなことは初めてだ」
「ふむ……例えばそれに答えがあったとして、それを聞いたあなたはどうするおつもりですか?」
「アンタには関係のない話だ」
「そう仰られても、あなたの望む答えをわたしは持ち合わせておりません。あなたの言う『力』とやらは持っていないのです」
「なら、あの力は一体なんなんだ」
「ほんの少しだけ、わたしの方があなたよりも心が強靭であった。それだけでしょう」
「どういう意味だ?」
「あなたは畏怖したのです、神に仕える者に。その心に。心の鍛錬を怠っていなければ、そのようなことは起こり得なかったでしょう」
「まやかしだな。精神論で片付くようなものではないはずだ」
「そのようなことはありません。我々人間は神から授かった心で生きています。その心を強くすることが我々の使命です。武道を志すならば、なおさら大事にすべきことです」
「結局は神か」
上手くはぐらかされたな。そうコンラッドは思った。この小さな老人はやはり何か隠しているのだろう。
あの力を神を信奉することで手に入れたのか、それとも元々持ち得たものかはわからない。だが、あれは確かに『心の鍛錬』で済ませられる現象ではなかった。
その日から、コンラッドはウェルザーが見せた力の秘密を探るべく、大聖堂に足繁く通うとうになった。
宗教的なことはさっぱりわからなかったが、ウェルザーの説教には何か不思議な力があるように感じられた。
ウェルザーの言葉を理解するために大聖堂で配布している教義の書かれた本を手に取り、『命の神』について少しずつ学ぶようになった。
ある日、コンラッドは『命の神』の伝承が書かれた本を読みながら大聖堂への道を歩いていた。
伝承自体は御伽噺もかくやという内容であり、さほど興味を惹かれるものではなかったが、これもあの力を手に入れるためと、頭に入れていた。
本の内容に注視するあまり周囲への注意を怠ってしまったのか、路地を通り過ぎるときに誰かの腕とぶつかった。
「ぶつかっておいて謝罪もなしかよ、舐めてんのか? え、おい!」
気にすることもないとそのまま通り過ぎようとしたところ、やけに響く声で呼び止められた。
そこでようやっと本から目線を外して相手を見やる。それは以前、完膚なきまでに叩きのめした音も知らぬ大男だった。
つい何週間か前にへし折った筈の鼻が無事なところを見ると、あの時は随分と手加減してしまったようだとコンラッドは思った。
「邪魔だ。またその鼻っ柱をへし折られたいか」
「言ってくれるじゃねぇかよ。本なんて読んで、お前たちとは違うんですってか?」
「オレが何をしようと、お前には関係のない話だ」
コンラッドは本を懐にしまうと、流れるような動作で腰に携行している三節棍を振り抜いた。
勢いよく振り下ろされた棍棒の先端が大男の顔面を捉えてように見えた。しかし、大男はその場にいなかった。下品な笑いだけがコンラッドの耳に届く。
「何!?」
「ここだよ、ここ。本ばっかり読んで頭でっかちにでもなったのか?」
頭上から響く声にコンラッドは上を見上げた。大男は裏路地を照らすために設置されて街灯の天辺に器用にしゃがんで、コンラッドを見下ろしていた。
更に大男は揺れる街灯からコンラッド目掛けて飛び降り、全体重を掛けて圧し掛かってきた。
「ぐっ」
全身を地面に打ち付けたせいで息が詰まる。衝撃で明滅するような視界を振り切って相手の鳩尾あたりに膝蹴りを当て、相手の動きが止まったその一瞬の隙を突いてなんとか脱出する。
「逃げてんじゃねぇよ」
腹を押さえながら立ち上がる大男の容姿が、煙を上げながら変貌していくのが見て取れた。顔や肌の表面が突起物にびっしりと覆われていく。
爬虫類めいた容姿に変化した大男は声だけで笑った。顔の作りが変化したことで、どういった表情をしているのかは読み取れない。
姿が変化しようとも無敵という訳ではないことは、先程の一撃で判明していた。
逃げ切ることはできないと思い、コンラッドは三節棍を連結して構え直した。
大男は体格に似合わない素早い動きでコンラッドとの距離を詰めると、鱗に覆われた右腕で殴り掛かってくる。
コンラッドは棍棒でその拳を薙ぎ払うも、相手に腹を蹴られて壁にぶつかった。
「いつまで涼しい顔をしてられるか、見ものだな!」
大男は大きく笑いながら、体制を立て直しつつあるコンラッドを殴り飛ばした。
再び姿勢を崩したコンラッドに対し二度、三度と容赦なく殴り付けてくる大男だったが、コンラッドは反撃の機会をじっと待っていた。
「お前ごときに倒される気はない」
「いい加減、やられちまえよ!」
段々と顔を狙っていた大男の拳の位置にずれが生じてきた。大男をじっと見ると、目の焦点が合っていないことにコンラッドは気が付いた。
「ガアァァ!」
とうとう大男は咆哮を上げると、あさっての方に向かって腕を振り上げた。その隙を見たコンラッドは大男に体当たりし、広い通りへと転がり出た。
「おや……」
転がったその先にはウェルザーがいた。小さな薬臭い袋を持っているところを見ると、アキムのところからの帰りのようであった。
「逃げろ!こいつは危険だ!」
コンラッドは無意識のうちに叫んでいた。コンラッドにも矜持というものがあった。例えいけ好かない首都の住民であれ、個人の闘争に巻き込む訳にはいかなかった。
緩慢な動きで大男は立ち上がると、ウェルザーとコンラッドを区別できなかったのか、ウェルザーに向かって拳を振り上げた。
「我を失っているようですね。いけないことです」
ウェルザーは異様な姿の大男に動じることはなかった。その小柄な体躯に見合う動きで、大男の攻撃を回避していく。
コンラッドは大男の視線がウェルザーに集中しているのを見ると、弾かれたように動いた。
棍棒を大男らの背後から振り下ろし、その脳天に叩き付けた。大男はそのまま地面に倒れ付した。爬虫類のようだった外見は、すっかり人のそれを取り戻していた。
荒い息で大男をじっと見つめるコンラッドも地面に座り込んでしまった。殴られた部分は酷く傷んでおり、立っているのは限界であった。
「大丈夫ですか?必要なら病院で手当をしましょう」
そこへウェルザーが特に慌てる様子もなく近付いてきて、コンラッドを見下ろしていた。
異形と化した人間を見ても動じないこの祭司は、どうあっても只者ではない。
「逃げろと言ったはずだ……」
「ここで逃げれば、あなたはもっと酷い目に遭っていたでしょう。覚悟を持って動く者を神は見捨てません。わたしは教えに従って行動したまでのことです」
「あんたは一体なんなんだ?」
「この世に生きるもの全てに大善なる愛を注ぐ神の教えを広めるだけの、ただの祭司です」
ウェルザーは人の良さそうな笑みを浮かべてそう答えると、コンラッドに手を差し伸べた。
「祭司が嘘を吐くもんじゃない」
この小さな老人の秘密を絶対に暴いてやる。コンラッドは決意を新たに、その枯れた手を取って立ち上がった。
「―了―」
3244年 「異能」 

ウェルザーに誘われたコンラッドは、聖ダリウス大聖堂を訪れていた。
ここはミリガディア王国の中心であり、当代の大君が神に祈りを捧げる場所として、聖地に定められている。
「何処へ行くのかと思えば。こんな場所に興味はないぜ」
「そう言いなさるな。命の神の教義を学ぶのに、最も適した所ですよ」
「勘違いするなよ、ジジイ。オレは神なんぞに興味はない。アンタの力を知りたいだけだ」
「何度聞かれても困りますよ。私は貴方が思っているような力など、持ってはおりません」
困惑の言葉を口にするウェルザーだが、表情はにこやかなまま崩れていない。そのことが一層、胡散臭さをコンラッドに感じさせた。
こないだの事件で交流を作ることができたものの、ウェルザーの持つ力の正体は依然としてわからなかった。何度かウェルザーの私生活に探りを入れようとしたが、ウェルザーは年齢に見合わぬほど鋭敏な感覚を持っているようで、微塵の隙も見せることはなかった。
ウェルザーに言われるがまま付いてきたのも、大聖堂で教えを学ぶためではなく、ウェルザーの秘密を暴くためであった。
大聖堂では子供から年寄りまで、あらゆる世代の人間が、最奥に安置された命の神の像に祈りを捧げていた。そして、荘厳なオルガンの音と聖歌隊の歌う賛美歌が大聖堂の中に響いた。
コンラッドはその様子をぼんやりと眺めていた。命の神に傾倒していないコンラッドにとって、大聖堂にいる人々の姿は異様なものに映った。
オルガンの音と賛美歌がそれを助長していた。異世界に来たような感覚がコンラッドを支配する。
「おい、ジジイ……しまった!」
大聖堂の空気に気を取られた一瞬に、ウェルザーはどこかへと消えていた。辺りを見回してウェルザーの姿が無いことを確認すると、コンラッドは外へと出た。
こんな所に付き合わされた挙句に見失うなど、あってはならなかった。
夜も更けてきた頃、ようやくウェルザーの姿を見つけることができた。だが、ウェルザーの様子はいつもと違うように感じられた。何かを警戒しながら、足早に進んでいく。
コンラッドは足音や衣擦れの音にさえ細心の注意を払いながら、ウェルザーの後を付けた。暫くすると、聖ダリウス大聖堂の裏手にある場所へと出た。
注意深く床を探ると、回転式の取っ手が姿を現した。音を立てぬように取っ手を引っ張り上げると、その下の地下へと続く階段があった。コンラッドは迷わずその階段を下りる。階段を降り切った先には細い通路があり、通路を歩いて行くと広い場所に出た。
周囲はやはり薄暗く、神経を研ぎ澄ませて周囲を注意深く見回した。コンラッドに耳に小さく空気を切る音が聞こえた。少しずつ大きくなるそれは、徐々にコンラッドに近付いてくる。
コンラッドは三節棍を音のする方向に向かって振り下ろした。同時に金属同士がぶつかる鈍い音が聞こえる。三節棍が弾かれる衝撃があった。
「ケケケケっ!」
コンラッドは目を見開いた。以前にスラムで襲撃を受けた爬虫類のような大男が、鋭い鉤爪を振り翳しながら殴り掛かってくる。
三節棍で鉤爪を弾き、同時に距離を取る。と、爬虫類の大男の後ろにもう一つ、蝙蝠のような人影が見えた。時を移さずに、羽ばたく音が耳鳴りとなってコンラッドを襲う。
「なんだ……これ……は」
耳障りなその音はコンラッドの脳を強く揺さぶった。コンラッドの動きが鈍ったところに爬虫類の大男が迫る。コンラッドは三節棍を連結して大男の懐に潜り込むと、大男の腹に向けて棍棒を突き出した。
「ぐげぇ……」
大男が呻く。更に棍棒を回転させながら、今度は大男の首を打ち据えた。よろめく大男から離れると、次は蝙蝠の男を迎撃しようとする。
叩き落とそうと近付いて棍棒を振るうも、蝙蝠の男は遠くへ飛翔して逃げる。耳障りな音はどんどん強くなり、ついにコンラッドはよろめいた。その間隙を蝙蝠の男に突かれて、体当たりをまともに喰らってしまった。コンラッドは受身も取れずに倒れ込む。
そこからは為す術もなかった。爬虫類の大男の鉤爪や蝙蝠姿の男の牙が、容赦なく何度もコンラッドに突き立てられた。
「そこまでにしておけ。この男は吾が預かる」
不意に、ウェルザーの声が辺りに響いた。
「ギュスターヴ様!」
「なにゆえこの男を気に掛けられるのですか!?」
ウェルザーはギュスターヴと呼ばれていた。しかし、意識を失いかけているコンラッドには、その理由を考える余裕はなかった。
「この男を唯の人間を侮るでない。この男は吾を良く観察しておったわ。そして、とうとう此処までやって来た」
ウェルザーが倒れ伏すコンラッドの前にしゃがみ込んだ。ぎらつく鋭い目には、普段の物腰の柔らかさは微塵も感じられなかった。
「どうする、コンラッドよ。吾と共に来るか、それともこのまま死に果てるか。選ぶがよい」
「し……に、たく……な……」
朦朧とする意識の中、コンラッドはそう答えた。
コンラッドの目の前には、あの蝙蝠のような男がいた。腕を翼に変化させて天井に張り付いている。
――ウェルザー、いや、ギュスターヴの治療を受けたコンラッドは、驚異的な回復力によって動けるようにまでなっていた。
サガイは目を細めてコンラッドに飛び掛かる。コンラッドは三節棍をサガイの翼めがけて振るった。サガイは翼に三節棍が当たるすんでのところで体勢を変えて地面に着地し、再び飛び上がる。
コンラッドはその場でじっと待った。飛び回る相手に近付くのは難しいことを、前の戦闘で学んでいた。
三節棍を棍棒状態にしてサガイの行動をじっと見つめる。集中すると同時に、頭が熱くなるような感覚があった。
ケタケタと喧しく笑いながら蝿のように飛び回る蝙蝠野郎を、どうにかして封じ込めたい。コンラッドの頭にはそれしかなかった。
喧しい笑いがコンラッドに耳を掠めたその瞬間、コンラッドは素早く三節棍を分離して振り抜いた。
そのままサガイの首に三節棍を巻きつけると、ありったけの力を込めて締め上げる。
「神よ……。憤怒の力をオレに与えたまえ!!」
コンラッドは無意識に呟いていた。同時にサガイの姿が人の姿へと戻ってゆく。サガイは驚愕しながら藻掻き続けたが、首から嫌な音をたてると同時に力を失った。
人の姿に戻ったサガイは崩れ落ちると、それきり動かなくなった。嫌な音を立てた首は有り得ない方向に曲がっており、瞳孔は開ききっていた。
「新しい仲間の誕生だ。歓迎しよう。コンラッド」
別の男――クロヴィスと呼ばれていた――の声が響き渡る。
「今は貴方に仕えましょう。オレに備わった力の意味を知るために」
コンラッドはギュスターヴの前に進み出て跪いた。ギュスターヴが目を細めるのが、一瞬だけ視界に映った。
それから暫くのときが過ぎた。コンラッドはローゼンブルグの山岳地帯にあるルピナス・スクールで、祭司として全てを任されていた。
ルピナス・スクールは所在こそグランデレニア帝國だが、全権は組織が握っている。その実態は、《渦》の侵蝕によって訪れるであろう世界の滅びを乗り越えることができる『超越者』を育て上げるための機関であった。
――大善世界の実現――。ギュスターヴは世界の滅びを乗り越えた先の世界をそう称し、それに向けて準備を進めていた。
ギュスターヴの志を胸に打たれた同志や出資者達は率先して自らの子供をスクールに入れ、過剰なまでの思想教育を行っていた。
「祭司様、ご相談したいことが……」
「コンラッド先生」
「祭司様、聞いてください」
命の神の教義、ギュスターヴがウェルザーとして話していたことを理解していったコンラッドは、スラムで荒れ果てた生活を送っていた時とは比べ物にならない程に柔和になった。
と同時に、命の神の教義はスクールの子供達を親とは別の方向から支援するのに大いに役立った。
子供達の中でも特に熱心に聖堂に通う生徒に、カレンベルクとビアギッテの二人がいた。命の神の教義に感銘を受け、コンラッドが話すことの意味を理解しようとする二人の姿は、とても好ましいものに映った。
自分の話を熱心に聞く。そういう行いをされるのは悪い気はしないということを、コンラッドは生まれて初めて知った。
「コンラッド、カレンベルクが出奔した件は知っておるな」
「存じております。ギュスターヴ様」
コンラッドは聖ダリウス大聖堂の最深部に呼ばれていた。
カレンベルクはルピナス・スクールの『教育』と『改造』を一身に受けた、新たな超人の第一号となる予定であった。
だが『教育』は失敗し、パートナーとなるビアギッテと共に出奔を企てた。
ビアギッテは『教育』の甲斐あってカレンベルクの出奔を阻止しようと奮闘したが、あと一歩のところでカレンベルクを逃してしまったとの報告を受けている。
「奴は失敗作だ。早急に始末せねば、吾らの計画に支障が出るは必至。コンラッド、お主ならどうする?」
コンラッドはビアギッテによく似た姿の超人をスラム近くの聖堂に置き、囮とした。
本物のビアギッテは聖ダリウス大聖堂に移され、彼女に続く超人のシンボルにするため、更なる『教育』を施すことになった。
スラムの聖堂にバイオリンケースを携えたカレンベルクがやって来た。
コンラッドはビアギッテの振りをした超人と共にカレンベルクを迎え撃つ。
「私の教育は失敗だったようだな。神の名の下に、私が直々に裁きを下してやろう」
「―了―」
3278年 「遺物」 
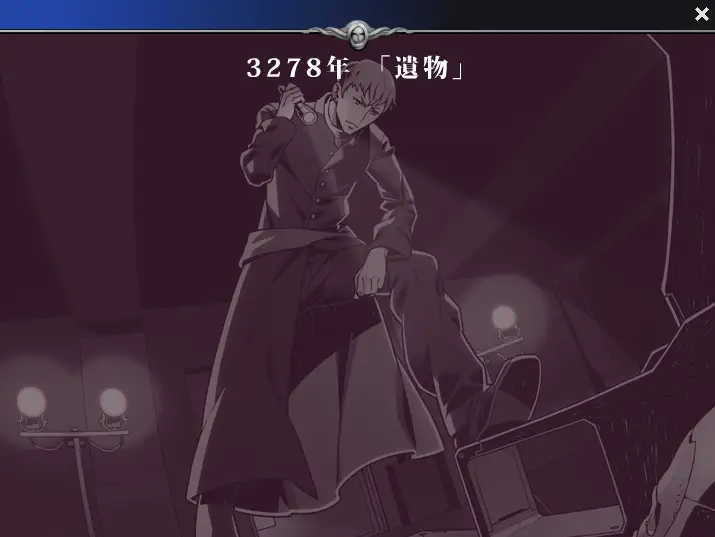
カレンベルクのバイオリンの音がコンラッドの身体に響く。
一瞬だけ身体が束縛されるような感覚があったが、コンラッドはそれを不屈の意思で跳ね除ける。
「甘い!」
振り抜いた棍はかカレンベルクを完璧に捉えた。
「がっ……ひ……」
カレンベルクは悲鳴とも呻きともつかない声を吐き出しながら、床に倒れ伏す。
だが、気を緩めるような暇は無い。カレンベルクは最新かつ最高の技術によって生み出された超人だ。当人が気付いていないだけで、あらゆる能力に於いて非凡の才を持っている。
事実、カレンベルクは必死の形相でありながらも正確にコンラッドの力量を測り、攻撃の隙を窺っていた。
しかしながら、戦闘の経験という一点に於いて、コンラッドはカレンベルクを遥かに上回っている。カレンベルクの立ち回りを確認しながら棍を振るうことで、彼を聖堂の最奥へと誘導していく。
もうカレンベルクに逃げ場はない。確かにそうだった。
「神の名の下に滅せよ、カレンベルク!!」
コンラッドの声とバイオリンの音が重なったその時だった。
体中の穴から暖かいものが溢れ出る感触があった。今の今まで言うことを聞いていた身体に力が入らない。
体内から流れ出るそれが血であると気付いたときにはもう遅かった。コンラッドは全身に走る激しい痛みと共に崩れ落ちた。
コンラッドは歴戦の猛者である。決して油断はしなかった。ただ、カレンベルクの生み出すバイオリンの音が、想定を遥かに上回る速度でコンラッドの体組織を破壊しただけだった。
冷たい目がコンラッドを見下ろす。
「コンラッド祭司、ビアギッテは何処にいるのです?」
ザジの弦を弾き、カレンベルクは問う。脳髄を直接揺さぶられる感覚がコンラッドを襲う。
「ビアギッテ、は……聖……ダリウス大聖堂に……いる……」
息も絶え絶えのコンラッドに止めを刺すことなく、カレンベルクは聖堂を去っていった。
それは、尊敬していた祭司への最後の恩情だったのかもしれない。
――やはり、奴は失敗作だな――
コンラッドは嘲笑して呟いたつもりだった。だが、声は音にならず、代わりにゴボリと培養液が泡を立てた。
目を開くが、周囲を伺うことができない。
誰かの声が遠くから聞こえた気がした。外が俄に慌ただしくなる気配がする。
培養液が流れ落ち、次第に五感がはっきりとしてくる。
再生槽の蓋が開く。白衣を着た研究者達が目の前で跪いていた。
己がカレンベルクを止められなかった所為で、この様な事態になってしまった。その思いがコンラッドを支配した。
「目覚めたようだね」
療養のために宛がわれたコンラッドの部屋に、クロヴィスがやって来た。
彼の姿を認めると、コンラッドは跪き、頭を垂れた。
「申し訳ありません。此度のことは全て私の落ち度です。そのような処罰でも受ける覚悟です」
「カレンベルクの件か?それについては組織全体の落ち度だ。それに処罰をするつもりなら、君は今ここで僕と対面していないよ」
「勿体無きお言葉」
「それよりも、君が目覚めてくれたことは組織にとって僥倖だ。ギュスターヴの治療を進めるための手が足りない」
「はい。これも神のお導き。私めを何なりとお使い下さい」
コンラッドの口から自然と言葉が漏れた。
力を求めていた己に更なる力とそれを満足に行使できる場を与えてくれたギュスターヴに対し、恩を返す時であると感じていた。
そのために己は生き長らえたに違いない。神というものを信じ切れていなかったコンラッドが、神の采配というものを信じた瞬間であった。
コンラッドは新たな決意を胸に、ルピナス・スクールのあるローゼンブルグに戻った。
そして、未だ超人として目覚めていないスクールの生徒達に対して『超人改造』を施すことを、スクールの教師達に宣言した。
「コンラッド祭司、この決定は些か性急なのでは?」
「これは神によって定められし使命だ。彼等の中に首領を復活せしめる鍵が眠っているやも知れぬ」
「で、ですが、未熟な者も少なからずおります。超人候補が死んでしまっては意味がありません!」
「ならば、教育に耐えうる者を見つけ出せ。これは神が我らに与えたもうた試練である」
首領の復活。その言葉に逆らえる者は、スクールの中にはいなかった。
粛々と超人改造が進む中、コンラッドはいくつかの計画を開始させた。
「第八階層の聖堂建設はどうなっている?」
「滞りなく進んでおります。それと、最下層の森林地帯における施設の建設も予定通りです」
「わかった」
ローゼンブルグの上級階層にもルピナス・スクールの賛同者は存在するが、それはごく一部に過ぎない。そのため、上層に聖堂を建設することで、魔都を支配する上級階層の人間を更に取り込もうとした。
加えて、ローゼンブルグの下層で暮らす孤児を救うためという名目で、施設の建設にも着手した。こちらは評議会や上層の慈善活動家に対して、ルピナス・スクールの母体となっている宗教が極めて慈善性の高いものであることを印象づける目的があった。
しかしその実体は、ギュスターヴ復活のための実験体として、孤児を効率的に集めることである。
いずれの計画も、協力な障壁によって渦から守られた魔都に残る高度な科学を全て組織の手中に収め、組織の更なる発展を促さんとしてのことであった。
「コンラッド祭司、ローゼンブルグ評議会から聖堂建設の詳細な理由を提示せよという勧告が届いております」
「目障りな奴等だ」
コンラッドはローゼンブルグを実質的に支配している評議会の横槍に、不快感を隠さずに吐き捨てる。
スクールの賛同者によって計画自体は進んでいるものの、ローゼンブルグ評議会はコンラッド達の動きを警戒し始めていた。
「如何いたしましょう」
「今は奴等に従う。事を急いで警戒を強められれば、こちらが不利となるのは目に見えている」
「では、詳細資料を用意いたします。会見を求められた場合はどうなさいますか?」
「私が直接出向こう。そうしなければ奴等は納得しまい」
「では、そのように」
評議会の人間との会見を終えたコンラッドは、その足で下層に建設中の施設へ赴いた。
建設工事で地下を掘り進めていたところ、古い遺跡とその遺物を発見したとの報告を受けたためだ。
「コンラッド祭司、こちらです」
「規模はどの程度だ?」
「深さは10アルレほど、広さは現在調査中です」
現場責任者に案内され、掘り抜かれた地面へと降りる。広く掘られた地面の四分の一ほどが、古い人工物のようなもので覆われている。
その一角には穴が空いており、下へ降りるための梯子が掛けられていた。
「この下か。中は?」
「先遣隊により、ある程度の安全は確保されています」
その言葉に頷くと、コンラッドは責任者と共に内部へと入る。壁には明かりが灯りそうな装置があったが、動かすための動力が切れているらしく、灯りが点くことは無さそうだった。
責任者を先頭に、遺物の置かれている部屋へと案内される。
その部屋には、薄暮の時代の物と重しき機械が大量に残されていた。だが、どれもこれも長い年月の内に機能を失っているようだった。
その中に、人のような姿をした奇妙な格好の機械がいくつかあった。
一つは完全に人型をしていたが、人工筋肉や衣装と思われるものは風化しており、基礎フレームのようなものが剥き出しになっていた。
「動くのか?」
古ぼけてはいたが、精巧な機械であるということは誰の目にも明らかだ。だが、コンラッドにはそれ以上のことはわからない。
「何にせよ、ここではどうにもできんな。運び出して本部に送れ。クロヴィス様かユーリカ様なら何かおわかりになるかも知れぬ」
「承知しました。おい、そいつを運び出せ」
責任者の指示で、作業員がその機械を外へ運び出そうとした時だった。
「楽園……を……創造……せよ……」
「ひぃっ!?」
作業員は突然のことに驚き、妙な悲鳴と共に機械を床へ落とす。
「我らは……使徒……幸福……世界……我ら……の……楽園……」
奇妙な人の姿をした機械は、床に打ち付けられてなお、壊れた記録装置のように雑音交じりの声で喋り続けるのだった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ