シャーロット
【死因】
【関連キャラ】
3274年 「別れの日」 

教会の音楽室に賛美歌を練習する声が響きます。私も聖歌隊の一人として練習に参加していました。
一週間後に行われる教会主宰の祭事で歌う、賛美歌の練習の最中です。
暫く歌い続けていましたが、一瞬だけ違和感が脳裏を襲い、声が裏返ってしまいました。
シスターの伴奏が止まり、周囲の視線が一斉に私に集まります。
恥ずかしくて、顔がとても熱くなりました。
「どうしたんだい、シャーロット」
歌唱を指導するカレンベルク先生も、不思議そうに私を見ておられます。
「あ……ごめんなさい」
「みんな、一度休憩にしよう」
立ち並んでいた聖歌隊の人達は、音楽室にある椅子や机で思い思いに休憩に入っていきます。
その様子を見ながらぼんやりと立ち尽くしていると、先生が私のところへいらっしゃいました。
「ごめんなさい……」
「大丈夫だよ。たまにあることさ」
先生は私の頭を優しく撫でると、安心させるように微笑みながら仰いました。
私は心が温かくなるのを感じながら領きます。
「カレンベルク先生!ちょっと良いですか?」
「なんだい?いま行くよ」
聖歌隊の一人に呼ばれて、先生は行ってしまわれました。私はその後ろ姿をぼんやりと見ているだけでした。
先生の姿を眺めているだけで、私は幸せだったのです。
「相変わらずカレンベルク先生はシャーロットに甘いこと」
「レミ……ごめんなさい」
聖歌隊の一人であり、同じ部屋で寝起きを共にするレミが、呆れたような顔で私を見ていました。
「気にしてないって。それよりアンタ、顔真っ赤よ」
「え、あ……やだ……」
「前々から怪しいとは思ってたけど。まぁ、先生は優しいしかっこいいもんね」
「そんなことは……」
からかうような笑い顔のレミに言われて、私はまた顔を熱くしながら首を振りました。
本当はその通りなのに。でも、それを友達に向かって面と言うことは、どうしてもできませんでした。
聖歌隊の練習が終わった後、私は教会の談話室に向かいました。
「先生、いま大丈夫ですか?」
談話室にいらっしゃった先生の姿を確認すると、私は談話室へ入りました。
夕方のこの時間は、司祭様や僧侶の方々は全員食堂へと出ていて、他には誰もいません。
「ああ、大丈夫だ。何かあったのかい?」
「あ、はい……あの……」
深呼吸して、先生を真っ直ぐに見つめます。
先生は優しい笑顔を浮かべて、私のことを見ておられます。
「先生、私は……」
意を決したその瞬間のことでした。食堂から司祭様が戻ってこられたのです。
「ああ、カレンベルク。ここにいたか」
「司祭様、どうかされましたか?」
「シャーロット、すまないが席を外しておくれ」
司祭様は私を見るとそう仰いました。司祭様の言葉には深刻なものがあり、私は逆らうことができずに談話室を出ていきました。
それから、私は何度か先生が一人になるときを見計らって声を掛けました。
「先生、この間の……」
「シャーロット!ごめん、ちょっと手が離せないんだ。すぐ終わるから!」
「あ……」
「終わった頃にまたおいで」
「ごめんなさい……」
ですが、何かに邪魔をされるように、先生に声を掛けることはできても、そこから先に進むことはできませんでした。
聖歌隊の練習が終わりを迎える頃、窓の外には雪がちらつき始めていました。
「あ、雪だ。雪が降ってくると祭事もいよいよって感じだよね」
「……そうだね」
屈託なく笑いかけるレミに、私は無理に笑って答えました。
もう私には時間がないのです。
次の日も、雪は止む事なくゆっくりと降り続けていました。
先生はこの日、誰にも知られることなく、ひっそりといなくなってしまわれたのです。何があったのかはわかりません。
でも、私はそのことを知っていました。
その日、私は旅装を身に纏う先生を教会の出入り口で見つけ、後を追いました。
先生を追っていくと、もう使われていない古びた大聖堂に辿り着きました。ホールから先生のバイオリンの音が聞こえてきます。
いつも先生が弾いているバイオリンとは違う音色に、私は不思議に思いながらもそっとステンドグラス越しに中を覗きました。
ステンドグラス越しに見る先生の顔はどこか憂いを帯びていらっしゃいましたが、とても綺麗に写っていました。
先生が弾いておられた曲は、いつもの讃美歌や聖歌のような荘厳なものではありませんでした。
それは、とある著名な作曲家が、結婚式に際して己の伴侶となる女性のために作った『愛の歌』でした。
それを先生は切なく、一心不乱に弾き続けていらっしゃいました。何度も何度も繰り返される『愛の歌』は、一つの区切りを向かえるごとに、より熱情を増していったのです。
私の目からは止め処なく涙が流れ続けました。
わかっていたのです、先生にとって私はただの生徒であるのだと。私を愛してくれることなどないのだと。
先生は、私が涙を流している間にどこかへと立ち去っていかれました。
私はまたしても失敗したのです。愛を得られないとわかっていながら、もしかしたらと、僅かな可能性に賭けていたのに。
「先生……」
人気のなくなった大聖堂へ入ると、私は先生が立っていたところに立ち、周りを見回しました。
手入れのされていない大聖堂は、滅びの気配に曝されながらも荘厳さを失うことなく、そこにあり続けていたのです。
私は大きく息を吸うと、一つの旋律を口ずさみます。
先生が「シャーロットにだけ教えてあげよう」と、伝授してくれた特別な詩篇。
古典音楽の法則によって作曲されたそれは、古の神への賛美を表した歌です。
白い息と共に先生への想いを込めて歌い続けていると、私の心は宙に浮いたような感覚がし始めました。
先生の笑った姿や優しい顔を思い浮かべながら、次こそは想いを伝えようと、私は歌い続けました。
気が付くと、私は教会で聖歌隊の練習を見学しているところでした。
聖歌隊の練習が休憩に入ると、カレンベルク先生がゆっくりとした足取りでこちらにやってこられました。
「シャーロット、大丈夫かい?」
「あ……」
「無理して声を出さなくても良いからね」
先生に頭を撫でられていると、ゆっくりとその日のことが頭の中に流れてきます。
今度の私は風邪で喉を痛めてしまっていて、練習を見学しているのでした。
「辛かったら横になるんだよ」
先生の優しい言葉に、私は戻ってきたことを確信しました。
期限は一週間。聖なる催しの前日、先生がいなくなってしまうその日まで。
私は潤む目を必死に堪えながら、練習に戻られる先生のことをじっと見つめていました。
「―了―」
3274年 「目覚めの日」 
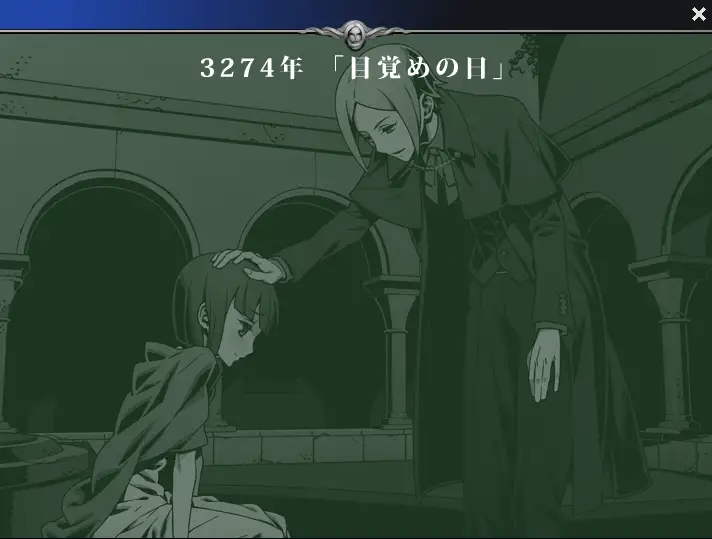
私の中の一番古い記憶は、カレンベルク先生の腕に抱きかかえられながらどこかへと向かって行くところです。
幼い私は、流れていく灰色の景色をぼんやりと眺めていました。
いま暮らしているこの教会に住まわせていただけるようになるまで、私と先生は様々な場所を転々と旅していました。
私はあまりに幼かったのでしょう。旅をしていた頃の記憶は途切れ途切れにしか思い出すことができません。
それでも、カレンベルク先生の暖かい腕の中で護られていたという記憶だけは、昨日のことのように思い出すことができます。
とても寒い夜だったと思います。私と先生は寂れた宿にいました。
周囲を照らす蝋燭の灯りがぼんやりと橙色に輝いているのが、とても印象的な場所でした。
「シャーロット、寒いのかい?」
「あんよ、つめたい」
「わかった、ちょっと待っておくれ」
先生はそう言ってすぐに、私に暖かい毛布を掛けてくださいました。
『寒い』という言葉すら知らない幼い頃の記憶です。
けれども、何故旅をしていたのか、何故私は先生に連れられていたのか。先生がそれらについて話をしてくださることはありませんでした。
この教会に辿り着いた時、教会を預かる司祭様は先生の知人であると、そう聞かされました。
「シャーロットをよろしくお願いします」
「ああ。彼女のことは我々に任せてくれ」
「何かあったら、すぐにご連絡を」
先生と司祭様がそんな会話をしていたことを覚えています。
私は先生の元を離れ、親のない子供として、この教会の養護施設に預けられることになったのです。
それでも、先生は私が無事に教会で暮らせているかどうか、たびたび様子を見に来てくださいました。
「教会はどう?」
「先生がいないからさみしい。ねえ、どうしていっしょにいられないの?」
同じような会話、同じような質問、同じような答え。
繰り返されるそれを先生がどのように思っていらっしゃったのかは、未だにわかりません。
ですが、何度も同じことを繰り返す私を見かねたのか、先生は一つの楽譜を私にお預けになられたのです。
「これ、なあに?」
「これはね、シャーロットだけに教える、特別な歌だよ」
「とくべつなおうた?」
「そう。シャーロットに勇気を与えてくれる歌だ。さあ、一緒に歌おう」
「うん!」
先生は拙い私の声に合わせるようにして歌を教えてくださいました。
「寂しくなったらこの歌を歌ってごらん。きっとシャーロットを勇気づけてくれる」
そうして私に『特別な歌』を教えてくださった後、先生は私と会う機会を少しずつ減らしていかれ、二年ほど経った頃には、教会へ来られることは無くなってしまわれました。
先生にお会いできなくなっても、私は暇さえあれば教会の入り口に佇み、先生の来訪を待ち望んでいました。
「今日はカレンベルクは来ないよ。そこにいたら体が冷えてしまう。さあ、中へお入り」
「どうして?なんでカレンベルク先生は来ないの?」
幼い私の質問に、司祭様は困った顔をなされていました。隙や暇さえあれば先生という外の人物を待ち続ける子供。いま思えば、私は少し扱いにくい子供だったのでしょう。
それでも、司祭様は分け隔てなく接してくださいましたが。
変化が訪れたのは、私が十三歳になったぐらいの頃でした。私が所属する教会の聖歌隊に、先生が指南役として就任されることになったのです。
「先生!」
聖歌隊の練習が終わってすぐ、私は廊下を歩く先生を呼び止めました。
「やあ、シャーロット。久しぶりだね」
先生は私に気が付くと、笑いかけてくださいました。
その笑顔を見ていたら胸が高鳴ってきて、なんだか顔が熱くなるような、そんな感じがしました。
「はい!あ、あの、先生も……お元気、でしたか?」
「うん。この通りさ」
あまりにも久しぶりすぎて言葉がつかえてしまい、上手く会話ができているのかどうか不安になるほどでした。
だけど……。
私が教会に預けられた時と殆ど変わらぬ先生のお姿を、私は不思議に思いました。
教会で暮らす子供達は、地場の学校に通うことが義務付けられていました。
司祭様が「教会の外で学ぶことも重要である」と仰っていたのを覚えています。
その学校からの帰り際、学友から突然呼び止められました。
「ねえ、シャーロット」
「なあに?」
「教会に若い男の人が出入りしてるって、本当?」
学校で一緒に学ぶ女子の一人でした。あまり交流はありませんでしたが、教会から通う親なしの私達にも普通に話し掛けてくれるような良い人です。
そして彼女が言う若い男の人、それが先生だということに思い当たるのはすぐでした。いま教会に出入りをする若い男の人といえば、先生以外にいませんでしたから。
「うん。でも、どうして知ってるの?」
「学校中で噂だよ。ほら、あの教会、すっごいお堅いことで有名だから」
「そう……なのかな?」
「あっと、教会の悪口じゃないよ?でさ、その噂の人、こないだ見掛けたんだけど、若くて格好いいよね」
「あの先生はね、聖歌隊に歌を教えてくれる先生なの。バイオリンがとてもお上手でね」
「ヘー!ねえねえ、その人ってどんな感じ?」
「どんな感じって……」
思い返せば、彼女はただ音楽の教師としてどういった方なのかを聞きたかっただけなのでしょう。ですが、私は咄嗟の返答に困ってしまいました。胸の辺りがざわついて、当たり障りのない返答をすることがどうしてもできなかったのです。
「なになに、どうしたの? もしかして、その先生のことが好きなの?」
「う、ううん。そんなことは……」
彼女は良い人ではありましたが、こういう風に込み入ったことを何の気なしに聞いてくる性分だけは、少し苦手でした。
「なーんてね。冗談だよ。でも、あれだけ格好いい人なんだから、憧れちゃうのは普通だって」
「そういうものかな?」
「うちの学校だって、若い男の先生や女の先生が担任になったらみんな騒ぐでしょ?それと同じだよ」
「そっか。あ、ごめんね、聖歌隊の練習があるから、もう帰らなきゃ」
胸のざわつきをごまかすように、私は彼女との会話を中断させました。ちょっと強引でしたが、彼女は納得したように領きます。
「ありゃ、引き止めてごめん。練習がんばってね!」
教会に帰っても、私は彼女の『その先生のことが好きなの?』という言葉が頭から離れませんでした。
そんなことを考えたことは、いままで一度としてありませんでした。
「シャーロット、どうしたんだい?」
あまりにも考え過ぎて寝付けなくなってしまい、同室のレミに迷惑をかけないようにと夜の庭に出てぼんやりしていた私に、先生が声を掛けてくださいました。
心臓が跳ね上がるというのはこういうことを言うのでしょう。
強く脈打つ心臓の音が先生に聞こえてしまわないか、そんなことばかりが頭を駆け巡りました。
「い、いえ……。ちょっと寝付けなくなってしまって……」
「珍しいね。昔の君はとても寝付きのいい子だったのに」
「そうでしたっけ?」
「そうだよ。お話をねだるんだけど、いつもお話の途中で寝ちゃって、そのまま朝までぐっすりだったよ」
笑いながら先生は、昔を懐かしむように私の頭を撫でてくださいました。その手は少しだけひんやりとしていて、とても心地が良いものに感じられました。
先生は私を見てくださいました。私に笑いかけてくださいました。それは聖歌隊を指導している時には見せない、とても優しい微笑みでした。
この顔は私だけが見られる特別なもの。そう感じた時、私は自覚したのです。これが『好きになる』ということだと。
「さ、お休み。祭事も近いんだ、風邪をひいてはいけないからね」
先生は私を部屋まで送ってくださると、教会の本堂の方へと歩いていかれました。
そしてこれが、先生とちゃんと言葉を交わした最後の日となってしまったのです。
教会主宰の祭事が行われる日のことでした。この催しは神に感謝し、祈りを捧げ、神に祝福された食物を戴き、その年の平穏を願う、とても大事な聖なる催しです。
ですが、朝から先生の姿は見えず、とうとう聖歌隊が歌を歌い終えても、先生が姿を現すことはありませんでした。
「司祭様!あの、カレンベルク先生はどちらに?」
祭事が終わってすぐ、私は司祭様に先生の行方を尋ねましたが、私の質問を聞いた司祭様は表情を堅くされます。
その表情に、私はとても胸がざわつきました。嫌な予感と言えばよいのでしょうか。とてつもない不安が襲ってきたのです。
「シャーロット、落ち着いて聞いておくれ」
そう言って司祭様は私に目線を合わせると、一つの絶望的な事実を告げられました。
――カレンベルクは昨夜旅に出た。ここへ戻ることは二度と無いと言っていた。
彼を追ってはいけない。これもカレンベルクが言付けたことだ。シャーロット、彼の最後の頼みを聞いておくれ。
翌日、司祭様から聖歌隊の皆に、カレンベルク先生が旅立たれたことが正式に告げられました。昨日聞かされたことは事実であると、改めて突き付けられたような気がしました。
次の日も、その次の日も、次の月になっても……、先生が教会に姿を現すことはありませんでした。
時間を重ねるにつれて、私は目の前が真っ暗になっていきました。
私が大人になったら、幼かったあの頃のように旅に連れて行ってくださると、大人になればずっとずっと先生と一緒にいられるのだと、愚かな私はそう信じていたのです。
先生が旅立たれてから、どうやってレミたちと共に過ごしたのか、あまり覚えていません。
覚えているのは、毎日のように教会の裏手にある女神像の足元に座り込み、先生から教わった『特別な歌』を、先生への思いを胸に口ずさんでいたことだけです。
そうしていれば、先生が「シャーロット、また一緒に旅に出よう」、そう言って戻ってこられる気がしたのでしょう。
そうやって過ごしていたある日、いつものように女神像の足元で『特別な歌』を歌っていると、心が宙に浮くような感覚が起こりました。
初めての感覚に戸惑いましたが、私の中の何かが変わるような気がして、そのままその感覚に身を任せて、喉が枯れるまで歌い続けていました。
「シャーロット、シャーロットってば」
突然、レミの声が隣から聞こえてきました。
はっとしてレミの方を見ると、真夜中の筈なのに、レミは何故か聖歌隊の制服を着ています。
「レミ……?」
「どうしたの?ぼーっとしちゃって。カレンベルク先生が呼んでるよ」
「え、先生が?どうして……」
彼女の言葉に私は大きな衝撃を受けました。周囲を見回すと、そこは教会の小さな音楽堂でした。
そして、いなくなった筈の先生が、不思議そうな顔でこちらを見ていらっしゃいました。
「―了―」
3274年 「決意の日」 

聖歌隊の練習が終わった後、私はすぐに自室で日付を確認しました。
その日はカレンベルク先生がいなくなってしまわれた、祭事の日のちょうど一週間前でした。
私は驚きを隠せませんでした。レミが心配そうな顔でこちらを見ていましたが、そんなことを気に留めることすらできません。
私は自室を飛び出して先生がおられそうな場所を探します。
先生はすぐに見つかりました。談話室でご休憩されていらっしゃいました。私は先生のところへ駆け出します。
「シャーロット、どうしたんだい?」
いつもと同じように優しい微笑みを浮かべる先生の目を、私は真っ直ぐに見つめます。
「先生、祭事の日に旅に出られるって、本当なのですか?」
唐突な私の質問に、先生は戸惑ったような表情をなさいました。
「なんだい?それは。誰かがそんなことを言っていたのかい?」
先生は困った顔で私を見ておられます。
「あ、あの、その……。ご、ごめんなさい……」
「カレンベルク、ちょっといいかね?」
「司祭様、どうかなさいましたか?」
「火急の用だ。シャーロット、すまんが外しておくれ」
司祭様は深刻そうに先生を見ていらっしゃいます。私は一礼して談話室を去りました。
お二人のやり取りが何であったかはわかりませんでした。ですがそれ以降、先生のご様子に変化があったことは確かだったのです。
一週間後、先生は私の前から姿をお隠しになられました。
私は再びあの歌を歌いました。すると、また祭事の一週間前に戻りました。
原理はわかりませんし、こんな恐ろしい力のある歌に恐怖も覚えました。
ですが、そんな恐怖を感じたのも一瞬のこと。あの歌を歌うことで過去に戻れるならそれでいい、とすぐに思いました。
カレンベルク先生と二度と会えなくなることの方が、私にとっては余程恐怖なのですから。
私は何度となく過去に戻ることを繰り返しました。
私が繰り返す一週間は、同じようで同じでない一週間でした。
ですがどのような一週間でも、先生は必ず祭事の前日にひっそりと出立されてしまいます。
私は一週間という時間を最大限に使って、何度も先生と会話をしようと試みました。
けれども、まるでそれが運命であるかのように、何かの力が先生との会話を遮ってしまうのです。
ある時、私は風邪を引いて熱を出した状態の過去に戻りました。
幾度かは体調の悪い過去に戻ることもありましたが、こんな風に動けない程悪いのは初めてでした。
体調を崩している暇など無いというのに。
先生は病に臥せる私を気に掛け、レミがいない時を見計らって尋ねてきてくださいました。
「大丈夫かい?シャーロット」
先生は心配そうに私を見つめていらっしゃいます。
「あ……。せん、 せ……」
「無理して喋ったら駄目だよ。また来るから」
先生とお話しできるまたとない機会なのに、私は言葉を紡ぐことができません。喉が腫れていて、声を出そうとすると酷い痛みが襲ってきます。私は悔しい思いに囚われました。
やっと体調が回復して声を出せるようになった時には、既に祭事の前日となっていました。
つまり、カレンベルク先生が旅立たれてしまう日です。
急がなければ先生を見失ってしまう。雪の降る中、私は病み上がりの身体を押して先生を追い掛けました。
先生のご出立を止められないのはわかっています。それでも、もしかしたら私の説得に応じてくれるかもしれない。私の言葉が届くかもしれない。
私だけに向けてくださる微笑に一縷の望みを見出して、私は先生を追い掛けました。
先生はいつかの時と同じように、古びた大聖堂の中心に立っておられます。
「カレンベルク先生!」
先生がバイオリンで楽曲を奏でようとしたまさにその時、私は叫ぶように先生の名を呼びました。
「シャーロット?」
先生は驚愕の表情で私を見ておられました。
「先生、あの、私……」
先生に思いを告げようとするも、上手く口が動きません。
「帰りなさい」
まごつく私に、先生は今までにない強い口調でそう仰いました。
「先生……?」
「教会に帰りなさい、と言ったんだ。シャーロット」
「先生、話を聞いてください。私は――」
「帰るんだ!」
先生が声を荒げる姿を、私は初めて見ました。
そして先生の鬼気迫る表情に、私は吃驚して固まることしかできませんでした。
「……ごめん、シャーロット。でも、お願いだから言うことを聞いておくれ」
はっとなった先生がいつものお優しい様子に戻られると、私の目を真っ直ぐに見つめてそう仰いました。
「いや……、嫌です。先生」
私は先生のコートを掴み、駄々っ子のように先生の言葉を拒否します。
ここで先生の言いつけをそのまま聞けば、また振り出しに戻ってしまうのです。
「君はいい子だ。だから僕の言うことを聞いてくれるね?」
先生は悲しい顔でコートを掴んでいる私の手を引き剥がすと、そっと私から距離を置かれました。
「先生……」
「探していた人が見つかったんだ」
先生は一方的に仰います。言葉の一つ一つに先生の必死な思いが込められており、私が何か口を挟むことなどできません。
「その人は僕の大切な人なんだ。だから、僕は行かなければ」
その言葉に、私は目の前が真っ暗になりました。先生の心の中にはずっと前から思い人がいらっしゃったのです。
「大切な……」
先生の言葉は決意に満ち溢れておられました。誰にも、司祭様でも止めることはできないでしょう。
私なんかが先生の行く道を阻むことなど、できる筈がなかったのです。
「僕はもう行かなくては。シャーロット、君も帰りなさい」
それだけを仰ると、先生はバイオリンケースを持って足早に立ち去られました。
私を教会に送り届ける時間さえ惜しかったのでしょう。私は古い聖堂に一人取り残されてしまいました。
「せん……せい……」
私は流れる涙に気付かないふりをして歌います。もう一度先生に会うために。
ずっとずっと、カレンベルク先生のことを思いながら歌い続けました。
薄れた意識がはっきりしてくると、聖歌隊の練習の最中に戻っていました。
先生はいつもと同じように、私達に熱心な指導をしておられます。
そっと先生の様子を目で追い掛けます。先生は休憩中やふとした拍子に、とても悲しそうな表情でどこか遠くを見ておられました。
私と目が合うと微笑みかけてくださいましたが、その瞳の中に私は映っていませんでした。
私は幾度となく最後の一週間を繰り返すうちに、一つの決意をしました。
どうやっても未来を変えられないのであれば、せめて私の思いだけでも告げようと思ったのです。
それで何かが変わっても、変わらなくてもいいのです。
カレンベルク先生が私の思いを受け入れることなど万に一つもないでしょう。それでも、先生の心のどこかに私という存在を刻み込むことができるのなら、それだけで構わないと。
この思いを告げることができるその日まで、私は最後の一週間を繰り返し続けることを決意したのです。
「―了―」
3274年 「諦めの日」 
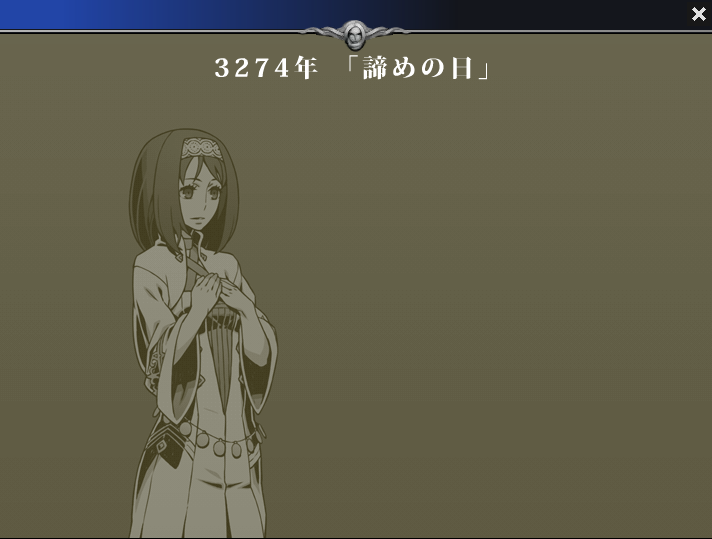
「先生!好きです!好きなんです!」
「……ありがとう。僕も君のことが大好きだよ、シャーロッ ト」
そう仰って、カレンベルク先生は私が初めて見るような甘い甘い笑みを浮かべ、私を抱き締めてくださいました。
なんて幸せなのだろう。私はなんて幸福な人間なのだろう。そう思うと、自然と目から涙が溢れ出てきます。
先生の腕の中で幸福を噛み締めようとしたその刹那、私は目を覚ましました。
今の私にとっては思いを告げることが全てです。本来なら幸せに感じる筈のこの夢も、今は悪夢以外の何ものでもありません。
そもそも、カレンベルク先生には何者にも揺るがされないほどに大切な誰かがいらっしゃるのです。そして、私の幼い恋慕に応えてくれる心の隙間は、先生には存在しません。
それを理解してなお、私はこの暖炉の残り火のように燻り続ける思いを先生に伝えたいと願っています。
挫けそうな心を何とか奮い立たせ、私は先生に思いを告げるその瞬間を、じっと探し続けるしかないのです。
祭事の一日前。つまりカレンベルク先生が真夜中にひっそりと旅立ってしまわれる日の夕方。偶然にも私は音楽室で作業をしている先生と会うことができました。
その時、私は音楽室に忘れ物をしていて、それを取りに行ったのです。
「あ、先生……」
「珍しいね シャーロット。忘れ物かな?」
「はい。楽譜を忘れたみたいで……」
何度も繰り返した一週間の中で、ようやっと巡ってきた機会でした。
緊張でどくどくと脈打つ心音が先生に聞こえてしまわないだろうか。それくらいに緊張で硬くなってしまいます。
でも、この機会を逃せば、また一週間前からのやり直しです。
「あの……、先生」
「何だい?」
「私、その……」
早鐘のように煩い心音を無理矢理に落ち着かせ、思いを伝えようとしたその時でした。
「カレンベルク、ここにいたのか」
司祭様が音楽室に入ってこられました。
「司祭様、どうかなさいましたか?」
「ああ。すまないが例の件で話がある」
司祭様の言葉で、先生のお顔から表情が消えるのが見て取れました。
「シャーロット、すまない。行かなければ」
「待って――」
「すまないな、シャーロット。大事な用なのだ」
お二人に厳しい表情でそう言われてしまえば、ただの少女である私が先生を引き止めることなど、できる筈がありません。
「明日は本番だからね。早く宿舎に戻って休むんだよ。じゃあ、また明日」
そう仰って私の頭を優しく撫でてくださった先生は、司祭様と慌ただしく音楽室を出て行ってしまいました。
私のために無理に作った笑顔で、引き攣った優しげな顔で、酷い言葉を私に告げて。
明日なんて無いのに。先生はそれを知っているというのに。
何と残酷な言葉なのでしょう。
その日のカレンベルク先生が旅立たれる瞬間に、私は立ち会うことができませんでした。
いつもであれば真夜中に旅立たれるのですが、教会のどこにも先生はいらっしゃいません。
翌日司祭様に尋ねると、司祭様とのお話を終えた後、先生はすぐに旅に出てしまったと聞かされました。
数少ない機会を生かすことができずに失敗し、そしてまた一週間前に戻る。
何度同じことを繰り返したでしょうか。
思いを伝えられなかった記憶が、カレンベルク先生の旅立ちの日に降る雪のように、私の中に静かに積もっていきました。
思いを告げることができるその日まで、一週間を何度でも繰り返し続けようと決意しました。ですが、数え切れないほどの失敗を繰り返した私の心は、少しずつ変わっていったのです。
少しずつ少しずつ、私の心は決意から諦めへと変貌していったのです。
そんな心の磨耗を映し出すかのように、私は繰り返される一週間の半分以上を、熱を出して寝込むようになりました。
「調子はどうだい?シャーロット」
「せん、せ……」
寝込んだ日は私を必ず見舞ってくれるカレンベルク先生ですが、私の喉は病魔に冒されていて、言葉を紡ぐことができません。
ですが、私の心はどこか満ち足りた気分を感じているのです。ずっとずっと、永遠にこの日々を繰り返していけばいいのではないか。そういった黒く暗い感情が、私の心を覆い尽くそうとしていきます。
自分の思いを先生に告げることが成し得ないのであれば、私を気に掛けて見舞ってくれる先生の姿を見続けていたい。そう思ってしまうのです。
そうやって、繰り返す一週間を先生に見舞ってもらうだけになった頃、不思議な夢を見るようになったのです。
最初は一週間に一度くらいの頻度でその夢を見ていました。
霞が掛かったような不鮮明なものでしたので、最初は高熱のせいだと思っていました。
ですが、幾度とない繰り返しを行っているうちに、ついにはその夢を毎晩見るようになってしまったのです。
その夢を見る度に、聖歌隊の練習の最中に戻る度に、霞が掛かっていた夢は徐々に鮮明になっていきました。
鮮明になっていったその夢は、カレンベルク先生と見知らぬ老人が、豪奢な聖堂のような場所で戦っている夢でした。
先生は私の知らないバイオリンを爪弾いて音を操り、それによって老人を攻撃しているようでした。
普通に考えて、音で人に危害を加えることなどできるわけがありません。ですが、私が特別な歌を歌うことで最後の一週間を繰り返しているように、先生は他人を攻撃できる楽曲を知っているとしたら。その可能性は十分にありました。
老人も杖を振るって怪しげな術を繰り出し、先生と渡り合っています。
老人の口が動いていることから、何かしらの言葉を喋ってはいるのでしょう。先生の口も、老人に対して言い返すように動いているのが見えました。
ですが、先生の言葉も、老人の言葉も、どちらも聞き取ることはできませんでした。
先生と老人の戦いは熾烈を極めます。
術と音のぶつかり合い、とでも言えばよいのでしょうか。
衝撃によって、私の周囲の空間が震えているのがわかる程です。
夢の中では私は空気のような存在ですが、何故かその衝撃だけは体感できました。
そして、術と音の打ち合いが暫く続き、ついに終わりを迎えます。
老人が倒れたと見せかけて、不意打ちで光り輝く不思議な紋様を出現させるのです。
先生はその不意の一撃を防ぐことができず、いつも必ず負けてしまいます。
先生が膝を突きました。もう何度も何度も見ている光景ですが、私はその光景を見る度に胸が締め付けられます。
先生の体のそこかしこから血が流れ出し、今にも倒れそうでしたが、必死に痛みを堪えて立ち上がろうとしています。
老人が先生に向かって何かを喋っているのですが、聞き取ることはできません。
先生は朦朧とする意識で、老人の言葉を悔しそうに聞いています。
老人は笑っていました。背をのけぞらせ、醜悪な笑みを浮かべ、先生を嘲笑しているように私には見えました。
「先生っ!先生!」
私は堪らずに叫びだし、先生の元へと走ります。
ですが、これは夢です。夢でしかないのです。
私は先生に触れることすらできず、ただただ 先生の前で立ち尽くすのです。
先生が完全に倒れ伏したと同時に、私は目を覚ますのでした。
「う、うぅ……」
カレンベルク先生が傷つき倒れる姿に、私は涙してしまいます。
この夢は一体何なのでしょうか。
思いを伝えることに失敗し続けている私の心が見せているものなのでしょうか。それとも、特別な歌が何か別の力を発揮して先生の未来の姿を見せているのでしょうか。
「教えてください、カレンベルク先生……」
その言葉は、私以外の誰もいない部屋に吸い込まれて、静かに消えていきました。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ