シラーリー
【関連キャラ】ノイクローム、ノエラ(女型自動人形)
「歪み」 
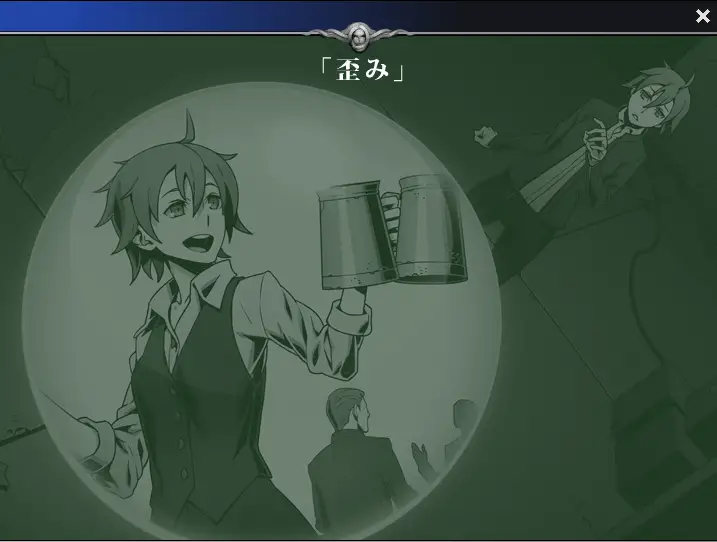
「一番テーブルにウイスキーとジャーキーお願いします!」
「はいよ!」
ローゼンブルグのとある酒場に、威勢の良い声が響く。
「これ五番テーブルさんね!」
「はい!」
注文を厨房に伝えたその足で、出来上がった料理を客席に運ぶ。
厨房と客席を行き来するシラーリーは、酒場で働くには不釣り合いに若かった。
シラーリーは、元はローゼンブルグ下層のスラムに暮らす孤児だった。
ある時、大金を手にした仲間に連れられて訪れた飲食店でおいしい料理に衝撃を受けた彼女は、いつか自分で飲食店を出すという夢を持った。
頭のいい仲間の助言を受けて一つ上の階層に潜り込んだシラーリーは、出自を問わずに働ける酒場で働き出した。
それだけでは経験が足りないと感じたシラーリーは、朝の市場でも働くようにもなった。市場で食材の流通を直に学び、酒場で飲食店の仕事を経験する。
周囲からは体が持たないと心配されたこともあった。
しかし、働いた分だけの給金が手に入った。朝から晩まで売れるかどうかもわからない廃品を回収して売り歩いていた頃と比べれば、遥かに良い環境だった。
そうやって寝る間も惜しむ程の努力を重ねたシラーリーは、働いていた酒場のオーナーから支店を任されるまでになった。
「じゃあ、店の準備は頼んだよ」
「はい!」
「もし困ったことがあったら、すぐに相談してね」
「ありがとうございます!」
酒場の同僚達は優しかった。暖かい人に恵まれたことにシラーリーは感謝し、幸せを噛み締めていた。
しかし、ここは出発点に過ぎない。これからも一層の努力をしなければと気を引き締めた。
支店の店長となったシラーリーは、より積極的に行動を起こす。
店を盛り立てながら、経営者達が催す会合にも積極的に参加し、経営に必要な知識や技能を学んでいった。
そうして何年かの時を経て、ついに経営者として自身の店を構えるまでになった。
シラーリーは久方ぶりに、かつて暮らしていた下層の廃ビルへと足を運んだ。
ここに暮らす仲間達に、自分の経営する店で共に働かないかと持ち掛けるためだった。
少しでも仲間達に良い暮らしをして欲しい。自分のように上の階層で働いた経験があれば、苦しい生活を断ち切ることが可能だと思ってのことだった。
「あれ?」
廃ビルに一歩足を踏み入れてすぐ、シラーリーは違和感を覚えた。
夜も近い時間なのに、廃ビルの中は話し声の一つもしていない。
ひと月程前にやりとりした手紙には、仲間達は変わりなく暮らしている様子が綴られていたし、住居を変えるなどという話も書かれていなかった。
何かがおかしい。そう思いながらシラーリーは、慎重に廃ビルの中を進んでいった。
「おーい、誰かいないのか?」
シラーリーの呼び掛けに応える者はいない。静まり返った廃ビルに、シラーリーの声と靴音だけが響く。
程なくして、仲間達がいつも集っていた広い部屋に辿り着いた。
立て付けが悪く、開きにくい扉を開ける。
「……なんだ、これ」
扉を開けた先に見えた光景に、シラーリーは愕然とするしかなかった。
「おい、みんな!?大丈夫……か……?」
シラーリーは室内にいた一人に駆け寄る。だが、近付いたその瞬間、誰も自分の問い掛けに応えられる筈もない事に気付いてしまった。
夕暮れの太陽によってオレンジ色に照らされた室内には、骨と皮だけになった様々な年齢の子供達の遺体があった。
「どういうことだよ……なんだよこれ!」
シラーリーは踵を返すと、部屋を出て廃ビルの階段を駆け上がり、仲間達が寝室にしていた部屋を一つずつ開けていった。誰か生きている仲間がいればと思っての行動だったが、どの寝室も同じような光景が広がっていた。
「一体どうしちまったってんだよ……」
シラーリーは呆然としたまま、自分が寝室としていた部屋を開けた。
部屋の様子を目にしたシラーリーは、その場で崩れ落ちた。
「なんなんだよ……どうなってんだよ……」
部屋の中にある小さなベッドには、他の仲間達と同じように、骨と皮だけになって横たわる自分の姿があった。
か細い呼吸を繰り返し、辛うじて生きているようだった。
身長からすると十代の前半くらいだろうか。混乱の極みにある筈の思考は、妙な冷静さで自分の年齢を分析していた。
「どうやら理解したようだな」
不意に、背後から女の声が聞こえた。
「誰だ!」
シラーリーは咄嗟に振り返り、後ずさる。
背後にいたのは、爪先から頭の天辺まで白尽くめの衣装を纏った、奇妙な女だった。
「そういえば名乗っていなかったな。私はノイクローム。故あって君の力を借りに来た」
「何を言ってやがる。てめえがこんなことをしたのか!」
「否。これは君がこの世界で辿った、歪められし因果の結果」
ノイクロームと名乗る女の芝居がかった態度に、シラーリーは苛々していた。
「なんだと。じゃあ、今ここにいるオレはなんなんだよ!」
激昂に任せてジラーリーはノイクロームの胸倉を掴み上げる。
確かに感触がある。シラーリーは自分が死にかけているとは到底思えない。そのことが更に苛立ちを募らせる。
「君は今まで夢を見ていたのだよ。苦役を乗り越え、幸せを掴んだという本来の因果。その夢をね」
「そんな馬鹿な話があるか!オレは、オレは!」
「現実を見つめよ。答えはそこにある」
ノイクロームはベッドに横たわっているシラーリーを指し示す。
シラーリーはノイクロームに言われるがまま、今にも死にそうな己をじっと見つめる。
何か引っ掛かるものがあった。この光景には、僅かに覚えがあった。
不意にあの日の記憶が蘇る。あの日、シラーリーがスラムを出ようと決意したあの日、仲間は自分を飲食店へ連れて行ってくれたのではなかった。
あの日、仲間が持ち帰ったのは大金ではなく、不思議な薬であった。
どんな病気や怪我にも効く魔法の薬。病気に苦しむ仲間のためにどこかから手に入れたという薬が、シラーリー達の人生を変えた。
最初は良かった。確かに仲間の病気は治った。怪我をした時も、その薬を飲めば立ち所に元気になった。
だが、シラーリーを含めた廃ビルの仲間達は、少しずつその薬によっておかしくなっていく。ちょっとでも風邪を引いたり怪我をしたりすればその薬を飲んだ。次第に、その薬が無ければ激しい嘔吐感や目眩に襲われるようになった。
薬を飲まなければ睡眠すらままならない。シラーリー達は薬を飲み続けるしかなかった。
薬を手に入れるためには大金が必要だった。シラーリー達は薬を買う金を手に入れるために、犯罪にも手を染めた。しかし所詮はスラムに暮らす者だ。すぐに薬を買う金は底を突き、身体の弱い者から順に死んでいくしかなかった。
シラーリーは息絶える直前、何故自分達がこのような目に合わなければいけないのかと憤りを感じていた。
「なんで、死にたく、な……」
貧しいけれど、仲間に囲まれて自由に生活していた。それが一つの薬で狂ってしまった。
シラーリーの胸中は後悔の念に埋め尽くされていた。
「そうか、オレ達……」
「思い出したようだな」
ノイクロームの口元には、僅かな笑みが浮かんでいた。
「ああ。この後すぐにてめえがやって来て、勝手に幻を見せたこともな」
シラーリーは精一杯の憎しみを込めて、ノイクロームを睨み付ける。
「私は君に正しい未来の姿を見せただけに過ぎない」
ノイクロームはシラーリーから少し距離を取る。同時に、二人の間に白い真珠のような光沢を放つ小さな球体が出現した。
「正しい未来を取り戻したくはないかね?」
「どういう意味だ?」
「先程まで見ていた幻影。あの様な幸せな人生を送りたくはないのかと聞いている」
「訳がわかんねえ……」
シラーリーは小さく首を振る。
その混乱に同調するかのように、夕焼けに照らされたシラーリーの部屋が、水に濡れて流れていく絵の具のように溶けていく。
「あまり時間は無いぞ。歪みを受け入れ、そのまま死するか。それとも歪みを拒絶し、生き長らえるか。どちらでも選ぶといい」
景色が溶けていくのと一緒に、シラーリーの意識もまた、眠りに落ちる直前のようにぼんやりとしてきた。
「嫌だ、と言ったらどうなるんだ?」
「さて。何分、私は死者となったことがない」
ノイクロームは首を振る。
「本当に死ぬってことかよ……」
「この世界の言葉を借りるなら、そうなる」
ノイクロームの言葉は、あまりにも現実から掛け離れていた。
いつの間にかシラーリーは、ベッドで寝ている息も絶え絶えの自分に戻っていた。
「さあ、選択の時間だ。私と共に正しい未来を手に入れたくば、この球体を取れ」
「オレ、は……」
シラーリーは何も考えられなくなっていた。だが、殆ど動かなくなった腕を、球体に向かって懸命に伸ばす。
あんなに幸せな人生を失うのは嫌だった。
ただそれだけだった。
「―了―」
「パーツ」 
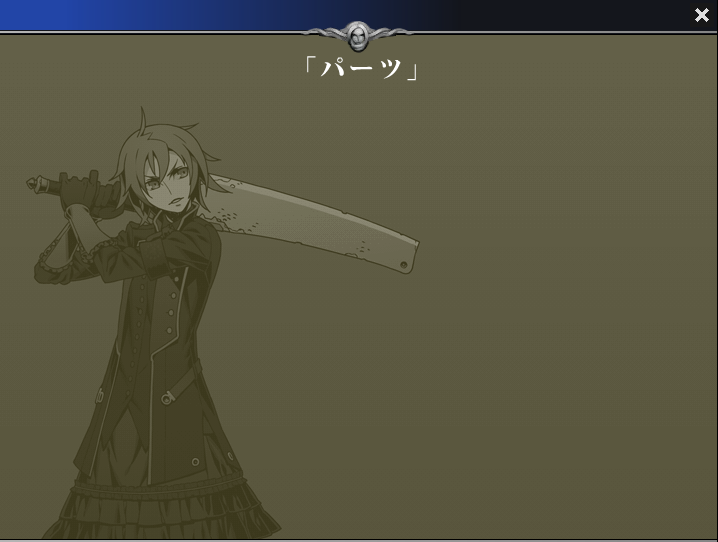
何の気配も漂っていない通路を、シラーリーは歩いていた。
無遠慮に通路を歩いては、目に入った扉を片っ端から開け放って中を調べていく。
真新しい服が埃で白く汚れるのも気に留めず、乱暴に、そして乱雑に、錆び付いた機械や道具類をかき集めて並べる。
経年劣化によって組成が脆くなっているものは、シラーリーの乱暴な扱いに耐え切れずに破損していった。
「ちっ、めんどくせえ。こういうのは苦手なんだよ……」
シラーリーは誰にも聞かれていないのをいいことに、舌打ちして愚痴を漏らした。
シラーリーは現在、ルビオナ王国北部にある遺跡にいた。
かつて人類に反旗を翻した自動人形達が拠点にした施設の一つであると、ノイクロームは言っていた。
そこに残されているであろう機能停止した自動人形から、電子頭脳に使われている小さなチップを探し出すこと、それが今回のシラーリーの任務であった。
「ハア……。どこもかしこも荒らされまくってんじゃねえか」
この遺跡がルビオナ王国の首都アバロンからそう遠くない場所に位置している所為もあるのだろう。遺跡の内部は何者かによってすでに荒らされた形跡があった。
薄暮の時代の遺物を求めて考古学者が発掘したのか。はたまた、金品目当てで盗掘されたか。
何にせよ、シラーリーが求めるものは既に持ち去られている可能性が高かった。
「はぁー……」
何度目かの溜息を吐きながら、シラーリーはここに来る前にノイクロームと交わした言葉を思い出していた。
「さて、仮初めの肉体を手に入れた気分はどうだ?」
何も無い空間で、シラーリーはノイクロームに見せられた夢と同じ肉体を得ていた。
「悪かねえな。でも、どうしてかりそめ?なんだ」
仮初めと言われたものの、骨と皮だけになって瀕死だったときと比べれば雲泥の差である。
「その肉体はだね、君のあるべき未来の姿を私が作り上げたものであって、君の本当の肉体ではないのだよ」
シラーリーはその言葉をすんなりとは受け入れられなかった。
「そうは見えねえけどな……」
「私は人間ではない、全く違う存在だ。故に人間の肉体が持つ機能の内、いくつかが再現できなくてね。例えばそうだな……痛覚とかいう感覚があったな」
そう言われて、シラーリーは自身の腕に痛みを感じるような刺激を加えてみた。しかし痛みが走ることはなく、ただ鈍い衝撃のようなものを感じただけだった。
ひとまず痛覚は機能していないことがわかった。おそらく他にも何らかの不都合があるのだろう。
「なるほど。じゃあ、どうすれば本当の肉体を手に入れられるんだ?」
「それには、世界の因果を歪ませているものを倒すだけでよい。そうすれば、君の魂は正しき因果によって現実へと復活を果たす」
「よし、わかった。なら、さっさとその歪みとやらをぶっ潰しに行こうぜ」
「待て。話は簡単ではないのだ。すぐにでも実行できるのなら、誰の手も借りずに、私一人で実行している」
勇むシラーリーをノイクロームは諫止する。
「何だよ?まどろっこしいな」
「世界を歪ませる力は強大だ。となれば、それを押さえつけるだけの力が必要となる」
ノイクロームは言葉を続けた。
「世界を歪ませたものの片割れである自動人形。まずはそれを探し出さねばならない」
ガタンガタンと強い音を立てながら、シラーリーは遺跡を荒らすように調べていく。
薄暮の時代には、一人の人間につき一体の自動人形が与えられていたという。つまり、それほど大量にある自動人形の中から該当する一体を探し出さなければならないというのは、正直無理な話に近かった。
加えて、シラーリーが降り立てる時代にも制限が存在していた。
シラーリーは、自身が『生きていた』時よりも過去の時代へ赴くことはできない。
「この世界のあらゆるものは、全て因果によって縛られている。君が生きていた頃よりも過去へ赴けないのは、君が存在するという因果が、それ以前に発生し得ぬからなのだ」
ノイクロームの言葉は壮大であり、教養のないシラーリーにとっては全くもって理解不能だった。
それでも一つだけわかったことがあった。本当の肉体を手に入れ、あの苦しくも明るい目標があった世界で暮らすためには、ノイクロームの指示に従わなければならない。それだけははっきりとわかった。
ノイクロームの難しい言葉を思い出しながら遺跡を調べていくと、自動人形の残骸が多数放置されている部屋に辿り着いた。人工筋肉が剥がれ落ち、白いフレームを剥き出しにした自動人形が何体も倒れている。
「気味がわりぃな……」
人間の死体とも違う異質なものを目にした、率直な感想であった。
とはいえ、ただ不気味がっている訳にもいかない。シラーリーは自動人形の頭部を探し出し、その場で分解していく。
必要なのは電子頭脳のチップだけ。それ以外のものは手に入れても邪魔なだけである。
自動人形の頭部を無心になって分解し続けていたその時だった。
突然空を切る音がして、シラーリーの右腕をジャベリンのような武器が掠めていき、そのまま床に突き刺さった。
「あぁん?!」
シラーリーが注意を払っていなかった背後に視線をやる。
そこには、何者かが立っていた。
「なんだ?てめえ」
手に持っていた自動人形の頭部を放り出すと、シラーリーはノイクロームから与えられた大蛇に手を掛け、その何者かにランプの明かりを当てた。
「……不気味な奴だな」
明かりの先にいたのは、完成された体躯を持つ女であった。
一見しただけでは人間の女と変わりはなかったが、皮膚の合間から僅かだけ自動人形と思しき白いフレームが露出している。
つまり、この女は自動人形なのだ。
無言で攻撃してきたところを見ると、この施設を護衛するために調整された、戦闘用の自動人形である可能性が高い。
「白くなった奴ばっかりかと思ってたけど、てめえみたいなのもいるんだな。おもしれえ」
シラーリーは笑うように喉の奥を鳴らす。
それとほぼ同時に女自動人形はゆらりと揺らめくと、左手に持っていた槍を右手に持ち替え、シラーリーに向かって突進してきた。
シラーリーはランプを女自動人形に投げ付ける。
このランプは薄暮の時代の遺物で、火を使わずに機械の力で明かりを照らす仕組みになっており、周囲に燃え移るようなことはない。
一瞬、女自動人形はランプをぶつけられた衝撃で怯んだ。
その隙をシラーリーは見逃さない。シラーリーは大蛇を薙ぎ払うように振り回し、胴体に攻撃を加えようとする。頭部を狙わなかったのは、この自動人形からチップを回収した方がいいと思ったからだ。
何もかもが沈黙している遺跡の中で、ただ一体だけ動く自動人形。それがどれほど貴重なものなのかは、無学なシラーリーでもすぐにわかるものだった。
女自動人形は身軽なだけでなく柔軟でもあった。シラーリーの一撃を高く飛び上がって回避すると、再び槍を投擲してきた。
「させるか!」
大蛇を縦に振るい、投擲された槍を弾き飛ばす。
女自動人形は武器を失ったのにも構わず、シラーリーに向かって突進してきた。
「ちっ!」
シラーリーの胴を女自動人形が捕らえた。
タックルを受けたシラーリーは、そのまま女自動人形と共に地面に激突する。その衝撃にも関わらず、シラーリーは大蛇を手放さないよう腕に力を込めた。
女自動人形が両腕を振り上げる。その腕から隠しナイフか何かの切っ先が見えた。
両腕がシラーリーの額に届く紙一重のところで、シラーリーは何とか右腕を動かすことができた。
大蛇が女自動人形目掛けて袈裟懸けに振り下ろされる。
その一撃によって動作をコントロールする機器が壊れたのか、女自動人形は機能を停止した。
「ふう……あぶねえとこだった」
シラーリーは盛大に溜息を吐く。
痛覚が無いとはいっても、肉体が傷付けば行動は制限されてしまう。それに、傷付いた肉体を修復するにはノイクロームの力が必要不可欠だ。
この肉体が動かなくなったら自分は一体どうなるのか、その辺りのこともよくわからない。そのため、なるべく肉体の損傷は避けたいというのがシラーリーの考えだった。
「さて、と」
シラーリーは女自動人形に近付き、その頭脳を解体しようと座り込む。
よく見れば女自動人形はとても綺麗な顔立ちをしていた。その人工皮膚を剥がして解体するのは何だか惜しい気がして、シラーリーは女自動人形の顔をじっと見つめていた。
「よくやった」
どれくらい女自動人形の顔を見ていただろうか。不意にノイクロームの声が聞こえ、シラーリーの眼前に現れた。
ノイクロームの手には、白い真珠のような球体が携えられている。
「ノイクロームか。どうした?」
シラーリーの問いに、ノイクロームは解体直前の女自動人形を指差した。
「その自動人形、修理すればまだ使えそうだと思ってな」
「どうやって修理するんだよ」
「私に考えがある。その人形といくつかのパーツを回収し、付いてこい」
「わかった」
ノイクロームの考えることはさっぱりわからない。
いずれわかる時が来るのだろうか? そんな疑問を胸に、シラーリーはおとなしくノイクロームに従うのだった。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ