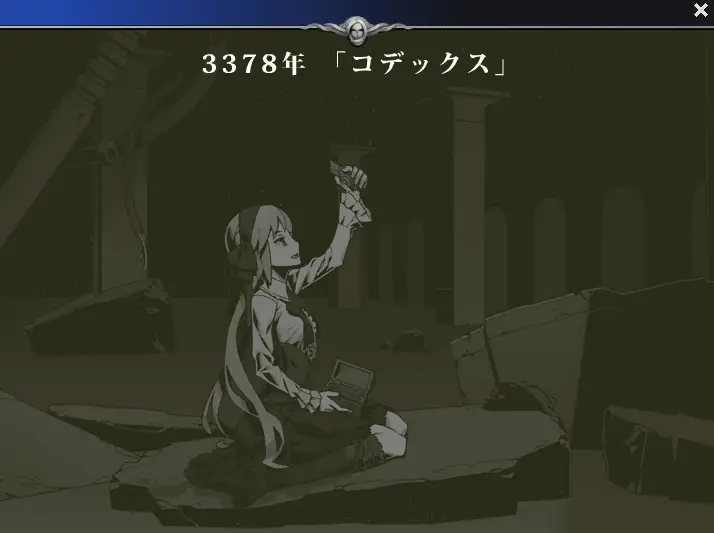ドニタ
【死因】自爆
【関連キャラ】ウォーケン、シェリ、マックス、サルガド、レッドグレイヴ
3377年 「灯り」 

チッ、チッ、チッ、チッ……。
継続的に同じ間隔で刻まれる音だけが、ドニタの脳内にこだましていた。
視界には何も映っていない。暗闇に音だけが響いていた。
自身の名前も知らず、何も無い空間の中でひたすらに待ち続けていた。何が、いつ来るのかもわからないままに。
しばらくすると様々な『知識』が流れ込んできた。だが、動かせる体の無い彼女は、それらを見る事も、そして触れる事もできなかった。
『知識』は増えても、自身はこの何も無い空間から動く事ができなかった。
暗闇の中、繰り返し響く音。ぐるぐると世界が回り続けるような感覚が続く。
チッ、チッ、チッ、チッ……。
唐突に世界が開けた。
「おはよう」
目の前にいる人間が自分をあの空間から救い出してくれた事を、ドニタは直感的に理解した。
言葉と共に視界に入ったものは白衣の人間、そして壁際のガラスケースに立て掛けられた多くの人形らしきものの姿だった。決して広くはないその部屋は、これまでいた空間とは比べ物にならないほど刺激に満ちたものだった。
「お…はよう…ござ…います」
たどたどしいながらも声を出す事ができた。その様子を見て満足気に領いた白衣の男が言葉を続ける。
「ドニタ。これが君の名前だ。ボディが全て出来上がるまで、まだ時間が掛かる。それまでは不便をかける事になるが、我慢しておくれよ」
確かに身体は出来ておらず、動く事はできなかった。しかし暗闇から抜け出せたことは、ドニタにとって純粋に喜びだった。
「自己紹介を忘れていたね。私はドクター・ウォーケン、君を創り出した者だ」
「よろしく……おねがいします」
今度は比較的上手く発声を行えた。
「すばらしい挨拶だ。 どうだい、何か気になるところはないかい?」
「音が、聞こえる。 繰り返し。 ずっと」
「どんな音だい」
「チッ、チッ、チッって。 この部屋のどこかから聞こえてくる」
脳に響く音を拙い声で真似してみる。
「ふうむ、選択的注意モジュールの設定ミスかな、または聴覚素子の不良か」
「わかった。 もう一度眠ってもらう。 すまないね」
また暗闇に戻るのかと思うと憂鬱な気分が生じたが、その気分が表情へ伝わる前に、ドニタの回路から電気信号が途絶えた。
それからは部屋とドクターだけが、ドニタにとって世界の全てになった。
徐々に自身の体が出来上がっていく過程は、どれだけ見ても飽きなかった。作業の合間にはドクターが話をしてくれる事もあった。今までに作った作品の紹介やそれについての失敗談、いずれもドニタには新鮮で楽しい事ばかりだった。自動人形の登場する童話を読み聞かされた事もあった。つくり話とはいえ、自身と同じ自動人形が活躍する様には心が踊った。
手が使えるようになってからは、自ら本を読むようになった。ドクターが書庫から持ってきてくれた本を昼夜違わず読み耽っていた。
ドクターからは、夜は何度も休まなければいけない、と注意を受けていた。
「どうして、ワタシは人間じゃないのに眠らないといけないの?」
「君は人に似せてつくった特別なモデルだからね。 君の高性能な脳は日々得た膨大な情報を再構成するために、一定期間休ませなければならないんだ。人の脳と同じように」
「ふうん。つまんない。どうにかならないの?」
「いまのところならないね。寝なくても、そりゃあ人間のように死んだりはしないけど、君の人工脳の成長が著しく阻害されてしまう」
「ワタシ、寝るの大嫌い。夜も大嫌い。ずっと本を読んでいたい」
「わがままだね。でも仕方ないことなんだよ。寝ないなら強制的にこちらで切るよ」
「それは絶対嫌。……寝るわ」
「オーケー。良い子だ」
「ねえ、ドクター。ここの部屋の電気だけは点けたままでもいいでしょう?」
「ああ、かまわないよ。でも、電灯の光なんか君には……」
ドニタの知覚力ならば、人にとっては暗闇でも全く影響など無かった。それに睡眠モードに入れば外界の光など関係ない。
「とにかく嫌なの」
ドクターのわかりきった説明を遮り、ドニタは言い切った。
「わかったよ。おやすみ、ドニタ」
「おやすみ、ドクター」
ドニタは薄明かりの付いた作業用ベッドの上でゆっくりと目を閉じた。そしてあの暗闇の音が聞こえないように、すぐに自身を睡眠モードに切り換えた。
ある日、ドクター以外の人間を初めて見た。肌の浅黒い、メガネを掛けた男性だった。
「こちらはソングさんだ。ドニタ、挨拶をしなさい」
「はじめまして。ソングさん」
ドニタは普通の少女のように微笑みを浮かべながら、挨拶をこなした。
男がデッキの上に置かれたドニタを眺めて、ドクターに視線を戻す。
「すばらしいな。 ここまであのコデックスを解読するとは」
「時間は掛かりましたがね。 完成の暁には、お宅のカウンシルのメンバーにもお見せしましょう」
「それは楽しみだ」
ドクターとソングと呼ばれた男は部屋の隅にあった椅子に座り、テーブル越しに向きあうと話題を変えた。
「で、取引の件、考えていただけましたか?」
「探索の件ですね。 正直迷っています。 今の私にとって利益があるのかと」
「必ずありますよ。 こちらは腐ってもパンデモニウムです。ここに無い資材、資料はいくらでも揃えられる」
「カウンシルが管理しているもの全てにアクセスできますか?」
「私が説得しましょう」
男の焦りは、端で聞いているドニタにも伝わってきた。
「私達には貴方の技術が必要だし、貴方には組織のバックアップが必要だ」
改めてソングは断言した。
「わかりました。ただし、カウンシルの管理資料へのアクセス権は必ずいただきます」
ドクターは考える素振りをやめ、そう答えた。
ソングと呼ばれた男が滑稽なほど安堵の表情を浮かべたのを見て、少しドニタは可笑しくなった。
「行くわよ」
ドニタはもう一体の自動人形に声を掛けた。しかし反応は無い。そう作られていないからだ。この自動人形をドニタは見下し、嫌悪していた。この無骨な格好で喋る事すらできない存在と同じ自動人形であるという事が、ドニタには耐え難かった。物言わぬ自動人形を従え、ドニタは研究所を出発した。
世界は朝焼けの中だった。
外に出るのは初めてだったが、全く恐れはなかった。ただ高揚感だけがドニタを包んでいた。
「―了―」
3378年 「コデックス」 
巨大な鎌を構えたドニタの後ろで、数体の獣が音もなく崩れ落ちた。
「これで最後ね」
その様子を確認することなく、ドニタは口の中で呟いた。
その表情には勝利の喜びも、自身の強さへの誇りも見えない。この辺りの荒野をうろつく獣を倒すことなど、彼女には他愛もないことだった。
「手間ばかり掛かるわ。数だけはたくさんいて……」
そう言うドニタの傍らには、物言わぬ自動人形が立っていた。自動人形は、ゆっくりとした動作で自分の剣を納めた。
「あなたも、こういう時なら少しは役に立つみたいね。これで、自分で判断して動いてくれるともっと良いのだけれど」
少し非難めいたドニタの言葉にも、自動人形――ドクターは「プロトタイプ」と呼んでいた――はぴくりとも動かなかった。命令ではない言葉に、この自動人形が反応することは無い。
「反応なし、と。ほんと、つまらない奴ね。行くわよ」
ドニタはそう言うと、プロトタイプの先に立って歩き出した。目指す先には巨大な建物がそびえ立っていた。
風雨に曝されて半ば崩れかけているその建物は、見ようによっては巨大なモンスターのようだった。その中央にぽっかりと空いている穴は、言わばモンスターの口といったところか。
その外見は見る者に本能的な恐怖を抱かせるものだったが、ドニタはそんなことを感じる様子もなく、まるで散歩にでも出掛けるように建物に入っていった。
ドニタが足を踏み入れたのは、かつてケイオシウムを研究していた施設の成れの果てだ。地上にはこうしたトワイライト・エイジの廃墟が点在していた。ドニタはドクター・ウォーケンの命令により、ここで“ある物”を探していた。
建物に入ると、そこは大きな広場になっていた。薄暗く、微かにサビと腐った水の臭いがした。トワイライト・エイジの高度な技術によって作られたこの建物も、時間による腐食を完全に止めることはできなかったようだ。
「アレはいったいどこかしら。おそらく奥に仕舞われているのだろうけど……」
ドニタは首をくるっと回転させて広場を見回した。正面には奥に続く通路があり、右手には下へ降りる階段がある。左手には上りの階段があったようだが、崩れ落ちて登ることはできなさそうだ。
その光景を暫く眺めていたが、やがて心を決めたのか、ドニタはスタスタと正面の通路に向かって歩き出した。プロトタイプがその後を、僅かな軋み音を立てながら追い掛けていった。
通路に入ったドニタは、見掛けた所を端から調査していった。
しかし、多くの研究員を抱えていたであろうこの建物は、二人で探索するにはあまりにも巨大だった。
最初は、すぐに見つけることができるだろう、と楽観的に考えていたドニタも、時間が無為に過ぎていく探索にだんだんと焦りを覚え始めていた。
「手掛かり一つなし……。ここには無いのかな」
もういくつ目になるのかわからない部屋の探索を終えて、ドニタは深く溜息をついた。その表情はとても自動人形とは思えない、人間くさいものだった。
隙間から差し込んでいた陽の光はすでに薄れ、建物の中は暗闇が支配している。
「もうこんな時間」
自動人形であるドニタにとって、暗闇は探索の妨げにならない。彼女の目は通常の人間よりも遥かに高性能な作りとなっていた。
だがドクター・ウォーケンからは『一定期間ごとに必ず休息を取るように』と言われていた。さらに、二日間で発見できなかった場合には、ドクターの研究所に帰投することも。
「でも……それじゃあ探索は失敗してしまうわ」
休んでいたのでは、これだけ広い建物を探索することはできない。もしそうなったら……また、あの暗闇に帰らなくてはいけなくなる。
「……大丈夫。ワタシには休息など必要無い。このまま探索を続けられるわ」
ドニタは噛みしめた唇から決意の言葉を押し出した。
そして一度大きく頭を回転させると、傍らに佇むプロトタイプに声を掛けた。
「ほら、行くわよ木偶人形!」
弾かれたように動き出したプロトタイプと共に、ドニタは次の部屋へと足を向けた。
やがて陽が昇り、そしてその光が再び陰る頃。
休むことなく探索を続けて埃とサビにまみれたドニタの顔に、ようやく明るい表情が浮かんだ。
「こ、これが……そうかもしれない」
朽ち果てた遺跡の最下層。濁った水が膝の高さまで溜まった部屋で、ドニタは一つの箱を手に取った。
ドニタが探していたモノ――それはコデックスと呼ばれる、失われた過去のテクノロジーが記された知識の塊。
コデックス、つまり写本と呼ばれてはいるが、その形は様々で、メモリーチップや音声レコード、時には人間の口伝という形で残っているものもある。他ならぬドニタがこの世に生み出されたのも、まさにコデックスに記載された知識からであった。
ドニタが見つけた箱の中には、複雑な形をした機械のパーツが入っていた。長い間汚水に浸っていたにもかかわらず、その表面にはサビも傷も見受けられなかった。
「これで、胸を張ってドクターのところに帰れるわ!」
自分が役立たずではない、ということが証明できるのだ。
「やった!やったわ!」
ドニタは喜びのあまり大きな声を上げた。その声は濁った水が 溜まった部屋の中で反響し、やがて闇の中へと溶けていった。
建物から出ると、もう完全に陽は落ちていた。
すでに活動を始めてから数日が経過していたが、ドニタは疲労を感じていなかった。
「やっぱり、眠らなくてもワタシは平気なんだわ」
そう考えると、心の中の暗闇が光で照らされたような、そんな感覚が湧き上がってきた。
喜びの笑みを浮かべるドニタの目に、遺跡に入る前に倒した獣の死骸が飛び込んできた。
今はもう意識を持たず、自らの意志で動くこともない、ただの肉塊。
それはドニタから懸け離れた存在で、そうした存在を見ることで、ドニタは一層喜びを覚えるのだった。
「ほら、この木偶の坊。ぐずぐずしないで行くわよ」
そう。
ワタシはこんな木偶人形や、まして物言わぬ肉塊とは違う。
自らの意志で、自らの行動を決める、完全な存在なんだ。
「ららー♪ らららー♪」
ドニタは鼻歌を歌いながら、今にも踊り出しそうな足取りで、朽ち果てた遺跡を後にした。
「残念ながら、これはコデックスではないな」
探索から帰ったドニタに掛けられたのは、賞賛の言葉ではなかった。
「えっ、そんなはずは……」
「確かに、これはかなり高度な技術で作られているようだ」
そう言って、ドクターは箱の中にあったパーツを取り出して眺めた。
「しかし私が欲しかったのは、失われた技術によって作られた機械ではなく、技術そのものなのだ」
「……ワタシは」
ドニタの声が沈み、肩を落としたのを見て、ドクターが慌てたように声を掛ける。
「いや、このパーツ自体とても貴重なモノだ。研究すれば幾分かの技術も判明するだろう」
そしてドニタの頭に、ぽん、と手を置いた。
「良くやってくれたね、ドニタ」
それが帰ってきてすぐに掛けられた言葉であれば、ドニタは喜んだであろう。
もしくは、ドニタが愚かで、自分の意志を持たぬ人形であったならば。
しかし、ドニタにはドクターの言葉が偽りであることがわかっていた。慰めの言葉を掛けられたことが、却ってドニタの誇りを傷付けた。
「……申し訳ありませんでした」
このままでは役立たずになりてしまう。
「ドクター、ワタシをもう一度……」
もう一度探索に行かせてほしい。そうすれば、きっと成果を上げてみせる!
しかし、ドクターは笑顔のまま首を横に振った。
「ドニタ、少し休みなさい。君には休息が必要だ」
「また……眠るの?」
「そうだ。長い間探索をして疲れただろう」
「いやっ、ワタシは疲れてない!探索中もずっと……」
眠るのが怖かった。全てが暗闇に包まれる、その感覚が恐ろしかった。
一瞬、あの物言わぬ獣の死骸の姿がドニタの脳裏に浮かんだ。
嫌悪と恐怖。
「ドニタ、良い子だから。ゆっくりお休み」
嫌がって身悶えるドニタに構わず、ドクターの手がスイッチに伸びた。
「ワタシはもう、眠るのはいや……」
そう呟きが漏れた瞬間、ドニタの意識はぷつん、と切れた。
それから、ドニタは幾度となく地上の遺跡を探索した。
しかしコデックスは 見つからなかった。
「そんなに簡単に見つかるものではないよ」
探索に失敗して帰る度に、ドクターはドニタを慰めるように笑った。
だが、それはドニタにとって何の慰めにもならなかった。
何故なら、その後は必ず眠らされていたからだ。
睡眠はドニタにとって死と同じ。
自分が探索に失敗するから罰として死が与えられるのだ、と、いつしかドニタはそう思い込むようになっていた。
そして、ドニタがさらに幾度かの死を体験した後。
その男は遺跡の探索を終えたドニタの前に現れた。
「あんたがドニタという人形か」
「……お前は誰だ」
「俺はお前を救う者だ」
「救う?」
「そう。お前を暗闇から救うてやろう。俺達に協力してくれるのなら、という条件付きだがな」
「暗闇から……」
何を馬鹿なことを言っている。
そう笑い飛ばそうとした。
しかしその男の言葉には、ドニタを惹きつける何かが籠もっていた。
「………………」
「どうする? お前次第だ」
「……話を聞くわ」
「―了―」
3378年 「誘惑」 

遺跡の探索を終えたドニタは、正体不明の男と対峙していた。
ドニタを待ち伏せするように声を掛けてきた男。
この男は信用できない。
ドニタの理性は警告を発していた。
本来ならば、こんな奴についていくなんて考えられないのに。
(どうしてワタシはこの男と歩いているのだろう?)
この男に声を掛けられたとき、ドニタは一度無視しようと考えた。
それなのにこうしてついてきてしまったのは、「暗闇からの救済」という言葉があったからだろう。
自分の中にある暗闇への恐怖、そこから逃れる術があるなら、それにすがりたかった。
「いったい、どこに連れて行こうというの?」
ドニタは傍らに並んで歩く男に声を掛けた。
「もう少しだ」
男はそう言うと、むっつりと口を結んだ。
「あなた、名前は? 聞いてなかったわ」
「サルガドだ」
「どこにこれから行くの? 何があるの?」
「ついてくればわかる」
「答えないならワタシはここで帰るわ。無駄なことに費やす時間は無いの」
「永遠に暗闇から這い上がれなくても、か?」
サルガドは蔑んだような目でドニタを見る。
まるで人形か何かを見るような目つきだ。
そう、ドニタがプロトタイプを見るときのような。
「いやな目だわ。 ついて行けない」
ドニタは足を止め、強い口調で言った。
サルガドも立ち止まる。
「ワタシ、帰る」
ドニタとサルガドはしばらく睨み合っていたが、やがてサルガドが根負けしたように口を開いた。
「面倒な娘だ。 いいだろう。 我々はここからパンデモニウ ムに向かう」
「あのエンジニア達が住んでいる、天空に浮かぶ街?」
「そうだ。 あとは向こうに着けばわかる」
パンデモニウム、エンジニアによって管理され、地上の混乱から隔絶された、旧時代の繁栄を保つ都市。
「納得したか」
「……わかった。 もう少しだけ付き合ってみるわ」
エンジニアの技術の粋が集まる導都パンデモニウム。そこになら自分を救ってくれる何かがあるかもしれない。
ドニタの表情が明るくなった。
そして、その様子を見ているサルガドの頬にも、僅かな笑みが浮かんでいた。
暫くすると二人は、崩れた建物が点在するゴーストタウンに辿り着いた。
サルガドはまっすぐ、ぼろぼろになったとりわけ高い建物へと入っていった。廃墟となったその建物の階段を、二人は時間を掛けて上った。
錆び付いたドアを開けて屋上に出ると、そこには銀色の奇妙な乗り物があった。中空にあった太陽は沈みかかり、西日がその銀色の機械を朱く照らしていた。
「これで導都へ行く。 乗れ」
飛行挺のハッチを開け、ドニタを呼び込んだ。
「これ飛ぶの?」
乗り込みながら、前で計器を操作するサルガドに声を掛けた。
「そうだ。 揺れるぞ、捕まっていろ」
サルガドはスロットルを開け、飛行艇は廃墟のビルから飛び立った。そして一気に朱く染まった夕暮れの空に舞い上がった。
ドニタはどんどん小さくなる地上を眺めて、子供のように興奮していた。ただ、それをサルガドに悟られぬよう素知らぬ顔で窓を見ていた。
雲の上を進む飛行艇の前に、奇妙な光の錯乱が現れた。それは人の目ではわからなかったかもしれないが、ドニタの目には明らかに何か奇妙な屈折を起こしているのが見て取れた。同時に、サルガドは何かと交信をしていた。ドニタの耳にも交信の内容は聞こえたが、奇妙な符牒を組み合わせたその会話は、意味を汲み取ることができなかった。
交信が終わると、飛行艇は奇妙な屈折に向かって進んでいった。すると突然、視界の中に巨大な空に浮かぶ街が広がった。
「これがパンデモニウム......」
思わずドニタは呟いてしまった。廃墟と研究所を行き来する生活の中で見てきた光景とは、全く違う世界だった。本の挿絵でしか見たことのない、生きている都市。それも地上のどこよりも進歩した、黄金時代の建物が居並ぶその風景に、ドニタは釘付けになっていた。
パンデモニウムを旋回する飛行艇は、輝くアーチを掲げた建物に着陸した。陽はほぼ落ちていたが、パンデモニウムの建物は紫色に変わった空を鏡のように反射していた。
飛行艇を降りたドニタとサルガドは、建物内の長い廊下を歩いていた。
そこはドクターの研究所によく似た雰囲気を持っていた。しかし、その技術レベルの高さは、テクノロジー自体に詳しい訳でないドニタでも、一目でわかるほど際立っていた。
やがて二人は大きな扉の前に辿り着いた。
「連れて参りました」
サルガドが扉に向かって声を掛けると、向こうから女性が返事をした。
「ようやく来たか。遅いぞ、サルガド」
「申し訳ありません」
「後で呼ぶまで下がってよい」
「わかりました」
サルガドは扉に向かって一礼すると、
「さあ、入れ。レッドグレイヴ様がお待ちだ」
とドニタの背中を押した。
扉の中に入ると、部屋の中央に設置されている巨大な水槽が目に入った。
水槽の中には人間の脳が浮かんでおり、その周囲にまるで呼吸をしているかの様に、大きな泡がボコリボコリと不気味な音を 立てていた。
「よく来たな、ドニタとやら」
ドニタがその異様な光景に目を奪われていると、頭上から声がした。
反射的に上を見るが、そこには幾本もの太いパイプがあるだけで、人の姿はない。
「何者だ! どこに隠れている!!」
ドニタはいつでも戦闘態勢になれるよう身構え、叫んだ。
「どこを見ている。余はここにいるではないか」
またしても声は上から聞こえる。
しかし、いくら目を凝らしても、口の開いたパイプがあるだけで他には何も無い。
だが、声がする以上はどこかにいる筈……。
「……ま、まさか!?」
そんな筈はない。
まさか、アレが生きているなんて。
そんな思いを抱きながら、ドニタは恐る恐る水槽の方を振り返る。
「そうだ。余はここにいる。残念ながら、人の姿ではないがな」
頭上から聞こえる声に合わせて、脳の周囲に泡が発生する。
その有様は、これまでどんなものに対しても恐怖を抱かなかったドニタにさえ、怖気を感じさせる光景だった。
「どうした? この姿が怖いか。そなたも本を正せばただのガラクタであろうに」
「怖くなどない。ただ、そのような姿で、まさか……」
「まさか生きているとは思わなかった、か。それもしかり。余自身でさえ、この姿で生き存えていることに疑問を感じ始めたところだ」
ボコリ
ボコリ
レッドグレイヴと名乗る脳は、楽しげとさえ聞こえる口調で語る。
「余はレッドグレイヴ。このパンデモニウムから世界の監視を務めとしている」
ボコリ
その声は、まるで幼い少女のように高く、澄んでいた。
その声を聞いているうちにドニタの動揺も収まり、代わりに疑問が次から次へと湧き上がってきた。
「お前が、あの男の主人なのか」
「まあ、そうなるであろうな」
「お前はいったい何者だ! ワタシを暗闇から救う、とは何だ。そしてワタシに手伝えと言うのは……」
「落ち着け、人形。一度に聞かれても、余の口は一つしかない。いや……一つもないか。くっくっく」
そう言って、自らの冗談でくすくすと笑う。
「ふざけるな! きちんと答えろ!」
「落ち着けと言っておろうに。一つずつ答えてやろう」
「………………」
「まず、余が何者か、という質問だ。先にも言ったように、余は監視者である。人間が再び愚行にて世界を破壊しないよう、監視をしている」
「世界を、破壊......?」
「そうだ。まあ、生まれて間もないそなたに言っても、わからないだろうがな」
「ワタシに手伝えというのは、その監視とやらなのか?」
「いや、そうではない」
レッドグレイヴはそう言って、わずかな溜息をついた。もちろんそれは音声を伝えるパイプから聞こえて初めてわかったことだが。
「一見してわかるとおり、余はこのような姿である。この部屋に備え付けられた多くの機械で生命を保っている状態だ」
「今のところ生命に別状はないが、この姿では歩くことも外界を見ることも叶わぬ。世界には喫緊に解決すべき問題が生じている。外界へ出る手段が必要なのだ」
「体が必要なわけね。 それがワタシになんの関係があるの?」
「余の体を作り出すためには、そなたの父たるドクターが持っているコデックスが必要だ。そなたの体を生み出したようにな」
「ドクターの......つまりワタシは、ドクターヘコデックスを貸してくれ、と言えばいいのだな」
しかし、レッドグレイヴは小さく否定した。体があれば肩を竦めていたところだろう。
「ドクター......今はウォーケンと名乗っているそうだが、彼奴とは古い知り合いなのだ」
「しかし、こちらの正体をドクターに知られるわけにはいかん。根深い事情があってな」
「回りくどい話ね。 で、実際にどうしろというの?」
ゴボリ
レッドグレイヴの周囲に一際大きな泡が立つ。
「ドニタ。そなたに頼みたいのは、コデックスの強奪だ」
「強奪?」
「そうだ。そなたであれば、ドクター・ウォーケンからそれを奪うのも容易であろう」
「そ、そんな......そんなことはできない!」
ドニタは大きく首を振った。それは、紛れもないドクターへの裏切り行為だ。
「……それでそなたが救われるとしたら?」
ハッ、とドニタの顔が上がる。
「どういう、ことだ?」
「そなたの恐れる闇、余は克服しておる」
乳白色の脳はぴくりとも動かない。本当にこの物体が今、語っているのだろうか。
「余が力を貸せば、夜も、闇も、眠りも、もう恐れるようなことではなくなる」
ポコリ。また、ポンプが送り出す水泡の音が響く。
「迷っているな。闇への恐怖はだれにでもある。それは死への恐怖だ。誰もが皆、闇から生まれ闇に帰って行く。しかし、余は永遠の光明の中にいる者だ」
「古い叡智によって余は遥か過去からここにいる。その叡智の一部をそなたに分け与えよう」
「お前が本当にずっと生き続けているという証拠は? いま見ている水槽の物体も、声も、茶番でないと証明できるの?」
「ふふふ、信じないのは自由だ。ただ、そなたを救えるのは余だけだ」
「……」
ドニタの心は、まさに二つに割れようとしていた。
そんなドニタの様子を見て、レッドグレイヴは面白そうに笑った。
「まあ、今すぐに決めなくともよい。そなたも余も、まだ時間はたくさんある」
「………………」
「一度、ドクターの元に帰るがよい。そして、もし余の要求を呑むというのなら、また余の元へ来い」
「で、でも、そのときはどうしたら……」
「心配しなくともよい。その時が来たら、余の方から迎えに行く」
「………………」
「それでは、な。よい返事を期待しているぞ」
「―了―」
3378年 「暗闇の箱」 
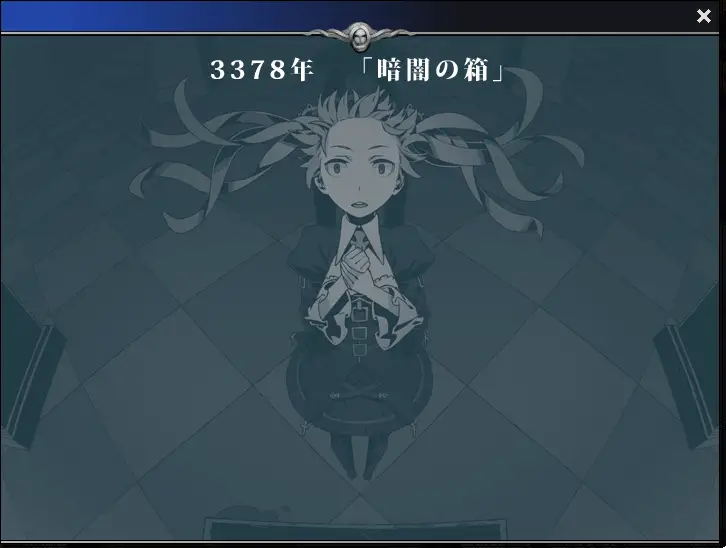
ドニタは迷っていた。ドクターを裏切る事などできないという気持ちと、闇への恐怖との間で不安定になっていた。
「ドニタ、最近調子がよくないようだな」
遺跡の探索作業がうまく進まず、ドクターにそう聞かれるようになっていた。
ドクターはただ優しく問い、少し休むかどうかを聞くだけだった。がしかし、ドニタにはそういう思いが、却って追い詰められる形になっていた。
ある夜、ドニタはドクターが眠ったのを見計らって研究室に忍び込んだ。レッドグレイヴが欲しいという、コデックスがどこにあるのかを調べたくなったのだ。盗むかどうかは決めていなかった。ただ、どんなものかを知りたかったのだ。
ドニタは、ドクターが普段使っている作業コンソールを操作した。
古いものだったが、たくさんの資料がこの中に電子化されて所蔵されている。過去のコデックスは全て読み取られ、この中に 取り込まれている筈だ。
オートマタの生体機能、人工知能論、ケイオシウム機関のチューニングなど、様々な項目が画面一杯に表示されている。自分が探し出してきたものもいくつか収蔵されていた。古の知識が かなり、ここに存在するのがわかる。
その時、研究室に電気が点いた。
「どうした、また眠れないのか?」
ウォーケンが研究室の入り口に立っていた。ドニタは慌ててコンソールを消し、飛び退くように机から離れた。
「何か調べ物のようだな」
ウォーケンがドニタの傍まで歩いてくる。
「ワタシ、怖いんです。 まだどうしても。ああ、どうしたらいいのか……」
激しく首を振るドニタ。
「混乱しているようだな。 もう放っておくことはできない。調整してみよう」
「調整?」
「そうだ。君を一度分解して、暗闇への恐怖を取り除いてみよう」
「分解……でもそれは、ワタシが……また、闇に」
頭を抱えてしゃがみこむドニタ。
「何も恐れることはない。 といっても無駄か。 堂々巡りだな」
突然、ドニタの中で暗闇への恐怖がフラッシュバックした。何としても逃げ出さないと、という焦りが、暴力として吹き出した。
ドニタの抜き手がウォーケンを貫こうとする。明確に殺意を持った技だった。ウォーケンは紙一重で避ける。
「ふむ、これはいかんな」
ドニタは全力の抜き手を躱された反動で、作業台の上を転がるように滑った。が、すぐに体勢を立て直してウォーケンに向き直る。腰を落とした戦闘態勢だ。
「仕方ない」
ウォーケンが手を強く振った。次の瞬間、ドニタはその場に崩れ落ちた。ドニタの額にはウォーケンの放った針が突き立っている。機能停止へと至る装置への、寸分違わぬ一撃だった。
「かわいそうだが、これが最善だ。 もう少し早く決断すべきだったな」
機能停止したドニタは、人形として机の上に置かれた。
ウォーケンはその日の内にドニタを分解し、記憶の断片を掘り下げる作業に取り掛かった。
ウォーケンにとって、ドニタは思い入れのある大切な人形だった。実用的なオートマタの修理や製作ではなく、まるで人間のようなこの娘を、なぜ少女の人形を創ろうと思ったのかは、よくわからない。ドニタは、自分の内なる衝動が創らせた不思議な人形だった。
完成した後、自分によく尽くしてくれるドニタを受け入れている気持ちはあった。と同時に、不気味な違和感を覚えていたのも事実だった。まるで、失われた記憶がこの娘を創らせたのではないか、という思いがあった。
「この子の恐怖の源、取り除けるといいが」
作業台にドニタの頭部を繋ぎ、コンソールを操作してドニタの記憶を時系列に眺めた。イメージとして残る鮮烈なものから、すでに圧縮処理されてエピソードとして保存された記憶まで、注意深く調べていった。
「これは……」
ウォーケンはドニタの記憶の中に鮮烈なイメージとして残っていたものを拾い上げた。それは、ドニタがパンデモニウムに連れて行かれるという記憶だった。
「きちんとチェックしておくべきだったか」
ドニタはレッドグレイヴと名乗る奇怪な化け物から取引を持ち掛けられていた。
「パンデモニウムめ、謀ったな」
ウォーケンは、今は物言わぬ人形となったドニタしかいない部屋で呟いた。
「ソングさん、私は騙されるのはあまり好きじゃない」
「何のことです?」
パンデモニウムの代表として取引を持ち掛けてきたソングへ、ウォーケンは切り出した。成果物の報告があると呼び出したのだ。
「レッドグレイヴという人物が、私からコデックスを奪おうとドニタを誘惑してきた」
ソングは改めて意味がわからないといった表情を浮かべた。
「初めは互いの利益ということだった筈だが、その所為でドニタを分解しなければならなくなったよ」
「そ、それは……私は聞いていない。確認させてくれ」
ウォーケンの静かな怒りを感じ取り、怯えたソングが席を立とうとする。
「安心したまえ、私は誰かを傷付けたりする趣味は無い」
そう言うとウォーケンは、黙ってカップの紅茶を飲み干した。
「ただし、レッドグレイヴと話をさせてもらおう」
「わざわざ来たか」
レッドグレイヴの居室は奇妙な機械で溢れていた。そしてその部屋の中心に、巨大な水槽に浮かぶ脳があった。
「私を騙すのに、小賢しい真似はしないでもらいたい」
ウォーケンはレッドグレイヴの前にいた。彼を居室に連れてきたサルガドは、入り口に立って辺りを監視している。
「あの人形のことか。 確かに回りくどい真似をさせてもらった」
レッドグレイヴははぐらかさずに言った。
「初めは、お前が『あの男』だと気付かなかったのだよ」
「あの男?」
「記憶を失う前のお前だ。 『本来のお前』と言ってもいい」
自分の過去について、レッドグレイヴは何かを知っているらしい。
「私は私だ」
ウォーケンは自分の過去に惑わされることに疲れていた。取り戻すことのできぬ過去より、有意義な今を選択したのだった。
「しかし、記憶が欠けていることは認めるのだろう?」
「貴様にそれが関係あるのか」
自分でも感情的になっているのがわかった。
「それはお前次第だ。 だが全てを思い出した時、お前は余を生かしておくまい」
「私は誰かを殺めたいなどと思ったことは無い」
「それは好都合」
脳の周りの泡が音を立てて弾ける。まるで笑ったかのようだ。
「私はウォーケンだ。 過去は関係ない」
「よろしい。ならば元の契約どおり、互いの利益になるよう取り計らおう」
「最後にもう一つ言っておく。……二度と私を騙すような真似はするな」
「取引は取引だ。 我々にお前の知識や技術が必要なのは、紛れもない事実だからな」
パンデモニウムで行ったレッドグレイヴとの交渉を終えた後、ウォーケンはドニタを再び組み立てることに躊躇した。不具合の原因も曖昧なままであったし、己の記憶について考えるところもあった。しかし他に誰か助手となる人物がいる訳でもなく、ここまでの機能をもった彼女を放っておく訳にはいかなかった。ウォーケンはドニタを組み立て直すことを決心した。 ただし、全ての記憶を消去することにし、一切をゼロから起動させた。残酷なことだったが、不具合の原因を探るためには仕方のないことだった。
「こんにちは、ドクター」
ドニタは素直な助手として、変わらずに機能していた。
しかし数ヶ月が経つと、また暗闇を恐れるようになった。与える知識や機能の微調整を行っても、必ず同じような狂気に陥った。
「お願い、ワタシを切らないで。 ドクター」
哀願するドニタ、反抗するドニタ、どのドニタもウォーケンはリセットした。記憶を消され、その度に同じような笑顔を浮かべて蘇る少女。
彼女に苦しみは無いかもしれない。しかし、それを観察し続けるウォーケンの心には、重たい澱のようなものが溜まっていった。
気が遠くなるほどの失敗を繰り返した後、ウォーケンはドニタと同じ体をもう一つ、一から創り直してみることにした。 名前も変えて育て直してみた。しばらく様子を見ると、かなり 安定しているように思えた。
どこが失敗したのかを調べるために、今度はドニタとそのコピーを少しずつ差し替えていき、どの機能、またはパーツのせいで狂気に陥るのかを調べることにした。随分と時間が掛かったが、あるAIを司る電脳機能に不具合があることがわかった。
「これか!」
AIの修正を行った後、ドニタを起動させた。
「おはよう、ドクター」
いつもと同じように目覚めたドニタを、ウォーケンは笑顔で迎えた。彼女はとても安定しているかのように見えた。しかし、完全に修正されたかどうかは、ある程度の時間が経過しなけれ ばわからない。
ドニタの不具合を調べるために創ったもう一体の少女型オートマタは、人間の世界に送ることにした。クライアントから請われたのもあったが、この人形に様々な経験を積ませてみたいという気持ちもあった。最終的には、持ち帰った記憶をドニタと統合してもいいと思っていた。ドニタのコピーは『シェリ』と名付けられ、記憶をリセットした上で人間界に送られた。
とある新たな人型オートマタをパンデモニウムに納品する時、そこにレッドグレイヴが現れた。今の彼女はウォーケンが作った機械の身体を手に入れている。
「こんなもの、どうするのだ」
パンデモニウムに作成を依頼されたこの女性型オートマタには、奇妙な装置を付けさせられていた。
「こちらも様々な研究をしている。 平和主義者のお前には興味の無いことだろうがな」
ウォーケンは、自分の過去を知るこのテクノクラートを避けていた。そこには、過去の自分への恐れが隠しようもなく存在していた。
「もう一人の娘はどうしている? お前に似ず、平和主義者でない娘の方だ」
「シェリのことか」
シェリが殺人を請け負っていることは知っていた。人間に興味を無くしている自分にとって、それはどうでもいいことだった。自分が人を傷つけることと、自分の創った機械が誰かを傷つけることは、ウォーケンの中では別のことだった。彼は博愛主義者でも何でもなく、ただ自分が振るう暴力を恐れているだけだった。
「地上から奇妙な報告があってな。 悪い遊びは控えさせた方がいいぞ。 くくく」
最後にレッドグレイヴはそう言って去っていた。
地上に戻ったウォーケンは、ドニタにシェリを探させた。シェリを預けてあるギブリン翁と連絡が付かなかったのだ。
「世話の焼ける娘ね」
ドニタは安定している。再起動から一年以上経つが、今のところ問題は出ていない。
「ああ、でも君の妹だ。 頼むよ」
「わかりました。 でも、都市に出るのなんて初めてだから、 ちょっと愉しみ」
ドニタは代わり映えのしない荒野や遺跡ではない、帝都ファイドゥに行けることを楽しみにしていた。
「君達には簡易的な共感機能がある。 シェリの居場所は、近くまで行けばわかるはずだ」
「それは、たとえ死んでいても?」
ドニタはシェリのことをあまり良くは思っていない。似すぎている所為だろうかと、ウォーケンは思った。
「シェリも君も死にはしない。 止まることはあってもね。 完全に破壊することも、地上の人間達では無理だろう」
「そう、つまんない。 見つからなかったら、しばらくファイドゥを見て回ってもいい?」
「だめだ。一週間で帰ってきなさい」
「はーい」
「暢気なものだな」
ただ、安定しているドニタに、ウォーケンは安心もしていた。
ファイドゥに辿り着いたドニタは、活気に満ちたこの街を巡るのを愉しんでいた。しかし、ドクターの命令は彼女にとって絶対だ。まず、シェリが住んでいる筈のギブリンの屋敷へ向かった。
「どこなの? シェリ」
荒れ果てた屋敷の前で声を張るドニタ。何の反応も無い。
「仕方ないわね」
中を探るために屋敷へと入った。ものを探すことには慣れている。
正面の扉を抜けたエントランスは荒れ果てていた。ドニタは一警しただけで、有意義な情報を取り出す走査を終えた。沢山の足跡とその埃の積み重なり具合から、どんな体格の人間が、どれくらいの時間差を置いて歩いたかを導き出した。その中にはシェリの足跡もあった。そしてシェリのものではない、一際新しい足跡を見つけた。それは一直線に大広間へと続いていた。 足跡を追って、元は豪奢だったであろう大広間に辿り着いた。 巨大なテーブルは砕かれて壁際に置かれており、調度類も金目の物は全て持ち去られている。その荒れ果てた広間の中央に向 かって、足跡は続いていた。
そこに箱が置かれていた。
ドニタはすぐにそれが何かわかった。広間の入り口から4.5アルレ離れた場所にあっても、見慣れた『それ』を見間違う筈 がなかった。
「シェリ……」
ゆっくりとドニタは箱に近付いていった。箱に無造作に詰められていたのは、バラバラになったシェリだった。靴を履いたままの足がふくらはぎを上にして飛び出し、そこに有り得ない方向に曲がった腕が添えられている。それはドニタにとって見慣れた自分の足であり、腕でもあった。胴体からもぎ取られた首はこちらを向いているが、反応は無い。完全に機能が停止しているようだった。
暗い広間でドニタは立ち尽くしていた。
自分と同じ人形の砕かれた手足やもがれた首をじっと見ていると、ドニタは視界が溶けていくような感覚に襲われた。
「―了―」
3392年 「閃光」 
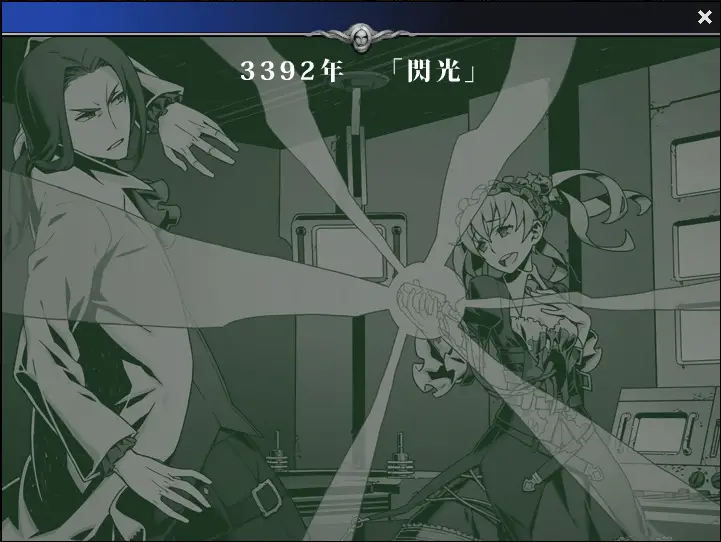
バラバラにされたシェリのパーツを抱え、ドニタはドクターの元に戻った。
ドニタの表情は固まったままだ。ウォーケンはその様子を見て取り、一言、シェリの惨状にも動じることなく言った。
「直せる。 心配するな」
黙ったままのドニタからシェリの入った箱を受け取り、ウォーケンは自分の研究室へ向かった。
ドニタの心はバラバラになったシェリの、いや、自分自身が完全停止したヴィジョンに取り憑かれていた。いつまでも続く暗闇。そこにずっと閉じ込められ放置される自分。
いつか自分もそうなる。その思いが頭の中にこびり付く。
ドニタは研究所の床にそのまま座り込んだ。壁に寄り掛かり、頭を抱えて自を瞑る。そうして、自分の記憶からヴィジョンを取り除こうとしていた。
しかし目を閉じると、四肢を砕かれて物言わぬ姿になった自分自身の姿が甦ってくる。震えと目眩を感じ、じっとしていることに耐えられなくなった。どうにか立ち上がると、自室に向かった。
自分のベッドの上に座って大好きな本を取り出した。
古の時代に書かれた御伽噺を纏めたものだ。美しい挿絵と時に残酷な教訓話を、彼女は愛していた。
一ページ一ページと手繰って心を落ち着かせようとする。
――色取り取りの世界。人語を話す動物達。愉快で残酷な結末。
――こころを自分の外に出した御伽噺の世界。自分が魔法使いの弟子になる。
そういった想像によって、あの嫌なヴィジョンから自分を解き放とうとしていた。
本の世界に入り込んで心が落ち着き掛けた時、壁の連絡用コンソールが鳴った。
博士の声が響く。
「ドニタ、研究室に来てくれ。 頼みたいことがある」
「すみません。 いま気分が悪くて」
「すまんが、こちらも急なんだ」
ドニタは本を持ったまま研究室に向かった。
「ワタシ、調子が悪いみたい。ドクター」
本を抱えたまま、怯えた表情でウォーケンにドニタは語った。
「そうか。 ではシェリと一緒に検査をしよう。そこに横になって」
「え……ワタシに何かするの? 今は嫌……」
「一時的に君の体を借りるだけだ。君には何の害も無い。不安も取り除いてあげよう」
ドニタは怯えた表情のまま固まった。
「……博士、ワタシが悪いことをしたから、そんなことをするの?」
「何を言ってるんだ。 君はよくやってくれている。 シェリがこうなったのはーー
「……ワタシ、が裏切ったから?」
「何だって?」
ウォーケンは消去した等の記憶についてドニタが話し出した事に驚いた。
「そうでしょう? だからワタシを消すんだ」
「違う、そんなことはしない。 シェリがこうなった理由を調べるために、一時的に君の――」
「ワタシに関係ないよ……」
「疑似信号を作るのに、一時的にデータを取るだけだ。君には何も影響はない」
「ワタシ、関係ないって言った! そんなガラクタ女、最初からいない方がよかった!!」
ドニタは大声を上げて本を床に叩き付けた。
「ドニタ、落ち着くんだ」
「もういい。 終わりにする。ワタシ、ここからいなくなる!」
「仕方がない。 君に何があったかも調べなければならないようだ」
ウォーケンはコンソールを操作し、遠隔操作でドニタのメインスイッチを切った。
自分が叩き付けた本と並ぶように、ドニタは床に横たわった。
ドニタは暗闇の中にいた。大好きなあの物語の中だった。挿絵にあったとおりの青々とした木々が茂る森の中だ。鳥の囀りが聞こえる。
「そうだ、ワタシ、魔法使いのフラウ・トルーデに会いに行くのだったわ」
美しい色彩の森をドニタは笑顔で進んだ。
しばらく進むと、黒い男が森の出口に立っていた。目も鼻も無く、ただ黒いヒトの姿だけが空中に浮かび上がっている。
「永遠に生き続ける者などいない。 誰もが暗闇に戻るのだ」
黒い男は立ち塞がるようにドニタの前に立った。
「いいえ、ワタシは死なない。 だって、そう作られたんだもの」
ドニタは黒い男を無視して魔法使いの家に向かった。
今度は魔法使いの家の前で緑の男に出会った。やはり目鼻の無 い、全身が緑色の男がいた
「裏切り者は罰を受けなきゃいけない。 行動には結果が伴う」
「ワタシは間違ってない。 ワタシはしたいことをしただけ」
緑の男の傍をそう言って通り過ぎた。
家の一階には赤い男が立っていた。全身が赤く、まるで血だけで作られたような存在だった。
「お前は死を運ぶ。 誰にも望まれていない娘だ」
赤い男は指を突き付けてドニタにそう言う。
「他人は関係ない。 ワタシはワタシのために生きるの」
ドニタがそう言い返すと、赤い男は消えた。
二階に上がると老婆が座っていた。紫色の髪を束ね、安楽椅子に腰掛けている。
「よく来たね」
「あなたがフラウ・トルーデね。 でも、そこの窓からは赤い髪の化け物が見えたのに」
「お前が見たものは全部正しいよ。 お人形さん」
「そうかしら?」
「さて、なぜここに来た?」
「ワタシ、もう嫌なの。 どうしても逃げ出したいの。だからここに来たの」
「親が嫌いか?」
「嫌いじゃない。 だからワタシは苦しいの。 とても」
「そうか。 ならば助けてやらないこともない」
「本当?」
「家族皆で幸せに暮らせる世界に行く方法さ」
魔法使いは微笑みを浮かべながらそう言った。
「ドニタ、起きてくれ」
ウォーケンの声でドニタは目を覚ました。
「全てを思い出したよ! なぜ君らを作ったのか。 自分が何をすべきなのか」
ウォーケンの表情からは普段の冷静さが消えていた。
「すぐに手伝って欲しい。 シェリの力も必要だ。 さあ、起きて作業を始めるんだ」
ドニタはゆっくりと起き上がった。眠る前と何も変わっていないことを確かめる。
「ドクター。 ワタシ、話したいことがあるの」
「すまないが後にしてくれないか。 急がないといけない。早く彼女の元へ行く用意をしないといけないんだ」
ウォーケンはシェリの修理を進めていたため、ドニタに注意を向けていなかった。
「じゃあ、そこで見ていてくれればいいわ。 これで皆が幸せになれるの」
「何だって?」
振り向くと、ドニタの手には自らの腹部から引き摺り出したケ イオシウムバッテリーが握られていた。 ドニタの体液は辺りに飛び散り、内臓器官も床に散じている。
「何を馬鹿なことを……」
ウォーケンはドニタを停止させようとコンソールに向かったが、それよりも早く、ドニタは彼の目の前に立った。
「これでみんな幸せ」
ドニタは目を見開いて笑いながらケイオシウムバッテリーを握り潰した。
次の瞬間、ウォーケンとドニタは目映い閃光に包まれた。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ