ナディーン
3372年「咆哮」 
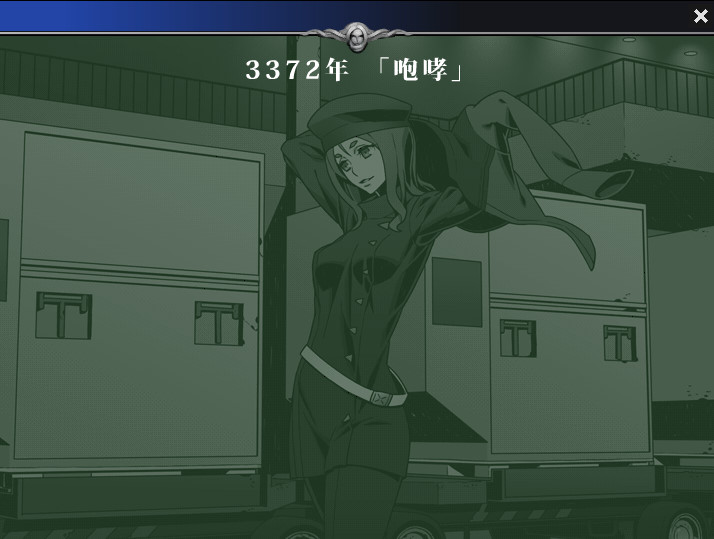
周囲には淡い光が明滅しており、小さな渦を形成しているかのように見えた。
視線を動かすと、四肢をもがれ、さらに胴体と頭部が切り離された少女の自動人形があった。
「何も変わらぬ。貴様の行動は全て無意味だ」
自動人形が口を開く。姿形に見合わぬその声色には、スクラップと化してなお威厳があった。
ナディーンは物言いたげに見つめてくる硬質ガラスの瞳を一瞥した。
「全ては世界の……ため……に……」
自動人形の言葉が途中で途切れる。完全に機能が停止したようだ。
何の感慨もなかった。全ては遅すぎたのだ。虚無感がナディーンを支配していた。
「お疲れ様、がんばったねえ」
眠たそうな目をしたエンジニアが杖を突きながら歩いてきた。
どこから現れたのか、ナディーンにもわからなかった。
「……貴方は」
その刹那、ナディーンの視界を黒い蝶が覆い隠していく。
「だけどねえ、間違っていたんだよぉ。君も、私も」
身体を揺さぶられる衝撃と、いつもと変わらないのんびりとした調子の『彼』の声だけが響いていた。
「ナディーン技官、起きてください」
エンジニアの一人がナディーンの身体を揺すっていた。
目を覚ましたナディーンは周囲をぐるりと見回した。
大型の機械が絶え間なく動く音が聞こえ、その機械の先には大きな飛行艇があった。
「交代の時間です、ナディーン技官」
「もうそんな時間か……。ありがとう」
起き上がって帽子の位置を正し、椅子に掛けてあった作業着を羽織ると、起こしに来たエンジニアと交代で外へ出た。
外では作業服姿のエンジニア達が、間を置かずに大小のコンテナを運んでいる。
ナディーンは飛行艇の搬入口に立ち、協定審問官や中央統括セ ンターに所属するエンジニアが飛行艇のことを探りにこないか、じっと監視していた。
一年程前、とあるライブラリアンの手によって、薄暮の時代の最高指導者レッドグレイヴが目覚めた。
類稀な指導者であるレッドグレイヴは、怠慢により堕落した導都パンデモニウムの体制を再統治した。そして、《渦》を世界から消滅させるべく行動を開始した。
レッドグレイヴはまず、《渦》の災厄の元凶であるケイオシウムに関して、その研究の一切合財を放棄するよう求め、キングストン協定を制定した。
これによってケイオシウムの研究は厳重に管理されることとなった。ケイオシウムに関連するほぼ全ての研究所は解体が決定され、ケイオシウム研究者達は厳しい監視の下、《渦》の調査に限り特例で行動を許されるのみとなった。
これに猛反発したのが、ケイオシウム研究の最先端を行っていたパストラス研究所であった。だが、所長のハワードが中央統括センターへ抗議に出向いたものの、レッドグレイヴはその抗議に耳を貸すことはなかった。
パストラス研究所の抗議も虚しくキングストン協定の施行が進んでいく中、ハワード達ケイオシウム研究者は地上への逃亡を計画するに至った。
その移動手段として用意されたのが、ナディーンの眼前にある飛行艇だ。中央には地上調査のためと申し出てあった。
逃亡計画は、ハワードを筆頭とするケイオシウム研究の権威とされてきたテクノクラートではなく、末端のエンジニアが中心となって進行されていた。レッドグレイヴの目から少しでも逃れるための策であったが、これが功を奏したのか、計画に協定監視局の手が伸びることはなかった。
搬入口でエンジニア達の出入りを見ていると、汎用ポータブルデバイスに通信が入る。
「ナディーン技官、地上調査計画の参画者を飛行艇に集めてください。飛行場にいる者だけで構いません」
「何があったんだい?」
「あと10分ほどでそちらに到着します。説明はその時に」
エンジニアからの通信が切れる。ナディーンはそのままポータブルデバイスを操作すると、飛行場内にいる計画参加者に向けて、緊急の暗号通信を送った。
搬入口や飛行場の出入り口が低に慌ただしくなる。
「何があったのだね?」
搬入口の扉が閉まったところで、飛行場の管理局員がナディーンに尋ねてきた。
「調査に使う機器に不具合が見つかった。渦の調査に必要な重要機器のため、飛行艇の中で緊急ミーティングを行う」
「それは失礼した」
予め取り決められていた言葉で管理局員を納得させると、ナディーンは飛行艇に乗り込んだ。
飛行艇の中は細工が施されており、盗撮、盗聴、防音に細心の注意を払った設備が備え付けられていた。
程なくして、ナディーンに通信を入れたエンジニアが到着した。
「緊急報告だ。パストラス研究所が審問官の襲撃を受けた」
飛行艇内のエンジニア達にどよめきが起きる。
パストラス研究所にはハワードや元研究員が密かに詰めていた。そこを狙われた形になる。
「研究所にいた者は全員が投獄された。だが、我々は我々が求める研究のためにも進まねばならない」
沈痛な空気がエンジニア達を包んだ。
協定監視局に投獄される、それは死と同義だった。
だが、この逃亡計画を頓挫させる訳にはいかなかった。
ナディーンは協定監視局の地下に作られた特別房へと案内された。
そこにはやつれ果てたハワードの姿があった。
ハワードは、処刑前の最後の面会人にナディーンを指定していた。
「ハワード所長」
ナディーンの呼び掛けにハワードは顔を上げた。
「君には申し訳ないことをした。君の知識は我々に恩恵をもたらしてくれた。なのに……」
ハワードは再び頭を垂れた。彼の膝は小刻みに揺れていた。
「何を謝る必要があるのですか?私がここにいるのは貴方のおかげです」
「他の所員達にも伝えておいてくれ。私の不甲斐なさが今回の件を招いてしまったと」
ナディーンは審問官達に気付かれぬよう注意しつつ、ハワードの膝に視線を移した。
それは一見、処刑への恐怖で震えているように見えるが、実際は一種の暗号であった。
ナディーンとハワードの間でしか通じない秘密の暗号。
キングストン協定が定められた後、どちらかに何かがあった時のためにと決めていたものであった。
面会が終わり、ナディーンは飛行艇へと戻った。
誰もいない飛行艇の一室で、普段は被ったままの帽子を脱ぐと、狐のような耳が現れた。
耳が外気に曝され、寒さに身震いする。
ナディーンはパンデモニウムの住民ではない。
数年前に地上調査に赴いたハワードによって発見、保護された、異界の住民だった。
ナディーンはハワードから伝えられた暗号を思い返していた。
ハワードが送った暗号は、端的ではあったが、決定的なことを告げていた。
「レナート……」
ハワードの暗号にあった名前を呟く。その名前には覚えがあった。
ナディーンがハワードと面会をした翌日、パストラス研究所で捕らえられたエンジニア達の処刑が執行されたと、大々的に報道された。
それは見せしめであった。
逃亡計画に参加するエンジニア達は、その報道を無表情に聞くことしかできなかった。
それから少しして、地上へと出発する日がやって来た。
エンジニア達は緊張した面持ちで飛行艇の最終検閲を受けていた。
貨物の全てが地上調査用機器として偽装を施してあるため、計画が露見する危険は小さかった。
しかし万が一のこともある。 緊張の一瞬であった。
全ての検閲が終了し、飛行艇のハッチが閉じられた。あとは離陸するのを待つばかりだ。
その時、大勢の審問官達が飛行艇を取り囲んだ。飛行艇に緊急通信が入る。
「ここで協定違反をしているとの情報が入った。積荷を検めさせてもらう」
飛行艇のエンジンは既に始動していた。通信機越しに、代表のエンジニアが会話を続ける。
「我々の計画は中央の認可を得ています。何かの間違いではないでしょうか?」
「聴取による情報は確かだ。逆らうとお前達のためにならんぞ」
「わかりました。しかし、既にこの飛行艇は発進準備に入っています。しばし時間を頂きたい」 通信を切る。代表に皆の視線が集まった。代表は一呼吸してから告げる。
「すぐに飛行艇を発進させろ」
「はい!」
飛行艇が動き出した。ナディーンは飛行場の様子が見渡せる窓に走る。
「ナディーン技官、審問官の動きは?」
「どこかへ向かいました。武装クリッパーが出撃してくる可能性があります」
「わかった、引き続き監視を頼む」
審問官がやって来る可能性は想定していた。計画に関与する者が処刑されることも、審問官が検閲に来ることも、ありとあらゆる事態が想定されていた。
「……早い!」
飛行場から飛び立って数分後、背後から武装クリッパーが迫るのが見えた。そのスピードは想定していた以上だった。
「6時の方向から武装クリッパーが迫っています。数が多い。機影10!」
「奴等は本気だ!何とか引き離すぞ、速度を上げろ」
代表の指示が聞こえて間を置かず、ナディーンはどこかに引っ張られるような感覚に襲われる。同時に武装クリッパーとの距離が開いていくのが見えた。だが、豆粒ほどの小ささの武装クリッパーが砲門を開いたのを、ナディーンの目は見逃さなかった。
「武装クリッパー、撃ってきます」
「高度を下げろ、射線から外れるんだ」
武装クリッパーから放たれた弾丸が、ナディーンが覗いている超硬質ガラス窓ぎりぎりのところを掠めていく。
武装クリッパーの動きは早かった。飛行艇の背後で衝撃が起きる。撃たれたことは明白であった。
「エンジンに被弾、出力低下!このままでは墜落します!」
飛行艇はどうにかして姿勢を維持した。エンジニア達は積んでいた調査用クリッパーに手早く乗り込むと、荷物と共に飛行艇から蜘蛛の子を散らすように飛び立っていく。ナディーンも同様に決められていたクリッパーに乗り、飛行艇から脱出した。
しかし武装クリッパーの追撃は収まらない。追いついてくると有無を言わさずに撃ってきた。
「審問官め……」
他の仲間の様子はわからない。ほとぼりが冷めた頃に定められた地点で合流する手筈にはなっていた。
だが、それも年単位での潜伏を考えてのことである。
渦がどこで発生するかわからないことも合わせれば、一度離れ離れになれば再合流は難しいことは、口に出さずとも皆わかっていた。
だがしかし、それでも逃げなければならない。この研究を絶や してはならない。
導都パンデモニウムの研究者であるという意地とプライドが、エンジニア達を突き動かしていた。
「何だと!ケイオシウム汚染濃度が上昇している!?これは……渦が発生します!」
「こんな時に……。場所は?」
「まずい!背後です!」
同乗していたエンジニアの鋭い声がクリッパーに響き渡る。
空中にいる筈なのに、地面が揺れたような衝撃が機体を襲った。
「駄目です、渦に飲み込まれます!」
「操縦不能! 機体が――!!」
エンジニア達の混乱する声が錯綜する。クリッパーは見えない手で引き裂かれるようにバラバラになった。
渦の中に落ちていくナディーンとエンジニア達。背後に迫っていた審問官の武装クリッパーも同様だった。
落下していく最中、ナディーンはクリッパーを引き裂いた異形の姿をその目で見た。
揺らめく無数の触手、眼前に迫る暗闇、そして空間を揺るがすほどの咆哮。
そのどれもにナディーンは覚えがあった。
忘れられる筈もない。それは――
「妖蛆……」
「―了―」
「接触」 

古の時代、この世界に偉大な魔法使いがおり、その者は超大な力を市井の人々のために振るっていた。
しかしある時、心無き者が魔法使いを害してしまった。復讐の念に取り憑かれた魔法使いは、自らを巨大な蛆の姿に変えた。
復讐を果たした魔法使いは、尚も我を忘れたままその姿で生き続けている。
そして、魔法使いはいつしか『妖蛆』と呼ばれる存在となった。
それは大母、大叔母に伝えられる伝承だが、ナディーンはある事情からこれを幾度となく聞かされていた。
宝珠の森に生まれた者は、宝珠を妖類や外敵から守る戦士となるか、あるいは森の長である大母と共に宝珠を奉る者となるか、いずれかの選択をしなければならなかった。
しかしながら、宝珠を奉る者になるには特別な才が必要であるため、殆どの者は戦士となる。
ナディーンの両親も、この例に漏れず森を守る戦士だった。
特に父親は、並び立つ者は暫く現れないだろうと言われた強者であった。
「行ってくる」
勇ましい父の手が、幼いナディーンの頭を撫でた。
「すぐに帰ってくるわ。いい子にして待っててね」
凛とした母がナディーンを抱き締めた。
「うん。いってらっしゃい」
それが、父母と交わした最後の言葉だった。
両親は森を守るために死んだのだ、と言われた。
宝珠の封印から逃れた妖蛆の一部が森を襲った時、妖蛆を森から引き離すために、宝珠と同じ気配を身に纏い、囮になったとのことだった。
大母はナディーンにかの伝承を明かし、両親は伝説の災厄に立ち向かった素晴らしい戦士であったと説いた。
森の戦士や大叔母達も、彼らを勇気ある英雄と称えた。
――だが、妖蛆がどれ程危険で、どれ程森の民にとって脅威かを説かれても。
――その妖蛆に立ち向かった両親が、とても素晴らしい英雄だったと称えられても。
――両親との平穏な暮らしを奪った妖蛆を。
――自分を置いて森を守ることを選択し、二度とナディーンの 元に帰ってこなかった両親を。
「ゆるさない」
と、ナディーンは強く憎んだのだった。
それからのナディーンは、ひたすらに強さを追い求める戦士となった。
なり振り構わないナディーンの態度は、他人には両親の仇討ちに燃える復讐者と映った。
しかしナディーンにとって、妖蛆の討伐は仇討ちなどではなかった。
両親が果たせなかったことを成し遂げることで、両親へ復讐しようと考えていたのだ。
そこまでして強さを追い求めたナディーンだったが、『黒い夜』にやって来た『黒いゴンドラ乗り』達に、その矢は一本も届かなかった。
彼らは圧倒的な力で森の戦士達を倒し、宝珠を奪っていった。
『黒いゴンドラ乗り』達は、未知の武力をもって瞬く間に森の戦士達を薙ぎ払った。
「……凄い」
怪我を負ったものの運よく逃れ、同時に圧倒的な彼らの力を目撃したナディーン。
だが、ナディーンの心に恐怖は無かった。
唯々、その力に魅せられた。この者達と同じ力があれば妖蛆を倒せる。その可能性に心を躍らせた。
しかし、『黒いゴンドラ乗り』達が再び現れることはなかった。
宝珠を捜しに旅立ったアインが戻るのを待たず、崩壊の時が来てしまったのだ。
生き残りを賭け、故郷の森から離れたナディーン達だったが、宝珠無き世界では妖蛆を止めることはできない。
大きな地響きが、かつては湖畔だった場所を揺るがした。
徐々に大きくなる揺れに、誰も立っていることすらできなくなった。
泣く者がいた。笑う者がいた。どうにもならない状況に追い込まれ、皆錯乱の最中にあった。
ナディーンはその様子をじっと見ていた。もう何もできないのだ。
すぐ近くに、事の成り行きを見守るしかできないスプラートがいた。
彼女と同様に、ナディーンもじっとその場で最後の時を待っていた。
視界を大きな暗闇が覆い始めた。足下が崩れ去り、真っ黒な奈落に何もかもが落ちていった。
赤、橙、黄、緑、青、藍、紫、赤、橙、黄、緑、 青、 藍、 紫……
一つずつ、あるいは複数の色がゆっくりと変化し続けるその空間は、ナディーンを酔わせる。
どちらが上でどちらが下かもわからない空間に、どうすることもできなかった。
こんな時、『黒いゴンドラ乗り』達の武力があれば、とナディーンは空想した。
一体どれ程そうしていただろうか。再び視界が真っ黒に染まる。
次にナディーンの視界に飛び込んできたのは、故郷の森だった。
妖蛆に飲み込まれた筈の森は仄かな星の光に照らされ、平和そのものに見えた。
森の奥で何かが淡く輝いた。歩いてみると、そこに近付くことができた。
光の中に人影が見えた。少女のようにも見える。ナディーンはその姿に見覚えがあった。
「アイン?」
ナディーンは彼女の名前を呟いた。大母によって選ばれ、宝珠を取り戻す使命を背負った少女だった。
だが、様々な雑音を退けて、「お役目を絶対に果たす」と確言した気丈な少女の姿はそこには無かった。
アインは鳴咽していた。それは歓喜の涙ではなかった。
ナディーンも身に染みる程に知っている、哀しみの涙であった。
彼女は失敗したのか?
その考えは即座に否定された。
アインの手には淡く光る何かがある。
それこそが森を、世界を救う宝珠であると、一目見た瞬間に理解した。
「彼を――の?」
少女のような囁き声が切れ切れに聞こえた。アインの哀しみを 解決する方法がそこにあると言わんばかりだ。
「ええ、もちろん!」
アインは叫んだ。
「じゃあ、――わ」
すると宝珠の光が増し、アインと森、そしてナディーンを包んだ。
アインの視線の先にあった宝珠には、『黒いゴンドラ乗り』の 一員の姿がはっきりと映っていた。
ナディーンはたくさんの色彩が変化し続ける空間に戻っていた。
「あれは……」
一体なんだったのか。
アインは何を宝珠に望んだのか?そもそも、宝珠にそのような力があったのか?
大母も大叔母達も闇に飲まれた今、その疑問に答えられる者はいない。
「うふふふふふ。知りたい?」
突然、先刻アインと会話をしていた女の声が聞こえてきた。その声はアインに語り掛けていたような荘厳さは無く、物語を楽しむ、只の少女のような声色だった。
この声を、ナディーンは昔から知っているような気がした。
「あれはアインが選択したこと」
「あはははは!そう!正解!アタシは背中を押しただけ」
故郷が無くなっても仕方がないと思うまでに、アインは何かを欲したのだ。 それだけは理解していた。
「だから、貴女にも選択権はあると思うの」
「アインとは違うことを望む可能性があってもか?」
「あの子は選択したじゃない。貴女もそうすればいい。単純な話よ」
少女は楽しそうに笑った。彼女にとって、世界がどうなるかということは些末なことなのだろう。
今初めて出会った筈の少女だったが、ナディーンはこの少女のことを何故か理解できていた。
「で、どうするの?」
少女が選択を迫る。
今も昔も、両親が帰ってこなかったあの日から、ナディーンの願いは唯一つだ。
「どんな手を使っても、例えそれで世界が滅びようとも、妖蛆を倒す。そのための力が欲しい」
「貴女の望みはいつもそれね」
「そうさ。私はずっとこれだけを願ってきた」
改めてナディーンは願う。妖蛆に対抗できる力がある世界へ赴き、力と知識を手に入れる。
その結果、『黒いゴンドラ乗り』の世界や故郷の森を滅ぼすことになっても構わない。
「じゃあ、行きましょうか。貴女が求める混沌へ」
少女の高笑いと共に光の奔流がナディーンを襲い、少しずつ風景を形作っていく。
無機質だが清潔な金属質の建物。そこで精力的に働く研究者の姿が、ナディーンの目に映った。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ