パルモ
【死因】
【関連キャラ】リュカ、アスラ
3397年 「檻」 

この季節にしては冷たい風が、深い青を湛えた湖の表面を揺らす。森に籠もった木々の匂いが湖岸に届き、少女は貝を採る手を休めて顔を上げた。
「珍しいね、こんな時期に。もしかしたら夜は嵐になるのかな、シルフ」
濡れ手を振りながら、傍らに佇む大きな獣に話し掛ける。狼によく似たその獣はじっとパルモの顔を見つめると、何度か瞬いた。
「そうだね。それじゃ早めに帰ろうか。もう少しで今日の分が摂り終るから」
少女はにっこりと微笑むと、再び腰を屈めて貝を採り始めた。
パルモが笊を抱えて家に戻ると、家には誰もいなかった。普段ならば母親が夕食の準備をしている時間だ。この時間に両親とも出掛けることは少なくなかったが、パルもの胸には何故かチクリと嫌な予感が走った。
「……すぐに帰ってくるよね」
外では、パルモの不安を掻き立てるように風が強くなっている。空には真っ黒な雲が広がり、気温も下がり始めた。
「……グルル」
パルモの不安を感じたのか、傍らの獣がパルモの脚に頭を擦り付ける。
「うん、大丈夫。ありがとうね、シルフ」
パルモはシルフの鼻面を撫でながら、明るい声を出した。
「それじゃ、先にスープでも作っちゃおうかな。貝もたくさん採れたしね。もちろん、シルフの分もあるよー」
パルモは笑いながら抱えている笊を振った。中で貝がジャラジャラと音をたてる。シルフは安心したように頷いて、家の入り口のところで丸くなった。
パルモがスープを作り終わり、太陽が全て隠れても、まだ両親は戻らなかった。さすがに心配になり、探しに行こうか迷っていたところで、ようやく入り口の扉が開いた。暗かったパルモの顔がぱっと明るい表情に変わる。
「お帰り、お父さん!お母さん。あのね……」
だが、その言葉は途中で止まってしまった。両親の後ろに見知らぬ男が立っていたからだ。
「ただいま、パルモ」
「おかえりなさい」
小さく呟くパルモを、男はじっと見つめる。男は細身の体に黒い装束を着け、冷たい目をしていた。その禍々しさにパルモは身震いした。
「お父さん、ご飯は……」
「すまん、これからちょっとこの人と話があるんだ。村長さんもすぐに来る。だからパルモは上に行ってなさい」
父親が疲れたような調子でパルモに語り掛ける。母親は今にも泣き出しそうだ。
「パンをもってお行き。終わったら、ちゃんとご飯にするからね」
「……うん。わかった」
今わたしが何か言っても、お父さんとお母さんを苦しめるだけだ。聡明なパルモには、それがわかってしまった。
「おいで、シルフ。上に行こう」
パルモはシルフを呼ぶと、一緒に二階に上がっていった。
ベッドの上でパンを齧りながら、パルモはじっと下の様子に耳を傾けていた。全部が聞こえるわけではないが、父の怒鳴り声や母のすすり泣く声、それに村長さんの押し殺した唸りなどが聞こえてくる。どう考えても楽しい話題には思えない。そして、その中に自分の名前が出てきたことに、パルモは気付いてしまった。
「……わたしのことを話しているんだ」
何か失敗しちゃったのかな。それとも、お父さんとお母さんはわたしをどこかへやっちゃうつもりなのかな。そんな考えが頭に浮かび、パルモの目は潤んでしまう。パルモは慌てて枕に顔を埋めて涙を拭った。
「……だって、まだ子どもなのに……」
「…………村がどうなっても……」
「……だからといって、パルモひとりに……」
何も見えない状態だと、下の声が良く聞こえる。どうやら、あの黒い男がわたしに何かをさせようとしていて、お父さんとお母さんが反対しているようだ。
「わたしが行かなかったら、村に何かする気なんだ」
だったら、わたしが行くしかない。話を理解すると、パルモはすぐに決断した。立ち上がったパルモを引き留めるように、シルフが唸り声を上げる。
「ごめんね、お前も危ないところに行くかもしれないのに。でも、お父さんとお母さんを困らせたくはない」
シルフはじっとパルモの目を見つめると、仕方がないと言った風情で溜息をついた。
「ありがとう、シルフ」
パルモはシルフの頭を撫でると、決意の表情で部屋を出た。
居間に入ると、ちょうど父親の怒鳴り声が聞こえてきた。
「だから何度も言っているでしょう!パルモを戦に出すなんて……」
「お父さん!わたし……行くよ」
「パルモ……上に行ってなさい。これは大人の問題だ」
険しい顔でパルモを睨む父親。こんなに怖い顔は、パルモが大事な水瓶を割ってしまった時にだって見たことがない。だがパルモのその言葉を聞いた黒い男は、ニヤリと唇を歪めた。
「さすがはコルガ―の聖獣を操るお嬢さんだ。勇敢な上に、物分りが良いと来ている」
「パルモ!?」
母親が悲鳴を上げた。父親はじっと男を睨んでいる。その向こうで、村長はどこかホッとしたような表情を浮かべていた。
「わたしがどこかに行けば良いんでしょう?」
「その通りだよ、パルモ。そこの大きな狼も一緒にね」
「この子は狼じゃありません。シルフです」
「そうか。それじゃ、シルフも一緒に」
「………………」
それを聞いて、母親は泣き崩れてしまった。震える背中を父親がゆっくりと撫でる。そして何か言おうとしたが、男に遮られた。
「私の名はアスラだ。明日、君はルビオナ王都へ旅立つことになる。準備をしておくように」
それだけを告げると、アスラは立ち上がって音もなく出て行った。残された四人は、ただ黙ってそれを見送った。
次の日。泣いて引き留める母親と、血が出るほど唇を噛み締めた父親を背に、パルモは森を出た。
「ねえ、アスラさん。わたしはどこへ行くの?」
森を抜けながらパルモは尋ねた。アスラは顔を前に向けたまま、ぶっきらぼうに答える。
「戦場だ」
「でもわたし、なにもできないよ」
「お前自身に何かしろとは言っていない。その獣にさせるのだ。お前が」
「シルフに?」
「そう、伝説の力を国のために役立ててもらう」
その言葉にシルフが唸り声を上げる。だがアスラは素知らぬ顔だ。
「決して老いず、決して死なぬコルガ―の聖獣。その力は万軍に値するが、誰にも傅かぬ」
アスラは詞を詠むかのように言った。
「だが、ついにその力を使役できる人物が現れたと聞いた。それがお前だ」
「そんな……。シルフはわたしを守ってくれているだけ……」
「よく考えろ。国が滅びればお前らも滅びるのだ。帝國がここまでくれば、お前の一族など間を置かずに踏み潰される」
「……戦いなんて、したことないのに」
「やらねばならぬ。家族のため、国のためにな」
パルモはうな垂れる。アスラの表情を横から眺めるが、冷たいその相貌に何かの感情を読み取ることはできなかった。
パルモは溜息をついて、アスラに置いていかれないように足を速めた。
森を抜け、此処コルガ―から連合王国の首都へ続く列車が通る街に辿り着いた。
「ここからは列車だ。それと、獣は檻に入ってもらう」
街の外に、大きな台車に載った檻が用意されていた。
「獣を町に入れるわけにはいかん。それに、姿を見られるもの問題がある」
アスラは冷淡に言った。
「こんなところにシルフを入れられない。歩いて行くわ」
「そんな悠長な真似はできん。黙って乗せろ」
シルフが地響きのような唸り声を上げた。だが、アスラは表情一つ変えない。
「やめて、シルフ。わかったわ。わたしも檻に入る」
「好きにしろ」
アスラはそう言って檻を開けさせた。パルモはシルフを連れて檻の中に入る。何か他の獣を入れていた物らしく、そこは汚れがひどく、きつい匂いが充満していた。
「シルフ、我慢しよう。村のためだもの」
殆ど光の入らない揺れる檻の中で、パルモはシルフに寄り掛かるようにしてそう呟いた。
しばらくすると檻が列車に乗せられ、移動を始めたのがわかった。貨物室に入れられた檻の中は暗闇となった。
真っ暗な中、パルモは不安に押し潰されそうになるのを必死で堪えていた。そしてあの美しい村を、故郷の景色を思い出しながら眠りについた。
「―了―」
3397年 「鉄」 

パルモは王都へ到着した。三日ほど詰め込まれた窮屈な烈車から出られた開放感はあったが、それも一時的なもので、すぐに知らない場所に来たのだという不安の方が勝っていった。
王都には、決戦に備えて周辺国からの軍勢が集結していた。混乱の中、パルモ達も集まった連合軍の閲兵に並ぶことになった。
パルモは辺境の戦闘集団として後方にいた。バルコニーに立つ女王の姿など、殆ど見ることができない。
そもそも、強引に集められたであろう辺境民族の集団は、ここにいる意味も価値もわかっていない様子だった。
パルモもその中で不安げな表情を浮かべていた。ただ、傍らにいるシルフはずっと彼女に寄り添い、佇んでいた。
前方で大きな鬨の声が上がった。背の低いパルモでは、前に起きていることなどわかりはしない。
ただ、その地鳴りのような声が不気味に聞こえ、強くシルフを抱きしめた。
閲兵式が終わると、王都の外郭に作られた野営地に留められた。ここから戦地へ向かうことになると、アスラから告げられた。
「私たち、戦いに行くのですか?人を殺めなければならないのですか?」
パルモはアスラを呼び止める留めるように聞いた。
「お前はそのために来た。その獣を使えば、簡単なことだ」
アスラは無表情に答えた。
「……無理です」
パルモは正直に言った。シルフとは確かに頭の中で意志を通じ合える。それに、獲物を捕る時や、怖い動物に襲われた時も助けてくれた。だが、武器を持った兵士との戦いなどしたことがない。
「戦わなければ、お前らの村も帝國に襲われるのだ。村のためだと思え」
「でも……、私もシルフも……」
「戦地には向かってもらう。力が必要だからな」
パルモは唇を噛んだ。敵の兵士といってもそれは人間だ。シルフを使って人殺しをするなんて、できるわけがない。パルモの目に涙が滲み、ぽつりと落ちた。シルフが慰めるようにその涙を舐める。暖かい感触と一緒に、シルフの慰めが頭の中に流れ込んできた。パルモはシルフの顔を見て頷く。
「逃げることはできない。やって来る驚異は紛れもない現実だ」
アスラの言葉に、パルモは何も言い返さなかった。
割り当てられたテントに入り、すぐにシルフと共に横になった。目を閉じると、慣れない長旅の疲労がずっしりと体に感じた。森を駆け回って培った体力も、ここでは発揮できない様だ。
――はやく、帰りたい。
頭の中で呟くと、すぐに眠りについた。
初めて見る戦場は異様だった。周囲には常に金属と金属が触れ合う音が響き、埃と汗の臭いが熱気と混ざって渦巻いている。
戦端はまだ開いていない、緊張が全軍を包んでいた。
「ここで防御にあたれ」
パルモとシルフは本陣に近い後方に配置された。
「ここなら、戦いは起きないの?」
「いきなり敵兵と接触することは無いだろう。だが、逃げる場所は無い」
アスラの眼に感情や憂いは無く、ただ冷たく光っていた。
「逃げるだなんて……」
アスラは本陣に戻っていった。
すると、大音量でラッパの音が響き渡った。同時に、銃や剣を構えて鎧に身を包んだ屈強な男達が、一斉に雄叫びを上げる。
「な、なに!?」
銃を突き上げながら宙に向かって吠える男達の姿に、パルモは恐怖を感じた。ここにいる全ての人間が、ただ人を殺すためだけに存在する。そして、それと同数の人間が、こちらを殺そうと同じように存在しているのだ。パルモの胸を恐怖と絶望が黒く塗り潰した。
「……ここは、私がいるべきところじゃない」
パルモはシルフに縋りつくと、静かに泣き始めた。涙が滲むことはあっても、決して泣かないよう心に決めていたが、限界だった。
怯えるパルモを余所に、戦闘は始まった。すぐに幾千もの剣戟の音と銃声が聞こえ始めた。そこに地震かと間違える様な地響きが加わり、パルモは地獄にいる心地だった。
「お願い、シルフ……」
必死にしがみつくパルモを護るように、シルフは体を伸ばした。前線から遠く離れているにも関わらず血の匂いが漂い、シルフは鼻をひくつかせる。
本陣の脇から装甲猟兵と呼ばれる禍々しい鉄の塊が、巨大な砲台を引きながら通り過ぎていった。
死を運ぶ無機質な鉄の塊を、パルモはそれ以上見ることができなかった。
砲台は位置に着くと、衝撃と爆音を轟かせて敵を砲撃し始めた。
爆音の中、パルモは泣き続けていた。
その傍でシルフは微動だにせず、ただ正面を見据えて彼女を支えるように立っていた。
「なぜお前のような者がここにいる?」
そう声を掛けられたのは、戦闘開始から二時間ほどが経ってからだろうか。パルモの顔は涙と埃でドロドロになり、シルフもまた戦塵に塗れていた。
急に話し掛けられて、パルモは声を出すことができなかった。顔を上げると、老齢の戦士が馬上にいた。
「……っ」
ひゅうっと喉が鳴り、口をぱくぱくさせる。すっとシルフがパルモを護るように立ちはだかった。
「……これを飲むといい。喉が枯れているのだろう」
老戦士は腰に付けていた水筒をパルモに差し出した。びっくりして一歩下がる。
「大丈夫、儂は敵ではない」
「………………」
恐る恐る手を伸ばして水筒を掴む。そして、老戦士の顔を見ながら水筒の中身を喉に流し込んだ。
「おいしい……」
水筒の中身は只の水だったが、それはパルモの体に甘く染み渡っていった。自分でも気が付かなかったが、緊張と涙のせいで喉が渇ききっていたのだ。そのままごくごくと飲んでしまい、水筒が空になってようやく我に返った。
「あ、ごめんなさい……」
老戦士は軽くなった水筒えを受け取り、再び腰に付ける。
「構わぬ。それより、どうしてこんな所にいる? まさか、聖獣を操るというのは……」
「わ、わたしは……」
地獄の様な戦場で急に優しくされて、パルモは戸惑った。言いたいことが溢れて、上手く声に出せない。
「怯えるな、ここまで敵は来ておらん。ゆっくりと話せ。まずは名を聞こう。私はリュカ」
「わ、わたしはパルモ……です」
「そうか。パルモ、話してくれるか?」
老戦士の穏やかな雰囲気に、パルモはようやくまともに声を出すことができるようになった。
それから、パルモはつっかえつっかえながらも、自分が森から連れてこられたこと、戦争はイヤだが、村を人質に取られたことを話した。
「そうか……それが事実なら、すまないことをした。アスラは私の部下だ」
「えっ、そうなんですか……」
「いくら強い力があるといっても、君のような幼い女の子を戦場に出すつもりはない。私からアスラに言って聞かせよう」
「帰れるんですか!?」
「ああ、もちろんだ。君も、その相棒も一緒にね」
リュカは優しくパルモの頭を撫でた。パルモの目に、今度は嬉し涙が溢れた。森を出てから初めて、パルモは人の優しさを思い出すことができた。
「……ありがとうございます、リュカ様」
「ははは、様はいらん。それじゃあ、こっちへおいで」
リュカはパルモを優しく立たせると、頭を撫でた。その暖かさと手の大きさに、パルモはホッとした。シルフもリュカのことを信用した様子で、パルモが触られても抵抗しなかった。
「アスラは冷徹な男でな。誰かがやらなければならない汚い仕事を引き受けてくれているのだが」
その呟きは、嬉しさで舞い上がっているパルモの耳には入らなかった。ただ、シルフだけがじっとリュカの顔を見つめていた。
「―了―」
3399年 「聖獣と死者」 
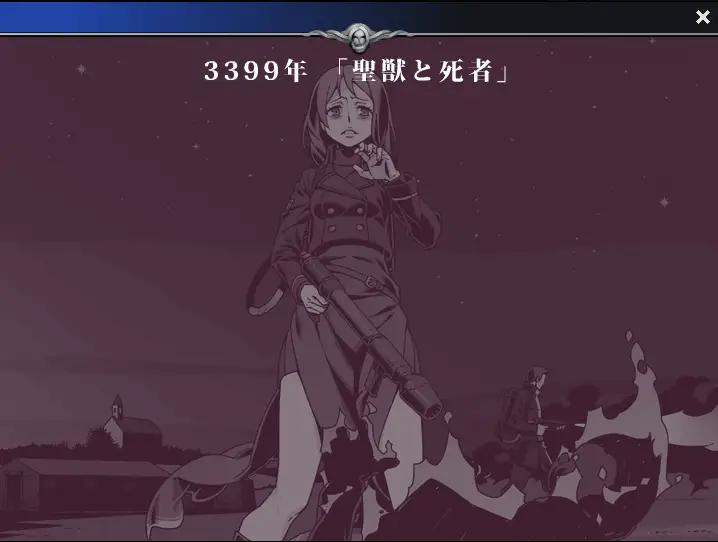
ルビオナ王国の西方にある、城塞都市プロヴィデンス。
戦争が起きる以前はグランデレニア帝國とルビオナ連合王国の文化が行き交う、最大の交易都市であったという。
しかし戦争が起きてからは、帝國と連合王国の両者の間で激しい制圧戦が繰り返されていた。
膠着する戦いに痺れを切らせた帝國は、『死者を操る術』を用いて、プロヴィデンスを死者の国へと変えてしまった。
死者の軍勢を討伐する戦いにお前達の力が必要だと、道中、パルモはアスラから聞かされていた。
パルモ達は今、封鎖されたプロヴィデンスへ向かう街道からおよそ1リーグ離れた場所に陣地を形成していた。
ここを仮の拠点として部隊を展開し、プロヴィデンスを解放する作戦を開始するのだと聞いていた。
「スプラート、本当にいいの?」
野営の準備をする最中、パルモはスプラートに尋ねた。
パルモがシルフと共に再び戦場に立つことを決めた時、スプラートも付いていくと言って聞かなかったのだった。
当然、パルモやシルフ、それにパルモの両親も反対したのだが、スプラートはパルモやシルフの傍を離れようとはしなかった。
根負けしたパルモとシルフが折れる形で、スプラートはこの部隊に参加することとなった。
「うん。早く戦争が終われば、それだけ早くアインを探しに行けるし」
「そう。でもこれだけは約束して。危なくなったらすぐに逃げるの。あなたにはやるべきことがあるのだから」
「パルモとシルフを置いては行けないよ!」
「この戦争は私達の世界の問題だもの。本当はすぐにでも――」
「ダメだよ!パルモたちにはすごく感謝してるんだ。それに、アインを探すのを手伝うって約束してくれたでしょう?」
スプラートに遮られるように言われてしまい、パルモはそれ以上何も言えなかった。
完全に陽も落ち、パルモ達がテントの一角で食事を摂っている時のことだった。
耳障りでけたたましい警報音が陣地に響き渡り、一気に周囲がざわめき始めた。
「ちょっと待っててね」
パルモ達と一緒に食事をしていた女性の兵士――アニスという名だ――が立ち上がり、テントの外へと様子を見に行った。
フォンデラート出身だというアニスは、兵士としての経験がないパルモ達へ上からの伝令を判りやすく伝えるために、パルモ達と行動を共にしていた。
「すぐに準備をして。死者達がすぐそこまで追って来ている!」
アニスは緊迫した面持ちで戻ってくるとパルモ達にそう伝え、テントに置いていた自身の武装を手早く装備した。
「ごめんなさい。こういうことを言うのは辛いけど、今は聖獣と貴女が頼りなの。急いで!」
パルモはシルフと共に立ち上がった。ここで死者の軍勢を留めることが村を守ることにつながることを、パルモは理解していた。
「死者の軍勢、来ます!」
「完全に燃やすか頭を壊せ!でなければ際限なく蘇るぞ!」
兵士達の伝令が飛び交う中、パルモとシルフは後方に控えていた。
「シルフ……。わかってる、村を守らなきゃ」
シルフの目を見ると、シルフの決意が流れ込んできた。
「火を放て!」
隊長格の兵士の号令で、いくつもの火炎放射機から炎が放たれた。
原始的ではあるが、完全に燃やし尽くして灰にすれば、死者はそれ以上蘇らない。
パルモを含めたプロヴィデンス制圧部隊の全員に、携行できる大きさの火炎放射機が支給されていた。
「第一部隊、突破されました!」
「怯むな!ここを突破される訳にはいかん!」
兵士達の雄叫びと銃声、炎が噴射される音が前線から響く。
何とも言い難い腐臭と、それが焼かれる臭いがした。シルフは前方を真っ直ぐに見据えている。
「奴らがここまで来た!パルモ、気をつけて!」
アニスが武器を構えたまま近くに寄ってくる。」
死者の呻き声がはっきりとパルモの耳に届く。死者達はすぐそこまで迫ってきていた。
「パルモ、武器の安全装置を解除して。構えて!」
「は、はい!」
アニスに言われるがまま、パルモは持たされた火炎放射機を構えた。
「来ます!備えて!」
アニス達兵士の火炎放射機から炎が放たれる。だが、パルモは何もできずにただ立ち尽くしていた。
「パルモ!怯むな!殺されてしまう!」
「でも……」
アニスに怒鳴られるが、パルモは動かない。
「パルモ!避けて!」
「きゃああ!」
誰かに突き飛ばされ、パルモは地面に転がった。
先程までパルモがいたところには、数体の死者が群がるようにしてやって来ていた。
「パルモ!!」
「スプラート!?」
目の前には、半分獣と化したスプラートとシルフがいた。
「だめ!逃げて!」
「ここで逃げたら、パルモもシルフも死んじゃう!」
スプラートはそう言うと、シルフと視線を交わし合った。
以前からこの二者の間で何かしらの会話がかわされている気はしていたが、それが確証に変わった。
シルフが臨戦態勢を取り、死者の軍勢を迎え撃つ。死者からの攻撃を受けてもシルフは全く意に介さずにその喉元を噛み千切り、頭を潰していた。
スプラートが獣の身体能力によって死者の動きを押し止め、シルフがそれに止めを刺す、といった連携をも見せた。
「すごい、あれが聖獣の力」
アニスが呟く声がパルモには聞こえた。
最後の死者が誰かの火によって焼却され、死者の軍団は退けられた。
この勝利は制圧部隊に希望をもたらした。火と聖獣、それが圧倒的な物量を誇る死者の軍勢を退ける有効な手段であるということが立証されたのである。
「二人とも、怪我はない?」
「このくらい平気さ。パルモは?」
「私も大丈夫。ごめんね、私、何もできなかった……」
シルフとスプラートの無事な姿を見て、パルモは涙した。
そっとその涙をシルフが拭う。
「ありがとう。シルフ、スプラート……」
夜が明けて、戦死者の葬儀が簡単に執り行われた。
悲しみに暮れる日もなく、日を置かずに制圧部隊は陣地を発った。
プロヴィデンスにあと300アルレというところで、再び死者の軍団と対峙することになった。
パルモも、今度こそシルフ達に遅れをとらないようにと、必死で死者を退けていった。
それでも、人を殺してしまっているという罪悪感から逃れることができず、パルモは泣きながら死者に炎を浴びせていた。
「ああっ!」
激化する戦いの最中、大量の死者によってパルモとシルフは引き離されてしまった。
死者に噛み付いて振り払うシルフだが、プロヴィデンスより際限なく出てくる死者達に取り囲まれてしまったのが、パルモから見て取れた。
パルモもスプラートと共にシルフを助け出そうとするが、死者達に阻まれてしまう。
「シルフ!!」
数が多すぎて、とてもではないがシルフの傍へ行くことができない。
このままシルフが死者の群れに殺されてしまったらどうしよう。そう考えると、気が気ではなかった。
「パルモ、危ない!」
あまりにもシルフに気を取られ過ぎて、パルモは自分に襲い掛かる死者への対応が疎かになっていた。
スプラートの声でそれに気付くが、時すでに遅く、死者がパルモの眼前に迫っていた。
その瞬間、死者の身体が炎に包まれる。
「ア、アスラ、さん?」
パルモの前には、東方の戦闘服に身を包んだアスラがいた。
プロヴィデンスの制圧部隊を指揮する立場にいるとは聞いていたが、最初の説明を受けてからは、ずっと姿を見てはいなかった。
「少しは成長したようだな」
「どうして……」
「シルフを御せるのはお前だけだからな」
「そうだ、シルフ!アスラさん、シルフを助けて!」
「いいだろう」
そう言うと、アスラの姿は掻き消えた。
直後、シルフの周囲から先程と同じような火の手が上がるのが見えた。
リュカ大公の側近である彼の戦闘能力は凄まじかった。死者達は次々と火柱に包まれ、その動きを止めていった。
アスラの助力もあり、パルモとシルフは無事に合流することができた。
「ありがとうございます!」
「貴重な戦力を失う訳にはいかない」
変わらず冷たい目でパルモ達を見るアスラが言葉を発するのと同時に、プロヴィデンスを囲う城壁の辺りから地鳴りと共に大きな音が響いた。
身体をびくりと震わせるパルモに、シルフとスプラートが寄り添った。
「城壁の破壊が完了したようだな。プロヴィデンスへ入るぞ」
「は、はい!」
アスラの視線をパルモは追う。その先には、死霊の住処となって荒廃した都市が広がっていた。
「―了―」
3399年 「屍」 
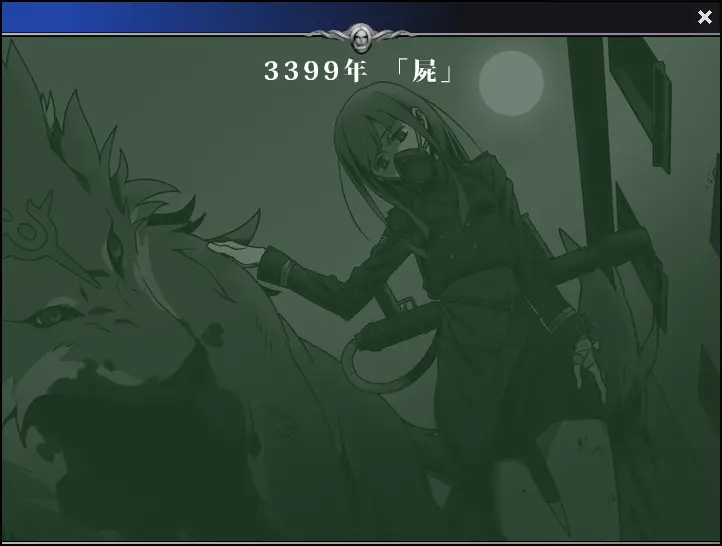
パルモは部隊からガスマスクを支給された。
部隊は何も装備しない状態でプロヴィデンスに入るのは危険だと判断を下していた。
ガスマスクを見たパルモは、今まで以上に厳しい戦地へ向かうのだと実感し、背筋が寒くなる思いがした。
そんなパルモの様子を感じ取ったのか、シルフがパルモにそっと寄り添った。
「大丈夫、シルフと一緒だもの……」
この場所が奪還できれば故郷に帰れる。そう思い込むことで、パルモは恐怖から目を逸らそうとしていた。
シルフの頭をそっと撫でながら、パルモは軽い柔軟体操をしているスプラートに声を掛けた。
「ねえスプラート、お願いを聞いてくれる?」
「うん、何?」
「状況が危ないと思ったら、私のことは構わずに、すぐに逃げて欲しいの」
「パルモとシルフが大変な時に、逃げ出せって言うの?」
「あなたはやるべきことがある。私たちの世界の事情に付き合って、死んでしまうわけにはいかないでしょう?」
「だからって、パルモとシルフを見捨てるなんてできないよ!」
「あなたはアインって子を探しにこの世界に来たんだから、何があっても生き延びなきゃだめなの」
スプラートはパルモの強固な意思に戸惑い、シルフと視線を交わす。
シルフと何かしらの交信があったのか、ややあって小さく頷いた。
「……わかった。……で、でも、パルモとシルフが危なかったら絶対助けるからね!」
いよいよプロヴィデンスの内部に突入した。
暗く濁ったような霧、あちこちから漂う腐臭と血の臭い。プロヴィデンスの内部は、まさに混沌と化していた。
アスラは死者の軍勢を生み出す原因を調査するため、先遣隊として都市の中へと入っていった。
死者の軍勢は今までのそれとは様相が違っていた。プロヴィデンスの内部にいる死者の着ているものは、軍人のそれであった。
死者達は銃を持ち、戦闘のための優れた装備を携行している。
「火を絶やすな!」
「補給部隊、まだか!」
生者の司令や悲鳴、怒号が飛び交う。
パルモも必死になって、部隊の助けになるよう火炎放射機で応戦した。
「シルフ!スプラート!」
死者の軍勢が大挙して押し寄せたことで、部隊は一時後退を余儀なくされてしまった。後退の混乱でシルフとスプラートと離れてしまい、パルモは言いようのない不安に襲われていた。
特に、常に一緒であったシルフと離れてしまったことに恐怖を掻き立てられた。
シルフのいる方向はぼんやりとわかるが、姿が見えないことがこれほど怖いものであるとは、パルモ自身も予想外だった。
一緒に行動していた軍人達が状況を確認し、本隊との合流を目指す。
「パルモ、聖獣のいる場所に変化はない?」
「は……はい……」
シルフとスプラートは無事だろうか。パルモはそればかりを考えていた。
死者の軍勢に見つからぬように大通りを避けて移動していたが、死者達はそこを狙ったかのように現れた。
「待ち伏せだと!?」
パルモ達の前を進んでいた兵士二人が犠牲となった。
彼らは僅かの間を置いて立ち上がると、死者の軍勢と同じようにパルモ達に襲い掛かる。
「火を放て!」
「奴等に殺されたら奴等と同じになるぞ!」
アニスの号令で火を放つ。パルモを襲った死者は焼き尽くされた。だが、この騒ぎに気付いたのか、辺りの死者の数は減るどころか増していた。
「数が多い……」
「何とかしないと」
パルモは意を決して火炎放射機を構えると、目の前に迫る死者達を焼き払った。
シルフとスプラートは近い場所にいる筈だ、彼等に無事な姿を見せなければ。
強い思いがパルモを突き動かす。
その時だった。低い唸り声と共に、シルフがパルモ達の前に躍り出た。
「シルフ!」
シルフはパルモとアニスを取り囲もうとしていた死者達を薙ぎ払う。
「パルモ、アニスも!無事だったんだね!」
続いてスプラートもやって来た。そのすぐ背後には、分断された本隊の面々とアスラがいた。
人数が増えたことで、死者達は為す術もなく焼き払われていった。
死者がいなくなったのを確認した後、近くにあった小さな教会で一時の休息を取った。
「パルモ、手当を」
「あっ、ありがとうございます」
部隊の指揮官とアスラ達が情報整理を行っている間、パルモは傷の手当を受けていた。幸い傷は浅く、すぐに手当したことで痛みもあまり出なかった。
情報の整理が終わり、指揮官から今後の進軍に関する指針が発表された。
「アスラからの報告で、ここから西に800アルレ程進んだところに帝國の戦艦ガレオンが停泊していることが確認された。そこに死者の軍勢を操る者がいる可能性が高い。そこを制圧できれば勝機が見える」
パルモは指揮官の話を聞いて、拳を握った。
そこを制圧すれば全てが終わる。シルフとスプラートと共に村へ帰れる。
そんな希望を抱いていた。
「パルモ、大丈夫?」
「え?どうしたの急に?」
ガレオンに向けて進軍する道中、不意にスプラートが尋ねてきた。
「顔色が悪いよ?」
「臭いに当てられちゃったのかも。でも大丈夫」
スプラートの言う通りだった。教会を出てからパルモの体調は少しずつ悪くなっている。そのせいか、シルフと交信が上手くできなくなりつつあった。
シルフにこの事を伝えると、シルフは何も言わずにパルモを気遣った。
こんな事は初めてだったが、スプラートにも言ったように、ガスマスク越しでも感じる程の臭気に当てられたのだろう。そんな風に考えていた。
部隊はガレオンを目視で確認できるところまで進軍している。ここで戦線を離脱することはできない。それくらいはパルモにもわかっていた。
パルモはシルフとスプラートに「大丈夫」と言い続けながら部隊に付いていった。
ガレオンの前には死者の軍勢が立ち塞がっていた。大通りを行き交う死者の数ほどではないが、それでも多い。
「死者の軍勢、来ます!」
「発射!」
パルモも部隊の号令に合わせて火炎放射機で死者を焼き払う。しかしパルモは自分の意識が段々と混濁してきているのを感じていた。
「ううっ……。だめ、こんなところで……」
必死に意識を保とうと気を張る。
「パルモ!危ない!」
スプラートの声が聞こえた。声のした方を振り返る。
「きゃあああああ!」
そこにいたスプラートの姿は、髪が抜け、到る所の肉が腐敗していた。
「パルモ!?どうしたの、パルモ!」
蠢く死者となったスプラートが迫ってくる。火炎放射機を取り落とし、パルモは後退ることしかできない。
周囲を見回すと、一緒に進軍していた部隊の面々が、全員死者の軍勢と同じような姿になっている。
「パルモ、こっちに!」
アニスが視界に入る。パルモに向かって叫んだその拍子に、彼女の目玉が零れ落ちた。
「シルフ!シルフ!!」
パルモは必死になってシルフを呼んだ。その声に応えるかのように、シルフがパルモの眼前に現れた。
「どうしよう、シルフ。みんなが……みんなが!」
だが、シルフは悲しそうな目でパルモを見つめるだけだった。
「ねえシルフ、どうして何も答えてくれないの?」
シルフに縋りつくようにしがみつく。すると、シルフから毛が抜け、腐敗した獣の肉が顕わになった。
抜け落ちる毛と皮と肉。瞬く間に、シルフの肉体はぐずぐずと崩れていった。
「あ、あぁ……いや、いやああああああああああ!!」
「―了―」
3399年 「光」 
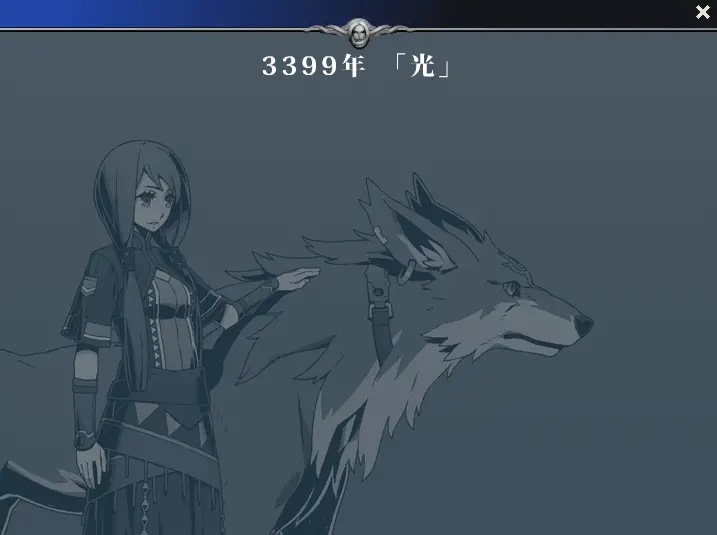
吹きすさぶ風の音が響く道を、シルフは一匹で歩いていた。
空がやけに赤かった。茜色の夕日がシルフの体毛を照らす。
シルフの視線の先に、見慣れた少女の残骸があった。
その肉は腐り、融けかけていた。一見しただけでは、それが誰であるかわかる筈もない。だが、シルフはその死を纏う肉を、自らと心を交わした少女パルモであると一目で理解した。
少女の形をした肉塊は、全身が黒い煙のようなものに包まれていた。
「たす……け、て……」
パルモは光の無い濁った目で、懇願するように呟いた。
腐りきった声帯で声を紡ぐなどできない筈だが、シルフには確かにその言葉が聞こえた。
シルフはパルモに飛び掛る。
喉笛に喰らいつき、力を込めた。
グチャリ、ゴキリと、気管が潰れる音がした。
更に力を込める。
紐が千切れるような音が聞こえ、その朽ちた肉にへばり付いていた黒い影が霧散した。
「あり、が……と」
喉を潰した筈なのに、パルモの声が聞こえた。
それはパルモの朽ちた肉に残っていた残留思念だったのかもしれない。
ようやっと、シルフは呪われた死からパルモを解き放つことができた。
シルフは完全に動かなくなったパルモを背負い、再び歩き始めた。
せめて彼女の体はコルガーの地へ帰してやらねば。そう思ったのだ。 物言わぬパルモを背負い、シルフは荒野を歩く。
歩いては休み、休んでは歩く。
その行動は、自身が小さくか弱かった頃のことを、嫌でも思い出させた。
あの時も、シルフは荒れ果てた道を一匹で進んでいた。
サーカスの皆は人間に害を成したということで、全員が壊された。シルフは一番信頼していた少女の助けによって難を逃れていた。
そして、サーカスが壊される直前に子供を連れて旅立っていった男を探すために、当てもない旅に出た。
だが、行けども行けども、子供と男の姿はどこにも無かった。
それどころか、自動人形と呼ばれた者はことごとく動かなくなっていたか、破壊されていた。
ある町の塵捨て場に積み上げられた自動人形の無残な姿を見て、シルフは子供と男を捜すことを諦めた。
自動人形達はどういう訳かみんな動かない。人間が再び動かそうとしても動かない。であるならば、きっと子供も男も、何処とも知れない場所で動かなくなって破棄されたに違いない。
そんな諦念に達したのだった。
そうして、シルフは彷徨った末に元いた世界によく似た雰囲気を持つ森に辿り着き、そこを住処としてひっそりと暮らすことにした。
シルフはその森で長い時間を掛けて成長していった。この世界の生き物が持ち得ない、不思議な力も身に付けた。
シルフの咆哮は空気を揺るがし、《渦》の進路をも変えることができた。思念を飛ばすことで、どのような動物とも意思疎通を図ることができた。
そうする内に、《渦》に追われた動物達がシルフの庇護を求めて森へと集った。
いつしか森は、周囲の環境とは比べ物にならないほど豊かになった。
このまま森の奥で静かに暮らし、朽ちていくつもりであったシルフの元に、一人の女性が現れた。
その者は装飾された衣装を身に纏い、たくさんの果実や獣肉に囲まれていた。
「森の主様……。どうか過の脅威から村をお救いください。そのためなら私はどうなってもかまいません。どうか村を……」
女性は祈りを捧げていた。
長い年月を生きるシルフは、短命の者から見れば超越した存在なのだろう。
何がどのように人里へ伝わったのかはわからなかったが、シルフは畏れ敬うべき森の主として認識されていた。
あの女性は《渦》から住処を守るため、シルフに捧げられるべくやって来た費なのだと、森の動物から教えられた。
シルフは困惑した。ある程度は《渦》の災いを退けられるのは確かだったが、その力を請われて振るってよいものなのかと。
シルフは女性を追い返すつもりで話し掛けた。森の動物達と言葉を交わすように、心に直接話し掛けた。
『立ち去るがよい。ここはお前のような者が来るところではない』
女性は吃驚した顔でシルフを見た。だが、すぐに表情を引き締める。 「森の主様、それは聞き入れられません。私は貴方様が《渦》の危機を退けることができると聞き、自らの意思でここまでやって来たのです」
『災いが迫っているというのか?』
「はい。人間風情がおこがましいとお思いでしょう。ですが、我々をお救いいただけるのは貴方様だけなのです。私の身はどうなっても構いません。ですから……」
女性は決意に満ちた顔でシルフの目をしっかりと射抜いた。その強い意志が、かつて自分を育ててくれた少女と重なって見えた。
だからだろうか、シルフはこの女性を助けてやりたいと思った。今度は自分が、自分の意志で何かを守る番なのだと、強く感じていた。
女性と共に村へ向かったシルフは、《渦》の脅威から村を守った。
以降、シルフはコルガーの地を守る聖獣として、崇められるようになった。
シルフと意思を交わした女性の家系は、聖獣の意思を汲み取る役目を担うことになった。自然との共生を信条とするコルガーの民らしく、役目に驕ることなく、只あるがままシルフに寄り添った。
そして、何百年という時間が静かに過ぎていった。
ついにシルフは老いた。不思議な力も、段々と行使することができなくなっていた。共に生きてきた女性の家系の者とも、意思疎通を交わすことが難しくなってしまった。
ついに寿命が尽きるのだと、シルフは悟った。
死が迫る中、久方ぶりに己と意思を交わせる者が女性の家系に生まれてきた。パルモである。
彼女ならば自身の死を見届ける人物になり得るだろう。そう思い、コルガーの自然とパルモと共に、残された時間を静かに過ごすつもりだった。
だが何の因果か。パルモの遺骸を背負って放浪している有様である。
シルフは後悔していた。
この様なことになるのなら、年端も行かぬパルモを自身の死の見届け人として選ぶべきではなかった。人との共生などせずに、森の奥へ隠匿したまま、ひっそりと生を終えるべきであった。
そんな徒労感から足が止まりかけた、その時だった。
「……シルフ」
パルモのものとは違う、とても懐かしい声がした。
懐かしいその声に惹かれるように、シルフは歩いていく。
――この世界に来たばかりの自分を、何くれと無く世話してくれた少女の声だった。
――力を持たない子犬の頃、たくさんの愛情を注いでくれた少女の声だった。
――『シルフ』という名前をつけてくれたのも、その少女だった。
忘れていた思い出が蘇る。
少女が名前を失っても、新しい名前を手に入れても。それでも、共にありたいと思っていた。
どれくらい歩いただろう。シルフは荘厳な造りの巨大建造物の前にいた。
シルフは足を速め、少女の所へ急いだ。
少女はどこかでずっとシルフのことを待っていた。そうに違いないと、シルフはあの呼び声を聞いて確信していた。
諦めていた思いが蘇る。それはパルモをコルガーに帰すことすら忘れる程の、強烈な思いであった。
声に導かれるまま歩いた先は、懐かしい光彩に満ちていた。
様々な光が明滅を繰り返しながら、ゆっくりと回転している。
『そう、この光だ……』
これこそが自分を別の世界へ誘った光である。数百年前、この光を辿ってこの世界へとやって来たのだ。
「シルフ……」
少女の呼び声が聞こえる。とても懐かしい呼び声だ。
『この先にいるのだな……』
シルフは懐かしい気持ちと共に、光の中をパルモを背に乗せたまま進む。
「やっと会えたね、シルフ。あれ?その子は?」
懐かしい声が近くで聞こえてきた。すぐ傍に少女がいる。
『この子はワシの友だ』
「そっか。一緒にこっちに来たんだね」
『ああ』
「歓迎するよ。その子とも友達になれるかな?」
『ああ、この子は良き子だ。きっとノームとも仲良くなれる』
「本当?それは楽しみだね!」
少女の嬉しそうな声。
そして、ふわりと頭を撫でられた。だが、かつてのしなやかな感触は無い。
シルフは顔を上げて少女を見やる。おかしいと気付いた時には遅かった。
少女の顔は確かにシルフの見知った顔である。だが、その顔は炎に包まれており、張り付いたような微笑みを浮かべていた。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ