ブロウニング
【死因】
【関連キャラ】
2837年 「ケース」 
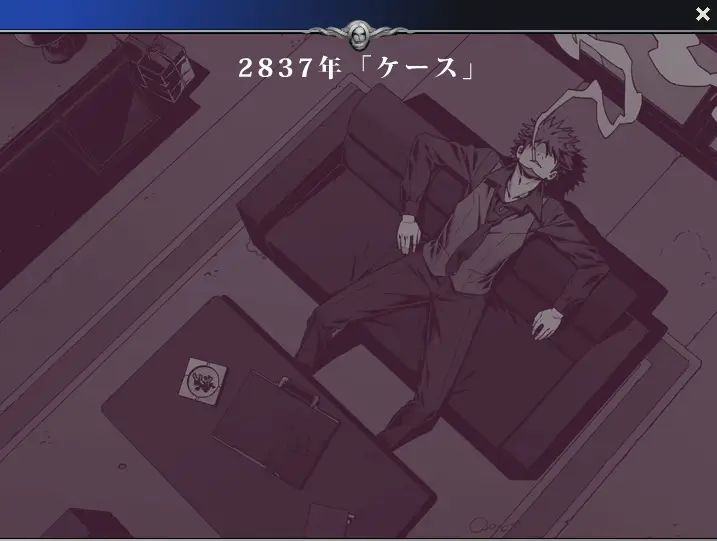
物語が語られることには必然がある。だが、今の俺には何も無い。
同じ事が繰り返される平凡な日常。依頼人にとっては重要な事も、自分にとっては類型的な作業に過ぎない。
「で、彼女の本心を確かめたいと?」
幸せの形は一つだが不幸の形は人それぞれ、と昔の人は言ったらしいが、俺にとってはそうでもない。
「ええ、僕としては彼女の気持ちを尊重したいだけなんだ。もし僕のことが嫌いで誰か他の……」
端末の向こうで、依頼人になる予定の男が何かを訴え始めた。
不信、不義、不満がない交ぜになった独白だ。
俺はお定まりの浮気調査に飽き飽きしていた。
「では指定の額を振り込んでいただいたのを確認してから、調査を開始します」
相手の気持ちが落ち着いて話が途切れたのを見計らい、定型の言葉で通信を切った。
俺はデヴィッド・ブロウニング。このローゼンブルグ第十階層の冴えないビルの一室で探偵業を営んでいる。
そうは言っても今の時代、昔のパルプ小説のような気取った依頼などありはしない。
巨大な虚栄の都市ローゼンブルグであっても、持ち込まれる依頼といえばせいぜいペット捜索――
この時代、生身のペットは流行の贅沢だ――、全て統治機構の警察機関が無視するような他愛もないトラブルばかりだ。
そもそも、この巨大都市の第十階層の社会情勢は安定している。
人間とオートマタの構成比率は1対1.2を越える。つまり一人につき一体の完璧な奴隷がいるのだ。
人々の暮らしに憂いなど無い。ただ、その憂い無き世界でも、いや、その憂いの無い世界だからこその濁った空気がある。
同じ日常、皮相的な流行を追うだけの日々。
ただ感情を弄び、死までの時間の暇潰しに充てているだけだ。
俺はこの世界を気に入っていない――世界の方も俺を必要とはしていないだろうが――。
それでも、これ以上階層を降りる度胸は無かった。
所謂支配階級の人間達が住む、一桁台の階層からの支配に逆らう気力も無い。
ただ、見かけだけでも、こうして何か自由であるかのように振る舞い続けていたいだけだ。
結局、社会からのアウトローを気取っても、自分のやってることなどままごとみたいなものだ。
そういう役割を世界から許されているに過ぎない。
誰かに取り替えられても問題のない人生、世界の書き割りみたいなものだ。
それでも日々の生活は続いていく。
依頼人との約束の時間からは三十分程過ぎていた。
階層の西の端、古くさい時代を模した街角にある、昔の映画に出てくるようなダイナーで依頼人と会う約束をしていた。
「すこしふっかけてやるかな」
時間は夜の九時を回ったところだった。
コーヒーのお代わりをオートマタのウェイターに頼み、趣味のパルプ小説を取り出して続きを読むことにした。
物語の中で主人公は美しい女クライアントと微妙な距離感の会話をしていた。
しばらく本に夢中になっていると、外が騒がしいことに気が付いた。表通りを警察車両がサイレンと共に走り抜けていった。
チップと料金をカウンターに置いて、パルプ小説をコートのポケットに仕舞い外に出た。
オートマタにチップが必要とは思えないが、ここではそういう習慣になっていた。
すでに野次馬達が通りに溢れている。目の前の通りを警察官達が封鎖し始めていた。
「武装した危険な強盗犯が逃げています」
「路上に出ている人は封鎖した地区に入らないように。危険です。建物の中に戻ってください!」
拡声器で警察官ががなり立てている。サイレンの音は鳴り響いたままだ。
武装強盗とは、この階層では珍しい出来事だ。騒ぎに引き付けられた人々がどんどん増えている。
少し思案し、このままだと時間を取られそうだったので事務所に戻ることにした。
どうせ依頼人も来そうにない。
大通りから少し離れたパーキングに人気は無かった。
非常線が張られた騒ぎに人が集められたせいか、遠くに響くサイレンの音以外は、やけに静かだった。
俺がドアを開けようとすると、何かが車に当たる音がした。
音がした方を見やると、怪我をした若い男がしゃがみ込んでいた。
「どうした、大丈夫か?」
十七、八の明るい髪色の、整った顔立ちの青年だ。駐車場の壁と車の間で、身を潜めるように座っていた。
「ブロウニングさんですよね……」
「ああ、そうだが。怪我してるよな」
その青年に見覚えは無かった。立ち上がった彼の手には、不釣り合いなトランクケースがあった。
「平気です。これをあなたに預けに来ました」
「届け物はいいが、物騒だな。話は車で聞こう。医者が必要なようだ」
青年の着ている小綺麗なスーツの前面には、黒い血がべっとりと付いていた。
俺はドアを開けて、彼を助手席に乗せようとした。
「これを届けてください。サーカスに。頼みます」
青年はトランクを助手席に置くと、後退りしながらそう言って、裏通りを走り出した。
「おい、ちょっと待て!」
車のドアを閉めて彼を追いかけた。
青年は怪我をしているとは思えない程の速度で走っている。
角を次々と回りながら、まるで追跡者を撒くように逃げていく。体力に自信がある自分でも驚くような早さだった。
二つ三つ角を曲がると、結構な距離を離されてしまった。
声を上げて彼を止めようとするが、息が上がって大声が出せない。
ビルの壁に手をあてて息を整えていると、手前の路地から銃を構えた警察隊が飛び出してきた。咄嗟に頭を屈めた。
あいつらの追っている武装強盗とやらに間違われて撃たれる訳にはいかない。
「いたぞ!」
「止まれ。止まるんだ!」
警察隊の叫び声が聞こえると、すぐにおびただしい銃声が聞こえた。
そっと壁から離れながら、銃声と青年が逃げていった方面を見た。
警官の足の間から倒れた青年が見える。警官達が追っていたのはあの青年だった。
彼の手には何も無い。丸腰の青年を警官達は撃ち殺したのだ。
この場から離れなければと判断して、俺はまた車に戻った。
助手席には、あの青年が俺に渡したトランクがあった。
警官に追われた青年、残された謎のトランク、巻き込まれた私立探偵。
プロットは陳腐なフィクションだが、この状況は俺にとってはシリアスだ。
一瞬、トランクを窓から放り出してそのまま走り出そうかと迷ったが、真剣な青年の眼差しを思い出し、やめた。
事務所はいつも通り誰もいない。
俺はソファーに腰掛け、天井を仰ぎ、大きく息をついた。
気持ちを落ち着けたつもりで座り直し、煙草を出して火をつける。だが、その手は小刻みに震えていた。
小説の主人公の様にはいかない。ただ、そんな自分におかしみを感じて苦笑した。
真っ先に浮かんだのは義父のマークだ。死んだ父親の代わりに母親と結婚した男だ。
俺の父親は捜査官だった。つまらない仕事上のミスを悔やんで自殺した。そういうことになってる。
そして父親の同僚だったマークが母親と再婚した。俺が十一歳の時の話だ。マークとは特に悪い関係じゃない。
説教がましいところはあったが、誠実な態度で接してくれた。
捜査官としても理想的な男だ。ドラマに出てくるグッドコップそのままの男。
ただ、どこかで距離があった。
俺は何度も捜査局に誘われたが、その都度断った。どこかにあったその距離、わだかまりのせいだ。
まあ、そんなことはどうでもいい。それより、マークは面倒ごとを楽しむタイプじゃない。
この事も仕事として、捜査官として処理してくれるだろう。
ローテーブルの上に置いたトランクをしげしげと眺める。トランクの作りはいい。金具も、張られた革も安物ではない。
開けるべきか開けないべきか、俺は思案していた。
トランクを開けずにマークに渡し、起きたことも全部正直に話して、あの死んだ青年のことを忘れる。
トランクを開けて中身を確認し、死んだ青年の謎を調査する。
パルプ小説の主人公だったらどちらにするかは、考えるまでもない。トランクを前にしたまま俺はソファーに横になった。
そして煙草の脂で茶色に変色した壁紙の花を眺めた。
印刷された壁紙の花は繰り返されている。ずっと見詰めていると、すぐにどこを見ているかわからなくなる。
同じことの繰り返し、変哲のない人生、書き割りの人生。繋ぎ合わされ、適当な場所で断ち切られる人生。
俺は起き上がり、トランクの蓋に手を掛けた。
少し血が付いているが、それ以外は大きな傷もへこみも見当たらない。
手前にはダイアル式の鍵が付いている。壊して開けてもいいが、なんとなく躊躇した。
ちまちまと数字を合わせていく。
こんなシーンはパルプ小説で何度も見た筈だが、主人公達がどうやって開けたかは思い出せなかった。
上着を脱ぎ、一時間程鍵と格闘すると、鍵が577でカチリという音と共に外れた。
思わず、小さくよしっと呟いてしまう。
トランクの扉をゆっくりと開けていった。そこにあったのは灰色のリールに収まった二本のフィルムだった。
フィルムを目にするのは初めてだったが、どんなものかは知識としては知っていた。
時代小説に出てくる巨大な海賊船と同じ程度だが。
アナクロ趣味の自分にぴったりのアイテムといえた。まるで仕組まれているかのように。
トランクに収まったフィルムを手に取ろうとした時、事務所の扉を誰かがノックした。
「―了―」
2837年 「フィルム」 
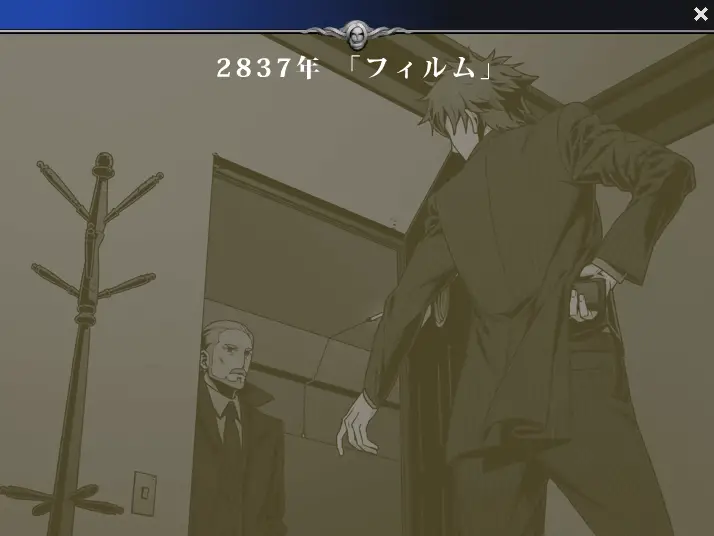
俺はノックの音を聞くと直ぐに立ち上がり、机に仕舞ってあった拳銃を手に取った。普段は使うことがないものだが、万が一ということもある。マガジンを装填してスライドを引いた。そして脱いでいたジャケットを素早く羽織った。
扉に近付いてドアスコープを覗く。背の高い、コートを着た見慣れた男が立っている。継父のマークだ。
「俺だ。開けてくれ」
拳銃にセイフティを掛けてベルトの背中側に差し込み、落ち着いてドアを開けた。
「どうした。ずいぶん遅くまで働いているみたいだな」
「ああ、仕事がちょっと立て込んでね」
マークは部屋に入ると来客用のソファーにどかっと腰を下ろした。さっきまで自分がトランクと格闘していた場所だ。
「そうか。面倒でも起きてるのか?」
冷えたグラスに注ぎ、マークの前に置いた。
「大したことじゃない。それより、何でこんな時間に?」
「何、帰り際に前を通ったとき、明かりが見えてな」
マークは時折、この事務所にやって来ては世間話をして帰ることがある。
「どうした、浮かない顔だな」
「言ったろ。立て込んでてね」
「また浮気調査か?」
「ああ。クライアントがなかなか面倒なタイプでね。やれこの写真じゃだめだ、経費に納得がいかないだの、うるさいのさ」
あまり饒舌にならないよう、いつも通りに答えたつもりだった。嘘を見抜くのがマークの仕事だ。
「なるほどな」
「所詮この家業は人付き合いさ。金のためだ。やるしかないね」
少し大仰に嘆いてみせながらソファーの背に寄り掛かった。ただ、ベルトに差した拳銃が背骨に当たり、すぐに身体を元の位置に戻した。慣れないことはするもんじゃない。
奇妙な沈黙が二人の間に漂った。
継父の刑事を前に隠し事、おまけに背中には不慣れな拳銃。これはあまりいいシチュエーションじゃない。
「「お――」」
二人同時に声を上げると、苦笑いしながら俺は相手に手振りで譲った。
「……お前、母さんから親父さんの事、どこまで聞いている?」
突然の意外な切り出しに少々面を喰らった。
「なんだよ、唐突に」
思わず口に出た。
「親父さんのトニーが最後に担当した事件は知っているな」
「ああ、確か芸術家が自殺に見せかけられて殺された事件だ。未解決で終わったって聞いてる」
こんなぼかした言い方をする必要はなかった。親父が最後に担当した事件については大人になってからかなり詳しく調べていた。ただ、上層で起きた事件だけに、自分の今の階級からでは官製メディアの概要情報を知るのが精一杯だったが。
「じゃあ、母さんじゃなく、トニーから何か聞かされたことは?」
「俺がまだ四歳かそこらの話だ。聞いたって、覚えてるわけがない」
「そうか」
「そういうのは俺じゃなく、母さんの方が知ってるだろう。にしても、なんで今更そんなことを?」
俺は聞いた。
「実はお前にこんなことを話すのは何なんだが……」
こんなマークの表情は初めて見る。
「まだ報道はされてはいないが、奇妙な事件が相次いで起きている。今じゃ上層も含めた俺達捜査官は、ずっとその事件に追われているんだ」
そう言うと、マークは大きく息をついた。タフな男がこんな姿を見せるのはめずらしい。
「それが親父と関係がある?」
「そう、トニーが担当した事件が今回の一連の事件と深く関わりがあるんじゃないか、という話が出てな」
「それで俺に話を?」
「そうだ。何でもいいんだ。ちょっとしたことでいい。思い出せないか?」
「悪いな、何も覚えていない」
俺は嘘を言っていた。この話を聞きながら、俺はあることを思い出していた。ただ、それをマークに気付かれたくなかった。
「そうか……わかった」
マークはそう言うと、コップの水を飲み干して立ち上がった。
「体には気をつけろよ」
「ああ、あんたももういい歳なんだから、無理せずにな」
マークには普段見られない疲労感が漂っていた。自分の嘘も気付かれていないようだ。これは幸運だと喜ぶべき事なのだろうか。
「分、やらなきゃいけないことはまだまだあるんだ。怠けてはおられん」
「母さんによろしく」
「ああ」
マークは出て行った。
俺は背中の拳銃を抜くとマガジンを抜き、薬室から銃弾を取り出した。そしてマガジンと拳銃を元の机に仕舞った。
マークがここに来た時には、てっきりトランクのことが監視カメラか何かに見つかって回収しに来たのかと思ったが、そうではなかったようだ。そして俺にトランクの中身に関するヒントを残して去って行った。
マークが言っていた親父のことを思い出していた。そしてフィルムについても。
あのフィルムは親父のもではないのか?親父はよく俺を古ぼけたカメラで撮影していた。それを家族全員で観た思い出が、マークと話している間に急に浮かび上がってきていた。
三人一緒に部屋を暗くしてフィルムを観ていた。生まれたばかりの自分の姿。笑顔の母親。奇妙な気分だったのを思い出した。
今思えば、親父にはそういう趣味があったのだ。親父が死んでから母親が全てを処分してしまったから思い出すこともなかったが、確かに俺はフィルムを観たことがあるのだ。
俺のこの時代遅れの骨董趣味は父親譲りだったのだ。なぜそれを忘れていたのだろう。
それでも、あのフィルムが親父のものであるという確信が、今はある。
俺はソファーの下に隠したトランクを取り上げ、フィルムを取り出した。
そしてすぐに部屋の照明に透かしてフィルムを眺めてみた。
指で隠れてしまうほどの細いフィルムには、肉眼では何が写っているのかよくわからない。
ただ、二人の人物が写っていることだけはわかった。
フィルムの中身を詳しく調べる必要だあると、俺は思った。
それと、フィルムの中身とは別に、もう一つ調べなければならないことがあった。
青年が最後に言った『サーカス』についてだ。
この階層にサーカスが来たという話は耳にしていない。どこのサーカスのことだろうか。何かの例えや隠語なのかもしれない。
それと、親父の事件とマーク達が追っている事件の内容も気になった。
――この二つの事件には必ず関係がある。
――そして、それは親父の死に結びつく筈だ。
自分が驚くほど興奮していることに気付いた。
俺はすぐにフィルムを自分の鞄に移し替えた。そして拳銃とマガジンも一緒にその鞄に入れた。
俺は端末で調べたい情報をまとめると、全てメモに取った。
そして、事務所を出て車に乗り、自宅へと戻った。
三ブロックほど離れた高層アパートメントの一室が俺の部屋だ。午前一時を回ったロビーには、ガードマンのオートマタ意外誰もいない。定型の挨拶をするガードマンを無視し、フィルムと拳銃を入れた鞄を持って二十階まで上がる。
早く休みたかった。奇妙な緊張の連続でひどく疲れていた。
鍵を開けて自分の部屋に入る。
ベッドサイドに鞄を転がしてジャッケットを脱ぐと、そのまま眠ってしまった。
朝、俺はいつもの目覚ましの音で目を覚ました。快適な朝ではないが、起きなければならない。現実はこっちの気分をお構いなしに進み続けるのだ。
いつものように情報端末のスイッチを入れた。設定されたニュースが流れてくる。
緊迫した様子のキャスターが何か早口で捲し立てている。俺はそのニュースに釘付けになった。
「暴動です!大規模なオートマタによる暴動です。この第十二階層すバース地区で労働用オートマタが突如、街で破壊行為に及んでいます。恐ろしい光景です!」
キャスターは望遠レンズで映し出される光景を、信じられないといった様子で実況している。
「今、鎮圧のための部隊が現れました。重武装です。今までこんな光景があったでしょうか?我々の所有物であり、労働の機械に過ぎない彼らが、主人たる我々人間に対して集団で抵抗しているのです。これは一体どういうことなのでしょうか」
カメラはパンをして道路脇から現れた鎮圧部隊を映している。たしかに商店の窓ガラスが割られ、路上の車からは炎が上がっている。ただ、実際に暴れているというオートマタの姿はどこにも見えない。
鎮圧部隊は隊伍を組んで通りを進んでいく。既に鎮圧用のショットガンを水平に構えていく。
俺はベッドの端に座って端末を食い入るように見ていた。
すると突然、鎮圧部隊の映像からキャスターのいるスタジオに映像が切り替わった。
「当局からの指導により、これ以上の中継画像は提供できなくなりました。これは安全上の理由であり、報道の自由を侵すものではないという発表です。なお、十一時から管理局による会見が予定されているとのことです。誠に申し訳ありませんが、続報は十一時までお待ち下さい」
時計は八時を回ったところだ。
「なお、第十階層にはまだ当局からの指導、警告は出ていません。引き続きオートマタ蜂起の話題について、専門家を交えて解説していきます」
キャスターがそう言うと、端末はCMへと切り替わった。にこやかな美男が出てきて自分がいかに優れた家事機能を持っているか説明しはじめた。暴動も起こせるのが最新機能か、そんな皮肉なジョークが頭に浮かんだ。
だが、俺にはやらなければならないことがある。ニュースに齧り付いているわけにはいかない。
俺はシャワーを浴びて着替えを済ますと、鞄を持って部屋を出た。
「―了―」
2837年 「監視」 
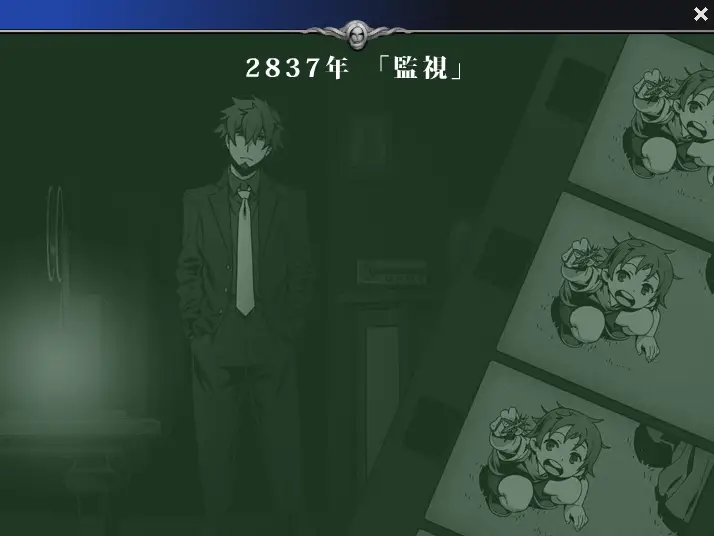
人通りもまばらな街中は、奇妙な緊張感に支配されていた。
普段のこの時間であれば混んでいる筈の幹線道路も、今日は随分と空いている。
仕事には都合がいいが、不安な気持ちがもたげてきた。堪らず音声放送のスイッチを入れる。
「――オートマタの一団に占拠された区画では通信のとれなくなった地域が出始めたようですが、この理由は何でしょうか?」
アナウンサーらしき女が言った。
「おそらく統治局の判断でしょう。オートマタには通信設備を接収する知恵などありませんからね。無駄な混乱を避けるための方法です」
解説者らしき男がそう答える。
「成る程。では、当局は状況をコントロールしているということでしょうか?」
「もちろんです。一種のアクシデント、または悪質な愉快犯による犯罪でしょうが、当局のコントロールは万全です。沈静化するのも時間の問題でしょう」
「なるほど――」
俺は音声放送を切った。こんなものは御用学者による統治局のお為ごかしに過ぎない。まともな知性を持った人間なら、状況が逼迫していることは明々白々だ。まあ、「まともな知性」とやらを持った人間が今の世界に何人いるのかは知らないが。
俺は車を馴染みの骨董屋に向けていた。その骨董屋は映写機を扱っていた筈で、とにかく最初の伝手はそこしかない。
通りを曲がり、骨董屋まであと二ブロックといったところで、大きなプラカードを抱えた男が大声を上げながら横断歩道を渡ってきた。
「裁きの時は来た!ついに我々の世界は滅ぶ!自らの作り出した機械によってだ!怠惰の罪はいま下る!」
プラカードには「怠惰な人類よ、改めよ!」と書かれている。ごくたまにいるアンチ・オートマタ信奉者だ。ここぞとばかりに大声を張り上げている。
普段は無視するであろう人々も、今は訝しげにではあっても彼を見つめていた。ひょっとしたら正しいのは彼なのかもしれない、と思っているかのように。
その時、通りの向こうから三人の警備官が一斉に走り出してきて男を取り押さえた。横断歩道の真ん中で取っ組み合いが始まった。信号は青になったが車を進めることができない。
「これは弾圧だ!真実は一つ――」
取り押さえられた男は引き摺られるようにして連行された。様子を見ていた人々は少し気まずそうな様子で顔を背け、再び歩き始めていた。
車は骨董屋に着いた。店主に事情を話し、映写機をその場で借りる。
カラカラと乾いた音を立てながら、フィルムは回転速度を上げていく。
暗闇の向こうに浮かび上がる色あせた世界には、俺が映っていた。
若い母親が幼い俺の手を握って歩いている。俺はその手を振り解いて道端に座り込む。何かを見つけたようだった。カメラもそれに近付いていく。その手にはバッタが握られている。母親は「はやく捨てて」と言う。
「ふふっ、恐がりだなあ」
カメラに映っていない父親の声が聞こえた。何故かとても懐かしく思えた。
これで、このフィルムが父親の物だということはわかった。
ただ、いくら眺めても特別なものは見当たらない。これは単なる子供の成長の記録に過ぎない。その子供は自分だが。
「親父さんはなかなかいい趣味をしているな」
骨董屋の店主が言った。
「変わり者だったのさ」
見たことのないフィルムだった。
映っている俺の年齢からすると、父親の死の直前に撮られたもののようだ。
フィルムの中の俺はバッタを握ったまま前に走り出した。そして投げるようにバッタを逃した。
そこでフィルムは途切れ、画面は暗いまま回り続けている。
父親は何を思ってこのフィルムを残したのだろうか。何故俺にこれが届けられたのだろうか。
その理由がずっと頭の中を巡っていた。
「ブロウニング捜査官、これが解析班が合成したオートマタの姿です」
俺は若い男女の画像を端末で受け取った。その二体はよくある市販のオートマタと違い、人工的な部分が全く見受けられない自然な顔立ちだった。おまけにどちらも美男美女だ。画像に下にはそれぞれ《ミア》《ウォーケン》と名前が表示されている。
「オートマタには見えないな」
自然な感想が口から漏れた。
「あの天才、グライバッハ氏の最後の作品ですからね。レベルが違いますよ」
自殺、いや、今は他殺だと思われている天才オートマタ作家の名前を解析官は口にした。
「そんなものか」
興奮した口調の解析官にそう答え、俺はメルキオールの監視へ向かうために局舎を出た。
メルキオールの監視を始めて二週間が過ぎていた。監視といっても、やることはバンの中で奇妙な研究者の独り言を聞き続けるという、一種の拷問だった。
「まったく、あの爺さんの繰り言を記録するのに意味なんてあるのか?」
同じ監視班の同僚、フリードマンがヘッドフォンを外して言った。
「さあな、何かしてないと上は満足しないからな」
コンソールを切り替え、自分のヘッドフォンに室内の音声を流す。モニターには研究室をうろつきながら独り言を言うメルキオールが映っている。
「いつもと変わらんな」
グライバッハ殺人の被疑者と見られたメルキオールは、捜査局の監視は許したが捜査員の同室は許さなかった。そのため捜査局はカメラを設置し、外のバンから彼を二十四時間監視することにした。
独り言を繰り返す神経質な老科学者は、まるで役立たずに見えた。二週間毎日見続けたが、様子に変わりはなかった。
「子供は元気か?」
監視に飽きたフリードマンが世間話を始める。
「最近会えてない。とにかく、この捜査が終わらないことにはな」
何日も家には帰れていない。家族を撮ったフィルムも現像にださなければならなかったが、忙しくて鞄の中にそのままだ。
「レントン部長は焦ってるしな」
「ああ。何も成果が上がらなきゃ、部長はおそらく左遷だろうよ。統治局の奴らに睨まれちまったからな」
「恐ろしい話だ」
「仕方がない。俺達は所詮役人さ。 上から睨まれちまえば逃げ場はねぇよ」
本当はレントン部長に同情している暇なんて無かった。俺達も今回の捜査でヘマをすれば、おそらくとんでもない目に遭うだろう。俺が見た統治局最高クラスのレッドグレイヴという人物であれば、冷酷に総判断する筈だ。
俺はフリードマンのやる気のない態度に少し苛ついていた。俺には小さい子供もいる、守らなきゃいけない家族がある。こいつのように暢気にはやれない。
フリードマンの会話を聞き流しながらモニターを眺める。たしかに代わり映えのない姿だ。メルキオールは中央にある煤けたボイラーのような機械と手前のコンソールを行ったり来たりしながら作業をしている。
ずっと独り言を言いながら思い付いたように二、三時間仮眠を取るだけで、同じ事を繰り返している。食事すら作業をしながら簡易なものを取るだけだった。驚異的な集中力ではあったが、その生活には人間味はかけらも感じられない。
「こいつが殺人犯だというのなら、よっぽど――」
「待て、今のところの録画を見せてくれ」
「フリードマンの会話を遮って俺は言った。
「どうした?」
「妙なものが見えた。巻き戻してくて」
フリードマンは動画をコントロールするコンソールを操作して、別のモニターに少し前の映像を出した。
俺は自分の見たものを確認した。
「ここだ!止めろ!」
そこには数フレームではあったが、画像の乱れが記録されていた。
「ただの接続不良じゃないか?別に続きはおかしくないし」
「よく見ろ」
コンソールをフリードマンから奪って一フレームずつ確認していく。そこには一画面の中で複数人のメルキオールが作業しているのが映っていた。
「確かにおかしいが、機械の故障じゃないのか?」
「いや違う、この画像は合成だ。あの爺さん、とんだ食わせ者だぜ」
何故かそういう確信があった。そしてその確信の下に振り返ると、メルキオールがずっと続ける独り言や異常な振る舞いこそが、却って演技的に思えてきた。
「本当か?もし勘違いだったら……」
「だとしても見逃したらことだ。お前は動きがないかここで見ていてくれ。俺が確かめてくる」
「わかった」
俺はバンの外に出た。ヤツがこちらの動きを察知したら偽装の証拠が掴めないかもしれない。であればヤツが偽装を切り替える前に乗り込まなければならない。俺はバンから持ち出したショットガンを構え、意を決して走り出した。
研究所の正面扉空ではなく、窓をショットガンでぶち抜いて所内に飛び込んだ。そして素早くヤツが今いる筈の研究所に向かう。
割れたガラスに反応してアラームが鳴っているが誰も出てこない。研究室のドアを開けると、この二週間毎日見続けてきた薄汚れた部屋があった。しかしメルキオールの姿はそこには無い。
俺は交信機でフリードマンを呼び出す。
「やはり偽装だ。研究所内をチェックする。こっちに来てくれ」
「了解した」
「あと、衛星監視システムで本当に人の出入りがなかったかを確認してくれ。ログがある筈だ」
そう連絡すると、俺は銃を構えたまま室内のチェックを始めた。
雑然とした室内は機械の周期的なノイズ以外何も聞こえなかった。
ヤツはこの研究所にいないのか?いや、ここ以外に行く必要のある場所は無い、ヤツが研究者であることは偽装のしようがない事実だ。ということは、俺達捜査員に見られたくない、何か別の作業をしているのだろうか。
正面扉の前まで来たフリードマンを中に招き入れ、二人で所内をチェックしていった。
捜査資料の見取り図にある全ての部屋、空間を見て回ったが、メルキオールの姿はどこにも無かった。
「くそ、どこかに逃げちまったのか?」
「それはないだろう。衛星監視ログには何も記録されてない」
「秘密の抜け穴か、またはログをハックしたか……」
どちらもこの短時間で自分達の目を眩ますには大仰すぎる。
「最後にヤツを直接見たのはいつだ?」
「一昨日だ。荷物を受け取る姿を見ている」
フリードマンは言った。であれば、ヤツは必ずこの研究所の何処かにいる。
俺は見取り図をもう一度眺めた。何か秘密がある筈だ。見取り図を見ながら所内を進むと、一箇所だけ、本来は左右対称である筈の壁が微妙に狭く作られているところがあった。
機材が積み上がって雑然とした所内ではわかりづらいが、そこには確かにスペースが存在していた。
「ここだ、この奥に何かある筈だ」
「どうする?応援を呼ぶか?」
正直、逡巡していた。応援を呼べば監視班は失態の責を取らされるだろう。がしかし、自分達の手でメルキオールを拘束できれば、責任問題は考慮されるかもしれない。
「とりあえず何があるか確かめよう」
俺はショットガンに弾を装填して構えた。今は時間が無い、悠長な真似はできない。
その時、シュッという空気圧の音と共に壁が開き、中からメルキオールが出てきた。
「動くな!」
俺はショットガンを構えたままメルキオールに警告した。
「撃ちたければ撃て、馬鹿者共が」
メルキオールは手を払う仕草をしながら、隠しエレベーターから出てきた。
「なぜ監視システムに偽装を仕掛けた?何をしていたんだ?」
銃を構えたまま問うたが、メルキオールは構わず動こうとした。仕方なくフリードマンがメルキオールの腕を掴む。
「あなたを拘束します、メルキオール」
フリードマンはメルキオールの両腕を乱暴に後ろに回し、結束タイで拘束した。
「ええい、これではあいつの思うがままだぞ。私を自由にせんか」
「全てを明らかにしていただかなければ、拘束を解くことなどできません」
「時間が無いのだ。お前らだって無事では済まんぞ、このままでは」
「だったなら尚のこと話してください。この状況の意味を」
ショットガンを下ろして俺は言った。
「時間が無いのだ、拘束を解け、説明はしてやる」
「拘束を解くのは納得のいく説明の後です。あなたは殺人事件の被疑者です」
「馬鹿な役人だ、まったく」
ぶつぶつと繰り言をいうメルキオールを手近な椅子に座らせる。
「地下には何があるんです?」
「ここのメインフレームと小さな作業室が置いてあるだけだ。お前らに邪魔されないよう、そこで作業をしていただけだ」
「なぜ我々に見せたくないのです?」
「愚にもつかない法とやらに抵触する作業だからな。研究にとっては、いや、この実験の顛末にとっては実に邪魔だ」
「なるほど、では作業室は後で見せてもらいましょう。それで、法に触れる作業とは何です?」
「二人の、いや、二匹のオートマタを追い詰めていたのだよ」
「そうだ。奴らはグライバッハを殺し、私の研究成果を盗んだのだ」
「我々もその二体を追っているところです。我々に協力してもらえれば――」
フリードマンが横から口を挟んだ。
「ふん、お前らなどは邪魔にしかならない」
「それは嘘だ。あなたは自分で彼らを捕まえて、自分の研究結果とやらを奪い返したいのですね?」
「当たり前だ。私の研究結果は私のものだ。他の誰にも私はしない」
研究者としては優秀かもしれないが、この老人は他人のことなど一顧だにしないエゴイストであるのがよくわかった。体よく言えば純粋なのだろうが。
「わかりました。とにかくその二体を捕まえましょう。話はそれからでもいいでしょう」
「初めからそうしろと言っているのだ。早くこの私を自由にせんか」
おそらく彼の研究結果というのはあまり公にできないものなのだろう。しかし今はそんなことは問題ではない。真犯人であろう二体のオートマタを捕まえるのが先決だ。
創造主を殺したオートマタ、親を殺した子、これは歴史的な事件になるかもしれない、そう俺は直感していた。
「―了―」
2837年 「カメラ」 
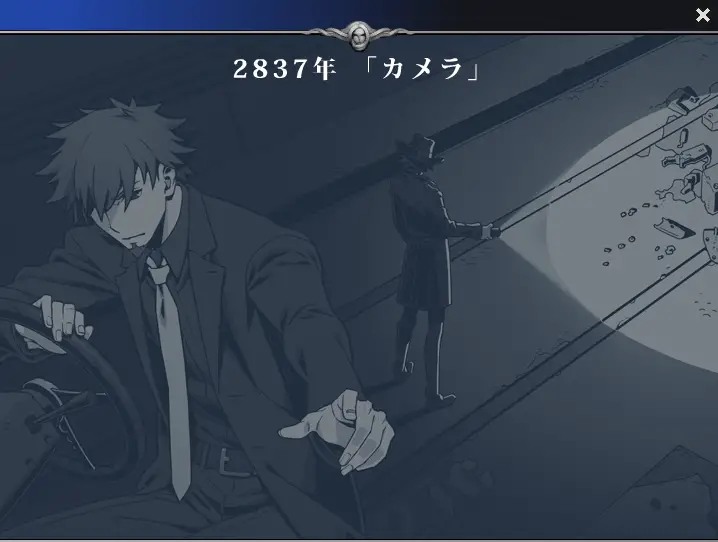
メルキオールの地下研究室で、俺は姿を消した二体のオートマタの行方を追っていた。
「現在地を追えるのか?」
「いま走査しているところだ。こちらが仕掛けた網が間に合えば位置はわかる」
グライバッハを殺した真犯人は逃げた二体のオートマタであるとメルキオールは語った。機械による殺人、ならば誰かが命令したことになるが、その正体はまだわからない。
それでも、危険なオートマタが市井に逃げ出したのならば、まずは捕らえるのが先だ。
「あれらは恐ろしく精巧に出来ておる。外見では決してオートマタだとはわからないだろう」
「姿だけでなく、行動も特別なのか?」
「そうだ。だが、その特別さを利用して網を仕掛けることができた」
メルキオールが特別な才能を持ったテクノクラートだということは資料でわかっている。その実績は末端の下級官吏に過ぎない自分とは全く次元の異なるレベルだ。今は彼を信用するしかない。
「もうすぐ居場所が判明する。先にこれを渡しておこう」
メルキオールは小さな棒状の装置を俺に渡した。
「グライバッハが用意していたオートマタの緊急停止スイッチだ。10アルレまで近付いて押せ」
手に収まる小さなスイッチには、大層な仕組みがあるように思えない。
「暗号化されたキーを特殊な通信方法で送るものだ。距離があると使えない。今はこれしか奴らを止める方法は無い」
「もしもの時は銃で撃っても構わないのか?」
「やめておけ。絶対に奴らと会話したり攻撃したりしようと思うな。ただ近付いてそのスイッチを押せ。それだけだ」
その時、コンソールがアラート音を出した。
「場所がわかったぞ。階層と階層を繋ぐ輸送シャトルの坑道にいるようだ」
どうやら、オートマタは階層を降りようとしているようだった。管理区域を越えられると捜査が面倒になる。急がなければならない。
「応援はどうする?」
フリードマンが聞いてきた。
「本部に連絡すれば挟み撃ちにできるかもしれんな」
「やめておけ」
メルキオールが口を挟んだ。
「何故だ?」
「奴らに無防備な人間が遭遇するのは危険だ。そのスイッチを持った者のみが近付くのが正しい」
「何か危険な武器でも持っているのか? 奴らは」
このオートマタの危険性については聞いておかなければならない。
「ああ、そうだ。気付かれぬように近付いてそのスイッチを押さなければ、皆グライバッハのような目に遭う」
「詳細は言えないと?」
持って回った言い方に苛つきを覚えた。
「言ったところで理解は不可能だろう。そういう類の驚異だ。油断すれば殺されると思っていればいい」
この男に誠実な受け答えを期待しても無駄だということは、この短い時間でもわかっていた。だが、急がなければならないのは確かだ。やるしかない。
「いいか、そのスイッチを言われたとおりに使えば何の問題もない」
「一緒に来るか?」
メルキオールに聞いた。
「いや、そのスイッチのコピーを作れるのは私だけだ。私が死ねばもう誰も作れまい」
「俺達を信用するわけか」
「確率の問題だ。有利な方を選ぶ、論理的な選択というべきだな」
こういう会話は建設的じゃない。実質的な話をしておこう。
「彼らの知覚能力は?」
「人間よりは上だろうが、細かなスペックは不明だ。だが、こちらに有利な点が一つだけある。奴らはこちらが先回りしていると思っていないということだ」
「会敵したときに一瞬のチャンスがあると」
「そうだ。奴らが向かっているのは整備中の127C坑道だ。現在シャトルは通っていない」
メルキオールがコンソールの画面を見せた。
「143Dが平行に走ってる。こちらのシャトルを止めて先回りできるように連絡しよう」
フリードマンとデータを確認する。
「サマリタン通り東24番の作業孔から降りられる。急げ、奴らは移動し続けているぞ」
俺達はメルキオールの地下研究室を出ると、急いで車へ乗り込んだ。
「飛ばすぞ」
ブロウニングは車のアクセルをふかした。サマリタン通りに飛び出し、目一杯のスピードで目的地へ向かった。
「銃はどうする?」
フリードマンが聞いてくる。こいつはこういう状況でイニシアチブを取るタイプではなかった。
「不安なら持っていけよ。俺はスイッチに集中する」
メルキオールの言葉を信用したわけじゃない。直感の判断だ。車が目的地に着く。フリードマンと共にハッチを開けて階段を降りていく。
「間に合いそうだ。D78のハッチを使え、そこで127Cに出る。奴らの現在位置を送る。待ち伏せのポイントも示しておく」
通信連絡がメルキオールから入った。
「通信は奴らに気付かれる可能性があるので、これで終わりにする。奴らが近付いたらスイッチを押せ。それで全てが済む」
「わかった」
俺とフリードマンはフラッシュライトを片手に、暗い地下道を慎重に進んでいった。D78のハッチを開け、目的の坑道へ出た。
127C坑道にはシャトルレール整備のための機械が雑然と並んでいた。電源が入っていない状態の作業用オートマタが何体も転がっている。
「やばい予感がするぜ」
フリードマンが小さな声で不安を口にする。
「急ごう」
なるべく音を出さないようにして、俺達は待ち伏せのポイントへ向かった。ポイントには退避スペースが作られている。そこに身を隠して奴らを待ち伏せすることになる。
待ち伏せのポイントに着くと、フリードマンはホルスターから銃を抜いた。
「念のためさ」
俺は黙ってスイッチを胸の前で握った。フラッシュライトを消して、奴らがくるのを待つ。
沈黙と暗闇の時間が続いた。遠くの小さな非常灯だけが小さく光る世界には、まるで現実感が無かった。
一五分程待てばいい筈だったが、この沈黙の時間はとても長く感じられた。蓄光材でうっすらと示された腕時計の針を何度も確認してしまう。
それから二〇分程待つと、足音が坑道に響き始めた。フリードマンが銃を構え、自分はスイッチを押す準備をする。
足音は確実に近付いて来ていた。姿は確認できない。奴らはライトを使わずに進んでいるのだろう。
音で距離を判断しなければならなかった。確実に近付いてから、そして近づき過ぎる前にスイッチを押さなければならない。
俺は必死に目を凝らして二体との距離を測ろうとした。だが、暗闇が濃くてよくわからない。足音に集中するしかない。
まだ距離は離れているようだった。俺は緊張で何度もスイッチを握り直した。足音の距離はかなり近付いてきていた。
こういう緊張状態は知覚をあやふやにする。できるだけ引き付けてから押すべきだと、俺は決心していた。
足音が止まった。
感付かれたか。奴らの知覚能力はこちらより鋭いだろう。一か八か飛び出してスイッチを押すべきだろうか。
フリードマンに声を掛けて飛び出すしかない。決断は一瞬だった。
「奴らに近付く、バックアップを頼むぞ!」
俺は暗闇の中を飛び出し、オートマタがいるであろう場所へ走った。
後方からフリードマンがライトを照らす。背後からの光で相手の姿が確認できた。オートマタが二体、確かに見えた。距離はギリギリに思えた。
成り行きに任せるしかない。俺はスイッチを押した。すると一体のオートマタがその場で倒れ伏し、もう一体がぐらつくのが見えた。
俺は踵を返す形で走り出した。暗い坑道で機械に殺されるのは御免だ。俺には家族がいる。任務より大切なものがある。
「やめろっ!!」
その叫び声を最後に、フリードマンは作業用オートマタに頭を潰された。もう勝ち目は無い。逃げるしかない。生きて戻らなければならない。
俺は必死に暗闇を走った。後ろを一度も振り返らず、入り口のハッチを目指した。
ハッチの小さな明かりを見つけ、そこに飛び込む。ハッチをロックして階段を駆け上がった。そして、俺は地上への出口まで辿り着いた。
息は上がりきり、目の前が霞んでいた。落ち着いて耳を澄まし、様子を窺う。追ってきている様子は無かった。どうやら生き残れたようだ。再追跡は時間が掛るかもしれないが出直すしかない。フリードマンの死や捜査の失敗より、今は生き残った安堵の方が大きかった。
息を整えると、扉を開けて通りへ出て、俺は車の方に足を向けた。
車の横には妻のヘレンが立っていた。
「忘れ物は見つかったの?」
彼女は声を掛けてきた。俺は家族で出掛けるところだった。滅多に取れない休日、家族で公園に行こうとしていた。遠出はできなくとも思い出は作れる。
俺は彼女に鞄を掲げてみせた。カメラ用の電池を忘れたのだ。
「さあ、行こう」
息子のデイヴはすでに車の中にいた。後ろの席で手持ちぶさたにしている。
俺は車に乗り込むと、カメラの入った鞄をデイヴの隣に置いた。
「中をいじるなよ」
「うん、わかったよパパ」
デイヴは元気よく答えた。家族で出掛けるのが楽しいようだ。
俺は運転席に座り、車を走らせた。ヘレンはデイヴの隣に座った。
「仕事はどうなの?」
ヘレンが聞いてきた。
「まあまあ、悪くない」
まあまあどころではない。大きな失敗をしたばかりだった。だが、今はそれを思い出したくはなかった。
バックミラーにデイヴがカメラを手にしているのが映った。
「おい、カメラはやめるんだ」
「この子、あなたの真似をしているのよ」
「ヘレン、やめさせてくれ。壊れやすいんだ」
このカメラは大した値段ではないが、骨董品で壊れやすい。俺はヘレンに頼んだ。
「さ、デイヴ、ママに貸して」
デイヴはまだカメラを振り回していた。
「パパの大事なカメラだから」
ヘレンはデイヴからカメラを取り上げようとする。
その時、目の前の道路に検問らしきものが見えてきた。近付くにつれてそれが物々しい、武装された捜査局の道路封鎖だというのがわかった。
「おかしいな、こんな場所で……」
俺が呟き、車のスピードを落とそうとした時だ。
「進んで!私達殺されるわ!」
ヘレンが声を上げた。カメラを手に握っている。
「パパ、怖い!早く行こう!」
後ろのデイヴが俺の肩を掴んだ。
「大丈夫、パパはやってくれるわ」
ヘレンはデイヴを抱きかかえた。
そうだ、逃げなきゃいけない。俺には守るべきものがある。
「心配するな」
アクセルを思い切り踏み込んで検問へ向かっていった。必ずやり遂げなければいけない。家族を守るんだ。車両と車両の間を目掛けて猛スピードで進む。
封鎖している捜査局の車両の影から、一斉に発泡炎が上がるのが見えた。
横転した車から飛び出した女性形のオートマタが一斉射撃を受ける。四肢に銃弾を受け、オートマタは回転するように地面に叩き付けられた。
「こうしなければ、もっと被害が出ていただろう」
捜査車両の裏で、メルキオールはレッドグレイヴに言った。
「家族には暫くしたら適当な死因を伝えなさい。今回の混乱については、一切を口外無用とする」
レッドグレイヴは秘書に事務的に伝えた。
俺は車の再生装置にデジタル化したフィルムのデータを再生した。
両親と自分のシーンが過ぎて真っ黒な画面が続く。再生を止めようとすると、その暗闇に瞬くような光が写ったような気がした。
ゆっくりとコマ送りをしていくと、何か静止画が紛れている。コントラストが淡く、そのままでは何が写っているかわからない。捜査用の特別な画像処理を施す。
探偵にとって証拠写真の処理は業務の一部分だ。何は写っているのか調べるのは慣れている。
そうして、三枚の奇妙な画像が抽出できた。
――一つは、変哲のない路地の写真。
――もう一つは、コンクリートの壁にかかれた『127C』という文字。標識のようだ。
――最後の一つは、壊れた作業用オートマタの認識番号。
これらはヒントらしい。
画像の内容を解析する。路地の写真はすぐに場所が判明した。オートマタの写真は、形から地下整備に使われる汎用作業オートマタだとわかった。
標識については時間が掛かったが、それは地下を走るシャトルの坑道の番号だった。
そこに行く必要がある。ヒントから得られた答えは明白だった。
坑道へのアクセスは意外と簡単だった。作業孔の鍵は簡単に開いた。どうやらこの区画は使われていないらしい。
下に降りると、写真と同じ場所に辿り着く。
坑道の一部が崩れている箇所があり、そこに貼られている非常戦のテープはボロボロだ。崩れた後にそのまま放棄されたのだろう。
フラッシュライトを片手に坑道を進む。放置されたままの状態で工作機械や作業用オートマタが散乱していた。
転がっている作業用オートマタの番号を一つずつ確認していく。五、六台も探したところだろうが、ついに写真に写っていたオートマタが見つかった。
四肢はもがれ、中身もぶちまけられていたが、電子頭脳は無傷で残っているようだった。
「こいつなのか……」
俺は電子頭脳の記憶装置部分だけを取り出して、持ち帰った。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ