ベリンダ
【死因】機能停止
【関連キャラ】マルセウス、レッドグレイヴ、サルガド、グリュンワルド(交戦)、ヴィルヘルム、エイダ、フロレンス、アスラ、タイレル(製作者)、エヴァリスト、アイザック、ブレイズ
3394年 「初陣」 
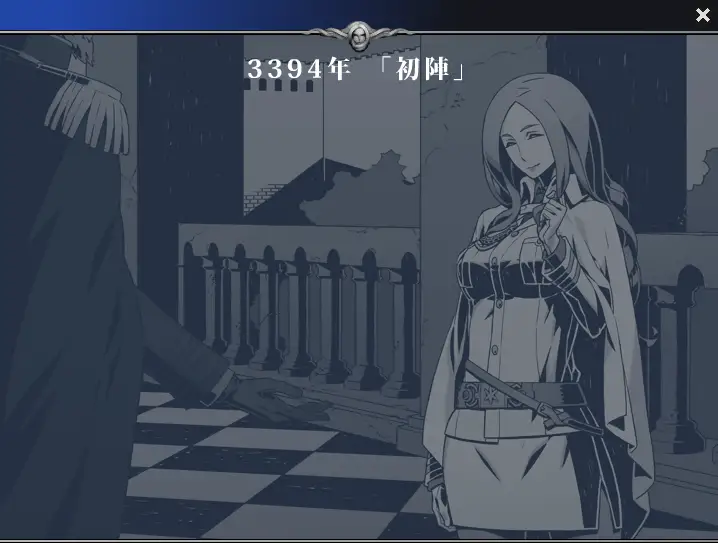
「また敗北か……」
会議室に大きな溜息が漏れた。
居並ぶ武官達は所在なさげに目を伏せ、忌々しげに報告書を机に置いた。
ルビオナ連合王国との戦争が始まって二年目の年。
これまで連戦連勝だった帝国の勢いが、ここに来て翳り始めていた。
王国随一の堅牢さを誇るトレイド永久要塞の戦いにおいて、第三軍の半分を失うという大敗を喫し、名のある将官をも数人失ったのだ。
王国装甲猟兵の勝ち鬨がこだまする中、帝国軍は無様に敗走した。
その後、帝国は幾度となくトレイド永久要塞に攻め寄せた。
だが、この堅牢な要塞を破ることはできず、逆に敵の猟兵に駆り立てられ、犠牲を増やすばかりであった。
連勝時は温和しかった文官達も、相次ぐ連敗を喫したことにより、声高に停戦を主張し始めた。
その急先鋒が、帝国切っての策謀家と言われるカンドゥン長官だった。
「今ならばまだ、こちらが有利な条件で和睦できるだろう。この先も敗戦を続ければ、それだけ相手に足元を見られることになる」
「そうだ!民は疲弊している。これ以上無益な戦争はやめるべきだ」
カンドゥン長官が述べたのに続き、停戦派が声を上げた。
それに対して武官達が反対意見を述べるが、自分達が敗れた、という引け目だからか、その声は停戦派のものよりも小さくなっていた。
室内が停戦派の声で溢れようとした時、突如、野太い声が響いた。
「何を言うか。ここでやめては帝国の威光、いや、皇帝陛下の御威光に傷が付く。一度や二度の敗戦で引き下がるなど、あり得ぬ」
うるさかった会議室が一瞬で静まった。
立ち上がった人物を見て、カンドゥン長官が舌打ちをした。
声を発したのはシドール将軍。帝国随一の武闘派で、今回のトレイド永久要塞の戦いにおいて総指揮を執っていた人物である。
「シドール将軍、あなたはそう仰るが、現にこの西部戦線は負け続きではないか。王国軍相手に敗北を喫することこそ、陛下の御威光に傷を付けることになるのではないのか」
言い募るカンドゥン長官に、シドール将軍は眉をひそめた。
「百戦して百勝できる。などと言うのは、戦場に出ない者の理屈だ。高々数度負けた程度で膝を屈すれば、今後諸国が帝国に対してどのような態度を取るか、わかりきっておるだろう」
「ならば、将軍にはトレイド永久要塞を落とせる見込みがあるというのか。幾度やっても落とせぬ、あの砦を」
「ガレオンを使えば、あんな砦など落とすのは容易いことだ」
「ガレオン?動くことすらままならない、前世紀の遺物となったあの船が?シドール将軍も冗談がお上手になられた」
カンドゥンが声高に笑い、周りの文官達もそれに追従するように笑い声を上げた。
しかし、シドールの表情には余裕が伺えた。
「ガレオンはすでに実戦投入できる段階にある。次の戦いでは、ガレオンを核とした新たな部隊が戦果を上げるであろう」
それを聞いたカンドゥンの顔に、驚きの表情が浮かんだ。
「な!?そんな勝手なことが許されるとでも……」
「すでに陛下のご内意も頂いている。まずはトレイド永久要塞ではなく、ノーザン川の渡河作戦に投入する予定だ」
「ば、馬鹿な……陛下の……」
呆然とするカンドゥンを尻目に、シドールは重々しく閉会を告げた。
閉会後騒がしくなった会議室の外で、物憂げな表情を浮かべた一人の女性が壁に寄りかかっていた。
腰まで伸びた長い髪に、人差し指をくるくると絡めている。
その姿はまるで恋人を待っている少女のようで、無骨な石造りの前線基地には全く不似合いだった。
やがて会議室から出てきたシドールが彼女に近付き、声を掛けた。
「待たせたな、ベリンダ。思ったよりも雑音がうるさくてな」
「いいえ。そんなに待っていませんわ」
ベリンダと呼ばれたその女性は、穏やかな笑みを浮かべた。
「それで、皆さんは私のことをお認めになりましたの?」
「認めるも何もない。陛下のご内意を頂いている、と言えば、それに逆らう者など居りはせん」
それを聞いたベリンダは、玩具を買ってもらった子供のような、無邪気な笑みを浮かべた。
「では、私は無事に戦場へ出られるのですね」
「無論だ」
「ありがとうございます。シドール将軍」
「礼など必要無い。必要なのは戦での勝利。ただそれだけだ。」
「わかっておりますわ。あのガレオンと私の力。まずは初陣でとくとご覧に入れます」
「期待しているぞ、ベリンダ将軍」
シドールはそう言うと、ベリンダに背を向けて歩き出した。
ベリンダ。そのたおやかな外見とは裏腹に、帝国軍の新設部隊であるガレオン急襲部隊の指揮官を務める将軍である。
去っていくシドールの背に一礼すると、ベリンダは反対の方向に歩き出した。
「戦場、音高く響く剣戟、そして血と誇りの臭い。ああ……」
笑みを浮かべたベリンダの美しい唇から漏れ出たその呟きは、誰の耳に届くこともなく、灰色の石壁に吸い込まれていった。
一週間後。
今日はガレオン急襲部隊の初陣の日だ。
ベリンダはノーザン川の上空に浮かぶガレオンの甲板に出て、軍の指揮を執っていた。
舞台はトレイド永久要塞と並んで苦戦を強いられてきた渡河作戦。
しかし、その戦闘は誰もが予想していなかった、一方的なものとなった。
ガレオンの大砲から轟音が響く度、地上に爆発が生まれ、王国軍の兵士が吹き飛んだ。
そこに帝国軍が突進し、残った王国軍兵士を打ち倒した。
空中を進むガレオンの下、王国軍は為す術もなく敗走した。
「そうそう、このままゆっくりと前進しなさい。敵の軍勢を擂り潰すのです。一粒たりとも残さないように」
ベリンダの美しい声が戦場に響くと、帝国兵がそれに応えて吠えた。
戦闘開始から僅かに一時間程度。これまで苦戦していたのが嘘のような快勝であった。
その様子を見ていたベリンダの顔は穏やかで、笑みが浮かんでいた。
一見すると戦闘の勝利を喜んでいるようだが、彼女の呟きを聞いた者がいたとしたら、何事かと眉を顰めただろう。
「……ああ、私は今無数の死に囲まれている。死がこんなにも心地良いなんて。もっと、もっと私に死をちょうだい。あなたたちの死を!」
ベリンダは両手を拡げ、水浴びをするかのような姿で天を仰いだ。
そのガラス玉のように輝く目に、微かに狂気の色が浮かんでいた。
敗戦続きで小さくなっていた拡大派の声も、ベリンダの勝利によって再び力を取り戻した。
美しい英雄の誕生も後押しし、帝国内の世論は再び戦争推進へと傾き始めた。
一方、苦汁を飲まされる格好となったのが、カンドゥン長官率いる停戦派だった。
一度は和平に傾きかけた流れを覆され、彼らは小さくなっているしかなかった。
凱旋を飾ったシドールとベリンダは、戦勝報告を終えて宮殿のバルコニーに立っていた。
「よくやってくれたな。ベリンダ」
「いいえ。これもガレオンの力のおかげですわ」
シドールは酒杯を片手に機嫌良く笑う。
「次はいよいよトレイド永久要塞の攻略だ。ここを落とせば、敵は一気に崩れるだろう」
「心得ております」
「頼んだぞ」
「はい」
小さく応えたベリンダの長い髪を、冬の訪れを感じさせる風が静かに揺らした。
その瞳には、戦場で見られた狂気の色は浮かんでいなかった。
「―了―」
3394年 「死者の力」 
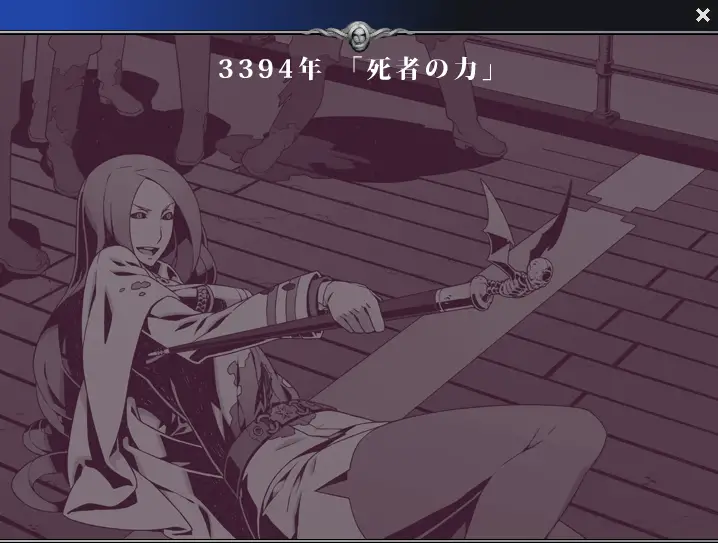
前回の戦いから数日後。
ベリンダとその部隊は、トレイド永久要塞から離れること約2リーグの位置に集結していた。
「ガレオンの調子はどう?」
「はっ。大きな問題は見られませんが、第2エンジンの出力が若干落ちております」
「艦の運行に支障はないのですね」
「はい」
「わかりました」
報告を受けたベリンダは、頷いて下士官を下がらせた。
下士官がいなくなると、ベリンダは立ち上がって窓から外の様子を眺めた。
眼下にはガレオン強襲部隊の兵士達に加え、帝国陸軍の精鋭が戦闘の開始を待っている。
昇ったばかりの朝日に剣や盾が煌めき、ベリンダはぞくぞくするような快感を覚えた。
「……もうすぐ始まるのね」
その声には、上擦ったような熱が籠もっていた。
やがて日は完全に昇り、帝国軍の陣容が整った。
「全軍、出撃!」
ベリンダの澄んだ声が響くと、ガレオンが低い唸り声を上げて動き始める。
それに合わせて、地上に居並ぶ帝国兵士達も一斉に進軍を始めた。
王国軍は進軍してくる帝国軍を迎え撃つべく、砦の前に陣を構えている。
「……ふふふ、今、戦いの狼煙を上げているわ。待っていなさい」
ベリンダはそう呟くと、右手のレバーを押し込んだ。
一瞬の間をおいて、王国軍の中央に爆発が起きた。
そこには大きな穴が空き、その場にいたはずの兵士の姿はどこにもなかった。
「ふふふ……っはははは!そうれ、もっと喰らいなさい!」
ベリンダがレバーを操作する度、王国軍の兵士はまるで人形のように吹き飛ばされる。
そこへ、前回の渡河作戦と同様に、陸上部隊が突撃をかけた。
砲撃で大きな損害を受け、陣を乱された王国軍はその勢いを押しとどめられず、帝国兵によってその命を刈り取られていった。
「そうよ、もっと死を!死を私にもたらして!あは、あははははは」
ベリンダは狂ったように笑い、次々と砲弾を放った。
見張り塔や城壁から黒煙が上がり、さしもの堅牢を誇るトレイド永久要塞も、もはや風前の灯火に見えた。
「ふふふ、これでさらに戦いが続けられるわ……」
ベリンダがようやく砲撃の手を止めて、椅子に腰を下ろした時。
鼓膜を揺るがす爆音がして、船体が巨大なハンマーで殴られたように大きく揺れた。
その衝撃で、ベリンダは椅子からはじき飛ばされた。
「!?」
慌てて立ち上がろうとするベリンダを、再度衝撃が襲った。
船体はあさらに大きく揺れ、損害を知らせるアラートが艦内に響く。
事態を把握できぬまま、ようやく立ち上がったベリンダの元に下士官が飛び込んできた。
「何があったの! 報告しなさい!」
「は、はい!装甲猟兵による攻撃です。やつらの兵器による攻撃がガレオンにまで……」
報告の間にも、爆音と衝撃の音が続く。
やがて、ガレオンは大きく前方へと傾いた。
「このままだと……落下します!至急、体制を立て直しなさい。砲撃班は猟兵共を集中的に!」
「は、はいっ!」
いつになく厳しい表情のベリンダを見て、下士官は慌てて飛び出していった。
「落とさせるものですか……」
ベリンダ自身もコンソールに貼り付き、必死に体勢を立て直す。
地上では王国軍が勢いを盛り返し、ガレオンの被弾によって狼狽した帝国兵を圧倒していた。
「くっ……でも、ヤツらさえ倒せれば!」
敵の攻撃の核となっている装甲猟兵を倒すことができれば、再び形勢は帝国に傾くだろう。
ベリンダはガレオンの姿勢を制御しながら、猟兵を狙って執拗に砲撃を続けた。
ベリンダでなければ、これほど長く持ち堪えることはできなかったであろう。
しかし、機動力と攻撃力に長ける猟兵を捕らえることは困難だった。
やがて、ベリンダの努力も空しく、ガレオンは地上へと落下した。
「かかれ!その戦艦を落とせば勝利だ!」
「させるな!まだ戦闘は終わってないぞ!」
ガレオンが落ちたのは、帝国兵と王国兵が入り乱れる戦場の真ん中だった。
甲板に出たベリンダの目前で、ガレオンの乗組員達もたちまち白兵戦に巻き込まれる。
彼らは兵士ではあったが、あくまでガレオンをコントロールする、いわば『水兵』であった。
剣を持って立ち向かったが、一合と渡り合うことなく敵兵に殺されていった。
「………………」
だがその惨劇を見て、ベリンダはこれまでとは比較にならない程の興奮を覚えた。
これほど多くの死が、自分の間近で発生している。
血が飛び散り、絶叫が辺りに響く。
その全てが、ベリンダの精神に高揚をもたらしていた。
「あそこにもいるぞ!」
「殺せ!」
恍惚とした表情で立ち尽くすベリンダの元へ、王国兵が殺到する。
「………………」
切っ先が届くかと思われた瞬間、ベリンダの前に氷の盾が現れ、剣をそらした。
「コイツ、怪しげな技を……」
そして、怯んた王国兵の体を下から氷の刃が貫いた。
「ふふふ、さあ、もっと私に死を見せて。あなたたちが苦しむ様を……」
「ば、化け物っ……」
近くにいた王国兵は、踵を返して逃げ出す。しかし、氷の刃はそれを追い、次々と串刺しにした。
体から流れる血が氷を赤く染め、辺りを血臭で満たした。
「女、貴様が指揮官か」
動く者が誰もいなくなった甲板に、一人の男が現れた。
「あなたは誰?」
「グリュンワルド・ロンズブラウ」
「そう……あなたがあの」
グリュンワルド・ロンズブラウ。
ルビオナ連合王国と同盟を組むロンズブラウ王国の王子である。
その狂気じみた戦い方は、敵味方の双方によく知られていた。
激戦の後を示すように、マントと鎧は返り血にまみれ、右手の剣は先が欠けていた。
「その命、もらい受ける」
そう言うと、グリュンワルドはベリンダへと突進する。
そのまま剣を振りかぶり、力に任せて振り下ろした。
ギィン
その剣をベリンダが生み出した氷の盾がかろうじて止める。しかし、刃はベリンダの左肩をわずかに傷つけていた。
「……くっ!」
グリュンワルドは密着した状態のまま連続して剣を振るう。剣戟の早さは、もはや人間の領域を越えていた。
ベリンダも良く防いだが、反撃に転じる事ができず、ジリジリと押されてしまった。
やがてベリンダは、甲板の舳先へとはじき飛ばされた。
「もう逃げ場はない」
グリュンワルドが腰を屈め、剣を水平に構える。
その構えには一分の隙もなく、ベリンダは蛇に睨まれたカエルの様に、動くことができなかった。
「……死ね」
グリュンワルドの体が霞み、次の瞬間にはベリンダの目前に出現する。
ベリンダが反応する間もなく、その刃はベリンダの体を貫いた。
「ぐっ……」
ベリンダは自分の腹に突き立った剣を凝視する。
これまで数多く見てきた死が、今度は自分を襲っている。
「……私は、まだ」
「まだ息があるか」
グリュンワルドはそう呟くと、無造作に剣を引き抜いた。
その感触には違和感がある。
「貴様……いや、言うまい。死ねば皆同じだ」
そして、剣を振りかぶった。
……まだ死ねない。私が死ぬ前に、もっと多くの死を。
もっと多くの者を死に追い遣るのだ。そのために何が必要か。死の力だ。
剣を振りかぶったグリュンワルドの背後で、ピチャリと音がした。
若干の粘りを含んだその水音は、聞く者に生理的な嫌悪感をもたらした。
「……っ」
振り返ったグリュンワルドが眉を顰める。そこには、あるべきではない光景があった。
首は半分ちぎれ、腕も片方無い帝国兵。足の腱も切れているらしく、立っているだけで揺れていた。
その向こうには、同じように片腕のない王国兵。その隣には、胸に大きな穴を開けた王国兵。
焼け焦げてどちらの兵か分からぬ兵士。
すでに死んだはずの兵士が立ち上がり、フラフラとグリュンワルドへ向かって歩いた。
「貴様、何をした。女」
「……死を。あなたも私に死を見せてくれるんでしょう?」
甲板に体を横たえたまま、ベリンダは微笑んだ。
その微笑みは、いつものベリンダと同じく柔らかく、かわいらしい。
しかし、その目だけが光を失い、ユラユラと蠢く死者の軍勢を映していた。
「―了―」
3394年 「彼岸」 
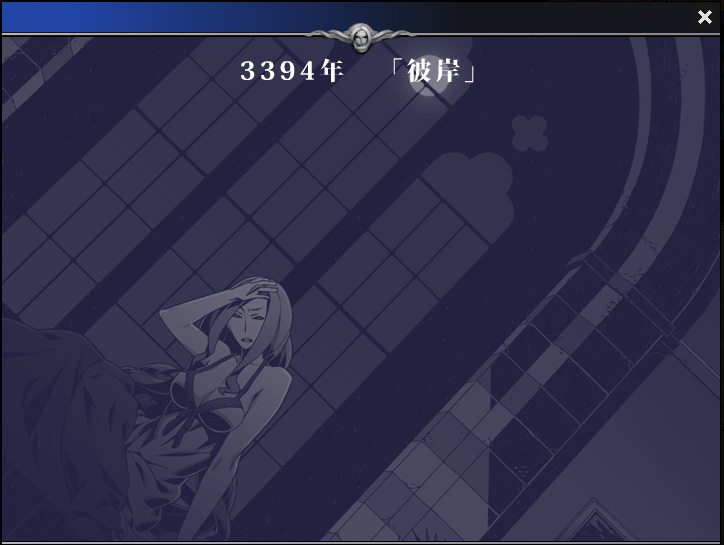
ベリンダは跪き、自分の腹部からはみ出た臓腑を手で押し込めていた。
そして、そうしていてもなお、ベリンダの口元には笑みが浮かんでいた。
爆音と共に、ベリンダを傷付けたグリュンワルドは死者達もろとも吹き飛ばされた。
ベリンダの足下には、黒く焼け焦げたグリュンワルドの右腕が転がっている。
その腕を拾い上げてゆっくりと立ち上がる。ベリンダの笑いが大きくなった。
「くっくっくっく」
自分の腹を抉ったこの腕はもう二度と動くことはない。全く愉快な光景だった。
この酸鼻極まる戦場が、彼女にはとても滑稽で愉悦に満ちたものに写っている。
「かわいそうな王子様。こんな風にバラバラになってしまったら、私のために働いてはくれなさそうね」
そう言って、グリュンワルドのものだった手の甲に口づけをすると、甲板からその腕を投げ捨てた。
落ちたガレオンの周りでは、王国兵達が勢いを取り戻そうとしていた。
地上から五アルレ程ある甲板に梯子を掛け、新手が登ってくるのが見えた。
「まだまだ楽しめそうね」
ベリンダは自分の身体の中に生じる汚れた世界の扉を再び開いた。
瘴気が漏れ出し、死者達にまとわりつくように伸びていく。
そして瘴気を浴びた死者達は身体を震わせ、ゆっくりと立ち上がり始めた。
死が死を生み出す悪夢の始まりだった。
甲板に登ってきた王国兵達は死者の軍勢に立ち向かおうとしたが、恐れも疲れも感じない『歩く死』に次々と飲み込まれていった。
「さあ、私のためにたくさんの死を運んできてちょうだい」
今度は死者の軍勢が甲板を降り、眼下の王国兵達を襲い始めた。
増えていく死者の軍勢は王国軍を圧倒する。
しかし同時に、戦線を接する帝國兵にも死者は襲い掛かっていた。
「かわいそうな人間達。はやく楽にしてあげなさい」
雲霞のごとく増えた死者は、見境なく生者を貪り喰った。
前線は崩壊し、トレイド永久要塞は死者対生者の戦いで大混乱に陥った。
甲板の端に立っていたベリンダは、眼下に広がる陰惨な光景を笑いながら眺めていた。
とその時、一瞬目の前が暗くなった。
体液を失いすぎたのか、知覚が混乱して立っていることができなくなり、欄干を背にして体重を預けた。
「こんな傷で…、もっと死を…」
意識が遠のきかける。目の端に小銃を構えた一団が上がってくるのが見えた。
銃口をこちらに向けながら近付いてくる。
「あなたたちも……死者になりたいのね。まってなさい…」
ベリンダは絞り出すように、ぼやけた視界に映る一団に声を掛ける。
しかし力が抜け、ずるずると腰を落としてしまった。
それと同時に、小銃の斉射がベリンダの身体を捉えた。
ゆっくりと倒れたベリンダに近付いてきたのは、帝國兵士の決死隊だった。
「機能停止を確認」
「とどめを刺しておいた方がよくないか、大尉?とんだ化け物だぜ、こいつは」
眼帯を着けた帝國兵士が、傍らの隊長に声を掛ける。
「いや、いい。 シドール将軍はこの玩具がお気に入りだ。処分は我々の仕事じゃない」
端正な顔立ちの若い将校は伝令を呼び、シドールの元へと行かせた。
シドール将軍は宮廷会議で窮地に立たされていた。
難攻不落の永久要塞をついに粉砕したが、帝國軍の被害も甚大だった。
しかもその被害の殆どがシドールの手引きで帝國に迎え入れたガレオン強襲部隊の暴走によるものだったからだ。
「これがガレオンの力というわけですな、将軍。まったく結構な結果だ」
カンドゥン長官が将軍に、これ見よがしに当てつけを言う。
「勝利に犠牲はつきものだ」
シドール将軍は苦々しい顔つきで言った。
「この犠牲は一体何のために必要だったのか、経過を説明してもらわんといかんな。まさか生き残りの将兵達の言うような、死者が蘇って敵味方関係なく共食いを始めた、などという荒唐無稽な話ではなく、だ」
他の統制派の大臣も糾弾に加わる。
「兵に罪はない。おそらくは会戦の中で敵が使用した、幻覚剤を用いた砲弾の効果だ」
「遺体の損傷は将校の証言と一致するが、それも幻覚剤を用いた兵器のせいだと?」
「奴ら王国は我々に勝てぬと知って、自暴自棄な作戦に出たのだ。犠牲は確かにあったが、それは我々の責任ではない。非人道的な行為に出た王国こそが問題なのだ」
シドール将軍は何が起こったのかを仔細に承知していた。
しかし、それを認めれば自分の地位が無くなることも、また承知していた。
「王国は、こちらが死者を使って要塞を落とした、と非難しているが」
「馬鹿げた濡れ衣だ。我々を冒涜するための流言だ。私は自分の兵を我が子のように思っている。そんな事が行われるはずがない」
会議に沈黙が流れる。要塞の攻略に成功したのは事実だ。
表向き英雄となったシドール将軍を処分するのは、民意を挫くことになる。
「とにかく、あの忌まわしいガレオンを再び使うことはないな、シドール将軍」
「もともと要塞攻略の兵器に過ぎぬ。もう用済みだ」
シドールにも今回の結果は予想外だった。
行われた出来事は、彼にとっても許し難い行為だったのだ。
「将軍、あなたの働きは認めています。しかし、永遠に戦争を続けるわけにはいかないのです。今後は我々と協力して事に当たるべきだ。 互いに帝國の未来を信じる気持ちは同じなのですから」
カンドゥン長官は丁寧な言葉で将軍を諌めた。
慇懃な長官の態度にシドールは心底怒りを感じていたが、それを押し殺して席を立った。
……痛い、痛いよ。
……誰か、誰か助けて。
……私は、こんなに痛いのに。
……私は、こんなに苦しいのに。
どうして、みんなは笑っているの?
どうして、私はみんなと笑えないの?
どうして、私、だけ、死ぬの?
そんなのおかしい。
私が死んで、みんなが笑っているのは。
私がいなくなったのに、みんながそこにいるのは。
次は、みんなが死ねばいい。
次は、私が笑えばいい。
死んだみんなを見て、私が笑う。
ベリンダはベッドから跳ね起きた。
辺りはまだ暗い。窓から薄明るい月の光が差し込んで、ベリンダの胸元を照らしている。
「今のは……」
脳裏に浮かんでいたのは、ベッドに横になっている自分とそれを取り囲む人々。
そして、隣で自分の手を握ってくれている男性。
ただ、そのどれもがベリンダの記憶には無いものだった。
しかし、胸に宿る死への恐怖と周りへの憎しみはとても夢で見ただけとは思えない程激しいものだった。
ベッドから降りようとすると、一人の少女が部屋に入ってきた。
「目覚めたようだな。もう一度仕事をしてもらうことになった」
「―了―」
3398年 「復活」 
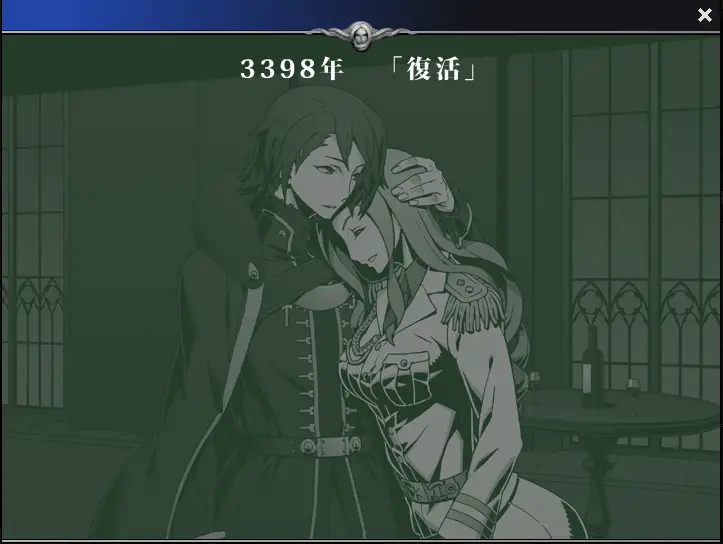
「レッドグレイヴ様……」
部屋に入ってきた少女は、ベリンダの真の主人、レッドグレイヴだった。
「戦いにお前が必要になったので、再起動した」
レッドグレイヴはそう言いながら、ベリンダの傍に立った。
「シドール将軍は?私は戦場で……」
そう、私は死を運ぶ不吉な悪夢。生者を憎み、呪っている。
「お前は機能停止していたのだ。あれから、千二百四十六万五千五百五十二秒が経過している。それと、シドールも死んだ」
「ああ、人は死ぬんだった。かならず」
俯き、虚ろな調子でベリンダは呟いた。
「新しい戦場がある。そこに行ってもらう」
レッドグレイヴはベリンダの様子を気にも掛けずに言った。両手は羽織ったコートに入れたままだ。
「たくさん殺せます?」
顔を上げ、きらきらとした少女のような笑顔でレッドグレイヴに聞いた。
「それが仕事だ」
「よかった。すぐに用意しないと」
「帝國の状況は変化した。その辺りはお前の目で直に確認するがいい」
レッドグレイヴはそう言って部屋から去った。
そして、取り残されたベリンダの元に医療エンジニアがやって来た。
「最も強く美しい将軍のご帰還だ」
マルセウスがローブのまま、ベリンダと彼女を連れてきたエンジニアを皇帝廟に迎え入れた。
周りにはマスクを着けたカストードが四人立っている。
「陛下のお導きで帰ってくることができました。何なりとお申し付けください」
膝を突き、ベリンダは頭を垂れた。
「面を上げよ、ベリンダ。そなたを待っていたのだ。我々が眠っている間、帝國を守ってくれたのだろう」
皇帝は手を差し伸べ、ベリンダを立たせた。
「向こうで晩餐の用意がある。カストードに案内させよう。話を聞かせてもらいたい」
初めて見る皇帝の姿は、まるで少年とも少女ともつかない痩身の人物だった。ガラスのように白い肌が、黒い長髪と赤い瞳を際立たせていた。
「わかりました」
カストードに案内され、ベリンダは皇宮の奥へと進んでいった。
残されたエンジニアが皇帝へ話し掛ける。
「マルセウスよ、レッドグレイヴ様は監視者だ。忘れるな」
フードを目深に被っているが、このエンジニアの眼光は鋭い。
「忘れるものか。だが、我々には我々のやり方がある。地上でただ一つの帝國の流儀だ」
「地上の流儀などどうでもいい。目的さえ達せられるのならな」
エンジニアはその機械でできた拳を強く握った。キシキシと音が鳴っている。
「貴様らエンジニアは無粋なのだ。世界は快楽のためにある。我々は世界に奉仕などはせぬ、世界に奉仕させるのだ」
両手を広げて笑顔のまま、マルセウスは語った。
「そうだ。サルガド、貴公も一緒に晩餐を楽しむかね?」
マルセウスの誘いを無視して、サルガドは踵を返して言った。
「接岸の時は近い。協定は守ってもらうぞ」
「依存は無い。レッドグレイヴにもそう言っておくがいい」
去って行くサルガドの背中に、マルセウスは言葉を投げつけた。
「傑作だ、まったく。是非この目で見ておくべきだった」
陰惨なトレイド攻略戦の状況を聞きながらマルセウスは言った。手に持ったワインを呷った。
「血と臓腑の臭い、とても懐かしいですわ。またそこに戻れるなんて、とても楽しみです」
晩餐の後、ベリンダはマルセウスの居室に二人きりでいた。
赤と黒の色調で染め抜かれ、奢侈(しゃし)を極めた巨大な居室は、永久皇帝としての威光を示している。
「兵力は用意させる。そなたの働き、是非とも見せてくれ」
「はい」
ベリンダの前にマルセウスが立った。不思議な香りがベリンダの鼻腔に届いた。
「死は好きか?」
ベリンダを立たせて、マルセウスは彼女を腕で包んだ。
「はい」
ベリンダは頭を彼の肩にあてるようにして目を瞑った。
「怖くはないか?」
マルセウスはベリンダの髪を撫でた。
「ええ、なにも。楽しみなだけです」
マルセウスの声色と匂い、そして暖かさに、何故かベリンダは懐かしい気持ちになった。
「夢を見たろう?」
「はい。でも、なぜそれを……」
囁くようなマルセウスの不可思議な問いに、ベリンダは戸惑い、顔を上げた。
「己をもっと知りたくはないか?」
マルセウスはベリンダの瞳を見つめている。
「夢は事実だ。それはそなたの過去の記憶、本当のそなたの一部分だ」
「本当の自分?」
「所詮、エンジニア共はそなたを道具としてしか見ていない。我々は違う」
「私は戦いと死さえあれば……」
戸惑うような表情を見せたベリンダを、マルセウスはもう一度強く抱いた。
「我々ならば、そなたの記憶を全て蘇らせることができる。本当の自分に戻るのだ」
ベリンダは目を閉じ、マルセウスに身体を預けた。
ベリンダの前に新しいガレオンに搭乗する兵員が並んでいる。
出撃前の閲兵であった。
ベリンダの前に居並ぶ兵は奇妙だった。訓練された均一な兵士ではない。老兵や、極端に若い者、明らかに負傷の癒えていない者さえ見受けられた。
確かに、長引く戦乱によって帝國の兵士は慢性的に不足していた。が、例えそうであっても、このような廃兵が戦場に派遣される事などはあり得ない。
言うなれば、この兵達は肉でできた兵器だった。ただ歩ければよかったのだ。戦場に着けば、すぐに歩く死者となる。それでよかったのだ。
生者のうちに船に詰め込まれ、前線で彷徨う死者として開放される。その運命を知っているのか、兵士達の顔は一様に絶望に満ちた表情だった。
居並ぶ兵士達の周りを、銃を持った兵が見張っている。
壇上に上がったベリンダは優しい笑顔を兵士達に向けた。そして、兵に向かって声を掛けた。
「死を恐れる必要はありません。皆、死ぬのです。例外はありません。喜びも悲しみも、全て暗い闇へと戻るのです。安心なさい、全て元に戻るだけなのです」
ベリンダの言葉が終わった時、兵団の後ろで呻き声とも叫び声ともつかない言葉を発しながら列から飛び出した兵がいた。
素早く周りの警備兵が、その痩せた若い男を射殺した。
「たくさんの死が必要です。そして、それは我々が用意するのです」
ベリンダは微笑みを絶やさぬままそう言って、壇上から降りた。
出撃前のガレオンに、彼らは無言のまま積み込まれていった。
その姿を眺め続けているベリンダの表情は、笑顔のままだった。
「―了―」
3398年 「ネクロポリス」 
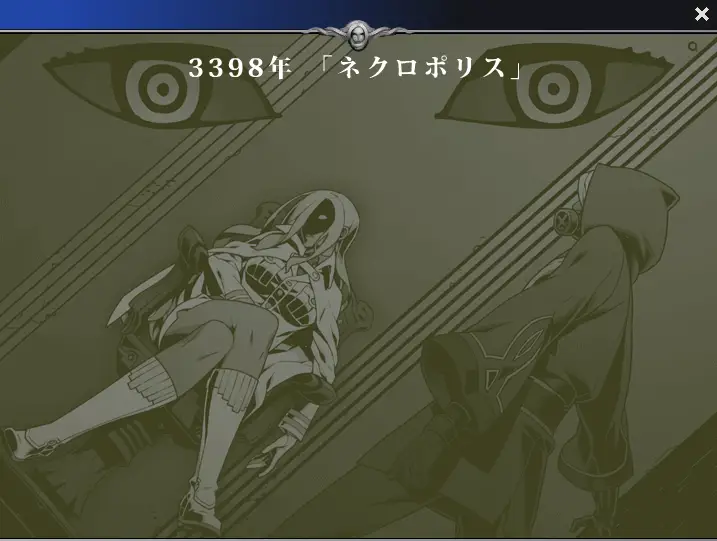
ガレオンは轟音と共に戦場の前線へと到着した。
東方の城塞都市プロヴィデンスは膠着状態に陥っていた。交易都市として栄えたこの街も、今は長く続く戦闘で荒廃していた。
帝國と王国は中央通りを挟んで互いに北部、南部地域を支配下に置き、散発的な戦闘を続けていた。
王国の装甲兵は市街戦に強く、帝國は物量でそれに対抗していた。皇帝は状況打開のために、この地にベリンダを派遣したのだった。
「さあ、私の『死』を放つのです」
ガレオンは中央通りの広場に着くと、ベリンダの号令でハッチを開いた。
先程まで生きていた死者の軍勢が放たれた。望まずに連れてこられ、放たれる直前に殺された者達の顔は、苦痛と怨嗟によって強く歪んでいる。
彼ら彷徨い歩く屍は、邪悪な瘴気を放ちながら次々とその眷属を増やしていった。
屍は正邪の区別をしなかった。王国兵も、隠れ住んでいた市井の人々も、皆、次々に死者と化した。
散発的な銃撃音と砲撃音が市街に響いていた。
「ベリンダ様、どうやら王国兵の殲滅が完了したようです。我々の勝利です。こちらの損害は一兵もおりません」
副官がブリッジにいるベリンダに報告した。斥候が街の様子を確認し終えたのだ。この副官は最初に使った自軍の死者達を損害に入れなかった。
「つきましては、死者達の停止と回収をお願いします」
副官が丁重に言葉を重ねる。
この副官には、ベリンダに暴走の危険があることが知らされていた。
廃兵を利用したこの邪悪な作戦は皇帝直々の作戦故に実行されているが、実際の将兵達は恐れ、忌み嫌っていた。
落ちかけた太陽の光がガレオンのブリッジを眩しく照らしていた。
奇妙な沈黙の間があった。
「そうだったわね。帰りましょう」
ベリンダは微笑みながらそう言った。
もしもの時のために、副官にはベリンダの緊急停止装置が渡されていた。
そして彼女が暴走したときは、迷わずそれを押すことも義務付けられていた。
副官はほっとした様子を見せた。
「死者を回収します。ハッチを開けなさい」
ベリンダの命令でハッチが開いた。
蹌踉めいた足取りで死者達が集まってくる。
「可愛い死者たち。よく頑張ったわね」
蠢く死者達を自愛に満ちた眼で見つめるベリンダの横顔は美しく、副官は思わず見とれてしまった。
「でも、まだ死が足りない……もっと必要だわ」
副官はその言葉をはっきりと耳にした。先程の邪悪な美しさとその言葉の意味が、狂気に由来しているものだと副官は悟った。
この女将軍を止めなければならない。
そう思ってポケットの停止装置に手を伸ばしたが、スイッチを入れる指に力が入らなかった。
副官は恐怖した。
「ねえ、気付いていないようだけど」
「あなたは死んでいるのよ。もう」
副官は慌てて周りを見てみる。ブリッジにいた兵達の眼は窪み、光を失い、力なく佇んでいた。
「馬鹿な……」
指を顔に当ててみるが、一切の感触がない。痺れたように指先は動かせず、肌の暖かさも感じることができなかった。
「あ、あ、あ……」
声を出そうとするが、意志が喉に伝わらない。意識も混濁を始めていた。
ベリンダの力は暴走を始めていた。生きている人間を直接死者へと変えていく能力までも有するようになっていた。
「生きている人間なんて大嫌い……ここは死者だけの国にするの」
幾万の死が都市を覆い尽くしていた。
今や帝國と王国の兵も、市民もいなかった。いるのは死者だけだった。
何度か両国の部隊が迫ったが、死者の軍勢に無残に飲み込まれた。
「皇帝陛下、ベリンダの暴走、如何なさいますか?」
玉座に座ったマルセウスのもとに将官達が集まっていた。
「放っておけ」
興味なさげにマルセウスは言った。
「少なくとも、王国側もあの街には近付けん。我々の軍を立て直してから攻勢に出る」
「ですが……」
「王国には、死の街は我々が掌握していると思わせておく。それだけで奴等は無残に消耗し続ける」
「成る程」
「こちらには間者もいる。上手くあの厄災を利用させてもらう」
ベリンダの暴走は、マルセウスからの報告がなくともエンジニア達は把握していた。
主任研究者のタイレルは問題無いと言い続けていたが、レッドグレイヴはその説明を求めるために呼びつけた。
「タイレル、ベリンダの暴走はこちらでコントロール可能であろうな」
「もちろんです」
若いエンジニアが答えた。
「彼女の力さえあれば、地上を再び我々の支配下に置くことが可能です」
「ふん、ただし死者だらけの国だろう」
レッドグレイヴの側近であるサルガドが口を挟んだ。
「恐怖が伴わなければ人は従いません。帝國にも王国にも、死者の軍勢に逆らうことはできないと知らしめれられればいいのです」
タイレルはサルガドに微笑みながら答えた。邪気のない様子が、却って研究への信念を感じさせた。
「我々エンジニアは傲りによって一度滅びかけた。今度はそうなるまいと決めている」
タイレルからはコンソールの並ぶ部屋の中心に座るレッドグレイヴの表情は読み取れなかった。声だけが中央管理室に響き渡っていた。
「よく理解しております。しかし、力なき知に意味はありません」
「わかっておる」
「生と死は隣り合っています。そして通常の現実では、互いに交わることはありません」
タイレルは優秀なエンジニアらしく、自身に満ちた調子で、己の見識を臆することなく語っている。
「しかし、ベリンダが作り出す『新しい現実』はその世界を曖昧にします」
「『新しい現実』か。昔、似たような話を余も聞かされた」
「黄金時代のですか?」
「そうだ。渦を作った男だ」
「お褒めの言葉と受け取ってよろしいでしょうか」
「それはこれからのお前の働き如何だ」
「必ずご期待に添えますよう、努力いたします」
タイレルがそう言って部屋から辞去すると、レッドグレイヴにサルガドが言った。
「どうなさいますか?」
「余は制御できぬものは許さぬ。どんなに力があろうとな」
「ベリンダのもとにタイレルを連れて行け。回収させろ」
「承知しました」
「ベリンダの様子がおかしければ、すぐに破壊しろ」
「はい」
飛行艇がプロヴィデンスの上空を舞っていた。
「まさしく地獄だ。それも極めて醜悪な」
サルガドが呟くように言った。プロヴィデンスは半年近く人を寄せ付けぬ死の街と化していた。戦争とその後に続く死者達による騒乱で、地上波荒れ果てていた。その荒れ果てた地上を幽鬼のように腐った死体達が蠢いている。
「たった一人、たった一体の力で街を征服したのです。すばらしい威力だ」
タイレルは全く悪びれる様子もなく、誇らしげに言った。
「ふん、私には塵芥が腐った死体に換わったようにしか見えん」
「研究への興味が貴方とは違うようですね」
サルガドの操る飛行艇は、ベリンダの反応があるガレオンになるべく近い場所を探して着陸した。死者達の多い大通りを避けて、小さい教会近くの広場に降り立った。
「急げ、奴等に集まられると面倒なことになる」
「わかっています」
二人はマスク越しに無線で会話をしていた。ベリンダの瘴気対策だ。
飛行艇はほとんど音を出さないが、それでも何人かの死者がこちらを見つけて迫ってきていた。
二人は走ってガレオンの元へ向かった。
大通りは空から見るよりずっと荒廃していた。至る所に死体が散らばっている。
そしてそれは、二人が近付くと起き上がって襲い掛かってきた。
サルガドは義手からワイヤーを引き出して死体を一凪した。上下ばらばらになった死体が地面に転がる。
しかしまだ、蠢きながらこちらに敵意を向けてくる。
「これではきりが無い」
「すばらしい!ここまで損壊してもまだ機能するなんて」
死体の様子に気を取られたタイレルの傍に死者達が迫っていた。
「タイレル!」
タイレルはサルガドの声に振り返ると同時に、腰元から電流を帯びたボールを取り出して自分の周りに浮遊させた。
その球状物体はタイレルに近付く死者達を一瞬で炭化させた。
「ええ、いま行きますよ。そんなに焦る必要がありますか?」
事も無げにタイレルは言った。次々と連鎖するように、タイレルの後ろで死者達が青い炎に包まれていった。
二人は死者達を薙ぎ倒しながらガレオンの元に辿り着いた。開いたままのハッチから中に入る。
船内は静かだった。動くものは一人もいなかった。通路には生者と死者が相争ったらしい血痕が残っている。
「ベリンダの反応は?」
「上です。おそらくブリッジでしょう」
ブリッジへ向かって、二人は慎重に歩を進めた。
階段を上がり、ハッチを通り、ブリッジに近づいていく。
「すごい瘴気の濃度です。絶対にマスクを外さないでください」
タイレルの忠告にサルガドは頷いた。船内に死者はいなかった。静かな船内で、動く者はタイレルとサルガドの二人だけだった。
ブリッジの扉に二人は辿り着いた。
タイレルがブリッジに入ろうとするのを、サルガドは止めようとする。
「心配はありません。ベリンダには私に対する制御回路を組み込んであります」
ブリッジにはタイレルを先頭にして入っていった。
ベリンダは船長席に座っているようだった。
「ベリンダ。私です。よくやりました」
そう言いながらタイレルはベリンダの前に出た。
「これは……」
タイレルは驚きの言葉を漏らした。サルガドもベリンダの様子を確認しようと前に立った。
ベリンダは座したまま死に、機能を停止していた。
かつての美しい容貌はどこにも無く、顔から皮膚が剥がれ落ち、醜い内部が露出していた。首は傾き、力なく項垂れている。
「いつからこうなっていたんだ?」
「人工皮膚の劣化程度から見て、作戦初期でしょう。しかし何故……」
タイレルが項垂れたベリンダの頭部に触れようとすると、前のめりにベリンダは倒れ込んだ。いや、腐った肉を纏った人形が四肢を唸らせ、床へと倒れ込んだ。
「何故機能を停止したのに瘴気が収まらんのだ?」
サルガドが問う。
「わかりません。しかし、ひょっとすると……」
「早く瘴気を止めろ!」
「ここから離れてください、サルガド。私は残ります」
「なにを馬鹿な……」
「彼女は今や『死』そのものになりました」
そう言うと、ベリンダだった人形から光る何かが立ち上がってくるのが、サルガドに見えた。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ