ベルンハルト
【死因】不明(発狂)
【関連キャラ】フリードリヒ(双子)、エヴァリスト(弟子)、アーチボルト、ミリアン、エプシロン
3381年 「渦」 
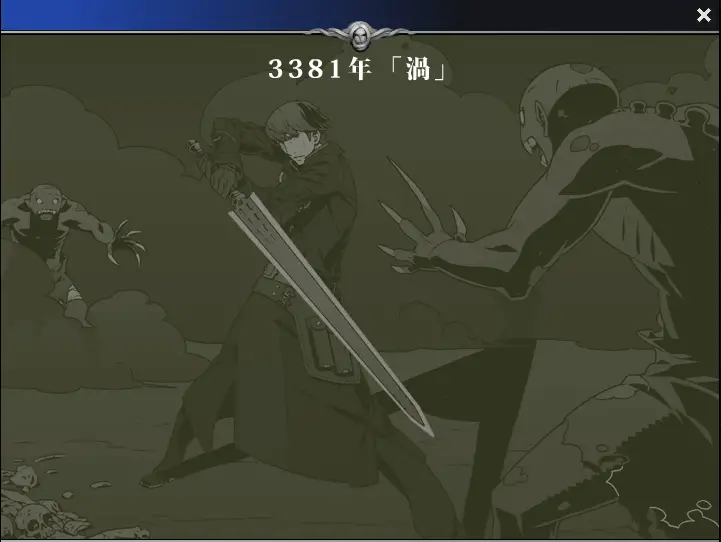
「補充は無しか?」
「そうだ。 装備が整っていない」
ベルンハルトはD中隊の長、ミリアンに問い質した。
「エンジニアの分析班は、今度の作戦にはお前の小隊で十分だと言っている」
ミリアンは渦を表すモニターから目を離さず答えた。
「お決まりの『損耗率は許容範囲』というやつか」
「そうだな」
「彼奴らの判断が常に正しければ、俺達はこんなところで命を賭けてない」
「そう当たるな、悪いが決定事項だ。作戦室はお前の小隊を信頼している」
「信頼しているならもう少し態度で示すよう、エンジニア達に言っておいてくれ」
ベルンハルトは最後にそう言って、中隊長の部屋から出た。
向こう側は闇だった。コルベットのヘッドライトが照らす部分以外は完全な闇。
コルベットの駆動音以外は何も聞こえない。
渦<<プロフォンド>>の中心部へ突入したのは陽も眩しい昼時だった。
こちら側とあちら側で時間の異なる事など珍しくはなかったが、空に見える星は一つも無く、
まるで一切の光が存在していない世界のようだった。
それでも引き返す訳にはいかない。
互いの世界を繋ぐ鍵を破壊しなければ、元の世界に歓迎されざる様々な異形が訪れ続けるからだ。
中には話の通じる友好的な異界生物が居ると考える者も居るが、
ベルンハルトはそのようなものに遭遇した事が一度も無かった。
代わり映えのしない視界に変化があった。
ベルンハルトはコルベットの操縦手であるメルコルに小声で静止を命じた。
「止まれ」
静止したコルベットのライトが照らし出したものは白骨の山だった。
大小様々で多様な部位の骨が、そこに積み重なっていた。
メルコルを残し、ベルンハルト率いる小隊は地表へ降りた。幸か不幸か、周囲に何かが居る気配は無い。
「どう思う」
ベルンハルトは白骨の山の前にしゃがみ込むと
骨の一つを掴み、それをしげしげと眺めながら傍にいた隊員に見解を問う。
「見た事の無い骨格も多いですが、人間と思わしき骨もあります。
恐らくは渦<<プロフォンド>>の発生時に巻き込まれたオールブルグの住民達でしょう」
「同意見だ」
悼ましい事ではあったが、オールブルグの住民達が生き延びていないであろう事は分かっていた。
こうして死を確認できた事は、むしろ幸運とも言える。気休め程度でしかないが小隊全員で黙祷を捧げた。
問題はこの場所に骨を集めたのは何者かという点だった。
ベルンハルトは未だ姿を見せぬ捕食者の体躯や習性を想像した。
ベルンハルトがコルベットへの引き揚げ命令を出そうとした時、敵襲を知らせる無線が響いた。
「三時の方向、襲撃!」
襲撃地点へ駆け付けようとするが、それは新たに現れた異形からの攻撃によって阻まれた。
「ぐ…!」
初撃は咄嗟に体を捻って躱し、第二撃は剣を使って受け流す。
武器こそ持っていないが、異形の持つ鋭く長い爪は並の短刀と同等以上の武器であると考えた方が良さそうだった。
攻撃自体はすんでの所で躱せたものの、ベルンハルトの代わりに切り裂かれたコートがそれを物語っていた。
ベルンハルトの前には二体、周囲を見渡すと皆一体から三体の異形と対峙を余儀なくされていた。
奇襲に対処しきれず傷を負い、明らかに分の悪そうな隊員も居た。
奇襲に失敗した為か、警戒を強めた異形達はベルンハルトと距離を取り睨み合う格好となった。
今度はなかなか飛び掛かってくる様子はない。
ゆっくりと間合いを広げると、素早く剣を銃に持ち替え、一体の頭部に狙いを定めて銃弾を撃ちこむ。
命中。紫色の液体を流しながら地面に倒れた。
もう一体に銃口を切り替えようとしたが、脱兎の如く闇の中へ戻ろうとしている最中だった。
他の隊員を襲撃した異形達も形勢不利を悟ったのか、次々と闇の中へ戻っていく。
誰もが奇襲に対応できた訳ではなかった。最初に攻撃を受けたトゥークは初撃を躱しきれずに傷を負った。
かすり傷程度でしかなかったが、異形達にはそれで充分だった。
動揺する事なく敵襲を知らせる無線を発し、目の前の異形と睨み合う。
そこまでは良かった。
再び異形が襲い掛かってきた時、我が身が思うように動かなくなっている事に気付く。
異形の爪は鋭いだけではなかったことに。
受け流すつもりが右腕への直撃を受けてしまい、大きくよろめく。
彼を弱った個体と判断した異形が次々に襲い掛かる。
トゥークにそれを防ぐ手立ては残されていなかった。
レジメント達の反撃を受けて撤退していく中、トゥークを襲った異形達は彼を抱えて闇の中へ去っていく。
後にはトゥークの持っていた剣だけが残された。
「それは確かなんだろうな」
「間違いありません。奴等はトゥークを運んでいきました。
方向は覚えています。今すぐにでも追いましょう」
ベルンハルトが辺りに転がる異形の遺体を検分していると、若い隊員のランモスから報告を受けた。
体毛が無く、大きく開いた眼を持ち、長く伸びた鋭い爪を持つ化け物だった。
ぼろぼろになっている服か布、痛みが激しくどちらなのか判別はできなかったが、
それらを腰巻きにしている個体も見られた。
恐らく奴等の作ったものではなく、犠牲になった人達が身に着けていたものであった事は想像に難くない。
「今は作戦続行が優先だ」
ベルンハルトはランモスの提案を一蹴した。
「ですが」
トゥークと仲の良かったランモスは食い下がり、ベルンハルトを睨みつける。
「命令だ」
ランモスは俯き、拳を握りしめ体を震わせたが、何も言わずにコルベットへ戻っていった。
道中、10体前後の異形達が群がる地点に遭遇した。
掃射を行って奴等を追い払うと、そこにはトゥークの遺体のみが残されていた。
全身の肉を食い千切られており、骨まで見えるような惨状だった。
必死の形相で固まった顔は、最後まで抵抗しようとしていた事が察せられた。
ベルンハルトはランモスに声を掛けるが、彼はベルンハルトの手を払い除けた。
仲間の死が何人目になるのか考えようとしたが、すぐに止めた。
感傷に浸る暇は無い。略式の葬儀を済ませ、一行の探索は続く。
カルデラを思わせる巨大な窪みの中に、この世界の結節点<<ノード>>となるケイオシウムがあった。
光の無い世界で常に様々な色に変化し続ける、あの輝きは見間違えようがない。
ケイオシウムを中心に、周囲にはあの異形達が何重もの輪になっている。
どうやらここでもケイオシウムは特別扱いされているらしい。そっと奪うという訳にはいかないようだった。
端から攻めるにはこの場所は広く、異形の数は多すぎ、そして味方の数が少なすぎた。
協議の結果、上空より中心部に降下し、ケイオシウムの回収成功後にすぐさま離脱する事になった。
ベルンハルトは愛用のセプターを手に取り、これまでの戦いに思いを馳せる。
兄弟で入隊し、今も共に生き延びているのは奇跡のようなものだ、と言われた事もあった。
これ以上仲間の死を見るのは御免だった。
大きく深呼吸を行い覚悟を決めた。
降下命令を下すと真っ先に自分が飛び降りた。
「-了-」
3386年 「過去」 
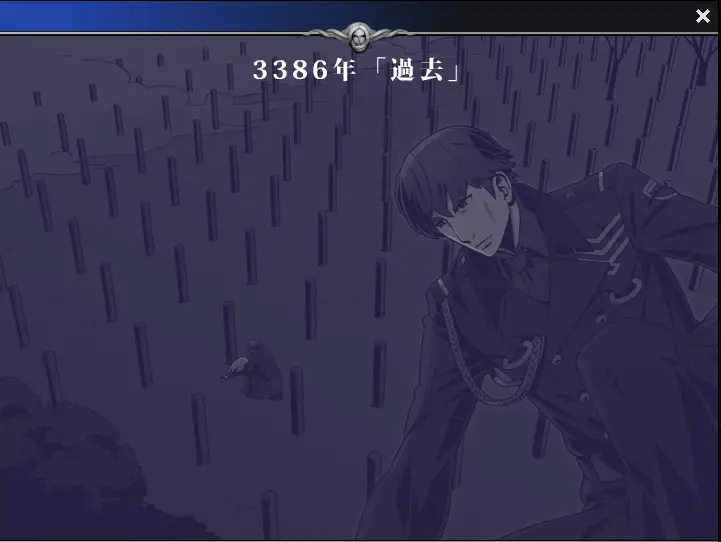
霧が出ていた。
ようやく夜の闇が薄れかかってきたが、太陽は未だ昇っていない。
立ちこめる霧で遠くを見通すことはできない。ベルンハルトはその霧の中に立っていた。
周りには膝丈ほどのモニュメントが無数に立っている。そのひとつひとつに名前が彫られていた。
ここは、渦における戦いで命を落としたレジメントの戦士達が眠る霊園だ。
渦内における激戦の中において、命を落とした戦士の体を持ち帰ることは殆ど不可能であった。
そのため、ここにあるのはただの墓標である。
それでも、生き残った者が先に旅立った者を悼む場所は必要だった。
ベルンハルトは一つの墓の前で腰を屈めると、その前にそっと花を置いた。
しばらく黙祷すると、視線を墓標に落としたまま鋭い声を発した。
「姿を現したらどうだ」
一人の訓練生が現れた。
「すみません。お邪魔をしてはいけないと思ったので」
「こんな時間に何をしていた?」
「すこし早くに目が覚めたもので。本当にお邪魔するつもりはありませんでした」
「別に責めてるわけじゃない。このあたりは散策にいい場所だしな」
「静かな場所です」
「ああ、ここでなら安らかに眠れる」
墓標に書かれた没年をエヴァリストが確認する。
3377~ ~クラウス・ローデ~。
「どんな方だったのですか?」
エヴァリストがそう水を向けると、ベルンハルトはもう一度墓碑銘を見つめた。
「俺を導いてくれた人だ」
「くっ……!」
背後にあるコアを守りながら、襲い来る巨大な虫を剣で叩き落とした。
ライフルの弾は尽き、もはや手元にある武器は一振りの剣のみ。
肩口からは真っ赤な血が止めどなく流れ、視界は霞んでいた。
ベルンハルトは、数人の仲間と共に部隊の斥候として渦に侵入した。
これといった敵が出現することもなく、うねった坑道状の構造物の最奥にあるコアに辿り着き、確保したまでは良かった。
が、直後に巨大な虫の群れに襲撃を受けた。
一体一体の虫はたいしたことがなかったのだが、あまりにも数が多く、
若い部隊員は一人、また一人とその数を減らしていった。
ついに立って戦っているのはベルンハルトのみとなった。
(ここで死ぬのか……)
緊張と興奮が途切れ、一瞬諦念がよぎった。
しかしベルンハルトは、もう一度コアを守るために自身を奮い立たせた。
もうすぐ本隊が駆け付けてくるはずだった。
ベルンハルトがコアを確保していれば、回収は容易になるだろう。
その時まで何としても力尽きるわけにはいかない。
それからどれ程の虫を潰したことだろう。
ベルンハルトは自らの血と虫の体液にぐっしょりと濡れ、辺りには無数の死骸が転がっていた。
ベルンハルトの体力は限界に達しており、コアを守る、という思いのみで体を動かしている状態だった。
「…………っ、……!」
耳に何かの音が届き、視界の片隅で何かが動く。
半ば意識を失っていたベルンハルトは、本能的に剣を振りかぶった。
ギィン!
振り下ろした剣は、何者かによって受け止められた。
「……ベルンハルト、しっかりしろ!」
視界がクリアになり、見覚えのある男の顔が目に入る。
「……小隊長?」
ベルンハルトの所属する小隊のリーダー、クラウスだった。
「ああ、そうだ。よく頑張ったな」
「コアは…確保しました……」
「ああ、わかっている」
クラウスは崩れ落ちそうになるベルンハルトを支えて、微笑んだ。
「あとは任せろ、コアを回収したら一緒に戻るぞ」
後続の本隊は、迫り来る虫どもを撃退しながらコアの回収作業に入っていた。
緊張の切れたベルンハルトは、コアの回収作業を横目で見ながら物陰に座り込んだ。
簡単な止血のみ行ったが、徐々に自分の体が冷えていくのがわかった。
エンジニアたちが帆走して回収装置が作動する。
自分達の世界との結節点を生み出したケイオシウムの蠢く光が収まり、エンジニア達が持つ収納容器に収められた。
あとはもう、離脱地点まで戻るだけだった。
「おい、終わったぞ。しっかりしろ」
意識を失いかけていたベルンハルトに、クラウスが声を掛ける。
「……置いていってください」
ベルンハルトはクラウスの目をまっすぐに見て言った。しかしクラウスは首を横に振った。
「それは、お前が判断することではない。命令だ。立て、ベルンハルト」
クラウスの肩を借りながら、ベルンハルトは身を起こした。
「この程度の傷で置いていったら、レジメントは誰もいなくなってしまうな。
お前にはまだまだレジメントで働いてもらう。だから連れて行く」
コルベットはコアのあった虫達の『巣』の外にある、そこまでは徒歩で行かなければならない。
クラウスはベルンハルトと共に、少し隊列から遅れてついて行った。
コアを回収した部隊は、より一層激しい攻撃にさらされた。
大小入り乱れた虫の大群が、隊列目掛けて突進してくる。
「もう少しでコルベットだ! 隊列を乱すな!」
クラウスがメンバーを叱咤する。
幸いここまで隊に大きな被害は無く、ベルンハルトも無事についてくることができていた。
「よし、コルベットだ!」
「もうすぐだぞ!」
数え切れないほどの虫を屠り、ついに隊はコルベットの待つ巣の外に出た。
喜ぶメンバーの声に、悲鳴にも似た叫びが被せられた。
「後ろに注意しろ!でかいのが来るぞ!」
振り向くベルンハルトの目に、巨大な甲虫の姿が映る。
その大きさはコルベットの大きさを遙かに凌駕し、体の表面は黒光りする外骨格で覆われていた。
「撃て!コルベットに近寄らせるな!」
クラウスの号令で一斉にライフルの銃弾が甲虫を襲った。
しかし、強固な表皮によって全て弾かれ、傷ひとつ付いた様子がなかった。
「くそっ、化け物め。相手をしても無駄だ!全員コルベットへ避難しろ!」
クラウスがそう命令を発し、隊員達はコアを守りながらコルベットへと向かった。
コルベットを護衛していた部隊も、帰ってくる本隊を援護しながら各自待避を始めた。
この状況で満足に動けないベルンハルトは、明らかに部隊の足手纏いだった。
「俺を……置いて早く戻ってください!このままでは追いつかれます!」
自分に肩を貸し、ゆっくりと歩くクラウスに必死に呼びかける。
事実、部隊が攻撃をゆるめたことにより、膨大な数の虫がコルベットへと殺到していた。
しかしクラウスは頑なだった。
「……それはできん。お前は早すぎる」
そして数人のメンバーを呼び、ベルンハルトの体を預けた。
「こいつを連れて行け。でかいのは俺が引きつける」
巨大甲虫は雄叫びを上げ、コルベットに向かってきていた。
「はっ」
「しかし隊長、時間が……」
コアが収束すれば一定時間で渦は消滅する。
それまでにこの世界から離脱しなければ、二度と元の世界には戻れない。
「わかっている、俺を待つ必要はない。行け」
クラウスはそう言うと、ライフルに新たな弾倉をセットした。
「後は任せたぞ」
最後にそう言うと、ベルンハルトに拳を掲げた。
「……隊長」
驚くベルンハルトは何も言えなかった。
すぐに踵を返すと、クラウスは虫の群れへと突っ込んでいった。
ベルンハルト達は、コルベットへ無事に辿り着いた。
「俺が回収された瞬間、コルベットは離陸した」
話を聞き終えたエヴァリストは、もう一度、物言わぬ墓碑に目をやった。
この下にクラウスの遺体は無い。
「俺達レジメントの戦士はいつか死ぬ。だがそれは渦と引き替えだ」
淡々と語るベルンハルトの頬を、ようやく顔を出した朝日が照らす。
「俺達は何かを得るために生きているんじゃない。 終わらせるためにいるんだ」
エヴァリストは言葉が出てこなかった。
「覚悟が必要だ。もし無ければ、ここから去った方がいい」
「……いいえ、自分にもあります」
「ならいい。いつかお前達に任せられる日が来る」
そう言ってベルンハルトは去った。
朝靄は光を浴びて黄金色に輝きを放っていた。
「-了-」
3387年 「氷河」 
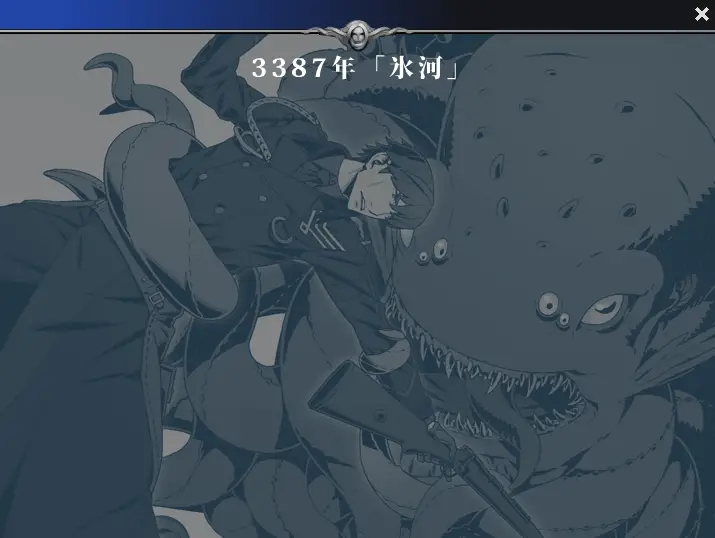
「A中隊の行方は、まだわからないのか」
ミリアンの低い声が静まりかえった部屋に響く。
「はっ。現在もまだ消息が判明しておりません」
「そうか……」
報告を終えた部下が退出すると、ミリアンの顔に微かな憂いが浮かんだ。
そして、傍らに立つベルンハルトの方へ顔を向けた。
「どう思う、ベルンハルト」
「そろそろ限界だろう。これ以上待つと、救援の意味が無くなる」
「そうだな……よし、全員に装備を整えるよう伝えろ。三時間……いや、二時間で出発する」
「了解した」
「A中隊がいるのは寒冷地だったな。それなら防寒装備も必要か」
「問題ないだろう。そんなに長居する訳じゃない」
「そうか、そうだな」
小さく頷くと、ミリアンは立ち上がってベルンハルトの肩にポン、と手を置いた。
「それじゃあ、一応報告に行ってくるか。仲間の救援にも申請が必要とはな」
部屋から出て行くミリアンを見送ると、ベルンハルトも続いて退出した。皆に出撃を伝えるために。
ミリアンの決定から正確に二時間後。D中隊から選抜された救出部隊は《渦》内に突入していた。
本来は温暖な気候の草原であった場所が今では冷たい氷に覆われており、囂々たる吹雪が視界の全てを白く染め上げていた。
過酷な環境にも耐えるコルベットですら、低温と雪により本来のスピードで飛ぶことができない。
メンバーの中には捗らない救出作戦に焦りを隠せない者も出てきたが、
さすがにミリアンやベルンハルトといったベテラン達は落ち着いていた。
「隊長、前方の地表に蛇のような生物を数体確認。コルベットと思われる機体へ攻撃を掛けています!」
《渦》の中に入って一時間程が経過し、ようやく吹雪が少し収まりかけた時、報告が上げられた。
「A中隊の人員は確認できるか?」
「ここからでは人影は見えませんが、時折銃撃と思われる光が確認できます」
怪物は巨大な頭足類のような形をしていた。
巨体から無数の腕が生えており、それぞれが独立した生き物であるかの様に動いている。
そして、その口には大型捕食動物の様な牙が並んでいた。
「急接近して敵性生物を攻撃。A中隊のメンバーを救出する!」
「了解!」
コルベットは急降下し、これまでの鬱憤と焦りを吹き飛ばすかの様な攻撃を仕掛けた。
上空から思わぬ攻撃を受けた怪物は口と腕を引っ込めてずるずると後退した。
そして、そのまま近くにあった沼に体を沈めた。
「よし、着陸しろ。ただし周囲の警戒を怠るなよ」
怪物の体が完全に見えなくなったのを確認し、コルベットは着陸した。
「ミリアン隊長!」
ミリアンがコルベットから降りると、地上で戦っていたA中隊のメンバーが歓声を上げた。
その数約二十人。中隊の三分の一にも満たない。彼らの傍には外装がひしゃげたコルベットと数人の遺体が置かれていた。
「生存者はこれだけか。ヘルムホルツはどこだ」
ミリアンが眉を顰めると、現場を統率していた第二小隊長のヨーナスが敬礼しながら報告した。
「ヘルムホルツ中隊長は最初の会敵時の戦闘で死亡しました。
第四小隊もコルベットごと……」
歴戦の勇士であるヘルムホルツの死は、この渦の脅威を改めてミリアンに認識させた。
「アーチボルト副長の下、第一、第三小隊の計二十二名がコア回収へと向かっております」
「そうか…だが、状況から考えてコアの回収は困難だろう。撤退の準備を始めろ」
そう言ってミリアンがさらに言葉を続けようとした時、ヨーナスがそれを遮った。
「ですが……我々の任務はコアの回収です! このままでは中隊長や仲間の死は……」
「冷静になれ。また機会はやってくる。これ以上、戦力を失うわけにはいかない」
「ですが……」
「安心しろ。アーチボルト達を置いていくようなことはしない」
「………………」
ヨーナスは唇を噛みしめて俯いた。
ベルンハルトはその姿をじっと見ていたが、やがてぼそりと言った。
「俺が行こう」
「ベルンハルト?」
「ミリアン、ヨーナスの言うことにも一理ある。
すでにアーチボルトが先行しているなら、俺達がそれをサポートして回収すればいい」
「ベルンハルト、お前……」
「ミリアン、ここでコルベットを確保していてくれ。回収は俺の部隊でやる」
「わかった。ただし無茶はするな。アーチボルト達の確保が最優先だ」
「……ああ。第一小隊は俺に続け!」
ベルンハルト以下16名のレジメント達は、再び強くなってきた吹雪の中、《渦》の最奥へと進んでいった。
吹雪が白い壁のようになってベルンハルト達の前に立ちはだかる。
地面も空も真っ白で、視界はお互いの体を確認するのが精一杯だ。
もう、引き返すべきか……。
ベルンハルトの脳裏にそんな考えが浮かんだ時、前方から地鳴りのような音が聞こえた。
「敵か!?」
咄嗟に身構えたベルンハルトの前に巨大な黒い影がそびえ立った。
巨体の周りには無数の腕が気味の悪いヌメリを帯びて生えており、グネグネと存在を主張している。
その姿は明らかに通常の生物の範疇を越えていた。
「こいつはコア生物だ……」
「えっ?」
ベルンハルトの呟きを聞いたレジメントが驚きの声を上げる。
「あの化け物の内部にコアがある」
渦の中で出会うコアには様々な形態があり、土地を守る宝珠であったり、動力や魔力の源として奉られ、守られていたりする。
しかし、希に土着の敵性生物の内部に取り込まれている場合があり、その生物との戦闘は非常に熾烈なものになるのが常だった。
「ほ、本当ですか!?」
ベルンハルト以外にこの生物がコアを持っていることを感知できる者はいなかった。
他の人物には無い経験と能力が、ベルンハルトには備わっていた。
「俺がコアを確保する。お前達は援護しろ」
「隊長!?」
そう言い捨てると、ベルンハルトはライフルを構え、単身で敵へと突撃した。
疾走するベルンハルトに次々と牙を剥いた腕が襲い掛かる。
ベルンハルトはそれを斬り割き、あるいはかいくぐって怪物の体へ近付いていった。
「よし、もう少しで……」
怪物の体の中央で黒く光るコアがベルンハルトの目には見える。
コア生物との戦いでは、コアと生物との繋がりを絶つことが鍵となる。
懐に潜り込んでしまえば、コイツを倒すのはそんなに難しい事じゃない。
それは油断と呼ぶには余りにも小さい、気の弛みとも言えない思いだった。
しかし、コアを確認したことで、一瞬だけ目の前の戦闘から意識を逸らしたのは事実だった。
「……ぐっ!」
左足に何かが巻き付いたかと思うと、ぐいっと引かれて体勢を崩した。
慌てて剣を地面に突き刺して堪えるが、そこに何本もの腕が襲い掛かってきた。
「くそっ……」
崩れた体勢のまま何本かの腕を払い除けるが、敵の数は無数だった。一本が胴体に絡みつき、また一本が足を封じる。
あっという間にベルンハルトは絡め取られてしまった。
「隊長!」
遠くで部下達が呼ぶ声がする。ライフルを構えたまま、撃つことを躊躇しているようだ。
「撃て、構うな」
ぬめぬめと蠢く軟体質の腕に締め付けられながら、ベルンハルトは叫んだ。
「早く撃て!」
「し、しかし……それでは」
ベルンハルトの体が持ち上げられ、地面に叩きつけられる。
「……っ!!」
「隊長!!」
「は、早く撃て……」
ベルンハルトは叩きつけられながらも体をよじり、ライフルを構え直した。
そして自らを縛る腕ではなく、敵の本体目がけて弾丸を発射した。
「……ぐぐっ」
ベルンハルトの攻撃を止めようと、腕の締め付けが強まった。
視界が暗くなり、呼吸さえも困難になる。しかし、ベルンハルトの右手はトリガーを引き続けた。
……ここが俺の死に場所か。
やがて弾が尽き、右手から銃が落ちた。それと同調するように、ベルンハルトの意識も無くなろうとしていた。
その瞬間。
空気を切る鋭い音と共に、ベルンハルトを縛る腕に何発もの銃弾が着弾した。
蠢くその触手に正確に命中させる神業を見せたのは、今はA中隊を率いているアーチボルトだった。
腕の力が抜け、ベルンハルトは地上に落とされた。
「大丈夫か、ベルンハルト」
駆け寄ったアーチボルトが話し掛けた。
「アーチボルト、助けるつもりが助けられたな……」
「こいつを追っていたが見失っていたところだった」
ベルンハルトの部隊とアーチボルトの部隊は今や合流して、触手の化け物を追い詰めていた。
「コアの位置、正確にわかるか?」
「ああ、顎の下だ」
「ここで始末をつける。お前はここで休んでいろ」
アーチボルトは戦闘に戻るために立ち上がった。
「なに、まだできる」
ベルンハルトは立ち上がろうとしたが、目眩を起こして再び膝をついた。
「メディック!」自分の小隊付きの衛生兵をアーチボルトは呼びつけた。
「無理するな。兵を借りるぞ、ここで仕留める」
アーチボルトはそう言って、戦いの場に戻っていった。
メディックに介抱されながら、意識に障害を残したベルンハルトの目に敵の巨体が崩れ落ちる様子が映った。
……まだ死ぬときではなかったらしい。
ベルンハルトは奇妙な喪失感を覚えながら、そのまま意識を失った。
「-了-」
3389年 「決戦へ」 
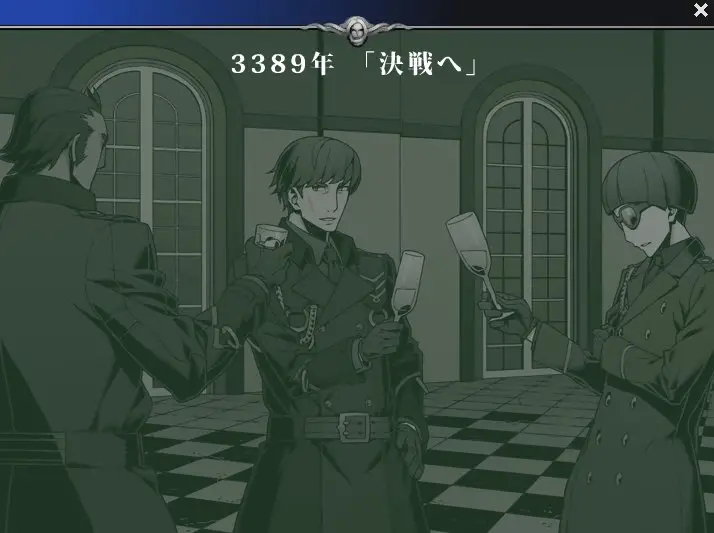
レジメント司令部の定期会議が開かれた後、ミリアンはベルンハルトを自室に呼んだ。
「いよいよ、ということか」
ベルンハルトは壁により掛かったまま話を聞いている。
「そうなる」
ミリアンはソファに座って訥々と語った。片手には酒があった。
「作戦室の説明は、納得できるものなのか?」
「俺達は信じるしかあるまい」
ミリアンは酒を呷った。
「これで全てが終わるという訳か」
ベルンハルトがそう言うと、しばらく沈黙が続いた。
「ジ・アイは混沌を撒き散らす渦の中で、最も巨大な結節点《ノード》ということだ。奴らの計算上、ジ・アイさえ潰せば、他の小さな渦も消えて無くなる……そうだ」
ミリアンが自分に言い聞かせるかのように言う。
「仕組みはいい、俺達は結局戦うことしかできない。確認したいのは作戦成功の見込みの部分だ。二つのコアの同時攻略、しかも正確に同期しなければならないのだろう?」
「静的なシミュレーションは重ねたそうだ」
また酒を飲む。
「机上のシミュレーションで片が付くなら、今までの苦労は無い。作戦が失敗すれば、また振り出しだ」
「E中隊の二の舞か……。レジメントを立て直すのに随分と時間が掛かった」
ミリアンは、数年前に初めてジ・アイに挑み、そして消滅した中隊の名前を挙げた。
「……だが、あの犠牲があったからこそ、今回の作戦を立てることができたとも言える」
ミリアンはそう言い直した。
彼らの死によってレジメントの強化が図られたことも事実だった。E中隊の全滅を機に各中隊は再編成され、入隊期は一年に二回に増えた。
それによって若い隊員達が多く参画するようになった。生き残った古参達は必然的に彼らを率いる形になり、連帯規模も大きくなった。
「次は俺達の番という訳だ」
ベルンハルトは、ミリアンが自分の為に注いだ酒杯をテーブルから取った。
「これを最後にせねばならんな」
「ああ」
ベルンハルトはそう返事をして、酒杯を呷った。
レジメントが『動的シミュレーション』と呼ぶ作戦訓練の休憩中に、フリードリヒが話し掛けてきた。
訓練は野外で行われていたが、休憩時にはコルベット用のハンガーに戻ってきていた。
「全部が終わったあとは、どうする?」
フリードリヒはB中隊に所属している。たまに若い奴らを訓練して廻っていたが、作戦が決まってからは中隊任務に専念していた。
「さあな、終わってから考えればいい」
ベルンハルトは装備を取り外しながら答えた。フリードリヒはまだ戦闘服を着たままだ。
「国に帰ってみるか?街を復興させようって話もあるみたいだぜ?」
「お前はそうすればいい」
興味なさげに銃の手入れを始める。
「ベルンハルトはどうすんだよ」
フリードリヒは苛ついた様子で問い質した。
「まだ戦いは終わっていない。先を見すぎるな」
「未来は誰にだって必要だぜ。いつか来るんだ」
「まずは目の前の戦いが全てだ」
フリードリヒは肩を竦め、諦めを態度で表した。
「わかったよ。終わってからゆっくり話し合おうぜ」
フリードリヒは銃を担ぎ直して自分の中隊へ戻ろうとする。
そして振り向きざまに、念を押すように指差しながら言った。
「アンタには人生を楽しむことが必要だ。家族としての忠告さ」
「俺の心配より、自分の中隊の心配をした方がいい。時間はあまりない」
ベルンハルトは視線も合わさずに答えた。
「ったく」
呆れるように手を振って、フリードリヒは去っていった。
連隊は訓練を繰り返した。コアの同時攻略はタイミングが全てだった。同時にコアを除去できなければ、アクティブなコアが除去された方を復活させてしまう。
そうなれば、E中隊と同じように、永遠に向こう側に取り残されることになる。
エンジニア達は専用の機器を作り上げて何度もテストを繰り返していた。
ミリアン、ベルンハルト達D中隊とフリードリヒのいるB中隊は、様々な設定で、二つのコアを攻略する動的シミュレーションを繰り返した。
シミュレーション・ゾーンの方から作戦失敗のアナウンスが流れた。
するとD中隊付きの選任技官であるロッソが、大声を張り上げながらゾーンから戻ってきた。
「制御装置の整備をした奴は誰だ!」
ロッソは女技官を呼び付け、首元を締め上げながら怒鳴る。
「貴様、テストせずに同期装置をいじったな!」
「すみません」
「オレを殺す気か!手順を守れ!」
女技官を突き放し、ロッソはマスクを叩き付けてハンガーに戻っていった。
「また失敗だ」
ロッソらエンジニア達の騒動を横目に、ミリアンがベルンハルトに話し掛けた。ミリアンの横にはB中隊隊長のスパークスもいる。
「成功率が低すぎる。機器も不安定だし、そもそもコアを同時に確保するのが困難だ」
二つのコアは別の世界軸に存在する。通信もできないと予想されている。
コア回収装置の同期だけは、ロッソが開発した装置によって取られるようになっていた。
「今までの中で、最大のずれは?」
ベルンハルトはBとDの中隊がコアを確保するまでのずれを聞いた。
「最大八時間だ。二時間以内に確保できたのは、十二回のうち、今のも入れて三回」
ベルンハルトの問いにスパークスが答えた。確保のずれが許されるのは、同期システムの限界上、二時間しかなかった。
「話にならんな」
ミリアンが言った。
「作戦室の連中は、この訓練でずれを収束させると言っているが?」
「まあ、やるしかない。少しでもましにしなきゃならん」
スパークスは気持ちを切り替えるように言った。
「おい、お前ら、ハンガーで待機。装備を整え直せ!」
ハンガーの周りでうろうろしているバックアップの若手隊員にミリアンは指示を与え、自分達もハンガーに戻っていった。
訓練の日々が終わり、いよいよ作戦決行まで一週間を切った頃、連隊全体での会食会が設けられた。連隊旗が掲げられたホールには、連隊メンバーがほぼ全員集まっていた。
テーブルには豪華な食事が並べられ、酒も十分に用意されていた。普段は食事で顔を合わすことがないエンジニア達も参加している。
会場の雰囲気は、作戦前の高揚と不安が入り交じった感情を反映するように、やけに騒がしかった。
「最後の最後で後詰めとはな」
ベルンハルトにアーチボルトがぼやいた。
A中隊は今回の作戦からまるまる外された。当然、作戦が失敗した場合のことを考えてだ。
「幸運を喜ぶべきだな」
酒杯を掲げてベルンハルトが答える。
「まあな。俺は別にこだわっちゃいない。だが、若い奴らがふて腐れててな」
「予想損耗率を聞かせてやればいい。後詰めでよかったと考え直す」
「違いない」
アーチボルトは話を切り替えた。
「シミュレーションの結果、芳しくないようだな」
「仕方ない、特殊な作戦だ。だが逃げるわけにはいかない。俺達の番だからな」
「幸運を祈ってるぜ」
「ああ、ありがとう」
アーチボルトと別れてミリアンを探すと、バーテーブルの前でロッソといるのを見掛けた。
「めずらしいな」
ミリアンの横に行き、声を掛けた。
「作戦の成功を祈って飲んでるのさ。俺達は運命共同体だろう?」
ミリアンの向こうからロッソが答えた。
「違いない」
「乾杯といこう、ベルンハルト。作戦の成功とD中隊の生還を願って」
ロッソが戯けるように杯を掲げた。三人で乾杯をする。
「おっと、ラームが来た。また後でな、ミリアン」
ロッソはラームを見つけて離れていった。
「意外な組み合わせだな」
「最後だからな。今回の作戦はあいつに命を預けるようなものだ。少しは腹を割って話しておこうと思ってな」
「そうか」
「最後の作戦、スターリングだったら何て言うと思う?」
ミリアンはホールの壁に掛かった初代連隊長スターリングの肖像に顎を上げて、ベルンハルトに言った。
「さあな、笑いながら『死んでこい。ただし、勝って死ね』とでも言うんじゃないか」
「ははは。そうはっきり言われると、こっちも肝が据わるな」
「無茶を言う親父だったが、憎めなかった」
ベルンハルトもスターリングの肖像を見ながら、酒杯を呷った。
「楽しんでるか?ベルンハルト。最後だぜ」
ぶつかるようにフリードリヒがベルンハルトの傍に来た。かなり飲み過ぎているようで、足元がおぼついていない。
「飲み過ぎているようだな、フリードリヒ」
ミリアンが呆れた様子で言った。
「なに、若い奴らに酒の飲み方を教えてやろうと思ってな。あれ、ちょっとやり過ぎたかな?」
壁際には何人かの若い隊員が酔い潰れて横になっている。大方、飲み比べでもやったのだろう。
「戦いの前に隊員を壊すなよ」
呆れた調子でベルンハルトも言った。
「なに、平気さ、無茶はさせてない。はず。うん。……で、二人で何を話してたんだ?」
「スターリングの親父の話さ。懐かしくなってな」
「ああ、親父の話か。最後の作戦だもんな……」
フリードリヒも肖像を見上げて呟いた。そして突然バーテーブルの上に立ち上がって叫んだ。
「おい、レジメントの野郎ども!古参も新人も関係ねえぞ、こっちに集まれ!」
フリードリヒの声がホールに響き渡り、一瞬静まりかえった。
「このレジメントを創った親父ことスターリングに乾杯するぞ、酒を持て!」
ぞろぞろと酒に酔った隊員達が、古参を中心に、フリードリヒ達とスターリングの肖像の前に集まった。
「俺達は親父に集められてここに来た。スターリングがいなきゃ、俺達もここにはいなかった。親父と死んだ仲間達に誓うぞ!渦に必ず勝利すると!」
おお、と隊員達は地響きがするような声を上げた。古参達の中には感極まっている者もいる。
「スターリング万歳!レジメント万歳!」
雄叫びともいえる声と共に、杯が上がった。
「レジメント万歳!」
その言葉が、終わることなく何度もホールに響き渡った。
「―了―」
3389年 「終局」 

ハンガーにレジメント全隊員が整列していた。
背後にはエンジンの暖気を行っているコルベットが振動している。
「これが最後の戦いだ」
ミリアンが大声で皆に伝える。皆、真剣な目付きで聞いている。
「必ずこれで終わりにする。俺達で最後にするんだ」
「死も栄光もここには無い。俺達は何を犠牲にしても必ず成功させる。それだけだ。」
「搭乗!」
コルベットに乗り込む際に、B中隊のフリードリヒと目が合った。兄弟は親指を掲げる。表情は普段のままだ。
コルベットのエンジン音が唸り、浮上する。向かい合って座っている隊員達の顔はいつもと変わらない。
ベルンハルトは作戦内容を反芻していた。
目の前のサイアスが大声で言う。
「到着まで何分だ?」
隣のギュアンが答える。
「二時間弱だ」
「OK、一眠りできるな」
「ああ、寝坊しても優しいママが起こしてくれるぜ」
お定まりのジョークが場を和ませる。
「境界を越えるまであと三十秒。衝撃に注意」
操縦席の指示がスピーカーから流れる。
コルベットはホライゾンと呼ばれる渦の影響領域の境界線を越える。
皆、自分のシートに体を押しつけ、予想される衝撃に備えた。
どのホライゾンでも衝撃や音を感じることがあったが、このジ・アイでは驚くほど静かだった。
「いよいよだな」
コルベットの天井部分にある小さな採光窓の変化を見つめながら、ギュアンがそう呟いた。
第二小隊のコルベットは、予定していた場所に正確に着陸した。
そこは赤い荒野だった。頭上には薄い赤褐色の月が浮かんでいる。
煌々と照らされる赤い光が、自身の目に入り込んでくる。
奇妙な静寂の中にいた。作戦開始時間まで小隊全員が口を開かず、黙って伏せていた。
生暖かな風が作る音と赤褐色の世界に囲まれていると、現実感が薄れていく。
どの渦の中もまるで一種の夢の世界のようだったが、この奇妙な静寂はよりその感覚を強めていた。
「まずいです、ベルンハルト」
観測手を務めていたランモスが言った。双眼鏡を受け取り、彼の言う場所を覗いた。
「進入地点に敵性生物の集団です」
事前調査ではこの時間帯に活動していない筈の竜人達が、松明を掲げてミリアン達第一小隊の進入路を塞いでいた。
「予定通りにはいかないものだな」
「ミリアン、ベルンハルトだ。そちらの経路上に予定外の敵がいる。見えるか?」
「ああ、確認した」
「こちらで陽動をかける。援護が薄くなるかもしれないが、うまく抜け出てくれ」
「了解した。頼む」
「こちらで陽動をかける。プロップのチームで東側から接敵してくれ」
陽動といっても、強力な火力がある訳ではない。
敵の数によっては身動きできなくなる危険が十分にあった。
「了解です」
プロップは命令を聞くと、自分の率いる分隊に命令を説明し始めた。
「我々は予定通り第一、第三の援護だ。その後に突入する」
「陽動の開始は二十分後だ」
正確に二十分後、戦闘が始まった。
散発的な射撃音が鳴ると、会敵した分隊に向かって敵性生物が一斉に動き始めた。
敵はクラスB型の人型生物だ。爬虫類様と情報にあった通り、二本足で立つトカゲといったところだ。
どれも自分の背丈の二倍程ある槍で武装している。
陽動部隊は八人で構成されており、小銃とセプターで武装している。
「思ったより多い」
「ええ、次々と巣から出てきているようです。援護が無ければ彼らも囲まれます」
ベルンハルトは無線で中隊付きのアーセナルキャリアを呼び出した。
「援護が欲しい。混戦になる前に敵の巣に砲撃を頼む」
「無理だ。竜が起きる。コア確保の前に危険は冒せない」
「どうせこの騒ぎだ。竜も気付く」
「だめだ。できるだけリスクは避ける。コアの確保を優先する」
ヘッドフォン越しの相手は、エンジニアを率いているロッソだ。
ベルンハルトは首を振った。
「俺達が行きましょう。ここから挟撃すれば分隊を助けられるかも――」
ベルンハルトはランモスの言葉を遮った。
「無理だ。誰かが突入部隊を援護する必要がある。退路の確保は絶対だ」
ランモスはそれ以上言葉を発しなかった。今何が重要なのかは、全員がわかっていた。
それは、死地に立たされているプロップの部隊もそうだと、ベルンハルトは信じていた。
巣から溢れた竜人は、プロップ達を囲むように追い詰めていた。
「突入小隊、進み始めました」
定刻通り静かに、だが素早く、ミリアン達第一小隊が突入口へ進んでいった。
さっき会話をしたロッソ達エンジニアの姿も見える。
コアがある場所は、作戦上『赤の玉座《レッドスローン》』と呼ばれる場所だった。
竜が守り、その使役種族の竜人達が崇めるコアが存在する場所だ。
横穴を進み、入り組んだ構造物を上るように進む。その頂上にコアがある筈だった。
「俺達も進むぞ」
ベルンハルトの部隊は突入口で退路を確保しつつ、突入部隊に何かあればコアの確保に向かうことになっていた。
作戦通りスムーズに事が運ぶとは思っていなかった。
コアは定刻に確保しなければならないのだ。なんとしても。
突入口さえ確保できれば、先行部隊はコアまで辿り着ける筈だった。
「ミリアン、どうだ?」
突入口で防御態勢を敷いたベルンハルトが確認の無線を入れた。
外のプロップの分隊はまだ持ち堪えているようだった。
だが、だんだんと銃声の間隔は長く、そして少なくなっていた。
「エリアHで足止めだ。しぶとい抵抗に遭ってる」
ベルンハルトは時計を確認した。コアの同期可能時刻まで一時間を切っていた。
二時間の余裕を鑑みても、実行が危ぶまれる状況だった。
「確保まで一時間も無い。俺もそちらに行く」
「G3ルートから上がってきてくれ。そうすれば敵の裏を突ける」
「ギュアン、サイアス、ブラック。俺と来い。レッドスローンに向かう」
「了解」
「ランモス、あとは頼んだぞ」
「了解です」
ベルンハルトは部下と共に奥に向かって走り出した。
竜人の作る奇怪な文様が続く回廊を上る。
分析班から提供された地図はしっかりと頭に入っている。
進むベルンハルトの耳に、銃声と人間以外の咆吼が聞こえてきた。
「ミリアン、もうすぐだ。状況を頼む」
「重戦士だ。数がいる。小銃が効かない連中だ。そちらから排除してくれ」
「了解」
ベルンハルトはミリアンが重戦士と呼んだ敵性生物の後ろ側に出た。
無言で銃を置いて抜刀し、セプターにエネルギーをチャージした。他の隊員も同じように抜刀した。
「征くぞ。奴等の弱点は足だ。恐れず踏み込め」
そう言うと、ベルンハルトは真っ先に敵に飛び込んでいった。
唸りを上げるセプターは、背中を向けていた2アルレに届こうかという緑色の獣人を横に切り裂いた。
咆吼と混乱が幅4アルレ程の回廊に響く。奥に敵が何匹いるかは確認できない。
だが、斬り続けなければ進路は決して開けない。
人の頭より大きい戦槌を持った重戦士が、黄色い牙と赤い目をこちらに向けた。
巨大な腕に力を込め、ベルンハルトを叩き潰そうとする。
巨大な重戦士の使う戦槌は、人間など二、三人同時に肉塊にしてしまう威力があると見えた。
だがその重さを支えながら振り回すために、足を大きく前に降り出す形になっていた。
ベルンハルトはその癖をあらかじめ分析していた。
戦槌をかいくぐり、低い姿勢のまま重戦士の巨木のような緑の膝をセプターで叩き切った。
巨大なエネルギーを解放していない戦槌は、足を失った持ち主を引き摺るようにしながら斜めに壁を打ち付けた。
鮮血が回廊を埋め尽くすように飛び散った。
ベルンハルトは逆手にセプターを持ち直し、バランスを崩した緑の巨人の頸椎へ刃を突き通した。
素早く持ち直して次の敵へ向かっていく。もう一匹の重戦士は仲間の死に怯むことなく向かってくる。
ベルンハルトは相手を挑発するかのようにわざとセプターを下段に構えた。
重戦士は戦槌を構えたままこちらを押し潰そうと突進してくる。ベルンハルトはそれを優雅な動きで避け、相手の横腹を切り上げた。
セプターは深く入り、相手の臓物は床にぶち撒けられることになった。
「うわぁっ!!」
斜め後ろでブラックの声が上がった。
ブラックは腰を床につけ、セプターも落としていた。重戦士の気迫に押されて足下を滑らせたのだろう。
振りかぶった戦槌がブラックを叩き潰そうとしていた。
ベルンハルトは床を蹴るように走り、背中から突き上げるように重戦士の心臓を貫いた。
しかし戦槌は振り下ろされた。
何か柔らかい物が石に押し潰される音が響いた。巨大な戦槌はブラックの右太腿を圧砕していた。
巨大な衝撃は大動脈と神経系を一瞬で破壊し、彼を即死させた。
「いいか、絶対に踏み留まれ!恐れるな、恐れさせるんだ」
ベルンハルトは残りの隊員を鼓舞して、再び巨人に向かっていった。
時間を忘れてベルンハルトは斬り続けていた。返り血を浴びていない場所は全身どこにも無い。
最後には、逃げ惑う重戦士を切り捨てる状態になっていた。
ベルンハルトは剣と一体化した死の化身となっていた。
静寂が訪れた後、ギュアンが負傷した腕を押さえながら、ベルンハルトに声を掛けた。
「ミリアン達は?」
回廊にいた重戦士は全て切り伏せるか退却していた。いる筈の場所にミリアンはいなかった。
ギュアンが倒れた突入部隊の隊員から、息がある者を見つけた。
「おい、どうした!?」
「隊長とロッソは先に行きました。 俺達は……ここで後続と合流しろと」
ベルンハルトは無線でミリアンに問い掛けた。
「どこだ?ミリアン。こちらはエリアHをクリアした」
「レッドスローンにいる。問題ない、コアの確保は間近だ」
「了解。そちらに向かう」
「上がるぞ」
ギュアンと共に、ベルンハルトはレッドスローンへ続く階段を上った。
コアへと近付く回廊は静かだった。
そこを進む内に、ベルンハルトの心に一つの不安がもたげてきた。
なぜ、俺を待たなかったのか。
時間は迫っていたが、玉座には下手をすれば竜がいる。なぜ二人だけで先を急いだのか。
ミリアンの判断ではないと直感していた。
ミリアンは剛胆な男だが、一方で中隊を率いる者としての慎重さも併せ持っている。
フリードリヒが言っていたロッソについての話が本当だったとしたら――。
作戦の成否とは別の予感が、ベルンハルトに迷いを与えた。
ベルンハルトはレッドスローンに着いた。
そこは竜人の塔の頂上にある吹き抜けで、赤い月が頭上に高く輝いていた。
そのオレンジの光の下、中央にある竜の巣に二人の男がいた。
ベルンハルトとギュアンは足早に二人の傍に向かった。
近付くと、既にコアはロッソによって回収装置が取り付けられていた。
「同期はまだか?」
ベルンハルトはミリアンに言った。
「ああ、まだだ。向こうの確保がまだのようだ」
「どうする、コアを下ろすか?」
「だめだ、ここでやる。まだ作業が残っている。そこでじっとしてろ」
ロッソが二人の会話の間に割って入った。
「そういうことだ。ここで待つ」
ベルンハルトは気付いていた。ミリアンの様子が違うことを。
「何故、俺を待たなかった?」
「時間が無かった」
「そうか」
ベルンハルトはロッソとコアに近付こうとする。
「おい、集中したいんだ。俺に近付けるな」
ロッソの言葉に反応して、ミリアンがベルンハルトの前に立ち塞がった。
「どうした、ミリアン。決定権はあいつにあるかもしれんが、お前はあいつの部下じゃないだろう」
「ベルンハルト……」
ミリアンがそう言った時、月の光が陰った。
頭上に竜がいた。巨大な竜だった。
「よし、ブルーピークの確保が終わった。コアが重なるぞ。衝撃に備えろ」
ロッソは一呼吸置いてから口を開いた。
「それと、そいつらを排除しろ」
素早くミリアンは銃をベルンハルトに突き付けた。
ギュアンは拳銃に手を伸ばそうとする。
「やめておけ」
ミリアンはギュアンを睨んだ。
「悪いが、俺はロッソと行く所があってな」
「何故こんな真似を?」
「心配するな。渦はなくなる。新しい世界が始まるんだ」
ミリアンの瞳はベルンハルトを見ていない。
「もうすぐ、あと十秒だ。殺せ!」
ギュアンがその言葉に反応して銃を抜こうとする。
反射的にミリアンはギュアンの頭を撃ち抜いた。
それと同時に、ベルンハルトはセプターを展開させながら銃を持ったミリアンの左腕を切り落とした。
「ええい、さっさと始末しとけばいいものを!」
ミリアンは一瞬腰を落とすと、肩からベルンハルトへ強く体当たりした。ベルンハルトは吹き飛ばされ、地面に転んだ。
ベルンハルトは素早く立ち上がろうとするが、ミリアンとロッソの向こうに降り立つ竜を見て、一瞬固まった。
竜は怒り狂った表情を浮かべながら二人に食い掛かろうとしている。
ロッソはミリアンを助け上げた。ミリアンが何かをこちらに叫んでいる。
だが、竜の羽ばたきと地面を蹴る音で何も聞こえない。
竜の顎門が二人を捉えるその瞬間、世界がぼやけ、コアを中心に光が広がっていった。
その光が、全てを白に塗り替えていた。
ベルンハルトはコルベットの天井部分にある小さな採光窓の変化を見つめていた。
「いよいよだな」
そう言ったギュアンの声が聞こえた。
明快な既視感と世界の違和感に、ベルンハルトは気付いていた。
「―了―」
 新規
新規 編集
編集 添付
添付 一覧
一覧 最終更新
最終更新 差分
差分 バックアップ
バックアップ 凍結
凍結 複製
複製 名前変更
名前変更 ヘルプ
ヘルプ